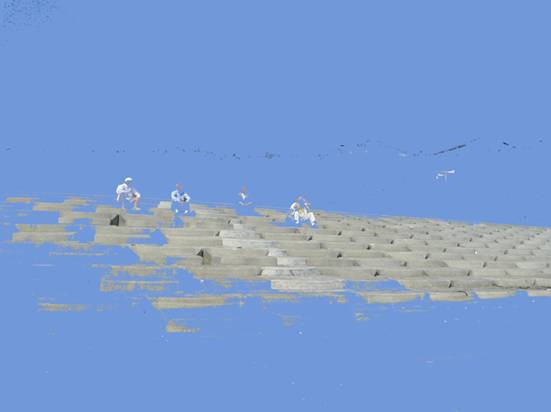解説にあたっての序文
これは人類の歴史書といって良いだろう。象牙の塔で豊富な資料と優秀な研究員たちとを使って出来上がったものではないし、膨大な予算を確保しての現地調査・解析に基づくものでもない。
隠居生活を送っている田中さんと現役技術者の山村君が、田中さんの書斎でコーヒーを飲みながら、時にはビールも入ったようではあるが、検討を続けた結果で顕になった人類史である。
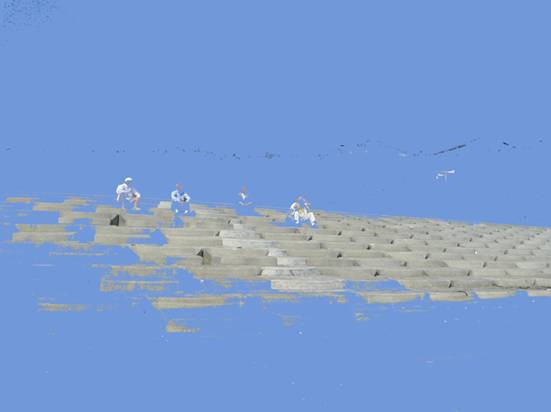
ヒト、まあ人間のことだが、ホモ・サピエンス・サピエンスという学名を持つこの生き物は、ある意味大変にユニークである。色んな見方はあるだろうが、このユニークさは頭脳の働きと体毛で代表されよう。生物学的には無毛とは言えないが、ヒトの体毛は本来の役割を果たせない状態にまで退化しており、 同じ霊長目に属する他の生物との違いは歴然としている。メガネザル、オナガザル、オラウータン、ゴリラ、チンパンジーと、服を着ていないヒトとを並べて、うしろ姿を(前から眺めるのは抵抗が有るだろうから)眺めてみれば、子供、成人の雄、成人の雌、どの場合でも一目瞭然でヒトが識別されよう。なんだかんだ言っても結局は毛の無い生き物がヒトである。
結局のところ、ヒトは頭脳の働きの良さ故に生き延びている生物だともいえる。衣服、家無しには非常に限定された環境下でしか生きていけない。熱さ、暑さ、寒さ、シャープエッジなど、全ての環境下で体毛の果たす役割は重要であり、この無毛の形質はヒトの大きなハンデキャップでもある。
服を着るようになったから要らなくなったのだという見解は無視しよう。好き嫌いは別にして、ゴジラ並みの体毛を持つヒトが現れたとすると、ロングレンジで見れば、この種族は無毛のヒトを押しやって世界を席巻するだろう。頭の働きが同じなら、耐環境性能が優れているほうが優位に立つのは目に見えている。
どうも、この長所と短所をあわせ持ったヒトのユニークさ、つまり頭脳と無毛はセットで獲得された形質と思われる。田中さんと山村君は本文の中で、ヒトの黎明期、すなわち頭脳と無毛を獲得するヒトの進化が始まったのはエデンの園からだったと結論付けている。
先ずはこのエデンの園である。
蛇がそそのかして知恵の木の実を食べさせるまで、アダムとイブは身にまとうもの無く、裸でここに暮らしていたとある。つまりエデンとはヒトが裸で暮らせるほどに温暖で、日焼けするほどの強い紫外線は無く、豊富な食料が容易に手に入る、そういった場所を示しているといって良いだろう。
田中さんたちはこのエデンの場所を見出し、安定した水系の水辺での豊富な高タンパク食糧の確保と、高酸素濃度・低紫外線環境の暮らしによって、体毛の減少と脳の進化が進んだと想定している。
さて、地中海の西端、ヨーロッパ大陸とアフリカ大陸が接するところにジブラルタル海峡がある。内懐の地中海と外の大西洋の広さから比べると、高々14kmの幅しか持たない狭い海峡である。
大よそ30万年位前、このジブラルタル海峡部が陸続きになった、と言うのが田中さんたちの仮説であり、本文の大前提でもある。
「突拍子も無い」
と、突き放してしまえばそれまでである。が、彼らは幾つかの拠りどころを持っていた。
その一つはオホーツク海からこのジブラルタル海峡部の間に存在する多数のミズウミである。オホーツク海が楔のように切れ込んだあたりからバイカル湖、バルハシ湖、アラル海、カスピ海、黒海、エーゲ海、東地中海、西地中海と、ミズウミが陸続と続いている。極端に狭い切れこみがある西地中海の最西端が陸続きであったとしても不自然ではないと。
それに、ユーラシア大陸(ヨーロッパ−スペイン)とアフリカ大陸(モロッコ)の海岸線が、大西洋側及び地中海側共にスムーズな連なりを示しているのも一つのヒントであり、ジブラルタル海峡の東海底を海図で調べると奔流のえぐった痕が見て取れると。
この陸続きをたった一つの前提として、ヒトへの進化、全世界へのヒトの拡散、ノアの洪水による地殻移動とヒト文化の壊滅、洪水後の後遺症探しと、これまでの人類史や地球環境の定説を覆す様々な見解を披露している。
大よそ30万年位前ではあるが、ジブラルタル海峡が陸続きになるとどういうことが起きるか。
2,000年ほど経てば地中海は半分以下の面積にまで干上がり、海水面も1,000m以上低下する。
これは現在の気象条件から引き出した値なので、本文の結論部分からするといわゆる2次補正が必要な値ではある。“この地域は地殻移動の影響は小さかったのでそれほどの誤差は無いでしょう”と言うのが我々の質問に対する山村君の答えである。
田中さんたちは干上がった地中海を眺めて、エーゲ海地域、特にクレタ島の北側にエデンを見出している。海抜マイナス1,000m強になるこの地域は、背後に大きな山脈を持った広大な土地が広がり、湖を備えて安定した水系の大きな河川を持ち、温暖な気候の実に快適な場所である。
数万年の単位で考えれば、ここには様々な生物が移ってきて、安定的に住み着くのは当然である。現代人類の祖先にあたる人族も(多分ネアンデルタール人か)おそらく20万年ほど前にはここに漂着して生活を始めたであろう。
本文ではもっと詳しく説明をしてあるが、このエデン、クレタ島の北側地域には様々な特殊環境が揃っている。安定水系、温暖気候の他にも、地理的な隔離環境、地形と気温から導かれる多湿環境、そして低紫外線・高酸素濃度環境である。田中さんたちは、ここに住み着いた現代人類の祖先にあたる人族が10万年程前にはブヨブヨして、ノッペリして毛の無い、メラミン色素も極端に少ないヒトに進化したと結論付けている。
さらに、もう一つのヒトのユニークさである頭脳も急速に発達した。田中さんたちはこんな風に表現している。
“栄養の摂取に困ることはなかったはずである。安定した水系の側で生活しているのだからむしろ
十分な栄養摂取ができたと考える方が正しいとも言える。しかも高濃度の酸素供給環境下である。
我々人類の特異性、最大の武器となっている脳の発達が、この二つの、栄養摂取と高濃度酸素供給で
急速に進んだと言える。“
“高濃度酸素供給環境下の故に、哺乳類の体の中でも極端に酸素を消費する特異な臓器である脳が、
急激な変化を続け、異常に発達した頭脳を持ったホモサピエンスが出現してくる。
そして数万年前、この人類が衣類や武器を考え出して、この隔離された土地から外部に進出を開始して、
急速に全世界に広がっていったと想定している。”
5万年ほど前から他所への拡散が始まった。この時代、大陸はグリーンランドのバフィン湾あたりを北極点として分布しており、陸地のたたずまいは今とは大分異なる。
先ずは南ルートが最初で、トルコ南岸からエジプト、スーダン方面へのルートである。
第二段階は南東ルートで、イラン、パキスタン、インド、ベトナム、インドネシア、ボルネオに到る。そして、第三段階は東と西のルートに分かれ、東はカスピ海、バイカル湖を経て太平洋に到り、海岸線沿いの南下とアラスカへの渡海。西はリビア、アルジェリア、モーリタニアへ。さらに大西洋の赤道海流を手助けにした南米アメリカへの渡海。
これらが本文での説明である。ヒトがほぼ全世界に行きわたった状況といってよかろう。ここではただ単に進出のルートとステップの検討に留まらず、逐次的な進出に伴う“ヒトの進化具合と地理的な分布”についてもユニークな指摘がなされている。
そして、1万2千年前、ジブラルタル海峡部が決壊し人類史は再スタートとなる。地球の人口は10万人規模にまで激減した。
決壊に伴うイベントを大きくは二つに分けて表現してあるが、一つは高速・大量の海水流入による地中海地域の壊滅であり、もう一つが海水分布の変化が引き起こした地殻移動による拡散先人類の激減である。
最後はこの1万2千年前のイベントの証拠探しである。無論、彼らの検討の中でもともと遡上にのぼっていたものもあるが、結構手広く事象を捉え、突っ込んでいる。
シベリアのマンモスの氷漬けと南アメリカの大量の動物の死滅、アラスカでの人類進出の行き止まり、グリーンランドの氷に含まれる酸素同位体から見た気候の急変、ナイル川の川床の変化、ハワイ島のズレ、こういったものからジブラルタル海峡の決壊に伴う地殻移動の証拠が提示されている。
あらましは以上である。
氷河期なぞは無かったと言うのも彼らの主張として述べている。こいつは錯覚だと。
本文は、二人の検討結果を田中さんが取りまとめて製本にまわし、山村君の結婚披露宴の引き出物の一つとして配布された本である。しかし、失礼ながら荒削りであり、ストーリも随分と飛び跳ねているため取っ付きにくく難解でもある。このため、現在の二人の事情を勘案してだが、我々が解説書を刊行することとなった。ここらのいきさつは以下のプロローグ部にまとめてある。
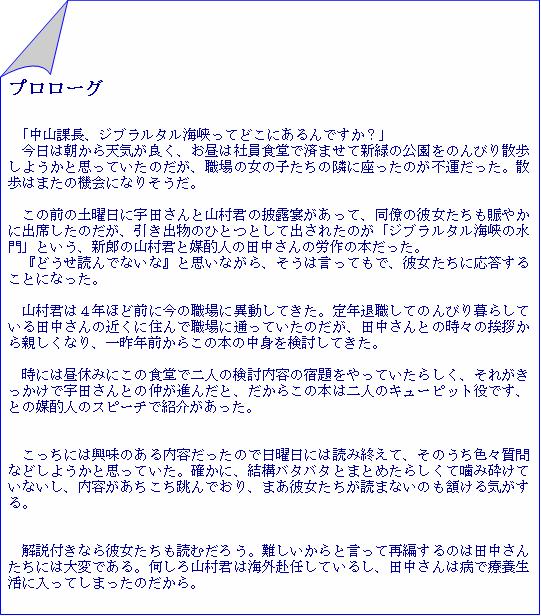
***************************************************************************************
本文は田中さんのワード文書を□の枠で囲って表示している。数箇所の誤字と、タイトルの一部の変更は入れたが原文には手をつけていない。各章・節ごとに短い解説を入れるだけで随分判り易くなったと思われる。是非ゆっくり読んで欲しい。
ただ、本文の結論は、現在のヒトにとって苦いものを残す様である。
解説文を書き進めて行く中で我々も鬱々とした気分になり、なんども停滞することが多かったのは事実である。
*****ジブラルタル海峡の水門解説委員会*****
***************************************************************************************
|