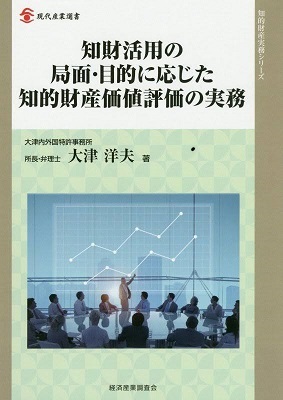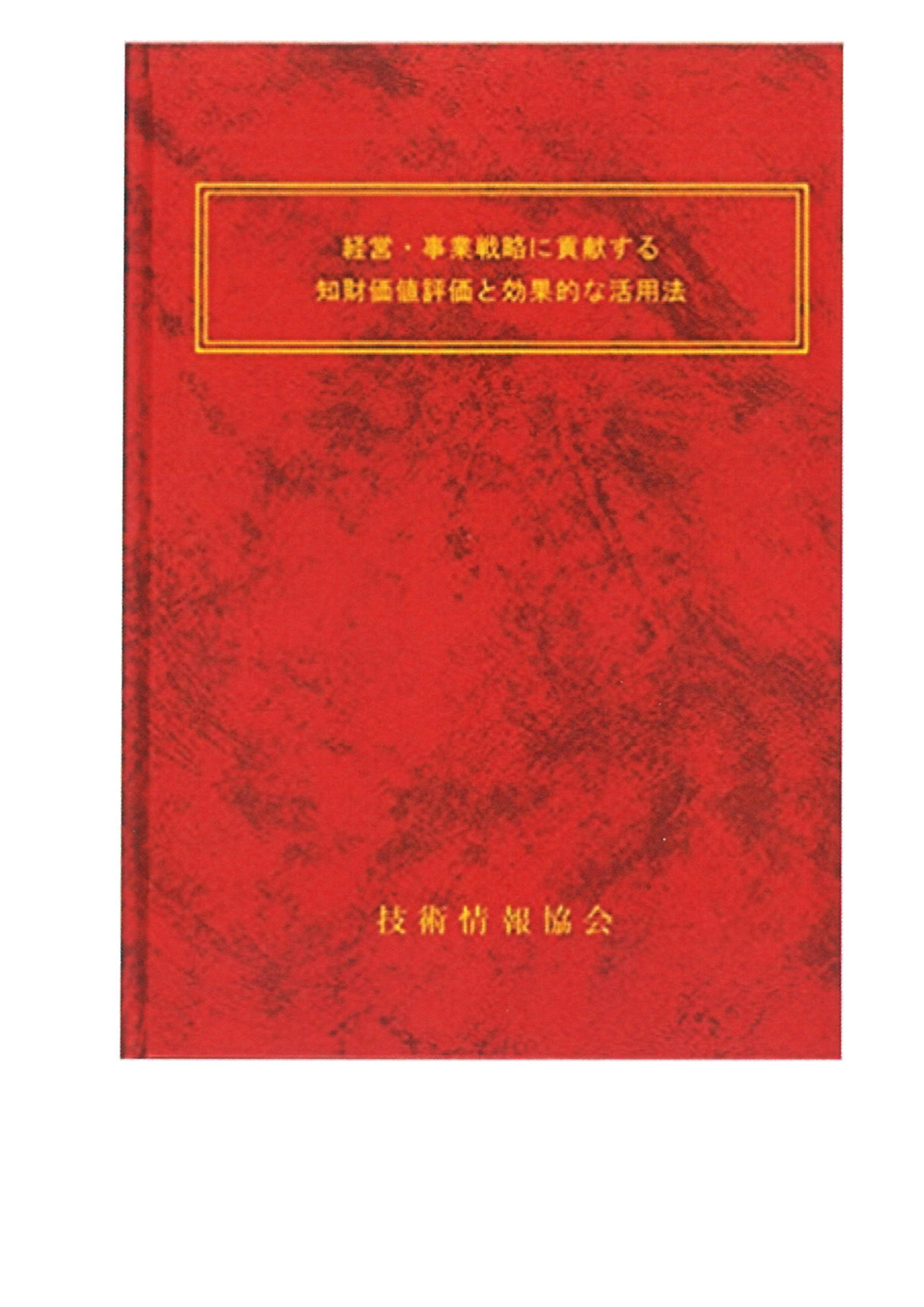<1>IP-mindは、変化の時代の未来を創る!
知的財産には新たな付加価値を創出して人間社会の経済的な進歩・発展に寄与する働きがあります。IP-mindは、新しい知識情報である知的財産を創造し保護し有効な活用することにより豊かな未来を構築するという考え方です。古来世の中には、安定と秩序のための考え方と、変化と進歩のための考え方がありますが、当該「IP-mind」は、変化と進歩のための考え方であります。ご承知のとおり現在は、IT技術の急速な進展による第5次産業革命(Society5.0)と、新型コロナ感染の蔓延による価値観やニュー・ノーマルへの変化により、人類は大きな社会変革に直面しております。「IP-mind」は、このような「変化の時代」における未来を築き、その中を生き抜くための考え方であります。 以下、このIP-mindの考え方についてご説明いたしますので、これによって厳しい社会変革の時代を乗り越えていっていただきたく思います
<2>知的財産の本質は有用な知的情報である。
知的財産の本質は「有用な知的情報」であり、これを保護したのが知的財産権であり、一般的に「情報財」と称されています。情報はある現象を特定のシグナルで示すデータとは異なり、データを認識・評価してその現象を利用できるようになったものである。従って、情報は、生物とともに生まれたものであるとされている。生物にとっての情報は、「特定の事柄を知ったり、知らせたりするもの」であり、「伝達性がある」とともに、「情報により環境の変化に合わせて自らを同化させるもの」という特性があります。
「情報の伝達性」とは、情報が無体であるため、同時に多くの人が所有し利用することが出来、瞬時に多くの人に伝わり拡散し易く真似されやすいものである。しかも、情報は物の所有とは違って、物理的に他人が使用するのを制限したりこれをコントロールすることは非常に困難である。知的財産も情報の一種ですから、当然上記の様な特徴を有しています。従って、知的財産を保護したり活用したりする場合には、上記のような特性を踏まえて対応したり戦略的な活用をする必要があります。
「情報の同化性」とは、情報を知った生物はその情報により認識した事象や環境の変化に合わせて自らを同化させようとするのであります。即ち、生物は、環境の変化や危険情報を認識すると、その変化や危険に対応して生き残ろうとするのである。もし環境情報や危険情報に適切な対応ができなかった生物は、絶滅していく運命にあります。
これに対し知的財産は「有用な知的情報」であり、その本質は情報ではありますが、それは「人間の知的活動によって創造された情報であること」及び「所定の目的や課題を解決する効果や機能など価値ある情報であること」という2つの要件を備えた特定情報であります。また知的財産は、その本質が情報であるところから「情報の同化性」という特性も備えております。そのため経営環境変化や危機的状況や急速な社会変革などのリスクに際しては、有用な知的情報である知的財産を保護・活用することにより、当該リスクを乗り越えて生存競争に勝ち残ることが出来るのであります。従って、知的財産は、未来を創り、進歩発展させる源泉になり得るものであります。
<3>知的財産を護るには3つの方法がある。
知的財産は、次の3つの方法によって護ことが出来ます。
第1に、知的財産は、国家権力により護られる。
つまり、国家権力に基づいた法律で権利として保護されるということである。権利によって保護されている情報を無断で利用すると、権利侵害として損害賠償を請求されたり、差止められたり、侵害罪として刑事罰を受けたりするということである。
そのため、知的財産権は「各国特許の独立」(パリ条約4条の2)といわれて各国別に権利が発生することになっているのである。
第2に、知的財産は自己管理により護ることができる。
ご存知のとおり、知的財産は、秘伝・家伝、ノウハウ、営業秘密として自己管理により護ることができる。
第3に、知的財産は、約束で護ることが出来る。
つまり、交渉と契約によって守ることが出来るのである。近代法における私的自治の原則の重要な一つとして「契約自由の原則」があって、契約により相手の動きの一部を制限することができる。もし契約違反した場合や、契約破棄した場合には、損害賠償請求することが出来るのである。
また国家間の約束としては条約や協定があり、これによっても知的財産を護ることが出来るのである。
知的財産の世界では、このような人為的な3つの方法を使い分けることによって護られたり、制限されたりして、コントロールすることが出来るようになっているのである。
<4>知的財産制度の仕組みを正しく認識して活用しよう!
知的財産制度がどんな制度なのかについては、国の産業政策としての認識と、企業や市場などの利用者側の視点からの認識の仕方の二通りがある。
産業政策としての知的財産制度というのは、その代表である特許制度における特許法第1条に「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業に発達に寄与することを目的とする。」と規定されている。この特許制度は、基本的に3つの理念と、1つの原則に基づいて構成されている。その3つの理念とは、①「知的情報は価値の源泉である」、②「創造力は模倣に勝る」、③「人は利益によって動く」であり、1つの原則とは、これまで存在しなかった財物を初めて人間社会に取り入れた人には、その財物を支配・収益・処分する権利(独占・排他的権利)を与えるという「所有権理論」に基づいて制度設計されたものである。
このように法律の目的として示された特許制度(知的財産制度)についての説明は、国の産業政策として保護者側(権利付与者側)の視点からその立法趣旨を説明したものである。。
これに対し利用者側の視点からみた知的財産制度の仕組みの認識は『知的活動で生み出された「価値ある知的情報」である知的財産は、本来自由に利用できる公共性のある情報財であるが、その情報を社会が必要とする限度で法的障害を与え、その自由な活用を制限することにより競争優位性という価値を創り出しているのが知的財産制度である。』
知的財産制度をこのように理解すると、開発した知的財産を権利化して活用すると、その競争優位性により企業価値を高めるメリットがあるが、反対に、当該知的財産を他人に権利化されると、その活用が禁止される。もしそれを活用したい場合には権利者から実施許諾受ける必要があり、もし不用意に実施した場合には、企業活動が制限されたり、企業価値を大きく下げるリスクにもなる。このように知的財産や知的財産制度を活用する場合には、矛と盾の両面の働きがあることに留意すべきである。
従って、知的財産を活用する際は、その知的財産価値評価によって知的財産の技術的価値、経済的価値、法的価値を明らかにしたうえで、知財活用に応じた局面、目的、評価の対象、利用者の知財力等を総合的に充分考慮して、定められている仕組(ルール)に従って効果的な活用をすることが重要である。
<5>知的財産の価値は一物多価である。
知的財産の価値は、常に一定ではない。それは内部要因、外部要因、時間の経過などによっても、その価値は常に変動するものである。具体的に述べると、
第1に、知的財産の価値は、実務的には、評価の局面、評価の目的、評価の対象、評価時点、評価の活用の有無、採用する評価手法、入手した評価用データいかん、評価者の立場などによってその評価結果は大きく変動する。
第2に、評価する知財価値の意味も具体的案件毎に異なっている。例えば、①経営戦略や事業計画の局面においては知財の効用価値を求めるのに対し、②流通の局面では交換価値や市場価値を求めることになり、③ライセンスの局面では使用価値を求めるものであり、④資金調達の局面では企業価値や事業価値が求められている。
このように局面や目的によって、求められている知的財産の価値の意味が異なっているのである。
第3に、知財の種類によってもその価値は異なっている。それは評価の対象となる発明(技術)や意匠{美感}や商標(信用)など保護する客体の特性が異なっているうえ、それらの保護法域が異なっていることから、当然その価値も異なってくるのである。
第4に、求められている価値評価の態様(評価表現)についても、定量評価か定性評価のいずれか、経済的価値評価・法的価値評価・技術的価値評価のいずれか、個別的評価か全体的評価なのかなど、多種多様である。
第5に、知的財産の価値は、活用しない場合には、原則として経済的価値は生まれないが、これを事業に活用することによって大きな経済的価値(事業収益)を生むことが出来るようになる。
第6に、裁判所や税務署などから依頼される公的案件の価値評価と民間企業等から依頼される民間案件の価値評価とでは、その評価基準が異なってくる。公的案件の場合は、中立性、良心誠実性が重視された公正価値が求められるのに対し、民間案件の場合には、合目的性、公正性、納得性が重視される適正価値が求められることになる。
因って、知的財産の価値評価に際しては、どのような種類の知的財産を誰が保有するのか、誰がどのように活用されるのか、市場環境はどうなのか等、評価の前提条件や価値評価要因によりその価値は大きく変動することになる。また、知的財産の価値評価は、知的財産の活用の局面や目的において、その財産価値の判断、使用価値の判断、交換価値の判断、技術や性能の優劣判断、成果の判断、能力の判断など、局面や目的に応じた多様な価値判断が求められているのである。
<6>これからはブランド経営の時代。
1.高まる商標・ブランドの重要性
近年の経営環境の変化が商標やブランドの重要性を高めています。
その経営環境の変化とは、①少子高齢化により国内経済の量的拡大を目指す経営は通用しなくなった。②グローバルな競争の激化により、アジア圏からの安価な商品が大量輸入され価格破壊により国内の産業競争力が急速に低下した。③情報化社会の進展に伴い物流チャンネルが多様化し、「モノ造り」から「価値ある情報造り」へ競争軸がシフトした。④新型コロナ感染によるニューノーマル時代の到来により、急速に企業経営や日常生活が情報に依存する高度情報化社会が実現するようになった。
このような経営環境の変化が、情報に依存した商品やサービスの提供や購買行動を加速させて商標やブランドの識別機能を高めるとともに、高度情報化社会の到来にともなって、商標やブランドが企業の存在意義そのものを示すシンボル標識に進化して、企業の継続的発展を支える資源としての重要性を増している。、
データとデジタル技術を活用したDX(デジタルトランスホーメーション)により顧客と社会のニーズに基づいた製品やサービスだけでなくビジネスモデルや業務の進め方など経営そのものを変革するようになった。その結果商標やブランドは、単に商品やサービスを識別する標識としてだけでなく、企業の目的や信頼や価値などといった企業の存在意義そのものを示す重要なシンボル標識に進化した。
2.商標・ブランドの社会的役割
我々の自由経済社会における商品取引やサービス提供は、お客様の「選択の自由」に依存しています。このお客様の「選択の自由」は、その望んでいる商品やサービスに商品商標や役務商標(サービスマーク)等の識別標識が付されることによって初めて可能になるものであります。このような自他商品・役務の識別標識のことを商標といいます。従って、市場経済における商品取引やサービス提供の自由競争原理は、商標によって支えられているのです。
即ち商標は、市場において次のような二つの基本的な社会的役割を果たしています。
第1は、商標の基本的な識別機能に基づいて生じる出所表示、品質保証、広告宣伝、財産的活用などの具体的機能によって、市場において商品やサービスを需要者の自由な選択の対象にする役割がある。
第2は、商標に基づき商品取引したり、サービス提供を受けたりしている需要者の信頼に応えて、常に公正な取引市場を確保する役割がある。
そのため商標やブランドは企業経営にとって継続的な収益を確保し競争力の源泉となるものであり、企業を支える経営資源としてその重要性が増しているのである。
3.商標のブランド化による市場における役割
商標は、使用されるとそのシンボル機能により使用者の信用が化体し、付加価値が付いてブランドになります。このように商標がブランド化すると、次のような三つのマーケティングにおける役割を果たすようになります。
その1は、消費者の購買行動においてブランドは、当該製品を他の製品から識別する手段を提供するだけでなく、購買の前後に取得される情報をそれらの製品と結びつける役割(シンボル機能)を果たします。その結果、各製品は、それぞれ一定の属性をもつものとして識別され、需要者の自由な選択により購買の意思決定が行われることになるのです。即ち、ブランドの識別手段としての役割は、使用によって商品を特定の認知や感情や行動と結びつけることになるのです。
その2は、消費者の購買行動においてブランドは、信頼の印としての役割を果たします。この信頼の印しとしての役割は、人々に一定の意味付けやイメージを創り出し、それを変容させ強化させることができます。つまり、ある商品のブランドが、長年にわたる使用により名声や評判を蓄積しグッド・ウィル(信用)が形成されると、当該ブランドを付しただけで、その対象製品について充分な情報がなくても、ブランドの信頼性が働いて、当該製品の選択的購買を動機付ける役割を果たすことになります(例えばベンツ、ルイビトン、ロレックス等)。
その3は、消費者の購買行動においてブランドは、ブランド自身が持つ独自の価値を想起させたり感知させたりして、これが購買行動を動機付ける役割を果たします。例えば、王室御用達の高級イメージのあるブランドの場合、そのブランド製品を所持するだけでステータスを感じ、その価値が購売行動を動機付ける役割を果たします。また逆に、子供が殺された誘拐事件に使用された乗用車のブランドについて、そのイメージダウンにより売れ行き不振となり、メーカーがそのブランド名の車種の販売を中止した例もあります。このようにブランドは、ブランド自身が有する独自の特徴や価値によって商品に付加価値(あるいは負の価値)をもたらすことになり、これが需要者の購買行動を大きく左右する要素となります。つまり、ブランドは、それを使用する者のグッドウィルだけでなく、バットウィルをもシンボライズすることになります。
その4は、価値観の変化したニューノーマル時代とIT技術の進展による高度情報化社会の到来に伴い、データとデジタル技術を活用したDX(デジタルトランスホーメーション)により顧客と社会のニーズに基づいた製品やサービスだけでなくビジネスモデルや業務の進め方など経営そのものが大きく変革する時代になった。このような社会システムの変革に伴って、商標やブランドは、単に商品やサービスを識別する標識としてだけでなく、企業の目的や信頼や価値などといった企業の存在意義そのものを示す重要なシンボル標識に進化しました。
以上のようにブランドは、市場における四つの役割を通じて、消費者の購買行動に影響を与えるので、企業のマーケティングという観点からは、より多くの消費者の購買決定を有利に導き得る価値の高いブランドとなります。
このように商標の使用により付加価値がついたブランドになると、それ自体に財産的価値が生まれて①価格の優位性、②高いロイヤルティ、➂事業拡張力といったブランドによる競争優位性が生まれ、企業の継続的発展を支える重要な経営資源になります。その際のブランドの価値は、企業における総資産の約24%以上にもなるのであります。
よって、これからは商標のブランド経営によって、企業価値を高め永続的な企業の発展を目指す時代になったと考えます。