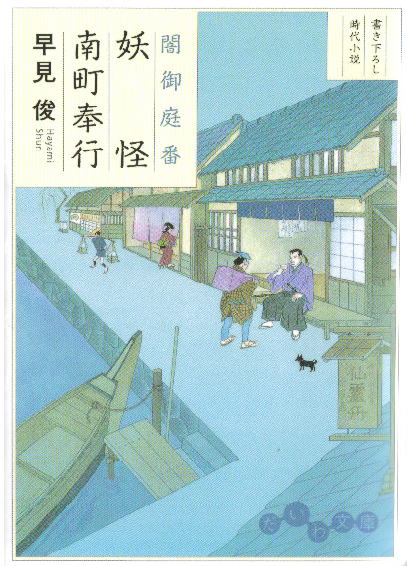
これは公儀御庭番を主人公とした小説であるが、この中に、天保改革を進めようとする老中首座水野越前守が、抵抗する南町奉行・矢部駿河守に業を煮やし、腹心の鳥居耀蔵に矢部罷免のための口実となる矢部のスキャンダルを探すよう命じるくだりがある。
こうして五年前の御救い米事件が蒸し返され、仁杉五郎左衛門の名が登場する。
以下、一部を抜粋して紹介する。
(前略)
翌朝、登城した矢部は水野に面談を求めた。
「世直し番、捕縛したそうじゃな」
水野は無表情に聞いた。
「捕縛した賊徒は世直し番ではございません」
矢部も無表情に返した。
「おお、そうであったな。世直し番を騙る盗賊一味であったのじゃな」
「仰せのとおりにございます」
矢部は慇懃に頭を下げた。
「ともかく、江戸市中を騒がせた殺しの一件は落着したのじゃ、庶民も安心して眠ることができよう。いや、庶民というよりは、町方の役人ども、と申したほうがよいか」
水野は口元を皮肉にゆがめた。
「同心どもの不正は、このとおり、お詫び申し上げます」
矢部は深々と頭を下げると、ゆっくりと面を上げ、
「同心どもの不正は弁解の余地はございません。しかしながら、同心どもが商人どもからたかりをおこなう背景を考えねばなりません」
静かに言い添えた。
「なにが言いたい」
水野は眉をひそめた。
「奢侈禁止令でございます」
矢部は水野の顔を見た。
「奢侈禁止令がどうした」
「少々行きすぎ、と。あれでは、庶民をいたずらに苦しめるだけにございます。結果、加納や亀吉のごとき、十手にものを言わせ、悪行三昧の者どもがはびこるのでございます」
「そのほう、町奉行の重職にありながら、ご政道を批判するか」
「批判ではございません。拙者は民を慈しむことの大事さを申し上げておるのでございます」
矢部は頼を紅潮させた。反対に、水野の顔色からは血の気がなくなっていく。
「黙れ!」
水野は真っ青な顔で肩をふるわせた。
矢部は口をつぐんだ。
「もうよい。退がれ」
水野は目を血走らせ、気を落ち着かせようと低い声を出した。
「失礼いたします」
矢部はていねいな物腰で退出した。
水野は、
「鳥居を呼べ」
廊下で控える御用坊主に命じた。御用坊主は水野の不機嫌口調に、急ぎ足で去っていった。
やがて、鳥居が入ってきた。
「お呼びでございますか」
烏居はざんぎり頭を下げた。
「近う」
水野は自分の前を扇子で指し示した。鳥居は、緊張の面持ちで膝行する。
「矢部を罷免する」
水野は鳥居の目を覗き込んだ。鳥居の目に緊張が走った。
「ついては、おまえ、矢部を迫い込むことができるよう処置いたせ」
「はは」
鳥居はしばらく蜘蛛のように這いつくばったまま、動かなかった。
「あやつめ、せっかく、目をかけてやったというに、改革を逸脱する考えを改めん。いまいましいやつじや」
水野は吐き捨てた。
鳥居はゆっくりと頭を上げた。目が輝きを放っている。
烏居にとって政敵をおとしいれることほど、心浮き立つことはない。ましてや、今回は矢部である。
矢部をおとしいれれば・・・。
「矢部の後任はわかっておろうな」
水野は頼をゆるめた。
鳥居は対照的に口元を引き締めて、水野を仰ぎ見た。
「手柄を立てよ。矢部を追い込むのじゃ」
水野が言うと、
「かしこまりました」
鳥居は腹の底から言葉をしぼり出した。
(中略)
そのころ、下谷練塀小路にある鳥居の屋敷では用人藤岡伝十郎が書斎に呼ばれていた。
藤岡は、鳥居が文政3年(1820)、25歳で鳥居家に養子入りした際、実家である林家から供侍として派遣された。以来、20年以上にわたって鳥居のそば近く仕えている。気難しい主人への仕え方は熟知していた。
「矢部のこと、調べは進んだか」
鳥居のおでこに燭台の蝋燭の明かりが揺れた。髪が伸び、ようやく貧相ながら髷が結われていた。
「はい、これに」
藤岡は緊張の面持ちで、報告書を差し出した。
鳥居は無表惰で報告書に目を通していった。 藤岡はうつむき加減でひかえている。
やがて、鳥居は報告書を文机に静かに置き、藤岡に視線を向けた。
「うむ、よく調べたな」
「はは。ありがとうございます」
藤岡はめったにない鳥居のほめ言葉に、身をふるわせた。
「だが、これだけでは、弱い」
鳥居は自分に言い聞かせるようにうなずいた。
報告は、矢部が不正を犯した与力の処罰を軽んじたり、すじ違いの調査をしたことを述べ立てていた。
不正を犯した与力とは、南町奉行所与力仁杉五郎左衛門のことである。天保7年(1836)に、「天保の飢饅」による米価高騰により、江戸市中でお救い米が庶民にほどこされた。そのお救い米を取り扱ったのが仁杉である。
仁杉は、米商人と結託し、賄賂を受け取った。藤岡は、矢部が仁杉の処罰に手心を加えたと断罪した。
.すじ違いとは、お救い米に関する調査を、天保七年当時管轄外であった勘定奉、西の丸御留守居役の身でおこなった、と訴えている。
いずれも五年前に起きた事件をほじくり返して、矢部の非を断罪しているのだ。
仁杉の罪は当時奉行であった筒井政憲の責任を問うべきであり、すじ違いの調査といっても、お救い米に関することであれば、幕府の要職にある者として矢部が調査するのは当然といえた。
藤岡としても、矢部を失脚に追い込めば主人が町奉行へ昇進することになることは、十分承知している。それだけに、調査は入念かつ慎重におこなっている。
だが、これだけで弾劾するのは困難と思わずにはいられない。藤岡はふたたび緊張の色を浮かべた。
「町奉行の重責にある者を弾劾するのじゃ。それ相応の落ち度がないことにはな」
「かしこまりました」
藤岡は額に順汁をにじませた。
「ただでさえ、矢部の評判は高まっておる。先月に起きた同心殺しと、米問屋に押し込もうとした賊徒の捕縛に成功したのじゃからな」
鳥居は言った。
「それが、巷では妙な噂がたっております」
藤岡は額を懐紙でぬぐうと、鬼吉一味が引き回しをされている最中、自分たちは世直し番を騙った覚えはないと叫んだことを話した。
「ふん、盗賊どもがなにを申そうがどうでもよいことであるが、ほじくれば面白いことが出てくるかもしれんな」
鬼吉一味の一件は、鳥居の嗅覚を刺激したようだ。
「そう思いまして、少々調べました」
藤岡は心持ち、身を乗り出した。鳥居は目に暗い光を宿らせた。
「殺された同心の一人、神山銀一郎ですが、ほかの同心や手先とは大違いの評判のよい同心だったそうです」
「それで神山だけは、お家断絶にならなかったのであろう」
「それだけでは、どうということはないのですが、神山、陽明学の学徒であったとか」
鳥居の目が光った。
「まさか、大塩平八郎とつながりがあるのではないだろうな」
.「それはわかりませんが」
「調べよ。いや是が非でも大塩とのつながりを明らかにするのじゃ。明らかにできる証拠がなくば・・」
鳥居は薄ら笑いを浮かべた。藤岡は両手をついた。
「でっち上げよ」
(中略)
水野は、矢部を江戸城中奥老中御用部屋に呼び出した。天保12年も暮れようとする12月21日である。居並ぶ老中の前で、
矢部駿河守、町奉行の要職にありながら、不行き届きの数々、なかんずく、天下の大罪人大塩平八郎を信奉する部下を見過ごし、その者が江戸市中を騒がせるとは許しがたい」
矢部を睨みつけた。
矢部は表情を消して水野の断罪を待った。
「よって、そのほう、町奉行の職を罷免し、家名断絶のうえ、伊勢桑名藩へお預けとする」
水野は勝ち誇ったように申しつけた。
矢部は薄ら笑いを浮かべ、両手をついた。
|