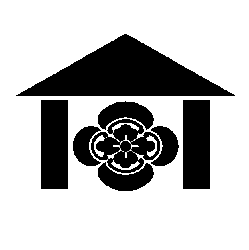|
仁杉圓一郎氏の父君である宰司氏が、祖先調査、家系調査に大変熱心で、圓一郎氏もその調査を続け多くの調査資料を残してくれた。このページもその資料に負うところ大である。
なお、これまで仁杉宰司氏の命名に従ってこの家系を「三島仁杉家」と称していたが、御子息で現在の当主圓一郎氏から、一族の居住した期間の長さから「裾野仁杉家」の方が適当だろうとのアドバイスをいただき、これに従う事とした。
圓一郎氏によれば、この家系が仁杉家の総本家で江戸の与力家は分家。分家であるが故に仁杉(にすぎ)と名乗ることが許されず仁杉(ひとすぎ)を名乗っているとのことである。
駿東郡に移住
「与力仁杉家」で述べたように
初代 伊賀守幸通
2代 徳川家御先手寄騎仁杉與兵衛(改め五郎左衛門)幸高
3代 御先手寄騎仁杉八右衛門幸重
4代 南町奉行所与力仁杉2代目與兵衛幸勝
と続く仁杉家は5代與兵衛(改め八右衛門)幸継(またの名前、幸次)の代に変化が起きる。
幸継は貞享4年に没した父幸勝より与カ職を継ぐが、病を得て与カ職うを務めるのが難しくなった。
 嫡男がまだ幼なかったため、弟勝安に一時与カ職を委ねた。 嫡男がまだ幼なかったため、弟勝安に一時与カ職を委ねた。
幸継はその後、元禄16年(1703)に江戸で死亡する。幸継の妻は幸継を江戸喜運寺に葬り、残された男子2人女子4人を連れて、仁杉家の所領である駿河国駿東郡仁杉(ひとすぎ)村に移住する。
移住して間もなく(2、3年後か)富士山の大噴火(宝永4年(1707)があり、富士山東部は甚大な降灰や火山岩の被害を受げた。
駿河仁杉参照
仁杉は1メートルもの灰に覆われ、田畑の耕作も馬や牛の飼育も出来ぬ状況になり、便用人や一族(この中に一杉姓もいたという)と共に、降灰の少なかった同じ駿東郡伊豆島田堰原(現裾野市伊豆島田)に移住した。
伊豆島田の仁杉家の土地は10里四方、屋敷も3千坪だったと伝えられる。
幸継は病弱ではあったが男子二人があり、二人は堰原で育った。長子源兵衛は元禄16年(1703)幸継から家督を相続したが、勝安が相続した江戸町奉行所の与力職は返還されることはなかった。
圓一郎氏によれば、江戸の仁杉家の家譜に「勝安から幸継(次)の子幸光に家督が返還された」とあるのはでっちあげで、実際には返還はなく、勝安の家系が与力家としてそのまま続いたとのことである。当代勤参照。
このようないきさつから圓一郎氏は、江戸の仁杉家はは分家であり、裾野の仁杉家が本家とのことである。
なお、源兵衛の弟は分家し伊豆島田の南、三島の宿に近い新宿に移住した。不思議なことに、弟も兄と同じ「源兵衛」を名乗ったという。駿東郡の仁杉家参照
仁杉家は、苗字帯刀を許された豪農として江戸後期まで続いたと伝えられる。
その家系は
| 幸次―源兵衛―半兵衛―源兵衛―与兵衛―勘蔵―熊蔵―(平吉)−宰司 ー圓一郎 |
とつながり、現在の当主は石巻市に住む仁杉圓一郎氏である。
江戸時代後期
圓一郎氏によれば元禄年間、幸次の長子源兵衛、長孫半兵衛の時代には、溶岩をくり掘り抜いた「涸れずの井戸」を利用して酒造業を営み、伊勢屋と呼ばれた。お伊勢参りに行く土地の人に多額の寄付をしたからだという。
三島、沼津、熱海に旅館、酒店の支店もあったと伝わっている。
風土記などに「幸通の後裔が熱海の伊勢屋という商人になった」という記述があるが、この事実と関係があるのだろうか。
源兵衛(2代目)、与兵衛、勘蔵までの時代は家勢も盛んであったが、勘蔵の妻が天保10年(1839)4月8日、流行病にかかり死亡し、その18日後には当主勘蔵も死亡してしまった。
長子熊蔵(3代目源兵衛)が家督を相続したが、この年、わずか4歳だったので、母親の実家で養育されることになり、田畑や蔵などの管理は親類筋に委託したが、結局これらの財産がが戻って来ることはなく、仁杉家の財産は霧散してしまったと伝えられている。
その後、伊豆田方郡の村長の仲立ちで、平吉に伊豆島田の屋敷だけは返してもらったが、これが約一町歩の広さだったという。
また、先祖代々伝わる古文書などを預かってもらった蔵の在り処もわかっているが、未だに「あかずの蔵」となっていて、仁杉家の人達はその中を見せてもらえない。
仁杉家の祖・幸通は仁杉・大乗寺に葬られたが、江戸では小石川白山下の喜運寺が菩提寺となった。駿河へ移った後は三島の長円寺が菩提寺となり、墓所は伊豆島田の屋敷内にあった。
源兵衛は堰原墓地(場所、不詳)に葬られているが、その妻および家督を相続した半兵衛以降の代々はこの墓所内に葬られている。また一族のひとりが長円寺の住職になっており、この人の墓もこの墓所内にある。
この墓所は今もこの地(三島市浄水場の近く)に残っている。
30坪ほどの墓地に大小さまざまな代々の墓が約10数基並んでいる。なかでも半兵衛の妻於市の墓石は蓮の花の上に観音様をあしらった立派なものである。
| 伊豆島田に今も残る仁杉家墓所〔右は半兵衛夫妻の墓) |
  |
この墓所について現在の当主圓一郎氏は次のように書いている。
| (前略) 後に墓所も宅地のすぐ近くに約50坪程の広さの、正面左右入り口に大きな溶岩が有り、周囲の畑との境に一抱えほどの噴岩が並ぶを設ける。
此の岩、14代圓一郎が蔓参の度に少しずつ墓所側に転がされているのを見ている。
源兵衛・半兵衛父子は母(幸継妻)没後、本家代々の墓を江戸分家の墓所に置けぬとして、父幸継嚢や幸高・幸重・幸勝墓並び子供墓10基以上を江戸より移葬し、堰原墓の右側に順に並べ建てる。13代多三郎は小青年期墓参の折、これらの墓石を見、父や父の叔父と共に法名を読み、これほどの法名なので武士でも身分の高い方だろうと話したと言っていた。
又東京の与カ子孫で平成没の仁杉(ひとすぎ)博氏は、古い先祖の墓は三島の近くに移したと伝え聞いておりますが場所が分からす塞参も出来かねておりますと、話しておられた。しかしそれらの墓は、墓守りに任せた40年ほどの間に誰かに持ち去られ無くなり、その為墓所右側部分は今でも空き地となっている。
多三郎と圓一郎は墓参の度近隣の薯所を歩き回り、3基ほどの子供墓を見つけ堰原墓に移した、これからも墓石探しは続けられるが、どうしても見つけられなげれば、幸高より幸継までの四代墓を建てるも考えている。.(後略)
|
「みょうちくさん」について
御殿場線岩波駅前にある畳大の石碑は裾野仁杉家の2代目当主半兵衛が建立したと、圓一郎しからお聞きし、このページに掲載していたが、その後三島市職員からの連絡で仁杉家とはかかわりがない石碑だとわかったため、このページから削除した。
みょうちくさん参照
明治以降
熊蔵(3代目源兵衛)は明治8年(1875)に38才で没しているが、その子平吉は、三島市壱町田(今の日本大学の近く)鈴木家の相続問題にかかわり、止むを得ず入夫したため、妹に仁杉を名乗らせたという。
この平吉が伊豆島田村字堰原に住んでいたことが明治三年(あるいは廿一年)の伊豆島田村の地図で確認できる。三島とその近郊参照。
平吉が入夫した鈴木家は古い家柄で「御座松」という屋号で呼ばれている豪農であった。かって源頼朝が富士の巻狩をした時に松の木に座ったいわれがあるという。
この鈴木家で生まれた子供の一人、多三郎氏が父・平吉の跡を継ぎ仁杉家13代となった。多三郎氏は姓名鑑定の勧めで後に宰司を名乗っている。
宰司氏は昭和11年、一時のつもりで妻の実家である宮城県石巻市に移住し、漁業共同組合長などを勤めたが、帰郷かなわず石巻で亡くなり、現在は圓一郎氏が当主となって茶の販売業などを営んでいる。石巻の他の仁杉姓を名乗る2軒は圓一郎氏の兄弟である。
平吉が鈴木家に入るにあたって、墓参が出来なくなるので裾野の市川家に墓所の守りを依頼し、市川家は3代にわたりこの墓を守ってくれたそうである。
「にすぎ」と「ひとすぎ」
ところで、石巻の仁杉家は「にすぎ」と名乗っているが、富士宮市に住む宰司氏の弟の仁杉光夫氏の家系は「ひとすぎ」と名乗っているそうである。
仁杉家では直系しか「にすぎ」と名乗ることが許されず、分家は「仁杉:ひとすぎ」や「一杉 ひとすぎ」と名乗ったということである。 江戸の与力家も分家であるから「ひとすぎ」と名乗ったのだろうか? 東京の与力家の子孫は現在、「ひとすぎ」と名乗っている。
また、江戸時代のいつ頃か不明であるが、一族のが浮島(沼津市原)に移住していると伝えられており、これが原一杉家のルーツである可能性が高い。(家紋 菊水の紋)
仁杉の語源は人の魂をもつ杉の古木「人杉」から来ているということである。
家紋
圓一郎氏は仁杉家の家紋について次のように書いている。
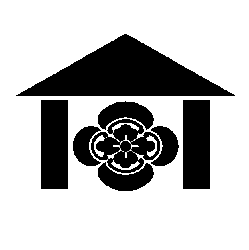 |
裾野仁杉家の家紋は「庵木瓜(いおりもっこう)」で、裏紋は「二重亀甲に唐花」である。
由緒ある武士階級では表紋(または正紋)、裏紋(または脇紋)のふたつの紋を持つ。 通常は表紋を掲げているが、止むを得ない事情により身を潜めたり、家門を明らかに出来ず、時の至るを待つ場合、あるいは負け戦の場合、裏紋に変えて退却するということである。
家紋によってもある程度家系が判ると言われている。鎌倉・室肛・江戸幕府に於いて、武士や武家たちは使用する家紋を届け出する事になっており、併せて家紋使用に至る系譜や、いわれ書きも届け出ており、此の事からも家系が探求できるのである。
鎌倉幕府の源頼朝は曽我兄弟の仇討ちで知られる工藤祐経の子、祐時・祐長等に工藤姓の名乗るを禁じ伊東姓を名乗るを命じ、又庵木瓜紋の使用も禁じ、工藤姓は工藤本流の祐清の嫡男祐光(狩野四郎)が従采通り名乗るとし、家紋も庵木瓜紋賄工藤本流のみ使用する事となる。
庵木瓜は藤原南家、工藤氏の系流に古くから伝わる紋どころである。工藤氏は藤原南家の流れであり、木工助(宮中の宮殿や神社などを建築、修理する役所の次官)を任じられたため、庵(家)の形を家紋とした。
木瓜(もっこう)はボケのことであるが、木工と木瓜(もっこう)の読みが同じため、ボケの花を図案化して庵(いおり)と組み合わせた紋にしたという説がある。(家紋大全)
累代33代藤原為患改め工藤為憲が定めた庵木瓜紋は工藤家紋として伝えられ、工藤維職(狩野九郎)工藤祐家(伊東太郎)工藤祐親(河津二郎)工藤祐光(狩野四郎)と伝えられ、累代56代工藤幸通(河津二郎三郎)改め、仁杉姓初代仁杉幸通を経て、現在に至る約千年の年月を経て伝えられている。
二重亀甲に唐花の紋は、江戸時代を通じて町奉行所の与力を勤めた江戸の仁杉家で同じ家紋を使っている。 |
裾野仁杉家当主の戒名、没年(仁杉宰司氏の資料による)
5代までは江戸の与力本家と重複している。
| 戒 名 |
|
名 前 |
没 年 |
場所 |
備考 |
篤心榮輝大禅門
大乗寺殿直道寂圓大居士
蒼杉院殿安誉豊国仁與居士 |
初代 |
従五位伊賀守幸通 |
天正20年(1584)
9月24日
|
仁杉 |
仁杉家の祖 |
桃蔭和玉禅定尼
慈照院殿圓妙寂玄大姉
|
幸通婁 |
天正18年(1582)
2月11日 |
仁杉 |
|
玉應宗関禅定門
珠實妙玉禅定尼 |
2代 |
幸高(初代與兵衛) |
元和9年(1623)
5月29日 |
江戸 |
与力 |
| 幸高妻 |
元和9年 |
江戸 |
|
月照院殿祖庵圓心居士
雲照院殿白法智清大姉 |
3代 |
幸重(八右衛門) |
寛文3年(1663)
12月8日 |
江戸
|
与力 |
| 幸重妻 |
延宝7年 |
江戸 |
|
見性院殿壁外全鐵居士
心光院殿秋淋智月大姉 |
4代 |
幸勝(2代目與兵衛) |
貞享4年(1687)
7月19日 |
江戸 |
与力 |
| 幸勝妻 |
宝永6年 |
江戸 |
|
|
善入院殿一空元超居士
妙快禅定尼
|
5代 |
幸継(次)3代目與兵衛 |
元禄16年(1703)
6月14日 |
江戸
|
与力
|
| 幸継妻 |
正徳5年(1715) |
裾野 |
駿河仁杉に移住、宝永噴火後に堰原に移る。 |
宗誉道覚信士
心誉貞月妙安法尼 |
6代 |
源兵衛初代 |
享保10年(1725)
5月22日 |
裾野 |
行年51歳 |
| 源兵衛妻 |
寛保2年 |
裾野 |
|
覚誉孤岳臨峯信士
綜誉練貞信女
深誉信知慧照信女 |
7代 |
半兵衛 |
安永4年(1775)
2月3日 |
裾野 |
行年68歳 |
| 半兵衛先妻 |
宝磨3年 |
裾野 |
|
| 半兵衛後妻 |
明和6年 |
裾野 |
|
往誉即無生信士
音誉妙響池生信女 |
8代 |
2代目源兵衛 |
寛政8年(1796)
12月20日 |
裾野 |
行年68歳 |
| 源兵衛妻 |
文化7年 |
裾野 |
|
到心欽洋信士
転成理清信女
|
9代 |
4代目與兵衛 |
文政10年(1813)
7月10 |
裾野 |
|
| 與兵衛婁 |
文化10年 |
裾野 |
|
隻屋常林信士
隻室妙輝信女 |
10代 |
勘蔵 |
天保10年 (1839)
4月26日 |
裾野 |
夫妻が同じ月に死亡 |
| 勘蔵婁 |
天保10年(1839)
4月8日 |
裾野 |
春光陽樹信士
證順至道信女 |
11代 |
3代目源兵衛熊蔵 |
明治8年(1875)
2月14日 |
裾野 |
|
| 熊蔵婁 |
明治9年 |
裾野 |
|
誠誉誓願信士
智誉妙春大姉 |
12代 |
平吉 |
大正13年(1924)
9月14日 |
三島 |
|
| 平吉婁 |
昭和27年 |
三島 |
|
鎌掌院足意多厳居士
普門堂圓鏡秋月田大姉 |
13代 |
多三郎 |
昭和55年 |
石巻 |
石巻に移住 |
| 多三郎妻 |
平成6年 |
石巻 |
|