
人間関係にもいろいろな形態があり、その関係にも深浅があります。
どんなものがあるか考えてみましょう。
(1) 自然発生的関係
自分は意識しなくてもいつの間にかできあがっている関係です。親子の関係などはこの典型です。また幼稚園、小学校、中学校と一緒にすすんできて、ついに大学まで同じ学校だったという人もいます。その間親友だという意識は別になかったが、なぜか離れることもなくつき合いが続いているなどは、この自然発生的な関係にあるといえましょう。
また何年も一緒に仕事を続けてきた男と女が、別に男女を意識しなかったのに、ふと気がつくと相手を好きになっていたなどもこの類です。
この関係の特徴は、「長い時間を共に過ごすことで成立する」ということにあり、ほとんどが良好な関係にあります。
(2) 自由選択的関係
自分の意志で自由に選択できる関係です。個人の好き嫌いの感情や、損得の利害計算などで選択しますからとても流動的な関係です。
私たちの生活の中で最も多いかたちの関係でもあります。
自分の意志で選択できるわけですから、まさに自由に取捨することができるというすばらしさをもっています。それだけに裏面では壊れやすく、憎しみあい、争い合うなどのリスクを背負った関係でもあります。
(3) 強制的関係
自分の置かれた立場や環境などから、自分の意志とは関わりなく受け入れなければならない関係です。
ひとつの集団がうまく運営されていくには、個々の自由を拘束しなければならない必要が生まれます。この思想が人間関係に投影されたものなのです。したがって拒否すると自分の存在を危うくすることにもなりかねません。
職場の人間関係を考えると容易に頷けることと思いますが、ほかにも関係を強制される場合はたくさんあります。
 このページの上へ このページの上へ
|


人間関係は、できあがるまでのメカニックがあります。初対面でいきなり恋愛感情が芽生えるケースもありますが、ふつうはそれなりのいきさつと時間をかけて作られていくものなのです。
知らない人同士が知り合い、良好な人間関係ができていくには、つぎのような順序を踏むこととなるでしょう。
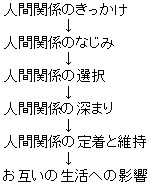
(1) 人間関係のきっかけ
人間関係はお互いが知り合うことから始まります。街角で言葉を交わした人、旅先で知り合った人、ビジネス上で名刺を交換する人などたくさんの機会があります。
これらに共通しているのは、出会った場で相手を意識し、ちょっとした言葉が交わされるということです。ほんの数秒であっても何らかのコミュニケーションがなされるということです。
わずかなものであれ、この交流がないとどれほど多くの人と対面しても、行きずりの人で終わります。
わたしたちは多くの人と人間関係を作ろうとするならば、積極的に話しかけていくという 能動的なはたらきかけをしてみたいものです。
もちろんこのレベルにおいては、1度だけで終わる関係、2度と会うことなく忘れられていく関係もたくさんあります。そうであってもこの機会を大切にし、有効に活かそうとの努力をしたいものです。
昔の人は「一期一会」といって、この縁を大切にしていました。
(2) 人間関係の馴染み
初対面が過ぎると、会うたびにあいさつが交わされ、雑談などが繰り返されてお互いに顔馴染みになっていきます。近所に住んでいてよく顔の合う人、職場でいつも顔を合わせる人などです。
こうして人間関係は「馴染みのレベル」に入り、人付き合いが始まっていくこととなります。
(3) 人間関係の選択
人は出会った誰とでも順調に人間関係を育てていけるかというと、それほど人間は単純にできていません。ふと立ち止まり(或いは常にかもしれませんが)現在の自分と相手との関係を見返ることがあります。それが人間関係の選択です。
この人との関係を続けようか、変更しようかなどを自分につぶやくのです。ただしいつも意識して行うのではありません。ほとんどが無意識の中で選択するのです。
選択には次の2つがあります。
① 関係の距離の選択
どの程度の関係にしようかとの選択です。
心を許し深くつきあおうか、気まずくならない程度の表面的なつき合いにしよ うかなどの選択です。
② 関係の取捨の選択
今後も関係を続けようか、それともここで断ち切ろうかと考えることです。
感情や利害打算が働くところでもあります。
「あんなイヤな奴とは知らなんだ。もうおさらばだ」
「嫌いな人だけど今離れると損になる。もう少し我慢しよう」といったもので す。
こうした選択は常に意識して選択するものではありません。多くは無意識におこなっているので自分でもわからない場合が多いです。
また選択はよく修正されます。冷静で理性的なときか、気分が激しているかで選択は変更され、それが修正され、再修正となり、再々修正となるなどいつも変化しているのです。
(4) 人間関係の深まり
前項を通り抜けた人間関係は、次第に深まりに入っていきます。友人間の関係は親密さを増します。若い男女には恋愛感情が生まれます。近所づきあいもスムーズに深まります。
協力関係はできあがり、お互いに助け合ったりするわけです。
(5) 人間関係の定着と維持
人間関係が深まり安定してくると関係は定着へとすすみます。そして人はこの形が長く続くようその維持に努めるわけです。
ただ人間関係は常に揺れ動いています。人間関係が深まって定着したといっても、決して変わることなく固定したというのではありません。ちょっとしたことから関係が壊れる危険性は常に内在しています。
人間関係維持に油断は禁物です。細やかに心配りをすることは、この時期にあっても必要なのです。
(6) 生活への影響し合い
好ましく深まっていった人間関係は、やがてお互いの生活に影響し合うことになります。さらにすすむと運命共同体という関係にまでなります。
例えば1組の男女が、恋愛し、結婚し、生まれた子供を育て、共に老いてゆくなどはその典型といえます。
 このページの上へ このページの上へ |

1,人間関係をつくる話し方
人と人との関係はまず顔を合わせ見つめ合うことから始まります。ついで声を掛け合うことが必要です。
話すことは、人間関係をつくる最も根元になるものです。よりよい話の交わし合いが、よりよい人間関係を約束するでしょう。
人間関係は話すことからつくられ、話し方によって様々に変化します。話し方によって深まるかと思えば、話し方によって不幸にも壊れたりするのです。
人間関係をつくるには、まず相手に敵意のないことを示す行動が必要です。何気ない言葉を交わすことはお互いの心理的な壁を取り除き、気持ちの接近をはかります。この行為を「日常のあいさつ」と呼んでいます。
(1) あいさつと人間関係
① あいさつはこちらから先にしましょう。
② あいさつは相手を見て明るくしましょう。
③ あいさつは状況に応じて変化をつけてしましょう。
④ あいさつ言葉に、相手への関心を示した言葉を加えましょう。
(2)返事と人間関係
① へんじはすぐにタイミングよく返しましょう。
② へんじは相手を見て返しましょう。
③ へんじは相手のはたらきかけにフィットしたかたちで返しましょう。
(3) 会話と人間関係
① 会話は話すよりも聞くことにより努めましょう。
② 話題は相手の興味のあるものを出しましょう。
③ ふだんから話題を広くするように努めましょう。
④ エチケットを守って会話を続けましょう。
⑤ 場を楽しく盛り上げることに努めましょう。
2,人間関係を維持する話し方
人間関係をつくることはもちろん大切ですが、それを育て維持していくことの方がもっと大切です。
人間関係はいつも流動的で、1度つくられた人間関係がいつまでも続くという保証はありません。
人間関係のありようを端的に左右するのが話し方です。
友好な人間関係を維持していくために、ふだんの話し方に配慮しましょう。
(1)自尊心を守った肯定的な言い方をする
① 相手がいやがる表現や言葉は使わないようにしましょう。
② 相手の意見や言い分は認めてあげましょう。
③ 相手を自分の下に置くような気持ちで、対さないようにしましょう。
④ 相手の気持ちや立場に配慮してあげましょう。
⑤ 相手の意見に反対するときは表現に気を配りましょう。
⑥ 相手の名誉や価値を損ねるような言い方はしないようにしましょう。
⑦ 相手に快く響く言葉(マジックフレーズと言います)をたくさん使いましょう。
(2)相手に心を開いて向かう
① 警戒心をなくし、気持ちを開いて対しましょう。
② にこやかな表情で対しましょう。
③ 明るく響く声で話しましょう。
④ こちらから相手に近づいてゆくようにしましょう。
(3)相手を受け入れる努力をする
① 自分を受け入れてもらうために、相手を受け入れるようにしましょう。
② 自分が好かれるために相手を好いていきましょう。
③ 相手に関心を向け、それを言葉で示しましょう。
④ 相手の名前を覚え、努めて名前で呼びかけましょう。
⑤ 相手の良いところを探し、認めてあげましょう。
 このページの上へ このページの上へ
 |
|
 |