�@�@
|
 |
�@�@�@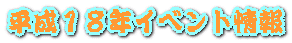 �@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ |


�@�m�吨�ɑ���b�����n
�@�吨��ΏۂƂ��Ă̘b���������グ�Ă݂����B�p�u���b�N�X�s�[�`�Ƃ������A�����̐l�������S�A������������b�̏�ʂł���B�吨�̑O�Řb�����Ƃ́A����Љ�ł͌l���D�ނƍD�܂���ƂɊւ��Ȃ��A�N�������ʂ���Љ�I�v���ƂȂ��Ă���B
�P�C�E�C�������Ęb��
�@�b����ʂł́A��Έ�ƈ���đ����S���̈���������A�b���ɂ�������������̂ł���B
���̍����̂��߂ɂ͂܂��h�E�C�������āh�Ղނ��Ƃ���{�ƂȂ�B
�@�u�����C���E�C�v�Ƃ����A�����C�����ĂΗE�C���N���A�E�C�������ėՂ߂Ό����C���N���Ă���̂ł���B
�@(1) �E�C�����ĂȂ�����
�@�A�A�b������邱�Ƃ������
�@�C�A�b��ᔻ����邱�Ƃ������
�@�E�A�b�̍I�ق����Ȃ����Ƌ����
�@(2) �E�C�������߂ɂ͂ǂ�������悢��
�@�A�A�����̘b�������Ŗ������Ȃ�
�@�@�ӎ����Ĉӗ~���������Ă邱�ƁA���̂��߂Ɉȉ��̂��ƂɂƂ߂����B
�@�@�@���e���l����
�@�@�A�b�ނ��W�߂Ă���
�@�@�B���ӎ������悤�ɂ���
�@�@�C�ӗ~���������Ă邽�߂Ɏ��̌��t�ɒ��ӂ���
�@�@�@���ł��c�A���ǂ����c�A�������āc�A�����߂��A���ł��Ȃ��A���ǂ�����
�@�@�@���A�ȂǂƂ������t�͌��ɏo���Ȃ��悤�ɂ���
�@�C�A���O�̔ᔻ������Ȃ�
�@�@������͂������ᔻ������̂��A�Ǝv���Ęb������
�@�E�A�b�̖ړI��Y��Ȃ�
�@�@�����͉���b���̂�����������ӎ����Ęb������
(3) �吨�̑O�Řb���Ƃ��̗��ӓ_
�@�A�A�����S���̈����ւ̑Ώ�
�@�@����邾���ł��Ă͘b�͂��܂ł��ł��Ȃ��B�h�悵�b�����h�ƐS�Ɍ�����
�@�@�����ē��ݏo���Ă݂悤�B�ӊO�ɐS���y�ɂȂ���̂ł���B
�@�C�A���O���͂ɓw�߂�
�@�@���O�͗l�X�ł���B�E�ƁA�N��A��̈Ⴂ���Œ��O�̔����͈Ⴄ�B
�@�@�܂����O�̎����A�h�b�����ɗ��钮�O�h�h�b���ɗ��钮�O�h�h�b���킩
�@�@��ɗ��钮�O�h�Ƃ���A���ꂼ�ꔽ���̈Ⴂ��������̂ł���B
�@�E�A���ʑ���̓��
�@�@�Ώۂ������Ȃ�قǘb�̌��ʂ̑���͓���Ȃ�B�܂����̑���@�Ƃ���
�@�@���̂͂Ȃ��B�����邱�Ƃ͎��n�̌o�����d�ˁA�����Ȃ�̑���@������
�@�@�o���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�m����n
�@ �P�C�b�����͓�̐���������
�@�����m�E�_�����𒆐S�Ƃ���b����
�@�@���e�̎���m�����A�܂����Y�������߂���b�ŁA
�@���v���[���e�[�V�����E�u�`�E�u���Ƃ������b�ł���B
�@����E����𒆐S�Ƃ���b����
�@�@�b�̓��e�����y�����A�������낳�A���݂��݂��A�S�̖����ƂȂ�b�A�Ƃ���
�@�@������h������b�ł���B
�@���W��ł̃X�s�[�`�A�g�[�N�V���E�A�b�|�Ƃ����镑���̘b�A�܂���
�@�@�����Ȃǂ�����B
�@�����̂ق��ɒ��ԂɈʒu����b����������
�@�@��\�Ƃ��ėc�t���E�ۈ牀�̋��t�����̘b����������B�q�������Ɋy����
�@�@�b�����A�V�т̒��Ŏq�����������炵�A�^���Ă��������ł���B
�@�@�q�������������b�͏�I�����A�b�̖ړI�͐l�Ԃ̋K���E�K�͂�
�@�@�w����Ƃ����_�����������Ă��邩��ł���B
�@
�Q�C�Z�\�I���ʂ��猩���b�̓���
�@�����m�I�E�_���I�b����
�@�@���e�̘_���I�\�����͂��邱�Ƃ����ʂ����E����B�b�̍\���@�́A����
�@�@�\���ƂقƂ�ǃI�[�o�[���b�v���Ă���̂ŁA���̎�@�ɏ]���悢�Ƃ�
�@�@���B����Γ��]�I�v�l���Z�\�ʂ̒��S�ɂȂ��Ă���B
�@����E��I�b����
�@�@�Z�\�̎�̂ƂȂ�̂́h�b���Ԃ�h�ł���B�����A�ɋ}�A����A�ԂƂ�����
�@�@���̂ŁA������g�ɂ���̂͑̌��ȊO�ɂȂ��Ƃ����B
�@�@�X�ɂ�������Ȃ̂́A�h�b�ɖ����o���h���Ƃ����߂��Ă���B�b�̖��Ƃ�
�@�@���ɂ͘b����̐l�Ԑ����w���Ă���̂ł���A�b�ɂ悢�����o���ɂ�
�@�@�b���莩�g�̐l�Ԑ������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂȂ�B����͂����Z�\
�@�@�z�������x���ɂ����āA�b���������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�@�R�C��������b�̋Z�\��g�ɂ���
�@ ��ɏグ����̘b�̋Z�\�́A�ǂ���ɕ��Ă����ʂ͂������Ȃ��B
�u�����͂킩�邪�b�͑ދ����v
�u�������낢�b���Ԃ肾���A��̐b���v
�@�Ȃǂ̕]�����Ȃ����߂ɁA�_���E����̋Z�\���Ă����������̂ł���B
�@�@�@�@�@ 

�@�@�@�@ 
�m�f����ɂ��ān�@
�@�@�i�����Y�O�w���j
�@�f�邱�ƂƂ́A����̐\������ɑ��Ď�����Ȃ����Ƃ�`���A�������Ă��炤�s
�ׂł���B�܂葊��̐����s�ׂɑ��A�t�ɐ������d�Ԃ����Ƃł���A�t�����Ƃ�����
���B
�P�C�u�f��v���Ƃ̓��
�@�u�f��v�Ƃ������Ƃ͗l�X�ȓ���������B����͒f������́A����Ƃ̊ւ��ɓ�������邩��ł���B��̓I�ɂ͎��̂��Ƃ���������B
�@�@ �S��I��R��
�@�@��������@�@���C�܂����@�@���ْ�
�@�A �l�ԊW�̕ω��ւ̕|��
�@�@���W�̈����@�@���W�̔j��A����
�@�B �������̕ω��ւ̕|��
�@�@�����Q�W�̈����@�@���s���v�̕��]��
�Q�C�u�f����v�ɂ���
�@(1) �S�̂̍\�z�i�헪�j�𗧂Ă� �傫�Ȏ����ɂ��Ēf��ꍇ�́A���O��
�@�@�@������āA�܂����Ԃ������āA�\�z�i�헪�j�����ĂėՂނ��Ƃ��K�v��
�@�@�@����B
�@�@�f����̋�̓I�Ȏ�@�Ƃ��āu���I�i���W���[�j��@�v�Ɓu���I�i�}�C�i�[�j��@�v���@����B���I�i�}�C�i�[�j�Ȏ�@�͍D�܂����Ȃ����̂��������A�����ɂ͎g���邱�Ƃ������A����Ȃ�̌��ʂ��グ�Ă���B
�@(2) ���I�i���W���[�j�Ȓf���
���\���̂Ȃ����Ƃm�Ɍ����i�������ɔz������j
��������Ȃ����R�Ɠ��e�������i���܂����A�͂��炩���̂Ȃ��悤�j
������˂Ȃ��悤�z������i����̎����S�ɔz������j
�����₩�ȕ\��Ƙb�����ő��i�G�ΓI���͋C�łȂ��j
�������E��Ă������i���̏����Ȃ�Ύ����Ȃǁj
�����������ʂɂ����C�����ő�
�����Ђ��ؗp����
�@(3) ���I�i�}�C�i�[�j�Ȓf���
�����فi�ق��Ă��đ��肪����������̂�҂j
���J������i�ł��Ȃ����̂͂ł��܂���A�ȂǂƂ����j
���͂��炩���i�_�_������ւ��ĞB���ɂ��Ă��܂��j
�������i���������ĉ��j
���v���C�h���Ȃ߁i���ƌ������Ă���Ƃ����́H�����������Ȃ��ŁA�ȂƂǂ����j
���Ђ��E�Ј��i�ォ�牟��������悤�ɒf��j
�@�m�����ɂ��ān�@
�@�i��c�x�j�w���j
�@�����́A����̂悭�Ȃ��s�ׂ�l�������w�E���āA���Ȃ𑣂��A���炽�߂����邱�Ƃ�ړI�Ƃ������̂ł���B
�@���������Ē����͑���̊������U���A�l�ԊW�j��ɂ܂łȂ���댯���������Ă���B
�@�������A���݂��̐��������悭���邽�߂ɁA�K�v�Ȃ�Β�R�������Ē��������A�܂�����������邱�ƂɂƂ߂������̂ł���B
�@�P�C�����̌��ʓI�Ȃ�����
�@������Ɏ�����������������
�@�@�i�P�P�������Ɏ��Ə���l����j
�@�����f�����Ȃ�
�@�@�i��т�C�����ł����j
�@����r�����Ȃ�
�@�@�i�����������Ȃ����߂ɁB�g�߂Ȃ��̂Ƃ̔�r�قǔ����������j
�@��������F�߂�
�@�@�i�C�����ɋ~����^����j
�@�Q�C�����̒��ӓ_
�@���d�˒����A�lj������͂��Ȃ��i�ꎞ�Ɉꎖ�̌����Łj
�@������ɂ܂��������̂�A��ϓI���f�ł��Ȃ�
�@�@�l�I���f�łȂ��A�W�c�̒N���������v���Ă��邱�Ƃ��Âɂ���
�@�����f����l�ԊW�Â���ɓw�߂�
�@�@�l�ԊW�������Ƃ̐��ۂ���Ƃ����Ă悢
�@�R�C�����̎�
�@�����������Ƃ������Ƃ́A�����̒m��Ȃ�������m�邱�Ƃł���B�S���I�Ɏ���ɂ������Ƃł����Ă��A���Ȃ̐l�ԓI�����̗ƂɂȂ���̂Ǝv���A����邱�ƂɂƂ߂悤�B
�@���܂�����̘b��f���ɕ����i�����̎����ӂ����Ȃ��悤�Ɂj
�@���w�N���猾��ꂽ���x�łȂ��w�����̉�������ꂽ���x���l����悤�ɂ���
�@�������ɋC������
�@�@�������t���@��������@���J������Ȃǂ����Ȃ��悤��
�@���������e�Ɍ��������A�킩�点�邱�ƂɂƂ߂�
�@���������ꂽ���ƂɊ��ӂ��錾�t��`����
�@�@���������l�������Ă���B���ӂ̌��t�͂��̏���@���Ă����邱�Ƃ�
�@�@�Ȃ�B
�@�m�t�^�n
�@�悭���������ɏo�������̂ɒ����ƒ��ӂ̈Ⴂ������B�Q�̈Ⴂ����
�@����ƁA
�@�����Ӂ@�c�@����̌������ꎞ�I�ɂ��炽�߂����邱��
�@�������@�c�@����̐����ԓx�i�������A�v�z�܂ł��܂߁j�����炽�߂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�����ЂƂA�����ƒ����Ƃ̖��m�ȈႢ�͂ǂ��ɂ��邩�Ƃ̖�������B
�@�������@�c�@�����́A�w�i�ɗϗ��E�����E���[���Ƃ������ϔO������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�s�ׂł���B�l�̏�������Љ�̃��[���ɏƂ炷�ƁA�Ԉ����
�@�@�@�@�@�@�@�@���邩����߂Ȃ����Ƃ����̂������ł���B
�@�������@�c�@��̂悤�Ȕw�i�͂Ȃ��B�����������ɂ�����P���̍l����
�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��炭���A�����قǂ̋����͂Ȃ��B
�@�@�@�@�@ 

�@�m�����̎d���n
�@��������ɂ����āA���̊�b�Ƃ��Đ����͂����߂Ă����K�v������B�������悭����������ɏ\���ȗ�����^����A�s���𑣂����Ƃ��e�ՂɂȂ邩��ł���B
�@�킽���̗Ⴞ������������ɋ������̎��t���𗊂��Ƃ�����B�ƒ�ɂ��鋋�����ł́A���o�[���グ��Ɛ����o��̂ƁA������Əo��̂Ƃ�2��ނ�����B�킽���̊��o�ł͉����Đ����o������C���[�W���悢�B
��������������͏グ�Đ����o��������t���悤�Ƃ����̂ł���B
�@�s�R�Ɏv���q�˂�ƁA�_�ˑ�k�Ђ̈Ȍ�����̒ʒB������A���̂悤�Ȍ`���Ɍ��߂�ꂽ�̂��Ƃ����B���̗��R�͉������������ƒn�k�ŗ����Ă������̂��A�����̃��o�[�ɓ������Đ��������������A�����o���ςȂ��ɂȂ邩�炾�Ƃ����B���ɐk�Ў��ɂ͂��̃P�[�X�������o�āA��Q���L�����Ƃ̂��Ƃ������B
�����ɔ[�������킽���͐���������ɑf���ɏ]�����̂ł���B
�@�P�C�����̑��
�@�����Ƃ́A�������肤���ƁA���Ă��炢�������ƂȂǂ��A����ɔ[����������A�s�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���b�̂͂��炫�ł���B
�@�킽�������̓���͒N���̋��͂��Ȃ���ΐ����ł��Ȃ��B������܂�������̋��͂����߂�̂ł���B�܂葊�ݐ����ɂ���Đ����͐��藧���Ă���̂ł���A�����͂����߂邱�Ƃ́A�����̐��������L���邱�ƂƂȂ�B�����ɐ����̑��������̂ł���B
�@�Q�C�����𐬌����������
�@�@ �����҂̈ӗ~�Ɛ���
�@�@�u�悵�������邼�v�Ǝ����Ɍ�������������
�@�A �������鎖���̗���
�@�@�u�����������Ȃ����ǂ���Ă���v�ł͂���
�@�B ��������l����
�@�@�����{�ʂɂȂ��Ă͂���
�@�B �����҂̑���ɗ^������
�@�@��ۂ������Ă͐������Ȃ�
�@3�C�����̎d��
�@�@ �ł��邾���������ɂȂ�
�@�@�@�u����ׂ�Ȃ���ׂ点��v�������Ƃ���
�@�A ��̓I�Ȍ��ʂ�����
�@�@�@�������͂����߂�ɂ͎����E���������
�@�@�@�������E����͋�̓I�Ȍ��t�Řb��
�@�@�@���b����̓I�ɂ���6�̗v�f
�@�@�@�@����r�E�Δ��p����c���X�Ƃ̒l�i���ׂ�Ȃ�
�@�@�@�@�������f�[�^�������c�m���Ȏ����̗��t���ƂȂ�
�@�@�@�@�����o�ɑi����c������������Ȃ�
�@�@�@�@���v���X���ʂ���������
�@�@�@�@��������
�@�@�@�@���E��������g���Ă݂�
�@
�@�B �����\�ȕ��@������
�@�C �����̍l����q���g��^����
�@�D �^�C�~���O�Əꏊ���l����
�@�E ��܂��Ɗ��ӂ�Y��Ȃ�
�@�m����n
�@�P�C�����̏������Ƃ��Ă̐������
�@����̐������X���[�Y�ɂ����߂��ł̐�����ʂł���B�ƒ�A�ߏ��A�F�l�E�m�l�ԁA�E��Ȃǂł����ӂ��ɂ݂�����̂ŁA�����̏ꍇ�u�����v���ӎ����Ȃ����̂ł���B
�@�@ ��̓I�Ȑ������
�@�@�@���Ȃ��v�Ɂu�U���̋A��ɃR���r�j�Ł������Ă��Ă��傤�����v�Ȃ�
�@�@�@���ߏ��̉�����Ɂu�ꏏ�ɔ������ɍs���܂���B���̂Ƃ����������Ăˁv
�@�@�@�@�@�Ȃ�
�@�@�@���F�l�Ɂu�����̃N���X��o�Ȃ��Ȃ����ˁv�Ȃ�
�@�@�@���E��ŁA�O�ɐH���ɏo��Ƃ������ԂɁu���̂͂����|�X�g�ɂ���Ƃ�
�@�@�@�@�āv�Ȃ�
�@�A �����̏�ʂŒ��j�ƂȂ�����̏d�v�v�f
�@�@�@���ǍD�Ȑl�ԊW
�@�@�@�@�ӂ���̐l�ԊW�̂���悤�������̐����傫�����E����B����
�@�@�@�@���u�����̂��������厖�v�Ƃ�������̂ł���B
�@�Q�C���m�ȃe�[�}�ƈӎu���������������
�@����ȑ���ɁA����ȃe�[�}�i�������ځj�������Đ���������̂ł���B�O���̏�ʂقǐ��͑����Ȃ����A���̐��ۂ͂�͂萶���ɑ傫�������̂ł���B
�@�@ ��̓I�Ȑ������
�@�@���Ⴂ�j���u���������ޏ��Ɍ�����\���������v�Ǝ����Ɍ����������Ȃ�
�@�@����������u�S�~�W�Ϗ������̉Ƃ̑O�ɐݒu���邱�Ƃ��������Ă���
�@�@�@�����v�Ȃǂ̂Ƃ�
�@�@���c�ƃ}�����u���̃��[�U�[�Ɂ����̔��荞�݂������悤�v�Ȃǂ̂Ƃ�
�@�@���l���������u���̐l�ɗE�ނ��������悤�v�Ȃǂ̂Ƃ�
�@�A �����̏�ʂŒ��j�ƂȂ�d�v�v�f
�@�@�����Q�̒���
�@�l�ԊW���������d�v�����A�����ė��Q�������d�v�ȗv�f�ł���B���Ƀr�W�l�X��ʂɂ����ẮA�����藘�Q�v�Z����s����B�]���Ăǂ̂�����Ő܂荇�����̌��������̌���ƂȂ��Ă���B���ɍ��ƊԂ̊O���́A���̗��Q�������ŏd�v�v�f�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�k���N�~�T�C�����ˎ����ł̍��A���ٌ��c�̂��������݂�悭������B
�@�ȏ�͕��ӎ҂̌l���z�ɂ����̂����A�Q�l�ƂȂ�K���ł���B
�m�t�^�n
�@�����̎�� �@�����Ƃ͐l�������ƂƂ����邪�A�����ڍׂ������ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
����͈ȑO���グ�Ă���̂ŁA�Čf�ƂȂ�B
�@�@�����������邱�Ɓc�u���������Ă��������v�Ɖ����������邱�ƂȂ�
�@�A���������Ȃ����Ɓc�u�����߂邩�炱��������_����v�Ǝq���Ɍ���
�@�@�Ȃ�
�@�B��藧�Ă邱�Ɓc���݂��Ă��邱�Ƃ��u�x�����A�����Ƌ}���Łv�ȂǂƂ���
�@�@����
�@�C�ύX�����邱�Ɓc�u�r���ł悢�����ɂ�����������Ă���v�ƕʂ̂��Ƃ�
�@�@������
�@�D��߂����邱�Ɓc���݂��Ă��邱�Ƃ��X�g�b�v������u�����ō�Ƃ͒��~�v
�@�@�Ȃ�
�@�E�e�F�E���������邱�Ɓc�u���炭���̏ꏊ�ɎԂ�u�����Ă��������v�Ȃ�
�@�@�̂���
�@�F�l����ς������邱�Ɓc�u�������疯��x���ɕς�낤�v�Ȃǐ��_�ʂւ�
�@�@���������̂���
�@�@�@�@�@ 

�@�u�̎d���v
�@�Ƃ͑��肪�m�肽�����Ă��邱�ƁA�܂��������m�点�����������A���m�ɓ`���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����b�����̂��Ƃł���B
�@�P�A�Ȃ��͏d�v�Ȃ̂�
�@(1) ���̊l���̂���
�@�@�@�K�v�ȂƂ��ɕK�v�ȏ��Ɏ����̎茳�ɂ���A�����A������
�@�@�@�Ȃ��������邱�Ƃ��ł��A���_�I�ɂ����肷��B
�@(2) ���f�̊�b�Ƃ���
�@�@�@�����̒��ł킽�������́A����C�P���C�D���C�i�ށC���l�X�Ȕ��f��
�@�@�@���ׂ����Ƃ������B���̔��f�̎����Ƃ��ĕ��K�v�ł���B
�@(3) �s���ւ̈ӎu����Ƃ���
�@�@�@�O���ɂ������h���f�h�͎��̃A�N�V�����Ƃ��Ă̍s���ɂȂ�����
�@�@�@�����B�����̈ӎu������ԈႢ�Ȃ����̂ɂ��邽�߂ɕ��K�v�ł���B
�@��̂R�͌q����������̂ł���B�Ⴆ�Ώo�Ύ��ɎP�����ׂ����ǂ������l�����Ƃ���B�����Łh���̊l���h�̂��߃e���r������B�e���r���ߑO���܂�A�ߌ�ꎞ�J�Ƃ����̂��āA�P�����ׂ��Ɓh���f�h����B�����Ŋ��ɐ܂肽���݂������āA�o�Ƃ����h�s���h�Ɉڂ�̂ł���B
�Q�C�������̎d��
�@�́A�����𐳊m�ɓ`���邱�Ƃ���Ώ����ƂȂ�B�����ŕ̎d���Ƃ��Ď��̂��Ƃ��l���Ă��������B
�@(1) �T�v�Q�g�������Đ��m�ɓ`����
�@�@�@ �v���������i���j�@�c�@���̂��Ƃ�
�@�@�A �v���������i�ǂ��Łj�@�c�@�ǂ��ł������̂�
�@�@�B �v�����i���ꂪ�j�@�c�@�N�ł�������
�@�@�C �v�������i�Ȃɂ��j�@�c�@�Ȃ�ł�������
�@�@�D �v�����i�Ȃ��j�@�c�@���R��ړI�͉���
�@�@�E �g���� �����i�ǂ̂悤�Ɂj�@�c�@�ǂ̂悤�ɂ��āE���@
�@�@�F �g���� ���������i�ǂ�قǁj�@�c�@������A�l�i�E�o��
�@(2) ������Ƃ��̐S��
�@�@�@ ����̓s�����m�F���Ă���
�@�@�A ���_���ɁA�o�߂͌ォ�猾���悤�ɂ���
�@�@�B �^�C�~���O���v������
�@�@�C �����Ǝ����̈ӌ��Ƃ͂͂������ʂ��Č���
�@�@�D ���_�ł��̂�����Ȃ�
�@�@�E �K�v�Ȃ璆�ԕ�����
�R�C�̎�
�@�𐳊m�Ɏ~�߂邱�Ƃ́A�����邱�ƂƓ����ɑ厖�ł���B
�@�@�@ ���炩���ߌ��_�����߂Ă����Ȃ��c����ς����������S�ɕ���
�@�@�A �����̕����ƁA����̈ӌ��Ƃ��A��ʂ��ĕ����悤�ɂ���
�@�@�B �˂��炢�̌��t��������
�@�m���K�@�ݖ�n
�@�ȉ��̂悤�ȓd�b���������B���̘b������v�̂Ɋ�Â��X�b�L���܂Ƃ߂Ă��������B
���������A�����d�͂���H���傤�Ƃ̃|�X�g�ɁA�O�ɓ������Ă��l�̖��O�ŁA���������͂��Ă�����ł����ǁA������ƒ��ׂĂ��������܂��B�����������z���Ă����̂͂T���Q�T���Ȃ�ł����B���ƁA�����̉Ƃ̓��H�ɗ����Ă���d�����ė~������ł���B�Ƃ�V�������Ă����ǂ��傤�Ǒ��̂Ƃ���ɓd���������Ă��邩��A��D�_�ɓ���ꂽ���Ȃ�����Ȃ��ł����B�W���܂łɍH�����I���悤�ɂ��肢��������ł����ǁA���ɂȂ邩�U���P�O���܂łɌ�A�����������B
|
�ǂ��ł����B����͂Q�̗p�������݂��Ă���̂őS�̂ɂ܂Ƃ܂���������Ă���B
����������ăX�b�L�����������B�ȉ��̂悤�ɐ������Ęb���Ό��ʓI�ȕƂȂ�B
�@ �����������ė~����
�@���O�̓����҂̖��O�Ń|�X�g�ɐ��������������@
�@�������������z���Ă����̂͂T���Q�T���ł���B
�A �O�̓��H�̓d�����ė~����
�@������O�ɗ����Ă���d�����ė~����
�@���V�z�����Ƃ̑��̋߂��ɓd��������A�D�_�̐S�z�����邩��
�@���W���܂łɍH���͏I���悤�ɂ��ė~����
�@�����̕Ԏ����U���P�O���܂łɗ~����
|
�@�m���ӎ҉���n
�@�Ƃ́A���ڂɎ�����m�邱�Ƃ��o���Ȃ��҂��A���炩�̋@�ւ�ʂ��Ď�����m��Ƃ����b�̂͂��炫�̂��Ƃł���B�@�ւƂ́A����ɂ���l�ԂƂ��A�V���A�e���r�Ȃǂ̃��f�B�A���w���̂ł���B
�@�s�쎁�̍u�`�ɕt��������Ƃ���͓��ɂȂ����A�O�̂��߂Ƃ����Ӗ������������Ă݂����B
�P�C�́u�P�����v�Ɓu�������v
�@�����̒��ł́̕A�����͒��p�_�̗���ł��邱�Ƃ���ϑ����B
�@�P���Ƃ́c�c�i�`�j���i�a�j�ŏI�����́B�N�_�̎����I�_�ƂȂ���̂ł���B
�@�����Ƃ́c�c�i�`�j���i�a�j���i�b�j���i�c�j�Ƒ������́B�N�_�ƏI�_�̊Ԃɂ������̒��p�_������@���̂ł���B
�@�N�_����I�_�܂ŊԈႢ�Ȃ����`���ɂ́A���ɒ��p�_�ɗ��҂̓w�͂���ƂȂ�B
�@�����Œ��p�_�҂́A
�@�����e�𐳊m�Ɏ~�߂邱��
�@�����e��I�m�ɓ`���邱��
�@�ɓ��ɐS�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@(1) ���m�Ɏ~�߂�ɂ�
�@�u�`����у��W���ɂ���u�̎��v�ɏ]�����Ƃł���B�����e�͎������ۂ����ᖡ���邱�Ƃ���ł���B�����̕ɂ͋^�킵���������悭����B�����łT�v�Q�g�Ă͂߂Ă����A�������ǂ����肷�邱�Ƃ͗e�ՂƂȂ�B����T�v�Q�g�Ƃ͎G���ȕs��������菜���h�ߍނ̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@(2) �I�m�ɓ`����ɂ�
�@������s�쎁�̍u�`�́u�̎d���v�ɏ]�����Ƃł���B�����ł��T�v�Q�g�͏d�v�Ȗ����������Ă���B����ɂ��A�`����ɂ��A�T�v�Q�g�̂͂��炫��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Q�C�̌`�ɂ́u��`�v�Ɓu���`�v������
�@�̓����Ƃ��āu�͂��̂悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����K��������A����ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B�ԈႢ�ł͂Ȃ������ۂ̐����ɂ����Ă͂���ɔ����Ȃ������邱�Ƃ��m���Ă��������Ǝv���B
(1) ��`�Ƃ��Ă̕�
�@�ǂ�ȓ��e�̂��̂��A�ǂ̂悤�ȍ��ڂɍ��킹�āA�ǂ�ȏ����ŕ��邩���K�������ł���B
�@�g�D�̂ł̋Ɩ���̕Ȃǂ�����ł���B���������Ă����̏ꍇ�́̕A�����S�����������Ă���B��`�Ƃ��Ă͈̕�ʓI�Ɏ��̂悤�ȏ����ƂȂ�B
�@�@ �\���c�c���ꂩ����邱�Ƃ�����
�@�A ���R�c�c���̂��̕����邩�̗��R������
�@�B ���e�ɓ���
�@�@ �����_�A���ʁA�ŏd�v�_���ŏ��Ɍ���
�@�@ ���T�v�Q�g�Ȃǂ̗��t���������ď㍀�̏ڍׂ�o�߂��q�ׂ�
�@�@ ������̎��ⓙ�ɉ�����
�@�C �����E�ӌ����q�ׂ�c�c���̏ꍇ���e�ƁA�͂�����藣���Č���
�@�D �I���c�c�͈ȏ�ł���Ƃ���
�@(2) ���`�Ƃ��Ă̕�
�@�O���̂悤�Ȍ`���ɂƂ��ꂸ�A�ԈႢ�̂Ȃ��������R���p�N�g�Ɏ�ۂ悭�`����`�̂��̂ł���B�v���C�x�[�g�Ȑ�����ʂł͈�ԑ����`�Ƃ�����B�����ŏd�����ׂ��́h�R���p�N�g�Ŏ�ۂ悢�b�����h
�Ƃ����_�ł���B�o�߂��������A���`�̏ꍇ�͋�����邪�A�o�߂������b�͂Ƃ����璷�A�疟�Șb�ɗ���₷���B���R�`���̕ł����Ă��A��͂胀�_�E�����̂Ȃ��b������悤�S�����邱�Ƃł���B
�R�C�ɂ����āA�ׂ�₷�����Ƃ���
�@����������̂܂܂ɓ`���邱�Ƃ��̎g�������A�����Œ��ӂ��Ă����������Ƃ�����B
�@�h�ԈႢ�Ȃ��`���Ă���h�h���������̂܂ܓ`�����h�Ǝv���Ă��Ă��A���ʂ͊Ԉ���Ă��邱�Ƃ�����B�����������Ƃ����ɒ��ӂ������B
�@(1) �Жʂ����̕i���킴��R�j
�@�b�������Ƃ͎����ł����Ă��A�����̑S�̂�`���Ȃ��������߂ɁA���ʂ͊Ԉ�������Ƃ�`�������ƂɂȂ���̂ł���B
�@�h���l���h�Ƃ������t����B�j�̃v���X�ʂ��������ă}�C�i�X�ʂ�����Ȃ����߂ɁA�����͒j�̐l�ԑ�������Ď~�߂Ă��܂��Ƃ������̂ł���B
�u�����I�Ȏ�����`���������ł́A�S�̂̎�����`�������ƂɂȂ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�S���Ă��������B
�@(2) ���_�ɂ��i���ʂɂ�鎖�����f�j
�@�ڂ̑O�̌��ۂ��������Ă��̔w�i�𐄑����A�����Ƃ��Ď~�߂Ă��܂����̂ł���B
�i���A�w�����x�\�������Ȃ���w�Z�̕��ɑ����Ă����p�����āA�w�Z�ɒx�ꂻ���Ȃ̂ő����Ă����̂��ȂƎv�����ނȂǁj
�@������ʂƎ����Ƃ͍��v���Ă���ꍇ���������A�傫���O��Ė��ƂȂ邱�Ƃ������̂ŋC�����邱�Ƃł���B
�@�ɂ����Ă͎������ۂ����m���߂Ă���A�`����K����g�ɂ��Ă����������̂ł���B
�@(3) �f��ɂ��i����I���l���f�j
�@�f��Ƃ́h���X�ł���h�@�h���X�ɂ������Ȃ��h�@�h���X�̂͂����h�Ƃ���������̌`�ł̕\���ł���B
�@���̒f�肪���̖��ƂȂ�̂��Ƃ����ƁA�q�ϓI������`��������A����I���ʁi�D���E�����A�悢�E�����j����̉��l���f�������������ƂȂ邩��ł���B�i���̐l�͂悭�R�����̂�A�킽�����R���ꂽ�B������M�p������_����B�Ƃ������悤�ȁj
�@�҂̊�{�ԓx�́A��҂����������f�����邽�߂̎����������̂ł���B���������ĕ҂́u���ʁE�f��v����̔��f�ŁA���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𒍈ӂ������B
�@�܂��A�u���킴��R�v�́A�҂��Ӑ}�I�ɑ��삷�邱�Ƃ�����̂ŁA����҂͒��ӂ��K�v�ł���B
�@�@�@�@�@ 

�u�����̎d���v
�@�����͏��`�B�́A�����Ƃ���ƂȂ�b�����ł���B�����ł͑��i�K�̃R�[�X�ɂ����Ď��グ�Ă����B
�@���肩����������߂�ꂽ�Ƃ��A�܂���������킩�点��K�v���������Ƃ��ɁA���̎����𗝉������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�@���̒P���̍u�`�͈ӊO�ɓ���A�ƍu�t�͂悭�����B�Ȃ��Ȃ�u�`���e���悭�킩�点���Ȃ������Ȃ�A���g�̐����͂����邱�ƂɂȂ�Ǝv�����ނ���ł���B���̎��ꎩ���Ɋׂ�̂ł���B
�@�P�C�����̎��O����
�@�����ɂ����āA���O�ɏ������邱�Ƃ����߂���B
�@�@�������邱�Ƃ��\���������Ă���
�@�@�������A�܂��킩���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�A���肪�ǂ̂��炢�������Ă��邩��͂�
�@�@���肪�ǂ̂��炢�͈̔͂𗝉����Ă��邩��͂ނ̂͑�ł���B
�@�@�Ȃ��Ȃ�A�����͑��肪�������Ă���Ōォ��͂��߂�̂���{�ƂȂ�
�@�@����ł���B���肪���ɒm���Ă��邱�Ƃ�b���Ɓu���ǂ��b���v�Ǝv�킹�A
�@�@�����͈̔͂����Ƃ��납��͂��߂ẮA���肩��킩�点���Ȃ�
�@�@����ł���B
�@�Q�C�����̋�̓I�Ȏd��
�@�����@�͎�X���邪�A�ȉ��̍��ڂ͂ǂ̐������ɂ����������Ƃ��ł��Ȃ��v�f�ł���B
�@�@�͂��߂ɁA�����ǂ͈̔͂܂Řb������\���Ȃǂ��ė��������Ă����B
�@�A�������ď����悭�b��
�@�B���_��ς��Ęb���Ă݂�
�@�C��v�X�A�d�v�_�͌J��Ԃ��Ȃǂ��ċ�������
�@�D���ʂ̈Ӗ��ɂƂ�錾�t�E�p���p����
�@�E��������p����Ȃǂ��āA����̗������m���߂Ȃ���i�߂�
�@�F�����o�ɑi����ȂNj�̓I�ɘb��
�@�R�C�����̎��ɂ���
�@���Ԃ̓s�����炱�̍��ɋy�ׂȂ��������A�e�L�X�g�ɂ͎��̍��ڂ�����̂ŎQ�l�Ƃ��ꂽ���B
�@�@���e��f���ɊԈႢ�Ȃ��������邱�Ƃɓw�߂�
�@�A�b�ɂ͗��ʂɐ^�ӂ�����ł����肷��B������c������悤�ɓw�߂�
�@�B������Ŏ��₷��Ȃǂ��āA��������������悤�ɂ���
�m���n�@ ���̐}��Ɍ����Ȃ��ŁA���m�ɏ����Ă��炤�ɂ͂ǂ̂悤�ɐ���������悢���@�@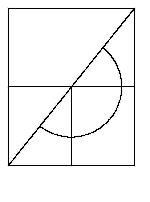
�@�m����n
�@(1) �w�������鎖���𗝉����Ă����x���Ƃɂ���
�@�@�������鎖�����悭�������Ă����ׂ��Ƃ����ƁA�Ƃ�����Ǝ������L���[��
�@�@�ڍׂɒm���ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����������A�����ł͂����܂ŗv��
�@�@���Ă��Ȃ��B�������b�����Ƃ���͈͓��ɂ����Ă͒m���Ă������A�Ƃ�����
�@�@�����ł悢�Ǝv���B�@
�@�@�ł́A�m���Ă��郌�x���Ƃ͂ǂ̒��x�������̂��낤���B
�@�@�����͌��t�����S�ƂȂ�̂�����A�������鎖�������t�Ō�����悤��
�@�@�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł���B������ǂށA���t�ɋl�܂�A�K�ȗp�ꂪ
�@�@��������Ȃ��A�[�I�ȕ\�����ł��Ȃ��Ȃǂ��A�Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ƃł���B
�@(2) �w���_��ς��Č����x���Ƃɂ���
�@�@����͓�����Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��B����̗���ɂ����A�������肪�������ɂ����Ǝv���A�����̕��@��ς��悤�Ƃ����̂ł���B
�@�@��̓I�ɂ�
�@�@���b�̏��������������Ă݂�
�@�@���p����p���ʂ̕\���ɂ���
�@�@�������ς��Ă݂�
�@�@������@�ɕς��āA����̂킩��Ȃ��Ƃ�����o���Ă݂�
�@�@�ȂǂƑ�������悢�Ǝv���B
�@(3) �w�����o��p���Đ�������x�ɂ���
�@�@�����̐�����ʂł͂ƂĂ��厖�ȍ��ڂ��ƒm���Ă��������B�����͌��t����̂ł��@�@�邪�A�����Ɍ��t�����ł͕\���Ɍ��E�����邱�Ƃ��A�m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@���������ăm���o�[�o��(nonverbal comunication)�i�g�U���U�蓙�܊���p������́j
�@�@����g���������@���S���Ă��������̂ł���B
�@�@��c�����}�`�̐������u�`�ɗp�������L���Ȑ����@�ł���Ƃ��������B
�@(4) �e�L�X�g�ɂ���������ڂɂ���
�@�@�����e�L�X�g�ɂ��鍀�ڂ����ł́A���ׂĂ̐�����ʂ��t�H���[�ł��Ȃ��B
�@�@�u�킩�点��v���Ƃ�ړI�Ƃ���b�̂͂��炫�́A�ق��ɂ܂���������̗v
�@�@�f������A�e�L�X�g�ɂ͎�Ƃ��@�鍀�ڂ��������̂��ƐS���Ă������Ƃł���B
�@�@�Ⴆ�e�L�X�g�ɂ��鍀�ڂ́A�w���m�E�_���x�̐��E�ɂ����Ă͗L�������A
�@�@�w��E��O�x�̐��E�ɂ͕K�������L���Ƃ͂����Ȃ��B�u�킽���̋C������
�@�@�킩���Ă�v�Ƃ��u�킽��������Ȃɋꂵ��ł�̂ɁA�ǂ����Ă킩���Ă���
�@�@�Ȃ��̂�v�Ƌ���ł��A�����荇���Ȃ��ʂ͑��X����̂ł���B��������
�@�@�w��E��O�x�̐��E�ł̐����@�͍���̌����̉ۑ�Ƃ��Ďc��Ƃ����
�@�@����B
�@�@�@�@�@ 

�@�@�u�l�ɍD�����w�́v
�@�]�_�ƂƂ��Ēm���Ă��������呠���̂��Ƃ���͂��߂����B
�@�����o�ŕҏW�҂ł��������A���鍑����b��Ɍ��e��Ⴂ�ɍs�������Ƃ��������B���e�͂��炦�����A���̂Ƃ��̃}�i�[���悭�Ȃ��������Ƃ����b�v�l���璉�����ꂽ�Ƃ����B
�u���Ȃ��͂��Ⴍ�������Ȃ��ł��傤����\���グ�܂����c�v
�ƌ����A���̂悤�ɋ�����ꂽ�Ƃ����B
�u���߂Ă̂������ɍs�����ڊԂɈē����ꂽ�Ȃ�A���̉Ƃ̐l���o�Ă���܂ł͈֎q�ɍ����Ă���̂ł͂���܂���B�Ƃ̐l�Ɋ��߂��Ă��������̂ł��B���ꂪ�}�i�[�ł��B���̂������͕ǂɌf�����Ă���G�Ȃǂ��ӏ܂���悢�̂ł��B�v
�@�ƌ���ꑐ�����͑傢�ɒp���������Ƃ����B���̌㓯���d���ŁA�O�H��s�̓c�������K�˂��Ƃ��́A������ꂽ�}�i�[������ĉ������̂ł���B����ɂ��ꂩ�璆�R�f������K�˂��Ƃ��ł���B
�u����A�҂��Ă���v
�@�Ƃ����Ȃ芽�}���ꂽ�̂ł���B���Ζʂł������̂Łu�Ȃ��H����قǁv�Ǝv�������Ă݂�ƁA
�u���͌N�͂ǂ������l���킩��Ȃ��̂ŁA�c������ɕ����Ă݂��B����Ɨ�V�������D�N���ƌ���ꂽ�̂ŁA�y���݂ɑ҂��Ă���v
�@�Ƃ������Ƃ������B
�@�}�i�[����邱�Ƃő������́A�c�����⒆�R���Ƃ����r�b�O�}���ɍD���ꂽ�̂ł���B
�@�킽���̓}�i�[�Ƃ������t���g�������A�{���̓}�i�[�Ƃ����\�ʓI�ȓ���łȂ��A���̉��ɂ���u�������A�Љ�l�Ƃ��čD�܂������������グ�邱�Ɓv���l�ɍD���������Ƃ���Ȃ��Ƃł���ƌ������������̂ł���B
�@�l�ɍD�����Ƃ������Ƃɂ��āA�킽���͋^�₪�Ȃ��ł��Ȃ��B
�@�D�����l�͑S�Ăɂ����Ă悭�A������l�͂��ׂň����̂��ƍl����ƁA�^�����������Ȃ��B���Ƃ������Ă��A�l�̂��߂ɉ������Ȃ��l�Ȃ�Ώ\���]�������̂ł͂Ȃ����B�����l����ƁA�D����邱�Ƃ����厖�A�D����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃɂ́A�����Ȃ��̂ł���B
�i���ӎҒ��C�I�����l����Ƃ悢�B�I�����ɐl�C�̂���l���A�K�������悢�����ƂƂ͂�
���Ȃ��B�܂��]���͈����Ă��s���̂��߂ɐs�͂��Ă���鐭���Ƃ������̂ŁA�u�t�̎咣
�͂悭�킩��B�����I�����Ɏx������Ȃ���ΐ����ƂɂȂ�Ȃ����Ƃ������ł���B�܂�
�[�I�ȗ�ŁA�ٔ����⌟���͔퍐�ɍD�����K�v������̂��A�ƍl���Ă݂�Ƃ悢�j
�@�l�ԊW�ɂ͂Q�̌`������B
�@������𗬂̐l�ԊW
�@�������𗬂̐l�ԊW
�@�ł���B
�@����𗬂́h�D���A�D�����h�̐l�ԊW�Ƃ����悤�B
�@���Ė����𗬂́A�h�ӔC�i���˂Ȃ�Ȃ����Ɓj�h�Ɓh�����i����Ă悢���Ɓj�h����݂���l�ԊW�ł���B���������Ė����𗬂̐l�ԊW�́A���Ƃ������Ă��ӔC�ƌ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@�l�ɍD����邱�Ƃ̑�������グ��Ƃ��́A�����ƍL���A�l�Ԃ̂���ׂ��p������Ղ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ킽���͎v���̂ł���B
�@�����̃e�L�X�g�ł́A�l�ɍD�����w�͖@�Ƃ��Ĉȉ��̂��Ƃ��o�Ă���B
�P�C�g�����S�������@�|�@����̐S���ω����@�m���đΉ����邱��
�Q�C����̉��l��F�߂�@�|�@����̒����������]������
�R�C�悢������ɂȂ�@�|�@����ɑ��A�����̂悢������ɂȂ邱��
�S�C����Y���Ȃ��@�|�@����̐S�ɗn������邤�ȏ_�a�ȕ\��Őڂ��邱��
�m�Q�l�n
�u�f�[���E�J�[�l�M�[�v�ɂ���
�@�����炭���E���Ǝv����b�����������A�A�����J�ɂ����ĊJ�݂����l�B
�@1912�N �b���������i�f�[���E�J�[�l�M�[�E�R�[�X�j���A�����J�ŊJ�n
�@1963�N ���{�ɂ����ď��߂ăf�[���E�J�[�l�M�[�E�g���[�j���O���J�ÁB
�@2005�N ���{�����E�f�C�E�Z�~�i�[���J�n
�@�o�Ő}���Ƃ��āA�w�l�����x�w���͊J����x�Ȃǂ͖����Ȃ̂Ő����������B
�@�@�@�@�@
�@�@�@ 
�@�@
 |
|