| 三月頃から、新刊本を読まなんだんだけれど、前回を作り終えて(『わん声・・』なんぞを作ったりもしたけれど)ボケ~としていたら五月の黄金週間もいつの間にか過ぎてしまい、店番中の暇で退屈を乗り切る為に、六冊程みつくろって注文したのがこのページの本。(八冊載せているけれど、棚に並んでいたのを購入) |
 |
『退屈の小さな哲学』 ラース・スヴェンセン 著 鳥取 絹子 訳 集英社(新書) 2005年4月20日 初版発行 |
『退屈の小さな哲学』 これまで一部の哲学者を除いてまともに考察されて来なかった「退屈」を著者は学際的に「問題」「歴史」「現象学」「倫理」と新書一冊故に浅く論を進める。 浅くと言っても哲学・文学・心理学・社会学の素養に乏しい者からすれば・・・(つまり私ですが)・・・所々「???」だった。 でも、各章「!!!」の文章が点在する。 例えば 『退屈では、時間はもちろん克服されたものではなく、そのなかに閉じこめられる監獄だ。退屈は死に似ているが、この二つは矛盾する関係でもある。・・・(略)・・・退屈は有限性と無に関係している』 さまざまな退屈の類型学の中で著者が選んだものは ① 状況の退屈・・・誰かを待っている時。授業中など。 ② 飽和の退屈・・・同じものがありすぎてすべてが平凡になる時。 ③ 実存の退屈・・・魂に中身がなく、世界が空回りする時。 ④ 創造の退屈・・・内容よりも結果で特徴づけられるもので、何か 新しい事をしなければならないと自己に強いる時。 実存の退屈の場合『実体験そのものが貧しくなったと理解すべき』で、逃れる為には『“体験”を身につける時間を取』るべきなのに、多くの人は『より強い「極端」な新しい冒険に』向かっていく。 因みに、家の嫁はんは定期的に(?)”創造の退屈”が訪れます。 典型的な戦後成長期の中で”良い子”だった見本ですね。 結局この種の本を手にする大多数の「た い く つ だぁ~」と思っている読者に著者は、退屈は意味の欠如から来るが『深い大きな意味の欠如と言っても、存在のすべての意味が消えているということではない。大きな意味欠如に集中すると、他のすべての意味を隠すことになり、僕たちに現実の世界が崩壊した印象を与えてしまう。深い退屈の発生源は、僕たちが小さな意味で甘んじなければならないときに、大きな意味を要求することにある』と書き、ぶっちゃけた話、『退屈には解決方法がないのである。』 まぁ、確かに類型の①を除けば解決方法なんて、まぁないわな。 あるとすれば”老荘”でしょうけれど、こんな本を手にしているようでは・・・・ね。 |
|
 |
『スバルを支える職人たち』 清水和夫・柴田 充 著 小学館 2005年6月20日 初版発行 |
『スバルを支える職人たち』 スバル1000が発売された1966年、わたくしはまだ紅顔の美少年でして、級友の”クルマ好き”達と大阪港の見本市会場で行われていた自動車ショーにカメラをもって行き、インボード・ブレーキのおかげでセンタービボット方式にしたと言うカタログを確かめるべく、這いつくばって見た覚えがあります。 その数年後、スバル1300Gにちょこっと乗る機会があり、下り坂の正面T字路に向かってぶっとばして行き、左に曲がろうとヒル&ツゥでギアを落としていったものの間に合いそうにないので少し強めにブレーキをかけハンドルを切った・・・曲がると思ったのに・・・前加重の思い前輪駆動車、しかも下り坂・・・真っ直ぐ進み、あわや、壁に・・・あわわあわあわ・・・と。 前輪駆動車に慣れていなかったのが悪いのだけれど、以来、「スバル車は買わずに指を銜えて見ているモノ」と決めた。 かような次第で正調”スバリスト”ではないけれど、スバル車の技術陣には心からエ~ルを送る、隠れスバリストのわたくしは、月刊誌「ラピタ」にこの本の広告が載せられるやいなや即刻注文した。 内容は、つまらんもんです。 「大人の少年誌」と称されるラピタに書いているからののでしょうが、書かれている水準が低いのです。 技術陣の人々を取り上げて褒め称える内容ですから・・・まぁ、仕方ない。 『浮と游』の「おまけ」のページの始めの方に『かって、Fー1ブームだった頃、四駆ワゴン車で有名な某重工製の水平対向12気筒エンジンを使ってFー1マシーンを製作すると言う話が有り、』なんて書いた事があるけれど、『頂点レースに挑んだ幻の水平対向12気筒』の取材の打診は芳しくなかったそうだ。 エンジン屋と呼ばれる自動車会社(日本ではHONDA)になれない事由がそこに見て取れる気がする。 |
|
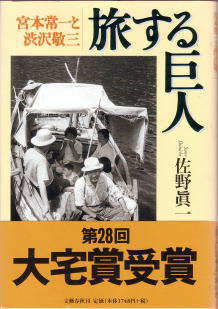 |
『旅する巨人 ・・・宮本常一と渋沢敬三』 佐野眞一 著 文藝春秋社 1996年11月30日 初版発行 |
『旅する巨人・・・宮本常一と渋沢敬三』 本屋のお客さんに八十歳になろうかと思われるお婆さんが「近畿民俗」の会員で、財団法人新日本宗教団体連合会(=新宗連)や近畿民族の会報に時々自分が書いたものが載ったのを持ってくる。 その内容は、大阪庶民の民具に関するものや習俗に関するもので、柳田国男さんの書かれた物とは「どこか違うなぁ~」と思っていた。 『旅する巨人・・・宮本常一と渋沢敬三日本縦断』を読んで「なぁんだ、そうやったんかいな」と分かった。 どうやら「近畿民俗」は昭和八年九月に宮本常一さんが始めた「口承文学」がその始まりらしい。(以後「大阪民俗談話会」そして「近畿民俗談話会」と名称変更される) ひたすら自分の足で歩き回り、柳田国男さんや折口信夫さんのように神や霊魂に関心が向かわず、庶民の暮らしに目を向け、二人のように大学を出ていないが故に、彼の書く物は既成の民俗学者から見れば「アカデミックではない」との烙印を押されるが、柳田国男さんのように『個別の伝承者に頼りながら、個を消去』するものではなく、それは地域性においても個別の土地を日本一般に普遍化するものではなかった。 日本資本主義の基礎を築いた渋沢栄一さんを祖父とする渋沢敬三さんは渋沢財閥の御曹司であり、日銀総裁・大蔵大臣を務めた経済人でありながら、自身も民俗学者として一流人であり彼が民俗学の分野への物心両面に支援した功績は大きく、バブル期の企業の文化事業支援活動(メセナ)とは大きく異なる。 (渋沢栄一さんは”養育院”の設立者でもある) 前回の『気楽な旅行者には”時間そのものを忘れさせる島”だった 後編』に稲垣尚友さんを引用したけれど、この本に彼が出ていた。 近畿日本ツーリストが出資し、開設された「日本観光文化研究所」所長の宮本常一さんに反発を覚えた稲垣さんなのに、臥蛇島に渡ってやった事は宮本常一さんが見たら喜ぶような記録を残したと。 宮本常一さんの著書を読んだ事はないが、その名前はこれまで嫌になるぐらい色んな本で眼にしてきた。 しいてこれからも著書を読もうとは思わない。 これほど日本中が均一化されつつある今、個別の伝承・習俗・風習すら何処か曲げられているように思える今、彼が記録に残そうとした”民俗”は個別の地域性と言う事では余程の孤島でもない限り・・・これとて疑問だが・・・広義の地域性文化は別にして・・・なさそうだ。 |
|
 |
『死は共鳴する ・・・脳死・臓器移植の深み』 小松美彦 著 勁草書房 1996年6月20日 初版発行 |
『死は共鳴する・・・脳死・臓器移植の深み』 日本移植学会前理事長 太田和夫さん。 『死はあくまでも個人的な現象ですね』 つまり”死”は個人の所有対象であり、脳死の選択は個人なんだから”死の自己決定権”は個人に属する。 この 「脳死者は、ただのモノなのだから・・・」と言う脳死・臓器移植推進論者に対して、感覚的批判から筆者はこの死は「個人閉塞した死」の暗黙の了解だと捉え、脳死と心臓死の選択(=死の自己決定権)は自由・権利・個人等の観念と対応する為に抵抗なく受容れられるが、そこには”共鳴する死”が隠蔽されていると主張する。 医学の言葉で語られる”死”は死を一般化した無人称の”死”であり、そこにはあるのは量や数の規格化された”死”である。 しかし『死が、死にゆく者と看取る者、死んだ者と死なれた者との関係において存立するなら、その関係の強さや質に応じて、人間個々人から死までの距離は異なるであろう』 それは、脳死をめぐる”死の自己決定権”を受諾する事により、自己の”死”を保持していたのだが、実はこの選択すると言う”自由”を得る事で”自己”を失っているのだ! 厖大な脳死・臓器移植の文献をあたり、筆者は他の反脳死・臓器移植論者とは異なる視点から本書を紡ぎだした。 もし、筆者が書くように脳死判定自体が百%ではなく、まだそこに居る他者に”意識”が残っているのならば、もしくは戻れる可能性があるとするならば、その時点において他者に脳死判定を下す者にはなりたくないし、するべきではない。 人はすべからく小心者であるべきなのだと思う。 場は異なるが、刑事裁判での死刑判決を下す恐ろしさと通じるものがある。 昨年末、仲間の一人が死んだ。 奴は突然の”死”だったので、奴の”死”を受容れる時間的なモノはなかった。 元気で泳ぎが好きな奴から、一転「死よりましてん・・・」と告げられた出来事だった。 儀式としての告別式の場において、死と対面した。 何か消化不良を起しそうな気分だった。 今春、もう一人死んだ。 奴には亡くなる少し前に会っていた。 告別式当日、式場ではなく自宅で奴の死と対面した。 包丁を持たすと職人並みの腕前を持つていた生きていた頃の奴と、この死んだ奴との対面は、筆者が言う”共鳴する死”だったのかも知れない。 ”死”自身は確かに個人的なモノなのだろうが、”死”そのものの受容れは個人のみに帰するものではないとつくづく思った。 その数ヵ月後に読んだ本なので、合理主義では片付かない”死”が整理できたように思う。 |
|
 |
『殴られ屋』 晴留屋 明 著 幻冬舎(文庫) 2004年12月5日 初版発行 |
『殴られ屋』 二十歳でプロボクサーになり戦歴は四勝八敗。六回戦になってからは、一勝もできずに引退した後、電気工事の会社を始め、会社は大きくなって行ったものの、人が良いのが玉に瑕でバンザイし、更に知人の負債も抱え込む羽目におちいり総額一億五千万円の借金を、自己破産で処理すりゃ良いものを晴留屋さんは、殴られ屋稼業にて返済するべく新宿歌舞伎町で開業し始めた。 殴られる以外に生きる道を見つける事も出来ず、殴られて死ぬかも知れない場所に立ち続ける。 この不器用な男の生き様に共感を覚える事はできない。 自虐性のご開帳物なんだけれど、彼の明るさが、底抜けの爛漫さが、根っからのものだとはとても思えない。 「こんな人もいるんだ!!よ~し、自分も頑張るぞ~!!」って思う人もいるかも知れないけれど、誰もが晴留屋さんのようなソロバンを持っているわけじゃない。 自前のソロバンを持たずにいる者は読むべきではない。 愛する家族と暮らしたいと願いつつ、その実、一緒に暮らす方向に少しも近づいて行かない彼の美学。 ”愛すべき阿呆”は好みだが・・・晴留屋さん、あんたは・・・違う。 |
|
 |
『となり町戦争』 三崎亜記 著 集英社 2005年1月10日 初版発行 |
『となり町戦争』 戦争行為当事者でも、前線でドンパチしている者なら戦傷もすれば戦死体も見るだろうけれど、艦砲射撃なら、爆撃なら弾が爆弾が落ちて炸裂し阿鼻叫喚の地獄図の様はその砲手なり爆撃機の搭乗員なりの個人の想像力で補うしかない。 『となり町戦争』では更に進み、目の前においては何も変わらない戦争を書く。 町からの広報に小さく書かれた「となり町との戦争のお知らせ」により主人公は開戦を知り、ある日、「となり町戦争課」から「戦時特別偵察業務者に任命」され、戦時下の日々をおくる。 さほど変わらない日常生活なのだが、広報には”戦死者”が載せられ、現実としての戦争は無機質な数と表され、これ自体は今も昔も変わらない。 非日常的な”戦争”を、生活の中にしっかりと入り込んでいるもののそれを感じる事がない非現実的な”戦争”として捉える作者の”戦争観”は、現代における戦争の捉え方として面白い。 余談だが、作者が地方公務員だからなのかどうか知らないが、戦時下における公務員の淡々と職務をこなす優秀さの描写には笑える。 多分、太平洋戦争中もこのような優秀な下級・中級公務員がてんこもりいたのだろう。 日常性の中にいつの間にか入り込んでいる現実としての”戦争”に恐怖感を覚えるが、この作品を読む限りでは”戦争”そのものへの恐怖感を現実のものとして、例えば「戦争反対!」と叫ぶ者を生み出す事はないように思う。 それは例えば、仮装世界で遊ぶ”戦争”を楽しむ者に、想像力として”戦争”を捉える事が出来るかどうかにつながる。 その意味で、もう一歩、不条理としての”戦争”を書いて欲しかった。 |
|
 |
『カヌー犬・ガクの生涯 ・・・ともにさすらいてあり』 野田知佑 著 文藝春秋社(文庫) 2005年4月10日 初版発行 |
『カヌー犬・ガクの生涯・・・ともにさすらいてあり』 一九八四年八月、千葉市生まれ。親父はシェパード系お袋は日本犬の雑種。 同年十月、野田知佑さんと暮らしだし、”ガク”と呼ばれる。 以後、日本国内はもとより、アラスカ・カナダ(八回)メキシコ(一回)を歴訪。 その間、表立っているものだけで、五木村でポインターとの間に三頭、横浜で雑種との間に六頭、北九州でG・レトリバーとの間に十頭の仔犬をもうけ、一九九七年二月、鹿児島にて死亡。 死因はフィラリア。 享年十四歳。 二千二年四月現在、野田知佑さんは、徳島県日和佐町にてガクの息子二頭と暮らし、寒い日には『ガクの皮で作ったチョッキを着』ているそうだ。 どのような環境で育つかで、人も犬も様々な経験を積んでいくのだろう。 犬としては、まぁ並みの環境に置かれたとは思えないガクと、ガクをそのような環境に置いた、これまた並みの生活ではない野田知佑さんとの一人と一頭の一四年間の物語は確かに「・・・ともにさすらいてあり」と思うけれど、浮と游を相方にして「・・・ともにさすらいてあり」なんて書ける経験を積む事など、まぁ、無理。 でも、『この頃からガクは激しく咳をするようになった。体力が衰えるとフィラリアの症状が出てきたのだ。彼が亀山湖にいた頃、ぼくは犬に関してまったく無知で、予防薬を飲ませていなかった。それでガクはフィラリアにかかった。一度これにかかると、あとで治療薬を飲ませても完治はしない。ぼくの手落ちである。』 なんて、悔やんでも遅い経験を積む事のないようには出来た。 もっとも、ガクは野田知佑さんを憾んではいないと思うし、野田知佑さん自身、ガクとの暮らしでわんこさんのいない暮らしは出来なくなっているように思う。 まさに「・・・ともにさすらいてあり」だったんだろう。 |
|
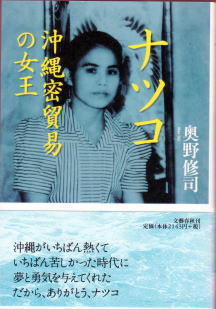 |
『ナツコ ・・・沖縄密貿易の女王』 奥野修司 著 文藝春秋社 2005年4月10日 初版発行 |
『ナツコ・・・沖縄密貿易の女王』 与那国島に渡った時、「戦後、この島は密貿易が盛んだった」と耳にしていたが、「そりゃ、そうやろなぁ。何せ台湾はそこに有るんやさかい」って思ったぐらいでそれ以上の興味は湧かなかった。 ただ、”密貿易”ってのはお上が言うコトバで、商人からすりゃ非合法とは言え、あくまでリスクも多いがその分うま味の多い”商売”。 ましてや、取引していた商品は阿片の如く国を滅ぼすモノではなく、戦後の沖縄が必要としていた、言わば生活物資。 類稀なる商才と博才と統制力の持ち主”沖縄密貿易の女王”と呼ばれていたナツコなる人物をこの本で初めて知った。 筆者は文献資料なんぞがある訳ない”密貿易”の様を、今じゃ高齢化した関係者達を捜し出し、且つ方言の壁を何とか乗り越えてこの一冊にまとめ上げた。 勇猛果敢さは並みの男達を平伏させるほどで、冒険小説として読んでも通用しそうなナツコのわずか三十八歳の生涯。 彼女は無秩序状況の中で「沖縄のために」と胸をはって警察に答え、得た利益の配分を公平に行う。 アナーキストの登場だった。 ナツコと言う人物が戦後の混乱期にいた事を、沖縄の人達は誇りに思って良い。 |
|