
トップページ ( 正確な新ボーア模型 )
電子スピンは実在しない。
スピン軌道相互作用は幻想。(14/8/17)
(Fig.1) 光子は 波か粒子か? → 明確な回答を避ける → 永遠に未解決。

このサイト や Scientific american などを見ると分かるが、21世紀の今になっても 私達は 単純な2重スリット実験や "光は波か粒子か?" という 基本的な質問から永久に脱却できないでいる。
ということは、非実在的な量子力学を信奉している限り、 今から1000年後でさえも、"光は波か粒子か?" という質問を 現在と同じように 延々と繰り返していることになってしまう。 恐ろしいことである。
基本的に このページに示したように、光子を扱うすべての実験は 光の 波動的な性質 (= 干渉、位相、偏光 ) に依存していると言っていい。
実際、 このサイト (= 最初のほう ) に載っているように、ノーベル賞受賞者である ラムシフトの ラムでさえ、"光子という粒子は存在しない" と断言しているくらいである。
(Fig.2) 架空のスピン、準粒子だらけ。 → 科学がストップ。 → 量子コンピューターがある? = カモフラージュ。

量子力学は 非現実的なスピン、多世界 (= シュレディンガーの猫 )、 架空の 準粒子 に完全に依存している。
当たり前の話だが、架空の粒子などに依存し続ける限り、科学の追求や進展はストップしてしまうことになる。
つまり、量子力学によって その上のすべての現代科学の発展が阻まれてしまっていることになる。
この 不都合な事実から 目を逸らすために 作られた架空のターゲットこそが 所謂 量子コンピューター と 量子もつれ (= "エンタングル" ) なのである。
量子もつれは 超光速の無気味なリンク ( ← もちろん 非現実的 である ) のことであり、量子コンピューターにとって 必須の概念であるため セットで考えていい。
そのため、量子もつれや 量子コンピューターのワードは 現在の様々なジャーナルに 引っ張りだこの状態で 見ることができる。
で、肝心の量子コンピューターの実態はというと、 このページ や このサイトにあるように、わずか数個の原子やビットの状態でしかなく、かつ 10-9 - 10-6 秒 (= 1 ns - μs ) という わずかな時間で 壊れてしまい、 まったくもって 実用化には程遠い状態である。( そもそもコンピューターの姿形はまったくない。)
(Fig.3) 光子は 水中では 光速以下に減速して、空気中に戻ると また加速?

ご存じのとおり、特殊相対論によれば、光子の速度は 必ず 光速の "c" でなければならない。
しかし例えば、水中では この光速度は "c" よりも ゆっくりになる。
そして 水中から空気中に再び出てきたとき、この光子は加速 (← ? ) されて、もとの光速度に戻ることになる。光子というのは 非常に 便利な粒子であることが分かる。
もし 光子が本当の粒子だとしたら、こんな都合よく媒質に応じて、減速、再加速するのは不自然極まりない。
致命的なパラドックスを考慮すれば、光子は 周囲の
媒質によって 影響を受ける 電磁波 と考えるのが 至極 自然なことである。
(Fig.4) 光子が電子から放出 → その時の加速度が "無限大" !
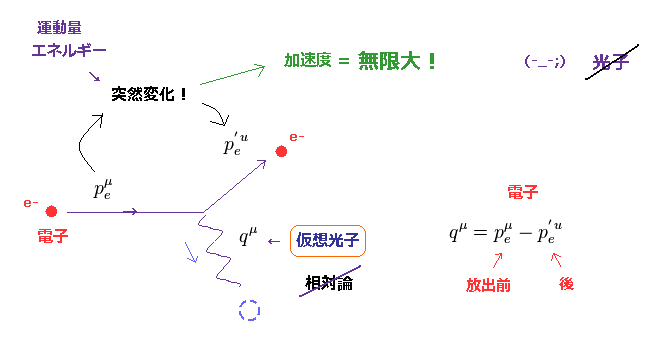
基本的に 場の量子論によれば、光子の現象は ファインマンダイアグラム によって記述されることになる。
驚くことに、放射 ( もしくは吸収 ) された光子と 電子が エネルギー・運動量保存という基本的な法則を満足するとき、この光子は 必ず仮想光子 というものになる。
このページ や このサイト にあるように、この仮想光子は "タキオン" のように 特殊相対論に 従わない。これが "仮想" と呼ばれる所以である。
さらに 光子が 電子から放出 ( もしくは 吸収 ) されるとき、この電子の運動量とエネルギーは 突然変化する。
これはつまり、この時点での電子の加速度は 無限大 ということになり、あり得ない現象であることが分かる。
私達は この変化の様子を その場、ドブロイ波全体も含めた ダイナミックで具体的かつ現実的なモデルで置き換える必要がある。
(Fig.5) 単一光子検出器は 光子の "粒子性" の証明には まったくならない。
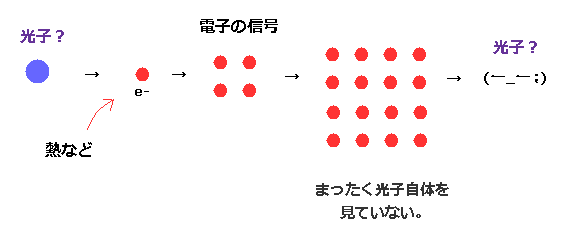
光子が"粒子" であると主張する唯一の実験的根拠は 単一光子検出器 にあると言っていい。
しかし、この単一光子検出器は 名前とは裏腹に 光子そのものを観測しているわけではない。それは 光電効果を利用して 光によってはじき出された電子信号を観測しているだけである。
また、単一光子自体を直接生成することはできない。
レーザーなどを弱めていって 光子検出器の電気信号が とぎれとぎれになるくらいになったときを 光子だと推定しているだけにすぎない。 このサイトを参照のこと。
結果的に、光子が粒子だという 直接的な実験的証拠は まったくないと言っていい。
一方で、光子の波としての性質を示す実験的証拠は 山のようにある。.
(Fig.6) ベルの不等式の破れは 現実世界ではあり得ない。

2つの もつれた光子対の間には 超光速の無気味なリンク (= エンタングルメント ) が存在すると言われている。
イオン対、超伝導量子ビットなどの 光以外のものは それらの間の距離が 余りにも近すぎる ( ~μm )ため、超光速のリンクの証明自体不可能であり、なされていない。
互いに反対方向に飛んで行ったペアの光子(電磁波)の片方 (光子Aとしよう) が 偏光板 A を通過した瞬間に 超光速のシグナルが もう片方の光子 (光子B) に伝わって 離れた この光子B の偏光(電磁波の振動方向)が 偏光板 A と同じ向きに模倣してなってしまうというものである。
もちろんこの過程は光速をいくらでも超えていていい=非局所性。(瞬時だから)。
このページに示したように、光子という幻想をやめて、 古典的な電磁波を用いれば、このベルの不等式の破れを 局所 かつ 実在的な現象として説明できる。
トリックは 単一光子検出器の 検出閾値にあると言っていい。
要するに、アインシュタインの言ったとおり、ファンタジックな 超光速の無気味なリンク自体 実在するはずがないのである。
(Fig.7) 光子が粒子なら 2つに分離できるのか?

このサイト (p.2) や このサイト (p.11) にあるように、
"もつれた" (← 非実在的であるが ) 光子対は パラメトリック下方変換という方法で生成する。
この過程では、 λ の波長を持つ光子が ある結晶中に入ると、 2つの 同一の波長 2λを持つ 光子対に分裂する。
つまり 全エネルギーは保存されるというわけである (= それらの振動数は半分になる )。
しかし、 光子が粒子だとしたら、こんなに簡単に分裂できるわけがないのだが、奇妙としか言いようがない。
生成された光子対の1つが 水平方向に偏光 (= H ) した光であり、もう1つは 垂直方向に偏光した (= V ) 光である。
見ての通り、この光子対というのは 明らかに古典的な電磁波そのものであるのだが、彼らは 不思議と "光子" というワードを使用したがるのである。
(Fig.8) 2つの異なった光子間の "偏光状態" (= V もしくは H ) の テレポーテーション。.

基本的に、量子テレポーテーションは スタートレックにあるような 実際の物体自体を テレポートすることは 不可能である。
それは 単なる偏光状態 (= 垂直 もしくは 水平 ) などの情報を 光速以下の速度で送るだけにすぎない。
Nature 1997 や このサイト にあるように、 光子 1 を 2つの光子3,4に分裂 (← ? ) させ、そのうちの1つが 垂直偏光 (= V ) の光で、もう一方が 水平偏光 (= H ) の光になるようにする。
そして 光子1の偏光状態の情報を 光子4にテレポートさせるわけである。
結論から言って、このテレポーテーション実験は 古典的な電磁波の性質を利用しただけで、何の不思議性もない。
(Fig.9) 水平、垂直偏光の光同士は 干渉して打ち消し合うことはない。

例えば、光子1が 垂直に偏光し、光子2が 水平に偏光している状態を考えてみる。
このケースでは、これら2つの異なった方向に偏光した光同士は ビームスプリッターのところで 互いに干渉し合うことはない。
なぜなら "水平" と "垂直" 方向に偏光した光は 互いに 直交しており 独立しているからである。
結果的に このケースでは A と B の両方の検出器で 2つの光子とも検出することができる。
(Fig.10) 2つの光子が検出されたとき、 光子 1 → 4 のテレポートが起きた !? ← 古典的に説明可能。

ここで、A と B の両方の検出器それぞれで 各光子を検出できたときを条件として 選ぶ。
このケースでは、これら2つの光子 (= 電磁波 ) は 互いに垂直方向のため 干渉して打ち消し合うことは ない。よって これら2つの光子とも 無事に生き残るわけである。
Fig.7 と Fig.8 で述べたように、光子 3 と 4 の偏光は 必ず 互いに垂直方向を向くように生成してある。
つまり、この条件のとき、光子1の偏光 (= 垂直方向 ) は 光子4の偏光 (= 垂直方向 ) と 光子3 (= 水平方向 ) を介して、同じになる。
このため、彼らは この結果は 光子1から 光子4へ 偏光状態が テレポートされたと主張しているわけである。
ご覧の通り、この結果は 奇妙なテレポーテーションでも何でもない。光の干渉に基づく 古典的な現象にすぎない。
(Fig.11) テレポーテーションなし。

Fig.11 では、光子1と3の両方の偏光が 同じ (= 水平方向 ) 場合である。
偏光状態が 同じとき、これらの光は ビームスプリッターのところで 互いに干渉し合うことができる。
(Fig.12) H -- H の偏光 → "打ち消し合う" 干渉 → 1つの光子のみ検出。

2つの光が 同じ偏光状態 (= 水平方向、H と H ) にある時、それらは 互いに干渉し合うことができる。
ビームスプリッターを調整して これら2つが 干渉して打ち消し合うようにする。
結果的に、このケースでは 干渉による打ち消し合いによって、A と B の両方の検出器で同時に2つの光子を検出することが 不可能になるわけである。
(Fig.13)

そのため、検出器 A か B のどちらか 一方のみで 光子が検出されたとき、光子1と3は 同じ偏光状態にあったことが分かる。
結果的に、光子1と4は 異なる偏光状態ということになり、テレポートは起きていないということになる ( 光子 3 と 4 は 互いに直交した偏光状態にあるため )。
ご覧のとおり、この実験は 2つの電磁波の古典的な干渉効果を示しただけに過ぎない。 このサイト (p.10) も参照のこと。
(Fig.14) 中性子の体部とスピンが分離? ← "チェシャ猫" は本当か?

様々なニュースサイト ( ここ、ここ、ここ、 ここ ) によれば、中性子を用いた実験で、不思議なチェシャ猫状態が観測されたとしている。
しかし、この種のメディアの文章は 肝心な部分を書いておらず、一般人が読んでも さっぱり実験の内容を理解することができず、ただ 量子力学の ファンタジー性 を煽ることだけに集中している傾向がある。
彼らによれば、この実験で 中性子の "体部" と "スピン" 部分が チェシャ猫のように 分離できたと主張しているが、 このサイトのコメントにあるように この実験のトリックは ポストセレクション (= 事後選択 ) にあると言っていい。
(Fig.15)

この論文にあるように、中性子のビームを スプリッターで 通路 I と 通路 II に分離する。
磁場を調整して、通路 I の中性子が右方向のスピン、通路 II の中性子が左方向のスピンを持つように設定する。
検出器 H は 左、右両方向のスピン状態の中性子を検出できる。
一方、 検出器 O は 左方向のスピン状態の中性子のみ検出されるように、特殊な装置をその前に設置する (= 事後選択, ← ここがトリック )。
(Fig.16)

このとき、ある吸収体を 通路 II に置いた時、左スピンの中性子の数のみが 減少する。
結果、検出器 O で検出される中性子の数も減少することになる。
(Fig.17) 吸収体が 通路 I に置かれたとき、減少は見られない。

一方で、吸収体を 通路 I に置いたとき、検出器 O で検出される中性子の数には 変化は 見られない。
この結果は 現実的な視点からして 当たり前の結果である。
しかし この結果から 彼らは 中性子の体部が 通路 II のみに存在しているように見えるとした。
(Fig.18) 通路 I の中性子のスピンの向きを 通路 II の中性子と同じ向きにすると..

Fig.18 では、 通路 I の中性子のスピン方向の一部を 磁場を用いて 左方向に変えると、同じスピン方向を持つ両通路の中性子が 互いに干渉し合うことができる。
この干渉効果は 検出器 H と O の 両方で 検出することができる。
あなたがたは 点状粒子の"スピン" が どうして 中性子のドブロイ波の干渉に影響を与えられるのか 奇妙だと思われるに違いない。
このスピンというものが ある種の 軌道運動だと考えると、その動きの向きによる 中性子ドブロイ波の干渉に影響を与えることが可能で、自然と言える。
(Fig.19)

一方で、通路 II の中性子のスピンの一部が 右方向へ変化すると、この右方向のスピンは 通路 I の中性子と 干渉することができる。
しかし、上で述べたように、検出器 O は、 左方向のスピンを持つ中性子のみを検出することができる。
つまり、この干渉効果は 検出器 H でのみ観察することができる。
Fig.18 と Fig.19 から、あたかも 磁気モーメント (= スピン ) が 通路 I のみに 存在しているように見えるわけである。
このことが 彼らが この状態を "チェシャ猫" と呼ぶ理由である。
しかし 見てのとおり、これらの現象は スピンの方向と 検出器 O における 人為的な事後選択によって生じるトリックにすぎず、現実的な視点から説明可能である。
様々なマスメディアは 肝心な部分も隠すことなく説明して、一般の人々を間違った方向に誘導することを慎まなければならない。
中性子が 電子と陽子の混成物質であることは周知の事実である。
これら電子や陽子は その周囲の広い範囲にわたって、自身の電場を
広がらせている。
つまり これらの粒子が動くとき、この周囲全体の場も 移動 ( もしくは 伝達 ) する必要があり、これが 広い範囲にわたって ドブロイ波を生じる要因になると考えられる。
実際に、ドブロイ波の一種である電磁波は 電場と磁場で構成されている。
この実在的なドブロイ波が 粒子の干渉効果を引き起こすと言える。
(Fig.20) 赤い光線が緑の光線に影響を与える ← トリック。

この種のウェブニュースサイト ( ここ、 ここ、 ここ ) などは 超光速の量子もつれや、光子などを広めようとする傾向にあるが、こういう現実離れした概念を 人々に信じてもらうには なおさら 肝心な部分も含めて 包み隠さず伝える努力をしなければならない。
一般の人々が記事を読んでも 実験の内容がまったくつかめないという状況は すなわち マスコミとして重要な情報を伝えていないことと等価である。
じっさい、この実験は 超光速のもつれなどに頼らずとも、 現実的 (= 古典的 ) な理論によって 十分説明可能である。
オリジナルのこの論文にあるように、入射した緑色の光線が NL1 という特殊な結晶によって 黄色 (= c ) と 赤色 (= d ) の光線に分離される。
この赤色の光線が 物体の線上を照らしたとき、その位相が変化して、それにより、緑色の光線 (= b ) に 影響を与える。、なぜなら それらは同一方向の偏光状態にあるからである。
結果的に この相互作用が NL2 というまた特殊な非線形結晶内部での 黄色の光線 (= e ) の生成過程に影響を与える。
この影響の違いを最後の干渉効果としてとらえることによって 物体のイメージを再構成させているにすぎない。
ここには まったく 量子力学のオカルト的な要素もなく、現実的な視点 (= 古典力学 ) から十分説明可能である。
(Fig.21) DFT における交換 - 相関汎関数は "任意の"関数をとれる。

この種のウェブニュースサイト ( ここ や ここ ) では、量子力学の密度汎関数という手法によって 高度な分子計算が可能かのごとく説明するふしがある。
しかし この密度汎関数は ”魔法のような”方法でも何でもないのである。
このページにあるように、密度汎関数は 任意の 交換・相関汎関数に完全に依存している。
この肝心な部分を 彼らははっきりと伝えなければ 180°違った意味としてとらえられてしまう。
ようするに DFT には 予測能力は はっきり言って 何もないのである。
任意の汎関数の形を 調整しているだけにすぎない。

2014/8/31 updated This site is link free.