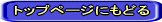松島泰勝「辺境島嶼・琉球の経済学」(『島嶼沖縄の内発的発展-経済・社会・文化』藤原書店2010.03.30所収)
松島泰勝「琉球人よ、目を覚ませ」(2006.10)
④松島泰勝「内発的発展による経済自立――島嶼経済論の立場から」(『地域の自立 シマの力(上)』コモンズ2005.7.30所収)
③松島泰勝「グローバリズムの中の琉球」を読む03.7.23
②グローバリズムの中の琉球/松島泰勝(『別冊環6号-琉球文化圏とは何か-』藤原書店2003)
①松島泰勝『沖縄島嶼経済史』(藤原書店2002)を読む
「内発的発展による経済自立――島嶼経済論の立場から」
1 「開発」の語られ方
2 沖縄社会のスピード化
3 島嶼経済論と内発的発展
4 節度ある生き方を前提とした「経済自立」
1 「開発」の語られ方
1972年から30年間にわたって、沖縄振興開発特別措置法や沖縄振興開発計画において、沖縄は「経済的に遅れている」とされ、開発の必要性が語られてきた。その理由は、沖縄の経済指標を本土他県のそれと比べると見劣りがしたからである。160以上の島々を有する沖縄は自然、文化上の多様性をもち、日本本土と異なる歴史、社会構成を有しているにもかかわらず、同一の経済指標が適用された。沖縄に欠けている点がことさら強調され、「未開発、貧困」地域として規定されたのである。また、沖縄の人びとも島の本来の豊かさに気づかず、「貧者」として政府への依存度を深めた。
日本政府は開発のための法律や計画を策定し、開発の手段と目的を定め、住民が歩むべき方向を指し示した。開発の語りのなかで、沖縄人は人的材料(人材)、島や海も開発の手段や対象とみなされるようになっていく。
沖縄の開発は、補助金の増大、消費需要の拡大、そして外部企業の投資が進めば、自動的に経済自立が達成されるだろうという、機械的・操作的社会観を前提にしている。また、沖縄という病人に開発という治療を施す機関として、沖縄開発庁が設置された。沖縄開発庁は、沖縄の非合理で非効率な部分を是正し、インフラを整備して島外から企業が投資しやすいような均質化した空間をつくろうとしてきた。
沖縄経済の特徴を示す指標として、「県民所得」「県内総支出」「経済成長率」などが用いられる。モノを購入すればするほど好況になると評価され、成長率が低いと、公共投資や個人消費の必要性が叫ばれる。しかし、支出や消費中心の経済は必然的に環境上のコストを増大させる。
財政支出、民間企業の設備投資、軍関係受取、観光収入などの県内総支出の数値を見ても、総支出のうち沖縄住民の手元にどれだけ資金が落ちたのかは明確ではない。経済指標が改善すれば自立度が高まるとされる。しかし、その場合、経済主体が地元企業ではなく、本土企業や外国企業であってもかまわない。基地関連の公共事業における沖縄県内企業の請負額は6割程度にとどまり、本土企業が米軍スクールバスの運行業務を行っている。基地や補助金は沖縄経済にとって不可欠という議論もあるが、むしろ本土企業と日本政府にとっての必要性のほうが大きいのではなかろうか。
沖縄の開発計画のなかで、「経済自立」が最大の目標とされてきた。しかし、どのような具体的指標をもって自立が達成されたと考えるのかは、明らかではない。失業率や県民所得が全国平均値になった時点をもって、自立したとみなすのであろうか。曖昧な「経済自立」論だけが先行して、人びとを開発に追いやり、生態系が破壊されているのが、沖縄の現状である。
沖縄開発庁は2001年、内閣府沖縄担当部局に組織替えされた。90年代後半に高まった沖縄の基地撤廃運動を抑え、基地と開発を統合して管理できる体制をとるためである。翌年には沖縄振興開発特別措置法が改訂され、公共事業から民間企業主導に重点を置き変えた沖縄振興特別措置法が制定された。「開発」の看板が取り払われ、「市場経済の導入」「自己責任原則」という経済自由主義の考え方が前面に出てきたのである。政府は自らの開発政策の失敗を認め、市場原理に沖縄をゆだねる方針に変えた。
また、沖縄の開発計画のなかには、沖縄だけでなく、さらに南の地域における「開発」をも視野に入れた日本の南進論を見出すことができる。アジア太平洋地域と日本との国際交流センターとして沖縄は位置づけられ、JICA国際センター、コンベンションセンター、各種の研究機関が設置されている。かつて沖縄は「大東亜共栄圏」のなかで南洋進出の拠点とされ、多くの沖縄人が日本の植民地に渡った。同じように、復帰前に提示された、西表島の高岡構想(1)、官民の機関が作成した沖縄開発計画、そして、3次にわたる振興開発計画にも、南進論の刻印が見られる。太平洋戦争で日本が敗れ、南方の植民地を手放したが、日本の南進政策は沖縄開発のなかで行き続けているのだ。
第二次世界大戦前の南進論は、日本の軍事的膨張主義と緊密に結びついていた。沖縄を拠点とする今日の南進論も、日本の軍事政策と無縁ではないだろう。日米安保の要は駐沖米軍基地にあり、沖縄の米軍基地を永続化するために、基地関連の補助金が集中的に投下されてきた。
そのほか、基地が市場経済を推し進めた面も見逃せない。基地は沖縄でエンクロージャーの役割を果たした。共同体をつぶし、土地から追い出された住民に基地労働者としての職を与えたのである。基地関連の産業が生まれ、人びとは市場経済のなかに放り込まれた。沖縄の振興開発計画では、島嶼であることの非効率性、沖縄戦による島の破壊、27年間の米軍統治、米軍基地の存在によって、開発が正当化されてきた。泡瀬(沖縄市)干潟埋め立て賛成派も、基地が島の平地部分を占拠していることを開発の理由にあげている。
軍事訓練による赤土の流出、有害廃棄物の投棄、軍用機による騒音・空気汚染など、基地そのものが環境を破壊し続けてきた。那覇市おもろ町、金城町、北谷町の美浜などの基地跡地には大型小売店が建設され、消費が謳歌されている。だが、旺盛な消費活動は廃棄物の増加につながる。基地の跡地利用においては、基地経済と比べた経済効果が重視される傾向にある。しかし、沖縄全体における環境コストの増加という面からも跡地利用についての考察が必要であろう。
2 沖縄社会のスピード化
沖縄経済が自立するには社会的基盤の整備が不可欠である、という言説が流布している。72年から2002年までの間、沖縄振興開発事業費として約7兆390億円が投下された。そのうち公共事業費が約6兆4975億円で、全体の92%に及ぶ。公共事業全体のうち、道路が36%、下水道・廃棄物等が18%、港湾・空港が12%、農業農村整備が12%となっている。(2)
しかし、工業団地、特別自由貿易地域、金融特区、道路、港湾、モノレール施設などを建設してきたにもかかわらず、島外企業が大挙して沖縄に進出してくる気配はない。公共事業の過程で自然が破壊されるだけでなく、これらのインフラは時間がたてば老朽化し、ごみとなる。沖縄各地で廃車が山のように積み上げられ、インフラの維持管理、廃棄物処理など膨大な財政・環境コストを沖縄は抱えている。さらに、基地関連の事業に対しても補助金がふんだんに投じられ、諸施設が次から次に建設されてきた。長期的にみれば、このような投資も基地周辺市町村にとって負担増につながり、財政や環境を脅かす要因になるだろう。
開発による島の改造は、まず海辺に見られる。サンゴ礁は島人によってイノーと呼ばれ、生活の糧を与えてくれた。玉野井芳郎や多辺田政弘はコモンズに着目し、沖縄のもう1つの生き方をイノーに住む人びとの生活のなかから提唱した(3)。だが、狭義の経済学からみると、サンゴ礁は少ない費用で広大な平面地を造成できる、効率的な場所である。これまでに広大な埋立地が開発されてきた。今後も、名護の米軍基地、泡瀬のレジャー人工島などの建設がひかえている。サンゴ礁が何万年、何十万年という長い年月でつくりあげた島を、人間は数十年でその形を大きく変えてきた。自然のサンゴ礁、海浜がつくり出す複雑で暖かい曲線美の島の景観が、コンクリートの埋め立てによって直線、平面という人工的で、冷たい空間に変貌していく。
公共事業費のなかでもっとも多いのが道路建設費である。96年から03年までの面積1km2あたり道路延長距離は、沖縄が全国平均を一貫して7~9%上回ってきた。(表1)。車の数も激増し、沖縄の自動車台数は72年の約19万8000台から、03年には約89万2000台と、約4倍になっている(4)。車での移動は、大型販売店での買い物を可能とした。沖縄経済の牽引力として、スーパー売上高の好調、新車販売台数の増大、観光客数の増加が指摘されているように、沖縄の消費傾向は高い。自らの貯蓄を減らしてまで消費しているのである(5)。また、使用電力量も、72年の約17億2147万kW時から、03年には約80億5243万kW時に増えた。(6)
沖縄社会のスピード化は、新しい振興計画によってさらに加速されつつある。社会のスピード化とは、人、土地、自然という生命のゆるやかな営みを否定し、激烈な競争に追いたてられて社会的速度が大きくなることをいう。世界的なデジタル化や市場の脱国境化の潮流に乗り遅れまいとして、沖縄でも自由主義的経済政策が導入されている。ノーベル賞級の研究者を集めた大学院大学、国際金融特区、情報技術特区が、新しい振興計画の目玉である。これらの分野では、何よりもスピードが求められる。研究者は誰よりも早く研究成果をあげ、実用化しなければ、評価されない。国際金融市場では、秒単位で莫大な資金が取引される。金融技術や顧客の需要は変化が激しく、国際金融市場への迅速な対応が求められる。情報産業部門も、需要の変化に素早く対応しなければ世界的な競争で敗北してしまう、生き残りが厳しい世界である。
内閣府は、沖縄に多国籍企業を誘致し、世界資本主義の一端を沖縄が担うことで、一挙に経済成長を実現させたいと考えているのであろう。財政危機状況にある日本政府は、補助金をふんだんに提供できないため、大学院大学や国際金融特区などを用いて、サバイバルゲームが展開されている世界市場に沖縄を投げ込もうとしている。
多国籍企業は、賃金の安い国の労働者を使い、資源の豊富な国から原料を輸入し、環境規制のゆるい国に工場を設置し、そして、製品を人口が多い国で販売するという、世界的分業体制をとっている。多国籍企業の求めに応じた地域づくりが行われ、情報技術や金融の各特区、特別自由貿易地域において環境や投資に関する規制が大幅に自由化された場合、企業は進出するかもしれない。しかし、多国籍企業にとって都合のいい経済環境が沖縄に形成されるだけであり、地元企業は淘汰されるだろう。経済指標上は経済自立が達成されるかもしれないが、沖縄の人間はそれで幸せになるのだろうか。
多国籍企業間の価格競争は熾烈である。とくに労賃は大きなコスト負担とされ、企業はリストラや生産拠点の海外への移転を進めている。アジア諸国に比べて賃金が割高な沖縄の労働者が雇用される保証は、まったくない。沖縄の金融特区が、太平洋諸国のタックスヘイブン(7)のようにマネーロンダリング(8)の場所として利用され、犯罪の温床になり、ヘッジファンド(9)の格好の標的になるおそれもある。
現在、沖縄の主要産業は観光業である。そこでも、いかに多くの観光客を呼び込み、欲望を満足させ、効率的サービスを提供し、他の観光地との競争に勝ち抜くかという市場原理がはたらく。その結果、沖縄の自然や物産だけでなく、文化、歴史、人びとの生き方までもが商品化の対象になっている。
沖縄全体の商品化は、日本市場の消費者の好みに合わせて行われる。沖縄観光における最大の「売り」は「癒し」である。しかし、米軍基地という暴力を沖縄に過重に押しつけて、その隣りで日本人観光客が「癒される」という、新たな差別構造が生まれている。沖縄人も「沖縄ブーム」におだてられ、「てーげー、おおらか、やさしい、金銭に頓着しない」など、ステレオタイプされた沖縄人像に自らがしばられる。「癒しの沖縄」は日本の苛烈な市場社会と連動しており、競争社会のなかで疲れはて、リストラされた人びとを温かく受け入れ、元気な労働者として再生させる機能が、求められているのである。
たしかに、沖縄の観光業は高度成長期にある。04年の観光客数は515万人を突破し、沖縄県は07年の目標値を580万人に設定した。しかし、観光関連収入の大部分は、本土の旅行代理店、リゾート・ホテル会社、航空会社が得て、利益の大半は本土に還流している。一方で、観光開発の過程で環境が破壊され、観光客はごみ、汚水、汚物を捨てていく。そうした環境コストは沖縄に転嫁されているから、本土企業はそれを負担せずにすみ、費用対効果のうえで沖縄は非常に効率的な市場になっている。
観光客は沖縄に「癒し」を求めてくる。しかし、内閣府沖縄担当部局と沖縄県は、沖縄をさらに効率的な島にし、合理的な市場社会にして、多国籍企業に差し出そうとしている。仮に沖縄の世界市場への統合が進み、沖縄人の多くが打算的でスピーディーな「合理的経済人」になり、インフラとごみが島中を覆うようになれば、観光客は沖縄に「癒されず」、自らを「癒してくれる」別の地域を求めるだろう。観光客のニーズと相反する経済政策が実施されているのである。
3 島嶼経済論と内発的発展
沖縄の経済問題である高失業率、県民所得の低さ、第三次産業に偏った経済構造、補助金や基地への依存状態は、大規模な開発が行われても解消されなかった。むしろ、開発が経済問題をさらに深刻にしている。沖縄の人びとは補助金に依存し、近代化によって時間に追われ、そして島の自然が減少している。大型スーパーには、欠乏感に駆り立てられて消費に走る沖縄人の姿がある。物質の面では満たされるようになったが、自律性、自然との共生、ゆとりある生き方、心の豊かさなどが失われつつあることを考えると、かえって沖縄は「貧困」になったといえよう。
援助金が投じられた世界の大半の途上国と、先進国との格差は、さらに拡大している。一部の競争の勝ち組を別にすれば、開発によって「後進地域」が「先進地域」になることはないだろう。
これまでの沖縄には、狭い意味での経済学が適用されてきた。それは、合理的経済人が、稀少な資源を用いて、自らの無限の欲望を満たすために市場の中で効率性を競えば、無限の経済成長が可能である、と想定する経済学である。狭義の経済学にもとづいた沖縄振興開発特別措置法が沖縄の基本法になったために、沖縄社会という土台の上に経済があるのではなく、経済が沖縄社会を牽引するようになった。
しかし、経済とは市場経済や経済的自由主義だけでなく、合理的や効率性の追求だけでもない。カール・ポランニー(10)がいうように、人類史において市場経済が社会全域を覆うようになったのはつい最近であり、市場経済は多様な経済活動の1つでしかない。経済の原義は経世済民(世を治め、民の苦しみを救うこと)である。広く人間の苦悩を取り除き、生活の安定を築く学問が、広義の経済学であるといえる。
人間は市場のなかでのみ生活しているのではなく、自然とともに生きている。人間を含めた動植物、島、地球全体の存続を前提にした経済学を、生命系の経済学(11)という。また、モノは経済合理性の原則にしたがってのみ流通するのではなく、祭り、助け合い、物々交換、自家農耕、漁労など、地域の社会的慣習のなかでもやり取りされてきた。これをサブシステンス・エコノミー(12)という。歴史的に形成された自治的共同体の営みであり、社会的弱者に対する経済支援を富者に課す経済社会のあり方であるモラル・エコノミー(13)もある。
市場だけではとらえきれない島の実相をこうした広義の経済学が明らかにしてくれる。島の生態系と経済との関係については生命系の経済学、島の文化・伝統・制度・慣習と経済との関係についてはサブシステンス・エコノミー、島の経済的相互扶助についてはモラル・エコノミーが、それぞれ分析の視角を与えてくれるだろう。
そして、沖縄の島嶼性にもとづいた経済学が島嶼経済論である。(14)
土地が狭く、海によって閉ざされた空間である島嶼では、環境コストが増大しやすい。島には平地が少なく、山やサンゴ礁が開発対象地になることが多い。川の距離が長くない島では開発された山から赤土が海に急激に流れ込み、海を汚す。生きている島のまわりを埋立地が覆い、サンゴの自然生長を阻んでいる。島は閉鎖空間であるため、開発にともない廃棄物などのエントロピーが目に見えて増大する。島外からの物資に依存しているため輸送コストが大きくなり、土地が狭く人口規模が小さいため経済効率が悪くなる。こうして民間部門が脆弱になり、雇用確保や景気浮揚を理由として補助金に大きく依存してしまう。
他方、島のなかには、地域共同体の文化的・社会的古層を現在でも見出すことができる。共同店や公民館による地域の自律、海と人とが共生するコモンズの経済、社会の広範に見られるユイマールの実践などである。島は狭く、人間関係が濃密であり、自然や社会的条件が厳しいため、人間同士の助け合いが強くなる傾向にある。島々は海上に分散しているがゆえに、文化的・歴史的蓄積も深く、多様である。狭義の経済学が前提とする単一の社会や人物像から逸脱しているのが、島であるといえよう。
狭義の経済学の立場に立つ官僚や学者などは、世界中に適用可能であるとする科学的普遍性を沖縄に適用しており、島嶼性や環境に対する考慮が欠如している。現在生存している人間だけでなく、将来生まれてくる人びともこの島に住むであろう。さらに島は、死んだ人びとの記憶が残り、その魂もニライカナイから戻ってくる場所でもある。ニライカナイとは海上他界であり、島に豊かさをもたらし、島人が死んだら還る理想世界である。時間、空間、生態系、コスモロジーなど島の全体性のなかに経済を埋め込む必要がある。ところが、今日の沖縄の開発は、経済的利益の獲得を最大の生きる目的にすえた人間のためだけに行われている。
「普遍的な経済理論」を沖縄に当てはめるのではなく、独自の島嶼性、場所性、歴史性、社会性、文化性を踏まえ、自然との共生をはかりつつ、沖縄人自身による参加を重んじる発展のあり方を内発的発展という。(15)生産や消費の水準や量、社会構造、人びとの生活速度を世界市場のペースに合わせるのではなく、島のペースに合わせる。また、金融、情報技術、最先端技術や研究による南北間の従属関係に沖縄が加担せず、南の地域と連帯する島嶼間ネットワークの構築も、内発的発展の課題となろう。
島の内発的発展にとって、島嶼間ネットワークは次のような諸点において重要である。
まず、似たような気候、風土、地理的特質、経済構造、人びとの気質、特産物の種類などを共有する島々にとって、生態的・社会的・経済的条件がまったく異なる大陸地域の成功事例よりも、同じ島における成功事例のほうが、問題解決のために役立つケースが多いだろう。また、島嶼は生産規模や消費市場が狭いために、コスト高になりやすいという「規模の不経済」問題を抱えている。島々が相互に生産・販売・消費などの経済活動を協力して行うことで、一定規模の生産・消費市場を生み出し、大国からの輸入依存状態から脱却する可能性がみえてくるだろう。さらに、島で内発的発展をめざす際、島嶼間の技術交流や資金協力が重要になる。たとえば、太平洋諸国14カ国とオーストラリア、ニュージーランドは太平洋諸島フォーラムという地域機構を形成し、経済自立に向けた相互協力を進めている。
島は単独では人口規模が小さく、行使しえる影響力におのずから限界がある。しかし、島同士で連合を組めば、国内・国際社会に対する発言力を増すことが可能になる。たとえば、二酸化炭素の排出規制を求めた京都議定書の採決において、太平洋・インド洋・大西洋にある43の島嶼国からなる小島嶼国連合が大きな役割を果たした。
沖縄だけの「経済自立」を実現するために、沖縄の内部に経済成長のエンジンをすえることを内発的発展であると認識するのは、一面的である。広義の経済学、生命系の経済学、サブシステンス・エコノミー、モラル・エコノミー、島嶼経済論などを踏まえた人びとの歩みを、内発的発展と呼びたい。島嶼間ネットワークによって、地理的・気候的・風土的・社会的特性を共有する島嶼同士が協力し合いながら、島の自律を向上させられるだろう。
たとえば、沖縄よりも面積が狭く、人口規模が小さい島が多い太平洋諸島は、沖縄を必要としている。太平洋諸島には、生息するウリミバエ(16)などの害虫のために農産物の輸出が思うにならない島々がある。筆者が99年から2000年までパラオの日本大使館に勤務していたころ、パラオ人が大きなアボガドを抱えて、「日本に輸出したいが、何か方法はないか」と聞きに来たことがある。日本の農林水産省に問い合わせたところ、「パラオにおいてウリミバエなどの害虫が駆除されないかぎり、輸出は不可能である」との回答が返ってきた。沖縄はウリミバエを駆除する技術と経験をもっており、それを太平洋諸国のために役立たせることができる。
また、01年に大浜長照・石垣市長らとパラオを訪れた際、レメンゲサウ大統領は石垣島で成功している黒真珠養殖の技術をパラオに導入してほしいとの希望を私たちに伝えた。パラオも石垣島と同じくサンゴ礁からなり、海水は透明度が高く、真珠養殖に適しているからである。沖縄と同じく太平洋諸島も他国からの援助金に依存し、島の産業育成が大きな課題になっている。沖縄では健康食品を中心に、地元農産物の加工、全国市場への販売に成功している事例が多い。沖縄と太平洋諸島との間で、ヒト、モノ、カネ、知恵の交流が進めば、島人の経済活動への参加機会も増えよう。沖縄も、太平洋諸島で実施されているエコツーリズムの実践や、タックス・ヘイブンが与える影響などを学ぶことができよう。
開発が正当化される理由として、地域財政の自立がある。補助金への依存から脱却するために、開発を進めて財政収入を増やさなければならないという主張である。しかし、考え方を変えると、財政支出を削減すれば、収入もそれほど必要ではなくなる。公共事業が実施されるほど、インフラ、施設、組織を管理するための人や金の配分が増え、行政部門が肥大化する。行政は自己増殖を図るよりも、NGO、NPO、住民の共同管理、地元企業の活動範囲を拡大するための社会的条件を整備する必要があろう。これまで地域行政はインフラの建設を重視してきたが、今後は地域内とともに世界的な島嶼間の人や組織のネットワークづくり、地域の資源や文化を内発的に発展させるための触媒的機能に重点を置くべきであると考える。
4 節度ある生き方を前提とした「経済自立」
現在、市町村の合併が進められている。しかし、それは地域行政制度を効率化し、ひいては中央による地域の管理を強化するために行われている側面が強い。つまり、経済効率の原則にもとづいて実施されているのである。住民が自決権を行使し、自らの生活、経済、社会のあり方を主体的に決定するという方向には、進んでいないといえる。
地域分権においてもっとも重要なのは、「市民社会」の確立ではないだろうか。住民が相互に信頼し合い、助け合う「市民社会」が形成されていれば、社会保障費などの経費も削減できよう。住民がアトム化され、揺りかごから墓場までの人生全般を行政に依存する社会システムではなく、住民自らが行政から自立し、社会的共同力を高めるように地域づくりをする。地域の人が心から生き生きと生活し、住民と地域社会との結びつきの度合いに応じて地域行政の範囲が形成されるべきであろう。
沖縄の高い失業率も、開発の正当化に使われている。公共投資や外部企業の進出によって、雇用機会が増大するといわれている。しかし、公共投資による雇用は短期的な経済効果しかない。ボーダレス企業は労賃をコスト負担と考えており、これ以上開発が進んだとしても雇用が増大する保証はない。
働くということをもう一度考えてみたい。パラオ人は住宅や車の購入資金を得たいときに、「シューカン」と呼ばれる集会を開き、親類や友人から資金援助を受けている。また、第一子誕生式、結婚式、葬式などの際、人びとは踊り、歌い、食事の準備をし、家庭を相互に訪問し、食べ物や石貨幣を交換する。土曜や日曜になると畑や海に行き、儀礼交換や自給用の食べ物を得る人も多い。沖縄の島々にも、島ごとに多様な儀礼や祭りがある。島の住民はそのために多くの時間を費やし、他所に住む島出身者もわざわざ祭りに参加するために帰郷している。
企業や役所での勤務や完全雇用形態は、働くことの1つの形でしかない。生産や利益のために体や知能を使うことも、1つの働き方でしかない。働くことには、家事、ボランティア、地域活動、祭りへの参加、介護、家庭内生産などもある。市場で取引されないモノやサービスを生産し、消費する過程では、貨幣がほとんど流通せず、経済指標では測れず、経済成長にも直接貢献しない。だが、人間が生きるうえにおいて重要な営みである。組織のなかで労働したくないという選択もある。市場経済、経済成長、「経済自立」に役立たなければ評価されないという暗黙の社会的圧力によって、もがき苦しんでいる人もいるだろう。
経済成長の起爆剤とされている事業は、次のように変更したらどうだろうか。
国際金融特区はすでに香港やシンガポールに存在しており、沖縄に設置する経済的理由は小さい。むしろ、共同体関係が濃密な沖縄では、人間の関係性にもとづく地域通貨特区として整備したほうが社会的意識は大きいと考える。現在、世界中で実践されている地域通貨に関する研究、実践者間の交流、新たな地域通貨の創設(たとえば島嶼間ネットワークで利用できる通貨)、沖縄内の地域通貨利用の促進などの拠点として位置づけ直すことを提案したい。
大学院大学も島嶼の必要性に合致した機関に変えたほうが望ましい。地球の温暖化にともない、太平洋のツバル、マーシャル諸島、キリバスなどは海面下に水没しつつある。廃棄物があふれかえっている島も多い。04年8月にマーシャル諸島のマジュロ島を調査した際、次のような光景を目にした。マジュロ島は細長く、山もない平坦な島で、左右を見渡せば海が見えるほどの狭い場所もある。市内を歩くと、20メートルくらいの間隔で巨大なごみ箱が置かれていた。ダンプカーの荷台をそのままごみ箱として利用しているのだ。住民は燃えるごみもそうでないものもいっしょに捨てて、いっぱいになるとダンプカーが荷台を海岸のごみ集積場に運んでいたが、ごみの一部はそのまま海に流し出していた。廃棄物を船に運んで海中に投棄することもある。
また、地球温暖化を原因とする海面上昇により、海抜の低いマーシャル諸島は大きく影響を受けている。波が海岸の砂を持ち去ったために、砂浜の岩盤が露出し、ヤシの木が海側に傾いたり、根こそぎ倒れた光景をよく目にした。マーシャル諸島は島内のごみ問題とともに、地球規模の環境問題にも直面しているのである。
こうした島嶼国は、地場産業の多様化によって援助金依存から脱却しようともがいている。大学院大学は、世界の島嶼が抱える問題を解決するための研究・実施機関、島嶼間のネットワークの拠点にしたほうが、世界的・歴史的に評価され、間接的に沖縄の経済自立にも役立つだろう。
沖縄の開発は再考を要する。人間の開発力を自然に対して振り回さないという謙虚な姿勢が必要ではなかろうか。島、鳥、魚、珊瑚、木々の声に静かに聞き入る。有限な空間である地球は、人間の開発によって悲鳴をあげている。地球と同じく、島も閉鎖空間である。にもかかわらず、島では無限成長路線が展開されてきた。赤土の流出、廃棄物の増大、土壌汚染など、島や海は声なき声を発している。環境修復や地場産業の創出に限定した公共事業を実施し、モノをふんだんに消費しないなどの、節度ある生き方を前提とした「経済自立論」が求められよう。島の外からもたらされる開発資金や手法に飛びつくのではなく、踏みとどまり、島の人、土地、自然に対する信頼を取り戻すことが、沖縄の内発的発展の一歩となろう。
(1)元衆議院議員で南方同胞援護会の理事であった高岡大輔が提唱した、東南アジアに対する日本の技術支援の拠点にすることを目的にした、西表島熱帯農業センターの建設計画。この構想をもとにして、日米両政府は西表島総合開発構想を1960年に策定し、日本の大学やスタンフォード大学の研究者が開発調査を実施した。沖縄の開発計画史に関する考察については、松島泰勝『沖縄島嶼経済史――12世紀から現在まで』藤原書店、2002年、273~290ページ、参照。
(2)譜久山當則編『沖縄経済ハンドブック2002年度版』沖縄振興開発金融公庫、2003年、72ページ。
(3)玉野井芳郎『地域主義からの出発(玉野井芳郎著作集第3巻)』学陽書房、1990年、多辺田政弘『コモンズの経済学』学陽書房、1990年。
(4)沖縄県企画開発部交通政策室編『沖縄の未来を育む交通体系の確立をめざして』沖縄県企画開発部交通政策室、2003年、3ページ。沖縄総合事務局ホームページ「陸運事務所」。
(5)『沖縄タイムス』2004年1月3日(社説)。
(6)前掲(2)、50~51ページ。沖縄県ホームページ「沖縄の統計:電灯・電力消費量」。
(7)外国企業の投資を促すために所得税、法人税、固定資産税などを免除する制度が実施された国や地域。本国での課税を逃れるためにペーパーカンパニーが設立されるケースが多い。タックスヘイブンに設立される銀行をオフショアー銀行という。たとえば、ナウルでは2001年、約400のオフショアー銀行が操業しており、そのすべてはナウル政府のメールボックスに登録していた。銀行の名前は公表されておらず、機密性が保証されていた。
(8)犯罪や不正手段によって得た資金を特定の銀行の口座に預金して、資金の出所や受益者をわからなくしようとすること。2003年、パリに拠点をおく国際的な金融作業チーム(FATF)は、マネーロンダリングの温床地として、次の11カ国をあげた。インドネシア、ウクライナ、エジプト、グアテマラ、クック諸島、グレナダ、セント・ビンセント・グレナディンズ、ナイジェリア、ナウル、フィリピン、ミャンマー。マネーロンダリングの温床地は、犯罪組織やテロリストに資金を提供するために利用されている。
(9)投資家や金融機関などから出資を受ける投資会社。タックスヘイブンに設立するケースが多い。
(10)カール・ポランニー著、吉沢英成・野口建彦ほか訳『大転換――市場社会の形成と崩壊』東洋経済新報社、1975年。
(11)ポール・エキンズ編著、石見尚ほか訳『生命系の経済学』御茶の水書房、1987年。
(12)Te’o Fairbairn, Islands Economics-Studies from the South Pacific, University of the South Pacific, 1985.
(13)ジェームス・スコット著、高橋彰訳『モーラル・エコノミー――東南アジアの農民叛乱と生存維持』勁草書房、1999年。
(14)島嶼経済論については、前掲(1)、参照。
(15)西川潤『人間のための経済学――開発と貧困を考える』岩波書店、2000年、参照。
(16)伊藤嘉昭・垣花廣幸『農薬なしで害虫とたたかう』岩波書店、1998年。
【参考文献】
ヴォルフガング・ザックス著、川村久美子・村井章子訳『地球文明の未来学――脱開発へのシナリオと私たちの実践』新評論、2003年。
ポール・エキンズ編著、石見尚ほか訳『生命系の経済学』御茶の水書房、1987年。
デビッド・コーテン著、西川潤監訳『グローバル経済という怪物』シュプリンガー・フェアラーク東京、1997年。
西川潤編『アジアの内発的発展』藤原書店、2001年。
松島泰勝『沖縄島嶼経済史――12世紀から現在まで』藤原書店、2002年。
松島泰勝「グローバリズムの中の琉球」を読む
松島さんは、この小論の中で「沖縄(県)」を指す呼称、タイトルも含め「琉球」という名辞で表現した。これは奄美をも意識してのことかも知れないが、「琉球」という名辞を“人々のアイデンティティ”と固く結びつけて論を展開しているように思われた。
彼は“人間にとっての基本的な豊かさとはなんであろうか。”と自問し、“平和で、健康で、自然の中で楽しく、他の人とも仲良く生活することであろう。…時間におわれることなく、ゆったりした生活空間のほうが人間にとって生きやすいと思う。地域を近代化して、取得する貨幣量を増やし、快適に暮らすための物を購入するという回り道をせず、直に目の前にすでにある琉球の豊かさを認識し、それを享受すればいいのではなかろうか。”と自答する。そして“グローバリズムに左右されず、琉球の本当の豊かさを維持し、発展させるための手がかり”として次の三点をあげる。
第一は“琉球の歴史的豊饒性を活用して、多様な関係性をアジア太平洋に構築する。”である。“歴史的な遺産を掘り起こし、「日本の辺境」に押し込められた琉球を解放し、…中央集権体制から脱するための源泉を琉球史の中から掘り当てる。”
第二は“政治的地位を変える。”これは“独自の法制度を導入することで、非市場経済の部分を維持し、またそれを再生して琉球の本当の豊かさを享受するためであり、経済自決権を発揮するためである。”
第三は“琉球の地理的、風土的多様性を生かす。…島嶼が抱える問題を解決し、可能性を広げるために琉球が蓄積したものを提供し、また、他の島嶼から学び、島嶼間の横のつながりを強化する。”
松島さんは、先の大著『沖縄島嶼経済史』(藤原書店2002)から02.9.7シンポの「一国多制度」「沖縄(自治)州」構想の提起を経て、更に一歩踏み込んだように思われる。彼の持論たる「海洋ネットワーク戦略」も、現行法体系下での蓄積可能な自治体外交の推進として方針化され、さらに琉球(弧)-奄美まで含む、“気候、風土、植生、社会的特質等”を踏まえたリアルなものへと進みつつあるように感じられた。例えば「沖縄経済の宿痾」とも言える公共事業(日本政府依存)などを念頭に置き、“非市場経済部門が広がれば、行政が支出する分は少なくなる。そして、観光業の利益が琉球内で循環するような課税制度にすれば、財政自立も実現できよう。”との政策提言も付け加えている。
ただ、彼の「豊かさ」を根拠づける「平和と環境」はもとより、新振興計画の目玉とされる大学院大学・金融特区も「苛烈な競争原理」を導入することにしかならないとし、“非競争社会”を展望する沖縄の未来像を描くが、敢えて無いものねだりに似た指摘をすれば、<政治>の重要性の着目が「政治的地位の獲得」という曖昧な表現で語られていることである。道州制を含む連邦制-特別自治制などを基礎に、独自の政治的行政的自立・自決を展望することが、今リアルに問われているのではないだろうか。例えば「沖縄自治研究会」の蓄積・成果など、彼らが「自立・独立派」を標榜していないが故に、尚更のことであろうと思う。
②グローバリズムの中の琉球/松島泰勝
『別冊環6号-琉球文化圏とは何か-』(藤原書店2003)所収
琉球におけるグローバリズムの4層構造
グローバリズムは、すべてのものを数値化、序列化、商品化しようとする。それにより地域は地球的規模の市場経済の論理に従い、貨幣を媒介にした関係性が主体になり、貨幣取得が至上の目的になる社会となる。また、グローバリズムにより地域は軍事戦略上の拠点にされ、中心部が地域の運命を握り、地域文化も中心部の意向に従って形成される。
琉球は、軍事、政治、経済、文化という4つの層において、グローバリズムの侵食を受けている。これら4つの局面は、琉球の政治地理、経済地理、文化地理と密接に関連している。琉球の島嶼性、東アジアにおける戦略的位置、南方的な風土等が、その軍事的、政治的、経済的、文化的な従属性を規定にしている。4層構造は琉球という地において相互に緊密に結びき、グローバリズムを推し進めている。
まず、軍事・政治地理の側面から琉球について考える。琉球には日米安保条約によって米軍基地が集中的におかれている。基地関連の事件や事故が山のように発生しても、日米地位協定は改善されないままである。琉球の中に基地があるのではなく、基地の中で琉球の人々は生活している。島の上の基地とともに、島のまわりの海域、空域には広大な米軍の訓練域が設けられており、民間機も訓練空域を掻い潜って離発着している。米軍基地は、日本がアメリカに対して自国の安全保障を丸抱えしてもらっているという意味での属国性を象徴している。それとともに、琉球の日本に対する従属性をも示している。
琉球の政治において中心的役割を果たしてきたのが沖縄開発庁(現在の内閣府沖縄担当部局)であり、沖縄振興開発計画の策定・実施に絶大な影響力を及ぼしてきた。「後進地域・琉球」に資金を投入して、上から開発するというトップダウン型の行政姿勢は一貫している。開発庁の一括予算計上方式によって補助金を獲得しやすいシステムが、琉球経済に組み込まれ、補助金に大きく依存する経済構造が形成された。補助金は米軍基地と交換される形で提供され、基地経済からの脱却を困難にし、基地を容認する状況がつくりだされた。
開発のために制度上の画一化が推し進められた。琉球はアメリカ方式である道路の右側走行制を採用していたが、「一国一交通方式」に基づき、1978年7月30日をもって、日本式の左走行方式に変更させられた。道路走行方式の変更に象徴されるように、行政・経済の諸制度において、琉球が経験したのはアメリカン・スタンダードからジャパニーズ・スタンダードへの移行であった。道路走行方式のほか、通貨変更(ドルから円へ)、商慣行、商品構成、本支店・親子会社関係、観光化、補助金等によって、琉球を日本の法・慣習・制度圏域の一部とし、均一空間にすることで、開発を容易に行うための基盤が形成された。
行政上の中央集権化が深まるにつれて、経済的な日本化も進んだ。本土の大企業はより安い投資コスト、市場、自然環境を求めて進出した。人々の生活、精神世界、自然よりも企業や中央政府の論理が優先された。その際、琉球人の目の前につり下げられたニンジンは、「経済格差の解消、経済自立」という数値化された目標であった。「本当の豊かさ」について議論されることなく、数値目標だけが一人歩きした。このままだと、あくなき開発によってすでに豊かな琉球をかえって貧困化してしまうだろう。
具体的な数字をあげて今日の琉球経済をみてみよう。1972年から98年までの県内総生産は約4592億円から約3兆4249億円へと約8倍に増大した。1999年における産業別就業者の構成比をみると、第一次産業が7.1%、第二次産業が19.1%、第三次産業が73.6%である。経済規模は拡大したが、第三次産業に大きく偏重した経済構造であることがわかる。
さらに、1998年度における県内総支出(名目)の主な構成比をみると、財政支出が34.3%、観光収入が13.0%、民間企業設備投資が12.5%、軍関係受取が5.3%である。琉球経済を押し上げる主な要因が財政支出と観光であることがわかる。1997年度における元請完成工事高(建設業者が発注者から直接受注した建設工事の完成工事高)構成比をみると、民間発注工事が45.2%であるのに対し、公共発注工事は54.8%に及んだ(なお、同年の全国における公共発注工事比は37.4%)。公共事業への依存度が大きい。現在の不況下において、地元企業だけでなく多くの本土建業者もまた仕事を求めて琉球の公共事業に参入している。
琉球最大の産業は観光業である。1972年から2000年までの年間の入域観光客数は、44万人から456万人へと約10倍に増えた。しかし、琉球経済を支える観光業には次のような問題がある。第一の問題は、観光業が琉球の中で飛び地的に存在していることである。1973年度と99年度の沖縄県の歳入構成比をみると、自主財源が21.6%から22.9%、依存財源が78.4%から77.1%になった。また、2002年における失業率は8.3%であり、全国平均の約2倍である。
観光客数が約10倍に増大しても、自主財源の比率はほとんど変化せず、観光業の成長が財政収支の改善に結びついていない。本土の大手航空会社、旅行代理店等があげる利益が日本本土に還流するシステムが確立されているため、琉球経済に観光業収入がうまく循環していない。琉球は本土企業に場所や機会を提供しているにすぎない。また、観光客数が増大しても高失業率の状態はいつまでも続いており、観光業の雇用効果も小さいといえる。さらに、地元食材の観光施設による利用がすすまず、県外産のお土産が広く流通しており、観光業の他の産業への波及効果も大きいとはいえない。
沖縄島から宮古島・石垣島、他の先島諸島へ、沖縄島の西海岸から東海岸へ、自然の砂浜の利用から埋立地の造成へというように、観光開発は琉球の島々を侵食している。現在、エコツーリズムのメッカである西表島において大規模観光施設が建設されている。また、沖縄市では、陸地のホテルが赤字経営であるにもかかわらず、広大の干潟を埋め立ててアミューズメント・宿泊施設が建設されようとしている。土木、建設等による短期的な経済利益を求めて、琉球の貴重な自然や人々の生活様式が失われつつある。
琉球の観光化は、本土側がつくりあげた「楽園、秘境、癒しの島」のイメージがそれぞれの島に付与される過程でもある。自然や文化の利用には多くのコストがかからず、企業は効率的な投資先として琉球を選択している。観光化は、温暖、自然の美しさ、文化等を商品化するだけではなく、「ゆったりした」生活形態、長寿社会等も観光資源として利用されているように、琉球全体が商品化の対象になっている。これまで琉球人の心の中で育まれてきた文化、アイデンティティーもまた、「琉球的なもの」として売買の対象にされている。企業が琉球文化の生成・受容・廃棄の過程に介在している。企業は利潤の創出という目的にそって、琉球文化を消費の動向に応じて取捨選択する。利潤を生む文化は利用するが、そうでないのは見捨てられる。琉球文化が生活から乖離し、人々のアイデンティティーが市場の論理の下に晒されるという、これまでにない文化状況が生まれている。
琉球ではこれまで、基地経済と比べて観光業は平和産業であるとして、その振興が安易に強調されてきた。しかし、巨大化した観光業は、グローバリズムの流れの中に琉球文化を引き込む装置であり、より批判的、客観的に観光業の実態をみる必要があろう。
グローバリズムをさらに深化させる新しい沖縄振興計画
これまで、琉球を経済的グローバリズムの波にのせて、経済自立を図ろうとする政策がとられてきた。1987年に自由貿易地区那覇地区、98年に特別自由貿易地域がそれぞれ設置され、税制上の優遇税制が設けられた。そのほか、情報通信産業振興地域、観光振興地域、工業等開発地区もつくられた。優遇税制のほか、運輸関連の規制緩和、入国手続きの簡素・合理化、施設の整備等が実施されている。
琉球のグローバリズム化はすでに本土復帰の頃からみられた。1972年、石油備蓄基地(CTS)を建設するために平安座島と宮城島の間を埋め立てる工事がはじまった。最終的に石油コンビナートの形成をめざし、経済成長の起爆剤にしようとした。これに対し金武湾を守る会は強く反対したが、屋良朝苗知事は埋め立て工事とCTSの建設を許可した。しかし、日本経済の中で石油コンビナートの時代はすでに峠を過ぎており、CTSだけが建設され、環境が破壊され、成長神話は夢と終わった。
同じ革新県政であった大田昌秀知事の頃にも、高度成長への夢が琉球を覆っていた。米軍基地を撤廃した後の経済開発策として、全島自由貿易地域構想、国際都市形成構想が提唱された。琉球全体を自由競争の場にして、香港、シンガポールのような都市社会にしようとした。その背景には1980年代におけるアジア経済の興隆があり、琉球王国の大交易時代と重ねあわせ、アジア経済圏の一角を占めたいという希望があった。しかし、地元企業・産業界の反対、保守県政の稲嶺知事の当選によって、同構想は実現をみなかった。
琉球においては保守や革新に関係なく近代化、開発行政が政策の中心にあった。米軍基地には強く反対するが、開発は「経済自立、格差是正」のために必要不可欠だと考えられてきた。しかし、開発行為自体、自然や生命の破壊であり、基地と同じ性格を持っている。
本土復帰後における経済政策は次のような特徴をもつ。①島外企業の誘致を図り、②大量生産、大量消費という高度成長という論理をあてはめ、③時代の流行となった開発方式をモデルにすることである。しかし、面積が狭く、市場規模が小さく、他に大市場から離れているという、琉球の島嶼性は、観光業を除いた島外企業にとって魅力的な投資地とはならなかった。それゆえに、優遇税制、規制緩和等を行ってきたが、世界における経済自由化の速度の方がはやく、琉球側が提示してきた自由化メニューが時代遅れになるというジレンマを常に抱えてきた。
30年にわたり琉球経済の方向性を規定してきた沖縄振興開発計画にかわり、2002年4月から10年を期間とした新しい沖縄振興計画が実施されている。その基本的な柱は次の通りである。①民間主導の自立型経済の構築、②アジア・太平洋地域の発展に寄与する地域の形成、③大学院大学を中心にした世界的水準の知的クラスターの形成、④安らぎと潤いのある生活空間の創造と健康福祉社会の実現、⑤持続的発展のための人づくりと基盤づくり、⑥県土の均衡ある発展と基地問題への対応である。
日本政府の財政逼迫状況を反映し、ふんだんな補助金が望めないことから、「民間主導の自立経済の構築」が第一の目標になったことが注目される。琉球振興の目玉とされたのが金融特区と大学院大学である。金融特区は、普天飛行場の代替施設を名護市が受け入れたことことから、見返りとして設置される。それはアイルランドのダブリン金融特別区をモデルにしている。ダブリンでは税制優遇措置により、約千社が投資をし、約7千人の雇用が生まれた。ダブリンの制度を模倣すれば、琉球経済が浮上するとの期待がある。
他方、大学院大学はノーベル賞級の教員をあつめた理工系の大学院である。2006年に開学予定であり、建設費が800億円、年間運営費が200億円、教授陣が200人、学生が500人という内容である。大学院大学は内閣府沖縄担当部局の管轄であり、琉球経済の振興を目的にしている。
2000年における大学進学率をみると、全国平均が45.1%であるのに対し、沖縄県は29.9%にすぎない。大学院大学のレベルと琉球の教育レベルとの落差が大きすぎる。大学院大学ではエリート教育が行われ、琉球の中で租界地となるだろう。琉球の社会構造とは異質である苛烈な競争原理が、大学院大学、金融特区によって導入される。競争社会は勝者と敗者の格差を明確にする。恒常化して琉球の失業問題はさらに深刻化するだろう。
グローバリズムによって本当の豊かさは得られるのか
琉球はグローバリズムの波の中に本格的に身を投じようとしている。それで豊かになるのかどうかを考えてみたい。琉球の人は、海辺で磯遊びをし、魚介類や海草をとり、海上他界であるニライカナイの神に祈りを捧げてきた。また、近辺の海で泳ぎ、ビーチパーティをして親睦を深めてきた。しかし、開発政策によってサンゴ礁が埋め立てられ、農地改善事業が原因で赤土が海に流れ、美しい浜辺をホテルが囲い込み、大勢の観光客が砂浜を覆っている。周りを海に囲まれた島に住む琉球の人々にとって、海は少しずつ遠い存在になりつつある。
島は面積が狭く、島自体が「成長の限界」を抱えている。限られた空間である島に多量の物を投入され、大量消費が行われ、ゴミや廃車が溢れかえっている。高度成長の論理が通用しないのが島であるにもかかわらず、西洋社会で形成された経済理論をそのまま当てはめてきたのである。その矛盾が今日、深刻な環境問題としてあらわれている。
人間にとっての基本的な豊かさとはなんであろうか。平和で、健康で、自然の中で楽しく、他の人とも仲良く生活することであろう。今日、ミネラル・ウォーターはガソリンより高価であり、有機農法で栽培された作物の価格も高い。人間が健康に暮らすために多くの貨幣が必要になっている。琉球ではまだ平均寿命がながく、大自然がのこり、相互扶助の関係も生きている。これらは無償であったが、近代化、開発の後には金銭を払って、これらの豊かさを手に入れなければならない。時間におわれることなく、ゆったりした生活空間のほうが人間にとって生きやすいと思う。地域を近代化して、取得する貨幣量を増やし、快適に暮らすための物を購入するという回り道をせず、直に目の前にすでにある琉球の豊かさを認識し、それを享受すればいいのではなかろうか。
グローバリズムに左右されず、琉球の本当の豊かさを維持し、発展させるための手がかりを次に示してみたい。
①琉球の歴史的豊饒性を活用して、多様な関係性をアジア太平洋に構築する。琉球王国は、中国、日本、朝鮮、東南アジア地域との外交・経済関係を築いてきた。近代でもアジア太平洋の各地に移民を送り出し、今日につながる琉球ネットワークを作り上げた。歴史的な遺産を掘り起こし、「日本の辺境」に押し込めらた琉球を解放し、アジア太平洋地域との間に多様な関係性を構築する。中央集権体制から脱するための源泉を琉球史の中から掘り当てる。
②政治的地位を変える。太平洋諸島をみると完全独立国、自由連合国、自治領、属領等、政治的地位が多様である。琉球よりもはるかに人口の少ない島々が独立の道を選んでいるグアム、北マリアナ諸島は米本土の西端に位置し、しかも面積が狭いという不利性を克服するために、独自な法制度を有している。なぜ、琉球だけが中央集権体制に縛られたままなのであろうか。周辺という位置づけでは、島嶼性の制約が顕著になる。本土政府主導で近代化政策が推進され、沖縄らしい生活様式が否定され、補助金依存という経済構造が固定化されてきた。
海洋民族として広大な海洋の中で自由に飛躍するには、周辺という身分から脱し、琉球の本当の豊かさを維持発展させるための政治的地位を獲得する必要がある。琉球固有の政治的地位を求めるのは、自由主義的経済政策をさらに推進するためではなく、独自の法制度を導入することで、非市場経済の部分を維持し、またそれを再生して琉球の本当の豊かさを享受するためであり、経済自決権を発揮するためである。非市場経済部門が広がれば、行政が支出する分は少なくなる。そして、観光業の利益が琉球内で循環するような課税制度にすれば、財政自立も実現できよう。
③琉球の地理的、風土的多様性を生かす。アジア太平洋の各地、特に島社会と琉球とは、島嶼性、暖かい気候、風土、植生、社会的特質等において共通点が多い。島嶼が抱える問題を解決し、可能性を広げるために琉球が蓄積したものを提供し、また、他の島嶼から学び、島嶼間の横のつながりを強化する。琉球には有人島が約40あり、島ごとに生態系、文化、世界観が異なる。それぞれの島が独自に対外的に多様なネットワークの網を張りめぐらせる。そのためにも、未だ残されている琉球の豊かな自然を維持し、傷ついた自然を再生する必要がある。
琉球はグローバリズムのなすがままにまかせ、市場経済、戦争の中で埋没してしまうのか。それとも、島々が織り成す多様な文化・歴史・自然の豊かさを育みながら、海洋世界の中で独自の光を放つ個性ある存在になるのか。琉球の運命は、その地を愛する人間の草の根的な意志と実践によって切り開かれると信じたい。
注
(1) 譜久山當則編(2001)『沖縄経済ハンドブック2000年度版』沖縄新興開発公庫調査部、16頁。
(2) 同上書、10頁。
(3) 同上書、13頁。
(4) 同上書、35頁。
(5) 同上書、38頁。
(6) 同上書、72頁。
(7) 沖縄県ホームページ、「統計」、「労働力調査」。
(8) 松島泰勝(2002)『沖縄島嶼経済史――12世紀から現在まで』藤原書店、258-290頁。
(9) 沖縄県(2002)『沖縄振興推進計画――21世紀沖縄 新たな振興に向けて』沖縄県企画開発部企画調査室、182頁。
①<抜粋とコメント>
松嶋泰勝『沖縄島嶼経済史』(藤原書店2002)を読む
【これは書評ではありません。沖縄の自立解放に向けた参考のための抜き書きにちょっとしたコメントを付けたものです。強調のための下線はすべて評者が付けたものです。02.9.1】
<序 論
P15/日本政府から膨大な補助金、特別措置制度に依存した現在の保護政策によっては、21世紀における沖縄経済の自立象を展望することはできない。また、沖縄経済の問題を一挙に解決するような革命的方法論と呼べるものは存在しないであろう。沖縄経済史の中から失敗の原因を学び、発展の可能性を明らかにすることによって沖縄の自立経済のイメージを描くことができるのではなかろうか。今日のような経済問題を沖縄が抱えるようになったのは、諸大国による支配に直接の原因があるのではなく、沖縄自らが生み出したものであるというのが本書の立場である。他に責任を転嫁するだけでは沖縄の経済は永遠に解決できない。自らの歴史を踏まえて経済問題の本質を分析し、内発的発展の事象を評価して、沖縄独自の発展の方向を定める必要があると考える。
復帰後、沖縄はいわば本土経済をモデルとして、経済格差の是正というキャッチアップ政策を実施したために、今日、補助金に大きく依存した沖縄経済が形成されたのであり、このような外来型開発によってもたらされた補助金依存の経済構造を打破するのが内発的発展であるといえる。
【自立・自力・自闘の心意気や良し。】
P16/米軍基地の依存を前提とする補助金や観光産業への依存は、持続可能な発展とはいえない。
P19/沖縄経済思想史を検討した結果、二つの経済の方向が明らかになった。それは、貿易や移民等を通じて、島嶼外部との経済関係を強化することで島嶼経済を発展させる方向と、島嶼内部の生産性を向上させて経済構造の安定化を目指す方向である。二重戦略は沖縄経済思想から導かれた経済政策であるといえる。沖縄史のそれぞれの局面に生じた経済問題を克服するために提起され、実施された二重戦略は、時代毎の諸条件下において有効であったといる。また、今日的な経済環境、経済条件、経済構造等を十分考慮して21世紀型の二重戦略を生みださなければならない。
【世界が不可逆的にグローバル化を強いられている現在、二重戦略とは「一個二重」のものであろう。】
P20/沖縄が歩んだ歴史から考えて、沖縄経済問題の解決は日本全体にとっても重要な課題であると認識している。つまり、主要な沖縄経済問題は沖縄だけの問題ではなく、日本本土との関連で生じており、また、その解決に対しても日本本土は大きな意味をもっていると思われる。近世において琉球王国は朝鮮とともに日本型華夷秩序を構成し、王国を沖縄県とした際には日本の国境線が明確にされ、広大な領海を得ることができた。日本本土を守る地上戦が沖縄で行われた後、沖縄の米軍基地を担保とする安保体制下において日本政府は軍事費負担を免れ、冷戦期そして今日における安全を享受することが可能となった。
【「日本型」「華夷秩序」とは?】
<第一章 アジア型世界秩序における島嶼経済の位置付け(12世紀~1879年)
<第一章・第一節 海洋と島嶼
<第一章・第二節 中国型華夷秩序と琉球経済
P43/トメ・ピレスは16世紀初頭の琉球または琉球人について次に述べていた。
「われわれの諸王国でミラン[ミラノ]について語るように、シナ人やその他のすべての国民はレキオ人について語る。かれらは正直な人間で、奴隷を買わないし、たとえ全世界とひきかえても自分たちの同胞をうるようなことはしない。かれらはこれについては死を賭ける。レキオ人は偶像崇拝者である。もしかれらが航海に出て、危険に遭遇したときには、かれらは、「もしこれを逃げることができたら、一人の美女を犠牲として買い求め、ジュンコの舳で首を落としましょう」とか、これに似たようなことをいって[祈る]。かれらは色の白い人々で、シナ人よりも良い服装をしており、気位が高い。(中略)レキオ人は自分の商品を自由に掛け売りする。そして代金を受け取る際に、もし人々がかれらを欺いたとしたら、かれらは剣を手にして代金を取り立てる。」(トメ・ピレス)『東方諸国記』岩波書店1966)
P51/首里城殿には琉球の海洋思想が明確に記された鐘が吊るされた。「…琉球国ハ南海ノ勝地ニシテ、三韓ノ秀ヲ鍾メ、大明ヲ似テ輔車トナシ、日域ヲ以テ唇歯ト為ス、此ノ二ノ中間ニ在リテ湧出スルトコロノ蓬莱島ナリ、舟楫ヲテ万国ノ津梁ト為シ、異産至宝ハ十方刹ニ充満ゼリ、地霊ニ人満チ、遠ク和夏ノ仁風ヲ扇グ、…」
【レキオ人-万国津梁の鐘、海邦民】
<第一章・第三節 日本型華夷秩序と琉球
P57/中国型華夷秩序は、周辺諸国や地域を道徳的観点に基づき中国を中心にして位置づけ、冊封使を中国から送り国王等の就任を認め、周辺国は進貢使を派遣して臣下の礼をとるという外交・儀礼関係を特徴とした。他方、日本型華夷秩序では、朝鮮からの通信使、琉球からの慶賀使、謝恩使が政府に送られたが、中国のように、幕府は朝鮮や琉球の国王就任を認める冊封使を派遣しなかった。中国は周辺諸国地域の内政に原則として介入しなかったが、日本は1609年に琉球を自らの支配下におき、内政にも介入した。中国や日本は自らを中心とする外交関係に並行した形で活発な貿易活動を認めたところに両秩序の共通性がある。
【「華夷秩序」とは「中華帝国」=中国型をさす。これに比して「日本」は1冊封使を派遣せず2内政に介入(監督官常駐)3自由な貿易を認めていない。-これを「日本型華夷秩序」としては日本の支配を「美化」することになるのではないか。】
P60/使節派遣において中国型華夷秩序との違いは、中国の場合、進貢使の派遣に対応する形で中国から冊封使が送られた。日本型では琉球側が一方的に使節を送ったが、その代わり琉球には薩摩の役人が常駐しており、中国型とは異なり政治経済的な介入が行われた。1611年、薩摩は「掟十五箇条」を琉球に示し、その遵守を命じた。
P61/以上のように中国が琉球王国の内政に干渉しなかったのに対し、日本は内政に干渉し、納税の義務まで課したことに大きな違いがある。次に引用する文章は1614年に琉球に漂着したイギリス人の書簡であり、当時のイギリス人による琉球認識の一端を明らかにしている。
「薩摩の藩主、島津殿によって支配された琉球は日本の法律や慣習の下にあり、中国貿易から得られる
特権的利益はもうその手にはない。」
【「大きな違い」と松嶋は述べるが、「質的な違い」であり、両者を「華夷秩序」というタームで括ることは問題を曖昧にしてしまうのではないか。】
P63/1609年の琉球の人口は約10万人であった。100年後には約18万人に、そして1879年には約32万人と約三倍に増大した。八重山の人口は1647年には1482人であったが、1761年には2万6792人へと約五倍に増大した。この人口の増大からも明らかなように近世琉球は薩摩による支配で社会が停滞していたのではなく、薩摩から生産性向上のために技術体系、物産、諸制度を導入することで経済発展を実現していたといえる。
【薩摩支配での発展(生産性向上など)を「従属的発展」「低開発の開発」という植民地経済の典型であることを忘れている。これは、朝鮮や台湾の植民地支配も「日本は良いことをしていた」なる言説に通底してしまうのでは?】
P70/白石[新井白石『南島志』1719]は実際に琉球人と対話して南倭(琉球)に日本の古俗が残っていると考え、琉球王から幕府に対する書簡を漢文からひらがな書きにあらためさせたが、これは同国意識から出たものであるといえる。
白石は他方で琉球異国化の措置もとり、琉球使節の役職名を日本名から漢名に変更した。この白石の相矛盾する行動は日本型華夷秩序における琉球の特殊な位置を明らかにしている。すなわち、琉球を日本の統治下におくために琉球文化は日本文化と同一であると強調する必要があるとともに、日本型華夷秩序という日本の世界秩序を形成するためには異国としての琉球が日本に朝貢することが不可欠であった。
しかし、琉球の同国化と異国化という二重性は日本との関係において生じるものであった。中国型華夷秩序の中の琉球は夷として中国に従属していても、それは儀礼関係上のことであり、政治的にはあくまでも独立した国家、つまり異国として存在していた。日本が琉球による中国への朝貢冊封を認めたのも、貿易上の利益を得ることと同時に、その異国性による日本を中心とした世界秩序をつくるためでもあった。このように日本型華夷秩序と中国型華夷秩序では琉球の位置付け方に相違がみられた。その違いが幕末期における琉球帰属に関する議論において大きな影響を与えることになる。
<第一章・第四節 琉球型華夷秩序の形成
P82/1571年、尚元王(1528~1572年、第二尚氏第五代王)が奄美大島に軍船50隻を派遣した際の理由も「貢を絶ちて朝せず」であった。日本型華夷秩序が薩摩による琉球の侵攻を契機として形成されたように、琉球型華夷秩序も王府による先島そして奄美諸島への侵攻によって作り上げられた。先島を夷とみなし、附庸国と考えたことは近世琉球においても変わらず、次の『救陽』、『琉球国由来記』、『おもろそうし』にも琉球型華夷秩序観をみることができる。
【琉球型は、中国型のミニ版の形式だろうが、オヤケアカハチ問題も奄美制圧問題も、近年、前者は八重山・石垣の内紛、後者は島津侵攻への予防的措置として、見直しがなされている。】
P96/つまり、ニライカナイは島嶼民にとって必要なものを供給してくれると同時に、島嶼民にとり害となるものを吸収してくれる場所でもある。島嶼社会の人々は孤立して生きてゆけず、島嶼外部の文化、制度、技術を導入する必要があり、そのために中国型夷秩序や日本型華夷秩序を積極的に活用することになった。それと同時に、ニライカナイ信仰は島嶼外部に存在する経済的豊かさに依存してしまう精神的傾向を助長し、後の章で論じるように企業誘致や補助金依存等、他律依存的な経済構造を琉球に植えつけた一因なったのではないかと考える。
陸地的政策については薩摩の指示に従った。しかし、貿易という海洋国家存立の生命線については譲らなかった。そこから羽地[朝秀]が琉球を近世においても海洋国家として存続させようとしていたことがわかる。
また、『中山世鑑』の中で羽地は琉球王国内の島々を華と夷に秩序付けており、琉球型華夷秩序という認識の枠組みを提示した。薩摩の侵入を受けて王国の体制が揺らぐ中、王国としての在立基盤を確立するために右記のような世界観を強調したと思われる。
【こうしたニライカナイ信仰の解釈は復帰闘争時にも言われた。うろ覚えだが琉大学祭のテーマが「ニライカナイとの訣別」だったような気がする。】
P107/ここ[蔡温がまとめた『御教条』]で重要なのは島嶼性から生じる問題を克服するために貿易を重視していることと、中国型・日本型華夷秩序に属することで様々な恩恵を獲得することが可能になったという蔡温の認識である。
他方で、蔡温は琉球史である『中山世譜』の編纂にかかわっており、先に論じたような同書の中で琉球王国の島々が華と夷に秩序付けられている。このように蔡温も羽地と同様に、琉球型華夷秩序という世界観を認識していたことがわかる。
蔡温は『御教条』において琉球にとって貿易を発展の軸としながら、中国や日本という大国と平和的な関係を維持してゆくことこそが国家最大の目的であると主張していた。その際、中国や日本の諸制度、技術等をそのまま導入するのではなく、琉球の生態系や政治経済状態を踏まえて経済政策が必要であると考えていた。その意味で蔡温の経済思想を琉球における内発的発展論の源流の一つとして位置付けることがでよう。
【この認識は、現状追認(というより追随)なのだ。苛酷な薩摩支配の下で何とか光明を見出したいとする蔡温への評価を見誤っては行けない。羽地から蔡温への「日琉同祖論」の真実を見極めたい。ちなみに評者は、かつて西銘を「現代版蔡温」としたことがある。】
<第二章 近代国家日本の中の沖縄経済(1879~1945年)
<第二章・第一節 近代沖縄における島嶼経済問題
P125/次のように沖縄独立を提唱したのが植木枝盛である。「夫レ琉球ハ独立セシム可シ。琉球ヲ独立セシムルハ有道ノ事ニシテ開明ノ義ニ進ムモノナリ。天下ノ勇アル者何ゾ為サゞル可ケン哉。」
P135/沖縄経済をさらに外部依存的な体質にしたのは、寄留商人をはじめとする本土の資本家の存在である。(…)
糖業において寄留商人による中間搾取が存在していた。その他の商業において他府県人が勢力を増大しており、さらに政治的力も手に入れており、太田[朝敷]はこのような状況を「植民地」であると規定している。
【寄留商人や本土資本家による「経済的支配」の前提こそを植民地(政治)支配なのだ。】
<第二章・第二節 近代沖縄社会の内発的発展
P161/沖縄の村落が保有している相互扶助の機能を利用してつくられた施設が共同店である。最初の共同店は1906年に設置された沖縄本島北部の奥区の共同店である。それが設置された背景には次のような事情があった。他地域の商人が村の林産物と日用品の交換を独占するとともに,「マチヤミシン」と呼ばれた延べ売りを行ない、村人の生活が困難に陥っていた。それに対して、村人は共同店により生産物の共同販売、日用品の共同購入を始めた。共同店は国頭村、大宜味村、東村、久志村等、他の本島北部諸村にも設立された。
北部諸村に共同店が設立されたその他の理由は次の諸点である。(一)村人が山林に対し平等な収益権を保持しており、共同体の基盤が強かった。(二)王国時代から村は船を所有しており、それを共同店が引き継ぐ形で利用できた。(三)1903年まで村人は耕作地を共有しており、土地の私有制が実施された後も村人には貧富の格差は殆ど存在していなかったため、村人は共同店経営に平等な立場で参加できた。(四)灌漑用水の共同利用、堰の構築や取壊し、用水路の掃除や補修を村人は協力して行なっており、そのような相互扶助の機能が共同店に受け継がれた。また、ブー、イーマール、カシィーと呼ばれた各種の共同作業も村の人々の団結力を強くした。
【貧しさゆえの共同性の転質】
P168/沖縄県からの移民は1899年にハワイに向けて出発した時に始まる。これを実現させたのが當山久三(1868~1910年、後に県会議員)であり、次のように述べている。「いざ行かん吾等の家は五大州 誠一つの金武世界石」
P169/ブラジル移民の大部分はサンパウロ州政府の渡航費補助を受け、コーヒー農園で働く契約移民であった。移民会社は州政府と契約して、日本の外務省の許可を得たうえで、各県において移民を募集した。外務省は1913年以来、農園からの逃亡者が多い鹿児島県とともに沖縄県からの募集を禁止したが、17年には解禁された。しかし、19年には沖縄だけが募集数を大幅に削減され、20年には再び募集禁止措置がとられた。
P170/他府県人からも沖縄県民の送金額の多さが指摘されており、送金額の多さは沖縄の貧しさを反映しているとともに、移民先と沖縄とが経済的に強く結ばれていることを意味していた。他方、移民の賃金がブラジル経済に循環されていないとして地元民の不満が生じていた。沖縄移民に対する批判を解消し、渡航制限を撤廃するために、1924年に沖縄県海外協会が設立された。同協会の会長は県知事であり、県庁内に事務局を置き、各市町村に支部が設置され、市町村長が支部長に就任し、ブラジル移民の再開運動を行なった。
その結果、1926年、外務省は次の条件付きで移民を許可したが、渡航制限措置は36年まで続いた。
(…)第19回初等教育研究会では小学校における移民教育として話し方教育と礼儀作法の必要性が主張された。また、31年の沖縄県海外協会の渡航心得「ブラジル渡航ノ方々ヘ」では沖縄県民同士の共通語会話の奨励、移民船上での三線使用の禁止が明記されていた。
以上のように、沖縄県海外協会が全島的な組織を有し、学校においても移民教育が行なわれたことからわかるように、移民活動が沖縄県民の生存にとって非常に重要であると認識されていた。沖縄方言や女性の入墨という沖縄の風俗を改めることが日本人として海外に行く際に要求された。その際に沖縄側が自主的に行なった標準語奨励運動等は、沖縄出身者が差別されず経済活動を行なうための方法であったといえよう。
【海外にまで行って、「日本/日本人」に差別されるとは?松嶋はあまりに淡泊すぎないか。】
<第二章・第三節 近代沖縄における経済思想
P178/1719年当時は、儒者の程順則(1663~1734年、琉球最初の教育機関である明倫堂の建立を建議)、画家の殷元良(1718~67年、国王お抱え絵師)、和文学者の平敷屋朝敏(1700~73年、和文の物語作者)歌人の恩納ナビ(生没年不詳、琉歌作者)、政治家の蔡温等が活躍したところであり、伊波[普猷]はこの時代を沖縄のルネサンス時代と呼んでいる。組踊り作者の玉城朝薫を紹介する際、日本からの影響と同時(普猷)に、琉球古典を復活させたことを強調し、西欧における文芸復興と比較することで琉球文化を世界史の中に位置付けた。
P179/伊波は近代において沖縄の歴史文化の独自性を探求したが、その前提には沖縄と日本本土の文化が同一であるという日琉同祖論が存在していた。近代化により日本本土で失われた文化の古い姿が沖縄には残っているというのが伊波の研究上の結論の一つであった。先に論じたように近世の羽地も同様な認識を示していたが、伊波は日琉同祖論を言語学、歴史学の観点から証明した。(…)ただ、これまでの同祖論との大きな違いは、日本本土と共通の文化的基盤を有することを前提としながら、独自な歴史を歩んだ沖縄の文化的な個性も明らかにしたことである。
次の引用は伊波最後の著作からの文である。米軍統治下におかれた沖縄を見据えながら沖縄の過去と将来について述べている。
「沖縄の帰属問題は、近く開かれる講和会議で決定されるが、沖縄人はそれまでに、それに関する帰属を述べる自由を有するとしても、現在の世界の情勢から推すと、自分の運命を自分で決定することの出来ない境遇におかれていることを知らなければならない。彼等はその子孫に対して斯くありたいと希望することは出来ても、斯くあるべしと命令することは出来ないはずだ。というのは、置県後僅々七十年間における人心の変化を見ても、うなづかれよう。否、伝統さえも他の伝統にすげかえられることを覚悟しておく必要がある。すべては後に来たる者の意志に委ねるほか道はない。それはともあれ、どんな政治の下に生活した時、沖縄人は幸福になれるかという問題は、沖縄史の範囲外にあるがゆえに、それには一切触れないことにして、ここにはたゞ地球上で帝国主義が終りを告げる時、沖縄人は「にが世」から解放されて、「あま世」を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することが出来る、との一言を附記して筆を擱く。」
【謝花昇の憤死を想起した。】
P181/以上のように伊波は琉球併合によって沖縄的なものが否定されてゆく時代背景にあって、沖縄文化の独自性を明らかにし、島嶼における貿易の重要性を指摘し、太平洋島嶼との比較研究の先達となり、世界システムに左右される琉球を緊張感をもって認識していた。近代国家日本の一部になった沖縄において近代化を浸透させるための実践を行なったり、日琉同祖論を展開して「琉球人」に対する差別を解消しようともした。
伊波が主張した琉球の独自性はあくまでも日本文化と琉球文化は歴史的に遡れば共通性をもっているということを前提としていた。それは学問的な探求の結果としての日琉同祖論であるとともに、羽地朝秀と同じく日本と調和した関係を維持するという戦略的な観点をも含むものであったと考える。
【羽地・蔡温から伊波への、松嶋の思い入れは十分理解し得る。】
P195/アジア型世界秩序は華夷という文化的秩序観に基づく国家間関係であった。19世紀に入りアジアにおいて国境線が確定されていく過程で、日本は近代国家建設の必要上、琉球王国を編入し、その島と海に対する所有の権利を明確にした。そして、琉球処分後、近代資本主義の中に沖縄が巻き込まれることで移輸入の増大、モノカルチャーの弊害、ソテツ地獄等、様々な諸問題が生じた。
【華夷秩序の中国(清)と、帝国主義としてアジアへ踏み出す日本。】
その問題に対し沖縄では内発的発展の試みが行なわれ、政治的自治と経済的自立を求めた運動や実践が展開された。また、伊波、太田、謝花等は近代的な島嶼経済の混乱という状況と向き合いながら、独自の経済思想を生みだした。これらの思想は沖縄経済社会の現実を踏まえたうえで、近代化を安定した形で推進することを共通の課題として考えていた。実際、沖縄では在来型の発展方法が存在しており、それが資本主義の進展にともなう諸問題をある程度緩和させたとはいえよう。
伊波は内発的発展の土台となる文化的独自性を学問的に確立し、太田は新聞を通じて沖縄内在の発展方法を押し進め、謝花は政治運動による政治的自立や農業協同組合による経済的自立について論じ、実践した。
近代沖縄において注目されるのは移民活動である。島嶼という地理的制約を越えて、アジア・太平洋に働く場所を求め、沖縄に送金等の形で経済的な還元を行なった。沖縄経済の活動範囲が海洋世界に広がったのは琉球王国時代の貿易活動と同様である。近代において王国が消滅し、諸外国と交渉する権限を失った沖縄は、国家に代わって島民の一人一人が対外活動の担い手となった。特に南洋群島において沖縄移民が産業振興の中心的役割を果たしたことは特筆されてよい。
【はてさて、こうした手放しの賛美で良いのか。日本帝国主義のドイツから奪い取った南洋諸島での植民地経営へ駆り出され、日本人移民の下層に位置付けられた沖縄人。】
<第三章 米軍統治下の島嶼経済(1945~1972年)
<第三章・第一節 島嶼経済の問題とその解決策
P213/海と島との経済関係について論じた議論にMIRAB経済論がある。MIRABとは次の言葉の頭文字を組み合わせたものである。MI(Migration)は移民社会、R(Remittance)は送金収入、A(Aid)は経済援助、B(Bureaucracy)は官僚組織の肥大化と民間セクターの欠如をそれぞれ意味している。島嶼経済において送金、援助金そして政府部門がどの様な意味をもっているかがMIRAB経済論では議論されている。
その提唱者はR・ワッターズとI・バートラムである。
P216/近現代の沖縄において送金、援助金等が構造的性格のものとなった段階では、外部的依存状態を直ちに脱却することは困難であり、島嶼経済内部の生産力を強化するために外部性の資金を効率よく利用し、徐々に経済基盤を強化することで経済的自立を図る必要があるだろう。
<第三章・第二節 復帰前の沖縄軍事基地と島嶼経済
P238/容易に収入の途が得られる軍作業の魅力、ドル景気と商業資本が生み出した消費的な風潮から、戦前と比べ農漁業は衰退していった。戦前には農家の平均耕作面積は七反五畝であったが、1953年頃には三反九畝に減少した。五反未満の耕作面積で働く農家は全農家の八割を占めるようになった。また、戦前の農家の78%が専業農家であったが、1953年頃にはその割合が25・8%に減少した。しかし、50年代の半ば以降、日本政府による砂糖、パインに対する特別措置が実施され、それらの作物の栽培が大規模に行なわれるようになった。
土地が基地用地として接収され農業をする基盤が奪われたこと、作業がきつく収入の少ない農業を嫌ったこと、基地関連の産業が生まれてきたこと等が農業離れを促した。
工業生産物の自給率はどのような状況にあったのであろうか。1967年の沖縄における工業製品の自給率は次の通りである。タバコ製造業が94%、木材・木製品製造業が71%、家具・装備品製造業が69%、皮革・同製品製造業が67%、窯業・土石製品製造業が65%、出版・印刷・同関連製造業が64%、食料品製造業が61%等であり、現在の状況と比べると自給率は高いといえる。
【現在の異常さを強調すべきではないのか。】
P241/為替レートは、基地建設とその維持を効果的に行なうことを第一の目的にして決定された。1949年に120B円=1ドルのレートが内定され、50年に実施された(B円は軍事布告に基づいて発行された「補助B型軍票」が正式名称)。これには次のような背景がある。基地建設をスムーズに行なうための経済的環境として軍部が重視したことは経済の安定とインフレの防止であり、基地建設労働者の確保であった。当時、基地労働者の賃金は民間企業で働く労働者賃金の3分の1から4分の1でしかなかった。低い賃金水準を維持するためには島内のインフレを抑える必要があり、インフレを防止するためにB円高に為替を設定して、輸入品の価格を下げようとした。米国民政府は輸入価格を抑制するためには「輸出産業を育成する必要はない」と公言していたという。
【輸出どころではない、自前の生産力を保持・拡大する必要のない輸入依存経済-それは米軍政・基地経済への依存することを強いられる-に落とし込められた。】
P243/沖縄の税制は日本本土と比べて次の点で異なっていた。『沖縄タイムス』の1961年の記事によると、沖縄の方が日本本土に比べて、日用品への税金が多く、奢侈品への税金が少なかった。貴金属や宝石類に対しては本土では70%から80%の税金が課せられていたが、沖縄ではそれが5%であった。自家用普通乗用車への自動車税は沖縄では21ドルであったが、本土では166ドルであった。つまり日用品の島内生産を奨励するような税制ではなく、奢侈品の消費を促し、輸入に大きく依存させるような性格をもつ税制であった。また、同税制は人々に所得を蓄積させ、投資に回すという通常の資本蓄積や製造業の育成を阻害し、島内の貧富の格差を拡大させるという問題を含んでいた。
【いわゆる「買弁勢力」育成と対になっており、ここでも問われているのは「政治」である。】
P247/53年に発行された『沖縄大観』には次のような記述がある。「沖縄における人口は、1950年末現在で、56万2447人で、そのうち沖縄産業の抱擁し得る人口を30万7888人とすれば、残りの25万45550人は過剰人口とみなければならない。しかし、そのうち9万8362人は軍作業に従事する2万人の労務者が扶養する人口である。軍作業が続く限り要移民数は15万6197人と推定される。しかし軍作業員が減少すれば、それだけ要移民数は増えるわけである。」
右の文で興味深いのは沖縄内部の経済力で養える人口水準を超える人々は、軍作業を行なうか、移住をしなければならないという指摘である。軍作業の機会が増えるほど移住者数は少なくてすんだという意味で、海外移住そして沖縄内の移住は基地経済と密接な関係があったといえる。戦前、戦後も島嶼経済の困難性が移民のプッシュ要因であったが、戦後は基地建設にともなって経済活動を行なうための場所が縮小されるという新たな要因が加わった。1955年に立法院は次のような「沖縄移民受入方に関する請願決議」を採択した。
「言語に絶する程の戦争災害を受け、更に軍事施設のために四万エーカー余の土地を接収され、土地狭隘、人口稠密で苦しんでいる沖縄において移民の送出しは絶対必要なことである。」
<第三章・第三節 米軍統治下における経済思想
P269/島産品愛用運動は「産業振興」、「輸出の増進」、「島内自給度の向上」、「輸入削減、輸入防止」を目標として展開された。1954年当時は琉球政府の保護措置をうけた醤油を除いて、輸入品に押され気味であった。同年の『沖縄タイムス』社説は以下のように論じている。
「島産愛用は単に産業関係のものだけであってはならぬ。それは同時に文化にたいしても言えることであろう。産業の場合、それが生活のながい伝統によって培われ、業者の生活と渾然一体化した、生産のよろこびが即生活の楽しさともなり、生産されたものは物質であっても、しかし業者の人間的な愛情がたっぷり注がれ、この愛情が売る人、買う人の関係を利潤追求の欲得だけにとどめないで血の通ったものとする、島産愛用もそうした極致に達しないと長続きしないだろう。(中略)廃藩置県以来かもされた郷土卑下の風潮が、島産の文化や産業に寄せる愛情を惜しみなく奪い、衰微の一途を辿らしたのである。島産愛用は、この愛情の煥発が先決であり、島産文化の振興もこの愛情がないでは望めぬだろう。とは言え郷土の古文化財は嘗ての戦争でおおかた失われ、郷土文化を示して、十分な理解に訴え、おもむろに愛情を煥発する、という啓蒙運動が容易でないことは返す返すも残念である。だが、万難を排して文化財保護に努力し、郷土文化の再認識をひろく一般にうったえることは、新しい文化創造のためにも是非望ましいことであろう。」
島産愛用運動が単に輸入代替という政策の段階にとどまるのではなく、生産や消費過程において島産品を通じて島民同士が相互理解することが目標とされた。
【復帰運動との絡みも忘れずに。】
P283/宮本[憲一]の経済思想の特徴は沖縄経済の現状を批判的に分析するだけではなく、自らが考える地域開発のための具体案を提示したことである。まず、沖縄の地域開発を実施するうえにおいて沖縄がもっている可能性を次のように挙げている。(一)沖縄住民の政治意識の高さ。「この自治意識にもとづく巨大な政治エネルギーが、基地を解放し、地域開発へ結集するならば、新しい開発方式は必ず生まれるであろう」としている。(二)沖縄住民の知的能力が優れていること。(三)民主的地方自治体が確立していること。(四)地元の資本や技術による開発が着実に進んでいること。
【米軍政支配下での民衆の闘いと相即であろう。】
<第四章 日本本土復帰と島嶼経済(1972~2000年)
<第四章・第一節 復帰後沖縄経済の構造
P295/沖縄開発庁の所管事務は次の通りである。(一)沖縄振興開発計画(沖振計)の作成とそのために必要な調査を行なう。(二)沖振計の実施を推進し、関係機関との調整をする。沖振計の事業経費の見積もり方針を調整し、特定経費ついての配分計画を行なう。(三)沖縄振興開発特別措置法(沖振法)の施行に関する事務を行なう。(四)軍用地の中で位置境界が不明確な土地の調査を実施する。(五)沖縄振興開発金融公庫の監督について総理大臣の補佐をする。(六)多極分散型国土形成促進法に基づいた沖縄における振興拠点地域の開発整備について総理大臣の補佐をする。(七)沖縄の復帰に伴う特別の措置に関する事務を行なう。
以上のような沖縄開発に権限をもつ沖縄開発庁に対しては、復帰前に次のような批判が見られた。(一)琉球政府が保持していた自治権が沖縄開発庁の設置により侵害される。(二)県の上にさらに機関が設置されることで二重行政の弊害が生じる。このような批判はあったが、沖縄と本土との経済格差を解消することが復帰後の最大の目標となったため沖縄開発庁と総合事務局は予定通り設置された。
沖縄開発庁が存在することで、他都道府県よりも有利な形で公共事業が行なわれた。沖縄開発庁一括計上方式と呼ばれる予算計上の方法がある。それは各省庁で実施する事業予算を一度、沖縄開発庁の予算に一括して計上した後に、執行段階で各省庁へ予算の移し替えを行なう方法である。例えば、1997年2月に開通した浜比嘉大橋は総事業費が約90億円であったが、他都道府県では自己負担額が約45億円にのぼると推定されているのに対し、沖縄県の自己負担額は約9億円ですんだ。その理由は沖縄において離島架橋事業の補助率が10分の9であったためである。その他の開発対象にも高い補助率が適用された。他方、85年と95年における各事業の予算比率を比較してみると、治山治水が1・03%から1・23%から、道路が3・86%から3・92%、港湾が8・68%から9・0%へと、ほとんど比率が変化していない。沖縄開発庁は固定された事業予算のシェアーを維持することを優先し、事業の効果を軽視した予算を作成する傾向にあるといわれている。この様な開発行政の結果、復帰後多くの公共事業が実施されたにもかかわらず、補助金依存の経済構造が形成されただけで、歪んだ産業構造の是正につながらなかった。
【「にもかかわらず」ではなく、「それゆえに」ではないか。】
P303/1999年における沖縄県歳入の構成比をみると、自主財源が23・0%(内、県税が13・7%)であるのに対し、依存財源は77・1%(内、国庫支出金が36・3%、地方交付税が32・9%、県債が7・7%)にのぼった。他方、全国平均値自主財源が47・1%、依存財源が52・9%となっており、沖縄県の財政が外部に収入源を大きく依存していることがわかる。市町村財政においても沖縄県の場合、自主財源が30・0%、依存財源が70・0%であるのに対し、全国平均では前者が50・9%、後者が33・5%であり、市町村レベルでも依存度が高い。
また、1996年における沖縄県の一人当たり行政投資額は47万5千円であり、全国平均の39万円を上回り、全国一の水準となっている。特に、復帰後から96年までの間、73年を除いて行政投資額の内、産業基盤投資、生活基盤投資、農林水産投資それぞれの金額は全国平均を上回った。国から産業関連、生活関連の多くの補助金が投下されてきたことがわかる。
【日本依存-補助金経済は、基地建設から引き継ぎ、格差是正・インフラ整備、そして今また振興策と、土建型経済のみを蔓延させた。】
P304/補助金は沖縄経済にとりどのような意味を持っているのであろうか。日本本土と沖縄との間には経済的ブーメラン効果と呼ばれる経済現象がみられる。それは沖縄に投入された補助金や投下資本が、日本本土からの商品の購入、本土企業による観光開発・企業の合併や下請け化等によって日本本土に還流する状態を指す。経済ブーメラン効果は「ザル経済」とも呼ばれ、外部から投下された資金が沖縄内に蓄積されず、歪んだ産業構造が改善されなかった。
【この「ブーメラン」こそ植民地経済の典型である。】
P307/沖縄の経済成長を目標として金武湾の珊瑚を埋めて造成したのがCTS(石油備蓄基地)である。CTSの関係者が当初、環境保全を説いていたにもかかわらず、海が汚染された。金武湾に面している与那城村だけで1972年に195トンの収穫量があったモズクが76年には1トンに激減した。埋め立てに際して漁民が手にした漁業補償は1億2千万円であった。72年の全水揚げ量を79年のセリ値で計算すると、約4億8千万円になるという。そして、クルマエビ、貝、ウニ、海人草、ヒトエクサ、サンゴ、ホンダワラ、アマモ等が少なくなり、カモも飛来しなくなった。さらに、当初、CTS内に設立されていた企業は480人を地元から採用すると約束しながら、実際は80年の時点で194人しか雇用せず、与邦城村でも安全対策のための経費が増えた。時代状況の波に乗り遅れたという側面はあるが、環境影響や経済波及効果に関する調査や対策が不備であったために、経済的だけでなく、生活上も人々や村役場に豊かさをもたらさなかった。
島嶼環境の破壊は沖縄本島の北部や中部、そして先島だけの問題だけではなく、都市部でも環境汚染が深刻になった。復帰特別措置として本土よりも二〇倍近い高濃度の畜産排水を放流することが許された。その結果、日本のワースト五河川の内の三つが那覇市内の川であった時期である。
【製造業だけではない、農漁業・第一次産業そのものが不必要とされる。極言すれば、この島は軍事基地機能維持のためだけに存在を許されたが故に、不断に、基地に依存してしか生存し得ない構造を作り上げられる。】
P307/基地と沖縄経済
2000年3月現在において、沖縄全面積の10・5%が米軍基地であり、沖縄本島だけに限定するとその面積の18・9%を基地が占有している。さらに、在日米軍の専用基地全体の74・8%が沖縄に置かれている。島嶼の陸地以外にも訓練空域、訓練水域、射爆場があり、沖縄は基地に取り巻かれているといえる。
P314/補助金の投入等で県民総支出自体が増大したことにより、軍関係受取が占める比率が低下したが、同受取は金額としては無視できない額である。
失業率の高い沖縄にとり基地は、沖縄県庁に次いで二番目に、大きな就職先である。つまり、2000年三月末現在、駐留軍従業員は8,450人に上っており、完全失業率が高水準にある沖縄にとって職場として基地は大きな意味をもっている。基地労働者の職種は事務、技能、公安(警備や消防)、医療等に分かれている。基地はその労働条件や給与条件のよさから多くの人々を引きつけている。
1998年において基地が撤去されると仮定すると、軍関連受取の約1,873億円が存在しなくなることを意味する。この金額を民間部門において生み出すのは容易なことではない。また、沖縄本島の中部や北部には基地関連交付金等の軍関連受取が歳入総額の20%以上を占める町村が四カ所存在している等、地方財政とっても基地経済が持つ意味は大きい。
以上のような沖縄経済の現実を踏まえて、沖縄の経済発展を考える必要がある。基地が撤去されれば自動的に沖縄経済が発展するという保証はない。基地撤去後に生じるであろう失業、軍関係受取の消滅等の問題に対する対策が重要な課題となろう。
<第四章・第二節 本土復帰後における沖縄の経済思想
P316/宮古島出身で、イリノイ大学の労働経済学教授であった平恒次は米軍統治時代から沖縄独立を主張していたが、沖縄県となってから平は全世界的琉球精神共和国論と呼ばれる独立論を展開した。琉球共和国の構成員は琉球列島に住む人々だけではなく、世界中で生活している沖縄県出身者を含めている。主権国家になることによって得られる特権は領海権であり、それにより入漁料、船舶の通過料等を財政収入とすることができる。そして、国際的な金融業や流通業、医療保健福祉サービス業等を自由に展開することも可能となる。もっとも島嶼国家は経済自立が困難であるため、世界の各地に住んでいる沖縄出身者による沖縄の経済発展のための協力が必要とされる。沖縄と世界各地に定住している沖縄出身者をつなぐものが、郷土沖縄に対する愛着である「世界的琉球精神」であるとしている。
平の島嶼国家論はMIRAB経済論と共通する側面をもっており、島嶼と外部世界との関連性の中で島嶼経済を認識している。しかし、太平洋島嶼は独立後間もないが、大国からの補助金に依存しており、経済自立化が最大の課題となっている。入漁料の対象となるのはマグロやカツオであるが、それらは回遊魚であり、近年、沖縄近海では減少しており、国家の収入源として期待することは困難であろう。また、島嶼国の中にはオフショアー市場(非居住者を対象にした、税制上の優遇措置がほどこされた市場)を設置している島嶼もあり、マネーロンダリング(犯罪組織が自らの資金を洗浄すること)に利用される等の問題が指摘されている。つまり、独立してもそのまま経済自立が保証されることはないのである。
島嶼内の経済自立化に関して平は次のように述べている。沖縄県の労働者は能力不相応の高賃金を得ている。地価は機会費用不相応の軍用地代に牽引されて高水準である。インフラ整備において規模の経済が働かず、インフラ整備の単価は高い。このような状態を引き起こしているのは日本政府の補助金である。よって、沖縄の経済自立を達成するには「日本依存謝絶計画」を作成し、経済非常事態を全県的に宣言することで、賃金相応の生産性を上げるべく様々な工夫を行なう必要がある。補助金依存が沖縄経済の構造的問題であるが、補助金を日本政府に返上して独立を図るには沖縄側の自助努力が前提であるとしている。
沖縄の独立論が現実的な可能性を持つには、次の二つの条件が必要となろう。一つ目は、補助金打ち切りに伴う経済水準の低下と景気の低迷などを県民が受け入れることである。二つ目は、補助金に替わる収入を得る方法を具体的に提示することである。
【経済政策論の前提は、その主体と条件であろう。繰り返すが「政治」である。】
P319/原田誠司、安東誠一、矢下徳治等の沖縄研究会による「沖縄経済自立の構想」を簡単に紹介する。
その論文によれば復帰後の沖縄経済は基地経済構造の強化、日本資本への従属化と沖縄経済内の非接合化、過剰労働力構造の深刻化等の特徴をもち、周辺資本主義化がすすみ、「低開発性の発展」という状況が明確になった。そして、沖縄経済の非自律的、非工業的周辺経済化は沖縄県民を収奪や抑圧・差別の構造に陥れたという意味で、沖縄は日本の内国植民地である。そしてこの従属化を打開する方法として次のようなものがある。
(一)S・アミンがいう世界資本主義経済からの離脱、の議論を沖縄にあてはめ、日本から独立することで周辺資本主義分業を拒否し、アジア太平洋圏における新たな分業関係を構築する。
(二)沖縄を差別する日本国家を解体するために、沖縄住民は少数民族として自己認識して日本国内の他の少数民族、社会的弱者、革命家と協力して闘う。
(三)沖縄独立の主体は沖縄民族ブルジョワジーや特権的公務員ではなく共同体民衆であり、沖縄共同体社会主義が目指すべき理想となる。
上の議論は従属論の概念をそのまま沖縄に当てはめたものであり、独立のための方法も具体性に欠け、沖縄側への影響は少なかったといえる。島嶼の外部で作られた理論を島嶼の特殊性を考慮することなく、島嶼の現実に押し付けている。島嶼に内在化する形で理論は形成すべきであろう。反面、従属論が第三世界で形成された理論であることを考慮すると、沖縄を世界的視点でとらえ、島嶼民と島嶼問題解決の担い手として位置付けたという意味では、この独立論は評価しえる。
【カワイソー。「世界(史)的視点」はもっと考究されるべき。】
P320/沖縄の政治形態として県よりもさらに自治性の高い形態を提起したのが特別県制論である。それは1981年に自治労沖縄県本部により提示されたが、沖縄開発庁が推進する開発により沖縄の自治が衰退したという認識から、特別県の設置を求めた。特別県は振興開発計画の策定権や実施権を有し、地方税、地方譲与税、地方交付税、補助金等が一括して特別県に交付され、その利用については特別県の自主性に委ねられるというものである。
島袋純は、沖縄の自治権を確立する方法の一つとして自治州を紹介している。それは復帰前の琉球政府が有していた法体系、組織、権限体系を基盤にし、課税権、関税自主権、そして沖縄開発庁の権限である予算編成権、教育に関する権利等を行使できる自治制度である。そのために、住民投票によって自治州設置のための地域特別立法をつくる必要があるとしている。沖縄が本来の自治を回復するためには、必ずしも県制である必要はなく、日本の国に属しながら他の形の政治形態のあり方が可能であると島袋は世界における自治制度の研究から導き出している。太平洋島嶼においても、ニュージーランドと自由連合協定を結んでいるクック諸島、ニウエ、トケラウは軍事権以外の内政権を有している。
【「自治の衰退」-これはキーワード。但し、日本併合による「制度的後退」だけではない。沖縄民衆の自己統治意識・能力こそ問われる。】
P322/[宮本憲一は]沖縄県民自身による経済活動によって沖縄経済が発展しなければならないとし、それを行政が支援する「沖縄方式」を確立する必要があるとしている。「沖縄方式」とは、沖縄の諸条件を考慮し、沖縄内部に自立した経済人や技術人を創出する試みであり、経営主体としては例えば協同組合方式、自治体の公社が望ましいとしている。宮本の「沖縄方式」は、近代沖縄の太田朝敷や謝花昇が提唱した産業組合の活用や「生産力」の形成という考え方と共通しており、島嶼内発の経済発展のあり方を目指している。
ただ、宮本の場合、右の「沖縄方式」を実現するためには沖縄の行政的枠組みの変更が不可欠であるとする点に独自性がある。宮本は復帰特別措置法終了後の沖縄のあり方に関して次のように述べている。地方自治法を改正して特別都道府県制を沖縄に適用する。それは、軍事、外交、裁判、貨幣制度等の一部を除いた内政的国政事務と、都道府県本来の業務を実施する機関であり、財源として国税を地方に委譲するとともに、自主財源だけでは十分でない場合には傾斜交付税で補い、起債は自由とし、補助金は全廃する。そして、沖縄開発庁は沖縄県庁に統合する。中央政府への財政依存をさけるために、一括贈与金を沖縄県に提供し、これを行政基金として利用する。宮本は特別都道府県制により沖縄の自治制度が強化されることで、沖縄独自の経済発展が可能になると考えている。
復帰後における独立、特別自治制を求める思想の背景には、復帰後の沖縄に対する膨大な補助金の流入と大規模開発によって自然が破壊され、沖縄独自の社会、文化が変容したことに対する危機感がある。そして、復帰特別措置によって本土との格差が解消せず、歪んだ産業構造が是正されないことから、新たな政治形態を求めることになった。しかし、独立や特別県に至る過程や、その後の経済運営についての具体的な議論が欠落している。
P324/[玉野井芳郎の]米軍統治時代は米軍が一方的に住民を支配していたのではなく、地元企業の勃興に示されるように自主性を発揮できる時代環境でもあったとの指摘は重要である。確かに、米軍の管理下にあるとはいえ、同時代は日本から切り離されることで擬似国家的性格を有することが可能となった。独立法貨としてのB円が1958年まで使用され、輸入代替化政策が行われていた。
【そうなのだ。この「擬似国家」にもっと注目しよう。】
P329/嘉数啓の経済思想
「世界規模にまで広がった市場経済の連鎖の中で、収奪・従属関係を止揚し、対等な相互依存関係を創り出すことが経済自立への基本的な課題である。経済自立はそれ自体が目的ではなく、対外的には政治的自立(自決=Self-determination)、対内的には各意思決定主体の自立(あるいは自治)を担保するものとして位置づけられるべきである。この場合、経済的自立が先か、政治的自立が先かという古くて新しい論争があるが、世界市場に深く組み込まれた現実を直視するとき、経済的自立を獲得することが先決であると思われる。」
P338/西川[潤]の沖縄自立論の独自性は世界新秩序の中で沖縄を考えていることである。西川が重視している参加型の市民社会像は太田朝敷や謝花昇等の産業組合論や、島嶼内在の内発的発展の試みとも共通している。文化、島嶼ネットワーク、持続可能な発展、人間の安全保障研究等に関する研究所を設置し、知的資産を蓄積する産業の育成を唱えており、土地・資源の限られた島嶼性を克服し、情報のボーダーレス化という現代の潮流を利用した沖縄型の経済自立論が展開されている。また、沖縄の経済問題と基地問題を統一的にとらえることで、平和な世界秩序を形成する重要なアクターとして沖縄が存在する可能性を明らかにした。
P339/基地の存在により沖縄経済は外部要因に大きく左右されやすくなった。例えば、基地建設ブーム、スクラップブーム、軍用地代受取、講和前補償、日米政府援助、ベトナム特需等が沖縄に好景気をもたらした。(…)沖縄経済は需要刺激政策により解決できる「需要不足型」の経済ではなく、生産力不足型という第三世界に特有の経済的特徴をもっていると牧野[浩隆]は論じている。生産力を重視する牧野が考える自立経済の主体となるべきものは、資本、労働力、技術、資源等を結合することで財貨やサービスを生み出す企業であった。
P340/沖縄で生産力の強化を図ろうとするとき、それを阻む動きがあり、牧野はそれを政治力学と呼ぶ。例えば、本土企業の沖縄進出を経済的ナショナリズムから拒否したり、1975年に開催された海洋博を運営する本部開発公社への民間企業の参加を阻むことで生産力の島嶼内形成を不可能にした。政治力学とは日本復帰に際して輸入関税の減免、内国消費税の減免、特別輸入割当制度等の特別措置の実施をも指すのであり、近代における旧慣温存政策と共通する性格を持っていると述べている。既得権益を政治力により保護することは経営基盤が脆弱な沖縄企業を守るという面では必要である。しかし、政府による保護政策が沖縄経済全体を対象とし、長期にわたる場合、沖縄側の自助努力の機会が失われるという問題が生じてくるだろう。
【「自助努力-この言葉は余り好きではないが-の喪失」こそ「国内植民地」的支配の結果であろう。】
P341/政治経済状況の変化や人々の関心の推移によって、「告発」という政治的主張の効果は長く続かない。制度的に実施される特別措置は急場を凌ぐだけで、生産力不足という沖縄経済の根本問題の解消には至らない。基地による被害を補助金や特別措置の取引材料にすることで、結果的に基地の存在を認めてしまうことになる。島嶼という狭い空間に広大な基地がおかれることで、他者依存的な経済構造になるとともに、島嶼民自身も基地による被害を理由として基地撤去を求めながら、結果的に基地を担保とした資金の流れに依存せざるを得ないところに基地経済の複雑な問題性があるといえる。
【「沖縄イニシアティブ」のブレーンにして、稲嶺県政の副知事たる牧野経済論は確かに或る面では説得力がある、と言わざるを得ない。】
<第四章・第三節 21世紀に向けた沖縄経済発展のための政策提言
P347/21世紀において沖縄経済が発展するためには、補助金や保護政策に依存するのではなく、沖縄県民自らが自助努力して経済社会を作り上げる必要がある。琉球王国時代の大貿易活動や、近代の移民活動、島嶼内での内発的発展の試み等は、沖縄の人々の経済能力を高さを示している。経済活動の面で長い歴史をもつ沖縄は、この歴史的に蓄積された経済発展の諸方法を経済思想の中から汲み取ることができる強みをもっている。
【「経済思想」は思想である限り、政治を抜きにし得ないのだ。】
P349/現在でも沖縄の歴史文化をイベント化して観光客を呼び込む努力が行なわれている。文化の観光化は、文化の商品化につながり、文化の内実を喪失させるとの見解もある。しかし、文化の観光化の過程で新しい沖縄文化の創造がもたらされ、観光客が沖縄文化を理解する手がかりとなるとともに、沖縄県民も自らの文化を理解し、アイデンティティを確立することもできる。(…)
沖縄文化は単にソフトとしての面だけでなく、物として商品化した物産としても沖縄経済発展にとり重要である。時代に応じて沖縄物産が開発され、今日、沖縄物産が健康食品として見直され、経済的利益をあげている。
村の物産振興において提言したいのは一シマ一品運動である。シマとは沖縄の伝統的な集落単位であり、幾つかの村や、一島を構成単位とする。沖縄は多くの島から構成されているため、市場が分断され、経済発展が阻害されていると指摘されてきた。しかし、発想を逆手にとり、それぞれの島(または過疎化が進む沖縄本島北部の村)において世界に通用する特産物を生産することができれば、必ずしも規模の不経済は問題ではなくなる。
【「わしたショップ」を成功に導いたが、稲嶺県政から追放された宮城弘岩は、今、独力で事業を立ち上げていることに注目しよう。】
P360/公共投資が非公的部門の発展を生み出すような道筋を作り出すのが開発行政の役割である。経済だけでなく、社会、環境にも配慮を払った総体的な観点から沖縄の発展を導く役割を実行し得る権限をもった機関の設立により、沖縄独自の二重戦略の実現が可能になると考える。
また、東京におかれた沖縄開発庁(現在は内閣府)において沖縄の経済計画を策定、実施し、沖縄に出先機関である沖縄総合事務局をおくという体制から脱却する必要がある。東京ではなく、沖縄に大きな権限を有した機関を設置し、地元出身者が主体的に働くことで、沖縄の伝統、環境、社会風土等の島嶼の独自性を踏まえた内発的発展への道が開かれるであろう。
【例えば、沖縄が自立経済を確立したとしよう。そこでは米軍基地も日本政府も必要がない。となれば日本政府は「本土」との「格差」を決して解消しようとはしない。】
<結びに代えて――島嶼経済論と沖縄
P370/沖縄経済思想史を検討した結果、二つの経済発展の方向が明らかになった。それは、貿易や移民等を通じて、島嶼外部との経済関係を強化することで島嶼経済を発展させる方向と、島嶼内部の生産性を向上させて経済構造の安定化を目指す方向である。それは、世界における島嶼経済論の二つの流れである、MIRAB経済論と輸入代替論と重なりあう。経済思想史の検討に基づき本書では最後に二重戦略という形で21世紀における沖縄経済のあり方について提言を行なった。
島嶼は海によって世界に開かれており、外部世界との経済的関係を築くことで、島嶼性から生じる様々な問題を克服することが可能となる。しかし、外部世界は変動的であり、島嶼はその変動に左右されたり、時には政治的な支配力の下に置かれることもある。外部世界の変動や支配による島嶼経済の不安定化を避けるためにも、島嶼内の生産力を向上させ、経済構造を強固にするとともに、草の根的な内発的発展を展開することで沖縄内に発展の機動力を据えおく必要がある。
【移民・貿易/内発型発展-経済的自立のための二重戦略は、自己統治意識-自治能力・自己決定権に裏打ちされていなければならない。その自治能力こそ「自立解放」への意志を必要とする。堂々巡りのような隘路を打ち破る方途を掴み出そう。】
このページのトップにもどる