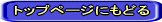『沖縄経済自立の展望― '79第2回シンポジウム報告―』
(比嘉良彦・原田誠司編著/鹿砦社1980.7)
比嘉良彦「沖縄自立経済論の問題点-第一回シンポジウム討論をふりかえって-」
阿部亮一「沖縄と南北問題」
中村敏夫「帝国主義と南北問題-S・アミンの周辺資本主義論に関する検討-」
原田誠司「沖縄経済の独自構造-その週辺資本主義的発展に関する諸問題-」
安東誠一「東北開発と沖縄開発-縁辺化を強いられる地域経済の構造-」
矢下徳治「プエルトリコ問題の歴史的・今日的位相-近代化『開発』と民族自決-」
中村丈夫「沖縄経済自立の展望・序説-地域・共同体・社会主義への一考察-」
※『沖縄経済の自立にむけて』(鹿砦社1979・6・25)
沖縄自立経済論の問題点
-第一回シンポジウム討論をふりかえって-
比嘉 良彦
一、 はじめに
第一回シンポジウムの全記録『沖縄経済の自立にむけて』(鹿砦社)を読んで、その中からいくつかの点について問題提起を行なってみたい。もともと昨年のシンポジウム(以下「自立シンポ」と呼ぶ)は、「沖縄自立経済のために-沖縄経済の現状と自立経済の方法的視点―」という『新沖縄文字(第39号)』の原田・矢下論文を叩き台に行われたものであり、また、その論文自体がこれまで沖縄の自立経済について論じられてきた幾多の著書・論文・地域構想等を批判検討したものであっただけに、自立シンポの内容は、質・量ともに多岐にわたり、そこで取り上げられた問題の全てについて理解し、総括し、整理して新たな問題提起を行なうことは私の力量をはるかにこえるものである。幸い、昨年6月には沖縄タイムス社が創立30周年記念事業として、「あすへの選択-沖縄の新しい経済社会を求めて-」というシンポジウムを開催しており、また今年の6月には、日本平和学会が「1980年代の沖縄-平和と自立・内発的発展の展望」を共通テーマとして1979年度の春季研究会を沖縄で開催している。タイムス・シンポは自立シンポを理解する上での豊富な資料を提供しているし、平和学会での討論には、自立シンポのいくつかの論点を深める意味で貴重なものがあった。これらのことを視野に入れつつ、第一回の自立シンポについて若干コメントしていきたい。
二、 第一回シンポジウムの論点
第一回自立シンポの主題は、問題提起者によれば次の三点であった。
第一は、沖縄経済の現状をどのように把握するか、第二は、これまでの自立経済論議をどのように総括しておくか、第三に、沖縄経済を考える視角の問題である。この第三の問題については『新沖縄文字』の論文では「沖縄経済の後進性・低開発構造の脱却は、自立論とどのように関連しているか」という表現になっているので提起者の意図はそういう点にあるものと解釈し理解している。そこで提起者としては、第一の問題については沖縄経済の現状を「国内植民地」としてとらえ、そこから第二の問題であるこれまでの「自立経済論議」がこの「国内植民地」としての現状認識を欠落させている点を取り上げることによって、その欠点ないし不充分性を指摘し、したがって、第三の問題である「沖縄経済の後進性・低開発構造の脱却」は、従来の「開発」経済学でなく、「自立」経済学の視角からのアプローチが必要であるという結論に導きたい意向のようである。このような整理の仕方が乱暴なことは承知の上で、あえて簡略化して話を進めると、この提起者の意図は半ばしか成功していないようである。なぜなら、第一回シンポの感想を一言で述べるならば、「定義づけ」のための討論会であったといえるのではないかと思われるからである。たとえば、討論は終始、国内植民地とは何か、なぜ国内植民地なのか、自立経済とは何かといった「概念」をめぐって行われており、討論の入口あたりで参加者のエネルギーが大半消費されているようである。
これはどこにその原因があるかといえば、問題提起のなかで用いられた三つの言葉、「国内植民地」「南北問題」「自立経済」といった重要な概念が明確でないことによる。勿論、言葉の意味は、その性質上、一義的に定義づけられるものではないが、論理の展開上ある程度の明確化ないし共同理解がなされなければならない。したがって、ここでも、これらの言葉を中心に第一回の討論をふりかえってみたいと思う。
三、「国内植民地論」の問題点
「国内植民地」についてであるが、提起者によれば「沖縄の経済構造は、72年『復帰』を契機に、それまでの米軍支配下における基地依存経済-軍事植民地的経済構造としての色彩を次第に薄めつつ新しい段階に入りつつある。われわれは、こうした新しい段階を迎えた沖縄と沖縄経済を国内植民地と規定する」と述べ、続けて「沖縄は、工業的中心地域=日本『本土』に対して、一次産品供給に特化された周辺地域であり、併合完成下において、日本国家内部の周辺地域、第三世界としての沖縄と沖縄経済は、日本帝国主義国家の国内植民地として存在しているのである」と沖縄経済の現状を把握している。
このような沖縄経済の把握の仕方が、現時点において適切かどうかについては疑問を感ずるが、はたして、討論において、川満信一氏が「これは別に今に始まったこと、新しいことではないんです。……そういう構造は、60年においてすでにとられていた。……現在の段階では、沖縄は純粋な意味で国内植民地ではない。植民地よりも悪い形で位置づけられている」と鋭く指摘している。
これに対して、中村丈夫氏が「植民地概念というものは、明らかに重商主義の時期と産業資本主義の時期と古典的帝国主義の時期、それからとくに私のいう新植民地主義の時期とでは内容が非常に違っていると思います」と述べ、植民地概念の多様性を指摘して理解を深めている。そして、中村氏は「国内植民地」とは「形式上は本国の平等構成部分であるという形をとりながら、実質的には特殊な質を持つ搾取・収奪・抑圧・疎外のもとにおかれた従属地域をさす概念」と定義づけている。
ここまでくれば、当然、川満氏のいう「植民地よりもっと悪い形で位置づけられている」という沖縄経済の特質や、中村氏のいう「特殊な質を持つ搾取・収奪……」の特殊性といった点が解明されなければならない。
しかし、討論の中では、それが充分に明らかにされたとは言えないようである。特に沖縄経済の現状を「国内植民地」と規定するためには、沖縄の現状が「植民地」概念でまず説明されなければならないことはいうまでもない。つまり、現在の沖縄経済は日本独占による「搾取・収奪・抑圧・疎外」といったものを受けつつ、さらにそれが日本国内の他の地域で行われているそれらのものと異なる特殊なものであることが説明されなければならない。なぜなら、国内の他地域と同様なものであれば、それは資本主義国家内の矛盾、資本家と労働者、支配階級と被支配階級といった階級間の問題としてとらえることができるのであり、あえて、沖縄にだけ「植民地」といった概念を持ち出すまでもないと思われる。しかし、また、たとえ「植民地」概念で説明がつくとしても、そこにさらに「国内」とつけるためには「植民地経済」といわれる沖縄経済が一般的な「植民地」概念を含むと同時にそれが形式上は国内の他地域と平等な構成部分であるという形をとりながら行われているという特殊をも合わせて説明できるものでなければならない。
問題提起者によれば、「国内植民地としての沖縄」、「国内植民地経済としての沖縄経済」という場合の「国内」とは「72年の復帰によって日本国家のなかに沖縄が再度組み込まれたとの意味です」と述べているが単に72年という時間を区切りに沖縄を「国内」植民地と規定するならば、歴史上早い時期に日本の統一国家内に併合された他の地域、特に中村丈夫氏が「東北六県は丁度イタリアの南北問題に匹敵する国内植民地といってもよい特別な地位に置かれていたことは明らかであろう」と述べているかっての東北地方や北陸・新潟地方の経済・社会問題と現在の「沖縄問題」がどこでどう共通項を持ち、どこがどう異質なのかということが「植民地」概念とからめて問題となるのであろう。そこのところがはっきりしないと「沖縄問題というのは単に資本と階級との間の問題とは別個な、日本総体と沖縄総体との支配の構造がどこかにあるわけで、やはり、沖縄の場合、先程の東北との場合とは違うのではないかという感じがします」という友寄英正氏のもっともな指摘がなされる反面、一方では、阿部亮一氏が「一部の先生達には『あなたは沖縄を国内植民地と規定するのか』と異議をぶつけられた」と他の研究会での体験を紹介しているように「沖縄人の感性的反発」(原田氏)をも受けることになるであろう。
四、「国内植民地」概念と沖縄経済
私は、中村氏の「国内植民地」概念、つまり「形式上は本国の平等な構成部分であるという形をとりながら、実質的には特殊な質を持つ搾取・収奪・抑圧・疎外のもとにおかれた従属地域」という定義に依拠しつつ、それがどう沖縄経済の現状と結びつくのかということを考えてみたい。
「沖縄問題」を論ずる場合、「反戦平和の問題」として「基地問題」を語ることは多いが、「経済問題」としての「基地問題」は「軍用地料の問題」として、あるいは「軍雇用員の解雇問題」として、つまり、基地需要(基地収入)の問題や雇用失業の問題として取り上げられるだけで、「軍事基地」総体、あるいはその「軍事基地」を提供し、「共同管理」を行っている日本政府の意思そのものが「沖縄経済」とどう結びついているかというような視点から論じられるということは、これまで少なかったように思われる。たとえば、従来の「沖縄経済」に関する「基地問題」の取り上げ方は、対GNP比率を通して基地需要の県経済に占めるウェイトが1966年の37%をピークに毎年漸減して、1975年以降は10%を割り、現在では、観光収入にほぼ匹敵するところまで低下している、といったかたちでこれが論じられている。それ故、基地需要の相対的低下をカバーしているのが復帰後急増した財政収入であり、県の対外受取総額に占める財政収入の割合は、復帰を境にして基地収入と完全に入れ替っていることから復帰後の沖縄経済が「基地依存経済(軍事植民地的経済構造)としての色彩を次第に薄めつつ、新しい段階(経済植民地的構造)に入った」と受けとられているようである。そして、そのことから、沖縄経済の現状を「工業的中心地域=日本『本土』に対する一次産品供給に特化された周辺地域」あるいは「日本の商品市場」さらには「資本進出と地場資本の系列化による国内植民地」と把握しているのである。それゆえ、このような沖縄経済の構造、つまり本土と沖縄の支配従属の関係、いわゆる北の南に対する支配従属の関係、文字どうりの「南北問題」としてとらえることもできるわけである。
しかし、復帰後の「沖縄問題」を「国内植民地問題」あるいは、いわゆる「内なる南北問題」としてとらえても、その内実を軍事植民地的構造としてではなく、経済植民地的構造としてとらえているかぎり、その対処策として出てくる「自立経済」論議も、たとえ第一次産業重視論や第二次産業重視論あるいは第三次産業重視論といったさまざまな自立論が出されたにしてもそれらはすべて「開発方法論」の域を出ないものである。
このような「格差是正論」の矛盾は、今さら指摘するまでもない。すでに1974年10月のタイムスの共同討論「開発と住民運動の思想」の中で「金武湾を守る会」の金城清二郎氏が「……いわゆる平和産業論の形で出されてくる較差是正論は基地に目かくしをして、基地から吐き出される軍離職者を開発によって吸収していくという側面を強く持っているのです。……開発による較差是正というスローガンを高く掲げることで基地に目かくしをし、基地撤去闘争のエネルギーを較差是正論の方向へ転載していった……。要するに基地の固定化を許しつつ、いっぽうでは日本独占の沖縄への導入を選択していったのが5・15以降の沖縄の状況ではないのか」と指摘しているとうりである。しかし、このような見解は未だ一般的見解とはいえない。
たしかに、今年の平和学会で「……重要なことは、財政支出が基地収入の低下を補強しているだけではなく、積極的な基地維持の役割を果していることである。例えば、復帰と同時に軍用地料は全額、日本政府によって肩代わりされ、また最近では基地従業員の賃金も日本政府が肩代わりしつつある。さらに防衛施設庁による『基地周辺整備賃金』と銘うった種々の財政支出も増大している。財政支出によって基地が維持されている状況は、沖縄の内発的・自立的発展を考える場合、極めて重大な問題を内包していると言える」という重要な指摘がなされているが、しかし、これはいまだに財政支出における直接的な軍事基地関係費の増加に注目したにすぎない。それゆえ、宮本憲一氏の平和学会での発言「沖縄県は基地として、日本経済に買いとられたようなもの」という沖縄の実相を突く重大な発言さえもそこではまだ比喩的にしか使われていない。
私は、「沖縄問題」として「経済」と「基地」の問題を考える場合には、基地需要の県経済に占めるウェイトの増減といった見せかけの基地経済としてではなく、また、基地の存在が産業構造・都市形成におよぼす影響といった開発に対する直接の疎外要因としてでもなく、もっと深い意味を持った、日本政府にとって「沖縄の存在価値」とは何かといったところにまず焦点をあてる必要があるのではないかと思われる。そして、そこに視点を定めた時に初めて、72年復帰の意味を今われわれが問い返す手がかりをつかむことになるのであり、また、「国内植民地」としての沖縄経済の構造的存在を明らかにしうるのではないだろうか。
したがって、私は「沖縄自立経済論」が持つ真の意味は「沖縄の存在価値」を「軍事戦略上の価値」としか認めない日本政府の意思そのものから沖縄を解き放つ「沖縄自立論」に強く結びつかざるをえないところに極めて重要な意味があると思う。
五、「振興開発計画」と「自立経済」
もともと、昨今の「自立経済論」の勃興は、「振興開発計画」の破碇に触発されて起ったことであるが、前記の視点からこの「振興開発計画」をみるならば、この計画自体のなかに隠された「日本政府の意図」というものが明白にみえるのである。1972年10月に沖縄県が作成し、内閣総理大臣に提出した「県案」をもとに、同年12月18日に政府において決定したものである。しかし、同計画は、当初の「県案」からはすでに全く異なるものであるばかりか、日米両国による「沖縄の共同管理」の実態を隠す“イチジクの葉”の役割を果すものにほかならない。
「振興開発計画」の目標は、本土との格差是正をはかるとともに、自立的発展の基礎条件を整備することにあるとうたわれ、そして、それを可能にするためには、第二次産業の拡大によって産業構造の改善をはかることに重点を置いている、ということになっているが、そもそも、何故にこのような格差が生じるに至ったかという基本認識においてすでに「沖縄県」と「日本政府」との間には大きな隔たりがあったのである。
「県案」では、「壊滅的な戦禍、長年にわたる巨大の米軍基地の存在と軍事優先統治および本土との隔絶等の諸要因によってもたらされた本土との格差……」となっているのに対し、「政府案」では、「戦後長期にわたりわが国の施政権外に置かれた沖縄は、……長年にわたる本土との隔絶により経済社会等各分野で本土との間に著しい格差を生ずるに至っている」となっており、まるで迷い子になっていた子供がヒョッコリ戻ってきたかのような歴史に対する政府の責任といったものは少しも感じられない。それだけに、将来に対する展望も、「県案」が「本土」との格差、産業経済構造、生活、社会環境等の不健全性を早急に是正し、軍事基地の撤去を推進させ、経済の自立的発展の基礎条件を整備することによって、基地依存経済から自立経済への移行を実現し……」となっているのに対し、「政府案」では、「沖縄の各面にわたる本土との格差を早急に是正し、全域にわたって国民的標準を確保するとともに、そのすぐれた地域犠牲を生かすことによって、自立的発展の基礎条件を整備し……」となっているのである。「県案」が自立的発展の基礎条件に「軍事基地の撤去」を挙げているのに対し、「政府案」では「すぐれた地域犠牲を生かすこと」と変更されているところに日本政府の真の意図が隠されているのである。そして、何よりも注目しておきたいことは、政府においても、沖縄の軍事基地が産業構造や都市形成に与える影響を全く無視しているのではなく、むしろ、「沖縄における米軍施設・区域は、大規模かつ高密度に形成され、しかもその多くが地域開発上重要な本島や南部地域に存在しており那覇市を中心とする中南部都市圏の形成に影響を与えている……」ととらえていることである。つまり、沖縄の軍事基地が沖縄の自立経済にとって重大な影響を与えていることを認識しつつも、「振興開発計画」の「目標」のなかから「基地撤去」が削除されているところに日本政府の真の意図が読みとれるのである。
そうした視点で、復帰後8年の諸施策を検討してみるならば、直接的な軍事関係費の増加はもとより、一見非軍事的な財政支出も全て沖縄の「軍事戦略的価値」を維持するための必要経費として支出されていることがわかる。文字どおり、「沖縄は基地として日本国家に買いとられた」のである。
一般には、「振興開発計画」の破綻は、ドル・ショック、オイル・ショックに続く日本経済の長期構造不況の影響と受けとられているが、前記の視点でみるならば、たとえ、高度成長期の日本に復帰したとしても、一次、二次産業中心の平和産業による自立経済への道(県民の求める道)と軍事基地沖縄の道(政府の意図する道)とは、両立するものではない。
六、軍事植民地としての「国内植民地」
沖縄の軍事基地は、土地を収奪したばかりか、労働力を搾取し、人権を抑圧し、さらには全国の52%の基地を集中することによって平穏に生きる国民の権利から沖縄県民を疎外している。また、日本国憲法下で行われている基地のための収奪は、得べかりし生産物の搾取ばかりか、生産技術の発達をも抑圧し、県民をして健全な生産者の生活から疎外するという点において、まさに「国内植民地」の要件をみたすものである。そして、国内植民地がとりわけ「軍事基地」という「特殊な質」を持つところに沖縄の「国内植民地」としての特異性が極まっているように思われる。
このように、沖縄の現状を軍事的植民地構造を内実とした「国内植民地」として把握し、そこからさらに「沖縄経済」の諸相を分析した場合、そこに多くの識者が説くように、「沖縄農業における砂糖・パインを中心とした植民地的モノカルチュア化」や「日本資本の商品市場化」また「日本資本の進出と地場資本の系列化」、さらには「本土に対する労働力の移出」といった「経済植民地」的な諸現象がみられるわけであるが、しかし、これらの現象は、あくまで「軍事植民地」としての沖縄を維持するための財政投資に対して日本独占によってさらに経済植民地的手段で財政資金の本土還流が行われていることを示すものであり、復帰後の沖縄経済が復帰前の「軍事植民地的経済構造」から本質的に変化しているということではない。むしろ、現状は「軍事植民地的経済構造」を基底として、さらに「経済植民地的」様相が加えられた最悪の「国内植民地」として把握されなければならない。こうした現状把握の上に、では、沖縄自立経済論を論ずることはどういった意味をもつのか、ということが次に問題となるのである。
七、「沖縄自立経済論」の総括
ここで最初に問題となるのは「自立経済」とは何かということであるが、この「自立経済」に関するイメージは論者によって各々に異なっている。『新沖縄文学』の論文では、「名護プラン」と呼ばれる「名護市総合計画・基本構想」のなかの「自立経済論」と牧野浩隆氏の「自立経済論」、さらには、サミール・アミンの「自立経済論」が主に検討されているが、それぞれにニュアンスの違いがあり、したがって前回の自立シンポにおいても「自立経済」の把え方をめぐって議論が分かれている。肝心なことは、定義の問題として「自立経済」を問題にするのではなく、沖縄の置かれた現実と結びつけて各々の「自立経済論」を検討することではないだろうか?
その点からすると、提起者の「経済自立とは、体系的経済発展の動態としてすぐれて主体的に理解されなくてはならないと同時に、他者との関係ではこの自己発展の客観的な構造連関を踏まえての連帯と共同の探求を含蓄する」という説明は具体的な意味内容を把握するのには難解すぎるのではないか。さらにまた、「自立経済とは、一定の社会的経済的単位とくに民族集団が自己発展力の主体と体系を内在させ、固有の経済発展の軌道をみいだし、それへの動態を開始している状態」と規定しているが、この概念規定に従うならば、72年返還以来、日本国家の一地域として位置づけられている沖縄で「自立経済」を論ずることは新たな政治的意味を含むことになるのではないか。
この点は「世界市場との断絶」を「発展の前提」とするサミール・アミンの「経済自立への道」も一定の政治的条件に保障された一定の社会的経済単位を予想して説かれているだけに沖縄の「自立経済」と結びつけて論じられると問題は同様であろう。その点、「名護プラン」や「牧野論文」のなかで説かれている「自立経済」は、その達成過程に「一次産業」か「二次産業」か、あるいは「主体は誰か」という点で重点の置き方に相違があるにせよ、「輸出入バランスのとれた生産経済を確立すること」(名護プラン)、「県内収支の拡大均衡をはかりうる経済力を確立すること」(牧野氏)と規定していることは沖縄県の経済論議としては極めて簡明である。しかし、牧野氏が、「沖縄経済の自立化ないし県内企業存続の可能性は……本土市場に参加しうるか否か、日本経済内において分業的諸関連を確立することを重要な条件としている。……即ち、まずもって復帰前における既得の制度を活用するならば本土市場に参入しうる類の加工製造業を育成し、かかる県内企業が日本経済内において分業上の位置づけを獲得しうる道を開き、しかる後に本土の産業政策の中に徐々に融合して行く方策をとるべきであろう」「振り出しに戻った沖縄経済」と述べているように日本政府の行財政上の保護育成策に強く期待していることや、「名護プラン」においても「沖縄における自立経済とは……農林漁業や地場産業の本質的育成・振興という正当な“金もうけ”を達成することによってのみ本質的に可能なのである」と述べたうえで、「そのためにも正当な生産活動と社会活動を阻害してきた、山地・平野・河海を問わず存在する基地の完全撤去を勝ち取り、国県などによる充分な行財政治的援助を断固要求し、それを基礎として住民自身による作業が出発しなければならない」と国の行財政的援助を「自立経済」達成の要件としていることは問題がある。
このような国の行財政の保護育成策を期待する「自立経済論」に接するとき、沖縄の現状を「軍事植民地的経済構造」を基底とした「国内植民地」と把え、日本政府の意図を「沖縄の軍事戦略的価値」の維持確保にあるとみる立場からは経済論としての当・不当以前の問題として、政府に対する過度の期待感や楽観論のうえに立てられた「自立論」であり、いまだ「復帰幻想」の延長線上に位置しているように映るのである。
そこで、日本国家内の一県として位置づけられた復帰後の沖縄で「自立経済」を論じることの意味があらためて問われることになる。討論のなかで川満氏が、「現在の段階でひとつ疑問なのは、何故こんなに自立経済の問題が人々に重要視され、問題とされているのか……沖縄を一つの地域として考えて、しかもその経済の自立を考えてみるというのは一体どういうことなんだろうか……」と疑問をなげているが、まさにそこが問題であろう。
八、「自立経済論」の展望
「自立経済」というのは、問題提起者がサミール・アミンに触発されて述べているように、「一定の政治的条件に保障された一定の社会的経済単位」においてはじめて問題になりうるのであり、ましてや、アミンの「経済自立の道」が「世界市場との断絶」を「発展の前提」とするならば、それはまさに「琉球独立国」に通じる道であり、「沖縄県」の経済論にはなりえないのではないか。
その点については、討論のなかで大石氏が「復帰が選択された一つの結論だと言うことになれば、ここからは当然にも、日本と沖縄は一つの国家でなくてもよい……」と述べて、「復帰」の意味を問い返すことも含めて「自立経済論」の方向性を示竣している。まさにその方向は、川満氏の「全く日本の法体系とか、国家体制というものから切り離すような形で沖縄自体を革命的な根拠地にして……新しい経済を構想して行くのか? 皆さんに聞かせてほしい」との問いに対する一つの答えにはなっていると思うが、それが現在行われている「自立経済論」の大勢ではないであろう。しかし、結局のところ「自立経済論」の行きつく先はその方向であり、そこまで論議が深められてはじめて、新川明氏が平和学会での議論を評して「……経済自立論や地方分権論を考えるに際して要求される長い射程の発想のバネとして……“独立論”にかかわる議論はもっと深められてよいと思う。この問題はそのまま日本の国家体制のありよう、さらには日本を含めた新しい国家関係についての将来構想にかかわる問題を提起せずにはおかないはずだからである」と述べている点を逆から補完・発展させる役割を担うことになるのである。
しかし、このような意味での「自立経済論」は大方の沖縄人の感性的反発を招くことは必至であり、建設的な論議にまで発展させることは困難が予想される。なぜなら、「復帰」が選択された一つの結論だとするならば、復帰運動の原点ともいうべき1951年の群島議会において、「琉球が日本を中心としたアジア経済圏から独立して存在することは恐らく不可能であろう。かく経済的に日琉の分離が不可能とするならば、寧ろ琉球の日本復帰が琉球人の経済福祉上望ましいことは当然である」という論議を経て「日本復帰」が選択されている。ある意味では「復帰論」というのは、「自立論」を、捨てたところから出発しているともいえるのであり、「復帰」の問い直しなくしては、いかなる「自立経済論」も論者の意図は別にして、政府の沖縄統治策を手直し的に補完するものでしかないであろう。それゆえ、復帰10年を前に、沖縄県民は復帰路線をさらに推進して、地域分権や参加論と結合した地域間分業論を受け入れて、本土と完全に一体化する道を歩むか、あるいは逆に「自立経済論」をトコトン追求して自立への道を歩むか、再び選択の岐路に立たされているのではないだろうか。
まさに今日の「自立経済論議」は、戦後一貫して沖縄の思想界を支配した「復帰思想」からの自立をも意味するものである。
(沖縄経済研究会)
沖縄経済の独自構造
-その週辺資本主義的発展に関する諸問題-
原田 誠司
はじめに
第一回シンポジウムでは、大きく三つの課題が残された。南北問題の方法、沖縄経済の独自構造、さらに経済自立の展望の三つである。ここでは第二の点の解明を通して、国内植民地としての沖縄経済の構造を若干なりとも明らかにしたい。
具体的展望に入る前に、「沖縄経済の独自構造」という視点の意味を前提的に考えておきたい。
地域経済を把える方法は、経済地理的、産業立地論など様様にあるにしても、ふつうは、全国平均と各地域経済との比較、あるいは地域間の類型的分析に留まり、経済政策上の格差是正が導びかれる程度である。だが、沖縄経済を把えようとすると、このような従来の地域経済の方法では決定的に不十分である。というのは、沖縄が独特な歴史をもった島嶼であり、経済的には一個の国民経済的展開を余儀なくされた地域であったからである。
沖縄の歴史的変遷(封建時代の日支両属状能、明治時代の日本への帰属=併合下の植民地的被差別状態、戦後の米軍占領、そして1972年以降の再度の日本への帰属=再併合)をみれば、沖縄経済を単なる日本の特殊な一地方経済として把えるのではなく、逆に沖縄経済の側から国際経済との独特な関連性を解明する必要があろう。しかも、この変遷は沖縄が日本列島とアジアの中継点に位置する亜熱帯の島嶼であることに大きく依っているとすれば、沖縄経済は島嶼経済の展開と構造において把握されなくてはならない。「独自構造」とは、このような意味で、まず、沖縄経済の島嶼経済としての国民経済的展開を把握することである。
さらに、これに留まらず、「低発展の発展」状態(S・アミン)を周辺資本主義の構造として深めることが不可欠である。沖縄経済が単に後進資本主義的発展の途を歩んできたというような近代化論的方法でなく、その後進資本主義構造自体の不断の再生産、S・アミン的に言えば、周辺資本主義化の構造が解明されなければならない。変動しつつも絶えず再生産される構造的特質は、ここにおいて把えることができる。かくして「独自構造」の分析とは、島嶼経済としての周辺資本主義的発展のメカニズムをとらえることである。
本稿は、そのための初発的提起である。72年復帰前と復帰後の比較を通して、基地経済の構造、工-農関係、労働力の構造の三点にわたって概観したい。
一、基地経済の構造
1
戦後沖縄経済の特徴は、一般に基地経済と言われてきた。広大な土地の米軍事基地への転用=接収、米軍政府の援助、基地関連産業の広範な存在、という三要因によって沖縄経済が規定され、存在させられてきた。誰しもこの現実は認めるところである。
だが重要なのは、沖縄経済の構造が軍事基地建設という経済外的要因によって生成し展開させられたという点である。周知のように沖縄戦と米軍占領、さらにサンフランシスコ条約による日本からの分離という形で沖縄は、米・日帝国主義の取引きの道具に使われた。その上、朝鮮戦争を契機に沖縄は米極東軍事戦略の要石(キーストーン)として位置づけられ大規模な米軍基地が建設された。戦後の基地経済がここに始まる。
ここで注目すべきは、基地経済とは軍事基地を維持するための経済であって、決して経済の軍事化ではないことだ。経済の軍事化とは、一定の資本主義的経済の展開を前提にした軍事費( 需要 )や軍事関連企業の増大を意味する。既存の生産構造に軍需が付加され、ビルトインされることである。帝国主義諸国では、ほとんどこの状態にある。だが、戦後の沖縄では、戦争により経済は文字通り破壊され生産活動はゼロから出発せざるをえなかった。つまり、すでに一定の沖縄経済の構造が展開した上に米軍基地が加わったのではなく、基地建設とその維持自体が沖縄経済を生成させたのである。戦後の沖縄経済は、はじめから基地建設・維持のための経済関係の形成であった。
このような事態は、島嶼としての沖縄の価値が外生的に「軍事基地」に特化され、利用されたためであり、それゆえ、沖縄経済は米対外政策の一手段・一分野であり続け、政治的関係に全く従属させられたのである。
2
では、基地経済の構造をどう把握すべきか。
(1)まず、50年代の大規模基地建設は、広大な土地の接収=囲い込みを前提条件とした(沖縄本島面積の14%山林を含め20%)。この土地接収は二重の意味で沖縄経済の構造を決定づけるものであった。一つは戦争で破壊された一次産業=農業の回復・再建を決定的に遅らせたこと、もう一つは戦争の結果としての不就業労働力に加えて言葉本来の意味でのプロレタリアートを創出したこと(これは農民層の分解というよりまるごとの農民層の農業外プロレタリア化である。)である。つまり、ここで文字通り経済外的強制によって戦前の就業構造が分解させられ、一次産業にはりついていた労働力が放出させられたのである。
(2)基地建設とその維持は、この大量の労働力を基盤にして軍労働者(約10万)と基地関連産業群(主として建設土木と諸サービス業)をつくり出した。これも沖縄経済の構造の特質を形づくった。つまり、生産手段生産部門(第二次産業)の勃興には全く結びつかず基地関連需要に依存する三次産業を発生させたのである。
(3)また、基礎・基幹経済部門が米軍支配下におかれそれが同時に沖縄経済の基礎・基幹部門とされた。電力・水道・石油などは琉球電力公社・琉球水道公社・石油配給基金に把られ、金融は琉球開発金融公社・琉球銀行が支配した。これら基礎・基幹部門は当然にも軍事基地の維持に必要なものに限られており沖縄経済の発展のための工業部門は全くらち外におかれた。
すでに明らかなように、基地経済とは単に基地依存経済と言うに留まらず、沖縄の価値が経済外的に軍事基地に特化されたために最初から自律的経済構造を剥奪された上に成立した。経済構造の「非接合性」は、当初から深く刻印されていたのである。
にもかかわらず、というより、それゆえにこそ、沖縄経済は60年代末まで高度成長した。成長率年平均15%、完全雇用の達成(失業者2~3000人)はその端的な表れである。だが、この成長は、米軍関係収入がGNPの30~40%を占め、対外収支は米軍関係受取り40~60%、米政府援助5~10%にみるように完全な赤字、つまり、沖縄外(米)からの移転収入によって支えられたにすぎない。「仮空の繁栄」!また日本政府の援助も60年代に開始され、日本資本主義のアジアへの進出の一環に沖縄が組み込まれたと言えよう。
3
では、72年日本復帰後の沖縄経済は、このような基地経済から脱却しえたであろうか。
(1)米軍基地の機能は全く変化しないが、日本政府が基地維持を肩替りした。軍用地料の大巾アップ(71年31億→ 78年287億)によって。しかし、基地関連収入(76年1000億)の比重は低下(65年GNPの30%→76年10%)している。軍労働者の大量解雇、基地関連サービス業の不振が目立つ。
(2)米軍および政府の収入・援助にかわって日本政府の財政資金撒布が大きな比重を占めている。地方交付税交付金や国庫支出金だけでなく、海洋博などの国家事業や第一次振興開発計画などによる資金撒布も加わって大いに沖縄経済は発展するかにみえた。だが、この事態は一方では日本政府への従属を強めつつ、他方で財政資金の本土資本への還流を進めるといった形で沖縄経済が日本の政府・資本に従属させられていることを示している。
(3)復帰後の新しい要素として石油産業収入および観光収入の増大がある。石油産業といってもCTS(石油備蓄基地)設置による原油備蓄が主であり、財政収入効果はあるものの雇用効果はなく、環境汚染という高価な代償と比較すれば沖縄にとって好ましいかどうかは自ずと明らかであろう。重要なことは、沖縄の価値が軍事基地に加えて石油備蓄基地にも見い出され特化され始めたことである。
観光収入の増加は、日本の航空資本・旅行業者のキャンペーンによってもたらされたが、これは、基地関連サービス業の観光サービス業への転換を促し、基地関連産業の不振を穴うめする役割を果している。
(4)経済成長は、海洋博時に異常な伸びを示した(46%)が、オイルショック後の構造不況とも重なり低下し、失業者は2.5~6万人、失業率は6~8%にのぼっている。第一次振興開発計画も達成見込みは立っていない。
4
72年復帰によって沖縄は基地経済から脱却できたか?
軍用地料を含めた基地関係収入の増大に着目すれば、答は否! 他方沖縄経済総体のなかでの基地関連収入の比重低下に着目すれば、答はイエス! だが、このような答え方は基地依存度による現象的判断でしかない。
まず、復帰によって何が変ったかを考えてみよう。沖縄が日本の一県に組み込まれることによって米政府援助・米軍関係収入が廃止されるか大巾減となり、これに代って日本政府援助=財政資金収入が当然のことながら大巾に増大した。したがって、基地依存経済の色彩は、表面上はうすれたといえる。
だが、基地経済の構造は、全く変らないばかりか、かえって奇型化した。つまり、対外収支は、圧倒的赤字であり米軍に代る日本政府への従属が明らかになった。より重要なことは、基地がつくり出した三次産業の肥大化と経済構造の「非接合性」が維持され、その上にCTS建設や観光業の「繁栄」が日本資本からもち込まれ、かつ、消費市場としてしか位置づけられないがゆえにこの構造がさらに拡大されたことである。復帰前の基地経済下で可能となった成長と一定の均衡すら破壊されたのである。
二、沖縄経済の非接合性
1
では、沖縄経済構造の「非接合性」とは何か? 農業-工業関係を軸に検討したい。
A 農 業
沖縄の戦後農業は、戦争による土地の荒廃と米軍の土地収奪による農地面積の縮少(戦前比26%減)と低自給率(30%)の状態から出発した。
1951年の割当耕作廃止-土地所有権証明をへてやっと50年代に米・甘薯・そ菜を主とする自給農業が成立した。生産額レベルでみると50年代末に戦前水準に達する。他方、沖縄の主要作物であるさとうきび、パインアップル生産も50年代に開始されるが、急速な成長は60年代に入ってからであった。
その要因は、原料・一次産品世界市場の変化、つまり日本資本主義の一次産品保護政策にあった。具体的には、50年代半ばから日本の政策として甘味資源確保政策がとられ、沖縄産糖もこの対象に加えられ関税免除と輸入粗糖に対する外貨割当制の特恵措置(52年~63年)の対象となった。きび生産は、この特恵措置に支えられ59年以降急激な伸びをみせた。パインについてもほぼ同様なことがいえる。これとは逆に、米作は日本政府の保護(食管法)対象に入れられず、国際商品市場での競争にさらされ衰退の一途をたどった。
かくて、50年代に成立した沖縄の自給農業は、国際市場の動向に左右され、沖縄住民の食糧政策を確立する方向へと発展することができず、きび・パインという輸出志向型の商業的農業へと特化されていった。
しかも、この過程は、沖縄農業の植民地的構造をつくり出すことになった。60年前後からの日本糖業資本の沖縄への進出によって沖縄糖確保での日本資本による系列化が行われた。それも大型原料糖工場の建設であるがゆえに一層、原料確保に特化した資本投下であった。ちなみに、沖縄では1971年になって初めて精製糖工場が設立されたのである。さらに、60年代の日本の貿易・資本自由化(沖縄は59年よりドル通貨体制)によって、大巾に一次産品価格が下落し、この低価格水準のまま63年からは糖価安定事業団への原料糖買上げ体制へと転換させられた。きび生産が大きな打撃を受けたのは言うまでもない。自由化による安価な精製糖の流入は、原料糖生産から精製糖生産への発展も困難にした。
かくて、米軍支配下の沖縄農業は、沖縄住民の食糧供給部門への成長の道を絶たれ、日本資本主義の対アジア進出の原料供給部門に組み込まれてしまった。
それは、また他方で、沖縄農業の基盤をさらに掘りくずすことにもなった。つまり、60年代を通じて急速に農業労働力が他部門に流出すると同時に農業の兼業化を促進した。とくに、全農家の90%以上を占める200アール未満の下層農家の解体傾向が強く、200アール以上層が逆に増加した。これは、50年代の米軍の土地収奪による大量の農業労働力のプロレタリア化につぐ第二次農業層分解とも言うべき性格をもっている。この労働力は、日本の60年代のように工業部門の成長による農業労働力の吸引ではなく、農業自体の行きづまりによる労働力の非農業化であって、結果的に三次産業・サービス部門に吸収されるしかなかった。
2
さて、72年の復帰は、この沖縄農業の植民地的構造のゆえの行きづまりを打開できたのであろうか。事実は、この構造を一層深化させたにすぎないことを示していると思われる。
復帰後の本土資本による大量の土地-農地買占めと軍用地料の大巾引上げによる農業ばなれ-農家戸数の急減は、かつての米軍による土地収奪と同様な影響を与えた。ただ手段が経済外的強制によるか巧妙な資本主義的搾取かのちがいだけである。三たび農民層は分解させられた。
また、きび・パインの買い上げ方式が生産費所得補償方式からパリティ方式へと日本本土の市場条件から変更され、沖縄側はますます不利な立場に追い込まれ、これらの生産は全くの低迷状態におち入ってしまった。きび・パインは、復帰前からすでに日本国内並みにあつかわれていたにもかかわらず、この結果である。逆に一体化していたからこそこうなったと言うのが正しいであろう。
77年頃から農業の体質改善-農業基盤整備などが始まり、例えば、きび生産では機械化による経営規模の拡大がはかられたりしている。畜産・野菜・水産などに力が入れられてはいるが、パイン・米作には展望が見えない。全体としては一次産業の純生産比率は低下しつづけ、農業人口も6万人台に減少し、まさに沖縄農業の“崩壊”状態が出現しているのである。
沖縄の農業-一次産業は、かくて復帰前のきび生産中心の構造が崩壊させられ50年代初期の時代と同じ地点に立たされた。振出しに戻ったのである。日本資本主義経済のなかで、沖縄の一次産業とは何か、その位置を島嶼の条件のなかでどう確定するか、根本から問う必要があろう。
3
B 工 業
さて、工業もこのような農業の構造と深く関連している。沖縄の工業(二次産業)は、何よりもまず、糖業=きびの加工部門として形成された。それは、原料糖の加工部門であり、60年代には進出した日本の糖業資本に系列化される。その他の製造業-縫製加工、合板、セメント、ビール等-も60年代に生成・発展する。しかし、これら製造業は、すべて同種輸入商品にたいする関税障壁、輸入規制によって保護されていた。
だが、60年代後半に日本からの輸入商品が増加するにつれ市場競争でじりじりと後退した(例えば、食品加工部門のみそ・しょう油など)。しかも、これら製造業自体が米軍基地需要に依存して発展したために、その需要減(60年代後半)が始まるや経営危機をまねいたのである。
もう一つの大きな比重を占める工業は建設業であった。50年代の米軍基地建設時に、基地工事を請負つた日本資本の下請的存在から生成した。基地需要への依存度30~40%といわれるように、基地需要と緊密にリンクして発展してきた。公共投資がもう一つの大きな需要であったが、60年代後半の基地需要減とともに、建設業も停滞におち入った。
かくて、復帰前の二次産業は、食品加工部門(きび・パイン)が日本の特恵措置に支えられ、系列化されつつも主流を占め(60年代の二次産業生産額に占める割合は60%)他方、それ以外では基地関連産業として建設業がしだいに比重を高めてきた(60年代後半)というのが実態であった。このような復帰前の沖縄工業は、次のような構造的特長をもっている。
第一に、工業の自律的・内発的発展の条件=接合性が欠如していること。電力・水・石油供給を米軍に掌握された上に、繊維・機械・製鉄・化学などの主要基幹部門が発展させられていない。
第二に、第一の問題の裏返しでもあるが、軽工業へ特化-偏向という事実である。非食品加工部門では軍事基地維持のための製造・建設業しか生成しなかった。基軸的な産業資本の発展が欠如したのみならず、工業の性格自体を日本の特恵措置と米軍に依存する限りにおいて成立するきわめて部分的・周辺的なものとした。
第三に、このような沖縄工業の周辺的存在は、外国(米・日)の経済的支配によってもたらされた。前述した輸入製品にたいする保護政策は、後進資本主義諸国がとった国内産業資本育成のためのそれとは全く異っていた。沖縄住民は、米軍支配下にあり自らの国家・政府をもっていなかった。保護政策の主体は米軍であって沖縄住民ではない。米軍が沖縄経済の発展のために貿易・為替・資本全般にわたる保護政策を行うはずもなく、またその必要もなかったのである。
4
復帰後、沖縄の工業は、混乱の渦に投げ込まれた。保護措置の撤廃(段階的)と本土資本・商品の進出・流入、および70年代世界不況が強襲した。
まず激しい倒産と系列化が進んだ。市場競争と不況のダブルパンチは、沖縄の資本を徹底した合理化・減量経営と本土資本との技術提携・系列化へと追い込んだ。その結果は、大量の失業者を排出しただけでなく、本土資本に系列化・下請化された一業界、一社ないし数社独占体制を出現させたのである。
また、二次産業の業種別変動も激しくなった。糖業は、精製企業が一社設立されたが、他の原料糖加工企業では過剰生産力をかかえ停滞している。これに比し建設業は、基地需要にかわる日本政府による復帰後の巨額の行政投資に支えられ、糖業を完全に追い抜いた。
しかし、この建設業にしても構造的脆弱性をもつ。海洋博等の大規模工事に明らかなように沖縄の建設企業は下請的ないし小規模工事しか受注できず、基幹的部分はすべて本工資本に掌握され、したがって投下された財政資金の多くは本土に還流してしまうのである。このような従属的存在とさせられながらも、かつての基地需要と同じく財政資金撒布に依存することによってしか建設業は成立しない状態におかれつつある。
さらに、復帰後目立った動きとしてCTSを軸とする石油産業の比重の増大がある。CTSの設置が、日本本土への資源・エネルギーの中継・備蓄基地として沖縄の位置が利用された結果であることは、すでに述べた。経済効果としては税収面くらいしかあげられない。だが、与那城村財政は、石油企業の固定資産税収によって支えられているが、そのかわり従来の交付税が大巾に減額され結局、村財政の規模は全く変らないといった状態にある。村財政は政府にかわって石油企業に従属したにすぎない。
すでに明らかなように、復帰の二次産業は大きく変化した。一言で、糖業中心の産業構造の崩壊といえる。だが、新しい発展的方法がそれにかわって敷かれつつあるわけではない。むしろ、二次産業の非製造業化が進み、沖縄の工業の危機を拡大させている。復帰前に成立した三つの工業の構造的特質が、増々顕在化したと言ってよい。とくに、行政投資が産業構造の「非接合性」のゆえに産業関連的波及効果をもたない現状において、二次産業の発展が依然として行政投資に依存する、あるいはさせられるとすれば、沖縄工業は崩壊へと向うしかない。
かくて、きび生産-きび加工部門の成立という形での復帰前の農-工関係は、復帰後、完全に崩壊させられた。沖縄産業の従属・衰退・周辺化が目につくばかりである。
三、過剰労働力構造の再生産
1
沖縄経済のもつ三つ目の問題は、労働力の問題である。
沖縄の人口は、戦前、57万人台で停滞したが、戦後、55年に80万人台、60年代に90万人台、70年代は100万人台へと伸びてきた。労働力は、戦前70%が農業にはりつけられ、二次、三次産業の未発達もあり海外移民が大量にのぼった。戦後は、60年代に就業人口35~40万人に達したが、その後、この40万人の壁が破れていない。復帰後逆に減少したがこの一年(77年)は若干増というのが現状である。
就業人口の内部構成は、農業労働力の流出によって大きく変化した。そのタイプは先進資本主義国にみられるような一次→二次→三次産業というものではなく、一次→三次、二次産業は漸増的という特徴的な型である。つまり、一次産業は15.2万人(60年)→6.4万人(78年)、二次は4万人→8.8万人、三次は15.9万人→26.1万人である。一次からの流出労働力は、50-60年代前半は軍・基地関連労働力へと吸収された。三次は、60年代は高い伸び(4万→約7万)であったが、復帰後は漸増傾向に留まる。建設業労働力が製造業のそれをこえた。
このような就業人口のあり方は、前述した沖縄経済の構造と対応している。問題は、復帰後発生した事態であろう。
2
第一に、大量の失業者の発生である。60年代の失業者は2~3000人だったのが、72年以降2万人(失業率5~7%)に急増し、若年層(15-20才)と中高年層(45-50才)の比重が高い。急増の要因は、①軍労働者の解雇(1.9万人)②沖特法関係解雇(8000人)③不況合理化による解雇(8000人)④新規学卒者の就職難からくる失業労働力化、の4つである。
この要因からみて明らかなことは、復帰自体がもたらした解雇(①、②)と不況下の市場競争の敗北による解雇(③)が沖縄労働者を直撃したことである。また、新規学卒の就職難は、60年代からのすう勢であったとはいえ、この精勢下ではますますその度を深めているといえよう。本土就職者が県内就職者数を上まわっているのは、その端的な証左である。
第二の特徴は、いわゆるUターンの増加である(毎年2000人)。日本本土でもUターン現象は起っているが、沖縄の場合はそれとは質的に異なっている。若年(20才代)労働力が圧倒的比重を占めること(本土就職者のうち3年未満での離職は70%にものぼる)、また沖縄に帰っても就職難であることなどをみれば、彼らが本土の労働慣行になじめないこと、より本質的に言えば、本土と沖縄における労働の質が異るところにUターンの原因があるとみなくてはならない。
日本への労働力移動は、60年代を通じて集団就職等で年平均4~5000人の水準で推移し復帰後はさらに増加した。新規学卒のみならず失業者の出稼ぎが夏だけでなく冬にも行われるようになったことにもよっている。しかも、これらの労働力は、東京、大阪、愛知などの大都市部での製造業(機械・自動車組み立て等)の下層労働者層を形成している。雇用形態は、常用・臨時ほぼ半々である。沖縄に帰っても彼らは大半は半失業-失業状態におかれる。このような沖縄-本土間の労働力の流出・還流状態は、戦前の海外移民とは異って現代の第三世界-先進資本主義諸国間にみられる(還流的移民)の存在を示すものといえる。
第三は、沖縄内部での労働力移動も顕著であり、それがまた失業問題を深刻化させていることである。離島・本島北部から那覇圏への労働力の移動・集中は、復帰後急激に進み新たな都市人口問題を発生させた。雇用保険切れによる生活保護世帯の急増(全国1位)は、その端的なあらわれであり、都市への失業-半失業者層が滞留しはじめたといえよう。
3
以上のような沖縄における労働力問題の現状は、復帰前には表面化しなかった重要な問題の所在を示している。一言で過剰労働力構造の存在といえる。
これは今後十分に研究しなくてはならないが、さし当って次のように問題はたてられる。
一つは、三次産業の肥大化は、生業的商業・サービス業の増加を意味しここに過剰労働力が吸収され、外観上失業状態の不在をもたらしたことのメカニズムの解明である。先進諸国における三次産業の比重の増大傾向とは異質な、むしろ労働問題としての三次産業の解明が必要である。
二つには、沖縄の企業における労働生産性と労働過程の特質についてである。「還流的移民」の要因把握と企業内の潜在的過剰労働力を解明することになる。
三つ目は、沖縄の過剰労働力構造を、経済的にどういう新しい範疇として把握すべきかという点である。扶養人口60万人説が根強くとなえられてきたが、これは島嶼経済の構造的把握の誤りに規定されていると思われる。むしろ、労働力構造の「マージナル化」(S・アミン)の観点から再把握することによって根本的解決の方向を見出すべきである。少くとも沖縄の過剰労働力問題は、先進諸国における景気循環にともなう相対的過剰人口問題ではなく、沖縄経済の周辺資本主義的発展自体にたいする「絶対的過剰」人口問題であることは、前述した経済構造の検討から明らかである。「還流的移民」や都市部への半プロレタリア人口の堆積は、その具体的表れとみてよいだろう。
四、若干の視点
最後に、以上の概念から今後沖縄経済の島嶼経済としての把握をさらに深めなくてはならないにしても、現段階での経済自立の視点をいくつか私見的に述べておきたい。
第一は、経済自立とは、政策的手直しではなく、沖縄の周辺資本主義的経済構造をどう変革するかという問題に行きつくことである。国内植民地構造の変革といってもよい。
第二には、それは、沖縄人民が歴史的・現実的に奪われてきた沖縄の政治・経済的位置(島嶼性)を自らの手にとりもどすこと、その具体的構想力の発展が中心とならざるをえないであろう。
第三には、さらに具体的・主体的には、労働力の「絶対的過剰」をどう根底から解決するか、その視点から日・沖の中心-周辺関係をいかに打破するかが核心的問題だと思われる。
<参考文献>
主として参考にした文献は次のとおりである。
『沖縄返還』朝日新聞社1966年/『あすへの選択』上・下沖縄タイムス社1977年/『沖縄経済を考える』牧野浩隆・琉球新報出版社1978年/『金融経済』各年版 琉球銀行調査部/『沖縄統計年報』各年版 琉球政府・沖縄県/『沖縄県の経済概況』各年版 沖縄県/『周辺資本主義構成体論』S・アミン 拓植書房1979年・その他アミン諸論文
(現代景気研究所)
沖縄経済自立の展望・序説
-地域・共同体・社会主義への一考察-
中村 丈夫
一、はじめに
1.沖縄は日本にとって(一)辺境の地域であり、(二)特異な位置(一般には、世界的規模での<中心-周辺>の中継点、特殊には、日本の南進拠点)にある島嶼である。ここまでは、だれしも異論はないであろう。そして、(三)歴史的に形成された、国内の植民地であり、マイノリティ(正確には少数民族)であると考える。さらに沖縄の独自性は、(四)日本では基本的には解体された共同体の強固な存続に由来するコンパクトな内部構造によって根拠づけられる、と考える。
では、日本は沖縄にとってなんであろうか?日本なしに、沖縄は、経済的、政治的、文化的に存立しえないであろうか?それを沖縄に聞きたい。
2.封建薩摩は、属領としての沖縄を搾取し利用しぬいた(特産品、密貿易など)。戦前日本国家は、搾取を多分に前期的ではあるが資本主義的に強化しつつ(甘蔗モノカルチュア化、重税など)、帝国主義的世界戦略のうえに沖縄を位置づけた(沖縄が大軍事基地化しなかったのは、日本の進攻路線が、一貫して「大陸国家」たらんとしたことと、早期に台湾を領有したこととのためであり、その北守南進=「海洋国家」化が開始されるや、沖縄の悲劇は必然化した)。アメリカは、より大規模な世界戦略のうえに沖縄を超大軍事基地化し、アジア大陸進攻を断念してからは、日本に「返還」したが、最低限、その西太平洋防衛線のキー・ストーン的位置になお執着している(米韓同盟-米日中同盟、大陸棚油田など)。東南アジア支配を中心に、ふたたびアジア帝国たらんとする日本は、一方では、資本進出と系列化によって、沖縄の内発的、自生的経済発展を圧殺しつつ、他方では、南進拠点の構築のための畸型的近代化を強行している(財政投融資、CTS、自衛隊強化など)。
この周辺資本主義的統合は、すでに「日本の内なる南北問題」として自覚されているが、問題はもはや、「南」の「北」にたいする抵抗一般、「南」の「北」からの解放一般にあるのではない。「南」自体の変革が、同時に「北」の変革を促進する--場合によっては主導する--契機となりうる綱領的立場が獲得されなくてはならない。沖縄の経済自立は、沖縄が存立する物質的基礎の実証的研究の問題であるとともに、沖縄を従属化、畸形化、寄生化させている日本(-世界)資本主義との対立点をとらえる方法の理論的研究の問題であると考える。沖縄での経済自立論議が、中間的にでも、なにに集約されているかを聞きたい。
二、「地域主義」と沖縄経済自立
3.沖縄を一般に日本の辺境の地域とのみ見るときには、「地域主義」ないしはその戦闘的翼が経済自立の理論的根拠や総称的表現たりうるかのごとくである。現行「地域主義」は、「地域に生きる生活者たちがその自然、歴史、風土を背景に、その地域社会または地域の共同体にたいして一体感をもち、経済的自立性をふまえて、みずからの政治的・行政的自律性と文化的独自性を要求することをいう」(玉野井芳郎教授の最新の規定)とされている。そのかぎりでは、「地域主義」とは少なくとも、独占資本主義と中央集権的国家主義の空間構造の再構成ないしは水平的統合の強化に対立する立場である。<地域-中央>の対立は、すでに<農山漁村・地方都市←→太平洋ベルト地帯=高度工業社会>のそれとして、いわば、<first and original Japan←→second and industrial Japan>という「二つの日本」間の対立の激化をすら意味するにいたっている。
だが、<地域-中央>の対立は、本来、資本主義と民族国家に固有なものであり、問題はより限定されなくてはならない。
(一)反中央(同時に中央依存でもある)の情念を超えた「地域主義」は、現実には、(a)地場産業(中小工業、農林水産業)の擁護、(b)地方自治・地方分権の貫徹、(c)地域文化の振興の要求であり、(a)、(c)は結局は(b)に収斂されると思われる。この政治的というより行政的な要求は、伝統的に市民主義的、小ブルジョア的な限界を突破しうるかどうかが、問われざるをえない。
(二)とくに経済自立については、「地域主義」は、従来の(a)<中央→地域>の近代化論的・「開発経済学」的立場(①経済地理学的、②産業立地論的、③「官庁経済学」的=地域連関表的諸方法)にたいし、(b)<地域→中央>の近代化論的・「自立経済学」的立場をとるものと思われる。そのさい、伝統的な①ナロードニキ的・農本主義的方法に逆行するのでなければ、言われている新しい②「広義経済学」的・生態学(エコロジー)的ないしエントロピー論的方法は、その経済学的未確立の点はいま問わぬとして、③マルクス経済学的・社会主義的方法と両立できるかどうかが、問われざるをえない。
(三)最後に、「地域主義」がよってたつ基盤である「地域」の概念は、独自の「自然・歴史・風土」なり「地域共同体」の存在なりによって構成されるのかどうか、とりわけ、沖縄が first and original Japanの諸地域のひとつというだけで包括的に規定されうるのかどうか、独占資本主義とその国家にたいしての独自性は、当該地域の客観的存在条件に尽きるものではなく、生活と生命の再生産軌道を基軸とする単位的な社会の質の問題であり、「共同体」はたんなる集合体としてのコミュニティではなく、その社会の構造原理の問題であるとすれば、沖縄(ウチナー)を日本(ヤマトゥ)に還元しうるかどうかが、問われざるをえない。
4.世界史的には、「地域主義regionalism」それ自体はなんら反資本主義的、反国家的なものではなく、まず「地方自治・地方分権」要求として登場したそれは、民族自決権要求を内包する場合を除いては、ブルジョア的行政改革によって統合されている。「地域主義」が自覚的に政治化、戦闘化したのは、南北の極度の構造的格差-国内植民地的な-をもつイタリアでの反ファシズム的「南部主義(メリディオリズモ)」など少数例にすぎず、それも戦後は、グラムシナ『南部問題』(北部労働者と南部農民との同盟、媒介としての南部の伝統的知識人の解体と有機的知識人の創出)の先見にもかかわらず、イタリア共産党の「自治体から国家へ」(「社会主義的レジオナリズモ」)の構造改良主義的指導によって革命性を骨抜きにされた。
レーニンは、地方自治については、①フェビアン主義的「自治体社会主義」批判、②民族問題としての地方自治権擁護、③労農問題=ソヴェトによる「自治体革命」、と見解を発展させ、晩年には、④死滅へ向うプロレタリア的半国家における経営--地域の自立・自決の役割を評価し、民族問題の解決についてはヨーロッパ--アジアにまたがる社会主義諸共和」国の平等な連合を志向した。
こんにち、危機に立つ独占資本主義の経済的・政治的構造再編は、生産関係の垂直的統合が擬似的「労資共同体」の形成という形態をとらざるをえないのに対応して、水平的には、国内的にも「低開発の発展」とテクノクラート的中央集権強化を、地域開発や住民参加の形態の修正をつうじ、さらには「地方分権化」の形態をすらつうじて展開されている(プエルトリコ、スコットランド、ウェールズ、カタロニアなどの特別自治権獲得にくらべて、日本の「地方の時代」は、とくに沖縄にたいし欺瞞的ではあるが)。現行「地域主義」は①この水平的統合にたいする自然成長的な地域的=人民的低抗およびそれを反映する一定の反資本主義・反国家的イデオロギーと、②帝国主義的構造再編に対決できず、階級闘争と社会主義的変革を回避する市民的急進主義との無定形な混合物であると、考える。とくに「地域主義」が地域問題の民族問題的内容を溶解しさる具に供せられる場合は、国家権力との対抗関係を拾象する市民的急進主義は批判されなくてはならないであろう。ただし、この場合でも、民族問題はその都度の権力関係の変動をつうじてつねに再構成されるのであり、その少なからぬ側面は経済、政治、文化での地域問題の形態をとって発現することに留意しなくてはならない。
問題は、このような「地域主義」の二重性を克服しうるだけの社会主義的「自立経済学」の方法的確立である。
5.現行「地域主義」は、多方法的とはいえ、広範な問題領域をカバーしており、地域問題への社会主義的アプローチは、それら領域について積極的回答をせまられる。たとえば、
A 主として経済学的には①「広義経済学」についてのエンゲルスの提起の展開。価値の経済学に対する使用価値の経済学の可能性。ポランニー経済学の評価。経済人類学の位置づけ。②「エコロジズム」-生態系と再生産の関係。公害経済学の確立。③「エントロピーの経済学」とエネルギー・資源問題の方法。③工農関係論-農本主義の再評価とニュー・フィジオクラシーともいうべき社会主義原理の可能性。
B 主として政治学的には、⑤共同体論-経済学的、社会学的でもある-の総括と展開。⑥分権論-集権・分権と官僚制との関係。社会主義的リージョナリズムのあり方。⑦地方自治論-自治体と国家権力体系、労働者権力と住民自治・地域文化問題などについての再検討。
C 主として哲学的には、⑧自然-人間社会の関係を中心とする史的唯物論の再構成。
沖縄とくに沖縄経済自立については、さしあたり、とくに①、④、⑤、⑧が集団的に追求されなくてはならないであろう。とくに、私見では、玉野井芳郎氏の「地域主義」の総合的提起と沖縄「憲法」論、杉岡碩夫氏の沖縄・庵美地場産業再建論、飯沼二郎氏の沖縄農業の共同複合経営論、川満信一氏の沖縄共同体論ないしいわば「共同体社会主義」論など貴重な先駆的業績は、沖縄にたいする「地域主義」の適用の可否を超えて、沖縄経済の自立、ひいては沖縄人民自決の理論的基礎の構築に集成されうるし、また集成されなくてはならない、と考える。
ただし、そのさい<中央-地域>一般には包摂されえないほどの搾取と従属におかれてきた沖縄の歴史的・構造的条件は、地域の自立ないし自治を主張する市民的急進主義にたいしてすらも本来、革命的に政治的な質を付与せざるをえない点が重視されなくてはならないであろう。その点では、「沖縄を日本の一地方、一地域として規定することによって地域間分業論に取り込まれることになり、不本意にも“沖縄問題”を地域経済・社会の見直し論一般の中に拡散させ、地方分権参加論と結合させることによって矮小化させてしまったのである。……地域主義の視座から自らを解放し、中央と地方という視野の中で沖縄の主体性・自立性を主張すべきであろう」(比嘉良彦氏)という発言に注目したい。
三、共同体と沖縄経済自立
6.前述の諸論点については別途述べることにして、ここでは共同体論についてのみ若干、方法的に提起しておこう。それは、沖縄経済自立を展望する場合、沖縄の島嶼性(特異な位置と全体性=共同性)がなによりも先行条件であり、しかも位置を運用--現状では逆用--しうる主体の形成は、まず共同性を掘り下げることのうちにしかみいだせないであろうからである。おそらく、主要な問題は、そこに共同体が<現存するか、しないか>の実証よりも、それが<どう再生産、再構成されているか>の方向、さらには、それを主導する主体、社会変革にとって共同体的な<共生と転生がどのような意味をもつか>であろう。
共同体(段階的には原始共同体-農村共同体-村落共同体-「地域共同体」、類型的にはアジア的-およびスラヴ的-・古典古代的・ゲルマン的共同体)にたいするマルクス主義の視点は一定していない。
(一)とくに資本主義-社会主義の過渡における共同体の役割については、共同体を社会発展の桎梏たる遺制とみて、その解体を前提とする立場と、社会主義の定礎たりうる萌芽とみて、その保全または復活を重視する立場とが極端に対立し、両者の止揚の契機がみいだされていない。
(二)共同体の本質の把握の点では、社会学的に血縁・地縁的共同生活形態や、経済学的に非個人的所有形態、協同的生産形態、非市場的交換形態や「経済人類学」的に生命再生産形態を基軸とする諸立場が乱立、混合し、それらを社会科学的に整序、統合する契機がみいだされていない。
(三)そして、現行「地域主義」では、共同体の基本的解体の現実--共同体を奪われた「共同体人間」は広範に存在するが--から遊離したところで「地域共同体」が虚偽意識的にもちこまれ、ときにはそれが地方自治体と重ね写しされ、市民主義的に体制内化の政治的用具に供されがちであり、沖縄のように単位社会として現存する共同体の革命的評価の契機がみいだされていない。
このような状況に終止符をうち、①古い共同体(ゲマインシャフト)を新しい共同体(ゲマインヴェ-ゼン)=社会主義共同体に再構成させ転成させる媒介契機-抵抗共同体の形成-のために、②主として労働と文化の共同性にひそむ発展的要素の解明に重点をおき、③いわば「共同体社会主義」の「戦闘的地域主義」への跼蹐を防止しつつ、それをプロレタリア・ヘゲモニーとの融合、新しい民族および民族主義の形成の道へと推進するためには、マルクス主義的共同体論の形成への道と推進するためには、マルクス主義的共同体論の確立はもとよりとして、内外植民地の反帝社会主義革命論と、それを裏づける現局面の帝国主義論についての、マルクス主義自体の具体的展開をはからなくてはならない。
7.(一)の点では、ヴェーバー大塚久雄的な近代化論的共同体論が決定的にのりこえられなくてはならないであろう。もっとも、ヴェーバーは「種属(エトノス)集団」にたいする「政治的共同体」の優位を強調していたし、大塚教授も「共同体の二面性」(権力の支配手段と生産者の抵抗組織)に着目し、「半共同体」(古い共同体規制に対抗する場合、「ある程度まで古いものと重なり合いながらも、彼ら〔小生産者〕自身が抵抗の組織として一種の共同体的な共同組織をつくりあげる」)の意義を指摘していた。資本主義の日本的発展は、労資関係でも国家関係でも、共同体をそれなりに運用し、再構成しての近代化であった(村落共同体-経営・軍隊家族主義的「共同体」)。日本的労働組合主義なり日本的労働者政党なりは、抵抗的「半共同体」として出発しつつも、市民社会の近代的爛熟のまえに、古い内部規制のみの形骸と化した(沖縄「復帰」後のそれらの特権化と本土系列化)。インドの村落共同体-カースト共同体は純保守的で、戦前日本の共同体ないし疑似共同体は近代化的だ、と一面的に言うことはできない。反近代化論的共同体論は、たんなる伝統的共同体への土着主義的依拠を超えざるをえないであろう。
(二)の点では、K・ポランニーの言う「贈与-互酬」の原理(自己完結的実物循環システム)や、C・メイヤスーの言う「家族制共同体(コミュノーテ・ドメスティク)」のメカニズム(「人間エネルギー」の再生産構造)が、資本主義とくに帝国主義による破壊と利用に対抗しうる接点が探究されなくてはならないであろう。このことは、生命と生活の経済の法則性が「広義経済学」=人間と使用価値の経済学として解明され、とくに共同労働と共同意識が、その解体の危機を契機として、総体として反資本主義・反国家的エネルギーに転化する過程が裏づけられることを必要とする。共同体は本来、閉鎖的な制度化されたゲマインシャフトと、潜勢的に形成されつつある開放的ゲマインヴェーゼンとの矛盾的重合物であり、後者の側面の飛躍的発現を保障しうる契機は、共同労働過程と共同体ぐるみの闘争のうちに存在する。
(三)の点では、共同体が「復古-革命」の弁証法(グラムシ)にしたがって政治的に登場する媒介契機が重視されるべきであろう。そのためには、個別共同体が共同体間の交通関係の拡大と能動化をつうじて民族に形成される過程の主導力、とくに知的・道徳的ヘゲモニーが問われなくてはならない。それは、すぐれて知識人ないし知識人集団の問題である。ヴェーバーすらも、彼の言う「価値の領域」に属する「民族」理念にとっての文化的「威信」の担い手として、知識人の役割をとらえていた。
8.マルクス主義的共同体論の原点としては、マルクスの『資本制生産に先行する諸形態』は、共同体の歴史的類型や段階移行の動態を分析したにとどまらず、所有を労働の一面ととらえ(「所有は生産諸条件にたいする関係である」)、労働=所有の発展過程を労働の視点から(労働の特化、協業と分業の成長)、原理的に解明した点に、大きな意義をひそめていると考える。この原理的立場が『資本論』を得て確立していればこそ(また、19世紀の世界構造を実質的に支配していた英露反革命問題にたいする世界革命戦略を構想していればこそ)、晩年のマルクスはザスーリチあての手紙や『宣言』露語版序文などで、ロシアのミール共同体の役割に期待を寄せたのであった。共同体が社会主義の基盤となりうる条件は、資本主義的生産様式の同時的な存在という、「集団労働のすべての条件が与えられるような歴史的環境」であり、近代的世界からは孤立していない世界史的視角である。したがって、「もしもロシア革命が西欧のプロレタリア革命の合図となるならば、両者がたがいに補いあうならば、現在のロシアの土地共有制は共産主義的発展の出発点となることができる。」この有名な一句は、労働共同体→抵抗共同体の可能性と、近代的な生産手段や管理組織の援助の必要とを語っているものと解する。
この史的弁証法はその後単純化され、ローザ・ルクセンブルクもレーニンも、共同体解体必然論に傾いたかにみられる。しかしローザは刻明に共同体の「共産主義的特質-計画と組織とをもった共同労働-」について調べ、レーニンは史上はじめて、非資本主義的な道での共産主義への移行、その起動力としての農民ソヴェト=新しい共同体について論じた。いま、共同体論のその後の豊富な資料と理論的停滞-とくにスターリン主義の「農業集団化」、すなわち共同体の古い規制の専制的・官僚主義的利用-とを踏まえて、マルクスがロシアにたいし語ったように沖縄にたいし語らなくてはならないし、また語ることができよう(それよりも、ファノンやゲバラが「先進国」について語ったように、沖縄が日本にたいし語るべきであるかもしれないが)。
9.旧来の「二重経済・社会論」や「開発経済学」を超える最近のA・G・フランク、S・アミンの開拓は、新しい帝国主義論の構築の出発点であった。こんにちでは、そこからどう世界的基準での支配、従属関係の法則性とその矛盾の展開についての理論を発展させるのか、が問題である。それは、資本主義的生産関係の普遍的浸透による近代化=共同体解体の視点から、共同体の変貌、再構成や「後進国」の「先進国」にたいする-一定の限度では「後進地域」の「先進地域」にたいする-対応の動態(積極的抵抗と消極的同化との複雑な合成)の視点へと、帝国主義の分析座標を転換させることを意味する。沖縄の場合は、たとえばアイルランドとは逆方向に、長期にわたる構造の潜勢的な民族形成的(ナシオリテール)近代化から民族的(ナシオナル)意識の熟成の道をたどっている、と考えることもできる。A・アブデルマレクの言う「民族性(ナシオナリテール)の現象」から「民族(ナシオナル)形成体」への過程である。近代化は、個別共同体や個々の島社会を琉球弧におよぶ広域の多元的連帯社会にまで促進せざるをえないし、経済自立についても搾取・収奪者との全面的関係で構想せざるをえない。また、ひろく、独占資本主義と中央集権的国家主義の国内再編の強化は縁辺化(マージナライズ)された「後進地域」の自立と自決を必然化させつつある。この新しい帝国主義論、とくにその経済学的方法については別報告に譲りたい。
10.この問題でまず注目すべきは、川満信一氏の共同体論である。氏は設問する。「そこで問題は、まだ資本主義に到らないベトナムで、社会主義への道が開かれ、あるいは農村共同体を根拠として、毛沢東の前衛たちが中国革命を達成し、そしてまた後進的なロシアが、都市のプロレタリア前衛と、抑圧された農民たちの蜂起で革命を遂行したように、この島島の村落共同体の民衆感性へ向けて、衝撃をつくりだし、資本主義の陥穽を一挙にまたいで社会変革へと飛翔する共同の幻想をひき出し得るか、あるいは社会意識の分割とアトム化を進め、ヨーロッパ資本主義社会下の、自我意識の確立と苦悶にまで進んで、そこから・近代超克・の課題を引き受けていくか、という思想における、民衆へのアプローチの分岐が問われてくる。」氏の解答は前者であり、「新たな共同性の創造を課題」として、「各単位の共働組織を確立していく具体的なスケジュール」が求められる。具体的なスケジュールは具体的分析によってしかみいだされえないが、氏の選択は、すでにイデオロギー次元を超えて、沖縄共同体-沖縄民族形成-沖縄社会主義の理論的基線を射当てていると思われる。抵抗概念としての共同体と民族の社会科学的普遍性が確認されなくてはならない。
11.肝心なのは、資本主義的規定のもとでの共同体の二重性ないし自己矛盾、すなわち、贈与-互酬と総体的・ボス的収奪、成員相互間の扶助と牽制、共同体ぐるみの抵抗と服従……を冷静に踏まえつつ、新しい共同体=社会主義的共同体への転生、飛躍の具体的契機をつかみだすことである。それは、一般的には、①資本主義自体を止揚せざるをえないプロレタリアートおよびプロレタリア革命的勢力の主導的媒介の機能と、②歴史的に形成された当該共同体の経済的・社会的・文化的特性-民族的特性に求められなくてはならない。
沖縄の場合、島ぐるみの日本-世界資本主義との対決を意識的に主導し、共同体的抵抗に普遍性を付与しうる勢力は、一定度発酵しつつあると考える。それは、もはや周辺資本主義の自生的発展ではありえないことはもちろん、プロレタリアートと中産諸層とを混在させ、事実上日本国家の人民統制機関と化した系列的労働組合でもありえず、「復帰」運動の挫折を内在的に総括、突破しようとするプロレタリアと知識人との新しい民族的指導体たらざるをえないであろう。ただし、それが沖縄経済自立を担う経済主体たりうるためには、特設の創造的構想力を必要としよう。
沖縄共同体の特性については、文字どおり沖縄に深く学ぶしかないが、外目からしても、その島嶼的・海洋民族的開放性、亜熱帯的商品生産の内部にまで貫徹している強い共同労働の互助性、共同体内分業における成員の公正な同権性、「都市」にまで貫徹されている近代的表層と共同体的基層との二重性……は、基本的には解体した日本の伝統的共同体を超える発展的な転生の基盤を提供していると考える。この特性を、日本的ないし近代化論的基準から、「後進性」に還元することはできない。この点では「共同体の経済学」の沖縄的深化を要しようが、教示を待ちたい。
四、沖縄経済自立と社会主義
12.今日において、経済自立とは社会主義的方向でのそれであり、社会主義的変革と民族自決とは両立可能であるどころか、メダルの表裏をなす不可分の関係にある。そして、社会主義のパラダイムについては、これもやはり根本的な視座の転換を必要とする。国際的にも、「第三世界」の多くの諸国は政治的自立を「社会主義」経済体制によって保障しようとしているが、その内実はほとんど後発的(または周辺的)国家資本主義でしかなく、また、村落共同体=人民公社からの国民的剰余生産物を挺子に「自力更生」的社会主義建設を志向した中国は、共同体の内部矛盾の処理を誤ったことと、世界市場を経由しての迂回的蓄積が帝国主義世界体制によって逆規定されたことのために、近代化路線に転換せざるをえなかった。農業を徹底的に犠牲にしてのソ連の重化学工業化路線の破産については、触れるまでもない。沖縄経済自立--沖縄共同体社会主義の展望は、あまりにも悪しき範例に先行されている。
しかしながら、既成の社会主義パラダイムの崩壊は、社会主義が集団的・共同体的な抵抗と労働との論理的帰結たらずをえない以上、社会主義概念の不断の新生を促さずにはいない。既成社会主義については、①社会主義を自称する資本主義か、②資本主義でもなければ社会主義でもない過渡的構成体か、③とにかくも社会主義ではあるが、前期的(フリュー)=変型的(メタ)・異性体的(パラ)なそれか、の見方がありうるが(私見は③)、このような歪曲は、当該社会の後進性-資本主義の未熟に起因するというよりも、世世界資本主義の規定性の把握が不十分なことと、それを規定しかえす根源的な主体的力量の構築に失敗したことに発していると言える。この主体的力量こそが、社会主義的共同体(労働者権力と旧共同体の転生)に他ならない。
社会主義は本来、世界体制たらざるをえず、自給的局地経済圏を形成しうるのは、例外的・一時的な場合にすぎない。沖縄の場合、経済自立が体制的に保障されるためには、日本帝国主義からの自立-民族自決とともに、日本資本主義そのものの変革、アジア・太平洋諸社会との連帯を必要とする。そのための起動力、本源的蓄積を提供しえなくては、日本のプロレタリアート・人民の自己解放はありえない。その相互作用・相即過程の原点は? それをつきとめたい。
五、むすび
13.すでに第三世界のマルクス主義的革命家たちは、共同体-民族が社会主義革命と社会主義建設にはたすべき役割について摸索してきた。スルタン・ガリーエフ(タタール)、タンマラカ(インドネシア)、ホセ・カルロス・マリアテギ(ペルー)などがそれであり、とくにマリアテギは、共同体にもとづくインディヘニスモ(原住民復権思想)と社会主義との結合を正面から主張した。彼らはまた、すでに実質的には、公認のスターリン的民族概念--一定の固定的な指標的特徴をそなえた社会学的共同体(ゲマインシャフト)・プラス・民族発展段階(前近代民族(ナロードノステ)-近代的民族(ナーツイヤ)-「社会主義的民族」)--を乗越えて、世界的にはプロレタリア・反資本主義的な、抵抗し自立する非ないし超階級集団としての民族、という新しい概念をも切り拓きつつあった。本来、民族とは、刻々の権力関係をつうじて不断に再構成されるものであり、その政治学的規定の基本は、「自立的政治共同体たろうとする要求をもっているところの社会的共同意識」(今中次磨)に求められる。とくに、1970年代からの帝国主義世界体制の文字どおりの危機とその擬似的「民族共同体」再統合を軸とする突破策とのもとでは、この共同意識は、旧来のブルジョア民族主義を革命する民族主義、反帝社会主義的民族革命へと晶結せざるをえない。沖縄は、アジア・太平洋諸社会の変革のうえでも、キー・ストーン的位置を占めている。
14.一口で言って、沖縄地域主義ではなく、それを止揚した沖縄民族主義を!この日本から沖縄への要請にたいし、沖縄は日本をどう位置づけ、どう批判するであろうか?さらに、沖縄資本主義ではなく、沖縄(共同体)社会主義を!この日本からの展望にたいし、沖縄は日本の社会主義的変革をどう想定し(または想定せず)、日本になにを要求するであろうか?
(長野大学)
このページのトップにもどる