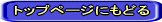亀壂撽宱嵪偺帺棫偵傓偗偰亁乮幁嵲幮1979丒俇丒25乯
仜壂撽帺棫宱嵪偺偨傔偵丂尨揷惤巌乛栴壓摽帯
丂彉亅帺棫宱嵪榑媍傪傔偖傞嶰偮偺栤戣揰
丂戞堦復丂暅婣俆擭丄壂撽宱嵪偺尰忬
丂戞擇復丂帺棫宱嵪彅榑傊偺帇揰
丂戞嶰復乽奐敪乿宱嵪妛偐傜乽帺棫乿宱嵪妛傊
丂亙曗榑亜壂撽帺棫偺巚憐亅愳枮怣堦巵偺乽嫟摨懱榑乿偵偮偄偰亅
亙帒椏侾亜壂撽宱嵪偺尰忬攃埇偺偨傔偵丂尨揷惤巌
亙帒椏嘦亜崙撪怉柉抧榑乮儗僕儏儊乯丂拞懞忎晇
亙帒椏嘨亜搰涀宱嵪榑乮儗僕儐儊乯丂拞懞忎晇
仸亀壂撽宱嵪帺棫偺揥朷乗 '79戞俀夞僔儞億僕僂儉曬崘乗亁乮斾壝椙旻丒尨揷惤巌曇挊乛幁嵲幮1980.7乯
壂撽帺棫宱嵪偺偨傔偵
乗乗壂撽宱嵪偺尰忬偲帺棫宱嵪偺曽朄揑堦帇揰乗乗
尨揷丂惤巌乛栴壓丂摽帯
彉亅帺棫宱嵪榑媍傪傔偖傞嶰偮偺栤戣揰
丂乽怳嫽奐敪寁夋乿偺攋抅偲擔杮宱嵪偺挿婜峔憿晄嫷偲偄偆尰幚偺側偐偱壂撽宱嵪偺妶楬傪偳偙偵尒偄弌偡偐丠丂暅婣5擭傪宊婡偵傑偒婲偭偨壂撽帺棫宱嵪榑媍偼丄條乆偵偙偺揰傪徠幩偡傞傕偺偱偁傠偆丅傢傟傢傟偵偼丄偙偺榑媍傪偝傜偵敪揥偝偣傞偵偼丄師偺嶰偮偺栤戣揰偺夝柧偑晄壜寚偩偲巚傢傟傞丅
丂戞堦偺栤戣偼丄壂撽宱嵪偺尰忬傪偳偆傒傞偐偱偁傞丅暅婣5擭偺寛嶼偼丄寢嬊壗傪柧傜偐偵偟偨偐丠丂壂撽抦幆恖偺懡偔偺榑幰偵傛偭偰暘愅偝傟偨傛偆偵乽怳嫽奐敪寁夋乿傕奀梞攷傕丄壂撽宱嵪偺峔憿乗乗堦尵偱偄偊偽奜晹丒婎抧埶懚宱嵪偲偄偆乗乗傪曄偊偼偟側偐偭偨丅杚栰巵偑塻偔巜揈偡傞偛偲偔乽怳傝弌偟偵栠偭偨乿偲偺幚姶偼恀幚偱偁傠偆丅偟偐偟丄暅婣5擭傪宱夁偟偨壂撽宱嵪偼丄屻栠傝偱偒側偄丅楌巎偼媡揮偟側偄丅暅婣偟偰傕曄傜側偄壂撽宱嵪偲偼壗偐丠丂偙偺揰傪妋掕偟側偄尷傝壂撽宱嵪偺帺棫偼偦偺揥朷偺偆偪偵尒摟偡偙偲偼偱偒側偄丅傢傟傢傟偼丄偙偙偵徟揰傪掕傔丄暅婣偺寢壥丄壂撽宱嵪偑慻傒崬傑傟偨擔杮宱嵪偲壂撽宱嵪偺峔憿揑娭學傪夝柧偡傞丅寢榑揑偵偼丄乽崙撪怉柉抧乿偲偟偰偺壂撽宱嵪偺峔憿揑懚嵼偲偄偊傞偱偁傠偆丅壂撽宱嵪偼丄偙偺傛偆偵埵抲偯偗捈偝傟丄乽廃曈乿帒杮庡媊偲偟偰夞揮偣偞傞傪偊側偄偺偱偼側偐傠偆偐丅帺棫宱嵪榑媍偼丄偙偺傛偆偵72擭暅婣帪偲偼堎偭偨儗儀儖乮宱嵪乯偱偼偁傟丄擔丒壂宱嵪偺丄峔憿揑娭學偺側偐偱嵞傃壂撽宱嵪偺帺屓婯掕偑晄壜寚偲側偭偰偄傞帠懺傪慛柧偵偟偨偺偱偁傞丅
丂栤戣偺戞擇偼丄帺棫宱嵪榑媍傪尰帪揰偵偍偄偰偳偺傛偆偵乬憤妵乭偡傞偐丠丂偱偁傞丅傕偪傠傫乬憤妵乭偲尵偭偰傕傢傟傢傟偑傛偔側偟偆傞傕偺偱偼側偄偙偲偼丄戞擇偺峴榑偐傜柧傜偐偱偼偁傠偆丅偟偐偟丄壂撽宱嵪偺帺棫傪揥朷傊偲幭偮傔傞偨傔偵偼晄壜旔偺嶌嬈偱偁傞丅懳徾偲偟偨彅庡挘偼丄壂撽宱嵪偺尰忬偵偮偄偰傎傏堦抳偟偨尒夝傪傕偪側偑傜丄宱嵪帺棫偺帇揰偲揥朷偵偍偄偰堎偭偰偄傞丅偟偐偟丄戝棯偡傟偽丄擇偮偺孹岦偵嬫暿偝傟傞丅堦偮偼壂撽宱嵪偺屻恑側偄偟掅奐敪偐傜偺扙媝傪嬤戙壔偵媮傔傞庡挘丄傕偆堦偮偼屻恑側偄偟掅奐敪帺懱偺壂撽揑撈帺惈偵埶嫆偟偰帺棫偺悈楬傪扵傠偆偲偡傞庡挘偱偁傞丅慜幰偑亀壂撽偺宱嵪奐敪亁丄亀奐敪偲帺帯亁偍傛傃杚栰榑暥偱偁傝丄屻幰偼乽庤偞傢傝偺帺棫宱嵪榑乿偲愳枮榑暥偱偁傞乮杮峞偱偼愳枮榑暥亖乽嫟摨懱榑乿亀怴壂撽暥妛亁32乣34崋偼乽巚憐揑帺棫榑乿偲偟偰戝偒側堄媊傪傕偮偑丄捈愙揑側宱嵪榑偱側偄偙偲偍傛傃巻悢偺娭學偱妱垽偟偨仺乽曗榑乿偲偟偰宖嵹乯 丅慜幰偺嬤戙壔榑偼丄懡偐傟彮偐傟丄擔丒壂宱嵪偺堦懱壔傪慜採偵偟偨榑媍偱偁傝丄偙傟偵懳偟丄屻幰偼丄壂撽宱嵪憤懱偺帺棫偲偄偆帇揰偺寚擛偑偁傝側偑傜傕壂撽揑撈帺惈傪乽嫟摨懱乿偺嵞専摙丄敪孈偟偰偍傝丄嬤戙壔偺尰幚偲榑棟傪斸敾偡傞帇妏偼妋曐偟偰偄傞丅偟偐偟丄傕偆堦偮偙偙偱偺戝偒側榑揰偼丄擔丒壂宱嵪偺娭學傪乬帺棫乭偲偺娭學偱偳偺傛偆偵攃埇偡傞偐偱偁傞丅偦偺揰偱偼丄杚栰榑暥偵懳偡傞昡壙偑堦偮偺婎弨偲側傞偱偁傠偆丅壂撽宱嵪偺妶楬偼嬤戙帒杮庡媊揑敪揥偐斲偐丠丂偲丅
丂偝傜偵戞嶰偺栤戣偼丄壂撽宱嵪偺屻恑惈丄掅奐敪峔憿偺扙媝偼丄偄傢備傞戞嶰悽奅偺宱嵪奐敪乗乗帺棫榑偲偳偺傛偆偵娭楢偟偰偄傞偐丠偱偁傞丅傢傟傢傟偑偙偙傑偱椞堟傪奼戝偟側偗傟偽側傜側偄偲峫偊偨偺偼丄杚栰巵偑柧妋偵攃埇偟偰偄傞傛偆偵丄壂撽宱嵪偺屻恑惈丄掅奐敪峔憿偼丄擔杮宱嵪偲堦懱壔偡傟偽夝寛偝傟傞傕偺偱偼側偄偲偲傜偊傞偐傜偱偁傞丅堦搙傃戞嶰悽奅偺宱嵪奐敪榑偵傢偗擖偭偨偲偒丄宱嵪帺棫榑偺崲擄偝偼柧傜偐偲側傞丅怴屆揟攈揑乽奐敪乿榑丄乽拞怱亅廃曈乿榑丄僜楢儌僨儖乽旕帒杮庡媊揑敪揥乿榑丄拞崙儌僨儖乽帺椡峏惗乿榑側偳偺庡梫側奐敪榑偼丄寢嬊丄嬤戙壔榑偺儚僋傪扙偗弌偰偄側偄丅偙偺昡壙偵偼丄憡摉偺堎榑偑弌傞偙偲偼丄廫暘怱摼偰偄傞偮傕傝偱偁傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄廳梫側偺偼丄堦崙宱嵪偺奐敪偑掗崙庡媊偺宱嵪峔憿偺醔宆揑丒廃曈揑堦晹暘偵偟偐寢壥偟側偄偲偄偆尰幚偱偁傞丅偦偙偵偼崙嵺宱嵪懱宯偵偮偄偰偺崻杮揑側擣幆偺揮姺偑偁傞丅掅奐敪仺奐敪偺嬝摴偼丄宱嵪帺棫偵偼慡偔寢傃偮偐偢丄媡偵戞嶰悽奅彅崙偼乽廃曈乿帒杮庡媊偱偁傝懕偗傞丅僼儔儞僋丄傾儈儞偺塻偄暘愅偼偙偺揰傪柧傜偐偵偟偨丅傢傟傢傟偼丄偙偺帇揰偲敪揥傪捛媦偡傞側偐偐傜丄壂撽帺棫宱嵪榑傪尒捈偝側偗傟偼側傜側偄偱偁傠偆丅
丂偙偺彫榑偼丄埲忋偺嶰揰傪幉偵偟偨庒姳偺栤戣採婲偱偁傞丅壂撽抦幆恖丄楯摥幰彅孼丄傑偨壂撽宱嵪偵愑擟傪傕偪偁傞偄偼娭梌偝傟偰偄傞彅孼偵屼専摙偄偨偩偒丄屼斸敾丄屼幎愑偄偨偩偗傟偽丄朷奜偺婌傃偱偁傞丅
戞堦復丂暅婣俆擭丄壂撽宱嵪偺尰忬
侾丄 攋嶻偟偨乽怳嫽奐敪寁夋乿
丂72擭乽暅婣乿偵敽側偄擔杮惌晎偑壂撽宱嵪偵懳偡傞擇戝巤嶔偲偟偰嶔掕偟偨偺偼丄暅婣摿暿慬抲朄偲壂撽怳嫽奐敪摿暿慬抲朄偱偁偭偨丅偙偺偆偪怳嫽奐敪寁夋偺幉偲側偭偨偺偑丄72擭搙傪弶擭搙偲偡傞10僇擭寁夋亖壂撽怳嫽奐敪寁夋偱偁偭偨丅偙傟偼丄嘆杮搚偲偺奿嵎惀惓丄嘇抧堟摿惈傪惗偐偟偨帺棫揑敪揥偺婎慴忦審偺惍旛丄傪庡梫栚昗偲偟丄偦偺偨傔偵嶻嬈峔憿偺夵曇丄偡側傢偪丄戞擇師嶻嬈偺奼戝丄傪払惉偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁偭偨丅偟偐偟側偑傜丄廃抦偺傛偆偵丄偙偺10僇擭寁夋偼丄婛偵偦偺慜敿傪宱夁偟偨偩偗偱戝暆側尒捈偟偑峴傢傟偰偄傞帠幚偑帵偡傛偆偵姰慡側攋嶻傪悑偘偰偄傞丅傑偨丄惌晎儗儀儖偼尵偆偵媦偽偡導儗儀儖偱偺寁夋尒捈偟傕帠幚忋丄摉弶寁夋偺榞撪偱偺庤捈偟偵棷傑偭偰偄傞丅
丂崱擔丄乽帺棫宱嵪乿榑媍偵偲偭偰昁梫側偙偲偼丄乽怳嫽奐敪寁夋乿傪乽暅婣乿埲崀偺壂撽宱嵪偺悇堏偺側偐偱憤妵偟丄偦偺寁夋傪娧偔曽朄儗儀儖偵懳偡傞斸敾偵傑偱崅傔傞偙偲偱偁傞丅偦偺堄枴偱乽帺棫壂撽宱嵪乿榑媍偼乽暅婣乿埲崀偺壂撽宱嵪偺尰忬傪偄偐偵攃埇偡傞偺偐丄偲偄偆揰偐傜弌敪偡傞丅
俀丄 72擭乽暅婣乿埲崀偺壂撽宱嵪
丂乽暅婣乿埲崀偺壂撽宱嵪偼丄柤栚忋偱偼丄戝偒側惉挿傪悑偘偰偄傞偐偵傒偊傞乮戝暆側宱嵪惉挿棪偺怢傃丄導柉強摼堦恖偵傛傞奿嵎偺弅彫摍乆乯丅
丂偟偐偟丄嘆挻娚枬側嬥梈娐嫬偺尰弌丄嘇岲嫷尒捠偟愭峴偵傛傞崅搳帒丄崅徚旓偺庝婲傪偦偺梫場偲偡傞偙偺堎忢偲傕偄偊傞壂撽宱嵪偺崅惉挿偼丄堦夁惈偵夁偓側偐偭偨戝宆僾儘僕僃僋僩亖奀梞攷偺廔椆偲嫟偵丄偍傝偐傜偺擔杮宱嵪偺晄嫷偲傕偁偄傑偭偰丄偨偪傑偪偺偆偪偵偦偺嫊忺傪偼偑偝傟偨偺偱偁傞丅
丂傑偢戞堦偵丄婇嬈宱嵪偺埆壔偵敽側偆婇嬈搢嶻偺媫憹偱偁傞丅76擭偵偼丄72擭斾審悢偱審悢偱30攞丄晧嵚妟偱22攞偲偄偆揤暥妛揑悢帤傪婰榐偟偰偄傞丅
丂戞擇偵丄幐嬈幰悢偺媫憹偱偁傞丅72擭埲慜偵偼2乣4愮恖偱悇堏偟偰偒偨姰慡幐嬈幰悢偼丄乽暅婣乿埲崀媫憹偟丄摿偵奀梞攷廔椆屻偺75丄76擭偼奺乆6000恖偢偮憹壛偟丄76擭偵偼2枩6愮恖乮71擭偺6攞嫮乯偵払偨丅傑偨丄幐嬈棪傕76擭偵偼6.3亾傪婰榐丄摨擭偺慡崙暯嬒幐嬈棪偺3.3攞偵払偟偰偄傞丅偙偆偟偨悢帤偼丄婎杮揑偵偼丄堦夁揑側奀梞攷僽乕儉傪尅堷椡偲偡傞壂撽宱嵪偺崅惉挿偑丄挿婜揑側屬梡岠壥傪惗傒弌偡傋偒壗傜惗嶻揑側傕偺傪惗傒弌偝側偐偭偨偙偲傪帵偡傕偺偱偁傞丅
丂戞嶰偵丄堏桝擖埶懚偺徚旓宆宱嵪偺側偐偱偙偺崅惉挿偺傕偨傜偟偨崅徚旓丄奀梞攷岺帠楯捓偺媫忋徃傪宊婡偵慡嶻嬈偵媦傫偩捓嬥僐僗僩偺媫忋徃偲偺暋崌偵傛偭偰庝婲偣傜傟偨乽杮搚乿傪忋傑傢傞崅僀儞僼儗偱偁傞丅偙偺偨傔丄壂撽偺幚幙捓嬥偼丄慡崙暯嬒傪戝暆偵壓夞偭偰偄傞偺傒側傜偢丄75擭偵帄偭偰偼丄偦偺愗傝壓偘傪彽偄偰偝偊偄傞丅偙偺傛偆偵壂撽宱嵪偺乽崅惉挿乿偼丄壂撽恖柉偺晉偺愨懳揑尭壙傪彽偄偰偄傞偺偱偁傞丅
丂乽暅婣乿埲慜偺壂撽宱嵪偼丄暷孯婎抧埶懚偵傛傞惂栺偺傕偲帒杮拁愊偑棫偪抶傟丄戞嶰師嶻嬈偺旍戝壔偑徾挜偡傞傛偆偵桝擖埶懚偺徚旓宆宱嵪偲偟偰偒傢傔偰惼庛側峔憿偵偁偭偨丅偦偟偰壂撽宱嵪偼丄忢偵奜晹偐傜偺帒嬥偺棳擖乮婎抧廂擖丄墖彆摍乯偵傛偭偰恏偆偠偰巟偊傜傟偰偒偨丅偙偺壂撽宱嵪偺峔憿揑摿幙偼乽暅婣乿傪宱偰崱擔曄壔偟偰偒偰偄傞偺偐丠
丂懡偔巜揈偝傟偰偒偨傛偆偵丄寢榑揑偵尵偊偽丄戞嶰師嶻嬈旍戝偺徚旓宆宱嵪偲偟偰偺壂撽宱嵪偺峔憿揑摿幙偼慡偔曄壔偟偰偄側偄丅傓偟傠戞嶰師嶻嬈旍戝壔偲惢憿嬈偺掆懾偼堦憌恑峴偟偰偝偊偄傞丅惢憿嬈偺掅柪偙偦丄偁偺乽崅惉挿乿偑丄壂撽宱嵪偵偲偭偰壗傜偺惗嶻揑宱嵪妶摦傪傕桿摫偣偢丄壗傜壂撽偵偍偗傞帒杮拁愊偵峷專偡傞傕偺偱側偐偭偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅
丂壂撽偺惢憿嬈傪丄偝傜偵堦曕偦偺撪晹偵棫偪擖偭偰専摙偡傞偲丄帠懺偼傛傝怺崗偱偁傞偙偲偑妋擣偝傟傞丅
丂75擭偺岺嬈晅壛壙抣妟丄恖岥摉偨傝岺嬈晅壛壙抣妟媦傃晅壛壙抣棪偼丄偄偢傟傕慡崙嵟壓埵偱偁傝丄偟偐傕晅壛壙抣棪偼丄72擭埲崀擭乆掅壓丄暅婣埲崀偺4擭娫偱俁暘偺侾傕掅壓偟偰偄傞丅偙偺寢壥丄慡崙暯嬒偲偺嵎偼傑偡傑偡奼戝偟丄係擭娫偱偦偺奐偒偼2攞偲側偭偰偄傞丅抧堟宱嵪奿嵎傪丄扨弮偵宱嵪庡懱偺惗嶻惈奿嵎偲嶻嬈峔憿偲偺憡忔偲偟偰攃偊傞側傜偽丄扨側傞岺嬈壔丄廳壔妛岺嬈壔偵傛偭偰偼丄奿嵎偼夝徚偵岦偐傢偢丄媡偵奼戝偟偐偹側偄丄偲偄偆嫵孭傪偙傟傜偺帠幚偼帵偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂懳奜廂巟峔憿偐傜傒偰傕壂撽宱嵪偼丄乽暅婣乿埲崀丄偦偺摿幙傪曄壔偝偣偰偼偄側偄丅72擭埲慜偐傜堦娧偟偰愒帤傪寁忋偟偨宱忢廂巟偼丄偦偺屻傕偙偺孹岦傪奼戝偟偰偍傝丄擔杮惌晎偵傛傞嵿惌帒嬥偺搳擖偵傛偭偰宱忢愒帤傪曗揢偡傞峔憿偲側偭偰偄傞丅嵒摐丒僷僀儞悖媗摍堦師嶻昳偵摿壔偝傟偨堏弌昳峔憿偺儌僲僇儖僠儏傾惈偼傑偡傑偡屌掕壔偝偣傜傟偰偄傞丅偙偆偟偨壂撽宱嵪偺堏桝擖埶懚搙偺偒傢傔偰崅偄偲偄偆摿幙偼丄乽暅婣乿屻傕慡偔曄壔偼側偔丄傓偟傠暅婣摿暿慬抲偵傛偭偰抧応嶻嬈偺妶摦椞堟傪壂撽撪晹偵尷掕偝傟偨寢壥丄偙偆偟偨摿幙偼堦憌埆壔偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂乽暅婣乿傪嫬偵桞堦曄傢偭偨偺偼丄偙偺傛偆側懳奜埶懚搙偺崅偄寢壥偲偟偰偺懳奜廂巟偺戝暆側愒帤傪丄廬棃偼孯娭學庴偗庢傝偵傛偭偰曗揢偡傞峔憿偵偁偭偨傕偺傪丄擔杮惌晎偵傛傞嵿惌帒嬥揚晍偵傛偭偰曗揢偡傞峔憿傊偲抲偒偐偊偨揰偩偗側偺偱偁傞丅
俁丄崙撪怉柉抧偲偟偰偺壂撽
丂壂撽偺宱嵪峔憿偼丄72擭乽暅婣乿傪宊婡偵丄偦傟傑偱偺暷孯巟攝壓偵偍偗傞婎抧埶懚宱嵪乗乗孯帠怉柉抧揑宱嵪峔憿偲偟偰偺怓嵤傪師戞偵敄傔偮偮丄怴偟偄抜奒偵擖傝偮偮偁傞丅傢傟傢傟偼丄偙偆偟偨怴偟偄抜奒傪寎偊偨壂撽偲壂撽宱嵪傪崙撪怉柉抧偲婯掕偡傞丅壂撽偼丄岺嬈揑拞怱抧堟亖擔杮乽杮搚乿偵懳偟偰丄堦師嶻昳嫙媼偵摿壔偝傟偨丄傑偨乽堦偮偺宱嵪僔僗僥儉偑奜晹偐傜墴偟偮偗傜傟丄掅奐敪揑僔僗僥儉偲峔憿傪嵞惗嶻偟嫮壔偡傞孹岦傪傕偮帺敪揑側彅椡偺婎慴傪宍偯偔偭偰偄傞乿廃曈抧堟偱偁傝丄暪崌姰惉壓偵偍偄偰丄擔杮崙壠撪晹偺廃曈抧堟丄戞嶰悽奅偲偟偰偺壂撽偲壂撽宱嵪偼丄擔杮掗崙庡媊崙壠偺崙撪怉柉抧偲偟偰懚嵼偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂壂撽宱嵪偺尰幚偼丄怉柉抧偵屌桳側彅懁柺傪柧傜偐偵帵偡傕偺偲側偭偰偄傞丅
丂戞堦偵丄壂撽偵偍偗傞擾嬈偺擔杮偵懳偡傞嵒摐丒僷僀儞嫙媼傪攠夘偲偟偨扨堦壔丄怉柉抧揑儌僲僇儖僠儏傾壔偼柧傜偐偱偁傞丅
丂戞擇偵丄乽暅婣乿偼丄壂撽偵擔杮惢昳傪斆棓偝偣丄擔杮帒杮偺彜昳巗応壔偑媫懍偵恑傔傜傟偰偒偨丅
丂戞嶰偵丄72擭埲崀丄埲慜偵傕傑偟偰媫懍側擔杮帒杮偺恑弌偲抧応帒杮偺宯楍壔傪恑傔偨偙偲傕柧敀偱偁傞丅
丂戞巐偵丄乽杮搚乿偵懳偡傞楯摥椡偺乽桝弌乿偵傛傝丄帺棫揑側宱嵪敪揥偺摦場偲偟偰偺婱廳側惗嶻彅梫慺傪憆幐偝偣傜傟傞偲偄偆怉柉抧揑峔憿偑側偍婎杮揑偵懕偄偰偄傞偙偲傕巜揈偱偒傞丅
丂壂撽偺怉柉抧壔偼丄擔杮崙壠傊偺暪崌偵傛偭偰懀恑偝傟丄僽儖僕儑傾摨尃偺榑棟偑偦傟傪崌棟壔偟偰偄傞偺偱偁傞丅壂撽偼丄擔杮崙壠偺堦晹偲偟偰慻傒擖傟傜傟傞偙偲傪捠偟偰怉柉抧壔忬懺偵堦憌嫮偔嬞敍偣傜傟偨丄傑偝偵崙撪怉柉抧側偺偱偁傞丅擔杮宱嵪偲壂撽宱嵪偺娫偵偼丄嵿惌傪彍偄偰崙柉宱嵪揑側桳婡揑愙崌惈偼懚嵼偣偢丄偁傞偺偼丄廬懏偲廂扗偲偄偆怉柉抧娭學偩偗側偺偱偁傞丅偙偺怉柉抧忬懺偺傕偲偱壂撽偼丄奜晹丄偡側傢偪擔杮偐傜丄堦曽揑偵宱嵪僔僗僥儉傪墴偟偮偗傜傟丄榗傫偩乽廬懏揑敪揥乿傪梋媀側偔偝傟傞廃曈揑帒杮庡媊偺搑傪嫮惂偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂妋偐偵丄壂撽偺掅奐敪惈偼楌慠偲偟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺掅奐敪惈偼丄岺嬈揑拞怱抧堟亖擔杮偺庡摫壓偱奐敪偑恑傔傜傟偨寢壥偲偟偰惗婲偟偨傕偺偱偁傝丄寛偟偰偦偺埲慜偐傜懚嵼偟偨傕偺偱偼側偄丅壂撽偼丄偐偮偰偼丄暷傪傎傏帺媼偟偊偰偍傝丄嵟弶偐傜崱擔偺傛偆側嵒摐乮媦傃僷僀儞乯偺儌僲僇儖僠儏傾偑懚嵼偟偰偄偨傢偗偱偼側偄偺偱偁傞丅
丂偩偑丄擔丒壂憃曽偵偍偄偰懡偔偺恖乆偼丄偙偺掅奐敪忬懺傪丄宱嵪揑掆懾丄偡側傢偪丄抶傟偲偟偰攃偊丄惌帯揑偵偼抶傟偐傜偺扙媝偲偟偰偺乽杮搚乿暲傒亖慶崙暅婣偑丄宱嵪揑偵偼奀梞攷摍戝宆僾儘僕僃僋僩傪壂撽奐敪偺婲敋嵻偲偡傞偛偲偒奜晹偐傜偺徴寕丄惉挿偺堏揮傪懳抲偟偰偒偨丅偟偐偟丄壂撽偺偙偺5擭偺尰幚偼丄偦偺傛偆側巚峫偵棤懪偪偝傟偨彅巤嶔傪攋嶻偝偣偰偒偨丅崱擔丄壂撽偵偍偄偰庡棳揑埵抲傪愯傔偰偄傞嵿惌帒嬥偵埶嫆偟偨暉巸偺搰傊偺揥朷傕傑偨丄婎杮揑偵偼丄奜晹巋寖丄惉挿偺堏揮巚峫偺垷庬偱偁傝丄寛偟偰壂撽偺帺棫揑宱嵪敪揥傪傕偨傜偡傕偺偲偼側傝偊側偄偺偱偁傞丅
丂傑偝偵丄偙偺5擭娫丄壂撽偑宱尡偣偞傞傪偊側偐偭偨傕偺偼丄乽宱嵪惉挿偼恑傓偑丄宱嵪偺拞怱抧堟傊偺廬懏惈偼媝偭偰恑傔丄帺棩揑敪揥傪傑偡傑偡崲擄偵偝偣傞乿偲偄偆乽掅奐敪偺敪揥乿乮A丒G丒僼儔儞僋乯偱偁偭偨偲尵偊傞丅偟偐傜偽丄偦偺撍偒偮偗傞栤戣偲偼丄扨側傞乽怳嫽奐敪寁夋乿偺尒捈偟傗丄傑偟偰傗庤捈偟偱嵪傓偼偢傕側偔丄乽奐敪乿棟榑偺曽朄偦偺傕偺偺嵞専摙偲斸敾偵棤懪偪偝傟偨丄壂撽恖柉偺塨抭偺偡傋偰傪廤拞偟偨撈帺偺乽奐敪乿寁夋丄偡側傢偪丄杮幙揑偵偼帺慜偺壂撽揑嬤戙偺揥朷偱偁傠偆丅
丂偙偆偟偨娤揰偵偨偮偲偒丄彅乆偺帺棫宱嵪榑偼丄偄偐側傞埵抲傪愯傔傞傕偺偱偁傠偆偐丠丂偙傟偑師復偱専摙偝傟側偔偰偼側傜側偄丅
戞擇復丂帺棫宱嵪彅榑傊偺帇揰
侾丄 怴怉柉抧庡媊偺奐敪榑
丂乽朙偐側壂撽乿丄乽壂撽帺棫宱嵪偺帺棫揑敪揥乿傪鎼偭偨壂撽怳嫽奐敪寁夋偑丄偡偱偵5擭偵偟偰乽敀擔偺柌乿偲壔偟偨偲偄偆偙偲偼丄偦偺奐敪寁夋傪巟偊偨壂撽奐敪棟榑傊偺斸敾傪昁梫偲偟偰偄傞丅
丂偦偙偱丄彅乆偺帺棫宱嵪榑傪専摙偡傞偵偁偨偭偰傑偢戞堦偵亀壂撽偺宱嵪奐敪亁乮1970擭丄埳摗慞堦丒嶁杮擇榊嫟曇丄挭怴彂乯傪偲傝偁偘傞偙偲偲偡傞丅偙傟偼堦岥偱尵偭偰丄嵟傕揟宆揑側怴怉柉抧庡媊偺乮壂撽乯宱嵪奐敪榑偱偁傞丅
丂挊幰払偺壂撽宱嵪奐敪偺婎杮揑側巙岦偼丄摉慠側偑傜岺嬈壔傪婎幉偲偡傞乽掅奐敪乿乗乗乽恖岺塰梴偺宱嵪乿乮戝棃嵅晲榊乯寳偐傜偺乽嬤戙壔乿揑奐敪偱偁傞丅偦偺嵺偺婎杮揑帇揰乗乗擣幆偼丄壂撽偼乽擔杮楍搰偺嵟撿抂偵偁傞偲偄偆擣幆傪傗傔偰壂撽偲偔偵撨攅偑搶撿傾僕傾偺愴棯揑嫆揰乿丄偮傑傝乽撿曽宱嵪寳偺嫆揰乿偵偁傞偲偄偆娤揰偵偨偮偙偲偱偁傞偲尵偆丅偙偙偐傜乽壂撽奐敪偺愴棯乿偲偟偰偺乽壂撽儊僈儘億儕僗偺憂憿乿乮埳摗慞堦乯偑寢榑偯偗傜傟傞丅
丂偦偺撪梕偼丄岺嬈婎抧壔偲崙嵺娤岝抧壔偺擇偮偱偁傞丅戞堦偺岺嬈婎抧壔偲偼丄擔杮傊偺愇桘嫙媼傪幉偵丄愇桘乗傾儖儈岺嬈傪婎姴偵偟偨娭楢彅岺嬈傪憂弌偟堦戝岺嬈抍抧傪宍惉偟傛偆偲偡傞偙偲偱偁傝丄傑偨丄戞擇偺崙嵺娤岝抧壔偲偼丄乽擔杮偺僴儚僀乿傪傔偞偟偰娤岝嶻嬈傪怳嫽偝偣傞偙偲偱偁傞丅偙偺拞偱丄撨攅傪拞怱偵丄巺枮偐傜愇愳偵帄傞搒巗傪崅懍揝摴丒崅懍摴楬偱寢傃丄帠幚忋恖岥70枩恖傪曪愛偡傞壂撽儊僈儘億儕僗乮嫄戝搒巗乯傪宍惉偟傛偆偲偡傞丅偙偺傛偆側岺嬈壔偲搒巗壔偑偦偺愴棯偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側乽嫆揰壔乿榑丒奐敪榑偑壂撽宱嵪偺帺棫側傝丄恑曕偵壗傜偮側偑傞傕偺偱側偐偭偨偙偲偼丄愭偵弎傋偨暅婣5擭偺壂撽宱嵪偺尰幚傪傒傟偽柧傜偐偱偁傞丅愇桘婎抧偼丄擔杮偵偲偭偰偺愇桘旛拁婎抧偱偼偁偭偰傕丄壂撽宱嵪偵偼屬梡岠壥傕娭楢彅婇嬈岠壥傕惗傒弌偝偢丄壂撽恖柉偵懳偟偰壗傜偺儊儕僢僩傕惗傒弌偝側偐偭偨丅媡偵丄擾柉偐傜搚抧偲奀傪扗偄丄岞奞傪傑偒偪傜偟偨偩偗偱偁傞丅懠曽丄奀梞攷傪宊婡偲偟偨娤岝奐敪傕搳婡揑側娤岝嬈幰偵傛傞棎奐敪偲丄偦偺寢壥偲偟偰偺夁戝搳帒偵傛傞搢嶻傪傕偨傜偟偨偩偗偱偁傞丅偙偆偟偨壂撽宱嵪偺峔憿偼丄傓偟傠媡偵擔杮宱嵪傊偺廬懏惈傪傑偡傑偡嫮傔偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
丂偱偼丄偙偺傛偆側乽嫆揰壔乿榑丄壂撽宱嵪奐敪榑偼乽枹棃妛幰乿嶁杮擇榊偺乽枹棃妛乿揑敀擔柌偲偟偰婛偵徚偟偲傫偱偟傑偭偨偲尵偊傞偱偁傠偆偐丠丂寛偟偰偦偆偱偼側偄丅嶁杮擇榊偺乽嶰偮偺慖戰乿乮孯帠婎抧偺摴丄幮夛曐忈偺搰傊偺摴丄幚尡偺搰偺摴乯偺戞嶰丄乽幚尡偺搰偺摴乿偲偟偰尰幚偺壂撽偼埵抲晅偗傜傟偰偄傞偲尵偊傛偆丅偙偺摴偼丄乽堦晹孯帠婎抧傪傕偪側偑傜傕丄偟偐偟孯帠婎抧偵傛偭偰惗偒傞偺偱偼側偔丄孯帠婎抧傛傝埲奜偺傕偺偵傛偭偰惗偒傛偆偲偡傞乿摴偱偁傝丄乽懳奜娭學偺拞宲婎抧偲偟偰怴偟偄傕偺傪愗傝戱偄偰偄偔偲偄偆摴乿偱偁傞丅乽堦晹孯帠婎抧乿偳偙傠偐丄傎偲傫偳孯帠婎抧偼揚嫀偝傟偢乗乗場傒偵丄挊幰払偼乽徍榓41擭4寧偵丄搶嫗戝妛偑峴偭偨悽榑挷嵏偺寢壥偱偼丄乧乧亀暷孯偺偄傞偙偲偑宱嵪偺岦忋偵栶棫偭偰偄傞亁偲擣傔傞傕偺偑67亾傕偁傞丅偙偆偟偨摦偐偟偑偨偄帠幚傪廳帇偟側偗傟偽側傜偸丅乧乧婎抧揚嫀偼朷傑偟偄傕偺偱偁傞偑丄偦偺僞僀儉丒僗働僕儏乕儖傪岆傑傞偲丄宱嵪丒幮夛柺偱戝崿棎偑惗偢傞乿偲偄偆娤揰偐傜丄孯帠婎抧偺宱嵪揑栶妱傪峬掕偟偰偄傞偑丄尰幚偼孯帠婎抧偩偗偑巆傝丄宱嵪揑栶妱偼慡偔側偔側偭偰偄傞偺偱偁傞丅孯楯摥幰偺戝検夝屬傪傒傛両乗乗丄CTS寶愝偼嫮峴偝傟丄尨敪愝抲偺惡偡傜忋偑偭偰偄傞尰忬偼丄乽幚尡偺搰乿偑尩慠偲惗偒偰偄傞偙偲偺徹柧偱偁傞丅
丂偟偐傕丄偙偺乽幚尡偺搰乿偲偄偆埵抲偯偗偼惌帯揑偵偼丄乽傢傟傢傟偼壂撽奐敪偲偄偆執戝側傞幚尡偑丄搶撿傾僕傾奐敪偵懳偡傞擔杮偺擬堄偲擻椡傪僥僗僩偡傞廳戝側堄枴傪傕偮傕偺偱偁傞偲峫偊傞丅壂撽奐敪偺偨傔偺旓梡偼丄偮偯偄偰揥奐偝傟傞偱偁傠偆搶撿傾僕傾偵懳偡傞墖彆寁夋偺偨傔偺尋媶旓側偄偟挷嵏旓偱偁傞偲峫偊傞傋偒偱偁傝丄偙傟偐傜摼傜傟偨庬乆偺嫵孭傗僨乕僞偼丄悽奅偵傓偐偭偰奐偐傟傞傋偒惈幙偺傕偺偱偁傞乿偲偄偆丄暥帤捠傝擔杮掗崙庡媊偺傾僕傾巟攝偺堦娐偲偄偆娤揰偱攃偊傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲偑廳戝偱偁傞丅
丂柧傜偐偵亀壂撽偺宱嵪奐敪亁偺棫応偼丄擔杮惌晎偺嵿惌墖彆偲擔杮帒杮偵傛傞岺嬈壔傪捠偟偰丄壂撽傪乽崙撪怉柉抧乿壔偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傝丄壂撽宱嵪傪丄擔杮帒杮庡媊傊偺廬懏惈傪怺傔偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄乽廃曈揑丒廬懏揑乿宱嵪峔憿偵棷傑傝懕偗傞偲偄偆峔憿傪懀恑偡傞傕偺偱偟偐側偄丅偦偺壂撽恖柉偵懳偡傞斀恖柉惈偑丄偙偺5擭娫偺壂撽宱嵪偺幚忣偲偟偰業掓偟偰偒偰偄傞偺偱偁傞丅
俀丄乽妚怴乿偺宱嵪奐敪榑
丂偙傟偵懳偟丄偄傢備傞乽妚怴乿偺懁偐傜偡傞乽壂撽宱嵪奐敪乿榑偑偁傞丅椺偊偽媨杮寷堦偺乽壂撽偺抧堟奐敪傪峫偊傞乿乮娾攇怴彂亀抧堟奐敪偼偙傟偱傛偄偺偐亁強廂乯丄壂嫵慻宱嵪尋媶埾堳夛偺亀奐敪偲帺帯亁乮擔杮昡榑幮乯摍偱偁傞丅
丂偙傟偼丄乽婎抧揚嫀乿丄乽岞奞偺側偄嶻嬈乿丄乽抧曽帺帯尃偺奼戝乿摍丄惌帯揑偵偼愭偺奐敪榑偲懳嬌偵偨偮傕偺偱偁傞丅偲偙傠偑丄偙傟偑壥偟偰怴怉柉抧庡媊揑側壂撽宱嵪奐敪榑偺攋抅傪恀偵斸敾偟丄崕暈偟偊傞傕偺偱偁傞偐偵偮偄偰偼偒傢傔偰媈栤偱偁傞丅埲壓丄亀奐敪偲帺帯亁偺庡挘偵懃偟偰庒姳偺栤戣傪採婲偟偰偄偒偨偄丅
丂榑揰偺戞堦偼丄壂撽曉娨偲帺帯尃扗夞偺昁慠惈偲偄偆栤戣偱偁傞丅徏揷夑岶巵乮杮彂尋媶埾堳挿乯偼丄乽壂撽曉娨偺堄枴偡傞傕偺乿傪堦曽偱丄僪儖懱惂偺曵夡仺擔杮傊偺尐戙傢傝丄偍傛傃傾僕傾埨曐偺惌帯丒孯帠揑堐帩丄嫮壔乮擔杮偺孯帠戝崙壔乯偵媮傔丄懠曽壂撽恖柉偺懁偵偍偄偰偼乽戞嶰偺棶媴張暘乿丄乽廧柉偺堄巙傪壗傜夘偡傞偙偲側偔丄奜揑尃椡偵傛偭偰堦曽揑丄嫮惂揑偵側偝傟偨乿傕偺偲偟偰攃偊傞丅傑偨丄徏揷巵偼曉娨夁掱偵偍偗傞壂撽廧柉偺堄巙偼暅婣塣摦偲偟偰昞尰偝傟偨偑丄偦偺棟擮偼72擭曉娨偵傛偭偰偼幚尰偝傟側偐偭偨偲丄72擭曉娨偺尷奅傪巜揈偡傞丅偮傑傝丄暅婣塣摦偺拞怱棟擮偼乽傾儊儕僇偺孯帠巟攝偐傜扙偟偰乮擔杮偺乯暯榓寷朄偺壓偵暅婣偡傞乿偙偲偵偁偭偨偑丄尰幚偺曉娨夁掱偼丄愭偵弎傋偨傛偆側撪梕偱偁傝丄偙偺棟擮偑宍奫壔偝傟丄棤愗傜傟偰偄偔夁掱偱偁偭偨丅偙偺揰偱乽斀暅婣乿偺巚憐偑忳惉偝傟偨偺傕摉慠偱偁偭偨丄偲偄偆丅偐偔偟偰丄徏揷巵偼丄暅婣屻偺暅婣塣摦偼乽帺帯尃扗夞乿偺塣摦傊偲曄傢傞丄偲偄偆偺偱偁傞丅
丂偟偐偟側偑傜丄偙偙偱偼擇偮偺栤戣偑偁傞丅戞堦偼乽戞嶰偺棶媴張暘乿偲尵偄偮偮傕丄72擭曉娨偺杮幙偑攃偊傜傟偰偄側偄偙偲偱偁傞丅廧柉偺堄巙傪壗傜夘偡傞偙偲側偔擔杮崙壠偺崙嫬嵞曇偑72擭曉娨嫤掕偵偍偄偰峴傢傟偰偄傞偙偲偵懳偡傞壂撽廧柉偐傜偺尨懃揑斸敾偑崬傔傜傟偨攃埇偑栤傢傟偰偄傞偺偱偁傞丅偮傑傝乽暪崌乿偲偄偆婯掕偱偁傞丅戞擇偼丄乽帺帯尃扗夞傊両乿偺嬻榑惈偲偄偆偙偲偱偁傞丅乽暯榓寷朄壓傊偺暅婣乿偑棤愗傜傟偨偲偡傟偽丄偦偺寷朄戞8復抧曽帺帯傊偺棟擮偑棤愗傜傟側偄曐忈偼側偄丅偐偔偰巵偺乽戞嶰偺棶媴張暘乿亅亅乽帺帯尃扗夞乿偲偄偆棫榑偼丄暪崌亅亅壂撽廧柉偺撈帺偺幮夛揑宱嵪揑撈帺惈偲偟偰偺壂撽恖柉偺帺寛尃偲偟偰撍偒偮傔傜傟側偔偰偼側傜側偄偺偱偁傞丅
丂榑揰偺戞擇偼丄擔杮惌晎偺奐敪惌嶔偵懳偡傞抧曽帺帯偺暅尃偲偄偆攃埇偱偁傞丅徏揷巵偼壂撽宱嵪奐敪偺尰忬傪擔杮帒杮庡媊偺楌巎揑懱幙丄尷奅偺栤戣偲偟偰愢偔丅擔杮偺柧帯埲棃偺奐敪惌嶔偼丄崙偲撈愯偲偺乽崿崌宱嵪乿揑奐敪偱偁傝丄偦傟偼懄乽擾柉愗傝幪偰乿岺嬈壔丄偍傛傃抧曽帺帯偺晄嵼偺夁掱偱偁偭偨丅愴屻傕帒杮偺偨傔偺惌嶔乗乗怴慡憤丄楍搰夵憿榑丄怴崙搚憤崌奐敪朄摍乗乗偑惌晎偵傛偭偰悇恑偝傟丄廧柉丄崙柉偺暉巸偼媇惖偵偝傟偰偒偨丅偦偺寢壥丄壂撽宱嵪偼愇桘婎抧偲岞奞丄僀儞僼儗丄揱摑岺寍偺攋夡丄奀梞攷偺棎奐敪摍丄姰慡偵攋夡偝傟丄擔杮帒杮偺帒杮桪埵偺奐敪偑岞慠壔偝傟傞傛偆偵側偭偨丅偙偺偙偲偼丄偁傞堄枴偱偼丄乽乬堎柉懓偵傛傞巟攝乭傛傝傕乬摨柉懓偵傛傞巟攝乭偺傎偆偑丄偼傞偐偵怺崗偱巆擡偱偁傞乿丅偙偆偟偰徏揷巵偼丄擔杮宱嵪偺奐敪惌嶔亖嶻嬈廤拞壔偲漢峈偡傞偺偼帺帯尃偺奼戝偵傛傞偟偐側偔丄偙傟偙偦乽壂撽偺怱乿偱偁傝乽壂撽偺柦乿側偺偱偁傞偲尵偆丅
丂偙偺傛偆側乬廧柉暉巸傪媇惖偵偡傞奐敪惌嶔乭仼仺廧柉暉巸亖廧柉帺帯偲偄偆敪憐偼丄擔杮偺妚怴帺帯懱偵偍偗傞堦斒揑尒夝偱傕偁傞丅偟偐偟側偑傜丄73擭愇桘僔儑僢僋埲棃偺晄嫷偺拞偱偙傟偑戝偒偔攋抅偟偰偒偰偄傞偙偲傕帠幚偱偁傞丅偦傟偼丄妚怴帺帯懱偑懡條側宍懺傪偲傝側偑傜傕丄崅搙宱嵪惉挿壓偺帒杮偵傛傞抧堟棎奐敪偺柕弬傪僥僐偵惉棫偟丄帺傜偺嶻嬈乗乗宱嵪惌嶔傪懱宯揑偵傕偪偊側偄偐傜偱偁偭偨丅宱嵪傪摦偐偡偺偼帒杮偱偁傝丄偦偺柕弬傪娚榓偡傞偺偑抧曽帺帯懱偲偄偆娭學傪曄妚偟偊側偄偺偱偁傞丅偟偐傕擔杮偺帺帯懱偼丄偦傕偦傕忋偐傜丄姱惢揑偵偮偔傜傟偨傕偺偱偁傝丄撈帺偺嶻嬈乗乗宱嵪懱宯傪庡懱揑偵憂弌偡傞楌巎揑忦審傪桳偟偰偄側偄偺偱偁傞丅
丂恀偺抧曽帺帯偼丄廧柉帺恎偺帺屓寛掕乗乗傑偝偵徏揷巵偺偄偆乽抧堟廧柉帺恎偑傒偢偐傜偺帺桼堄巙偵傛偭偰傒偢偐傜傪帯傔傞乿偲偄偆乗乗偺塣摦亖恖柉帺帯偺塣摦偵傛偭偰偟偐惉棫偟偊側偄丅偙偙偱弶傔偰帒杮偺榑棟偼僠僃僢僋偝傟傞偩偗側偔丄斲掕偝傟傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傞丅偲偡傟偽丄乬廧柉暉巸傪媇惖偲偡傞奐敪惌嶔乭偲偄偆尵偄曽偼乬廧柉帺帯傪媇惖偲偡傞奐敪惌嶔乭偲尵偄偐偊傜傟傞傋偒偱偁傝丄徏揷巵偑丄乽摿偵壂撽偺応崌丄偦偺廧柉暉巸偼扨偵乬杮搚暲傒強摼悈弨乭偩偗偱夝寛偑偼偐傜傟傞傋偒偱偼側偄乿偲尵偆偺傕丄偙偺傛偆側娤揰偵棫偭偨偲偒偵桞堦丄偦偺曽岦偑柧傜偐偲側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂戞嶰偺榑揰偼丄偱偼偙偺傛偆側廧柉暉巸亖廧柉帺帯偲壂撽帺棫宱嵪偲偼偳偺傛偆側娭楢偵偁傞偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅杮彂偱偼丄帺棫宱嵪偲偼丄乽婎抧埶懚宱嵪乿乗乗乽奜晹埶懚偺徚旓宱嵪乿偐傜偺扙媝傪丄岺嬈奐敪桪惈庡媊偱偼側偔丄廧柉嶲壛傪婎挷偵偟偰峴偆偙偲偲婯掕偟丄師偺傛偆側惌嶔傪採婲偟偰偄傞丅嘆擾嬈偼偝偲偆偒傃壙奿堷忋偘傪拞怱偵偟偨惌嶔丄嘇惢憿嬈偼丄慡懱揑宱塩婯柾奼戝傪婎杮偲偟丄桳婡揑丄懡條側楢娭傪傕偭偨嶻嬈峔憿傊偺揮姺丄嘊娤岝奐敪偼廧柉庡懱偺傕偺傊丄嘋帺帯懱傪惗妶娐嫬惍旛桪愭庡媊偵揮姺偝偣傞丄嘍廧柉怰嵏惂偵傛傞娐嫬丄岞奞僠僃僢僋摍偱偁傞丅
丂偙偺帺棫宱嵪榑偼丄寢嬊偺偲偙傠帺帯懱乮導乯傪偳偆摦偐偡偐偵嵟戝偺椡揰偑偍偐傟偰偄傞丅偦偺巚憐揑婎慴偲側偭偰偄傞偺偼乬僔價儖丒儈僯儅儉乭偺巚憐偱偁傞丅僔價儖丒儈僯儅儉偲偼丄乽偡傋偰偺巗柉偑偦偺抧堟偵偍偄偰嬤戙揑惗妶傪憲傞偆偊偱昁梫偲偝傟丄偐偮尃棙偲偟偰曐忈偝傟傞傋偒嵟掅尷偺惗妶悈弨乿偲偟偰攃偊傜傟丄偦偺婎杮棟擮偼丄寷朄25忦偺惗懚尃偺曐忈偐傜摫偒弌偝傟偰偄傞丅偙傟偵偮偄偰擇揰傎偳栤戣傪巜揈偡傞偙偲偑偱偒傞丅戞堦偼丄乽柉庡揑乿帺帯懱乮妚怴帺帯懱乯偲偄偊偳傕帺帯懱亖崙壠尃椡偺堦暘巬偱偁傝丄恖柉側偄偟廧柉帺帯丄帺屓摑帯偺栤戣偲偼暿屄偺栤戣偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄戞擇偼僔價儖丒儈僯儅儉偲尵偭偨応崌丄偱偼壂撽恖柉偵偲偭偰偺僔價儖丒儈僯儅儉偲偼壗偐丄偲偄偆栤戣偱偁傞丅
丂偲傝傢偗丄壂撽恖柉偵偲偭偰偺僔價儖丒儈僯儅儉偲偵偮偄偰偼寢嬊偺偲偙傠杮彂偱偼慡偔柧傜偐偵側傜側偄丅徏揷巵偑斸敾偟偨乬杮搚暲傒偺強摼悈弨乭偲偳偆堘偆偺偐丠丂戞堦偺栤戣偲傕娭楢偡傞偑丄偮傑傝偙偺偙偲偼丄宱嵪帺棫偲偄偆帪偺庡懱偑晄柧妋偱偁傞偲偄偆偙偲偵桼棃偟偰偄傞偺偱偁傞丅帺帯懱丄帺帯尃傪棟擮揑偵慬掕偟丄偦偙偵寷朄25忦偺棟擮偐傜僔價儖丒儈僯儅儉偺巚憐傪傕偪弌偟偰偒偰傕丄尰幚偵壂撽偺幮夛揑宱嵪揑庡懱偵偲偭偰偺帺屓敪揥偺婳摴偑偳偙偵偁傞偺偐傪妋掕偟偊側偄丅杮彂偵宱嵪帺棫榑偑丄擔杮宱嵪偲偺娭學偵偍偄偰壂撽宱嵪偺乽廃曈揑丒廬懏揑乿惈奿傪壗傜攃偊傜傟側偄偺傕偙偙偵尨場偑偁傞偲尵偆偙偲偑偱偒傞丅
俁丄庤偞傢傝偺帺棫宱嵪榑
丂師偵専摙偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄偁傞堄枴偱偼嵟傕壂撽揑側乬庤偞傢傝偺帺棫宱嵪榑乭偲偱傕尵偆傋偒乽柤岇巗婎杮峔憐乿傪幉偵偟偨曽岦惈偱偁傞丅偙偺曽岦惈偼丄慜擇幰偑嬋偑傝側傝偵傕慡壂撽揑帇揰偵棫偭偰偦偺宱嵪妶摦傪榑偠偰偄傞偺偲堎側偭偰乬抧堟乭乮婎杮揑偵偼巗挰懞椞堟乯偵嫆偭偰偦偺宱嵪妶摦傪榑偢傞丅偄傢備傞乬抧堟庡媊乭揑帺棫宱嵪榑偱偁傞丅乽柤岇巗婎杮峔憐乿乮埲壓乽柤岇僾儔儞乿偲徧偡乯偺偦傟偼柤岇巗乗乗杒晹乮崙摢乯偺抧堟庡媊偲偟偰尰傢傟偰偄傞丅
丂抧堟庡媊偲偄偭偨応崌丄偦傟偼宱嵪揑偲偄偆傛傝惌帯揑側奣擮偱偁傠偆丅帠幚丄乽柤岇僾儔儞乿偼擇偮偺巚憐揑潣_揑懁柺偑廳側傝崌偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅戞堦偵丄偄傢偽乽嫟摨懱拞怱庡媊乿偲傕尵偆傕偺偱偁傝丄壂撽撈摿偺懞棊嫟摨懱偺懚嵼傪傕偭偰乽僾儔儞乿偺妀怱偲偟偰偄傞偙偲丄戞擇偵丄斀拞墰偺巙岦乮偙偺応崌偺乽拞墰乿偲偼撨攅丄乽導乿摉嬊丄偦偺乽怳嫽奐敪寁夋乿傪巜偦偆乯丄偦傟傪巟偊傞屄桳尃榑揑帺帯亖抧堟暘尃庡媊偺偲傜偊曽偑偁傞偲巚傢傟傞丅偙偺擇偮偺廳側傝崌偄偙偦丄乽柤岇僾儔儞乿偺堄媊偲庛揰偺憃曽傪塮偟弌偡傕偺偲側偭偰偄傞丅
丂乽柤岇僾儔儞乿偼丄壂撽撈帺偺嫟摨懱乮嬶懱揑偵偼柤岇抧堟偺帺慠揑丒揱摑揑嫟摨懱乯偺忋偵棫偪偮偮撈帺偺擾嬈乮戞堦師嶻嬈乯宱嵪嵞寶傪攠夘偵偟偨抧堟娐嫬o嵪榑偱偁傞丅偦傟偼丄堦曽偱嬤戙壔擾嬈斸敾偲偦傟傊偺懳抲乗乗椺偊偽丄奜晹埶懚偺宱嵪楬慄丒寁夋傊偺斸敾丄嬤戙壔擾惌傊偺斸敾丄擾嬈丒擾懞偺尰忬斸敾偲偙傟偵懳偡傞擾丒嫏嬈乗乗抧応嶻嬈傊偺埶嫆丄桳婡擾嬈偺嵞寶乮廤栺壔丒暋崌壔乯擾懞偺朙偐偝乮嫟摨惈丄嫟摨巤愝乯偺尒捈偟丄摍乆偺棟榑揑採婲乗乗傪慜採偵偟偮偮丄懠曽偱丄偒傢傔偰嬶懱揑側抧堟宱嵪峔抸偺曽嶔乗乗塩擾曽幃丄惗嶻亅棳捠偺婡峔榑乗乗傪採埬偡傞丅偦偺拰偼丄嘆椫嶌丒峩抺寢崌丒搚偯偔傝偵傛傞偲偙傠偺暋崌擾嬈偺峔抸丄嘇擾壠偺暋崌宱塩偺廤棊扨埵偺廤棊擾嬈偲偟偰偺慻怐壔丄嘊寭嬈栤戣偺暃嬈丄乬埨怱寭嬈乭偲偟偰偺夝寛丅嘋帺庡揑抧堟揑側棳捠婡峔偺寶愝丄偺巐揰偱偁傞丅
丂壂撽乮柤岇乯偺撈摿側嫟摨懱偵棫偮偲偄偆堄枴偱偼丄巐偮偺拰偺偆偪嘇偑嵟戝偺栤戣偱偁傠偆丅偮傑傝丄嘇偺偄偐傫偑嘆傪幚峴偟偆傞楯摥椡傪曐忈偡傞娭學偲側偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅暋崌擾嬈偼楯摥椡偺堦憌偺廤栺揑搳擖傪梫惪偡傞偨傔偵丄偙偺廤栺揑搳擖傪曐忈偟丄奺擾壠偺暋崌宱塩傪惉棫偝偣傞偩偗偺嫟摨懱揑側嫤摥傪慻怐偟偆傞偐斲偐丄偙偙偵乽柤岇僾儔儞乿偺惉斲偺偡傋偰偑偐偐偭偰偄傞偺偱偁傞丅乽嫟摨懱拞怱庡媊乿偼丄偙偺傛偆偵嬶懱壔偝傟傞偑丄偙傟傪扴偆庡懱偺僄乕僩僗偲栚揑偼偳偺傛偆側傕偺偱偁傠偆偐丠摉慠丄乽柤岇僾儔儞乿偺僾儔儞僫乕偨傞搒巗寁夋丒愝寁幰偺偦傟偱偼側偄偙偲偼尵偆傑偱傕側偔柧傜偐偱偁傞丅
丂幚偼丄偙偺庡懱偺僄乕僩僗偑偳傟傎偳壂撽乮柤岇乯偺嫟摨懱堄幆偐傜偺拪弌暔偲偟偰攃埇偝傟偰偄傞偐偑壂撽揑乽嫟摨懱庡媊乿偺梫偱偁傠偆丅偙偺揰偼丄傗偼傝丄抧堟庡媊偺榞慻傒偲偺娭學傪尩枾偵専摙偟側偔偰偼妋掕偱偒側偄偲巚傢傟傞丅擔杮偺抧堟庡媊偼丄戝偒偔擇偮偺孹岦偵暘偗傜傟傞丅堦偮偼丄帺帯懱拞怱偺暘尃庡媊偱偁傝丄傕偆堦偮偼丄廧柉帺恎偺抧堟暘尃庡媊偱偁傞丅慜幰偼丄壂撽偵偍偄偰偼妚怴帺帯懱偺婡擻嫮壔傪庡挘偡傞徏揷夑岶巵揑側寷朄揑暘尃庡媊偲偟偰偁傞丅偦傟偑僔價儖丒儈僯儅儉捛媮塣摦傪捠偠偨妚怴帺帯懱嫮壔榑偱偟偐側偄偙偲偼偡偱偵弎傋偨丅
丂栤戣偼屻幰偱偁傞丅偦偺戙昞揑庡挘偼丄乽柤岇僾儔儞乿偺僾儔儞僫乕払偲傕恊偟偄偲尵傢傟傞悪壀愖晇巵偺乽抧堟暘尃庡媊乿偱偁傞丅懞壀巵偺強愢偺摿挜偼丄嘆崅搙惉挿偱峴偒偡偓偨幮夛宱嵪塣塩偺拞悤娗棟懱惂偺暘尃壔丄嘇暘尃壔傪捠偟偨尰戙偺媄弍懱宯偲慻怐懱偺偮偒偔偢偟丄嘊抧堟廧柉偺惗妶曄妚亖暥壔妚柦偲偟偰偺抧堟庡媊丄偲偄偆揰偵偁傞乮亀抧堟庡媊偺偡偡傔亁1976擭乯丅悪壀巵偺庡挘偼丄崅搙岺嬈幮夛擔杮亖娗棟乮夋堦壔乯幮夛斸敾偲偟偰偺抧堟庡媊偵妀怱偑偁傝丄偦偺尷傝偱帺棫偟偨抧堟宱嵪乗乗廧柉帺帯傪栚偞偡傕偺偱偁傞丅壂撽偺抧堟庡媊傕偙偺堦娐偱偁傝丄娗棟幮夛斸敾偲偟偰柧妋偵埵抲偯偗傜傟偰偄傞丅
丂偙偺傛偆側抧堟暘尃庡媊偼丄壂撽揑乽嫟摨懱拞怱庡媊乿傪擔杮偵偍偗傞斀娗棟幮夛丄斀嬤戙偺堦娧偲昡壙偡傞偨傔偵丄壂撽揑乽嫟摨懱拞怱庡媊乿傪扴偆庡懱偺僄乕僩僗傊偲怺偔暘偗擖傝偊側偄偺偱偁傞丅偦傟偼斀擔杮娗棟幮夛亅斀擔杮嬤戙偺掞峈懱偲偟偰偺壂撽揑乽嫟摨懱拞怱庡媊乿偺堄媊偑摍娬偵晅偝傟傞偙偲偱傕偁傞丅偐偔偰丄乽柤岇僾儔儞乿偺抧堟庡媊偼丄壂撽揑乽嫟摨懱拞怱庡媊乿偲壂撽宱嵪偺娭學傪柧傜偐偵偡傞偙偲側偟偵偼丄悪壀巵偺乽抧堟暘尃庡媊乿偲摍幃偱寢偽傟傞偙偲偼昁掕偱偁傠偆丅
丂尰怳嫽奐敪寁夋偑攋抅偟偰偄傞偲偟偨傜丄奺抧堟偼偄偐側傞曽岦惈偵偍偄偰宱嵪帺棫傪揥朷偡傋偒偐丄奜晹埶懚偑傛偔側偄偲偟偨傜丄擔杮宱嵪偲偺娭學偼偄偐偵峫偊傞傋偒偐丄偦偙偵偍偄偰乽柤岇僾儔儞乿偺曽岦惈偑偄偐偵帺恎偺抧堟宱嵪榑偺彅慜採傪揥奐偟偆傞偐丄偙傟偑栤傢傟偰偄傞丅
係丄嬤戙帒杮庡媊偲偟偰偺帺棫壂撽宱嵪榑
丂擔杮宱嵪偲偺娭學傪懳徾壔偟偮偮壂撽宱嵪偺乽敪揥乿傪偲傜偊傞傕偺偲偟偰偼丄偄傢備傞杚栰榑暥偑専摙偵抣偟傛偆丅乽庡栶晄嵼偺宱嵪奐敪乿偲乽怳傝弌偟偵栠偭偨壂撽宱嵪乿乮亀嬥梈宱嵪亁182丄185崋強廂乯偱偁傞丅杚栰峗棽巵偺棫応偼丄偄傢備傞嬤戙壔榑偱偁傞偑丄偦傟偼柧妋偵丄屻恑崙宱嵪寳壂撽傪偄偐偵嫮椡側嬤戙帒杮庡媊壂撽傊偲敪揥偝偣傞偐傪榑偠偨傕偺偱偁傞丅
丂杚栰榑暥傪堦娧偟偰偄傞惛恄偼丄偄傢偽乬壂撽僽儖僕儑傾僕乕偺儖僱僢僒儞僗偺嫨傃乭偲偱傕尵偆傋偒傕偺偱偁傞丅杚栰巵偼丄暅婣屲擭傪宱偰偺壂撽宱嵪偺攋嶻傪傑偢巜揈偟丄怳嫽奐敪寁夋偺尷奅傪師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅偡側傢偪丄壂撽宱嵪偺崿棎偺嵟戝偺尨場偼丄乽宱嵪奐敪偺庡栶偼帠嬈懱亖婇嬈偺扴偄庤偱偁傞偲偄偆柦戣偵懳偡傞擣幆寚擛偲庡栶晄嵼偺帠幚乿偵偁傝丄偙偺乽婇嬈幰妶摦偺扴偄庤亖奐敪偺庡懱乿偵偮偄偰偺嫟捠擣幆側偟偵偼帺棫宱嵪奐敪偼偁傝偊側偄偲丅偙傟偼丄帒杮庡媊憪憂婜偺帒杮壠惛恄亖僄乕僩僗偺傒側傜偢丄戞嶰悽奅偺宱嵪奐敪榑偺憤妵乗乗捓嬥墖彆傗媄弍摫擖偺傒偵傛偭偰岺嬈壔傪偼偐傠偆偲偟偨楬慄偼幐攕偟丄傓偟傠岺嬈壔傪巟偊椞摫偡傞婇嬈幰惛恄傗婇嬈幰擻椡偺栤戣偑梫偲側傞丄偲偄偆乗乗傪傕摜傑偊丄偦偺帇揰丒曽朄傪壂撽宱嵪奐敪榑偵揔梡偟傛偆偲偟偨傕偺偱偁傞丅
丂巵偼丄偙傟傑偱偺壂撽宱嵪偺憤妵傪丄扴偄庤帺恎偺栤戣偲偦偺惌帯丄宱嵪堄幆偺寛掕揑尷奅偲偟偰妳攋偡傞丅偦偺斸敾偼嬌傔偰捝楏偱偁傞丅傑偢丄壂撽宱嵪偺戞嶰師嶻嬈曃廳偲偼抧尦帒杮偑桝擖丄斕攧偵愱擮偡傞乽彜嬈帒杮乿偲偟偰惗惉偝傟偨偙偲偵傕偲偯偔傕偺偱偁傝丄偙偺乽彜嬈帒杮乿偼宱嵪奐敪偵偼栶棫偨側偄偲尵偆丅乽彜嬈帒杮乿庡摫偱偼撈帺側嵞惗嶻峔憿偺峔抸傕桳岠廀梫惌嶔傕岠椡傪傕偨側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅傑偨丄戞擇師嶻嬈亖嶻嬈帒杮偼丄壂撽宱嵪偑婎杮揑偵偼乽彜嬈帒杮乿壔傪懀恑偡傞帺桼杅堈惂搙偺忋偵惉棫偟偰偒偨偑屘偵丄堟撪巗応偺傒傪懳徾偲偟偨僒乕價僗揑丒徚旓嵿揑嵼棃岺嬈偵棷傑偭偰偟傑偭偰偄傞丅偙偆偟偨丄壂撽宱嵪偵偍偄偰偼彜嬈帒杮傕嶻嬈帒杮傕乽奐敪偺庡栶傪扴偆椡検乿傪旛偊偰偄側偄偲尵偆偺偱偁傞丅偙傟偵壛偊偰丄愴屻偺壂撽偺惌帯夁掱偼丄壂撽恖偵宱嵪揑旐奞幰堄幆傪堦斒壔偝偣傞傛偆偵嶌梡偟丄乽宱嵪榑棟偺愻楃傪庴偗偨奐敪偺嬯擸亖妛廗夁掱乿傪懱尡偝偣偊側偔偝偣偨丅偙偺乽懠椡埶懚宆奐敪乿偲偦偺敪憐曽朄偼丄乽峴惌椡偺拁愊晄懌乿傪彽偒丄椺偊偽丄柧帯帪戙偺擔杮帒杮庡媊偑乽愭尒惈偵晉傫偩姱椈乿偺崙壠帒杮庡媊揑巜摫偵傛偭偰偼偠傔偰嫮椡側敪揥偑壜擻偲側偭偨傛偆側乽峴惌椡乿傪拁愊偟偊側偐偭偨偺偱偁傞丄偲偄偆丅偮傑傝丄峴惌亖姱椈傕傑偨奐敪偺庡懱偨傝偊側偄偲偄偆偺偱偁傞丅寢嬊丄壂撽傊偺奜晹梫場乗乗擔杮惌晎側偄偟帒杮乗乗偺摫擖偵傛傞僀儞僷僋僩偑晄壜寚偺峔憿偲側偭偰偄傞偲尵偆丅偟偐偟丄曉娨夁掱偵偍偗傞擔杮惌晎偺媆嵩惈偺備偊偵丄擔杮惌晎丒帒杮傊偺晄枮丄晄怣偑惗偠丄偙傟偵懳偡傞嫅愨揑巔惃偑偒傢傔偰嫮偄丅慶崙暅婣塣摦偼偙偺昞尰偱偁傝丄偦偙偐傜惗偢傞宱嵪堄幆偼旐奞幰偺堄幆偱偁傝丄宱嵪偵偍偗傞乽宱嵪幰偺栶妱乿偺寉帇丄宱嵪栤戣偺惌帯揑夝寛偲偄偆巔惃傪堦斒壔偝偣偰偄傞偲尵偆丅
丂偙偺傛偆側杚栰巵偺憤妵偼丄壂撽偺偡傋偰偺庡懱丄惃椡偵斲掕揑夁嫀偲偺抐愨傪敆傞偲摨帪偵丄宱嵪奐敪偺庡懱偼嶻嬈帒杮亖怴偟偄僽儖僕儑傾僕乕偺憂弌偵偙偦偁傞偲偄偆偙偲傪撍偒偮偗偰偄傞丅暅婣塣摦傪摤偭偨庡懱丒惃椡偼偙傟偵壗傪懳抲偡傞偺偐偑寛掕揑偵栤傢傟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂師偵丄偱偼偦偺壂撽宱嵪奐敪偺嬶懱揑惌嶔偼偳偆偱偁傞偺偐丠丂巵偼宱嵪奐敪偺堄媊傪扨弮偵嶻嬈峔憿偺揮姺亖戞擇師嶻嬈偺堢惉偲偄偆傛偆偵偼尵傢側偄丅傓偟傠丄乽幐嬈栤戣偺夝寛乿偲偄偆懎帹偵擖傝傗偡偄栤戣偐傜愢偒丄寢嬊丄怑応偯偔傝偲偼暔揑惗嶻椡偺奼戝乮嶻嬈帒杮偺堢惉乯偱偁傞偲偄偆榑棟傊偲摫偄偰偄偔丅偦偺忋偵偨偭偰丄偦偺惂栺忦審偺嫟捠擣幆傪捠偟偰乽帺棫宱嵪偺妋棫乿傪偼偐傠偆偲偡傞丅巵偼丄壂撽宱嵪偺惼庛惈傪乽暔揑惗嶻椡傪桳偟側偄偨傔偺堏桝弌擖廂巟偺戝暆愒帤乿偲偟偰偲傜偊丄乽帺棫乿偲偼乽亀導奜廂巟偺奼戝嬒峵亁傪偼偐傝偆傞宱嵪椡傪價儖僩僀儞偡傞偙偲乿偱偁傞偲棟夝偡傞丅偙傟偵傛傟偽丄嘆堏桝弌戙懼嶻嬈偺怴婯愝棫仺導撪帺媼棪偺堷忋偘偍傛傃懳奜巟暐嶍尭丄嘇摨嶻嬈偺惗嶻検奼戝仺屬梡丒強摼忋徃仺廀梫憹壛仺惗嶻婯柾奼戝仺惗嶻惈岦忋仺徚旓幰偺娨尦丄偲偄偆宱嵪弞娐偺恾幃偑攇媦偡傞偲峫偊傜傟偰偄傞丅偙偺恾幃偼丄導嶻昳偲偺嫞憟惂尷慬抲偺晄壜擻惈丄100枩恖巗応偲偄偆嫹瑗惈丄導嶻昳桪愭峸擖嫮惂偺尷奅側偳偺壂撽宱嵪傪傔偖傞惂栺忦審傪峫椂偟偰傕丄堏桝弌偺奼戝憹嫮偑偁傟偽払惉偱偒傞偲尵偆丅偟偐偟丄抧尦帒杮偵偦偺擻椡偑側偄尰忬偵偍偄偰偼丄乽婇嬈桿抳乿亖擔杮帒杮偺摫擖偵傛偭偰扴傢偣側偔偰偼側傜偢丄壂撽宱嵪偼偙偺乽桿抳婇嬈傪嵟戝尷偵妶梡乿偟丄偦偺夁掱偱撈帺偺嵞惗嶻峔憿傪峔抸偡傞偨傔偺乽妛廗乿傪偟側偔偰偼側傜側偄丅偦偺堄枴偱乽栧屗奐曻揑乿偱偁傝丄偐偮擔杮巗応傪懳徾偵偟偨乽懳奜巙岦宆乿偺曽岦傪偲傞偱偁傠偆偲尵偆丅
丂埲忋偐傜柧傜偐側傛偆偵杚栰巵偺尵偆乽帺棫宱嵪偺妋棫乿偲偼丄擔杮帒杮偺摫擖傪悇恑偟偮偮丄偦傟傪揙掙揑偵妶梡偟丄偦傟傪僥僐偲偟偰壂撽嶻嬈帒杮傪杣嫽偝偣帒杮庡媊揑拁愊峔憿傪峔抸偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅斾歡揑偵尵偊偽丄柧帯堐怴屻偺擔杮帒杮庡媊偺崙壠帒杮庡媊揑拁愊夁掱偺彫宆斉偱偁傞偲尵偊傛偆丅巵偼丄偙偺夁掱傪悇恑偡傞偨傔偵丄嶻嬈帒杮桿摫婡娭偺怴愝丄桿摫嶻嬈偺嬶懱揑慖掕丄擻摦揑桿摫婡娭偺悑峴傪採婲偡傞丅偙偙偵偼丄壂撽偺杮奿揑丄帒杮庡媊揑嵞峔抸偺忣擬偑傒偛偲偵榑棟壔偝傟偰偄傞丅
丂偟偐偟丄杚栰榑暥偵傕栤戣偑偁傞丅偦傟偼偙偺傛偆側壂撽僽儖僕儑傾僕乕偺儖僱僢僒儞僗偺崻嫆偼壥偟偰懚嵼偡傞偺偐偳偆偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅帒杮庡媊偺杣嫽婜偵偼僾儘僥僗僞儞僥傿僘儉偺椣棟偑帒杮壠惛恄傪宍偯偔傝丄傑偨屻恑庡媊彅崙偵偍偄偰偼柉懓揑帺棫丄柉懓揑僉儍僢僠丒傾僢僾偑僽儖僕儑傾僕乕偺惛恄偱偁偭偨丅偝傜偵丄戞嶰悽奅彅崙偵偍偄偰偼丄掗崙庡媊偺怉柉抧巟攝偐傜偺柉懓撈棫亅柉懓崙壠偺宍惉偑柉懓僽儖僕儑傾僕乕偺惛恄偲偟偰懚嵼偟偨丅壂撽偺応崌偼偳偆偐丠杚栰巵偼壂撽僽儖僕儑傾僕乕偺尷奅傪捝楏偵斸敾偟丄偦偺偮偔傝偐偊傪傔偞偟偰偄傞丅偩偑丄媽棃偺孯帠怉柉抧宱嵪峔憿偺側偐偱丄偦偺棙塿傪掄庴偟偰偒偨壂撽僽儖僕儑傾僕乕偑丄擔杮傊偺暅婣偲尵偆怴忣惃偑摓棃偟偨偲偼偄偊丄壗傪攠夘偵丄偁傞偄偼壗傪栚揑偲偟偰帺屓曄妚偱偒傞偲偄偆偺偩傠偆偐丠尰幚偼巵帺恎偑塻偔暘愅偟偰偄傞傛偆偵怴偨側柨庡偨傞擔杮庡媊偲崙壠偵廬懏偟夝懱偝傟偮偮偁傞偲偡傜尵偊傞偺偱偁傞丅
丂杚栰榑暥偼丄壂撽僽儖僕儑傾僕乕傪庡懱偲偟偨壂撽乽帺棫宱嵪乿榑偺幚慔揑攋抅偺拞偱丄壂撽乽帺棫宱嵪乿偺惌帯揑庡懱傪戞堦媊揑偵柧妋偵偡傞偙偲偵傛偭偰巭梘偝傟傞偺偱偁傞丅
戞嶰復乽奐敪乿宱嵪妛偐傜乽帺棫乿宱嵪妛傊
丂
侾丄宱嵪帺棫偺奣擮
丂惌帯宱嵪妛揑偵尵偭偰丄乽帺棫乿偺奣擮偼丄乽掅奐敪亅奐敪搑忋乿傗乽屻恑乿偺偦傟偲偼埵憡傪堎偵偡傞丅傑偨摉慠偺偙偲側偑傜丄乽帺棫乿偲偼丄乽帺媼帺懌乿偱偼側偄丅乽掅奐敪乿傑偨偼乽屻恑乿揑宱嵪悈弨偱乽帺棫乿偟偰偄傞幮夛亅崙壠偼偁傑傝偵傕懡偔尰懚偡傞偟丄崙嵺廂巟傗椵愊愑柋傪婎弨偲偡傞偲丄乽帺棫乿偟偰偄傞崙壠偼乽愭恑乿崙偱傕嫵偊傞傎偳偟偐側偄丅乽帺棫乿傪乽廬懏乿偵懳抲偟偨応崌偱傕丄椉幰偺奣擮偺嫟鏱斖埻偼偁傑傝偵傕戝偒偄丅偟偨偑偭偰丄宱嵪帺棫偲偼丄偝偟偁偨傝丄尩枾惈傪寚偔偲偟偰傕丄堦掕偺幮夛揑宱嵪扨埵偲偔偵柉懓廤抍偑丄帺屓敪揥椡偺庡懱偲懱宯傪撪嵼偝偣丄屌桳偺宱嵪敪揥偺婳摴傪傒偄偩偟丄偦傟傊偺摦懺傪奐巒偟偰偄傞忬懺丄偲偱傕峫偊偰偍偔傋偒偱偁傠偆丅偦偺忬懺偼丄堦掕偺惌帯揑忦審偵曐忈偝傟側偔偰偼側傜側偄偙偲偼丄尵偆傑偱傕側偄丅
丂宱嵪帺棫偺忬懺偼丄堦恖摉傝偺俧俶俹丄崙柉強摼丄峼岺嬈惗嶻傗丄偁傞偄偼惗嶻揑搳帒棪丄宱嵪惉挿棪側偳偺検揑巜昗偵傛偭偰偼妋擣偝傟偊側偄丄偲尵偆傋偒偱偁傠偆丅嶻桘崙偺傛偆偵丄摉奩崙柉宱嵪偑傑偭偨偔廬懏揑偵峔憿壔偝傟偰偄傞応崌偵偼丄斾妑揑崅偄偙偺庬偺巜昗偼側傫偺堄枴傪傕偪偊側偄偟丄媡偵尰嵼偺巜昗偼憡懳揑偵掅偔偲傕丄宱嵪揑帺屓敪揥乗乗倂丒倂丒儘僗僩僂偺尵偆杤庡懱揑駪虒n揑側乽棧棨乿乮亀宱嵪惉挿偺夁掱亁乯偲偼杮幙揑偵堎側傞乗乗偺婳摴傪摜傒偩偟偮偮偁傞幮夛偼丄傛傝帺棫揑偱偁傞丅
丂偨偲偊偽丄儔僥儞丒傾儊儕僇傪椺偵偲偭偰傒傞偲丄斀妚柦僋乕僨僞乕慜偺僠儕偺堦恖摉傝崙柉強摼偼丄乽儊僕儍乕乿亖愇桘挻撈愯懱偺巟攝壓偵偁傞嶻桘崙儀僱僘僄儔偺偦傟偺擇暘偺堦偵傕払偟側偐偭偨偑丄摉帪偺僠儕傛傝儀僱僘僄儔偺曽偑帺棫揑偱偁傞偲偼丄摓掙尵偄偊側偄偱偁傠偆丅傾僕僃儞僨惌晎偼僜楢偺乽墖彆乿傪婜懸偟偰宱嵪惌嶔傪岆偭偨偑丄俬俿俿傗傾僫僐儞僟偺巟攝偵懳峈偡傞偦傟側傝偺宱嵪帺棫壔傊偺曽岦偼丄暷僜乽暯榓嫟懚乿亖僨丒僼傽僋僩偺悽奅暘妱嫤掕偺傕偲偵柍嶴偵傕埑嶦偝傟偨丅偪側傒偵丄嵒摐儌僲僇儖僠儏傾偐傜晹栧娫惍崌敪揥偺宱嵪懱宯傊偺廋惓傪懨嫤揑偵抐擮偟偨僉儏乕僶偼丄宱嵪埨掕偲傂偒偐偊偵丄僜楢傊偺廬懏壓偵儔僥儞丒傾儊儕僇妚柦傊偺摴傪暵偝傟丄暥帤偳偍傝偺乽寣惻乿偲偟偰孯戉傪桝弌偡傞偵偄偨偭偨丅
丂懠曽丄庡懱揑丄懱宯揑偱偁傠偆偲偡傞偩偗偱偼丄宱嵪帺棫偺幚幙偼偐側傜偢偟傕曐忈偝傟偊側偄丅偙傫偵偪丄偡傋偰偺崙柉宱嵪偼悽奅宱嵪偵嬞枾偵楢摦偟丄掗崙庡媊悽奅懱惂摿偵偦偺愭抂偵棫偮悽奅婇嬈亖懡崙愋婇嬈偺摦岦偵懡偐傟彮側偐傟婯惂偝傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄宱嵪帺棫偼柉懓揑側偄偟崙壠揑婯柾偱偺乽帺椡峏惗乿偵傛偭偰昁梫偐偮廫暘偵払惉偝傟偆傞丄偲偄偆柦戣偼丄柧傜偐偵嵞専摙傪梫偡傞丅
丂偨偲偊偽丄姰慡庡尃崙壠偱偁傝丄帒尮揑偵偼乽帺媼帺懌乿傕壜擻側丄偦傟帺懱堦売偺乽悽奅乿偱偁傞偐偺偛偲偒拞崙偱偡傜丄僜楢傊偺廬懏傗僗僞乕儕儞庡媊揑廳岺嬈桪愭傪嫅斲偟偰丄擾岺嬒峵偺撈帺偺宱嵪敪揥傪捛媮偟偰偒偨偲偼偄偊丄擾嬈偱偺崙柉揑忚梋傪悽奅巗応傪攠夘偲偟偰崅搙惗嶻庤抜偲岎姺偡傞塈夞揑嵞惗嶻婳摴傪偲偭偰偒偨丅偦偺偝偄丄乽戞嶰悽奅乿偵偨偄偟偰偼丄峆忢揑側曅摴杅堈亖桝弌挻夁偺乮擾嶻暔_嶻壛岺寉岺嬈惢昳乗乗愴棯暔帒乯傪傕偭偰椪傫偱偒偨丅偦偟偰丄寢嬊偼丄傕偭偲傕埨堈側懳乽愭恑乿崙愇桘桝弌偵埶嫆偡傞摴傪曕傫偱偄傞啀憘獊A乽戞嶰悽奅乿偺柨庡傪傕偭偰擟偢傞偺偱偁傟偽丄乽墖彆傛傝杅堈傪乿偲朷傓彅崙偲偺娫偱偺怴偟偄桳婡揑楢懷偺摴偑扵媶偝傟側偔偰偼側傜側偐偭偨偱偁傠偆偵丅
丂偟偨偑偭偰丄宱嵪帺棫偲偼丄懱宯揑宱嵪敪揥偺摦懺偲偟偰偡偖傟偰庡懱揑偵棟夝偝傟側偔偰偼側傜側偄偲摨帪偵丄懠幰偲偺娭學偱偼丄偙偺帺屓敪揥偺媞娤揑側峔憿楢娭傪摜傑偊偰偺楢懷偲嫤摥偺扵媶傪娷拁偡傞丅
丂尰幚偺悽奅宱嵪峔憿偱偼丄椉幰偺曽岦偼廧乆乗乗偲偄偆傛傝奣偟偰乗乗柕弬偟憡檸偡傞丅偦傟偼丄掗崙庡媊悽奅懱惂乮偍傛傃偦傟偵側偍婎杮揑偵偼婯掕偝傟偰偄傞婛惉乽幮夛庡媊乿悽奅乯偺傕偲偱偼丄宱嵪敪揥偑嬌搙偵晄嬒摍揑偱偁傝丄偄傢備傞乽屻恑乿傑偨偼乽廃曈乿椞堟偱偺岺嬈壔偝傜偵偼廳壔妛岺嬈壔傪幉偲偡傞扨側傞嬤戙壔偼丄彮悢偺乽拞恑崙乿揑椺奜乗乗偦偺幙偼栤戣偲偟偰乗乗傪彍偔偲丄乽愭恑乿傑偨偼乽拞怱乿椞堟偲偺宱嵪奿嵎傪傓偟傠懀恑偟壛懍壔偡傞傛偆偼偨傜偔偐傜偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側戝偒側奿嵎偺傕偲偱宱嵪帺棫傪払惉偡傞偵偼丄傕偼傗偨傫側傞帺惗揑帒杮庡媊偺敪揥側偄偟偼崙壠帒杮庡媊壔傗宱嵪寁夋壔傪婲摦偲偡傞帺棫偵偲偳傑傜偢丄悽奅宱嵪峔憿傪傕曄妚偟傛偆偲偡傞偦傟偑捛媮偝傟側偔偰偼側傜側偄偱偁傠偆丅婛惉乽幮夛庡媊乿悽奅偼丄偦偺撪晹偱偁偭偰偡傜丄僜楢偲拞崙丄僜楢偲搶儓乕儘僢僷彅崙偲偺懳棫偵傒傞傛偆偵丄偦偺傛偆側曄妚丄偦偺傛偆側乽撿杒栤戣乿偺夝寛偵幐攕偟偨丅偄傢傫傗丄乽幮夛庡媊揑乿墖彆偵傛傞乽戞嶰悽奅乿偺乽旕帒杮庡媊揑敪揥乿偼丄尪憐偵偲偳傑偭偰偄傞丅惌帯揑側堄枴偱偺帺棫偲偟偰偺柉懓乽帺寛乿偺奣擮偼丄僽儖僕儑傾柉庡庡媊揑乮亖崙楢寷復揑乯偵傕丄僾儘儗僞儕傾幮夛庡媊揑偵傕丄偦傟側傝偵尨棟揑偵偼傎傏柧妋偵掕媊偟偆傞偑丄宱嵪帺棫偺曽偼偦偆側偭偰偄側偄偙偲偼丄偙偺傛偆側尰幚偺崲擄傗柕弬傪斀塮偟偰偄傞丅
俀丄乽奐敪乿宱嵪妛偺攋嶻
丂堦岥偵尵偭偰乽掅奐敪乿丒乽屻恑乿椞堟傪懳徾偲偡傞廬棃偺宱嵪妛揑曽朄偼丄幚慔揑偵偙偺椞堟偺帺棫傊偺宱嵪敪揥傪朷傓傕偭偲傕椙怱揑側傕偺偱偁偭偰傕丄乽崅搙敪揥乿丒乽愭恑乿椞堟傪儌僨儖偲偡傞乽奐敪乿側偄偟乽嬤戙壔乿偺偨傔偺偦傟偱偁偭偨丅偦傟傜乽奐敪乿棟榑傗乽嬤戙壔乿棟榑偼丄崙楢愱栧埾堳夛偵傛傞乽掅奐敪崙奐敪偺偨傔偺彅曽嶔乿乮1951擭乯偺敪昞埲棃丄傑偝偵娋媿廩搹偺娤偑偁傞丅偙偙偱偼偦傟傜偺妛愢巎揑梫栺偑庡戣偱偼側偄偺偱丄偒傢傔偰戝抇偵惍棟偟偰丄偦傟偧傟偺摿挜傪庒姳偲傜偊偰偍偔偵偲偳傔傛偆丅
丂廬棃偺乽奐敪乿丒乽嬤戙壔乿棟榑偼丄摉柺偺昁梫忋丄偮偓偺傛偆偵暘椶偡傞偙偲偑偱偒傛偆丅
俙丄嬤戙宱嵪妛揑曽朄
乮侾乯怴屆揟攈揑乽奐敪乿榑乗乗戙昞揑側傕偺偲偟偰僰儖僋僙乮杒乯乗乗儈儞僩乮撿乯
乮俀乯乽拞怱亅廃曈乿榑乗乗戙昞揑側傕偺偲偟偰儈儏儖僟乕儖乮杒乯乗乗僾儗價僢僔儏乮撿乯
俛丄儅儖僋僗庡媊宱嵪妛曽朄
乮侾乯 僜楢儌僨儖乽旕帒杮庡媊揑敪揥乿榑乗乗僪僢僽丄僜楢彅妛幰丄
乮俀乯 拞崙儌僨儖乽帺椡峏惗乿榑
丂偙偙偱偼丄俙偱偼乮侾乯偵愭峴偡傞岞慠偨傞掗崙庡媊揑怉柉抧宱嵪榑偼徣偄偰偁傞丅俛偵娭楢偟偰偼丄杮棃偺儅儖僋僗宱嵪妛偨傞儗乕僯儞傗儘乕僓丒儖僋僙儞僽儖僋偺掗崙庡媊偲旕帒杮庡媊椞堟偲偺娭楢偵偐傫偡傞婱廳側尵媦偵偮偄偰傕摨條偱偁傞丅
丂乽奐敪乿宱嵪妛偼丄屆揟揑丒掗崙庡媊揑側揱摑揑尒夝乮僀僊儕僗傪揟宆偲偡傞帺桼側巗応丄壙奿儊僇僯僘儉偺傕偲偱偺巹婇嬈傪庡懱偲偡傞宱嵪敪揥偺宱楬乯偵塻偔斀敪偟丄崙壠帒杮庡媊揑岺嬈壔傪婎幉偲偡傞乽掅奐敪乿彅崙偺媫懍側嬤戙壔揑乽奐敪乿傪巙岦偡傞丅偦偺傛偆側尒夝偺戙昞揑側傕偺偲偟偰丄乽愭恑乿崙懁偱偼儔僌僫乕儖丒僰儖僋僙乮僐儘儞價傾戝妛嫵庼乯偺庡挊亀掅奐敪彅崙偵偍偗傞帒杮宍惉偺彅栤戣亁乮1953擭乯偱偁傝丄乽屻恑乿崙懁偱偼偙傟偵懳墳偡傞偺偼價儖儅弌恎偺儔丒儈儞僩乮儔儞僌乕儞戝妛憤挿乯偺亀掅奐敪崙偺宱嵪妛亁乮1964擭乯傪嫇偘傞傋偒偱偁傠偆丅
丂僰儖僋僙偼丄乽掅奐敪乿崙宱嵪傪乽昻崲偺埆弞娐乿乮帒杮偺廀梫丒嫙媼椉柺偵偍偗傞掅惗嶻椡側傞偑備偊偺搳帒桿場晄懌偲掅挋拁椡乯偲偲傜偊丄偙偺乽掅奐敪嬒峵乿偲徧偡傋偒掕忢忬懺傪懪攋偡傞偨傔偵丄乽愭恑乿崙揑側壿暭揑桳岠廀梫奼挘偱偼側偔丄寁夋揑側幚暔帒杮偺乽嬒峵偺庢傟偨惉挿乿偲懡條壔傪庡挘偡傞丅偦偺婎幉偼丄寁夋揑側惌晎搳帒偱偁傝丄儌僨儖偼擔杮偍傛傃惌帯揑尷掕偯偒偱偁傞偑僜楢偱偁傞丅僰儖僋僙偼丄偦偺偐偓傝偱偼丄乽掅奐敪乿崙偺乽帺椡峏惗乿偵婜懸偟丄偦偙偱偺帒杮宍惉偺尞傪惗嶻椡偲惗妶悈弨偺槰棧傪埲壓偵杽傔傞偐偲偄偆揰偵扵傠偆偲偟偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂偙傟偵懳偟丄儈儞僩偼丄僰儖僋僙偲摨偠偔嬒惸揑惉挿榑幰偱偁傞偑丄乽戞嶰悽奅乿弌恎幰傜偟偔丄偦傟偧傟偺敪揥抜奒偵偁傞偝傑偞傑側椶宆偺乽掅奐敪乿崙偵揔墳偟偆傞乽慖戰揑暘愅儌僨儖乿傪採帵偡傞丅偦偺嵺斵偑嫮挷偡傞偺偼丄岺嬈亅擾嬈偺憡屳曗姰揑敪揥偱偁傞乮岺嬈偑敪揥偟偰傕擾嬈偑掆懾偟偰偄傟偽偦傟偼岺嬈偺瑗楬偲側傞乯丅尰幚偵偼擾嬈偺嬤戙壔亅桝擖戙懼岺嬈壔傪採帵偟偨丅偦偺揰偱偼丄儈儞僩傕乽掅奐敪乿崙偺乽帺椡峏惗乿傪捛媮偟偨偲偄偊傞丅
丂偙偺僰儖僋僙亅儈儞僩揑側嬤戙壔揑乽奐敪乿宱嵪妛偼丄1960擭戙屻敿丄乽撿杒栤戣乿偑敋敪偡傞偵媦傫偱偦偺尷奅傪業掓偟偨丅乽撿乿偲乽杒乿偲偺娫偵偼偨傫側傞乽奐敪乿丄偦偺偨傔偺乽墖彆乿偵傛偭偰偼挻偊偑偨偄峔憿揑側奿嵎偲懳棫偑懚嵼偡傞偙偲偑柧敀偱偁傞埲忋丄乽屻恑乿崙偼乽愭恑乿崙偺宱嵪敪揥偺愓傪捛偆傋偒偱偁傞丅乮宲婲揑抜奒榑乯偲偐丄乽婛奐敪乿崙偲乽掅奐敪乿崙偲偺暲懚忬懺傪廋惓偡傋偒偱偁傞乮擇廳峔憿榑乯偲偐偺丄乽杒乿偐傜乽撿乿傊偺乽墖彆乿偦偺懠偺徴寕偺昁慠惈傪寢嬊偼惀擣偟崌棟壔偡傞棟榑揑帇嵗偦偺傕偺偑摦梙偣偞傞傪偊側偔側偭偨偺偱偁傞丅
丂乽墖彆傛傝傕杅堈傪乿偲偟偰昞尰偝傟偨乽撿乿偺庡挘偺婙庤偼丄儔僂儖丒僾儗價僢僔儏乮傾儖僛儞僠儞尦憼憡丄倀俶俠俿俙俢憂愝幰乯偱偁偭偨丅僾儗價僢僔儏偼丄倀俶俠俿俙俢偺巜恓揑惌嶔偵帺傜偺棟榑傪偙傔偰丄乽墖彆傛傝傕杅堈傪乿偺挿婜揑慬抲偑晄壜寚側偙偲傪採帵偟偨丅斵偼丄乽掅奐敪乿偺愢柧尨棟偲偟偰擭棃嵦梡偟偰偒偨亙拞怱亅廃曈亜榑偵棫偭偰丄偙偺娫偺奿嵎偼乽廃曈乿懁偺堦師嶻昳偺峴堊忦審埆壔亅杅堈廂巟埆壔偵廤拞揑偵昞尰偝傟傞偲偡傞丅偙偺岎堈埆壔偺崕暈嶔乮堦師嶻昳偺崙嵺彜昳嫤掕丄堦斒摿宐娭惻丄俧俶俹侾亾梈帒摍乯偲乽掅奐敪乿崙偺帺庡揑搘椡偙偦乽掅奐敪乿偐傜偺僟扙媝偺婎幉偱偁傞偲偟偨丅摿偵慜幰偺乽奿嵎乿惀惓偺偨傔偺斀帺桼杅堈尨懃偼丄乽掅奐敪乿崙偺敪揥偺偨傔偺悽奅愴棯偲偟偰乽愭恑乿彅崙偵偮偒偮偒傜傟偨丅
丂偙偺乽撿乿偺岞慠偨傞晄暯摍惀惓偺尨懃揑梫媮偼丄乽杒乿偱偼丄俲丒僌僫乕儖丒儈儏儖僟乕儖乮僗僂僃乕僨儞丄尦崙楢儓乕儘僢僷宱嵪埾堳夛埾堳挿乯偵傛偭偰恏偆偠偰巟帩偝傟偨丅儈儏儖僟乕儖偼丄偡偱偵亀宱嵪棟榑偲掅奐敪抧堟亁乮1957擭乯偱乽掅奐敪乿崙偲偺娫偱偺宱嵪揑晄暯摍丄晄嬒摍敪揥偺昁慠惈傪愢柧偟丄廬棃偺宱嵪棟榑偺尷奅傪柧傜偐偵偟偰偄偨丅幮夛柉庡庡媊幮偨傞斵偺壙抣慜採偼乽嬤戙壔棟擮乿偱偁傝丄暘愅曽朄偼乽惂搙揑暘愅乿偱偁傞偑丄偦偺尷奅撪偱偼乽奐敪乿宱嵪妛偑乽撿杒栤戣乿夝寛偵岦偭偰偺梡嬶偨傝偊側偄偙偲傪帺擣偟偰偄傞傕偺偲偄偊傛偆丅偮傑傝丄巗応彅椡偵姳徛偡傞偙偲側偟偵宱嵪敪揥偼偁傝偊偢丄偦傟偼杮幙揑偵乽惌帯揑寁夋乿偱偁傞偙偲傪柧傜偐偵偟丄僾儗價僢僔儏偺庡挘傪巟帩偟偨偺偱偁傞丅
丂偟偐偟丄偙偺傛偆側僾儗價僢僔儏乕儈儏儖僟乕儖揑側晄暯摍惀惓偺庡挘偼丄杮幙揑偵乽奐敪乿宱嵪妛傪挻崕偡傞傕偺偱偁傠偆偐丠寢榑揑偵偼丄斵傜偺庡挘偼悽奅揑椙幆偲側傝偮偮傕丄傗偼傝乽撿乿亅乽杒乿娫偺栤戣堄幆丄乽廃曈乿偺乽拞怱乿壔亖奿嵎偺検揑尭彮偺堟傪挻偊傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偲尵傢偞傞傪偊側偄丅偦傟偼乽掅奐敪乿偲偦偺埆弞娐偲偄偆楌巎揑\憿揑幙傪晜偒挙傝偵偟乽撿乿撈帺偺帺棫揑敪揥偺摴傪撪嵼揑偵傒偄偩偟偊側偐偭偨偐傜偱偁傞丅懠曽偱丄偦傟偼傑偨丄嬤戙宱嵪妛偺尨棟揑麞@揑尷奅傪帵偡傕偺偱傕偁偭偨丅
丂偙偺揰偱偼丄婛惉偺儅儖僋僗庡媊宱嵪妛傕寛偟偰寳奜偵棫偮傕偺偱偼側偄丅偦偺乽屻恑崙乿宱嵪榑偺慡柺揑憤妵偼暿搑榑偢傞偙偲偲偟偰丄偙偙偱偼師偓偺偙偲偩偗巜揈偟偰偍偒偨偄丅儌乕儕僗丒僪僢僾亀宱嵪敪揥偺庒姳偺懁柺亁傗億乕儖丒僶儔儞亀惉挿偺宱嵪妛亁側偳偺愭嬱揑嬈愌傕偄傢傫傗拞僜偺崙壠揑懳棫傪攚宨偲偟偰乽戞嶰悽奅乿偵採帵偝傟偨僜楢偺乽旕帒杮庡媊揑敪揥乿榑丄拞崙偺乽帺椡峏惗乿榑偍傛傃偦傟傜偵傕偲偯偔乽墖彆乿幚慔傕丄嬤戙壔榑偺榞慻傒傪攋傝偊側偐偭偨偙偲偱偁傞丅
丂偦偺偙偲偼丄愴屻儅儖僋僗庡媊偺悽奅宱嵪偵懳偡傞棟榑揑帇妏偑丄偄傑偱偼嫊栂偵摍偟偄帒杮庡媊偺乽慡斒揑婋婡乿榑偵峉懇偝傟偮偯偗偰偒偨偙偲丄傑偨乽掅奐敪乿宱嵪偺懪攋傪僜楢側偄偟偼拞崙偺妚柦偲宱嵪寶愝偺儌僨儖偵偟偨偑偭偰偟偐峫偊傜傟偰偙側偐偭偨偙偲偲嬞枾偵娭楢偟偰偄傞丅傂偲偨傃婛惉乽幮夛庡媊乿悽奅偑掗崙庡媊悽奅懱惂偵宱嵪朄懃柺偱傕杮幙揑偵婯掕偝傟偰偄傞偙偲丄偦偟偰僜楢偺乽幮夛庡媊乿寶愝傕拞崙偺偦傟傕丄偦傟帺懱偑柉懓崙壠揑嬤戙壔傪杮幙偲偟偰偄傞偙偲偑敾柧偟偰偟傑偊偽丄堦愗偺棫榑偼幐偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅
丂偐偔偟偰丄崱擔丄偨偲偊偽椵愊嵚柋偺朹堷偒梫媮偵尒傜傟傞傛偆側乽掅奐敪乿彅崙偺宱嵪婋婡丄偦偺撪晹偱偺幮夛婋婡偺恑峴偼丄帺棫揑宱嵪敪揥偺忦審丄楬慄丄庡懱側偳偵娭偡傞慡偔怴偟偄儅儖僋僗宱嵪妛揑夝柧傪媮傔傞偙偲傪梋媀側偔偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
俁丄乽帺棫乿宱嵪妛偺戀摦
丂乽奐敪乿宱嵪妛偑乽撿杒栤戣乿偺寖壔偺側偐偱丄嬤戙宱嵪妛攈傕儅儖僋僗庡媊宱嵪妛攈傕攋嶻偟偝偭偨尰嵼丄乽戞嶰悽奅乿偺宱嵪帺棫傪棟榑壔偟傛偆偲偡傞乽帺棫乿宱嵪妛偺戀摦偑巒傑偭偨丅偦偺戙昞揑側傕偺偲偟偰丄傾儞僪儗丒僌儞僨儖丒僼儔儞僋乮僠儕偺斀妚柦僋乕僨僞乕屻惣僪僀僣偺儅僢僋僗丒僾儔儞僋尋媶強媞堳尋媶堳乯偲僒儈乕儖丒傾儈儞乮惣傾僼儕僇丒僟僇乕儖偺崙楢宱嵪奐敪丒宱嵪尋媶強挿乯偺強愢傪傒偰偍偙偆丅
丂僼儔儞僋偼丄乽乧乧尰戙偺掅奐敪偼戝晹暘丄夁嫀傕尰嵼傕懕偄偰偒偰偄傞掅奐敪揑塹惎彅崙偲愭恑拞悤彅崙偲偺娫偺宱嵪傪偼偠傔偲偡傞彅娭學偺楌巎揑強嶻偵傎偐側傜側偄丅偟偐傕丄偙傟傜偺娭學偙偦丄悽奅揑婯柾偱偺帒杮庡媊懱惂偺峔憿偲敪揥偺杮幙揑晹暘傪側偟偰偄傞偺偱偁傞乿乮亀悽奅帒杮庡媊偲掅奐敪亁1976擭乯偲妳攋偡傞丅僼儔儞僋偺尵偆亙拞悤亅塹惎亜娭學偼丄僾儗價僢僔儏偺暯柺揑箲稉I側亙拞怱亅廃曈亜娭學偲偼杮幙揑偵堎側偭偰丄堦尦揑丄峔憿揑側憡娭亅憡懄娭學偱偁傞丅偙偺暘愅帇嵗偐傜僼儔儞僋偼丄乽掅奐敪乿偑乽堚惂偺巆懚傗帒杮偺晄懌乿偵尨場偑偁傞偺偱偼側偔丄乽帒杮庡媊偺敪揥偦偺傕偺偵傛偭偰憂弌偝傟偨乿偲攃埇偡傞丅偟偐傕丄偙偺娭學偼丄乽掅奐敪乿崙撪偱傕乽拞悤乿搒巗偲乽塹惎乿抧堟偲偦傟偵懨摉偡傞丅嵟傕廳梫側偺偼丄偦偙偱偼乽掅奐敪偺敪揥乿偲偄偆峔憿偑堦斒揑偱偁傞偙偲偩丅偮傑傝丄乽帒杮庡媊懱惂偺悽奅揑奼挘偲摑堦丄偦偺楌巎傪捠偠偰堦娧偟偰偄傞撈愯揑峔憿偲晄嬒摍敪揥丄偦偺寢壥丄掅奐敪抧堟乮斾妑揑岺嬈壔偑恑傫偩崙傕娷傓乯偵偍偄偰崻嫮偔懚懕偟偰偄傞廳彜帒杮庡媊乿偲偄偆峔憿偱偁傞丅
丂僼儔儞僋偼丄偙偺乽敪揥乿傪僠儕傗僽儔僕儖偵偮偄偰嬶懱揑偵専摙偟偨丅偦偙偐傜寢榑偝傟傞偺偼丄惌帯揑夝曻偼傕偲傛傝宱嵪揑帺棫傕傑偨丄乽恑曕揑柉懓僽儖僕儑傾僕乕乿乗乗幚偼乽拞悤乿偵傛傞乽掅奐敪乿嫮壔偺摴嬶乗乗偵埶嫆偡傞偙偲偼偱偒偢丄乽恀偺宱嵪揑丒恖娫揑敪揥傪峴傢偣傞愭摫揑側丄幚岠偁傞惌帯峴摦偺扴偄庤偼丄昁慠揑偵搒巗_懞偺帒杮庡媊揑塹惎偨傞旐嶏庢憌偱偁傞乿偲偄偆偙偲偱偁傞丅僼儔儞僋偼丄1967擭偺榑暥偱乽帒杮庡媊揑掅奐敪偐丄幮夛庡媊妚柦偐乿偲懳抲偟丄乽愴弍揑偵尵偊偽丄儔僥儞傾儊儕僇偵偍偗傞柉懓夝曻偺摉柺偺揋偼丄僽儔僕儖丄儃儕價傾丄儊僉僔僐側偳偺柉懓僽儖僕儑傾僕乕偱偁傝丄儔僥儞傾儊儕僇擾懞晹偺抧曽僽儖僕儑傾僕乕偱偁傞丅愴棯揑偵傒傞側傜偽乮傾僕傾傗傾僼儕僇傪娷傔偰乯掗崙庡媊偙偦庡梫側揋偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦傟偼恀偱偁傞乿丄偲戝抇偵掕幃壔偟偰偄傞丅
丂僼儔儞僋偺乽怴掗崙庡媊乿亅乽怴廬懏乿榑偼丄奒媺峔憿丄巟攝峔憿偺惌帯妛揑丒幮夛妛揑暘愅傪捠偠夝曻塣摦榑偵捈寢乗乗偲偄偆傛傝抁棈乗乗偟偰偍傝丄僾儗價僢僔儏偺乽奐敪乿棟榑斸敾偼塻偔偲傕丄杮峞偺壽戣偱偁傞宱嵪帺棫偦偺傕偺偵偮偄偰偼廫暘偵榑媦偟偰偄側偄丅傕偪傠傫乽柉懓僽儖僕儑傾僕乕乿傪庡懱偲偡傞偡傞側傜偽偲傕偐偔丄斵偑夝柧偟偨傛偆側乽掅奐敪乿崙撪偵傑偱怹摟偟峔憿壔偟偰偄傞亙拞悤亅塹惎亜娭學偺揙掙揑懪攋偼丄傑偢惌帯偲愴棯韽p偺栤戣偱偁傞偵偼偪偑偄側偄丅偟偐偟丄乽掅奐敪乿偺宱嵪揑曄妚亖乽帺棫乿偺曽岦偼丄夁搉揑偵偣傛愽嵼揑偵偣傛丄傕偭偲惓妋偵扵媶偝傟側偔偰偼側傜側偄丅偦偺扵媶偼丄乽掅奐敪偺敪揥乿偺峔憿揑廳埑偵峈偡傞偒傢傔偰嬶懱揑側摤憟偺撪梕傪備偨偐偵偟丄嵟戝偺夞摎偑幮夛庡媊偱偁傞偲偡傟偽丄偦偺揥朷偵帒偡傞偼偢偱偁傞丅
丂偦偺揰偱偼丄傢傟傢傟偼丄僼儔儞僋偺曽朄揑奐戱傪彸偗偮偮丄宱嵪乽帺棫乿偺壜擻惈偵惓柺偐傜偲傝偔傫偩傾儈儞偵堦憌妛傇偙偲偑偱偒傛偆丅傾儈儞傕丄亀悽奅婎弨偱偺拁愊亁偱丄媽棃偺乽廬懏乿棟榑丄偨偲偊偽丄乹愭敪亅屻敪乺偺抜奒揑宲婲榑傗乹帒杮庡媊乗慜帒杮庡媊乺偺暪懚揑擇廳峔憿榑傪揙掙揑偵斸敾偡傞丅尰懚偺偡傋偰偺幮夛偼帒杮庡媊揑悽奅懱宯偵慡偔摑崌偝傟偮偔偟丄偦偺撪晹偱偺乹拞怱亅廃曈乺娭學偼悽奅婎弨偱偺壙抣堏揮偺棳傟偵傛偭偰丄堦岥偱尵偆偲悽奅揑側杮尮揑拁愊偺儊僇僯僘儉偵傛偭偰堦娧偟偰婯掕偝傟偰偒偨偟丄偄傑傕婯掕偝傟偰偄傞丅乽嫟嶻庡媊悽奅乿傕偦偺毥奜偵偁傞傕偺偱偼側偄丅偦偙偱偼丄帺棫揑側帒杮庡媊崙撪偍傛傃帒杮庡媊崙娫偺傛偆側堦売偺憡娭揑慡懱傪宍惉偡傞宱嵪丄偦偺椵愊揑側惉挿傪傒傞偙偲偼偱偒側偄丅帒杮庡媊揑悽奅懱宯偵慻傒偙傑傟偨偙偺乽廃曈乿帒杮庡媊壔偼乽拞怱乿宱嵪偺墑挿偱偟偐側偔偒傢傔偰醔宆揑側傕偺偱偁傞丅
丂傾儈儞偼丄偙偺乽廃曈乿帒杮庡媊壔偺夁掱傪桳柤側師偺僔僃乕儅偵傛偭偰夝柧偡傞丅鼤訐I丒廬懏揑僒僽丒僔僗僥儉苽祩膫虠A弌晹栧偲汎樖揑徚旓晹栧偑丄乽拞怱揑丒帺棫揑僒僽丒僔僗僥儉乿偲偟偰偺戝廜徚旓晹栧偲愝旛晹栧傪掆懾偝偣丄偐偮醔宆揑乽掅奐敪乿宱嵪峔憿傪偮偔傝忋偘傞丅偙偺僔僃乕儅偐傜摫偐傟傞乽帒杮庡媊揑悽奅宱嵪偲偄偆扨堦偺儊僇僯僘儉偺晹暘偱偁傞掅奐敪宱嵪乿丄拞怱偺敪揥夁掱偲摨帪偵恑峴偡傞掅奐敪夁掱丄偡側傢偪丄乽掅奐敪偺敪揥乿亅乽敪揥側偒惉挿乿傪丄乽奐敪乿傗乽嬤戙壔乿偵傛偭偰懀恑偟傛偆偲偡傞堦愗偺乽掅奐敪偺棟榑偼悽奅婎弨偱偺拁愊偺棟榑偨傜偞傞傪偊側偄乿偺偱偁傞丅傾儈儞偺偙偺尨棟揑夝柧偼丄條乆偵偝傜偵嬶懱壔偝傟偰偄傞偑丄嵟嬤弶傔偰朚栿偝傟偨乽帺棫揑敪揥丄廤抍揑帺棫偍傛傃怴崙嵺宱嵪拋彉乿乮亀揥朷亁1977擭12寧崋乯偼偦偺戙昞揑榑暥偱偁傠偆丅
丂傢傟傢傟偑嵟傕娭怱傪傕偮偺偼丄摉慠乽廃曈乿帒杮庡媊偺乽敪揥側偒惉挿乿偐傜扙媝偟偰宱嵪帺棫傪偐偪偲傞乽敪揥忦審乿偵偮偄偰偱偁傠偆丅亀悽奅婎弨偱偺拁愊亁偺枛旜偱偼丄偦傟偼偮偓偺傛偆偵揥朷偝傟偰偄傞丅偦傟偼丄虒n揑丒峔憿揑曄妚乿偱偁傝丄乽摍幙揑丒帺屓拞悤揑丒帺屓塣摦揑崙柉宱嵪偺帺庡揑寶愝乿偱偁傝丄慜婰偺峔憿揑摿挜傪堦憒偡傞宱嵪敪揥惌嶔偱偁傞丅偦傟偑慜婰僒僽丒僔僗僥儉偲偟偰偼戝廜徚旓晹栧亅愝旛晹栧傊偺揮姺傪幉偲偡傋偒偙偲偼帺柧偱偁傞偑丄偦偺偨傔偺戝慜採偼帒杮庡媊揑悽奅宱嵪懱宯偐傜偺棧扙偱側偔偰偼側傜側偄丅偙偺擄栤傪丄傾儈儞偼偳偆夝偙偆偲偡傞偐丠
丂斵偼尵偆丅宱嵪帺棫偺摴偼丄戞堦偵掅惗嶻惈晹栧偐傜崅惗嶻惈晹栧傊偺丄摿偵惗寁堐帩揑擾嬈偐傜嬤戙揑岺嬈傊偺廇嬈恖岥偺慟師揑堏峴偺慻怐壔偱偁傝丄慜幰偱偺惗嶻惈偺堷忋偘丄崻尮揑側媄弍揑曄妚偱偁傞丅偦偺偙偲偼丄婛惉偺晄嬒摍敪揥偺婎慴偵偁傞崙嵺暘嬈偲徴撍偣偞傞傪偊側偄丅戞擇偵偼丄惓偟偔慖戰偝傟偨敪揥栚昗偵偟偨偑偭偰怴偟偄宱嵪偵桳婡揑側娭楢惈偲摑堦惈傪曐忈偟丄擾嬈丒寉岺嬈偍傛傃徚旓嵿岺嬈丒婎慴岺嬈乮僄僱儖僊乕丄峾揝丄婡夿丄壔妛乯娫偺楢寢揑嬒徴傪奺崙偺嬶懱揑忦審偵墳偠偰惗傒偩偡偙偲偱偁傞丅偙偺乽撪岦揑乿峔憿壔偼u拞怱乿巙岦偲抐愨偣偞傞傪偊側偄丅戞嶰偵偼丄怴偟偄宱嵪偺乽帺屓塣摦乿偺偨傔偵丄懳奜杅堈峔憿傗塣捓惂搙偺崻杮揑曄妚偵偲偳傑傜偢丄壛懍揑敪揥偺梫惪偵墳偊傞強摼暘攝傗嬥梈偵娭偡傞惌嶔傪妋棫偡傞偙偲偱偁傞丅偲偔偵昁梫側偺偼丄宱嵪敪揥偺偨傔偺岺丒擾娫偺壙奿惌嶔丄帺屓嬥梈惌嶔偱偁傞丅偦傟偼丄崙嵺暘嬈偺尰峴宍懺傗撪奜偺巹婇嬈拞怱懱惂偲惓柺偐傜摤偆宱嵪寁夋壔傪昁梫偲偣偞傞傪偊側偄丅埲忋偺傛偆側忦審傪妋曐偡傞偨傔偵丄乽悽奅巗応偲偺抐愨乿傪乽敪揥偺慜採乿偲偟偰採埬偡傞丅
丂傾儈儞偼丄偙偺乽悽奅巗応偺抐愨乿傪僜楢丄搶墷偑乽姱椈揑崙壠帒杮庡媊乿傊偺夁搉宍懺偱偟偐側偄尰幚偵偍偄偰丄扨側傞乽廃曈乿偺夝曻偱偼側偄乽怴偟偄夁搉宍懺乿偺偆偪偵峫媶偟傛偆偲偡傞丅偦傟偼媞娤揑偵幮夛庡媊揑曄妚偺昁梫傪堄枴偟偰傕寛偟偰廫暘偱偁傞偲偼尵偊側偄丅偙偺傛偆偵斵偼丄僼儔儞僋偲偪偑偭偰丄帺棫傊偺惌帯塣摦棟榑傪廫暘偵柧傜偐偵偟偰偼偄側偄偑丄斵偑憂弌偟偨亙拞怱亅廃曈亜偺悽奅帒杮庡媊偲偟偰偺堦尦揑棟夝偺曽朄偼丄柉懓帺寛=惌帯揑夝曻偺搚戜偲偟偰偺宱嵪帺棫偺偨傔偺徟揰傪妋掕偡傞偆偊偱丄戝偒側晲婍偲側傝偆傞傕偺側偺偱偁傞丅
係丄宱嵪帺棫偲柉懓帺寛
丂埲忋丄偒傢傔偰嬳偗懌側偑傜丄乽掅奐敪乿栤戣偵偮偄偰偺曽朄榑巎傪奣娤偟偰偒偨丅偄傑偺偲偙傠丄偦偺愭抂偵棫偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞僼儔儞僋亅傾儈儞偺曽朄榑偼丄宱嵪帺棫傊偺摴偵偮偄偰偼丄宱嵪偲惌帯丄峔憿偲忋晹峔憿傪摑堦揑偲傜偊傞揰偱傑偩擄揰傪巆偟偰偼偄傞丅偩偑丄乽掅奐敪偺敪揥乿側偄偟乽廃曈揑帒杮庡媊乿偺奣擮偵徾挜偝傟傞塻偄媞娤揑攃埇偼丄傑偝偵悽奅峔憿偺夁搉婜偵偝偄偟偰丄偦偺曽岦傪寛掕偡傋偒嵟廳梫偺摦場偺傂偲偮偱偁傞偙偺栤戣傪捛媮偟偰偔慴愇偨傝偆傞傕偺偱偁傞丅偦傟偵傕偲偯偄偰丄宱嵪帺棫偺夁掱偲偦偺惌帯揑曐岇偲偺娭楢偵偮偄偰丄庒姳曗懌揑偵採婲偟偰偍偙偆丅
丂僼儔儞僋亅傾儈儞偺応崌丄宱嵪帺棫傊偺摴偺揥朷偼彮側偔偲傕丄幮夛庡媊偍傛傃幮夛庡媊悽奅乗乗惓妋偵偼丄幮夛庡媊悽奅懱宯偺桳婡揑峔惉晹暘偲偟偰偺幮夛庡媊懱惂乗乗偱偁偭偨丅僜楢宆側偄偟拞崙宆偺慜婜揑側婛惉乽幮夛庡媊乿偲偼偍偦傜偔杮幙揑偵堎側傞偱偁傠偆偙偺幮夛庡媊偺惌帯宱嵪妛揑撪梕傪峫偊偰偄偔応崌丄偄傑偩廫暘偵夝偐傟偰偄側偄偝傑偞傑側栤戣偵偮偒偁偨傞偙偲偵側傞丅偨偲偊偽丄乮堦乯乽掅奐敪乿崙撈帺偺幮夛庡媊揑帺棫偲丄揱摑揑偵乽戞嶰悽奅乿夝曻偺怱慠揑宎楬偲偝傟偰偒偨柉懓帺寛偲偺娭學丄乮擇乯偙偺幮夛庡媊揑帺棫偺扴偄庤偨傞庡懱偺妋掕傪拞怱偲偡傞奒媺暘愅丄乮嶰乯乽掅奐敪乿崙偺幮夛庡媊揑帺棫偲乽婛奐敪乿崙偺幮夛庡媊揑庡懱偲偺楢懷偺壜擻惈丄乮巐乯幮夛庡媊悽奅懱宯傪峔惉偡傞彅柉懓側偄偟彅崙壠娫偺怴偟偄寢崌尨棟丄側偳偱偁傞丅
丂拪徾揑偵偼丄偮偓偺傛偆偵峫偊傜傟傛偆丅
乮堦乯偵偮偄偰偼丄偐偮偰柉懓僽儖僕儑傾僕乕傪庡懱偲偡傞斀掗柉懓妚柦=僽儖僕儑傾柉庡庡媊妚柦乮側偄偟偼恖柉柉庡庡媊妚柦乯偺戙柤帉偲偝傟偰偄偨乽柉懓帺寛乿偲偼丄偙傫偵偪偺乽柉懓帺寛乿偼幙揑撪梕傪敪揥偝偣偞傞傪偊側偄偱偁傠偆丅偦偺偙偲偼丄偡偱偵1975擭偵丄償僃僩僫儉妚柦偺彑棙偑幚慔揑偵柧帵偟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅偙偺彑棙偵傛偭偰惉棫偟偨摑堦償僃僩僫儉偼丄傑偝偵幮夛庡媊償僃僩僫儉偱偁傝丄償僃僩僫儉妚柦偲偼瓊葌瓊苽鄡C儞僪僔僫妚柦偲晄壜暘側崙嵺庡媊揑側柉懓夝曻幮夛庡媊妚柦偲婯掕偟偆傞偟丄傑偨婯掕偡傋偒妚柦偱偁偭偨丅偦傟偼丄偄傢偽乽柉懓庡媊傪妚柦偡傞柉懓庡媊乿丄乽悽奅妚柦揑柉懓庡媊乿偺奐巒偱偁偭偨丅偙傫偵偪偺宱嵪帺棫偼丄乽拞怱乿偲偔偵悽奅婇嬈偺宱嵪揑巟攝偲懳寛偟丄偦傟傪堦憒偣偞傞傪偊側偄偲偄偆堦揰偐傜偩偗偱傕丄傕偼傗柉懓帒杮庡媊偺帺惗揑敪揥偱偼偁傝偊偢丄幮夛庡媊揑幮夛曄妚傪昁慠揑偵偲傕側偆偲偄偆偙偲偼丄偙偺傛偆側柉懓帺寛偺撪梕曄壔偵懳墳偡傞丅乽柉懓帺寛偐丄幮夛庡媊妚柦偐乿偲偄偆愝掕偼丄柍堄枴偲尵偆傎偐側偄丅
乮擇乯偵偮偄偰偼丄乽廃曈乿帒杮庡媊偺惈奿偑偁偒傜偐偵偝傟傞偙偲偼丄偐偮偰偺攦曎帒杮庡媊偺婯掕埲忋偺廳梫側堄媊傪扴偭偰偄傞丅偦傟偼丄嶻嬈僽儖僕儑傾僕乕偱偁偭偰傕E婇嬈偺宯楍偵摑崌傑偨偼廬懏偡傞僽儖僕儑傾僕乕偱偁傝丄乽拞怱乿僽儖僕儑傾僕乕偲堦掕搙偺棙奞偺懳棫柺傪傕偪偮偮傕顤{揑偵偼柉懓帺寛乗宱嵪帺棫傪扴偄偆傞傕偺偱偼側偄偱偁傠偆丅偦偆偱偁傞偲偡傟偽丄乽掅奐敪乿崙撪偱偺亙拞怱亅廃曈亜娭學偵偼廫擇暘偵棷堄偟側偔偰偼側傜側偄偑丄壓憌擾柉丄旐梷埑彮悢柉懓丒垷柉懓丄嶨嬈嵶柉憌側偳偺嵟乽廃曈乿偲楯摥幰奒媺偲傪偙偲偝傜偵懳棫揑偵晍抲偡傞傑偱傕側偄偱偁傠偆丅傕偪傠傫J摥幰奒媺傪棙偟偰偄傞強摼悈弨偺奿嵎偺栤戣偼偁傞偟丄懡暘偵乽嫟摨懱揑乿側嵟乽廃曈乿偲搒巗壔偝傟偨楯摥幰奒媺偲偺抐憌偺栤戣傕偁傞丅偟偐偟丄婎杮揑偵偼丄娞梫側偺偼丄楯摥幰奒媺偲傑偝偵慡恖柉揑婋婡乗乗慡恖柉揑曄妚偺梫場偲偟偰偺柉懓栤戣偲偺娭學偱偁傝丄幮夛庡媊揑柉懓摑堦愴慄偺宍惉偱偁傞丄偲峫偊傜傟側偄偱偁傠偆偐丠丂傕偪傠傫眰虛_偼丄愴弍揑婲敋栻偲愴棯揑鄖栻偲偺娭學偲摨堦帇偝傟偰偼側傜偢丄暥帤偳偍傝嬶懱揑側奒媺暘愅傪昁梫偲偟傛偆丅
乮嶰乯偵偮偄偰偼丄乽拞怱乿偺楯摥幰奒媺偲乽廃曈乿偺旐嶏庢恖柉偲偺棙奞偺摨堦惈丄柍忦審楢懷偺昁慠惈偲偄偆丄偄傢偽乽恄榖乿偼寛掕揑偵婞偰傜傟側偔偰偼側傜側偄偱偁傠偆丅乽拞怱乿偺巟攝幰偲乽廃曈乿偺偦傟偲偼摨惗嫟巰偱偁傞偲偟偰傕丄乽拞怱乿偺旐巟攝幰偲乽廃曈乿偺偦傟偲偱偼丄宱嵪揑棙奞偼墲乆側偄偟偼奣偟偰懳棫偡傞偲峫偊偰偍偄偨曽偑柍擄偱偁傠偆丅偙偙偵偲偔偵悽奅婇嬈偺姰慡彾埇壓偵偁傞乽廃曈乿偺宱嵪帺棫偵偨偄偡傞乽拞怱乿偺楯摥幰奒媺偺柍棟夝傑偨偼揋堄偲偄偆崲擄側忈暻偑偁傞丅応崌偵傛偭偰偼丄儗乕僯儞偑乽僗僀僗掗崙庡媊乿偵偮偄偰暘愅偟偨傛偆偵丄乽拞怱乿崙撪偱偺乽廃曈乿弌恎楯摥幰偺嶏庢丄楯摥幰奒媺撪偺柉懓揑埵奒峔憿偺栤戣偑廳戝壔偟偆傞丅偨偑u悽奅婎弨偱偺拁愊乿偺傕偲偱偼丄帺慠敪惗揑側宱嵪揑懳棫偼偐側傜偢偟傕婎杮揑側奒媺懳棫偱偼側偄丅乽悽奅婎弨偱偺曄妚乿偵岦偗偰惌帯揑偵帺妎偟偨楯摥幰奒媺偼丄暘恑崌寕偺側偐偐傜崙嵺庡媊揑奒媺楢懷偺娐傪偮偐傒偲傝偆傞偱偁傠偆丅栤戣偼傓偟傠丄乽拞怱乿崙楯摥幰奒媺偺媅帡乽柉懓嫟摨懱乿揑懱惂撪摑崌丄乽柉懓僾儘儗僞儕傾乕僩乿壔偺峌寕傊偺懳墳偱偁傞丅
乮巐乯偵偮偄偰偼丄宍懺偲偟偰偼夁搉揑側楢朚惂傑偨偼偦傟偵嬤偄楢崌偟偐峫偊傜傟側偄偱偁傠偆丅偟偐偟丄楢朚惂偺傕偲偱亙拞怱乗廃曈亜娭學偑寖壔偡傞椺偼枃嫇偵壣偑側偔丄寢崌乗乗梈崌傊偲愙嬤偡傋偒乗乗偺尨棟偼丄偄偐偵偟偰帺棫揑丒帺寛揑楢崌偑壜擻偐丄偲偄偆揰偱峔抸偝傟側偔偰偼側傜側偄偱偁傠偆丅偦傟偼丄崻掙揑偵偼丄崙壠巰柵偐傜柉懓巰柵傪傑偱揥朷偡傞尨揰偱傕偁傞丅杮棃丄柉懓側偄偟垷柉懓廤抍偲偼丄偦偺搒搙奺廤抍偺壓偐傜偺僀僯僔傾僥傿償偲偟偰偺帺寛亖帺屓尃椡偺尨棟偑妋擣偝傟側偔偰偼丄偨偲偊幮夛庡媊偺柤偵抣偄偡傞幮夛庡媊懱宯偺傕偲偱偁偭偰傕丄斲丄偦偺傛偆側懱宯偺傕偲偱偙偦丄姰慡側摨尃偵傕偲偯偔柉懓側偄偟旕摍幙揑幮夛廤抍偺帺棫揑側丄帺桼側楢崌偑桳婡壔偝傟偆傞偱偁傠偆丅
丂埲忋偼丄拪徾揑側師尦偱偺栤戣採婲偱偟偐側偄丅宱嵪帺棫偑娷拁偟悇恑偡傞惌帯揑壽戣偼丄傛傝嬶懱揑側師尦偱傑偝偵暋嶨懡條偱偁偭偰丄偦傟偧傟嬶懱揑偵暘愅偝傟丄嬶懱揑偵夝寛偝傟側偔偰偼側傜側偄丅偩偑丄宱嵪帺棫偼丄偦傟偲妚柦傗撈棫偲偺慜屻娭學丄婯掕娭學傪榑偢傞偙偲偵傑偝偭偰丄旐梷埑柉懓偺惌帯揑旘桇偺搚戜傪惂栺偟丄悽奅揑偵偼彅柉懓偺暯摍側楢崌偺暔幙揑婎斦傪桳偡傞傕偺偱偁傞偙偲偑丄堦崗傕朰傟傜傟偰偼側傜側偄偱偁傠偆丅乮昅幰丒尰戙宨婥尋媶堳乯
亙曗榑亜
壂撽帺棫偺巚憐亅愳枮怣堦巵偺乽嫟摨懱榑乿偵偮偄偰亅
丂帺棫宱嵪榑媍偺拞偵偼擖傝偵偔偄偐傕抦傟側偄偑丄峀偔壂撽偺帺棫偺栤戣偵偮偄偰榑偠偨傕偺偲偟偰尒偺偑偣側偄偺偼丄愳枮怣堦巵偵傛傞乽嫟摨懱榑乿偺採婲偱偁傞丅
丂偄傢備傞斀暅婣攈抦幆恖偺70擭戙弶摢偵偍偗傞懚嵼偼旕忢偵戝偒側傕偺偑偁偭偨偑丄72擭暪崌偐傜75擭崰偵帄傞偦偺惌帯揑側姰惉偺拞偵偁偭偰丄斀暅婣攈抦幆恖偺敪尵偼丄傗傗偦偺検傪尭偠偰偒偰偄傞偲巚傢傟傞丅偑愳枮巵偺乽嫟摨懱榑乿偼偦偙偵偍偗傞嬯摤偐傜堦曕敳偗弌偰丄壂撽偺帺棫偺栤戣傪偦偺巚憐揑儗儀儖偐傜柾嶕偟偨傕偺偲偟偰婱廳側傕偺偲偄傢側偔偰偼側傜側偄丅
丂巵傕偄傢傟傞傛偆偵丄愘懍傪攔偟曕堦曕恑傔傜傟側偔偰偼側傜側偄嫟摨懱榑偺柾嶕偵偍偄偰丄愭憱偭偨尵媦傪峴偆偙偲偼偁傑傝傛偄偙偲偱偼側偄偩傠偆偟丄傑偨帺棫偺巚憐傪扵傞復偵懳偟偰丄壂撽帺棫偺尰幚揑揥朷傪栤偆偙偲偼揔摉偱偼側偄偐傕抦傟側偄丅偟偐偟丄帺棫宱嵪榑媍側偳偺宍偱壂撽偺帺棫偺栤戣偑恀寱偵峫偊傜傟偰偄傞帪偵丄嫟摨懱榑偺傛偆側帇妏偐傜偺傾僾儘乕僠偑丄傂偲偮晄壜寚偱偁傞偲偄偆偙偲傪妋擣偟偰丄偄傢偽偙偺尰幚偐傜偺嬞媫惈偲偄偆偙偲偵偍偄偰丄愳枮巵偺強榑傪偁偊偰偲傝偁偘偰傒偨偄偲巚偆丅
侾
丂巵偺栤戣愝掕丄栤戣堄幆偼丄乽嫟摨懱榑乿乮忋乯偺偼偠傔偵弎傋傜傟丄傑偨乮壓乯偺朻摢偵嵞愢偝傟偰偄傞丅偦傟偼丄楯摥幰奒媺偺摤偄偺娤擮揑嬻揮丄寢壥偲偟偰偺懱惂撪壔乮崙壠巙岦偁傞偄偼儅僀儂乕儉庡媊乯傪挻崕偡傞帇揰傪媮傔偰丄柉廜榑傊偲暘偗擖傝丄偦偺柉廜偺尰懚偺婎慴傪扵傞偨傔偵丄偝傜偵柉廜偺弌帺偨傞搰乆偺懞棊嫟摨懱偺懳徾壔傪巙偡偲偄偆偲偙傠偐傜偼偠傑傞丅
丂偟偐偟丄巵偼偦偺懞棊嫟摨懱偺楌巎揑側曄慗傪愓偯偗傞偲偄偆曽朄傪偲傜偢丄偦偺曄慗偺偁傝曽傪扵傞丅偡側傢偪乽偦偺傛偆偵偁傜傔偟偨晄壜帇偺梫慺偲丄娐嫬偲偟偰偺彅忦審傪扵傝丄傢傟傢傟偺尰幚偺懚嵼偺婎慴傪惉偟偰偄傞僄乕僩僗傪懳徾壔偡傞偲偄偆曽朄傪偲傞乿丅偦偟偰巵偼丄偙偺僄乕僩僗傪懳徾壔偡傞嶌嬈偵偍偄偰丄搶峕暯擵偺怱棟妛揑傾僾儘乕僠傪攔偟丄怴愳柧巵偺桞暔榑揑帇揰晄懌傪偄偄壀杮宐摽巵偺乽嫟摨懱偺惗棟丄堄幆乿偲偦傟偵壛偊傜傟傞帺慠揑丒幮夛揑彅忦審偲偺娭學偺愢傪摫偒偲偡傞丅
丂偦偺壓偵巵偼丄戞堦偵嫟摨懱偺恄乆偺栤戣丄戞擇偵憂悽恄榖偺栤戣丄戞嶰偵偦傟偲娭楢偟偰棾媨丄僯儔僀僇僫僀偺愢榖丒揱愢偺栤戣傪偲傝忋偘丄偦傟傜偲嫟摨懱偺偁傝曽偲偺娭學惈傪暘愅偟偰偄偔丅偦偟偰偙傟傜恄榖丒揱愢乮偦偟偰嫲傜偔偼嫟摨懱偺恄乆傕乯偺壢妛揑帇揰偐傜偡傞夝懱偵傛偭偰丄嫟摨懱惉堳偺怺晹偺僄乕僩僗傪媯傒弌偟丄傕偭偰怴偨側嫟摨懱偺憂憿偵帒偡傋偒偲庡挘偡傞丅
丂傕偪傠傫丄巵偺揥奐偼偙偙偵偲偳傑傜側偄丅尰幚偺嫟摨懱偺僄乕僩僗偲偟偰偺乽嫟惗乿巙岦偑搒巗僾儘儗僞儕傾偺曄妚巙岦偲偄偐偵愗傝寢傇偺偐偲偄偆揰偵尵媦偟丄偄偭偨傫偼丄乽帒杮庡媊偵婎偯偔擾抧巹桳惂傪傕偆堦搙壗傜偐偺宍偺嫟桳惂傊曄妚偟丄奺扨埵偺嫟摥慻怐傪妋棫偟偰偄偔丄嬶懱揑側僗働僕儏乕儖偑採埬偝乿傟傞傋偒偲採婲偡傞丅偑巵偼丄偙偙偵偁偒偨傜偢丄偝傜偵乮壓乯偵偍偄偰丄嫟摨懱偺撪嵼揑側曄妚棩傪墴偝偊側偑傜丄曄妚偺帪傪寎偊偰偄傞尰幚偺嫟摨懱偺書偔柕弬傊偲壓岦偣傫偲偡傞丅偦偺幉偼偄傢偽梸朷榑偵抲偐傟偰偄傞偲巚傢傟傞偑丄巵偺榑朜傕偙偙偵帄偭偰嬯摤偺怓傪懷傃丄偝傜側傞柾嶕偺昁梫惈傪嫮挷偟偮偮丄揮奐偡傞丅
丂偙偺傛偆側乽嫟摨懱榑乿偺杮嬝傪娧偄偰偄傞傕偺偼偄偆傑偱傕側偔丄尰嵼偺壂撽偵偍偗傞嫟摨懱乮偦偺廆嫵揑尪憐惗妶椣棟乯偺妋屌偨傞懚嵼偵懳偡傞巵偺妋怣偱偁傞丅偦傟偼丄乽妋怣乿偲昞尰偡傞偺傕溳傜傟傞傛偆側丄帠幚偦偺傕偺偺採帵偱偁傞偐傕抦傟側偄丅榑幰偼偙偙偵偍偄偰偼丄巵偺愢偔強傪彸擣偡傞埲奜偺偡傋帩偨側偄丅偑丄72擭乽曉娨乿慜屻偺夁掱偵偍偄偰壂撽楯摥幰奒媺偺僿僎儌僯乕偑攕杒揑側傕偺偱偁偭偨偙偲偑妋擣偝傟丄壂撽偺曄妚亅帺棫偺庡懱偑傛傝僩乕僞儖側帇栰偐傜嵞峫偝傟偹偽側傜側偄尰嵼丄嫟摨懱傊偲暘偗擖偭偨峫嶡偑昁梫偱偁傞偲偄偆榑偺奜榞偼廫暘偵椚夝偝傟傞偺偱偁傞丅巵偺嫟摨懱榑傊偺摓払偼丄壂撽偺曄妚亅帺棫傊岦偗偰偺棟榑嶌嬈偺拞偵偍偄偰丄戝偒側慜恑偱偁傞偲偄傢側偔偰偼側傜側偄丅
丂偟偐偟丄巵偼嫟摨懱偺栤戣傪曄妚亅帺棫偺尰幚揑揥朷偵偍偄偰傕偭傁傜榑偠偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偦偺傛偆側尵媦偼悘強偵偁傝丄傑偨偙偺榑偼嵟廔揑偵偼摉慠偦偙傊偄偒偮偔傕偺偱偁傞偑丄巵偼嫟摨懱偺栤戣傪巚憐偺儗儀儖偐傜庢傝忋偘傞偙偲傪戞堦偵偟偰偄傞丅
丂巚憐偺儗儀儖偐傜嫟摨懱偺栤戣傪庢傝忋偘傞応崌丄偦偺悥偔曽岦偼擇偮偁傞偲巚傢傟傞丅堦偮偼嫟摨懱偲偮側偑傞抦幆恖偺巚憐傪偄偐偵偆偪棫偰傞偺偐丄偲偄偆曽岦惈偱偁傝丄擇偮偵偼丄嫟摨懱帺懱偺巚憐乮廆嫵揑尪憐丄惗妶椣棟乯傪偄偐偵敪孈偟偰丄柉廜揑儗儀儖偵偍偗傞怴偟偄嫟摨惈偺憂憿偵帒偟偰偄偔偺偐丄偲偄偆栤戣偱偁傞丅乮屻幰偼摉慠偵傕丄偄傢偽暥壔揑側摤偄偺栤戣偱偁傝丄曄妚亅帺棫偺尰幚揑揥朷偲捈愙偵寢傃偮偔傕偺偱偁傞偑丄摉柺丄嫟摨懱偺桳偡傞巚憐偲偟偰偄偐側傞傕偺傪敪孈偟偆傞偺偐丄偲偄偆偲偙傠偵壽戣傪桳偡傞傕偺偱偁傞丅乯
俀
丂戞堦偺抦幆恖偺巚憐偺妋棫偲偄偆揰偼丄巵偺揥奐偵偍偄偰傕偄傢偽暃嬝偲側偭偰偍傝丄榑幰傕慡柺揑偵偲傝忋偘傞傢偗偵偼偄偐側偄丅偑丄壂撽偺曄妚偺庡懱傪傛傝僩乕僞儖側帇栰偐傜嵞峫偡傞偲偟偨応崌丄壂撽抦幆恖榑偺栤戣偼旕忢偵廳梫偲峫偊傜傟傞偺偱庒姳弎傋偰傒偨偄丅
丂巵偼丄壂撽抦幆恖偺乽孾栔偲偄偆嫟捠偺僗僞僀儖乿偵偮偄偰偺婱廳側帵嵈傪偟丄偦偺桼偭偰棃偨傞偲偙傠傪峫嶡偟偮偮丄亀帺棫偺巚憐亁偲乽懳徾偲偟偰偺柉廜傑偨偼嫟摨惈偦偺娭傢傝偵偮偄偰師偺傛偆偵偄偆丅乽偦偺帺慜偺巚憐偼娭學偲偟偰偺尰幚傪懳徾偲偟偰丄偦傟偲偺實暿丄妘棧丄暘愅偲偄偆巚峫丄忣擮偺椡妛娭學傪捠偟偰偟偐嶻弌偱偒側偄傛偆側楌巎揑忦審偵傢傟傢傟偼婯掕偯偗傜傟偰偄傞偲巚偆丅偡傞偲丄偙偺搰乆偱丄恖乆偑偁傞帪偼嗦抭傪傕偭偰懳張偟偁傞帪偼傂偨偡傜偵偆偢偔傑傝丄傑偨偁傞帪偼噣巰庣乭偟斀峈偟側偑傜丄偦偺楌巎夁掱偱偮偔傝惉偟偰偒偨堄幆丄姶惈偺僄乕僩僗丄偁傞偄偼暥壔偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕傪偳偆偮偐傒弌偡偐偑丄偦偺巚憐偺惗柦偺寛傔庤偵傕側傞丄偲偄偊傞丅乿
丂乽實暿乿乽妘棧乿偲偄偆偙偲偲丄乽暘愅乿偁傞偄偼偮偐傒弌偟偲偄偆偙偲偲偺丄偄傢偽曎徹朄揑側娭學傪偄傢傫偲偟偰偄傞傢偗偱偁傞偑丄偙偙偱堦峫偟側偔偰偼偄偗側偄偙偲偼丄偦偺乽暘愅乿偁傞偄偼偮偐傒弌偟偑壥偟偰壜擻偐丠偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅傕偪傠傫偄偐側傞儗儀儖偺傕偺偱偁傟丄偮偐傒弌偡偲偄偆偙偲偼壜擻側偺偱偁偭偰丄栤戣偼惓摉惈丄晛曊惈偁傞傕偺傪偮偐傒弌偟偆傞偺偐丠偲偄偆偙偲偱偁傞丅
丂榑幰偼晄壜抦榑傪偲傞傢偗偱偼側偄偺偱丄偦傟偑壜擻偱偁傞偲偡傞傕偺偱偁傞丅偑丄偦偙偵偍偄偰偮偐傒弌偝傟偨寢榑偑丄巚憐偺惗柦偺寛傔庤偲側傝偆傞偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼丄夰媈揑偨傜偞傞傪偊側偄丅壗屘側傜偦偙偱偼傕偭偲傕曪妵揑側弎梘偝傟偨寢榑丄敿偽壢妛偲偟偰偺偦傟偑採帵偝傟傞偺偱偁偭偰丄巚憐偺惗柦傪晩妶偡傋偒崿撟偼幐傢傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅榑幰偵偼丄壀杮巵偺嫟摨懱偺惗棟丄堄幆偵偮偄偰偺愢傊偺埶嫆丄偦偙偵偍偗傞乽嫟惗乿巙岦偺拪弌傕丄偙偺傛偆偵巚偊偰側傜側偄丅
丂偱偼丄壂撽抦幆恖偺帺棫偺巚憐偼丄柉廜偺僄乕僩僗偐傜巚憐揑側壗傕偺傕媯傒弌偟偊側偄偺偱偁傠偆偐丠
丂偦傟偵偮偄偰偼丄抐屃偲偟偰斲偲摎偊側偔偰偼側傜側偄壗屘側傜丄偦偺傛偆側棳楬偼抦幆恖偺柉廜偺拞偵偍偗傞幚慔偵傛偭偰愗傝戱偒偆傞偐傜偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺幚慔揑棳楬偵偍偄偰傑偨丄抦幆恖偺巚憐傕戝廜傊偲怤摟偟丄偦偙偵偍偄偰偼偠傔偰丄巚憐偺惗柦偲偄偆傕偺傕妉摼偝傟傞偺偱偁傞丅偙偆峫偊偰偄偔偲乽實暿丄妘棧丄暘愅偺椡妛娭學傪捠偟偰偟偐亙巚憐亜嶻弌偱偒側偄傛偆側楌巎揑忦審乿偵偁傞偲偄偆巵偺擣幆偑栤戣偲側傠偆偑丄偙偺偙偲偵偮偄偰偼丄偟偽傜偔巵偺揥奐傪懸偮偟偐側偄丅
丂埲忋偺偙偲傪堦斒榑側偑傜傕偍偝偊傞偲偡傟偽丄嫟摨惈偲抦幆恖偲偺娭傢傝偵偍偄偰丄傕偆堦曕抦幆恖榑偺曽偑怺傔傜傟傞傋偒偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅偄傢偽庡懱偺栤戣偲偟偰抦幆恖偺栤戣傪堷偒偮偗傞偺偱偼側偔丄媞懱偲偟偰偺抦幆恖偺巚憐偲峴摦傪偮偒曻偡偙偲偱偁傞丅
丂偙偺傛偆側抦幆恖榑偺怺壔偼丄摉慠偵傕峀偄堄枴偵偍偗傞惌帯偺師尦傪偔偖傞傕偺偱偁傞偑屘偵丄偦傟偼傑偨丄壂撽偺曄妚亅帺棫偺庡懱偺嵞峫偲偄偭偨嶌嬈傪傕捈愙偵棙偡傞傕偺偱偁傞偼偢偱偁傞丅
丂偙偺怺壔丄偮偒曻偟偼丄傑偢懳徾偲偟偰偺壂撽抦幆恖偺奣擮偺奼挘丄嬶懱壔偵偐傜偼偠傑傞偱偁傠偆丅偦偺揰偱偼巵偺乽壂撽偱堦掕偺抦揑側儗儀儖偵払偟偨傕偺乿偲偄偆婯掕偑惛枾壔偝傟傞傋偒側偺偱偁傞乮偙偺婯掕帺懱偼抐慠惓偟偄偑乯丅懞乆偺柤朷壠憌丄嫵堳憌摍乆偺惗棟偐傜丄奺惌搣惉堳偺巙岦傑偱偑夝柧偝傟偹偽側傜側偄偺偱偁傞丅偦偟偰丄偦偺壥偰偵壂撽抦幆恖偺摿惈偲偱傕偄偆傕偺偑尒摟偐偝傟傞偲偡傟偽丄偦傟偼婛惉偺抦幆恖榑偺揔梡偐傜偱偼側偔丄擔杮偝傜偵偼拞崙丄挬慛偺抦幆恖偲偺尩枾側懳斾偺拞偐傜尰傢傟偰偔傞傕偺偱偁傞偵偪偑偄側偄丅
丂偲傕偐偔丄偙偺傛偆偵抦幆恖榑傪峔憐偡傞拞偵偍偄偰丄嫟摨懱僄乕僩僗偲抦幆恖偲偺尰幚揑側娭傢傝崌偄傕晜傃忋偑偭偰偔傞偼偢偱偁傞丅
俁
丂乽偙偺搰乆偱丄恖乆偑偮偔傝惉偟偰偒偨堄幆丄姶惈偺僄乕僩僗丄偁傞偄偼暥壔偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕乿傪丄堦墳乽嫟惗乿巙岦偲偟偰墴偝偊偨忋偱丄巵偼丄偦偺乽嫟惗乿巙岦偦偺傕偺偑杮幙揑偵奜揑忦審偺曄悢偵傛偭偰條乆偵揥奐偡傞傕偺偱偁傞偑屘偵丄嫟摨懱偺奜棃暥壔傊偺懳墳偺巇曽偵僗億僢僩傪摉偰傛偆偲偡傞丅偟偐偟丄偦偺懳墳偺巇曽傕乽懞棊嫟摨懱偺楌巎夁掱偐傜幚徹揑偵夝柧乿偟偰峴偔嶌嬈偼峴傢傟偢丄傓偟傠巵偺峴榑偼丄嫟摨懱偺恄乆偺懚嵼偺巇曽偺栤戣偐傜憂悽恄榖丄愢榖丄揱愢偺栤戣傊偲丄偄傢偽嫟摨懱僄乕僩僗傪捈愙揑偵媮傔偰偄偔曽岦傪偲傞丅丂偙偙偵偍偄偰丄朻摢弎傋偨嫟摨懱榑偺巚憐揑側揥奐偑偍傕傓偐偣偞傞傪偊側偄戞擇偺曽岦丄偡側傢偪嫟摨懱僄乕僩僗傪偮偐傒弌偡偙偲偵傛偭偰捈愙揑偵怴偨側嫟摨惈偺憂憿偵帒偟偰偄偔偲偄偆曽岦偑奐偗偰偔傞偺偱偁傞丅
丂戞堦偺嫟摨懱偺恄乆偺懚嵼偺巇曽偵娭偡傞峫嶡偼丄恄乆偺懚嵼偲嫟摨懱惉堳偺懚嵼偲傪娧偔摨埵奣擮傪偄偭偰丄偝傜偵乽嫟惗乿巙岦偺暎尮偺巜揈偵媦傃丄傕偭偲傕惉岟偟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅偟偐偟丄戞擇偺憂悽恄榖偺峫嶡偵偍偄偰偼丄嫟摨懱偺敪揥抜奒偺娤揰傪嫮挷偡傞梋傝丄抝彈懳偺憂悽恄榖偵偮偄偰偄偒偡偓偨嵸抐乮抝彈懳偺憂悽恄榖偑偡傋偰惌帯揑尃椡丒廆嫵揑尃埿丒惈揑嬛婖偑旛傢偭偨幮夛偺嫊峔偱偁傞偲偄偆乯傪峴偭偰偄傞偐偵巚傢傟傞丅巹尒偵傛傟偽丄抝彈懳偺恄榖揑側憐掕偼懢暯梞偺搰乆偺憂悽恄榖偵晛曊揑偵傒傜傟傞偲偙傠偱偁傝丄栤戣偼傕偭傁傜偦偺抝彈懳偺偲傞埵憡偺偄偐傫偵偁傞偲峫偊傜傟傞丅
丂巵偺媨屆搰偺憂悽恄榖偺堷梡偵懳偟偰丄敧忎搰偺憂悽恄榖傪傒偰傒傛偆丅埥帪戝奀鄋偁偭偰泂傒偨傞彈偺傒偑擄傪偺偑傟偰丄偦偺彈偺嶻傒棊偲偟偨傞巕嫙偑岾偵抝巕偱偁偭偨偑屘偵丄曣巕晇晈偲側傝丄恖偺庬傪揱偊丄斏傜偟傔偨偲偄偆僞僫汷揱愢偱偁傞丅僀僓僫僊丒僀僓僫儈偺恄榖偵懳偟偰偙偺傛偆側屆宍偺傕偺偑擔杮偵偁傞偙偲偼嬃偔傋偒偙偲偱偁傞偑丄偙偺恄榖偺摿挜偼丄戞堦偵憂悽偵乽恄偟偐娭梌偟側偄偙偲丄偮傑傝戝攋柵偵愭傫偢傞嫟摨懱偺懚嵼傪慜採偲偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偙傟偱偼憂悽恄榖偵側傜偸偲傕偄偊傞偑丄偦傟偼恖抭偑奐偗偨屻偺峫偊曽偱偁偭偰丄屆杙側傞惛恄偵偲偭偰偼丄憐憸傪愨偡傞梱偐側愄偐傜楢慄偲懕偄偰偒偨嫟摨懱惗妶偺偦偺巒尮傪恞偹傞偙偲偼側偐側偐偵梕堈側偙偲偱偼側偐偭偨偺偱偁傞丅嫮偄偰偦偙偵摜傒崬傔偽丄憂悽恄榖偼捁傗嫑偺強堊丄憪栘偺壔惗傪愢偔帺慠恄榖偺拞偵梟偗偙傫偱偄偭偨偼偢偱偁傞丅偙偺恄榖偺戞擇偺摿挜偼偄偆傑偱傕側偔惈揑僞僽乕偑屭椂偝傟偰偄側偄揰偱偁傞丅巵偺弎傋傞孼枀寢崌偺宆傛傝傕恟偟偔丄偙偺曣巕寢崌偺宆偑傛傝屆憌偵埵抲偡傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅
丂偙偺傛偆偵丄偙偺庬偺憂悽恄榖偵偍偄偰偼丄曣巕寢崌偺宆乮晝巕寢崌偺宆乯丄巓掜丒孼枀寢崌偺宆丄巓掜丒孼枀偺偦傟傪乽恄乿偑帵尰偟偰傢偞傢偞彸擣偡傞宆乮巓掜丒孼枀寢崌傪偄偲偆嫟摨懱偺斀塮偱偁傞乯丄摍乆偑懚嵼偡傞乮擮偺偨傔偵偄偊偽丄偙偙偵偍偗傞寢崌偼堦懳堦偺懳寢崌偲偼尷傜側偄乯丅抝彈懳偺恄榖揑憐掕傪嫟摨懱偺敪揥抜奒偲寢傃偮偗傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偁偭偰丄偦偺抝彈懳偺埵憡偑偦偺斀塮側偺偱偁傞丅
丂憂悽恄榖偵尷傜偢丄壂撽偵偍偄偰偼恄榖偼偲傝傢偗壢妛揑側夝懱偺懳徾偱偁傞偺偐傕抦傟側偄丅巵傕偄偆偛偲偔丄恄榖傪婰嵹偡傞壂撽偺暥專偼旕忢偵怴偟偄偑屘偵丄婔憌偵傕傢偨偭偰嶌堊偝傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅暥專婰榐偺壢妛揑夝懱傪峴偆堦曽偱丄岥旇揱愢偺椶偐傜巆曅傪偡偔偄偲傝丄傑偨峀偔傾僕傾丒懢暯梞偺恄榖偲偺懳斾傪峴偭偰偄偔偙偲偼丄戝晹暘偑崱屻偺帠嬈偲側偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅
丂偙傟傜偺嬯摤偺拞偐傜丄怴偨側嫟摨惈憂憿偺偨傔偺椘傪偐偪偲偭偰偄偔巇帠偼丄偦偺傑傑暥壔揑側摤偄偱偁傞偲偄偆偙偲偼丄偡偱偵弎傋偨丅堦斒偵暥壔揑側摤偄偼丄帺棫偺偨傔偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕傪妉摼偡傞偨傔偵戝偒側堄媊傪桳偟偰偄傞丅彅乆偺恖柉偺帺棫亅帺寛偺塣摦偺拞偵偁偭偰丄婔懡偺峌惃揑側暥壔暅嫽偺塣摦偑偁偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅
丂偦偆偟偨娤揰偐傜傒偨応崌丄堦揰栤戣偲偟偰偍偔傋偒偙偲偼壂撽偵偍偗傞尵岅偺栤戣偱偁傠偆丅巵偺峴榑偺拞偵偼搊応偟側偄偑丄嫟摨懱偺尵岅偲偄偆偙偲偼嫟摨懱榑偵偲偭偰柍帇偱偒偸梫慺偱偁傞偼偢偱偁傞偟丄傑偨堦斒偵帺棫亅帺寛偺塣摦偺拞偵偍偄偰傕丄偦偺愯傔傞斾廳偼偼側偼偩崅偄丅椺偊偽丄偐偮偰傾僀儖儔儞僪偺撈棫摤憟偺拞偵偍偄偰偼丄僟僌儔僗丒僴僀僪摍偺僎乕儖岅偵傛傞暥寍暅嫽偺塣摦丄乽僎乕儕僢僋楢柨乿偵傛傞僎乕儖岅嫵堢偺塣摦偑偁偭偨丅乮偙偙偵偍偄偰偼丄巆擮側偑傜丄夵傔偰妛峑傪奐偄偰嫵偊偹偽側傜偸傎偳丄僎乕儖岅偼悐旝偟偰偄偨偺偱偁傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄傾僀儖儔儞僪恖偼彂暔偲妛峑偲偄偆嬤戙偺擇戝庤抜傪梡偄偰昁巰偵僎乕儖岅偺巰柵傪杊偄偩偺偱偁傞丅乯
丂榑幰偼偙偺栤戣偱徻榑偟偆傞帒奿傪帩偨側偄偑丄惓捈偄偭偰丄妛栤揑側椺徹傪廳偹側偗傟偽乽摨堦尵岅乿偨傞偙偲傪嫮曎偟偊偸擔杮岅偵傛偭偰丄壂撽岅偺拞偵惙傝偙傑傟偰偒偨姶惈丄悽奅娤傪戙懼偟偆傞偲偼怣偠傜傟側偄偺偱偁傞丅
係
丂巵偺乽嫟摨懱榑乿偼偙偺傛偆偵巚憐揑儗儀儖偵偍偄偰揥奐偝傟傞偑丄巵偺榑朜偼寛偟偰偦偙偵偼偲偳傑傜偢丄曄妚亅帺棫偺尰幚揑揥朷傊偲愨偊偢壓崀偣傫偲偡傞丅偙偙偵偙偦巵偺巚峫愭恑惈偑偁傞偲巚傢傟傞偺偱偁傞丅
丂偙偺巵偺巚峫偺摫偒偺巺偲側偭偰偄傞偺偑丄乽嫟摨懱榑乿傪娧偄偰懚嵼偡傞師偺傛偆側擇幰戰堦偱偁傠偆丅
丂乽偙偺搰乆偺懞棊嫟摨懱偺柉廜姶惈傊岦偗偰丄徴寕傪偮偔傝偩偟丄帒杮庡媊偺娮鈜傪堦嫇偵傑偨偄偱幮夛曄妚傊偲旘隳偡傞嫟摨懱偺尪憐傪傂偒弌偡偐丄偁傞偄偼幮夛堄幆偺暘妽偲傾僩儉壔傪恑傔丄儓乕儘僢僷帒杮庡媊幮夛壓偺丄帺変堄幆偺妋棫偲嬯摤傑偱恑傫偱丄偦偙偐傜乬嬤戙挻崕乭偺壽戣傪堷偒庴偗偰偄偔偐丄偲偄偆巚憐偵偍偗傞丄柉廜傊偺傾僾儘乕僠偺暘婒偑栤傢傟偰偔傞丅乿
丂偙偙偱偼巚憐偵偍偗傞傾僾儘乕僠偲偝傟偰偄傞偑丄偙偺擇幰戰堦偐丄屻抜丄擾抧巹桳惂偺嫟桳惂傊偺曄妚丄嫟摥慻怐偺嵞妋棫偲偄偆傗傗僫儘乕僪僯僉揑側揥朷傊偲傎偲偽偟傝弌傞偙偲偼丄朻摢徯夘偟偨捠傝偱偁傞丅埲壓丄偙偺擇幰戰堦偵偮偄偰峫偊偰傒偨偄丅
丂巵偺嫟摨懱傊偺搳擖偑丄堦扷曄妚偺栤戣偲寢傃偮偄偨応崌偵丄偙偺傛偆側擇幰戰堦偑惗婲偟偰偔傞偙偲偼榑棟揑昁慠偱偁傞偑丄偙偙偵偍偄偰偼傕偆堦曽偵丄巵偺乬嬤戙乭偲偄偆傕偺偵懳偡傞撈摿偺尒峔偊曽偑愙崌偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅乽嬤戙偺挻崕乿偲偄偄丄偦傟傪乽悽奅偑摍偟偔捈柺偟偰偄傞岺嬈壔幮夛偺柕弬挻崕乿偱偁傞偲偡傞傂偲偮偺晛曊庡媊偱偁傞丅
丂堦斒偵僫僔儑僫儖側揥朷偺捛媮偵偍偄偰丄偙偺傛偆側晛曊庡媊偺娤揰傪寢崌偝偣傞偙偲偼傓偢偐偟偄栤戣偱偁傞丅偦偺憃曽偼捈愙揑偵偼寢崌偟側偄偲偄偭偰傕傛偄偱偁傠偆丅惣墷丒擔杮傪偼偠傔偲偡傞乽嬤戙乿偵懳偟偰丄乬旕嬤戙乭偲偟偰偺壂撽偑懳抲偝傟傞偲偟偨傜丄偦傟偼帠幚偵偍偗傞寢崌偱偼側偄偐傜偱偁傞丅乽嬤戙乿偼壂撽傪傕曪娷偟偨悽奅偺乽嬤戙乿偲偟偰偲傕偐偔懚嵼偟棃偭偰偄傞偺偱偁傞丅偙偙偵偍偄偰栤戣偲偝傟傞傋偒偼丄乽嬤戙乿乽岺嬈壔幮夛乿偲偄偆傕偺偺尰壓偺悽奅揑側懚嵼宍懺傪懳徾壔偡傞偙偲偱偁傠偆丅偦偟偰偦偺偙偲偼丄偦偺拞偵偍偗傞壂撽偺懚嵼宍懺傪帺屓攃埇偡傞偙偲偵偮側偑傜偞傞傪偊側偄丅偙偺傛偆側悽奅亅壂撽偺媞娤壔偙偦偑丄乽嬤戙乿斸敾偺晛曊庡媊偲僫僔儑僫儖側揥朷偺捛媮偲偺帠幚偵偍偗傞寢崌偺応偲側傞偼偢偱偁傞丅
丂榑幰偼丄偙偺悽奅亅壂撽偺媞娤壔傪傛偔側偟偆傞傕偺偱偼側偄偑丄愭掱偺巵偺擇幰戰堦偼丄偙偺傛偆偵墴偊傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺尰幚揑堄枴傪幐偆偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅榑棟揑儗儀儖偵偍偗傞嫟摨懱傊偺埶嫆偐丄偦偺曻婞偐偲偄偆戰堦偵懳偟偰偼丄摉慠偵傕慜幰偑慖戰偝傟偹偽側傜側偄丅楌巎揑偵傒偰傕丄儘僔傾丄拞崙丄儀僩僫儉偺妚柦偼偦傟偧傟偺巇曽偵傛偭偰嫟摨懱偵埶嫆偟偨傕偺偱偁偭偨丅
丂壂撽傕悽奅偺乽嬤戙乿偺拞偵偁偭偰丄壂撽帒杮庡媊偺惉棫偺棥偵丄乽嬤戙乿傊偺懌偳傝傪偲傕偐偔傕摜傒弌偟偰偄傞偺偱偁偭偰丄偦偙偵偍偗傞嫟摨懱偼帪乆崗乆偲曄壔偟側偑傜懚懕偡傞傕偺偺偼偢偱偁傞丅嫟摨懱偺乽偨偨偢傑偄乿亅宨娤偼曄傜側偄偲偟偰傕丄偦偺惉堳偺堄幆偺曄壔偼偁傞偲偟側偔偰偼側傜側偄丅偦傟偼丄偡偱偵偟偰乽帒杮庡媊偺娮鈜乿傊偲懌傪撍偭偙傫偩傕偺偱偁傠偆乮傕偪傠傫丄偦偺敿柺偵偍偄偰丄偦傟偼寛偟偰儓乕儘僢僷揑側乽幮夛堄幆偺傾僩儉壔乿偵偄偒偮偐偸傕偺偱偁傞乯丅巵傕乮壓乯偵偍偄偰丄嫟摨懱惉堳偺愗幚側傞乽嬤戙婓媮乿傪愢偄偰偄傞偺偱偁偭偰丄嫟摨懱傕偦偺乽嬤戙婓媮乿偺懁柺傪娷傔偰峫嶡偝傟側偔偰偼側傜側偄丄偦偺傛偆側帪戙偵擖偭偨偺偱偁傞丅
丂偦偟偰巵偼丄偙偺偙偲傪捈娤偡傞偙偲偵傛偭偰丄妋幚偵偐偺擇幰戰堦偺儗儀儖傪挻偊傫偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅乮壂撽帒杮庡媊丄壂撽偺乽嬤戙乿偼丄傾儊儕僇偵傛傞揟宆揑側乽嬤戙乿偺斆棓偲擔杮偺嵞怤弌偺拞偱丄1958擭崰偵巒偭偨偲峫偊傞傋偒偐丅柧帯崙壠偵傛傞旝壏揑側乽嬤戙乿摫擖偼乽僜僥僣抧崠乿偱戝攋嶻偟偨偲巚傢傟傞丅乯
丂峫偊偰傒傟偽丄偙偺乽嬤戙婓媮乿偲偄偆巜揈偼傑偙偲偵廳梫側堄枴傪傕偮丅偦傟偙偦偼丄壂撽偺惼庛側乽嬤戙乿偑丄悽奅偺乽嬤戙乿偵偍偗傞堦乬廃曈乭偲偟偰懚嵼偟偰偒偨偙偲傪暔岅偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅偙偺偙偲傪傆傑偊偰丄偙偺乬廃曈乭偺曄妚揑側帺棫偺搑傪峫偊傞側傜偽丄偦傟偼崻杮偵偍偄偰撈帺偺嬤戙傪偮偔傝忋偘傞偙偲偲偟偰傂偲傑偢揥奐偣偞傞傪偊側偄偱偁傠偆丅偙偺曽岦惈偼丄擔杮偺懁偵墲乆尒傜傟傞丄悽奅亅壂撽傪傒傞偙偲偺偱偒偸埨堈側斀乽嬤戙乿偺晛曊庡媊幰偺巚榝傪挻偊偰丄偨偔傑偟偔傕娧揙偡傞傕偺偱偁傞丅偦偟偰偦偺撈帺偺嬤戙偑帺傜偲悽奅偺偦傟偲傪偄偐傎偳巭梘偡傞宊婡傪傕偮偐偲偄偆偙偲偼丄曄妚揑側帺棫偺偦偺摤偄偺傕偮幙偵傛偭偰偺傒寛掕偝傟傛偆丅嵟屻偵偦偺幙偲偼壗偐丠偲偄偆偙偲偵偮偄偰偄傢偹偽側傜偸偲偡傟偽丄榑幰偼丄僄僕僾僩偺乬廃曈乭宱嵪偺棟榑壠丄僒儈乕儖丒傾儈儞偺師偺尵梩傪堷梡偣偞傞傪偊側偄偺偱偁傞丅
丂乽変乆偺棟榑偼丄廃曈晹偵偍偄偰偼丄惉弉偟偨丄帺棫揑側帒杮庡媊偺惉棫偼晄壜擻偱偁傞偲偟丄偦偙偱偼廃曈揑帒杮庡媊僔僗僥儉偐傜偺幮夛庡媊揑側棧扙偑媞娤揑偵昁梫偲偝傟傞偙偲傪庡挘偡傞丅乿乽廃曈晹偵偍偄偰幮夛庡媊偑昁梫側偺偼丄偦傟偑敪揥偲帺棫偺晄壜寚偺忦審偩偐傜偱偁偭偰丄亀帺桼亁偵偊傜偽傟傞僀僨僆儘僊乕揑側偄偟偼摴摽揑側摦婡偵傛傞偺偱偼寛偟偰側偄丅乿
亙帒椏侾亜壂撽宱嵪偺尰忬攃埇偺偨傔偵丂尨揷丂惤巌
嘥丂偼偠傔偵
丂偙偺儗僕儏儊偼丄壂撽宱嵪偺楌巎揑揥奐傪戝偞偭傁偵偮偐傒丄乽崙撪怉柉抧乿偲偟偰偺壂撽宱嵪偺摿幙傪柧傜偐偵偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅偦傟偼丄堦斒偵掅奐敪側偄偟屻恑偲偲傜偊偰偄傞壂撽宱嵪偺峔憿傪悽奅乗乗擔杮帒杮庡媊偲偺娭學偵偍偄偰偲傜偊捈偦偆偲偡傞戞堦曕偱偁傞丅
丂偦偺嵺丄擇偮偺帇揰偑廳梫偩偲峫偊傞丅乮侾乯壂撽宱嵪偺帪婜嬫暘丄偍傛傃乮俀乯宱嵪峔憿偺彅巜昗偺擇偮偱偁傞丅屻幰偺巜昗傪幉偵慜幰傪柧傜偐偵偡傞偲偄偆娭學偱偁傠偆丅
丂巜昗偵偮偄偰偼丄師偺彅揰傪偁偘偨偄丅乮侾乯嶻嬈峔憿乮搚抧強桳偍傛傃岺丒擾娭學乯丄乮俀乯楯摥椡峔惉乮捓楯摥偺懺條乯丄乮俁乯嵿惌峔憿乮嬥梈娷傔偨乯丄乮係乯宱嵪偺埵抲乮懳奜廂巟偍傛傃搰偟傚惈乯丅惌帯丄孯帠揑忦審傕丄戝偒側梫慺偱偁傞偑丄偙偙偱偼乮係乯偵擖傟偰偍偔丅
嘦丂帪婜嬫暘偵偮偄偰
侾丏帋榑揑偵壂撽宱嵪偺敪揥夁掱傪師偺屲婜偵嬫暘偱偒傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傞丅
丂戞堦婜乮1878擭乣1899擭乯乗乗攑斔抲導乮戞侾師棶媴張暘乯偐傜搚抧惍棟傑偱
丂戞擇婜乮1900擭乣1929擭乯乗乗搚抧惍棟偐傜悽奅戝嫲峇杣敪傑偱
丂戞嶰婜乮1930擭乣1949擭乯乗乗愴憟宱嵪偵傛傞廂扗偲崿棎偺帪婜
丂戞巐婜乮1950擭乣1971擭乯乗乗暷孯巟攝宱嵪偺奐巒偐傜擔杮暅婣慜傑偱
丂戞屲婜乮1972擭乣丂丂丂乯乗乗擔杮暅婣屻偺宱嵪
俀丏奺帪婜偺摿挜傪巐偮偺巜昗偵増偭偰娙扨偵慺昤偡傞丅
乮侾乯戞堦婜乗乗偙偺栺20擭娫偼丄偄傢備傞乽媽姷乿壏懚偺帪戙偱偁傞丅
丂倎抧妱惂偑懕偒丄擾嬈偑埑搢揑偱偁傝丄倐捓楯摥偼峔憿揑偵憂弌偝傟偢丄們嵿惌傕晻寶抧戙丒峷擺偑巟攝偟偰偄偨丅倓壂撽宱嵪偼丄擔杮帒杮庡媊偵傛傞尃椡揑廬懏婡峔偺傕偲偵彊乆偵嵞曇惉偝傟丄偦傟偼擔杮帒杮庡媊偺崙壠帒杮庡媊揑拁愊偵偲偭偰乽懏椞乿揑廂扗宱嵪偲偟偰埵抲偟偨丅
丂偙偺帪戙偺摿挜偼丄惌帯揑側偲偙傠偵傓偟傠偁傞丅擔惔愴憟乮1894乣5擭乯偵傛偭偰壂撽偺擔杮婣懏偑嵟廔揑偵寛掕偝傟傞乮暪崌乯傑偱偺乽懏椞乿揑廬懏偑壂撽宱嵪偺乽屻恑乿惈傪曻抲偡傞偙偲偵側偭偨丅
乮俀乯戞擇婜乗乗偙偺栺30擭娫偼丄擔杮帒杮庡媊偺掗崙庡媊揑敪揥偺廃曈揑廂扗抧堟亖崙撪怉柉抧偲偟偰埵抲偯偗傜傟偨帪戙偱偁傞丅
丂倎搚抧惍棟偵傛傝抧妱惂偑攑巭偝傟巹揑搚抧強桳偑妋棫丅晻寶揑峷擺攑巭偵傛傞抧慸丄慸惻惂搙偑妋棫偝傟偨丅倐偙傟傪宊婡偵夁忚楯摥偺堏丒桝弌偑奐巒偝傟丄峔憿壔偝傟傞丅們娒潋乮彫塩嬈乯乗乗惢摐嬈乮擔杮帒杮乯偺嶻嬈峔憿偑宍惉偝傟丄儌僲僇儖僠儍乕宱嵪偑揥奐偝傟傞丅戞堦師嶻嬈偑埑搢揑丅倓嵿惌偼丄崙惻廳壽乮娫愙惻乯乗乗嵒摐徚旓惻乮幚偼惗嶻幰惻乯偵傛傞廂扗丅斀懳偵擔杮嵿惌傛傝偺嶶晍側偟偲偄偆峔憿偐傜壂撽懁偺姰慡弌挻丅倕偲偔偵1920擭偺枬惈晄嫷偼丄摐壙壓棊乗乗乽偦偰偮抧崠乿傪傑偹偔丅導奜廂巟偼姰慡愒帤傊偲揮壔偟偨丅
丂偙偺帪戙偼丄壂撽宱嵪偑擔杮帒杮庡媊偺堦娐偵慻傒崬傑傟偨偑丄偦傟偼擔杮帒杮庡媊偺掗崙庡媊揑敪揥乮擔業愴憟丄堦師戝愴乯偺偨傔偺廃曈揑廂扗亖崙撪怉柉抧宱嵪傊偺揮壔偱偟偐側偐偭偨丅
乮俁乯戞嶰婜乗乗偙偺栺20擭娫偼丄掗崙庡媊愴憟乮擇師戝愴乯宱嵪壓偱偺廂扗偲宱嵪攋夡偺帪戙偱偁偭偨丅
丂倎1930擭戙偵擖傝乽偦偰偮抧崠乿偐傜偺乽媬嵪乿傪傔偞偟丄乽怳嫽10擭寁夋乿偑幚巤偝傟偨偑丄梊嶼斾幚巤棪20乣30亾偱偁傝丄乽怳嫽乿偼慡偔側傜偢丄倐偦傟偩偗偱側偔丄擔杮偺掗崙庡媊愴憟傪巟偊傞偨傔乽憹嶻乿偲乽挋拁乿傪嫮惂偝傟丄堦師嶻嬈帺懱攋柵傊岦偐偭偨丅們擔杮偺嵟戝偺媇惖偲側偭偨壂撽愴偱擾嬈攋夡偺嬌偵払偟偨丅倓愴屻偺暷孯愯椞偼丄搚抧偺戝暆廂扗乮婎抧乯傪傕偨傜偟丄宱嵪夞暅偺曽搑傪憆幐偝偣偨丅
偙偺帪戙偺摿挜偼丄擔杮掗崙庡媊偲暷孯愯椞偵傛傝丄崙撪怉柉抧宱嵪偡傜姰慡偵攋夡偝傟丄廂扗偝傟偮偔偟偨帪戙偱偁偭偨丅
乮係乯戞巐婜乗乗偙偺栺20擭娫偼丄暷孯怉柉抧宱嵪亖暷乽懏椞乿宱嵪偲偟偰埵抲偯偗傜傟偨帪戙偱偁偭偨丅
丂倎偄傢備傞椻愴傊偺撍擖偵傛偭偰丄壂撽暷孯婎抧偺搰偲偟偰埵抲偯偗捈偝傟丄1950擭偐傜朿戝側婎抧寶愝梊嶼偑慻傑傟偨丅偲摨帪偵柉惗埨掕偺偨傔偺暅嫽嬥梈婎嬥丄懳擔柉娫杅堈奐巒摍暷孯帠怉柉抧宱嵪峔憿偑揥奐偝傟巒傔偨丅倐偙偺宱嵪峔憿偼丄婎抧廀梫偵埶懚偟丄嵒摐丒僷僀儞偺儌僲僇儖僠儏乕嶻嬈傪幉偲偟丄偐偮擔丒暷椉嵿惌墖彆偵傛偭偰曗姰偝傟傞傕偺偱偁偭偨丅們偲偔偵1958擭僪儖捠壿惂傊偺堏峴偲60擭戙偺擔杮帒杮丒擔杮惌晎墖彆偺憹戝偵傛偭偰乽崅搙惉挿乿傪払惉偟偨丅楯摥椡偺堏桝弌偼憡懳揑偵尭彮偟偨丅倓偟偐偟丄懳奜廂巟偼丄婎抧娭楢廂擖偲墖彆傪彍偗偽慡偔偺愒帤偱偁傝丄帺棫宱嵪偺峔憿偼慡偔懚嵼偟偰偄側偄丅
丂偙偺帪戙偺摿挜偼丄壂撽偑暷掗崙庡媊偵傛偭偰傾僕傾孯帠婎抧偺梫偲埵抲偯偗傜傟丄宱嵪揑偵偼暷偺乽懏椞乿宱嵪偲偟偰懚嵼偟偮偯偗傜傟偨偲偙傠偵偁偭偨丅
乮俆乯戞屲婜乗乗72擭暅婣埲屻偺擔杮掗崙庡媊偺崙撪怉柉抧偲偟偰埵抲偯偗傜傟偨帪戙偱偁傞丅
丂倎暅婣偵傛偭偰壂撽宱嵪偼丄怴偟偔擔杮宱嵪偺堦娐偵慻傒崬傑傟偨丅偟偐偟丄乽帺棫揑敪揥乿傪傔偞偟偨乽怳嫽奐敪寁夋乿偼偡偱偵攋抅偟乮暅婣摿暿慬抲傕墑挿乯丄乽怳傝弌偟偵栠偭偨乿偲偝偊偄傢傟傞丅倐嶻嬈峔憿揑偵偼丄埑搢揑戞嶰師嶻嬈偺斾廳乮戞巐婜偱宍惉乯偺傕偲丄戞堦師嶻嬈偺婋婡丄戞擇師嶻嬈偺晄怳偼偍偍偆傋偔傕側偄丅們偙偺晄嫷壓偱屬梡亅楯摥椡堏弌栤戣偼怺崗壔偟丄幐嬈棪丄堏弌棪偲傕憹戝偟偰偄傞丅倓嵿惌帒嬥嶵晍偼偐偮偰乮戞擇婜乯偲偼堎側傝丄嫄戝偲側傝乮岎晅嬥丄崙屔巟弌嬥丒嵿惌乯丄傑偨擔杮帒杮偺恑弌偲宯楍壔偑恑峴偟丄乽廬懏乿傪怺傔偰偄傞丅倕導奜廂巟偼傕偪傠傫愒帤偱偁傞丅偙偺傛偆側丄尰嵼偺壂撽宱嵪偼戞擇婜偲偼堎側傞堄枴偱偺崙撪怉柉抧偲偟偰懚嵼偡傞丅擔暷嫟摨孯帠嶌愴偺搰乮婎抧宱嵪偺堐帩乯偱偁傞偲摨帪偵丄擔杮掗崙庡媊偺傾僕傾撿恑乽嫆揰乿亖尨椏挋憼丒帒尮奐敪偺乽嫆揰乿偱傕偁傞偲偄偆擇廳偺惈奿傪傕偮丅戞擇婜偲偺憡堘偼丄嵿惌帒嬥嶶晍偺懚嵼偩偗偱側偔丄偙偺擇廳偺堄枴偱偺惈奿傪傕偭偨搰偟傚幮夛亅宱嵪偲偟偰埵抲偯偗捈偝傟偨偙偲偱偁傞丅
嘨丂栤戣採婲偲庒姳偺傑偲傔
丂埲忋偺専摙偐傜丄師偺傛偆側栤戣揰傪巜揈偡傞偙偲偑偱偒傞丅
侾丏壂撽宱嵪偼丄偄傢備傞嬤戙帒杮庡媊揑敪揥偺摴傪偨偳偭偰偼偄側偄乗乗偦傟偼嶻嬈峔憿偺僶儔儞僗偺栤戣偱偼側偔丄帒杮偺拁愊峔憿偑丄乬帺棫揑乭偵宍惉偝傟偰偄側偄偐傜偱偁傞丅
俀丏偟偐偟丄偦傟偼屻恑側偄偟掆懾丄掅奐敪偺帩懕揑丄堦斒揑懚嵼傪堄枴偟側偄乗乗壂撽宱嵪偼丄楌巎揑偵悽奅乗擔杮帒杮庡媊偲偺峔憿揑娭學偵偍偄偰曄揮偟偮偮懚嵼偟偰偒偨丅偦偙偵偼乽掅奐敪偺敪揥乿偑摿挜揑偱偁傞丅
俁丏廃曈揑帒杮庡媊偲偟偰偺壂撽宱嵪偺懚嵼偼楌巎揑帠幚偱偁傞偑丄廳梫側偙偲偼丄搰偟傚幮夛丄宱嵪偲偟偰偺壂撽宱嵪偺摿幙偵偍偄偰偲傜偊傞偙偲偱偁傠偆乗乗偦偺揰偱丄戞擇婜偲尰嵼偺斾妑専摙偼廳梫偱偁傞丅
亙帒椏嘦亜崙撪怉柉抧榑乮儗僕儏儊乯丂拞懞忎晇
堦丄掕媊偲崻嫆
丂崙撪怉柉抧偲偼丄恖岥堏廧偲偟偰偺搶儓乕儘僢僷側偳偱偺撪崙怉柉Binnenauswarderung偺懳徾抧堟偲偼堎側傝丄峀媊偺怉柉抧乮弮怉柉抧丒廬懏崙側偳傪曪妵乯偺堦晹傪側偡奣擮偱偁傝丄堦斒偵偼丄宍幃忋杮崙偺暯摍側峔惉晹暘偱偁傝側偑傜丄幚幙揑偵偼摿庩側幙傪傕偮嶏庢丄廂扗丄梷埑丄慳奜偺傕偲偵偍偐傟偨廬懏抧堟傪巜偡丅偙偙偱帒杮庡媊揑怉柉抧偲偼丄乮侾乯杮尮揑拁愊婜偺偄傢備傞old colonial system乮搶惣娫偺杅堈丒孯帠嫆揰丒尨廧柉偵偨偄偡傞搝楆揑丒晻寶揑嶏庢偵傕偲偯偔嵧攟怉柉抧plantation colony丄搝楆嫙媼抧側偳乯丄乮俀乯嶻嬈帒杮庡媊婜偺岺嬈惢昳乮庡偵慇堐惢昳乯偺斕攧巗応偍傛傃儓乕儘僢僷偵偨偄偡傞岺嬈尨椏丄怘椏嫙媼抧丄乮俁乯屆揟揑掗崙庡媊婜偺帒杮桝弌傪幉偲偟偨帒尮撈愯丄掅楑楯摥椡嶏弌偺偨傔偺暥帤捠傝偺怉柉抧偍傛傃孯帠怉柉抧丄乮係乯偄傢備傞乽怉柉抧懱惂偺曵夡乿埲崀丄偲偔偵悽奅婇嬈亖懡崙愋夛幮偺奼戝偺傕偲偱偺怴怉柉抧庡媊揑塹惎抧堟亖乽掅奐敪偺敪揥乿抧堟偵楌巎揑偵嬫暘偝傟傞丅崙撪怉柉抧偼丄僀僊儕僗偵偍偗傞傾僀儖儔儞僪丄傾儊儕僇偵偍偗傞Westward movement偺堦帪婜偱偺僀儞僨傿傾儞惔憒乗乗擾嬈抧堟偺傛偆側椺傕偁傞偑丄揟宆揑偵偼乮俁乯偺抜奒偺掗崙庡媊崙偵偡傋傝偙傒偊偨屻敪丒憗弉帒杮庡媊崙偺撪晹偵傒傞偙偲偑偱偒傛偆丅偡側傢偪丄僀僞儕傾偺撿晹丒搰晹丄儘僔傾偺僐乕僇僒僗丒僩儖僐宯彅柉懓埲奜偺廬懏抧堟乮僂僋儔僀僫丄敀儘僔傾丄増僶儖僩丄暿偵億乕儔儞僪墹崙丄僼傿儞儔儞僪戝岞崙乯丄僆乕僗僩儕傾丒僴儞僈儕傾偺僗儔償宯丄傾儖僶僯傾丄儌儞僥僱僌儘側偳丄偦傟偵擔杮偺撿杒曈嫬乮壂撽丄搶杒乯側偳偱偁傞丅
丂偙傟傜偺抧堟傪崙撪怉柉抧偲婯掕偟偆傞崻嫆偼丄柉懓栤戣偺尠嵼偵恠偒傞傢偗偱偼側偔乮柉懓廤抍偼偦偺搒搙偺宱嵪彅娭學牀蛷攰謱W墳偠偰偮偹偵嵞峔惉偝傟傞偙偲丄傑偨僗僀僗偺傛偆偵暋悢乽柉懓乿偐傜峔惉偝傟偰傕堦斒柉庡庡媊偑娧揙偝傟傟偽柉懓栤戣偼敪惗偟側偄偙偲乯丄帒杮拁愊偵偲偭偰偺抧堟奿嵎偺幙揑栶妱偵拲栚偟側偔偰偼側傜側偄偩傠偆丅儘乕僓丒儖僋僙儞僽儖僌偼丄偦偺嵞惗嶻榑攃埇偵擄揰偼偁傞偲偟偰傕丄帒杮拁愊傪旕帒杮庡媊揑抧堟偺晄抐偺暪崌偲偺娭楢傪拞怱偵偲傜偊丄偦偺揰偱偼崙奜怉柉抧偲崙撪擾嬈偍傛傃嫟摨懱抧堟偲傪嬫暿偟側偐偭偨乮亀帒杮拁愊榑亁丄亀宱嵪妛擖栧亁乯丅偦偺偙偲偼斵彈偺掗崙庡媊榑傪抜奒榑揑偵偁偄傑偄偵偝偣丄惌帯揑偵偼丄柉懓帺寛尃偺斲擣偵偄偨傜偣偨偑丄尰幚偵帒杮庡媊偼杮尮揑拁愊奜偐傜偺廂扗傪偲傕側偄丄偲偔偵撍娧岺帠揑敪揥偺昁梫傗奀奜怉柉抧妉摼偺崲擄偑懚嵼偡傞応崌偵偼丄旕帒杮庡媊揑娐嫬偐傜偺廂扗偺峔憿揑曐忈偑梫審偲側傜偞傞傪偊側偄丅儗乕僯儞亀掗崙庡媊榑亁偵偍偗傞怉柉抧奣擮偺懳奜揑奼戝偼丄屆偄帒杮庡媊崙撪晹偱偺乽暪崌偲柉懓揑梷埑偺嫮壔乿偺巜揈乮俋復乯偲暪偣撉傓偲偒丄乽抧忋恖岥偺埑搢揑懡悢偺怉柉抧梷埑偲嬥梈揑峣嶦偺悽奅揑懱宯乿偲偟偰偺掗崙庡媊乮暓撈斉彉暥乯偺庡懱偱偁傞乽傂偲偵偓傝偺乬愭恑乭彅崙乿傪乽傂偲偵偓傝偺嬥梈壡摢惂乿偵偍偒偐偊傞偙偲傪壜擻偵偡傞偲峫偊傜傟傞丅
擇丄斾妑揑帠椺乮侾乯乗乗僀僞儕傾撿杒栤戣
丂乽杒晹偺僽儖僕儑傾僕乕偼撿晹僀僞儕傾偲搰晹傪惇暈偟偰丄偦傟傜傪嶏庢偺偨傔偺怉柉抧偵傂偒偝偘偨丅杒晹僾儘儗僞儕傾乕僩偑帒杮壠揑偔傃偒偐傜帺屓傪奐曻偡傞側傜偽丄杒晹偺嬧峴偍傛傃婑惗揑嶻嬈帒杮庡媊偵楆懏偝偣傜傟偰偄傞撿晹偺擾柉戝廜傪傕夝曻偡傞偱偁傠偆乿乮亀僆儖僨傿僱丒僰僆乕償僅亁1920擭侾寧俁擔乯偺揥朷偵敪偡傞僌儔儉僔偺撿晹栤戣榑乮慖廤戞俀姫乯偼丄偦傟傑偱偺帺桼庡媊揑撿晹庡媊meridionalismo傪妚柦壔偝偣傞僿僎儌僯乕愴棯偵傒偪傃偄偨丅僀僞儕傾撿杒栤戣偺幚懺丄戞擇師戝愴屻偺撿晹奐敪惌嶔偺媡岠壥偵偮偄偰偼亀僀僞儕傾宱嵪亁乮搶梞宱嵪乯強廂抾撪孾堦榑暥側偳傪嶲徠丅僌儔儉僔偺扵媶偼撿杒宱嵪娭學偵偲偳傑傜偢丄撿晹巟攝偺惌帯揑袎飺I儊僇僯僘儉偵偍傛傃丄撿晹擾嬈僽儘僢僋偺夝懱丄撿晹抦幆恖偺傂偒棧偟傪偮偆偠偰偺杒晹楯摥幰偲撿晹擾柉偲偺摨柨傪崙柉揑恖柉揑塣摦偲偡傞曽岦傪捛媮偝偣偨丅偙偺曽岦偼丄掗崙庡媊崙撪偺廃曈帒杮庡媊揑抧堟偵偲傝堦掕偺晛曊惈傪傕偪偊傛偆丅
嶰丄斾妑揑帠椺乮俀乯乗乗搶杒栤戣
丂偐偭偰嶳揷惙懢榊亀擔杮帒杮庡媊暘愅亁偼丄業擔帒杮庡媊亖孯帠揑晻寶揑掗崙庡媊偲偄偆岆偭偨帇妏偐傜偱偼偁傞偑丄敿晻寶揑擾嬈憤懱傪崙撪怉柉抧偵弨偠偰偲傜偊丄偙偺婎掙偵惂栺偝傟偰嶻嬈帒杮偑怉柉抧亖僀儞僪埲壓揑掅捓嬥偵傕偲偯偔慜婜揑惈奿傪偍傃傞偲偲傕偵丄擾嬈抧堟偼搶杒宆丄嬤婨宆丄杒奀摴宆丄挬慛宆偺庬嵎偵暘壔偟偨偙偲傪巜揈偟偨丅偦偺偐偓傝偱偼丄傛傝晻寶揑側掅奐敪抧堟偨傞搶杒偑挬慛偲暲楍偝傟偰偄傞偙偲偵拲堄乮楆擾惂揑廬懏娭學亅傾僀儖儔儞僪傛傝杮幙揑偵抶傟偨亅偺乽怉柉抧偱偺嵞尰乿乯丅搶杒栤戣偼乽掗崙偺晧扴乿偲偟偰1913擭乽搶杒怳嫽夛乿愝棫埲棃昞柺壔偟丄擾嬈嫲峇壓偵1931丄34擭偺戝嫢嶌傪婡偵敋敪偟偨丅戝栰曱帯亀搶杒偺庡挘亁乮1920乯偼亀壂撽媬嵪榑廤亁偲懳斾偝傟傞儔僨傿僇儕僘儉傪偟傔偟偨丅搶杒偺乽屻恑惈乿偼丄乮侾乯楌巎揑側彜昳惗嶻偺枹弉丄乮俀乯戝抧庡惂偲摿庩彫嶌姷峴亅岺嬈枹敪揥丄乮俁乯柧帯堐怴偵偍偗傞懐孯揑抧埵亅抧慸夵惓偺晄暯摍丄崙桳椦傊偺嫟桳抧廂扗偵傕偲偯偔偲偝傟傞乮惣愳廐梇乽搶杒怴嫽栤戣乿亅亀擔杮擾嬈敪払巎亁戞俉姫乯丅偩偑丄嵟掅偺堦恖摉傝強摼悈弨乮懳慡崙暯嬒40乣60亾乯偼丄島嵗攈揑側敿晻寶惂嫮壔榑偐傜偱偼側偔丄摿庩側廃曈帒杮庡媊揑敪揥乮暷嶌婎抧丄掅捓嬥搚忞丄揹椡丄峼嬈丄椦嬈媼尮丄嫮暫婎斦乯傪偮偆偠偰偺崙撪怉柉抧揑抧埵偐傜偲傜偊側偍偝傟側偔偰偼側傜側偄偱偁傠偆丅廃曈揑帒杮庡媊壔偐傜傒側偔偰偼愴屻偺奿嵎惀惓乮擾嬈偱偼愭恑壔乯偼愢柧偝傟偊側偄丅搶杒栤戣偺夝寛曽朄偵偮偄偰偼丄擾柉偼搚抧妚柦傪丄抧曽僽儖僕儑傾僕乕偼崙桳椦夝曻傪丄偦偟偰曐庣媍堳偱偡傜愴憟偺廳埑乮惣擔杮亅枮廈偵廳揰乯斀懳傪丄崅媺姱椈偱偡傜乽搶杒摿暿巤愝乿傪梫媮偝偣偨偑丄摉帪偺僾儘儗僞儕傾搣偵偼丄僌儔儉僔揑帇揰偼懚嵼偣偢丄搶杒栤戣偼搶杒怳嫽亖揹尮奐敪偵廂澥偝傟偨乮亀幮夛惌嶔帪曬亁搶杒栤戣尋媶丄1935擭俁寧傪嶲徠乯丅崱屻偼丄僽儖僕儑傾揑夝寛傪傊偰丄柉懓栤戣揑惈奿偼傕偨偢偲傕丄幮夛庡媊揑儕乕僕儑僫儕僘儉傪暘斿偣偞傞傪偊側偄偱偁傠偆丅
巐丄崙撪怉柉抧偲偟偰偺壂撽乮棯乯
丂壂撽栤戣偼丄1950亅72擭偺傾儊儕僇孯帠怉柉抧婜傪夘嵼丄攠夘偝偣偰愴慜揑崙撪怉柉抧亅愴屻揑丒怴怉柉抧庡媊揑崙撪怉柉抧偺嵟埆偺埵抲偯偗傪嫮惂偝傟偰偄傞偲巚傢傟傞丅孯帠怉柉抧揑亅醔宆揑偱偼偁傝側偑傜丄乽敿撈棫崙揑乿嬤戙壔丒懱宯壔傪堦掕搙敪夎偝偣偨偺偑嵙愜偝偣傜傟偨偺偼丄搶杒栤戣偲偼偝傜偵幙揑偵堎側傞柉懓栤戣傪撪曪偝偣偰偄傞偐傜偱偁傠偆丅宱嵪揑帺棫亅惌帯揑帺寛傊偺懱宯偲庡懱傪偦側偊偨帺屓敪揥椡傪斀掗崙庡媊揑懳寛傪偮偆偠偰峔抸偟側偔偰偼丄栤戣偼婎杮揑偵夝寛偝傟偊側偄偲峫偊傞偑丄徻偟偔偼暿曬崘偵忳傝偨偄丅
亙帒椏嘨亜搰涀宱嵪榑乮儗僕儐儊乯丂拞懞忎晇
堦丄婛惉偺搰涀惈榑
丂乽搰涀惈乿偲偼丄廬棃丄宱嵪妛揑偵偼撪奜偲傕偵嬤戙宱嵪妛揑亅怴屆揟攈揑側岠棪惈尨棟偵傕偲偯偔摿庩惗嶻梫慺榑偲偟偰埖傢傟偰偒偨丅偦傟偼堦岥偵尵偭偰丄乽屻恑惈乿偺嬌尷傪側偡乽曈嫬惈乿乽屒棫惈乿偲摍抲偝傟丄偦偺惀惓偼丄揟宆揑偵奐敪宱嵪妛揑偵乽埵抲學悢Location quotient乿偺棙梡偲偟偰扵媮偝傟偨丅偦偺偐偓傝偱偼丄island economy偲偼丄僔儞僈億乕儖側偳彮悢偺椺奜傪彍偄偰丄偁傑傝揥朷偺側偄暵夞楬偱偁傞丅
丂偨偲偊偽丄崙楢摑寁偼丄LDC乮掅奐敪崙乯偐傜LLDC乮嵟掅奐敪崙 Least developed countries乯傪暘棧偟偰張棟偟偰偄傞偑丄偙偺僇僥僑儕乕偵懏偡傞彅崙偼搰涀崙偲撪棨崙偱偁傞丅UNCTAD偑1971擭偵搰涀崙10儠崙傪懳徾偲偟偰偍偙側偭偨挷嵏傕屻恑惈崕暈偺偨傔偵帒杮丒搚抧丒楯摥偺庡惗嶻梫慺埲奜偺斾妑揑桪埵惈偺晩懚忬嫷傪挷傋偨傕偺偱偁傞丅偙偺傛偆側曽朄偼丄Rn儘僢僪亀崙嵺宱嵪妛亁偵廤惉偝傟偰偄傞丅傑偝偵棧搰嬯亖乽搰偪傖傃乿丅
丂傢偑崙偱偺搰涀惈尋媶偼丄噽U嫽號趽I偱偍偙側傢傟偰偒偨偑丄塃偺傛偆側堦墳偺嬤戙宱嵪妛揑崌棟惈偵偮傜偸偐傟偰偄傞偲傕尵偊偢丄傓偟傠搰涀惈亖曈嫬惈偺尋媶偼丄嬨妛夛楢崌偺懳攏挷嵏偵傒傞傛偆偵丄廬棃偺奐敪偵娫愙偵曭巇偡傞偙偲傪傔偞偟偮偮丄乽擔杮暥壔偺杮尮揑側傕偺偑暺墦偺抧偵巆傞傕偺傪扵傠偆乿偲偄偆恖暥壢妛揑曽朄偵庡偲偟偰埶偭偰偒偨乮栘撪弐憼亀抧堟奣亁搶戝弌斉夛乯丅偦偙偱偼丄搰涀揑屻恑惈偼丄抧堟屄懱愢偑惉棫偟偆傞偐偺偛偲偒桳婡揑摑堦惈亖嫟摨懱惈偲偟偰偲傜偊傜傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偙偺傛偆側棫応偼丄搰涀偺宱嵪揑帺棫丒敪揥偺崲擄偵捈柺偡傞偲偒丄儘儅儞揑儔僨傿僇儕僘儉偲偟偰偺乽棧搰僐儈儏乕儞乿榑傪偡傜偆傒偩偟偰偄傞丅
擇丄埵抲偺堄媊
丂搰涀偵偲偭偰埵抲偺栤戣偼丄偨偟偐偵孯帠揑偵偺傒側傜偢丄宱嵪揑偵傕廳梫偱偁傞丅偙偺埵抲偑彅屻攚抧偵偨偄偡傞廳怱揑側傕偺偲偟偰傑偝偵偄傢偽丄宱嵪揑帒嶻偲側偭偨椺偼丄僔儞僈億乕儖丄崄峘丄偵傒傞偙偲偑偱偒傞丅偡側傢偪丄拞宲杅堈亅depotindustry亅岺嬈壔亅嬥梈僙儞僞乕丅
丂僔儞僈億乕儖偼丄偙偺埵抲傪屌庣偡傞偨傔丄儅儗乕僔傾偲偺楢朚偐傜扙戅偟丄悽奅婇嬈偺慜恑婎抧偲偟偰椫擖戙懼岺嬈偐傜恑傫偱廳壔妛岺嬈傪啇i崙I偵敪揥偝偣丄偝傜偵丄傾僕傾丒僟儔乕巗応傪憂愝偟偰儐乕儘丒僟儔乕丄僆僀儖丒僟儔乕偺棳擖傪娷傔丄搶撿傾僕傾偺怴怉柉抧庡媊揑奐敪偺嬥梈僙儞僞乕偲側傝乮僜楢偡傜嬧峴傪恑弌偝偣偰偄傞乯偄傑宱嵪敪揥偺尷奅偵捈柺偟偰丄摢擼丒忣曬僙儞僞乕偨傞傋偔丄壢妛媄弍丒暥壔巤愝傪嫮壔偟偮偮偁傞丅
丂崄峘傕傎傏摨條偺楬慄傪偨偳傝丄偲偔偵嬤戙壔傪媫偖拞崙丄償僃僩僫儉偲愭恑帒杮庡媊崙偲偺宱嵪揑寢崌偺娐愡偺婡擻傪偼偨偟偮偮偁傞丅
丂偩偑丄椉幰偼丄戝棨偲偺椬愙傗壺嫛幮夛偺宍惉偲偄偆忦審偵宐傑傟偨婬側椺偱偁傝丄傑偨乽拞恑崙乿亖儘僗僩僁棳偺乽棧棨乿偺摴偼丄LLD側偄偟LD偺搰涀偵偲偭偰朷傑偟偄傕偺偱偼側偔丄宱嵪帺棫偲偼惓斀懳偺悽奅婇嬈傊偺廬懏偺摴偱偁傠偆丅埵抲丄棫抧傪斾妑揑桪埵偺摿庩惗嶻梫慺偲偡傞奐敪曽幃偺尷奅偼丄僾僄儖丒僩丒儕僐偵偟傔偝傟傞丅
丂偙偙偱偼丄傾儊儕僇偺挻嫄戝愇桘帒杮偲嶻桘抧乮儀僱僘僄儔乯偲傪偮側偖埵抲乮偍傛傃愽嵼揑丒憡懳揑夁忚擖岥偵傕偲偯偔掅捓嬥乯偑柸枾偵嬤戙宱嵪妛揑亅嶻嬈棫抧榑揑偵寁検偝傟偰丄愇桘惛惢亅愇桘壔妛亅崌惉慇堐岺嬈偺奐敪寁夋偑悇恑偝傟偨乮W丒傾僀僓乕僪懠亀Industrial Complex Anaysis and Regional Development,1959亁乯丅寢壥偼丄娒潋儌僲僇儖僠儏傾偲憡傑偭偰丄傾儊儕僇杮搚傊偺婞柉揑楯摥椡桝弌傪傕偨傜偟偨丅
丂壂撽偺応崌偼丄愴屻偼傕偭傁傜抧惌帯妛揑丒暫梫抧棟妛揑偵傑偝偵僉乕丒僗僩乕儞偲偟偰傾儊儕僇掗崙庡媊偺傾僕傾愴棯忋偵埵抲偯偗傜傟偮偮丄愇桘儊僕儍乕偺恑弌傪彽偄偨偑丄愇桘婎抧偼懳擔杮偍傛傃搶傾僕傾偺惛惢婎抧偵偲偳傑偭偰偄傞乮僈儖僼偼愲妕楍搰亖戝棨扞桘揷奐敪嫆揰傑偱憐掕偟偰偄偨偲尵傢傟傞乯丅
丂栤戣偼丄搰涀惈偡側傢偪屻恑惈丒掆懾惈偲傒傜傟側偑偪側埵抲偵偁傞抧堟傪傕娷傔偰丄宱嵪帺棫傪傔偞偡搰涀恖柉偺棫応偐傜埵抲偵偐傫偡傞壙抣偺揮姺傪偳偺傛偆偵峔憐偟偆傞偐丄偄傢偽媡庤偵偲傝偆傞偐丄偲偄偆偙偲偱偁傠偆丅偙偺偙偲偼丄摉奩搰涀偵偐傫偡傞帪嬻揑娭楢峔憿亅楌巎揑摦懺偲懠抧堟偲偔偵屻攚抧偲偺娭學亅傪嬶懱揑偵嵞専摙偡傞偙偲傪梫媮偡傞丅偦偟偰偦偺偙偲偼丄搰涀撪晹偺摑堦惈totality偺棟夝丄偦偺摑堦惈傪曐徹偡傞庡懱偺栤戣偵偮偒偁偨傞丅
嶰丄搰涀揑摑堦惈
丂搰涀揑摑堦惈傪怴偟偄師尦偱嵞寶偡傞偨傔偵偼丄壠懓亅抧堟嫟摨懱偲帒杮庡媊側偄偟掗崙庡媊偲偺娭楢偲偄偆丄側偍廫暘偵偼夝柧偝傟偰偄側偄栤戣偵愙嬤偟側偔偰偼側傜側偄丅堏柉栤戣偺崻尮傕偦偙偵偁傞乮C丒儊僀儎僗乕亀壠懓揑嫟摨懱偺棟榑亁拀杸彂朳丄偵偍偗傞乽娨棳揑堏柉乿榑偍傛傃丄傾儈儞亅儊僀儎僗乕榑憟傪嶲徠乯丅
巐丄搰涀偺惌帯妛
丂搰涀偼堦斒偵丄宱嵪揑敪揥偺搙崌偄偵偐偐傢傜偢丄惌帯揑側偄偟峴惌揑偵撈帺偺抧埵傪晩梌偝傟偞傞傪偊側偄丅
丂惣栰徠懢榊乽搰涀廧柉偺帺寛尃偲帺帯尃乿傪嶲徠丅
偙偺儁乕僕偺僩僢僾偵傕偳傞