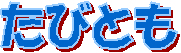第52日 市振−和倉
1997年8月4日(土) 参加者:安藤・奥田・藤原
 平塚駅の改札口で奥田クンと外周旅行初参加となる藤原クンと落ち合い、平塚21時05分発の東京行き926Mに乗り込むと安藤クンの姿があり、外周旅行のメンバーが揃う。東京で山手線に乗り継ぎ、22時30分前に上野に到着。アプローチとなる急行「能登」が発車する16番線ホームに急いだが、発車時刻の23時58分まで1時間半近くもあるので、さすがに列車を待つ乗客は少ない。夏休み中なので混雑するのではないかと懸念していたのだが、案ずるほどではなかったようだ。
平塚駅の改札口で奥田クンと外周旅行初参加となる藤原クンと落ち合い、平塚21時05分発の東京行き926Mに乗り込むと安藤クンの姿があり、外周旅行のメンバーが揃う。東京で山手線に乗り継ぎ、22時30分前に上野に到着。アプローチとなる急行「能登」が発車する16番線ホームに急いだが、発車時刻の23時58分まで1時間半近くもあるので、さすがに列車を待つ乗客は少ない。夏休み中なので混雑するのではないかと懸念していたのだが、案ずるほどではなかったようだ。
23時25分になると福井行き急行「能登」が入線してきた。白い車体にピンクとスカイブルーのラインが入った斬新なデザインのボンネット型489系だ。昼間に上野−金沢間を往復する特急「白山」と車両を共用しているので、6号車にはラウンジ&コンビニエンスカーが連結されているが、当然のことながら急行「能登」では営業していない。
入線直後は多少なりとも座席に余裕はあったが、次第に空席が埋まって来る。サラリーマンの姿が多く、今日は金曜日なので仕事帰りに飲んで、高崎方面の終列車である993Mに乗り遅れた人達が「能登」へ流れて来ているのだ。「能登」は、赤羽、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷と小まめに停車するうえ、急行券を購入すれば定期券でも利用できる。さすがに京浜東北線が運転されている大宮までの利用者は少なかったが、上尾からは徐々に下車客が目立ち、深夜1時33分の高崎に到着すると閑散とした車内になった。4人でワンボックスに小さくなっていた我々も、隣のボックスが開いたのを幸い、4人でツーボックスを使わせてもらう。座席を向い合せにして足を延ばせるので、これで今夜は快適に過ごせそうだ。
うとうとして気が付くと横川に停車中で窓には雨が叩き付けている。最後尾では、EF63型電気機関車の連結作業が行われているはずだ。碓氷峠越えの横川−軽井沢間は、「横軽」または「碓井線」と呼ばれる鉄道名所で、JR線最大の急勾配となる66.2パーミルの高低差がある碓氷峠が控えている。1キロで66.7メートルも登るのであるから、通常編成だけでは馬力不足で、EF63を2両連結することで不足を補う。もっとも、このような作業が行われるのも来月30日まで。今年の10月1日の長野新幹線の開業と引き換えに横川−軽井沢間は1893年(明治26年)4月1日の開業から104年6ヵ月の歴史に幕を閉じる。開業当初はラックレールを利用するアプト式鉄道を採用し、現在の粘着方式に完全に切り替わったのは、1963年(昭和38年)9月30日である。
雨の中、カメラを抱えた熱心な鉄道ファンがホームを右往左往しているのを横目に車内で大人しく過ごす。帰りも「能登」を利用する予定にしているので、連結作業などの見納めは、そのときで十分だ。それに時計を見ると横川発車時刻の2時04分を過ぎている。列車が遅れている理由については、深夜なので特に案内もないが、下手にホームに降りて深夜の横川に置いて行かれては大変だ。しばらくすると10分遅れで列車が動き出したのでひと安心。深夜の碓氷峠に響くモーター音を子守唄代わりに眠りについた。
原因不明の遅れを持ち越したまま翌朝は糸魚川で下車。慌ただしく5時17分の富山行始発列車520Mに乗り継ぐ。やがて右手には海中に迫り出した北陸自動車道の高架が現れ、前回の外周旅行で難儀した親不知に到着。親不知からはしばらくトンネルを出たり入ったりを繰り返し、ヒッチハイクで送り届けられた市振からが本番となる。本来であればスタート地点に敬意を表して下車すべきであろうが、次の列車まで1時間もロスしてしまうので、そのまま520Mに乗り続ける。市振を出るとすぐに境川を渡り、長かった新潟県の旅も終り。いよいよ富山県に突入した。
黒部の手前で宇奈月温泉から続く富山地方鉄道の線路が北陸本線を跨いで海側に出たので、6時01分の黒部で下車。安藤クンから冷たい視線を浴びながら、電鉄石田駅を目指して早々に歩く。電鉄石田駅は黒部駅から1キロ程しか離れていないが、黒部駅には電鉄石田とは正反対の東側にしか改札口がないので、迂回を強いられる。多少迷いながら電鉄石田駅を見付けると踏切の遮断機が下り始める。ちょうど6時39分の電鉄富山行きが来たところで、運良く捕まえることができた。
富山地方鉄道は、片貝川を渡り、次の経田を出ると進行方向左手から北陸本線が寄り添って来て、並走状態となる。我々は北陸本線との接続駅である新魚津で下車した。同じ場所にあるのに北陸本線の駅名は魚津であり、利用者には不親切だ。
まずは特別天然記念物に指定されている魚津埋没林を見学しようと魚津港へ向かって出発。早朝から歩いてばかりなので安藤クンの機嫌を損ねるが、旅は始まったばかりで体力はまだまだ有り余っているだろう。
日本カーバイド工業の工場を迂回するようにして魚津港に到着。ところが現地に到着してから魚津埋没林は、魚津埋没林博物館に保存されていることが判明。公園のようなところに埋没林が残っており、自由に見学できると思い込んでいたので当てが外れた。博物館の開館時刻は9時なので、まだ1時間以上も待たなければならないのである。魚津埋没林は、1930年(昭和5年)の魚津港改修の際に海底から発見された杉の原生林だ。約2,000年前に片貝川が氾濫して流れ出た土砂が杉の原生林を埋没させ、その後、海面が上昇したことにより海底に沈んだと考えられている。土砂によって原生林一帯を完全に地下に密閉されたことにより、杉の株だけでなく、種子や花粉、昆虫なども残り、過去の環境を推定する貴重な資料となっているようだ。
「そういえば魚津は蜃気楼の街だったな。海の向こうに蜃気楼が見えないか?」
魚津埋没林を見学できなかったことによるメンバーの白い眼を反らせるべく、思い付きで蜃気楼の話をするが、高校時代に物理部地学班に所属していた奥田クンより厳しい指摘。
「蜃気楼が出現するのは冬だから夏には見られないよ」
蜃気楼は富山湾の海面上に冷たい空気が層をつくり、その層の上にある暖かい空気との間で急に密度が変わるときに出現するとのこと。夏場に蜃気楼などと口にして知識のなさを露呈し、墓穴を掘った結果になった。
魚津港から電鉄魚津に出る。次の列車まで時間があったので駅前のコンビニエンスストアで朝食を仕入れてホームで食べる。私は朝からしっかり運動したので「メキシカンピラフ」なるものに手を出した。住宅街のホームで弁当を広げるのは多少なりとも抵抗はあるが、人があまりいないのが救いだ。
電鉄魚津8時08分発の列車で中滑川へ向かう。途中の西魚津を出たところで北陸本線と交差して内側に入ってしまったが、依然として並走状態が続いているので気にしない。魚津に続く北陸本線との接続駅である滑川では、魚津とは対照的に富山地方鉄道、北陸本線とも同一駅名を名乗っており、魚津との違いがよくわからない。滑川市の中心部に近い中滑川には8時22分に到着。ここから富山地方鉄道は内陸部へ折れてしまうので利用できない。
中滑川駅前からは8時44分に富山地方鉄道バスを利用して外周ルートを繋げる。運転手に岩瀬浜まで海岸沿いのバス路線がないかと確認してみたが、このバスも常願寺川の手前で内陸へ入り込んでしまうという。それでも常願寺川を渡って少し歩けば、別のバス路線が通じているという貴重な情報を入手することができた。
滑川市街地を抜けるとやがて富山湾が顔を出すがすぐに内陸へ左折してしまう。慌てて腰を上げると運転手から「なるべく橋に近いところで降ろしてあげるから」と声がかかる。「この道をまっすぐ歩いて行けばいいから」と言われて降ろされたのは水橋公民館前という停留所であった。
運転手に教えられた方向に向かって歩く。周囲は住宅街で今日の歩きはあまり面白味がない。白岩川に架かる浦の橋を渡ってしばらくすると安藤クンから声が掛かる。
「橋を渡ったらすぐにバス停があるんじゃなかったの?」
「いや、バス停があるのはこの先の常願寺川を渡ってからだから…」
安藤クンは黙り込んでしまい、早めにこの状況を打開しなければ大変なことになりそうだ。
立山連邦から富山湾に流れ込む常願寺川に架かる今川橋を渡る。常願川は標高差が3,000メートルもあるに対して延長がわずか56キロしかない世界有数の急流河川として名高い。明治時代、常願寺川の改修工事のために政府から派遣されたオランダ人の技師のヨハニス・デ・レーケが、「これは川ではない。滝である。」と言ったと伝えられているが、河口で眺める限りでは、急流河川と言われてもあまりピンとこない。やがて先行していた藤原クンが大きく手を振る姿が見え、どうやらバス停があったようだ。後方を歩いていた安藤クンにもバス停があった旨を伝えて頑張ってもらう。
ユースホステル前という停留所の前には富山ユースホステルの案内板があり、近くには浜黒崎の海水浴場やキャンプ場がある。天気も次第に回復して夏の日差しも出てきた。
「外周なら自転車でサイクリングロードを行くべきだよ」
海岸沿いには自転車専用道路が整備されており、藤原クンは自転車でたどってみたいと言い出すが、周囲にレンタサイクルなんて見当たらないし、乗り捨てができなければ再びここまで戻って来なければならないので却下。
ユースホステル前から9時40分の富山地方鉄道バスに乗り込み、しばらく岩瀬浜沿いを走る。もっとも、防砂林が並んでいるので海岸の様子はあまり伺えない。
「ユースに泊まったの?」
運転手から尋ねられたが「いいえ」と答えると怪訝な顔をされたので、滑川から海岸線沿いのバスを乗り継いで旅をしていると簡単に説明する。富山港線の岩瀬浜駅前でバスは左折し、内陸へ入り込むが、この先の神通川の河口には橋がないのでやむを得ない。
しばらく富山港線に並走する道路を南下し、神通川に架かる萩浦橋に近い昭和町停留所で下車した。地図を見ても近所に昭和町という番地は見当たらないが、近くには昭和電工の関連工場が立ち並んでおり、停留所名の由来になっているに違いない。
さて、ここで再びバス路線が途切れてしまった。工業地帯を延々と歩くのは安藤クンならずとも気が進まないが、神通川を渡ってしまわないことには先に進まない。このあたりのバス路線は富山を中心として放射状にバス路線が設定されているので、どうしても海岸線沿いをたどろうとすると途切れ途切れになってしまう。
大型車両の交通量が多い萩浦橋は全長523メートルもあるため、日陰もない炎天下の中を歩いて渡ろうとすると気が遠くなる。藤原クンはスタスタ先に行ってしまうし、安藤クンは押し黙ってしまって、空中分解寸前だ。あまり余計なことを口にすると反感を買うだけなので、あとは成行きに任せるしかない。
神通川は四大公害病のひとつであるイタイイタイ病で汚名を着せられた河川である。神岡鉱山の製錬に伴う未処理排水に含まれていたカドミウムが原因で、カドミウムの溶出した水を農業用水として利用していた婦中町で収穫した米を常食としていた農民を中心に被害が拡大した。余計な知識があるから神通川の水には有害物質が含まれていそうな偏見を持ってしまうが、現在の神通川にはサクラマスの増殖事業が行われるまでに環境が改善している。
萩浦橋を渡り終えたところには草島停留所があり、運良く10時30分に四方新明町行きの富山地方鉄道バスがあったので安堵する。5分遅れでやってきたバスに揺られて7分で小さな漁港のある四方集落に運ばれる。ところが困ったことに四方神明町でもバス路線が途切れた。
「もう歩かないからね」
とうとう安藤クンが道端の日陰で座り込んでしまった。
「歩きたくないのはわかったけれど、隣の停留所まで行けば別系統のバス路線も乗り入れているので、そこまで歩いてバスがなかったらタクシーを呼ぼう」
なんとか安藤クンを説得して隣の停留所まで歩くことにする。ここでタクシーを呼ばずに隣の停留所まで歩くことに拘った理由は、別系統のバス路線が1980年(昭和55年)3月31日を限りに廃止された富山地方鉄道射水線の代替バス路線だったからだ。射水線はもともと富山−新伏木口(現在の加越能鉄道六渡寺)間の19.9キロを結ぶ路線であったが、1966年(昭和41年)4月に富山新港の建設に伴い新港東口−越ノ潟間が廃止。越ノ潟−六渡寺間は加越能鉄道に譲渡された。しかし、これが原因で射水線の乗客は半減し、廃止とされてしまった悲運の路線である。廃止されたときも決して空気ばかりを運んでいたようではないので、代替バスの本数も適度にあるのではないかと予想した。
四方神明町から西へ5分も歩けば新出町停留所があり、30分以上の待ち合わせとなるが11時37分に新港東口へ向かうバスがあることが判明。自動販売機で買ったジュースを飲みながら日陰でじっとバスを待つ。
今度も5分遅れでやって来た富山地方鉄道バスで新港東口へ。バスはすぐに富山市から新湊市に入る。沿線は思ったよりも集落が多く、新湊高校の甲子園出場を祝したポスターがやたらと目立つ。新湊高校と言えば1986年(昭和61年)の選抜大会で初出場ながらベスト4まで進み、新湊旋風と騒がれた。偶然、その夏の大会の1回戦を甲子園で観戦したのだが、アルプススタンドだけではなく、外野席からバックネット裏までも新湊高校の応援団が埋め尽くしていたので驚いた。街の様子を見る限りでは、当時の熱狂は今でも引き継がれているようだ。ちなみに夏の大会は1回戦で優勝した天理高校に4−9で敗れている。
 新港東口に到着すると目の前に富山県営渡船が待っていた。分断された射水線新港東口−越ノ潟間をカバーするために運航が開始された渡船で、乗船料が無料なのは驚いた。いくら公営渡船といえども、利用者に一部の負担を求めるのが通常であるが、不便を強いられる地元から相当な反発があったのだろうか。我々のような旅行者までその恩恵に預かれるのは少々気がひけるが、有り難く利用させてもらう。
新港東口に到着すると目の前に富山県営渡船が待っていた。分断された射水線新港東口−越ノ潟間をカバーするために運航が開始された渡船で、乗船料が無料なのは驚いた。いくら公営渡船といえども、利用者に一部の負担を求めるのが通常であるが、不便を強いられる地元から相当な反発があったのだろうか。我々のような旅行者までその恩恵に預かれるのは少々気がひけるが、有り難く利用させてもらう。
12時05分の富山県営渡船で富山新港を横断する。近くには富山新港火力発電所があり、富山新港周辺は工場で取り囲まれている。だからといってこの辺りが工業地帯かと言えば、その工場の背後には集落が残っており、どうも富山新港の開発は中途半端なような気がする。
5分足らずで対岸の越ノ潟へ運ばれると、こちらも目の前にあるバス停留所のようなホームに加越能鉄道のいかにも路面電車といった車両が待ち構えていた。加越能鉄道は、今でこそ高岡−越ノ潟間の12.8キロを結ぶ中小鉄道であるが、設立当時は加賀、越中、能登を結ぶ鉄道を建設するという壮大な計画の下に設立された会社であった。計画自体は1970年(昭和45年)に中止されてしまったが、加越能という社名に当時の野望が残されている。
加越能鉄道に乗るのは初めてであるが、車両が悪いのか路面が悪いのかよく揺れる。車内でメモを執ろうと思ったがすぐに諦めた。しばらくは新湊市街地を走り、越ノ潟では閑散としていた車内も活気が出てくる。沿線には新湊高校もあり、「祝 新湊高校 甲子園出場」という垂れ幕が見える。約10年ぶりに新湊旋風が吹き荒れるのか注目だ。
加越能鉄道の撮影名所とされる庄川を渡るとかつての射水線の終着駅だった六渡寺に到着。古い駅舎が今も残っていて新湊港線の0キロポストがあるのが特徴だ。周囲は木材置場のようになっていて、工場の引き込み線のような雰囲気である。我々は次の中伏木で下車した。
小矢部川の河口にあり、伏木港の一部でもある中伏木も六渡寺と同様に工場の引き込み線のような雰囲気がある。小矢部川の対岸にはJR氷見線の伏木駅があり、橋は架かっていないものの、代わりに如意の渡しと呼ばれる渡船があるとの情報をキャッチしていた。貨物線の線路を横切って川岸に向かうと、伏木港に停泊しているロシア船籍の大型貨物船の姿があり、国際港湾都市の片鱗を伺える。
「おおっあれに乗ってロシアに行こう!」
藤原クンが冗談めかして声をあげる。乗り込めばナホトカかウラジオストックまで運んでくれるのだろう。いずれロシアに渡ってシベリア鉄道に乗ってみたいものである。
 如意の渡しの桟橋はすぐに見付かったが、渡船の姿はなく、しばらく対岸からやって来る船を待つ。概ね15分間隔で運航されているようで思ったよりも頻度が高い。5分も待てば次の便に乗れるのである。てっきり富山新港と同様に公営渡船と思っていたのだが、伏木港湾交通株式会社と民間の経営だったのは意外だ。やがて如意の渡し丸という定員18名の小型船が対岸からやって来た。
如意の渡しの桟橋はすぐに見付かったが、渡船の姿はなく、しばらく対岸からやって来る船を待つ。概ね15分間隔で運航されているようで思ったよりも頻度が高い。5分も待てば次の便に乗れるのである。てっきり富山新港と同様に公営渡船と思っていたのだが、伏木港湾交通株式会社と民間の経営だったのは意外だ。やがて如意の渡し丸という定員18名の小型船が対岸からやって来た。
如意の渡しとは小矢部川河口の渡船場の古名で、室町時代の軍記物語「義経記」に1187年(文治3年)春、源義経が平泉の藤原秀衡を頼って落ち延びる途中、この如意の渡しに差し掛かったという。渡守の平権守(たいらのごんげんのかみ)に義経一行ではないかと怪しまれるが、弁慶が「加賀の白山より連れて来た御坊だ」と嫌疑を晴らすために扇で義経を打ちのめすという転機で切り抜け、無事に乗船できたというのだが、これは安宅の関での出来事ではなかったか。
200円の乗船料を払って、少々霞んだ立山連邦や二上山を眺めながら小矢部川を渡るものの3分で対岸に運ばれてしまう。お気楽な旅行者にとってはあっという間の3分であるが、船上の義経や弁慶は、この上なく長い3分間に感じられたに違いない。対岸の伏木桟橋には立派な待合室もあり、こちらが如意の渡しの玄関口であったようだ。桟橋の近くには弁慶が義経を扇で打ちのめしている銅像があった。
「勧進帳は如意の渡しでの話を参考に創作されたものみたいだね」
解説を熱心に読みふけっていた安藤クンが解説してくれた。すっかり安宅関での出来事が実話なのかと思い込んでいた。外周旅行でも安宅関を訪問することになるだろうし、安宅関でも実話のように言い伝えられているのではなかろうか。
伏木からは久しぶりに氷見線の利用となって、ようやく北陸ワイド周遊券の活用となる。5分遅れの13時14分の441Dに乗り込めば、国鉄型車両のキハ40系で旅の雰囲気が出る。越中国分を出るとすぐに進行方向右手に富山湾が広がり眺めが良い。折角なので駅名に魅かれた雨晴で下車してみる。
踏切を渡って雨晴海岸へ出ると、岩礁、白い砂浜、青松が続く景勝地となっていた。今日は霞んでしまっているが、天候次第では富山湾越しに見える立山連邦が雄大な姿を見せてくれるらしい。万葉の歌人の大伴家持は、この雨晴の風景をこよなく愛し、多くの歌を詠んだという。
雨晴から乗った13時56分発の443Dも6分遅れで、単線の氷見線では一旦生じた遅れを取り戻すのはなかなか難儀であるようだ。当然のように遅れを持ち越したまま終点の氷見に14時10分に到着する。
氷見から七尾までは鉄道空白地帯となるが、今度はJR時刻表にもバスの時刻が掲載されているので安心だ。途中で乗り継ぐ必要があるものの、七尾までの足はしっかりと確保されている。バスは駅前に入らないので、国道160号線沿いの氷見駅口停留所まで足を運び、次のバスの時刻を確認する。JR時刻表の記載と同じ15時03分だったので、1時間近い待ち合わせとなるので遅めの昼食とする。氷見駅から停留所まで来る途中に「氷見うどん」の舌代を掲げた食堂があったので入ることにする。
なかなか学生の身分ではグルメとは縁遠い旅が続くが、うどんぐらいであれば手を出すことができる。食堂は時間がずれているため先客はなく、営業しているのかも定かではないが、声を上げると奥から婆さまが出てきて営業中であるとのこと。4人ともご当地名物の「冷やし氷見うどん」(580円)を注文する。氷見うどんの特徴は、強いこしと餅のような粘りと風味であるそうだが、普通のうどんより歯ごたえがあるのかなというぐらいの感想だ。さて、そろそろバスの時間だと腰を上げると婆さまは1人630円を要求する。
「氷見うどんは580円じゃないのですか?」
店内に掲げられた舌代を指さして抗議をするが、婆さまは別の舌代を指さす。
「細めんうどんだから630円」
この態度には唖然とした。確かに我々が食べた氷見うどんは細めんうどんだったが、舌代には「氷見うどん580円」「細めんうどん630円」と別メニューとして掲げてあるのだから、「氷見うどん」を注文しているのに勝手に「細めんうどん」を出す方がおかしい。事前に断りがあればまだしも、自分のミスをお客に転嫁する態度に腹が立つ。結局、婆さまは譲らず、バスの時間もあったので630円を置いてきたが、氷見に対する心象はすこぶる悪い。
「あのババァ〜とんでもない奴だな。やってること詐欺じゃねえか!」
藤原クンの怒りももっともで、氷見駅近くの食堂は要注意である。
氷見駅口からは3分遅れの加越能鉄道バスを捕まえて、石川県との県境の集落である脇に向う。氷見線同様に富山湾沿いを走るので景色は良いが、お腹が満たされたためか、他のメンバーは居眠りをしてしまっている。大境洞窟住居跡なるものがあり、降車ボタンを押して睡眠を妨げてやろうかとも思ったが、午前中からの経緯もあるので大人しくする。バスは氷見駅口からは30分程で脇に到着した。
脇は氷見市の北端にある集落で、小さな海水浴場の他には取り立てて何もなさそう。ここからは加越能鉄道ではなく北陸鉄道系列の七尾バスの管轄になるが、加越能鉄道が富山県(越中)と石川県(能登)の県境手前で路線を打ち切るのはけしからん。脇でも1時間近い待ち合わせとなり、奥田クンと藤原クンは元気に海辺で繰り出したが、安藤クンは依然として動かない。
16時30分の七尾バスで富山県と石川県の県境を越える。早朝に富山県入りしたばかりだが、わずか1日で富山県を駆け抜けてしまった。バスは百海(どうみ)で富山湾に背を向けて七尾市街地に向い、終点の七尾駅前には17時08分に到着。脇からの運賃は720円であった。
七尾市は能登半島の中核都市に過ぎないが、なんだか久しぶりに都会へやって来たような錯覚に陥る。そろそろ今宵の宿を確保しなければならない時間だが、ここまで来たら和倉温泉に泊まってみたい。17時38分の七尾線147Dで1駅隣の和倉温泉へ移動する。
七尾湾に面した和倉温泉は北陸を代表する温泉街だ。開湯は約1200年前と歴史もある。和倉で暮らしていた漁師夫婦が、湯気の立つ海で白鷺が傷を癒しているのを見て、温泉を発見したのが始まりという。当時は「湯の湧き出づる浦」から「湧浦」(わくら)と呼ばれるようになった。もともとは海中に湧き出る温泉だったが、1641年(寛永18年)に加賀藩主前田利常が湯口の整備と周囲を埋め立てて、湯島とする工事に着手した。その後も湯島の埋め立ては続けられ、京都や大阪などから多くの湯治客を迎えるようになったという。現在のように陸続きになったのは1980年(明治13年)と意外に最近のことである。
さて、そのような和倉温泉に夏休み期間中の土曜日に飛び込みで宿泊しようとする試みはかなりの難儀で、見当を付けていた安宿からはことごとく宿泊を断られる。七尾に戻ってビジネスホテルでも探そうかと諦めかけた頃、公衆電話の受話器を手にした藤原クンから声が掛かる。
「素泊まり4,000円って言ってるけどいい?」
4,000円ならビジネスホテル並みの宿泊料でまったく問題はない。藤原クンが予約をしたのは「湯の華湯口旅館」で、駅構内に広告看板が出ていたので試しに電話をしてみたという。しかも15分後に駅まで迎えに来てもらうことも約束したというのだから大したものだ。普段はあまり旅行もしないというのに行動力は抜群で頼もしい限りである。
出迎えに来た女将さんが運転する車に乗ると5分で「湯の華湯口旅館」に到着。和倉温泉のバスターミナルの正面に位置しており、交通の便も良い旅館だ。それほど大きくないがやはり小奇麗な旅館で、少々我々には場違いのような気もする。もしかしたら空き部屋を安く提供してくれたのかもしれない。
夕食は女将さんから「安く済ませたいのであれば」と紹介してもらった旅館近くの平島食堂へ。どこにでもある感じの食堂で、うどんがメインのようだが、昼食も氷見うどんだったので「コロッケ定食」(735円)で済ませる。後で「鍋焼きうどん」が看板商品だったと知り、悔しい思いをした。
夕食後に温泉街を散策すると「わくわく夏まつり」というイベントが開催中で和倉温泉わくわくプラザと呼ばれる広場では縁日の屋台も出ているのだが、雨が降って来て盛り上がりに欠ける。我々も早々に旅館へ退散し、ゆっくりと温泉に入り、旅の疲れを癒したのであった。
第51日目<< 第52日目 >>第53日目