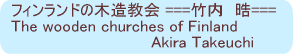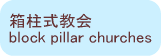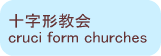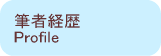|
Aamulehti紙 2010.7.14 Olli
Helen記者 訳竹内晧
より天国へ近く
日本人の建築家がフィンランドの木造教会に惹かれた
1985年、日本で宣教活動をしていたペンティ・カリコスキ牧師はフィンランドを知ってもらうために、日本からグループを招いた。カメラのシャッターを切りながら、名所旧跡を巡る観光客はよく見かける姿だ。そんな一般の観光客と竹内晧(71歳)は完全に違っていた。彼は小さな弁柄色の田舎の木造建築に興味を抱いた。それらは自然の中で美しく調和していた。彼は遠くで眺め、詳細は近づいて観察し、そして弁柄板に触ったりした。そんな彼であったから、まさに新しい運命に導かれていった。竹内は、2010年の春、東京で、“フィンランドの木造教会-17世紀、18世紀における箱柱教会の構法と歴史”という美しい本を出版した。
ノキアの携帯電話のように
竹内は1985年以降、毎年のようにフィンランドを訪ねた。どこに素晴らしい村が有るか、教会村が有るか、場所を決めてフィンランドを廻った。彼は教会の内外を調査し、写真を撮り、計測し、図面を描いた。彼は教会の管理人に頼んで屋根裏にも上がった。
とりわけ、西海岸地域の、堂々とした、聖堂風の木造教会には大きな魅力を感じていた。1600年代のそれらの木造教会には、ストックホルムや中央ヨーロッパの成熟した石造教会の影響が色濃く見られると彼はいう。箱柱式教会の高い技術を駆使し、ヨーロッパの成熟した石造教会の高い天井、空間を木造教会で可能にした。
竹内はスウェーデンやノルウェーの木造教会も調べたが、そこには、箱柱式教会のような高い技術は見いだせなかった。このような技術は、フィンランド西海岸地域だけに見られる固有のものである。それは、ノキアの携帯電話に匹敵する革新的なものだと彼は言う。
フィンランドで仕事が
竹内は日本の三菱地所設計部で建築家として働いていた。彼は日本の各地に巨大ビルを設計していた。彼の最後の作品は、大阪アメニティー・パークで事務所とホテルの複合ビル、4ヘクタールの敷地に40階の高層ビルであった。・・・・・・・省略・・・
1996年彼は早期退職すると、フィンランドへやって来た。
キリスト教の目で
竹内は最初、トゥルク大学でフィンランド語を学んだ。3年間でフィンランド語も上達した。その後、タンペレ工科大学・大学院に移り、17世紀、18世紀の木造教会について研究を始めた。その研究に当たり、フィンランド文化財団と政府建築芸術委員会の助成金を受けている。2008年、彼はフィンランドの木造教会の技術について東京大学で博士号を取得した。
昨年の秋、東京に戻り、フィンランドの百以上の木造教会を視察した結果を纏め、上梓したのである。・・・・元々、仏教徒の彼は、フィンランドでキリスト教の洗礼を受けた。クリスチャンの目で木造教会を見た方がより理解できると考えたからだ。
村の中で
竹内はフィンランド語を上手に話すが、しかし言語の行き違いはいくつかあった。例えば、教会を調査している時に、その教区の牧師に会った。竹内はこう話した「一緒に天国に行きませんか」。牧師は「未だその準備が出来ていないから」と答えたので、彼は「教会の屋根裏のことですよ」と訂正した。
この夏、竹内はフィンランドにやって来た。日本で出版した本を、フィンランド語に訳し、出版できないかを探るためである。
「フィンランド人は木造教会をほんとに大切に守っている。教会はフィンランド人にとって大切な建物で、あたかも心臓のように、町の中心に位置している」と竹内は言う。
写真の説明:竹内はタンペレのテイスコ教会の素晴らしい屋根架構、天井に注目している。調査した殆どの教会の屋根裏を訪ねたと彼はいう。 |