

「ごんぎつね」は新美南吉のすてきな童話のひとつですが,4年生にあの何ともいえない世界を
味わわせるのは,至難の業です。「何もしないで,味わえばよい」という意見もありますが,やは
り教師としては,「深い読み取りをして作品の世界を味わい,作文や音読で,その世界を表現さ
せたい。」と思わせる作品です。
| 学習問題へ | 国語の部屋へ | 指導案へ | 児童の感想文から |
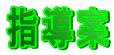
| 4年国語科学習指導案 |
| 指導者 4年○組 松井 直 |
| 1 単元名 『ごんぎつね』 |
2 目 標 ○ 生き生きとした表現を通して、人物の様子や気持、場面の情景を思い描き、作品の世界 にひたらせる。 ○ 様子をあらわす言葉や比喩表現の役割を理解して、物語を読み取ることができるように する。 |
3 指導観 (1) 教材観 ひとりぼっちになってしまった兵十とごんは、お互いの境遇を一番理解し合える仲でありながら,死をもってしか心を通じ合えなかった。この2人の姿は読む者に何ともいえない哀しさを伝えてくれる。 ごんはひとりぼっちでさびしかった。ごんのいたずらはそのあらわれである。兵十のうなぎを逃した時も軽いいたずらのつもりだったのである。しかし、兵十のおっかあが死んだ事を知ると、ごんの心は大きくゆらぐのである。自分の犯したいたずらと兵十のおっかあの死を結びつけ、自分のせいだと思い込むようになる。物語を読むと兵十のおっかあが「うなぎをたべたい。」と言いながら死んだかどうかは定かではない。しかし、ここではそう思い込み、悔いるごんの姿がいじらしい。ひとりぼっちであるが故に、兵十にとっておっかあがどんなに大切なものであるか、痛いほどわかるのであろう。 物置の後ろから、ひとりぼっちになってしまった兵十をじっと見つめるごん。いわしを投げ込んで、かけもどる途中の坂の上でふりかえるごん。その姿は兵十を自分と同じ境遇へ追いやってしまったことへの深い後悔が感じられ、なんともいえないいとおしさがわいてくる。そっと兵十を見つめるごんには、兵十の心が痛いほどわかったにちがいない。なぜなら、その姿はまさに自分の姿だったからである。だから、ごんは次の日も次の日もおくりものを持っていく。それがごんのやさしさであり、ごんにできるただ一つのつぐないだった。 兵十と加助の後をつけて、危険をおかしてまで二人の話を聞こうとするごんの姿もまたいじらしい。兵十の影法師をふみふみいくごんの姿はかわいらしくもあり、兵十とごんの気持ちのずれを考えると、悲しいほどに美しい情景である。きっとお念仏の間ごんは自分の罪を悔い、ひたすら兵十のおっかあのめいふくを祈っていたことであろう。 ごんのそうしたつぐないは、兵十に神様のおかげだと思われても続くのである。 私はこれまで、ごんが「その明くる日も」兵十の家へくりを持っていったのは、ごんが「兵十と友達になりたい。兵十におれだとわかってもらいたい。」という気持ちが強いからだと考えていた。しかし、裏口からこっそり入るごんの姿や、うなずくごんの気持ちを考えてみると、どうもそうではないような気がする。ごんは、自分が兵十にとって憎むべき相手であることを知っているはずである。そういう関係にあるものに対して、「友達になりたい。」という気持ちを持つというのはどうもすっきりしない。いやむしろおかしいと思うのである。 ごんは、引き合わないと思ったあの夜、悩み考えた上で、「それでもいい。それでもおれは、兵十のためにできるだけのことをしよう。」と決心したにちがいない。明くる日、ごんは「おれなんだよ。」というそぶりは全く見せず当たり前のように裏ロヘまわる。そこに、神様だと思われても、つぐないをやりぬこうとするごんのいじらしいほどの決心が見えてこないだろうか。兵十のおっかあの死を自分のせいだと思い込むごん。兵十の心を自分に置きかえて考えるごん。そして,けなげでいじらしい決心を持って兵十の家へ行くごん。ごんのそんな姿を思うと,この最後の結末は何ともいえない哀しさ,あわれさに包まれてくる。 ひとりぼっちの村の中で,ただ一人,自分をあわれみ助けてくれていた本人を,兵十は撃ち殺してしまったのである兵十は,ごんを撃ち殺して,はじめて,ほぼ直感的にすべてを知る。ごんの心が兵十に通じる。しかし,そのためには,死という代償を払わなければならなかった。人間というものは,こんなにも哀しい存在なのであろうか。つつから出ている青いけむりは,そうした人間の哀しさの象徴であるような気がしてならない。 優しく哀しく描き出されたこの物語を,美しい情景描写の中でしみじみと読み味わわせたいものである。 (2)児童の実態 本学級の児童は、これまで学習問題を設定した後、自分たちで問題解決をはかり、残された重要問題をみんなで考えていく形で学習を進めてきた。初めは表面的なことしか気づかず、作品の核心に迫るような学習問題ができなかったが、2学期になり『一つの花」では、学習問題も意図的で重要なものが多くなった。そのため感動的な場面も見られるようになり、楽しい授業ができた。 今回は、全文視写から書込みの時間を多く取って学習問題を作り、そこから何とかこの作品の世界にひたらせてみたい。 (3)指導にあたって 指導にあたっては、最後まで貫かれたごんのいじらしいほどのつぐないの姿をクローズアップさせ、最後の場面ヘつないでいきたい。そのため、ごんの「六地蔵さんの影から、のびあがる姿」、「物置の後ろからそっとのぞく姿」,「坂の上から振り返る姿」、「井戸のそばにしゃがんで、お経を聞く姿」、「兵十の影法師をふみふみいく姿」を大事にしておきたい。 また、この物語のクライマックスは最後の場面であるが、ごんの「それでもいい』という、いじらしい決心を明確にしておき、死をもって自分の心をわかってもらえたごんのあわれさ、ぼうぜんとする兵十の心の中を読みとらせたい。そのためには、「かためて」にこめられたごんの思い、「ごん。お前だったのか・・・・」の内容の追求が核になると考える。そこが読みとれれば、「うなずきました。」、「バタリ」は、おのずと子供たちの心の中へはいっていくのではないだろろか。 |
| 4 指導計画 (1) 全文を読み、語句指導をする。(1時間) (2)みんなで学習問題をつくる。(2時間) (3)書き込みをしながら、おおまかな内容をつかむ。(2時間) (4)みんなで話しあいながら、内容を読みとっていく。(6時間)(本時6ノ6) (5)まとめをし、感想を書く。(1時間) |
| 5 本時の目標 ○ 死をもってしかわかりあえなかった、「ごん」と「兵十」のかなしさ、あわれさを読み取る。 |
| 学習内容及び学習活動 | 主な発問と児童の反応 | 指導上の留意点 |
| 1 学習問題を確認し、(6)の場面を読む。 |
○今できる最高の読みで1回読んでください。 |
・ 読みの指導を通して、本時のめあてをはっきりする。 ・指名読みをさせ、読みとりの実態をさぐる。 |
| 2 「その明くる日も」くりを持っ ていくごんの気持ちを考える ○ かためて ・ その明くる日も ・ こっそり |
○ つまらないと思ったはずなのに、なぜごんはくりを持っていったのですか。 ・それでもつぐないをしたかった。 ・兵十と友達になりたかった ・わかってほしかった。 ◎ ごんはくりをかためながらどんなことを考えているでしょう。 ・兵十,ごめんよ。ゆるしてくれ。 ・おれの気持ちをわかってくれ ・おまえが好きなんだ。 |
・ 「かためて」を中心に話しあわせ ごんのいじらしい気持ちを明らかに していく。 ・ わかってほしかった。友達になりたかった。も認めていく |
| 3 ごんの行為の意味に気づいた兵十の気持ちを考える。 ○ ごん。お前だったのか。 ○ うなずきました。 |
◎ 「ごん。お前だったのか。」は、だれに向かって言った言葉ですか。また、それはなぜですか。 ・ごん ・兵十 ・まさか、そんな ・大変な事をしてしまった。 ・ごん。ゆるしてくれ。 ◎ ごんはどんな頗でうなずいたんですか。 ・うらみのない、安らかな顔 ・兵十をうらんでいる。 |
・ 家の中=くり=ごんと移る兵十の目の、くり=ごんを大事にする。 ・ 声にならないためいきのような兵十の声を、朗読を通じて感じとらせる。 ・ ここでは、ごんは兵十をうらんでいない。対立する意見が出たらつぶしていく。 |
| 4 ぼうぜんとする兵十の気持を考える。 ○ パタリ ○ 青いけむり |
5 兵十の心、見えますか。 ・なにもない。 ・大変な事をしてしまった。 ・どうしたらいいんだ。 |
・ 何も考えられないほど、心が動揺してしまっでいる兵十のあわれさをつかませる。 |
| 5(6)の場面を表現読みし、まとめをする。 ・ 音読 |
◎ 今日、学習した内容をこめて読んでください。 | ・ 体を使い、内容を表現する朗読をさせる。 ・ 次時の予告をする。 |
国語の学習では,音読がとても大切だと思います。1時間の授業の中で,最低でも3回,できたら
5回は声に出して読む時間がほしいですね。特に,心を込めて体を使って読むという活動を大事に
したいです。
3年生や4年生は,その気にさせると,力を発揮しますので「ほめながら」上手に読める力をつけて
いきましょう。6年生ぐらいになると,合唱の実践のページにある「かたくりの花」のような質の高い
表現ができるようになります。