武蔵円明流の歴史 ※ご参考に「武蔵円明流の剣脈図」(一頁)を併せてご覧ください。
 |
↑武蔵円明流神霊図
(高砂市宮本武蔵伊織顕彰会蔵) |
武蔵円明流(むさしえんめいりゅう)は、神明武蔵政名流(しんめいむさしまさなりゅう)とも言う。
武蔵円明流の原祖は、剣聖・宮本武蔵玄信である。流祖は宮本武蔵政名(みやもとむさしまさな、岡本馬之助祐実 おかもとうまのすけすけざね/改名)である。
◆起 源◆円明流流祖・俊乗房重源
宮本武蔵玄信が創流した兵道鏡円明流・二天一流の原祖は、円明流流祖・俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん、俗名/紀刑部左衛門尉重定、1121〜1206年)である。
平安時代末期、京都・鞍馬にて、源義経は鞍馬天狗大僧正(一演僧正)を師として鞍馬流を修業し、鞍馬山に封ずる所の兵書数巻を得、後に義経流を創流した。重源もまた鞍馬天狗大僧正(一演僧正)の弟子で技芸の達人であり、義経より鞍馬流(義経流)を極意伝承された。
【資 料】
『此の書は大江匡房中華伝の兵書也。兵法就中剣法大悟す。義経流剣術修錬偉大なる義経公の功也。御門下の俊乗房重源能八ヶの妙術有る流法を得門士を教道し伝え来る。』
重源が創流した円明流は、門弟の八尾別当顕幸へ印可された。顕幸の門弟、岡本三河房は円明流の印可を受け、後に岡本円明流を創流した。
重源はまた、後に義経流を陰流に改めた陰流・新陰流の原祖でもある。
【資 料】
『年起伝来曰(い)う、文治の此(ころ)、右大将源頼朝・義経両公不和を生じ給い。終(つい)に義経、奥州高館の城に亡び給う。因(よ)って、俊乗房重源は鎌倉殿下(源頼朝)を憚(はばか)り義経流の号を止(とど)め陰流に改む』
重源の門弟、愛洲移香斉久忠(あいすいこうさいひさただ)は印可を受け愛洲陰流を創流した。久忠の門弟、愛洲元香斉小七郎宗通は猿飛陰流を創流し、宗通の門弟、上泉伊勢守信綱(かみいずみいせのかみのぶつな)が新陰流を創流した。二刀流は柳生新陰流奥伝に伝承されており、武蔵円明流・二天一流は、新陰流と同じ系統の流派である。
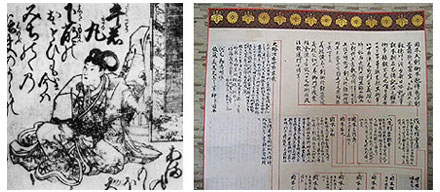
左:牛若丸、右:剣脈図部分(高砂市宮本武蔵伊織顕彰会蔵)
◆創 流◆武蔵円明流原祖・宮本武蔵玄信〜武蔵円明流流祖・宮本武蔵政名
宮本武蔵は、青年時代(通説22歳・推定33歳)に当理流(養父・宮本無二之助、円明流から分派)から独立して二刀兵法の兵道鏡円明流を創流した(晩年、二天一流創流)。
「兵道鏡」の極意は「真通之位(じきつうのくらい、「兵道鏡36箇条」では真道之位)」であり、これは当理流には無く、宮本武蔵自身が得た剣理である。「真通之位」は定まった型があるのではなく、自分が思ったとおりに戦いを展開し勝つ境地のことである。武蔵は「兵道鏡28箇条」の中で「真通之位」とは「兵法之魂也」と言いきり、これを自得すればもはや「表」と「奥」も無いと説いた。
「奥と云、これよりも奥なし。されば、大師高野山奥の院を立たんと山深く分け入りて、おもえばいまだあさし。奥の院なればなお深く尋ね行きて見れば、又家村近く見ゆる。さて云へり、
中々に人里近くなりにけり あまりに山の奥を尋ねて、 と也。」
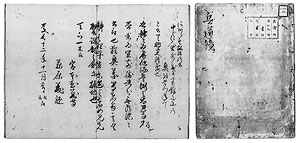 |
「兵道鏡」写本の表紙と末尾
(慶長12年11月の増補判。高知県立図書館蔵) |
武蔵は「真通之位」という独自の境地を切り拓き、門弟の宮本武蔵政名(岡本馬之助祐実/改名)と政名の兄・宮本武蔵義貞(岡本小四郎政名/改名)へ兵道鏡円明流の極意を伝授した。義貞は武蔵流を創流、父・岡本新右衛門義次(備中蘆森城主、岡本円明流)より伝わる十手刀術は『常用の器にあらず。太刀は常用の具なる』をもって、この十手鍛錬修業の極意を太刀打ちの道にうつし、武蔵流の兵法とした。のち政名は父兄の岡本円明流、武蔵流の流意を相伝して、慶長15年(1610年)武蔵円明流を創流した。
宮本武蔵政名は、師の宮本武蔵玄信と同じく文武両道であった(著書は20数冊)。江戸時代中期は、武蔵玄信より武蔵政名の方が有名で、『撃剣講談』では宮本武蔵政名が佐々木小次郎と決闘したとし、宮本武蔵玄信と宮本武蔵政名を同一人物視しているが誤りである。
 |
| ↑巻物(高砂市宮本武蔵伊織顕彰会蔵) |
武蔵円明流の兵法は「兵道鏡36箇条」であり、武蔵の心身に対するこまやかな心配りと観察眼、そして己が取り組んでいる兵法に対する誠実さが伝わってくる。「五輪書」では詳しく書かれていない型の動きが「兵道鏡」においては、対照的に実に具体的に書かれている。これによって武蔵の二刀の使い様がうかがい知ることができる。
◆中興の祖◆武蔵円明流初世宗家師範・岡本勘兵衛正諠
武蔵円明流の初世宗家師範、宮本武蔵政名6代目孫の岡本勘兵衛正諠(おかもとかんべえまさよし)は、父祖伝来の岡本円明流とともに岡本流体術・二刀剣法を合わせて武蔵円明流を大成させ、「三学の巻伝授の義理(大義)」「修業目録」「極意の大義」「当流相続の義理(大義)」を確立した。武蔵円明流は正諠により鳥取地方に元文・寛保(1736〜1743年)頃伝えらえた。
正諠は、諸国をめぐって鍛錬を怠らなかったが、彼はこれを武者修行とはいわないで単に「行脚(あんぎゃ)」と呼んでいた。元文・寛保の頃、因幡に来て覚寺に足を止め農家の若者たちに体術を教えたが、村人は浪々の武士で食うに困るであろうと各自米を持ってきて謝礼とし、正諠に「どうかこれで濁酒をつくり、売って糊口の資としていただきたい」と申し出た。正諠はこの申し出に応じたが、すこしももうけようとはせず、ある時は一文で三合売り、ある時は二文で五合売るというありさまであって、とても商売にはならなかったので、村人も再びこれをすすめようとはしなかった。
その後、正諠は門人のすすめにしたがって鳥取に移り、豆腐町に住んで剣術指南の看板をあげた。
これを見た東軍流師範の井村九郎三郎が門人を使者として、「師範に挨拶もなく道場を開くとは無礼である。さぞかし腕に覚えがあろう。わが道場に来て試合をせよ」といった。これに対する正諠の応対が面白い。「わが剣術指南は武士の剣術ではなく、その日その日の食を得るための浪人剣術である故、何卒お許し願いたい」と弁明したが、九郎三郎は一向にきき入れない。正諠はしかたなく井村道場を訪れ立ち合うこととなった。まず主だった門弟と試合をしたが、とても相手にならない。みるまにことごとく打ち込まれてしまった。そこで師範九郎三郎も立ち向かったが、これもまた見事に打ち込まれてしまった。九郎三郎は潔く刀を措いて、今までの無礼をわび直ちに入門した。
この話はまたたくうちに城下にひろがり、正諠の武名は大いにあがったので、鳥取藩(因洲藩)の池田定就よりも招きを受けるに至った。これは岩流の師範小谷成福(疋田流剣術の師範も兼ねていた)の推薦によるものであった。定就の命により正諠は成福と試合をしたが、やはり正諠の勝ちで、成福もその場で直ちに弟子の礼をとって入門した。池田家でも正諠の素晴らしい腕前と立派な人柄をみとめ、微禄ではあったが召し抱えることとなった。
正諠は鳥取藩の剣術指南になり、正諠の門人中、鱸武允時維・松井源太夫満雄・井尻武左衛門孟雅・藤田順蔵・広沢清蔵・井村九郎三郎・寺島金左衛門・小谷十左衛門成福を「岡門の八士」と呼び、特に傑出していた。
 |
左:鳥取城古写真(鳥取県立博物館蔵)、右:鳥取城跡
鳥取城は標高263mの久松山に築かれた城である。鳥取藩は32万石、幕府から家門大名並の待遇を与えられる。池田忠継(輝政次男)を家祖とする外様大名。父:輝政、母:徳川家康の次女督姫との最初の男子。 |
武蔵円明流は俊乗房重源から約860年、流祖宮本武蔵政名からは約400年、初世宗家師範・岡本勘兵衛正諠から現在の15世宗家師範・荒川公延まで続いている。

左:笠打序之書、中:口授書、右:修業目録(高砂市宮本武蔵伊織顕彰会蔵)
(最終更新:121011)
|