PETER BEETS
結局は、ライヴはライヴで聴くのが一番という結論になるのであろう
"LIVE AT THE CONCERTGEBOUW VOLUME 1"
PETER BEETS(p), FRANS VAN GEEST(b), GIJIS DIJKHUIZEN(ds)
2005年4月 ライヴ録音 (MAXANTER RECORDS CD MAX 75233)
このアルバムに掲載された6曲、全ての曲は今まで掲載してきた4枚のアルバム(JAZZ批評 63.、133.、182.、270.)の中で演奏されている。そういう意味では、今回のライヴ・アルバムは今までの集大成としてのライヴだったのかも知れない。だから、僕にとっては聴き慣れた曲ばかりで、新鮮味に欠けた。⑤を除く全ての曲がBEETSのオリジナルだ。ライヴ録音なので、どの曲も8分以上の長尺ものだ。
更に面白いことに、僕が所持している4枚のCDと、このアルバムでは全てのサイドメンが入れ替わっているのだ。この辺に、このピアニストのポリシーがあるのかもしれない。同じ曲は何回も演奏しているが、同じメンバーでは録音しないということが、BEETSの面白さなのかもしれない。より新しい発見を求めてメンバーチェンジを繰り返しているのかも知れない。メンバーを替えることによって新しい何かを導き出そうとしているのかも知れない。でも、やるからには更に煮詰まって濃密、濃厚になっていかなくてはいけないと思うのだ。果たして、そうなっているか?単に実験で終わってしまっては寂しい気がする。
①"DEGAGE"
②"IT HAS HAPPENED"
③"THE JUDGE"
④"TRISTITY" ここまでは硬軟取り揃えて、ほどほどにバランスよく演ってきたと思う。
⑤"I'VE GOT MY LOVE TO KEEP ME WARM" この曲と次の曲ではプレイヤーのテンションが高まってきている。ライヴという環境は聴衆の反応が即、ダイレクトに反応するから、ややもするとオーバー・プレイになる場合がある。その塩梅が結構難しいのだと思う。もう、脇目も振らず没頭しているという感じなのだ。
⑥"IT'S HAPPENING" この演奏をナマで聴いた聴衆にとってはノリノリの演奏で「最高!」と思うに違いない。ここが、CD化の難しいところだ。その場に居合わせないリスナーとその場にいたリスナーとでは聴衆自身のテンションがまるで違うのだから。結局は、ライヴはライヴで聴くのが一番という結論になるのであろう。
BEETSのピアノは録音の回数を追う毎に饒舌になってきたような気がする。もともと音数の多いピアニストであったが、今回のアルバムでは今まで以上の饒舌さが目立つ。ライヴという環境が余計そうさせているのだろう。
BEETSのようなテクニシャンが陥り易いのが「饒舌の罠」だと思う。あたかも「鍵盤を叩いていないと不安に駆られる症候群」のようでもある。BEETS自身が「これは最高の演奏だ!」と言ったどうかは知らないが、僕としてはMARIUS
BEETS(お兄さん)、JEFF HAMILTONを従えた"FIRST DATE"(JAZZ批評 182.)やLARRY GRENADIERとWILLIE JONES Ⅲを従えた"PAGE TWO"(JAZZ批評 133.)の方が印象に残る。この2枚にはサイドメンから得た程よい抑制が働いている。
BRAD MEHLDAU(INDEX A TO Z)が凄いのは抜群のテクニックがありながらも、それに埋没しない自制心を持っていることだ。何と言っても、「間」が良いのだ。この違いは大きい。
BEETSは1971年の生まれだというから、現在34歳。まだまだ若いし、発展途上と言えるだろう。今後、更に進化して「間」の良いピアノを聞かせてくれるものと期待したい。 (2005.12.09)
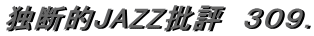


![]()