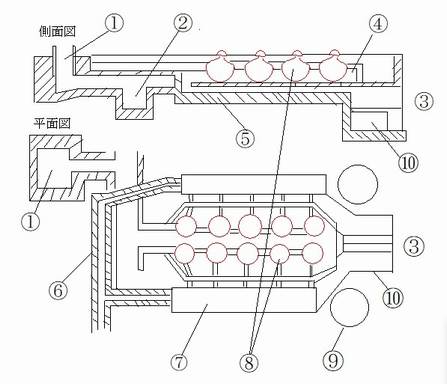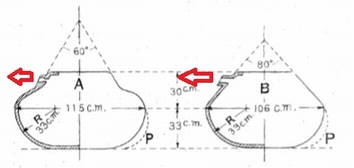��������̓���
��V�s�X�n�����̎c��R����o��B
�A�v���[�`���猃�M�ŁA�t�߂ɂ͓��ݕ���������Ȃ��B
���ɃA�^�b�N������I�ԍz�R�Ղ��ƌ�����B

�F���̖铹�Ȃ��Ζʂ��AGPS����łЂ��o��B
�퉷�̗����͉��F�̌ő́A���_���Ⴍ120���ȏ�ʼnt�̂ƂȂ�B
���̕��_���͍������A�����̐��B�Ɣ�r����Ɨy���ɒቷ�ŏ����\���B

�����o��ƍr�n�̕��ꂪ����B
���_�̒Ⴓ���K���������z�ɑ����̔M��������ƁA�����𒊏o���邱�Ƃ��ł���B
�܂���C���ł�370���Ŕ��A��_������
�iSO2�j�ƂȂ�B

�O�B�t�߂������ς�炸�p����ԁB
�����͋�����
�u�������v�����₻������z���̌��f�ƌ��ѕt���Ăł���������
��
�u���_���z���v���_�̐��f���������f�Œu���������������B�d���E�p�Ȃ�
�Ƃ��Ď��R�E�ɗl�X�Ȍ`�ő��݂��Ă���B
�����Ɖ������₷���A��̑����i������ō����ނ̂͗�����
�iAg2S�j�ƕω����邱�Ƃ������ł���B

�����̃v�[���[�炵����\�B�t�߂ɂ̓��C���[���c��B
�ΎR�n�тł͉������łȂ��P�̗̂����Ƃ��đ��݂��A
����͉ΎR���K�X�Ɋ܂܂�闰�����f�iH2S�j��
��_�������iSO2�j�������ʼnΎR���ӂɗ������������R�ƂȂ�B

���̐�ɂ́B�~�Y�o�V���E�̌Q��������B
���{�̗����z���͂��ׂĉΎR���ŁA
�u�z�����z���v�}�O�}���番�������M���E�K�X����̊���ڂŗ������A
�u���a�z���v�J���f���Ȃǂŕ��C�ɍ������Ă������_���܂ޓD�E������`���A
�u���؍z���v�ΎR�K�X���̗������Ό��╬�C�E�ŏ����Ăł����z���A
�u�n���z���v���Ό��╬�C�E����n�Z�����������d�����Ăł����z��
�Ȃǂɕ��ނ����B

���[���̈�\�B
�O�Ԃ�410�������x�̃i���[�ő傫���A�[����`���Ă���B
�t�߂ɂ͋��O�B�A�O�B�A���l�B�����݂��Ă����B

�����ɂ̓��C���[�̈�\�B
�����O���̃�12mm���x�B
���炭�����̍��ՂŁA����͌�ɏؖ��Ɏ���B

��̎c��Ζʂ��A�O�B�Ƌ��l�B�B����T���ĕ�������B
�吳�������珺�a�ɂ����Ă̎����́A
�����Ƃ≻�w�@�ۋƂ̔ɉh�ɔ��������z�������Y�K�͂����܂�B

�����Ĕ��������͖̂��v�����O�B�̍B���ł���B
�����H��ŕK�v���u�N���t�g�p���v�v�h�C�c�ꁁ�����p���v�A�������̌���
�������ɕs�������O�j���������A
����ɂ͗����i�g���E���iNa2S�j���g�p����A�܂܂��̂͗����iS�j�ł���B

���v�B������`�����ށB
���[�����Ȃǂ̉��w�@�ې������ɂ�
���Y�f�iCS2�j���g�p����A������܂܂��̂͗����iS�j�ł���B

�B�������͌��������v���Ă�����̂́A
�x�ۍH���c��A�h�����Ă̌��Ԃ�����B
�������Ȃ���A���B�͕s�\���B

���Ȃ��Ζʂ�o��A����ɏ㕔��ڎw���B
�펞�F���Z���Ȃ鏺�a19�N�i1944�j�ɂ͊�Ɛ����߂ɂ��A
�����E
�y���Ȃǂ�
��K��9�����z�R�������A�啔���̗����z�����x�R�ƂȂ�B

�X�ɐi�����B�t�߂ɂ̓��[�����c������B
���A���N�����̌R���i�C���ǂ����ƂȂ�A���a21�N�i1946�j10�z�R�ł����������z���́A
���a28�N�i1946�j�ɂ�36�z�R�ɑ�������B

���[���̉ʂĂ�s����ɂ͍B���A�����B�̐���̉ʂĂł���B
�I�V�@��̗����z���͑��z�R�ɔ�r���A���Ȃ����������ŋN�Ɖ\�ł���A
��z�����Z�p�͂��K�v�Ȃ��A�����z�R����C�ɂ��̎����ɉh����B

���Ă�ꂽ���[���B�B
�R�����������ȍ~�͗������i�̖\�����������A�㏬�z�R����C�ɕR�A
�Ȍ�R�z�R���𑼍z�����Y�����ŕ₢�A�N��20��t�̐��Y���ێ����ꂽ�B

����͓|�ꂽ�����̎x���ł���B
�X�ɎR��̐V�܍B����A
�A�v���[�`�|�C���g�̊C�݉����܂ŁA
�����̋L�ڂ��z���}�ɂ͂���B

�W�����҂��Ƃ����͐A���̖����Y���R���B
�����ɂ͗����������܂܂�Ă���A���̂܂ܔR�Ă���Η����_�����������A
����͌��Q�̌����ƂȂ�B

�Y���R�̏�ɂ͗������̈�\������B
�����A�����͕i������̂��߂����ɒE������Ă������A
���Q��肪�����������a42�N�i1967�j�u���Q���{�@�v���{�s�����B

�������̈�\�͉��˂̂悤���B
���Q���Љ��艻�����ȍ~�A�d���̒ᗰ�����͊�{�����ƂȂ�A
�E���ɂ���������̐��Y���A�����z�R���ނ̗v���ƂȂ��Ă����B

���˕t��
���ˏ�ɂ͒��|���̊�����������B
������110���ŗn�Z���邽�߁A�z������ȏ�ɉ��M����Η�����������B
�����@�Ƃ��Ă̓_���j�@�A���R�@�i�g�����L�j�A�Ď�@�A���C���B�Ȃǂ�����B

���̒����̓|�b�g�i�ۊ��j�ƌĂ��B
�_���j�@�͕��q�ɕi��80���ȏ�̏��ؗ���������
300�����x�ɔM���A�\�ʏ�̗��������������B

���R�@�i�g�����L�j�͍ł����n�I�Ȑ��B���@�ŁA�z���ƔR�āA�n�Z����������A��������50�`55���B
��_�������A�������f�̉��Q�A�����Đ��i���s�����������ƁA
���K�͍z�R�Ő��̔R���s�����Ɏ{�H���ꂽ���@�ł���B

��������z�R�ł͂��̏Ď�@���{�H���ꂽ�B
���炩���ߔM�����|�b�g�i�ۊ��j�i�G�j�ɍz�����A�����i�B�j����Ίi�q�i�I�j�ŐΒY�Ȃǂ�R�āA
���i�����i�D�j�Ə�i�����i�C�j��ʉ߂����M�C��p���āA
220���Ń|�b�g�ꕔ�ɗ������͐ρB
450���ɕێ�����Ɨ����͋C�����ăR���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j��ʉ߁A
��p����t�̂ƂȂ��������𗭊��i�H�j�ōd��������B
�C�̂Ƃ��ď����������ؗ����͉ؑ��i�͂Ȃ���j�i�E�j�ňꕔ�ߏW����B
�]��M�C�͑剌���i�A�j��ʉ߂��A���ˁi�@�j�Ŕr�C�����B
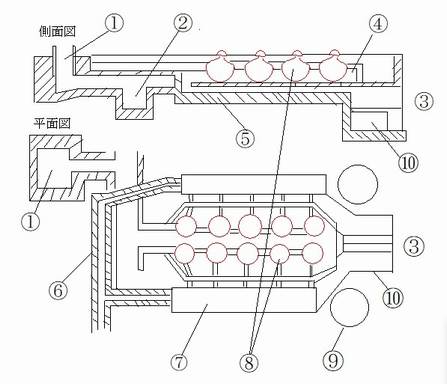
�����i�B�j�t�߂ł���B
����42�N�i1909�j���Ɏn�܂����Ď�@�́A���̌�ł����y�����A
���{�����B�p�Ƃ�������B

�܂����̕����i�B�j�ŐΒY�A�d�ށA�R�[�N�X�A�d���Ȃǂ�p���ĔM������������B
�\�z�ɂ͐ԗ���20,000���A�ωΗ���850�����x��p����B
�ωΗ����͑ωΓx1,630�`1,970�����x�ł���B

�����i�B�j�A�����i�C�D�j�A�R���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j���̔z�u�ł���B
�����i�B�j���琅����9�`11m���i���鉺�i�����i�D�j�A�㕔�܂�Ԃ��ĐL�т��i�����i�C�j�B
���̏㕔�Ƀ|�b�g�i�ۊ��j�i�G�j�����܂�A�O�����R���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j���B�i�}�E�Xon�j

���ꂪ���߂�ꂽ�|�b�g�i�ۊ��j�i�G�j�ł���B
���̒ꕔ�ɉ����i�C�D�j������A���̃|�b�g������������M������̂ł���B
���̏������͒��a1,150mm�A�[��630�o���x��450�`525�s/�ƂȂ�B

���̂悤�Ȓ��|���̏d���ȊW�Ŗ����A
���ۂɂ�10�`14���ԘA���ʼnΕ����s�����߁A
���̊ۊ��̎�����8�`18�����ƂȂ�A�g�p��͓��ցE�j�������B

�|�b�g�i�ۊ��j�i�G�j�̒f�ʐ}�ł���B
�C�����������͏㕔�̃p�C�v������ʉ߂��āi�Ԗ��j�A
���̍H���A�R���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j�֗��ꍞ�ށB
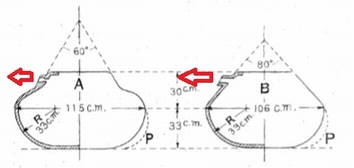
���ꂪ5����ԃR���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j���B
���a750�`900�o�̉~���`�Œ���6�`9m�A�O���ɉt�������̗��o��������A
��������o���Ȃ���X��10�`15���ʼn���A��p����Ă����B

�t�����W�Őڑ�����Ă���̂́A���������������ł���悤�ɁA
�����\���ƂȂ��Ă邽�߂ł���B
�R���f���T�[�̃��C���@�\�͋C�����������������p�t�����邱�Ƃł���B

�����i�B�j�ƕ���ŃR���f���T�[�i���a�ʁj�i�F�j�̔r�o���ł���B
�����ł̔�������
SO2+2H2S=3S+2H2O�ƂȂ�A�܂�
��_�������i�����_�K�X�j�Ɨ������f���������A�����Ɛ����������邱�ƂƂȂ�B

���Ȃ��͏o�����������c��B
���̌�A�����i�H�j�ɗ����߂���A���̎�O�ɂ͈�i�̉���������B
����͗����Ɠ����ɏ������ꂽ��f��Z���j�E�����d���ŏ������邽�߂̂��̂��B

���ꂪ�͏o�����̎M�A�����i�H�j���B
�����œK���܂ŗ�p�̌�A�^�ɛƂ߂Č`��𐮂���B
��������75%���x�A�K�v�Ƃ���R�������i1t������3,000�`4,000kcal�Ɣ�����ł������B

�����͉ؑ��i�͂Ȃ���j�i�E�j�Ղł���B
�ꕔ�������������͂����ŕߏW�����B
���ʂȂ��}���Ă���悤�����A�ۊ��̑ѓd�ɂ�藰���̋C�����}�������ꍇ���������B

�ؑ��̘E�ł���B
����͍����̎x�����B
��600m�̍�����p���āA�������^�������悤���B

�V5�B�t�߂Ń��[�����Ζʂ��B
�Ď�@���ߑ�I��
���C���B
�́A
�I�[�g�N���[�v�Ƃ����������C�e����g�p����B

���[����6�s���ׂ̍����̂ŁA�����N�_�ƏĎ折�Ԃ�����ł����悤���B
�������C�e��ɍz�𓊓����A���C�𐁂����݁A
�����E���M���邱�Ƃŗn�Z��������@�����C���B�ł���B
 �i�}�E�Xon)
�i�}�E�Xon)
�O�Ԃ�510�o���x�̋��O���B
�I�[�g�N���[�v�͍|���ŁA
�ώ_�^�C���̓������{���Ă���B
 �i�}�E�Xon)
�i�}�E�Xon)
���C������
�~�b�V�����̂悤�ȕ��i���R�^�|�̃C�P�[���ŕ����Ă���B
�I�[�g�N���[�v�ɍz�𓊓���A�e�ϔ�2�{�̐������A
�h�a��A�����C�𐁂�����40����150���܂ʼn�������B
 �i�}�E�Xon)
�i�}�E�Xon)
�v�[���[�₻�̎Ԏ����X�ɖ��v���Ă���B
�I�[�g�N���[�v����4�`5kg/cm2�ƂȂ���3�`5���Ԍ�Ɋh�a��~�A
�ꕔ��藰���r�o�A���V�[�o�[�^���N�ŕۉ��Òu�A��ߌ㐻�i�ƂȂ�B

�`�F�[����J���A�M�����F�Z���c��B
���C���B�͏Ď�@�ɔ�r���Ă����Q�������A������80���ƍ������ł���A
�R����1t������1,700kcal�Ɩ��ʂ̂Ȃ��ߑ㐸�B�@���ƌ�����B

�����̋N�_���ɂ̓v�[���[��ˑ䂪�c��B
���������C���B�̒Z���͍z�̐����◱�x�����ɐ��i�i�������E����₷�����ƂŁA
�܂萻�B�O�i�K�ł̕��V�I�z�Ȃǂɂ��z�Εi�ʂ̌���A�ώ������s���Ȃ��Ƃł���B

��5�B���ʂɂ̓R���x���[�Ȃǂ̈�\�������B
�������������̔��o�A�����ւ̐ύڂ��s���Ă����悤���B
���ɂ͋@�ւ�����B

����͉��^����f�B�[�[���G���W�����B
�o��20�n��/500rpm�A�����N���1953�N��(���a28�N��)�B
�R�����R�@�i���j�������}�[�f�B�[�[���i���j�ɕϑJ��������̑㕨���B

���炭�������R���x���[�̉ғ��p�̋@�ւł��낤�B
�����A��^�Ŏn�����舵������������f�B�[�[���G���W�����A
���^�����n����������A�_�Ɨp����|���v�쓮�p�ɕ��y�������i���B

���䂩��]�ލz�R�ՑS�i�B
�����A�������B���̓K�X�ނ̕��U���悭���邽�߁A
�J���I�Ɍ��z�����B

�V�z���t�߂���ĂэB���̒T���Ɍ������B
���J�͍\���̍z�̊�����W���A
���B�̑S���тɐr���������e�����y�ڂ��B

�㕔�ɂ͐A���̖����A�����̃Y���R���B
���J��h�����߂ɁA���B���̖��x�����߂�ƁA
�K�X�̊g�U���s�\���ƂȂ�B

�Ȃ�Ƃ��Y���R��o��B
��_�������iSO2�j�������10������2�̔Z�x�ɂȂ�ƁA
�l�̂ւ̊댯�����O�����B

�Y���R�̃s�[�N����C��ՂށB���㉜�ɂ͖ڗ�������\�͂Ȃ������B
�Ď折�̌���������o������A�t�������������ꍇ�A
�����ɒ����Ė\�����邱�Ƃ��������������B

�X�ɓˑR�A�t�����W�t���̔z�ǂ��]����B
����͎g�p�ς݂̃R���f���T�[�z�ǂł��낤�B
�s�v�c�Ȍ��i���B

���R�����B�t�߂������낷�B
�����̕��H������\��������B
�z���}�ł͋��O�B�ƌĂ��t�߂��B

�@�ւƃ^���N�A�ǂ���Ђǂ����H���Ă���B
�R���v���b�T�[���������j�b�g���B
���܂Ȃ����Ă݂悤�B

�@�ւƃ^���N�A�ǂ���Ђǂ����H���Ă���B
���a30�N��㔼�A�ΒY�ɑ���Ζ�����ʂ��N�X���債�Ă����ɏ]���A
��������̐��Y�͋}���ɑ������Ă����B

�f�B�[�[���G���W���Ƌ���ȃX�N�����x���g�̃v�[���[���ˑ�ɍڂ��Ă���B
�����̗����z�R�̐��Y���͏��a43�N�i1968�j�ɍő吔�ʂ�26��t���݂����A
��������̕��Y���ł��邪�̂̒�R�X�g�ɂ͑����ł��ł����A���N���琶�Y��������B

�����}�[�@2LDL�^�A���b�J�[�A�[����b�V���A�W���X�^�[����̃X�v�����O��������B
���a45�N�i1970�j�ɂ͍z�R����10��t�ɑ��A�������24��t�Ƃ��ɋt�]���A
���̗����z�R�̕R�����������ƂƂȂ�B

���k��C�Ŏn������_�C���f�B�[�[���A�܂�O�H�d�H�Ƃ̑O�g�ł���B
�����ď��a47�N�i1972�j�Q�n�������z�R�̕R�ɂ��A
���{�����̂��ׂĂ̗����z�R���p���������B

�@�֕t�߂̋���B�Y���R��o��B
�Y�z������z�R�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��A
�}���Ȑ��ނƕR�A���ꂪ�����z�R�̔߂��������ł���B

�X�ƊC�ݐ��̒N�����Ȃ��u�⊴�̒��ɁA�����̈�\���ł����B
�Ȃ����݂ł͔N��176��t�ɂ��y�ԉ�����������Y����A
���̂������������60��t�A�c��͗A�o���ꂻ��9�������������ł���B

�����܍B��
�߂�