
|
 |
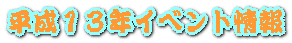  |


平成13年11月勉強会抄録
[いのちの電話について]
[1]いのちの電話とは
いのちの電話は1953年イギリスのチャンドラーという牧師がはじめたものです。師は12歳で自殺したある少女のことから、自殺に至る少女の心の痛みを強く感じ、悩みを持つ人たちのためにロンドンで組織的な電話相談活動を始めたのです。
現在では世界60数カ国、数百の都市で「いのちの電話」活動が行われていて、日本では1971年、東京で開設されました。現在は全国50カ所の都市で開設されており、約8000人の人が全員ボランティア活動で携わっています。うち24時間体制のところが20局あります。
1,なぜ電話による相談行為なのか
電話の方が情緒的コミュニケーションに適しており、孤立している人にとって電話の果たす役割は大きいのです。
2,なぜ専門家が当たらないのか
相談員はボランティア(多くはふつうの主婦)によって構成されていますが、なぜ専門的知識を持った人が当たらないのでしょうか。
これについてロスアンゼルスの自殺予防センターのリットマンドクターは次のようにいっています。
「人間の心の危機というものは、それが深刻であればあるほど、専門家よりも普通の人を
必要としている」
つまりボランティアは安上がりだからというのではなく、ボランティアこそ必要であるとの次元に立って考えているからなのです。
3,人の心の危機を支える
自然に四季があるように、人生にも移り変わる節目があります。その節目にたったとき人は心の危機に対面するのです。そして危機を抜け出すために悩んでいる人たちの支えになるために、いのちの電話があります。
4,「千葉いのちの電話」について
「千葉いのちの電話」は、1989年10月に開設、1993年に千葉県の社会福祉法人の認可を受けました。開局以来24時間体制をしき、相談員は330名、年間相談件数は約25,000件、年間維持費約2,000万は会費・寄付金でまかなっています。
なお相談員は無料奉仕であり、交通費なども自費負担となっています。
相談内容としては、
●人生問題(自殺・不安・孤独・性格) 26.2%
●医療・健康問題 13.8%
●恋愛・結婚問題 11.0%
●家族の不平・不満 9.8%
●職場や近隣の人間関係 9.5%
●性の疑問・不安 6.9%
●学校・教育問題 3.0%
●法律・経済問題 1.1%
●いたずら・その他 18.7%
年代別では、男は20代がいちばん多く、30代、10代の順であり、女は50代が多く、20代、30代の順となっています。 5,相談員の資格等
相談員の資格を得るには次のような研修を受けることとなります。
1年10ヶ月にわたり、週1日程度の研修を受ける。終了すると資格がもらえます。また研修期間内に月1度の実習モニターがあり、実際に相談席に座ることになっています。
いのちの電話は「さりげなく、しかも誇りを持ってやっていける仕事だ」と実感できるようになります。
6,ボランティアの心
ボランティアとは単に無料奉仕な行為と考えられるが、もっと奥深いものがあります。高島いわお園長は、「ボランティアとは、富めるものが貧しいものにではない。持てるものが持てないものにではない。勇者が劣者にではない。ボランティアとは自分自身の生き方を考えることだ」といっています。
また国際いのちの電話連盟前会長のアン・オーモンド・ロンカ氏は、講演の中で次のようにいっていました。
「私はボランティア活動とは『かかわり合うこと』だと思います。これは消極的な受け身の姿勢であっては成り立ちません。
いのちの電話では、『聴かせてください』という姿勢そのものが、人間の奥深い問題を明るみに出し、真実の人間性をあらわにします。私はいのちの電話の相談員になって、自分が与えたものよりはるかに多くのものをいただいたと感じています」と。
[2]具体的な相談の事例
様々なことがらがあります。電話に出ると何もいわず切れることがあり、それが続くことがあります。察するに自分の好みの声の
人が出るまでかけ続けるらしいのです。また、明らかに作り話と思えることを相談してくる人がいます。何時間も長く話し続ける人
もいます。電話料は相談者負担なので大変だろうと思います。次に幾つかのケースをあげてみます。
◆別れて暮らしている息子を訪ねたら、オッパイは大きくなっており、性転換
をしていてスカートをはいていた。主人には話せないしどうしたらよいか。
◆40代の女性。膝が痛くて歩けない。父はガンで母は腰痛で寝ている。
一家病気で困っている。
◆夫が死んだので60坪の宅地に2世帯住宅を建て、娘一家と住むことにし
た。しかし現在は3度の食事も自分で買ってきて食べる状態で、本当に
孤独だ。
◆低い男の声で「死にたい、欲しいものは何もない、ただ死にたい。ピスト
ルを買おうとしたが40万するのでだめだ」
◆入れ墨を入れたのでまともな仕事に就けない。裏の世界に入ったがスケ
ープゴートにされそうなので逃げてきた。いまは表街道は歩けないという。
彼は次のように話していた。
○ 同情の後には軽蔑がくる
○ 人の不幸は密の味だ
○ 人生七転び八起きはうそだ
○ 馬には乗ってみろといわれるが、乗った馬に蹴飛ばされた。
○ 慎重に馬に乗り、うまく乗り切れると思ったのに結局蹴飛ばされた。
◆庭に、女が3代続けて(姑、嫁、そのまた嫁)首を吊った柿の木があ
る。
◆1浪した息子があり、夫は岡山に単身赴任している。息子が家を出たい
という。私がうるさいからだと言われ、つい言い合いになるが、本当に
わたしが悪いのだろうか。
◆人生の賭(恋愛)に失敗して風俗に入った。30万稼げるが、意志の強い
人は流されないが、弱い人は染まっていってしまう。
◆毎週温泉場に女を探しに行く。職場の女はだめだ。温泉にいくと女中さ
んが、いい女性を捜してあげましょうかと優しくしてくれる。
◆今死にたいという電話を受けた人がいる。その相談員は、
「死にたいの?ではね、あなた今すぐやかんで湯を沸かして、砂糖湯を作りそれを飲んでちょうだい。
それから今の続きを聞くから。それまで決して電話を切らずに待ってるわ。
砂糖湯を飲んでからなぜ死にたいのかを話してちょうだい」
そういって時間をおき、相手の感情を沈めて話を聞いたので、相手は自殺を思い止まったという。
[3]話し方といのちの電話との関連
1,あいさつの効用
相談者は普段あいさつをしていない人が多いようです。わたしは機会を捉えてあいさつの大切さを説き、また、会話、人間関係についても話すようにしています。
2,聴く心構え
相手と話していると「それわね、でもね」などと、ついこちらから言いたくなることがあります。これは相談員としていけないことだ
といわれます。相談を聞くときの心構えを整理してみますい。
①あいづちを打って相手の話を引き出す。
②言葉より気持ちを聴く
③自分の価値観は、一時横に置いて聞く
④集中して聴く
⑤相手によって整理して聴く
受話器を置くときの終わりの言葉でつい「がんばりましょうね」と言いたくなりますが、これは禁句だと言われます。なぜなら相手はこれ以上がんばりようのない人たちなのですから。
3,聴くことの効用
①相手に好かれる
②知識が豊かになり、人間性が高まる
③協力が得られる
④相手に話す意欲を起こさせる
⑤思考力が高まる
⑥決断力がつく
⑦相手の心が安まる
話を聞いてもらえたことに礼を言われることがあり、聴くことの効用を実感しています。


平成13年 9月勉強会抄録
[印象ゲーム] (佐藤雄三指導)
相互理解をすることを目的とした印象ゲームを行います。このゲームは、「ジョハリの窓」手法(注;参照)によって、自分は自分をどれほど理解しているか、また他人は自分をどのように見ているかを、実験を通して見つめ直すものです。この手法は「日本交流分析協会理事長」横田僖郎氏創案によるものです。
[ゲームの進め方]
1,グループ編成
はじめに5~6人の単位のグループを編成する。
2,下記のような「印象項目表」を配布する
①表にメンバーを書き入れる。
②下記の印象項目10のうちから、はじめに自分について5項目を選び、該
当すると思える項目に○をつける。
③続いて3~5分の時間を取り、1人のメンバーに対して他のメンバーが、
その人の人柄・印象を捉えられる質問をしてみる。
④時間がきたらその人について、印象項目から該当すると思えるもの5つ
を選び○をつける。
⑤メンバーが一巡したら一区切りとする。
[注;印象項目]
1 明るく、楽しい人 6 親切な人
2 責任感がある人 7 我慢強い人
3 おとなしい感じの人 8 計画的な人
4 観察力ある人 9 やさしい人
5 楽天家の人 10 礼儀正しい人
[評価用配布用紙] 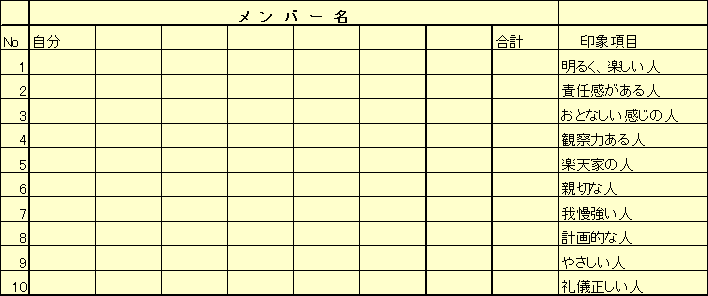
3,集計作業
①質問と採点が一巡したら「集計表」を配布し、メンバーを書き入れる。
②先に配布した印象項目表から、自分が自分につけた○を書き写す。
③次いで各メンバーから自分についてどの項目に○をつけたか発表して
もらい書き入れる。
④終わったら、メンバーがつけた○の数を右欄に書き出す。
(自分の分は計算に入れない)
4,評価作業
①集計作業が終わったら、別紙「ジョハリの窓」表を配布する。
②自分がつけた○と、メンバーがつけた○が合致した項目の数を、「開か
れた窓」の該当項目に書き出す。
③自分が○をつけたのに、メンバーがつけなかった項目の数を、「隠された
窓」の該当項目に書き出す。
④自分が○をつけないのに、メンバーがつけた項目の数を「気づかない窓」
の該当項目に書き出す。
⑤自分もメンバーもつけなかった項目があったら、「閉ざされた窓」の該当
項目に書き出す。
⑥「開かれた窓」+「隠された窓」の数と、「気づかない窓」+「閉ざされた窓」
の数はともに5項目あることをチェックする。
5,ふりかえり
①隠された窓、気づかない窓を縮小するにはどうしたらよいかを考えてみる。
開かれた窓の拡大につながる。
③閉ざされた窓の現状を再点検してみる。自分も他人も気づかない自分が
存在しないかどうかを考え直してみる。
[集計用配布用紙] 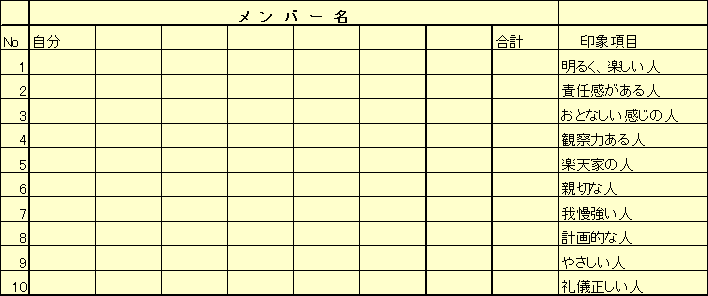
[注;ジョハリの窓について]
ジョー・ルフト(Joe Luft) とハリー・イングラム(Harry Ingram)の共同発案の性格構造論であり、「ジョハリの窓(JOHARI'S
WINDOW)」と呼ばれている。
わたしたちには「ありたい自分」と「傍目の自分」があり、この二つにギャップがあるのがふつうである。ギャップが大きくては、周囲に歓迎される人間にはなれないので、ギャップを小さくする努力が必要である。自分はどのような実態にあるかを、見つめ直すためによく用いられる。
[意見のまとめ方・発表の仕方 ]
(原 茂一指導)
孫子の兵法に「彼を知り己を知れば百戦して殆からず。彼を知らずして己を知れば一勝一敗す。彼を知らずして己を知らざれば戦う毎に必ず殆し」との言葉があります。
「意見を言う」場合も同じことが言えます。自分と相手をよく知ってなければ、自分の意見を通すことができないのです。
ここで「意見のまとめ方、発表の仕方」を考えてみましょう。
1,意見を持つことの大切さ
「個性の大切さ」がよくいわれます。個性とは何かといえば、その人なりの感じ方考え方を持つということではないでしょうか。
いつもみんなに合わせるというのでは自分を持っていないのと同じです。自分なりの感じ方考え方があるからこそ、他の人と同じ・違うということが言えるのであり、また良い・悪い、賛成・反対も言えるのです。
ここで「感想」と「意見」の違いを述べます。
「感想」 … その人の感覚的、印象的な感じを述べること
「意見」 … その人の主張が入っていること
2,意見を持つには
意見は相手に納得してもらう必要があります。それには十分な根拠を持つことが大事です。
①いいたいことを裏付ける (データを集めるなど)
②他人の言い分も集める
③意見は正しいかどうかをチェックする
3,事実を伝える大切さ
事実をいうことは、話し手が意見を言うに当たっての根拠を示すことです。それは相手に判断する材料を与えることでもあります。
したがって話し手の主観・感情が交ざらないことが求められてきます。
4,事実と主観、感情について
ものごとの判断には「事実は何か」が問題となります。したがって情報を伝えるには「事実」と「主観・感情」を区別して提供することで大切です。
①主観が入ると、ねじ曲げや推論が入りやすい
②感情が入ると断定やふくませが入りやすい
5,言葉の通達性と感化性
言葉には、事実を伝える性格(通達性)と感じや思いを伝える性格(感化性)とがあります。通達性には、数学や科学、ニュースを伝えるなどがあり、感化性には、感覚でつかまえた詩、小説などがあります。
①言葉の通達的はたらき
報告したり、ニュースを伝えるなどは、このはたらきを活用しています。
②言葉の感化的はたらき
芝居や落語を楽しんだり、読んでいて思わず涙がこぼれてくる小説などは、
このはたらきによるものです。
6,反対意見に反論する
意見を戦わすときは当然反論が予想されます。相手と意見が違うとき
反論できなければ相手の意見が優位となり、自分の意見は通らないこ
とになります。
また自分の考えだけにこだわっていても正しい反論にはなりません。
①幅広い視野を以て考える
②幅広い知識を持つ
③深い洞察力を持つ
④すばやい対応力を持つ
7,反論するには
①相手の意見は例外、特殊ではないか考える
②矛盾がないか
③全体視野から見てどうかを考える
8,意見の発表の仕方
交渉するときは相手が納得するに主張ができることです。それには事実に基づいた意見を述べることであり、客観的視野がを持つことが必要となります。
話し合い、会議でも同じことが言えます。また論点に対して感想でなく意見として述べなければ相手を説得することはできません。
①現状、経過を報告する
②問題点を指摘する
③主張する
・考え方見方を示す
・解決案を提示する
④裏付け、根拠を示す
・体験、経験、知識に基づく
・他の意見の取り入れ
・事実を述べる


平成13年 7月勉強会抄録
「話しことば検定について」
話しことばの検定は、「日本話しことば協会」が主宰しています。
検定は、3級~1級に別れていて、それぞれ次のような基準になっています。
1,検定の目的
正しく豊かな話しことばを広めることにあり、具体的には次のようです。
①社会生活に必要なコミュニケーション能力を客観的に評価す
る
②話すことを仕事としている人(秘書、受付など)に資格を与え
る
③企業が求める「話す力」を診断する
2,3級検定の基準
ことばを意識的に学習し、正しいことば遣いや整った表現を学び、相手の立場に立った話し方を身につけることをねらいます。
①検定レベル
・話しことばの基本的な知識を持てる
・社会においてよりよいコミュニケーションができる
・ビジネスシーンにも適応できる能力を持っている
②試験領域
・話しことばの基本知識(敬語その他)
・日本語の音声表現
・話す、聞くの基本
・話しことばの実際
③試験形式
・筆記テスト、20分
・リスニングテスト、30分 合計200点
3,2級検定の基準
ことばを十分生かし、社会生活に適応できることをねらう
①検定レベル
・話しことばの一般知識
・社会生活やビジネスシーンに、的確に適応できる能力
②試験領域
・話しことばの一般知識
・音声言語の表現技術
・話す、聞くの実践
・ビジネスシーンの運用
③試験形式
・筆記テスト 30分
・リスニングテスト 40分
・スピーキングテスト 3分話(テーマは当日出題)
上記各テストのそれぞれ70点以上が合格4,1級検定の基準 さまざまな場面に対応できる能力を持ち、話しことばを真に肉体化しているかをみます。自身が話せるだけでなく、指導的な
立場、プロフェッショナルとして活動できる能力をみます。
①検定レベル
・高度で専門的な話しことば知識を持っている
・ビジネスシーンに対応でき、話しことばの指導者としての能力を
備えている
②試験領域
・話しことば全般の専門知識(敬語、音声、プレゼンテーション)
・共通語音声の知識と技術
・社会のあらゆる場面での実践技術
③試験形式
一次試験
スピーキングテスト 課題3分、当日出題3分
課題テスト ・スピーチする、リポートする、プレゼンテーション
する
当日出題 ・文章を音声表現する、面接員との一問一答
二次試験
筆記テスト 60分 (80点以上が合格)
主宰社
日本話しことば協会
530-0041 大阪市北区天神橋-3-10-605
06-6242-0849 FAX 06-6357-0780
160-0017 新宿区左門町6-7-703(東京事務所)


平成13年 5月勉強会抄録
「発声、発音訓練」
「声は人なり」です。声を磨くことは人柄を磨くことでもあります。わたしは長年電話応対訓練などに携わってきましたが、参考となるところを話してみたいです。
1,美しい日本語とは
、
◎正しい言葉で(発声、発音、アクセント等を含め)
◎美しい言葉で(品位ある言葉)
◎生きた言葉で(TPOに応じた)
話された言葉を指すのである。
2,標準語、共通語
文部省(旧)は標準語という語を廃し、共通語としている。
共通語とは
◎全国共通語
◎地域共通語
◎職域共通語のことである。
3,呼吸法について
声は息を吐くときにつくられます。声の原料は空気です。空気をどのように出し入れするかによって、声のありようが決定されます。そこに呼吸法を考えることが必要となってきます。 肺からはき出された呼気(吐く息)が声帯を振動させ音を出します。これが「声」といわれるもので、発声とは呼吸によって声を出すことをいいます。声を発する力はすべて呼吸作用にあるわけで、話し方の基本はまず適切な呼吸法からといえるのです。
(1)腹式呼吸(横隔膜呼吸)
横隔膜の収縮により.肺を下のほうに拡げる呼吸法
(2)胸式呼吸(肋骨呼吸)
左右の肋骨の運動で、肺を左右.前方に拡げる呼吸法
(3)肩呼吸(鎖骨呼吸
鎖骨をつり上げることによって、肺を上の方に広げる呼吸法
4,音域(オクターブ)
人によって高い音域の人、低い音域の人とありますが、だいたい4つくらいに分類されています。高い音域の人は、低音を出す
のは割合楽ですが、低い音域の人は高音を出すのに苦労します。
5,呼吸法訓練
(1)基本形
ア、吸息量は自分の感じで約80%とし,肉体的ゆとりを残す
イ、吸息は緩やかなときは鼻からとし.できるだけ腹部深く吸い
込む
ウ、姿勢は垂直な壁に、後頭部,肩,尻が均等に軽くふれる姿勢
が好ましい
踵を10~15センチの幅に開き、一方の足を少し〈7、8センチ)
前方にずらした八字型にするのが合理的。
エ、重心は,直立,坐位の状態でも,練習を行うときは重心をや
や前に、足の甲のあたりに保つほうが合理的。
(2)呼吸練習
ア、腹で深く息をする
イ、肩の力を抜き、リラックスする
ウ、息を吐く
エ、息の吐き方は、
吸った息を保息時(息を止める)10秒、呼息時30秒位でで
きるよう訓練する。
6,その他全体にわたり
(1)標準音声
ア、母音 (vowel)
単音の分類の一つ。声帯の振動を伴う呼気が、口腔内で著し
く通路を妨げられることなく通過して発せられる音。口の開
き舌の位置などの相違によって音色の相違を生じます。
現代日本語では「ア・イ・ウ・エ・オ」の5つ。
呼気がもっぱら口腔を通過するならば口母音、一部鼻腔に流
れるなら鼻母音となります。
イ、子音(consonant)
単音の一つ。発音器官で作られる妨げ(閉鎖・狭めなど)を
息が通過することによって発せられる音。
妨げの作り方(調音法)、作られる位置(調音点)、声門の状
態(有声・無声)によって特徴づけられる。
<子音は父音ともいわれる>
ウ、破裂音((plosive)
発声器官で閉鎖を作り、息がそれを破る際に発せられる子
音。
(p.b.t.d.k.g)など
エ、摩擦音(fricative)
口腔内の発音器官が狭めを作り、息がそこを通過する際に
発せられる子音。
(f.v.s.z)など
オ、破擦音(affricate)
破裂音の直後に摩擦音が続き、全体で一つの単音と見なさ
れる音。
(ts.dz)など
カ、弾音(flap)
舌などの弾性のある発音器官が歯茎などを弾くように短く
接触して発せられる子音。
語中に現れる日本語のラ行音。
キ、鼻音(nasai)
鼻腔の共鳴を伴う音声。ふつう口腔内の調音器官が閉鎖を
形成し、声を伴った呼気が咽頭からすぐ鼻腔を通じて流出
する場合に生ずる子音。
(m.n)など
(2)母音の発声発音
(ア・イ・ウ・エ・オ・a・i・u・e・o)のこと
ア、母音の無声化
イ、長母音化作用
2種類の母音が重なる二重母音、および母音が続く連母音
は長音化する。
ウ、鼻濁音
発音を美しくするために発音する。
(3)話し方と語調
ア、語調要素
感じのいいコトバの調子は.つぎの要素によって構成されて
いる。
①発声
②発音
③声の強弱変化
④声の高低変化
⑤アクセント
⑥イントネーション
⑦プロミネンス
⑧ポーズ(問)
⑨言葉の緩急変化
イ、声の強弱変化
表現の「メリハリ」のこと。声の強弱や高低はその人にそな
わったものだが、学習によって変化するものである。
ウ、イントネーション 〈抑揚〉
アクセントは語につくものだが、イントネーションは文(一つ
のまとまった意味をもつ語のつながり)につくものである。
イントネーションの型は、大別すると次のようになる。
◎平 調
◎降 調
◎昇 調
◎降昇調
◎昇降調
エ、プロミネンス(きわだてる)
表現で最も大切なところを強く、または高く発音し、相手に
印象づけようとする。これを「きわだてる」つまり、プロミネ
ンスをつけるという。
◎強さの関係を主とした強弱の変化
◎高低の関係を主とした高低の変化
7,ポーズ(問〉
話しているとき、発音が停止されている時間のことです。
ポーズは息つぎのためだけではなく、無言の発表行為であるといわれる。ポーズは言葉としてはあらわれないが、いろいろな意味をもたせることができます。
8,緩急変化(言葉の早さの変化)
わたくしたちが対面で話ときのスピードは、1分間300~350音節くらいといわれている。(1音節はカナ1文字分、長音「-」も
1音節にかぞえる。ただしキャ.シュなどの拗音は2文字でも1音節する)


平成13年 03月勉強会抄録
「俳句と言葉と話し方」
わたしは話し方は30年ほどになるが、俳句歴は5,6年です。俳号を「英巣」といいます。
俳句は五,七,五の17語ですべてを表現しようとする文学です。そして上五、中七、下五と我々は呼んでいます。それに季語を入れることが決まりになっています。季語があるから俳句はおもしろいのです。
また五,七,五の文字数の決まりはありますが、俳句はリズムがあることが大事で、必ずしも文字数に
とらわれません。
「七福詣二つ残してしまひけり 英巣」
さらにいうと俳句の世界では、旧仮名を使うことが妙味ありとして、あえて使うことが多いのです。
「古池や蛙飛びこむ水のをと」
の「をと」など。(古池やは、はじめは山吹やだった)
さて、俳句の構成は、話し方と共通することが多い。
1,俳句作りと話のまとめ
2,季語と言葉について
季語とは季節を表す言葉ですが、使う期間がきまっています。
3,俳句言葉と話し言葉
俳句の言葉の基本は、書き言葉と読み言葉ですが、話し方は話し言葉と聞き言葉が基本となります。これが本質的な違いだといえます。
4,俳句表現と話し方表現
①「切れ字」は俳句にリズムを作る
切れ字とは「~や、~けり、~かな」といった言葉。17音が単調
にならないように屈折を作るため、切れ字を有効に使います。
(切れ字は一句に一つが原則)
②口語体と文語体
話し方は口語体が基本ですが、俳句は「韻」が大事なので文
語体が基本といえます。
③最短定型には文語体が適切
省略を必要とする俳句は、文語で簡潔に表現することになります。したがって話し方の説明調、スピーチ調では散文的になり、俳句に向きません。
また俳句は基本的に一人称の詩であるので、「自分、わたし」などの語はあまり使いません。


平成13年 1月勉強会抄録
「話し方における音声について」
S・Iハヤカワは、著「思考と行動における言語」のなかで、
「話での第一の感化的要素は、声の調子、その高さ、柔らかさにある」といって、声の影響の大きさを述べています。
また金田一春彦は、「話し言葉の技術」の中で、「言語は、音声の姿で聞き手に伝えられる。つまり音声は記号の外見である。従って外見の如何によって、同じ記号がいろいろ違った効果を生ずる」とのべています。
1,話し方と音声
①音声とは
音声とは、言葉を「いき」と「こえ」で空気を振動させる物理的現
象だといえます。
例えば美しい花を見て、その印象を表現しようとするとき、内言
(心に浮かぶ言葉)を口を通して「マアキレイダワ」と表現する。
この場合「マアキレイダワ」は空気の振動音にすぎないが、この
音が言葉の意味を持って発せられたとき、「イキ」+「コエ」の音
は意味あるものとなり、これを音声といいます。
音声に類似するものに「声音」があります。声音は「こわね」「声
の音色」のことをいっています。
2,音声についての基本的知識
①よい声、悪い声
声は生まれつきのものではなく、正しい発声・発音法を身につ
けることで、悪声は解消する。
よい声の7条件
・よく透る声
・若々しい声
・よく響く声
・音域の広い声
・心地よく聞こえる声
・枯れない声
・説得力のある声
②声のつくりかた
・呼吸 肺に空気を出し入れする
・発声 声帯振動で声をつくる
・発音 声帯でつくられた声を、口・鼻を共鳴させ加工して、言
葉を組み立てる音をつくり出す動作をいう
③呼吸法
腹式呼吸法で行う
④日本語の発音上の特徴
・母音の無性化
・鼻濁音 発音をきれいにする「が・ぎ・ぐ・げ・ご」のこと
・長音化 「映画」は「エイガ」ではなく「エーガ」、「経済」は
「ケイザイ」でなく「ケーザイ」というなど
・高低アクセント 外国語のアクセントは「強弱」だが、日本語
は高低アクセントになる
3,音声表現の基礎
①イントネーション 「抑揚」といわれるもので、息の切れ目や、語
尾に現れる高さの変化をいいます
②プロミネンス 強調法。重要な部分を強めて他の言葉と対立さ
せることで、表現の効果を高めます
③間(ポーズ) ポーズは無言の表現
④ポーズ4つのはたらき(斉藤美津子)
・理解・考察を与えるはたらき
・興味・期待を持たせるはたらき
・強調をさせるはたらき
・情緒・感動をもたらすはたらき
⑤ポーズの種類(大西雅雄(言語学者)
・文法的ポーズ
・律動的ポーズ
・強調的ポーズ
・情緒的ポーズ
4,話し方テキスト上の音声関連用語についての考察
①「心理変化」との関わり
②「あいさつ・へんじ」と音声の関わり
③「あがること」と音声の関わり
④「態度」と音声の関わり
⑤「言い方の原則」と音声の関わり
⑥「会話・あいづち」と音声の関わり
⑦「電話応対」と音声の関わり
⑧「敬語」と音声の関わり
⑨その他
5,教場における実践的音声指導のポイント
①声の小さい人
②早口の人
③口ごもる人
④間の取り方が下手な人
⑤単調で事務的な人
⑥センテンスが長い人
⑦ヘッドボイスの強い人
⑧語尾の弱い人、強い人
⑨「声」と「動作」の一致
⑩口を結ぶことの大切さ
6,まとめ
声の響きは心の響きである。

 |
|