|
 |
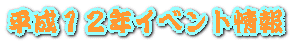  |


平成12年11月勉強会抄録
[聞くとはどういうことか]
1、話は対応が大切
話し方には、「話す」と「聞く」ことのふたつの分野があります。「話す」ときは、相手に合わせて話すことが大切になります。大ぜいに向かって話す場合もそうですが、対話をする場合には、さらに強く相手を把握していくことが大切になってきます。
2,聞くことの意義
人は、人の話を聞くことは、大切だと思っていても、聞き上手になろうとの訓練はしていません。聞いていなくても、ほかの人にはわかりにくいことなので、あえて訓練をしようとは思わないのです。そのため、聞く能力が身についていない人が多いといえましょう。
しかし正確に聞けなければ、相手に正しく対応できません。聞くことができると、日常の様々なことが、スムーズにいくようになるのです。
3,聞くことの効用
(1) 話し手の立場から見て
①話し手を楽しませ、人間関係をつくる
②話す意欲をおこさせる
③相手の心を浄化できる(カタルシス)
(2) 聞き手の立場から見て
①話の内容が理解でき、知識が豊富になる
②相手の人柄、考えがわかる
③刺激を受け、聞き手が変わる
④話し手に合わせる事柄を受け取れる
4,聞くためには
ことばを聞くだけでは聞いたことになりません。では聞くにはどうすればよいのでしょうか。
(1) からだで聞く
①目をむける
②表情を豊かに聞く
③うなずいて聞く
④身をのりだして聞く
(2) 相づちを打って聞く ①誘いの相づち …それで、それから等
①同意の相づち …そうですね、なるほど等
②反対の相づち …私はそうは思いせんが等
③同情の相づち …大変でしたね、つらかったでしょうね等
④喜びの相づち …よかったですね、嬉しかったでしょうね等
⑤疑問の相づち …おかしいですね等
(3) 意欲的に聞く
(4) 何を聞くのか
①事柄を正しくとらえる
②話し手の感情を聞く
5,聞く方法
「聞く」とは、話し手の話を受け取ることであり、受け取る基本は返事(反応)にあります。
①耳で聴く 話の事柄を聞く、音声に現れた感情を開く
② 目できく 態度に現れたものをくみ取る(観察する)
③ 口できく 不明なものを聞く (質問する)
④ 心できく 話の裏を読み取る(察知する)
6,話の事柄をつかむ
①再現できること
その事柄を繰り返せなければ、聞いたことにはなりません。
②聞くためには
・要点をつかんで聞く
・場面を考えて聞く
・ことばをきちんと捕まえる
・態度、語調と関連させて聞く
・意味の不明な点を確かめる
・ことばの奥を考えて聞く
・事柄をつかむには
7,感情を聞く
感情を聞くとは、ことばの不完全さを補うためのものです。
表現されたひとつのことぱには、話し手のさまざまな感情が込められています。この感情が読めれば、より的確に相手に応ずることができ、コミュニケーションがよくなってくるのです。
①話し手の気持ちを聞く
文字で表現されたものは、そのことばの背景などが説明されていて、意味がつかみやすいですが、話 の場合は、音調や態度から類推して、意味を判断していかなければなりません。ことばだけでの判断 は、話し手が伝えようとする意味を、聞違えてしまう危険性があります。
②ことばはごまかせる
話し手の意志で自分の気持ちとは違う話をすることができます。詐欺師
は、相手をごまかすつもり で話しますが、わたしたちも相手によって
自分の意志と違う表現をしていることがよくあるものです。
話を聞くときには、漫然と聞くだけでなく、相手の気持ちを聞くことが必要
になってきます。
③正しく聞くためには、
・相手の話を検証する
・質問して確かめる
8,聞きやすい話とは
話し手の立場に立って考えると、話をするときは聞き手に、自分の伝えたいことを受け取りやすいように配慮することが大切となります。話し手が自分勝手に話しては、正確に伝わるとは限らないのです。
(1) 聞き取りにくい話とは
①話の仕方によるもの
・話のスピードが早い
・話が聞きにくい
・まとまっていなくて、つかみにくい
②ことばによるもの
・固有名詞(人名」地名など)
・数詞が多くはいるもの
・同音語、類昔語・専門語などが入るもの
③その他
・話の背景がわかりにくいもの・知らない分野の話
・難解な話し等
(2) 受け取りやすい話をするには
①一番言いたいことを、最初に話す
②項目をあげて、全体像をつかませる
③解説はあとで行う


平成12年10月勉強会抄録
「エニアグラム概論」
[1]エニアグラム概論
1,エニアグラムとは
エニアとは…ギリシャ語で「九」のこと。
グラムとは…「グラフ」すなわち「図」のことです。
つまりすべての人間の性格や生きようは、9つのタイプに分けられるという考えがエニアグラムのもっとも根本をなすものです。
したがって人は、自分は9つのうちのどのタイプであるかを知ることによって、自分の実存を認識し、よりよく成長していくために、
具体的にどのような努力をすべきかを、追求する学問だといえるわけです。
[エニアグラム図]
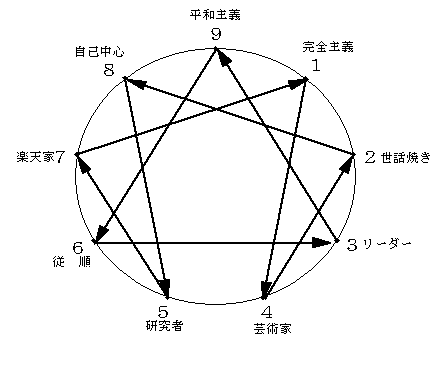
2,エニアグラムの歴史
①エニアグラムはおよそ2000年前、アフガニスタン地方でその
体系が築かれ、7世紀に生まれたイスラム教に受け入れられ、
徐々にイスラム世界全域に浸透していきました。
②イスラム教の神秘主義的宗派、スーフィー派はエニアグラム
理論を重視し、リーダー育成のマニュアルとして、必要性と論
理性を高めていきました。
③スーフィー派では門外不出の秘伝とされ、霊的指導者から2人
の弟子だけに伝えられたのです。ただしエニアグラムを使える
のは次代の指導者だけであり、もう1人は指導者の不慮の死
に備えたスペアの存在であって、使うことは許されなかったの
です。
④エニアグラムを西欧社会にもたらしたのは、コーカサス地方出
身の高いカリスマ性を発揮したゲォルギィ・イワノヴィッチ・グル
ジェフ(1877-1945)でした。
3,エニアグラム各タイプ
①タイプ1 完全でありたい人(完全主義者タイプ)
何事にも完璧を期し、努力を惜しまないタイプです。
「~すべき」という言葉をよく口にします。
②タイプ2 人の助けになりたい人(世話焼きタイプ)
情愛深く、周囲の人々の助けになることに労をいとわずつくしま
す。
③タイプ3 成功を追い求める人(リーダータイプ)
常に効率性を心がけ、成功するためには自分の生活を犠牲に
するのもいといません。
④タイプ4 特別な存在であろうとする人(芸術家タイプ)
何よりも感動を大切にし、平凡を嫌うタイプです。自分は特別な
人間だと自負しています。
⑤タイプ5 知識を得て観察する人(研究者タイプ)
分析力や洞察力に優れ、客観的にものをみることを好み、賢
明であろうと心がけるタイプです。
⑥タイプ6 安全を求め慎重に行動する人(従順タイプ)
忠実・誠実で、安全のために強い保護者を求め、保護者に対
して従順、責任感を発揮するタイプで す。
⑦タイプ7 楽しさを求め計画する人(楽天家タイプ)
万事に楽天主義的で陽気であり、自分の周囲に楽しさを見い
だす能力に長けているタイプです。
⑧タイプ8 強さを求め自己を主張する人(自己中心タイプ)
自分が正しいと思うことのために全力で戦う戦士的タイプです。
勇気とエネルギーにあふれ行動力があります。
⑨タイプ9 調和と平和を願う人(平和主義者タイプ)
葛藤や緊張を避ける平和主義者タイプ。他人に同化でき、他
人の気持ちになることができます。
4,エニアグラムを形づくる源泉
こうしたタイプはどうして形成されるのでしょうか。すべては誕生から始まります。生まれたときは、誰も自己愛の固まりですが、
次第に環境への適応を学んでいきます。この適応の仕方を学習する過程で、その人にとってもっとも生きやすい方法を身につけて
いくのです。これを「性格」といいます。この生き方を9つに分類したのがエニアグラムなのです。人はこの形作られた性格を、自分
にとっての最高善と考え、それに拠って人は自己実現を図ろうとするのです。
[2]エニアグラムにおける「囚われ」
エニアグラムでの9つのタイプには、良否、善悪はありません。いずれのタイプにも個性があり、誰もがすばらしい能力を持っています。同時に短所や欠点も持つことになります。これらの問題点は、苦境、逆境におかれたときほど強調される傾向があります。
そこで人が生まれ持っている「すばらしさ」から生じる、この悪い傾向を強める原動力を、エニアグラムでは「囚われ」と呼んでい
ます。
1,悩み苦しみの根元は「囚われ」からおこる
エニアグラムを学習する最重要テーマに「囚われを知る」があります。囚われの姿は、内面の深い部分に隠されていることが多く、自分にも周囲にも見えにくいのです。
自分の「囚われ」を知ることがより成長するために必要なものなのです。
2,「囚われ」と「落とし穴」
①タイプ1の人の「囚われ」と「落とし穴」
自分や周囲に憤りを感じる(勤勉の落とし穴)
人生すべてに完全を求めますが、現実には完全なものはない
ので、自分にも周囲にも憤りを感じます。
この憤りは自分の中に溜め込んでしまうので自覚がありません。
容易に憤るのは自分が完全 でないと思うからです。しかしど
こかに現れてしまいます。
②タイプ2の人の「囚われ」と「落とし穴」
他者からの愛の必要を認めない(奉仕の落とし穴)
他者を援助するのは大切だと思い、一生懸命に他者に愛情を
注ぎます。しかし周りから「愛情や助力を受けたい」という願望
を自分の中で否定します。
つまり「自分は愛情を与える人間であり、受ける人間でない」と
の「囚われ」があるのです。
③タイプ3の人の「囚われ」と「落とし穴」
目標達成しか考えない(成就の落とし穴)
目標達成することだけが自分を証明するものだと思い、人生の
価値をすべて「成功」という尺度で測ってしまいます。そのため
には自分の生活すら犠牲にします。周りの人は、自分が成功
するための道具と考える傾向があります。
④タイプ4の人の「囚われ」と「落とし穴」
平凡さを避ける(ユニークさの落とし穴)
平凡であることを避け、他人とは違った特別な人間であると思
いこみたい「囚われ」があります。
自分の感受性に自信があるので、感性の世界に入り込み現実
を無視する傾向があります。
⑤タイプ5の人の「囚われ」と「落とし穴」
空虚さを避ける(知識の落とし穴)
空虚さを避ける「囚われ」を持ちます。他者から離れ、空虚さを
埋めるために知識を吸収しようとします。
⑥タイプ6の人の「囚われ」と「落とし穴」
権力への不信感(従順の落とし穴)
強い保護者に守られ、彼に尽くしたいとの思いと同時に、彼へ
の疑念的な面が共存しているので、権力への不信感という「囚
われ」があります。
⑦タイプ7の人の「囚われ」と「落とし穴」
苦しみを避ける(快楽、奔放の落とし穴)
人生は楽しいものであるべきと信じ、つらい苦しいことを避けよ
うとする「囚われ」があります。楽観的でナルシストで、最高のも
のだけをつまみ食いしたいと思っています。楽しみを後回しにし
て、困難に立ち向かうことが、このタイプ7には非常に難しいの
です。
⑧タイプ8の人の「囚われ」と「落とし穴」
強さを誇示し、弱さを隠す(傲慢の落とし穴)
強さを誇示し弱さを隠そうとする「囚われ」がありまする。自分
を守るものはひとえに力であると信じていますので、テリトリー
を強く意識し、それを侵すものは全て排斥しようとします。他人
の弱点を素早く見抜き、挑まれると容赦なく相手の弱点を攻撃
していきます。
⑨タイプ9の人の「囚われ」と「落とし穴」
葛藤を避ける(ノンビリの落とし穴)
平和を乱すことを避け、周りの人に適応しようとして葛藤を避け
る「囚われ」があります。
無気力で怠惰になりがちで新しいものを受け入れにくいです。
優柔不断と思われがちで、周囲からプレッシャーを与えられる
と、意志を示さぬばかりか動くことをやめて、無言の抵抗を示し
ます。


平成12年05月勉強会抄録
「民謡からみた発声法」
講師 坂田富男
わたしは意外と神経質なところがあって、神経性胃炎を病んだこともあり、ストレス解消のため1980年頃から民謡を始めました。
稽古はなかなかつらいものがあり、はじめは腰が痛んだり、腹が張ったり、疲れているのに寝付かれないこともありました。20年も続けていると多少民謡について人に話せるものができてきます。参考までに話してみます。 民謡は単純素朴な歌です。長唄、清元、新内、浪曲などの源流に当たるもので、歌を生み出す畑のようなものです。したがって民謡を唄うときの声は、共同社会での生活道具の一つであり、自然に鍛えられてきたものなのです。
本来の民謡の声は、大きく伸び伸びと素朴に出すもので、技巧は用いず、日常会話に用いるような声でよいのです。そして人がいわゆる都会生活を始めるまでは、本来の民謡の歌い方が受け継がれてきていたのです。
「正調○○節」といわれるものです。
しかし、社会環境が変わり、生活様式や環境が変わってくると、大きな声を出す機会が少なくなり、場所も限られ、そして大声を出す必要性もなくなってきました。いつの間にか都会人は、自然で素朴な大きな声が出せなくなってきてしまったのです。
当然民謡もこれらの影響を受けることとなります。そもそも民謡は、外で太陽の下で歌うことでしたが、いまは屋内のステージで唄うようになってしまいました。そのため自然で、大きく、力強く、遠くまで透る民謡を歌うためには、あらためて人工的に声を作らなければならなくなってきたのです。
まず民謡はどのようにして生まれてきたのでしょうか。次のようなことが考えられます。
①はやし声、はやし言葉から生まれた唄
盆踊りなどに「そーれ」とか「ハイ、ハイ」などのはやし声が出て
きますが、これらの言葉からいつか唄が生まれした。
②辛い労働の泣き言から生まれた唄
昔の労働は辛く苦しいものでした。その辛さを紛らわせ、耐え
るための言葉から、いつか唄が生まれました。
③調子を合わせるものとして生まれた唄
おおぜいで作業をするときなど、(例えば田植えやヨイトマケな
ど)みんなで調子を合わせて行わなければなりません。その必
要性から唄が生まれてきました。
④情報通信手段として生まれた唄
昔の人は、いまの都会人のように密集した生活ではなかった
のです。一人一人が離れて仕 事をしていたので、お互いの様
子を知らせ合う必要がありました。その通信手段として生ま れ
てきたのです。例えば刈り干し唄などは、山に入って草を刈る
唄ですが、こちらの峰に一人、あちらの峰に一人と離れて仕事
をしていたのです。そこで大声を出して誰がどこにいるか、無
事でいるか、仕事がはかどっているかなどを知らせ合ったので
す。
◆民謡を分類するとどのように分けられるか。
1,労作唄…人が労働することの中から生まれた唄
①漁業の唄 舟こぎ唄、網ほし唄、大漁唄など
②農業の唄 田植え唄、豊年唄、麦打ち唄など
③林業の唄 木挽き唄、山唄など
④土木業唄 土端打ち唄、土づき唄など
⑤酒造り唄 酒造り唄、酒屋唄、酒仕込み唄など
⑥その他
上のものは民謡の中核をなすものですが、ご存じのように現在ではこれらの労働はほとんどありません。船は櫓をこぐのではなく、動力で動いており、田植えはコンバインで簡単にすんでしまいます。
山の木も斧や鋸を使わずチェーンソーであっさり倒してしまいます。
ためにいまの民謡には、土のにおい、汗のにおい、労働の過酷さを感じさせるにおいが消えつつあるのです。
2,祝い唄 …祝い事で歌う唄
①新築祝い 木遣り唄、喜代節など
②結婚祝い 長持唄(秋田、宮城ほか)など
③門出祝い 隠岐祝いなど
3,盆踊り唄、座敷唄、酒盛り唄、騒ぎ唄、その他
[民謡の声づくり]
1,立ち方(姿勢)
声を出すためには姿勢が大事です。
①男性は肩幅程度に足を開く
女性は利き足を前に、他を半歩後ろに引く
なお草履は少し大きめな方が力を入れやすい
②腰を落とし気味にゆったりとたつ。膝をゆるめるようにする。
③肩の力を抜く。
2,息の吸い方、吐き方
息のエネルギーを声に変えて唄うので、呼吸は大切となる。
①膝をゆるめて腰を落とし、まず息を全部吐く。
②膝、背中を伸ばしながら、ゆっくり鼻から吸う。
唄っているときは、鼻だけでは間に合わないので、鼻、口の
両方から吸う。
③十分吸ったら息を止める。
④唄を送る目標点を決めてしっかり見る。ふつうは鴨居の上あ
たりを見る。
⑤ゆっくりていねいに息を出す。
3,口の動かし方
発音をしっかりするため口の形をつくる。
①大きく開く
②はっきり動かす
4,声の分類
①高い声 … 低い声
②大きい声 … 小さい声
③太い声 … 細い声
④明るい声 … 暗く重い声(というより、しみじみとした声)
⑤ほかに固い声、粘る声等
一般的には明るい声、高い声は軽快で派手な感じを作り、低い声、しみじみとした声は情感や哀愁を作り出しています。そして明るい唄は「高い音階」の部分を聞かせどころにし、しみじみした唄は「低い音階」の部分を聞かせどころに味を見せます。
5,発音の仕方
①母音をしっかり発音する。特に「ア」を大事にする。
②優しい曲を一音だけで唄ってみる。(例えばアだけで唄う)
③節尻は長音になるが多いので、母音にして力を入れ唄う。


平成12年01月勉強会抄録
「プレゼンテーションについて」
最近はプレゼンテーションに用いるツールには、パソコンを使ってのものが広まってきています。パワーポイントソフトを使ってのものが主なものですが、今後更に発展し、大がかりなものになっていくと思います。わたしも昨年からパソコンを入れてツールづくりに頑張っています。今日は時間の関係でパソコンを用いてのデモはできないが、できれば機会をつくってみたいと思います。
今日は配布したレジメを説明することとします。
1,プレゼンテーションとは何か
「相手のニーズや場の状況に応じ、好印象を与えながら自分の主張や提案を受け入れさせること」と定義できます。また対象に
は、1人から多人数まで様々にあります。
2,「プレゼンテーション」と「社交スピーチ」の違い
①プレゼンテーション
はっきりした目的があり、相手に有益な情報を提供するもの
です。また内容の確実さや質の高さが要求されます。
②社交スピーチ
内容に論理性や正確性がなくても、スピーチを行うことに意
味があり、内容が雑談的であったり曖昧さがあっても、あまり
問われません。
3,プレゼンテーションの場面
①社外に対して
新製品等の説明、企画・提案の説明や説得
②社内に対して
QC・小集団活動の成果発表、研究発表等
4,プレゼンテーションの特徴
①視覚化された話し方
②論理性が強く求められる
③話の場の主役が話し手自身とは限らない
④プレゼンテーションの目的により話の性格が違う
5,プレゼンテーションの種類
①話すプレゼンテーション
②書くプレゼンテーション
③見せるプレゼンテーション
6,プレゼンテーションの話し方の基本
①平常心で臨む
②ものおじしない態度
③声・言葉
7,プレゼンテーションの実際
①話を構成する
・主題を決定する
・話材を集める
・話を組み立てる
②視聴覚ツールを活用する
・フリップ、パネル
・OHP
・パソコン投影器
・スライド
・ビデオ映像
・その他

 |
|