



















��P�߁@���푽�l�Ȓނ肪����
�u���̃X�|�[�c�Ƃ͈Ⴂ�A�ނ�͊Ԍ����L���v
�ނ�͕��ނ����ށH
��Q�߁@�ނ�͉��łȂ���
�ނ�͎Ќ�I�E�Љ�I�ȗV�тł͂Ȃ�
�l�ɉ��Ȃ����߂̒ނ�A�v�����^���A��ƁE�t�R�Î��̒ނ�
�ނ�̓Q�[���ł������ȗV�тł��Ȃ�
�ނ�͋��Z�ł͂Ȃ�
�ނ�̓X�|�[�c�Ƃ͈Ⴂ�A�q�ǂ��ɂƂ��āu�����ɖ𗧂v�����ł͂Ȃ�
��R�� �ނ�͊l���̂���V��
���{�̒ނ�́u�B���_�I�v�Łu�y���S���I�v�ł���
�P�V���I�p���A�n�Y�o���h���[�ɂ�����ނ�
�p���́u�H�ׂ邽�߂̒ނ�v�A�R�[�X��t�B�b�V���O
�ނ�̓��[���ō��ꂽ�Q�[���ł͂Ȃ��A���ڂɎ��R�ƑΛ�����V�тł���
�����V�сA��������������ʔ���
�v���ƃA�}�̋��
���t�̢�v�����
�ނ�Ǝ��
���������E�����Ƃɂ���
�����𒇊ԂƊ����邱��
���H�ƕ���
�u�ނ������͐H�ׂ�ׂ��v���u�E�����������ׂ��v���B�ǂ��炩������������ƌ����邩�B
��S�߁@�ނ�̉��Ǝ�{�\
�ǂ����Ēނ������̂��B�s�K�Ȑ���
�ނ�́u��{�\�v�ɂ��s���H
�{�\�s���Ƃ�
�����s���w�Ɩ{�\�T�O
�ނ�Ƣ��{�\������т��邱��
�ނ�ɔ����댯
�ނ�͓��퐶������̒E�o�B�댯�ʼnp�Y�I�ȍs�ׁH
�{�\�Ƃ�����̓���I�ȈӖ�
�ނ�D���͒j���z�������Ō��܂�H
�ނ�D���� nature or nurture?
�����̂������ɂ���
�m���l�E�����l�̐��_�J���Ɣ�m���l�E���l�̌��n�I���X�P��(���Ɓj
�ނ�̊y����������ł��Ȃ��������R
��T�߁@������ƍ��킹�\�\�ނ�̉��̌��_
�u������v�Ɓu���킹�v
���o�I���Ɖ��̔��f
�ނ�̌o��
�َ������E�̑���ƂȂ���
��U�߁@���R���y���ށB�ǓƂ��y���ށB�Ќ����y����
�K�c�I���̒��N���ȍ~�̒ނ�
���V�A�̍�ƃA�N�T�[�R�t�̒ނ�
�V�сE��y�̕��ށA����
���ʓI���邢�͓����I�ł��邱�ƁA���邢�͌ǓƂ��D�ނ���
�Ќ��Ɗƒނ�A��ނ�
��V�� �ނ�̉��ƒނ�̋�
��W�߁@��s���̂��̂̒ނ�\�J�����͂Ȃ��ނ���y���߂Ȃ�������
�ނ�͕����̋��C����̒E�o�H
�J�����ɂƂ��āu��͐��v���������H
��X�� �u�ނ�͘J���v�F�N�w�ҁE���R�߁i�������j�̐��B�����Ď��̔��_
(1)�w�R���̒ނ肩��x�̎O�̃e�[�}�B�k���ނ�A��A�R���̕�炵
�@�k���ނ�ɂ���
�ނ�ւ́u���Ȍ����v
�ނ��ʂ����u���R���v�H
�A��ɂ��āA����̎v�z����p���̎v�z��
�_�����݁A��s���́u����זE�v
�B�R���̐����Ɓu�l�Ԃ̎��R���v
�R���̘J���Ɛ����́u�l�Ԃ̎��R���v
���⓮���Ƃ̋����H
��L�O�̃e�[�}�Ɋւ��鎄�̔��_
�@ ���R�́u�E�H���g���́u�ނ�̓N�w�v�v�ᔻ�ւ̔��_
���R�̃E�H���g���ᔻ�F�u�ނ�̒��ɐl���̈Ӗ��������������Ƃ͑ޔp�̎v�z�v
�E�H���g���̐l�ƂȂ�A�ނɂƂ��Ă̒ނ�̈Ӗ�
�E�H���g���^�X�G�l��w�ދ���S�x�̏Љ�
�E�H���g���́w�ދ���S�x�́u�N�w�v�ł͂Ȃ��f�p�Ȓނ�^�̂ł���
�E�H���g���́��E�J����
���R�͒P�ɓs�s�̐l�Ȃ̂��B�܂��s�s�I�����Ƃ͉����B
�A��̍r�p�͓s�s���̃_�����݂ɂ��Ƃ������R���̔ᔻ
�_�����݂𐄐i���Ă���̂́u�s�s���v�ł͂Ȃ�
�����ɑ���s�s���̐ӔC
�s�s���E���R�͓s�s�̊����ɑS���ӂ�Ȃ�
�����Ԍ��Q�ւ̓��R�̖��S
�B�����k�����ƂŐl�Ԃ́u���R���v�����̂��B
���l�Ɩ쐶�����́u�����v�H
�S�C���g���Ȃ������]�ˎ���̔_���Ɩ쐶�����Ƃ́u�����v
�u�l�Ԃ̎��R���v�Ƃ����T�O���s���Ăł��邱��
�C����ׂ��Љ�ɂ���
�R�d���̌������ɑς���ׂ����Ɠ��R�͌���
�ǂ̂悤�Ɏd���̌������ɑς��邩
�ӂ��̎�҂͎��R�����̗L���Ŏd�������߂�킯�ł͂Ȃ�
(2)�u�ނ�͘J�����v�Ƃ������Ƃ���ɑ��鎄�̔��_
�J���ł���悤�ȁ��R���̒ނ聄�Ƃ�
�ނ�͓���A�r�A���_����̉������u���n�I�J���v
�_�ƂƃA�\�r
�ނ�́u�L�`�̘J���v
���_�P�D��쑺�ł̓��R�̔����͗V�тł���
���R�͂Ȃ��ނ�͘J�����ƌ��������̂�
���_�Q�D�ނ�̊y�����Ɣ_�Ƃ̊y�����͈�v���Ȃ�
���_�R�D���Ă̎Љ�ɂ��E�J���ƗV�т����߂��l������
�ΕׂȔ_�v�Ɣ��R���ĉƏo�������q�̘b
���_�S�D���ݑr���H�ނ�͌��n�I�J���̋[���I�o���H
����̘J���҂Ɂu�r���̌��v�͂Ȃ�
�{�\�Ƃ��Ắu���n�I�J���v�ւ̗~���H
�Q�O���I�t�����X�̘J���҂͂ǂ����Ēނ���D��
�ނ�l���̑����͗]�Ɋ����S�ʂ̍��܂�̔��f
���_�T�D�ނ�́u�Ӗ��t�^�v�Ȃ��ɁA�P�ɖʔ����Ɗ����邩��s����
(3)���R�̗]�ɖ��p�_�Ƃ���ɑ��锽�_
�]�ɂƐ�������
�u���Ă̐E�l�v�F�u���͎҂��镃�e�v�E�u��l����v�v�̃C���[�W
�]�ɂ��v��I�ɉ߂������Ƃ͗]�ɂ̔ے�H
�]�Ɋ����̎Y���Ŏ�����͖̂������H
���R�́u�d���̏[�������R�v�Ƃ����u���R�v�ςƗ]�Ɋ�
�Ñ�M���V�A�ɂ�����u�ՉɁv
���{�̘J���҂́u��ƌ����v�ł���u�J�������v�ł͂Ȃ��H
���܂ē������Ƃ��u�J���̈Ӗ��v�ł���A�]�ɂ͕K�v���B
�ԑt�ȁ@��l�����y�v
�S�̖̂ڎ���
��������Ƃ̂Ȃ��l�����̗V�т��邢�̓X�|�[�c�ɂ��Ēm�肽�����Ƃ́A����̂ǂ����A�ǂ����Ėʔ����̂��Ƃ������Ƃł���A����𗝉�����̂ɕK�v�Ȍ���ł̂��̗V�ѕ��ł��낤�B�Ƃ��낪�A�ނ�ɂ͑����̎�ނ́A�܂�ނ���̈قȂ鑽���̒ނ肪����A�ނ���̈Ⴂ�ɉ����āA�ʔ������قȂ�B�ނ�́A���ۂɂ́A���ނ̗V�тƂ������́A���ɑ����̎�ނ̗V�тł���A���ꂼ��ɉ����Ă��̖ʔ������������K�v������̂ł���B�����A����������ނ�͑�ꕔ�u�ނ�v�ɏ����Ă���A���������S�A�T��ނ̒ނ�ɂ������A���̒ނ�͂�������Ƃ��Ȃ��B������{���́u�ނ�v�̖ʔ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�������A�ȉ��ł͂�������Ƃ̂��鐔��ނ̒ނ���ׂȂ���A��������Ԗʔ����Ǝv���Ă���ނ�̂ǂ����ǂ̂悤�ɖʔ�����������������Ǝv���B�ނ�̖{�͂�������o�Ă��邪�A�قƂ�ǂ́u�ނ���v�ɂ��Ẳ���ł���A�ނ�̖ʔ������������{�͏��Ȃ��̂ŁA�����͈Ӗ������낤�B�����āA���́A���̖ʔ����A���y�A���͂́A���̒ނ�ɂ����Ă����ʂ��Ă���Ɩ����ɍl���Ă�����̂ł���B�܂�A���̐�ɂ����j�ɋ���������Ƃ������Ƃ��瓾���邻�̒P���ȉ��y���ǂ̒ނ�ɂ����Ă����S�ɂ���Ƒz�������̂ł���B�ق��̒ނ�̖{�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�܂��A�ނ�̑��l�������邱�Ƃ���͂��߂����B ��P�߁@���푽�l�Ȓނ肪����
��j�A����ȂǂƖ��A���̋[�a�j�ł���t���Cfly(�{���̓n�G���̂悤�ɔ�Ԓ����Ӗ�����)���g���Čk������ނ�̂��t���C�E�t�B�b�V���O�ł���B
�ʐ^�͉p��Lake District�̐�̈��River Eaden �ɂ�����t���C�t�B�b�V���O�B���i���������Bhttp://www.goflyfishinguk.com/fly-fishing-locations/chalk-streams/river-test.php�ɂ��B

�w�t���C�t�B�b�V���O�]�́x�i�����Ёj�̒��҃��C���Y�ɏ]���A�t���C�E�t�B�b�V���O�ƈ�ʂ̒ނ�Ƃł́A�u�P�Ȃ���s�ƕ����̃o���[�قǂ̈Ⴂ������v�B�t���C�Œނ�l�X�́A���̒ނ���ł����ƊȒP�ɒނ�Ă��A������t���C�Łu�������v�ނ肽���ƍl����B�ނ����s�ɒu�������Č����ƁA���ʂ̐l�������čs���̂ɁA���̐l�����́A�o���[�����Ȃ���i�ނƂ����킯���B
�����̒ނ�I�s�����������J�����i�H��܍�ƁB�P�X�W�W�N�v�j�́A�a�����Ēނ�u�y���S���v�̒ނ�łȂ��A�M���K���̒ނ�ł���t���C����邱�ƂɌ��߂��ƌ����A�t���C�́u�|�p�v���Ƃ����Ă���B���C���Y�������o���[���|�p�ł���B�t���C�����l�́A���̌|�p�I�D�����A�@�ׂ��ɖ��͂�������̂��낤�B
�T�P�Ȃ̃A�}�S�ƃ��}���́A���z��͂͂�����قȂ邪�A�`�Ԃ̂悭�������ŁA�����ɑ�����Ƃ����k�����ł���B�����͐쒎��~�~�Y�Ȃǂ������G�T�ނ�ł��_���邵�A�уo���i�L�W�̉H���h���イ���Ŋ����������̒P���ȍ\���́u�a���уo���v�Ɩ{���̒��ɐ��I�Ɏ������u�m���уo���v�܂�t���C�Ƃ�����j���g���Ēނ邱�Ƃ����邵�A���A�[�i���A�[lure�͂��т�����́A�܂�u�^���a�v�ł���B�����ȂǂɎ����������Ђ�����������̂ŁA�����̎�ނ�����j���g�����W�M���O�i���[�����g���ă��A�[�������j�ł��ނ邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�k�����ł��A�G�T�ނ�h�Ƙa���уo���h�i����͂Ƃ��Ƀe���J���ނ�ƌĂ�Ă���Ƃ����j�A�����ăt���C�h�����ăW�M���O�h�̈Ⴂ������B
�\���̏�i�E�̎ʐ^�́A���؊ό������̊Ǘ�����w�O�썇���x�G���A�ɂ����鑊�͐�̃A���ނ�̖͗l�B�������g�o(http://atsugikanko.gyokyo.info/)�ɂ��B��̒��Ɍ�����R���N���[�g�̒��́A�n�}���Q�Ƃ���ƁA��s���A�����������ԓ��̋��r�Ǝv����B���R�Ɛl�H���Ƃ����R��̂ƂȂ������{�I�ȕ��i�ł���B
���͏C�P���A����̈��ނ�B�������]�[�g�z�e�����t�H�[���C�P���g�o�ihttp://plus.laforet.co.jp/blog/�j2010�N5��22���́u�A�E�g�h�A�ŃA���}�Z���s�[�v�Ƒ肹��ꂽ�L���ɂ��B

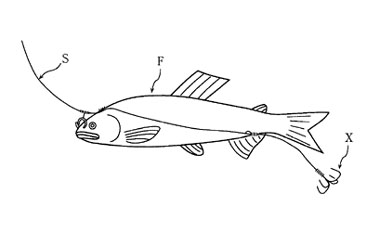
�}��http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2012125157�A�}0011�ɂ��B�������A���̋L���͋ʖԂɂe�Ƃw����ꂽ���Ɋ|���j���Ԃ̒�Ɉ���������Ȃ��悤�ȓ���ȋʖԂ̐������@�ɂ��Ă̋L���ŁA�d�|�����̂��̂̋L���ł͂Ȃ��B
�ʐ^�͉p���Wikipedia�ŁuFisherman jigging with a big fish from his boat�v�Ƃ����肪���Ă���Bfisherman�̓A�}�̒ނ�l�Ƌ��t�̗������Ӗ�����B���{�ł͐E���t�ŃW�O���g���đ�^����ނ�Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ����A�p�ꌗ�ł̓W�O�Œނ�E���t������̂�������Ȃ��B

�W�O�̓��A�[�̈��ł��邪�A�W�O���g���ނ�ɂ����낢�날��B���[�P�O�O���ȏ�̊C�ŁA�T�O�L�����z����J���p�`�A�Q�O�L�����z����q���}�T�A�X�O�L���̈�}�O���Ȃǂ�_���W�M���O�́A�E�l�Z�Ƃ��Ⴄ���A�܂��D�낳���C��邱�Ƃ��ł����A�x���`�v���X�A�_���x���Ȃǂŋؗ͂�b���Ă������Ƃ����߂���A�p���[�̒ނ�ł���B�W�M���O�ő啨��_���l�X�ɂƂ��āA�ނ�̉��Ƃ́A�����Ƃ̊i���ɑł������A���Ȃ̗̑͂̋������������Ƃ̂Ȃ��ɂ���B�ÒJ�G�V�w�W�M���Oshock!�x�T���ނ�T���f�[�A2002
 �E�i�M��A���ȂǁA�H�ׂĂ��܂�����ނ�̂��D�ސl�����邪�A�����ŁA�w���u�i�ނ��o�X�ނ�̂悤�ɒނ邱�Ǝ��̂��ړI�ŁA���͌v�ʂ̌�A�H�ׂ��ɕ�������Q�[���E�t�B�b�V���O�ɉ������o���l������B�O�҂͐H�ׂ邽�߂ɁA������O�����̂䂦�ɒނ�B���͂����O�����E�t�B�b�V���O��Ɩ��Â������B��҂́u�ނ邽�߂ɒނ�v�B���邢�̓Q�[���Ƃ��Ċy���ނ��߂ɒނ�B�O�����E�t�B�b�V���O�ƃQ�[���E�t�B�b�V���O���܂��S���ΏƓI�Ȏu���ɓ�����Ă���B
�E�i�M��A���ȂǁA�H�ׂĂ��܂�����ނ�̂��D�ސl�����邪�A�����ŁA�w���u�i�ނ��o�X�ނ�̂悤�ɒނ邱�Ǝ��̂��ړI�ŁA���͌v�ʂ̌�A�H�ׂ��ɕ�������Q�[���E�t�B�b�V���O�ɉ������o���l������B�O�҂͐H�ׂ邽�߂ɁA������O�����̂䂦�ɒނ�B���͂����O�����E�t�B�b�V���O��Ɩ��Â������B��҂́u�ނ邽�߂ɒނ�v�B���邢�̓Q�[���Ƃ��Ċy���ނ��߂ɒނ�B�O�����E�t�B�b�V���O�ƃQ�[���E�t�B�b�V���O���܂��S���ΏƓI�Ȏu���ɓ�����Ă���B
�ʐ^�͕x�m�܌̈���i(����ށj�̃w���u�i�ނ�B�u�w���u�i�ނ����v�Ō�������ƁA�����{�A�����{���킸���ɑ����̒ނ�ꂪ�ڂ��Ă���B���͂̌i�F�̂悢�Ƃ�������Ȃ��Ȃ����A�w���u�i�ނ�͋��Z�ł���B
�G���N���u�ҁw���M�@�ގ����x�i�͏o���[�V�ЁAS.34�N���j�Ƃ����{������B�G���i�����j�Ƃ́A�_�����̂ł͂Ȃ������̂��Ƃł���B���炷�����̓`�������W���R�Ƃ������B�W���R�ƃU�R�͓������̂ł���B�l���E�F�a���Ȃǂł͎G��������g�ɂ��ėg�������̂��u�W���R�V�v�Ƃ����A�P�Ɂu�Ă�Ղ�v�Ƃ����ƁA���̃W���R�V���w�����Ƃ�����B
�u�G���N���u�v�́A�ނ�D���̉�ƁA��ƁA�W���[�i���X�g�A�\�y�t�A�~���[�W�J���̉̎�Ȃǂō��ꂽ�N���u�ł���i�������j�B���̖{�̎��M�҂͂Q�S�l�ŁA�����ɂ͢�������m��ƌĂꂽ�w�R�`�v�̕�������A�䕚����A�O�V�����n�A���c�����A�Ζ숯���ȂǁA�L���l�������Ă���B�����o�[�̈�l�A�����V���햱�E�O�Y�G���́A��ނ�V����Ƃ������ŁA�ނ�̎���O�ɕ����A
�P�j�t�i�E�R�C�Ȃǂ̖�ނ�ł͐l���N�w�I�ȉ�E���ς��āA���]�ƒށA�������S��ފƂ̋��n�ɖv�����邱�Ƃ��ł���B
�Q�j�k���ނ�B�X�|�[�c�I�A�ӗ~�I�A�|�p�I�ȋ����Ƌ������������߂�B�Q�������̋���̏�ɗ����Ĉ��Ȃǂ�ނ�S���́A�Ò����A�����Â̍H�v���v�������B�C�s�i�K�Ƃ��ẮA��ނ�̐Ò��̍H�v������ʂɂ���B���̒ނ���o�����A���͑��̒ނ�ɂ͂��܂�ł����܂Ȃ��B
�R�j�C�ނ�B�C�̍K�����߂�l�Ԃ̖{�\�����@�Ƃ��Ă���A���������S�A�勛�Ǝ��g�ޑu�����A�務�̊�тȂǁA��������̂̐����̖���������B�O�Q�҂��B�S�_�I�ł���̂ɑ��āA�C�ނ�͂����܂ŗB���_�I�ł���B���������āA�O�Q�҂ł͊l���͑��`�I�A�C�ނ�͒މʂ����`�I�A�ƌ����B
�C�ނ�ł͑務�����҂���

�O�Y�̃G�b�Z�[�ł͒ނ���܂��ꏊ�ɂ�蕪�ނ��Ă���B�ꏊ�ɂ���āA�Ώۋ��A�ނ�����ς��A�ނ�l�̍\���A�ԓx������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�������A���Ƃ��u���]�ƒޖ������S��ފƂ̋��n�v----����́A���Ԃ�A���X�Ƃ����~�̐�ň�l�ނ�B�F���S�̂̂Ȃ��ł�����{�̊Ƃ̓����������S���ł���A���̈�͖��ł͂Ȃ��A�Ƃł����Ƃ��ł��邾�낤��----���́u���n�v�́A�C�ނ�̏ꍇ�ɂ��A�~�̊������ɘp���ň�l���D���o���Ēނ�Ƃ��Ȃǂɂ͏\���ɓ��Ă͂܂�B
�܂��A�k���ނ�́u�X�|�[�c�I�����v�̓n�}�`��q���}�T�Ȃǂ�_�����g�ނ�(�g���[�����O)��W�M���O�Ȃǂɂ��C�ނ�̌`�e�ɂ҂�����ł���B�܂��A���̗��ꂪ�������r��Œނ�O���i���W�i�j�ނ�Ȃǂ́A���̃X�|�[�c���ɂ����Ĉ��ނ�ɏ���Ƃ���炸�Ƃ����邾�낤�B
���������_�͂Ƃ������Ƃ��āA��̕��ł́A�ނ�Ƃ����Ă����܂��܂ŁA��ނ�ɂ����Ă͓N�w�I�ȉ�E�̋��n���A�k���ނ�ɂ����Ă̓X�|�[�c���ƌ|�p�����A�C�ނ�ɂ����Ă͊l�����ނ�̒��S�I�S���ł���Ƃ���A�����R��̒ނ�̈قȂ�S�����������Ƃɗ͓_��������Ă��āA���ʂȊS�������ł���̂��͏q�ׂ��Ă��Ȃ��B�ނ�̑��l���ɂ��Ă͌���Ă��邪�A�l�X�Ȓނ肪�Ƃɂ����ނ�ł��邱�Ƃɂ��Ắi���Ԃ�A���Ɛj�Ȃǂ��g���ċ���ނ邱�Ƃ��Ƃ����j�펯��O�Ă��āA�����𑼂̃X�|�[�c��V�тƔ�ׂ��Ƃ��̒ނ�Ƃ��������ɋ��ʂ�������A�ނ�̊S���A�ʔ����A���͉͂��ł���̂��͌���Ă��Ȃ��B�ڎw���Ƃ���E�ړI�̈قȂ邳�܂��܂Ȓނ肪����A�l�͂��ꂼ��̒ނ�ɈقȂ�������߂�B�Ƃ���u�Ȃ��ނ������̂��v�A�u�Ȃ��ނ�͖ʔ����̂��v�̓����͒ނ�l�̊Ԃł͈�v���Ȃ����ƂɂȂ�B
�S���ނ���������Ƃ��Ȃ��A������ˑR�A�l�ɗU���đ�^�̃t�B�b�V���O�E�{�[�g���g�����O�m�ł̃J�W�L�}�O���ނ���n�߂����A����ȊO�̒ނ�ɂ͈�؋������Ȃ��Ƃ����悤�Ȑl�����邩������Ȃ��B�������A�����̐l�͎q�ǂ��̎��A�N��̗F�B��e�ɘA����čs������ł̏��u�i�ނ�A���邢�͍`�̒�h�ł̏��A�W��C���V�Ȃǂ̏����ނ肩��n�߂āA����ɑ��̒ނ�ւƔ͈͂��L���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�������ނ̒ނ������̂ł͂Ȃ��A����ނ��̒ނ������l�͑������A��ɂ���Ă�������ނ����߂đ��̒ނ�ɕς��Ă����l������B�����āA���̗V�т�X�|�[�c�ł͂Ȃ��A�ނ��I���A�����ނ�����Ă���B���̂悤�Ȑl�������Ǝ��͑z������B�Ƃ���A��͂�A�����̒ނ�ɋ��ʂ���u�ނ�v�̓����A�ʔ����A�ނ肩�瓾������y�Ƃ������̂�����ƍl������B�O�Y�̐����ɂ�������炸�A����𖾂炩�ɂ���K�v���c���Ă���B
�i�c����(���Ŷ�)�w�C�ނ�x�i�ۈ�ЁAS�S�P�N�j�Ƃ����{�����Ă݂悤�B�i�c�͂P�X�O�R�N���܂�B�������p�w�Z���m��ȑ��ƌ�A�����V���ЂɋΖ����A�w�����J�����x�̕ҏW�̎d�������Ă����B�ނ͉�ƂŁA��������������A�ނ蒇�Ԃ���u����̖��l�v�ƌ����Ă����Ƃ����B�w�C�ނ�x�͕��ɖ{�Ɠ������炢�̕��ʂ̖{�����A�ق��ɢ���{�ދ��j��Ƃ������ׂ��w�]�ˎ��ォ��̒ނ�x(�V���{�o�ŎЁA�P�X�W�V)�Ƃ����T�O�O�y�[�W�ɏ��咘���܂߁A�����̒ނ�Ɋւ��钘��������A�܂��w�v�����^���A�G��_�x�Ȃǂ̒���������B
�i�c�͏펯�I�ɒނ���X�|�[�c�̈��ƍl���Ă��邪�u���̃X�|�[�c�Ƃ͂����ւ�Ɉ�����Ƃ��낪����v�Ƃ����B�ނɂ��ƁA
1�j �Ώۋ������ɑ����B
2�j �����̃X�|�[�c�͈��̓���ƈ��̃��[���ɂ���čs�Ȃ����̂����A�ނ�ł͊e�Ώۋ��ɂ���ē���ƒނ�����Ⴄ�̂ŁA���ނ��̓���ƒނ��������B�����Ώۋ��ɂ��������̒ނ��������B
3�j �Ώۋ��ɂ��A�a�A��i�͂�j���Ⴆ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
4�j ��ʂ̃X�|�[�c�ł͏��s�𑈂����_���𑈂����A�ނ�ł́A�ނ���ȊO�A���s�͑���Ȃ��B
5�j �l��������B��Ɠ����B�O���ł̓N���u�����ƒނ�N���u��Ƃ��č���A�p��X���G������ƒނ肪��ɂȂ��Ă���B
�k�J�W�L�}�O���Ȃǂ�ނ�l�r�b�O�Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ�������ł́A�ދ�̋K�肩��ނ�K���܂ō���A����ɂ��������ĔN�ԋL�^��������肵�Ă��āA�ł���ʃX�|�[�c�ɋ߂����A�ނ�S�̂̒��ł́A�ق�̏������ꕔ��ɂ����Ȃ��B
6�j ��ʃX�|�[�c�ł̓v���ƃA�}�́A�K��ɂ���Ė����ɕ�������Ă��邪�A�ނ�ł͓��ʂȋ��E���Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ������B���{�̓`���I�ȑD�ނ�i��ނ�j�Ȃǂ̕���Ɍ�������ꐫ�Ƃ�����B
�u�����Ƃ���Ȏ���ŁA�Ƃɂ����ނ�Ƃ����̂͊Ԍ����L�����A���s�����[�����̂ł���v�B
�i�c�́A�ނ肪���̢��ʃX�|�[�c��Ƃ͈قȂ�A��Ԍ��̍L������ƁA�܂�ʂ̃X�|�[�c�ƌ����Ă������قLjقȂ鑽���̒ނ肪����Ƃ������Ƃ��w�E���Ă���B�����đ��̃X�|�[�c�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ��ẮA���Z�ł͂Ȃ�(���s�𑈂��ނ�͂����ꕔ�ł����Ȃ�)�Ƃ������ƂƁA�A�}�ƃv���̊Ԃ̋��E���͂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ����_���グ�Ă���B
�i�c�͒ނ�ɂ��ďd�v�Ș_�_�����ׂĎw�E���Ă���B�ȉ��ł́A���Ȃ�̊ϓ_�ŁA�i�c�̋c�_��~�����āA�q�ׂ�B
�i�c�������悤�ɁA���۔��ɂ��܂��܂Ȓނ肪����A�j�Ǝ����g���_�������A����ȊO�̓���E�p��A�a�A�ނ���ɋ��ʓ_�͂Ȃ��Ƃ�������B�ނ�͉��ɃX�|�[�c�ƍl����ɂ��Ă��A�ЂƂ̎�ނ̃X�|�[�c�ƍl��������A���Ƃ��A���㋣�Z�A���Z�Ȃǂ̂悤�ȁA���̒��ɑ����̎�ނ��܂ދ��Z�̈ꕪ�ނɑ���������̂ƍl�����ق���������������Ȃ��B
�ނ�ɂ́A�C�ނ�A��ނ�A�Ώ��̒ނ肪����A�C�ނ����Ƃ��Ă��A�u�ꏊ�v�I�ɂ͑D�A�������A�h�g��A��A�l����̒ނ肪����A�Ώۋ��Ƃ��ẮA�}�_�C�A�C�V�_�C�A�N���_�C�i�`�k�j�A�u���i�n�}�`�j�A�A�W�A�C�T�L�A���X������A���ꂼ��p��A�ނ���͈قȂ�B
���ؓ��Y�w�N���_�C�E�E�L�ނ����x�i�r�c���X�A�P�X�X�U�G���҂̓_�C�����H�̃t�B�[���h�e�X�^�[�j�ł́A�N���_�C�ނ�Ƃ��Ĥ�E�L�ނ�̂ق��Ƀu�b�R�~�ނ�A�����ނ�A�~���N�ނ�A���Ƃ����ݒނ�A�_���S�ނ�A�t�J�Z�ނ�A�ȂǂP�P��ނ̒ނ�����������Ă��邪�A����ɁA�u����炪�n��ɂ���ĖL�x�ȃo���G�[�V������W�J����v�B�u�E�L�ނ�v�͑����̒ނ���̂ق�̈��ɉ߂��Ȃ��Ƃ����B
�N���_�C�ނ�ł͎g����a�̎�ނ�����߂đ����B�C���C�\���A�t�N���C�\���Ƃ��������G�T�ށA�J�j�ށA�C�L��A�P�~�L�Ȃǂ̊L�ށA�T�i�M�A�I�L�A�~�A�C�\�M���`���N�A���̐�g�A�t�i���V�A�C�J���^�A�X�C�J�A�T�c�}�C���A�X�C�[�g�R�[���A���X�B�����āA�G�T���قȂ�Ǝd�|����ނ�����قȂ�B�E�L�̎�ނ������A�����E�L�A�J���E�L�A�~���E�L�A���^�_�E�L�A�Q�i�E�L�A�_���S�ނ��p�̒������O�E�L�A���X�Ƃ���A�Ⴄ�E�L���g���A�ނ�����܂��قȂ�B
�����A�ނ�ɑ��푽�l�̒ނ肪���邩��Ƃ����āA���ꂪ���̃X�|�[�c�ƈقȂ�ނ�Ƃ����X�|�[�c/�V�т̓����ł���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��u�ނ�v�Ɣ�r���邽�߂ɁA�X�|�[�c�Ƃ��āu���㋣�Z�v���Ƃ�Ƃ���A���㋣�Z�̒��ɂ̓g���b�N�ƃt�B�[���h�̈Ⴂ������A�g���b�N�ł͒Z�����i�P�O�O���A�Q�O�O���A�S�O�O���j�A�������A�������A��Q�������Ƃ���A�t�B�[���h�ɕ����сA����сA�_�����сA�O�i���т�����A���ɓ������Z�Ƃ��āA�C�ۓ����A�n���}�[�����A�������A�~�Փ���������A����Ƀ}���\���A�����A�\�틣�Z�Ȃǂ�����A�Ƃ����悤�ɁA��ڂ��ЂƂ�������ƁA�����Ȑ��́A�܂肳�܂��܂Ȏ�ނ́u���㋣�Z�v������B
�����Ă����قȂ��ڂ͂��ꂼ�������u�S���v�������Ă��āA���Ƃ��P�O�O�����ƃ}���\���͑S���قȂ��ڂł���A�n���}�[�����Ƒ��荂���т͑S���َ��ȃX�|�[�c���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����u�ނ�͐j�Ǝ���ɂ��ċ���ނ�v�g�̉^�����ƌ����̂Ɠ��l�ɁA�u���㋣�Z�Ƃ͈��̏ꏊ�A�R�[�X�ő��A���A���̗͂������^�����v�Ƃ����ӂ��ɂ��āA�ЂƂ̃X�|�[�c�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ͂ł���B
���̂悤�ɍl����Ɓu�Ώۋ����قȂ�v���ʂƂ��Ď�ނ������Ȃ邱�Ƃ��ނ�̓����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�X�|�[�c�͊e��ڂ����[���ɂ���Č��܂��Ă���i�����āA�P�T�O�����A�Q�T�Om���A�R�O�Om���ȂǁA���[������肳�����������ł����͑��₹��j�̂ɑ��āA�ނ�ɂ́i�Q�[���E�t�B�b�V���O�������j�u���[�������݁v�����A��ځE��ނm�ɋK�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߂ɁA�݂��Ɏ�ނ��Ⴄ�ƌ����邩�ǂ����͂����肵�Ȃ����A�ׂ����Ƃ���ŏ������Ⴄ���푽�l�Ȓނ肪���݂���Ƃ����_�ɓ���������̂ł���B
��������Ώۂɂ����l�X�Ȓނ�����������A�ЂƂ̒ނ���ŗl�X�Ȏ�ނ̋���_�����Ƃ��ł���B������ŕ������Ǝv�����炠����ł͓���̃O���[�v�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B�ނ�͌n���I�ȕ��ނ����ނƌ����Ă��悢�B���������A����ނ肪���̒ނ�ƈ���Ă���Ƃ����ׂ��������łȂ����͂����肵�Ȃ��B���ꂼ��̒ނ�́A����ϓ_�ł͈قȂ�ނ肾���ʂ̊ϓ_�ł͓����ނ�Ȃ̂��B�̒ʂ�����ʂ͂ł��Ȃ��B�����A�X�|�[�c�́A���[���ɂ���č��o�������̂ŁA�e��ڂ̗p���R�[�g�ȂǓ��e�I�ȈႢ�ׂĂ݂�܂ł��Ȃ��A�͂��߂���Ⴄ���̂��Ƃ������Ƃ����炩�ł���B�����āA�Ⴂ�E��ʂ��͂����肵�Ȃ���A���ނ̂��悤���Ȃ��̂ł���B
�ނ�́A�x�e������^���邱�Ƃ�����ɂ��Ă��e�����D���Ȃ悤�ɍs�Ȃ����̂ŁA���[���ɂ���ē���̒ނ肪���ݏo�����̂ł͂Ȃ��B�ނ�ɂ͂܂����l�Ȍ���������B���܂��܂ɈقȂ�ނ�́A���O���Ȃ��Ă����݂�����B���Z�X�|�[�c�́i�N���ɂ����Ă͂Ƃ������j���Z�ł���_�ŁA�ŏ����畡���i�Œ�A�ΐ�҂̂Q�l�A���s�肷��l������R�l�j�̊W�҂̑��݂�O��B�����āA�����̐l�X�����̃X�|�[�c���s�Ȃ��i�ΐ킷��j���Ƃɓ��ӂ��邽�߂ɁA���̃X�|�[�c�Ƌ�ʂ��Ă�����w�������K�v������A���̂��߂ɂ́A���[���Ɩ��O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂼ��̃X�|�[�c�̓��[���Ɩ��O�ɂ���āA���̃X�|�[�c�ƈقȂ��̃X�|�[�c�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ��ł���B�����ċ��Z�ł�����褏��s�����߂郋�[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���O�́A����ɂ��đ��̐l�Ƙb������Ƃ��ɕK�v�Ȃ̂ł���A�ނ�͈�l�Œނ邱�Ƃ��ł���̂�����A���̌���ł͖��O���s�v�ł���B�e�l�����̒ނ����m���Ă���������悢�B���Z�X�|�[�c�͈�l�̈��D�҂����邾���ł͐��藧�����A�����̐l�A�Љ�̑��݂�O��B�X�|�[�c�́i���Ƃ��Ƃ́j�l�����̗V�Y��}��ɂ��Đl�ƊW�����Ќ��̂��߂ɂ���Ƃ�������B�ނ�͔�Ќ�I�A��Љ�I�Ȍ�y�ł���B
�@��Q�͂ŁA�G���A�X���L�c�l���͑��̎�ƈقȂ��āA�X�|�[�c���Ƃ��Ă������Ƃ��݂��B���̍ۃG���A�X�����p���Ă���P�W���I���̏��ABeckford�gThoughts�@on�@Hare�@and�@Foxhunting�h�ł́A�u�ނ�͑ދ��Ȍ�y�Łv����A�u��͒��Ԃ������]�n�����邪�A�l�͑����͂���Ȃ��B�ł��邾�������̐l�X�����}�����ώ��ɔ�ׂāA�����Ƃ��l�I�ŌǓƂȌ�y�ł���v�ƌ����Ă���B�ώ��͑吨�Łu���āv�y���ނ��̂Ƃ��ẴX�|�[�c�ƍl����ꂽ�����ƒނ�́A�����ĂƂ��ɒނ�́u���Ԃ������]�n�v���Ȃ��A�l�I�ŌǓƂȌ�y�Ƃ݂Ȃ���Ă���B
�P�V���I�ɏ����ꂽ�u�ނ�̐����v�ƌ����邱�Ƃ����餃E�H���g�����w�ދ���S�x�M��̌��G�ɁA�����̕\���ɕ`����Ă���G�̎ʐ^������A���̒��ɂ�The compleate angler or the contemplative man's recreation�u���S�Ȓނ�l�A�ґz�I�Ȑl�̃��N���G�[�V�����v�Ƃ���������������icompleate ��complete�̌Ì�j�B�܂��{���̒��ɂ́A�u�_���h���v���[���l�Ԃ��ґz�ɂ����Ƃ��K�����V�тł���v�Ƃ��������o�Ă���B�F�B�Ƙb�����Ă��Ă��ґz�͂ł��Ȃ��B�ނ͈�l�Œނ邱�Ƃ��D�̂��낤���A�ނ�Ƃͤ�ǓƂ��ґz���y���ޗV�т��ƍl�����̂ł���B
���ҏە��͔ނ̒����A�w�]�˒ދ���S�x�i���}�ЁA�P�X�X�U�j�̒��ŁA�]�ˎ���̍ł��悭�m��ꂽ�ނ�̏��w���A�^�x�i������낭�j�����Ìy�я��i���˂߁j�ƃE�H���g���̋��ʓ_�ɐG��Ȃ���u�ނ�͌l�̓��������V�сv���Ƃ����A�܂��E�H���g���̒����̕���ɂӂ�A��ނ�͎Ќ��̂��߂̗V�тł͂Ȃ���Ƃ����B���́A�ނ肪�A���ɌǓƂ����߂�A���邢���ґz�����߂�V�т��ƌ����ς�͂Ȃ��B�������A�ǂ��炩�ƌ����A�l�ƌQ��A�l�ƗV�Ԃ��Ƃ��y���ށu�Ќ��̂��߂̗V�сv�ł͂Ȃ��Ƃ����_�ɂ����āA���҂Ɏ^������B
�����Ĥ�l�ɉ�����Ȃ��A�l�ɉ��Ȃ����߂ɒނ������Ƃ������Ƃ�����B�c��u�ދ��S�g�v�A�ێR�M�ҁw���m�ƒނ�x�i���⏑�[�A���a�T�S�N�j�ɂ��ƁA�t�R�Î��i�悵���j�i�P�W�X�S�|�P�X�S�T�j�́A���{�̘J���ҕ��w��v�����^���A���w�̑��������Ƃ������A�t�R�̒ނ�͂܂������A�l�ɉ��Ȃ����߂̒ނ肾�����B
�t�R�͎v�z�ƂƂ��ĉ��Y�����ɓ���A�����ŏ������������F�߂��A�v�����^���A�^��������ɂȂ�ɂ�l�C�����܂����i�˒�)�B�������A���{�S�̂��E�X���A�R����`������Ȃ��ŁA���ʂ܂œ����̊Ď����ɒu���ꂽ�B
�t�R�͏��a�P�R�N�ɖؑ]�쉈���̑��Ɉڂ�Z�B�����������Ƃ��������A��ƂƂ��ċꂵ�����łȂ��A�q�ǂ��̒��w���w�����ۂ���A��������u���v�Ƃ��u�X�p�C�v�ƌ���ꂽ�肷����퐶���ł̋ꂵ�݂���������B���L�ɂ́u�����Ȃ��B���������Ȃ��B�������Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ă͂Ȃ�ʂ��Ƃ��������̒��ɂ���̂��v�Ə������B�ނ̒��Ɂu���܂��̂͋�Y�Ǝ��Ȍ����v�����ł���A�������瓦���ɂ͎����ނ肪�K�v�������B�u�ނ��Ă���Ԃ����́A�������l���Ȃ��ōςށv�B�ނ̒ނ�͈�C�T�^�ŁA�l�̑吨����ꏊ���������B�u�l�ɉ�����Ȃ������v�A�u�l�Əo���Ȃ��悤�ȁA�k����I��ők�シ��v�Ə����Ă���B
�u�t�R�Î��̒ɂ܂������U���l����ƁA���͋��������ς��ɂȂ�B�������̔ނ̐��U�̂Ȃ��ŁA�ނ肪��̋��͂Ȏx���ƂȂ��Ă������Ƃɋ~����������B�����ނ��ނ��m��Ȃ�������A�ނ̐����͂����Ƒς�����̂ɂȂ��Ă����͂����B���̐��ɒނ肪���݂������Ƃ͗t�R�ɂƂ��čK��������---�v�Ɠc��͏����Ă���B
�Y�����ł͌��͂Ɠ����Ă���Ɗ�����ꂽ���낤�B�������A�R���ŁA������������̊�]���Ȃ��A��������ꎺ�ɕ��������Ă����狰�炭�C�������Ă��܂��ł��낤�B�l�ɉ�킸�Ɉ�l�łł��邱�ƁA��l�Ť�����ɂȂ��Ăł��邱�Ƃ�t�R�͒ނ�Ɍ��o�����̂��낤�B
--------------------------------------------------��)�O�D�s�Y�ҁw���{���w�S�j �U����x�i�w���ЁA���a�T�R�N�j�ɂ��A�t�R�Î��́A�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j�ɍĊ����ꂽ�G���u���|����v�i���l�̍�a�쑠���w���H���j�x�����s�����j�ɁA�w�����w�x�吳�P�S�A�w�Z�����g�M�̒��̎莆�x�吳�P�T�������Ĉ�����ڂ��ꂽ�B�܂��A����ɓ��{�ߑ㕶�w��̗D�ꂽ��i�ł���w�C�ɐ�����l�X�x�吳�P�T�N�������Ђ��犧�s�����B�ނ͎��ۂ̘J���̌����������A�Ƃ����B -------------------------------------------------
���������ނ������̂́A�ނ�Ȃ��Ƃ��ɂ͖V����o��ŁA���R�����Ƃ̂����Ђ��i�C�V�_�C�Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͓����ƌ����Ă��������j���y���ނ��߂ɍs���̂ł���A��������ł����āA�l�Ԃ�����Ȃ̂ł͂Ȃ��B�z�C�W���n���������悤�ɁA����Z��͐l�Ɛl�̌𗬁i�Ќ��j�A�����I�𗬁A���̐l�ɑ���D�z���������������߂̌𗬂̂��߂ɍs����B�����Č����A�ނ�͎��R�Ƃ̌𗬂�ڎw�����̂ŁA���̐l�ԂƂ̌𗬁A�Ќ����ړI�Ȃ̂ł͂Ȃ��B
��ŁA�u�r�b�O�Q�[���E�t�B�b�V���O�v�Ƃ����ꂪ�łĂ������A���ۑg�D������A�֎~�s�ׁA����ʂɒ�߂�ꂽ���̋����ȂǁA���[���ɂ��������Ēނ�����A���̑傫���������ނ���Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂ�ł���B�J�����̓t���C�����Œނ����킯�ł͂Ȃ��A�J�i�_�̊Ǘ��ނ��ŃL���O�T�[�����̑啨��ނ����Ƃ��ɂ͉a�ނ�ł������B�������A�ނ�グ������d�ʂ𑪂��ă����[�X���Ă���B���́A���ۑg�D�̃��[���ɂ�����Ə]���ނ�ł���̂��ǂ����Ɋւ�炸�A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�ɂ����A���傫�ȋ���ނ�����A��葽���̓��ꋛ���ނ����肷�邱�ƁA�܂�u�L�^�v��ڎw�����苣�Z��ł悢���т�ڎw�����肷��ނ���A��ʓI�ɁA�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂԂ��Ƃɂ������B
�N���_�C�i���ł̓`�k�j��W�i�i���ł̓O���j�̈�ނ�ŁA�ދ�[�J�[���X�|���T�[�ɂȂ��Ċe�n�̒ނ薼�l���W�߂ĊJ�Â���u�ނ�I�茠�v���s�Ȃ��Ă���B���߂�ꂽ���ԁA�אڃ|�C���g�ŏꏊ�����ւ��Ȃ���i�R�[�g�E�`�F���W�Ɠ������j�A�����̋����ǂꂾ�������ނ邩�������B
�Q�O�P�R�N�P�O�����{���m���ŁA��Q�U��S�����N�����գ�̑��J�Â��ꂽ�B�u�S���̍���Җ�P���l���X�|�[�c�╶�������Ō𗬂�[�߂�v�W���Ť�u�˂���s�b�N�v�ƌĂ�Ă���B�����ł́A�T�b�J�[�␅�j�A�͌餏����ȂǂQ�R��ڂ̂ق��ɁA�i���̔N�͑䕗�ڋ߂Œ��~�ɂȂ������j�t�B�b�V���O���Z�i���Q�V���j�������́u��ނ�v�i�m�g�j�j�̎�ڂ��s���Ă���B
�������A���̂悤�ȋ��Z��`���̒ނ�́A�ق�̈ꈬ��̐l���Q������ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B���{���ł́A���ςP�C�Q�O�O���l���N�P�O��ނ�����Ă���i�˒��j�B�S�O�O���l���N�ɂR�O��i���ɂQ�`�R��j�ނ�ɍs���ƌ��邱�Ƃ��ł���B�����A�u�ނ�I�茠�v�ɏo�ꂷ��̂͑S���ŕS�l�������������S�l���x�ł��낤�B���������āA�������̒ނ������l�́A�ނ�l���̂P�����̂P������ȉ��ł��낤�B
-------------------------------------------------------
�i���j�w���W���[�����x�Q�O�O�W�N�łɂ��A�ނ�̎Q�����i�ΐl����j�A�N�ԉA�N�Ԕ�p�́s�P�O�D�S���A�P�O�D�P��A�T�D�Q���~�t�ł���B�P�X�X�U�N�łɂ���Ēm����W�V�N����X�T�N�܂ł̂X�N�ԂƔ�r����ƒނ�́u�Q�����v�͂R������S���ቺ�������A�N�ԉ͕ς��Ȃ��B
-------------------------------------------------------
���̃X�|�[�c�ł́A���Z��N��A�������̊w�Z���A���邢�͊w�N���ɁA�s�������x���Ŏn�܂�A����裸n����螺S��������A���ꂼ�ꂪ�N�ɉ��s����B�N����N���ǂ����Ŏ��������A����̃��x����ڎw���B���ꂼ��̎�ڂ̃X�|�[�c���s���l���̉ߔ������邢�͔����߂������炩�̋��������ɎQ�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�u�ܖڒނ�v�Ƃ����āA�捇�̗V���D�ŁA���S�҂��A�D���C���ŁA���̓��A���̎��G�ɒނ�邢�낢��ȋ���ނ�C�̒ނ肪����B�������A�����o���̂���ނ�l�́A���G�ɂ��A�ނ肽�������ނ��ꏊ�ɍs���A���̋���_���Ēނ낤�Ƃ���B�ނ�l�ͤ�P�Ɉ�ނ�A���邢�͑D�ނ�ɍs���̂ł͂Ȃ��A�`�k�i�N���_�C�j��ނ�ɁA�O���i���W�i�j��ނ�ɁA���邢�̓C�V�_�C��ނ�Ɉ�֏o������̂ł���A��^�̃A�W���˂炢��C�T�M�i�֓��ł̓C�T�L�j���˂炢�A���邢�̓}�_�C��_���đD�ɏ��B
�������A���Z��ł��悤�ɁA�����ꏊ�ɂƂǂ܂��āA�����ނ̋����A���܂������ԓ��ɒނ�Ƃ������Ƃ��A���ۂ̒ނ�ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ��Ƃ͑S�R�v���Ȃ��B����ꏊ�ł��炭�ނ�Ȃ���A���̏ꏊ�Ɉڂ�B�D�ŁA�C���V�⏬�A�W��_���̂łȂ���A�����ނ̋����P�O�C���ނꂽ��A���Ȃ�A���̋���ނ肽���ƍl����B���^�̃}�_�C�����C���ނ�����A�����̍��v�d�ʂ��͏����y���Ă����^�ȏ�̂P�C��ނ邱�Ƃ̂ق��������Ă��̒ނ�l�͊�ԁB�C�V�_�C�Ȃ�Q�L���̃C�V�_�C���R�C�ނ�����S�L���̃C�V�_�C���P�C�ނ邱�Ƃ̕����ނ�l�ɂ͂邩�ɑ傫�Ȋ�т�^����B�_�������ȊO�̋��͊O���i���ǂ��j�ƌĂ�邪�A�ӂ��̊C�ނ�ł́A���Ƃ��A�A�W��_���Ēނ��Ă��āA�}�_�C���ނ�Ă�����A�O���ł͂����Ă��傢�Ɋ��}�����B�������Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�ł���ΊO���̓Q�[���̖W�Q���ł��낤�B
���{�ōL���s���Ă���Q�[���E�t�B�b�V���O�A�o�X�ނ�ƃw���u�i�ނ�ł́A��{�I�ɁA�ނ������͌v����A�����i�����[�X�j���A�l���Ƃ��Ď����A������H�ׂ���͂��Ȃ��B�ނ��Œނ邱�Ƃ������y���ޒނ�ł���B
�o�X�ނ�͎�҂ɐl�C������B�ʐ^��BIGLOBE�E�F�u���u���O http://36423425.at.webry.info/�u���w���A���O���[TERU�̃o�X�ނ���L�v2011�N7��17���̋L������ؗp�B��t�������ݎs�𗬂���(��Ёj��㗬�̍r�؍��_���ł̒މʂƂ����B�O�[���匴�w�͂����ݎs�ɂ���BTERU�N�͎��]�ԂŒނ�ɍs���Ə����Ă���B

���Ƃ��ƃt�B�b�V���O�Ƃ͋����l�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����ނ�A���邢�͋��Ƃ��̂��̂��Ӗ����Ă����B�O�����h�E�R���T�C�X�p�a���T�ł�live by fishing�́u���ƂŐ�������v�ƂȂ��Ă���B�����A���ĂōL���s���Ă���T�P��}�X�̃t���C�E�t�B�b�V���O�Ȃǂ́A�قƂ�NJǗ��ނ��ŕ�����O��ɍs����ނ�ŁA�H�ׂ邽�߂̒ނ�܂��͋��t���s�Ȃ����Ƌ�ʂ��ꂽ�A�Z�~��g���{�����̂Ɠ��l�̗V�т̂��߂ɂ̂ݍs�Ȃ��ނ�ł��邱�Ƃ���A�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂ��̂ł���B
�Q�[���E�t�B�b�V���O�ł́A����̋�������ނ낤�Ƃ��A�����������A���ĐH�ׂȂ��B����́A���̓����ɂ͖ڂ����ꂸ�ς�����ǂ������A�������l����H�ׂȂ��A�G���A�X�̂����C�M���X�̢�ώ�裂ƑS�����l�̢�X�|�[�c��ł���B�G���A�X�̌����u�X�|�[�c�v�Ƃ́A�u����v�����łȂ��u����v���Ƃ��d������A��y�A�V�т̈Ӗ��ł���A�X�|�[�c�̎����ɂ����ăv���[���[�����łȂ��ϋq�����̃X�|�[�c�ɎQ�����Ă���ƌ��Ȃ����B�ނ̌����u�X�|�[�c�v�́u�g�̉^���v���Ӗ����Ă��Ȃ��B�ނ́A�Q�[����t�B�b�V���O�́A�ϋq�����邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�����炭�A�X�|�[�c���Ƃ����ł��낤�B�G���A�X�̌����X�|�[�c�́A�����ȗV�т��Ƃ����Ƃ���ɓ���������B���v�ł�����l�����ړI�ł͂Ȃ��A�v���Z�X���́A�v���[�A�����ł͒ނ邱�Ǝ��̂��ړI�Ȃ̂��Ƃ��������ł͂Ȃ��A���v�A�l���������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�l���͏����ɒނ�v���Z�X���y���ނ��Ƃ̖W�����ƍl����̂ł���B
���{�ł́A�{�E�̋��t���s����{�ނ�������A�ނ�͗V�тɕ��ނ���邪�A�V�тōs������Ƃ����āA�ނ��ʂ̓Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ͌Ă�Ă��Ȃ��B���{�ł́A�ނ�́A���t�łȂ��Ă������l���Ƃ��Ď����ċA��A�H�ׂ�Ƃ����̂����ʂ�����Ƃ��������A�قƂ�ǂ̒ނ�l�͊l�������߂āA�܂苛��ނ��Ď����A��A���͂Ɍ�������H�ׂ��肷�邱�Ƃ���ړI�ɒނ�����邩��ł���B�ނ�Ȃ������Ƃ��ɂ́A�ނ�l���ƂɋA��O�ɋ����āA�������ނ������̂悤�Ȋ�����邱�Ƃ��炠��B
�ނ�ɂ͗]�\�A���v�������B�Ƃ������A�l�������̓��̒ނ�̐��ہA�Q�[���ɂȂ��炦�Č����Ȃ�Ώ��������̔����Ȃ̂ł���B�ނ�ł́A����j�ɂ����A�|�����������茳�ɊĎ�荞�ނ܂ł́u�ނ�v�v���Z�X���y���ނ��A�����͂��Ȃ��B���������ċ��͒P�Ȃ�]�\�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��͂�ڎw�������́A���邢�͖ړI�ł���B
�މʂɌb�܂�Ȃ����Ƃ��������邹����������Ȃ����A�C�V�_�C�ނ�̏ꍇ�ɂ͊l���͗]�\�Ƃ������i��тт邱�Ƃ�����B���͓����ɏZ��ł����Ƃ��A�C�V�_�C�ނ�����Ă����B�ŏ��ɂT�L�������^�̃C�V�K�L�_�C�i�C�V�_�C�̈��j��ނ����Ƃ��ɂ́A�ނ������Ƃ������̎v�������ł���܂łɍő�E�ō��̍K�������P�N�Ԗ��킢�����邱�Ƃ��ł����B
�ނ邱�Ƃ��ړI�ł������B�������܂����͍d���ĐH�ׂ��Ȃ����Ǝ��ȊO�̂Ƃ���͂��ׂĐH�ׂ��B���̓C�V�_�C��H�ׂ邱�Ƃɂ���Ď������C�V�_�C��ނ������Ƃ����������̂��낤�Ǝv���B�������Ēމʂ́A�Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�̂悤�ɁA�̒���d�ʂ�C���Ƃ����P�Ȃ鐔���A�܂袊ϔO�I�ȣ���̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A��̓I�ʼn��l�̂�����́A�l������ł���A�H�ׂ邱�Ƃɂ���Ċm�����A�u�B���_�I�v�Ȃ��̂ł���B
�����āA���̂悤�Ȓނ�́A��V�т͋��\����Ƃ������ɑ�������Ƃ��L�͂Ȕ��ƂȂ�V�тł���B���\���̊C�̒����狛��ނ�グ��Ƃ��ɁA���������A�_��̐��E���疂�@�ŋ������o�����̂悤�Ɋ����邱�Ƃ�����B�������\�̐��E����͐������������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�ނ�Ɗl���Ƃ��Ă̋��͈�̂̂��̂Ƃ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������āA�H�ׂ邽�߂̒ނ�́A�l���Ɩ��W�ɍs����u�����Ȑg�̉^���v�Ƃ��Ă̗V�сE�X�|�[�c�ł͂Ȃ��A�͌�⏫���̂悤�ɁA���̒������́u���\�̐��E�v�ōs����Q�[���ł��Ȃ��B�����̐��E�ɂ�����A�u�B���_�I�v�V�тł���B
���āu�Q�[���v�Ƃ�����͗V�т��Ӗ�����ƂƂ��Ɂu���Z�v���Ӗ�����B�J�C�����͋��Z���A�S�[���ƌĂ��A�A�S�[���Ƃ͂ł��邾�������ȏ����̉��Ől�Ɛl�����s�𑈂��A�D��������V�тł������B�����āA���������A�D���܂邽�߂ɂ̓��[����������ƌ��܂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������āA���J�̉e�����Ȃ������̃R�[�g�Ŏ������s���K�v������A���O�ł��A�ʉ���ʂ���݂̂Ȃ�������Ƃ����R�[�g��g���b�N�Ŏ����A���[�X���s���K�v������B�܂苣�Z�͍D���ȏꏊ�ł�邱�Ƃ͂ł����A���Z����g�p���邽�߂Ɏ��Ԃ̐�������B���炩���ߌ����Ă���ΐ푊��ƌ��߂�ꂽ�����A���ԂɁA���܂����ꏊ�܂苣�Z��œ����B
�����A�l�ԓ��m�̐킢�Ƃ��ẴQ�[���ɂ����ẮA�ΐ푊�肪�l�Ԃł��邱�Ƃɂ���āA���̐U�镑�����A�̂̓��������Ɍ��肪���邾���łȂ��A�܂��A���[���i�V�ѕ��j�ɂ���ċK�肳�ꂽ����̂������ōs�ׂ��A�̂����̂ŁA�Q�[�����̑���̓����͗l�X�ɕω�����ɂ��Ă����͈͓̔��ɂ����܂�B�������ė\�z�O�̂��Ƃ��N��������A���R���������肷�邱�Ƃ͏��Ȃ��B
�ނ�ł͈�ʂɋ������Ƃ��Ȃ��A�����ȏ��������߂�K�v���Ȃ�����A���[���͑��݂����A�R�[�g�̂悤�ȓ���̏ꏊ�𗘗p����K�v�����Ԃ̐������Ȃ��B�V��Ƃ��������������A�ނ�l�́A�����̑̒���C���A�����Ď����̓s�������ɏ]���āA���R�ɁA�ނ���J�n���邱�Ƃ��ł��A���[���Ȃǒm��Ȃ����R�̐�������ɂ��A�u���R�v�ƑΛ�����̂ł���B���[����K��Ƃ����l�דI�Ȕ����̉�݂Ȃ��ɁA�ނ�邩�ނ�Ȃ����̒P���Ȍ��ʂ��A������l�ŁA����̂܂܂Ɏ���邱�ƂɂȂ�B
�����A������A����ꏊ�ŋ����ނ�邩�ǂ����A���邢�͓���̓��ɖ]�ދ���ނ邽�߂ɂǂ��̒ނ��ɍs���ׂ����ɂ��Ă͌�肦�Ȃ��B�Ƃ��ɊC�ł���A���́A�a�����߂āA���邢�͑��̋��ɒǂ��āA���邢�͎Y���ꏊ��T���Ĉړ�����B�܂�������_�f�̔Z�x���邢�͂܂��킩���Ă��Ȃ��ق��̌����ɂ���āA�ϋɓI�ɉa��H������A�H��Ȃ������肷��B�����Ă܂��ނ�邩�ǂ����͒����̕����⋭���ɂ���Ă܂������ς�邪�A���̗�������݂̒n�`�Ɗ����A���������ɂ���Č��܂�̂ł͂Ȃ��������̍����Ȃǂ̐����◬����̉e������B
�������āA�ނ���������肷�邱�Ƃ��قƂ�ǂł����A���鎞������ꏊ�ł��鋛���ނ�邩�ǂ����́A�������������܂��Ɍ����邾���ŁA���m�Ȃ��Ƃ͑S���킩��Ȃ��B���t���x�e�����̒ނ�l���o���i��������ƌĂԂ��Ƃ�����j�ɂ���Ă̂݁A��G�c�Ȍ��������Ă���ɉ߂��Ȃ��B�������A����ŏ\���Ɋy���߂�̂ł���B�ނ�͎����̊��ɗ���A�����ɂ��邩���̋߂��ɂ��ăR�}�Z�ɂ���Ă��т����Ă��鋛��j�ɂ�����Z�ʂ�����ƂƂ��ɁA�����͋��R�ɋ��Əo��̂��y���ޗV�тȂ̂ł���B
���̃X�|�[�c�A���Z�̈Ӗ��ł̃Q�[���ɂ����āA���Z�����Љ�l�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����܂ɂ��邪�A����́u�^���悩�����v����ł͂Ȃ����̍��Z���Ɏ��͂�����������ł��낤�B�����炭���̍��Z���͂��̌���J��Ԃ��ǂ����т��グ�邾�낤�B���S�҂��x�e�������^��u���v�ŕ������ȂǂƂ������Ƃ͂܂����肦�Ȃ��B�������ނ�̏ꍇ�ɂ̓r�M�i�[�Y����b�N�Ƃ������t������B���s�����x�e�����������ς�ނ�Ȃ������̂ɁA���S�҂��啨��ނ�Ƃ������Ƃ��悭����B
�ނ�ɂ����Ă��Q�[���E�t�B�b�V���O�ł���Ǘ��ނ��̃w���u�i�ނ�ł́A���ꂪ�Ȃ��A�ނ��i�g�R�[�g�h�j���قڋψ�ɂł��Ă��邩��ł��낤���A�ׂ荇�����Ȃ̓�l�̒ނ�l�̐��т����߂�̂́A�a�̍����A�^�i�i�d�|�������鐅�[�j�̑_�����A�����ē�����̎����ƍ��킹�����ȂǁA�v����ɘr�������ƍl������B
�����A��ނ�ł́A������ɏ������l���S��������މʂ邱�Ƃ͒��������Ƃł͂Ȃ��B�i����͂قڒ��̌����ɂ�邾�낤�B�j�D�O�@�D�݂̑��D�ɏ��A�n�}�`��^�C�̗{�B���ŁA���邢�̓A�R���L�{�B�́u���v�ȂǂɑD���|���āi�W�����āj�ނ�ꍇ�A�����d�|���œ����G�T�łQ���Ɨ���Ă��Ȃ��Ƃ���ŕ���Œނ��Ă����l�̂����̂ЂƂ�A��������S�҂̕��ɂ����A���C���ނ�āA�x�e�����̂ق��ɂ͈�C���ނ�Ȃ������B���邢�́A�����̐H���̂����ԑт���ނ��Ă����ނ�q���S���ނ�Ȃ������̂ɁA���߂��ɁA���̋q���A�������Ƃɂ����Œނ����l����ނ�������Ƃ����悤�Șb�͂�����ł�����B�܂�A�C�ނ�͂��邢�͐�̒ނ���A��R�[�g��̂悤�ɐl�דI�ɍ��ꂽ����裂��ꂽ�ꏊ�łȂ��A�s��`�Ő₦���ω����鎩�R�̏ꏊ�ł̗V�тł���A�����ȏ����ŋ������Ƃ͂Ƃ��Ă��ł��Ȃ��̂ł���B�ނ�́A��ʂɁA�Q�[���܂苣�Z�ł͂Ȃ��̂ł�B
������A�������ɁA�������Ԃ�ʂ��Ă݂�Ώ��Ȑl�قǑ����ނ邱�Ƃ͊m�����낤���A��邢�͐���́u�����v�ł�������ނ�������ƌ����ĒދZ���ゾ�Ƃ͌����Ȃ��ƍl������B�������āA���܂����ꏊ�Ō��܂������Ԃɓ������𑽂��ނ�A�d�ʂ������悤�ȋ��Z��Ӗ��̂�����̂ƍl����ނ�l�́A�قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B
���̃X�|�[�c�ł́A���ׂẴX�|�[�c�I��A�����ŃX�|�[�c���s���Ă��钆�����A�q�������A���邢�͂��̎��͂̐l�X�A�X�|�[�c�t�@���́A���[���h�J�b�v��I�����s�b�N�̑��͂������A�����̋��Z���ł��A�����ɏo�ꂵ��ʂɓ��܂����I���傢�ɏ^���A�����܂����Ǝv�����肷��ł��낤�B�����A�ǂ�Ȃ��ƂɊւ��Ă������ɏ����Ƃ����ׂĂ��ƍl����ǂ����̑卑�̐l�Ԃ������A�ނ�l�E�ނ�t�@���͒ނ苣�Z�̃`�����s�I���ɑ��Ă��̂悤�ȏ]�̔O�������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�ނ�̍��ۑ��̂悤�Ȃ��̂��s�Ȃ�ꐢ�E�`�����s�I�����I�ꂽ�ɂ��Ă��A�����ł��낤�B
�X�|�[�c���D�Ƃ���B��]�ނ悤�ɁA�ނ�l���ނ�ɂ��܂��Ȃ肽���ƍl����B�������A�ނ�ɂ����ẮA��B�͐l�Ƌ������ď����߂ɋ��߂���̂ł͂Ȃ��B�ނ�́A�J�C�����̗p����g���A���h�D�X�ł͂��邪�A�S�[���ł͂Ȃ��B���������y���߁A����w�A���R�����ɓ������A�����Č����Βނ�̋Ɉӂ̂悤�Ȃ��̂�m�肽���Ƃ����A��Љ�I�E�l�I�ȊS���狁�߂�����̂��B
�C���̂��߂̒lj��i2016/12/15�j
�w���u�i�ނ�ȂǃQ�[���i�����j�ł���悤�Ȓނ�͓��{�ł͗�O�I���ƍl���Ă������A���̗l�Ȏ��������邱�Ƃ�m�����B �w�l���̐�ނ�@River Fishing in Shikoku�@�ގt��ނɂ��A���E�A�}�S�V�R�K�C�h�x�i�l��4�V���Ѝ����o�ŁE���Q�V���Д��s�A����10�N�j�Ƃ����{������B�l����24�{�̉͐�̃A���ƃA�}�S��360�|�C���g�̓���n�}�A�ʐ^�A�������Ȃ�350�y�[�W�̖{�ł���B���̒��ɓ������ޘA�����Z�����Ƃ����l���܂ޓ����̃A���t�ɂ����k��u�����̃A���ނ�v�Ƃ����L�����ڂ��Ă��āA�����ł͎��̂悤�ɏ�����Ă���B���ߑ�X�|�[�c���́A��y�E�V�тƂ��Ďn�܂������A���Z�������܂��ėV�т̗v�f�����Ȃ��Ȃ����g�̉^���Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�ނ�́A�t�ɁA���p�E���v����n�܂��āA�u�V�сv�̗v�f�����܂����g�̉^���ƌ����邾�낤�B�����āA�V�т͏�艺��͂����Ă�������������Ȃ����Ƃł��邪�A���ߑ�X�|�[�c���͋��Z���𑝂����Ƃɂ���āA���̐l�X�����D�ꂽ�͂�Z�������A�l�ɏ��鏭���̃X�|�[�c�E�G���[�g�A���I�ȉ^���I�肪�o�ꂵ���������邱�ƂɂȂ����B����ɃX�|�[�c�̓V���[������A�E�Ɖ�����邱�ƂɂȂ�A�����̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A�X�|�[�c�̋Z���A�\�͂����߂邽�߂Ɏg���l�X����Ȃ�X�|�[�c�E�����܂ꂽ�B
��Q�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�w�Z�ɒʂ����k�����������ŁA���������K��K�v�Ƃ���X�|�[�c�𑱂���̂́A�ł���Ώ����v���̑I��ɂȂ��č������҂�����A�I�����s�b�N�Ȃǂɏo�ꂵ�u�L���ɂȂ肽���v�Ƃ������Ƃ����@�ƂȂ��Ă���P�[�X�������Ǝ��͑z������B�P�ɂ��̃X�|�[�c���D���ŁA���܁A���𗬂��Ċy���݂������畔�������̂��Ƃ������k�͏����h���Ǝ��͎v���B����́A�W�c�ŗ��K���邱�Ƃ�K�v�Ƃ����A�D���Ȏ��ɍD���ȂƂ���őǂ����K�ł���͌�⏫���ɂ��Ă�������B������͌�͐g�̂�b���邽�߂̐h���g���[�j���O�͕K�v�Ȃ�����A�X�|�[�c�ƈႢ�A�y�����Ƃ��������ł���Ă���q�ǂ������邾�낤�Ǝv���邪�A������B����A��͂�v���ɂȂ肽���ƍl���邾�낤�B�������A��l�ɂȂ��Ă�����X�|�[�c���邢�͈͌鏫������Ƃ��đ�����l�����邱�Ƃ͂������ł��邪�B
�������A�ނ�����鏬�w����������A�ꗬ�̢�ނ�̑I�裂ɂȂ邱�Ƃ���Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�ނ肪�D���Œ��w�A���Z���I�������ƁA���t�ɂȂ邱�Ƃ�I�Ԏq�������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A����͋ɂ߂Ă܂�Ȃ��Ƃł��낤�B�ނ�͏����Ƃ͊W�Ȃ��A�����ς猻�݂��y���ޗV�тł���B
�͌饏����ł��T�b�J�[��싅�̂悤�ȃX�|�[�c�ł��A�܂��ނ�ł��A�ŏ��͊y��������n�߂�ł��낤�B�����A��������Ėʔ����Ǝv��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B�͌�⏫���͏�B�����A�ǂ��Ă���������������ɂȂ邾�낤�B�����邩�ǂ����́A�˔\�����邩�Ȃ����ɂ������Ă���Ǝv����B�ނ�́A�ނ��̋߂��ɏZ��ł���Α�����\���������Ȃ�B�������A�N��ƂƂ��ɑ��̎�Ɉڂ�҂����邾�낤�B�ނ�𑱂�������̂͋��������ł���B�������X�|�[�c�̏ꍇ�ɂ́A�q�������ɋ����ƍ˔\�̂ق��ɂ��A���K�ɑς��āA�p�����邱�Ƃ��\�ɂ���ʂȗv��������B
�X�|�[�c�E�j���[�X�͖����̂悤�Ƀe���r�ŕ��A�S���w�Ō����A�X�|�[�c�I��Ƃ̓��ꎋ���N����₷���B�q�ǂ������͎����̏�������`���B�e�������ł���B�q�ǂ��͂��̋P�������ڕW�Ɍ������āA�e�ɗ�܂���A���K�̐h���ɑς���Ƃ����ʂ����Ȃ肠��Ǝv����B���炭�ʂ��ĖO��������A���K����������ƌ����āA�����ɂ�߂�q�ǂ��͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�X�|�[�c��N���u�ɒʂ��q�ǂ������̓X�|�[�c���A���݂��y���ޗV�тƂ��čs���̂ł͂Ȃ��A���݂��]���ɂ��邱�Ƃ��o��ŁA���炵�������Ɍ������ēw�͂��銈���Ƃ��čs���̂ł͂Ȃ����B�ނ�́A�T�^�I�ȗV�тł���B���݂��y���ނ����̗V�тł���B
��ŎO�Y�G���̓R�C��t�i��ނ��ނ�A����R����ނ�k���ނ�́A���̏C�s�I�v�f������Ƃ����_�Łu�B�S�_�I�v�����A�C�ނ�́u���`�I�Ɂv�l���A�務�����߂�̂Łu�B���_�I�v���ƌ����Ă����B�ނ�͋����K�v�̂��߂ɁA���邢�͐H���₨�̑����ɂ��邽�߂ɍs�Ȃ���̂ł͂Ȃ��B�܂�ނ�͐�����i�Ȃ̂ł͂Ȃ��B������i�Ƃ��ċ����l��J���͋��ł���B�ނ�͋��ł͂Ȃ��A�ނ邱�Ƃ��y���ނ̂���ړI�ł���B�Ƃ͂����A��͂�H�ׂ邽�߂ɁA�O�����̂��߂ɍs�Ȃ���̂ł���B�ނ邱�Ƃ��y���ނ̂����A���̂��߂ɂ͒މʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A�l���̓Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�ƈ���āA��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�č��Ȃǂł̓X�|�[�c�Ƃ��đ啨�Ɛ킢�`�����邱�Ƃ�ړI�ɃT���ނ�������Ȃ��Ă���悤���i�ѓc�w�ނ�ƃC�M���X�l�x���Q�Q�X�j�B�������A���{�ł́A�啨��_���ЂƂтƂ��T����ނ낤�Ƃ͂��Ȃ��B�T���͈�ʂɐH�ׂ��Ȃ�����ł���B�T����ނ�̂͂ӂ��Q�b�쏜�̂��߂ł���A���Ƃ̈�Ƃ��Ăł���B
�ʐ^�́u�J���b�N�ɏ���ăT����ނ�グ���j�����v�ihttp://gigazine.net/news/20071015�j�B�J���b�N�ƒނ�グ��ꂽ�l�Y�~�U���̑傫���͂قړ����B���̃`�[���̓A���X�J����I�[�X�g�����A�ɂ���Ă��Ēނ����B�댯�Ȃ̂ŕ��ʂ̓{�[�g�i���ԂD�Ȃǂ̂��Ƃ��낤�j�Œނ�Ƃ����B
 �ނ�l��������_���Ƃ�����N�G�ł���B�����ăN�G�͔��ɂ��܂����ł���B�N�G�ނ�͋��Ƃ̊i����ړI�Ƃ���ނ�ł���B�������A�ނ�グ�鋛���H�ׂĂ��܂����ł��邩��A�i���̒ނ肪�P��K-1��{�N�V���O�Ȃǂ̊i���Z�ł͂Ȃ��A�܂��Q�b�쏜�̘J���ł��Ȃ��A�܂������ނ�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�ނ�l��������_���Ƃ�����N�G�ł���B�����ăN�G�͔��ɂ��܂����ł���B�N�G�ނ�͋��Ƃ̊i����ړI�Ƃ���ނ�ł���B�������A�ނ�グ�鋛���H�ׂĂ��܂����ł��邩��A�i���̒ނ肪�P��K-1��{�N�V���O�Ȃǂ̊i���Z�ł͂Ȃ��A�܂��Q�b�쏜�̘J���ł��Ȃ��A�܂������ނ�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B
������A�H�ׂ�ړI�ŋ���ނ�ɁA�C�����łȂ����R�A���邢�͌k�J�ɂ����i�s�����j�̂ł���A�u�B���_�I�v�ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��B���{�̒ނ�̑����́A�C�s�A���邱�Ƃ��u���`�I�v�ȖړI�Ƃ��ĂȂ����̂ł��Ȃ����A�t���C�E�t�B�b�V���O�̂悤�ɋZ�̔������A�Z�I��Nj�������̌|�p�Ƃ��āA�M���I��Ƃ��čs�Ȃ�����̂ł��Ȃ����A�Z�~��g���{������ėV�Ԃ̂Ɠ����悤�ɋ��ƗV�сA�Y��邽�߂ɂ̂݁A�ނ������̂ł��Ȃ��B���{�ň�ʓI�Ȓނ�͒ނ邱�Ƃ��y���ނ̂����A�����Ɋl����H�ׂ邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���B���̈Ӗ��Łu�y���S���v�I�ŁA�B���_�I�Ȓނ�Ȃ̂ł���B
�w�}�� �X�|�[�c�j�x���҂́A�������[���b�p�̔_���̗V�тƂ��ċ|�˂ƒނ肪�s���Ă����ƌ����A�����`���������̊G���ڂ��Ă���B�|�˂ƒނ���y���_�������́A���R�Ȃ���A�ˎ~�߂�����E�T�M��H�ׂ����낤���A�ނ�������H�ׂ��ł��낤�B�܂��ѓc�́w�ނ�ƃC�M���X�l�x�Ō���悤�ɁA�ߑ�ɂȂ��Ă�����A�t���C���g���Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ͕ʂɁA�H�ׂ邽�߂̒ނ�A�R�[�X�E�t�B�b�V���O���s���Ă���B���Ƃ��Ƃ͐��E���ǂ��ł��ނ�͋���ނ��ĐH�ׂ邽�߂ɒނ����B�������ނ�͑��̘J���Ƃ͈Ⴂ�A�y�����B�����ŁA���̎d�����K�v�ȂƂ��ɃT�{���Ăł��A���ނ肪�ǂ����Ă��K�v�łȂ��Ƃ��ɂ��A�ނ������B�������Ēނ�́A�J���̐��Y�͂��������ĊF��������K�v�ȘJ���ɒǂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ����Ƃ��A��ɗV�тƂ��čs����悤�ɂȂ����ƍl�����邾�낤�B
���łɑ�Q�͂Ō������Ƃ����A�ߑ�I�ȁu�X�|�[�c�v�͂��̔��˒n�ł���p���ɂ����ẮA��y�E�V�тƂ��Ďn�܂����B�X�|�[�c��ʂ́A�V�тƂ��āA�t�b�g�{�[�����j�Փ��ɍs��ꂽ�悤�ɁA�ߐH�Z�̐����ɕK�v�ȍ�Ƃ�J���Ƃ����g����E�o���邽�߂Ɏn�߂�ꂽ���̂�����A���퐶���ɂ����Ă͖��Ӗ��ŁA����Ɩ��W�ȓ���E�g�̉^�����琬�藧���Ă���B���Ƃ��A���肪������{�[�����o�b�g�őł��ĉ����ɔ���Ƃ�������́A�����̕K�v�Ƃ��������̂Ȃ��ł͈Ӗ������������A�u���[���v��ɂ���Ă͂��߂ĈӖ��������Ƃ̂ł��铮��ł���B�X�|�[�c�͌���ɂ����Ă͐E�ƂƂȂ�A�I�肽���̓X�|�[�c���s�Ȃ����Ƃŋ����҂��������c�ށB�����A����ȊO�̐l�X�́A�d���ȊO�̎��ԂɃX�|�[�c��V�сA�y���ށB
�����A�ނ�́A���Ƃ��Ƃ́A���������̤�����̂��߂ɍs���Ă����Ƃł���A���ł́A�ނ�́A�C���ő̂��g���ċ���ނ��Ċy���ޗV�тł���B���t�̂悤�ɁA�����E�Ƃɂ��邱�Ƃ��\�����A����́A���Ƃ��ƒނ肪���Y�����̈��Ƃ��āA���Ƃ̂��߂ɍs��ꂽ�����ł���A�l��������A�����H���ɂ��邱�Ƃ��A�������đ��̕�������ɓ���邱�Ƃ��ł���Ƃ����A�ނ�Ɂu���ݓI�v�ȗv�f�ɂ��B����̃G���^�[�e�C�������g�Y�Ƃ̂悤�ɁA�A�}�`���A�̃X�|�[�c�ł�������y�E�V�т��A���{�Ƃ��ƂȂǂ̗͂ŁA���Ɖ��A�Y�Ɖ�����A�v���[���[�̐E�Ɖ����Ȃ��ꂽ�̂Ƃ͎���S���قȂ�B
�哇����u���J�����v�w���}�ЕS�Ȏ��T�x�ɂ��ƁA�q���r�Ƃ������͓��{��Łq������r�Ɠǂނ��A����́q�鋁�H��(����������)�r����]�����Ƃ����B���Ȃ킿�A��ŊL�ނ�ނ��W�߂���A�����œ��������ꂽ������b�k�ނ���Â��݂ŕ߂炦��Ƃ����s�ׂ����J�̍ŏ��̌`�ł���B�������q���r�Ƃ��������q���Ȃǂ�r�Ɠǂނ̂́q�鋛�߂�(�����Ȃǂ�)�r����]�����Ƃ���邪�A�܂��Ɉ�ł��̂悤�ȏ�����߂炦�邱�Ƃł����āA������g�����ƂȂ��̏W�s�ׂ�������̂Ƃ����Ă悢�B����̓~�̊��ł́q�C��(�̂�)�݁r�܂�C���m���̎������̍��l�ł́q�������r���A������̂悤�Ȍ����`�Ԃ̋��J�����̂Ȃ��肾�A�Ƃ����B
���́A��Œނ�����Ă��āA���������ċ����ނ�錩���݂��Ȃ��Ȃ�ƁA�T�U�G��Ƃ��Ԃ���T������A�p�S�ɌR����͂߂ĕt�߂̊�̊���ڂ�T���ăJ�j��������肵���B�q�g�f��M�ы��̂悤�ȐH�ׂ��Ȃ����͍̂̏W�Ώۂł͂Ȃ��B��V�тƒނ�͂ӂ���肪�͂����A�����Ȃ��Ƃ���ɂ��鐶������߂܂��邱�Ƃ��ł���_�ŋ��ʂ��Ă��āA���Ɋy�����B�ɉ����Ēނ�ł͂Ȃ���V�т�����̂͑S�����R�ŁA���҂͓�����ނ̊�т�^���Ă����B
���āA�O�f�ѓc���w�ނ�ƃC�M���X�l�x��ǂނƁA�C�M���X�ł́A�قȂ鎞��ɈقȂ�K���̐l�X���A���܂��܂ɈقȂ�ނ���s�������Ƃ��킩��B�����āA�������q�ׂ����Ƃ́A�P�V���I�ɐ���ɍs��ꂽ�n�Y�o���h���[�Ƃ����_�Ƃ̒��ōs��ꂽ�ނ�Ɏ��Ă���A�܂��A�P�X���I�A�Q�[���E�t�B�b�V���O���邢�̓t���C�E�t�B�b�V���O�Ƌ�ʂ��ꂽ�A�R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɂ����߂��悤�Ɏv����B�����̓_�ɂӂ�Ȃ���A�C�M���X�ɂ�����ނ蕶���̗��j����˂��Ă݂悤�B
���C�E�|�[�^�[�^�ڗ����a��w�C���O�����h�P�W���I�̎Љ�x�i�@����w�o�ʼn�A�P�X�X�U�j�ɂ��ƁA�P�V�O�O�N����ɂ́A�C�M���X�̋M�����邢�͒n��K���Ȃǂ̃W�F���g���}���i�S�l���̂P�D�Q���j���y�n�̂Q�O������R�O�������L���A����ɂQ�O�l�قǂ̏㗬�M���͂P�O���G�[�J�[�ȏ�̓y�n�����L���Ă����B�i�P�G�[�J�[�͖�S�O�O�O���āA�P���G�[�J�[�͂S�O�O�Oha�j�B�]�ˎ���̓��{�̔ˎ�̂悤�ȑ��݂ƍl���Ă����̂�������Ȃ��B�ނ�́A�����h���Ɠc�ɂ̗����ɉƂ������A�c��J��̓����h���Ő����ƎЌ��̐����𑗂������A����ȊO�̎����ɂ͓c�ɂŗV�тƁA�F�l�m�l�������Ă̎Ќ��̐����𑗂����B��ɤ19���I������͕s�ݒn�剻���邪�A����܂ł͓c�ɂő��̔_�������Ƃ������A���̏j�Ղ̃X�|���T�[�Ȃǂ����߂Ă����B
�ѓc�ɂ��ƁA�W�F���g���}���́A�����̉��~��q����܂߂��_���̊Ǘ��A�ʎ��E�뉀�̎����A�ƒ{�̎���ȂǂɎ���ւ�����B�����āA�_�������ɂ����邱�̂悤�ȁu�Ɛ��̒m���ƕ��@����镪��v�̓n�Y�o���h���[�ƌĂ�Ă����B����̔��B�Ƃ��֘A���A�P�V���I�ɂ͑����̃n�Y�o���h���[�̏��������s���ꂽ�B�n�Y�o���h���[�̂Ȃ��ł́A���A���ނ�A�ߒ��A���ɂ���A���{�Ȃǂ̃��N���G�[�V�����ɂ��Ă�������Ă����B
�M����W�F���g���[�͍L��ȓy�n�����L���A���z�̒n��������ґ�Ȑ����𑗂��Ă����B���������n�Y�o���h���[�́A��Y�ƣ�܂藘���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��銈���ł͂Ȃ��A�c�ɂ̎����̉��~�ɂ���Ƃ��ɁA�����ł̎����������ґ�ȐH�����̂��߂́A�y���݂����˂čs�������ł������B�ѓc�͢�����A���̂悤�Ȕ_��Ƃ����ꎩ�̃��N���G�[�V�����ɂق��Ȃ�Ȃ������B�����̎���͐����ƗV�т����E���̂͂����肵�Ȃ��܂܂ɋ������Ă�������---�ł������v�ƌ����B
���N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ���L�߂铭���������E�H���g���́w�ދ���S�x�����s���ꂽ�P�V���I�́A���N���G�[�V�������u�J���̂Ȃ��̊y���݁v����u�J�����番�������V�сv�Ƃ��Ă̈Ӗ����l�����Ă�������ł��������B�₪�ăC�M���X�̔_�ƁE���Ƃ�����剻���A����ɎЉ�S�̂��Y�Ɖ�����ɂ�A���v��Nj�����ނ�͎d���Ƃ��ĐE�Ɖ�����A���N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ�̓X�|�[�c�Ƃ��Ď���Ɋg�債�A��O�����Ă䂭�B����ɉ����Ēނ�̖{�ɂ����邱�̃��N���G�[�V�����ƃn�Y�o���h���[�̕����̌X���������ɂȂ����Ɣѓc�͂����B
���v�����˂��n�Y�o���h���[�̈ꕔ�Ƃ��Ă̒ނ�ƃ��N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ�̕����̒��Ńt���C�E�t�B�b�V���O�̐l�C�����܂����B����A�C�M���X�ɂ����ẮA�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƃR�[�X�E�t�B�b�V���O�Ƃ�����ʂ�����B
�C�M���X�̖@���ł͉͐�ɂ����鋙�l���͂��̉͐�̒ʂ�y�n�̏��L�҂̂��̂ł���A�C��͌��̢������죂̂悤�ɂ͊J������Ă��Ȃ��B�����̎{�݂ł���^�͂⒙���r�Ȃǂ̏ꍇ�����l���͒ނ苦��A���Ƒg���Ȃǂɒ��݂�����A���̊Ǘ��E�^�c�͂����̒c�̂Ɉς˂��Ă���B
�u�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƃt���C�E�t�B�b�V���O�͂قڏd�˂čl���邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�Ɠ��l�A���݂ł́A�����̏ꍇ�����@�[�E�L�[�p�[�ƌĂ����ʂ̊Ǘ��l��u�����l��@�l�̏��L����ނ��ŁA���̊��ԁA����ꂽ�l�����̃X�|�[�c�Ƃ��Ċy���܂��ނ�ł���B����ɑ��ăR�[�X�E�t�B�b�V���O�ƌĂ����̂�����B�R�[�Xcoarse�͖{���A�u���́v�Ƃ��u���i�ȁv�Ƃ����Ӗ��ŁA�R�[�X�E�t�B�b�V���̓T�P�ȈȊO�̎G���������B���������āA�R�[�X�E�t�B�b�V���O�̓T�P�ȈȊO�̎G����ނ�Ӗ����琶�܂ꂽ�ƍl������B�������啔���̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�͉a�����Ēނ�x�C�g�E�t�B�b�V���Obait-fishing�k�a�ނ�l�ł���A���̂悤�Ȓނ���ꋉ���Ɍ���Ӗ����܂܂�Ă���悤�ɂ��v����v�Ɣѓc�͂����B
�R�[�X�E�t�B�b�V���O���u���i�v���ƍl�����Ă���A���邢�͂��̃j���A���X���Ă��闝�R�́A�ѓc�����p���Ă��邢�����̏����̕��͂ɂ���悤�ɁA�x�C�g�A�܂�a�Ɂu�E�W�⒎��j�ɂ���v�Ƃ��́u�s�������v��u�c�����v�ƁA�m�b�Ɓu�Z�part�v�̍�i�ł���[���t���C���g���ނ�̢��������Ƃ̑Δ�A�ȒP�Ɍ����t���C�͒m�I�ł���A�x�C�g�E�t�B�b�V���O�͎��R�I���n�I�ł���Ƃ��������Ɋ�Â��Ă���Ƃ������Ƃ͊m�����낤�B
�����A�G���A�X���ώ��̃X�|�[�c���ɂ��Đ������Ă���c�_���Q�l�ɂ��čl����ƁA����ɕʂȗ��R�����������B�P�X���I�Ƀt���C�E�t�B�b�V���O�̐l�C�����܂��������A���邢�̓W�F���g���}����������R�[�X�E�t�B�b�V���O������������̒ނ�ł���Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƌ�ʂ��A������悤�ɂȂ��������ɂ́A17���I�A�E�H���g���̍��Ƃ͈���āA�W�F���g���}�������͂��łɃT�P�Ȃ̋��������Œނ��ĐH�ׂ�̂���߂Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�G���A�X�ɂ��P�V���I����܂ł̃W�F���g���}�������́A�Q�b�̋쏜�ƐH�ׂ�y���݂����˂Ď��̌�y���y����ł����B�������P�W���I�ɂȂ�ƐH�ׂ�y���݂��������ƂƂ��ɁA����̎�Ŋl�����E�����Ƃ��~�߁A�����������P���������ɂ�点�A����飂̂��y���ޢ�X�|�[�c��Ƃ��Čώ����s���悤�ɂȂ�B�X�|�[�c�́u���v�v�����˔����Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl������悤�ɂȂ�A�X�|�[�c�͂���ΐ��_�I�A�u�B�S�_�I�v���y�Ƃ����������ꂽ�ړI�̂��̂ɕς�����B
���̊ϓ_���炷��A�W�F���g���}���������A�Ǘ����ꂽ�ނ��ŁA�X�|�[�c�Ƃ��Ẵt���C�E�t�B�b�V���O�Œނ�T�P�Ȃ̋��͐H�ׂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������͂��ł���B�H�ׂ�̂́u�B���_�I�v�ȁu�yݕS���v�̂��邱�Ƃł���B�W�F���g���}������������H�ׂ����Ƃ��ɂ́A�s��̃��X�g�����ɏo�����邩�A���邢�́A�����̉Ƃ̏��g���������l�Ɏw������悢�B����炪��Ƃ̋��t������肵�����𗿗�����ł��낤�B����A�����̒ނ�ł������R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɂ����ẮA�H�ׂ邱�Ƃ���v�ȖړI�ł���B�R�[�X�E�t�B�b�V���O�́A�����Ȣ�X�|�[�c����s���]�T�̂Ȃ����w�̐l�Ԃ��A�ݑ܂������߂ɂ���ނ�ł���B�������A�ނ�����������u�����ȃX�|�[�c�v���邢�́u�Q�[���v�Ƃ��đ����邱�Ƃɔ�����҂������B
�ѓc�ɂ��ƁA�V�F�����K���́A�u�E�H���g���́w�ދ���S�x�ƕ��Ԓނ�̖����Ƃ�����v�P�X�P�Q�N�́w�R�[�X�E�t�B�b�V���O�x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B �u�ނ�k�R�[�X�t�B�b�V���O�l�ɂ����āA�E���̂��߂̎E����]��ł͂Ȃ�Ȃ��B---�������A�t(��)�A�����Ăӂ��������ł͂Ȃ��Ԃŋ�����낤�Ƃ���̂́A���ł͂Ȃ��B�����̈Ӑ}�͎E�����Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��A�m�b�ƋZ�p�������������ƁA�H�ׂ邱�ƁA���邢�͗��v�邱�Ƃɂ���̂��v�B
�܂��A�P�X�Q�S�N���s�w�z���ƃh���C�E�t���C�x�ŁAJ�EW�E�_���͎��̂悤�Ɍ����Ă���B �u�X�|�[�c�v�̓Q�[���ł͂Ȃ����A���̂悤�ɍl�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B��y�̂��̂Q�̌`�Ԃ͍��{�I�ɈقȂ�B�u�Q�[���͖{���I�ɂ́A���ꂽ���̂ł��B���̋K����K�肪����𐬂藧�����鍜�Ɛg�Ȃ̂ł��B��������苎��ƁA��l�̐l�Ԃɑi����ɑ�����͉̂����c��Ȃ��ł��傤�B�������A����ނ�́A�Q�[���Ɍ����Ă�������A���Ȃ킿�A���ꂱ��Ɖ�����ꂽ�K���Ȃǂ܂������Ȃ��ɑ��݂����{�I�Ȗ��͂Ɩ��f���ӂ�ɂ���y�Ȃ̂ł��B----�Q�[���ł͐키����͋K���ɔ���ꂽ�l�Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�������A�X�|�[�c�ɂ����ẮA����͎��R���̂��̂Ȃ̂ł��B�쐶�́A���R�ȁA�@�ɔ����Ȃ����R�A����ŁA�x���A��������A�����̂����A����Ȃ����l�ŁA�₦���ω����č���D�����R�Ȃ̂ł��B�v
�����ŗp�����Ă��颃X�|�[�c��Ƃ�����́u���ނ�v�Ȃǂ̎��R����ɍs����V�т̊������w���Ă���A�u�Q�[���v�Ƃ�����͋K���ɂ���č��ꂽ�X�|�[�c���w���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B���͂��̃_���̕����A�Q�[���E�t�B�b�V���O�ȊO�̂ӂ��̒ނ�̖{���I�ȉ��ƁA���̋��Z(�Q�[���j�I�ȃX�|�[�c�ƈقȂ�ނ�̓����Ƃ����S�Ɍ������ĂĂ���Ǝv���B�ނ�́A�l�Ԃ�ɂ����A�K���ɂ���č���A�K���ɔ���ꂽ�V�сA�܂�Q�[���łȂ��A�@����Љ�I�u����v����E�o���A���̐l�ԂƂ̊W���ŏ����ɂ������R�I�ȗV�тł��邪�䂦�Ɋy�����̂��Ǝ��͎v���B
�����A���̓_���������悤�ɃQ�[���ł́A�K����K�����苎��Ɓu��l�̐l�Ԃɑi����ɑ�����͉̂����c��Ȃ��v�Ƃ͎v��Ȃ��B�q�ǂ��͂Ƃ������A��l�ł�������A�K���ɂ���Ď葫��A�l�דI�ȍ���ȏœ������Ƃ��y�����Ɗ�����A�ߑ�X�|�[�c�̃Q�[���̈��D�҂��������邱�Ƃ��\���ɗ����ł���B
���̓X�|�[�c���G���A�X�̊T�O�ɂ��������ė�������B�܂�ϏO�ƃv���[���[����̂ƂȂ��ċ������y���ނ��̂ƍl����B�����āA�قƂ�ǂ̃X�|�[�c�����������𑈂����Z�ł���A���R�A���[����K�v�Ƃ��A���̈Ӗ��ł̓Q�[���ł���B���Z�ł���Q�[���͌���l��������������̂ł���B�X�|�[�c�̓A�}���x���ɍs�Ȃ��Ċy���ނ��Ƃ��ł��邪�A�������A�ϏO���W�߂邱�Ƃ��ł���Ȃ�A������(�ׂ���)��T���Ă������������ł����݂��A�v�����A���Ɖ����\�ł���B
����ɂ����ẮA�X�|�[�c�͂����ꂷ�ׂăv��������邾�낤�B(�E�H�[�L���O��W���M���O�ȂǁA�v��������Ȃ��g�̉^���͢���W���[������ƌĂ�Ă���B)�X�|�[�c�̓v���E�X�|�[�c�ł��邩�A�������̓v���������ł��낤�g�̉^���ł���B�X�|�[�c���ϏO���l�������邽�߂ɂ́A�v���[���[�̓��[���Œ�߂�ꂽ�Q�[���^���Z�̃v���[�ɑS�͂𓊓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A���̉ߒ��ŃQ�[���ƊW�̂Ȃ����v�A�]�\�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ϋq�������߂��邾�낤�B�X�|�[�c�͏����ȃQ�[���i�V�Y�j�ł�������A�ϏO�̋����Ɗ�т��l���ł���B������A���́A�X�|�[�c�ƃQ�[������ʂ��Ȃ��B
�����ŁA���́A�i�قƂ�ǂ́A���{�ɂ�����j�ނ�́A�X�|�[�c�ł��Q�[�����Ȃ��ƍl����B�قƂ�ǂ̒ނ�͐l�Ƌ��������A�l�Ɍ��Ă��炤���Ƃ����҂����ɁA���ƑΌ����邱�Ƃ��y���ޗV�тł��邪�A����ɂ͗]�\�A���v�������B�Ƃ������A�l���̗L�������̓��̒ނ�̐��ۂ̔��f��ł���B���������ċ��͒P�Ȃ�]�\�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��͂�ڎw�������́A���邢�͖ړI�ł���B���{�̒ނ�̑����́A�p���̂��Ẵn�Y�o���h���[�ɑ������Ă���A19���I�ȍ~�̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɋ߂��B�܂�A�ނ��Ċl���邱�ƁA�����H�ׂ邱�Ƃ����̊y���݂̈ꕔ�A�d�v�Ȉꕔ�Ƃ��Ċ܂ޒނ�ł���B
�������n�Y�o���h���[�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�ނ肪�A�ѓc�̌����悤�Ɂu���v�Ɗy���݁v�����˂����̂��Ƃ������ƂɊւ��ẮA������^�₪�c��B�ґ�������̐H�����𑗂邱�Ƃ̂ł����W�F���g���}���������A�ނ��V�тƂ��čs�������Ƃ͓��R���Ƃ��Ă��u���v�v�����߂��Ƃ͍l���ɂ�������ł���B�ނ������Ƃ��������邽�߂Ɏ����ċA������������Ȃ��B�����ď��g�������������̂��A���������H�ׂ���������Ȃ��B�������A�H���ɂ���u�K�v�v�͊����Ȃ������̂ł͂Ȃ����B
���C�E�|�[�^�[�ɂ��A�ނ�͑吨�̋q�������āu���[�X�g�r�[�t�̎R�v��H�ׂ��B�ނ������ł��ĂȂ��K�v�����������ǂ����������B�n�Y�o���h���[�̏����̂Ȃ��Œނ���ӂ���Ă����ɂ���A������A�X�|�[�c�ɏ��������^���ɂ������̂ł͂Ȃ����B�n�Y�o���h���[�Ƃ��Ă̒ނ�́A�W�F���g���}���ȂǏ����҂��A�s��ł͎Ќ����y����ł�������ŁA�c�ɕ�炵������Ƃ��ɂ́A��͂�F�l��ƈꏏ�ɗV�сA�ނ�����ĂȂ��A�������y���ޕ��@�Ƃ��āA�����Ȃǂƕ���ōs�Ȃ����X�|�[�c�ŁA���������A�������̂��肩�����A�����ƑS������Ă���B�n�Y�o���h���[�Ƃ��Ă̒ނ�́A�l����H�ׂ��Ƃ����_�Ŏ��Ă͂��邪�A�����̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�Ɠ���ނ̊����ƍl����͓̂���̂ł͂Ȃ����B
������{�ɂ�����ނ�́A�킸���Ȏ�ނ̃Q�[���E�t�B�b�V���O��ʂƂ���ƁA��V�сA�������A�R�؎��ȂǂƂƂ��Ɏ��n���A�l����_���V�тł���B�ނ�ɂ���Ă����͐H������ɓ���邱�Ƃ��ł���̂ł��邩��A���̐g�̉^���ɂ���ėV�сA�y���ނ̂ł͂����Ă��A�P�Ȃ�u�Q�[���v�A��V�Y��ł͌����ĂȂ��B
�A���ނ��E�i�M�ނ�̂悤�ɁA�����ɐH�ׂ邽�߁A���邢�̓O�����̂��߂̒ނ������B���̒ނ�͊C�ނ�ł���B�[���S(���A�W)�Ȃ��g���ɂ��Ă����ؒЂ��ɂ���B���_�C�⒆�A�W�A���^�C�T�L�Ȃ�J���Ĉ�銱���ɂ��ėⓀ�ۑ����Ă����B���^�ȏ�̃}�_�C���A�W�A�C�T�M�Ȃ�A��C����l�ŐH�ׂ�ɂ͑�������̂ŁA���̗F�l��e�ʂɑ���A���邢�͋��D���ŃO�����̒m�l�ɔ����Ă��炤�B��R�ނꂽ�Ƃ��ɂ�(�m�l�̊��߂Łj�s��Ɏ����Ă��������Ƃ����邵�A�m�荇���̗��ق�X�g�����ɔ����Ă���������Ƃ�����B�v�����璍��������A���邢�͒ނ�̘r��]�����Ă�������肷��Ƃ��ꂵ���Ȃ�B
�G�T�͂قƂ�ǂ͔������A�C�V�_�C�ނ�p�̃E�j�̌Q���ꏊ�������ŒT���Ď������A�n�}�`�̉g���ނ�p�̒���Ȏd�|�������肷��Ƃ��Ȃǂ́A�{���̋��t�ɂȂ����悤�Ŕ��Ɋy�����B���ɂƂ��Ēނ�͢�B���_�I��Łu�y���S���v�I�ȂƂ��낪�ʔ����̂����A����������ƗV�тł���Ă��邱�Ƃ������ɐ����ɖ𗧂���A���邢�́A�l�Ɍق��Č��߂�ꂽ���ԓ����ċ��������炤�̂łȂ��A���������Ƃ��ɂ����A�܂������̂�肽�����Ƃ���������ē����ĉ҂����Ƃ��ł��A�ق�̏��������u���������v�Ɏ����������ł��邩��A�܂蔼���V�тŔ��������Ă��邩��A�ʔ����̂��Ǝv���B���̓G���A�X�̌����u����I�v�ő����̂���E�ƘJ���͋�ɂɊ����邪�A��I�ȁA�܂�s�K���ŁA�D�݂₻�̎��X�̋C���ɏ]���čs���J���͌����Ă���ł͂Ȃ��B
���͋����Œނ肾�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�q�I�E�M�L�Ƃ����z�^�e�L�Ɏ����L�̒t�L�����炢�A�{�B���Ă���B�n���̎�Y�Ƃł���A�R���L�̗{�B���s���Ă��鋙�Ǝ҂̗F�l����肽�A�R���L�{�B�p�̃l�b�g�ɓ���ĊC���ɒ݂邵�Ă����A�N�ɂQ�`�R��l�b�g������������A�L�̕\�ʂɕt������t�W�c�{��J�C�����Ȃǂ̐����������藎�Ƃ��B���͂����������S�ł��邪�A����͂����U�`�V�N�����Ă���B�����S�́u�A�I�T�A�g�E�S���E�C���V�A�i�K���R�A�c���i�c���u�L�j���̂�A�q�I�E�M�L��{�B����v�Q�ƁB
�܂��A�Q������߂��̈�ɐ�����C�ۂ��̏W������A�t�ɂ͗��R�Ńc���u�L�����B�g�E�S���E�C���V�̖ԋ�����`���i�ԂɎh�������C���V��Ԃ���͂����j�B�Q�L���قǂ̂Ƃ���ɂ��闣��ɑD�œn��A�E�F�b�g�X�[�c�𒅂ĉ����g�C�ɐZ����Ȃ���g�R�u�V���̂�A�Ȃǁu���ቻ�v����Ȃ��l�X�ȋ��J���s���B�ǂ���V�`�W�N�ԂɂP�A�Q�ł���A�͂��߂ĂŒ����������������������ł͂Ȃ�������ꂻ�������A�����Ƃ���͌����Ȃ��B�g�E�S���E�C���V�͗U���Ă�����Ď�`�����N�̌�A�Q�N�̓C���V�����Ȃ������B�R�N�ڂɋ��͊�������A������ꂩ�琳���ɏ��R�ɋA���Ă���Ԃł������B�Ԃ������Ă���ׂ̂͗̏W���̐l�ŁA����������킹��킯�ł͂Ȃ��B�������Ƃ������ɉ�ΗU���Ă����B�������������R�ɂ��ǂ��Ă���A�U���Ă��炤���Ƃ͂ł����A���̔N�͏I���ł���B
�C�ۂ̍̎�ɂ��ẮA�C�ۂ͔N�ɂ��o�����قȂ�B�Q�A�R�N�����ďo�������������Ƃ����B�����ĐC�ۂ������Ă����ɍs�����߂ɁA�܂��A�`��̂����C�ۂ��o�P�c�ƃU�����g���ĉ��x���C���Ő���č����Ȃǂ���菜����Ƃ��s�����߂ɂ́A����̑D�������Ă���l�ɗU���Ă����Ȃ���Ȃ炸�A�~�A�C�ۂ̉肪�łĂ���P�������炢�̂������ɁA��̂Ƃ��ɁA�D�������Ă���F�l�̓s�����ǂ��Ȃ���A���̔N�͏I���ł���B
�g�R�u�V�͂Q�O���R�O�̂낤�Ǝv���T�����{�̑咪�̊������̂Q�A�R���̂������ɏ������ꂽ�����ɍs���˂Ȃ�Ȃ��B���̊ԂɊC���r���������̔N�͍̂�Ȃ��B3���̑咪���`�����X�ő��l�̒��ɂ�3���ɍs���l������B�������A���̂���͐������Ⴍ�����Ɏア���ɂ͖����ł���B���������킯�ŁA�s�����Ƃ��Ă��Q�x������ƂȂ̂ł���B
�����̊����A�V�т͑��l���s���Ă��邪�A��͂蓯���悤�ɁA���N�����Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���X�ɂ����s���Ă��Ȃ��B�����ɏZ��ł��Ă��A�C�̏ɍ��E������ƊC�̗V�тł���u�̏W�^�ߊl�A�͔|�v�����͖��N�R���X�^���g�ɂł���킯�ł͂Ȃ��̂ł���B�@�����Ί��ł�邪�A�`�����X�����Ȃ��̂ł���B�����ă`�����X�����Ȃ�����ʔ����̂ł���B
�J�C�����́A�V�т͘J����|�p�ƈقȂ�u�����Ȃ�x�������Ȃ��i�����ݏo���Ȃ��v�B�u�V�т͏����ȏ���̋@��v���ƌ����Ă����B�������ɁA�Q�[���E�t�B�b�V���O�͢�V�Y��܂�P�Ȃ�V�тł���A�ނ������̓����[�X���A�l���ɂ��Ȃ��B���n�����邢�͐����ɖ𗧂��̂ݏo�����A���肳���Ă���Ȃ��B�����A���{���ōs���Ă��鑽���̒ނ���V�т͂����ł͂Ȃ��B
�ނ�́i�����Ĉ�V�т́j�m���ł͂Ȃ��A���C���K�v�����A�傢�ɗL�v�ȕx��^���Ă����B�V�тȂ̂�����A�ނ��������������Ƃ��ĐH�ׂ��ĐH��̌y���ɖ𗧂��x�͖��ł͂Ȃ��B�s���ł������ʔ�Ȃǂ��܂߂āA�V�тƂ��ē��R�K�v�Ȍo������������A�}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B�d�v�Ȃ��Ƃ́A�ނ肪�����炷���̂́A���Z��Q�[���ő���Ɂu���v�Ƃ����P�Ȃ�u���_�I�v�u�B�S�_�I�v�Ȋ�т��Ƃ��A���b�L�Ō��郁�_�����Ƃ��Ƃ��ł͂Ȃ��āA���ۂɖ��킢�A�H�ׂ邱�Ƃ��ł���l�����Ƃ������Ƃɂ���B�ނ�͉��\�̐��E�ɂ�����V�тȂ̂ł͂Ȃ��A�������E�̒��ł̗V�тł���A�ߐH�Z�̐����ƘA�����Ă���B
�ސE�҂̎��́A�A�p�[�g��炵�̊w�����ߐH�Z�̐������s����w�ɒʂ��Ă���悤�ɁA�܂��_�����ߐH�Z�̐����������Ԕ��ɂł�����悤�ɁA���̋����̉ƂŐ����������Ԃ͊C�ɂłĒނ������B�N���ŕ�炵�Ă���A�ނ�Ő��v�𗧂ĂĂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����_�ŁA�_���ƈقȂ�A�w���̐����Ɏ��Ă���B�������A2�T�Ԃ��邢��3�T�ԂÂ��ċ����Œނ�����ĕ�炷�Ƃ��ɂ́A�ނ�́A��������ȂǕ�炵�ɕK�v�Ȋ����ƘA�������A����́u���������v�̑傫�Ȉꕔ�ł���A�J�C������z�C�W���n�������悤�ȁu�͂��߂ƏI���v�̒�܂����u��������̒E�o�v�̊�Ăł͑S���Ȃ��B���������́A60�̂Ƃ��̑ސE�ɂ���āA����܂ł̎d���^�J������E�o���āA���̒ނ蒆�S�̌����I�������J�n�����B���X�̒ނ�͓���̂ق��̎d���^�����A���邢�͐����ƘA�����Ă���A���̊C�ӂ̑��ł̎��̐����S�̂͒E�d���^�J���̗V�тł���B
�����̃X�|�[�c�̏ꍇ�ɂ��Ă͂܂颃v����Ɓu�A�}�v�̋�ʂ��A�ނ�ɂ͂��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ͒ނ�ƃX�|�[�c�̈Ⴂ���l�����ŏd�v�ł���B��ʼni�c�����͈�ʃX�|�[�c�ł̓v���ƃA�}�́A�K��ɂ���Ė����ɕ�������Ă��邪�A�ނ�ł͓��ʂȋ��E���Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ������Ƃ����Ă��邪�A���������v�����A�}���Ƃ�����ʂ́i�ߑ�j�X�|�[�c�̒a���ƂƂ��ɐ��܂ꂽ���̂ł���B
�X�|�[�c�E�ɂ�����v���ƃA�}�̈Ⴂ�͢�v���X�|�[�c��Ƃ������x�ɂ���č�肾���ꂽ���̂ŁA�v�����A�}���Ƃ�����ʂ͂��̃X�|�[�c�E���x����Љ�I�Ȏd�g�݂ɂ���Đݒ肳���B�ߑ�X�|�[�c�͋����𒆐S�Ƃ���̂ŁA���[���𖾕������A�{�ݥ�p����K�i�����A���Z�̊Ǘ���^�c�����ꂼ��̋���Ȃǂőg�D�I��n���I�ɍs���B���̎�ޖ��ɂ͂����肵�����[������߂��Ă���A�����̍s�����A���邢�͋��s�̍s�����Ȃǂ��Ǘ��E�^�c����@�\�i���{���o����A�i�e�k�T�b�J�[�A���A���{�v���S���t����A���j�����݂���B�v���E�X�|�[�c�v���C���[�ɂȂ邽�߂ɂ́A����i������A�v���̃`�[���ɏ������邽�߂̑I���e�X�g��̗p�����̂悤�Ȃ��̂�ʂ�K�v������B����̓v���ł��邱�Ƃ̢�`����ɂ������B
�v���ɂȂ邽�߂ɂͤ�e�X�g���č��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�{�����͍��Z���ŁA�܂��A�A�}�������Ƃ��ɁA���{���q�v���S���t�����Ẫc�A�[�ŗD�������B�k�ޏ��̓v���e�X�g�͖Ə����ꂽ�Ƃ����B�l�܂����Q���o�g�̏��R�p������w���ŃA�}�������Ƃ��ɓ��{�v���S���t�����Ẫc�A�[�ŗD�������B���������������A���Ƃ����ϓI�ɂ̓A�}�ƃv���̎��͍��͒f�R�傫���Ƃ��Ă��A�v���ł���Ƃ������Ƃ́A�A�}������ɋZ�\����ł��邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B��v����͢�v������`����Љ�I�Ȏd�g�݂ɂ���ė^������`���ł���B
�������A�A�}�ƃv���̎����I�ȈႢ������B�A�}�͑��l�ɋ����ĕ�V����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i����b�X����v����̐��x������B�j���A���ŁA��ʂɓ��܂��Ă��A�܋��⏤�i�����炤���Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ŃA�}�́A�S���t�ŐH�ׂĂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������������̂��߂ɂ͢�v����ɂȂ�K�v������B
�ނ�ɂ����ẮA�E�B�[�N�G���h�E�A���O���[�Y��Z�J���h���C�t�E�A���O���[�Y�̂悤�ɗV�т̒ނ�ł���̂������Ƃ����t�Ƃ��Ă̐��Ƃ̂��߂̒ނ�Ȃ̂��Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A�X�|�[�c�E�ɂ�����A�}�ƃv���̋�ʂƂ͈قȂ�A���̈Ⴂ���ʂ͉��炩�̌_��⎑�i�̗L���ɂ���Đ�����̂ł͂Ȃ��B�����n�߂�����̉���ȋ��t�́A����ł����Ă��A���Ő����𗧂ĂĂ���Ȃ�A���̂Ƃ����łɁA�v���Ƃ����Ȃ�v���̋��t�ł���͂��ł���B�A�}�̋��t�i�܂��͒ގt�j�����炩�̎Љ�I�Ȏd�g�݂̊֗^�ɂ���ăv���̋��t(�ގt)�ɕς��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B
�����̑g�������i�́A���t�Ő����𗧂Ă邱�ƂƂ͊W���Ȃ��B�����Ԃ��Ă��g�������łȂ���A�܂��{�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�����ɉ������Ȃ��Ă��A�N�ł����R�ɁA���邢�͏���ɍs�����Ƃ��ł���B���ꋙ��Ԃ��Ă��g������������ɂ́A������ʂ��Ď����̂̋�����K�v������B�������A�g���ɉ������邽�߂ɂ͍ŏ����̏o���������Ƃ����߂��邾���ŁA�����Z�ʐR����e�X�g�̂悤�Ȃ��̂�����킯�ł͂Ȃ��B�������āA����ł����t�ɂȂ�邵�A�܂��A�����̑g�����ɂȂ邱�Ƃ��ł���B
�������A�����̑g�����ɂȂ邱�Ƃ͐����̕ۏ�Ƃ͊W���Ȃ��B�T�b�J�[��싅�Ȃ�v���̃`�[���ɏ������邱�Ƃŋ������x������B���邢�͓��{���o����ɏ�������u���o�����v�ɓ���A�֎�ɂȂ�܂ł͕����̎d�������A���������������ۏႳ��A�֎�ƂȂ������Ƃ������������炦��B���������ɒ�u�ԂȂǂ����L���A�����ɂ����鋛�𐅗g�����ďo�ׂ���d���������Ƃ��Ă���Ă���Ƃ��������悤���B���̏ꍇ�ɂ͋����������ɉ������邱�Ƃ͑��̉�Ђɓ����ē����̂Ƃ��Ȃ����ƂɂȂ�B�������A��{�ނ�̋��t�̏ꍇ�ɂ́A�u���i�v�⢏�����ɊW�Ȃ�������̎��͂����Ŏ����ƉƑ��̐������x����B�ނ肾���Ő����𐬂藧������͓̂���A���̃A���o�C�g�ŕs�������҂��u���Ƌ��Ǝҁv�����邪�A���Ȃ����ނ肪���v�𗧂Ă�҂��Ƃ��čs���Ă��邩����A�A�}���v�����ǂ��炩�ɕ��ނ���Ƃ���A�v���̋��t�Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�����������Ƃ͋��Ɓi�ނ�j�Ɋւ��Ă������Ă͂܂���ꎖ��ł͂Ȃ��A��Ƃ��Ď��Ɨp�̕Ă��؍����s���Ă���_�Ǝ҂Ȃǂɂ����Ă͂܂�B���̗F�l�ŁA����N�w�ȑ��ƂŁA�_�Ƃŕ�炵�Ă���҂�����B�_�Ƃ��c�ނ̂Ɏ��i�͕K�v�Ȃ��B����̓T�����[�}������ŋx���ɔ��������Ă���̂Ƃ͂킯���Ⴄ�B�v���ƃA�}�Ƃ������p���āA�J���i�g�̊����j�v�̂��߂ɍs���Ă���̂�����Ƃ��V�т̂��߂Ȃ̂��ނ���Ƃ���A���̎��̗F�l�̓v���̔_�Ǝ҂ł���B
���t�ł͂Ȃ��A�ނ��[�J�[�Ȃǂ��狋����Ⴄ�����̢�v���̣�ގt������B���̃v�������͋����A�H�ׂ��蔄�����肷�邽�߂ɒނ�̂ł͂Ȃ��B�V�����J�����ꂽ�ދ���e�X�g����e�X�^�[�Ƃ����d���ɂӂ��킵���ދZ�������Ă��邱�Ƃ��������߂ɒނ�̂ł���B�����̎Љ�o�ϓI�n�ʂ��K�肷��Ƃ���A���ʂ̋Z�\���Čٗp����Ă���u�����v�Ƃ����Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B
�V�т��N���ɂ��X�|�[�c�A���邢�́A�ߑ�ɂȂ��ĐV���ɍ��o���ꂽ�X�|�[�c�ł́A�g�̉^���Ƃ��̋Z�́A���p�I�Ȏ����ݏo�����Ƃ̂Ȃ��u�V�Y�v�ł��邪�A�ނ�͂��Ƃ��Ɗl���A�H������ɓ���邽�߂̋Z�Ȃ����Ƃł���B���i�⏊���ɂ��A�}�ƃv���̈Ⴂ���Ȃ��Ƃ��������łȂ��A�Q�[����t�B�b�V���O�������A�ނ�ɂ����Ă͒P�Ȃ�V�т̒ނ�Ɛ��Ƃ̒ނ�̂������̋�ʎ��̂����݂��Ȃ��B�ސl���މʁA�l�����ǂ̂悤�Ɉ������A�����Ǝ����̉Ƒ��̎�Ȑ�����i�ɂ���̂��ǂ����̋��ڂ̂͂����肵�Ȃ��Ⴂ�����邾���ł���B
���n�E�l��������ƌ����_�ł́A�ނ�́A�ƒ�؉��ł̖�؍���A�R�؎��A�������A��V�сA�f����A��ȂǂƂ��Ȃ��O���[�v�ɓ���B�ނ�́A���܂��܂ȗV�сA��̂����A(�m�I���_�I���y��Ƃ�������)�l���邱�Ƃ�ڎw���A���O�ł́A���邢�͎��R���̂Ȃ��ł̗V�т̈��ƒ�`�ł���B
�x�W�^���A���I�u�������l�X�́A��ؤ�R���������̂����肷�邱�ƂƁA�������E�����ƂɂȂ��ނ�i����ɒ��������H�j�Ƃ̊Ԃɤ�������������Ǝv����������Ȃ��B�x�W�^���A���́u�����ϗ��v�ɂ��Ă͋c�_���Ȃ����A���́A�ނ�Ǝ�Ƃ̊Ԃɂ͂��Ȃ�̈Ⴂ������Ǝv���B
�O���ɂ͒ނ�Ɨ��P�̃N���u�ɂȂ��Ă���Ƃ��������Ƃ����B�ނ�����������l���Ƃ��đ_���_�͋��ʂ���B�������A���҂̈Ⴂ���傫���悤�ɂ��v����B�����߂�͕ʂƂ��āA�e�œ��������Ƃ������Ƃ͎E�����Ƃ��Ӑ}����Ƃ������Ƃł���B�E�����Ƃ��ɂ����Ƃ����͕̂��ʍl�����Ȃ��B�G���A�X�ɂ��A��ł͐l�Ԃ����ڂɊl�����E�����A�p���ɂ����āA�P�W���I�����炢����n�܂����X�|�[�c�Ƃ��Ă̌ώ��ł́A�l�Ԃ͒��ڎ���������A�P���������ɒǐՂ����A�߂܂�������ŏI�I�Ɍ��ɎE������B��������ł��A�ς�ǂ������A�����A�E���̂��u����v�������y���ނ̂ł���B
�������A�ނ�ɂ����ē���ɍ��킹�Ēނ�j�ɋ����|���邱�Ƃ́A�E�����Ƃł͂Ȃ����A�E�����Ƃ��Ӑ}���Ă��Ȃ��B�e�œ�����_���̂́A�����o���̖\�͂ɂ���Ĥ�L�������킹��������E�����Ƃł���B�ނ�ɂ����ẮA�a������ē����悤�Ƃ��鋛�Ƃ̋삯����������B�ނ�l�͂����Ήa���̂��܂����ɉa������ĉ�������B�j�Ɋ|������A�C�V�_�C��n�}�`�Ȃǂ̑�^���ł͗͂����̐킢�ɂȂ邪�A�����Ă��́A������J������o�����肵�ċ��Ƃ��Ƃ�����Ȃ��炷��������A�����Ђ����y���ނ̂ł���A��荞���Ƃ��A�D���̐��łȂǂɓ���ċA��A���̌�A�����Ƒ傫�Ȑ��łɈڂ��āA���炭���߂Ċy���ނ��Ƃ�����B���́A�}�_�C�ނ���n�߂ĊԂ��Ȃ����ɒނ����A�Y���O�ł��ꂢ�ȍ��F�ɋP���V�O�Z���`���̃}�_�C���A�P�T�ԁA���a�P�D�T���[���Q���قǂ̐��łɓ���Ė������߂��B�������A�Ō�͐��ł̖Ԃɂ�����ĕЕ��̊Ⴊ�������Ă��܂����B���łɓ���Ă����܂ł����C�ɉj�����Ă����͖̂����Ȃ̂ł���B
���A�D����ނ����C�V�_�C�A�C�V�K�L�_�C�A�}�_�C�������܂܁A�Ȃ��݂̗��قɎ����Ă����A�q�Ɍ����邽�߂̐����ɓ���ĉj���������Ƃ�����B���̂Ƃ��A�ނ�̖��������ł������������B�i���̋������ӁA�q�̒����ɉ����ĐH��ɋ������邱�ƂɂȂ�̂����B�j
�����ɂ����Ƃ��ɂ́A�O��Ȃǂő�^���܂߂P�O�C�قǃC�V�_�C��ނ������A���ׂāA����ł���ƂɎ����A��ق��Ȃ������B���Q�̋����ɏZ�݁A�D�Œނ����C�V�_�C�͍ő�ł��R�L�������炸�B�����͂Q�L���قǂő傫���͂Ȃ��������A�����ĉj�����̗E�p���݂邱�Ƃ��ł��A�������y���������B���Ȃ������Ȃ��Ǝv�����A�����ŕ�̐������̌�납��h���ĎE���i�Y��j�̂͊y�����Ȃ��B���̐l����������̂��u����v���Ƃ��y�����͂Ȃ��B�ł͎E�����Ƃ̋������y���ނ̂ł��邪�A�ނ�ɂ����Ă͑S���Ⴄ�B�ނ������͍ŏI�I�ɂ́Y�āA�܂�E���āA�����ŐH�ׂ���A�����ɑ������肷��̂����A�ނ邱�Ƃ����E�����Ƃł͂Ȃ��A�܂��ނ��������E�����Ƃ��y���ނƂ������Ƃ͑S���Ȃ��B�ނ�͗Ƃ͈قȂ�A����������B
Hunting,�p���Wikipedia

�w���}�ЕS�Ȏ��T�x�ɂ��A��Ƃ͐l�ނ��������ƌ�����`�Ԃ̈�Łu�ی�A�،h�A�����Ȃǂƕ��ԓG�̊W�ɑ����A���̐����Ƃ��ɖ쐶���b��ߊl�E�Q���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���s�ׁv�ł���B�u�l�ނ��쐶���b�Ƌ�����������đ����r�����悤�Ƃ���������A�l�̑�����݂��ꍇ�̌ď̂ł����āA��������̐�����i�Ƃ��Ă���҂���l�ƌĂ��B���̌Â��Ӗ����l�ނ̏��������炩�ɂȂ�ɂ�Ă�����Ă����A�������Ɍ�y��X�|�[�c�Ƃ��Ă̈Ӗ��𑽂��܂ނ悤�ɂȂ����̂�����̎�ł���v�Ƃ����B
������{�ɂ����ẮA�l�ԎЉ�A�n���^�[�ƌ�������ƣ��ʂ��āA�N�}��C�m�V�V�Ȃǂ̓������E�Q��r�����āA�����Ȑ�������낤�Ƃ��銈��������Ƃ������Ƃł���B�ό��q��Z���������̓����ɏP���鎖�����N����ƁA�n���̗F��Ȃǂɕߊl�v�����s����B���������ꍇ�ɂ́A��͗V�тł͂Ȃ��A���I�Ȏd���ł��邱�Ƃ��͂����肷��B�J���Ȃǂ͏����Ⴄ���낤���A�e�����邩��Ƃ����Ă��A��͖������̐킢�ł���A�ނ��S���t���y���ނ悤�ɁA��ʃT�����[�}�����ȒP�Ɏ�ɂ��邱�Ƃ͂Ƃ��Ă��ł��Ȃ��r���ۂ��X�|�[�c�ł���B
�l�H���U���Ȃ�u�Q�b�v�Ƃ��āA�E���A�r�����邱�Ƃ�ړI�ɒނ邩������Ȃ����A��ʂ̋���ނ�̂́A�����Ɓu�����E�������đ����r���v���邽�߂ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ƃ͐H���邽�߂̊y�����J���Ƃ��āA�����Č���ɂ����Ă͑啔���͋��Ƃ̋삯������i�����y���݂܂��������͐����ɖ𗧂����邽�߂ɁA�ނ�̂ł���B
�����Ŏ�������������g���Čς��E������C�M���X�̢�ώ�裂̂悤�ɁA�u�E������v���Ƃ��S�������悤�Ɏc�����Ɗ�����l�����邾�낤�B����l�́A����I�ɓ�����|��ł��邢�͏e�ŁA�l�⑼�̓����Ɛ킢�A�E�Q����K�v���S���Ȃ��B�푈�Ƃ����ُ펞�ɂ���ʎs���́A���Ă����͂邩�ɂЂǂ���Q����\���͋��܂��Ă��邪�A�G���E�Q���邽�߂ɒ��ڂɎ����Ŏ���������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ł��낤�B
�T�O�N�ȏ�O�A�܂�q�ǂ����������ɁA���́A�����Ĉ�Ă��j���g����E�T�M�����̐e���i�߁A�H���ނ���A�����̂���̂��������A���̓����g����������H�ׂ��o��������B�����͓��{�̌o�ϐ����O�œ��͏\���H�ׂ��Ȃ������B�s�c�Z��c�n�ł��������A���͂̉Ƃł��j���g���������Ă���Ƃ͂�����ł��������B�������A���݂ł́A�c�ɂł����Ă��A�����������i�͂߂����Ɍ���ꂸ�A�قƂ�ǂ̐l���X�[�p�[�Ȃǂœ����B��E����v���Z�X�͉ƒ납�牓�������Ă��܂����B
����Љ�ŕ�炷�������́A����������������E�����肷�邱�Ƃɂ͊��炳��Ă��Ȃ����A������Ă����Ȃ��B����ꂪ����I�ɕK�v�Ƃ���ߐH�Z�Ɋւ��i�X�̂قƂ�ǂ��ׂĂ͎����ō�邱�Ƃ͂Ȃ��A�o�������̂��̂��B�Ƃ���邱�Ƃɂ��Ă͌����ɋy���A�C�X��e�[�u���A�{���Ȃǂ����l���ǂꂾ�����邾�낤���B�H�����A�H�ނ��Ă��Ē�������Ƃ����̂����������ŁA�R���r�j�ŕٓ�������A�t�@�~���X��[�����X�ł�������イ�H�ׂ�Ƃ����l���������낤�B�����āA�H�ނ����O�Œ��B�ł���ƒ�͂قƂ�ǂȂ��B���X�̖�Ȃ�A�낪����Ύ����ł���Ă邱�Ƃ��ł��邪�A���⋛��ނ̏ꍇ�ɂ́A�������Ă������E����̏������邱�ƂȂǂƂ��Ă��s�\�����A�C�ӂɏZ��ł��Ă�����L���l�邱�Ƃ��ȒP�ł͂Ȃ��A�����́A�E�ƂƂ��čs���A���̖q�{�Ǝ҂�H�������ƎҁA���邢�͋��ƊW�҂Ɉˑ���������A�����̐l�X�̎���o���H�ނƂ��ē��肷��ق��Ȃ��̂ł���B
�������́u�j�{��v�ɉ^�ꂽ�ƒ{���u�j�E�v�����Ƃ������Ƃ͒m���Ă���B�������A���̕��@�͒m��Ȃ��B���̎g���Ă���p�\�R���́u�����v�ɂ́u�j�{��v�Ƃ�������u�j�E�v�������Ă��Ȃ��B�������͎E���ꂽ�����̉�̏����ɂ��ĉ����m��Ȃ��B���������ڂɂ�����͂��łɐ蕪�����p�b�P�[�W���ꂽ���̂��A�݂⒰�̓��e���Ȃǂ͂������̂��ƌ��t�Ȃǂ����Ă��Ȃ��A���ꂢ�ɏ������ꂽ�}���ł����āA�����́A�E�����Ƃɔ�����J�╉���ڂ���؊������ɐ�̉��y�����𖡂키���Ƃ��ł���B�����͓���̐H���ɋ�����M�������������ŎE���Ă���H�ׂȂ����ƌ���ꂽ��A���Ԃ�H�ׂ��ɉ䖝���邱�Ƃ̂ق���I�Ԃ��낤�B
�܂茻��l�̂قƂ�ǂ́A�������̐H���ɑ���~���A���邢�͓����̓���H�ׂ邱�Ƃւ̗~���������Ă͂��Ă��A���̓�����ߊl���E�����ƂƂ͖����̐����𑗂��Ă���̂ł���B�������āA���������E�����ƁA���������������𗬂����Ƃ��A�����̐H�ׂĂ�����⋛�ƌ��ѕt���邱�ƂȂ��A�u�c���v���ƍl����B
���̂P�O�N�����������P�T�N�قǂ̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����A�C�m�V�V�Ȃǖ쐶�������l���Ɍ���Ė��ɂȂ��Ă���B���̏Z�ދ����ł��C�m�V�V���o�v���A��������̂��邢�͂킸������̔��̍앨�����ꂽ�ƏZ�������ڂ��B�����ɗ��ݕߊl�p�̟B���d�|����ꂽ���Ƃ��������B�܂��A����Ƃ��A�A�R���K�C�{�B�̎d�����̋��Ǝ҂��A�C���j���ł���C�m�V�V�ɏo���킵�A��l������Ń��[�v���|���ĕߊl�����B�`�ɂ����Ƃ���Łu�Q���m�E��H��킵���v�������ɂ͎��Ȃ��A����ɔ������܂܍�Ɨp�̃z�C�X�g�Œ݂邵�A�A����ĎE�����B�q�����������l�A���킳�����ďW�܂������A�߂Â��Ċώ@���悤�Ƃ���i���͂��������̂����j�q���͈�l�����Ȃ������B�����ŕ����A�ڂ����`�����āA�T�`�U��������Ă��킲�풭�߂邾���������B�ߊl���A�u�Q���m�E��H��킹�v�A�A������̂́A�V�O�߂��̋����ł���B���ꂩ��тJ�ɏĂ��Ă��ꂢ�ɂ���B��̂Ƃ��낪���܂��̂��Ƃ����B�ނ̑��q�̓T�����[�}���ł���B���q�͂����ƃC�m�V�V�Əo����Ă��A�����̎�ŕߊl���悤�Ƃ��A�E���ĐH�����Ƃ͂��Ȃ����낤�B
���̃C�m�V�V�ł��������ʂ̂��̂��������͐q�˂Ȃ������̂����A�t�Ղ�̐܁A���h�c�̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ�V�V��ɌĂ�ł��炢�A�C�m�V�V�̓���H����@��ɗ^�����B�\�z�Ƃ͈���āA���炩���A�Ȃ��܂������Ȃ��A�������������B�����A�����A�s���炵�������Ȃ��Ă��܂������߂��Ƃ����l�����Ȃ����A�H�ׂ邽�߂Ɏ���̎���������Ƃ͉����������Ǝv�����A�܂��A����͑傫�����ł͌����Ȃ����A�Ƃ̗��ɃC�m�V�V������A�ߊl�p�̟B���d�|����ꂽ�Ƃ��ɂ́A�C�m�V�V�������ɓ���Ȃ��悤�Ɋ���Ă����B
�����́A���悵�����ɁA�����ł͂Ȃ����o�ɂ����āA�Ώۂڂɑ_���ĎE���͍D�܂Ȃ��Ȃ��Ă���̂��B���{�l�̂قƂ�ǂ͚M���ވȏ�̓���������̎�ŎE�Q���邱�Ƃ��D�܂Ȃ����A�E�T�M��j���g���̂悤�ȏ������ł���H����̏������ĐH�ׂ�Ƃ������Ƃ͂��Ȃ����낤�B
�Q�O�P�P�N�P���S�����Q�V���ɂ́A���J���Q�y�[�W���g���āu�b�����́g�t�P�h�A�����쐶������Q�͍��v�Ƒ肷����W���s�Ȃ��Ă���B���̓��W�Łu�]�_�v�������Ă��鈤�Q��w�_�w���̌����҂ɂ��A�_�ыƂ̐��ށA�_���̏k���ɂ��A�����������R���畽�암�ɂ���Ă�����悤�ɂȂ������ʁA��Q���g�債�Ă���Ƃ����B���̂����ł̋c�_�ƊW������̂́A�����b�̋쏜�Ɋ֘A�����A��Ɋւ���_�ł���B�Q�O�N�قǂ̊ԂɁu��l���v�͂Q���قnj������B�e�Ƌ��擾�Ґ��������Ă���B�������A��ȗƋ��̎擾�҂͑����Ă���Ƃ����B�쐶�����ƓG�ΊW�������Ă���ɂ��Ă��A���ڎE�����Ƃ͔��������Ƃ����X�������邱�Ƃ̕\��ƌ��邱�Ƃł���̂ł͂Ȃ����B
�Ñ�M���V���l�͈�������t��b���l�Ԃ����������Ƃ͈قȂ鐶�����Ƃ݂Ȃ��A���n���݂ɁA�z��Ƃ��Ĉ������Ƃ��}��Ȃ������B�����A�����ŁA�ҏb�⢊Q�b��ƈقȂ�A�t������������Ȃ��A�l����L���A�l�Ԃ̎p�������ɋ߂��M�������Ɋւ��ẮA���������̓��ނƂ��������B��ނ̑����͎l����L���Ă��Q�b�ł��邩�A�w�r�g���̂悤�ȓ���ȐE�Ƃ̎�����ȊO�ɂ́u�������v���R���Ȃ��Ɗ�����ꂽ���낤�B�������E�~�K���Ȃǂ͊C�m�����ɂƂ��āA�e�ߊ������������݂�������������Ȃ��B���w���̍��A�C������J�G���������̐����Ŏ����Ċώ@�������Ƃ����邪�A�����ނ������Ē��߂�Ώۂɂ͂Ȃ肦�Ă��A�e�����u�t�������v�W�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B
����L�ȂǂƊr�ׂ�A��^�ŕ��̎n���Ȃǂ͑�ςȂ̂ł͂Ȃ����Ƒz������鋍��n�Ȃǂ̉ƒ{���A���Ĕ_�ƂŐl�̕�炷���Z�����ɓ������Ă������Ƃ�����B����́A�@�B�̑��݂��Ȃ�����A�P�ɁA�J���͂Ƃ��ďd�����ꂽ���ʂ��Ƃ���͎v���Ȃ��B�y�b�g�ɑ���̂Ɏ����e�ߊ���l�X���������Ƃ��ł�������ɈႢ�Ȃ��B
�������w�Z�̍��ɂ̓n�g�������̂����s�����B�����n�g����������Ă��炢�A���H�����������A�n�g�͌����A�悭�Ȃ��A�F�B�ɂȂ邱�Ƃ��ł����B�����ȂǁA���������l�ł���B����Ƃ��A�S���R�Ɩ̎}�̖����g���č��p�`���R�i�S���|�j�����s�����B�n�g�����������ƑO�ł���B�d���Ɏ~�܂��Ă���X�Y����_���đł�����A�^��������A�X�Y�����n��ɗ������B�u�������I�v�Ɗ�͈̂�u�����ł������B���͏����ȃX�Y���̎��[����ɂ��āA���킢�����Ȃ��Ƃ����Ă��܂����Ƌ�������̔O�Ɏ���ꂽ�B����́u���ɂ͑�������l�ԂɎ��Ă���v�Ǝv���Ă�������ł͂Ȃ��B��щ���Ă���̂�����̂��y�����̂ɁA�����������̂����Ŏ���œ����Ȃ��Ȃ��Ă���X�Y��������̂��߂����A�������Ƃ������Ɗ������̂ł���B�����ߏĂƂ������̂��L��A�̂͂����ݖԂȂǂŎ���ĐH�Ƃɂ������Ƃ��������悤���B�܂����ł��A�����Ƃ��ĐH�ׂ�����X������悤���B�������A�X�Y���̂悤�ȏ����͐H���Ƃ��Ẳ��l�͏��Ȃ��B���́A�p�`���R�ʼn�����_���đł��A�I�ɓ��Ă邱�Ƃ��y�������������ł���A�������l���ĐH�ׂ悤�Ƃ���ς�͂Ȃ������B�����͐H�ׂ邽�߂ɑ��݂��Ă���̂łȂ��A��щ���Ėڂ��y���܂��Ă���鑶�݂������B
�쒹�ł��a�t�������܂������Ύ������Ƃ��ł��āA�E�O�C�X��W���̂悤�ɖ����Ől���y���܂��Ă���钹������B���邢�͑��ł́A�ώ��̗��̂悤�ɁA�l�Ԃ̃X�|�[�c�̏���Ƃ��āA���邢�͐l�Ԃ͂����ł͒P�Ɂu����v�������Ƃ���Ȃ�A�u�v���[���[�v�Ƃ��Ċ��āA�l�Ԃ��y���܂��Ă����B�������āA���͐l�Ԃ��u�t�������v���R���傢�ɂ��铮���ł���B���ނ͐l�Ԃɐe�������̂ł���A�߂����̂��Ɗ�������B
�Ă����ɂ���̂ł���h�g�ɂ���̂ł���A�����łP�C���̋����Ƃ��ɁA�C���������Ɗ�����l�͂قƂ�ǂ���܂��B�����A�N���X�}�X�Ƀ��[�X�g�`�L������낤�ƁA�u���C���[�A�܂蓪�Ƒ���A�H�т̂��Ă��Ȃ��j���g���Ȃ����{�����ۂ��ƈ�H���邢�͈�C�����Ƃ��ɁA�S�����������Ȃ����{�l�͂ǂꂭ�炢���邾�낤���B�j���g���͢��H��Ƒځi�����j�����Ă���B�܂�A��葫�������B���Ȃ��Ƃ���{�̑�������B�b�Ⓓ�͑����g���ĕ��s����B���̎�v�Ȉړ���i�͗��ł���ɂ���A���łɁA�l�Ԃ̎�Ő�ł��ꂽ�h�[�h�[�̂悤�ɕ��s�������Ȃ��������Ă͑��݂������A�j���g���̂悤�ɁA�قƂ�ǂ͕����Đ������钹�ނ�����B���s�͐l�Ԃւ̋߂��̏d�v�Ȏw�W�Ɗ��o�I�ɂ͊�������B
�������A���́A�q�������ł���B�q��������b�́A�����Đl�Ԃ́u�葫�v�Ɏ��Ă���Ɗ�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B�����āA���͑����g���ĕ��s����̂ł͂Ȃ��A�q���ʼnj���̂ł���B
�C�U���E�I�͘r�̂悤�ɑ������r�����g���āA�l�Ԃ̐Ԃ�V���������悤�ɊC����Ĉړ�����B�z�E�{�E�́A�傫�ȃ��i�r���̐�[���T�T���̂悤�ɕ�����Ă��āA������ׂ������������邱�ƂŁA�C����Ƃ�����芊�s����悤�ɐi�ށB�z�E�{�E�́u���i�́j���ڂ��v�A�܂袔����E�I����ꌹ���Ƃ����B
�C�U���E�I�́A�i���O����ڂ����q�ׂ�K�v�͑S���Ȃ��̂ɁI�j�A���R�E�ځiӸ�j�̋��ŁA�A���R�E�Ɠ��l�A�w�т�̕ό`�������̂ł���u���[(�ӂ�)�G��v��h�蓮�����ĉa������U������B�A���R�E�̉p�ꖼanglerfish�͢�ނ�����鋛����Ӗ�����B�C�U���E�I���ނ������̂ł���B�q�A���R�E�̑҂��H���r�Ƃ������Ƃ킴������Ƃ������A�A���R�E�͎��ۂɂ͊C��ɐÎ~�����܂܉a�̓������߂Â��̂�҂����ł͂Ȃ��A�����Β��w�Ȃ����\�w�܂ʼnj���オ���ĉ�V���̋���C����H���ƌ����i���}�ЁADVDROM�w���E��S�Ȏ��T�x�j�B�A���R�E�͋��r�����傫���A���܂��j�����Ƃ��ł���̂��낤�B�������C�U���E�I�̃��i�r���͂قƂ�ǘr�̂悤�ʼnj�͂͏������Ǝv����B�̂��������Ђǂ��傫���A�j���̒x���n���Z���{����肳��ɂ��肵�Ă���B����ł͑f�����j���ʼna�����𑨂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��͂����B����D�~���X����������������Ȃ��B�C�U���E�I�������ƌ������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���͕������A�j���̂��ƌ��������̂ł���B
�܂��A���͐����ɏZ�݃G���Ōċz���邪�A����b�͐l�ԂƓ��l�A�n��ɏZ��Ł\�\���Ԃ͋���Ԓ�����́A�n�ʂɐ����Ă�����Ɏ~�܂��ĐQ��̂ł���\�\��C���z���A�x�Ōċz����̂ł���B�܂��A�����w�I�ɂ́A���̃E���R�͒��̉H�т⓮���̖̑тƓ��l�A�畆�̕ω��������̂��Ƃ���邪�A���o�I�ɂ́A�E���R�́A���̎p�`�Ɠ��l�A����b�Ƃ̈Ⴂ�������؋��ł���悤�Ɏv����B
�ߑ�̗L���Ȑ����w�҂��͂邩�ɒ����Ă���ƃ_�[�E�B���Ɍ��킹���A�����ꂽ�����w�����҂ł��������A���X�g�e���[�X�͓������ꏊ�ɂ���ċ�ʂ��A���������Ɨ�����������ї����̓����ɋ敪������ŁA�C���J�ƃN�W�����u�����铮�����ōł���فv���ƌĂB�ނ͋����G���Ōċz���邱�Ƃ͂������A�����ŃC���J�ƃN�W���������ǂ������x�Ōċz���Ă��邱�Ƃ�F�����Ă����B�܂��M�����邱�Ƃ��m���Ă����B���ނ͂قƂ�Ǘ����ł���B�����ŃA���X�g�e���[�X�̕��ނł̓N�W����C���J�́u�ِ��i�M���j���������v�ł������B�m���ɁA��C��������Ĕx�Ōċz����ɂ�������炸�A�����ŕ�炷�Ƃ����͕̂s�ւł��낤����A�u��فv�Ɣނ������̂������Ƃ��ł���B
�܂��A�ނ͓�̗ށA�����ނȂǂ��u���������v�ƌĂԈ���A�u�L���v�܂�Ԃ��������Ғœ������A���s�i�l�Ԃƒ��ށj�A�l�����s�i�b����ށj�A���ނɕ������B�ނ͓����̖{���͊��o�Ɖ^���ɂ���ƍl�������A���͉^���̎�v�튯������ł���B�ނ��u���̐����d�������v�i�w�������x�̖�ҁE����O�Y�̉���B��g���ɂ��R�T�X�D�j�̂����R�ł���B
���{�ɂ����Ă��̂���A�����C�m�����ł����Ă��q���������ނ�4�{�̑������T�i���j�Ƃ��͂�����Ƌ�ʂ��Ă������Ƃ́A�Y�����Y�̕��ꂩ�番����B����͋��t�ł��苛���l���Đ������Ă������A�T�͏����Ă�����B
�i���j�C�K���̑��̓q���̂悤�Ȃ����������Ă���B�w������S�Ȏ��T�x�ɂ��J���̎l���͌w���Ŏw��ɂ߂�����Ă��邪�A������ɂ͎w�Ԃɐ����������B����B�l���̓��N�K���ł͒���ŃE�~�K���͟D��ƂȂ�A�Ƃ����B�E�~�K���̑��̓q���Ɏ��Ă��邪�q���ł͂Ȃ��u�D��v�̑��Ȃ̂ł���B
�������āA�N�W���ނ��x�Ōċz���Ă���A�M�������ł����Ă��A���̒��ŕ�炵�Ă���A������������Ȃ��Ƃ���A���̗���̓����������ނɎ������́A���̒��Ԃƌ��Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă����̕s�v�c���Ȃ��B�����̓���̊��o�́u�Ȋw�I�A�����w�I�v�m���A���邢�͌���̓������ފw�̊T�O�Ƃ͈�v���Ȃ��B
�l�Ԃ͑��̓�����H�ׂ邽�߂ɎE���̂����A�E�����Ƃɒ�R�������邩�ǂ����́A�l�Ԃ����̐����������ɋ߂����̂Ɗ����A���Ԃƌ��Ȃ����ǂ����Ƃ������Ƃɂ���č��E�����B�������āA�̂��狙�ƍ��ł������m���E�F�[���̂����A���ď����̕ߌ~�̑S�ʋ֎~�̗v���ɂ�������炸�A�������{�l�́A�N�W������H�ׂ邱�Ƃ͋����j���g���̓���H�ׂ�̂Ɗr�ׂāA�͂邩�ɁA��R���Ȃ��B�i��������̕ۑ��̕K�v�Ȃǂ͂܂��ʂȖ��ł���B�j
�Ƃ͂����A�N�W������H�ׂ�̂́A�I��/�s�풼��Ƃ͈Ⴂ�A�K�v����ł͂Ȃ��B�����̐H�K���̉�����̂��Ƃł͂��邪�O�����̂��߂ɐH�ׂ�̂ł���B����ƁA��̕ۑ����d�����A�܂��N�W����C���J�𒇊ԁA�F�B�ƌ��Ȃ��āA�ߌ~��C���J�̋��ɋ���������A���ď����̐l�X�̊���d���Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B�C���J�̕ی�c�͔̂ނ�̕����̒��Ō`�����ꂽ�n�r�g�D�X(�K��)�ɏ]���A�C���J���͐l�Ԃ̋s�ғ��l�ɋ����Ȃ����̂Ɗ�����̂ł���B����ƁA���͕����ƕ������ǂ̂悤�ɐ܂荇�킹�邩�Ƃ������Ƃł���B�m���ɔނ�̍s�ׂ̒��ɂ͈ꕔ�s���߂�����������������Ȃ��B�������A�C���J�������m�\�������Ă��āA�����Ȓ��x�R�~���j�P�[�V�����\�ł��邱�ƂȂǂ��e���r�Ȃǂŕ��f���ꂽ��A�����̐����قŃV���[��������ꂽ�肵�Ă��āA���{�l�ł��A�q�������ɂƂ��ẮA���Ȃǂ̃y�b�g�ɗ�炸�A���������ɋ߂����e�����A�F�B���l�̑��݂Ɗ�������悤�ɂȂ����Ǝv����B�����炭�A�߂������ɁA�C���J��H�ׂ�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����͓̂��{�ł����_�ɂȂ邾�낤�B�_���ȂǓ`���I�ȕ����̂��߂ɃC���J�̕ߊl���K�v���Ƃ����̂ł���A�ǂ������̂悤�ɑ����̃C���J��ߊl����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�܂��A���ۂɎE�����ɁA�͋[�I�ȍs�ׂɕς���H�v���l������̂ł͂Ȃ����B
�����͑O�͂ŃG���A�X�ɏ]���āA�u�X�|�[�c�̗��j�v���\�͂�}������u�������̉ߒ��v�ł��邱�Ƃ������B�l�Ԃ́A�푈�Ƃ�����펞�������A�\�͂̍s�g��}������X�������߂Ă����B�����m�̂悤�Ȑl�ԓ��m�ɂ�����E����������łȂ��A�L���ĎE���Ċy���ނƂ����悤�ȃA�j�}���E�X�|�[�c�͎���Ɍ�����悤�ɂȂ����B�p���W�F���g���}���̍D�X�|�[�c�ł���ώ��������I�ɓ����āA���ΐ��_�̍��܂�ɂ���āA�֎~���ꂽ�B�y�b�g�����̋s�҂����������X���ɂ���B�ߌ~��C���J���ɔ����A�̂��đj�~��W�Q�̍s�����s�Ȃ��Ă���B���́A�c�����Ɗ����郌�x�������╶���I�`���ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ͔F�߂邪�A�c�����Ɗ�������s�ׂ͂ł������i�Ƃ����͕̂K�v�Ƃ̊W�ɂ����Ăł��邪�j���炷�ׂ����ƍl����B
�u�������̉ߒ��v�́A���ԂƂ݂Ȃ����́A�߂����Ɗ���������̂ɑ��čs�g����\�͂�����ɗ}������ߒ��ł������B���邢�́A���ނƊ����A���Ԉ������铮���͈̔͂��L����ߒ��ł������B�\�̗͂}�������߂�͈͂́A�l�ԂɁu�������́v����n�܂�A����ɍL�����Ă����Ƃ������Ƃ͂��������낤�B
�P�W���I�㔼�ȍ~�̃C�M���X�ł́A�A�j�}���E�X�|�[�c�ɔ�����^���������Ȃ���悤�ɂȂ����B�ѓc�O�f���A�܂��A����ǖ��u����ꂽ���O��y�\�C�M���X�ɂ�����A�j�}���E�X�|�[�c�̋ֈ��ߒ��v�]�c�K�j�A�������i�ďC�w�X�|�[�c�x���ߑト�[���b�p�̒T�����G�i�~�l�����@���[�A�Q�O�O�Q�j�A��S�́j�Ȃǂɂ��ƁA���̎���ɕ�����`�҂����ɂ��l����`�I�ȁA��������_���W�J���ꂽ�B�A�j�}���E�X�|�[�c������łȂ��ނ���c�����Ƃ���_�҂������B���̉^�����ō����ɒB�����̂́A�P�W�Q�S�N�Ɂu�������싦��v���ݗ�����A�u���n����@�v��u���{�֎~�@�v�����������Ƃ��ŁA���U�߂⓬�{�ȂǏ����̃X�|�[�c�͋֎~���ꂽ�B�����A�ނ�͋֎~���ꂸ�A�܂��x�z�K���ł���W�F���g���}�������̃X�|�[�c�ł���ώ����֎~����Ȃ������B��҂ɂ́A��O�I�Ȍ�y�ł͂Ȃ����䂦�ɖڗ����Ȃ��������ƂƁA�܂��c����x�z����҂����̊K���I�G�S�C�Y�����W���Ă���Ɛ��������B
�����A��O�I�ɍs�Ȃ��Ă����ɂ�������炸�ނ肪�֎~����Ȃ��������R�͖��炩�ł��낤�B�܂�A�L�⋍�Ɋr�ׂċ��͐l�Ԃ̐e�ʂƂ͊������Ȃ��������䂦�ɁA�ނ邱�ƁA�ނ��ĐH�ׂ邱�Ƃ��c�s�ȍs�ׂ��Ɗ�����l�����Ȃ������Ƃ������Ƃł���B�L���ĎE���A�������Ȃ��悤�ɂ������Ɍ�������������̂��݂�A�L�⋍���ꂵ��ł��邱�Ƃ͈�ڂł킩��B�Ȃ�قǁA�W�F���g���}�������͌��Ɍς����ݎE������̂��y����ł����B�������A�L�⋍�͉ƒ{�Ƃ��Đg�߂ɂ��铮���ł���̂ɑ��āA�ς͖쐶�ŁA�����Ă���j���g�����P���Q�b�ł�����ȂǁA�ꉞ�A��ʂ͂ł���̂ł���B�����āA���́A�s��ɍs���A�����Ŕ����Ă���B����͐H���Ȃ̂ł���B�ނ�l�ȊO�́A�j�ɂ������Ė\��鋛��ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ĉ������A�p�`���A����̓����Ƃ͑S���قȂ�B���͐l�Ԃ����ԂƊ�����ɂ͋ɂ߂ĉ����ɂ��鑶�݂ł���B���́A�p���E�l����`�҂̉^�������ނ�̋֎~�Ɏ��s�����͓̂��R���Ǝv���B
���͐�g�Ŕ����Ă�����̂����邪�A�������P�C���Ŕ����Ă���B���{�l�̑����̓T���}��T�o�A�A�W�A�C���V�Ȃǂ��ƒ�Ŋۂ̂܂܂��A���邢�͎O���Ȃ����Ɂu���낵�āv�����g�ɂ��āA�Ă�����ς��肵�ĐH�ׂĂ���B���̂悤�Ȍ�����{�ɂ�������퐶����w�i�ɂ����A���ɑ���펯�I�ȍl�����A�������̂Ȃ��ŁA�����͒ނ�����A�ނ��������Y�A�H�ׂĂ���̂ł���B�l�Ԃ̈��D�������̓����Ɋւ��ċs�҂�E�Q���ւ���@�������ۂɑ��݂��邵�A���͈̔͂��g�傷��\���͂��邪�A������ʂ��E�����Ƃ����Ƃ��ċւ��邱�Ƃ�ϗ��w�I�ɍ����t���邱�Ƃ͕s�\�ł��낤���A�����N�̊ԁA������H�ׂĂ����l�Ԃ̑������ؐH��`�ɐi��ňڂ邱�Ƃ͍l���ɂ����B
�����A�ނ�Ǝ�Ƃ̊ԂɁA���ނ��E�����ƂƚM���ނ��E�����ƂƂ̊ԂɁA��ΓI�ȈႢ������Ƃ������Ȃ��B�܂��A�l�Ԃ�����������ς������Ƃ�Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��Ƃ����A�����w�I�A���邢�͈�w�I����������Ƃ��v���Ȃ��B�����A�܂��A�q�{�͑傫�Ȋ����ׂ�^���邩�狍���Ȃǂ̏���ʂ͌��炳���ׂ����낤���A����ނ�H�ׂ邱�Ƃ���؎~�߂āA�܂�A�C�m�����ɗ��邱�Ƃ���؎~�߂āA����ς��������ׂĐA�����̂��̂ɐ�ւ���ׂ����Ƃ����悤�ȁA�n������ی삷��ϓ_����̍���������Ƃ��v���Ȃ��B
���ǁA�ǂ̓�����H�ׂ邩�A�ǂ��H�ׂ邽�߂ɎE�����Ƃ����܂�Ȃ��ƍl���邩�́A�ϗ��w�A�Ƃ��Ɋ��ϗ��w�I�c�_�ɂ���Ăł͂Ȃ��A���̎Љ�̗��j�A�����I�w�i�ɂ���Č��܂邱�Ƃ��낤�B������{�ɂ����ẮA���̂Ƃ���A����قǑ傫�ȍ߈����������ƂȂ������E�����Ƃ��ł��邪�A�������A�M���ނ̓����ɂ��ẮA����ƈ�����������A�l����������l�������Ƃ������Ƃ͂͂����肵�Ă���Ǝv����B
�ނ�̢�l����ɂ��Ă��������l���悤�B�o�X�ނ�A���邢�̓w���u�i�ނ�Ȃǂł́A�ΏۂƂȂ鋛�́A�ނ������ƁA�������܂܌v�ʂ����ă����[�X����A�܂萅�ɖ߂��̂ł���A���̒ނ�̏ꍇ�̂悤�ɒނ��������l���Ƃ���̂ł͂Ȃ��A��������ނ�グ��܂ł͓��������A�H�ׂ邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B����j�Ɋ|���A�ނ�グ��v���Z�X�i�����Ēމʂ𑼎҂Ƌ������Ɓj�Ɋy���݂����o���B���ꂪ�ړI�ł���B
���́A�H�ׂ��Ȃ��������������鋛�ȊO�͂��ׂĊl���Ƃ��Ď����ċA��B���̒ނ�͊l���邱�Ƃ��ړI���B�Ƃ͂����A���݂͎������g�ŐH�ׂ邱�Ƃ���ȖړI�ɂ��Ēނ�̂ł͂Ȃ��B���łɏ��������A�R�O�N���O�A�����ɂ����Ƃ��ɍs�Ȃ����C�V�_�C�ނ���A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�Ɏn�߂��̂ł͂Ȃ����A�ނ����C�V�_�C�͐H�ׂ���Ƃ���͂��ׂĐH�ׂ��B�����āA�U�N���O�A���Q���암�A���쒬�̋����ɗ��đD�ނ���͂��߂�����̍��͖����̂悤�ɒނ�������H�ׂ��B����Q����T�͒��́u���D�����������v�Q��
�������A���ł́A�ނ������̂����A�����ŐH�ׂ�̂͂P���ɂ������Ȃ����낤�B�قƂ�ǂ͉Ƒ��ɐH�ׂ����邩�A�m�l�A�F�l�A�e�ʂɂ����邩�����Ă��炤�B�����Ă��炤�̂͐��v�̂��߂ł͂Ȃ��A�ނ�̊y���݂𑱂��鎑���̈ꕔ�ɏ[�Ă邽�߂ł���B�]���Č��݂̎��̒ނ�̖ړI�͂قڒނ邱�Ǝ��̂ɂ���Ƃ�������B�������A�ނ��������Ăѓ������Ă��Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��B
���́u�H�ׂȂ��i��������j�Ȃ�ނ�ȁv�Ƃ��A�u�P�ɏ��킹�ĕ�������Ƃ����ނ�͎ד����v�Ȃǂƌ����i�˒��j����͂Ȃ��B�m���Ɂu�V�ԁv�����̖ړI�ő��̐�����������͎̂c�����Ɗ�����l������Ǝv���B���͑Ώۂ��M���ނȂ�A���邢�͒��ނł��A�������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���B�������Q�[���E�t�B�b�V���O���֎~�����ׂ����Ƃ͎v��Ȃ��B
���͌��݁A���{�ɁA����ނ�͎̂c���������߂�ׂ����Ƃ��������ł���ʓI�Ȉӌ�������Ƃ͎v��Ȃ��B������A�ނ莩�̂̐������̂��߂̋c�_���K�v���Ƃ͎v��Ȃ��B�ނ�Ɋւ��đ����c�_���s�Ȃ��Ă���̂́A���������A�H�ׂ邱�Ƃ����R�ƍl���Ă���l�X�ƕ�����O��Ƃ���Q�[���E�t�B�b�V���O���D�ސl�X�Ƃ̊Ԃ̋c�_���炢���낤�B���̋c�_�́A�����l�߂�ƁA�V�т̂��߂ɋ��������邽��E�����肷�邱�Ƃ̐���̖��ɂȂ�B
�܂��A����́A�����������A�H�ׂ邽�߂ɒނ��Ă���̂ł���A�P�ɗV�тŒނ��Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ����O��ɗ����Ă���悤�Ɏv����B���̑O���邩��A�����ɑ��āA�V�Ԃ����ŁA�ނ�������H�ׂȂ��̂͊ԈႢ���Ƃ�����������̂��낤�B�������ނ��ĐH�ׂ�ɂ��Ă��A�����̕K�v����H�ׂ邽�߂ɒނ�Ƃ������ƂƁA�V�тŒނ邪�ނ������͐H�ׂ�Ƃ������Ƃ͈قȂ�ł��낤�B
�u�V�т̒ނ�v�͒�`���e�Ղł���B�܂��A�]�Ɋ����Ƃ��āA�����݂̂��߂ɍs����ނ�́A�����ŐH�ׂ悤���Ƒ���F�l�ɐH�ׂ����悤���A���ׂėV�т̒ނ�ł���B�����ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł���A�܂苛���w�����邾���̎����͂���̂ɁA�V�N�ł���Ƃ��A�����Ŕ����Ȃ����������ł���Ƃ��̗��R�A�����l�߂�O�����̂��߂ɍs���ނ�́A�ނ邱�Ƃ����H�ׂ邱�Ƃɏd�_���u����Ă���悤�ɂ��v���邪�A��͂�V�т̒ނ�ƍl������B�ނ�Ȃ��Ă��������������邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B
�ł́A���t�ł͂Ȃ��̂ɁA�����̕K�v����ނ�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤���B����ɂ����Ă͂قƂ�ǎ���������������Ƃ��ł��Ȃ����A��O�̓��{�ƁA���Ԃ��Ȃ�����̓��{�ɂ͂��̗�������������Ƃ��ł���B
��́A���Ԃ��Ȃ�����̍��m���ł̗�ŁA��ŐG�ꂽ�G���N���u�ҁw���M�ގ����x�̒��ō�Ƃ̐X���J������������^�E�݁E����Ƃ������M�ɓo�ꂷ��ނ̒ނ蒇�Ԃ̐X�c�Ƃ����l�̗�ŁA�X�c�́A�푈�̍������ɐ������̓y�n���A�Ƃ��Ȃ����A�m�ق̓X������Ă���������ɂ����Ȃꂽ�푈�]���҂ŁA�킸���Ȓ������s���āA�H�����߂ɁA���܂��ܒm�荇���Ɋ��߂��ċ����n�߂��Ƃ����B���t�ł͂Ȃ��̂Ɂu�H����߁v�ɍs�Ȃ����X�c�̒ނ�Ɋւ��Ắˑ�ꕔ�u�ނ�v��U�́u �J�̒��A���̒��̒ނ�A�����A�����̒ނ�v�̂Ȃ����u���̓}�]�q�X�g�Ȃ̂��v�̐߂ŏ����Ă���B������̗�́A���a�P�P�N�ɏo�ł��ꂽ�w���ӎ蒠�x�i�|�����[�j�Ƃ����{�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���҂̑��c�����F�Ƃ����l�́u�������v��E�ƂƂ��Ă������A���a�S�N�̑��t�A��Ƃ������āA��������A�헤�̍��i���̈��j�A�����i�������j�̒��O��ɁA�v�w�Ǝq�ǂ��T�l�ňڏZ�����B�F�l����Љ�ꂽ�l�𗊂�ɂ��āA�S���ߋ��ɉ��̂Ȃ��������̓y�n�ցA�u�u���W���ږ���낵���̊o��łł������v�̂ł���B
�u�����̕��@�́A�܂��V���͏]���̎G�������A�c��R���͋��l�ƐS�ɂ����߂āA�������āA����ɓw�͂��Ă����ĂU���S���A�₪�Čܕ��ܕ��̔������e�Ƃ����Ƃ���܂ł������邱�Ƃ��ł���A����Ŋ�]�̑����֓��B�B���ꂩ�珬����������āA�₨������́u�P�������v�̊l���ւƂ����l���ł������v�B�u�P���Ȑ����v�ɂ��Ă̐����͂Ȃ����A���������̑f�p�Ŏ��R�I�Ȑ������w���悤�ł���B��ɁA�O��Œނ�����ĕ�炷���ƂɌ��߂��Ƃ��A���̓��ɂ́u���Ȃ��ʎ��R�͂���A�w偂̎��̓͂��ʎ��R�͂���A�Y��������K�v�Ƃ��ʖL���Ȋy�y�͂���悤�Ȏv�������ꂽ�v�ƌ����Ă���B
�����ɗ��āA�ŏ��́u���炾���炵��n�������ɐ��ʂ��邱�Ƃ��̗v�v�ƁA�ߏ��̔_�Ƃ���P�z�̓c�M����āA���X�A�u���ߓ�����䂂������ĕ����ނ������v�B�v����ɂ���͒ނ肪�D���ŁA�����Łu�G���v��������炵�ɖ����ł����A�����n�тŒނ�����Ȃ����炻���ƍl�����̂��ł���B����͘I���⌤���̒ނ�̂悤�ɁA���͂��������Ԃ����āA�C���]���̂��߂��邢�́u���y�v�̂��߂ɍs���ނ�ł͂Ȃ��A�����̂V�������̎����ŏ[�Ă��c������͂��̎d���ł�����悤�ȁA���̋��l�ɂ���Đ����̗Ƃ邽�߂̒ނ�ł������B���̒ނ�́u�K�v����̒ނ�v�ƍl������B
���ۂɂ́A�ڏZ��Ԃ��Ȃ��A�Ȃ������̋r�C�������ē����̕a�@�ɓ��@���Â�����K�v��������Ȃǂ��āA�P�N���o���Ȃ������ɂ��́u�ږ��̊�Ă�---���܁v���A�����ɂ�������߂�B�Ȃ̑މ@��́A���C�̑��������n�т͋r�C�ɂ悭�Ȃ����߁A�����ɖ߂邱�Ƃ͂�����߂��B�������ߏ��ɎO��̏h���̒������Ƃ����l�����āA���̐l�̂Ăō��x�͎O��ɈڏZ���A�����̒r���Œނ�����ĕ�炷�̂ł���B���̑�c���̏ꍇ�ɂ́A�ނ�D���́u���}���`�V�Y���̉ߏ�v�i��c���j�������炵�����Ƃ����A�ނ͗V��ł���̂ł͂Ȃ������̂��߂ɒނ�����Ă���B�ނ��ނ�Ȃ���T�l�̎q�ǂ��ƍȂɐH�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���̂悤�Ȗ��C�ȃ��}���`�V�Y���ƈ�̂ɂȂ����u�����̕K�v�v����̒ނ���s���Ă���l�́A���݂̓��{�ł܂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���������āA���t�ł͂Ȃ��ނ�l�͂��ׂėV�тŒނ���s���Ă���ƍl������̂ł���B
�����ŁA���q�ׂ��H�ׂ�ނ�l�ःQ�[���E�t�B�b�V���O�ŕ�������ނ�l���A���҂Ƃ��V�тŒނ���s���Ă���̂ł��邪�A����͐H�ׂ邽�߂ɎE�����A�����͎E�����A����������Ƃ����Ƃ���ɗ��҂̈Ⴂ�����邱�ƂɂȂ�B
�ނ�������H�ׂ��ɕ��u���Ď��Ȃ��邱�ƂƁA�����A���ĐH�ׂ邱�ƂƂ��r����Ƃ��ɂ́A���炩�ɑO�҂͂悭�Ȃ��ƁA�����Ă��̐l�͎v�����낤�B�������A�ǂ��������E����̂ł���B���������āA�����ł́A�E�����ǂ����A���邢�͋ꂵ�܂����ɎE�����̂��ǂ����Ƃ����悤�ȁA�ʏ�A�����ϗ��ƌĂ��̈�Ŏ����ϓ_�Ƃ͕ʂ̊ϓ_����A�P���̔��f���s�Ȃ��Ă���B�����ł́A���p�ł�����̂͏\���ɗ��p���ׂ����A���͖��ʂɂ��ׂ��łȂ��Ƃ����A�����I�ϓ_�����f�̍����ɂȂ��Ă���B
�����ɂ��Ȃ����ƁA�Q��I�ł��邱�Ƃ́A��ʂ̃S�~�̔p���ƁA���������Ă܂����j��ƂȂ����Ă���B�����Ċ��j��͐�������̈��S�ɂ�����邱�Ƃł���B���������āA���Ƃ��A��Ƃ����j��I�s�����s�Ȃ��Ȃ�A�����͂���ɍR�c�����̍s�ׂ��������邱�Ƃ����߂邱�Ƃ͂ł���B�ł���Ƃ��������łȂ��������ׂ��ł��낤�B�܂��A�ނ��������h�̏�ɕ��u���đ��̒ނ�l�̖��f�ɂȂ�Ƃ����ꍇ�ɂ́A����𒍈ӂ���̂����R�ł��낤�B�������A��ʂɁA�ނ�������H�ׂ��Ɏ��Ȃ��邱�Ƃ͑��̐l�ɖ��f���Q���y�ڂ��s�ׂ��Ƃ͌����Ȃ��B�����āA�e�l�����Ȃ̏��L���i�ނ������͂��̐l�̂��̂��j���ǂ̂悤�ɏ������邩�͊e�l�̎��R�Ɉς˂���Ƃ������Ƃ͎��R��`�ɗ�����Љ�̈�ʓI�Ȍ����ł���A���҂��A���̐l�Ƃ�����ׂ��W�ɂ���ꍇ�ɂ́A�A�h�o�C�X������Ȃǂ̂��Ƃ͂��肦�Ă��A�Ԃ̑��l�����o�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�܂�A�ނ�������H�ׂ邩�H�ׂȂ����́A�e�l�ɂƂ��Ă̌����̖��ł���A���҂��֗^���ׂ����Ƃł͂Ȃ����A������������U�������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�u�H�ׂĂ�邱�Ƃ������ɂ��邱�Ƃ��v�Ȃǂƌ����l������B����͢���ʂɂ���̂͂悭�Ȃ���Ƃ������ƂƂ͏����Ⴄ�B���̎咣�ɂ͎��R�E�̐H���A���̎d�g�݂��n�߂Ƃ��鐶���Ԃ̑��݈ˑ��W�A���鐶���͑��̐����̖��ɗ����߂ɑ��݂��Ă���Ƃ����ϓ_���܂܂�Ă���B���R�̐ۗ��ɂ���āA���鐶���͑��̐����ɐH���邽�߂ɑ��݂��A�H����͓̂��R�ł���B�l�Ԃ�����⋍��H�����Ƃ́A�����̖{���̈Ӗ��A�����A�g�������������Ă�邱�ƁA�����d���A��ɂ��邱�Ƃł���A���R�@���Ɉӎ��I�ɏ]�����ƂƂ��āA���̍l���͐��F�����悤�Ɏv���邩������Ȃ��B
�����A����͐l�Ԃ������E�̒��_�ɗ����Ă��āA�H����S�z���Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��痈��A�����������킹�邱�Ƃł͂Ȃ��̂��B�l�Ԃ������E�̒��_�Ɉʒu����Ƃ����̂͊��Ⴂ�ł���B�l�Ԃ̓m�~��V���~�ɐH����B���邢�͊���ۂ⃔�B���X�ɂ���Ċ����B�l�Ԃ��A���R�E�̐H���H����W�A���p�����p�����W�̒��ɂ���B���̂��Ƃ܂�����ŁA���̐l�́A����ł��A���̎��R�̖@���ɐi��ŏ]�����Ƃ͐��������Ƃ��ƍl���A�̓��Ɋ������邱�Ƃ��������Ă��������͈��܂��A�m�~��V���~���̂ɂ��Ă���Ɏ����Đ����������邾�낤���B
�H�ׂ邱�Ƃɂ�苛�̖���D���Ă����āA����͖����ɂ��Ă��邩�炾�Ǝ咣������A���邢�́A�Ђǂ��ꍇ�ɂ́A��������S�đ�ɐH�ׂĂ�邱�Ƃ�����{���Ɉ����邱�ƂȂ̂��A�Ƃ��������l������̂����A����ɏo�Ă���T�ⓚ�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����A��A���A�������͂��炩�����Ƃ���Ӑ}�Ō�����̂łȂ��Ƃ���A�S���̓Ƃ�P����A��������Ȏv�����݂ł����Ȃ��B
�������ɂƂ��Ă͐����Ă��邱�Ƃ��P�ł���A���͐��̔ے�ł���B�����n�߂��爫�ł��葶�݂��ׂ����̂łȂ��Ɖ��肷��̂łȂ���A���ɂƂ��Ă��̔ے�ł��鎀�͈��ł���B�l�Ԃ͒N�ł������}���A���ł����̓����ł��A�͂܂��ĎE���ꂻ���ɂȂ�A�K���ɓ���悤�Ƃ���B���̒N�����m���Ă���P���Ȏ����𒊏ۓI�ɕ\���������̂�����͑P�Ŏ��͈��ł���B�����Ă�����̂��E�����Ƃ͈��ł��飂ł���B���̐����𗘗p���邱�ƁA�E�����Ƃ��A�l�ԂɂƂ��āA���Ȃ̐����ێ����A�܂��V�т��܂߂Ď��Ȃ̍K���傳���邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ������ł���ɂ���A���̂��Ƃ������ɂ��̗��p����E����鐶���̐����ɂ��邱�Ƃł�������A���̐����Ɉ���������Ƃł���ȂǂƂ������Ƃ́A�S�������Ȃ��B
��O�̓��{�ł͈�ʂɁA���邢�́A�s��サ�炭�̊ԎЉ�n�����������ɂ́A�ނ�͐����̈ꕔ�Ƃ��āA�����ɕK�v�ȍs�ׂƂ��čs�Ȃ��Ă������A���̂悤�Ȃ��̂��ƈ�ʂɍl�����Ă����B�����Đ��Ԃ̏펯�Ƃ��āA���͑�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒN�����l���Ă����B���̂悤�ȏ������ł́A�ނ肪�A�����Ίy���݂̂��߂ɁA���̎d�������ڂ��čs�Ȃ��邱�Ƃ��������ɂ��Ă��A��͂��ʘ_�Ƃ��Ģ�ނ�͐H�ׂ邽�߂ɍs�Ȃ���������Ƃ݂Ȃ���Ă����B�����āA���R�A�ނ������́A�ǂ�ȎG���ł��A��Ɏ����A���ĐH�ׂ����A�H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ������B
�ނ�͊y�����B�������ނ�̖ړI�͊y���ނ��ƁA�V�Ԃ��Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����l�����͂��̂悤�ȎЉ�ň�����l�X�������Ă���n�r�g�D�X�A�K���̒��Ŋl�����ꂽ���̂̌����A���l��ł���s�����K�肷�錴���A�����̈ꕔ�ł���B���̂悤�ȍl�����ɗ��l�X���炷��A�ނ�������H�ׂ��ɕ�������ނ�A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�����ނ邱�Ƃ�����ړI�Ƃ���ނ�͢�ד��ł��飁A�l�̓��ɔ�����s�ׂł�������悤�Ɍ�����B�������A����́A���Ă̎Љ�ň�����l�����̍l���ł����Ȃ��B
�L�ȎЉ�Ɉ炿�A�܂��A�������E�ƘJ���ɍS�����ꂽ�s���R�Ȏ��ԂƂ���ȊO�̎��R���ԁi�e���̍ٗʂɂ��������Ďg�����Ƃ̂ł��鎞�ԁj�ɋ�ʂ��ꂽ�����`�Ԃ���ʓI�ł���悤�ȎЉ�Ɉ�����l�́A�ʂȍl���������Ă���B�ނ�́A��������A���Ȃ��[�H�̂������̑����ɂ���K�v����s�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�K�v����s�Ȃ����Ԃ̂��邢�͏T���̎d�����������ꂽ��ŁA�V�тōs�Ȃ����̂��ƍl���Ă���B�V�тɂ́A����ނ�A�ނ�������H�ׂ�V�тƁA�H�ׂ��ɒނ邱�Ƃ������y���ޗV�т�����ƍl���Ă���B���݂̎Љ�ɂ����ẮA�ނ�͐����̕K�v����s�Ȃ��s�ׂł͂Ȃ��B�ނ�͗V�тł���B�ǂ̂悤�ȗV�ѕ������悤�ƁA�l�ɖ��f���|�������Q���y�ڂ����Ƃ��Ȃ������莩�R�ɍs�Ȃ��č\��Ȃ��̂��B
����ł́A���̂悤�Ȏ咣�͉\���낤���B�L���b�`��A���h������[�X�́A�����͂��Ă��E���Ȃ��Ƃ����_�ŁA���̐������ɂ��邱�Ƃł���B������A�ނ���A�H�ׂ邽�߂ɍs�Ȃ��ނ�A�E���ނ�͂�߂�ׂ��ŁA�ނ������͂��ׂĕ������ׂ����B���̂悤�Ȏ咣�͐������ƌ����邾�낤������͌����Ȃ��Ǝv���B
���̂悤�Ȏ咣�́A���������邱�Ƃ͍\��Ȃ��A�������Ƃł͂Ȃ����A�E�����Ƃ͈������Ƃ��ƌ������ƂƓ����ł���B�������A���̂悤�ȋ�ʂ͂ł��Ȃ��B�����A�Q���邱�Ƃ̍ő�̍s�ׂ��E�����Ƃł���A���������邱�Ƃ̋Ɍ����E�����Ƃł���B�����Đ����������A�Q���邱�Ƃ����ł��邩��A���̋Ɍ��ł���E�Q�͈��Ȃ̂ł���A�E�Q���������ł���A�E�Q�Ɏ���Ȃ����Q�͈��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���݂̓��{�̏펯�ł́A���͐H�ׂĂ悢���A���������ĎE���Ă��\��Ȃ������ł���B�܂��A�V�т̒ނ���L���F�߂��Ă���B���݂̓��{�̏펯�ł́A�ނ��āi�E���āj�����ŐH�ׂ�A���邢�͐l�ɂ����邱�Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A�܂��Q�[���E�t�B�b�V���O�ŏ����i�ĕ������j��̂��������Ƃł͂Ȃ��ƍl�����Ă���B�i���̏펯���������\�����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A�����͂Ȃ����낤�B�j
�����A�����A�����E�����邱�Ƃ��A�l�Ԃ��E�����邱�Ƃ��邢�͐l�Ԃ̒��ԥ�F�B�ƍl�����Ă���y�b�g�������E�����邱�ƂƓ��l�ɁA�����ƍl�����Ă���Ƃ���A�Q�[���E�t�B�b�V���O���A����ȊO�̒ނ�������悤�Ɉ��ł���B
�Y�@�ɂ����Ă͏��Q�߂͎E�l�߂����Y�͌y���B�������A���̂��ƂƋ��̎E����ޔ�I�ɍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͎E�����Ƃ������邱�Ƃ��Ƃ��Ɉ��ł���A�ւ����Ă���̂ł���B���̏�ŌY�̌y�d������B�������A���̏ꍇ�ɂ́A���������E���͋ւ����Ă��Ȃ��B�ւ����Ă��Ȃ��A�܂舫�łȂ����ނ̍s�ׁA�����E�����ƂƏ����邱�Ƃ̈��̓x��������邱�Ƃ��A�ǂ��炪��舫�������������Ƃ��ł��Ȃ��B����̒ނ�͑����̒ނ�����A��舫�����Ȃ����A���悭���Ȃ��B���������Ēނ�������H�ׂ�ނ�����L���b�`�E�A���h�E�����[�X���s���Q�[���t�B�b�V���O�̕����u���ǂ��v�ނ�ł���A���߂���ׂ����A�Ƃ����咣�͊Ԉ���Ă���B
�����ϗ��Ƃ����w�╪�삪����B���̒��ŕ��q�̒{���͎E���āi�H�ׂāj�悢���A�N�W���͎E���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������������A�����Ȃ鐶���ɢ���������F�߂�ׂ����Ƃ����A�ꌩ�̒ʂ����A�������������Ƃ͎��͎v��Ȃ��A�������̐������Ă̓N�w�҂ɂ���Ē�o����Ă���B���������ҐV�Łw���Ɨϗ��x�i�L��t�A�Q�O�O�T�N�j�A��U�́A�ɐ��c�N�����������_��ł����̐��̏Љ�Ȃ���Ă���B��W�͢���R�ی�\�ǂ�Ȏ��R�Ƃǂ�ȎЉ�����Ƃ߂�̂���ł͎��������������ւ̔��_���s���Ă���B�܂������ҁw�ϗ��͂�b����x�i���w�فA�Q�O�O�R�N�jPART2�Ŏ����S����������ƕߌ~�֎~�͐�������A���łɕm���鐶�������g���l�Ԃ����i�ł��邩��ւ̓����A����ɐٍe�u���R�ی�E�G�R�t�@�V�Y���E�Љ�i���_�\�L�����R�b�g�̊��ϗ��v�z�̌����v�A��{���j�A�����v��Y�ҁw���p�ϗ��w�̓]���x�i�i�J�j�V���o�ŁA�Q�O�O�O�N�j���Q�Ƃ��Ă������������B
���āA�ނ�́A���R�̒��Ŋl���邱�Ƃ��y�����Ɗ�����l�ɂ���čD�܂�邾�낤�B�ނ������͖̂���������A�ʔ������炾�Ƃ������Ƃ͊m���ł���A���̖ʔ����A���͂͂��Ă݂����B�����A�Ȃ��A�ނ������̂��Ɩ��ꂽ�Ƃ��ɁA�������̐��������邪�A�����ɂȂ�Ȃ����̂�����B�������܂��ނ��Ă��������B
��ł́A���푽�l�Ȓނ肪���邱�ƁA���邢�́A���푽�l�ȖړI�Œނ肪�s���Ă��邱�Ƃ������B�u�ǂ����Ēނ������̂��v�Ƃ����₢�ɑ��Ă͑��푽�l�ȓ������\���Ƃ������Ƃ��ł���B���́A�ɂ�������炸�A�ނ�ɋ��ʂ���ʔ�����������悤�Ƃ��Ă���B
�����A�ނ�͐������������ߎE�Q����s�ׂł���ƍl����l�́i���Ă��������Ȃ��Ǝ��͐M���邪�j�Ȃ�����Ȗ�ȍs�ׂ��s���̂��Ɩ₤���낤�B�₢�̎�|�͈قȂ邪�A���̏ꍇ�ɂ��u�ǂ����Ēނ������̂��v�̐��������߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�ȉ��ł́A�ѓc�̒����̒��ŁA�Љ��A���p����Ă���A�C�M���X�l�������s�Ȃ����c�_���ޗ��ɂ��āA�u�ނ�����闝�R�v�ɂ��Č������Ă݂�B
�P�W�S�O�N���ł́w�T�P�ƃ}�X�̐�ނ�x�̒��҂̃����K�[�́u���N�ɂ悢�Ƃ��A�����I���ґz�̎�i�ł���Ƃ��A�������c���ɏo����߂ł���Ƃ��A���I��������N���邽�߂ł���Ƃ��Ƃ������R�t���Ƃ���ɑ��邳�܂��܂Ȕ��_���Љ�v���邱�ƁA�ނ�ɂ��Ă��̂悤�ȁu�u�߂����邱�Ƃ����n���炵���̂ł���A�����̒��Ɏc�����ŗǂ̕����A���Ȃ킿�q�ǂ��̕������̂̂܂܂ɂ���������̂��ނ�ł���Əq�ׁv�Ă���B
�����A�����K�[�̐������ǂ����Đl�͒ނ������̂��Ƃ����₢�ɑ��铚���ł���Ƃ���A�u�l�̒��Ɏc���Ă���q�ǂ��̕������ނ�����߂�����v�̂��Ƃ��������͂قƂ�LjӖ��̂Ȃ����̂ł���B�q�ǂ��̍��ɖ����ɂȂ�V�т͂��낢�날��B�{�[���V�сA���l�`�V�сA�썑�̊C�ӂȂ琅�V�сA�k���Ȃ�X�L�[�A�X�P�[�g�B����炪��l�ɂȂ��Ă���̃X�|�[�c���̑I���ɑ傢�ɉe�����y�ڂ����ƍl���邱�Ƃ͏\���ɉ\���B���Ƃ��{�[���V�т��T�b�J�[�ɁA���l�`�V�т͉����ɁA���V�т̓X�L���[�o�_�C�r���O�ɁA�X�L�[�A�X�P�[�g�͖{�i�I�ȃX�L�[�A�X�P�[�g�ɁB�����K�[���̐����ł́A����炷�ׂẴX�|�[�c���u���̐l�̒��Ɏc���Ă���q�ǂ��̕��������̃X�|�[�c�����߂�����̂��v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�q�ǂ��̎��ɖ����ɂȂ����V�т��A�������đ�l�ɂȂ��Ă�������̂܂ܑ����Ă��邩���邢�͂���Ɠ���̃X�|�[�c�����s���Ă���l����ł͂Ȃ����낤���A���̂悤�ȃP�[�X���������Ƃ��Ă��A�������������ł́A���ꂼ��̃X�|�[�c���̂����Ă��邳�܂��܂Ȗ��͂͂��A�𖾂��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ͖��炩���낤�B
�C�M���X�ł͂P�W���I���ɁA������`�҂����ɂ�铮������^���������Ȃ���悤�ɂȂ����B�ނ肾���ł͂Ȃ����A�ނ�͐��������E���B�����̉p���ł͢�V�тŐ��������E�����Ƃ͎c���ȍs�ׂ���藧�Ă邱�ƂɂȂ飂Ƃ����Љ�I��������
���i��Ƃł������X�N���[�v�̂P�W�S�R�N�̒����w�c�E�B�[�h��ł̃T�P�ނ�̓���x�́A��O�X�|�[�c�Ƃ��Ă̐ϋɓI�y�����������̂ŁA�ނ�ɑ�����ɔ��_���邱�Ƃڂ̖ړI�ɂ��ď����ꂽ���̂ł͂Ȃ��悤���B�������A�ނ��ނ���u�������v����K�v�������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B
�u�E�H���g���̎��ォ�猻�݂܂ŁA�ނ�ɂ��ď�������Ƃ͒N�����A�ނ�̊y���݂𐳓������邽�߂ɂȂɂ������̓w�͂����Ă����Ǝv���܂��B---�������ނ�ɂ��̂悤�Ȑ��������K�v�ł��傤���B---�����ނ���ɏ]�킹�悤�Ƃ����̂ł���A���͍��f�������ł��B����́A�{�\�ł���A��M�ł���A���Ƃ��Ɛ����̂��߂ɐl�Ԃɗ^����ꂽ�͋������̂Ȃ̂ł��B---�v
���́A���A�u�ނ�𐳓����v����K�v������ƍl���ď����Ă���̂ł͂Ȃ����A���ɁA�����������߂�ꂽ�Ɖ��肵�Ă݂�B�X�N���[�v�́A�ނ�́u�{�\�ł���A��M�ł���A���Ƃ��Ɛ����̂��߂ɐl�Ԃɗ^����ꂽ�͋������́v���Əq�ׂ邱�ƂŐ������ł���ƍl���Ă���B���邢�́A������A�ނ�͐���������K�v���Ȃ��Ƃ������Ƃ̗��R�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B
�u���Ƃ��Ɛ����̂��߂ɗ^����ꂽ�͋������́v�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤���B�ނ�́A�ŏ��́A�P�Ȃ�V�сA�y���݂Ƃ��čs��ꂽ���̂łȂ��A�����̂��߁A�H�Ƃ邽�߂ɂ����Ȃ�ꂽ���R�Ƃ̓����Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��낤�B����͍m��ł���B�������A�u���Ƃ��Ɓv�����ł������ɂ��Ă��A���A�P�X���I�p���̉�Ƃ��A���Ƃ��R�[�X�E�t�B�b�V���O�Ƃ��ĐH�ׂ邽�߂ɒނ��Ă���̂��Ƃ��Ă��A�T�P�ނ���u�����v�̂��߂̐H�����i�Ƃ��čs�Ȃ��Ă���̂łȂ����Ƃ͊m��������A�����ނ肪�����Ă���Ƃ���A�u���Ƃ��Ɓv�������o���Ă��A�������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�u��M�v�Ƃ͉����B�ނ������l�X�͒ނ�ɋ�����M��������B���Ԃ����낤�B�������A��M��������y���݂�X�|�[�c�͒ނ肾���ł͂Ȃ��B�S���t���A�I�[�g�o�C�̔������A�؎�W�߂��A�����̏W���A����Ă���l�̑����͏�M�������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�ʂ̌��t�Ō����A�����̊y���݁A�X�|�[�c�́A���ɖʔ����Ƃ������Ƃł���B�����A���̃X�|�[�c�ɉ�����肪�����Ĕ���Ă���Ƃ���A�����Ď��ہA�V�тŐ��������E���͎̂c�����Ƃ����悤�Ȕ�����Ƃ���A�u���ꂪ���ɖʔ�������v�ƌ����Ă��A���ɂ��Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ��A�l�̐������s���Ă���ꏊ�̋߂��ł̃I�[�g�o�C�̔����͑����ɂ���Đl�X�̐�����W�Q���邱�Ƃ͖��炩���B�܂��S���t��̌��݂ƈێ��Ǘ��ɂ͎��R�j��Ɗ��������Ƃ�����肪����B�i���Ƃ��A�J�R�S�Y�w���{�S���t�\������X�A������鐅�\�x�A���{����ҘA���w�S���t��͂���Ȃ��x�ȂǎQ�ƁB�����q�v�w�X�|�[�c���[���̎Љ�w�v�i�����V���ЁA�P�X�X�P�j�́A�X�|�[�c���D�҂̊ϓ_����S���t�ꌚ�݂̖��_���P�O�y�[�W�ɂ킽���Ę_���Ă���A�Q�l�ɂȂ�B�j����͔����ɏ�M�������飁A�u���̓S���t�����ɖʔ����v�Ƃ����Ă��A���E�ᔻ�ɓ��������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�X�N���[�v�͒ނ�͢�{�\����Ƃ������Ă���B�ނ͓����̃C�M���X�ɂ������ނ�ɑ�����^��ᔻ�ɉ����A�ނ�𐳓������邽�߂ɖ{�\�������o���Ă���ƍl������̂����A���݂̓��{�ł́A�ނ�ɑ�����̂悤�Ȃ��̂́A�ނ��������}�i�[�̈����ނ�l���܂܂��邱�ƂƁA�O����ł���u���b�N�E�o�X�Ȃǂ�����Ɏ������܂�ݗ���̋��ނ���������A���邢�͌Ȃǂ��s�S���҂ɂ�莄��������Ă��邱�Ƃɂ��Ă̎w�E�Ȃǂ�ʂƂ���A�قƂ�ǂȂ��ƌ����Ă悢�Ǝv����B�����A�������̂��߂ɂł͂Ȃ����A�ނ�̉��y��������悤�Ƃ��āA�����Ζ{�\�������o�����B
��Ō����O�Y�G���́u�ނ�V���v�Ƃ������ł́A�u�C�ނ�ɂ����ẮA�C�̍K�����߂�l�Ԃ̖{�\�����@�Ƃ��Ă���A���������S�A----��������̂̐����̖���������v�ƌ����Ă����B
�܂��剺�F�Ɏ��i1896�|1966�j�͖{�Ƃ͐��������Ƃł��������A���̋L���ł́A���Ăm�g�j���W�I�̢��\�̔ࣂ���b�̐�ǂ��炩�̃��M�����[�o���҂ł������B�ނ́A�u�ڂ��͌��n�l�v�i�w�ނ�t�̂�����x���W�� ���{�̒ނ蕶�w�U�� ��i�ЁA1995 �j�Ƃ������M�ŁA�u�Ȃ��ނ��ʔ������ƕ������ƌ��n�l�̎�{�\���c���Ă��邩�炾�A�Ƃł�����������ق��Ȃ��B�܂�A�ڂ��́A�r�����n�l�I�ł���B-----���n�l�ł���ڂ��́A���n�l�ł���؋��ɂ́A���㕶���̓��Y����~�����Ǝv��Ȃ��B�p���ւ��s�������Ȃ��B�悢�J������悢���v�A�悢���N�M�ł���Ƃ��ɗ~�����Ƃ͎v��Ȃ��B�ق����̂́A�悭�ނ��A�Â��ȁA�����đ���̂����삾�����v�ƌ����Ă���B�ނ́u���܂�������ア�v�Ƒ��̂Ƃ���ŏ����Ă���B
���������{�\���������Ƃ��Ă���B���͖���40�N����c��w�p���ȑ��ƁA�����������珺�a�����ɂ����Ă̎��R��`��ƂƂ��Ēm���Ă���l���ł���B����́w�ނ肴��܂��x�i1935�N�A���a10�N���j��4�э\���ŁA���сu�ނ�̕����v�ɂ͒ނ�⋙�ɂ��ď����Ă���Í������̕�������̕��͂��W�߂��Ă���B���сu�ނ�̓N���v�Ől�͂Ȃ��ނ�����邩�Ȃǂ̋c�_���Ȃ���A��O�сu�ނ�̎��ہv�͒ނ���A�ނ�a�Ȃǂɂ��ď�����A��l�сu�ނ�̐��M�v�ɂ͂P�W�҂قǂ̐��M���ڂ��Ă���B�ȏ�͊ێR�M�w�ނ�̕������x�̏Љ�ɂ��B
�����ǂ̂́w�ނ�ЂƋx�i���W���@���{�̒ނ蕶�w���P�D�j�Łw�ނ肴��܂��x���сu�ނ�̓N���v���Ę^�������̂ł���B���́u���Ԃ������A���܂��܂ȏ��������A�܂��͊C�̌����`���ċ���ނ낤�Ƃ���A���̒ނ�̎�A�E�Ƃł��Ȃ��̂ɋ���߂炦�悤�Ƃ����~�]�̌����͉����v�Ɩ₤�āA�H���A�ނ�D���ɂȂ鎖��A�����́u�����I�A�ӎ��I�Ȃ��̂łȂ�����I�A�ӗ~�I�������͖{�\�I�Ȃ��̂ł��낤�v�B�����A�ނ肪�{�\�I�A���邢�͖{�\�ɂ����Ƃ��߂����̂ƍl���闝�R�͖��C�Ȏ����܂����m�Ȗ�ؐl�ɋ���������Ă��邩�����ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̌��n����̐�����i�̂����Ƃ��d�v�Ȃ��̂̈���痈�Ă��邩��ł���B
�u�����������͐l�Ԃ̖{�\�͓�A���ȕۑ��Ǝ푰�ۑ��̖{�\�B���ȕۑ��{�\�ɑ�����ƌ������Ƃ́A�E���Ƃ̏ꍇ�ɂ͂҂����蓖�Ă͂܂邪�A�V���Ƃɂ͊ԉ����悤�ȋC������B�����H���悤�Ƃ���{�\�Ƃ��������łȂ��A�푰�{�\�k�܂萫�~�l���W���Ă���̂ł͂Ȃ����v�ƌ����B
���͓��y�ƌ����قǂ̂��̂͏��Ȃ��������A�u�Â�ق��Łv�A�u���w�����ŁA���͌�������͋|�������B�O�Ԗڂ��ނ肾�v�Ƃ����B�ނɂ��ƁA���~�����s�ׂ��u���s�Ɉڂ��Ƃ��ɂ͓D�܂Ԃ�ɂ��Ȃ�A���܂Ԃ�ɂ��A�����Ɖ������̂ɂ��Ȃ�v�B�����āu�l���̌����͉��킢�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̌����ɑς���Ȃ����̂��A�����A�|�p��A��y�ɓ���A���ɂ����炤�v�B�ނ́A�u���w�͐��~�A���Ȃ킿�푰�{�\�̕ϑԁk�ό`�l���Ƒ�������l���Ă����B�ނ����������Ȃ����v�Ƃ����B�ނ́A��������������Ƃ��A���ƈ��������Ƃ��̉������A�u�㓪���ɁA�����łȂ�����Ŋ�����B����͐��I�����Ǝ��Ă���v�ƌ����B�������́u�D�܂Ԃ�v�ɂȂ邱�Ƃ������āA���~�������������ʁA���w�ƒނ���s�����ƂɂȂ����̂�������Ȃ��B
�w�v�z�̉Ȋw�x�Ƃ����G���̕ҏW�҂��������Ƃ�����A�܂��E�H���g���́w�ދ���S�x�̖�҂ł���A�X�G�l�́A�ގt���C�֗U�����͓̂ꕶ�l�����ւ̋��D�ƌ��Ă���Ƃ����B�ނ͒ނ���Ƃ����āA�u�ڂ��̒��̌Ñ�l�@���Ă���----�B�l�Ԃ̖{���̎p�̓P�_���m�ł���Ǝv���v�Əq�ׂĂ���Ƃ����B�i�����ˈ�u�ދ��_�|���Ԃƌ�y�\�v�A�����ҁw�����y�̍\���x�A���a�S�W�N�A���a���[�j
�܂��A�X�́w���{��S�ȑS���x�i���w�فA���a�U�Q�N�i�P�X�W�V�j�j�̔ނ����M�����u�ނ�v�̍��ڂł́A�u�j���̂ق����������ނ���D�ނ̂́A�j�����A���h���Q���Ƃ���j���z�������̕����A�h���i�����i���t�玿�z�������j�̕���ɂ����āA���������邩��ł���B�ǂ���̕������A��{�\�A�U���{�\��������v�Əq�ׁA�ނ���u��{�\�v�Ɋ�Â����́A�������A��{�\�ɂ͐���������A�ނ�͒j���ɂ���āA���D�܂��ƌ����B�����Ɋւ��Ă͂��Ƃōēx�G���B
�X�͢�ւ畩�̐��ԣ�i�������M���S�w�ށx�j�Ƃ������M�̒��ł́A�u����̂ւ畩�ނ͎�Ɏ����Q�[���ɂȂ��Ă���B���q�k���l�̑O�G��́A�˂炢���߂Ē��̗��̐Â܂�̂�҂��Ă���n���^�[�Ɠ����S�ۂ�^����B���́A�˂炢�̌����ɓ����Ă��x�����ď������Î~���Ȃ��B�S�̏L���A�l�Ԃ̏L���A�Ζ�̏L�������̒��ӗ͂����߂邩��B��Ƃ͈������ɓ��Ă��l�����w�ɗ͂����߂��܂܁A������������炵�ă`�����X��҂B���q�̑O�G�ꂪ�u�ԁA�킸���Ɏ~�܂�A�ق�̐��~�������A���������ƒ��ށB�u���[�L�̌������d�ʊ��̂��铖����ł���B���Ƃ̃T�I�K��������߂��E�肪�O���ɂ����Ɠ˂��o�����B���̊��G�̓n���^�[�����������Ђ�����Ƃ܂������������Ă���B----�v�ƌ����B
�X�́A�����������Ƃ�����A�w���u�i�ނ�Əe���g������ɋ��ʂ���A�ْ��A���������o�����̂�������Ȃ��B�����āA�n�C�e�N�f�ނɂ��ދ���g���A���̃G�T���H�v����A�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌ����錻��̃w���u�i�ނ�̖ʔ������A�u��v���L�[���[�h�ɂ��āA�l�ނ̑c��́u��s���v�ƌ��т��āu�A�z�v�����̂�������Ȃ��B
�����A�ނ�ɂ����鍇�킹�ْ̋����A�e�˂���Ƃ��̈������������u�ԂƏd�ˍ��킹�邱�ƂɕK�R���͂Ȃ��B���Ƃ��A�����������Ƃ͂Ȃ��싅��M�S�ɂ���Ă���l�́A�R�{�[���Q�X�g���C�N�̂��ƁA����̓������ω�����ł��Ԃ��ׂ��A�_���ς܂��ăo�b�g��U�낤�Ƃ���u�Ԃ��v���`����������Ȃ��B�܂��A����̒Z�������ɂ����ăX�^�[�g�̍��}��҂����i�[�����A�`�[���ōs���X�J�C�_�C�r���O�Ŕ�s�@�����яo���^�C�~���O���v��_�C�o�[�����Ȃǂ������悤�ɋْ���������͂����B������A�ނ�̍��킹������������ْ������X�G�l�ɂ͏e���̏u�Ԃ�A�z�������ɂ���A�l�X�ɉ\�ȘA�z��1�ɉ߂������Ƃ̌��т�����ɍ����t������̂ł͂Ȃ��B
�قƂ�ǂ̐l�́A�����Ƃ��Ă̊�{�I�ȗ~���̎����ɂ͉���������悤�ɂȂ��Ă���B���n�l�ł���A����l�ł���A�قƂ�ǂ̐l�ɂƂ��āA�����͉��ł���i���͋��|�ł���A��ł���j�A�H�����ł���A�Z�b�N�X�����ł��낤�B�����邱�Ƃ���ɂɂȂ�A�H�ׂ����Ȃ��Ȃ�A�Z�b�N�X�������Ƃ���A��ʓI�ɂ́A�S�g�ɉ��炩�̕s�����N�����Ă��邽�߂��ƍl���Ă������낤�B�A���X�g�e���[�X���w�������x�̂Ȃ��Ő��B�ƐH�̒Nj��Ɋւ��Č��u�{���ɓK�������Ƃ͉����A���ׂĂ̓����͖{���ɓK�������y�����߂�v�ƌ����Ă���i�T�W�XA�j���Ƃ́A�l�Ԃɂ����Ă͂܂�B
�ނ肪���ł���A�y�����̂́A�������邢�͓����Ƃ��Ă̊�{�I�ȗ~����������Ȃ̂��낤���B��{�I�ȗ~���͖{�\�Ƃ����Ă����̂��낤���B���������{�\�Ƃ͂Ȃ�ł��낤���B�A���X�g�e���[�X�̂����{���Ƃ͖{���I�Ȑ���������Ƃ����Ӗ��ł���A���܂����Œ�I�ȍs���p�^�[�����Ӗ�����{�\�̂��Ƃł͂Ȃ��B
�����ł́A�{�\�Ƃ́u�������O�͂̕ω��ɑ��čs���A�����I�ł��̎�ɓ��L�Ȕ����`���v�ŁA�{�\�I�Ƃ́u�{�\�ɂ���đ̂⊴���������邳�܁v�Ƃ���i�w�L�����x��S�Łj�B�܂��A����������܂�Ȃ���ɂ����Ă���\�͂ŁA�o����w�K�ɂ�炸�Ɋ��ɏ������̂���ю�̈ێ�������B���߂��V�I�X����ŁA�{�\�I�Ƃ́u�ӎv���������{�\�ɂ���ē��������l�v�Ƃ���i�w�L���сx��T�Łj�B���́w�L���сx�̐����̂ق������K���Ǝv���B
�l�Ԃ͑��̓����ƈقȂ�A�o����w�K�Ɋ�Â��āA�܂��m�I�ȓ��@�Ɋ�Â��čs�����邱�Ƃ������B�������A�l�Ԃɂ����̓������l�A�����{�\��Z�b�N�X�̖{�\������Ƃ������B���܂ꂽ����̐l�Ԃ̐Ԃ�V�́A�������Ȃ��Ă��A���̓����Ɠ��l�A��{�\�I�ɣ��e�̓��[�����킦�A�z�����Ƃ��ł���B�������A�l�Ԃ̎q�ǂ��́A����ȊO�ɂ͑��҂��狳�����邱�ƂȂ��ɂ͂Ȃɂ��ł��Ȃ��Ƃ����B�T�̒��ň���������͎l����ő����������Ƃ����Ă���B�����ĕ������Ƃł����A�������A�K��Ȃ�����܂��ł���悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B�l�Ԃ͌��t��b���\�͂������Ă��邪�A�i���Ƃ��Α��̐l�Ԃ���u������Ĉ炿�j�������Ȃ���A���t��b����悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�����A���X�͓y���@���Ė̎��߂�s�����s�����A���̒��ԂƐ藣����Ĉ�Ă�ꂽ�̂ɂ����Ă��A�����i�K�̂��ꂼ��̎����ɂȂ�ƁA������ƍs�Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�i�˒��j�B���̓����ł́A���̎�ɓ��L�̑����̕��G�ȍs�����o����w�K�ɂ�炸�ɍs�����Ƃ��ł���B��`�ɂ���Ă��̍s���l�����v���O��������Ă��邽�߂ł���B�{�\�s���Ƃ͂��̂悤�Ȉ�`�I�Ƀv���O�������ꂽ�s���p�^�[���̂��Ƃł���B
---------------------------
�i���j���X�͖̎����A�a�s���ɔ����Ēn�ʂɌ����@���Ē����邪�A�����ł́A�̎����o���ł��Ȃ��悤�ɉt�̂̉a�ň�āA�����̕K�v���Ȃ��悤�ɉa����ɑ�ʂɗ^���A�����@��Ȃ��悤�ɏ��͌ł��Ƃ���Ŏ��炵���B�������A���X�͍ŏ��ɖ̎��ƒn�ʂ��݂��Ƃ��ɁA��͂茊���@���Ă���߂��B����͐����I�ȍs���ŁA�{�\�ƌĂԂ��Ƃ��ł���B�X���[�^�[�w�����s���w����x�����q����S���_��A��g���X�A�P�X�W�W
--------------------------
�����̍s���l�����������Ă����j�D���[�����c���͂��߂Ƃ���w�҂����́A�P�X�R�O�N��ɏڂ��������E�ώ@���s���A�{�\�Ȃ����Փ��s���ɂ��Đ���ɘ_�����s�����B
���[�����c�͓����̂����܂��Ȣ�{�\��Ƃ����T�O��ᔻ���A���������悤�Ƃ����B�u�����I�ł��������܂�Ȃ���ɍ��ړI�I�ȍs���l�������݂���Ƃ������Ǝ��̂́A���łɒ����ȗ��m���Ă����v�B����́u�����R�I�v���v�Ƃ���Ă���B����́A�����́u����̍s���l���A���炩�ɈӖ�������A��ێ��̖ړI�ɂ��Ȃ��Ă���̂����A���̍��ړI���������Ɏ��g�̑̌�����m���Ă��闹���@�\�Ɋ�Â��Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȍs���l���ɏo��ƁA��ɂ��݂̂��������̐����Ɏ����o�����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B
�ނ�����ɑ����Ē�o�����T�O���܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B�{�\�͓��������܂�������Ă�����̂ŁA�O���̎h���ɔ������āA����L�̌��܂����`�ł̉^���ɂ��A��ړI��i�����A�U���A�A�a�Ȃǁj��B������s���l���ł���B�u�d�������s���l���v�����A�p�u���t�Ȃǂɂ�茤�����ꂽ�@�B�I�Ȕ��ˉߒ��Ƃ͈قȂ���̂ŁA�h���ɑ��锽�������������獂�܂��Ă���u�������v�ɂ����̂ł���B�ڂ����Љ�͔����邪�A���̎����̓����s���w�҂����́A�{�\�Ƃ���ȊO�̔\�́A�w�K�\�́A�m�I���@�\�͂Ȃǂ��͂�����ƒ�`���A�����̋�ʂƘA�ւ𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ����B
���[�����c�̒��ނ̖{�\�s���Ɋւ���_�������߂��w�����s���w�\�T�x�̌����͂P�X�U�T�N�ɏo�ł���Ă���B�����q���ɂ��M�ł̏o�ł��V�V�N�ł���B�����q���I�W�Ȃǂɂ��ƁA�U�O�N��㔼�ȍ~�A�����s���ɂ��āA�]���Ė{�\�ɂ��Ă�����ɘ_�����A�G�\���W�[������s���w�̗����͂W�O�N��܂ő������悤���B
�����̂P�X�V�P�N�ɏ����ꂽ�u�{�\�Ƒ㗝�{�\�̊ԁv�i���I�W�u�� �����_���n�E�X�u�k�ЁA2007�N�B������1966�N �j�Ƃ������ł́A�{�\�Ƃ������t�̒�`�͑�ϓ�����A�{�\�͏Փ��Ƃ͈قȂ��āA���ۂɂ����ꂽ�s���ɂ��ėp������ׂ����Ƃł���B�s���͏Փ��������Ă͂��߂ċN������̂�����A�s���ƏՓ���藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��B����ǁA���Ƃ��ΐ��Փ�������Α��A���s�����N���邩�Ƃ����A�����ł͂Ȃ��B������ׂ��Ώۂ��甭����A������ׂ��h�����K�v�ł���B�h���i�̋��x�Ǝ�ށj�E�����[�T�[�k���l�A����ɐ��̏o����̌`�ɂ��s���̌^�����܂�B�����ł͎��̌^�͈�`�ɂ���Č��܂��Ă���B���̏ꍇ�A�����{�\���Ƃ����B
�����́w�����ɂƂ��ĎЉ�Ƃ͉����x���I�W�U���ł́A�}���O�[�X�͓Ŏւ̓łɑ���Ɖu�������Ă��Ȃ��B�I�݂ȍU���ɂ���Ď����͙��܂ꂸ�ɁA�Ŏւ���I�ɑ����ĐH�����Ƃ��ł���{�\�s����L����B����Ƃ����铮���ɑ���U���@��{�\�I�ɐg�ɂ��Ă���ȂǂƂ������Ƃ͂��肦���A�{�\�s���͕K�R�I�ɓ���I�ł���B
�����A�l�ނ͂��̒a���̎�����A���̐��Ƃł��Ȃ������B���鎞�̓��M���E���P���A�쐶�E�}���P���A�Â��̓}�����X��A�ѐ[�T�C�܂ŏP���ĐH���ɂ����B����瓮���ɑ���{�\�I�ȍU�����@��g�ɒ����Ă��Ȃ����������l�ނɂ͂����炭�]���҂����������ł��낤�B�l�Ԃɂ�����{�\�̌��@�͎��ɋ����ׂ����̂ł���B���{�\�Ƃ��A����𑽏����܂������푰�ێ��̖{�\�Ƃ��������̂́A�l�ԂƂ��ɒj�ɂ͂��Ȃ炸���Ȃ���Ă�����̂ƁA��������v������ł���B�����A����͂ǂ������S�ɊԈ���Ă���炵���B�l�Ԃ͐��Փ������������Ă���̂ł����āA����������߂̍s����l�Ԃ̖{�\�͒m��Ȃ��̂��B�l�Ԃ͂�������炩�̕��@�Ŋw�Ԃ̂ł���B���̂悤�ɓ����͏q�ׂĂ���B
�����̕�����A�����s���w�Ŏg���Ă����u�{�\�v�̈Ӗ���������A�܂����̈Ӗ��ɂ����Ă͐l�Ԃɂ́A����H�̂悤�Ȃ����Ƃ���{�I�~���Ǝv������̂��܂߁A�u�{�\�v�͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��m����B�l�Ԃɂ���̂͐H���U���́u�Փ��v�����ł���B�{�\�s���͊w�K��A�v�l�Ȃ��ōs�����Ƃ��ł���B�����p���āA���̎g�������}�X�^�[���čs���K�v�̂���悤�ȍs���́A�{�\�s���ł͂��肦�Ȃ��B�����l�Ԃ�����ߊl���悤�Ƃ���{�\�������Ă�����A���ڂ�b�R�̂悤�ɁA���̒��ɔ�э���ŁA��ŕ߂܂��悤�Ƃ��邩�A���ځA���Ŋ��݂����Ƃ���ł��낤�B
�Ί펞��̑c�悽���́A�n�߂͎��ɂ��̂ł͂Ȃ��A�n�C�G�i��n�Q�^�J���l�A�����̎��̂����i�����j��Ȃǂ��āA�����̓�����ɓ����A�������������������i������H�������j�ł������B�₪�āA����ς����̐ێ�ɂ��]�����B���A�Ί�삷�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�Q�O���N�O���炢�ɓo�ꂵ���V�l�N���}�j�����͂���ȑO�̋��l�l�A���f���^�[���A���l�A���l�Ƃ͖��炩�ɈقȂ�A���ʂȗp�r��@�\�ƌ��т�������Ȍ`��̓���i���A��̋�j�����o�����B���Ί�v���ƌĂԌ����҂�����Ƃ����B
�E�}�A�V�J�A�o�C�\���̓l�A���f���^�[���l�Ƌ��ʂ��Ă������A�N���}�j�����l�ɂ����Ă̓}�����X�ƃE�T�M���d�v�ȃ��j���[�Ƃ��ĉ�������B����l�̑c�悪�����Ă����u�{�\�v�͕����������邩�A�J�j�⒎�Ȃǂ̏���������ŕ߂܂���Ƃ��������̂ł��������A��ɓo�ꂵ������l�́A���G�Ȏ������A�����p���ăR�~���j�P�[�V�������s���Ȃ���A����s�����i���q�ҁw�l�ޑ�ړ��\�A�t���J����C�[�X�^�[���ցx�����V���o�ŁA�Q�O�P�Q�N�j�B���������l�ފw�I�Ȓm�����猩�Ă��A����s���w�Ō����{�\�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ��͖̂��炩���Ǝv����B
�����A�ŋ߂ł͓����s���̌����҂����̊ԂŁA�{�\�Ƃ�����͂�������g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���悤���B���Ƃ��A���[�����́A�u�l�Ԃ̖{���͈��Ȃ̂��H�v�w�z�~�j�[�[�V�����x���u�����Ԑl�ފw����W���i���s��w�w�p�o�ʼn�A2001�j�̒��ŁA�u�{�\�ƌ����p��́A���̈Ӗ�����Ƃ��낪���G�łނ������A���B���Ȃ̂ŁA���܂ł͂�������g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����p�ꂾ�v�Əq�ׂĂ���B
�l�ނ�����s���Ă��������̌o�ς́u�̏W�E��o�ρv�ƌĂ��B�l�ނ͂��̎����ɂ͎�ɂ��l������łȂ��A�쐶�̐A���A�̎��Ȃǂ��u�̏W�v���ĐH�ׂĂ����B�������A�ƒ�؉����u�̏W�{�\�v�Ɍ��т��Đ������悤�Ƃ���l�͂��Ȃ��B���łɎ�́u�{�\�v�Ƃ������̂́A�����s���w�ł����悤�Ȍ����ȈӖ��ł͑��݂��Ȃ����Ƃ͏q�ׂ����A�ނ����{�\�Ɍ��ѕt���Đ������邱�Ƃɂ͂ǂ̂悤�ȈӖ������邾�낤���B
�ނ�Ɋւ��Ă��ꂪ�{�\�Ɋ�Â����̂��ƌ�����Ƃ��ɂ́A�ނ�Ƃ����s���̐����w�I���邢�͓����s���w�I�������Ӑ}����Ă���̂ł͂Ȃ��A�u���n�l���s�����v�̂Ɠ������Ƃ��u����l�v���s���Ƃ������ƂɈӖ������o����Ă���̂ł���B���Ƃ��A�����̔_���̂Ȃ��Œނ���D�ނ��̂������Ƃ��āA���̗��R��q�˂�ꂽ�Ƃ��A�����Ɛ̂̐l�Ԃ��ނ���D�Ƃ������Ƃ𗝗R�ɂ���Ƃ͎v���Ȃ��B�G�A�R���̌������r���̃I�t�B�X�ŁA�p�\�R�����g�p���āA�@����K����_��Ȃǂɔ����Ȃ���d�������Ă��錻��l�����炱���A�������炿����Ɨ��ꂽ�C���ŁA��ؐl���D�܂݂ꌌ�܂݂ꊾ�܂݂�ɂȂ��Ď���s�����ł��낤�̂Ɠ��l�A�ׂƂׂƂ����R�}�Z��a���g���āA���ɁA���ɂ͑D�ɐ����Ěq�f���ɂ܂݂�Ȃ���A��������ߊl����Ƃ����s�ׂ��A���ʂɁA�u���n�I�v���Ɗ�������̂ł͂Ȃ��낤���B
�剺�F�Ɏ��́A�p���ɋ����͂Ȃ��A�u���㕶���̓��Y���v�A�悢�J������悢�r���v���ق����Ƃ��v��Ȃ��ƌ����Ă���B�����A�ނ̏����Ƃ����ĕ����l�Ƃ��Ă̐����́A�܂��ɁA��s�����ɉc�܂�Ă����B�ނ͓s�s�A�J�����A���v�ɉ����Ȃ���炵�����Ă������猴�n�l���Ɗ������̂ł͂Ȃ��A�����Ɏ��͂܂�Ă��肵�A��������E�o�������Ɗ����Ă������炱���A���������n�l���ƌ����Ă���̂ł���B
�ƒ�؉����y���ސl�������Ă���A������R�؎����y���ސl�������B�ƒ�؉��̊y���݂́A�f���}�Y�f�B�G�����������悤�ɁA����炪��@�B�̎��ԣ�ɏ]�������Ɏ����̃��Y���ɏ]���������ł���A�H��ł̢�a�O���ꂽ��J���̂悤�Ɏ����̘J���̐��ʂ����l�̂��̂ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�����̓w�͂����ׂĕ���Ƃ����_�ɖ�������������Ƃ����ӂ��ɁA�����ł���B���������n����̢�̏W��{�\�̌���ꂾ�Ƃ��������͂��Ȃ��B�����ċ��Ί펞��̍̏W�o�ς͌�ɔ_�ƂɎ���đ���ꂽ�B�_�Ƃ͌���Ɏ���܂ŏd�v�Ȍo�ϊ����Ƃ��đ����Ă���A�u���R�v�I�ł��A�u���n�I�v�ł��Ȃ��B�s��݂̑��_���ōs�����Ƃ̂ł���ƒ�؉����~�j�_�ƂɁu���n�v�̎�����߂�̂͂Ƃ��Ă������ł���B���ǁA�ƒ�؉��̖ړI�́A�@�B�I�J���̑㏞�Ƃ��Ă̎��R�Ȏ��Ԃ̋���Ɛ��Y���̏��L�Ƃ������ƂɂȂ�B
�������ނ�͎��R�Ȏ��Ԃ̋����Y���̏��L�����łȂ��A�u���n�v�̎���y���ނ��Ƃ��ł���̂��B�ނ�́A���n�l���s������Ɠ��l�Ɂu�l���v�����߁A�u�����v�ł͂Ȃ����R�̊��Ɠ����悤�ȁu���I�v�Łu��ȁv�̂Ȃ��ōs����B�������āu�ނ�͌��n����̎�{�\�̕\��v�Ƃ����������s���邱�ƂɂȂ�B�i�������A���̂悤�Ɍ��Ƃ��A���̐l�́A�ނ�ɏo������Ƃ��ɁA�����Ԃ��g���Ă��邱�ƁA�`����ނ��܂ł́A���n���D���V���D�ɏ��̂��Ƃ������ƁA�ނ̓���n�C�e�N��p���č��ꂽ�J�[�{���̒ފƂł���A�`�^�������̃��[���ł��邱�ƁA���邢�͉a�������Ď����Ō@�������̂łȂ��A��X�m�Ŋl��ꂽ�I�L�A�~�ł��邱�ƁA����炪���x�ȎY�Ƃ̔��B�ɂ���Ďx�����Ă��邱�ƂȂǂ���������Y��Ă���̂����B�j
�ނ�͓o�R�A�_�C�r���O�ȂǂƓ��l�A���R�Ƃ����ɐG�ꍇ���čs���邾���ɁA�����������Ƃ�����B��ނ�ł��A�����̑D�ɂ��ނ�ł��A����g�̂���Ƃ��ɂ͊댯�ł���B��Ŗ�ނ�����Ă��Ĕg�ɂ�����Ď��S����Ƃ��������͂����N�����Ă���B����������Ă�����ނ���n��Ƃ����B���������Ă���Ƃ��ɂ͊ȒP�ɍs���邪����������Ɠr�������v���Ă��܂��悤�Ȓނ�������B�n��̒ނ�ł͒������ԈႦ��ƓV�D���Ă��߂�Ȃ��Ȃ葘��邱�Ƃ�����B�D�œn�鉫�̏������ʂ̒ނ�������Ƃ����B����ł́A���X�A�n�D�i���n���D�j�����̂��N�����A�ނ�q���]���ɂȂ��Ă���B
��ꕔ�u�ނ�v�́u�֓��ł̃C�V�_�C�ނ�v�ł́A�^�߂Ŏ����g����������������ƁA�O���쌴�Q�ʁi�ʏ́A�O�{�x�j�̂����ŁA�����ނ��Ă����ꏊ�ɂ��Ƃœn���Ă�����҂��A�D���̎w���ɏ]�킸�Pm���قǒႢ���̒i�ŊƂ��o���Ă��Ĕg�ɂ����ꂽ���ƁA�ʂ̈�Ŗ閾���O�̈Â��C�œn�D�����Ɍ��˂��A����Ă����ނ�q���������������������������ƁA���邢�́A�����Q�x�s�������Ƃ����邾���́A�K�B�Ƃ����_�Ó��̉��̐�C�̌Ǔ��ƌ����Ă������悤�ȏ����ŁA�ނ�q����ɓn��������ɑD���D������Ƃ�����ł��܂��A�ނ�q�������ɂȂ��ċ~�����ꂽ���������������ƂȂǂ������Ă���B�n�}�`�̉g���ނ��C�V�_�C�ȂǑ�^���̒ނ�ł́A���ƈ����������Ƃ����荞�݂̂Ƃ��ɑD��邩��]������댯������B
���̂悤�ɒނ�ɂ͊댯�������A���������Ēނ�ɂ͂����̖`���̗v�f������B�������A�A�����Ȃ�͖앺�s�Ȃǂ̒T���ƥ�`���Ƃ̂悤�ɖ`����ړI�Ƃ��A�댯�Ɠ������߂Ɋ댯��`���̂ł͂Ȃ�����A�ނ�ɂ�����`���̗v�f�͂����ꕔ�ł���B�������A�ނ�͐l�H�I�ŁA���S�Ȋ��̒��ł̗V�тł͂Ȃ��A���R�̂Ȃ��ōs���V�тł��邱�Ƃɂ��댯�����邱�Ƃ͊m���ł���B����1980�N��ɍs�Ȃ��Ă����C�V�_�C�̈�ނ�͂����Ă��P�ƒލs�ł������B�g�ѓd�b���܂��Ȃ������B���̏ꍇ�ɂ́A�����N�������Ƃ��ɑ��̐l�ɏ����Ă��炤���Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA����Ɋ댯���������A����ɂ�������炸�ŏ��ɗ��Ă��ڕW���ɒB������Ƃ����A���傫�ȒB�����A��т�����B
�̑O�f�����V�X�D�ł́u�����̎�̏W���̎Љ�ł��A�H���̑唼�͖쐶�̐A���Ɉˑ����Ȃ���A��ɑ��Ăُ͈�Ȃقǂ̊S�������A�Љ�̃V���{���Ƃ������̂�������ɂ��Ȃނ��̂ł���v�Ƃ����B��͒P�Ȃ鐶�Ɓ\�o�ϊ����Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�̂łȂ��A�@���I�A�ے��I�Ӗ��������̂Ƃ��čs��ꂽ�ƍl����ׂ���������Ȃ��B
���n�l�͎�ɗ���Ȃ��Ă������ł����B�����Ď��������Ȃ����̂͐H�̕K�v����ł͂Ȃ����̃X�������D���炾�Ƃ����������i�����i�u�e�N�m���W�[�ƗV�т̊ԂɁv�A�u���A����Љ�w�Q�O�j�B
�����̐��܂���ƁA���n�l�͌���l�Ɠ��l�A�����邽�߂̍H�v---�����ł����܂����̂���������H�ׁA�����⏋����Ƃ�ĉ��K�ɖ���A���y�Ȑ����𑗂邽�߂̍H�v----���s�����ł��낤���A�����ŁA�������������݂ŕ��}�ȁu���퐶���v�𑗂邾���ł͖������ꂸ�A�������̍s�����s�����ƂŌ����o���悤�Ƃ����A���̓����ɂ͂Ȃ����ʂ̗~���������Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł���Ǝv����B
����l�́A���܂��܂ȗV�тɂ���āA���}�ȓ��퐫�A�������E�o���悤�Ƃ���~���������Ă��邪�A���n�l���܂���r�I���S�ȓ��퐶���ɖO�����炸�A�����o�������Ƃ����~���������Ă����̂ł���A�������������s������ł������B�u�V�сv�̎����̂��̂ł������̂��A����Ƃ��u�@���I�v�ȁA���Ȃ���̂Ɍ��������Ƃ�����̂ł������̂��ɂ��ẮA���ɂ͘_����͂��Ȃ��B�������A����������ōs������̂��Ƃ����_�ŁA�����q���C�b�N�Ȃ��́A���v���z�����A���I�ō����Ȋ������Ɗ�����^�l����l�����邾�낤�B�i�������A�x���M�[�ł́A�ŋ߁A�A�t���J�Ɏ�̂��߂ɏo�������������A�����������ᔻ�����Ƃ����B��́A���͂�A�G���[�g�̗V�тƂ��Ă����܂�������悤�Ȓn�ʂ������Ă��܂��Ă���̂������̂悤���B�j
�ނ�́A�{�N�V���O�Ȃǂ̊i���Z�͕ʂƂ��āA���̃X�|�[�c�Ɣ�ׂāA�댯�ɐg�����炷�x�����������傫���B��ނ�ł͈邩��]��������g�ɂ����ꂽ�肷��댯������A�܂��V���D�ł����Ă��u�q�ꖇ���͒n���v�Ƃ����悤�ɁA�~�����߂̒��p���K�v�ŁA���S�ł��Ȃ��Ƃ���̂���A�u�`���v�I�v�f�����V�тł���Əq�ׂ����A���������ނ肪��̈��Ȃ̂��Ɖ��߂ĕ��ނ��Ȃ������Ƃ��ł��A���̃X�|�[�c�ɔ�ׁA�댯�ł��邪���ꂾ���q���C�b�N�ŁA�����Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ�A�D�z���������邱�Ƃ��ł���B
�������āA��̈��ƌ��Ȃ��ꂽ�ނ�͑��̃X�|�[�c�Ƃ͈قȂ��āA���̋N���ɂ����Đl�ނ̒a�����߂��ɂ܂ők�邱�Ƃ��ł���R�����銈���ł���A�������A�������Ō������E�o���悤�Ƃ����A���I�ō����Ȋ������Ƃ������ƂɂȂ�B
�u�ނ�͎�{�\�̕\��v�Ƃ������t���Ӗ����Ă���Ƃ�������傰���Ɍ������̂悤�Ȃ��̂��Ǝv����B�������A���͎����̒ނ�ɂ���Ȃӂ��ȑ匩�����ς���͑S���Ȃ����B
�����͗\�m�\�͂�����Ƃ�������B�����́i�l�Ԃ̒m�肦�Ȃ����@�Łj�n�k�̔�����m�肤��Ƃ���A����́u�{�\�v�ɂ��̂��ƁA�����͌����B���[�����c�́u���炩�ɈӖ�������A��ێ��̖ړI�ɂ��Ȃ��Ă���̂����A���̍��ړI���������Ɏ��g�̑̌�����m���Ă��闹���@�\�Ɋ�Â��Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȍs���l���v�ɏo��Ƣ�{�\��ƌ������Ƃ�����ƌ����Ă���B���̐����̍s�����A�l�Ԃ̎��T�̊��o���g���Ċm�F���邱�Ƃ̂ł��鎖���⍪���������邱�Ƃ��ł����A�_���I�Ȑ��_��Ȋw�I���_�ɂ���Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ȃ������ŁA�ړI�ɓK���A�L�Ӗ��ł���Ƃ��ɁA�����{�\��ƌĂ�ł���Ƃ����̂ł���B
�l�Ԃ̏ꍇ�A�w�L�����x�̗p��Ţ�ނ͖{�\�ɐg�������߂���Ƃ����̂́A�l�Ԃ̗~�]���m���◝���ŃR���g���[���ł��Ȃ��Ȃ�����Ԃ��w���Ă���B�����炭�A�����͒m����������������A���A�H�݂̗̂~���ōs�����邪�A�����݂̂A�����̍s�������ׂĢ�{�\��ƌ��Ȃ��A�����I�ȍs��������l�Ԃ�{�\�ōs������A�ƌ����̂��낤�B
�n�l���A�[�������`�Ō��f���ꂽ�s���A������s�Ȃ����Ƃ��K�������ł��邱�Ƃ�l�ɂ������ł���s���͢�{�\�I��Ƃ͌����Ȃ��B�t�ɁA�������g�[���ł����A�����đ��l�ɂ������ł��Ȃ��i�܂�Љ�I�ɂ����F����Ȃ��j��肩���ŁA�H��Ɋւ���~�]��Փ�����������Ȃ�A�����{�\�I�ƌĂԂ̂��낤�B
�������A�ނ肪�Љ�I�ɐ��F����Ȃ��y���݂ł��邪�䂦�ɁA�ނ�ɑ���D�݂���{�\�I�Ȃ��̣���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A�{�\�������o����鑽���̏ꍇ�A�ނ�͂��̊y�����𑼂̐l���킩��悤�ɐ����ł��Ȃ��ƌ����_�ŁA��{�\�I�Ȃ��̣�ƍl�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�����ł��Ȃ����Ƃ̈�̏d�v�Ȍ����́A�ނ�̉��̌��_�Ƃ������ׂ������肪�A���ǁA��Ŋ�������̂ł���A���t�Ő������ɂ������̂��Ƃ����_�ɂ���Ǝv����B���͂��́u������v���A��ŁA�ڂ��������������Ǝv���Ă���B
�����ŁA�w���{��S�ȑS���x�u�ނ�v�ɂ�����X�G�l�̋L�q�ɂ��ď��X�G�ꂽ���B�ނ́A�u��{�\�v���j���z�������Ȃǂɂ�袑�����������A�����Ēނ���D�ޒj���������̂́A�j���z������������������ł���Əq�ׂĂ���B���Ȃ킿�A�u�j�����������ނ���D�ނ̂́A�j�����A���h���Q���ƌĂ��j���z�������̕����A�h���i�����k���t�玿�z�������l�̕���ɂ����ď��������邩��ł���B�ǂ���̕������A��{�\�A�U���{�\��������v�Ƃ����B�������A�u�{�\�v�͏Փ��A�~���̈Ӗ��Ŏg���Ă���̂��낤�B
�X�́A�����̕������A�u��̏Փ��v�u�U���Փ��v��������Ƃ������A�ǂ̂悤�ȍ����Ɋ�Â��Ă���̂��낤���B������l�Ԃɕ��p�����A���ۂɒނ肪�������Ȃ邩�ǂ����Ƃ��������̂悤�Ȃ��̂��s�Ȃ�����Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��B�}�E�X���̑��̎��������ɂ����𓊗^����A���������a��ϋɓI�ɐH�ׂ�悤�ɂȂ�Ƃ������ʂ������邩������Ȃ��B�������A�������A�}�E�X�́i�����a�́H�j�A�a�����ƁA�l�Ԃ́u��{�\�v�A�u�U���I�{�\�v�Ƃꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���������̕��������������s���ւ̌X����Փ������߂�Ɖ��肵�Ă݂悤�B�X��������U���I��Ƃ����̂́A�����Ɍ��V���l����������E�Q������Ƃ������ۗ������X���̂��ƂłȂ��A�ނ���D�ސl�ɊY��������x�̍U�����ł���B�܂艽���������̕��ɂ������A�����ɒ��킵�����A������B���������ƍl���A�ϋɓI�ɍs������Ƃ������x�́u�U�����v�̂��Ƃł��낤�B������A����́A�ɂ߂ē����I�ŁA���₩�ł��邩�A���邢�͏��ɓI�ł���悤�Ȑ��i�̐l�������A�����Ă��̐l�ɓ��Ă͂܂���̂��B�����y�Ȃǂ���l�ŐÂ��Ɋy���ށi���Ƃ������Ȃ��j�悤�Ȑl�������A������͌�A�����X�|�[�c���܂߁A���������̔����A�S�ẴX�|�[�c���D�ސl�ɂ��Ă͂܂邾�낤�B
�܂�Y���z����������U����{�\���h������Ƃ����Ă��A����͂��܂��܂ȁA�Q�[���A�X�|�[�c�ւƋ�藧�Ă�̂ł���B�������Ƃ���A�Y���z���������A�ނ�̌������邢�͗U���ɂȂ�Əq�ׂ邱�Ƃ͂قƂ�LjӖ��̂Ȃ����Ƃ��Ǝ��ɂ͎v����B�A�h���i�����������������߂邱�Ƃ͒m���Ă��邪�A�������A���̕��傪�������Ƃ͂��̐l�������I���Ƃ��������ŁA���ʁA�ނ�Ɍ����āA�����Ӗ�������킯�ł͂Ȃ����낤�B
�����ŁA���̂悤�ɍl����ƁA���̓�̕����̕���ʂ��j���ɑ����Ƃ������Ƃ́A�ނ�l���j���ɑ����Ƃ������������������̂ł͂Ȃ����Ƃ�����B�m���ɤ�c���͊Ƃ��������̗̑ͤ�r�͂����܂ł͒ނ�͖��������A������āA�̗͂��ቺ����Α���̈����Ƃ���Œނ������͓̂���Ȃ�B�������A�����Α�ނ�͎~�߂ă}�L�R�{�V�ނ�̂悤�ȑ̗͂����܂�K�v�Ƃ��Ȃ��ނ�����Ă���悤�ɁA�ނ����I�ׂA���Ƃ��Ă��A����B�܂�A�j�����������A��قǑ̗͂ɗ��l�łȂ���A�ނ�����邱�Ƃ��ł���B�]���āA�X�̋c�_�ɏ]���Ȃ�A�j�ł���A���ł���A�ނ�����Ȃ��ŁA���̃X�|�[�c������l���ǂ����Ă���Ȃɑ����̂����s�v�c�ł���A�܂��A���ϓI�ȑ̗͂⊈���x�̒j�����͋͂��ł��邩��A�����̒ނ�l���j���Ɋr�ׂď��Ȃ�����Ƃ������Ƃ��s�v�c�Ȃ̂ł���B���Ԃ�A�����͐����w�I�ɂł͂Ȃ��A�Љ�I�ȗv���ɂ���������邱�Ƃł��낤�B
�j���ɍ������Ēނ���y���ނP�X���I�̉p�������B�ѓc���w�ނ�ƃC�M���X�l�x���
 �ނ�͂P�X���I�̉p���ɂ����Ă͎Ќ�ړI�ōs�Ȃ��A�������ނ�������B�܂��A�S�Ȏ��T�̂Ȃ��ŐX���q�ׂĂ��邪�u���E�ōŏ��̂���发�v�͂P�T���I���ɃC�M���X�̃W�����A�i�E�o�[�i�[�Y�Ƃ��������ɂ���ď����ꂽ�B���{�ł͖�������ɂ́A���邢�͏��a�̎���ɂȂ��Ă��O���܂ł́A�ނ�����鏗���͔��ɏ��Ȃ������B������ƌ����āA�킽���́A�C�M���X�̏����̒j���z�������ƃA�h���i�����̕���ʂ͓��{�l������葽���̂��낤�Ƃ́A�l���Ȃ��B
�ނ�͂P�X���I�̉p���ɂ����Ă͎Ќ�ړI�ōs�Ȃ��A�������ނ�������B�܂��A�S�Ȏ��T�̂Ȃ��ŐX���q�ׂĂ��邪�u���E�ōŏ��̂���发�v�͂P�T���I���ɃC�M���X�̃W�����A�i�E�o�[�i�[�Y�Ƃ��������ɂ���ď����ꂽ�B���{�ł͖�������ɂ́A���邢�͏��a�̎���ɂȂ��Ă��O���܂ł́A�ނ�����鏗���͔��ɏ��Ȃ������B������ƌ����āA�킽���́A�C�M���X�̏����̒j���z�������ƃA�h���i�����̕���ʂ͓��{�l������葽���̂��낤�Ƃ́A�l���Ȃ��B���{�ł��A�L���Ȓނ�l�̍Ȃ►�Œނ������l�����Ȃ肠��B���l�̎����Ґ��͒ނ薼�l�Ƃ��Ă��m���Ă������A���̖��A�������q���ނ肪�D���ŁA�ނ萏�M�̖{������B�剺�F�Ɏ��̕v�l�������u�ꗬ�̒ނ�t�v�������ƌ����i������F�w�ނ苶�x�j�B����ƁA�ނ�����邩���Ȃ����A���邢�͏�肩���肩�͒j���z�������̕���ʂɂ���āA���܂�̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�����邢�͂c�m�`�ɂ���Ă��܂�ƍl����l�����邩������Ȃ��B�i�v�l�͕ʂ����B�j�������A�l�̐��i��S�g�̔\�́A�s���̎d�����X���c�m�`�܂��`�ɂ���Č��܂�̂�����Ƃ����̐�����ɂ���Ă��܂�̂��A�܂莁���炿���inature or nurture�j�́A�قȂ���ň�Ă�ꂽ�ꗑ���o�����̌������܂߁A���܂��܂Ȍ������Ȃ���Ă������A���̈�������ł��ׂĂ������ł���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��B
���̓�������łȂ��A�l�Ԃɂ����Ă��A���R������ʂ����i���̑������Ƃ��Đe����q�֓`�������`�q���s���ɉe����^���Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�����A�l�Ԃ̏ꍇ�A�s���ɂ͋ɂ߂đ傫�ȕ�������B�����āA�l�Ԃ����ɕ�炵�Ă�����́A�l�ނ����Đi�����Ă������Ƃ͎��Ă������ʑ㕨�ł���B�i���̉ߒ��Ŋl�����ꂽ��`�q�͕��G����������Љ�ɂ�����s���̈������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������͐��܂�Č�A�w�K���o���������Ƃ�����ɂ��āA���ɓK�������s��������_��������Ă���̂��B���̍s�����u���肷��v��`�q�����o�����Ƃ��Ă����ʂł���B
�P�X���I�̃C�M���X�Œނ���������������͏�w�K���ɑ����Ă����B�ޏ���͎Ќ��Ƃ��Ă̒ނ�������Ȃ��O�ɁA���R�ɎЌ��E�ɏo���肷�邱�Ƃ��ł����̂ł���B�ޏ���͎����ɗ^����ꂽ���̒��ŁA���̓����̃C�M���X�̏㗬�K���ɢ�K������邽�߂ɁA�܂�A�K���Ȕ��������o�����߂ɁA���܂��܂ȍs���������Ȃ��B���̈���ނ�ł������낤�B
�Ȃ��ނ������̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă̐����͗l�X�Ȏd���ōs�Ȃ����Ƃ��ł���B�A����E�i�M��A�I���C�J�̂悤�Ȃ��܂�����C�J��ނ��ĐH�ׂ������炾�B����͂���ŏ\���ɔ[���������B�r��ŋ����Ɛ킢�A���邢�͢���̋����ނ�グ�Ă݂����B������܂��[�����������낤�B�����Ď��͂��ꂩ��A�����������ċ����|���邱�Ƃ̈��̃X�����ƃT�X�y���X����������^���Ă����Ƃ������Ƃ��\���������悤�ƍl����B���̂悤�ɁA�s���A�s�ׂɊւ�������ɂ́A�X�l�̎��_�ɗ������A���̐l�̓������猩���A�����������̍s���A�s�ׂ̐���������B
�����A�O����́A��Ȋw�I��ȁA���邢�͈��ʓI�Ȑ������\�ł���B�l���A���邢�͑����̒j���A�ނ������̂́A���{�\��Ƃ�����̂ɍ��ꂽ��`�q�̓����ɂ�邱�Ƃł���Ƃ�����̐����`��������B���邢�́A�j���z�������ƃA�h���i�����Ƃ������w�����̕���ɂ��̂ł���Ƃ������������̈�ł���B�X�͔ނ̒ނ�̐�����Ȋw�I��ɍs�Ȃ����Ƃ����̂��낤���B���Ԃ�A�����͂���������B�������A�ނ́A���������n�I�Ȗ{�\�̂悤�Ȃ��́A�U���I�Փ��̂悤�Ȃ��̂������Ă���Ƃ��q�ׂĂ���B������A�u�ނ�͖{�\���v�Ƃ������̗����́A�����́A�ނ̒����A���ȔF���A�Ȃ�����ϓI�ȑz�O�̓f�I���Ƃ��l������̂ł���B
�ނ͕��M�ƂɌg����Ă���B�ނ�͎�ł��顁i�{�E�̋��t�ł͂Ȃ��B�j�E�H���g���́w�ދ���S�x��|�A�ނ蕶�w�ɏڂ����A�����̒ނ�̐��M�������Ă���B�܂��w�v�z�̉Ȋw�x�̕ҏW�҂Ƃ��āA�����̕��͂�ǂށA�v�z�Ƃł����������낤�B�����A�ނ́A���Ɍ������ĕ�����ǂ菑�����肷�邱�ƂƁA�ނ�����邱�ƂƂ̊ԂɂȂɂ��َ��Ȃ��̂�����A���҂̐��_�\���ɑ傫�ȈႢ������Ɗ��������Ƃ��Ȃ��������낤���B������ǂݏ������邱�Ƃ́A�C���e���A�m���l�A�����l�^�����l�ɂӂ��킵���B�����A�S���t�Ȃ炢���m�炸�A�C���ŁA�����Ε��ɐ�����J�ɒ@����Ȃ���A���邢�͊��܂݂�D�܂݂�ɂȂ�Ȃ���~�~�Y�⒎�Ȃǂ�j�Ɏh������ނ�̂́A��ؐl�Ƃ܂ł͂���Ȃ��ɂ��Ă��A�m���l�Ƃ͈قȂ鏎���A�J�����̌��t���g���u�yݕS���v�̂�邱�Ƃ̂悤�Ɏv����B���͂���͎����g�����������Ƃł���B
���͂Q�O�㔼����S�O�ɂȂ邱��܂ŁA�w���^����J���^���ɉ�������o��������B�P�X�U�O�N�㖖�̑�w�����ɎQ�������B�����Ĥ��������A�E������ɍē��w����w�@�ɐi�w�����̂����A����ǂ́A�w���̓����ɑ����āA�����E�����҂Ɍق��Ă���Վ��E���A�u�ՐE�v�ƌĂ�Ă����l�X�́u������v��v������u�ՐE�����v���N�����Ă���A���͂��̉^���̎x���ɉ�������B
���肵���A�V�W�N�ɓ��傪�n���P�O�O�N���}���邱�Ƃ��u�L�O�v���āA���������Ƃ��Ċ�ƂȂǂ���S���~�������A�u�S�N���v��Ҏ[����Ȃǁu�S�N�Ձv�����s����Ƃ����v�悪���\���ꂽ�B�����ɁA�u�ՐE�v���g���̂Ăɂ��Č����Ɛт�Ƃ��߂��Ă��������E�����҂̎x�z�̐���ᔻ���錩�n���炱�́u�S�N�Ձv���̐����オ�����B�܂������A��w���ł́A�]�O�Ȃ̋�����ɂ�銳�҂ւ̐l�̎����I�ȁu���{�g�~�[��p�v�ȂǁA���_��w�ɂ�����u���������`�v��ᔻ�������t��𒆐S�Ƃ���^�����������B�܂��H�w���ł͏���̉F�䏃���i��A����勳���j��ɂ��A�����a�ɂ����铌��W�҂̌�����Ƃւ̉��S��ᔻ����������u����u���v�^�����s���Ă����B���̂悤�ȏ̒��ŕ��w���w���Ȃǂ���u����̕S�N�v��₤�����オ��A��ƕ�����̉^�����N�������B���͗ՐE�����x�����s���Ȃ���A���́u���S�N�Ձv�̉^���ɉ���邱�ƂɂȂ����B
���͂��̂Ȃ��ŁA�菑���̃r��(�`���V)�����---�����͂܂��r���͓S�M�Ō������A���ʔł��g���āA�܂�ꖇ�ꖇ�����ň�����Ă����B�V�O�N�㔼���烊�\�O���t��������悤�ɂȂ������A���e�͐�ׂ̍���p�̃y���ŏ�����---���A��w�̖�̑O�ŁA�o���Ă���E���Ɏ�n�����ƁA�܂��A�x�j���Ɗp�ނ�B�őł����ė��ĊŔ����A���������ςč�����ЂŎ���\��A��n��n�`���g���đi���̕����������A�����Ƃ����̊ԂŁu���X�P���v(�h�C�c��Łu�ؓ��v���Ӗ�����)�ƌĂꂽ�A�����������ƁA���邢�͓��̘J�����y�����Ɗ������B
�w�ҁE�����҂Ƃ�����x����E���E�J���҂Ƃ̊Ԃ̎x�z�E��x�z�̊W�ɂ������s�����ȊW�ɍR�c���銈���̂��߂̍�ƂƂ��ėL�Ӌ`�Ɋ�����ꂽ�Ƃ������ƂƂ͕ʂɁA��Ƃ��ꎩ�̂��y�����Ɗ�����ꂽ�B���ͤ�������Ƃ��Ĥ�w�[�Q���N�w���������Ă����B�h�C�c��Ńw�[�Q���́w�_���w�x��w���_���ۊw�x�Ȃǂ̓���Ȓ����ǂB�������������g�����_�J���Ƥ�r�������褗��ĊŔ������Ƃ��������Ƃ̘J���Ƃ̊Ԃɂ͒f�₪����Ɗ������B����_�Ǝ��H��A���邢�͢���_�J���Ɠ��̘J����ȂǂƂ��āA�J��Ԃ������̓N�w�I�ȋc�_�̃e�[�}�ɂ��Ȃ��������ł���B���͂����������Ƃ�_��������̓N�w�҂�v�z�Ƃ̒����ǂ��A�[���̂����������Ƃ��A�܂����牽���������o�����Ƃ��v��Ȃ������B�˂��l�߂čl���悤�Ƃ͂��Ȃ������B���͎����̌l�I�ȍs���̒��ŁA���H�I�ɂ���痼�҂̓���𐬂������Ă���ȂǂƁu�����炩�Ɂv�l���čς܂��Ă����B�������A���̌㤒ނ�����悤�ɂȂ��Ă�����A��w�ɐ��K�̐E�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł������A�������͑����Ă���A���̎����̢�d����Ƣ���ɂ����鐸�_�Ɛg�̂̂�����ɑ傫�ȈႢ������Ƃ��������͑������B
�ՐE�����̎x���̂��߂ɁA���x���ꏏ�ɢ���荞�ݣ�Ȃǂ�������S�����^���̎w���҂Ɩڂ��ꂽ�x���������̎x�����Ō�܂ő����Ă����B�������ނ̎���X�|�[�c���Ƃ͕����Ă��Ȃ��B�ނ͢������Ɋւ���Ă���Ƃ��ȊO�́A��т��Ċw���I�Ȑ����𑗂��Ă����悤���B����͉������̉Ȋw�j�̑咘�����B����͖{����/�����ɒm���l�ł��蕶���l�������B���̒��ɂ͗l�X�ȌX���̐l������Ǝv����B�����ōs�Ȃ����_�I�Ȏd�����������D�ސl������B��O�ő̂��g���ĉ������邱�Ƃ��D�ސl������B���̂悤�ɂ����������Ƃ����l�Ԃ�����B
�ӂ����^�����̒��ɂǂ��Ղ�ƐZ�����āA������g���Ă��邩�炱���A���X�A���R�̒��ŁA�����x�ߑ̂��g���Ēނ������̂������Ȃ̂��Ƃ��l�����邪�A�����l�ɓO������Ȃ����Ƃɕs���������A�����l�^�����l�ł���A���R�̒��œ��̂��g���V�тɊ�т����o�����Ƃɖ�����������l�����邩������Ȃ��B���́A���҂̈Ⴂ�͊��������A�����̐������ɖ���������Ƃ������ɂ͎v��Ȃ������B�������A�X�G�l�͂����������炻������������������l�������̂�������Ȃ��B
�����āA�����╶���͌��n�̔ے�A���邢�͔��Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����͌��n�I�A�{�\�I�Ȃ��̂̐i���E���W�̌��ʂȂ̂��l���邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�m���l�A�����l�ł���A�ނ�D���ł��邱�Ƃ͖����ł��Ȃ�ł��Ȃ����Ƃł���B�ނ�́A�����i�����邢�͕������̉ߒ����o�āA�l�Ԃ��l�����������Ƃ����x�ȍs���`�Ԃ̈�Ȃ̂��B�ނ�́A���n�l�̎����Ă�����{�\�A�U���{�\�ɗR��������̂ł���A��w��Ȋw�̗p���p���Č����A�j���z��������A�h���i�����̑����ɂ���ċq�ϓI�ɐ����ł�����̂ł���B�����āA����Љ�ɂ����āA�l�Ԃ͐i�����W������{�\���A�ނ�Ƃ����m�I�ȃX�|�[�c�̌`�ԂŔ������A������y���ނ̂ł���B�ނ�͓��]�Ɛg�̂Ƃ����l�Ԃ̗����ʂ����A�l�Ԃ̖{�������������ł���A�]�X�B�i�ނ́A�E�H���g���w�ދ���S�x�́u��҉��v�̒��ŁA�u�ދ���P�Ȃ�q���̗V�тƂ��V�l�̉B�����y�ł����Ȃ��ƍl����l�X�͕s�K�ł���B�ލs�͌��݂ɂ����Ď���̂��̂ł���A��������͂邩�ɓ���Z�p�ł���A�l����V�Y�̍ō��̂��̂Ȃ̂��v�ƁA�ō����̌�����ނ�ɒ悵�Ă���B�j�ނ�ɂ��Ď������܍s�����������傰���ł킴�Ƃ炵�����Ƃ͔F�߂悤�B�����A�ނ肪�A�l�Ԃ̎��R�I�Ō��n�I�Ȋ����ɗR���������ɕ����I�Œm�I�Ȋ����ł���Ƃ����������A�Ȋw�̗p����g�킸�ɁA����������肭�q�ׂ���������B
�ĂсA�ѓc�́w�ނ�ƃC�M���X�l�x������p���悤�B����̓f�C���B�ƌ����l���t���C�E�t�B�b�V���O�̍D�܂�����������P�X���I�̕��͂ł���B�������A�����ɏ�����Ă��邱�Ƃ́A�t���C�E�t�B�b�V���O�Ɍ��炸�A�ނ��ʂɓ��Ă͂܂�
��H�ƒNj��́A�����̖{���ɑ�����{�\�ł���B���_�⑄�ŗb�⋛���E���ł��e��Ō��n�I�ȏ�Ԃ̖�ؐl����A���̖ړI���m���ɂ��邽�߁A�I���ȍH�v�i�g�����������������h�j�Ɠ���A�l�X�Ȃق��̓��������̎�i�Ƃ��ėp����ł������������Љ�̐l�ԂɎ���܂ŁA�y���݂̋N���͗ގ����Ă���A���̖ړI�͓���ł��顑�ςȋZ�p�i�g�������h�j��v���邱�̎�̊y���݂́A�ł������Œm�I�ȏ�Ԃɂ���l�Ԃ̓����ł���ƌ����邩������Ȃ��B�t���C�ŃT�P��}�X��ނ낤�Ƃ���ސl�́A�����̓��̓I�ȗ͂������邽�߂ɓ����p���邾���łȂ��A������������邽�߂ɓ����g���̂ł���B�g�̂��g�������̊y���ݓ��l�A�I���Ȏ�i�ƍH�v��������o�����y���݂��t���C��t�B�b�V���O�ɂ͂��飁B
�u�t���C�ŃT�P��}�X��ނ낤�Ƃ���v�Ƃ��������폜���A�u�t���C��t�B�b�V���O�v���u�ނ�v�ɒu��������A���̕��͒ނ��ʂɊւ��Č��ꂽ���ƂɂȂ邪�A���́A���̂悤�ɕ������������邱�Ƃ��\���ɗL�Ӗ��ł���Ǝv���B�v����ɁA�ނ�͑e��Ō��n�I�Ŗ�ȗv�f�ƁA����I�Ȓm�I�ōI���Ȏ�i�A�Z�p�Ƃ��������Ԃ̊u������Č��ѕt�����A�������ꂽ�����ł���A���]�̊����Ɛg�̂̊����̗��������т����A���_�Ɠ��̂Ƃ��������ꂽ�������Ƃ������Ƃł���B�܂��A��ɁA�u�ނ����{�\�̌���v�ƍl���邱�Ƃ̓��ɂ́A�ނ���u�������Ō������E�o���悤�Ƃ������I�ō����Ȋ����v��q���C�b�N�ȣ�`���ƍl���邱�Ƃ��܂܂�Ă���ƌ��������A�����t��������ƁA�ނ�́A�l�ނ̒a��������̗��j��w��ɂ��R�����銈���ŁA�������A�ߑ�I�Z�p�Ŏx����ꂽ�A�m�I�ŁA���`���I�Ŕ��I�ō����ȁA�������̂��銮�S�Ȋ������Ƃ������ƂɂȂ�B
���̂悤�ȑ������A���S���͌|�p�����ɂ͂Ȃ��������ꂸ�A�܂��`�F�X�⏫���̂悤�ȁA�����čs�Ȃ��m�I�ȃQ�[���ɂ��Ȃ��ƌ�����B�������A����͒ނ�ȊO�̂قƂ�ǂ��ׂẮA�g�̂�p���������A�X�|�[�c�ɂ͑����ꏭ�Ȃ��ꓖ�Ă͂܂邱�Ƃł��낤�B�l�ނ��ŋ߂ɂȂ��āA�S���V�����[�����甭�������悤�ȃX�|�[�c�̖��O��������͓̂�����낤���A�܂��A�g�̂̍s�g�Ɋւ��č����댯�����z����K�v���S���Ȃ��悤�ȃX�|�[�c���قƂ�ǂȂ����낤�Ǝv���邩��ł���B���́A�ނ肪�A�l�ԂɂƂ��Ă���ȏ�Ȃ����S�ȁ@���炵�������ł���Ȃǂƍl����K�v���A�^������K�v���S�������Ȃ��B�V�сA�X�|�[�c�͂��ꂼ��D�݂ɉ����đI�Ԃ��̂ŁA������s�Ȃ����Ƃ��l�ނ��邢�͐l�Ԃ̊����Ƃ��Ď���������Ȃ��Ӗ����邢�͈Ӌ`�ɏƂ炵�āA�I�Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B
�剺�F�Ɏ��́u�悢�J������悢���v�v�Ƃ����������̗�����ق����Ƃ��v�킸�A�܂����E�����̒��S�n�A�Ԃ̓s�A�p���ɍs���Ă݂����Ƃ��v��Ȃ��B�ނ��u�ق����̂͂悭�ނ���v���B�ނ���Ƃł��蕶���l�ł����āA�ނ�̎�Ǝ����̎d���Ƃ̊ԂɁA�َ��Ȃ��̂������Ă���B�������A�ނ́A����ɂ��قǂ����������Ȃ��B�d���͎d���A��͎�ł���Ɗ�����Ă���B�������A�Ȃ��ނ肪�ʔ����̂��͐����ł��Ȃ��B�����Łu���n�l�̎�{�\���c���Ă��邩�炾�Ƃł���������ق��Ȃ��v�ƌ����̂ł���B�ނ͂��ꂪ�����ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�ނ�̖ʔ����ɂ��Đ����ł��Ȃ�����A�������Ȃ��ɁA���������Ă݂������̘b�ł���B������k�Ō����Ă���̂ł���A�ނ́A�l�Ԃ̂Ȃ��ɂ͌��n�l�Ɠ����u�{�\�v���c���Ă���A���邢�͓ˑR�ψق̂悤�ɂ��������{�\�A���邢�͏Փ����萶����Ƃ������Ƃ��A�{�C�Ŏ咣���Ă���킯�ł͑S���Ȃ��B
�����āA�ނ�̊y����������ł��Ȃ��̂́A����܂Œނ肪�����Ȃ��A�y���݂ł���A�ǂ����Ė������̂��ɂ��ďڂ������������߂���@����Ȃ��A�������قƂ�ǎ��݂��Ȃ��܂܂ɂ������ʂł͂Ȃ����Ǝ��͎v���B
���łɑO�͑��߂ŐG�ꂽ�� �ނ�Ɋւ��鑽���̕����������K�c�I�����ނ�̖ʔ����Ɋւ��Ă͂قƂ�ǐ������Ă��Ȃ��B�u�����Òނ�̋L�v�ŁA���킹�����������܂��Ƒ҂Ԃ̊y�������u����������Y��ʂĂĎv�Ўז������S��źۂ̐̂Ɋ҂�A�܂����̉��̔߂��ނׂ��J�ӂׂ����Ƃ̂����m�炸�v�Ə����Ă��邭�炢�ŁA�ނ�̖ʔ����̕��͍͂s�Ȃ��Ă��Ȃ��B�ނ͍ŏ��̂P�O�N���炢�͂��܂��܂Ȓނ����薲���ɂȂ��Ēނ������A���̌�A�ނ邱�Ƃ͓�̎��őD���ׂĎ��ɂ͎������݂Ȃ�����͂̌i�F���y���ݎ��̂����̂�т肵���ނ���y���ނ悤�ɂȂ�B�j�Ǝ����g���ċ����|����Ƃ����ނ�̖ʔ������\�����͂��Ă݂悤�Ƃ͍l���Ȃ������̂��Ǝv����B
���̏͂̑�W�߂łׂ̂邪�A�J�������ނ肪�ǂ����Ėʔ����A�y�����̂���������Ă͂��Ȃ��B�ނɂƂ��āA�ނ�͐��E�̕Ӌ��ɏo�|���A�Ɋ��A�M���A���_�j�̖ҍU�ɑς��A���ɂ��̋����ŋ��勛�Ɗi�����邱�Ƃł��������A�ނ͊y����ł��Ȃ���������ł���B�ނ͋���ނ�グ���ʂ�Տꊴ���ӂ��M�����Ō����ɕ`���Ă���A�ǂގ҂�����������B�������A�J�����g�͌����Ċy�����𖡂킢�Ȃ���ނ�����Ă��Ȃ������B�����Ēނ�̏�i��`�����Ƃƒނ�͂ǂ����Ėʔ����̂���������邱�Ƃ͑S���ʂ̂��Ƃ��Ǝv����B
�Ќ�I�ȗV�сA��Ƃ��Ă̕��w�≹�y�A���邢�̓Q�[���⋣���I�ȃX�|�[�c�̏ꍇ�ɂ́A���ۂ̍�i�̐���i���Ƃ��Δo��j�A���y�̉��t�A�싅�̎����A�S���t�̃v���[���X���y���ނ����łȂ��A���̑O��ɁA�ʂȏꏊ�ŁA���Ԃ�`�[�����C�g�ƁA�����A�����ɂ��Č�荇���A�_���������Ƃ��s�Ȃ��A����������炢��������̈ꕔ�ɂȂ��Ă���Ǝv����B�����̎��X�|�[�c�̊������A���̐l�ԂɌ������āA���邢�͑��̐l�ԂƂƂ��ɍs����Ƃ����Љ�I�E�Ќ�I�Ȑ��i��A���Ԃ̊Ԃł͒P�ɋZ�p����̂��߂̏����������łȂ��A���̖��͂��邢�͖ړI�Ȃǂɂ��Ă������Ό�肠�����Ƃ��s�Ȃ��A������y���ސl�̑����ɂ́A���̎��X�|�[�c�̂���{�I�Ȗ��͂�ړI�Ɋւ��鋤�ʂ̗������ł��Ă���Ǝv����B
����ɑ��āA�ނ�͊�{�I�ɔ�Ќ�I�ȗV�тł���A���R�̂Ȃ��Ŏ��R�Ɍ����ĉc�܂��B�C���ŁA��l��l�����Ɍ����������ł���A�ނ�N���u�ɓ����Ă���̂łȂ���i���邢�͓����Ă��Ă��j�A���Ԃ��W�܂��ĂȂ��ނ�͖ʔ����̂��A�ǂ����ʔ����̂�����荇���@��Ƃ������̂��A�قƂ�ǂȂ��B�ނ�G���͂����Ă��A�ǂ�������ނ�邩�������葁���m�肽���Ƃ�����l��l�̒ނ�l�̊S�ɂ�������ׂ��A�f�ڋL���́A�ނ��Ɋւ������A�ނ�̋Z�p��d�|���Ɋւ��������قƂ�ǂł���B�}���قɕ���ł���ނ�̖{���A�قƂ�ǁA�Ώۋ��A�ނ肩���A�K�v�ȓ���Ȃǂ̐�������ŁA���ǂǂ��������ނ�邩�Ƃ������Ƃ��������Ă��Ȃ��B�ނ�ɂ��ď����ꂽ���M�W��ނ蕶�w�́A�ނ��X�|�[�c�̒I���牓���͂Ȃꂽ�u���w�v�̒I�ɒu����Ă���B
�������āA�ނ�l�͒ނ邾���̐l�ł���A���w�D���̐l���A���܂苻�������������Ƃ̂Ȃ��ނ�ɂ��ď����ꂽ�������܂��܌����ēǂނƂ����A�X�|�[�c�ƕ��w�A�g�̂Ɛ��_�A�Z�p�ƒm���A���v�Ƌ��{�̕����������Ă���B���Ԃ�ނ蕶�w�A���邢�͎����������Ă���悤�ȁA�ނ�ɂ��Ă��ꂱ��l���Ă݂�Ƃ����悤�ȁA�����ɂ܂����������͂́A�ނ�D���̐l��������w�D���Ȑl������D�܂ꂸ�A�ǂސl�͂قƂ�ǂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�ނ�l�́A�ނ�̂ǂ����ʔ����A�Ȃ��ނ肪�D���Ȃ̂��Ɋւ��āA�����ōl�������Ƃ��Ȃ����A���̐l�Ƙb���������Ƃ��A�ق��̐l�̐��������Ƃ��Ȃ��B�����ŁA�ނ�̖ʔ����A���͂̂䂦�������ł��Ȃ��܂܁A���܁A��������K�v�ɔ���ꂽ�Ƃ��ɁA���̕��ւƂ��āA����ނ肽�����l�������Ƃ����Փ�����ƌ��т��A���A�����ɂ����l�ɂ��킩��悤�ɐ����ł��Ȃ����߂Ɂu�{�\�v�������o���A�ނ�͢��{�\�̕\�ꣂƂ������Ƃɂ��Ă��܂��Ă���B���̂悤�Ɏ��͐�������B
�����A�ނ�͂Ȃ��ʔ������A�Ȃ��ނ������i�D�ށj�̂��ƕ����ꂽ�Ƃ��ɁA�u�{�\�v�������o�����Ƃ́u�y�����v�u���ł���v���Ƃ̏��ȁA���邢�͗��R��������邱�Ƃɂ͖𗧂��Ȃ��Ƃ������Ƃ���Ŏ������B���̏��Ȃ◝�R��m�肽���ƍl����l������̂��ǂ����͖��炩�ł͂Ȃ����A�Ƃɂ����A���́A�����������Ȃ����B���̐����̖��ɗ����Ȃ��A�{�\���͑ނ����̂ŁA���x�́A���悢��A���Ȃ�̐����ɂƂ肩���낤�B
����ł́A�ނ�̉��͂ǂ��ɂ���̂��낤���B�l�X�Ȓނ���ɂ��A���܂��܂ȋ���Ώۂɂ����A�����̎�ނ̒ނ肪���邪�A�ނ�͐����l�߂�ƁA���Ɛj�A�����Ċl���ł��鋛�ɋA������B���̃X�|�[�c�Ƌ�ʂ���A�����ׂĂ̒ނ�ɋ��ʂ���ނ�̖��͂́A����j�Ɋ|���A�茳�܂ň����邱�Ƃ̂Ȃ��ɂ��邾�낤�B�H�ׂ邱�Ƃ������ړI�Ȃ爼�͖Ԃł����邵�A�E�i�M���u�n���v�Ƃ����A���邱�Ƃ͂ł��邪������������Ă��܂��Əo���Ȃ��Ȃ铛��̎d�|�����g�������Ŋl�邱�Ƃ��ł���B�������A�j�Ǝ����g���ނ�ɂ͂���狙�Ƃ͈قȂ�ނ�̖ʔ����A�ނ�̉�������͂����B
�ނ�ɂ����ẮA���͐j�Ɋ|���邱�Ƃɂ���Ēނ���B�A���̗F�ނ�ł͐j�ɂ��Ă���A�����j�����Ă��A���ꂪ��̒��ɂ��鑼�̃A���̓꒣��ɓ����Ă����ƁA��������ނ��悤�Ƃ��Đ�̒��̃A�����A�d�|���ɂ��Ă���ق��̐j�Ɉ����|�����Ă��܂��Ƃ����d���Œނ���̂ł���B�������A����͔��ɓ���Ȓނ���ł���B���̂قƂ�ǂ̒ނ�ł͐j�̐�ɉa���h�����A�a�Ɏ������[�a�j���g���A��������ɐH�킹�Đj�ɂ�����B
�t���C�E�t�B�b�V���O�ł͒��Ɏ������[�a�j�E�t���C�𐅖ʂ𗬂�����ʂ��ꂷ��̂Ƃ���ɓ����Ă��ƃT�P�Ȃ̋����H�����B���������͂��킦���u�Ԃɖ{���̉a�ł͂Ȃ����Ƃ�m��A�����ɕ����B�ނ�l�͋����t���C�����ɓ����Ɠ����ɊƂ��������Ď��������A���̌��ɐj���|����B���̓�����u���킹��v�Ƃ����B
�w���u�i�ނ��O���i���W�i�j�ނ�Ȃǂ̒ނ�ł́A�j�ɖ{���̉a�����Ă���B������h���a�Ƃ����B���͎h���a��H���B�C�ł́A��ɐ���ł��Ēꕨ�ƌĂ��z�S�i�J�T�S�j�A�R�V���E�_�C�Ȃǂ͑�����J���Ċۓۂ݂��邪�A�j����鑽���̋��͊ۓۂ݂���̂ł͂Ȃ��A�a���������ݍӂ��Ȃǂ��ēۂݍ��݁A���̐j��f���o���Ă��܂��B�����A�w���u�i�ނ��O���i���W�i�j�ނ�Ȃǂ̒ނ�ł͓����̓r���ɃE�L�����Ă��āA�ނ�l�́A�����G�T�����킦���Ƃ��ɐ����鎅�̏����ȓ����i������u������v���邢�́u���M�v�Ƃ����j���E�L�ɕ\���̂����āA���₭�Ƃ�U��グ�Ď��������āu���킹�v���s�Ȃ��A����j�Ɋ|����B
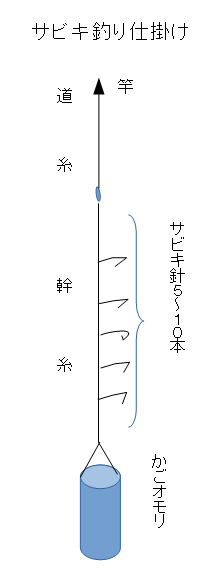
���S�҂���h�Ȃǂōs���ނ�ł́A�Ƃƃ��[�����g���A�����̐�ɃT�r�L�Ƃ����[�a�j���P�O�{�قǂ����d�|���ƁA�I���������˂��R�}�Z�J�S����������A�u�T�r�L�ނ�d�|���v��p����B
�R�}�Z�J�S�ɃA�~�G�r�Ȃǂ����Ďd�|���𓊓����ĊƂ��㉺�ɐU��R�}�Z���T���ƁA���A�W��C���V�Ȃǂ�����Ă��āA�R�}�Z��H���A�����ăT�r�L�j���H���Đj�Ɋ|����B�����j����蓦���悤�Ƃ��铮���͊Ƃɓ`���Ƃ��㉺�ɗh��A�Ƃ�����ɂ���������B
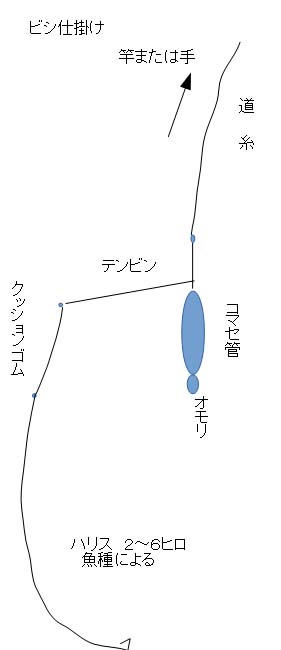
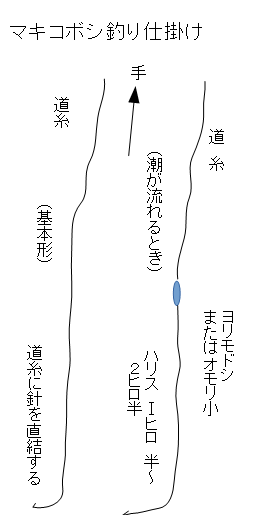
�����̍����ď�ł́A���������ɉj���܂���ċ����ʼna��H���̂ŁA�������킹�Œނ�邪�A�}�L�R�{�V�ނ�̖{�̂́A�������������ċ��̐H���������A�����~�܂��ĐÂ��ɉa��H���~��ɔ��������B�������a�ɋߕt���m���߂Ă���H�����߂ł��낤�A�[�a�j�ɂ͂��܂�ɐH�����Ȃ��B�܂��A�V����I���������Ă�����A�Ƃ��g���ނ�ł́A�ӂ��A�����a�ɐG�ꂽ�����̏����ȓ�����͂킩��Ȃ��̂ŁA�����Â��ɉa��H���A�j��f���o���Ă��܂��ꍇ�ɂ́A�ނ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������A�T�����ڂ��ނ�ł́A�����Ɛj�̂������ɉ�ݕ����قƂ�ǂȂ����߁A�����ȓ����肪�X�g���[�g�ɓ`���A���������Ă���w��Ɋ�������B
�����悭�s���ꏊ�ł͂R�O�Z���`����S�O�Z���`�A�Ƃ��ɂ͂T�O�Z���`�������^�̃A�W���ނ��B�d�|����������ăR�}�Z���T���Ă���ƁA�����Ă��A�R�c���Ƃ��J�T�b�Ƃ������O�����肪����B�g�ɂ��D�̏㉺���A���邢�͕��������ɓ����邱�Ƃɂ���Ă��A�w�ɕω����������邪�A�����G�ꂽ�Ƃ��ɋN����ω��͑S���Ⴄ�B���̓����肪�o��Ǝ��͋��̓�����m��A�u��[���v�ƋC�������������߁A�����Ɗ��҂̉���������B�A�W�̏ꍇ�A�O������ɑ����ăJ���J���b�A���邢�̓J�T�R�\�b�A���邢�̓v���v���b�Ƃ��������肪����B���ꂪ�Ȃ�Ƃ������Ȃ�����^����B
�A�~�G�r�Ȃǂ̃R�}�Z�Ɋ���Ă�����A�W�́A�~��͓��ɁA�h���a�i�I�L�A�~�A�Ƃ��Ƀ{�C���j����C�ɓۂݍ��ނ̂ł͂Ȃ��A������Ƃ��Ė�����������A�[���ۂݍ��܂��A���悾���ł���Ԃ����肷��悤���B�����Ă��̂��ƂŖ{�i�I�Ɍ��̒��ɋz�����݁A�a�����ݍӂ��A�ٕ��ł���j��f���o���悤���B
�Ƃ����̂́A�܂��A�J�T�R�\�A���邢�̓��]���]�A�v���v���Ƃ����ׂ��������肪�����Ƃ��A�����Ɏ��������Ă������۔����A�����̎h���a���A���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA�ŏ��̓�����ł͉a�����̒��ɓ���Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B�����Ă��̃��]���]�A�J�T�R�\�̂܂ܑ҂��Ă���ƁA�₪�ĉa�͂Ȃ��Ȃ�A��j���A���Ă���B�����ł��ׂ̍��������肪�ł��獇�킹�̃^�C�~���O���v��B�͂����肹���A�f���I�ȃJ�T�R�\�̓����肾���ŁA�����킹�悤���A���ɍ��킹�悤���Ɩ����B�J�T�R�\�A���]���]�̂��ƃW���[�b�Əd���Ȃ邱�Ƃ�����B����͉a�����̒��ɋz�����܂ꂽ���ŁA���킹��Ƃ����Ă��|����B�J�T�R�\�A���]���]�������ꍇ�ɂ́A�W���[���o�Ȃ��Ƃ����킹��Ɗ|���邱�Ƃ�����B�������킹���A��������������������Ə�ɂ����邾���Őj�|�肷�邱�Ƃ�����B�����z�����݂��������a��������Ɗ����ċ}���Ō����Ƃ���̂��낤�B
�C�T�L�͂T�`�U������ď�ɒނ��B�ŏ��̒Z��������ł́A�܂��{�i�I�ɐH���Ă��Ȃ��炵���A���킹���Ă��قƂ�ǐj�ɂ͂�����Ȃ��B�Q��ڂ̂�����Ŏh���a�����ɓ����Ɠ����ɉa���Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�Q��ڂ̂������҂��A�f�������킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Â��ɐH���Ƃ�������A�W�������Ƃ����d�݂�������ꂽ�獇�킹��B�������ȓ������W�������Ƃ����d�݂̕ω��Ȃǂ��킩��悤�ɂȂ�ɂ́A��͂�A�o��������悤�ŁA���͂R�`�S�N���������悤�Ɏv���B
�I�L�A�~�̐��ς͖���������Z���Ȃ̂ł��낤�B��C�ɓۂ݂��ނ��Ƃ������B�����Đ��̃I�L�A�~�͂��炩���ȒP�Ɏ���Ă��܂��B��������Ă������Ƃ��킩�������u���C�����A�Z�����B�{�C���͐H���̂Ɏ��Ԃ�������A���킹�ɑ����̗]�T������B���������킯�Ŏ��͐^�~�ȊO�̓{�C�����g�����A�����ꏏ�Ɏh���B
�A�W�A�C�T�L�A�^�C�ňقȂ邪�A�{�C���̏ꍇ�A�Q��ڂ̃J�T�R�\�ō��킹�Ă��j�|�肹���A�R��ڂ��S��ڂɍ��킹��̂��悢�Ƃ������Ƃ�����B�������A�Q��ڂ̃J�T�R�\�ʼna���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����B����ڂō��킹��̂��悢���͂��̓��ɂ���ĈႤ�B
�a���Ȃ��Ȃ�̂ŋ�������炵���̂����A�Ȃ��Ȃ��͂����肵�������肪�łȂ����Ƃ�����B����Q�`�R�Z���`�������āu����/�����v���A���邢�̓q�W���Ȃ��L�����ĂP�O�������Q�O�����قǂ������グ���艺�����肷��ƁA���ꂪ�u�U���v�ɂȂ�悤�ŁA�K�c���Ɨ�����A�X�b�Ɖa��ۂݍ��ނ͂����肵�������肪�o�A�Â��ɍ��킹�邾���Őj�|���肷��B���̓����̓��ŐH�������Ⴄ�B
�������āA�����肪�o�Ă���A���킹�ċ���j�Ɋ|����܂ł́A�����ĂQ�O�b���R�O�b�̊ԁA�w��ɒ��ӂ��W�����ē�������Ƃ��Ă���Ƃ��ɁA�X�����������A�ْ�����B���̂Ƃ��ڂ͊J���Ă��Ă��������Ă��Ȃ��B�n���ł̓}�L�R�{�V�ނ���o�N�_���ƌĂԁB�n���̃x�e�������u�o�N�_��������ɂ͖ڂ͂���Ȃ��v�ƌ��������Ƃ�����B�ƒނ�ł͂Ȃ��A�w�œ���������}�L�R�{�V�ނ�ł́A�����������Ă���Ƃ��ɂ͂���͎����ł���B
���ꂾ���ł͂Ȃ��B�����������Ă���Ƃ��ɂ́A�����l���Ă��炸�A���͋���ۂł���B�܂��g�̉����ۖ���U�������Ă���͂��ł��邪�Ȃɂ��������Ȃ��B����ɁA���̒ނ���n�߂��P�N�قǂ́A�w��Ŋ�����͂��̓����肪�u�J�T�R�\�v�Ƃ��u�v���v���v�Ƃ��u�J���J���v�ƁA�n�b�L���Ɓu�������������v�B�s�v�c�ł���B�������A�ŋ߂͉��͕��������A�w��̊��G�����ɂȂ����B���A�Ƃɂ����A���̓�������Ƃ��Ă���Ԃ́A�ْ��Ɗ��҂́A���N���N�A�h�L�h�L������y�ɂقƂ�NJ��S�ɐZ�肫��B
����������A�Â��Ɏ�����J���ċ������A�D���Ɏ�荞�ށB���[���T�O������Ƃ���ł́A�悭�ނ��Ƃ��ɂ��A�d�|���𓊓����ċ����|���Ēނ�グ��܂łɂP�O���߂�������B�������ĂR�O�Z���`�ȏ�̃A�W�Ȃ�Ύ��͂P�O�C�ȏ�ނ�Ώ\�������ł���B
�}�_�C�͓~�̒ᐅ�����������A�����肪�͂����肵�Ă���B�Ƃ��Ɏ�̂Ђ��̂��̂���R�O�Z���`�ȉ��̂��̂̏ꍇ�ɃK�c�[���ƂЂ�������悤�Ɍ��������킹�ŐH�����Ƃ��������A����ȏ�̌^�ɂȂ�Ƃ������ĐÂ��ɐH���B�A�W���Ǝv�������ȓ�����ŃR�c���Ɨ��āA���̃J�T�b�ō��킹��ƃO�[���Əd���Ȃ�B
�i���́u��S�́v�̃t�@�C���̃n�C�p�[�e�L�X�g�����s���Ă���2016�N��2���A�ق��̋������҂ł��Ȃ������̂ŁA�^�C���悭�ނ��A���[�R�O����̐ނ��Œނ�������B3�`�S���Ԃ̒ނ��20�Z���`����40�Z���`���܂ł̃^�C��6�`7�C�ނ����B�^�C�����ނꂸ�A�������Ȃ����^�~�����炵�������Ȃ��B���̂Ƃ��͈����͂����肵���A�^���͂łȂ������B�J�T�b���Ȃ��{���ɂ������ȃ��������b�Ƃ������������荇�킹�Ēނꂽ���A���邢�͂܂����������������Ȃ��������i�����҂�����d�|�����グ�邱�Ƃɂ��Ă���̂Łj�d�|���������悤�Ƃ��ĐH���Ă��邱�Ƃ��킩��A�ς��Ƌ��������Ċ|�����B�j
�傫���͍��킹���u�Ԃɂقڂ킩��B���͕K������B�����炢�Ȃ�P�q�����Q�q���i�Q�`�R���j�A�����Ƒ傫���Ƃ��ɂ͂����Ƃ����Ԃ��Ȃ��S�`�T���˂�����B�����ꂳ���邽�߂Ɏ��̓u���[�L���|���Ȃ���o�����A�����傫���ꍇ�A�u���[�L�̊|�����������Ǝ�ɂ₯�ǂ����č����Ղ����B
���͏��������Ď~�܂�̂ŁA�~�܂����玅����J��B���͔��]���Ă܂�����B��������J��Ԃ��ĕ�������B�����~�܂������ɂ͂ӂ����������������Ď�����J�邪�A���������Ă���Ƒ��肪�C�����Ȃ��悤�Ƀe���V������^�����ɏ�����������J��ƁA�S������R�ɏオ���Ă��邱�Ƃ�����B����������肩���łłT�O�Z���`����V�O�Z���`���x�܂ł̃}�_�C���P���ɐ��C�ނ������Ƃ����������B�������A�|������A����I�ɉj���ꎅ�������o��������ŁA�~�߂��Ȃ�������x���|���A������Ă���B����͎d�����Ȃ��Ƃ�����߂Ă���B
����j�|�肳���Ă��瓹������J���ċ�����Ƃ��ɂ��傫�ȉ���������B�啨�̏ꍇ�ɂ́A�D�̒��Ɏ�荞�݁A�j���O���Ƃ��ɋ����Ŏ肪�k���邵�A�u��[���I������[�I�v�ƃK�b�c�|�[�Y����肽���Ȃ�B
�����A���܂ɂ����ނ�Ȃ��啨�̏ꍇ�͕ʂƂ��āA�����́A��͂�A����j�Ɋ|�����u�Ԃ��A�S�̂Ȃ��ʼn��Ƃ����ԏu�Ԃł���A�����肪�o�n�߂Ă��狛��j�Ɋ|����܂ł̐��b�ԁA�����Đ��\�b�Ԃ��ْ��ɖ������ő�̉��������鎞�ԂȂ̂ł���B
���̂悤�ɁA����������A�����|����܂ł̎��Ԃɍő�̉���������Ƃ����̂́A���Ԃ�}�L�R�{�V�ނ���L�̎���ɂ�邱�Ƃł��낤�B�������A�����|���邱�Ƃ����߂Ȃ��ނ�͂��肦���A�܂������|�����i���Ƃ��킩�����j�u�Ԃ́A���ׂĂ̒ނ�l������������u�Ԃ��낤�B������A������̂Ȃ��ނ�́A�ނ�Ȃ������A�ނ�ɂȂ�Ȃ������ނ�ł���B�����肪����A�����|���āi�����|���āj�����A�ނ�̉����y���ނ��Ƃ��ł���̂ł���B����͂��ׂĂ̒ނ�ɋ��ʂ��Č����邱�Ƃł���B
���a�����̎��l�Œނ薼�l�̈�l�A�����y�V���i1890�|1942�j�́w���S�ސS�x�Ƃ����{�̂Ȃ��ŁA����������A���킹�A�����|���Ċ�Ƃ��ɁA�u�����[�r�̊��o�v�Ƃ��u�@�x���v��������ƌ����B
�u�ޓ��̐^��---�Ɛu�˂���ƁA-----���������������ɂЂ�����A�����ɂ��邩�Ƃ����ƁA�ǂ����ނ�l�̗����s���Ƃ���́A���̓��������ʊ��o�̔����ɂ���悤�Ɏv���B�܂�A���̃A�^���A���͂Ƒ��������A�܂��͂����Ƃ��c���I�ȐG�o�ɂ���悤�Ɏv����B������܂���Ƃ���B�����Ƃ���B���邢�͑�햡�ƌ����Ă��悵�A�����͂Ȃ����������ƌ����Ă��悢�B-----���V�ꔯ�̊Ԃɟ��i�����j����Ő������C���Ƃ����Ă���Ă��鋛�M�A---���̈����͂Ƃ������̂͐���荜��Z�����ăV���k�}�}�B�u�S�v�ł��낤�l�g�ɉ�����B�����Ƃ��āA�����Ƃ��āB�d���y���A�d���̔@���A�d�g�����܂炸�g�ɉ����閡�Ƃ������̂͌��O�̌��A�H�Ȃ�A�܁k���F���邭�P���l����A���o��₵�����\�̗₽���ԉł���v�B
�܂��u�����������āA�O�O�Ɨ�����A�c�c���Ƃ������Ă���u�Ԃ̖@�x���A���̃A�^���Ƌ����܂����������̂��̂Ƃ��Ă��܂��܂ł̉��b�ԁA���ꂪ�ދZ�̐[���̖ړI�ł��蓩�����Ȃ̂ł���B----�u�ނ�͍Ō�̓��y���v�ƈ����B�S�����B���̖@�x���ɔN��͖����A�܂��S���I��ʂ�����悤���Ȃ��B�����[�r�̊��o�C���̃A�^���͈�_�������Ă��̏u�Ԃɂ���v�Ƃ������B
�����͎��l�炵���A�A�^���́A�u�g�[���ƌy���A�Ƃ�Ƃ�ƁA�݂�݂�A�����A�����ƁA�Ă��Ƃ���Ă���----�v�Ƃ��܂��܂ɕ\�����Ă���B
�����͓����肪�^����u�@�x���v�܂苭�����y�ɂ́A�u�N��͖����܂��S���I��ʂ�����悤���Ȃ��v�Ƃ����A�u�����v�A�u�G�o�v�A�u���o�̔����v���ƌ����Ă���B�}�L�R�{�V�ނ�ł͓�������w��Ɋ����A�ْ����A�킭�킭���A�������A����������B
�������A������̉��͎w��̃}�b�T�[�W���Ă���Ƃ��Ɋ�����C�����悳�Ƃ͑S���ʂł���B�������w�����̑����̕��ʼn����t���邩��Ƃ����āA�w�͋C���������킯�ł͂Ȃ��B���̑傫���ɂ���Ă͂Ђǂ��ɂ����Ƃ�����B��x�A���킹�Đj�|���肳�����u�Ԃɑ�^�����˂�����A�Y�V���Ƃ����育�����Ɠ����ɁA�����Ŏw��(�P�`�Q�~���̐[���Łj�X�p�b�Ɛ�A�������ɂ݂ɏP��ꂽ���Ƃ�����B���̂Ƃ��͑傫�ȁu�g�̓I��v�Ɉ��|����Ă��܂����B��яo�čs�����̖��C�Ŏw���Ă��č����Ȃ������Ƃ͉��x������B
�ŏ��̏����ȓ�������������Ƃ��̉��A�����|�����u�ԂɊ�������́u���������I�v�A�u�����|�����I�v�Ƃ������f���琶���鐸�_�I�ȉ��ł���B���̉��͈��̏������A�ڕW���B���ł����Ƃ��A���邢�͂Ȃɂ����v��ʂ�Ɏ����ł����Ƃ��Ɋ�����̂Ɠ����A���_�I�Ȋ�тł���B
�����A���̈Ӗ��ł́A���̉��̓S���t�ŃV���b�g�����o�[�f�B�p�b�g�����܂����Ƃ��i���͎��̓S���t����������Ƃ͂Ȃ��̂����j�A���j��H�ō�肽�������{�I�����܂����������邱�Ƃ��ł����Ƃ��A���邢�̓L�m�R�̂�ŐH�ׂ����Ǝv���Ă����L�m�R�������邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ɋ�����A�u������I�v�A������������I��Ƃ�������������тƓ���̉��ł���B�قȂ��Ă���̂́u������v�A�u���������v�Ƃ������f�������N�����M���Ȃ������ł���B�S���t�ł̓{�[�����z�[���̒��ɗ����Ă��Ă�u�J���[���v�Ƃ������ł���A���j��H�ł͐��@�ǂ���ɂ�����Ƒg�ݗ��Ă�ꂽ�{�I�̒����`�̌`�ł���A�L�m�R�̂�ł͎�̂Ђ�̒��̃L�m�R�̌`��F�⊴�G���낤�B�����Ă��ꂼ��̗V�сA�X�|�[�c������l�ɂ́A�������u�����v�̃V�O�i���Ƃ��ēǂݎ��A�m�I����_�I�\���A�g�g�݂��p�ӂ���Ă���B
���㏬���ƁE��썁�l�Y��S���t�l����Ƃ������M�i���Q�V���P�P.�P�O.�Q�T�A�u�l�G�^�v�j�́A�u������V���b�g��Ȃ�Ă��̂͂قƂ�ǂȂ��B���s���d�˂Ă��A���P���������ƂŐl���݂Ƀz�[���A�E�g�ł���̂��B---�ڂ̑O�̈�łɏW�����āA���̂Ƃ��ɂł��鎩���̋Z�p�őO�ɔ���A�r��o���J�[�ɓ����Ă��A�ߒQ�ɕ�ꂸ�A���Ɍq����V���b�g������B---�ł����s����B���܂������Ȃ�����ʔ����̂�������Ȃ��B�v�Ə����Ă���B
�Ō�̃p�b�g�����܂������ɂ����u������I�v������̂łȂ��A���ꂼ��̃V���b�g�ɢ������I�������悤�ł���A�r��o���J�[�ɓ����Ă��A���Ɍq�����Ƃ��ł���B�����ǂނƃS���t�̊y�����͔��ɕ��G�ȓ��e�������Ă���A��O���̎��̓S���t�ɂ��ăs���g�O��̂��Ƃ������Ă���̂�������Ȃ��B�����ŁA�ނ�̉��́A��͂�A�P���ł���Ƃ��v���B�����H���Ă��Ȃ���A�i����ڂ�����ɂ��Ă��j�ǂ��ɂ����������Ȃ��B�Ȃɂ�����P��s��������Ƃ��ł���킯�ł͂Ȃ��B
�}�L�R�{�V�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�w�Ɋ����铖����^���M�܂蓹���̐U�����u�����v�̔��f�̌��ł���B�����|�����Ă���A��������J���Ƃ��ɁA���邢�͊Ƃ������ă��[���������Ă���Ƃ��ɁA�������鋛�̈������܂߂čl���悤�B��������J���Ă���ԁA���邢�̓��[���œ�������������Ă���ԁA�u����ނ����v�Ƃ����u���f�v���ێ�����A�u��������v�u�ނ������v�Ƃ������ɖ����������������B���ꂪ�ނ���L�̉��ł���B
�������A���̂悤�ɍl����ׂ��ł͂Ȃ����B���̓I�ȉ��Ƌ�͐l�ɂ�肻�̊������₻��ɑ��锽���͏������قȂ�Ƃ͂����A�l�ԂƂ�����ɂقڋ��ʂ��Ă��邾�낤�B���Ƃ��Α̂̕\�ʂ��������̂œ˂����Βɂ݂������A���ꂩ�瓦��悤�Ƃ���B�}�]�q�Y���͋H�ȗ�ł���B�D�������ł�ꂽ��A�}�b�T�[�W���ꂽ�肷��C�����悢�B�����Ă���͎q�ǂ��ł���l�ł��A��̓����ł���B�l��▯���ɂ��Ⴂ�����قǑ傫���Ȃ��Ƒz��ł��邾�낤�B�l�ԂƂ�����ɂقڋ��ʂ̂����g�̓I�ȉ��Ƌ��y��ɂ��āA�D�݂̌����ƂȂ�DNA�����݂������e�������邩������Ȃ����A�����ɁA���邢�͎�Ƃ��ē���̕����I���̂Ȃ��Ŋw�K����邱�Ƃɂ���āA���_�I�ȉ��Ƌ�̊��������`������A�������A�K�����A�܂��l���ށB���w���D�����X�|�[�c���D�������y���D�����A�ǂ�ȃX�|�[�c�i���o���{�N�V���O���j���ʔ����Ɗ������A�ǂ�ȋȁi���̂��W���Y���j���Ր��ɂӂ�邩�A�D�݂݂͂ȈႢ�A�q�ǂ��Ƒ�l�ł͍D���ȁu�V�сv�͈قȂ�B
���M�^�����肪�^���銴�o���A�l�ԂƂ�����ɋ��ʂȂ��̂Ƃ��āA�q�ǂ��̂Ƃ�����A�͂��߂��������y������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B����́A�͂��߂͉��ł���ł��Ȃ��A�Ȃ��߂����畆���o�ł���B�����A���̊��o���A��߂������������炩�ɂȂ����Ƃ��A�s���ɑł������ĂȂɂ��𐬂��������Ƃ��A�蕿�𗧂ĂĎ��͂���^�����Ƃ��ȂǂɊ������тɗނ����A���_�I�ȉ��A�K�����ƌ��т����ƂŁA�u�����I�v�A�u�|�������I�v�u�����Ă�A�����Ă�I�v�̉��������N�����M���ɂȂ�̂��낤�ƍl������B
�h�g���D�̏ォ�猩����������L����\�ʂ��Ă��邾���ŁA�Â��C�̒��͌����Ȃ��B���߂Ă̒ނ�ł��傫�ȋ����|�������Ƃ��悤�B�������̂̒m��Ȃ����̂������|����A�����������̎��Ƃ�D����낤�Ƃł����邩�̂悤�ȕs�C���ȓ���������B������Ƃ��A�ْ�����B�������C�̒��œ����������ĊƐ���Ȃ��A�����Ƃ𗧂Ă�̂ɒ�R����B����͏��w�Z��w�N�̂Ƃ��ɂ͂��߂Ē�h�ނ�ɘA��čs�������q���A�C���V���ނ�Ă����Ƃ��ɂ́A�M���A�M���A�����Ȃ���ނ��Ă����̂ɁA�}�ɖق荞�ݕK���̌`���ŊƂ�����œ������Ƃ��Ȃ��Ȃ������̔ނ̐S�̒��̏�i��z�����ĕ`�������̂ł���B���Ɏ�`���Ă�����Ēނ�グ���̂͂P�T�`�U�Z���`�̃��W�i�ł��������A�ނɂƂ��ẮA�\�z���Ȃ������啨�������B
�͂��߂đ啨���|�����Ƃ��ɂ́A�C�̎ア�ЂƁA���a�Ȏq���͋����Ɗ����A�������������ɂ͎�𗣂��Ă��܂������Ǝv���ꍇ�����邾�낤�B�������A�ꏏ�ɗ����A�o���̂���F�B��e�ɗ�܂��ꂽ���`���Ă�������肵�āA�K���Ƀ��[�������B���\�b�̐킢�̂̂��A�C�̒����炫�炫������������p�������A�����ĂԂ��Ԃ��Ƒ̂�k�킹�Ȃ��甲���グ���A�h�g��̏�ɓ]�������B�댯�Ȑ����łȂ����Ƃ�m��ق��ƈ��g���A���邢�͋����Ō��Ēm���Ă��鋛���A���A�����ł͐����Ă��Ă҂�҂˂�̂ɋ����A�������A�u�悭������v�u�������A�������v�Ƃ܂��̐l�ɗ_�߂��A�����̐������������Ƃ��ւ炵�������A�����Ċ�ԁB
�u�J�k�[�C�X�g�v�̖�c�m�C�́w���ᖟ�V��G�L�x�i�V�����ɁA1988�j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�A�����J��Z���i�o�z���̎�ނŃA�����J�ɑ؍݂��Ă����Ƃ��A�R�����h��������~�߂č��ꂽ�l�H�̊ݕӂŒނ�������B�T���炢�̏��̎q��A�ꂽ���l�̉Ƒ����ނ��Ă����B�---���̎��A���̎q�̗��ĂĂ����Ƃ��|��ăX�[�b�Ɛ���𑖂�o�����B�������������̂��B���ɔ�э���ŊƂ����܂��A�グ�悤�Ƃ��邪�A�Ƃ͋������Ȃ�A�Ԃ�Ԃ�Ƃӂ邦���B���炭���Ԃ����Ăӂ���Ă������̎q�͂Ƃ��Ƃ������o�����B����������A�������������ς��Ă����̂悤�I�---�j�͎���悤�Ɍ������B������ŏグ��B�͂����ς������ς�B���Ȃɕ������Ȃ����I����̐����ƂƂ���ɏ��̎q�͕ϐg�����B����܂ł̊Â����ꂽ�Ԃ�V�I�ȗl�q�͏����A���R�Ƃ����\��ɂȂ�A�E�A���ɂ�ꓮ���Ƃ������Șr�ł�������͂݁A���Ɗi�����n�߂��̂ł���B----�����Y���Y���Əオ���Ă����B�T�O�Z���`���炢�̌�ł���B�u�������A���炢�I�v�܂��̑�l�͕�������ď��Ȃ���A�ޏ��̓��u���ق߂���B
���̏��̎q�ɂ�����x�ނ�̌o�������邱�Ƃ́A���̏���Ƃ�����o�����Ƃ��ɁA��э���Œ͂Ƃ����Ƃ���ł킩��B�������u�T�O�Z���`�̃R�C�v�̈����͏��߂ĂŁA�s�����狃���o�����B�����A�ޏ��͕��e�̗�܂��ɂ�肱���ނ�グ�A�����Ď��͂̑�l�����ɂ���ė_�߂�ꂽ���Ƃ�ʂ��āA�啨�̢�育������A�����̉����o�����邱�Ƃ��ł����̂ł���B��l�����̔����̂������ɂ���ẮA���̏��̎q�́A���̎p�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A�����C���̈������̂Ɉ����ς�ꂽ�Ƃ����s���Ȍo���A���邢�͒ނ�グ�Ă��P�ɔ�ꂽ�����̂܂�Ȃ���J�������Ƃ����o���������ƂɂȂ������낤�B
�ނ肪�D���ɂȂ�ɂ͂��������ނ�̌o�����K�v���B�����������o�������邱�ƂŁA�l�͑̂Ŋ�����u������v���邢�͋��̈��������Ɗ�����悤�ɂȂ�B�畆�Ɋ����鐶�ς̊��G���͂��߂�����ނ̂ł͂Ȃ��B���̐��ς̊��G���u�����|���������Ɓv�A�u��������ɂ�����邱�Ɓv�̐M���ɂȂ邱�Ƃɂ���āA���ށA���邢�͉��Ɗ�������悤�ɂȂ�̂ł���B
�ނ�ɂ����ċ��M���L���b�`���Ċ�������́A�ނ���I������ŋ�������Ȃ��犴������A�ޗF�Ɏ�������Ƃ��̉��A�v���o���A���L�ɂ��Ȃ��犴������Ƃ͑S���Ⴄ�B�����̉��͎w��r�Ɋ�������̂ł͂Ȃ��B�����͏����ɐ��_�I�ȉ��ł���B�����A������Ɗ|�������̈����̉��y�͒��ڎw��r�Ŋ�����A�g�̓I�ȉ��ł���B�������A�w�Ŋ����鎅�̐U���A�r�Ŋ�����Ƃ̕ω����邽��݂��s�C���ŕs���łȂ��̂́A���ꂪ���M�ł��苛�̈������Ƃ������f�������o������ł���B����́u���������ʁv���o�ł��邪�A�w��r���L�����Ă��鋛���炭�铖���肾�Ƃ킩���Ă��邩��y����������^����̂ł���B���̂悤�Ɍo����ʂ��Č`�����ꂽ�m�o�̘g�g�݂ŁA���̓����肠�邢�͋��̈������Ƃ킩��w��̊��G�A���o�i�ƒނ�̏ꍇ�ɂ͊Ƃ̋Ȃ���j�������A���a�����̎��l�����y�V���������A�u�ޓ��̐^���v�A�u��햡�v�ł���A�ނ�̉��ł���B����������̈������܂߁A�����肪���ׂĂ̒ނ�ɋ��ʂ���ނ���L�̖��͂Ȃ̂��Ǝ��͎v���B
�܂��A���̓���������A���킹�̃^�C�~���O���v��Ƃ��납��ْ��Ƌ����ɖ��������Ƃ̂����Ђ����n�܂�B�����|�����u�Ԃɋ����̈�̎R�ꂪ����A���Ƃ�����B��������Ŋ����Ȃ̂ł͂Ȃ��B�����|����̂͑D�̂قڐ^���A�R�O������V�O���قǂ̊C��ł���A������J���ċ��������A��荞�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����|��������ْ��Ƌ����������B
���͐j�Ɋ|�������獇�킹�̃V���b�N�ɋ����Ė\��A�������邱�Ƃɒ�R���A�K���ɉj���B���̈����͂̋���A�n���X�̑����ɉ����āA�����̎�J�������������K�v������B
�A�W�͔�r�I���̃y�[�X�ʼnj���A���̗͂Œ�R���Ȃ���オ���Ă���̂œ�����������蓯�����x�Ŏ�J��悢�B�������^�C�̈����͑傫���ω�����B�����炪����������������J�������R����B�r���Œ�R����܂�A�ߊ���ė����Ǝv���ƍĂь��C����߂�������ς��ē˂�����B�����������Ƃ��ɂ�����x�j�����Ă��Ȃ���A������邩�j�������L����ĊO��邩����B�ނ�l�p��ŁA�o����A���邢�̓o�������ƂɂȂ�B
�ƂƁA�h���b�O�i�����������������ƃ��[�����t��]���Ď��������I�ɏo�鑕�u�j�̂������[�����g���ꍇ�ɂ́A�Ƃ̒e�͂ƃh���b�O�@�\�ɂ�苛�̋}�ȓ����͋z������A�Ƃ��ɉ������Ȃ��Ă��A���[�����Ď������������ŋ����Ƃ肱�ނ��Ƃ��ł���B��������ނ�ł͎���g���̂̓����őΏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i��荞�ݕ��ɂ��ẮA��ꕔ�u�ނ�v�u��P�́u�}�L�R�{�V�ނ�v��ǂ�ŗ~�����B�j
�������āA�����o������A��J������A�������������A���Ԃ��|���ċ����A�C�ʂɕ���������Ō�ɋʖԂŋd���đD���Ɏ�荞�ށB�A�W�Ȃ̂��^�C�Ȃ̂��͓r���̈���������e�Ղɔ��f�ł���B�������A���̂ǂ���ł��Ȃ����Ƃ�����B�����ꏊ�łR�O�Z���`���z�����^�̃J�C�����A�E�}�d���n�M�A�C�g�����A���W�i�A�V�}�A�W�A�C���u�_�C�A�S�O�Z���`�ȏ�̃E�X�o�n�M�A�T�O�Z���`���z����`�k�i�N���_�C�j�A�U�O�Z���`���z����R�V���E�_�C�A�U�O�Z���`���x�̃n�}�`�A�Ȃǂ��H���ė��邱�Ƃ�����B�����܂��ɂ͌����������A�ŏI�I�ɂ͊C�ʂɋ�������܂ł͂킩��Ȃ��B�}�_�C�͂�������イ�ނ邪�A���̑傫���́A�������Ă݂���r���̈���������z�����Ă����̂Ƃ͂����Ԃ������Ƃ������Ƃ��Ƃ��ǂ�����B�v���Ă������͂邩�ɑ傫���������Ƃ����邪�A�Ă������Ă���͂��Ȃ�傫���Ǝv���Ă����̂ɂS�O�Z���`���Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����B�����C�ʂɕ����u�Ԃ��ނ�̊y���݂̈ꕔ�ł���B
���C���Y�́w�t���C�t�B�b�V���O�^�́x�ŁA�ނ�́u�X�q����e�����o���Ƃ��ɖ��키�v���@�Ɠ��l�̌o�����Ƃ����Ă���B�u�����̋��͉\�����̂��̂ł����Ȃ��B������������ł��Ȃ���������邩�ǂ������܂������킩��Ȃ��B�ނ莅�Ɍ��т��Ă�����̂ɋ���H�������A�������̐��E�Ɉ������荞�ނ��Ƃ́A�_��̗̈悩�猻�����E�ւƂ����̐�������a�������邱�Ƃɂ�����邱�ƂȂ̂��B����͈��̑n���Ȃ̂��B----�|�ʐ^�ƃL�e�B�E�s�A�\������B���Z���g�́A���͌����I�Ȑ��E�Ƃ͈قȂ鎟���ɂ�����̂��Ɛ錾���A���̎��o�I�o����`���悤�Ɠw�͂��Ă���B�����āu���͕ߑ������������ӎ��̐��E��p�j���閲�Ɏ��Ă���B����߂炦�邱��---�ɂ͖锼�̖���̒��̈Â��傩���̖������ݎ��A�߂��߂��Ƃ��ɂ��݂��߂�A���̋����̊��o������v�ƕt�������Ă���v�Ə����Ă���B
�����A�j�ɂ��������������̂����̂��ƂŐ��ʂɕ����яオ��Ƃ��A���̖��@�Ɏ������o���������Ɋ�����B����_��̗̈悩�猻���̐��E�ւƈ����o�����̂��Ɗ�����B���̂悤�Ɉَ����̐��E���牽�����ˑR����邱�Ƃ��^����A���p���l�̋����̊��o���ނ肪�^������̈ꕔ�ł���B
�w�J�̓��̒ގt�̂��߂Ɂ@�ޕ��w�R�T�̌���x�i�c���f�E�p�E�i���^�J�����ҁA���^���r��A������Ђs�a�r�u���^�j�J�A�P�X�W�T�j�̂Ȃ��́ADavid�@Herbaert�@Lawrence�́u���v�́A�u����A��������^����Ȃɂ�����������v�ł͂��܂�A�P�W�T�s�̎��ł��邪�A���̏I���ɋ߂��ӏ��ŁA
�u�ڂ��݂͊ɗ����Đ��`�����ސl�̂悤��
�ڂ��̑��݂̋��E�ɗ����A���̌���������
����ƁA�O�̂ق��̐��E�ɁA��������̂�������̂��v
�Ƃ������t���łĂ���B
�܂��A�A�[�T�[�E�����T���u�ފƂƎ��v�Ƃ������ɂ�
�u���͕ʂ̐��E�ɏZ��ł���̂ł����āA���̐��E�ɂ���ނ�l�́A����Α�l�����A�s�m�̐��E�ɒގ��𐂂��̂ł���v
�Ƃ������t������B
����Ԓ��͊ȒP�ɂ͐G�ꂽ��A�߂炦���肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����A���̖��������Ƃ��ł��A�����Ă��p�����邱�Ƃ��ł���B���͐l�ԂƂƂ��ɂ��̐��E�̋�C���z���Đ����Ă���B�������܂��Ȃǂ��āA���x�����_�ɌĂяW�߂邱�Ƃ��ł���B�J���X��X�Y���͖_��U�����𓊂����肵�Ēǂ��������Ƃ��ł���B���͋߂��ɂ��āu�ڐG�v���邱�Ƃ��ł���B�l�ԂƂ͈�����d���łł͂��邪�A���͂��̐��E�Ɋm���ɑ����Ă���B
�Ƃ��낪�A��������ł���C���́A���[���P�O��������A���邢�͂Q�`�R���ł��A�����A����͌������A���̎p�͌����Ȃ��B���̂悤�ɐ����������Ă��邱�Ƃ��Ȃ��B�C���̕\�ʂɂ͂ӂ�邱�Ƃ��ł��邪�A��������������͂�����̐��E�ƂȂ�̂Ȃ�����Ȃ��B
�C���ɒ����ԁA�Ƃ����Ă��P���Ԃ������炾�낤���A���낤�Ƃ���A�d���A�N�A�����O��g�ɕt���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Đ���Ă����������T�O�����x�܂łł���ȏ�̐��[�ɂȂ�ƌ����͂����^���ÂŁA����ɂ͓��ʂ̌P������K�v������悤���B
�C�̒��ł̊����̍���́A��^�̃��P�b�g�ɂ��Ȃ���s���Ȃ�������̏�̉F���ł̊������F�����𒅂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ƕς肪�Ȃ��B�[�C�Ƃ��Ȃ�A���q������O�֏o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�C(�C��)�͗���̐l�Ԃ̐��E����f�₵�Ă���̂ł���B
�Ƃ���Ȃ�f������ŁA�����[����A�N�A�����O�𒅂��A�������ĊL���̂邱�Ƃ͂ł���B����������߂܂��邱�Ƃ͎�ɖ�(�ʖ�)�������Ă��Ă��A�܂��ł��Ȃ��B���͐����Ŏ��R���݂ɍs���ł��邪�A�l�Ԃ́A�d����낢��g�ɕt���Ă��邩�̂悤�ɁA�̂�̂�Ƃ��������Ȃ��B
���t�͖Ԃ��Ă��d�|���ċ������B�������A���t�ȊO�̐l�Ԃ��A����ߊl���悤�Ƃ���A��ʂɁA�ނ�̎d�|�����g�������Ȃ��B�܂��A�Ԃ��Ă͂������ɋ�����邱�Ƃ͂ł��邪�A�d�|�����Ԃ��Ă͒u���ꂽ�܂܂ŋ����ނ�̂ق�����ԂɈ����������Ăɓ���̂ł����āA�����l�͊C�̏�ő҂��A��莞�Ԍo���Ă�������グ�Č���̂ł���B���t�����Əo��̂͊C��A���邢�͗���ł̂��Ƃł����āA�C�̒��ŋ���߂��邱�Ƃ͂���ɂ��ł��Ȃ��B
�ނ莅�Ɛj�Ƃ����d�|���́A�C���邢�͐�̒��ɐl�Ԃ��u���L�v���A�l�Ԃ������Ɂu�����āv�A���Əo��A����߂���قƂ�ǗB��̕��@�Ȃ̂ł���B�i�u�قƂ�ǁv�ƌ����̂̓��X�␅���e�����邩��ł��邪�A�������A�����̓�����g�����Ƃ͎E�����ƂɂȂ�A�u�߂炦��v���ƂƂ͈قȂ�B�j���ɂ͊C�̒��ɂ��鋛�ɋ߂Â��āA�����̎�ŋ���߂܂�����@�͂Ȃ��B�ނ莅�Ƃ������ʂȑ��u���Ȃ���A���̐��E�Ɋւ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�C���Ɨ��͂܂��Ɂu�ׂ����v�ł����Ȃ����Ă��Ȃ��̂ł���B
����������A���킹�ċ����|����B�����Ēނ�グ��B���̋����Ƌْ��̃v���Z�X�ɒނ�̉��̐��������߂�̂Ƃ͕ʂ́A������̍l����������B����͎��R���y���ނƂ����l���ł���B����̕��i�ȂNJᒆ�ɂȂ������ς�l����ǂ����߂�ގt���������A�މʂ͓�̎��A���邢�͎O�̎��ŁA���R�̂Ȃ��ł̂�т�Ǝ����߂������ƁA���R�����邱�Ƃ�ނ�̖ړI�ƍl����l������B
�J�C�����̗V�т̕��ނɎ��R�u���̂����т��܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɕs�����q�ׂ��ۂɐG�ꂽ���A�����]�A�C���́A�͐��Œނ莅�𐂂炵�Ă͂������A����ނ�C�͂܂������Ȃ�����(�j�����Ă��Ȃ������B���邢�͂܂������Ȑj�����Ă���)�Ƃ����b���`����Ă���B�l�������߂Ȃ������]�I�Ȓނ�l�́A�C���A�Ȃǂ̎��R�̂Ȃ��ł������Ɨ���鎞�Ԃ��y���ނ����Ŗ����ł���̂��낤�B���̂悤�Ȓނ�̓G�s�N�[���X���A�傢�ɐ���������������Ȃ��B
�ނ�ɂ́A���R���y���ނƂ����v�f������B�������A�l����S�����߂��A�����A���R�̒��ʼn߂������Ƃ��������߂�ނ�Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��B�����]�́A���R�̒��ʼn߂������Ƃ����߂Ă����̂ł͂Ȃ��B����́A��ł͂Ȃ��A���������ɂȂ����������ނ邱�ƁA���ւ̎d���̌������߂Ă����Ƃ����B���̂悤�ȍ]�ˎ���̐��������F��ނ�グ�Ă݂���̎�ꂽ�⣁i�O�f�A���ҏە��w�]�˒ދ���S�x�j�B �u�ނ����Ⓖ���Ȑj�䂦���������v�A�u�����Ȑj����ނ�グ��v�Ƃ������������B�i��؍����w��i�����j�x�����̂Ɛl�Ԃ̕����j���U�X�A�@����w�o�ŋǁA�P�X�X�Q�j
�ѓc�i�O�o�w�ނ�ƃC�M���X�l�x�j�́u�ꌾ�Ō����A�C�M���X�̐l�X�́A�ނ�̒��Ɏ��R�����Ƃ߂��v�Ƃ����B�C�M���X�l�ɂƂ��Ĕ��������i�̑�\�I�Ȃ��̂̈���������܂ޓc�����i�������B�ނ�͂��̂悤�ȓc���ɐڂ��G�߂̕ω���̊�����ꂾ�����B�܂��A�C�M���X�l�͂��Ƃ̂ق����R�������鍑���ł���A���̎��R�̒��Œނ�����邱�Ƃ��D�ƂƂ��ɁA���̎��R�̔��������i�ƋG�߂̕ω����A�����͂��߂Ƃ��镶�͂Ɏc�����B�C�M���X�l�͔��������R��w�i�ɁA�ނ�ƌ|�p�Ƃ��������A�Ƃ����B

�p���̔������c�����i�̒��ł̒ނ�B���̏͂̃g�b�v�y�[�W��i���̎ʐ^�ƂƂ��ɁA"Go Fly�@Fishing UK"�@http://www.goflyfishinguk.com/�ɂ��B
�g�b�v�y�[�W�̎ʐ^�́ALake District�ƌĂ��C���O�����h�k�����𗬂���̈�Athe River Eden�ł̒ނ�̖͗l�B���̐�ł̓u���E���g���E�g�A�O���C�����O�A�T�[�������ނ��Ƃ����B
���̎ʐ^�̐��Chalk streams �̈�BChalk streams �Ƃ̓`���[�N�܂�ΊD�⎿�̋u�˒n�т��痬��o���̂��ƂŁA�A���J�����Ő�������ł���̂������B���E���ɂQ�P�O�{�̃`���[�N�E�X�g���[��������A���̂����̂P�V�O�{���p���ɂ���B�t���C�Ń}�Xtrout�ނ���s���ނ�l�ɂ͂Ȃ��݂̂��̂Ƃ����i�p���Wikipedia)�AChalk streams �̈��the River Test�͂���HP�ɂ��u���E�ōł��L���ȃt���C�t�B�b�V���O�̐�v���Ƃ����B���̎ʐ^��the River Test���ǂ����͕s���B
�ѓc�̓C�M���X�l���u�������܂ޓc�����i�v�Ƃ��̒��ł̒ނ���D���Ƃ��������Ă���B"Go Fly�@Fishing UK"H.P.�ɍڂ��Ă���ނ��͊m���ɔ��ɔ������B�����������͂܂�ł悭����ꂪ�s���Ă���傫�Ȓ뉀�̒��̐l�H�I�ȗ���̂悤�Ɍ�����B
�ѓc�̒����̒��ł�������Ă���悤�ɁA�p���ł͉͐�Œނ������ɂ͂��̐삪�����y�n�̏��L�ҁi�W�F���g���}���Ȃǁj�ɂ�鋖���K�v�ł���A�p���̒ނ�ꂪ���ɔ������̂́A��͂��Ă͓y�n�̏��L�҂Ɍق�ꂽ���o�[�E�L�[�p�[�ɂ���āA���݂ł͂��̏��L�҂���ϑ����ꂽ�ނ�N���u�Ȃǂɂ���āA���邢�͏ꏊ�ɂ���Ă͉͐�Ǘ��ǂɂ���āA�ނ����ނ�̎������������K������Ă���ƂƂ��ɁA���O�ɊǗ�����Ă��邱�Ƃɂ��̂ł��낤�B
�����A���{�̉͐�́A�r���Ƀ_���������ė��ꂪ���f����Ă�����A��̒��ɓS���⎩���ԓ��̑����R���N���[�g���̋��r�������A�����}��Ԃ⎩���Ԃ��������܂������𗧂ĂĒʉ߂���B���邢�͐쉈���ɂ͂����Ă��ܑ����ꂽ���H�������Ă���A�����߂��ɐl�Ƃ�q�ɂ������Ă����肷��B�����A����ł��A����A�}�S��ނ�|�C���g�ł́A�������Ƃ���������B�����āA���{�̐�Ɏc���Ă���������́A�p���̉͐�́A�����Ȃ炳������̍s���͂����l�H�I�Ȕ������Ƃ͈���āA����̂܂܂̎��R�̗��ꂪ���������ł���B
�I���̒ނ�͎Ⴂ����ƒ��N�ȍ~�Ƃł͑傫���ς�����B�ڂ����͑O�̏͂̑�Q�߂��Q�Ƃ��Ă������������B�����ň��p�������ƈꕔ�d�Ȃ邪�A�S�O����̍K�c�I���͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�u����ɒނ�Ƃ����Ă��A��X�l�X�ŁA���̂���͍̂����罽�ނ�݂̂ł��B----��ނ��----�������݂Ȃ���ł��A����T��Ȃ���ł��A�܂��A���W�o�~�Ȃǂ�ǂ݂Ȃ���ł����܂��B�]�T��Ƃ肪����A��ԃm���L�Ȓނ�ł��B�����͐��̏�ŗV��ł���悤�Ȃ��̂ł��B------�L���i�F�̒��ɑD���ׂāA���悻�敗�ɐ�����Ȃ��炨�ƂȂ����V�ԁA���ꂪ�ʔ����̂ł��B�܂��[���̃N�C�i�A�ł̐璹�A�Èł̌܈ʍ�ȂǁA�������������N�������܂��B�k�X�Y�L�ނ�͖�ނ�ōs�Ȃ����Ƃ��������l���Ԃ͒��ԂŁA�����̓V�ۂ̕ω��A�����A�L���A�J�A�_�A�[���A�������Ƃɂ�����͂���߂Đe����������āA�P���Ƃ��Ɏ��R�ɕ������̂ł��B�W���A����炪�����̑啔���𐬂��܂��̂ł��l�v�B
�u��͂��������������畩�ł��ނ�l�ɂ����ނ����̂ł͂Ȃ����A���̖ړI�i���āj�Ȃ��ɂ͂����Ȃ����炱���������ƂɂȂ�̂ł��B����ɑD�𑆂�����A����g������A�J�V�k�͊݁B�V�ԏꏊ�A�ނ��l��ς��邽�߂ɐ���������肷�邽�߂ɁA�����̘J�������A�V���܂��ЂƂ̖ʔ��݂ɂȂ�̂ł��āA----�����݂̂ɂ�����̂ɂƂ��ẮA�J�����Ĕ�������̂������ȋC������v�����ł����炩������܂���B�\���i�R���i�ŐS�n�̂悢�V�т����̂ł�����M�V�т��D���Ȃ̂ł��v(�u�ނ�k�v�j�B
�܂��u�������ނ낤�Ƃ��ӂ̂�B��̖ړI�Ƃ��Ă���l�͑�T�l�������Ȃ��Ƃ��傰�Ԃ��Ă��܂����A����͒ނ�̐^�̎��x�O���������̂ŁA���͍D�݂܂��ʁB���̐^�̎�ł����A����͂ނ���ނ�ȊO�̎l�Ӂi������j�̌��i�ɂ���̂ł���B���̎�͂��Ƃ��l�G�ɂ��Ĉ�Ђ܂����A������ɂ��Ă��R�쑐�A��R�̔��������R�̂����A�S�Â��Ɏ��𐂂�Ă���̂ł����́A�S�n�̂悢���Ƃ͂��̏�������A���R�̔��Ɨn�������悤�Ȋ��������܂��v�ƌ����Ă���i�u�ދ��ʁv�j�B
���N���ȍ~�̘I���͒ނ�����Ȃ���A���R���ۂ��u�ɂ߂Đe�������키�v���Ƃ��y����ł���B�ނ͋����H���̂�҂ԁA���邢�͒ނ�Ă��ނ�Ȃ��Ă��A���R�ƌ��������R�ɗn�����ށA�Â��ȗV�т��y���B
�I�����P�O�O�N�قǑO�̃��V�A�̍�ƃA�N�T�[�R�t���A�ނ�l���u�����������������̂Ȃ�킢�v�A�u���v�Ȏv�l�v�A�u�C�����A�C��J�v���瓦��āA�u�����c�ɂ́A�Î�A�����A����̂܂܂̐����A�ȑf�Ȑl�ԊW�v�ɁA�����āu���R�̐^�������v�ɂ���Ă���ׂ����Ƃ����B
�Z���Q�C�E�e�B���t�F���B�b�`�E�A�N�T�[�R�t�i1791�|1859�j�̏ё�
 �������A�ނɂ��A�u�����鎩�R�̔��A���炵���������ꏊ�A�G�̂悤�Ȓ��]�A�s��ȓ��̏o�܂������v�A�u�ЂƂ߂ł킩��v�悤�ȁA�u���i��v�I�Ȏ��R�͖{���̎��R�ł͂Ȃ��B�u������������X�̐_��Ȗ؉A���C�̒��v�u��̍������̖�A���n������̑呐���v�A�u�����Ă̖�̈ł̐Î�i�����܁j�̒��Ɍ����̊ݕӁv�A�u����Ɉ��̐��������Ƃ��Ɨ��ތ̊݁v�A�u��̒��⒎�̂Ƃ���Ȃ��̂��A���������v�A���̂悤�ȁA����ꂪ���̏����Ȉꕔ�������m��Ȃ��A���������͂݁A��ݍ��ޑ厩�R�������{���̎��R�Ȃ̂��Ƃ����B�ނ́A�l�Ԃ��⏬��������������A�厩�R�̒��Œނ邱�Ƃɉ������o�����BS.T.�A�N�T�[�R�t�^�L����Y��w�ދ��G�M�x��g���ɁA�P�X�W�X
�������A�ނɂ��A�u�����鎩�R�̔��A���炵���������ꏊ�A�G�̂悤�Ȓ��]�A�s��ȓ��̏o�܂������v�A�u�ЂƂ߂ł킩��v�悤�ȁA�u���i��v�I�Ȏ��R�͖{���̎��R�ł͂Ȃ��B�u������������X�̐_��Ȗ؉A���C�̒��v�u��̍������̖�A���n������̑呐���v�A�u�����Ă̖�̈ł̐Î�i�����܁j�̒��Ɍ����̊ݕӁv�A�u����Ɉ��̐��������Ƃ��Ɨ��ތ̊݁v�A�u��̒��⒎�̂Ƃ���Ȃ��̂��A���������v�A���̂悤�ȁA����ꂪ���̏����Ȉꕔ�������m��Ȃ��A���������͂݁A��ݍ��ޑ厩�R�������{���̎��R�Ȃ̂��Ƃ����B�ނ́A�l�Ԃ��⏬��������������A�厩�R�̒��Œނ邱�Ƃɉ������o�����BS.T.�A�N�T�[�R�t�^�L����Y��w�ދ��G�M�x��g���ɁA�P�X�W�X
�ނ����ł͂Ȃ��B�L�m�R���A�R�؎��ŎR�ɓ���A���Ƃ��A�ړI�̃L�m�R��R�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ă��A�������������R�̎Ζʂ�����~�肵�A�؉A�ŗ����������Ĉ�x�݂���̂́A�ɂ߂đ傫�ȉ��y�ł��낤�B�o�R�A�L�����v�A�n�C�L���O�A�o�[�h�E�H�b�`���O�Ȃǂ��A���R�̒��łȂ����X�|�[�c�A�A�E�g�h�A�E���W���[�A�V�тł���A�u���R�ɕ�����v�ėV�ԑ傫�ȉ�������B
�����̃��W���[������V�т́A���ꂼ����L�̊y�����A�ʔ���������ɈႢ�Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A�͌�⏫���A�S���t��T�b�J�[�ȂǁA�����ŁA���邢�͐l�H�I�ȋ�ԂŁA���]���g���Ă��邢�͉^���Z�\�ɂ����Đl�Ƌ����A���Z�E�Q�[���Ƃ͈قȂ��āA���R�̂Ȃ��Ŏ��R������傫�Ȋy���݂����ƌ����_�ŁA���ʂ��Ă���B�������āA�ނ�́A���R���y���ޗV�т��邢�̓��W���[�����̈�킾�ƌ�����B�����Ă��ׂ̍��ȋ敪�ɂ����āA�o�R�A�L�����v�A���X�Ƃ̈Ⴂ�����߂Ė����Ƃ������ƂɂȂ�B
�ނ�̖ʔ����̌��_�́A����������A����j�Ɋ|����ނ�グ�邱�Ƃɂ���Ƃ����̂͂P�̊ϓ_�ł���B�ނ�l�͈قȂ�Ώۋ���ނ낤�ƁA���܂��܂ɈقȂ�ނ���ŁA�ނ���y���ށB�����ē�����A�������y���ޓ_�ł͋��ʂ��Ă��邪�A�ނ���̈Ⴂ���琶���邻�ꂼ��̒ނ�̂Ȃ��ɁA�قȂ�������o���B�Q�[���Ƃ��Ċy���ނ̂��A�މʂ�H�����키���Ƃ��y���ނ̂��B�����������y���ނ̂��A�����ȓ����������A�@�m���邱�Ƃ̒��ɉ������o���̂��B�j�ɉa��t���ĐH���̂�҂̂��A�^���a�E�[�a�j���g���x���ĐH�킹��̂��B�D���Ȓނ�����D���Ȃ̂��A�����Ȋi�����y�����̂��B�����ċ��M���Ȃ��Ƃ��ɂ͂ǂ����邩�B�Ȃ�Ƃ����Ĉ�C�ł��ނ낤�ƍŌ�܂ʼna��t���ւ��A�d�|���̓���Ȃ������J��Ԃ��A�ނ낤�Ƃ���邩�A�y��̏�ɂ��邢�͖h�g��A�D�̏�ŐQ�]�сA��ߋx�����邱�ƂŁu�ÓI���v�����߂邩�B���܂��܂Ȓނ��������B����炷�ׂĂ̂Ȃ��ɋ��Ƃ̊W������B
�����A�I����A�N�T�[�R�t�������悤�ɁA����ނ�グ�邱�Ƃ͓�̎��ɂ��āA���R�̒��ŗV�ю��R�����邱�Ƃ̉����A�ނ�ɂƂ��Ă��{���I�Ȃ��̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B���̂悤�ɍl����ꍇ�ɂ͒ނ�̂ق��ɂ��A���R�����邱�Ƃ��y���ޗl�X�Ȑg�̉^���E�V�т�����A�ނ�͎��R���y���ނ����^���E�V�т̂P�ł���Ƃ������ƂɂȂ�B���M���L���b�`�������|����Ƃ��̉���A�ڎw���R��L�m�R���������n����Ƃ��̉��A����������g���{�������ߊl����Ƃ��̉��A���邢�͖̏�ł������钹�̎p��o�ዾ�Ŕ`�����A���邢�̓J�����Ɏ��߂�y���݂́A��ړI�ł��鎩�R������l�X�ɈقȂ���@�E�X�^�C���̗V�т��ƍl���邱�Ƃ��ł��A�ނ�͂��̈��ł��邱�ƂɂȂ�B
�����A���ׂĂ̗V�т�W���[�����A��y���A���R���L�[���[�h�ɂ��ĕ��ނ����Ƃ���A���̂悤�ȕ��ނ��l������B�܂��A���R��ɂ���̂����邢�͐l�Ԃ�ɂ���̂��ő傫���Q�ɕ������A����ɁA���̂��ꂼ�ꂪ����ɐe�a�I�ł��邩�A�����ł͂Ȃ�����I���Ƃ����ϓ_�ŋ敪�����B
���̂悤�Ȋϓ_����A���̂悤�ȁA�V�сA��y�̕��ނ��\��������Ȃ��B
---------------------------------
�P�j�l�Ƃ̐e���������A�Ќ����y���ށF�_���X�A���y�A�������V�сA���Ȃ����Ȃ���
�Q�j�l�Ɛ킢�������Ƃ��y���ށF�قƂ�ǂ̃X�|�[�c�A�����A���������@
�R�j���R�ɒ��킷��A���R�Ɠ����F��A���b�N�N���C�~���O�A�T��
�S�j���R�ƌ����A���R�ɐe���ށF�C�ӂ̗V�сA�n�C�L���O�A�R�؎��A�o�[�h�E�H�b�`���O�A��V�сA�M�V��
---------------------------------
���݂ł́A�قƂ�ǂ̒ނ�͂S�Ԗڂɕ��ނ����B�啨�ނ�͂R�j�ɓ��邾�낤�B�������w���u�i�ނ��o�X�ނ�Ȃǂ̃Q�[���E�t�B�b�V���O�́A�u���R�v�ɐe���ނ̂ł����킷��̂ł��Ȃ��A�Q�j�́u�l�Ɛ킢�������Ƃ��y���ނ��Ɓv�ɓ����ׂ���������Ȃ��B
�P�X���I�̃C�M���X�ł́A�ނ肪�Ќ��̏�ƂȂ������Ƃ��������B�����ł͒ނ�͎Ќ��̒P�Ȃ��i�A�����ł������ɂ����Ȃ��B�Ќ��͂��낢��ȏ�ʼn\�ł���B�S���t�͖{���͂Q�j�ɕ��ނ����ׂ��X�|�[�c���낤���A�Ќ��i�r�W�l�X�j��ړI�ɂ��čs�Ȃ���ꍇ������B
�܂���̂�т�ƒނ莅�𐂂��ނ裂͢�啨�ނ裂ƑΔ䂷��Ƃ��ɂ́A����R�ɐe�a�I��ƌ��邱�Ƃ��ł��邪�A���͒ނ��l�ԂɐH����̂�����A�����ς碐l�Ԓ��S�I��Ȋϓ_����̕��ނɂ����Ȃ��B
�K���������ׂĂ̗V�т���������ƕ��ނł����킯�ł͂Ȃ��A���_�͂��낢�날�邪�A�ق��̕��ޖ@�ł����ׂĂ̗V�т����܂����ނ��Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��l��������A���̂悤�ȕ��ނ��ꉞ�F�߂Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B
�_���X�E�����ł͎�⑫�̌`�⓮�삪���܂��Ă���B���y�ł́A�y���ɏ�����Ă��������Y���ɂ��������ĉ��t���Ȃ����B���Z��͌�E�����Ȃǂł̓��[���ɏ]���������⋣�������߂�B�P�j�ƂQ�j�ł́A���܂��Ɋ�Â��āA�V�сE�X�|�[�c���s����B���܂��͎��R�ɂ͑��݂����A�Љ�╶���܂�l�Ԃɂ���č��ꂽ���̂ŁA�P�j�A�Q�j�͐l�Ԃ�ɂ����u�V�сv�ł��邽�߂ɁA���܂���K�v�Ƃ���B
2017�N1���V��������ŏ㉉���ꂽ�̌��u�J�������v�̈��ʁi�u�`�P�b�g�҂��vhttp://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b1633630�ɂ��j

���܂��Ȃ��ɁA�l�Ԃ�Ɉ���I�Ɂu�e�a�v��u�Z���v�����߂�Ȃ�A�\�Ԃ�x�z�ɂȂ邾�낤���A�����Ƃ���Ό��܂�푈�ɂȂ邾�낤�B���Ƃ��A�J�������̓n�o�l���̂Ȃ��Łu���Ɍ��܂�ȂǂȂ��B���͍D���ɂȂ�����A�~�����Ȃ����礂Ȃ�Ƃ��Ăł���ɓ����B���͎��R���v�Ɖ̂��A����I�Ƀh���E�z�Z�Ɍ������B���̂Ƃ�����Q�l�̐l���͔ߎS�Ȍ����Ɍ������Đi�ނ��ƂɂȂ�B
���R��ɂ���V�тł́A�⌈�܂�͑��݂����A�����̍D���Ȃ悤�ɐU�������Ƃ��ł���B�ނ�͋������܂����Ƃ��Ƃ����̂͂����݂���l���ł���A���̏Z�ޒn���̘V�l�̂Ȃ��ɂ́u���A�[�v���u���܂��v�ƌĂԐl������B�a��t���Ă��Ă����̒��ɐj����܂��Ă���̂�����A���́u���܂������v�ł���A�ƒN���������Ă����B
���R��ɂ��Ĉ�l�ōs���V�т́A�����̎d���̂Ȃ��Łu�����v��u�����v�����߂��X�g���X�������Ă���l�ɂ́A�傢�ɐ����ł���B�u��V�v��u����v�ɂ��������ĐU�������Ƃɂ��肵�Ă���l�ɂ́A�ނ�͑���i���j���x�����Ƃ��܂߁A��肽����������y���݂�����B�������A�����ؕԂ���H�炢�A�����������A�ꍇ�ɂ���Ă͖��𗎂Ƃ����Ƃ�����B
���R�̒��ōs�Ȃ���X�|�[�c��V�тƂ����Ă��A�p���̂��鎞��̒ނ�̂悤�ɁA���R���y���ނ��Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��A�Ќ���ړI�ɍs���Ă������Ƃ�����B���邢�̓L�����v�͎��R�̂Ȃ��ōs�Ȃ�����̂����A���R���y���ނ���łȂ��A���邢�͂���ȏ�ɁA�ꏏ�ɎQ�����钇�ԂƂ̊W���y���ނƂ����v�f������B�����Ēނ�ɂ��A�Ǘ����ꂽ�ނ��ŁA�������Ƃ𒆐S�ɂ����w���u�i�ނ�Ȃǂ�����A�ނ肪���ׂāA��l�Ŏ��R�Ɍ����V�т��Ƃ͂����Ȃ��B
�ނ�͐l�ƌ���邱�Ƃ�ϋɓI�ɋ��߂�i�吨�Łu����オ��v�j�V�тɂ͕��ނ���Ȃ��B�������A��O�̍�ƁE�t�R�Î��̂悤�ȃP�[�X�������A�ǓƂ����߂邱�ƂȂ����͎��R�̒��ŌǓƂ��y���ނ��Ƃ��ނ�̎�ȖړI���Ƃ͌����Ȃ��B�Ƃ��ɁA�����ނꂽ�Ƃ��ɂ́A�C�����V�g���A���邢�́A���Ɋy�����Ȃ�B���̊y������ړI�ɒނ�ɂł�����̂��B�������A�ނ�͂����Έ�����܂������ނ�Ȃ����Ƃ����邵�A�ނ��Ƃ��ł��҂��Ԃ��������Ƃ�����B�ǓƂ��y���ދ@��͂�����ł�����B
�ނ肪����̋�����i�̐l�Ɍ����Ă���A���邢�͒ނ���D�ނ͓̂���̐l�ł���ƌ����邾�낤���B
�u�ނ�̐����v�Ƃ�������w�ދ���S�x�̓C�M���X��I.�E�H���g���̏��������̂����C���̏��ł͂P�U�T�R�N�ɏo�Ă���B���ҏە��w�]�˒ދ���S�x�ɂ��ƁA�E�H���g���͗T���ȑ@�ۏ��l�ł������B�����A�P�V�Q�R(���ۂW)�N�A�]�ˎ���ɏ����ꂽ�w���A�^�x�͓��{�ŌÂ̒ނ�̏��Ƃ�������B���̒��ҁA�Ìy�я��i�E�l���j�́A�Ƙ\�S�O�O�O�̊��{�ŁA�o�ϓI�ɂ͌b�܂�Ă����B�E�H���g�����я����A�Ƃ��ɉƒ�̍K���ɉ��������Ƃ��낪���ʂ��Ă���ƁA���҂͂����B
�я��͂P�U�ŕ����Ȃ����A�S�l�̌Z��͍я��Q�U�܂łɁA�Q�U�A�Q�Q�A�P�U�ł��ׂĎ��B�Ȃ͌�����P�N�ŕa�������B�č������ȂƂ̊ԂɂX�l�̎q���������������A�Q�U�Ŏ��������܂߁A�����A�R�ԖځA�S�Ԗڂ����B�я��͂S�V�̂Ƃ��ɌܔԖڂ̎q���ł���O���ɗ{�q���}�����B���̌���A�U�Ԗڂ���X�Ԗڂ܂ł̗c���q�������X�Ɏ��B
�E�H���g���͂T�̂Ƃ��ɕ��e��S�������B�R�S�̂Ƃ��Ɍ��������Ȃ͂P�O�N��Ɏ��B��l�̊Ԃɐ��܂ꂽ�V�l�̎q���͂��ׂĚ�܂����B��ȂƂ̊Ԃɐ��܂ꂽ���j�͚�܂����Ƃ����B
�������A�����̎Љ�̈�ʓI�ȏƊr�ׂăE�H���g����я������ʁA�ƒ�I�ɔ��K�ł������Ƃ͂����Ȃ��B�O�o�w�C���O�����h�P�W���I�̎Љ�x�ɂ��A�P�V�O�O�N�ɂ́A�V�����̂T���̂P�͐��܂�ĂP�N�ȓ��ɁA�R�l�Ɉ�l�͂T�ΈȑO�Ɏ��ɁA�����̉p���̕��ώ����͂R�V�������B�P�V�S�O�N��̃����h���̂������̋���ł͂S�l�ɂR�l�̎q�ǂ����U�Ζ����Ŏ��B
�㗬�K�����܂�̗��j�ƃM�{���̌Z��o���U�l�����ׂėc�����Ɏ����A�M�{�����g���a�ゾ�����B�A�������̎q�ǂ��͈�l�����N�ɒB���Ȃ������B�����āA�����l�ƌ����������Y��Ŏ��Ƃ����B��w����O�q���������B�ȑO�ߑ�̉p���Љ�ɂ����Ă͈��S�ȏo�Y���q�ǂ��̌��₩�Ȑ������܂������ۏ���Ă��Ȃ������̂ł���A�]�ˎ���̓��{�ł��ς��Ȃ������͂����B
�����S�O�N���܂�̖����w�ҥ�{�{���́A�U�l�Z��ł��������q�ǂ��̂Ƃ��ɂR�l�����B�ނ̕��ɂ͂T�l�̒햅�����������A�Q�l����͂�c���̂Ƃ��Ɏ��Ə����Ă���Ƃ����i��c�d���w�{�{���@��E�̖����w�ҁx�͏o���[�V�ЁA�Q�O�P�R�j�B�������A�q�ǂ��̎����߂����h�����Ƃ��ǂ����́A�q�ɑ���e�̈���̑��ǂɂ���Ă��܂�ł��낤����A���܂ꂽ�q�ǂ��̐�����������Ƃ����Ďq�ǂ��̎����s�K�ł͂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��v���B
���҂͢���q���n�߁A�����Ղ�Ìy�я��̑I�������́A�{���ނ肪�l�̗V�тł���A�����Ƃ����Ύ��Ȃ̓��ʂƌ����������s�ׂł��邱�ƂƖ��W�ł͂Ȃ����낤��ƌ����Ă���̂ł���A�Ƒ��I�Ȕ��K���E�H���g���ƍя���ނ�Ɍ����킹���u�����v���ƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ�́A�l�Ԍ����Ƃ܂ł͌���Ȃ��ɂ��Ă��A�Ќ��Ƃ͑ɓI�ȁA�l�I�ȗV�тł��邱�Ƃ͊m���ł���B�E�H���g���͕\���contemplative man�܂��ґz�I�Ȑl�ƌ���������Ă���B�ґz�I�Ȑl�́A�Ќ��Ƃł͂Ȃ����낤�B
�����C�V�_�C�ނ�ɂ̂߂荞�����ƁA���߂Đ��܂ꂽ��������P�����قǂŏ������Ɣ������A���N�̓��@�Ƃ��̌㐔�N�Ԍo�߂����邽�߂ɒʉ@�����������d�Ȃ�B�u�傽��ƌv�̎x���ҁv�ł������Ȃ͓�����w�a�@�ɋΖ����Ă������A�����́A�a���ɒ��x�݂Ɋ���o�����炢�ł���B���j���͍Ȃ��Ō삵���B�i�Ȃɂ͋x�����Ȃ��������ƂɂȂ�B�j���͏m�⎄��̔��u�t�ȂǂŏT�R���d�������Ă����B���ƁA�����ɋ삯���Ă��ꂽ���̕�e�����������Ŕ��荞��ŊŌ�������B�Ȃ̎o���a���j���ɑ����Ă��ꂽ�I���S�[�����x�b�h�̘e�őt�ł�u�h�肩���̉̂��J�i���A���̂���---�v���Ђǂ��₵�������A�ڂ̑O���Â��Ȃ�悤�Ɋ��������Ƃ�Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���͌��ɂQ�`�R��x���ɒނ�ɏo�������B�ɓ�������[�������ȂǂɎԂɏ悹�ĘA��čs���Ă����F�l�ƈꏏ�̒ނ�����������A�ɓ����������S�ŁA�哇�A�O��ȂǂɈ�l�Œʂ����B�C�V�_�C�́A�ŏ��̂P�C��ނ�̂ɂP�O�N�ȏォ���邱�Ƃ��������Ȃ��قǂ߂����ɒނ�Ȃ��B������Ȃ��B�قƂ�ǂ̎��Ԃ�䩗m�ƍL����C�߂ĉ߂������ƂɂȂ�B���͈�̏�ŁA���̂���͎���̂��ǂ����A���̂܂���ł��܂��̂ł͂Ȃ����A�������Ƃ����炻�̔߂��݂��痧������邾�낤���A�u���Ȃ̓��ʂƌ��������v�Ƃ����̂Ƃ͏����Ⴄ���A�Ƃɂ������̕a�C�̂��Ƃœ�����t�ł������B�������A���肪�p�ɂɂ���A�₦�����킹�̃^�C�~���O���v��A�����č��킹�āA�͂����ς����[���������Ƃ����悤�ɁA�ނ�ŖZ������A�S�z��Y��邱�Ƃ��ł�����������Ȃ��B�����ɓ��哇�ŏ��^�Ȃ���n�߂ăC�V�_�C��ނ�A���̂Q�����قnj�A�O��ő�^�̃C�V�K�L�_�C�E�N�`�W����ނ����̂́A�����މ@��������ł������B
�ނ�͋���ނ邱�Ƃ�ړI�ɏo������B��������ނ��ΐl�͉����ɂȂ�A���X�̗J���Ȃ犮�S�ɐ�������A�܂���������̎d���Ɍ��������Ƃ��ł���B�������A��l�ōs���ނ�ŁA�ނ�Ȃ��Ƃ��ɂ́A�͌�⏫�����w���Ă���Ƃ��̂悤�ɁA�w�����ǂނ̂ɏW�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�吨�ŃL�����v������Ƃ��̂悤�ɂ킢�킢�����Ȃ����Ƃ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂�����A�ۉ��Ȃ��ɁA�����I�ɂȂ炴����A�C�Ɋ|�����Ă��邱�Ƃ��v���o���A��䍂��Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ��B
���͂̌i�F�߂邱�Ƃ����邪�A�O���͊C�ł���A�ނ�����Ă���Ƃ��ɁA����߂邱�Ƃ͂��܂肵�Ȃ��B�i�F���y���ނ͈̂�ɓ���܂ł̓r���̌���ꂽ���Ԃł��邱�Ƃ������B�����āA�L����C�߁A���邢�͐�ʂ����Ȃ���Ƃ��o�����Ƃ͌i�F�߂Ċy���ނ̂Ƃ͈Ⴄ�B
���҂́A�я���E�H���g���͈�l�Ŏv����z���ɂӂ��邱�ƁA�����̓��ʂɌ��������Ƃ����Ƃ��ƍD���ł����āA�������������̂䂦�ɒނ�ɍs�����ƌ��������̂��낤���B����Ƃ��A�я���E�H���g���͓��e�����Ŏ������Ƃ̔߂��݂œ����I�ɂȂ��Ă��܂��A�l�ƕt������Ȃ��ōςޒނ�Ɍ��������ƂɂȂ����ƌ����Ă���̂��낤���B���́A���肪�قƂ�ǂȂ��A��ɊC�߂Ă��邵���Ȃ��������߂ɁA���̕a�C�ɂ��čl������Ȃ������̂��Ƃ����C������B����ɂ��Ă��A�ނ�Ȃ��ނ�ɂ͐l����ʂɌ����킹����̂�����Ƃ������Ƃ͌����邾�낤�B
���́A���̓��@���A�C�V�_�C�ނ�ɏo�����邱�ƂŁA������̗J���𐁂�������Ƃ��ł����Ƃ͎v��Ȃ��B�����A���炸���̂܂ܖ������ʂ�������Ȃ��Ƃ������낵���s���A���邢�́A���������đމ@�������܂��Ĕ��̉\�����c���Ă���ƌ���ꂽ�����Ɋ����Ă����A���̂��݂������ɂ��������Ă���悤�ȋC���Ɋ���悤�Ƃ��Ă����B�������Ƃ��N���邱�Ƃ�\�z���A�����Ȃ��Ă��䖝���邵���Ȃ��̂��ƌ����������悤�Ƃ��Ă����B���ʂ����m��Ȃ��A���ʂ��낤�B����͂Ђǂ��߂������Ƃ��B���́A���̗c�����Ď����̂��Ƃ�Y��邱�Ƃ��ł����߂��݂Ȃ���A�l�����čs���̂��B�������̂Ȃ����Ƃ��B������l�����B�����ɑ��邻�����������́A���ۂɖ�������ł����牽�����ɗ��������ǂ����������B�߂��݂ɑł��Ђ�����Đ��_��a��ł�����������Ȃ��Ƃ��v���B�G�s�N�[���X�͖����̕s�K�A�ꂵ�݂���肵�ċꂵ�݂𑝂₷�����A�y�������Ƃ�z�����邱�Ƃ̂ق����悢�Ƃ����B�������ɂ��̂ق������͑傫���B�G�s�N�[���X��ᔻ����L�P���́A�ꂵ�݂̕s�ӑł��͋�傳����ƌ����A�\�߂���ɔ����邱�Ƃ��L�����ƌ����Ă���B���ɂ͂ǂ��炪���������͂킩��Ȃ��B
���肪�p�ɂɂ���A������������ނ��Z�����ނ�͐l�����ʓI�ł��邱�Ƃ������Ȃ��B���肪�߂����ɂȂ��A�ނ�Ȃ����ɂ́A���̐l�ɐڂ��Ă��Ȃ����A���ꂾ���A����Ύ��R�ɓ��Ɍ��������Ƃ��ł���B�������A�ނ�Ȃ��Ƃ��ɉ������Ȃ��łڂ��肵�Ă���l�͂��܂肢�Ȃ��B�����Ă��̐l�̓G�T��t���ւ�����A�ꏊ��ς����肵�ĉ����ނ邽�߂̍H�v������B���邢�͒��N���ȍ~�̘I���̂悤�ɂ��������ނ낤�Ƃ͂��Ȃ����A����Ɉ�t���Ȃ��琅��ł̃s�N�j�b�N���y���ށB�ڂ���Ƃ��Ď��Ԃ��߂������߂ɒނ�ɍs���Ƃ����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B
�l�ƈ͌�⏫�����邢�̓e�j�X��S���t�����Ċy���ނ����A��l�ő̂����ėV�Ԃ��Ƃ��D���Ȑl�i��O�͂łӂꂽ�G�b�Z�[�C�X�g�̋ʑ��͏������Ƃ������l�V�т����Ă����j�͒ނ肪�D���ɂȂ邩������Ȃ��B�ЂƂ�ł��邱�ƁA�ǓƂ��D�ސl���ނ���D���ɂȂ�Ƃ������Ƃ͌�����B�������A��l�ɂȂ�Ƃ��Ă��A���ʓI�ɂȂ邩�ǂ����͕ʂł���B�J�C�����̌����z�r�[�ɑł����ސl�͈�l�Ń~�j�A�`���A�̖͌^�̐���ɖv�����邾�낤���ނׂ͍��Ȏ��Ƃɒ��ӂ��W������̂ł����āA�����āu���ʓI�v�ł���̂ł͂Ȃ��낤�B��l�ʼn��y���̂��D���Ȑl�A��l�Ō������R�ɓo��̂��D���Ȑl�A�����Ĉ�l�Œނ������̂��D�ސl���A�K���������ʓI�ł���Ƃ͌����Ȃ����낤�B
���͒ނ�ɂقƂ�ǂ�����l�ōs���B���������Ԃƈꏏ�ɒނ���y���ސl������B�Ќ��_���X��S���t�ȂǂƓ��l�ɁA�ނ肪�Ќ��̏�ƂȂ邱�Ƃ����肤��B�Ƃ��g�����ނ�ƃ}�L�R�{�V�ނ�Ƃł͓�����̕\������قȂ�A�����Ă��̌��ʁA�Ƃ��g�����ނ�Ǝ�ނ�Ƃł́A�Ќ��ɖ𗧂��ǂ����ɑ傫�ȈႢ��������B
�r�V�ނ�Ȃǂ̊ƒނ�ł́A�����j�Ɋ|��Ɠ��������������ĊƂ��Ȃ���B�D���̊Ɗ|������L�т��Ƃ��C��Ɍʂ�`���A���̐�[���C���ɓ˂��h����悤�ɑ傫���h�ꓮ���l�����āA�ނ�l�́u�H�����I�v���邢�́u�ނꂽ�I�v�Ɣ��f���A��ԁB
�u�H�����I�v�B�Ƃ��傫���Ȃ���B���R���ł̒ނ�A�V���D�u���ފہvHP(http://www.aicyomaru.jp/index.html)���ؗp�B
 �����A�Ƃ��g�킸�����������Ɏ�Ŏ����Ēނ�}�L�R�{�V�ނ�ł́A�����������̈������w����畆�̉��̐_�o��ʂ��Ĕ]�ɓ`���A�u�ނ����I�v�Ƃ������f�ށB�}�L�R�{�V�ނ�̏ꍇ�̊�т́A�����Ă݂�A���̋����ȑ̓��ɂƂǂ܂��Ă���B
�����A�Ƃ��g�킸�����������Ɏ�Ŏ����Ēނ�}�L�R�{�V�ނ�ł́A�����������̈������w����畆�̉��̐_�o��ʂ��Ĕ]�ɓ`���A�u�ނ����I�v�Ƃ������f�ށB�}�L�R�{�V�ނ�̏ꍇ�̊�т́A�����Ă݂�A���̋����ȑ̓��ɂƂǂ܂��Ă���B�ƂŒނ�ꍇ�A������͊Ƃ̓����ɕ\��A�߂��ɂ��镡���̐l�̎��o�ɂ���ē����肪���L�����B�����āA�C�V�_�C�ނ�Ȃǂł́A���̓����肪�A����������ƌ��ɂ��킦�Ă݂������̑O�Ԃ�ŁA���������H�����ނ̂�҂��Ă��獇�킹���ق��������ȂǂƂ������Ƃ��x�e�������狳���Ă��炤���Ƃ��\�ł���A�܂��A�|�������̑傫�����Ƃ̋Ȃ��������\�z�����A�������Ƃ킩��A���̒��Ԃ͈�˂��邾���Ŏ����̒ނ�ɐ�O���A�啨���Ƃ킩��A�����̊Ƃ�����Ă����āA���Ԃ������グ�Ă���̂������A�ʖԂ������Ď�荞�݂���`�����Ə��������肷�邱�ƂɂȂ�B�������Ēނ肪���Ԃ̊Ԃŋ��L�������B�i���Ԃ��F�A�ނ����l�Ɠ�������Ԃ��ǂ����͕ʂȘb���ł���B�j
�����A�}�L�R�{�V�ނ�ł́A������͎w�悩��`��銴�G�����ł���A���̊��G�͌��邱�Ƃ��������Ƃ��ł��Ȃ��B�ׂ�̐l���u������v���Ƃ��s�\�ł���B�ނ��Ă���l���P�l�ŋْ����A�������A��Ԃ����Ȃ��B�����|������́A����̂Ȃ�̑S�̂��g���Ă̂��Ƃ�ɂȂ邩��A�ׂ�̐l�ɂ��킩��B�������A�����Ă��́A�i���Ƀx�e�����͊�ɏo�����j�ނꂽ���ނ�Ȃ����͓����������グ�鑬�x���Ⴄ�����ŁA�ق��ĐÂ��Ɏ�����J��̂ŁA�T�Ō��Ă��Ă��킩��Ȃ����炢���B�}�L�R�{�V�ނ�͐��l���W�܂��ċ߂��Œނ��Ă��Ă��P�l�Œނ��Ă���Ƃ��ƂȂ��ς��Ȃ��Ƃ�����B
�ނ�͑��̗V�т��邢�̓X�|�[�c�A�Ⴆ�S���t�ȂǂƔ�ׂāA���R�Ƃ̊W�������A�l�ԂƂ̊W�A�Љ�i�Ќ𐫁j���������A�ނ�̒��ł��A���Ƀ}�L�R�{�V�ނ�͐l�ԊW�̍ł������ނ肾�ƌ�����B�}�L�R�{�V�ނ�ł́A�l�͊�т⋻����N�Ƃ��������������ƂȂ��A�܂��l�Ƌ������邱�Ƃ��Ȃ��A�����P�l�Ŏ��R�ƌ��������B�i�Ƃ͂����A�D��j�⎅���̑��p��ɂ����Ă͂������A�ǂ̋���ނ肽�����A�ǂ̋���ނ����Ƃ��Ɏ��̊�т��傫�����́A���ׂĎЉ�ɂ��x�����A�K�肳��Ă��邱�Ƃ��܂������Ȃ̂����B�j
�ނ�̉��̌��_�́A����������A�����|����u�ԂɁA���邢�͋����|���Ă����荞�ނ܂ł̊Ԃɋ��̈����������邱�Ƃɂ���Əq�ׂĂ����B�����āA���̃X�|�[�c��V�тƔ�ׁA�l�ԎЉ�̂Ȃ��ŁA�Ќ������߂���A�Q�[���ŋ������肷��̂ł͂Ȃ��A���R�̂Ȃ��Ŏ��͂̎��R�����邱�ƂɁi���j��т����o���s�Ȃ��A�V�т��Əq�ׂĂ����B
��ŁA�������ł��傫�ȉ������o���Ă���ނ�ł���A�}�L�R�{�V�ނ�ŋ�����ɂ��čl�����B�}�L�R�{�V�ނ�ł́A�啨���|���đS�g�œn�荇���A�i������̂ł͂Ȃ��A�Â��ɁA�������܂܂ŁA�����ȓ�����L���b�`���邱�ƂɎ傽���������B���̒ނ�ł́A�I��������̐��R�O���S�O�W�߂ĉ^�ԁA������Ƃ����J���͕K�v�����A�n�}�`�̉g�ނ�E�g���[�����O�̂悤�ɁA�D�𑖂点��Ԓ��A�����d���r�V�������������邱�Ƃ��Ȃ��A�C�V�_�C�̈�ނ�̂悤�ɁA�����ƁA�傫���d�����[���A�I�����A���ȊƊ|���A�Ɗ|���p�̃s�g�������ɑł����ނ��߂̃n���}�[�A���X�A�d��������^�ԕK�v���Ȃ��B�D���g���ނ�ł������A�ǂ�Ȓނ������ɂ���A�D���Ǘ������J�����邪�A����������A����̒ނ�́A�ł��y�ŁA����⎖�̂̊댯�����ł����Ȃ��B
�D���g�����ނ�ł��A�C�V�_�C�ނ�́A�ނ��ɂ���ẮA�O���̃R�u�_�C�ȂǂɔY�܂����B�P�O�L������R�u�_�C�Ɠn�荇�����Ƃ̗͑͂����������Ղ�����B�̗͂��������V�l�ɂ́A�C�V�_�C�i��_���j�ނ�́A����ɔ����ꂪ�傫������B
����ɑ��āA�}�L�R�{�V�ނ�́A�啨�ނ�̖ʔ����Ƃ͕ʎ�́A�������A����ɏ���Ƃ����ʑ傫�ȉ��������A�������ꂪ�ł����Ȃ��ނ肾�B������A�}�L�R�{�V�ނ�ɂ��Ă����l����A��ɂ��čl����K�v�͗]��Ȃ��Ƃ�����B�������A���ƂP�A�Q�N�ŌÊ���}���邪�A���͂��܂ɂ̓X������i���̑啨�ނ�ɍs�����Ǝv���B�k���ہA���̑�O����S�́u�ނ�ɂ��āA�ނ�̉��y�ɂ��āv�������グ�ĂQ�N�قǂ��Ď��͉j�����ނ�Ńn�}�`��ނ��Ċi�������B�������A���̂��Ƃ������荘�ɂȂ����B�ˑ�ꕔ���͂̂R�D�Q�Ɓl�܂��A�ނ�͈�ʂɂ��ł��ނ��킯�ł͂Ȃ��A�ނ�Ȃ����ɂ͉����[�����Ƃ������ނ���}�C�i�X�܂��ɂȂ邱�Ƃ�����B�ȉ��ł͒ނ�ɂƂ��Ȃ�����l���邽�߁A�C�V�_�C�ނ���ɂƂ��čl���邱�Ƃɂ���B
�G�s�N�[���X�ɂ��A�K���͍ő�̉��邱�ƂŒB������B�����ĉ��̑��ʂ́A����ꂽ���Ɩւ�����������������ē�����B�C�V�_�C�ނ�Ɍ��炸�A�ނ�͊y���������łȂ��A��������B�^�Ă̎ܔM�̑��z�̉��ŁA���邢�͗₽���J�̒��ŁA���邢�͂��������Ɛ��������̂Ȃ��ŁA����爫�����ɂ����Ƒς��Ȃ���ނ�𑱂��i�ˑ�ꕔ��U�́u�J�̒��A���̒��̒ނ�A�����̒ނ�A�^�Ă̒ނ�v�Q�Ɓj�A�����ĉ��̓�������މʂ��Ȃ��������̒ނ�͋ꂵ�������炳�Ȃ��B
�A�`���āA�D���W�����Ă���ꏊ����Ƃɖ߂邽�߂ɂR�O�O���[�g�����S�O�O���[�g���̊ɂ�����ɂȂ�����������Ƃ��̑��͋ɂ߂ďd���A���x�������~�܂��đ��𐮂��Ȃ��ƑO�ɐi�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B�������A���̋������邽�߂ɒނ����߂悤�Ƃ́A���֍ێv��Ȃ��B�ނ���A���X�ނ�Ȃ����Ƃ����邩��A�ނꂽ�Ƃ��̊�т����̕��傫�Ȃ��̂ɂȂ�Ɗ����A���X�ނ�Ȃ����Ƃ͂悢���Ƃ��Ƃ���������悤�Ɏv���B�ނ�ł����J�͒ނ�̉��̌��Ƃ�������B
���͓����ɏZ��ł�������A�C�V�_�C�ނ���P�O�N�߂�������B�C�V�_�C�́u���Ƃ��Ēނ�Ȃ����Ƃ�����v�ǂ��납�A�N����N���قƂ�ǒނ�Ȃ��B�ʍe�u�֓��ł̃C�V�_�C�ނ�v(�ˑ�ꕔ��R�͂̂Q�D�j�̒��ł��ӂꂽ���A�X�|�[�c���ɍڂ��Ă�������C�V�_�C�ނ�t�@���͍ŏ��̈�C��ނ�̂ɂP�R�N���������Ƃ����B���N���C�V�_�C��ǂ����������A��C���ނ邱�Ƃ��Ȃ��܂܁A�C�V�_�C�ނ����߂��l����������B���͉^�ǂ��A���\��̒ލs�ɂ��A�n�߂Ă���Q�N�ōŏ��̃C�V�_�C��ނ邱�Ƃ��ł����B�����A���������ŃC�V�_�C�ނ������Ă����P�O�N�قǂ̊ԂɁA�ލs�����͂P�O�O���Q�O�O��ł͂����Ȃ��B�����Ċl���i�C�V�_�C�A�C�V�K�L�_�C�j����ɂ����̂͂P�O����x�ɉ߂��Ȃ��B���������S�̒ނ�Ȃ������ލs���A�C�V�_�C��ނ�グ���Ƃ��̎����A�܂������A�V�ɂ�����S�n�ɂ����Ă��ꂽ�B��^�C�V�_�C���ŏ��ɒނ�グ�����́A���Ȃ��Ƃ��A���̌�̂P�N�Ԃ́u�ނ����A�ނ����v�Ƃ��������������A���̎v�������ŏ\���K���ł������B
�C�V�_�C�ނ�ł͑傫�������j�A���C���[�n���X�Ȃǂ̎d�|�����g���̂ŁA�ق��̋��͂܂��ނ�Ȃ��B��Ţ������ނ肽���Ƃ����̂ł���A�ׂ��i�C�����̎��Ə������j���g�����㕨�i���Ɂj�ނ�̂ق����މʂ₷���B�������A�����̎��̓C�V�_�C�ނ�ȊO�̒ނ����낤�Ƃ͈�x���v��Ȃ������B�u�����v�ł͂Ȃ��A�C�V�_�C������ǂ����߂��B�C�V�_�C�͒ނ�Ȃ��B�ނ�Ȃ����炱���A�ނ����Ƃ��ɍō��ōő�̊�сA�K��������̂��Ǝv���B
�C�V�_�C�ނ�͋ɒ[�ȗ�ł���B�������A�ق��̔�r�I�ނ�₷�����ł��A�ނ�Ȃ����Ƃ͂�������B�����Ă��̒ނ�Ȃ����ɂ͐S�g�Ƃ��ɔ�J���ނ��A�����������v���Ɏ��t�����B�������A�������������J���A���_�͂P���A�Q���̌�ɂ͏�������A����̒ނ�ւ̉����A�y�������Ҋ��������Ă���B
�J�����͂P�X�V�O�N���납�玀�ʒ��O�̂W�W�N����܂ł̊ԂɁA�G���Ђƌ_�A�^�]��A�J�����}���ȂǂƂƂ��ɉ��x�����E�𗷂��A�啨��ނ�A���̕L���������B�������A�_���勛�͂����ȒP�ɒނꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�ނ́A�A���X�J�̐�ŃT�P�ނ�����Ă���Ƃ��̏�Ԃ����̂悤�ɕ`���Ă���B
�u�X�J�Ƌ����őS�g����(��ށj��Ă��܂��A�������P�S���ԑ����ĊƂ�U���Ă����Ɉ����A�^�����Ȃ������B---���߂��܂ŕX�͂̐�������ɂ���A�������D�ɐ[�������肱�݁A�������璭�߂�Ǝ��͐�Ɏh��������{�̖_�̂悤�ł���B-----�_�Ɖ������������̎p���������猩����A���ɂ��H�Ȑ�捂̌����Ƃ��o�J�̂�����Ƃ��f�邾�낤�B�������A�{�l�̔畆���͂��ł݂�ƁA�Ȃ��Ȃ�����ǂ���ł͂Ȃ��B�ő��ƌ��ӂ�����邪��閾�ł��āA�ς����݂����ɂȂ��Ă���̂��B��Ƃ��Ă���͒ނ�Ȃ����Ƃ��炭��̂����A�ق��ɒނ�Ƃ͊W�Ȃ��ϔO�A�ϑz�̗ނ������Ƃ��݂����A����܂肠���ďo�v�����f���[�T�̎ւ̂悤�ɂȂ��Ă���B�ނ�����Ă��邠�����Ɏ��̂�����ɕ����������t���O��������ɂ�����A�v�킸���w�������Ȃ邾�낤�B�X���A����A�����A�A�S�A�ƂĂ���捂̌����ȂǂƂ��������̂ł͂Ȃ��B�����P�C���ނ�Ȃ��Đ��ӂ��狎��Ƃ��ɂ��ڂ��邠�̔�J�̂��т��������́A�̗͂̏��Ղ��͂����Ɣ^��ŕ��s���������痈��̂ł���B���͎��g�̏X���ƉA�S�ɂւƂւƂɂȂ�B�����������̂��炢����������ɓ����o�������Ȃ��Đ��ӂ֗����͂��Ȃ̂ɂ܂����Ă��o����Ă��܂��v�i�J�����u�i�N�l�N��̃L���O�v�P�X�V�O�N�A�w�T�Ԓ����x�ɘA�ځB�����M�S�A�u�t�B�b�V���E�I���v�w�I�[�p�x���J�����S�W�A��P�U�����j�B�Ȃ��u��捂̌����v�Ƃ������t�̓E�H���g���́w�ދ���S�x���痈�Ă���悤���B�i���j
�i���j�ѓc�́w�ނ�ƃC�M���X�l�x�̂Ȃ��ŁA�w��S�x�́u���ł̍Ō�ɂ���u�����݁A�Â����Ɠ��ƒނ�������邷�ׂĂ̐l�X�̏�ɁA�j��������܂��悤�Ɂv�Ƃ������t�A�����đ��ňȌ�t��������ꂽ�u�Â��Ȃ邱�Ƃ��w�ׁv�i�hStudy�@to be quiet�h�j�Ƃ����u�e�T���j�P���̎莆�v����̈��p�ɁA���̖{�̐��_���W��Ă��邱�Ƃ͊m���ł���v�Ɨ͐����Ă���B��62,244,250�ȂǁB
�����A��ܔłɂ��ƂÂ��Ƃ����X�G�l�ɂ��M��́i�E�H���g�����g�̕M�ɂȂ��ꕔ�́j�����ɂ����ẮA���̌ꂪ������Ȃ��B���O�̗t�́u�_�̎����ɕ�܂ꂽ�����Ƃ���������̂����ׂĎ��M�����A��Ɋ��ӂ���悤�A�F���Ď~�݂܂���B���y�e���̏j�����A���Ȃ��̏�ɂ��A���̏�ɂ�����܂��悤�Ɂv�Ƃ������t�ɑ���A�ނ�t�i�E�H���g���j�̌��t�́u�����āA���������A�_�̐ۗ���M������̂̏�ɂ��B����ɉ��a�Ȓނ�t�̏�ɂ�����܂��悤�Ɂv�Ƃ������̂ł���B
�ѓc�̏����Ă��邱�ƂƐX�̖�̂ǂ�������ׂ����͌��߂��Ȃ����A���炭Study to be quiet�Ƃ������t�͂����ꂩ�̔łɂ͂���A�J���͂��̔ł��p��œǂ�ł����ƍl������B�u��捁v���邢�͐Â����́u�����v�ȂǂƂ����ꂪ�ЂƂ�łɂłĂ�����̂Ƃ͎v���Ȃ��B
�Ȃ��A�u�����v�̃e�T���j�P��ꏑ�Ȃɂ͑�S�͂P�P�߂Ɂu�Ƃ߂ė������������������A�����̎d���ɐg������A�肸���瓭���Ȃ����v�i���{���������j�Ƃ������t������A International Bible Society��HP(http://www.biblica.com/ )�ɂ��� "make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands"
�ł���B
�������肪�Ȃ��̂ɁA14���Ԃ��X�͂̐�������̗����₽����Œނ葱�����ނ̔S��͐q��ł͂Ȃ��B���ʂ̐l�Ȃ�A����Ȉ������̉��ł̒ނ�ł���A�ǂ�ȂɔS���Ă��S�`�T���Ԃ��ւ̎R�Ƃ����Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B�q��Ȃ炴��J���̔S��A���C���A�ނ�14���ԗ₽����ɗ��������������B�������A�l�����l�����Ƃ����C���������ł́A���ꂻ�̒����Ԃ̔S��͐����ł��Ȃ��B
�J���́A���t�ł͂Ȃ��B�������A��l�ŗ��āA�V�тŃT�P��ނ낤�Ƃ����̂łȂ��A�ލs�L�������Ƃ����d���̈�Ƃ��āA�ނ�K�v������̂ł���B�m���ɁA�ނ�Ȃ��Ă��A�ލs�L�A�ނ�̋�S�k�͏����邾�낤�B�������A�ǎ҂��ǂނ��Ƃ����҂��Ă���̂́A�ނ�Ȃ������ނ�̋�S�k�ł͂Ȃ��A�勛�������グ�A�傫�������J���ď��ގt�̎ʐ^���Y����ꂽ�A�����ɋ�J���Ēނ�グ�����������ꂽ�L�ł��낤�B���{�̉����Ƃ����ǎ҂ɁA�ނ�Ȃ������ނ�̋�S�k�������̂ł́A�����̎g���A�E�����ʂ����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B�ނ̃i�N�l�N��ɂ�����S��̂́A�W���[�i���X�g�A�ޕ��w�҂Ƃ��ėǂ��d�������悤�Ƃ���q��łȂ���M���A�ƌ����邾�낤�B�������A�ނͤ���ǁA�ނ���y���ނ��Ƃ��ł��Ȃ������B�ނ͏�M�I�ɒނ���s�Ȃ������A����͈��̋�s�ł������B�ނ́A���悤�Ƃ��čr�s���s���s�Ȃ��m�Ɠ����悤�Ȏp���Œނ�Ɍ������Ă����B
�H��܍�ƁA�����Ƃ̊J�����́A�����ɁA�W���[�i���X�g�A���|�E���C�^�[�Ƃ��Ă̎d���ɁA�H�L�̍˔\�������ЂƂł���B���̍˔\�́A�����E�^���������̊�Ō��A�̌�����ƂƂ��ɁA�l�ɍL���`���悤�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ă̋�����M�ɂ��x�����Ă����B�ނ͑����̗��j�I�厖���̌���ɍs���āA���ڎ����̖ڂŌ��A�����͂��̎����Ɏ�����֗^���A�L�����������B�R�T�̂Ƃ��A�x�g�i���푈�́u�����v��`���邽�߂ɓ�x�g�i�����{�R�ɂ��Ă������W�����O���ł́A�������e����Ɋ������܂�A�㎀�Ɉꐶ���B���{�R���Q�O�O�l�̂����A�����c�����̂͋L�҂̊J�����܂߂P�V�l�����������B�ނ͂��̃W�����O���킩�琶�҂ł����Ƃ��A�悵�A���ꂩ��Ȍ�̐l���̓I�}�P���A��肽�����������邼�A�ƌ��S�����Ə����Ă���B�w�I�[�p�A�I�[�p!!�����S��������ҁx�u�����A�W�A�̑����ɂāv
�u���̔������v�ւ́u���Ƃ����v�i�P�X�V�S�N---���̂Ƃ��S�X�j�ł́A�R�O�ア���ς��ƂS�O��O���A���낢��ȍ��̐���A�����n��A�w���\���Ȃǂ����|���ĕ������B����Ȍ���C�O���Q�͑����������݂�����Ă��邪�A�����ς�i�`�������X�g�k���R���D�Ɓl�Ƃ��ĒފƕЎ�ɂł���A���͂�߂���ƌ����Ă���B�ނ̂�肽�����Ƃ͒ނ�ł������悤���B�������A�ނ͏������Ƃ͎~�߂Ȃ������B
�P�S���Ԑ�̒��ŊƂ�U�葱���Ă��_���������ނꂸ�A�����肳���S���Ȃ��Ƃ���A�͂��o�����Ă������Ǝ��́A�����������������A�{��Ɏ����悤�Ȃ��̂Ɏ��t����邾�낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�������A�ނ������Ă���͎̂��]��{��Ȃǂɗ��܂�Ȃ��B�ނ́A���̂Ƃ��̏�O�������Ɓu�X���ʼnA�S�v�Ȃ��̂��Ɗ����Ă���B�������������R�́u�^��ŕ��s�������v�A���i�A���̒��ɂ���Ɓu�����̏X���ƉA�S�v���ӎ��������āu�ւƂւƂɂȂ���́v�A�u���ꂩ���ڎU�ɓ����o�������Ȃ��Đ��ӂ֗����͂��v�̂��̂Ɂu�܂����Ă��o����Ă��܁v��������ł���B
�ނ������Łu�܂����Ă��o����Ă��܂����v��^��ŕ��s�������̣�Ƃ͕ʂ̌��t�Ō����Ƣ�����̋��C�v�ł���B�ނ͕������A�O�̎��R�Ǝ��Ȃ̓��̗����Ɍ��o���Ă���B
���{�ł͓S���̉��𗬂��삪�A���ނ�t�����ō��݂����Ă��镗�i�������Ό���B���{�̉͐�͕���������l����������قǗ���Ă͂��Ȃ��Ɗ�������B�����A�A���X�J�̉͐�Ƃ����Ζ��l�̍r��𗬂��u���R�v���̂��̂Ǝv�����݂����ł���B�Ƃ��낪�A�J���ɂ��A�A���X�J�ł��L�[�i�C��ɂ͔N�ԂQ�O���l�̒ގt���k�Ă��牟���A�V�[�Y�����͖����Q�T�O�ǂ���R�O�O�ǂ́k���[�^�[�l�{�[�g���o�āA�V�`�Wm�����ɕ���Ő�𗬂�Ȃ���ނ�B���邾������ƍĂя㗬�ɖ߂��āA�������Ƃ��J��Ԃ��B�u��̗���̂܂܂Ђ�����---����čs���{�[�g�̐��ƁA���̂������������ƍ��g���R���Ăď㗬�֓ːi���Ă����{�[�g�̌��i----�A���̃{�[�g�̖����ƌ��������Ђ��߂�����˂���ƁA�N�͋����̍������܂��܂ƌ����t�����āA�w�^�w�^�ƂȂ邱�Ƃ��낤�B��O�ւ������ƁA�ނ�ɍs�����Ƃ���C�܂݂�̊��p��Ō�������C�̕�������̈̑�ȓ�����ł���Ȃ�A�����Ď������̒ʂ�Ȃ̂����A���C�̍��ׂ��瓦���o�������肪�����łӂ����т����Ƃ��I���ȋ��C�̕����ɂł������ƂƂȂ�B�v
�L�[�i�C��Œނ�グ���L���O�T�[�����������J���B�ʐ^�̓}���n�j�`���E�T�[�����~���[�W�A���A�u�T�P�ƕ����v
�ihttps://www.maruha-nichiro.co.jp/salmon/culture/b01.html�j�̕\������ؗp�B�u�͖͂���Ȃ��v�͂Q�O�O�X�N�Q����
���|�t�H�Ђ���ł��ʐ^�𑽂��܂ޒ����ŁA�L�[�i�C��ł̃{�[�g�̗����ނ�̖͗l���܂܂�Ă���B�����̓���
�i��f���Ԗ�T�O���j���Q�O�P�U�N�S���V����YouTube��Ō��J���ꂽ�B
�Ȃ��A�ѓc�́w�ނ�ƃC�M���X�l�x�̒��ŁA�c����`���ނ蕶�w�̎傾������i�̈�Ƃ���Roderic Haig=Brown�́w��͖��炸�x
A River never sleeps�@�Ƃ����{���グ�Ă���B�J���̂��̒����Ɠ���̖��͂������痈�Ă���̂ł͂Ȃ����B

�J���́A�ނ�Ɋւ��ď��������̑����̐��M�̂Ȃ��ŁA��ł��C�ł��A�ł��A�ނ�ꂪ���łɕ����ɂ���ĉ�������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��J��Ԃ��w�E���Ă���B�����āA�u��������̒E�o�́A���R���l�ׁE�l�H�̔ے�Ƃ����l�����邢�͒Z�������낤�B���Ƃ̈�Έ�̑̂����Ό��H�������{�[�g�A����A�l�H�I�Ȃ��̖����ł͒ނ肪�n�܂�Ȃ��v�Ƃ������B
�J���́A�����̋��C���瓦��悤�Ƃ��ăA���X�J�̑厩�R�̒��ɂ���Ă����Ƃ����̂ɁA�ĂсA���̕����́u���C�̕����v�ɏo���킷�B�A���X�J�̎��R�Ƃ����Ă��A���[�^�[�{�[�g�������ƍ��g�𗧂āA�悢�ꏊ����낤�Ɛl�X�������������Ă��āA�Ó�̊C��A����A�����Ƃ�����s��̌�����Z�����Ɣ�ׂĂ��A���͂������Ĉ��Ȃ����Ƃ�����B�������A���ꂾ���Ȃ�A�ȂA���Ă��O�ꂽ�ƁA���_���邾���ŏ\���ł͂Ȃ����B������������͒ނ�͐l�H�I�Ȃ��̖����Ɏn�܂�Ȃ����Ƃ��[�����m���Ă���͂����B
�ɂ�������炸�A�s����X�Ŕނ��A���R�Əo���̂��Ď��R�Ɠ��������Ƃ������ł���B�A���X�J�̌���𗬂��E�b�h���o�[�A�k�V���K�N�쐅�n�ł̃T�P�ނ�ł́A��h���Ȃ���{�[�g�Ő�������Ēނ�B�N�}���o��ꏊ�ŏe�������Ă����B�����āA�u�A���X�J�ɂ͉Ⴊ����B�A�}�]���̉�̓}�����A���������A��������ł���V���܂ł̂P���ԂɌ�����B�A���X�J�̉�͓ł͎����Ă��Ȃ����A���A���A�ӁA�ꏊ����݁A���ؗсA�ΔȁA�������������܂��Ȃ��B���ł��A�ǂ��ł��A���܂ł��A�O��I�ɂ��܂Ƃ��O��I�Ɏh���܂���B�_�Ák�ρl��̉A�ł��悤�Ǝv���ƁA����łׂ̂��E�̂��K���҂���҂��Ⴝ�����Ă��Ȃ��Ƃ����܂����ʂɂȂ�B�v
�u���W���̃W�����O���𗬂���ł́A�A���A��A���ƁA���N�C���i�čf���炢�̑傫���̃_�j�ŁA�̂̏_�炩���Ƃ���͂��ׂĂ����B�җ���y���A�Ȃ��炵���B�������A�P�T�Ԃ��P�O�����ƓˑR�u���Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����B�j�ƁA��i���킲��̃W�[�p���̏ォ��ł����܂킸�h���Ă���j�ɋꂵ�߂��A�u���������Ȃ����悤�Łv��E�ς��A�͓����A���s������B
�I���m�R��Ńp���H���i�o�X�̈��A�s�[�R�b�N�E�o�X�̃X�y�C���ꌗ�ł̖��́j��ނ낤�ƃx�l�Y�G���Ŏ~�����h�́u�V����ǂ������A�e���ۂ��R���N���[�g�̑ł����ςȂ��ŁA���������Ȃ��B�x�b�h������ɂ͂��邪�̂���ɒ���ł݂���A�S���S�������������Ă݂���B�_�ÁA�䎶�āk�ρl�͌ˊO�̑��ނ�łǂ����A�Ƃ����C�����B���[�\�N�̓��������Ă��܂��Ɛ^���ÁB---���Ă������Ă������Ȃ��M���ł���B�S�g���ʂ�ʂ�т���т���̊��܂݂�ł���B�ł̒��ʼn��H����Ⴊ�ˊO���玩�R�ɂ���Ă��ău���u����т܂��A�`�N�`�N�Ǝh���B-----�������C���Ȃ���̔M������Ӓ������邱�ƂȂ������A���̂����������ςȂ��̔˂���R�[��������э���ł�����A�o�b�^���|�S�̂͂�̂悤�ȑ��Ŋ���܂�����肷��v�B
�C�g�E�i�T�P�Ȃ̋��œ��{�ōő�̒W�����j��ނ낤�Əo�����������S���ł́A�����ŋ�������蹂̍��������₽���J�̂��߂ɁA�����ԃe���g�ɕ����߂�ꂽ�B�u�X�J���~��A���ꂪ�k�݂���l�ɂȂ�A���ꂪ����ɂȂ����B--���ꂪ��ނƋ����ɂȂ����B���ꂪ��ނƁi�܂��j�X�J�ɂȂ����B�������炵�̍����ŁA�X���т������Ȃ��Ƃ���łR����������B���肶�肵�Ȃ��炽���ς���B������킽���Ă����ҕ��̉����X���[�s���O�E�o�b�O�ɂ����肱��ŃG�r�̂悤�ɑ̂��ۂ߂Ă��v���B���ꂪ���R�Ƃ̑Λ��A���R�Ƃ̐킢�łȂ��ĂȂ�ł��낤�B
�S�U�̒��N�j�J���́u�Ⴂ�Ƃ�����̕s�ې��̂��߂ɁA�w�������݂����ɂȂ�A���͌Ճo�T�~�Ƃ����|�S�̂�ȂɐH�����܂ꂽ�݂����ɒɂ��A���E�̎��w���V���V���ƒɂ��Ȃ�����A���тꂽ�肷��----�̂Ń}�O�l�b�g�����O----���������蔃���Ďw�ɂ͂߂��肵�Ă����v�Ə����Ă���B
�Ƃ��낪�A�ނ藷�s�ɂł����A���R�ƑΛ����邱�Ƃ́A�ނ̒��ɂ��鎩�R�Ō��N�ȓ�������߂�����B���N�C�����̏P�����A�A�}�]���͌�����u��]�������̂ڂ邤���A�O�������ƁA���̒ɂ݁A���̋ꂵ�݁A�w��Ⴢ�A�������������Ă��܂����̂ŁA��̃����O�͍b����͂֒@�����B�܂�A�_�o�̗}�������Ƃ��Ƃ��������炵���̂�----�v�B�����ł́A�����̋��C���Ճo�T�~�̂悤�ɁA�ނ̐S�g�̂��ׂĂ����킦����ŗ������Ƃ͂Ȃ������B�Ƃ��낪�A���R�̑����Ŏ��R�Ɠ����Ă���ƁA���̌Ճo�T�~�͂ǂ����ɍs���Ă��܂��̂��B
�ނ�́u�{�[�g�����A�����Đl�H�I�Ȃ��̖����ł́v�n�܂�Ȃ��B�������A�ނ�́u�̂����Ό��v�ł��邱�Ƃ������ł���A�ނ�̗��ɏo�邱�Ƃ́A�ނɁA�̂̒��Ɏc���Ă��鎩�R��ڊo�߂����A�{���̗̑́A���N���ꕔ�ł͂���A��߂�����̂��B�ނ�̗����A���ււ̕�������A�����A�o�ŊE�A���{�A�܂蕶������̒E�o�ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B
�ł͂Ȃ��ނ́A���i�A�����̂Ȃ��Ŋ����Ă���Ƃ����u�X���ƉA�S�v�����Ȃ��悤�ɐ�̒��Ŋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��낤���B
���ɏo�Ă��Ȃ��Ƃ��́A�����ɂ���Ƃ��̊J���͂��Ȃ�Ȃ��珑�ւɕ�������A���e�̒��ߐ�ɒǂ��鐶���𑗂��Ă����B�u���̐����́A�܂�ʼnB�҂̂悤���B�ꎺ�ɂ��ꂱ�߂�����ň�����Ȃ�ƂȂ��E�������ɉ߂����A�����[�т�H�ׂ�Ƃ��������Ɩ��N���ɂ����肱�݁A��X���ɂނ�����N���オ��B���̂S�����납��k�[�́H�l�T������܂Ŋ��Ɍ��������A�����Ă��A�O�����ɍ����ĉ��������A�悵�Ȃ����ƂɎv���ӂ����ĂƂ��ɂ͂��₵�������������Ȃ�B----����̂悤�Ƀo�[����o�[�֓n������Ă����̂͂U�N�O�A�S�T���炢�܂łŁA����Ȍ��----�S�������P�ނ����B---�����Ď��̈���͈ꎺ�ɂƂ�������������ŏI�n���A�g�C���ƁA���ƁA���N���̎O�_���������邾��������A�Ɩ[�̎��l�ƂقƂ�Ǖς��Ƃ��낪�Ȃ��B---�������[�^�[������o���ꂽ���Ƃ����������A���Ȃǂ͈���Q�O�O����������ǂ����B---�ɒ[�ȉ^���s���B�j�R�`���B�A���R�[���B�ϑz�B�S�����X�g���X�B----�����ׂʼn������ł��邩�������߂����Ȃ��Ȃ������_�̖�����������----�v�B
�J���́A�ނ̔����R�I�ȕ��������A�܂�d������E�o����K�v�������Ί������B�E�o��͊C�ł���A��ł����āA�ނ͒ނ�ɏo�����邱�Ƃŕ����̋��C���瓦�ꂽ���Ǝv�����B��O�ւ������ƁA�ނ�ɍs�����Ƃ͢���C�̕�������̈̑�ȓ�����̊�Ăł������B
�ނ̂��������̋��C�Ƃ́A�ނ���芪�����A��s����A���{�Ƃ��������Љ�̒��ɂ���A�ނ����̒��ɕ����߁A�B�҂̂悤�Ȑ����𑗂邱�Ƃ�ނɋ����Ă�����̂ł���B�B�҂Ƃ́A�l�Ƃ̌�����₿�A�����Љ�𗣂�ĎR��̒��ŕ�炷�l�̂��Ƃł���B�������A��ƊJ�����̎d���͂P���́u�����Љ�v�̐l�X�Ɍ����āA�����Љ�̗L�l���������Ƃł���A�ꎺ�ɢ���ꂱ�߂ģ����͕̂a�ސg�̂����ł���B�S�͑��ς�炸���C�̕����Љ�̒��Ŝf�r�𑱂��Ă���B
�u�����I���w�_�v�ŊJ���́u�������͓��{�Ɠ��{�l�������Ȃɂ����Ă������Ă݂����Ǝv���B�`�x�b�g�ƃj���[���[�N�A�����Ւf�Ɠd�q����H��A�y��Y�z�ƈ�{�P�O���~�̃i�|���I����R�j���b�N�ɖO���Ă���㗬�K���A������k�A�l�������ɔ×����Ă��邱�̓ʉ��A�M�N�V���N�̜�Y��L����S�e�ɂ����ĂƂ炦�����B���b�A���b�A�������A���b�A���������A���A���|���^�[�W���A���̑����ׂĎ�ɓ������̔��z�@�ɂ����ĕ`���Ă݂����B�v�ƌ����Ă����B
����́w���{�l�̗V�я�x��w���蓌���x�Ȃǂœ��ă`�L���푈�A�[��i���A�v���I�����s�b�N�A�^�N�V�[�^�]��̐��E�A���w�A�y�b�g����A���n�̂���s�S���A���䂠�ꂱ��A�\���Z�A�J�Еa�@�A��ˎ����̖���A�o�҂��A��쓮�����A���n�̗\�z���A���ς݂̐V���o�D�A���̎t�A����A�z�e���w�Z�A���V���Aetc�Aetc�̂W�O�ҋ߂����|�ŁA���푽�l�ȁu�����Љ�v�̐l�ԂƂ��̎p��`�����B
���́A�R�O�㔼�̂���A���䓇�Œނ�������A��A���C�D�D�̑D�̒��ŁA�R���s���[�^�[�v���O���}�[������Ă���Ƃ������N�y�̐l�ɂ������B����͐����ԋx�݂����A���䓇�̈�Ńe���g���Ĉ�l����ʼn߂��������ƁA�Ăюd���ɖ߂�Ƃ��낾�ƌ����Ă����B�ނ̓v���O���~���O�̎d���𐔃����̊ԁA�x�݂���炸�ɂԂ������ł��̂��Ƃ����B�d�������Ă���Ԃ͋x�݂����Ƃ͎v��Ȃ��Ƃ����B�������A��Ђʼn��������d���𑱂��Ă���ƁA������ˑR�A�����ɁA���R�̒��ň�l����ʼn߂��������Ȃ�B�����Ȃ�����A�ނ͖���|�����܂炸�A�L�����v�p��̋l�܂��������b�N��͂ނƔ��䓇�ɂ���Ă��āA�ł���g�̉��╗�̉����Ȃ���A�����ԁA�e���g�ŕ�炷�B�h�ɂ͔��܂�Ȃ��B�l�Ƙb���������Ǝv��Ȃ��B�ނ���V�т��������Ǝv�������Ƃ͂Ȃ����A�i�F���y���ނƂ����̂ł��Ȃ��B���ł����Ȃ���ΓV������ł͂Ȃ��B�����A��̏�ɒ������e���g�ŕ�炷�����ł����B�d���𗣂�āA��l����ł��邾���ł����B���̂悤�Ɍ���Ă����B�A��̑D�̒��ł́A���̎��R�ɐZ�肽���Ƃ����~�����������ꂽ�ゾ�����̂ŁA���Ƃ̎G�k�ɂ��������̂��낤�B
�����̎��́A������w�̔��u�t��\���Z�̍u�t�Ȃǂ̃A���o�C�g�����Ȃ���A�u�傽��ƌv�̎x���ҁv�ł������Ȃɑ����āA�Ǝ��A�玙���s�Ȃ��A�c�n�̎�����̊����Ȃǂɂ����Ȃ�̎��Ԃ������Ƃ������A�ꖖ�̉f��ٕ��݂̂R�{���āA�S�{���Ă̐����𑗂��Ă����B��̎d���ɏW�����邱�Ƃ͂Ȃ������B�x���ɂ͍Ȃ��Ǝ��E�玙���s�Ȃ����̂ŁA���́A���ɂP�A�Q��͍D���Ȓނ�ɏo�����邱�Ƃ��ł����B
�O�ł̎d�����A�Ǝ��E�玙�̎d�������肪����A�d�����s�Ȃ��Ă���Ԃ́A�ق��ɂ�肽�����Ƃ������Ă��A���̓��e�̈��ʂ̎d�������Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�`���ł���A����������B�ނ�����Ă���Ƃ��ɂ͑S�����R�ł���B����͋��ł���B�ނ�Ȃ��Ă����܂�Ȃ��B�������s���A�ނ邽�߂̍H�v�E�w�͂��ő���s�Ȃ����A�ނ�͋`���A�d������̉���ł���B��������̒E�o�ł���B
�������A���̃R���s���[�^�[�v���O���}�[�̂悤�ȁA�E�o�̕K�v�ɑ���ؔ����A�Q�슴�̂悤�Ȃ��̂͊��������Ƃ͂Ȃ��B�H�L�ȍ˔\�Ɍb�܂ꂽ��Ƃł������J���́A���̃v���O���}�[�ȏ�ɁA�d���ɏW�������͂��ł���A���ꂾ���ɁA���X�́A�d������E�o����K�v���A���ɋ������������낤�Ǝv���B
�m���ɕ�������̒E�o�A���R���u�����邱�Ƃ͒ނ�̖ړI�̈ꕔ�ɂȂ肤�邪�A�J���̏ꍇ�A���̕�����������̒E�o�Ƃ������@�����܂�ɍV���āA�ނ���y���߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƌ����Ȃ����낤���B
�J���͂P�X�W�W�N�ɂT�W���X�Ŏ��B���̒Ǔ����w�����C�J�x�����W��J������1990�N�V�����ŁA���{�a���i�G�f�B�^�[�j�́u��͐��v�Ƒ肷�镶�ŁA�u�x�g�i���푈�A�r�A�t���̐푈�A���ߓ��̕����Ɛ푈��ǂ����J������́A������������Ƃɔ��Ă��܂����B----�ގt�ƂȂ����J������͐푈��ǂ�������悤�ɐ�֏o�����Ă������B��͐��ł������B��̐��ŏo������킢��{�ɂ��āA�o�ł�----�v�Ə����Ă���B
�w�����C�J�x�����ł́A�J���̍ȂŎ��l�̖q�r�q���A�J����]�������̍�Ƃ̌��t���Љ�Ă���B�J���͍�Ƃł���Ƃ͉����Ƃ������Ƃ����낵���^���ɖ₤���B�ނ͎����ɎO�̖������B���͌����͉����Ɩ₤���ƁB�����̑e�e�i���炠��j������f��Œ͂�ł݂邱�ƁB���͎��ȂƂ͉����Ɩ₤���ƁB��O�͏����Ƃ͉����Ɩ₤���Ƃ������A�Ƃ����B
���{���u��͐��v�Ƃ������t�Ō������Ƃ����̂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��낤�B�J���́A���̐l�����Ă��Ȃ��^����͂݁A�ގ��g�̃{�L���u�����[�ł��̐^����\�����A�l�X�Ɏ������Ƃ�O��I�ɒNj������B�J���̓x�g�i���̐��ł͓G�̑|����C���Ƃ��镺�m�ƍs�������ɂ������A����́A���̌���ɍs���Ȃ���킩��Ȃ��^���A������͂ނ��߂ł��������낤�B��ꂩ��P�ނ����J���́A���x�́A���ۂɐ��C�ɍs���āA����ނ��āA����������̌��t�ŕ`���o�����Ƃ����B�����������Ƃ{�͌��������̂��낤�B
���́A����Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ŁA�J���ɂƂ��Đ�͐�ꂾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ނ͂P�O�����ԁu��{�̖_�v�̂悤�ɐ�̒��ɓ˂������ăT�I��U���Ă���Ƃ��A�u�ő��ƌ��ӂ�����邪��閾�ł��āA�ς����݂����ɂȂ��Ă���v�ƌ����Ă���B�ނ������̏��ւɕ�������A���ߐ�̔����Ă��錴�e��O�ɂ��āA�M���i�܂��ɂ��炾���Ă���p�Ǝ��Ă��Ȃ����낤���B�i����͖����т������Ă���̂����j�l�C��ƂɂȂ�ƁA�A�ڏ������P�O���{�������A�P���̌��e���R�ς݂ɂȂ�Ƃ����B���ǁA��������ׂĂ��Ȃ��̂�����A��Ƃƌ����̂͂��������̂����A�u�`���Ƃ�����݂ł�����߁v�Ŏd����f��Ȃ��炵���B��Ƃ��ǂ�قǍ˔\������A�V������i�̍\�z�╶�͂⌾�t�����X�ɗN���o��ɂ���A���N�ɂ킽���āA�u���ߐ�v�ɒǂ�ꑱ���邱�Ƃ͐S�g�ɖ����������邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�J���͢�Ճo�T�~��ɋ��܂�Ă���悤�ȑ̂̂��������̒ɂ݂₵�т��s�ې���̂����ɂ��Ă������A�s�ې��͂����P�ɔނ̌l�I�Ȑ��i���{�I�Ȑ����ԓx�Ȃǂ������炵�����̂��Ƃ͍l�����Ȃ��B�T�����[�}���̂悤�Ɏ��Ԃɔ����邱�Ƃ͂Ȃ����A�܂��t�ɕs�K���Ȑ�����������������A��Ƃł��邱�ƂƐ[���W������Ǝ��͎v���B
�ނ͐H������Ŏ��B����o�������A���R���O�Y���A���V�ƂŔ��H�Ƃł��������Ƃ��������k�߂����ł��������Ƃ͊m�����Ə����Ă����B���������V�Ƃł�����H�Ƃł��������Ƃ͔ނ̂c�m�`�ɂ�邱�ƂȂ̂��낤���B�X�g���X�����܂�ƃA���R�[�����~�����Ȃ�Ɠ��l�A�X�g���X������V��Ɍ����킹�邱�Ƃ��悭���邱�Ƃ��B���͊J���̍�Ɛ����̃X�g���X�����V�ɁA�����ĕs�ې��Ɍ����킹�A�����đ̒��̒ɂ݂�Ⴢ�������N�����a�C��ނɂ����炵���̂ł���A�ނ��ɂ��������ƂƂ��W������Ǝv���B
���ɂ́A�ނ����������̋��C�Ƃ͉��ł���̂��悭�킩��Ȃ����A�ނ͎����������̋��C�Ɉ͂܂�Ă���Ɗ����A�ގ��g�����C�Ɏ��t����Ă���Ɗ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�u���]�ƒޖ������S��ފƂ̋��n�v�Ƃ܂Ŕ������Ȃ��Ƃ��A�u��捂̌����v�Ƃ������炢�̂��Ƃ͌������������̂��낤�B�����A�ނ͎��g���u�X���A����A�����A�A�S�A�ƂĂ���捂̌����ȂǂƂ��������̂łȂ��v�Ƃ����B�ނ́A����u��̒��̈�{�̍Y�̂悤�Ɂv���������Ĥ�ނ�𑱂��Ă��鎩�����u�X���A����A����----�v���Ɗ�����B�ނ͓��̒����u�ނ�Ƃ͊W�Ȃ��ϔO�A�ϑz�̗ނ������Ƃ��݂����A����܂肠���ďo�v�����f���[�T�̎ցv�̂悤�ɂȂ��Ă���ƌ����B
�ނ�Ȃ����ɤ�ނ�ȊO�̂��Ƃ����낢��v��������ł��邱�Ƃ͂�������B���ꂪ�A��������Ă���A�ڂ̒��ߐ��A�\�z�A�o�ŊW�҂Ƃ̌��������ꂽ����̍�i�̕]�����X�A�d���ɂ��Ă̂��Ƃ��Ƃ���A�悭���邱�ƂŁA���R�Ƃ����v����B�������ނ́A�l���݂͂��ꂽ�^�����ŁA�O�̐��E�̌����𑨂��邱�ƁA���ȂƂ͉����A�����ď����Ƃ͉����Ɩ₤���Ƃ�Nj������B�u�ނ�̌����v���Ɠ��̃{�L���u�����[��ςݏd�˂Ă������ɂ���ċɂ߂Ė��͓I�ɕ`����Ă��邪�A����͔ނ̕��˂��炷����قǂ̋�J��v���邱�Ƃł͂Ȃ��������낤�B
���́A���̂��߂ɤ�N�̂��߂ɁA�ނ�̌����������̂��A�����˂Ȃ�Ȃ��̂��A�A���X�J��x�l�Y�G���̐�̓r�A�t����x�g�i���A�U�W�N�T���̃p�����X�Ɠ������u����v�Ȃ̂��A�ނ�����邱�Ƃ͐��ɕ����A�f���̑���ɉ����̂Ɠ������u�����𑨂���v�s�ׂȂ̂�----�u���낵���^���Ɂv��Ƃł��邱�Ƃ̈Ӗ���₤�₢���A�ނ�̂��Ȃ��ɔނɌ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B
����̓C�g�E��ނ邽�߂ɏo�����������S���̍����ŋ�������蹂̍��������₽���J�̂��߂ɁA�����ԃe���g�ɕ����߂��A�X���[�s���O�o�b�O�ɂ������Ċ����ɑς��Ă����Ƃ��̑z�O�����̂悤�ɏ����Ă���B
�u����܂ł̂T�U�N�Ԃ̐��U�A����������蔄�肷�邱�ƂƔE�ς��邱�Ƃɂ����A�v�����Ă����悤�ȋC�����ɂȂ�B������ƌ֒��͂�����̂́A�����ł���B�R�T�̂Ƃ��ɓ���A�W�A�̃W�����O���킩�琶�҂ł����Ƃ��A�悵�A���ꂩ��Ȍ�̐l���̓I�}�P���A��肽�����������邼�A�ƌ��S�������̂ŁA���̂�����͂悭���ڂ��Ă���̂����A���ꂩ��Q�O�N�A����ς�蔄��ƁA�Ë��ƁA�E�ςł������B���肾�A���Â��B���A��A���A��A����B�����v�B
�u�j�R�`���B�A���R�[���B�ϑz�B�S�����X�g���X�B------�����ׂʼn������ł��邩�������߂����Ȃ��Ȃ������_�̖�����������----�v�B�J���̉s�����Ȉӎ��́u���ւɐ��ꂱ�߂�v�s���R�A�����R�̍�Ɛ������A�����̋��C�Ɏ�����Ă���Ɣނɍl���������悤���B�ނ͕����ƁA�܂���Ƃł��鎩�ȂƓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl�����B���R�̑����ŊƂ��ӂ���Ď��R�Ɋy���݂����B�������ނ��ނ�ɏo������͕̂�������E�o�A�������邽�߂ł���A�y���ނ��߂ł͂Ȃ��B�ނ�͕�������̒E�o�̒P�Ȃ��i�ɂȂ��Ă��܂��B�ނ́A�������͂��Ă���Ɠ����Ɏ����̒��ɑ��H���Ă���Ǝv��ꂽ�����̋��C�Ɛ키���߂ɁA�����̊C���ɍs�����̂��B�������A�ނ��ł���줊C�ɍs���Ă��A�������ς�����킯�ł͂Ȃ��B�ނ́A���ς�炸�A��Ƃł���A�ނ�̕��������A�u�蔄��v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��҂͕a�l�����Â���������B�_�Ǝ҂͕Ă�������Ĕ���B��Ƃ͕��͂������Ĕ��邱�ƂŁA���v�𗧂Ă�B���̕s�v�c���Ȃ��A�����Ȏ����ł���B�ނ�̍D���ȍ�Ƃ��X�|���T�[�̔�p�ŁA���E�𗷂��Ēނ�����邱�Ƃ��ł���̂ł���B���܂��������̂Ȃ��Œނ�邩�ǂ����A�����̃v���b�V���[�͂��邾�낤���A�Ƃɂ������̕������Ƃ����͓̂�����O�̂��Ƃł���A�����ď������Ǝ��͉̂��ł��Ȃ����Ƃł���͂����B�ނ�D���ȍ�ƁE�J���ɂƂ��Ă���߂Ă��܂��b�������͂��ł���B�����A�ނ́A�f���ɁA���邢�̓i�C�[�u�Ɋ�ׂȂ������B
�ނ͍�ƂƂ��Ă��̒ލs�L�������B���Ȓނ藷�s�͂��̕�V�̈ꕔ�ł���B�x�g�i���ɍs�����̃��|���^�[�W���������ۂɁA�ނ͐V���Ђ�����h���Ƃ��Ă̕�V�����B�푈�̌�����`���邱�Ƃɂ͏\�̈Ӌ`��ނ͌��o�����B���炭�A��V�������Ă��A�ނ́A������댯�蓖�̂������Ƃ͍l�����A���̏̕d�v���ɂ��̂��ƍl���邱�Ƃ��ł������낤�B�������A���Ԃ�A�ނ́A��Ō����R�̖₢��₢�Â��Ă�������A�ލs�L���������Ƃɂ́A�x�g�i���̃��|���^�[�W���Ɠ����悤�ȈӋ`�����o�����Ƃ��o���Ȃ��������낤�B�ނ́A���ւł̎d�����~�߂āA�ނ�ɂł����A�������A�ލs�L�������_����ȏセ��͎d���ł���A�V�тł͂Ȃ��B�������A�d���ł���Ȃ�A���̂��߂ɏ����̂��A�l������Ȃ��B���邢�́A�A���X�J�́A�A�}�]���́A��ɍs���͕̂�������̒E�o���ƈʒu�t����B�����������Ƃ́A���{�A�o�ŊE�A��Ɛ����ł���B�ނ��ނ������̂́A���{�̒ނ�t�@���A�o�ŎЂ����߂Ă������ƂƂ��ď������߂ł���B�ނ͐�̒��ŁA�����̒��ɗ��܂葱���Ă��鎩�Ȃ��Ĕ�������B�ނ͂��̖����������Ȃ��l�₵�A���ȂƓ����B
�ނ̒ނ肪���̂悤�Ȃ��̂ł������Ƃ�����A�ނ͒ނ���y���ނ��Ƃ��ł��Ȃ������ł��낤�B�ނ́A��ŁA��������ѕ��������ꂽ���ȁA��Ƃł��鎩�ȂƂ����G�Ƒ������A�키�B��͐��ɂȂ��Ă��܂��B�ނ肪�����E�勛�Ƃ̊i���ł͂Ȃ��A���Ȏ��g�Ƃ̊i���A���邽�߂̏C�s�A��s�ɂȂ��Ă��܂��B�J���͒ނ���y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������A�Ƃ����̂͂��̂悤�Ɏ����z�����邩��ł���B
�J�������a�������Ə����Ă���l������悤�����A���́A�J���̒ނ�Ɋ֘A���ď�ŏq�ׂ����Ƃɂ��āA���a���W���Ă���ƍl����K�v�̂�����͑S���Ȃ��Ǝv���B�ނ̍s���A�����Ƀx�g�i���̐��ɍs���Ė��E���������ƁA���̌�̓i�`�������X�g�ɓ]���������ƁA�ނ肪��D�����������y���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��������Ƃ̂��ׂẮA�ނ��������v�z�Ƃ̊֘A�ŏ\���ɗ����\���ƍl����B
���͂���܂ŁA���̐l�̐����Љ�Ȃ���ނ�͈��̗V�т܂��̓X�|�[�c�ł��邪�A�ړI��ނ���̈قȂ邳�܂��ܒނ肪����A���m�ȕ��ނ͂ł��Ȃ��Əq�ׂĂ����B�Ƃ��낪�A�N�w�ҁE���R�߂́u�N�w�҂̖ڂ���݂��ނ�v�Ƃ������̂Ȃ��ŁA�ނ�͗V�тł͂Ȃ��J�����ƌ����Ă���B�ނ͋��t�̍s���{�ƂƂ��Ă̒ނ�Ƃ͈قȂ邪�A�V�тł��X�|�[�c�ł��Ȃ��A�J���ł���ނ肪����Ƃ����̂ł���B�i���������Y��w��P�X����J�u�����w�ނ���w�ԁ\���R�Ɛl�̊W�x�r�c�퐶�ҁA���R�����X�A�����V�N�j
���R�͂P�X�T�O�N���܂�ŁA�q���̍��͓����߂��̊C���ʼn��ł��ނ��Ă����B�P�X�V�O�N������Q�n����쑺�ɍs���悤�ɂȂ�A���Ɠ������������ĕ�炵�Ă���B������w��w�@�̋����̐E�������Ă��邪�A��쑺�ł͎R���̂�����A�肽���Ŗ�����Ȃ���A���Ԃɋ߂��̌k���Œނ�����Ă���i�w�u���v�Ƃ����v�z�x�A�V���ЁA�Q�O�O�T�N�j�B�Ώۋ��̓��}���ƃC���i�A�^�ĂɎ��X���̗F�ނ�A�~�Ɋ��o���B�ŏ��ɒނ���ނɂ����{�́w�R���̒ނ肩��x�i���{�o�ϕ]�_�ЁA�P�X�W�O�j�Ƃ��������ł������B
���}����C���i���Ώۂ��ƂȂ�ӂ��͌k���ނ�ƌĂ�邪�A�ނ͌k���ނ�Ƃ������t�ɂ͒�R������Ƃ����B�k���ނ�Ƃ́A�s��̐l���A�s��Ƃ͕ʕ��Ƃ��Ă̎��R�̌k�J�ɓ����čs���V�т̒ނ肾�B�{���̒ނ�͎d���Ƌ�ʂ���d���ɑΗ�������̂Ƃ��Ă̗V�тƂ��Ă̒ނ�ł͂Ȃ��A��炵�A�d���ƈ�̂ŁA���̊y���݂͎d���̍��ԂɊ�������d���Ɋւ���y���݂��Ƃ����B����͎����̒ނ肪�V�т̒ނ�ƌ����邱�Ƃ������āA�k���ނ�ł͂Ȃ��A�R���̒ނ肠�邢�͌k������ނ�ނ肾�ƌ����̂ł���B
�d���Ƌ�ʂ���Ȃ��u�J���ł���ނ�v�̃��f���́A��쑺�̈�ԉ��̏W���ɂ���z��h�̎�l�̒ނ�ł���B���̐l�͎����Œނ�������H�ׂ邱�Ƃ����邾�낤���A��ɁA�h���q�ɒ���H���̂��߂ɋ���ނ�̂ł���A�h���o�c����T�[�r�X�ƂƂ��Ă̘J���̈ꕔ�Ƃ��čs������̂��B�m���ɂ��̐l�̒ނ�́A�E���t�����ƂƂ��čs���ނ�ł͂Ȃ����A�d���^�J���Ƃ��čs���Ă���B�������A���̗��ق̎�l�́u���Ƌ��t�v�ƌĂԂ��Ƃ��ł��A�u�V�тł͂Ȃ��ނ�A�d���^�J���ł���ނ肪����v�Ƃ����咣���A���̏h���̎�l�̍s���Ă���悤�Ȓނ�̂��Ƃ��Ƃ��������̘b�Ȃ�A�����Ŏ����u���܂��܂Ȓނ�v�̈��ނƂ��Ăӂ��قǂ̂��Ƃł��Ȃ��B
���R�̋c�_�͂���������ɍs���B��쑺�̂ق��̑��l�����Ɨp����̂��߂ɂ����Ȃ��ނ���A�����Ɛ藣���ꂽ�����ȗV�тł͂Ȃ��B�R���ł͎����邽�߂̘J���Ǝ��Ɨp�앨���������H����������肷��J���Ƃ̊Ԃɋ�ʂ��Ȃ��B�����āA�R���̐����ł́A���ׂĂ����R�ƌ𗬂��s����i�w�R���̒ނ肩��x�j�B
�u�J���Ƃ͎��R�Ɛl�Ԃ̌�ʂł���v�Ƃ͂��ĎႫ�}���N�X���q�ׂ��L���ȃe�[�[�ł���B�܂��A���R�́u�ނ�͘J�����v�ƌ����e�[�[�́A�}���N�X�̒���̈ꕔ��ʂ肢����ɂ����ǂ��Ƃ̂Ȃ����ɂ��v���o�����w�h�C�c�E�C�f�I���M�[�x�̂Ȃ��ŏq�ׂ��Ă��鋤�Y��`�Љ�̃C���[�W�A�Љ�S�ʂ̐��Y���K�����Ă���A�N�����Œ肵���E�Ƃ������ƂȂ��ɁA���R�Ɂu���͎���A���͋��k�ނ�l���A�[�ׂɂ͉ƒ{�������A�H��ɂ͔ᔻ������v���Ƃ��ł���A�Ƃ�������A�z������B���R�́A�k���ł̒ނ�����A�}���N�X�i��`�j�ɂ�����u�{���̘J���v����сA�a�O���ꂽ�J���ɂ��Ă̎v�z�A�i�}���N�X�ɕs�����Ă���j���R�ی�v�z�A�����Ď��{��`�Љ�ɑ���Љ�ɂ��Č��̂ł���B
�ނ́u����̐��_���ɓo�ꂵ���������̐��h�̓N�w���T�u�e�L�X�g�ɂ��ēN�w���w��ł����v�ƌ����Ă���i�w���R�ƘJ���x�j�B���́A���̘_���Ń}���N�X��`�ɂ������̐��̕K�v�����������Ƃ����~�{���ȁi�w���j�厫�T�x�̒ߌ��r��ɂ��j�̖{���A�V�O�N��Ɉ��������ǂ��Ƃ�����Ƃ��������œ��e���S���o���Ă��Ȃ��B���ɂ̓}���N�X��`��v���_�A���邢�͎Љ��`�Љ�Ȃǂɂ��Ę_����͂��S�������Ă���B
�������A�ނ�́A�{���A�V�тł͂Ȃ��A�l�Ԃ͖{���J�����鑶�݂ł���A�J���Ɛ藣���ꂽ�V�т�X�|�[�c�����߂�ׂ��ł͂Ȃ��ƌ����āA�m���U������Ēʂ�߂���킯�ɂ͂����Ȃ��B
�����܂߁A������{�̎Љ�ɐ�����l�̂قƂ�ǂ́A�ނ�́i��쑺�̏h�̎�l�̂悤�ȁ����Ɓ����t�̒ނ���܂߁j�{�E�̋��t�̒ނ�ȊO�́A�V�тł���ƍl���Ă��邾�낤�B���̏ꍇ�A�V�тƂ͎d���ɑΗ�������̂ł���A�d������E���łĊy���ށA���R�Ȋ����ł���B���������āA�ނ�͗V�тł͂Ȃ��J���^�d���̈ꕔ���ƌ������R�̎咣�́A����������ʓI�ȍl�����ɗ����́u�ނ聁�V�сv�_�̂���ΑS�ʔے�ł���B
���̑O�ɗ����ӂ��������̂́A����u�N�w�ҁv�Ɩ���鐔���Ȃ��v�z�ƁA�����҂̈�l�ŁA�����̒�����ʂ��Ď����̎v�z��W�J���Ă���_�q�ł���B����������̐��́u�J���ߒ��_�v���Ƃ����A�w�J���̓N�w�x�Ƃ�������������B����́A�E�Ƃ�J���Ɋւ���v�z�̐��Ƃł���B���͓�G�̓��R�̐��ɂ��܂��������A������i�삷�邱�Ƃ��ł��邾�낤���B
�ނ̓Ɠ��ȁu�ނ�ρv�͔ޓƎ��̘J���ρA�l�ԊρA����ɂ͎��R�ςɂ���ė��ł�����Ă���A�ނ͂��̘J���ρE�l�ԊρE���R�ςɊ�Â��Č�����{�Љ��ᔻ���A����ׂ��Љ���\�z���Ă���B���́A�ނ�͗V�тł͂Ȃ��J�����Ƃ����ނ̐��ɔ��_���A�ނ�͗V�т��Ƃ����펯�I�Ȏ��̗����i�삵���������ł���B�ނ̐l�ԊρA�J���ρA���R�ρA�����Ă���ׂ��Љ�ɂ��Ă̔ނ̍\�z�̑S�̂�������Ɨ������A�K�v�Ȃ炻���ᔻ����Ƃ�����Ƃ�{�i�I�ɂ�肽���Ƃ͎v��Ȃ����A���̗͂�����Ƃ��v��Ȃ��B
�������A�ނ́w�R���̒ނ肩��x�ƌ����{�́u�ނ���ނƂ����{���v�Ɣނ͌����Ă���̂����A�����ɂ͔ނ̘J���ς͂������̂��Ɛl�ԊρA�Љ�ρA���R�ρA����ׂ��Љ�ɂ��Ă̍\�z�ɂ��Ă����Ȃ�̒��x�q�ׂ��Ă���B�����ŁA�܂��ȉ��́i�P�j�ł͂��́w�R���̒ނ肩��x���Љ�Ȃ���A�ނ̐l�ԊρA�J���ρA���X���܂����炩�ɂ������B���ꂩ��i�Q�j�Ō��J�u���ł́u�ނ聁�J���v�_�����������_���邱�Ƃɂ���B�Ȃ��ނ̘J���ς��邢�́u�ނ�ρv�́u�]�Ɋρv�i�ނɌ��킹��u������]�Ɂv�ɂ��Ă̔ނ̔ᔻ�I�����j���܂ށB�����ł��łɁA�i�R�j�Ŕނ̗]�ɘ_�ɂ��Ă����_�������B
�w�R���̒ނ肩��x�ł͂����ɎO�̃e�[�}���������Ă���B�܂��A�s��l�ł�����R���k���Œނ���s�Ȃ��Ă���p�����͂̎��R�ƂƂ��ɕ`����Ă���B�ނ��ނ������̂́A�������A��̈�p��O���R���痬��o�ė�����ɒ����_���i����ȁj��Ƃ����k��ł��邪�A�R�̎��R�̒��ɓ���u���R���v������Ɗ����Ȃ���ނ������ނ̎p���`�����B
���̃G�b�Z�[�̑��̃e�[�}�͐�ł���B�ނ͐_���쉺�������̊X���ƒ��̂Ȃ��褐삪�ʂ��Ă��������̕ϑJ���]�ˎ���ɂ����̂ڂ��ĕ`���B��͂��Ĕ��������s���A�����ł͕������^������D���s��������u����v�ł�����������݂͓r���ł������̃_���≁�Œf����ꤒ��߂Ďg���p���ɕς����Ă��܂����B�ނ́A�_���͖L�x�Ȑ��g�p���\�ɂ���Ƃ����s�s���̗��v�̂��߂ɍ��ꂽ���̂ł���A�_�����݂͓s�s���ɂ��R���̐l�X�̍��Y�i�Ƃ┨�j�ƐX�т₻���ɏZ�܂����������Ɛ�ɏZ�܂����Ȃǎ��R��j���R�����𗪒D����s�ׂł���ƁA�_����B
�O�ڂ̃e�[�}�͓s�s�̃T�����[�}�������Ƃ͈قȂ�R��(��쑺)�̐l�X�̕�炵�ł���B�����ł́A����̔_�Ƃ̂悤�ɒP��앨�����_�ƂƂ��Ⴄ�A�R���̖L���Ȏ��R�𗘗p�������l�ȘJ������炵��V�тƘA���������́A��̂̂��̂Ƃ��čs�Ȃ��Ă���Ƃ����B�����āA�܂��R�ɏZ�ޒ��⓮���Ƃ̑��l�̢������������B
�G�b�Z�[�́A�����O�̃e�[�}���ӑR��̂ƂȂ��čI�݂ɐD�グ��ꂽ�ꖇ�̐D���̂悤�Ɏd�グ���Ă���B�����đS�̂��т��āA�s�s�ƎR���A�l�ԂƎ��R�A����(�ߑ�)�ƑO�ߑ�̑Η��E�����A�O�҂ɂ���҂̔j��Ƃ����傫�ȕ��ꂪ�����B���������ڂ������e���Љ�悤�B
����͎q�ǂ��̂���A�܂�����������Ă����������c�J�̐�ł��܂��܂Ȓނ������Ă����B������ł������ނꂽ�B�������A�����̐�͎��X�ɂǂԐ�ɉ����āA�߂��̐�͈Ë��ɂȂ������܂����B����������̂ЂƂł������낤�B�܂������炭�A�ނ��A������e�N�j�b�N��v����ނ�A�ǂ��łł��ނ��G���ł͂Ȃ��A���̒ʂ����u�������v��_���ނ����肽���Ȃ����̂ł��낤�B�Q�O�̂���ɐ_����ɗ����B�h�͕l���Ƃ����n��ɂ���A�̂��炠��z��h�ł���B
�k������ނ�͓̂���B�Ƃ��ɎR���́A�{�B���͕̂ʂƂ��āA�a�����킦�Ă����ٕ̈��i��j�����m����Əu�ԓI�ɓf���o���Ă��܂��̂ŁA���킹������A�͂��߂͑S���ނ�Ȃ������B���֓��A���߂��ɓ������A�[���ꎞ�ԂقNJƂ��o��������ނ�ʂ܂܊����ɕ����đ��X�ɏh�Ɉ����グ�Ă���ƁA������ɂ�����l�������B�u�����A���Ă����̂����v�B�u����ȂɊ����Ă͋C�͂������Ȃ��ł���v�B�u��������ǂ��Ă���悤���Ⴞ�߂��B���ꂩ�炾��B�ǂꎄ�ɂ��Ă�������Ⴂ�v�B
�h�̎�l�́A���R����قǒނ����A�ނ̊Ƃɂ͋��M�i������j���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ���ŁA�ނ̖ڂ̑O�Œނ��Č������B����́u�傢�Ɍh�����A---�[�H���Ƃ�Ȃ���ЂƂЂƂ�����邱�Ƃɂ����v�B
���R�͕l���ɗ��Ă���P�N�Ԃ͑S���ނ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�u���̍��͋���ނ邱�Ƃɖ����������v�B�h�̎�l�Ɉꏏ�ɍs���Ă��炢�A�ނ���̃A�h�o�C�X������������B���ʂ̉a�������Ă�����Ă悤�₭�⋛��ނ邱�Ƃ��ł����B�u�������Ƌ����Ŏ���̌i�F���^�����Ɍ������قǂ��B---�̒��̌��ǂ��h�N�h�N�Ɩ����v�B
�u��N������Ƃ����ς��̒ނ�l�̂悤�Ȍ��������悤�ɂȂ����B�������A���ꂩ��܂���N����������A---�X�����v�Ɋׂ����B�S�R�ނ�Ȃ��̂ł���v�B�������A������r�N�i���āj���������A�ƐU��̗��K�����ɂ��悤�Ƃł������Ƃ���A�u��ςȑ務�ɂȂ����B���X�Ɋ⋛��������A�R����������B������Q�O�Z���`���z���̂���ł���v�B�������ăX�����v��E�����B�������u�܂���N������������v�A�܂肱�̒ނ���n�߂ĂR�A�S�N���������납��ł��낤���A����̒ނ�́u����߂ĒW���ɂȂ����B�����ɒނ낤�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B---�ނ邽�߂ɒ������N���邱�Ƃ��A�܂��R���[�����邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����B----�������ނ�̃R�c�����悤�ȋC�����Ă����v�B
�ނ͒ނ�Ȃ��Ă��悢�Ƃ����C�����ɂȂ��Ă����B����ނ邱�Ƃɑ��鎩�Ȍ������������B�u�l�����͎R�����r�p�����Ă������ɂ���l�Ԃł���B�s�s�͎R�������ȑ��B�̎�i�Ƃ��ė��p���Ă����B�����Ă���זE�̂悤�ȓs�s�����o���Ă����B���̐l�Ԃ��ĂюR������i�Ƃ��Ĥ�V�я�Ƃ��ė��p����A�����ɂ����̎��Ȗ����������Ȃ��̂��낤���v�B���́u���Ȗ����v��^���ɍl����Ȃ�k���ނ���~�߂�����̂ɂƎ��͎v�����A�ނ͈Ⴄ�B�ނ͌k���ނ�������l�̓s�s���̖������鎩�Ȃɂ��Ă̈ӎ����܂߁A������{�Љ�̌������ώ@���L�q����Ƃ������ƂɎ��Ȃ̎�̐��������������Ƃɂ����悤�ł���B
�u�����������ɂ͖l�͎R���ɒނ�ɍs���B�����ɂǂ̂悤�Ș_���������Ƃ��Ă��A���傹��A��l�̓s�s�̐l�Ԃ��R���̐���r�炵�ɂ����Ƃ����W�ł����Ȃ��B�R���̐l�X���ނ������͎̂R���̍Đ��Y�����̒��̈�ł���B�������l�̒ނ�͎R�����r�炷�����ł����āA���̍Đ��Y�ɂ͏�������^���Ă��Ȃ��̂ł���B����ނ邱�Ƃɑ��鎩�Ȍ����Ƃ͂��Ԃ�������Ă݂����Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B���X�ނ�x�̂ق��������Ɍ����Ă��邱�Ƃ�����B�ނ�x�Ȃ�l�͒ނ�x����i�Ƃ��ė��p�ł���B����Ȃ瑊���B������ł�����Ȃ��Ƃ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�_����ɗ����ĊƂ�U��ƁA���̏u�Ԃ���l�͒ނ�ɖ����ɂȂ��Ă���B�R����⋛�����Ƃ̂����Ђ��ɂ��ׂĂ̐��_���W�����Ă����B����������ł��Ȃ�����ނ邱�Ƃɑ���W���Ȉӎ��͏������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�B
�������āA���N�ԁA����ނ낤�Ɛ��������A�J���k��R���ɓ����Ă��������A���̒ނ邱�Ƃɂ������A���R�Ɂu����������v�s���͔ނ��R���̎��R�ɗn�����݁A�����ɐ��ސ��������ƌ𗬂��A�ނ����R������邱�Ƃł��������B�u�l�̂��Ȃ��V�R�т̎R�͑̂̒�ɑ͐ς���Ă����悤�ȋ��|����^���A�������R�ɕ�炷���������̐����̏ꏊ�����肾���B�ނ�l�����傹��R���r�炷�҂ł����Ȃ����褐l�����痣��Ă������Ƃ͂��ł����|�������̂ł���B���������Ɠ����悤�ɎR�̒��Ŏ������Đ��Y����k��炷�l���Ƃ��ł����Ȃ礎R�ւ̋���͏����͎�蕥���邩������Ȃ��v�Ɣނ͍l����B
�N�����Ȃ���ɉ����ĕ����A�Ƃ���ǂ���ŊƂ��o�����ނ�Ȃ��B����I��R�����A�Ƃ��o������͂�H��Ȃ��B�u�u���č����͋A�낤���B�v�N�����Ȃ��J�ň�l�Ő����o���ĊƂ����܂��B���Ɉ�C���ނ邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������ړI�͒B���Ă���悤�ȋC�������B�������̑�������B---���̂���ꏊ���o�����B----�����͈�x���s�����o���Ȃ������B�l���R�Ɋ���Ă����v�B�ނ͂������Ď��������R�Ɂu����v�A�u���R���v���Ă���Ɗ������B
�ȏオ�A��쑺�̎��͂̎��R�ƌ𗬂��k���ōs�Ȃ��Ă�����R�̒ނ�̕`�ʂƁA�ނ���s�����Ȃ̏Ȏ@�ɂ��Ă̊T���ł���B
�u�Ñォ����{�ł́A�p���̕ւ��m�����邱�Ƃɂ���đ�n�����n�тɕς��A�r���̐������邱�Ƃɂ���āA���n�т�c�ւƓ]�����Ă����B---�A���̊Ǘ��͑��̏d�v�Ȏd���ł���Â��Ă����v�B�R���ɂ������̖����͈��n�т̂���Ƃ͑S���قȂ�B�u���ɐ����̏�ł������B�P�O�N��炩�O�ɂ͐�͐����ݏ�ł��萆����ł���A�����ł������v�B�u�R�̂悤�ɐς܂ꂽ����������������Ă���i�F�v���������B�u���ɐ�͋���ł������B��O�ɐ쉈���ɃR�~���j�P�[�V�����̃��[�g���ł����B---��r�I�傫�Ȑ�ɂ͕K�����Y���悤�ɊX��������A�����ɏW�������܂�Ă����B---��Ɛ삼���̓����A�l�Ԃƕ��Ƃ̌Â�����̌𗬘H�ł��������炾�낤�B�����ɐ�̑�l�̖����������B�Ƃ����̂͐쎩�g���ЂƂ̌�ʎ�i�������̂ł���A�����ɗp���̊m���Ɣ䌨����قǂ̐�̑傫�Ȏd�����������v�B�R�����o���ꂽ�ۑ��͞��ŎΖʂ����낳��A��ł������ɑg�܂�������B���a�����ɂ́A���̂悤�ɂ��čޖ���������o�ē����ɉ^�ꂽ�B
�u�ߐ��ȍ~�̓��{�̓������̕����̗A���͐���g�����D�^�����S�ł������B---�]�ˎ��㏉���ɂ͊e�n�Ő����---�͐���C���s���A���̏�ɍ]�˒����ȍ~�̏��i�o�ς͊J�Ԃ���̂ł���B---������͍]�˂Ɗ֓��S����Ȃ��悤�ȑ哮���ւƕϖe�v�����B
�u��͑傫�ȗ��ʘH�������̂ł���B�Ƃ�킯����Ȃ��R���ɂ����āA��̖����͐���������ɔ�d��������Ă����v�B�����A����ł́A�R���ł�����̎v�z���������n�߂Ă��Ă���B�����̕��y�Łu�����̏�v�Ƃ��Ă̖����͏������A�{�B���̏o���͋���Ƃ��Ă̖��͂����r���������B�u�������Đ�͋}���ɁA�l�Ԃ̓����������A�i�ςƂ��Ă̐�ɕϖe���Ă���---�B�R������̐�̑ޔp�̐i�s�ł������v�Ƃ����B
���d�̂��߁A�_�Ɨp���A�H�Ɨp���A�������邽�߁A�܂������̖ړI�ŁA�����{�ɂ����đ����̉���_���k�������P�T���܂ł̂��̂���{�ł͉��ƌĂ�Ń_���Ƌ�ʂ��Ă��邪�A��{�I�ȈႢ�͂Ȃ��l�����݂���Ă����B�_�����݂ɂ���Đ�̗���͒f�����A�_�ƁA�H�ƁA�����p���́u�����r�v�ɕς���ꂽ�B
������̎x���̈�_����ɂ��鉺�v�ۃ_���B���R�����h���Ēނ�ɒʂ�����쑺�E�l���͂��̏㗬�ɂ���B�ʐ^��Wikipedia�B

�_����ɂ͉��v�ۃ_��������Ă���A�ʖ��_���Ƃ������B�����ɂ��߂�ꂽ���͓����ǂ��Ƃ����ē����ɐ����p���Ƃ��đ����Ă���B�_���́u�����͟��ꂽ�͐�~�ƂȂ��Đ̌��̊Ԃɑ������Ă���v�B���v�ۃ_���̏v�H�͂P�X�U�W�N�B��̍����͂P�Q�X���[�g���B���̃_���̒��ɁA�Q�T�L�����[�g���̓��H�A�R�P�O���тV�V�R���̉ƁX�A�w�Z�A�����ɁA�X�V�w�N�^�[���̓c���A�P�V�W�w�N�^�[���̎R�т��������B�V�O�N��̒����A�H���̂��߂Ƀ_���͓�N�߂����������グ���B���R�̓_���T�C�g�ɎԂ��~�߂āA�_���̒ꂩ��p�����������Ă̑��̑S�e���݂��Ƃ����B
�u������ꂩ��ς��Ă��܂��̂͂Ȃ�Ƃ����Ă��������̊J���ł���B�֓��̒n�ɂ͓�������s���Ƃ����Ƃق����Ȃ��傫�Ȃ���זE�����݂��Ă���v�ƁA���R�͓����Ǝ�s�����A���ׂĂ�ۂ݂��ݎ��Ȃ���u����זE�v�ɂ��Ƃ��Ă���B
�h��K�˂��߂��̑��l���A���R�����Ă����e���r�̃j���[�X�ɓo�ꂵ�����Z���m����ᔻ����B�u�����̒m���Ƃ��Ă͂悢�m����������Ȃ����A�Ȃ�ł������̓s���ǂ���ɐi�߂悤�Ƃ��Ă���̂��C�ɂ����v�B���l�����������Ƒ��̂��̂����Ȃ������B�u������̐��ȂS�������s������Ȃ����v�B����͓��R�̌����������Ƃł�����B
���∼����ł͂Ȃ������̋����C�Ɛ���s�������A�����Ə㗬���ړ�����ƌ����B����������_�����݂͂����̋����ړ����邱�Ƃ�s�\�ɂ���B���������Ȑv�ō��ꂽ�����������A���͎��ۂɂ͑k��ł��Ȃ��Ƃ����B��͍��ł́A���������_���Œf�����A���͒ʍs�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B
��͂��đD�^��������Ȃǂ��s�����嗬�ʘH�ł����������A���݂̐�͔_�Ɨp���A�H�Ɨp���A�㐅���̂��߂̒����r�ɂȂ��Ă���B�ߑ�ȍ~�̗��j�̒��ŗ���̎v�z�����ɁA���߂Ďg�����Ƃ�������̖����ɂȂ����B�u���Đ��1�̕��������Ȃ��Ă����B����ɉ����ĊX���ł���l�ƕ��ƕ����̌𗬂��s��ꂽ�v�B�u���ʂ��Ă̂��̂悤�ȊW�������邱�Ƃͤ�����̑����Ǘ����邱�Ƃ������B---���ʂƂ��ĎR���̉ߑa������������R���͓s�s�ւ̐��Ɠd�͂ƘJ���͂̋�����n�ɂȂ����v�B
�ȏオ��쑺�𗬂��_������ЂƂ̎x���Ƃ��A�֓�����𗬂ꉺ���ĊC�ɒ��������삪���x�o�ϐ����A�Ƃ�킯�����s���̂��߂̃_���̌��݂ɂ���Ă����ނ����ω��A����Ƃ��Ă̐삩��Ǘ����ꂽ�p���ւ̕ω��Ɋւ���ނ̐����ł���B
�̂���A�R���ł͎Ζʂ̔��ɔ��∾��B�A�����Ȃǂ�����Ă������A���������H�ׂĂ����̂ł͂Ȃ��A��H�ł���Ă��ĐH�ׂĂ����B�R�̎҂͕Ă���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ă������������ς��H�ׂ邱�Ƃ��ł����B���ہA�R�ɂ͌����邢�낢��Ȓ��d�����������A���̂悤�ɓ��R�͌����B
�u�l�X�͎R�Ŗ���ĉ��։^�B���}������A�Y���Ă��A�d���������B�Ắk��l���t�ł���~�͗t�ł������B���̂����\���������B������Ԃɂ͕S���ł������B---���̂悤�ȎR���̐����͂��܂ł���{�I�ɕς��Ȃ��B�����̑��ł͑����̉ƂŒő��ƂȂ߂�������Ă���B���ɂ������Ƭ����A�����Ă���B�~�ɂ͌F���傫�Ȏ��v��^����B�ŋߍĂђY���Ă��l���łĂ����B�����̂����R�ɂ͐��◎�t����˂�A���Ă���B�����Đl�X�͖̐�o���≺����̎R�d���ɏo��B���������H�H���ɏo��B���₻�̑O�ɗX�Lj��ł���A�c�я��̏����ł���v�B
�u�R�̊�I�Ȏd���������ł͓��H�H���̓����ɂ��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��B���l�͕S��������Ă��Ă͑����Ƃ����B����͔_�Ƃ���������Ȃ��ƌ������Ƃł͂Ȃ��A���d���̓����ɔ�ׂė��������ƌ������Ƃł���B�����瓖�R�̂悤�ɋ��t�͂ǂ��̑��ł����Ȃ��Ȃ����v�B�d���̎�ނ͌o�ρE�Љ�̕ω��̉e�����ω����Ă������A�R���ɂ͏�ɐl�X�̐�����L���ɂ��Ă����d���������Ղ肠�����B
���l�̘J���́A���ړI�Ɏ��R�ƌ𗬂��čs������̂ł���Ɠ����ɐ����i��炵�j�ƈ�̂ł���A���邢�͘A�����Ă��邱�Ƃɓ���������B
���c�͂Ȃ������͂���A���܂��܂ȍ앨�������B���s�ɂ���Ēl���オ�������́A�ׂ����ł�앨�͏o�ׂ���邪�A�����͎��Ɨp�ɏ�����B�u���̑��ł͂��܂��܂ȘJ�����s���Ă���B---���l�͘J���ɂ���ē��������������Ŕ��ɂ����A��������̎�Ŏ����̍D���ȘJ�����v��A���̒��a�̒��Ŏ����̘J����I�яo���B������\�ɂ��Ă�����̂́A�J���̈�����̓I�ł���Ƃ����R���̘J���̐��i�ł���悤�Ɏv����v�B
�R���̐��������o�����Ƃ���ǂ����Ă��J���͎G���Ȃ��̂ɂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l���̍z��h�̎�l�������ďh�������Ƃɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B��ʂł͔_���ł���A�����Ēő���Ȃ߂����͔|���A�܂����t�ł���A�R�̐��Y�����̎悵�A�܂�����Ĕ��̂��A����Ɏ����̉Ƃ��Ȃ����Ƃ��͑�H�ł�������B����ɍŋ߂܂ł͑��̋��璷�ł����������B�u���ׂĂ��J���ł���A���ׂĂ������̗Ƃł���Ƃ����R�̐����ƘJ���͊m���ɓs�s�̘J���Ɛ����ɑ���ЂƂ̃A���`�E�e�[�[���Ȃ��Ă���B�J���Ƃ͂ЂƂ̊�Ƃɋ߂邱�Ƃł���A���Ɏ��c�Ƃ��c�ނɂ��Ă��A���Ȃ��Ƃ��A�ЂƂ̎d�����Ƃɂ��邱�Ƃł���Ƃ����A�s�s�̊��o�͎R���ł͒ʗp���Ȃ��v�B
���R�̐�����ǂ�ł���ƎR���̘J���͂ƂĂ��y�������ł���B��N�ސE���Ă���ł͖�����������Ȃ����A�̗͂̂��邤���ɑ����ɑސE���R���ŕ�炻���ƍl����l�����邩������Ȃ��B
���R�͔�����čk���A���낢��ȍ앨������Ă݂��B�W���K�C���͏\���ɐ����������A��͂��܂��炽�Ȃ������B�W���K�C���̂ق��ɐ����������̂͑�Z�\�����������悤�ł���B�ނ́u�y�n�ɍ��������̂łȂ�����߁v���ƌ����B
�u����琬���⎸�s���J��Ԃ��Ă����Ȃ��Ŗl�ɂ��������R�̔��̂����R���Ƃ������̂��킩���Ă����B�y�n���삦�Ă����Ƃ������o��X�Βn�ƌ����y�n�̐��i���킩���Ă����B---���s�҂��R�������Ƃ�������悤�Ȕ��R�Ƃ������́A���ۓI�Ȃ��̂Ƃ��Ă̊��o�������������ꋎ��A�R�Ɛl�Ԃ̌����Ƃ������̂��킩���Ă����̂ł���B�����---���炩�ɖl���g�����R�̈���ɉ�����Ă����ߒ��������B�J���Ƃ͎��R�̐l�ԉ��ł��邪�A���ʂɂ����Đl�Ԃ̎��R���ł���B����͒ނ�l�Ƃ��ĎR���ɂ�������Ă��邩����킩��Ȃ����Ƃł������B�J���ɂ���Ď��R�Ƃ̊W������Ă������Ƃ��l�Ԏ��g�̎��R���𑣐i����B�R���̔��₢�̂������r�炵�I�����F�����݂ɗ���B�k���l���l��������e���邱�Ƃ��ł���̂́A---���l���g�����R�̈���ł���Ƃ������o���琶���Ă���̂��Ɩl�ɂ͎v����B---�J���͎��R���������邱�Ƃł͂Ȃ��A���R�Ƌ������邱�ƂɂȂ���v�B
�u�l�ԂƎ��R�Ƃ͂ǂ��܂Őڋ߂����Ƃ���ŁA���傹�̎��ȑa�O�W��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������_������Ƃ�܂�����ȓV�R�т̒��ŁA�ЂƂƓ����������̗ޓI�����邱�Ƃ͉\�Ȃ̂�������Ȃ��B�������l���G�łȂ����Ƃ�m��ƁA�l�Ԃ̓������������̐������̂Ȃ��ɐD�荞��ł����B---�F�����Ė{�B�̌F�͌����ċ��낵�����̂ł͂Ȃ��B�l�Ԃ̐���������Ɏ��߂Ȃ���A�����̂ق�����l�ԂƂ̋������͂����Ă����S�D���������ł���v�ƌ����B
���R�͌����u�J���Ƃ͎��R�̐l�ԉ��ł��邪�A���ʂɂ����Đl�Ԃ̎��R���ł���B����͒ނ�l�Ƃ��ĎR���ɂ�������Ă��邩����킩��Ȃ����Ƃł������v�B�����ނ͔����k���앨������Ă݂āA���̂��Ƃ��킩�����ƍl����B�u�J���ɂ���Ď��R�Ƃ̊W�������Ă������Ƃ��A�l�Ԏ��g�̎��R���𑣐i����̂ł���B---�������g�����R�̒��ɂƂ����܂��Ă������ƁA�����ɘJ�����Ȃ肽�ȏ�A�J���͎��R���������邱�Ƃł͂Ȃ��āA���R�Ƌ������邱�ƂɂȂ���B�����ɎR�ɐ��ސl�Ԃ̃��}����`���萶����v�B �ȏオ�R���̐����ɂ��Ă̔ނ̊ώ@�ƁA�l�ԂƎ��R�̊W�ɂ��Ă̔ނ̓N�w�I�e�[�[�u�l�Ԃ͘J���ɂ���Ď��R��l�ԉ����A�����Ɏ��������R������v�Ɋ�Â����_�I�����ł���B
�w�R���̒ނ肩��x�̒��ŏ�����Ă��邱�Ƃ��܂��ɎO�ɕ����āA�Љ���B�ȉ��ł͂����e�[�}�Ɋ֘A���ē��R�̏q�ׂĂ��邱�Ƃɑ��鎄�̔ᔻ���邢�͔��_���q�ׂ����B
���̇@�͓��R�������̒ނ�ɂ��ďq�ׂĂ��邱�Ƃɑ���ᔻ�ƌ������́A�w�ދ���S�x�̒��҃E�H���g���ɑ��ē��R���s���Ă���ᔻ���邢�͍U���ւ̔��_�ł���B�ގ��g�̒ނ�ɂ��Ă̍l�����̔ᔻ�͌�́i�Q�j�ŏЉ��u���J�u���v�ɂ�����ނ�_�̔ᔻ�Ƃ��čs���B
���R�́A�ނ��ʂ������R�Ƃ̈�̉��ɂ��ďq�ׂĂ����̈��p���̌��ɁA�u����ނ�ɂ��ċ���ނ�Ӗ����l���邱�ƂقNj����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�l�̓E�H���g���̂悤�Ȑ��_�͎������킹�Ă��Ȃ��v�Ƃ����ꕶ��t�������Ă���B���̉ӏ��ł͂��̕��̈Ӗ��ɂ��Ă͉��̐������Ȃ��A���˂Ȋ���������B�������w�R���̒ނ肩��x�́u��L�v�̂Ȃ��ōĂуE�H���g���̖��O�������A�w�ދ���S�x���u�ނ�N�w�̏��v�ł��邱�Ƃ��U�����Ă���B�u���J�u���v�̍u���̂Ȃ��ł��E�H���g���́u�ނ�N�w�v�����ʂɋ������Ă���B
�u��L�v�œ��R�͎��̂悤�Ɍ����B�u���̂Ȃ��ŃE�H���g���͋��ނ�̋Z�p���狛�̗����@�܂ʼn�����Ȃ���A�l���ɂƂ��Ēނ�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ������Ƃ�ȁX�Ƃ��ďq�ׂĂ���B�ނ�l�ǂ����̉�b�A���Ȃǂ��Ƃ����Ēނ�N�w������Ă����̂ł���B---���������͂��̒ނ�N�w�ƌ����v�l�����ɍ���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�ނ�̒��Ől������邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����Ƃ����_�ɂ܂����^�I������ł���B
�����ނ�N�w�̒��Ől������邱�Ƃ��ł���Ƃ���A����͗V�т̂Ȃ��Ɉꐶ�������邱�Ƃ̂ł���ЂƂ����ɋ�����邱�Ƃł��낤�B�������̓��V�A�����[���b�g�̎v�z�ł���B---�����������V�тł��邪�A�����������ɂ͗V�т̒��ł��������̐������m�F�ł��Ȃ��Ȃ����A�M�������̒�̂Ȃ��ޔp�̎v�z������B
�ނ�l���܂��ނ�̒��ɂ����������ł��Ȃ��Ȃ������ɂ̂݁A�ނ�̒��ɐl���������邱�Ƃ��ł���A������������܂����p�̒��ɐg�߂邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�Ԃ��ނ�N�w����邱�Ƃɂ́A�ǂ����ɃE�\������̂ł���B---���݂̒ނ�͐����Ƃ̊֘A�̒��ł����������Ȃ��B����Ȃ�ނ�Ƃ͂Ȃɂ��Ƃ������Ƃ��A���݂̐����Ƃ̊W�ŏq�ׂ��ق��������ł���v�B
�܂����R�́A�u���J�u���v�ł́u����ނ�s�ׁv�ɉ߂��Ȃ��ނ�Ɂu�v�z��l�����d�˂Ă����̂͋��Ȃ��Ƃ��v�ƁA�ނ��ނ�����Ȃ���t�����X�𗷍s���Ă����Ƃ��ɗ���������{���̎�l���������Əq�ׂĂ���B����͔ގ��g�̍l���ł����������낤�B
�Ȃ�قǃE�H���g���͔ނ̒����̒��ŁA���R�Ƃ͈���āA�l���ɂ����ĐE�Ƃ�J������߂Ă�������̏d�v��������������A�E�Ƃ�J���̈Ӗ��ɂ��Ē��ڌ�邱�Ƃ͂��Ă��炸�A�����̍D���Ȓނ�ɂ��Č���Ă���ɂ����Ȃ��B���������͓��R�̃E�H���g���ɑ��錃�����U���ɋ����B�E�H���g���͒ނ�D���̏��l�ł����āA��w�̌����҂ł��w�҂ł��u�N�w�ҁv�ł��Ȃ��B���R���ߐ��ȍ~�̓��{�Љ�̕ω��A�Ƃ�킯���o�ϐ����������炵���Љ�E�o�ϓI�ȕω������n�����悤�ɁA�E�H���g�����u�s���[���^���v���v�ƌĂꂽ�����A���������������炵�����������̉p���Љ�̌��ς����ʂ����Ƃ��ł����Ƃ͓���v��ꂸ�A���������Ă܂����������Љ�̕ω���w�i�ɁA�E�Ƃ�J���ƗV�т�X�|�[�c�Ƃ̊W��_���邱�Ƃ��ł����Ƃ��S���v���Ȃ��B
����������͒ނ��I�сA�ނ�ɂ��Ē�������s�������́����H���ɂ����āA�����̑����̐l�������������Ċւ�낤�Ƃ��������I�E�@���I�Ȃ��Ƃ���Ɂu�����������v���Ƃ����ۂ��A�l���ɂ͐�����@�������d�v�Ȏ���������Ƃ����ނ̎v�z���͂�����Ǝ����Ă���B�܂��ނ͒����̂Ȃ��ŁA�Ȃ����ꂪ�A�J���^�d�����܂߂��̂ق��̐��������ނ��I�Ԃ̂��ɂ��Ă�����Ă���B�E�H���g���ɂƂ��Ēނ�́A���_�⌠�͂�x��Nj����鐶���̋��ۂł���A�������������Ƃ̌��т���f�s���A�܂�V�т̈��ł��邪�䂦�ɁA�����Ƃ́u�W�v�ɂ����Ēނ��`�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
����͂��Ԃ�A���R���A�l�Ԃ͎��R�ɓ��������J�����鑶�݂��Ƃ����N�w�I�O��ɗ����䂦�ɁA�ނ���u�l�Ԃ̎��R���v�Ƃ����ϓ_�ƌ��т��A�u�J���������v�Ƃ����ϓ_�ɊW�t���Ę_���邱�Ƃ͂ł��Ă��A�ނ�̊y�����𑼂̗V�т�X�|�[�c�Ɣ�r���Ȃ�������ł����A�V�т̐��E�ɂ����Ēނ肪��߂�ʒu�A�܂�ނ�̑��̗V�тƂ̊W�ɂ��đS�������ł����A�������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃƃp�������ł���ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�w�ދ���S�x���ȒP�ɂ��Љ�Ă������B�w�ދ���S�x�́u�ނ�̓N�w�v�̏��q�́A�ނ����܂��ܓ��A��ɂȂ����鏠�A�t�Ɗe���̈��D����Ƃ���ɂ��Ă��̗ǂ����݂��ɔ�I�������������Ƃ����`���œW�J����Ă���A�M��̏����͑�ς��������Ȃ��̂����A�����Ŏ�����Ă���l�ԊρA���R�ρA���E�ς͂����f�p�Ȃ��̂ł���B
�w��S�x�ɂ͑����̎������p�����B�ނ�D���������C�[�g���E�J���b�W�w�����̃w�����[�E���b�g�����̎��ŁA�A�����������A�u��������̂��₩�Ȋ�тɂ��ӂ�A�����ɖ��������ĐV���������ށv�c���̂Ȃ��Œނ������y�������q�ׂ���B�W���[�E�_���B�I�̎��ŁA�u����҂͖@�ɔw���ĕx��~���A����҂͎��ɂ��ڂ�A�����╂�C�Ɍ������Ă���B���y�����߂���͉̂��y�ɐg���䂾�˂�悢�B�킽���͈�l�A���q��ɗV�ѓ��X����₩�Ȑ�ӂ��U������v�B�����ĂS�O�s�߂��ɂ킽���đ厩�R�̂��炵���������������ƁA�u����炷�ׂĐ_�̑n�����ɖڂ𗯂߁A�ނ�l�͂��̕s�v�c���A���̂��炵���ɋ����Ƃ��߂�����B�[���ґz���A--��т̖ڂŎ��R�����߂�Ƃ��A�S�͜����Ƃ��ċ������オ��v�ƌ����B
�����ĒN�̍삾�Ƃ������Ă��Ȃ��̂Œ��Ҏ��g�̍�炵���u�ނ�t�̉S�v�ł́A�u�S�ɐ[��������A���̈��݂̂�������B����ЂƂ���Ȃ��������ŁA���邢�͑��닅��S�̌����܂܂������ށB�������ЂƂ̘r�̂Ȃ��ɂ��̐��̍K���������A���ЂƂ�ނ���y���ށB��Ɋ댯�͂����̂ŁA�鏠���܂��R��������炤�B�q���͐S����킹�āA���̓V�g�͐g�̔j�ŁB�ނ�̓�����͊����Ȃ��B���̐��Ɋy���ݎR�قǂ���ǁA����C�܂܂Ȓނ�i���j��ԁB���̗V�т͖O�݂₷���B�ނ�݂̂ЂƂ�Ŋy���߂Ď��R�̓V�n��搉̂���v�B
�����ł́A���̐��Ɋy���݂͎R�قǂ��邪�A�ЂƂ͂��ꂼ��̈��D������ƌ����Ă���B���D���̐l������A�����e�j�X���D���Ȑl������B�����āA�q��������ɂ��ڂ�邱�Ƃ͐g�̔j�ł��ƌ����B����C�܂܂ɁA���R�ɍs�����Ƃ��ł���ނ肪��Ԃ��A�ƌ����Ă���B
�������u�ނ�l�̊肢�v�ł́A�u���Ԃ̍��ɂ����܂�Ă����炬�ɂ͎����X���A���R�ƒނ莅�������B---�����Ɍe�����͂Ђ����ɑ����̂��Ȃ��Ɏv�����͂���B�Ƃ�ɂ���ʔY�݂��ƁA�����̒��̌����G���A�������Ă��ЂƂ�ݕӂɍ����Ċy���܂�B---���z�̋P���₪�Ėv���������B��������̓��̏o�̋P�����������̖�ł��܂����݂�B�Î~�̂Ȃ��Ŏ��𑗂�ނ�̂ق��ɎG�O���Ȃ��₷�炩�Ȃ鉝�����Ƃ���v�B
�܂��n���[�E�E�H�b�g���������������̂��Ƃ������̈��p������B�����ł́u����Γ�S�т䂭�����Ȏ҂�A���ǂ��Ĉ����������t������B---�����Ƃ͂ނȂ����؍����ς��A�����͑��̉��̓y�����ڂ��B�h�_�͂킸������̗��l�B--���ƂƂ͉����̘S���ɂ��Ď��R�̉H���Αł��Ђ����B����т₩�Ȃ���̍s��A���͚����`�[�̌��{�Ȃ�B�M���̐��܂�ƌւ�ǂ��A����̗͂ɂ��炸�A���̈З͂ɂ��炸�A��`�̌����ւ�̂݁B���_�A�����A���ƂɌ����A����т₩�Ȃ�ߏւɔ��e�A�����͂��ׂ�����w�ԁB--�k�ȉ��U�O�s�l�B
�E�H���g���͎Ќ��ƂŁA�m�����܂ޑ����̗F�l���������k�ѓc�O�f���l�Ƃ������A�Ƃ��ɒm���K���ɑ����Ă����킯�ł͂Ȃ��B����������l�̏��l���ނ�̊y���݂ɂ��Č�邱�Ƃ��A�u�N�w�v���Ƃ����Ȃ炠���Ă���͔ے肵�Ȃ��Ă����܂�Ȃ��B���p�������͂��́w�ދ���S�x�́u�v�z�v�Ȃ����u�N�w�v�̃G�b�Z���X�Ƃ�������̂ł���B�����A�f���Ɍ���A���́w�ދ���S�x�͒ނ�̊y���݂�������f�p�Ȓނ�]�̂Ƃ����ׂ��ł���B
�E�H���g���͐ϋɓI�ɍs���͂��Ȃ����������}�h�ł������B�܂�v���e�X�^���g�̈�h�s���[���^���ł͂Ȃ����䂦�ɖ��炩�ɁA�ΕׁE�֗~�̗ϗ��Ɋ�Â��A�d���ɑł����ނׂ����Ƃ����l���������Ă��Ȃ��B
�n�̕��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���Ƃ��낪����B�u�����͌��N�ł���A�z�C�ł���A�킸���Ȃ����Ŋy�����H�ׁA�����݁A�����A�����Ēނ�����A�̂������A�������薰�邱�Ƃ��ł��܂��B�����ڊo�߂�ƐS�z���Ȃǂ����ƖY��ĉ̂��A���A�����Ēނ������̂ł��B�������̎l�\�{�̍��Y�Ƃ����āA���̍K������邱�Ƃ͂ł��܂���B----�ߏ��ɂ������Ԃ�Ƌ������̂ЂƂ����܂����A�ނ͂�����肷��ɂ��Ȃ��قǖZ�����̂ł��B�Ȃɂ�����ȂɖZ�����̂��Ƃ����A����ׂ��邽�߁A����ɑ����̋���ׂ��邽�߁A�̈ꎖ�ɐs����̂ł��B----����͂����Ƒ����̋���ׂ���ł��傤�B�����Ă����Ƃ����ƍ��Y�ƂɂȂ�ł��傤�B�����ēz��̂悤�ɔڂ����d���𑱂��Ȃ���A����̓\�������̌��t���ɋ�����̂ł��B��ΕׂȎ肪�x����飂ƁB���̌��t�͂Ȃ�قǐ^���ł��B�������l�Ԃ��K���ɂ���͕̂x�̗͂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɔނ͋C�Â��Ȃ��̂ł��B----���肬��̕n������������A�����Ă����ɂ��鎑�Y��^�����Ă�������Ƃ��Ă͖����ƂƂ��ɐ_�Ɋ��ӂ�������A�s������������A�_�̑��蕨���s�������ȂǂƂ������̂ł͂���܂���v�B
���̕��͒����̐̂��狳��Ő�����Ă����u���n�v�̎v�z���J��Ԃ��Ă���ɉ߂��Ȃ����A�E�F�[�o�[�ɏ]���Ύ��{�ƓI���_�̓y�䂽��v���e�X�^���g�I�u�ΕׁE�֗~�v�ϗ����E�H���g�����͂�����Ƒނ��Ă���̂��킩��B
�����Ă܂��ނ͐l�Ԃ��z���E�t�@�[�x���Ƃ���l�ԊρA�l�Ԃ̖{���͘J�����邱�Ƃ��Ƃ����l�Ԋς������Ă��Ȃ��������Ƃ͊m���ł���B�����ĔނɂƂ��Ď��R�́A�l�Ԃ��J���ɂ���������A�l�ԉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�u���̕s�v�c���ɋ����A���̂��炵���ɋ����Ƃ��߂����A--��т̖ڂŌ��߂�v�ׂ��_�̑��蕨�ł���A�^�����邪�܂܂Ɋ��ӂ��Ď��ׂ����̂ł������B����̓E�H���g���Ǝ��́A���邢�͔ނ̓Ƒn�I�ȍl�����ł͂Ȃ��A�����ȗ��ǂ��̋���ł������ꂽ�����ł���B
�ނ́A���R�Ƃ͔��ɁA�J���^�d���Ɛl���ꎋ���Ȃ��B�J���^�d���Ƃ́u���肬��̕n������������A�����Ă����ɂ����v�����̎����邽�߂ɍs�������ł���A�d���ȊO�̎��ԂɁA�D���Ȋ����ł���ނ�����R�ɍs���āA�_�̋Ƃł���厩�R�ƌ����A�_��m���т������������Ƃɐl���̈Ӗ�������ƍl���Ă����B�Ƃ���A�J�����邢�͎d���ɂ��ďڂ����q�ׂĂ��Ȃ��Ă��S���s�v�c�͂Ȃ��B
���R�́u���݂̐l�Ԃ͂����Ȃ�K�w�ɑ����Ă��悤�Ƃ��A�ꐶ��V�т̂Ȃ��ɐ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���ꂪ�ł��Ȃ��Љ�\��������B����Ȃ̂ɒނ�̒��Ől������낤�Ƃ���Ύ��ۂ̐����ɖڂ��ނ�K�v������v�Ƃ����B�����A�E�H���g���́A�ނ�����邱�Ƃɉ��́u���Ȍ����v�������Ă��Ȃ��B���Ȃ����܂������߂ɁA�u���ۂ̐����v�܂�E�Ɛ�������Ƃ���Љ�I�W�Ɂu�ڂ��ނ�v�K�v�������邱�Ƃ͑S�����������͂����B���łɏq�ׂ��悤�ɔނ́u�Љ�I�W�v���������A�l�@���邱�Ƃ��ł���m���K���ɑ����Ă��Ȃ������B�����ĉ������A�ނ́A�����̐l�X�ɂƂ��ďd�v���Ǝv��ꂽ�ł��낤����������@�������Ȃǂ́u�����̒��̌����G���v�ɑ���ւ����͂�����Ƌ��ۂ����̂Ɠ��l�ɁA�J���^�d����l���ɂ�����d�v���Ƃ݂͂Ȃ����A�����̎�i�ł����Ȃ����̂ƍl�����B�d�v�łȂ����Ƃ��ǂ����Ă��ꂱ�ꌤ�����l�@���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����낤�B
���R�́u�ނ�̒��Ől������邱�Ƃ��ł���̂��ǂ����Ƃ����_�ɉ��^�I�Łv�A�u�ނ�̓N�w�v�܂�u�J���������Ƃ͈قȂ銈���ł���ނ�̂Ȃ��ɐl���̈Ӗ������������ׂ����Ƃ����v�l�����u���ɍ���Ȃ��v�ƌ����B�����������R�̉��^�Ɓ��A�����M�[�̎�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���҂��������i�ނ�̕��@�E�Z�p�_�ł͂Ȃ��j�ނ�_�A�u�ނ�̓N�w�v���u�ޔp�I�v���́u���v���̂ƈ���I�Ɍ��ߕt���������낷�A�U���I�ԓx�͑S�����������Ȃ��B
���āA���R���ނ�ɂ��ďq�ׂ�Ƃ��ɐS�ɗ��߂Ă���͂��́u�����Ƃ̊֘A�v�Ƃ́A��쑺�ł́u�����Ƃ̊֘A�v����łȂ��A�ނ̉Ƃ�����܂��{�Ƃł���d�����s���Ă���s�s�ɂ�����u�����Ƃ̊֘A�v���܂�ł���Ǝv����B�ނ͎R���̐l�X�̐����A����єނ��R���ɂ���Ƃ��̒ނ�Ɣ��d���ɂ��Ă͏ڂ����ׂ̂Ă���B�������ނ̓s�s�ɂ����鐶���ɂ��Ă͉����q�ׂĂ��Ȃ��B
���R�͔ނ���������ʂ��Ă���ƌ����Ă��邾���ł���A�����ł̔ނ̐����A�܂���ʂɓ����s���̐������ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�ɂ��ĂقƂ�lj����q�ׂĂ��Ȃ��B�܂��A�s�s�Ƃ͒����J�����x�z�I�ŁA�u�J���Ɛ��������������v�Ƃ���ł���A�܂��R�������D���ɉh���Ă����l�X�̏W�܂��Ă���Ƃ���ŁA�l�X�́A�s�s�ł͎���ꂵ�܂������R�ɐe���ނ��߂Ƃ������������̓s�������ŎR���ɗV�тɂ���Ă���̂��ƌ����B�ނ́A���ۉ�����A�P�������ꂽ�s�s�����Ɠs�s�̐l�ɂ��Ă������Ȃ��B
�ނ̖{�Ƃł����w�����Ƃ����E�A����Ƃ��邢�͐V���̊�e�҂̂悤�Ȑ��_�J���́A�����ԍH��̗����Ƃœ����J���Ɠ������A���������ݏo�����s�s�^�J���ł��낤�B�����A�u��̐��v�Ƃ����ϓ_����͑S��������^�C�v�̘J���ł���B���҂����Ȃ��悤�ɁA�s�s�^�J���Ƃ��Ă����邾���ł����̂��B���̂悤�Ȑ��_�J������ł��鐶���ƁA�R���ł̔��d���ƒނ�Ƃ����ނ̗V�т̐����͊W������̂��Ȃ��̂��A����Ƃ���ǂ̂悤�ȊW���l�����邩�A���X�̕��͂�����������Ǝv�����A�ނ͓s�s�̐l�ԁ������J���҂Ƃ��ĎR���̐l�X�ɑΒu���邾���ł���B
���J�����s�s�ɂ����Ďx�z�I�ȘJ���ł���Ƃ������Ƃɂ͊ԈႢ���Ȃ��Ǝv���邪�A�����ŁA�s�s�ɂ�����J���`�Ԃ����̂܂܁u�s�s�̐����v�ł͂Ȃ��B�s�s�ł́A�R���̐����ƈ���āA��炵�A�������]�ɂ̊����ƐE�ƘJ���Ƃ��u�����v���Ă���B�����A�܂��A�s�s�̐����Ƃ͕��Y�E�̔����āA�����k���Ȃ��Đ��Y����l�u���������v�ł��邾���łȂ��A����������������A���܂��܂ȎЉ�^���ɎQ��������A�u�����ɂ���������v�A���ׂ���q�����ɖ����ɂȂ�����A���y��X�|�[�c�Ȃlj����D���Ȃ��ƁA���D���邱�Ƃɑł����݂Ȃ��琶���Ă������Ƃł����낤�B����͘J���Ƃ͋�ʂ���邱���s�s�����̏d�v�Ȕ��ʂɂ��Ă͉������Ȃ��B
�������A���R�͓s�s�����ɂ��ĉ�������Ă��Ȃ������łȂ��R���̐����Ɋւ��Ă��A�l�X�͎R�ł̎d�����y����ł���ƌ��������ł���B�k���ނ�ȊO�Ɏ���y���S���Ȃ��Ƃ����l����Ȃ̂ł��낤���B
���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�E�H���g�����A�����̎d���ɂ��قǑł����܂��A�����̉p���̈��d�v���ł����������ɂ��ϋɓI�ɂ�����낤�Ƃ����A�ނ肪���̗V�сi����ł͑�����͂قƂ�ǖ����ł��邪�j�Ɣ�r���āA�܂����ׂ��▼�_�⌠�͂�ǂ����߂鐶�����ɂ���ׂĂ��炵�����̂ł���ƌ�������Ƃɂ͏\���ȈӖ�������B
�قƂ�ǂ̐l�͗V�Ԃ����ł́i���邢�͂����ɂȂ�Ȃ��{�����e�B�A�̎Љ�������ł́j�����Ă����Ȃ����A������Ƃ����āA�����邽�߂̊����ł���J���������l���̖ړI�Ȃ̂��ƍl����K�v�͂Ȃ��A�����邽�߂ɕK�v�ł��邻�̕��ʂ��������A�c��̎��Ԃ������̍D���Ȃ��ƁA���Ƃ��Βނ�ɑł����݁A���̊y��������������{�������Ƃ������Ƃ��A�\���ɍm��ł��邱�Ƃł���B
�������Ƃɂ��čl���邾���łȂ��A�V�тɂ��čl���邱�Ƃɂ��\���ȈӋ`������B�l�Ԃ͖{���J�����鑶�݂��Ƃ������R�̑O��͂Ȃ�疾�炩�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�E�H���g���́u�ނ�̓N�w�v�ɑ���ނ̍U���͓����ɂ���Ȃ��B�i����c�����I�ɂȂ�����������Ȃ��B�j
���R�̒��슈���̍ŏI�ړI�͌�Ō���悤�Ɂu�J���{�ʁv�Љ�̎����ɂ���Ǝv���邪�A���́w�R���̒ނ肩��x�������ړI�́A�⋛���ނ��悤�Ȍk�����c�����ƁA���������L���A�R�������̈ꕔ�ł��鎩�R��ی삷�邱�Ƃɂ��邾�낤�B����͎R���̎��R��ی삷�邽�߂ɂ́A�R���̐l�X�̎��������������\�ł���悤�Ȏd�g�݂����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ����B���̓��{�̌o�ϐ������x�����u�J���v�z�v�́A�u�R����s�s�����̎�i�ƍl���v�A�R���̕x�k��̗���A�X�сA�R�l��D���A�R�����������邱�Ƃ�s�\�ɂ��Ă����B�k����X�т̕ی�́A�s�s�̐l�X���ނ��ό����y���ނ��߂̎����Ƃ��ė��p����Ƃ������z�Ɋ�Â��Ă����߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�R���̐l�X���g���R�̎��R�𗘗p���Đ������s���Ƃ����A���������o�ύ\�������K�v������B���ꂪ�w�R���̒ނ肩��x�̎�|�ł���B
�ނ̌����u���������R���o�ρv�Ƃ����l���ɂ́A�R���̐l�X�̋��K�I�Ȏ������ǂ��m�ۂ��邩�A�E�ƑI���ɂ�����D�݂̖����ǂ��l����̂��Ȃǂ̓_�ŋ^�₪���邪�A��܂��ɂ����A�������J���i�ꕔ�Ɂu�^����h���v�������j��ړI�Ƀ_�����݂�i�߂邱�Ƃɔ����A�R���̐l�X�̐����ƎR���̐X�т����i���E���R��ی삷��j�ׂ����Ƃ����咣�ł���Ɨ������邱�Ƃ��ł��A���̌���A���R����ƃ_���Ɋւ��ďq�ׂĂ��邱�ƂɎ����^������B�Ƃ��ɁA���́A�_�����݂ɂ���āA�����ЂƂ̒n��Љ�̂��̂����ł��Ă��܂��Ƃ������ƁA�����łȂ��Ă��A���̒n��Љ�Ђǂ����Ȃ��A�������̐l�X���Ƃ┨�������A�����̓y�n�ŐV���ɐ������n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͔ނ�ɑ�ςȋ]���������邱�Ƃł���A�_�����݂͋ɗ͂�����ׂ��ł���ƍl����B
�����w�R���̒ނ肩��x�ł́A�_���̌��݂͎��������̗��v�����ᒆ�ɂȂ������҂ł��铌���s���i���̗��Ȏ�`�̑̌��҂ł�����Z���s�m���j���A�����҂ł���Q�n�̎R���̐l�X���]���ɂ��邱�Ƃɂ��A���������̗��Q���ѓO���邱�ƂƂ��āA���邢�̓_�����݂Ƃ͍H�ƕ����Ȃ����s�s���u�l�ԁv�ɂ��A�R���𗬂��쁁�u���R�v�̔j��Ƃ��ĕ`����Ă���B�������A���������}���͖��̒P�����ł���Ƃ��������A�Ԉ���Ă��肫��߂ĕs�K�ł���A�Ǝ��͎v���B
�P�X�W�O�N��ȍ~�A�_���͓s�s���̕K�v�i�܂�s�s�ɂ�����ɐ����p���̕s���j�ɂ��ƂÂ��Čv�悳��Ă���̂ł͂Ȃ��B�����玟�ւƃ_���̌��݂��v�悵�A���肵�Ă���̂́A���H�⋴���A��h�A�S�����`�A����Ƀ_���ȂǁA�R���N���[�g��S���g���u�y�،��݁v���s�����Ƃ����Ƃ̔ɉh�ɂƂ��ĕK�v���ƐM���A�܂����Θ_�����ēƒf�I�ɂ��̌������s�g���č\��Ȃ��ƐM���Ă��鍑���Ȃ̋Z�p�����A����т��̓V�����̐������J�����c�i�����j�̊����n�a�����ł���A�܂��_�����݂̗��������߁A�܂����������ɋ��͂��邽�߂Ɏ��͂ɌQ�����Ă��鐭���Ƃ��w�́u�����ҁv�A�����Ċ�Ƃł���B
�_�����݂́A���̌������ƂƓ��l�u�����ƍفv�ɂ���Đi�߂���B�u���̃V�X�e���ɂ̓_���������s�����̎咣��c��͑��݂��Ȃ��B���S�Ȃ钆���W���Łv����i�\���h�쑼�w�������Ƃ��ǂ����邩�x��g�V���A�P997�j�B�����āA�_�����݂́A���ׂĂ��������Ƃ͌���Ȃ����A�����A�ˋ�̐����v�\���A�����̂Ȃ��u�����̐������̕s���艻�v�Ȃǂ̗��R�Â��A�����n�̍~�J�f�[�^�̉�����A�i�����_���̏ꍇ�ɂ́A���肳��Ă��Ȃ��u�~�J�f�[�^�v�Ɋ�Â��u�^���\���v�j�ȂǂȂǁA�Z�p���������ɂ���ĝs�����ꂽ�u�K�v�v�ɂ���Čv�悳��A�^���h�̈ψ��i�u�w���o���ҁv�j���W�߂��u�R�c��v���o�āA�����̂ق��̌������Ƃƈꏏ�Ɂu�t�c����v�����B
�ȏ�Ɋւ��ẮA�\�������̂ق��ɁA�V���@�K�w�Z�p�����x�i��g�V���A2002�j�A���Ý��V�w����茴�_�x�i�k�l�o�ŁA1991�j�A�٘_�u�_���Ɗ��ϗ��v�ێR�������ҁw��g ���p�ϗ��w�u�`�Q�D���x�i��g���X�A2004�j�A�ْ��w���Q�̌������Ɓ@�R����_���ƒ��\�������l����x�i�n���Џo�ŁA2001�j�Ȃǂ��Q�Ƃ��Ăق����B
�_�����݂͓s�s���̂�������m��ʂƂ���ŏ���Ɍv�悳�ꌈ�肳��Ă���̂ł���B�����āA�s�����邢�͓s�̐����s������s���Ɍg����Ă���E���̒��ɂ́A�_�����v�悪���炩�ɂȂ����Ƃ��ɁA���ꂪ�����n�Z���̐����j��ł���ƂƂ��Ɏ��R�j��ł���A�܂��ŋ��̖��ʎg���ł��邱�Ƃ�ᔻ���A�����n�Z���̃_�����݂ɔ�����l�X�ƘA�т��āA�S���I�Ɍ��ݔ��̉^����W�J���Ă���l�X������B���Ƃ��w����茴�_�x�u���Ƃ����v�Q�ƁB
���̓_�����݂͂��ׂāu���R�j��v�ł���s���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ͍l���Ȃ��B�}�s�ȎR�n�ɍ~�����J�����C�ɗ��ꋎ��܂܂ɂ����A�_��������Ĕ_�Ƃ�s�s�̐������ɗ��p����Ƃ������Ƃ͊ԈႢ�ł͂Ȃ��B�Ƃ��ɐ��Ԃ��Ȃ����́A�s�s���̐l���}���ɔ����������̊m�ہA�_�Ɨp���̊m�ۂ�A�䕗���P�ɂ��^����Q�̑�Ƃ��čl����ꂽ�������̃_���̌��݂͂����ł���B�i���������v�n�Z���ւ̕⏞���K�ɍs��ꂽ�Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B�j���͕K�v���ɂ��Ă̔��f�������I�Ȃ������ōs��ꂽ�ǂ����ɂ���B1980�N��ȍ~���ۂ̐����v�͊g�債�Ă��Ȃ��ɂ�������炸�ˋ�̐����Ɋ�Â��āA�y���ƊE�̗��v�ȂǕʂ̖ړI�̂��߂ɐŋ��𓊓��������邱�Ƃ��Ԉ���Ă���̂ł���B
�_�����݂ɂ����鍑���Ȃ̓ƒf��s�i�Ƃ�����x���闘���W�c�̍s���j���\�ɂ���w�i�Ƃ��āA�s�s���i���邢�͈�ʍ����j�̐����ɑ��閳�S���w�E���邱�Ƃ��ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���ہA���x�������̓��{���{�̐������J�������ᔻ���A�����v��}�����ׂ��Ɛ����_�҂̒��ɂ��A�s�s���̐����ɑ��閳�S���w�E����l������B�u�s�s�Z���̓��퐶���ɂ����鐅�ւ̖��S�͂��ǂ낭�ׂ����Ƃ��Ǝv���B���������̒f���Ƃ������ƂɂȂ�Α呛�����邪�A����A�ǂꂾ�����ɂ��čl���Ă��邾�낤���v�B�ʏ�N�w���̎v�z�x�i�_�n�ЁA1979�j�B
�����g�A1960�N�㔼�ɑ�w�ɓ��w���Ă���30�N�߂������ŕ�炵�����A�����ɂ��čl�������Ƃ��S���Ȃ������B���́A�S�T���߂��Ďl���A���R�ɏZ�ނ悤�ɂȂ��Ă���1994�N�ɐ��S�N�Ɉ�x�Ƃ����ُ튉���ɂ�钷���f�����o�����A�܂�2000�N�ɕ��サ�����s���R�ɐ����������邽�߂̐V���ȃ_���̌��v��ɑ��锽�Ή^���ɉ����A���R�ւ̐V���Ȑ������������s�K�v�ł��邱�Ƃ�_���邽�߂ɖ{������������ƂɂȂ������A���������u�����v���Ȃ�������A������^���ɍl���邱�Ƃ͂Ȃ�������������Ȃ��B
��w�Łu���ϗ��v�̎��Ƃ������Ă���l�Ԃɂ��Ă����ł���B��ʂ̎s�����ӂ����ɊS�������Ƃ͓���B�����Ă��̌����͋ʏ�������悤�ɁA�u���Ǘ����W���I�ȍs�������̓Ɛ蕨�Ƃ���Ă���v���Ƃɂ���B�܂肻���ł������u�Z���͐��̒P�Ȃ����҂ł����Ȃ��������܂����Ȃ̎����̐ӔC�͈̔͂ɂ���Ƃ������Ƃ����o�ł��Ȃ��v����ł���B
�������A�����ɂ����āu�����̐ӔC�͈̔́v�ɂ���ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ������͐���肾���ł͂Ȃ��B�H�̈��S���̖��A�����E�G�l���M�[����̖��A�s�s�ɂ������C�����ȂNJ����A�q���̊w�Z����̖��A���邢�͈�Â�ی��̖��A���X�A����ꂪ�s���Ƃ��āA�Z���Ƃ��āA�����A���邢�͔[�Ŏ҂Ƃ��āA�S���������łȂ��A�����̈ӌ��������A�W�@�ւɑ��Ĉӌ����q�ׂ�ׂ����Ǝv���邱�Ƃ�����グ�Ă������肪�Ȃ��B�ӂ���A�s�s�̏Z�����u�����v�I�A�u����v�I�ɂ��܂��܂Ȗ��Ɋւ�邱�Ƃ̕K�v���͂킩���Ă��A�Ƃ��ɐ����ɋ����S�������A�^���Ɏ��g�ނ��Ƃ͉����̋@��܂�f���̌o���Ȃǂ��Ȃ������茈���ėe�Ղł͂Ȃ��B
���R���w�R���̒ނ肩��x�Ŏ��グ�Ă��鉺�v�ۃ_���͍^�����߁A���d�A�㐅���A�H�Ɨp���A�����Ȃǂ�ړI�Ƃ���u���ړI�v�_���ł���A�㐅���͓����s�ƍ�ʌ��ɁA�܂��H�Ɨp���Ƃ��č�ʌ��ɋ������A�_�Ɋ��̂����p�����������邱�Ƃ�ړI�Ɍ��݂��ꂽ�B������ꊇ���āA�s�s���̗��v���ƌ����Ă��܂��͕̂s���m�ł���قƂ�NJԈႢ�Ƃ���������B�܂����v�ۃ_���̏v�H�͓��R�������Ă���悤��1968�N�ł���B�������A���ݏȒ����_���Ƃ��Čv�悳�ꂽ�̂͂���10�N�ȏ�O�̂��Ƃł���A65�N�ɂ̓_���{�̂̍H�����J�n����Ă���B
�����A�����}���x���Ă����s����ᔻ���āA���Z�������m���ɂȂ����̂�67�N�ł���B�Ȃ�قǁA���v�ۃ_���̊����ɂ��A���Z������m���Ƃ��铌���s�����������̋��������Ƃ������Ƃ͎����ł��邪�A���R���A��쑺�̏Z���̌���ʂ��Č��킹�Ă���悤�ɁA���Z���m���������s���̖��ӂɂ��ƂÂ��ă_�����݂����߂��킯�ł͂Ȃ��̂ł���B
�������A���̂悤�Ȃ��܂��Ȏ����͂ǂ��ł��悢�̂�������Ȃ��B���R�ɂƂ��ẮA�_�����݂ɂ����ẮA�����ł���s�s�������v���A���R���j��A�����̎R���̐l�X���]���ɂȂ�Ƃ����\�}���������Ȃ̂ł��낤�B
�������A���ɂ́A���̂悤�ɎR���̐l�X�Ɠs�s���A�R���Ɠs�s�A���R�ƕ�����Η������Ă݂Ă��Ӗ�������Ƃ͎v���Ȃ��B�����ă_�����݂́u�����v�Ƃ��āA�R���̎������܂ߍ��y�̎�����Ɛ肵�悤�Ƃ���u�s�s���̗��Ȏ�`�v����ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ�ł���B
�\����̌����܂���A���݂̂悤�Ȍ������Ɛ��i�̎d�g�݁A�܂�s���V�X�e������т��̍����ł���͐�@�̑̌n��啝�ɕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͈�т��ēy���I�Ȍ������Ƃ𐄐i���Ă��������}�������ł͕s�\�ł��낤�B������_���i�⍂�����H�A���邢�͐V�����Ȃǁj���݂��X�g�b�v�����邱�Ƃ͔��ɓ���i���j�B�������A���R�̂悤�Ȍ����͂���̋c�_�������Ȃ����Ƃ͂��̍�����������đ��傳���邱�Ƃɂ͂Ȃ��Ă��A�_�����݂��X�g�b�v�����邱�Ƃɂ͂قƂ�ǖ𗧂��Ȃ��Ǝ��͎v���B
���R�ƕ����ƌ����\�}�ɂ��Ӗ�������Ƃ͎v���Ȃ��B�����ɂ����낢��ȕ���������B�����Ǝ��R���d�����A�����ƍقɂ��o�ϐ�����J����y�،��݂ɂ��������Ƃ�i�߂�̂ł͂Ȃ�����������Ǝ��͍l����B
�i���j�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA���̌�2005�N�ɂ͏�쑺�ɁA�����d�͂́A��̍���120���A���{�ő�̗g�����_�����V���ɍ��ꂽ�Ƃ����B
���R�̋c�_�ł͒P�������ڗ��B�_�����݂ɂ���ēs�s���͂����ς痘�v���邩�̂悤�ɂ݂Ȃ���A�s�s���݂͂ȓ����悤�ɁA���x�o�ϐ����̉��b�ɗ����Ă��邩�̂悤�ł���B�������X�ƍs����_�����݂ɂ���āA�s�s���͏���҂Ƃ��Ă͐��������̒l�グ�ƌ����`�ŕs�K�v�Ȏx�o���������A�܂��[�Ŏ҂Ƃ��Ă̓_�����݂ɔ������������Ƃ����u��܂��v�ɂ�薳�ʂȐŋ��킹���Ă���B�ߐ��̓w�͂Ȃ��ɍD���Ȃ����Q��I�ɐ����g�p�ł��邱�Ƃ́u���v�v�ł��K���ł��Ȃ��B�y���ƊE�A�����ƁA���X�̓_�����݂ɂ�藘�v����ɓ����B�s�s���͗��v���邱�ƂȂ��A�s���v������ւ��Ă���Ƃ�������B
�����Ƒ傫�ȁu�P�����̃~�X�v�́A���R�����R�Ƃ͐l�̗������邱�Ƃ̂Ȃ��u�������R�v�̂��Ƃł͂Ȃ��A�����ɏZ�ސl�Ԑ����ƊW���鎩�R�̂��Ƃ��ƌ����Ă���ɂ�������炸�A�ނ����R�ی�Ƃ����Ƃ��ɂ́A�R���̐l�X�̐������ł��鎩�R�A�܂�R�̐X�тƓ��������A�k���Ƃ����ɏZ�ފ⋛��R���Ȃǂ̂��Ƃ��������l���Ă��炸�A�s�s�Z���̎��R�Ɛ������̖��ɂ͑S���ӂ�悤�Ƃ��Ȃ��_�ɂ���B
�ނ́u��L�v�ň�s�u�{���ł͌��ݖ��ɂȂ��Ă��鎩�R�j��ƌ��Q�ɂ��Ă͒��ڂɂ͂Ȃɂ��ӂ�Ă��Ȃ��v�ƌ����A���ہA�{���̒��ł́A�����삪�H��r���ʼn�������A�ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ƂQ�A�R�s�A�s�s�̉͐�̊����ɂӂ�Ă��邾���ŁA���̂ق��ɂ͊������A���Q�ɂ��Ăӂ�Ă���Ƃ��낪�S���Ȃ��B
1970�N��̓s���́A�R���̐���D���ēs�s�����̉��b�����鑶�݂������Ƃ������́A�H�ꂩ��̔r���A�r���A�����Ԃ̔r�K�X�Ƒ����A���������ʎ��̂ȂǁA�}���Ɋg�傷��o�ϊ����Ɓu�H�ƕ����v�ɂ����Q�A���j��ɂ���Đ����̈��S�ƌ��N����������N�Q����������B�����a�Ȃǎl����Q�a�ɑ��锽�Ȃ���悤�₭�A���{�Ŋ��ی�{�i�I�ɂ͂��߂��悤�Ƃ��Ă��������i�����Ȃ̈ꕔ�ǂ���Ɨ����āu�����v���n�݂��ꂽ�̂�1971�N�j�ł��������A��������Ȃǂ̑�s�s�ł͂Ƃ��ɑ�C�������Q���[���������B
�����ł͌ċz�펾���ɜ�����w�����ɓ���[���ɂ���A��̎{�݂ɑa�J���A�܂������Ԃ̔r�C�K�X���匴���Ƃ���u�����w�X���b�O�v�ɂ��A�^�����̍��Z�����Z��œ|���ȂǁA���N�����l�̔�Q�҂����������B����������������݂���ꂽ���A�����ԋƊE�Ȃǂ̔��œ�_�����f�̊�����ɘa����A�A���A�e���r�A���W�I�̓V�C�\��̎��Ԃɓ�_�����f�̔Z�x�\�Ȃ����ȂǁA�������H�����̒n��𒆐S�ɐ[���ȑ�C�������������B�����Ƃ����Ă��R�̎�Ɖ����ł͔�Q�̑傫���͈قȂ�A�����A�H��n�тł͕��o�ɂ���Q���܂ߑ�C�����͂͂邩�ɐ[���ł������B
�܂��A�}���Ɏ��Ɨp�Ԃۗ̕L�䐔���������A70�N�ォ��80�N��ɂ����ẮA��ʎ��̂̎��Ґ��͖��N�P���l���A�����Ƃ��ɂ͂P���T��l�ȏ�̎��҂��������B�����̊������߂��Ă������s�S�⓹�H�����̒n��̂قƂ�ǂł��̊�͑S������Ă��Ȃ������B�r���̃I�t�B�X�ł͖h������Ă���B�����������⓹�H�����̈�ʏZ��ŕ�炷�l�X�͎����ԑ����ɐ�����W�����A���_��a�ސl�X���������B��s�s�𒆐S�Ɂu��ʐ푈�v���N�����Ă����B�܂������Ԃ̔r�K�X�Ŋe�n�̐X�т̔�Q���N����������B
�S�~�̑�����[���Ȋ����������N�����A���Z���s�m�����u�S�~�푈�錾�v�����قǂł������B�ċp�{�݂���������O�ɃS�~����o���Ă�����ƁA�����n�����肻���̃S�~���������܂��]����Ƃ̊Ԃɕ����������A�]����͋�O����̃S�~�����������Ƃ���S�~�E�g���b�N�����͂őj�~�����B
���͐�������V����������ɂȂ��Ă��鉺���̉^�͐Ղ��A���������P����V���D���s���������c��Ȃǂ��A80�N��܂ł͐^�����Ȑ��������ǂԐ�ł������B���͌����ɂȂ��Ă���A���̓��̐�̃S�~�����n�̒�h����ނ�铌���p�̋��͖��L�������B�i����ł������܂ߑ����̏����������p�̖����n�̎���ŁA�T�b�p�A�Z�C�S�E�t�b�R�A�N���_�C�Ȃǂ̒ނ���s�Ȃ��Ă����B�j���R�͒ނ�Ƃ̊W�ŁA�����̉͐�̉����ɂ͋C�����Ă����B�������A�Ȃ����A����́u���Ǝ����v�Ƃ���A�����̊����ɂ͊S��������Ȃ��̂ł���B
���R�́A�R���̎��R�ی�ɂ͊S�����������A�����𒆐S�ɓ����s�����ꂵ�߂Ă��������ɂ͂قƂ�ǑS���ӂ�Ă��Ȃ��B�����āA�Ƃ�킯�A�����Ԍ��Q�Ɋւ��Ă͑S�����S�ł������悤�Ɍ�����B�ނ͎R���̐�ōs���V�т̒ނ�́A�_�����݂�ʂ��Ă̓s�s�ɂ��R���̕x�̍��A���D�Ƃ��Ȃ������̍s�ׂ��ƌ����A�ނ�����Ă��鎩���Ɏ��Ȍ����������Ă���Ə����Ă���B�Ƃ��낪�ނ��Ԃ��g���Ēލs���Ă��邱�Ƃɂ��Ă͂ЂƂ�����̂�܂����������Ȃ������悤�ł���B
�����������命���̓s�s�ΘJ�Z���̓o�X��d�ԁA�n���S�𗘗p���ĒʋA�ʊw����B�����A���c�Ǝ҂Ȃǂ��d���ŎԂ��g�����Ƃ͍m�肳��邾�낤�B�n���ł͌�����ʂ̕ւ������A�Ԃɂ���炴��Ȃ��B�����A�s���ɏZ�ޑ�w���t�ł���ނ������Ԃɏ��K�v���������Ƃ͎v���Ȃ��B�������A�ނ́u�k�_�����݂Łl�����̔ɉh���������Ă����ɗ^����ꂽ���̂́A�e���r��������悤�ɂȂ������ƂƎ����Ԃ����L����悤�ɂȂ������Ƃ��炢�ł���B����ƈ����ւ��ɑ��̎��������̂͑傫�������v�Ə����A���邢�͔ނ��Ԃœ��������쑺���K�˂�Ə����A�܂��Ԃœ��{�e�n�̌k����K��ނ�����Ă���Ə����Ă���B
������ǂނƂ��A���R�́A�����Ԃ̗��p�͑��҂ɒ��ړI�Ȋ�Q�������邱�Ƃ�����A�܂������������āA�l�̌��N��N�Q���X�є�Q�������N�����Ƃ����A���łɓ����}�X�R�~�̘A���̕ɂ���Ė��炩�ɂȂ��Ă��������Ԃ����d��ȃ}�C�i�X�̑��ʂƎ����Ԃ������N���������Ɋւ����{�I�ȔF����S�������Ă��Ȃ����F���͂����Ă��m���ӂ�����ߍ���ł��������Ă������Ƃ��킩��B�R�̎��R����y���݂邱�Ƃɂ͕����ڂ������Ă������A�Ԃ������Ƃő��҂ɕs���v�������炵�։v�邱�Ƃɂ͂Ȃ��̕����ڂ������Ă��Ȃ��B
�ނ́A�_�����݂ɂ���Đ�̗����f���萅�����߂ė��p����Ƃ����A��̎��R�ւ̂��������̕ω��ɁA�����̓��{�̊����������������B�����āA�ނ́A�⋛�ƎR���̎��R�̕ی������B���̂��Ƃ�ے肷��K�v�͂Ȃ����A�R���̎��R�Ɠs�s�̕����A���邢�͎R���̏Z���Ɠs�s�Z����I�ɑΗ������A��҂ɂ���ă_�����݁A���R�j�i�߂��Ă��邩�̂悤�ɐ�������̂͊ԈႢ�ł���B�ނ͓s�s�𗘌ȓI�Ȑl�X�̒P��ȏW�܂�ł��邩�̂悤�ɕ`���A�@�I������Ɛ肵�ŋ��̖��ʎg�������Ă��銯���W�c�A�_�����݂Ŗׂ��Ă���ƊE�A����ƑΏƓI�ɍH��⎩���Ԃ̔r���A�r�C�K�X�A�����ȂǂŌ��N��Q���A�܂�����Q������]���ȗ������x���킳��鏎���ȂǁA�u�s�s���v�����ɑ��݂���Ⴂ�����Ă��邪�A������Ԉ���Ă���B�w�R���̒ނ肩��x�ɂ�����ނ̋c�_�ɂ͂����������_������A�S�̂Ƃ��đS���^���ł��Ȃ��B
��O�̃e�[�}�Ɋւ��āA���R�̔ᔻ���s�����Ƃɂ��悤�B���R�́A�k��J�������R�Ɏ�������A���R��J�������邱�Ƃł���Ɠ����ɁA�J������l�Ԃ����R�����邱�Ƃł�����ƌ����B�ނ����̂悤�ɍl����悤�ɂȂ����̂́A�ނ����l�Ɠ��l�Ɏ��ۂɔ����k���āA���R�ɑ��铭�������������Ȃ����o���ɂ��ƌ����Ă���B�ނ̔����́A���l�������i�����j�̕K�v����s���Ă��锨���Ƃ͑S���Ⴄ�Ƃ������Ƃ́A��́i�Q�j��ނ�͘J������ɑ��锽�_�̂Ƃ���ŏq�ׂ�B�������������R���̐l�X�̐����͢�l�Ԃ̎��R���v�ƌ�����̂��ǂ������m���߂Ă݂悤�B
���R�͐l�Ԃ̎��R���A�����Ƃ̋����ɂ��Č�钼�O�̉ӏ��ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B���l�����Ɏ�������ⓤ�́A�J�P�X�i�J���X�Ȃ̒��j��L�W�o�g�����ł��āA�H�ׂ��Ă��܂��B���Ƀe�[�v�����肵�Ă������ڂ��Ȃ��B�Ƃ��ς₵�����l�͕߂܂����J�P�X���E���āA�݂����߂ɒ݂邵���B
�u���N���̑��ł�---�k�F�Ɂl�I���������B����͎R�ɐ��ނ�������̕K�v�o��ł���B---�����Ƃ��A��������܂肵���ɂȂ�Ή��炩�̖h��[�u���Ƃ邱�ƂɂȂ�B�������Ă��܂���ꂽ�F������v�B
���l�͔��̍k��ɂ��ĐF�X�ȕi��������Ă݂邾���̗]�T�͖������A�܂��������Ɏ���ق���ꂽ��A���邢�͎��n�O�̍앨���C�m�V�V�ɐH���Ă��܂����肷�邱�Ƃ����e����]�T���Ȃ��B������A��Ȃ��d�|���ĕߊl����Ȃǂ��܂��܂ȑ���u���悤�Ƃ��Ă���̂��Ǝ��ɂ͎v����B���l�̘J���͗V�тł͂Ȃ����䂦�ɁA���n���ł��邾���m���Ȃ��̂ɂ��悤�Ɠw�͂���B
�����A���l���g�������͎��R�̈�����ƍl���Ă���ƌ������Ƃ�����A���͂ǂ̂悤�ȈӖ��ł����Ȃ̂��ƕ����Ă݂����B�q�ϓI�Ȏ����Ƃ��āA���l�͓~�G�ɂ͌F��ߊl���є��u�F�̒_�v���ĉ҂��B�܂����l�́A���Ȃ̘J���̐��Y������邽�߂ɁA�e��ߊl�p�̂�ȂȂǗp���ē������E�����肠�邢�͈Њd�����肵�Ă���B
���l���u���R�̈���v���Ƃ����Ƃ���ŁA�l�Ԃ͓��ʂ̓��������������݂Ƃ��ĐU�����Ă���̂ł���A�������m�ɂ���ĉ\�Ȃ炵�߂Ă���ɉ߂��Ȃ��B�l�Ԃ͓����̎��R�ȑ��݁A���R�ȍs�������F���Ă���̂ł͂Ȃ��A�E�����A���邢�͐l�Ԃ̓s���Őݒ肵���敪�ɂ���āu�Q�b�v�ɂȂ�Ȃ��悤�A���̘g���ɔނ���������߁A���������ɓs���̂悢�u���̋����v���������Ă���̂ł��낤�B
�Љ�S�̂����炩�̌����ŋɓx�ْ̋���Ԃɂ���Ƃ��������A����̐l�ԎЉ�ɂ����Ă��̍\�����̈ꕔ�����̍\�������E���Ē݂邵����A���̂����ɂ����肵�Ă��߂ɖ���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ȎЉ�͂Ȃ��Ƃ����Ă悢���낤�B�Ƃ��낪���R�������l�Ԃ��܂ށu���R�̎Љ�v�Ȃ���̂́A�����ɂЂǂ����ʂ����݂��A���c�s�s�ׁ����F�߂��Ă���Љ�ł���B�����āA���̑��l����l�Ԃ̓����W�c�͂���炪�ێ����镐����m�ɂ���Ă��̍��ʓI�u�����v���ێ����Ă���̂ł���B�i�������A���͓����Ɛl�Ԃ́u�����̕����v�Ƃ����A�ꕔ���Ă̘_�҂Ɍ������_�͎���Ă��Ȃ��̂ŁA���q�ׂ����Ƃő��l����悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�j
����͈͂̓y�n�̒��Ő�������������̐��������G�ȑ��݊W��L���������Ă��邱�Ƃ���A���Ԋw�ł͂��̐����̏W�܂�S�̂��u�R�~���j�e�B�i�����́A�����Q�W�j�v�ƌĂԂ��Ƃ�����B�R���̐l�Ԃ����̈Ӗ��ł͑��̓�����A���ƂƂ��Ɂu�R�~���j�e�B�v�̈���ł���ƌ������Ƃ͂ł���B����������͏�쑺�̐l�X���ЂƂ̑��������̂Ƃ��Ă̐l�ԎЉ������Ă���Ƃ������ƂƂ͖��m�ɋ�ʂ���˂Ȃ�Ȃ��B
�l�ԎЉ�̓R�~���j�P�[�V�����ɂ���Đ��藧���A�܂����̍\�����͕����Ȋ�{�I�l����L���Ă���B�J�P�X��C�m�V�V�ɔ����r�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��点���i�͑��݂����A�܂������点�邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A�����r�炷�s�ׂ͎��ɒl����Ƃ����悤�ȋK����܂ޖ@�������肳��A�l�Ԃɂ��K�p�����Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�B��{�I�ɖ쐶�����́A�܂����ߓ������A���Y���ی삳���悤�ɁA�ی�́u�Ώہv�ł͂����Ă��A�l�ԎЉ�́u�\�����v�ł͂Ȃ��B�܂��A�t�ɐl�Ԃ͂����玩�R�ɗn���������Ɠw�͂��Ă��A�����i�l�ԎЉ�́j�@�ɂ��ی�Ȃǂ���؎̂ĂȂ�����A���̓����Ɠ��������̌��������L���邢�͊Îׂ��u���R�̎Љ�v�̈���ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��̂ł���B
����ɓx�̓������ʂ��s������̎R���Љ���A�S�C���g�킸�ɖ쐶�����Ɓu�����v���Ă����]�ˎ���̔_���Љ�̃P�[�X�Ɣ�r���Ă݂悤�B����O��w�S�C��������Ȃ������S�������|���납�疋���܂Łx�i�����V���o�ŁA�Q�O�P�O�j�͈ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B
300�N�قǑO�A�]�˂̎��ӂɂ́A�L��ȐX�т��L�����Ă���A�����ɂ͂�������̎���C�m�V�V�Ȃǂ��������Ă����B����Ŗ��{�̊J�i����œc�����L����A�_���͍őO���Ŗ쐶�̓����ƑΛ����A�܂����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����̔_���̐H�Ǝ���͕n�����A���͂قƂ�ǐH�ׂ��Ȃ������B����C�m�V�V�̎�͔��̍앨����邽�߂ɕs���ł���A��������ѐ�̂��y����������Ƃ���A�_���͒�����Ď�������Ȃ����ƍl�������Ȃ�B�Ƃ��낪���{�͔_���̓S�C�̏����A�g�p�����т��������܂����B
�������āA���Ƃ��A��쑺(��ʌ��Ƃ����풬)�́A�قƂ�ǂ��X�Βn�ŁA�k��n��98�������ŁA�Ăł͂Ȃ����A�B�A���A���Ȃǂ�H�ׂĂ����B�_�Ƃ̍��Ԃɒj�͒Y�Ă������A�܂����ق��ʼn҂��B���͖��A�ؖȕz�Ȃǂ����������D��A�߂��̎s��Ŕ����Ă킸���Ȏ����Ă���B�˂̌�т�14�ӏ��A�S�����R��110�ӏ�����A�������瓾����ŒY�Ă����s���Ă���B�i�����܂ł͓��R���q�ׂĂ���u���R���������p�����J���Ɛ����v���c�܂�Ă���u���Ă̔_���v�̕�炵�Ƒ�̈�v����B�j
�����A�R���Ȃ̂ŃC�m�V�V�A���������o�v���Ģ��������Ă���B��Q�͔��n�S�̂̂T�V���ɋy��ł���B����20�N(1735�N)�ɂ́A�N�v�����艺����A�啝���ƂɂȂ����قǁA�r�n�ƂȂ�����������B
�ЂƂ��яb���o��A��ԁA���ɐ݂��������ɔ��܂�A�C�m�V�V�ǂ�������B�S�C�̐������Ȃ��̂ŁA�|����_�A���Ƃ����Ȃǂ̕��@�Ŗh���B�S�C���g�����Ȃ��ɂ͏n�����K�v�ŁA���Ƃɂ��Ă���t���ق����Ƃ����������B��p�͑��S�̂Ō�����ɂ��Ďx�������B���C�͂S������V���Ɍ����Ă���A����ȊO�̎����͗��Ƃ����A�|���A�_�Œǂ��U�炵���B�S���ɂƂ��Ă͢��V���ɣ�ł������B
�����Ɍ���_�������́A�̎�ɂ���ĔN�v��������A�������b�ɍ앨���r�炳��ĂЂǂ��������Ă���B�n�������̂̒��ʼnc�܂ꂽ�u�����ƘJ�����������Ă��Ȃ��v�ƂƂ��Ɂu���R�Ƌ����v����]�ˎ���̓��{�̔_���́A�������Ԃ�����ďb�Ɛ���č앨�����Ȃ���Ȃ炸�A�u���x�݁v�̗]�T�������Ȃ��Ђǂ����т��������𑗂��Ă����̂ł���B�ނ�͂܂������u���R�̈���v�ƌĂԂɂӂ��킵�����A����͓��R�̌����悤�ȁu���}����`�v�Ƃ͑S�������̂��̂ł���B
�u��v�Œ��ׂ�Wikipedia�Ɍf�ڂ���Ă���摜�B�������[���b�p�̊G��ł�
�Ȃ����Ǝv���邪�A��҂͕s�ځB���m�炵���l�������ŃC�m�V�V�Ɠ����Ă���B

2012�D11�D8�D���Q�V���f�ځu�l�G�^�v�Ő������R�w�Z��\��R�{�M�m���͎��̂悤�ɏ����Ă���B�u�]�ˎ������A�l���̎R�ԕ��ł͏Ĕ����s�Ȃ��Ă����B�����ɂ��ƁA�R���Ă��āA������G�����͔|���Ă������A���O���ăC�m�V�V��V�J��ǂ�����Ȃ���Ύ��n�ǂ���ł͂Ȃ������炵���v�B�]�ˎ���̔_�����������甩�̍앨����邽�߂ɐQ���̋�J���Ă����̂́A�֓�����ł��l���ł������������悤���B
���Đl�Ԃ͌��݂����͂邩�Ɂu���R�ɋ߂��v���݂ŁA�����Ɠ��l�A�S�C�Ƃ��������̗���������Ă��炸�A���R�Șr�͂����s�g�ł��Ȃ������Ƃ��ɂ́A�쐶�������䂪����ŕ������A�l�Ԃ́u��V���Ɂv�Ȑ�����������ꂽ�B����̎R���ł͐l�Ԃ��x�z�҂̒n�ʂɂ��A�\���ɖL���Ōo�ϓI�]�T�����邪�䂦�ɁA���������̏��X�̓��݂͌������Ă���Ă��邪�A���ł����̋C�ɂȂ�Βe�����A�s�E������B�܂�A�̂������A�R���̐l�X�͖쐶�����ƃ��}����`�I�ȁu�����v���邢�͋����������s���Ă͂��Ȃ��B
���͐l�Ԃ̖{���͘J�����邱�Ƃ��Ƃ����l���ɂ͎^�����Ă��Ȃ��B�������A�J���ɂ��u���R�̐l�ԉ��v�Ƃ������Ƃ̊T�O�͖��ĂŐ^���ł���B�l�Ԃ͂قƂ�ǂ̏ꍇ���R�̎��������̂܂ܗ��p����̂łȂ��A���炩�̂������ŘJ���������l�Ԃ֗̕��̂��߂ɉ��H���ė��p����Ƃ������Ƃł���B�������u�l�Ԃ̎��R���v�̊T�O�͂Ȃ�疾�炩�łȂ��B
���R�͏�쑺�ł̐����A�Ƃ��ɔ����k���_�앨��������ނ̘J����ʂ��A������X�т�V��Ȃǎ��R���Ɋ���A�܂����̓y��Ɋւ���m���Ȃǔ_�Ƃ̒m���������Ȃǂ������Ƃɂ���āA�ނ��u���R���v�����Ɗ����Ă���B
�i�g���N�^�[���g������̔_�ƂƈႢ�j�R�Ԓn�ő̂��g���L�ōk���k��̘J���́A�s�s���̃I�t�B�X�ɂ����鎖���J����A�H��ɂ�����x���g�R���x���[�̗����Ƃɂ�����J���Ƃ͈Ⴂ�A�m���Ɂu���R�I�v�v�f����߂銄���������B��쑺�̐l�X�́A�܂��A���R�̍s�����k��J���́A����Љ�ɂ�����ق��̘J���`�Ԃɔ�ׁu���R�I�v�ƌĂԂ��Ƃ͂ł��邾�낤�B�����Ă��̏ꍇ�A�l�Ԃ́A���R�Ɋւ���m���𑽂��L����ł��낤���A���R�I�J���`�Ԃɂӂ��킵���A�̂̎g�����A�Z�ʂ̂悤�Ȃ��̂����߂��邾�낤�B
�����ŁA��l�̐l�Ԃ͈�ʂɎЉ���ꂽ���݂ł���B�܂�(��Q�͂łӂꂽ�j�m�D�G���A�X�ɏ]���A�l�Ԃ͎��R�I�����Փ��ɍ��E���ꂸ�ɁA�����ɂ���čs�����s���u�������v���ꂽ���݂ł���B�����āA�l�Ԃ͐��܂ꂽ�Ƃ��ɂ͓����ł��邪�A�����̉ߒ��ŁA����ɁA�l�Ԃ炵���U�镑������g�ɂ��Đl�ԂɂȂ�B�u�l�Ԃ̎��R���v�Ƃ́A������ے肵�A�l�Ԃ��l�Ԃ炵�����̂Ăē����ɖ߂邱�Ƃ��w���̂ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A���R���������R���͂��̎Љ�╶�����̂悤�ȊT�O�Ƃǂ̂悤�ȊW������̂ł��낤���B
������{�ɂ����āA�����k���R������ĕ�炷�����𑗂邱�ƁA���邢�͕����I�ɂ��̂悤�Ȑ����ɐe���ނ��Ƃ́A�s�s�̃T�����[�}���Ƃ͊����قȂ鐶�����s�����Ƃł��낤���A�������A�e���r��V����ʂ��ē��������ɐG��A�①�ɂ�Ԃ�d�C���g�������������s���_�ł͕ς��͂Ȃ��B�s�s�Ő���������l�X�ƎR���ŕ�炷�l�X�̊ԂɁA�s�s�I�u�l�ԁv�Ǝ��R�I�u�l�ԁv�Ƃ����悤�ɋ�ʂł���悤�ȁu�l�ԁv�̈Ⴂ�����݂���̂��낤���B�s�s�I�l�Ԃ́A���炭�R���ŕ�炵�����k���u���R���v���āA���R�I�l�ԂɂȂ�̂��낤���B
����Ƃ��A�Ƃ��������R�Ɋւ���m���������A���R�I�Ȋ��Ɂu�����v���Ƃ�A�J���̑ΏۂƘJ�����s������ɍ����悤�ɁA�J���̕��@���ω����邱�ƂȂǂ����āu�l�Ԃ̎��R���v�ƌ����V�������p����悤���R�͒�Ă��Ă���̂��낤���B�����A����ɂ��J���̊T�O�ɐV���ȓ��e�I�ȕω���������悤�ɂ��v���Ȃ��B�}����p��̐��́A�������ׂ����e�ɕς�肪�Ȃ��Ȃ�A�ł��邾�����Ȃ��ق����悢�B�R���ɂ�����i�V�т��܂ށj�����ƘJ���͎R���̊��ƑΏۂɓK��������肩���ōs����ƌ����Ώ\���킩�邩��ł���B
�ߑ㎑�{��`�E�H�ƎЉ�́A���R�̊J���E���p�i�u���R�̐l�ԉ��v�j��Ώd���Ă����B���R�ɂ͂��̂��Ƃɑ���ᔻ������B�������A���̔ᔻ�́A���R�E���ی�������͊J���̗}���Ƃ��đł��o�����ׂ��ł���A�u�l�Ԃ̎��R���v�ȂǂƂ������e�̂͂����肵�Ȃ��d���Ō�邱�Ƃɂ͎^���ł��Ȃ��B
�ȏ�́w�R���̒ނ肩��x�̂Ȃ��ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃ̏Љ�Ƃ���ɑ��鎄�̔ᔻ�ł���B���R�͂����Ől�ԂƎ��R�Ƃ̊W����ї��҂����т�����̂Ƃ��Ă̘J���Ɋւ���N�w�I�咣���q�ׂĂ���B�����āA�܂����̂Ȃ��ŁA�s�s���邢�͕������邢�́u�l�ԁv�ɑΒu�����ׂ��A�A���`�e�[�[�Ɣނ��l����A���R�ȁu�R���v�̐����^�J���ƌk���ɂ�����ނ��`���Ă���B���͔ނ����̂Ȃ��ŎR�ъJ����_�����݂Ȃǂɂ�鎩�R�j��ɔ������R�ی�̕K�v����������Ƃ͎x���������A���R�ƕ����A�R���Ɠs��Ƃ����P���ŕs�K�ȓ_�͎x�����Ȃ������B
���R�͓��{�Љ�̌����ᔻ���邾���ł͂Ȃ��A���{�Љ�ς���Ă����ׂ������ɂ��Ă�����Ă���B
���R�́u�s�s�ɂ�����J���͖l�̊�ɂ͎��ɂ䂪���̂Ɍ�����B����͐l�Ԏ��g�������̘J�����m�F���A�J����ʂ��Ď��R�ɓ��������A�J���̒��ɐ��������A�����ĘJ���ɂ���Đl�Ԏ��g���Đ��Y���Ă������Ƃ��ł��Ȃ�����v�ł���B����ɑ��āA�����I�@�ւł̎d������ق��̓y�؍H���Ə��Ƃ�ό��ȊO�́A�R�؎��A�V�C�^�P�͔|�A���d���Ȃǂ̔_�ƂƁi���L�т́j�ыƂȂǁA�{���̎R���̘J���́A�����ƈ�̂̂��̂ł���A�u�s�s�^�̘J���Ɛ����ɑ���ЂƂ̃A���`�e�[�[���Ȃ��Ă������łȂ��A���̕��̕������������鉽���̎�����^����v�Ƃ����B
�R�Ԃ̂��ׂĂ̑��������������邱�Ƃ͖����ł���A���炩�́u���Ɓv���K�v�ł���B�������u�J���̕������g���A�����œ����l�ɂƂ��Ă̘J���̏��݂��A�X�l�ɂƂ��āA���邢�͋��ƘJ���҂ɂƂ��ĔF��������`�ł����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�ݕ��ɂ��Ȃ��A���ړI�ȘJ���ƘJ���̌����ł���悤�ȁu�P���ȁv�����ɂ�镪�ƁA���邢�́u���Ɓv�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����B ���̎Љ�ł́A�����́A���Ƃ��A�s�s�������ɃC���^�[�l�b�g���g���Ēn���̎Y����̔�����Ƃ����悤�Ȍ`�ł͍s��꓾�Ȃ��B�ݕ����g�p���鏤�i�̌����͢���i�o�ώ��g���J���̂����Ɏ������Ă��܂��v�A�u�J���̏��݂��킩��Ȃ��Ȃ�v����ł���B����ɓs�s���Ƃ̌����́A�R�����s�s�Ɉˑ����邱�Ƃł���A�s�s�^����Ɓv���m�肷�邱�ƂɂȂ�B���������Č����͗אڂ��鑺�Ƒ��̊ԂŁA���݂��̊�����Ȃ���A�i���������ɂ����킹�Ȃ���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B
�v����ɁA�R���̘J���̂悤�ɒ��ړI�Ɏ��R�ɓ���������悤�ȘJ�������Ő��Y���s���A���̎Y�������ŁA���邢�͊炪������悤�ȑ���Ƃ̌����Ŏ�ɓ��ꂽ���̂������g���āA�������s����悤�ȎЉ�u�䂪��ł��Ȃ��v����ȎЉ�ł���A���ꂪ�ނ̎����������u����ׂ��Љ�v�̊�{�\�z�ł���B���̎Љ�́A�J���҂����Ȃ̘J�����Љ�̒��ʼnʂ����Ă����������m�F�ł���Ƃ������Ƃ���ɂ��čl�����Ă���A���̈Ӗ��Łu�J���{�ʁv�̎Љ�Ƃ�������B
���̎Љ�ɂ͏��l�͑��݂��Ȃ��̂�����A���ɂ́A���j�I�ɂ́A��{�I�Ɏ��������I�Ȍo�ς��s���Ă��������ȑO�̎Љ���l�����Ȃ��B���������āA���̊�{�\�z�ɑ����̕�������ɂ��Ă��A���̎Љ�ł̓e���r�A�N���}�A�P�C�^�C�ȂǕ��G�ȋ@��E�@�B�ނ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ͊m�����낤�B�g���N�^�[�����Ȃ�����A����n��ಂ���������_�Ƃ��s����B�d���H��͑��݂����A�m�~��J���i���g���E�l���Ƌ�Ȃǂ����肷��̂ł��낤�B
���̓N���}�͎������A�s�s�E���R�Ƌ����E���쒬�Ƌ������n��Ƃ̊Ԃ��o�X�ōs�����藈���肵�āA�����ŕ�炵�Ă��邪�A�����ŕ�炵�Ă���Ƃ��ɂ͋߂��̒��܂Ŏ��X�F�l�̎Ԃɏ悹�Ă��炤���A�X�̋߂��̎V���܂Ŏ����̑D�Ɏ��]�Ԃ�ς�ł��������āA�������ɍs���B���R�ł͓k���Ǝ��]�Ԃƃo�X�ňړ�����B�Ƌ��ł̓e���r�̓f�B�W�^�������ɐ�ւ���Ă���͎@���Ȃ����Ă��Ȃ��B�P�[�^�C�͑D�Œނ�ɂł�����Ƃ��ɕK�v�ł���B�����Ȃ��ɑD�ʼn��ɏo��͕̂|���B�����P�[�^�C���Ȃ������璆�w3�N�̂Ƃ��ɂƂ����n���̖Ƌ�����������o���A���^�̃g�����V�[�o�[���g�������낤�B�����A�X�}�z�ȂǕK�v�Ȃ��A�K���P�[�ŏ\���ł���A���ꂳ�������R�ɂ���Ƃ��ɂ͓d������Ă��邱�Ƃ̂ق��������B�����̐l���p���Ă��邩�Ȃ�̂��̂��Ȃ��Ă����܂�ł���B
�G���W�����̑D���Ȃ���A�ނ�������Ă������h�⏬�邩��̒ނ肩��ނ�ʼn䖝����B1960�N����܂ł̓��{�Љ�ɖ߂�ƌ����Ȃ�A���́A��ɖ������Ƃ͎v��Ȃ��B�������A�قƂ�ǂ̐l�́A���R�̌����悤�ȎЉ�̓}���N�X�̋��Y��`�Љ�����A�͂邩�Ƀ��[�g�s�A�I�E��z�I�ŁA�S�����A���\�I�ƍl����̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȣ�A���`�e�[�[�v�A��{���I�Љ�v�̑�����o�����Č���Љ��ᔻ���Ă��u���̕��̕������������鉽���̎�����^����v���Ƃɂ͑S���Ȃ�Ȃ��Ǝv����B
�����A���ꂪ�R���̐��������f���ɂ��č\�z���遃����ׂ��Љ�A�����Ɍ����čs���c�_�����炭���ǂ邱�Ƃɂ��悤�B
���R�́A1970�N��ȍ~�̎R���ł͎R���{���̘J���͎��ۂɂ͌������Ă��܂��Ă��邪�A���̖{���I�ȘJ���̊�ՂƂȂ鎩�R�����͎c���Ă���ƌ����B����͎R���{���̘J�����ێ����g�傷�邱�Ƃɂ���āA���������R���o�ς��m�����邱�Ƃ��\�ł���A�ނ̐����u�J���{�ʁv�Љ�̎����Ɍ������ƂɂȂ�ƍl���Ă���B
���Ȃ킿�A�����̎R���̌o�ς́u���͖���A�_���ȂǍL���Ӗ��ł̌����I�ȋ@�ւł̎d���A���͓y�؍H���A��O�͔_�ƁA�ыƁA���ƁA�ό����܂ނ��̑����ׂĂ̎d���v���琬�藧���Ă��邪�A�����ɂ́u�R���Ȃ�ł͂̎����I�Ȍo�ϓI��Ղ��قƂ�ǂȂ��v�B�{���́u�R���o�ς̕�����ł͂Ȃ��A�R���̘J�����d���̕������ɂ��Ȃ���Ȃ�ȁv���B�u�R���ɂ͍L��ȐX�сA�R�A����͂��߂Ƃ���---���R�����v�A�o�ρu��Ձv�͂���B���̎��R���������p����A�d���E�J���̂�����������ꂽ���Ƃ����Ȃ̂��Ƃ����B�w���R�ƘJ���x
�ނ͒n���̋����ɂ�郄�}���̕����ɔ����Ă���B�܂��ό��z�e�����݂ɂ�������B�s�s�����Ăэ������Ƃ��邱�Ƃɔ��ŁA�R�����s�s�Ɉˑ����Ȃ����������o�ς����ׂ����Ƃ����Ă���B�ȒP�ɂ����A�҂��̘J���A���d�������炵�A�R�̎d�������ׂ����Ƃ������Ƃł���B
�������A���̂��Ƃ��l������˂Ȃ�Ȃ��͂����B�ނ̌��t���g���u�R���̘J���͈�ʂł͓s�s�̘J�����͂邩�ɂ��т������̂ł���ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ��ɂ���͖������ł���A�܂��Z�����Ƃ��ɂ͑�������[��ɂ܂ŋy�ԁv�B�����A���̂悤�Ȍ������d���ɂ������ƍl����l�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�l�X�ɂ��̂悤�Ȏd���ɂ����Ƃ����߂�Љ�͖]�܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��������ۏ�쑺�ł��A�������Ȃǂ́u�y�ȁv�d�����A���邢�́A���ق��d���Ȃnj����悭�u�҂���v�J���ɂ��A�J�����Ԃ����炻���Ƃ���l����������悤�����A����͓��R�Ȃ̂ł͂Ȃ����H
��ʂɓs�s�̒����J���̑����͊y�������̂ł͂Ȃ��B�������A�]���A�_�R���̖����s�s�̘J���͂̋������ƂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ́A�_�R���̕n�����ƂƂ��ɂ����ł̘J���̌��������������Ă���Ǝv����B��҂̒��ɂ͎��R���ɂ��炳��čs�����Ƃ̑����_�R���̌������J���ɂ���ׂĐl�H�I�Ȋ��̒��ł́u�y�ȁv�d���̂ق����D�ގ҂������B�Ƃ��Ɋy�������邢�͗L�Ӌ`�Ɋ�������d���łȂ���Ό������d����I�ԗ��R���Ȃ��B
�����R�����L�̘J���Ő��������Ă���l������B���R�͘J���̌������ɂ͑ς����邵�A���ۂɑ��l�͑ς��Ă���ƌ����B�u���l���ς��邱�Ƃ��ł���̂́A���R�̐l�ԉ��Ƃ��������̘J���v���Z�X���������g���͂�����F�����A�����̘J���̏��݂������Œm���Ă��邩��ł���v�Ƃ����B�w�R���̒ނ肩��x
�����̍s�Ȃ��Ă���d���̘J���v���Z�X��m��Ȃ���Ύd���ɂȂ炸�A�ǂ̂悤�ȘJ���҂������ꏭ�Ȃ��ꎩ���̘J���v���Z�X��F�����Ă���͂��ł���B���ɂ́A�����̎d���̘J���v���Z�X��m���Ă��邱�ƂƎd���̌������ɑς�����Ƃ������ƂƂ̊ԂɁA���ʂ̊W������Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��e�l�͗l�X�ȗ��R�ŘJ���̌������ɑς���ł��낤�B���Ƃ��A�d���͌������������Ȃ���ΉƑ��͋Q���Ă��܂����낤�B��ȉƑ��̂��߂Ɋ撣���ē����̂��B���邢�́A���̎d���͈�ʂł͊m���Ɍ��������A�ƂĂ��ʔ����B����Ȃɖʔ����d���͂ق��Ɍ�����Ȃ�����A�䖝���Ăł����̎d���𑱂���̂��B���邢�́A�|�\�l��X�^�[�ɂȂ铹�͂Ђǂ��������A�������B�������A���͂Ƃɂ����L���ɂȂ肽���A���X�B�������A�u�J���͎��R�̐l�ԉ��ł���v�Ƃ������Ƃ�F�����Ă��邱�Ƃ��A�d���̌������ɑς��闝�R�ɂȂ�ȂǂƂ͐M�����Ȃ��B
�����A���R�́u�����̘J���̏��݂������Œm���Ă���v���Ƃ��d���̂��т����ɑς��邱�Ƃ��\�ɂ���A�Ƃ������Ă���B�J���̏��݂Ƃ�����͈Ӗ������܂�͂����肵�Ȃ����A���݂Ƃ́u���݂���Ƃ���A���肩�A���݂��v�ł���(�w�L�����x)����A�����炭�A�J�����Љ�̒��ŁA�܂��l�ԑ��݂ɂ����Đ�߂Ă���ʒu�E�����̂��Ƃł��낤�B���R�́i�����Ǝ����̉Ƒ������̂��߂́j�����邽�߂����ɓ������Ƃ͘J���Ӗ����ƍl���邱�Ƃ��ƌ��邩��A�u�����̘J���̏��݂�m���Ă���v�Ƃ́A�J���҂��Љ�Ƃ̊W�ɂ����鎩���̘J���̖����A�Ӌ`��m���Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�w���R�ƘJ���x��T�͖����Q�ƁB����������Ύ����̎d���̎Љ�I�d�v����m���Ă���A�Љ�I�ȐӔC���ӎ����邱�Ƃł���B���̂悤�ȔF���A�ӎ����d���̂��т����ɑς��邱�Ƃ��\�ɂ���d�v�ȗv�f���Ƃ������Ƃ͊m�����Ǝv����B
���������R�������Ă��錻�ݏ�쑺�ōs�Ȃ��Ă���R�d���A�R���̂�ő����͔|���A�����k�����Ƃ��A���ʂɂ��̂悤�ȎЉ�I�Ȗ�����ӔC�ɂ��Ă̈ӎ������߂邱�ƂɂȂ邾�낤���B�ނ���A���R���q�ׂĂ���悤�ɁA�����R�d���͏o�ׂ̂��߂łȂ��A��Ɏ��Ə���̂��߂ɍs�Ȃ��Ă���Ƃ����i�����ɐ��Y�Ə���̕��������s�s���̐����Ƃ̂�����������A�Ɠ��R�͌����Ă���B�j���Ƃ��炷��A���̂��Ƃ�������悤�Ɏv����B�R���̔_�������Ə����ړI�ɂ��Ă��̘J�����s�����Ƃ́A�H��J���҂������̂��߂ɒ������҂����߂ɘJ�����Ă���̂ƁA���̈ӎ��ɂ����Ă͓������낤�B�R�d���������쑺�̐l�X���A�H��̒����J���҂��A�u���Ȃ̘J���̏��݂�m��v�A�Љ�I�g�����ʂ����߂ɁA(�������ɑς���)�J�����Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͓����ł���B
���R�́A��쑺�̐l�X�́A���Ɨp�앨���]�����Ƃ��ɂ͏o�ׂ���Ƃ����B����������͊�{�I�ɁA�Վ��ɍs���邱�Ƃł���B����҂ƒ��ړI�ȃR�~���j�P�[�V�������s���Ȃ���p���I�A�v��I�Ɉ��ʂY���o�ׂ���Ƃ����̂łȂ���A�Љ�Ƃ̊W�͔����A��͂�u�J���̏��݁v���ӎ����A�F�����邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B���R�̍l���邠��ׂ��R���͊�{�I�Ɏ��������̎Љ�ł���B�����I�ɂ͋ߗׂ̑��ƒ��ړI��face-to-face�̌������s�Ȃ���̂�������Ȃ����A�Љ�͈̔͂��L����̂ɂ�āA�ӔC���͔����B
������A�u���Ȃ̘J���̏��݁v���J���̎Љ�I������ӔC���Ӗ�����Ƃ��Ă��A�R���̘J��������������ڎw�����̂ł���A���Ə���̂��߂ɍs�Ȃ�����̂ł���Ȃ�A�R�����L�̘J���̌��������x������̂͢�J���̏��ݣ�ł͂Ȃ��B
���͎d���̌������ɑς��邱�Ƃ��\�ɂ���̂́A���̎d�����D�����Ƃ������ƂƁA�d���̂����������Ō��߂čs���邩�ǂ����Ƃ������Ƃ̓�ł͂Ȃ����Ǝv���B
�����w�ҁE�{�{���́w�C�̖��x�̂Ȃ��ŁA�u��{�ނ�͂���ɏ]�����̂ɂƂ��Ă͐��ƂƂ��Ă̈Ӗ������������A���ʂɂ̓X�|�[�c�Ƃ��Ẳ������Ă����B���̂��Ƃ������̋�����n�R�Ɉ����߂Ă����Ƃ����Ă����v�ƌ����Ă���B���Ԃ��{�ނ�łȂ��ق��̋��@�i�Ԃ��Ă̋��A���邢�͉���j�̂ق��������I�Ōo�ϓI�ɂ͗L���ł��낤�B�������A��{�ނ�́A���̋��@�ɂ͂Ȃ��A��C��C�����|���Ēނ�グ��Ƃ��́u�X�|�[�c�Ƃ��Ẳ����v�𖡂킦��B�������A���̋��@���s���̂Ƃ��Ȃ������̎����悤�Ƃ���A���V��̂Ƃ��ɂ��o������Ȃǂ��Ă�葽���̘J���������Ȃ�˂Ȃ�Ȃ��B�܂�ʔ����͘J���̌������ɑς��邱�Ƃ��\�ɂ���d�v�ȗv���ł���B�����ł͎R�̎d���̖ʔ����͂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����Ȃ��Ƃ��A�x���g�R���x���[�ɒ�����ĒP���ȓ�����J��Ԃ��H��J���ɔ�ׂ�A�R�̎d���ɂ́u�ʔ����v������Ə\���ɍl������B
�������A�����Ȃ�d����ʔ����Ɗ����邩�͐l�ɂ��A�܂��N��ɂ��قȂ�B�N�����ނ��ʔ����Ǝv���킯�ł͂Ȃ��B�܂肢���Ȃ�d�����ʔ����̂��͋q�ϓI�ɂ͌����Ȃ��B�D�����Ƃ�����ϓI�ȗv�f���d�v�ł���B�D�����Ƃ���ΐl�͊��ł��̎d�������A�������Ă��ς��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
�܂��A�l�͂��̎d���̂����������Ō��߁A���R�ɂ����Ȃ����Ƃ��ł���Ȃ�A���l�̖��߂ɏ]���čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɔ�ׁA�����Ƃ��̎d�����C�ɓ��邾�낤���A���X�́A�h���A���������N����ɂ��Ă�����ɑς����邾�낤�B�ٗp����ē����Ă���A�N�����l�̖��߂Ŗ�����肻�̏��䖝�����Ƃ���A�i���̎d��������j����͑��̎d���Ɉڂ邾�낤�B
�������āA�R�̎d�������R�ɍs�����Ƃ��ł��A����l�ɂƂ��Ă͊y�����Ɗ����邱�Ƃ�����ɂ��Ă��A�N�����R�d�����y�����Ɗ�����킯�ł͂Ȃ����A�Ƃ��ɒ����ԂɂȂ����茵�����J�����܂ނ��Ƃ�����Ƃ���A�R�̎d����K�������D���ł͂Ȃ��Ƃ����l�X�ɂ͎R�d���͊��߂��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł���B
�R���ɏZ�ސl���ǂ�Ȏd���ɏA�����A�ǂ�ȗV�т����邩�͊e�l�̍D�݁A�I���ɂ䂾�˂邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�ЂƂ́A�X�l�ł́A���邢�͑��Ƃ��Ă��A������Ƃ����������S�̎Љ�̂�����A���{��`�I�Ȍo�ς̎d�g�݁A�����Đ��{���i�߂�o�ϐ����Y�Ɛ���A�Љ��Ȃǂɂ���Č��܂�����A�܂������̉Ƃ��ǂ̒��x���������Ă��邩�A�R�т������Ă��邩�A�܂��A�ނ����l����܂łɂǂ̂悤�ȕ������{���l�����Ă��邩�A�Ȃǂ̏������܂��āA�����̍ł���肽���d���ɏA�����Ƃ���B���̌��ʁA�R�d�������Ő����Ă������Ƃ��邩�A���̊O�Ɏd�������߂邩�A������ɋ߂邱�ƂɂȂ邩�A���ق��d�������ł��Ȃ����A���X�����܂�B���͂��R�ł���A�X�сA�삪���邩��Ƃ����āA���̐l�������̏A���ׂ��d�����w�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���R�͂ӂ��̎�҂��Ȃ��s��œ����������𗝉��ł��Ȃ����낤�B�Z�p�������Ă�����̂͋Z�p���ł���d���ɏA�����Ƃ��ł��邪�A�����łȂ��҂͔�r�I�P���ȘJ���ɏA������Ȃ��B���̍ہA�����ԍH��̂悤�ȗ����Ƃɔ�ׂ�A�R��C�̎��R�̒��ōs����d���̂ق����ʔ�����������Ȃ����A����ɂ����ؓ��J���͐h������łȂ��ʔ��݂Ɍ�����Ƃ����ʂ�����̂ł���B�E��ł����߂⌙���点���Ȃ���A�ڋq�Ƃ�T�[�r�X�Ƃ̂悤�Ȑl�Ԃ�ɂ����d���A��b�����Ȃ���s���d���̂ق����D�܂��̂ł���B���i���W���邾�낤���A�����O�̎�҂̑����́A�͂��߂���A�فX�ƎR�Ŗ��A�����k���A�C�ŖԂ������悤�Ȏd���ɏA�������Ƃ͎v��Ȃ��B�K����������������Ă��Ȃ��Ă��������Ƃ̂ł�����H�X�₻�̂ق��̏��X��I�t�B�X�œ������Ƃ��ł�����̂ق����D�܂��B
�܂��A�R���⋙���ɂ͗V�ԂƂ��낪�Ȃ��Ƃ������t�����ɂ��邱�Ƃ�����B���N�ȏ�̐l�ԂȂ�R�؎�����̂�A���邢�̓o�[�h�E�H�b�`���O�⎩�R�T���A�C�Ȃ�ނ���y���ނ��Ƃ��ł���B��������҂͊C��R�̃X�|�[�c�������Č����ł͂Ȃ����A�F�B��K�[���t�����h�A�{�[�C�t�����h�ƈꏏ�ɂ������Ƃ��D�ށB�����āA�l���吨����X�̂Ȃ��ŗV�Ԃ��ƍD�ށB�����ŁA�R���A�����̎�҂́A�ԂŒʂ��鋗���ɂ���X�œ������Ƃ��邩�A�K���ȏZ��������ΊX�ɏZ��ŊX�œ������Ƃ���B
���������āA�R���A�_���A�������ό��J���ɓw�߁A���܂����������݂�����z�e�������ĂāA�s���l�X���Ăэ��݁A���̓��Y�����g���������������A���y�Y�����肷��r�W�l�X���s�����Ƃɂ͏\���ȈӖ�������B
���̐l��������A����ɉߑa������͎̂�҂��X�ɏo�čs������ł���B��������X�ɂł����̂����N�ɂȂ��Ă���A����܂ł̎d������߂āA���ɂ���d���ɏA�����߂ɉƑ��ƈꏏ�ɖ߂��Ă���Ƃ������Ƃ͓�����낤�B���������ē��R�������悤�Ȏ��R�ƌ��т����J���ɂ���Ď��������o�ς����R�����S���ɍL���聃�s�s���͂��遄�悤�ȕ����ɎЉ�ς���Ă����Ƃ����W�]�������Ƃ͔��ɓ���Ǝ��ɂ͎v����B
�����āu�N�w�҂̖ڂ���݂��ނ�v�ƌ�����łȂ��ꂽ�A���J�u���ł̓��R�̒ނ�_�A�܂�u�ނ�͘J�����v�Ƃ����ނ̎咣�����A����ɔ��_�������B
���R�͌k���ނ�Ɓu�R���̒ނ�v�Ƃ͈قȂ�Ƃ����āA�����̍ŏ��̒ނ���ނƂ����{�̏������w�R���̒ނ肩��x�Ƃ������R��������Ă���B�u�k���ނ�Ƃ͂����P�Ƀ��}����C���i��ނ邽�߂ɂ̂ݎR�Ԃ̐�ɍs���Ēނ������Ƃ������o��\���v���Ă��邪�A�ނ̒ނ�́u�R���ɕ�炷�l�X�̒ނ�ɋ߂����́v���Ƃ����B�u���̑��l�Ɠ����悤�ɁA�������Ԃ͔��d�������āA�[���ɐ�ɍ~��Ă����k�ނ�����l�܂��B�t�ɂ͎R�؍̂�A�H�ɂ͑����l�ƈꏏ�ɂ��܂��B���l�Ƃ̕t���������������������Ă��܂����B����͎R���ɕ�炵�Ȃ���̒ނ�ł��B���ƎR�A�X�A�삪��炵�̒��ň�̂ɂȂ�A���̕�炵�̒��ɒނ������̂ł��v�Ɣނ͌����Ă���B
�u���R���̒ނ聄�Ƃ͔��A�R�A�X�A��A�R������̂ƂȂ������E�̂Ȃ��Œނ�����邱�Ƃ�----�ʂ̕\��������A�l�X�Ȍ�ʂ̒��ɒނ������A�Ƃ������Ɓv�ł���B�u���d�����Ƃ����āA���l�͎��R�̐��E�ƌ�ʂ��A���l���m��---���͂������Ȃ���---�R��X�ŎR������̂�����A�d���W�߂���A�Ƃ��ɗыƂ����Ȃ���A�����ł����l�͎��R�ƌ�ʂ��A���l���m�̌�ʂ��������Ă��v��B�u�����Ēނ���܂��ƂƎ�����(�j��p�������R�Ƃ̌�ʂł���A�ނ�ɕ������l���m�̌�ʂ̏�ł�����v�B���̂悤�ȑ��l�̂����Ȃ��u���R�Ƃ̌�ʁv�ł��肩�u���l���m�̌�ʁv�ł���悤�ȁ��R���̒ނ聄�ɔނ̒ނ�́u�߂��v���̂��Ɠ��R�͌����B
���āA��ʂɁA�ނ�ɂ����ẮA���ʂ悤�Ƃ���Έ��̋Z�p�܂�r���K�v�ł���A�܂�������d�v�ŁA�ނ�l�͗ǂ�����ɂ������B�r�͒m���E�Z�p���g�̂ƈ�̉��������̂ł���A������̘r�̉����ł�����B���̓_�Œނ�l�͐E�l�Ǝ��Ă���A�ނ�l�̘r�͐E�l�̋Z�Ǝ��Ă���B�E�l�̓J���i�Ȃ�Ȃ�ł��悢�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�������̃J���i���Ŗ����B�E�l�̎d���ɂ͌�������B�ނ�́u����Ƙr�A���_����̉����Đ�������v���̂ł���u����䂦�Ɉ�l��l�̒ނ�Ɍ�������v�B���R�͂��Ă̐E�l�̘J���̂悤�ɘr�A����A���_����̂ł���J�����A�{���̎p�̘J�����Ƃ��āu���n�I�v�J���ƌĂԁB�������āA�ނ�́A����Ƙr�Ɛ��_�����т��Ă���_�ŁA���n�I�ȘJ���Ƃ��Ȃ��\���������Ă���A���n�I�J���Ɏ��Ă���B
�A�_���E�X�~�X(1723-1790�j�̏ё���AWikipedia�ɂ��B<>
�`�D�X�~�X�͔_�Ƃ́u���炵���v�ƌ����Ă��邪�A�ނ�͔_�Ƃɂ����Ă���Ɠ��R�͌����B�X�~�X�́A�_�Ƃ̓������O�w�E���Ă���B�_�Ƃɂ����ẮA�J�����d�˂邱�ƂƘr�̒~�ς���v����B�����āA���̘r�̌�����앨�̏o����ʂ��Ď������g�̎�Œm�邱�Ƃ��ł���B����ɁA�k����Ԃ��K�v�ȐE�l�J���Ƃ͈���āA�_�Ƃ͂P�N�ڂ̔_���ł��앨�����n�ł���ƌ����Ă���B���R�́u�ނ�ň�ԏd�v�Ȃ��Ƃ͌o���v�ł��邪�A����͔_�Ƃ̏ꍇ�Ƃ��Ȃ��ł���B�����Ēނ�l�͗l�X�ȍH�v���s�����A�u�_���͖��N���Ȃ��_�Ƃ����Ă���悤�ŁA���ۂɂ͓��X�V�����H�v�������āv����A���X�A�_�Ƃ͒ނ�Ɓu�ƂĂ��悭���āv����ƌ����B
���R�͂܂��_�ƘJ�����y�������̂��Ƃ������Ƃ�͐�����B�ނ́u�R�`���̔_�ƗщƂ̌I�c����v���狳��������Ƃ����ƁA�u�V�сv�Ɓu�A�\�r�v�̈Ⴂ���������B
�s�s���́A�d���ƗV�т́u�ʂ̂��́v�A���ɂ͑Η�������̂ƍl���Ă���B�I�c����́u���̂悤�ȈӖ��ŗp������V�тƂ������t�͔_���̂��̂ł͂Ȃ��v�ƌ����B�_���ɂƂ��ăA�\�r�Ƃ̓n���h���̃A�\�r�Ƃ����Ԃ̃A�\�r�Ƃ������̂ɋ߂����̂ł���B�u���Ȃ킿�A�d���̊O�ɃA�\�r������̂ł͂Ȃ��āA�d���̂Ȃ��̊ԁk�܁l�Ƃł������悤�Ȍ`�ŁA�_���̃A�\�r�͐��܂�Ă���v�Ƃ����B������āA���R�́A��쑺�ł̔��d�����A�����ɃA�\�r�ɖ������y�������̂ł��邩���������B
���̏�ł̓������́A�����Ă��鎞�Ԃ��x��ł��鎞�Ԃ̂ق��������B�ꐶ���������Ă���������邪�A����قǓ����Ȃ���������B���̒��ō����̎d���̗\����l���A�K�v�ȓ���������Ĕ��ɍs�����A���ɗ��Ɨ��̌i�F���ڂ̑O�ɍL�����Ă���B�E�O�C�X�̖������������Ă���B�������Ă���i�F�Ȃ̂Ɍ��Ƃ�Ă��܂��B�d�����n�߂Ă���Ƃ������Β��f���A�ʂ肪����̑��l�Ƙb������B���邢�͑��Ԃ⒱�⒎�Ɍ��Ƃ�Ă���Ƃ�������A���X�B�u�����͊ԈႢ�Ȃ��u�y�����v�ł���A�d���̒��Ɍ���Ă���ԁi�܁j�ł�����v�B���̊�(�܁j�̒��ɃA�\�r������B���̔��d����R�d�����I�����[���A��֍~��Ēނ������B�u���̒ނ�̎��Ԃ��R���̈���̂Ȃ��̊ԁi�܁j�Łv����B�ނ�́u�R���̎d���̌n�ɕ�ݍ��܂�Ă���v�ЂƂ̊ԁi�܁j�ł���A�\�r�ł���B
����͎����̔����Ƒ��l�����̔������ƌ��Ȃ��A�܂����l�́u�����v�Ɓu�́v�̗V�с^�A�\�r���Ȃ������ɂ��Ȃ���A�_�Ƃ̊y������`���B�u���n�I�ȘJ���Ƃ��Ă̒ނ�Ƃ������i�́A���̂悤�ȁk�_�Ɓl�J���̈�ʂ��[���I�ɑ̌������Ă����Ƃ���ɂ�����悤�ȋC�����܂��B�N�����d�˂邱�Ƃɂ���Ęr�����܂�A���̘r�ƌ��т����`�ŁA�ނ�̂Ȃ��ɃA�\�r�̐��E�������Ă���̂ł��B�ނ�l���܂��A���낢��ƍH�v���܂��B---��������ďɉ������ނ肪�o����悤�ɂȂ��Ă���ƁA�ނ�̐��E���Ђ낪���Ă��܂��v�Ɣނ͌����B
�R���̐����ɂ͐����ƘJ���̕����͖����A�J���́u���n�I�v�ł���B���̂悤�Ȑ����ƘJ���̑̌n�ɕ�ݍ��܂ꂽ���̂Ƃ��čs����ނ肪�A�܂�A�J�����������J���̊ԁi�܁j�Ƃ��ĎY�ݏo���y���݂Ƃ��čs����ނ肪�A�ނ̌������R���̒ނ聄�Ȃ̂ł���B���R�͌����u�������R���̒ނ聄�ƌĂԂ��̂́A���̂悤�ȃA�\�r�̈�`�ԂƂ��Ă̒ނ�̂��ƂȂ̂ł��v�B
�������A���̌I�c����Ƃ����_���͓��R�́w���R�_�x(��łӂ��j�̒��ɂ��o�ꂷ�邪�A�ނ̉Ƃ͑�X�����_�ƗщƂł���Ƃ����B�܂�R�т����L����_�Ƃł���A��Q�̔N�ɂ͕s�삾�����Ă̌����߂ɐ�����Ĕ��邱�Ƃ��o�����B�ނ͎��Ɨp����̂��߂̔��Ə��i�앨�Y����c�������Ă��邾���łȂ��A�����ƌ����Ƃ��ɍޖ��o�����Ƃ��o����R�т����L���Ă���B�ނ͏\���ɗ]�T�̂���_�Ƃ��c�݁A���̗]�T���A�\�r�ɂ��Č���Ă���̂ł���B�_�ƘJ����ʂ��A���R�̔��̍k��̂悤�ɉɂ��炯�ŁA�A�\�r�������Ղ莝���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͐S�ɗ��߂Ă����Ă��������낤�B
���R�́A�R���̐l�X�����Ɨp����̂��߂ɍs���Ă���J����s�s�J���҂̒����J�����u���`�̘J���v�Ƌ�ʂ��āu�L�`�̘J���v�ƌĂԁB���R�́A����ł͒����J���������J�����ƍl�����Ă��邪�u�J���Ƃ͂��Ƃ��Ƃ͂����������̍L�����̂ł������͂��v�Ƃ��������Łi�w�����Љ�x�j�ڂ������������邱�ƂȂ��ɁA���́u�L�`�̘J���v�Ƃ���������A�R���̐�����̂̐l�X�̐����͂��̂悤�ȘJ���Ő�߂��Ă����ƌ����B
���炭���̂悤�Ȃ��Ƃ����R���Ǝv����B�s�s���������Ă����H�ނ��ƂŒ������ĐH�ׂ�Ƃ��A�Ǝ��J���ɂ��čl����Εʂł��邪�A�����Ă��͏�����̊����ł���ƍl����B�Ƃ��낪�R���̐l�����Ɨp����̂��߂ɎR�֍s���đ���R���̂�A�ƂɎ����A���āi���̈ꕔ�͏o�ׂ��Ă��A�������j�������ĐH�ׂ�Ƃ��A�R�����~��Ă���Ƃ���܂ł��J���ʼnƂɈ��������ꂽ�����̊����Ȃ̂��ǂ����A����̒[�ɘJ�������葼���̒[�ɏ������ƍl���邱�Ƃ��ł��邪�A�ǂ��܂ł��J���łǂ����炪����̊����Ȃ̂����͂����茾�����Ƃ��ł��Ȃ��B�J���ƉƂł̏�����Ƃ��͂����蕪���邱�Ƃ��ł����A���҂͘A���������̂Ƃ��Ă������B�����ɎR�������̘J���E�����ƁA�s�s�̒����J���Ɛ����Ƃ̈Ⴂ������B���������̂��߂ɍs����R���̘J�����J���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��V�������O������K�v���Ȃ��Ƃ��v���邪������ƘA�����Ă����ʂł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��������悤�Ƃ��ē��R�́A�V�������t��p����̂��Ǝv����B
�Ǝ��E�玙���L�`�̘J�����Ɣނ͌������A�����ǂT�A�U���̔ނ̒���̒��ł́A�Ǝ��J���ɂ��Ă͂Ƃ��Ɏ��グ�Ę_���Ă��Ȃ������͂����Ă��Ȃ��B����͘J���Ə�����̘A�����A���邢�͐����ƘJ���Ƃ̓��ꐫ�Ƃ����Ƃ���ɂ̂݊S�������Ă��邩�炾�Ǝv����B
�Ƃ��낪�A�ނ́u���Ƃ��ΗF�l�W������Ă����Ƃ�---������̂悤�ɏW�܂�̏������Ă����Ƃ��v���܂߂��ׂĂ̊������J���ł���A�u�l�Ԃ̈ꐶ���̂��̂��J���̐ςݏd�˂̒��Ɏ������Ă���v�ƌ����B�u�l�Ԃ͊�����܂��Ă��邩����J�����s�������Ă���悤�Ɏv����B���̘J�����܂߂����̂��L�`�̘J���ł���v�i�w�R���̒ނ肩��x�u��L�v�j�Ƃ������Ă���B�R���̐����ɂ����ẮA���Y�J���Ə�����Ƃ͘A�����Ă���A�J���Ə�������ȒP�ɕ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ͊m���ł���B�������A�ނ͈���̐������邢�͈ꐶ�͂��Ȃ킿�u�L�`�v�̘J���ł���ƌ����B�܂肷�ׂĂ̊������J���Ɖ��炩�̊W������A���������āu�L�`�́v�J���ł���ƍl���A�J���ƑΗ����銈���i�V�сj���܂߁A�J���ł͂Ȃ����������݂��邱�Ƃ�ے肵�悤�Ƃ���̂ł���B
�ނ͋x�e��x���A���邢�͍��x�߂Ƃ����ӂ��g���Ă�����J���̊ԁi�܁j�Ƃ��A�\�r�Ƃ������Ȃ�Ȃ����t�Ō���������B�ނ̍l���ł́A�܂��J��������A�Ԃ��A�\�r���A�J���̍��Ԃɂ���A�J���ɂ��Y�ݏo���ꂽ�����Ȃ̂ł���A�J���ƕʂ́A�J������Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A����ΘJ���ɏ���������́A�J���̈ꕔ�ł��邱�Ƃ�������Ȃ̂ł���B�x�e��x���Ƃ͘J������������x�ނ��ƁA���邢�͘J�����Ă��Ȃ��A�E�J���̎��Ԃł���ƕ��ʂ͍l����̂����A�ނ͂��̂��Ƃ�ے肵�悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�x�e��x���͘J���������Ă̂��̂��Ƃ����킯�ł���B
���͑�Q�͂R�߂ł��l�@�������A�����́A�J��(�E�ƘJ���ƉƎ��E�玙�J���j�ƐH����V�тȂǂ̊����Ɛ����i�x�{�j�Ȃǂ̔����琬�藧���Ă���A���̐������Ԃ̑�����J������߂Ă���ƍl���邪�A�ނ́A��Ȃ��ƂɁA�������邢�͐�����Ƃ������Ƃ��̂��̂��J���������͘J���ɕt�����������Ɣ��Ȃ̂��ƌ����̂ł���B
��̊������J�����Ƃ���A�ĂсA���̂Ȃ��ɁA�H�ׂ�J���A�k���J���A�V�ԘJ���A�x�e����J���A���X���l���邱�ƂŁA���ʂ̐l�̍l���鐶���ƈႢ�͂Ȃ����ƂɂȂ�ƁA�`���I�ɂ́A�ނ̂��̂悤�ȁu�������J���v�ς̖��Ӗ������w�E���邱�Ƃ��ł��邪�A�ނ́A�����I�ɁA�̂̐l�X�͈�����d�������Ă���A���x�߂͂����Ȃ������A�]�ɂ�V�тȂǂ͑��݂��Ȃ������A�Ǝ咣����̂ł���B
�̂́A�_�Պ��Ɂu�_�������͘A�ꗧ���ē����ɍs������A���Ղ肪�s��ꂽ�肷����̂ł����B����͍����I�ɂ����A�V�тɍs���Ƃ������ƂȂ̂ł����A���ۂɂ͎d���̌n�ɑg�ݍ��܂ꂽ�A�\�r�̎��ԂƂ��Đ������Ă��܂����v�B�u���J�u���v
�ނ́A�����������I�ɘJ���^�d������ł���悤�Ȑ��������L�Ӌ`�ȁA�ǂ��������ł���A�l�͘J���������ł���悤�Ȑ����ɖ������ׂ����A�J���^�d���ȊO�̂Ƃ���ɐ���������������������A�]�ɂ̑�������߂�̂͊ԈႢ�Ȃ̂��A�Ɛ����Ă���̂ł���B
�ނ͂`�D�X�~�X���_�ƘJ���͂��炵���ƌ��������ƂȂǂ����������ɏo�����A�̂́A�������Ԃ̂��ׂĂ��J���Ő�߂��Ă����悤�Ȑ����́u�ǂ��v��_���悤�Ƃ͂��Ȃ��B�i�_�Ƃ͂��Ƃ��L���������ƍl�����Ă��錴���A���Ƃ��ΐl�Ԃ͍K���ɂȂ錠���A�����Ȏ��R�̌�����L����Ƃ����悤�Ȍ����Ɋ�Â��āA�ǂ��Љ�A�������Љ�̂�������q�ׂ�A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B�j�ނ͘J���{�ʂ̎Љ�A�������Ԃ̂��ׂĂ��J���Ő�߂��Ă����悤�ȎЉ�u�ǂ��Љ�v���Ƃ������A�ނ͂�����u�D�ށv�Ƃ��������ŁA�_���Ȃ��B
�w�R���̒ނ肩��x�u��L�v�ł͎��̂悤�Ɍ����Ă���B�u�{���l�ԂɂƂ��Ă͂��ׂĂ̍s�ׂ��J���ł������B----�Ƃ��낪�ߑ�ȍ~�̏��i�o�ς̗��j�̒��ł́A���i������J��---�Ƃ������`�̘J���������J���Ƃ��ď��F�����悤�ɂȂ����B���̌X���͎��{�����Y�l���ɂ���Č���I�ɂȂ�B�^�i���s�j��������J���Ɛ����̕����������A�܂��J���������邽�߂̘J��ɂȂ����B�������Ăł��������Ă����̂�����̎s���Љ�ł���B�^���͂��̂悤�ȎЉ�D���ł͂Ȃ��v�B
���������Ɋ��s���ꂽ�w�J���̓N�w�x�ł͂����Ƃ͂�����Ǝ��̂悤�Ɍ����A�u��������ꂸ�Ɍ����A���{���Љ��ǂ��Ƃ��邩�����Ƃ��邩�́A�����A�n���A�J���̑a�O�Ƃ����悤�ȌX�̖��ł͂Ȃ��A���{���I�Ȑl�Ԃ̑��ݍ\���������̂�����Ƃ����ۂ���̂��Ƃ����v�z�Ɗ����̖��ł���Ƃ����C������B�m���Ɏ��{���Љ�͈��̐l�Ԃ�n���Ɋׂ��B---�����������̑����h�͔ނ���Љ�̔s�k�҂Ƃ݂Ȃ��ċ����邱�Ƃ��ł���̂ł���B----����ɘJ���̑a�O������͘J���҂̒�߂�ꂽ�^���Ƃ�����߂邱�Ƃ��ł���̂ł���B���Ȃ킿���{���Љ��ے肷��_�@�́A���\�ȕ\���ł͂��邪�A�Ȋw�I�Ș_���ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���̂ł���B���̎����̑��݁A�l�Ԃ̑��݂�ǂ��Ƃ��邩���ۂ��邩�Ƃ����A�l�Ԃ̎v�z�Ɗ����̖�肾�ƍl����̂ł���v�B
���{���Љ��ǂ��Ƃ��邩�����Ƃ��邩�́A���{���̎d�g�݂������炷�s�����A�n���A�J���a�O�A���邢�͌��Q�A���R�j��A���X�̋�̓I�Ȗ��̌̂ɂł͂Ȃ��A�u���{���I�Ȑl�Ԃ̑��ݍ\���v�A�܂�u�J���Ɛ����̕����v������邩�ǂ����ɂ���Ă��܂�̂��Ƃ����B�ނ͂��̎Љ�Ő�����l�X�̍K�E�s�K�A�ꂵ�݂��тɊS������̂ł͂Ȃ��i����́u�����v�̖��̂͂������j�A���ۓI�ȁu�l�Ԃ̑��ݍ\���v�A�����ƘJ���̘A�����^�s�A�����Ƃ����`���ɊS������̂ƌ����ł���B�������ɎЉ�̍��{�\������̊�{�I�`�����A���ꂪ�Y�ݏo���������̌����̖��Ɛ藣���āA�ǂ��������u�_����v���Ƃ͂ł��Ȃ�����A���ǁu�D�������v�̖��ɂ��Ă��܂����ƂɂȂ�̂��낤�B
���R�́w���R�ƘJ���x�́u�N�w�̎�̐��v�Ƒ肳�ꂽ�u�I�́v�ŁA�N�w���w�����@�ɖʂ��Ă���̂�������������A�����̎Љ�ɑ��鉿�l���f��������悤�Ƃ���X��������ƌ����Ă���B���j�A�Љ�Ɋւ����ΓI�A�q�ϓI�^���͑��݂�����̓I�^�������邾��������A���l���f�͕s�����Ƃ����B���́u�N�w�̎�̐��v�̕K�v�Ƃ����咣�ƁA���{���Љ��ǂ��Ƃ��邩�ۂƂ��邩�Ƃ������f�̖�肪�W����ƍl����ꂻ���ł���B
�������A���ۓI�ȎЉ�̍\�����̂��̂��D�������������������ƂƉ��l���f���s���Ƃ������Ƃ������ł���킯�ł͂Ȃ��B�u�l�Ԃ̑��ݍ\���v�Ƃ��A�����ƘJ���̘A�����^�s�A�����ȂǁA���ꎩ�̂��A���w�̒藝���������Ƃ������łȂ��Ƃ��ƌ����悤�ɁA�ǂ��Ƃ������Ƃ����l���f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���l���f���s����Ƃ���A�ꕔ�̐l�����ʂ�}�����A�n������Q�ɋꂵ�ނ悤�ȎЉ�̂�����ɂ��āA�ǂ��i���邢�͍\��Ȃ��j���������̉��l���f���s����̂ł��낤�B
�������Ĕނ́A����i���{�j�Љ������A�n���A�J���a�O�A���Q�A���R�j��A���邢�͊����ƍفA���X�̋�̓I�����I�����Ƃ̊W�ɂ����āA���{�����Y�l���Ƃ������{�\�������ۂ��āA����ׂ��Љ���Ă���̂łȂ��A�u���n�I�J���v�ł���E�l�I�A�_���I�J�����x�z�I�ȁA���Y�Ə���A�����Ă���A�J������̎Љ���������ׂ����Ǝ咣����̂ł���B���ꂪ�ނ̌����u�L�`�̘J���v�Љ�ł���B
���R�͂��̂悤�ɂ��đ�����ꂽ�A�����Ɉˋ����A�J���Ƃ���ȊO�̐����Ƃ������ꂽ����̓s�s�^�����ƁA���Ɨp����̂��߂̘J���Ɉˋ����A�J���Ə���A�����Ă���A�����������I�ɐ������Ԃ��قƂ�ǘJ���Ő�߂��Ă���悤�ȎR�������Ƃ̑Δ��w�i�ɂ��āA�ނ̒ނ���A�s�s�̐l���s���Ă���A�V�т̌k���ނ�ł͂Ȃ��A���R���̒ނ聄�A�u�A�\�r�̈�`�Ԃł���ނ�v�܂�u�J���ł���ނ�v�ł���A���邢�͂���Ɏ��Ă���Ǝ咣����̂ł���B
�@���R�́A�u���̒ނ�́A�R���ɕ�炷�l�X�̒ނ�ɋ߂����̂ł��v�ƌ����B�������A�ނ̒ނ��J���ƌ��Ȃ����Ƃ͓���B�ނ肪�J�����Ƃ�����̂́A���������I�Ȑ����𑗂��Ă���l���A�_�Ƃ�ыƁA���̑��̘J���̍��Ԃɍ��x�߁A���邢�̓A�\�r�Ƃ��Ēނ���s���Ƃ��ł���͂��ł���B�������ނ͑��l�Ɠ����悤�ɏ���ƘJ������ʂ���Ȃ��悤�Ȑ����A���������I�����𑗂��Ă���̂ł͂Ȃ��B
���R�͎������u�ʂ��_���v���Ƃ����Ă���B�����A��쑺�ɒʂ��Ă��āA���l�ƈꏏ�ɎR���Ƃ�����A�肽�����k�����肵�A�d�����I������A�[���A���l�ƈꏏ�ɒނ�����Ă���Ƃ����B���̂悤�Ȓނ�͖��T���ɂ���Ă��Ē��Â���������Ƃ��o���A�Ȃ�Ƃ��މʂ悤�ƈ�����S���Ēނ������u�s��̐l�X�̒ނ�v�����A�������ɎR���ɕ�炷�l�X�̒ނ�Ɏ��Ă͂���B
�������A�ނ͂ӂ���A�����̑�w�ŋ����A�G�b�Z�[�������A�����Ő������Ă���B�R���Ő������Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ͏�쑺�ł͗��قɐ������āA�k���Œނ���y���ޒނ�q�Ȃ̂ł���B�������ɂ���͔����k���Ă���B�������A�ނ͏�쑺�Łu�����k�����Ԃɒނ������v�����ł͂Ȃ��A�����̌k�������������K�˂āA�����ʂ�́��k���ނ聄�����Ă���B�܂��A�����A�C�O�ɂ��u���ł��ފƂ������āv���s�ɍs���B�i�w�R���̒ނ肩��x�U�j�B
���Ɉ�قɔ��܂��Ĉ�T�Ԓ��x�؍݂��邱�Ƃʂ͐����Ƃ͌ĂȂ��͂����B�C�O���s�ł͔��N�قǗ��������Ƃ������Ă���B���̂Ƃ����͂ǂ��Ȃ�̂��낤���B���̌o���ł͉ċG�͏T�Ɉ��A�~�ł����ɂP����x�̎����ł͔��͑��ڂ��ڂ��ɂȂ��Ă��܂��B�ނ͗L�@�_�@������Ă���Ƃ͌����Ă��邪�A�u���R�_�@�v������Ă���Ƃ͌����Ă��Ȃ��B�u���R�_�@�v�͏��R�ׂ̗̈ɗ\�s�o�g�̌̕������M�������_�@�ŁA�k�����A���������Ȃ����B�w���R�_�@�E����{�̊v���x�i�t�H�Ёj�ȂǎQ�ƁB
���R�̔����́A���l�������̕K�v����s���Ă��锨���Ƃ͑S���Ⴄ�B�ނ́A���ł��܂��܂ȍ앨�������I�ɍ���āA��쑺�̋C���y�ɍ������̂����ł��邩�������Ă��邪�A���l�͂���܂ł̎��т���A�m���Ɏ��n�������܂����̂��������Ə����Ă���B���l�̘J���ɂ́A�������������Ă���A�����Ă݂邾���̗]�T���Ȃ�����ł���B��������Ƃ͂����������Ƃ��낤�B
����ɑ��āA���R�́A���s���Ă������̐S�z�͂Ȃ��̂ŁA���܂��܂ȍ앨�������I�ɍ���Ĕ_��Ƃ��y����ł���̂ł���B���A���^�X�A�L���x�c�A�Ƃ����낱���A�������Ȃǂ͂���Ă݂������߂������Ə����Ă���B�ނ͑�Z�\�����܂��ł��đ��l�ɕ����Ă����u�ۑ��e��Ƃ��Č��\�֗������Ă���v�ȂǂƎ��掩�^���Ă��邪�A�Ƃ̒��ɂԂ牺���ď���A���邢�͎�̓���Ƃ��ėp����Ƃ����̂Ȃ�b�͕ʂ����A�e��Ƃ��Ă̎��p�����炢���A�Z�\�����Ƃ����͔̂ނ̔��d�����V�т��Ƃ������Ƃ̖��m�ȏ؋��ł���Ǝ��ɂ͎v����B
�ނ̖{�Ƃ͑�w���t�A�G�b�Z�[�C�X�g�ł���A���d���ɐ����͂������Ă��Ȃ��B�{�Ƃ��邢�͐��ƂƂ͕ʂ̊y���݂ōs�������́A���ʁA�V�тɕ��ނ����B�ނ̏�쑺�ł̔����͗V�тł���A�s��̐l����ōx�O�݂̑��_���ōs�������ƂȂ��ς��Ȃ��B
�ނ��A��쑺�̐l�Ɠ��l�A�k����܂ߕ����́u�d���v���s���Ă��邪�A�ނ̐����͔����ƁA�R�؎�����̂�A�����Čk���ł̒ނ�Ő��藧���Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ́A�_�������ɂ͂Ȃ��A���肵����������ʂɎ����Ă���B�ނ��u�R���̔_���v�ƌ��Ȃ��͓̂���B���������āA�ނ̒ނ���d���^�J���ł���Ƃ݂Ȃ��̂͂����Ɠ���B�ނ̒ނ�Ɩ{�Ƃ̊W�́A��R�͂ŏq�ׂ��K�c�I���̒ނ�Ə����ƂƂ��Ă̖{�ƂƂ̊W�Ɠ����ł���A���̒ނ�͎d���Ƃ͕ʎ����̊����ŁA�I�������������Ă���悤�ɁA�V�тł���B
���́A���R�̏�쑺�ł̔��̍k��͏�쑺�̐l�X�̘J���ƈقȂ�A�����̕K�v����s����Ă�����̂łȂ��A�ނ́u�������J���v�ł���悤�Ȑ������������Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA���������Ĕނ̒ނ�́u�J���������v�̈ꕔ�ł���悤�ȁ��R���̒ނ聄�ł͂Ȃ��A�܂�J���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ������A�Ȃ�����́A�����̔��̍k�삪��쑺�̐l�X�Ɠ����悤�ɘJ���ł���A���������Ă܂������̒ނ肪�J�����ƌ��������̂��낤���B�ނ̒ނ�́A�Ȃ��A�����̎�A�V�тƂ��Ă̒ނ�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B�Ȃ��ނ̐����͓s�s�I�C���e���̐����ł����Ă͂Ȃ炸�A�R���I�����Ƃ݂Ȃ������̂��낤���B
���ɂ́A�ނ��Ǝ��Ȏv�z�Ɋ�Â��u�D�����v�Ǝv���A�D�܂����ƍl����u���Y�ƘJ�����A�����Ă���v�u�l�Ԃ̑��ݍݍ\���v�����R���I��������юR���I�ނ�ƁA�����̐�������ђނ�ꎋ�������Ƃ�����]�����̂悤�ȑԓx�������N�����Ă���ƍl���邵���A�����̂��悤���Ȃ��悤�Ɏv����B
�u�����ނ���y���ސl�X�̐��͑����Ă��Ă��܂����A�Ȃ��ނ肪����قǑ����̐l�X�𖣂����Ă���̂��Ɩ����A���͒ނ�̌��n�I�ȘJ���Ƃ��Ă̐��i�������܂��B���̍s�ׂ̒��ɉ��ꂽ������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B�Ƃ���ƒނ�̖��͂́A�����ł́A���X�s���Ă��遃�n�����J�����̐��E���Y�ݏo�������̂��Ƃ������Ƃ��ł��邩������܂���v�B�u�����������E�ɖ�����Ă����̂́A---�������̌����̘J���������Ă�����̂��A�ނ��ʂ��ċ[���I�ɑ̌������邩��Ȃ̂�������܂���v�Ɣނ͌����Ă���B�u���J�u���v
�������A���̌��t�́A���ړI�ɔގ��g���w���Č����Ă���̂ł͂Ȃ��B�܂����R�́A�ނ̑�w�������G�b�Z�[�C�X�g�Ƃ����J�����n�����y�����Ȃ��ȂǂƂ͂ǂ��ł������Ă��Ȃ��B���������ꂪ�u����Ƙr����̂ƂȂ����v�u���n�I�J���v�A�E�l��_���̘J������͉����u���������i�̂��̂ł���A��҂ɂ����������̂��͓̂��R�̌����̘J���ɂ͑��݂��Ȃ��i�u�����Ă���v�j���Ƃ͊m���ł��낤�B�ނ͏�쑺�ɂ����鎩���̒ނ��ʂ��āA���n�I�ȘJ�����E���[���I�ɑ̌����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�A�ނ͂����������E�ɖ�����A�����̒ނ�Ɣ��̍k������̐��E�̘J���Ɠ��ꎋ���Ă���̂�������Ȃ��B�����l����ƁA�ނ������̒ނ�͘J�����Ǝ咣���邱�Ƃ������ł���悤�Ɏv����B
�������A�ނ��u�D�ށv�Ƃ����u�J���Љ�v�����������������Ƃ���ǂ����낤���B���R����Ă��Ă���J���{�ʎЉ�ł́A�l�Ԃ̈���͂��ׂāu���n�I�J���v����Ƃ���u�L�`�̘J���v�ɂ���Đ�߂��Ă���A�x�e��x���A���x�߂Ȃǂ̃A�\�r�͑��݂��邪�A�E�J���ł���悤�ȗV�т͑��݂��Ȃ��B���̎Љ�ł́A���W���[�A��̊����A�X�|�[�c�⎩�R�ȕ��w��|�p�����Ȃǂ͑��݂����Ȃ��͂��ł���B�u���n�I�v�J������͉����u���������_�J���Ɍg���A�����Βނ���y���ނ悤�Ȑ����́A���̗��z�Љ�̒��Ɉʒu�Â��邱�Ƃ͓���悤�Ɏv����B
�����A����������ƁA���̎Љ�̓G���[�g�̂��߂ɁA���Ɉ�T�ԂقǍk��J�����s���A���̍��x�߁A�A�\�r�Ƃ��Ă��ł��D���ȗV�т��s�����Ƃ��ł���Ƃ�����������p�ӂ��Ă���̂�������Ȃ��B����Ȃ�A�ނ̒ނ�́A���̎Љ�ł������\�ł��邱�ƂɂȂ�B�����āA���̎Љ�ł́u�J���Ɛ������A���v���Ă���u��{�\���v�������d������A�n����s�����⊯���ƍٓ��X�̋�̓I�Ȗ��͖��������X���ɂ���Ƃ���A�G���[�g�����̂悤�ȓ������s�g���邱�Ƃ́A���ɂȂ�Ȃ��̂�������Ȃ��B
�X�~�X�͔_�ƘJ�����u���炵���v�ƌ����Ă����B��������͂���ꂪ�ނ���u�ʔ����v�Ɗ����邱�ƂƂ͑S���ʂ̂��Ƃł��낤�B�X�~�X�������u���炵���v�Ƃ͔_�ƘJ�����A�E�l�J���⑼�̘J���Ɣ�ׂ��Ƃ��Ɏ��u�o�ϓI���_�v�̂��Ƃł���悤�Ɏv���邩�炾�B�����ėV�т̊y�����͌o�ϓI���v�Ƃ͕ʕ��ł���B
�܂��A�u�r�A����A���_�̈�̐��v�Ƃ����u���n�I�J���v�̍\���ƒނ�̍\�������Ă��邱�Ƃ́A�_�Ƃ�E�l�d�����^����u�y�����v�ƒނ�́u�y�����v�������ł��邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B�V�т́u�\���v�͗V�т́u�y�����v���\�������̗v�f�ł���ɂ��Ă��A����́u�y�����v���̂��̂ł͂Ȃ��B�ނ肪�_�Ƃƍ\�����������Ƃ������Ƃ��ނ�̊y�����̐����ɂȂ�ƌ����̂Ȃ�A�ǂ����ĉƒ�؉����D�ސl�ƒނ���D�ސl������̂������ł��Ȃ����낤�B
���J�u���œ��R�́A�ނ�̐��E�ɖ������̂́A�H��J���̂悤�ȁu�����̘J���������Ă�����́v�A�܂�u���n�I�ȘJ���v���u�ނ��ʂ��ċ[���I�ɑ̌������邩��v���A�Ƃ������Ă���i��o�j�B����ꌻ��l�́A�u���n�I�ȁv�J�����邢�́u�r�Ɠ���Ɛ��_����́v�ł���悤�Ȗ{���I�J�����A�[���I�ɂł���A�̌������������߂ɁA�ނ�����悤�ƍl����̂��Ɣނ͌����Ă���B�{�����ǂ����͌�Ŋm���߂邪�A���R�̌����ʂ肾�Ƃ��Ă݂悤�B
�ނ͓����A�G�b�Z�[�����������w�ŋ������肷��Ȃǂ��Ă���A�u���n�I�v�J������������Ԃɂ������B�����Ĕނ͂���Ƃ��k���ނ���n�߂��B�₪�Ĕނ͔��d�����n�߂��B����͒ނ�Ƃ͂������āu���n�I�v�J���̋^���̌��ł͂Ȃ��A�{���̔_�ƘJ���̑̌��ł���B�s��̉ƒ�؉��ł̋^���̌��Ƃ͈Ⴂ�A�ނ͎R�Ԓn�̎Ζʂ��k���A�E�O�C�X�̖������A���邢�͑��Ԃ⒱�⒎�Ɍ��Ƃ�A�܂��ʂ肪����̑��l�Ƙb������Ȃǂ����B�ނ͗V�тł͂Ȃ��A�u�A�\�r�v�ł��鍜�x�߁A�d���̍��Ԃ̋x���A�u�ӂƎ���x�߂Ȃ���A�V�������Ƃ��l���Ă���Ƃ��A���邢�͋A��r���œ��[�̑��Ԃɖڂ��~�߂Ă���Ƃ��v�̂悤�ȁA�u���R�őn���I�Ŋy�����v���Ԃ������͂��ł���B
�������āA�{���̎R�Ԓn�̔_�Ɓ����n�I�J������邱�Ƃ��ł����Ƃ������ƂŁA�\���ɔ�s�s�^�̐������y���ނ��Ƃ��ł�������ɂ́A�ނ͂����A���n�I�J���̋[���I�̌��ɉ߂��Ȃ��ނ�A���邢�́A�u�]�Ɂv��O��ɂ����u�s��̐l�Ԃ̂��k���ނ�v�ɍ��������A�u�R���̒ނ�v�𑱂���K�v�͂Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�ނ͏�쑺�ł����łȂ��A�Ԃ�����č����̂��������Ōk���ނ�����A�O���ɍs���Ă܂Œނ����������A����͂����Ȃ��ނ̊����������̂��낤���B�I�c����́u�A�\�r�v�ƔF�߂邾�낤���B�I�c������A�A�\�r�Ƃ͕ʂɕ��ʂ̗V�т�����Ă����̂��낤���B
�V�т͗V�тŁA���Â��聁�_�ƘJ���̊y�����Ƃ͈قȂ�y����������ƍl������B�V�т�X�|�[�c�́A���Ƃ��Ă̋x���Ƃ͈���Ċ����ł���B�A�\�r�ł͖����̎d���̂��Ƃ��l���đn���I�ł낤�Ƃ���悤�����A�V�т�X�|�[�c�ł͉����l���������ɂȂ��Ċ������Ă��Ă��\��Ȃ��̂ł���B�J�C�����������Ă����悤�ɗV�т͏����ȏ���ł���A���Y�I�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������Ȃ����A���Y�I�ł��邱�Ƃ͗V�т́i�s���́j�v�f�ł͂Ȃ��̂ł���B
���R�̒��ōs����ނ�̊y�����͂ق��̃X�|�[�c�Ƃ�����Ă��邪�A���n�I�J���������Ă���u�r�Ɠ���Ɛ��_�̈�̐��v�Ƃ������ۓI�\���ɂ���Ă͑S�������ł��Ȃ��B
�ނ�ɂ����āA�����̊댯��`���čs������Ƃ����v�f�A���邢�͑�^����ނ낤�Ƃ���i���̗v�f�A�܂��t�Ɏ��R�̒��ŗI�R�Ɖ߂�����Ƃ����v�f�ɉ���������l������B�i���S�҂����łȂ��j�ނ肠���������D�̏�Ŕ�ђ��˂�̂���������肷�邱�Ƃ����Ɋy�����Ɗ�����l������B���l�̍����y�V���́A������ɍ��킹�āA�����|���Ċ�Ƃ��ɁA�u�����[�r�̊��o�v�Ƃ��u�@�x���v��������ƌ��������A�قƂ�ǂ̒ނ�l���A�����|���������ƁA�Ƃ���r�ɓ`����Ă��鋛�̈����ɁA��������������̂ł���B���̓}�L�R�{�V�ނ�ł������ȓ����������č��킹�̃^�C�~���O���v���Ă���Ƃ��̏W���ɒނ�̍ő�̉��������邪�A������܂��u�r�Ɠ���Ɛ��_�̈�̐��v�ȂǂƂ������ۓI�\���Ƃ͑S���قȂ���̂��Ǝv���B
���R�ɂ��A��쑺�̐l�X�͂��������A���̎d�����I���Ă���߂��̐�ɂ���āA������ƊƂ��o���u�A�\�r�v�̒ނ肪�y�����A���Ɏ����y���K�v�Ƃ��Ă��Ȃ����̂悤�ł���B��쑺�̐l����łȂ��A���́u�_�ƗщƂ̌I�c����v�̂悤�ɁA�d�������ׂĂő��̂��Ƃɂ͈�؋������Ȃ��A�x���ɂ͂̂�т�ƍ��x�݂����邾�����Ƃ����l�����܂ɂ͂��邾�낤�B�O�͑�l�߂Ń`�N�Z���g�~�n�C�����Ă���悤�ɁA�d�����ł̊O�Ȉ�̂悤�Ȑl�����邾�낤�B
�������A�u�A�\�r�̒ނ�v���s���l�ɔ�ׂ�Έ��|�I�ɑ����̐l���u�V�т̒ނ�v���s���Ă��邱�Ƃ������ł���B�����āA�ٗp����ē����J���ҁA�T�����[�}�������łȂ��A�_�Ƃ⏤�X����҂Ȃǎ��c�Ǝ҂̈��|�I�������A�x���ɁA�E�J���^�E�d���Ƃ��Ă̗V�т��s���Ă���B�_���̗V�т͗V�тł͂Ȃ��A�\�r�ł���Ƃ��A�ނ�͘J�����Ƃ������R�̐��ɔ[���ł���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��ł��낤�B
���R�ɂ����Ă̎Љ�ł́A�����ƘJ���͋�ʂ���Ă��Ȃ������B�������Ԃ̂قƂ�ǂ��ׂĂ͐��Y�̂��߂��Đ��Y�i���X�̐����j�̂��߂̘J���Ő�߂��Ă����B�����ł͒E�J���̗V�т̎��Ԃ͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ������B�ނ肪�s��ꂽ��������Ȃ����A�ނ�������ȗV�сA�E�J���̗V�тł͂Ȃ��A�J���Ƃ��čs���Ă����A�Ɠ��R�͌����B�܂��A���Ă̎Љ�ł͗V�т�W���[�̊T�O�����݂��Ȃ������Ɠ��R�͌����B
�T�O�Ƃ͂悭�m���Ă��鎖���������\�����t�̂��Ƃł��낤�B�������[���b�p�Љ�ɂ����ċ���̒�߂��x����j���͑��݂������A����I�ȃ��W���[�E�]�ɂ̎��ԂƂ͍l�����Ă��炸�A�����͂T���Ȃ����͂U���̘J���̂��Ƃł���Ă���x���i���R�̌����u�A�\�r�v�j�̓��ł���A����ɂ����m���̐��������߂̓��Ɨ�������Ă����B
�V�Ԏ҂͎q�ǂ����܂߂ĂقƂ�ǂ��Ȃ������B�����ɂ͎q�ǂ��͓��ʈ�������邱�Ƃ͂Ȃ��A�ނ�́u�����ȑ�l�v�ɉ߂��Ȃ������B�A�����E�R���o���́A�P�W���I���ɂȂ��Ă��A�_���̎q�ǂ��͂����c���Ƃ����炻�̐g�̔\�͂ɉ����ĉƒ{�̐��b�������Ȃ��ȂǑ�l�Ɠ����悤�Ɏd�������Ă������Ƃ���Ă���i�R���o���ҁw���W���[�̒a���x��V�́j�B�V��ł�����̂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B
�V�Ԃ��̂��قƂ�ǂ��Ȃ��������A�������Ȃ������Ƃ��ɂ́A�V�т̊T�O�A�V�т̂��߂̋x���A���邢�͗]�ɂ̊T�O�����݂��Ȃ��Ă����R�ł���B�������A���Ԃ�A�_�Ɛ��Y�͂����シ��̂ɔ����āA�l�X�͎���Ɏ��Ԃ�������y��V�т��s���悤�ɂȂ�A�x���͋���ɍs���������x�����邾���̓��łȂ��A�V�т��y�̓��ɂȂ�A����͂�����ׂ�ƎЌ��̏�ɕώ����čs�����B�������A�͂��߂���A�J�����D�܂��A�V�т����ƍl����ҁA�_�ƘJ���̖�������E�o�������ƍl����҂������B
�w�������[���b�p�������x�T�D�i�i�쓡�v�ق���A�����Ёj�̂Ȃ��ŁA�I�b�g�[��{���X�g�́u�����A�n��A�d�ŁA�N�v�Ȃljߍ��ȕ��S���������āv���������̔_�����A�R���o���̕���P�W���I���̎����̓y�n�����_���Ɠ��l�A��ʂɁA�����ċx�����邱�ƂȂ��A�����������x���܂œ����Ă������ƁA�u���ɋΕׁv�ł��������Ƃ���Ă���B
�����A�܂��{���X�g�͎��̂悤�ȕ��ꂪ�c���Ă��邱�Ƃ��Љ�Ă���B�����ɂ́A�u��l�v�ł���M���⋳��ɑ���u��d�v�𐳂������ƂƐM���Ă���_�v�w�����u���q�g�Ɣނɔ��R���鑧�q���o�ꂷ��B�_�v�͌����u----���O�����đP���l�ԂɂȂ�邼�B���O�͔���ಕԂ��Ă�������悢�̂���I��������Α吨�̐l�̂��߂ɂȂ�-----�v�����u���̔_�Ƃ̋M���q���鑧�q�a�͂��̋C�ɂȂ�Ȃ��v�B���q�́u���e���y�����Ȃ��āA����Ȃ��Ƃ������̂ł���B�u----���̍����܂�S���͓̂�x�Ƃ��߂B���̂��߂ɁA��₵���Ԃɐςނ̂��肢�������B---�v�v�B�ނ͋M���ɂȂ�̂��Ƃ���ꂽ���������ĉƂ��o�čs���B���q�͌��ǁA�o���Ɏ��s���A�����c�̒��ԓ�������邪�A�Ō�͔����ɂȂ�B
���̕��ꂩ�玟�̂悤�ɍl���邱�Ƃ��o����B�w�����u���q�g�̑��q�͘J������̐�������E���o�悤�Ƃ��ĉƂ��ł��B�ނ��_�ƘJ�����y�����Ƃ͊����Ȃ������Ƃ������ƁA�J�����D�܂Ȃ������Ƃ������Ƃ͊m���ł���B���q�Ɉ���Ȗ��H��p�ӂ����A���̕���̍�҂̓w�����u���q�g�Ɓi���邢�͂܂����R�Ƃ��j�����l���ɗ����Ă����Ƃ������ƁA�܂�A�J���A�Εׂ��P�ł���A�_���̎g���͘J���ɂ���ƍl���Ă������Ƃ��m���ł���B�����āA�܂��A���̔_�v�̂悤�ɐ����Ƃ͎d���^�J���Ɠ������Ƃł���ƍl����l���������A�����ŘJ���͐h���A�ł���Δ��������Ǝv�����l�����݂����Ƃ������Ƃ��m���ł���B
�w�����u���q�g���_�Ƃ𑱂����͔̂_�Ƃɂ̓A�\�r�i�x���j�������āA�y������������ł͂Ȃ��B���[���b�p�ł́A�m�����̎�⋳��ɐł�[�߂邱�Ƃ͐_�ɂ�薽����ꂽ���Ƃł���A�������Ƃ̓L���X�g���k�̂��Ȃ킿�l�Ԃ̋`���ł���A�g���ł���Ɛ����Ă����B�����Ă���ɏ]��Ȃ����Ƃ͔j��A�Ǖ����Ӗ������B���邢�͉i���̒n���ɗ��Ƃ���邱�Ƃł������B�����̔_�������̂قƂ�ǂ͋���̋����ɏ]�����B�_�������͘J�����y������������ł͂Ȃ��A����̋�����M���邱�ƂŐh���J���ɑς����̂ł���B�s�M�S�҂͂P�U���I�̏@�����v�A�@���푈�Əd�Ȃ��ċN�������_�������ɗ����オ�邩�A��l��l���ɔ_�����瓦�S���āA�X�ђn�тɏZ�݁u�����v�ɂȂ邩�A�X�Ō�H��������A�ق��d���ɂ����肵���B
�w�����u���q�g�͂܂��߂ɓ������Ƃ����l���Ȃ��������A���q�͉Əo������O�́A�x��������A���Ԃ�A�l��������Ȃ��ɂ�����炸�A�߂��̐X��ɒނ��|�˂ɂł������ł��낤���A�j���ɂ͊X�ɂł����āA�V�ł��낤�Ǝ��͑z������B
�{���X�g�͓s�s�𒆐S�ɔ��ł�����ɍs���Ă����Ƃ����B�{�E�����O���̑������̗V�т��s���Ă������Ƃ����Ă���B�����āA�_�������́u�����R���ԁ��͍Ղ�̎��ԂɏW�����Ă����v�Ƃ����B�_�������͑哹�|�����A�������݁A�̂��������x���x���ėV�B���Ă̔_���ł́A����Љ�̐����Ƃ������āu�������Ԃ̂قƂ�ǂ��ׂĂ��J���Ő�߂��Ă���A�J�������̂܂ܐ����ł������v�ƌ������Ƃ��ł���ɂ��Ă��A���R�A���ԁA���Ԃɋx�����Ƃ�ꂽ�ł��낤���A�܂�����Ȃ�x���ł͂Ȃ��u�����Ȋ����v�ł���悤�ȁA�ϋɓI�Ȍ�y��V�т��܂܂�Ă������Ƃ��m���ł���B
P.�u�����[�Q����The Fight between Carnival and Lent�Ƒ肳�ꂽ�G��B
�ӓ��Ղ���l�{�߂܂ł̊Ԃ̊X�̓��₩���ƌ�����`���Ă���BWikipedia�ɂ��B

�w�����u���q�g�̑��q���Ƃ��o�����Ƃǂ��ɂ������͂킩��Ȃ����A�_������o�čs�������̂̑����͓s�s�ɗ��ꍞ�B�s�s�͔_���̂悤�Ɂu�����߂��炻���Ɂ����݂����̂ł͂Ȃ��v�B�s�s�Z�������������͔̂_���ł���B���Ƃł��邢�͎�H�Ƃň���グ�悤�ƍl�������A�P�ɁA�_�Ƃ����邢�͓������Ƃ�����ɂȂ����������A�u��l�v�ł���M����m���ɔ��R���A���R�����߂Ĕ_�����瓦�S�����̂��A���R�͗l�X���낤���A�s�s�Z���͎��ӂ̔_�����痬�ꍞ��ł����l�X�ɂ���Č`�����ꂽ�B
�����ēs�s���傫���Ȃ�A�s���K�����͂����������Ƃ��A�������x����̈�̗v���ł���B�����̎�̖v���Ɠs�s�̔��W�́A�����̔_�����_�����瓦�S�����o�������Ƃ̖T�ł���A�܂��_�ƘJ�����]�T�E�A�\�r�̑����A�y�������̂ł͂Ȃ��������Ƃ̈�̖T�ł���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
���{�ł͂ǂ��ł��������낤���B���R���A�_�Պ��ɂ͔_�������������ɍs������A���Ղ肪�s��ꂽ�肵�����A����́u���ۂɂ́A�d���̌n�ɑg�ݍ��܂ꂽ�A�\�r�̎��ԁv�܂荜�x�߂�x���������A�Əq�ׂĂ��邱�Ƃ͂��łɂӂꂽ�B�Ȃ�قǁA�����́u���x�߁v�Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��邾�낤�B�����A�Ղ�͘J���̓���ɑ�������I�ȍs���ł���A�����ĒP�Ȃ鍜�x�߂��邢�͂��̗ނ̂��̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B�_�`�̂Ԃ��荇���Ȃǂł͂����l���ł��ł��낤�B�p���ɂ�����t�b�g�{�[���ł͂����Ύ��l���o���B�u�X�|�[�c�v�͓��퐶���A�J�����قƂ�ǂł�����X�̕�炵����E�o���A��炵�̗J����Y��邽�߂ɍs��ꂽ�B���{�̍Ղ�����Ȃ��ł���B�̂̓��{�̔_�����A���R�̌����A�J���ɓ��݂���u�ԁi�܁j�v�܂�x���A���邢�̓A�\�r�̊y���������ł͖����ł��Ȃ������͂����B
�u���ۂɂ́A�d���̌n�ɑg�ݍ��܂�Ă���v�Ƃ����َ͓̂��ɉ߂��Ȃ��B���R���A�_���̃A�\�r�Ƌ�ʂ��錻��̓s�s�T�����[�}���̏T���̗V�сA���W���[�������A�������A���h�ɁA�u���ۂɂ́v���j������̎d���ɖ𗧂��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�������A�d������̒E�o��ڎw���Ă��邩���肻��͗V�тł���B���Ԃ�A���ʓI�ɁA�V��ł͎d���ɗʁi�͂��j���s�����낤�B������Ƃ����ėV�т͂��̎d���̂��߂ɗV�Ԃ̂ł͂Ȃ��B
�O�͑��߂Ŏ������悤�ɁA�R�O��܂ł͏����ƂƂ�������_�J����҂ł������I���͂܂������̒E�J���̒ނ���s�����B�������ނ͂��̓����́u�d������v�Ŏ��y�̒ނ�́u�q�v�i�]�j�ł���A�����̘J��/�d���ւ́u�n���I�v�@�\�����ׂ��ł��邱�Ƃ�����Ă����B���y�͒P�Ɏ��y�̂��߂ɍs����̂ł͂Ȃ��A�u�E�Ə�̕��C��r����v���߂ɍs����ׂ����Ɛ����Ă����B�����̘I���̒ނ�́A�d���̍��Ԃ̍��x�߂ł���悤�ȁu�A�\�r�v�ł������B��ɂ͂��́u��q�v�̋�ʂ��Ȃ��Ȃ�B���������R�������̂Ƃ͔��ɁA�I���͒��ҏ����͓r���ŕ����������A���߂�ꂽ���Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���w�̐E���������B�ނ͑S�����R�ɖ{��ǂ݁A�a�����w�ɂ��Č������A���M�⎍���������A�ނ�����A�����̌����������B�ނ�����Ȃ��玍���r�B�ނ͂T�X�̎��ɂ́u�������߂ɗV�ԁv�Ƃ����l�����͂�����Ɣے肵�A�u�V�Ԃ��߂ɗV�т����v�Ə������B
�����ɂ����Ă��A���{�ɂ����Ă��A�̂���A�P�Ȃ�x���ƍ��x�߂ł���A�\�r�����łȂ��ϋɓI�ȗV�т�l�X�͋��߂Ă������A���ۂɐl�X�͗V��ł����B���炭�_�Ƃ̐��Y�͂̌���ƂƂ��ɁA�_�������̃A�\�r�̎��Ԃ��������ł��낤�B�����Ă��̂��Ƃ͂܂��V�тɑ���~���ł��낤�B�����Ĕ_�Ƃ̐��Y�͂̊g��͓s�s�̔��B�𑣂����B�������ĎЉ�͎��������I�_�Ƃ��甲���o���A�Y�Ɖ��A���{��`�����i�̂��Ǝv����B
���̌��J�u���ł́A�E�H���g���́w�ދ���S�x�́u�����̒��̎���ꂽ���E�v���������G�b�Z�[���Ƃ����B�����āu�ނ�̃G�b�Z�[�����܂�Ă���w�i�ɂ́��������������l�X���̓o��v������B�u�w�~���O�E�F�[�͂��̑�\�I�Ȉ�l�v�ŁA�u�����Ԃ̑r�������ނɓ����Ȓނ�̐��E��`�����v���A�Ɠ��R�͌����B
���̎���ꂽ���̂Ƃ́A�u�����̌n�v��������Ȃ����u�J���̌n�v�Ȃ̂�������Ȃ��B���邢�́u�l�����̂��́v��������Ȃ����A�u�N�w�I�ɕ\������A���݂̑r���ƌ�����肾�v�Ɠ��R�͌����B�ނ͏d�X�����N�w�I�\�����D���炵���B�u���݁v�Ƃ͂����炭�����̐��Ȃ��Łu���ꂱ���������v�ƌ�����悤�ȁA���̐l�ɂƂ��Ă����Ƃ��d�����Ȃ����̂��w���Ă���̂��낤���A�u���݂�r�������l�Ԃ������A�ނ�̒��ɁA�[���I�ȑ��݂��m������Ƃ��A���z�I�Ȓނ�̐��E�����܂�Ă���v�Ƃ����B
�ŏ��̂ق��Ł��R���̒ނ聄�́u���M�I�ނ�v�ƌ����Ă����B���M�I�Ɛ��z�I�Ƃ͓��R�ł͂��������̂Ȃ̂ł��낤�B����́u�ނ�̐��E��A��Ɛl�Ԃ̊W�̐��E���A���܂ł���炵�̌n�̂Ȃ��ɕ�ݍ��ނ悤�ɂ��Đ������Ă���R���̐l�X�̒ނ�́A�ނ�̐��E�Ɏ��Ȃ̎���������������ړ����悤�ȂǂƂ͍l���܂���v�Ƃ����B���̒f��I�Ȍ��������炷��A�ނ͋[���I�ȎR���̐l�ł͂Ȃ��A�{���̎R���̐l�ł���ƍl���Ă��邱�Ƃ͊m���ŁA�ނ�̒��ɋ[���I�ȑ��݁i���Ȏ��g�j���m�����悤�ȂǂƂ͂��Ă��Ȃ��̂��Ǝv����B
���āA�u���݁v�̂����́A�J���ɂ��Č����A�ނ�̐��E�ɖ������̂́u�����̘J���������Ă�����́v�A�܂�u���n�I�ȘJ���v���u�ނ��ʂ��ċ[���I�ɑ̌������邩��v���Ɠ��R�͌����B����ꌻ��l�́A���n�I�ȘJ�����邢�͖{���̘J�����A�[���I�ɂł���A�̌������������߂ɁA�ނ���������Ǝv���̂��낤���B
�O�����̑��ԁA�h�C�c�̘J���҂͔_������ڏZ���ēs�s�ŘJ���҂ɂȂ����B�ނ�͔_�������̂̒��Ɏ����Ă����ނ�̍����������������A�s�s�ɂ����Ă͂��ẴM���h�̂悤�ȐE�l�̋����͉̂�̂���Ă���A�������Ĕނ�͕����������A�t�@�V�Y���̉����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����B���̏ꍇ�J���҂͎����̍��ł��鋤���̂̑r�������ۂɑ̌������B�����āA�f���}�Y�f�B�G�����y����_������o�Ă��čH��œ������t�����X�̘J���҂́A���ۂɁA�q�ǂ��̂Ƃ��Ɏ�`���Ōo�������_�ƘJ���ɂ����čH��̘J���ɂȂ����́i���Ԃɔ����Ȃ����Ɓj��ނ�̒��ŋ��߂�ƍl���邱�Ƃ����Ȃ����s�\�ł͂Ȃ��B
�������A������{�̎����ԍH��œ����l�X�ɂ́A�r���̌��͂Ȃ��͂��ł���B�ނ�͕ʂ̘J���̌��Ȃ��ɁA�͂��߂���e�[���[�E�t�H�[�h�I�V�X�e���Ǘ��̂��Ƃœ����̂ł���A���̂��Ƃɂ���Ă��Ď����Ă����������������Ƃ͂Ȃ��B���̘J���҂͂��Ă̐E�l�������Ă�����̐��������Ă��Ȃ����A���߂�������Ă��Ȃ��̂ł���A�r���ŒD��ꂽ�̂ł͂Ȃ��B�D��ꂽ�ƌ���̂́A�u���āv�Ɓu���v���ׂ���R�ł���B �x���g�R���x�A�[�ɒ���t���ĒP����Ƃ��s���Ă���J���҂́A�x���g�R���x�A�[�̑��x����������Ɗ�������A�ē̖��߂̎d���ɕs�����������肷�邱�Ƃ͂��邩������Ȃ����A�������A�w���E���߂��čs���J���̂�������̂ɕs���������A�Ⴆ�Ύ���Ǘ������ɂ��u��̓I�v�J���ւ̕ύX�����Ƃ߂悤�Ƃ���悤�Ȃ��Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ł��낤�B
�܂��A����̘J���҂͎����̘J���ɒP�����A�u���_�̒��v�i�G���A�X�j�Ȃǂ������邾�낤���A�o���������Ƃ̂Ȃ��u�r�Ɠ���Ɛ��_����̂́v�u���n�I�v�A�u��̓I�v�J���Ȃ���̂������Ȃ���̂ł��邩��m�炸�A���́u�r�����v�������Ƃ͂Ȃ��A������������ƍl���邱�Ƃ��Ȃ��͂��ł���B
����̘J���҂͎����̌��݂̘J�����y�����Ȃ��Ɗ����A���̘J������߂đ��̐E�ɏA���Ă݂����Ǝv���A���ۂɂ������邱�Ƃ����邾�낤���A���������������߂Ă�������̂ł͂Ȃ��B�����āA���ʂ̓s�s�J���҂͎����̍s�Ȃ��Ă���J�����ʔ����Ȃ��Ɗ���������Ƃ����āA�����ɑ��̎d���Ɉڂ낤�Ƃ͂��Ȃ����낤�B�y�����J�����ȒP�Ɍ�����킯�ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă��邾�낤���A���Ƃ̊댯��`���ĕʂ̐E�Ƃ�T���Ƃ����l�͑����Ȃ����炾�B
�ނ͍��̎d���𑱂��E�J���̗~���������邾�����낤�B�ނ́A�P���Ŗʔ����Ȃ��d���^�J���ƈႤ�A����Ɂu�Η�����v�C���炵�A�y�������ƁA���������ł��邱�Ƃ����߂邾�낤���A�ނ́u�������Ȃɂ��v���Ƃ���ǂ����Ƃ���̂ł͂Ȃ��B�܂�A����̘J���҂͋x����]�ɂɁu���n�I�ȘJ���v���[���I�ɑ̌����悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���������̘J���̒��ɂȂ��y���݂�^���Ă����l�X�ȃX�|�[�c��V�т����Ƃ߂Ă���̂ł���B
������A�Z�p��r�⓹��Ƃ͖��W�ɋ����ł���A�T�b�J�[�̎������ɂȂ��ĉ�������X�|�[�c�t�@���ɂȂ邩�����ꂸ�A���������g���͌�⏫���ɌX�|���邩�����ꂸ�A�܂�������������ނ�����邩������Ȃ��B�����A�ǂ�ȗV�сE�X�|�[�c���y�����Ɗ����邩�A�D���ɂȂ邩�́A���o�����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��B
�����A�@�B�����ꂽ�u�n������J�����y�����Ȃ��Ɗ����Ă���J���҂��A��̓I�ȁA���n�I�J���Ɏ������̂����߂Ă���A�͂��߂��炻�̗~���������߂ɒނ����낤�Ƃ���Ƃ������Ƃ�����Ƃ���Ȃ�A���̂悤�Ȍ��n�I�ŁA��̓I�ȘJ���ɑ���{���I�A���邢�͐����I�ȗ~���������Ă���Ƃ������ƂɂȂ낤�B�Ȃɂ��{�\�Ɏ����~�����ނ�����߂�����̂��Ƃ������ƂɂȂ낤�B
�l�ނ̗��j��ʊς��āu�l�Ԃ͘J�����鑶�݂��v�Ƃ����咣�͂��肤��B����܂ł̗��j�ɂ����āA�J���ɂ�镨����ӂ����Ȃ��ő����������Љ�͒m���Ă��Ȃ��B�l�Ԃ͘J�����邱�Ƃ��Љ�I�Ɋw�сA�p�����A�������ĘJ���͐l�ނ̗��j�ɊђʓI�ɍs���Ă����B�������l�Ԃ́A�H�ׂ邱�Ƃ�Z�b�N�X���邱�Ƃ̂悤�ɁA�J���ɑ��鐶�܂���̗~���������Ă���Ƃ����咣�͂ł��Ȃ��B�Ñ�M���V���̃|���X�s���̂悤�ɓz��̘J���Ɉˋ����Đ��������l�X���������B�܂��A�قƂ�ǂ̎Љ�ŁA�J�������ɁA�Ќ���V�т��y���ޏW�c�܂�K�������݂����B
�܂��A�J���́A����@�B�Ɏ���đ�����܂ł́u���n�I�Łv�A�Ε��ł���J���i�ł���Ȃɂ�������g���A���Ȃ̘r�ŁA�ӎ��������đΏۂł��鎩�R�ɓ���������s�ׂł������B
�J���ߒ��ł̎��ۂ́u�r���̌��v���Ȃ��ɂ�������炸�A����̘J���҂���̓I�ɓ��������A���邢�͌��n�I�J�����������Ƃ����~�������Ƃ���Ȃ�A�l�Ԃ͘J�����邱�Ƃ��Љ�I�Ɋw�ԁi���邢�͋��������j���Ƃɂ���Ăł͂Ȃ��A�e�̂ɐ����I�ɁA�܂�{�\�I�ɁA�J�����������Ƃ����~���������Ă���ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ނ���������Ƃ����~������{�\�Ő���������̕s�K���ɂ��Ă͂��łɏq�ׂ����A�o���������Ƃ̂Ȃ��u���n�I�J���v��~������ƌ����l���́A�ނ����{�\�Ő�������̂Ɗ�{�I�ɂ͂��Ȃ����Ƃł���B�������A�u���n�I�ȘJ���v�ɑ���{�\�������͖{�\�Ɏ������܂���̗~���ȂǂƂ������̂����݂��Ȃ����Ƃ����炩�ł���B�i�{�\�s���͓����Z�p��K�v�Ƃ��Ȃ��B�j
������������A�u���n�I�ȘJ���v��u�{���̘J���v�ɂ��ď����ꂽ�{��ǂ݁A�u���āv�̘J���͎�̓I�Ŋy�����������A�����̘J���͑a�O���ꂽ�J���ł���A�ƍl����l�����邩������Ȃ��B�ނ͂��Ԃ�C���e���ł���B�������ނ��^���ɂ����l�����Ȃ�A�ނ�ɂȂǂ������A���݂̒��グ������v������J���^����ᔻ���A����Ǘ��������邢�͊v���I�T���f�B�J���Y���̉^�����͂��߂邩�A���̏������Ȃ��Ƃ��ɂ́A�����ĉ\�Ȃ�A�_���ɍs���A�_�Ƃ��s��������̂ł͂Ȃ����낤���B�������A������ɂ���A�����̍H��̘J�����ʔ������̂ł͂Ȃ��Ɗ�����ꂽ�Ƃ��Ă��A������Ƃ����āA�J���҂������ЂƂ�Łu���n�I�v�A�u��̓I�v�J�����s�������ƍl���A�x���Ɂu�[���I�ȑ��݂��m������v���߂ɁA�ނ�����悤�ƍl���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B
���R�́A�ނ���y���ސl�̐��������Ă��邪�A����́A�ނ肪�u���n�I�v�J���Ɏ��Ă��邩��ł���A�ނ�l���̑����͍����̕n�����J�����E�̔��f���ƌ����Ă���B�f���}�Y�f�B�G�́A�w�]�ɕ����������āx �̒��ŁA�_������s�s�ɈڏZ���čH��J���҂ƂȂ����҂̑������ނ���D�ƌ����A����͎��Ԃ�Q������Ƃ������ӎ��̏Փ��̕\���A���邢�͢���Ԃ̌����ȊǗ���ɑ���u���Q�v�������Ƃ����l�����q�ׂĂ���B���̉��߂́u����ꂽ���n�I�J���̋[���I�m���v�Ƃ����A�ނ�ɑ�����R�̐����Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ��B
�������A�t�����X�̍H��J���҂��ނ���D���Ƃɂ��Ẵf���}�Y�f�B�G�̐����͕s�\���Ȃ����s���m���Ǝ��ɂ͎v����B�����������ӎ��̏Փ��A���邢�̓��T���`�}�����琶�܂��s���́A���Ƃ��A�A���R�[���ˑ���A���A�q�����ւ̂̂߂肱�݂̂悤�ȁA�l�K�e�B�u�Ŏ����I�Ȑ����s���`�ԂƂȂ��ĕ\��邱�Ƃ����肦���ł��낤�B���邢��1930�N��̃h�C�c�̘J���҂�������悤�Ƀi�`�X�ɓ����ēˌ��s�����s���Ƃ������Ȍ`�Ō����邱�Ƃ����肦���B
�������A�ނ��I�J���҂����́A�Փ��△�ӎ��ɂ���ċ�藧�Ă�ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�J���̑ދ����ɂ̑㏞���A�ӎ��I�ɁA�x���̐ϋɓI�Ȋ����̊y�������Ԃ������Ƃɂ���ē��悤�Ƃ����̂ł���B�ނ�͒ނ�Ƃ������W���[�s����ނ�̗L����̒��ŁA�����Ă݂�A��̓I�ɑI�������̂ł���B�ł͂Ȃ��ނ��I�̂��B����́A�H�Ɠs�s�Ɉڂ��Ă���O�A�ނ炪�Z��ł����_���Ŏq�ǂ��̂���Ɏ��ۂɂ���āA�ނ肪�y�������Ƃ�m���Ă�������ł���B�ނ�́u���n�I�J���v���s�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�q�ǂ��̂Ƃ��Ɠ����悤�ɁA�ނ�����ėV�сA�y�������Ƃ����̂��B���͂����l����B
�ނ������l�������Ă��邱�Ƃ͊m���ł��邪�A�����ŁA�T�[�t�B����_�C�r���O��o�R��S���t������l���}���ɑ����Ă���ł��낤�B�ނ�l�̐��������Ă���̂́A�S�ʓI�Ƀ��W���[����������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ̔��f�ł��낤�B�T�����[�}���̊Ԃł̓S���t���ނ�l�C���������ƌ����Ă���B
�ނ�͒ފƂ�[�����g���ċ���ߊl����V�тł���B������g���A���n�̂���s�ׂƂ��ĘJ���Ɏ��Ă���B�S���t�̓N���u�Ƃ���������g���čs�Ȃ��X�|�[�c�^�V�тŁA������g���Ƃ����_�Łi���́A������g��Ȃ��A���j����j���O�Ɣ�ׂ�j�ނ�Ɏ��Ă���ƌ����邾�낤�B�ł́A�S���t�����n�I�J���Ɏ��Ă���ނ�Ɏ��Ă���V�тƂ��āA���n�I�J���̋^���̌��Ƃ��Đl�X�̓S���t���s���Ă���̂��낤���B
�����͌����Ȃ����낤�B�ފƂ�[���́A���R�ɓ����������n�Ȃ����͐��Y���邽�߂̓���ł���A���L�Ɠ��l�̘J����i�Ƃ݂邱�Ƃ��ł��邪�A�S���t�̃N���u�͐��Y�Ƃ͊W���Ȃ��J����i�łȂ����Ƃ͖����ł���B�S���t�̂悤�ɉ��炩�̓�����g���čs����X�|�[�c��W���[�����ɂ��āA�������Ƃ�������B������g���Ă��邩��Ƃ����āA���Y�J���ƊW���Ȃ���A���̊������u���n�I�J���v�̋[���̌��Ƃ��čs�Ȃ��Ă���Ƃ͌����Ȃ��B������^���C��Ƃ݂Ȃ��Ȃ����Ƃɂ���A���j��E�H�[�L���O��W���M���O�A���邢�̓}���\���̂悤�ɁA���ʂ̓�����g�킸�A���������āu���n�I�J���̋^���̌��v�Ƃ͑S�������Ȃ��A�X�|�[�c�̐l���������Ă���B
��Q�͂Ō����悤�ɁA�X�|�[�c�̋N���́A�p�������̔_���������N�ɐ��������J�����x�ނ��Ƃ��ł����Փ��ɁA�E�J���̗V�тƂ��čs�����u�t�b�g�{�[���v�ɂ���A�����Ă���͋ߑ�ɂȂ��ē����K�v�̂Ȃ��W�F���g���}�������̏����ȗV�тƂ��Đ��x�����ꂽ�B�X�|�[�c�͘J���ł͂Ȃ��Ƃ���ɓ���������B�l�X�́A�X�|�[�c���J���Ɏ������̂�����s�����Ƃ���̂łȂ��A���ꂪ�J���Ɏ��Ă��炸�A�J���̔ے�ł���A�E�J���̊����ł��邩��s���̂ł���B
���R�́u���_�v���炷��A�J���Ə�����Ƃ����Ă�����J�����x�z�I�ł���s�s�̐l�X�́A�[���I�Ȍ��n�I�J����Nj�����͂��ł���B�Ƃ��낪�����ł͂Ȃ��B�s�s�I�����𑗂��Ă���啔���̐l�i�Ƃ������Ƃ́A���{�l�̑啔���j���u���n�I�J���v�Ƃ͊W�̂Ȃ��A���푽�l�̃X�|�[�c��V�т��y����ł���̂ł���B�X�|�[�c�E�N���u����ɐ��ł���A�l�X�ȐV�����X�|�[�c�����o����Ă���B�����Ēނ���܂��A���܂��܂ȗV�сE�X�|�[�c�̈�Ƃ��āA�E�J���̗]�Ɋ����Ƃ��ċ��߂��Ă���Ƃ������Ƃ͖��炩�ł���B
�]�Ɋ���������Ȃ̂͐l�X���J���̒��ɖ��������������Ȃ�����ł��邪�A�]�ɂ��y���ސl�̒��ɂ́A���R�������Ă���_���̂悤�Ȋy�����J��������Ă���l�����邾�낤�B�_�������łȂ����R�̂悤�ɑ�w�ŋ����A���슈�����s���l�X�̑������A�����̎d�����r�⓹��Ƃ͊W�Ȃ��Ă��u��̓I�v�ɍs�����Ƃ��ł��邩����A�d�����y�����s���Ă���ł��낤�B�i���R�͂Ȃ������̕���̎d���̊y�����ɑS���ӂ�Ȃ��B�j�����������̐l�X���ނ�����邾�낤���A���̃X�|�[�c�����邾�낤�B
�C���e���͂��̎d���ɂ�����u�J�����n���v������A�J���̏[�������߂āA�r�Ɠ����̂́u���n�I�J���v���s�������ƍl���Ēނ������̂��낤���B����Ƃ��A�R�O��܂ł̘I���̂悤�ɁA�����ΏW�����Ďd�����s���i��̓I�ŁA�ʏ�A�d�����������낢���߂Ɂj�d�������������Ƃ��A���R�̒��ł̗V�т����̂��ꂽ�_�o���x�܂��Ă���A���炬��^���Ă���邩��ނ������̂��낤���B�C���e���ɂƂ��āA�ނ�͢�n���ȘJ���v�̂䂦�ɋ��߂�u�[�������J���v�̑�p�i�ł͂Ȃ��A�ł����݂�����d������̎��X�̒E�o�A�܂�V�т��ƍl�����ق����������₷���B
�����ɘJ���̕n�����������J���҂��A�͂��߂���A�����Ƙr�Ɛ��_����̉����Ă���v�J���̋[���I�[�������߂Ēނ�Ɍ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������B���ۂɁA�ǂ�ȗV�т��X�|�[�c������Ă݂ď��߂āA���ꂪ�ʔ������ǂ�����������B
�ނ�����邫�������́A���̃X�|�[�c�ł����l�����A���R�ł���B�F�B�ɁA��y�ɗU���ĊC(�D)�ނ������Ă݂�B�������A�D�ɐ����Ղ��l�͂Q�x�Ƃ����Ȃ���������Ȃ��B���[���̎������ꂳ���āA���邢�̓T�r�L�j�̈��������܂��������A�����ɂȂ邩������Ȃ��B���邢�̓C�\���Ȃǐ����a�����Ƃ����l�����邩������Ȃ��B�����̃n�[�h�������z���ĂƂɂ����A�����H���A�����肪�o�āA�����ނ�Ă͂��߂Ċy�����̂ł���B�����āA���̋����|�������Ƃ��́A�Ƃ�ʂ��Ċ����颓��������ʁv������[�r�̊��o�v�������Ă��̐l�͋C�ɓ����āA�Ȍ�a�ݕt���ɂȂ�̂����A������l�ɂ��B
�����āA�l�͂��܂��܂ɈقȂ闝�R�Œނ���D�܂��A���̗V�сE�X�|�[�c���D�ށB�S���t���D���ɂȂ邩���m�ꂸ�A���n���D���ɂȂ邩������Ȃ��B�T�b�J�[��싅�̃t�@���ɂȂ��ĉ����A�T�|�[�g���y���ސl������B
���R�́u�R���̒ނ�v�Ƃ́u�R���ɕ�炷�҂������A�R���̎Љ�A���R���܂߂��Љ�Ƃ̊W�̂Ȃ��ŁA��ɊƂ�L���A����Ȓނ�ł��B�����ɂ͓��ʂȈӖ��͂���܂���v�ƌ����B���J�u���̖����ł́u�Ӗ��t�^�v�����Ȃ���s���ނ�́u�������ނ�v���ƌ����Ă���B
��쑺�̑��l�͂��܂��܂ȘJ�����s���Ȃ���A�u���R�̐��E�ƌ�ʂ��A---���l���m�̌�ʂ����o���āv����B�u�ނ���܂��ƂƎ������p�������R�Ƃ̌�ʂł���A�ނ�ɂ����ނ����l���m�̌�ʂ̏�Łv������B�����āu���̂��ƂɋC�������Ƃ��A�킽���́A�悤�₭�ނ�͎��R�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�܂莩�R�ɐ�̎��R�₻���ɕ�炷�������ƌ�ʂ���悢�̂ł��v�Ɠ��R�͌����B
�ނ́A��쑺�Œނ���n�߂�����̍��A�ނ邱�Ƃɑ��鎩�Ȍ������������B�s�s�͂���זE�̂悤�Ɏ��ȑ��B���Ă������A���̎�i�Ƃ��ĎR���𗘗p���Ă����B�����ނ͍l���Ă����B�����̓s�s�̐l�Ԃł��鎩�����ĂюR������i�Ƃ��Ĥ�V�я�(�ނ��)�Ƃ��ė��p���Ă���B�����̓s�s���̓_�����݂ɂ���ĎR���̎��R�����E�J��������D�������A�ނ������Ɠ����悤�ȗ��D�s�ׂł���B
�����A���̂悤�Ɏ��Ȍ����������Ȃ���ނ�𑱂��邱�Ƃ̎��Ȗ����́A���炭��쑺�ɒʂ��Â��A�����̐����Ɏ��������𑗂邱�Ƃɂ���āA�������ꂽ���̂悤�Ɍ�����B
�u�R���̐����v�ɂ����Ă͘J���Ɛ����͘A���������̂ŁA�܂����̘J���������͎��R���l�ԉ�����l�Ԃ����R�������A���ݓI�ȉߒ��ł���A�ǂ��炩��������D������j���肷��W�ł͂Ȃ��B�܂����l�̒ނ�͐������J���̍��Ԃɍs������́A���̈ꕔ�ł���A�u�L�`�̘J���v�ł���A�u�A�\�r�v�ł��邱�Ƃ���R�͔��������B�ނ͎R���̒ނ�͌����Ď��R�̗��D�ł͂Ȃ��A���R�Ƃ̌�ʂł���A�����ł��邱�ƂɁu�C�������v�B
�܂��͔ނ͏�쑺�ɒʂ��A�����̐l�X�ƌ�ʂ��A�����悤�ɎR�d�����ǎd��������āA�����Ɠ��������𑗂��Ă����B�ނ̐����͑��l�̐����Ɏ������́A�߂����̂ł���A�قƂ�Ǔ����ł���B�����ŁA�ނ̒ނ�����l�̒ނ�Ɠ��l�ɁA���R�Ƃ̌�ʂł����āA�����Ď��R�𗪒D����s�ׂł͂Ȃ��B������ނ�͎��R�ɍs�Ȃ��Ă悢�̂��B
�����A�k�{�����܂߁l�s��̐l�X�́A�J���ƗV�т���ʂ��Η��I�ɂƂ炦�Ă���B�����Ēނ���J���ł͂Ȃ��V�тƂ݂Ȃ��Ă���B�ނ�͒ނ�͗V�тł���A�J������̒E�o���ƈӖ����^���Ă���B�����R���̒ނ�ł́A����ȈӖ����^�͂���Ȃ��B��쑺�̐l�X�̒ނ�́A�J���������̍��ԂɁA�������̐������J���̊����̈�Ƃ��āA���R�ɍs���銈���ł���B�Ӗ����^���Ȃ���s����ނ�͋������ނ�ł���B
���R�́u���̋��߂Ă�����̂́A�Ӗ��t�^���Ȃ���ނ������Ƃ����������ނ�����Ȃ��Ă��悢�l�Ԃ̑��݂����肾�����Ɓv�ɂ���A�ƌ����Ă���B�ނ̖]�ށA�J���{�ʂ̗��z�Љ�A�������Љ�ɂ����ẮA���ׂĂ̐l���Ӗ����^����K�v�Ȃ��ɁA���R�ɒނ���y���ނ��낤�B
�ꌩ�A�������R���̔_���Ƃ݂Ȃ����R�͏����̂悤�Ȏ��Ȍ����ɂ����邱�ƂȂ��ɁA�܂��v�z�ƍs���̊Ԃ̖����������邱�ƂȂ��ɁA�ނ���s�Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����悤�ɂ�������B
�����A�R���̒ނ�͎��R�Ƃ̌�ʂł���A�����ł���A�u�L�`�̘J���v�ł���Ƃ���ނ̐����́A�ގ��g���ނ���s���Ă��邱�Ƃɂ��Ăٖ̕��ł��邾���łȂ��A�ނ�ɑ���u�Ӗ����^�v�ł�����B�܂��ނ́A�ނ�͈�ʂɁA�u�ƂƎ������p�������R�Ƃ̌�ʁv�ł���A�E�l��_���̘J���̂悤�ȁu����Ƙr�Ɛ��_����̉������v�u���n�I�J���v�Ɏ��������ł���Ƃ��������������Ȃ��Ă���B�ނ̓Q�[����X�|�[�c�Ȃǁi�V�сj�ƈقȂ�A�A�\�r�Ƃ��Ă̒ނ�̊����Ɂu�Ӗ����^�v���s���Ă���̂ł���B���̂悤�ɓ��R�͈Ӗ��t�^���s���Ȃ���A�ނ�����Ă���B�����A����͔ނ́u�Ӗ��t�^���Ȃ���s�Ȃ��ނ�͋������v�Ƃ����l���ɂ�����Ȃ��B����������悤�Ɋ�������B
�������A���炭�ނ́A�������������Ă��Ȃ��Ɠ�����ł��낤�B�w�R���̒ނ肩��x�́u�O�̃e�[�}�v���Љ���Ƃ���łӂꂽ�悤�ɁA�ނ͏����Ɏ��Ȍ����������Ȃ���ނ�����Ă���ۂɂ��A���̍s���ɖ���������Ƃ͊����Ă��Ȃ���������A�ނ�𑱂����̂ł��낤�B���̌��Ŏ��͑����̔�������߂Ď��̂悤�ɐ��������B�u�ނ͌k���ނ�������l�̓s�s���̖������鎩�Ȃɂ��Ă̈ӎ����܂߁A������{�Љ�̌������ώ@���L�q����Ƃ������ƂɎ��Ȃ̎�̐��������������Ƃɂ����悤�ł���v�ƁB
���������ڂ��������A����J���҂�����E�����ƘJ���Ƃ̕������Ƃ͍l�����A�u���R�v�̂��Ƃ��R���̎��������D���u�V�т̌k���ށv����s���Ă���̂ɑ��āA���R�́A���Ȃ��ނɂ��āA���Ȍ����������Ȃ���ނ������l�Ԃ����݂���Ƃ�����������邱�Ƃ́A�����Љ�ɖ��������݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����̕��@�ł���A����ׂ��J���{�ʂ̎Љ�̎����Ɍ����Ă̑������ƍl����̂ł���B���̂悤�ɍl����A���Ȍ����������ނ�𑱂���Ƃ����ނ̍s���́A�ӂ��͖������ƌ��Ȃ���邪�A�����ł͂Ȃ��A�����̎Љ��ڎw�������I�Ȏ���ɗ��s���Ȃ̂��Ǝ咣���邱�Ƃ��ꉞ�\�ł���悤�Ɏv����B
�����āA��ɂȂ�ƁA�ނ́A�ނ�͗V�тł͂Ȃ��J�����Ƃ����Ӗ��t�^�����Ȃ���ނ�����邱�ƂɂȂ邪�A��͂肻����������ƌ����B�����āA���̂悤�ȋ������ނ���s���l�Ԃ����݂��邱�Ƃ��A��͂�A�����Љ�̖������������ƂɂȂ�Ǝv����B���ꂪ�ނ�����A���̈Ӗ����^�������Ȃ��A���������ĂނȂ����ނ���s���Ă���̂́A�����Љ�̖�����\�I���A���������z�Љ�̑��݂��������Ƃ��ړI�Ȃ̂ł���B�����l����A�ނ́i�n�߂�����̍��ɂ͎��Ȍ����������A��ɂ͋������Ɗ����s�Ȃ��Ă���j�ނ�ƁA�ނ���ނɂ������슈���Ɓu�J���{�ʁv�́u���z�Љ�v�����߂邱�Ƃ̎O�́A����̂������̂ɂȂ�B
�������A�����̐l�́A���R�̂悤�ɁA���Ȗ��������ނ�i�l�j�̑��݂������Ă����Ȃ��Ă��A���㎑�{��`�Љ�A�l�ԘJ���Ǝ��R������Q��A����j�Đl�ނ̑������̂��̂Ɋ�@�������炵�Ă��邱�ƂȂǁA�͂邩�ɋ���Ő[���Ȗ�������_��������Љ�ł��邱�Ƃ�m���Ă���B�܂��A������łȂ��A�����炭�قƂ�ǂ̐l�̓��[�g�s�A�̎����̂��߂ɒނ�����悤�A�ނ肪���[�g�s�A�̎����ɖ𗧂ȂǂƂ͍l���Ȃ����낤�B�J���^�d�����Ώd����A�����ԘJ������������s���R�Ȍ��݂̎Љ�ɂ����āA�y�����Ɗ������邩��ނ���������ƍl����̂��낤�B
�����܂ߕ��ʂ̒ނ�l�́u�Ӗ��t�^���Ȃ���v�ނ�����Ă͂��Ȃ��B�����y��������ނ�����Ă���̂ł���B�u�ނ�͗V�т��v�͓��ʂȈӖ��t�^�ł͂Ȃ��B�J���^�d�����y�����Ɗ����Ă���l������ł��낤�B�������A�����܂ޑ��������̐l���J���^�d�����y�����Ƃ͊������A�d��������Ƃ��ɂ͐����ɍs���ɂ���A������Ƃ����ē����Ȃ��Ă��ςނȂ�ΐi��œ��������Ƃ͎v��Ȃ��B�ł���ΘJ���^�d���������A���R�ɗV�т����Ǝv���B���̂悤�ɁA�d�������炵�A�V�т����ƍl���A�V�тƂ��Ēނ���s���Ƃ������ƂɁA�v�z��N�w�ɂ��Ӗ��t�^�͑S���K�v���Ȃ��B
���́A�J���^�d���̎��Ԃ��������A���R�Ȏ��Ԃ����Ȃ����ƁA�����Ă��̏��Ȃ����R���Ԃ̂��ׂĂ�V�тɏ[�Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�l�͌���ꂽ���R���Ԃ̒��ŁA�Ǝ��玙�Ȃǂ̎d����A�{�����e�B�A���̑��̎Љ�����s���ׂ����Ɗ�����B�����͗V�тƂ͈قȂ�A�y�����̂䂦�ɍs���銈���ł͂Ȃ��A�s�����߂ɂ͍��ȁA�w�͂̕K�v���������銈���ł���B���������Ă����̊����ɂ͉��炩�́u�Ӗ��t�^�v�A�u���R�t���v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�V�Ԃ��߂ɂ́u�Ӗ��v��u���R�v�͂���Ȃ��B�y��������V�Ԃ̂ł���A�D��������ނ������̂ł���B
��ŁA�I�����͂��߁A�ނ�Ƃ����V�т͒P�Ȃ�u�V�Y��y�v�ł͂Ȃ��A�u�E�Ə�̕��C��r����v�܂�A�d���̃X�g���X���������A�{�Ƃɑł����ނ��Ƃɖ𗧂ׂ����ƍl���Ă������Ƃɂ��Ăӂꂽ�B�I���͌R����`�҂ł͂Ȃ��������A�B�Y���Ƃ̃X���[�K���̂��ƁA�ΕׁE�ΘJ���d�����ꂽ��������Ɉ�����l�ł���A�R�O��܂ł͒ނ�Ɉ��̈Ӗ��t�^���s���A�ނ�������̂ł���B21���I�̌���ɂ������Ă���ΘJ���_�A���邢�͋Ε֗~�̗ϗ��Ɋ�Â��A�l�Ԃ͖{���Ȃ�A�V���ɁA���ׂĂ������ĐE�ƘJ���ɂ������ނׂ��Ȃ̂ł���B
�ނ薼�l�̈�l�ŁA�s��̗��N�E���a21�N��l�Ђ�ݗ��A�G���u��l�v��n�����������C�ɂ��A�푈���A�ނ�́u�S�g�̗����ł���Ƃ��A�̈ʂ̌���ł���Ƃ��A���S��y�ł���Ƃ��A���낢��̗�����t���v���A�u�V�тł͂Ȃ��v�Ƃ��ꂽ�B�푈���́A�����͏e��ɂ����Ă��A���̂��߂Ɉ�g����������o��ŁA�d���ɂ������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ���ꂽ�ł��낤�B�P�ɗV��ł��Ă͂Ȃ�Ȃ��A����A��펞�ł��邪�䂦�ɁA�ꎞ���V��ł��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ނ������ɂ��Ă��A�������̂��߂ɖ𗧂��˂Ȃ�ʁA���̂悤�Ɍ���ꂽ�ł��낤�B
�ނ�ɈӖ��t�^�����A�����t�������悤�Ƃ���̂́A�ނ��V�т������̊y���������ł��邱�Ƃ�ے肵�A�Љ�⍑�ƂɗL�Ӗ��Ȋ����ł���i�ׂ����j�ƌ������Ƃ��邩��ł���B���R�́u�ނ�͘J�����v�Ƃ����咣�����̂悤�Ȋ�{�I�l��������o�Ă���Ǝv����B�������A���a���ɂ́A�ʏ�V�тƍl�����Ă���ނ��X�|�[�c�͋x���Ȃǂ́u���R���ԁv�ɂ����s�����Ƃ͂ł��Ȃ����A����ł����̌���ꂽ���Ԃ̒��ł́A���ꂪ�u�N�w�ҁv�ɂ��A���邢�͎Љ�ɂ��A�ǂ̂悤�Ȉʒu�A�Ӗ���^�����邩�ɂ͊ւ�肪�Ȃ��A�D���Ȑl�͎��R�ɍs�����Ƃ��ł���B
�ނ��]�ɂɂ��Ę_���Ă���̂́w���R�_�x�ɂ����Ăł���B���̖{�ł́A�u���Ă����N����Ă����v�ߑ�I���R�ɑ���Č����A�u���R�����������v���Ƃ��ڎw����Ă���B�ނ͍Ō�̏͂Ŏ��̂悤�Ɍ����B�u�ߑ�Љ�́A�J������̂��肩���Ƃ͊W�Ȃ��A�Ƃ���---�s���Ƃ��ẮA�Ƃ���----�����Ƃ��Ă̋��ʂ̌l��ݒ肵�A���R�����ʂ̌l�̌����ɂ������̂ł���B�������āA���R�͌l�̂��̂ɂȂ����v�B�����Ă��̂��Ƃ��A���Ŏ��R����ɓ���悤�Ƃ���u�G�S�C�X�e�B�b�N�ȁv���l����Ȃ�ޔp�����A���̓��{�Љ�ݏo�����̂��Ɠ��R�͌����B
�ނ��A�����ł��̌�����{�Љ�ɑΒu����̂́A����܂ŏЉ���ނ̒ނ�_�ŏq�ׂĂ����u�J���{�ʁv�̎Љ�Ƃ��Ȃ����̂ł��邪�A�O�̂��߂ɁA���p���Ă����B�u���ĕ��ʂ̐l�Ԃ����ɂƂ��ẮA�J���ƂƂ��ɍ���Ă���W���������d�v�ł������B���Ƃ��A�_���ɂ́A�_�̉c�݂ƂƂ��ɐ��܂��W�̐��E������B����͔_�ƘJ�����Y�ݏo�����R�Ɛl�Ԃ̊W�̐��E�ł�����A�Ƒ���P�ʂƂ��āA�c�܂�A�p����Ă����A�Ƒ��I�ȉc�_�̊W�̐��E�ł�����A�_���̘J���ƂƂ��ɂ��鑺���Љ���o���A�W�̐��E�ł��������v�B�ނ́u���Ƃ����v�ł́u�l�̎��R������ɂ��ĎЉ���␢�E�������\�z���悤�Ƃ��鐢�E�ς���A���҂Ƃ̊W�̒��Ɏ��R�⎄�����̎Љ�n������Ă����A����Ȑ��E�ςւ̓]�����͂��肽�������v�̂��ƌ����Ă���B
���̂悤�Ȋ�ŏ�����Ă���w���R�_�x�̂Ȃ��Ŕނ̗]�ɘ_���q�ׂ��Ă���B
���R�͗]�ɂƂ́u����ӂ�v�Łu�s�v�c�ȊT�O���v�Ƃ����B�u�����ŕ\������Ɓu�]�����ɂȎ��ԁv�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���A����͒P�ɘJ�����ԈȊO�̎��ԂƂ������ƂȂ̂��A�������Ԃ��܂ނ̂��B��Ћ߂̍��ԂɁA�_�Ƃ�������G��`�����肵�āA��������������Ă���l�ɂƂ��ẮA�_�Ƃ�G��`�����Ƃ͗]�ɂ̉߂������Ȃ̂ł��낤���A������܂��J���Ȃ̂ł��낤���v�ȂǂƖ₤�B���́u����ӂ₳�v�́A�u�����Љ�I�ɋc�_����Ă���]�ɂƂ́A�S������Ă��Ȃ����Ԃ������Ă���B�Ƃ��낪�����S���Ɗ����邩�͈�l��l����Ă��āA�������Ĉ�ʂ�ł͂Ȃ��v���Ƃ��炭��̂��A�Ƃ������B
�܂��A���R�����ɂ���A�]�ɂ������������Ԃ��܂ނ��ǂ����Ƃ����_�ɂ��āA���łɁA���R���Ԃɍs�Ȃ��Ă��鏔���������ቻ�̒��x�ɏ]���ăX�y�N�g����ɔz��Ƃ����A�G���A�X�̕��́i��R�́A��R�߁j�̂Ȃ��ł����炩�ɂȂ��Ă������Ƃ����A�ēx�A���Ȃ�̍l�����q�ׂĂĂ݂悤�B
������{�̘J���҂̏ꍇ�A�ӂ��A�J�����Ԃ��I���������Ƃ����āA�e���������̎v���ǂ���ɂł��鎩�R�Ȏ��Ԃ�����킯�ł͂Ȃ��B�E��ɍS������Ă��Ȃ������ŁA�܂��Ǝ���玙�Ȃǂ��܂߂������ɕK�v�Ȉ�̊����Ɛ�����x�������̎c��̎��Ԃɍs����̂ł���B�ށ^�ޏ��͎��͂̎Љ�I���́A�펯�A�u����v���l�����A�ȁ^�v����юq�ǂ������ɑ��鈤��ƁA�������g�̐l���ς�ϗ��Ȃǂɂ��������āA�܂�A������x���R�ɁA�������`���ӎ��ɂ����������āA�Ǝ���玙�̘J�����s���B
�����Ă���炪�I��������ƂɁA�`���Ƃ͊����Ȃ��A�����̂��������Ƃ����鎩�R�Ȏ��Ԃ��c��B��������邱�Ƃ��D�����Ƃ����l�����낤���A�������A�����̍D�݂̂��̂���ł͂Ȃ��A���̉Ƒ��̍D�݁A�����Ďq�ǂ�������ꍇ�ɂ͉h�{�Ȃǂ��l�����A�����A���K�v������A�y�����Ƃ���͌����Ȃ��B�q��Ă��A�Ԃ�V�̃E���`��I�V�b�R�̐��b���܂߁A���܂ꂽ�Ƃ������łȂ��A�u�傽��Ǝ��E�玙�̒S����v�Ƃ��Đ��b�������o���̂���l�́A�N�ł��A���ꂪ��ςȎd���ł���Ƃ������Ƃ�F�߂邾�낤�Ǝv���B
�����A�ށ^�ޏ��͂���������A�����̗L���鎞�Ԃ�����ɓ��Ă邱�Ƃ������Ō��߂�̂ł���A���f������A��������A���܂������肹���A���邢�͂܂��A�N�����̐l�ɉ����t�����肹���A�䖝���āA���Ȃ̕����ׂ��ӔC���ʂ��̂ł���B�ށ^�ޏ��́A���Ȃ̒u���ꂽ�̒��ŁA��̓I�ɁA�\���ɐl�Ԃ炵���s������̂ł���A�L�Ӗ��Ȑ����Ă���̂ł���B�`�����ʂ��������邱�Ǝ��̂��ϗ��I�ɗ��h�Ȑ������ł��邩�炻�����ׂ����ƌ����̂ł͂Ȃ��B���̘J���^�d���͕K�������y�����A�[��������������̂ł͂Ȃ����A������������i�����ɐ��_�I�ȁj��ɂ�ւ邱�ƂɂȂ�A�����K�v�����ʂ������ƂŐS�̈��炬�������A���_�I�ȐÓI�����邩�炻�����I������̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł���B�����ĕK�v�ȁA��ނȂ����܂��܂ȁu�S���v�I�Ɗ�������J���^�d��������A������s�Ȃ����c��̎��ԂɊy�����������ł��邾�������s�Ȃ����ƍl����B
�u�����S���Ɗ����邩�v�͐l�ɂ���ĈقȂ邪�A�d���͍S����������������̂ł���A�S���������Ȃ����R���ԁA�����ė]�ɂ��K�v�ł���Ƃ������Ƃɂ��ėL�Ӗ��Ɍ�肤��B
���R�͘J���Ƃ́A���Ȃǂ̋����̂��邢�͂��ẴM���h�̐E�l�g�D�̂悤�ȎЉ�I�W�̒��ŁA���R�ɑ��ē���������s�ׂ��ƌ����Ă���B�܂��L�`�̘J���Ƃ������p���ĉƎ��E�玙�̂悤�Ȃ��ׂĂ̐����������J�����ƌ����Ă���B�w���R�E�J���E�����Љ�̗��_�\�V�����W�_���߂����āx
�Ƃ��낪�ނ͐̂̐E�l�A�R���̔_���A��Ƃ̃T�����[�}���A�A���o�C�g�A�i��w�́j�p�[�g�Ȃǂ̘J���A���邢�́u�ƋƁv�̘J���ȂǁA�E�Ɓi�I�j�J���Ƃ��ꂪ�s����Љ�I�W�ɂ��Ę_���Ă��邪�A�ƒ���ł̘J���ƉƑ��̊W�ɂ��Ă͂قƂ�ǑS���q�ׂĂ��Ȃ��B����͎R���̐����ł͐��Y�����i�J���j�ƍĐ��Y�����i����E�����j�Ƃ��A�����Ă��Đ����ƘJ���͈�̂��Ƃ������A���ōk���R�����n���邱�Ƃ������_�����Ă���A����������藬����Еt�����肷��ƒ���ł̘J���͂ӂ���Ȃ��B�����ł́A���R���u�����ŗ��������̂��D���Ō��\��������ӂ���Ă��܂��v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��u�]�k�v�Ƃ��Č���Ă���ɉ߂��Ȃ��B��쑺�̒ނ�h�̉^�c�ƉƎ��ɂ́u��l�v�̍Ȃ��������Ă���͂������A�v�̎d�����������グ���Ă���B���ǔނ����グ�Ă���̂́u�o�ϓI���l�ށA�����ɂȂ�v�J���A�u���`�̘J���v�����ł���B
�ނ͓����ŁA�ߑ�Љ���V�X�e���ɏ]�������Љ�Ƃ��Ĕᔻ���Ă��邪�A�u�����̃V�X�e�����v�Ƃ��������o�������Ď��̂悤�Ɍ����B�����x�O�́A�j���[�t�@�~���[�ƌĂ��ƒ�ɂ��Ă̒���������B�u�����A���ɓ����ɏo�Ă��Ȃ������͂��Ȃ莩�R�Ȏ��Ԃ������Ƃ��ł��邪�A���̎��Ԃ��������ƊǗ����悤�Ƃ���l�����l�������B���Ƃ��ΉƎ��̎��Ԃ�����Q���ԂƂ��߁A---�q�ǂ��ƗV�Ԏ��Ԃ͈���R�O��---�Ƃ����߁v�A�����Ԃ������̎��ԂƂ��Ďg���B�u���������������g�̎�ɂ���ăV�X�e���ɂ��Ă����B---�ƒ뎩�̂��V�X�e���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B��������Ƃڂ��͈�̉ƒ�Ƃ͂Ȃ낤�Ƃ����C�����Ă���B���̎Љ��Ƃ����Ƃ����낢��Ȍ`�ŃV�X�e��������Ă����Ȃ��ōŌ�Ɏc���ꂽ��V�X�e���I�Љ�̈�Ƃ��ĉƒ����������c���Ă������Ƃ̂ق�������ۂLjӋ`������͂����Ƃ����C���ڂ��ɂ͂���v�B�ʂ̃y�[�W�ł́u���܂ł����܂�V�X�e���ɐN�H����Ă��Ȃ��悤�ȉc�܂�������Ă���ƒ���݂Ă���ƁA���������ƒ�̍ő�̗ǂ��_�́A�l�Ԃ̊W���܂��ߑ�I�ȉ��l�ӎ��Ɏx�z����Ă��Ȃ����Ƃ��Ǝv���v�B
���͔ނ̌����u�ߑ�I�ȉ��l�ӎ��Ɏx�z����Ă��Ȃ��ƒ�v�Ƃ́A�������ł͂Ȃ��A�v�͉�Ђɋ߂Ă��邩���c�Ƃ��c��ł��āA�M�S�Ɂu���ɂȂ�J���^�d���v�����Ă���u��l�v�ł���A�Ȃ́u�Ɠ��v�A�u��e�v�ł���A�Ǝ��玙�����A�]���ɕv�Ɏd���Ă���悤�ȉƒ�̂��ƂȂ̂ł͂Ȃ��낤���Ƒz������B
���Ă̐E�l�͎����̘r�ɂ���邱�Ƃ̂ł���A���������A���R�ȘJ���҂ł������B�ނ̐l���͎d�����̂��̂ł������B���R�͂��̂悤�Ȑ��͎��R�ł���ƍl���Ă���B�������A����ɂ����āA�����悤�ɁA�\�͂�����d�������ׂĂł���悤�Ȑ��������\�Ȑl�͂��������Ă��邾�낤�B�܂��A���̂悤�Ȑ��������\���Ƃ��Ă��A���́A�������ׂ����Ƃ͍l���Ȃ��B
���Ă̐E�l���j�������̂�肽���悤�Ɏd�������A����ȊO�̂��Ƃ͈�u�Ɠ��v�A�܂菗�ɉ����t���Ă���ꂽ�̂ƈႢ�A���݂ł́A�������܂������������̘r��˔\�����A�K���ɂȂ錠����L����̂ł���A�v���u��l�v�̏��g�ł���̂ł��A�j���A�Ŏx���邱�Ƃ����܂���̖����E�g���ł���悤�ȑ��݂Ȃ̂ł��Ȃ��B
�܂��A����Љ�ɂ����ẮA�e������Ƃ����āA�q�ǂ��ɑ��āA����I�ɖ��߂��A�������Ƃ��Ȃ�����ʼn���ȂǂƂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B����Љ�ɂ����ẮA�ꐶ�Ɛg�Œʂ��Ƃ����̂łȂ���A�ʔ�������A�D��������Ƃ����āA�������Ԃ̂قƂ�ǂ��d���^�J�������ɏ[�ĂĐ����邱�Ƃ͕s�\�ł͂Ȃ����낤���B�v�Ƃ��āA���邢�͐e�Ƃ��āA���邢�͔N�V�����e�̑��q�Ƃ��ĉʂ����ׂ����R�̐Ӗ����ʂ������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�\�����傫���B���R�́u�V�����W�_�v��ڎw���Ƃ������A�ނ̌����V�����Ƃ́u�ߑ�I���l�ӎ��ɐN�H����Ă��Ȃ��v�������l�ӎ����ێ����邱�Ƃ̒��ɂ���悤�ł���B
���R�͌����u�J���̂��Ƃł́A���̒����̉̎��Ԃ��K�v�ł��낤�B�������A�d���̍��Ԃ̋x���ł��莩�R�őn���I�Ŋy�����Ƃ��́A�킸���Ȏ��Ԃł����Ă��\���ɂ��̖����������Ƃ����邵�A�d���̒��ł��A�����Ό���Ă�����̂ł���͂��Ȃ̂ł���B�ӂƎ���x�߂Ȃ���A�V�������Ƃ��l���Ă���Ƃ��A���邢�͋A��r���œ��[�̑��Ԃɖڂ��~�߂Ă���Ƃ��A����ȕs�ӂɌ���Ă���Ƃ����܂��A�������ɂƂ��Ă͊y�����������肽�Ƃ��ɂȂ�B�t�ɂǂ�قǒ����]�ɂł����Ă��A���ԂɈ�������Â��Ă���Ȃ�A�����ł��������͎��Ԃ̏d�����������������ł���v�B
��������Ƃ���ł́A������{�̑����̍H��J���҂�T�����[�}���͏T���̂Q�����ǂ̂悤�Ɏ��Ԕz�����悤���l����i���j�B�����Ă��́A����������Ղ�V�сA��������͂������Ƌx�ނ��ƂɎg�����낤�B�Ƃł̂�т�߂��������Ȃ�A���Ԃ��l������s���v��𗧂Ă��肷�邱�Ƃ͕s�K�v���낤���A�O�ɏo�����ėV�Ԉ���ɂ��ẮA���R�Ȃ��玞�Ԃ��܂߂��v�悪�K�v�ł���B���R�̌����ł́u���ԂɈ�������Ă���v�Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���A�����ƗV�т����̂ɁA����̎��Ԃ̒��������܂��Ă���̂����瓖�R�ł���B���邢�͂�ނȂ����Ƃł���B
���́A���ԂɈ������ꂸ�ɁA������肵�����R�Ȃ���Q���Q���Ԃ�����́A����͂̂�т�߂����A��������͂ǂ����ɏo�����A���Ԃɒu���V�ԂƂ����A��ʓI�ȃT�����[�}���̋x���̉߂������ɗ^����B�T�x���R�����邢�͂S���ł���A�����̖��͂��邪�A���Ԃ����܂�C�ɂ����ɁA�������ƗV�Ԃ��Ƃ��ł��邾�낤���A�܂��A�̂�т�Ɖ߂������Ԃ������Ȃ邾�낤�B�x�ɂ͒����قǂ悢�B���́A���������j���ł���悤�ȑސE��̐������ł��邾�������ł���悤�ɁA����̐��������đ����ɑސE�����B�u�ǂ�Ȃɒ����]�ɂł����ԂɈ��������Ȃ�v�Ƃ͖��Ӗ��ȉ���ł���B
�i���j�T�x������́A���{�ɂ����ẮA1988�N�ŁA���ƂłS����A�S�̂ł͂V�����̗̍p���ɂ����Ȃ��A�Ƃ����B�w���j�厖�T�x����V�ŁA�O�ȓ��A2005�B���̌�A���S�T�x�Q��������������1992�N����A�����w�Z��2002�N������{���ꂽ�B
---------------------------------�T��������x�����Ȃ������Ƃ��ɂ́A�V�Ԍv��ȂǗ��Ă悤���Ȃ��A�����e���r�����邩����Q�����ĉ߂��������Ȃ�������������Ȃ��B���̂Ƃ��ɂ͎��Ԃ̂��ƂȂǍl���Ȃ��������낤�B�����I�ɂ����x�����邾���̈��������A�܂����̓��ɂ͏o���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł��낤�B�T�x�Q���ƂP���̏ꍇ�ƂŎ��Ԃ̈����͂ǂ���̂ق��������ƁA���R�͍l����̂��낤���B
�R���o���ɂ��A�t�����X�v����̔_�������̐����ɂ͗]�ɂ͑S���Ȃ��A�ނ�͓��̏o�ƂƂ��ɋN���ē�������܂œ����A���X�x�����Ƃ�A�H�ׁA�����Ė������B�ނ�͍H��J���҂̂悤�ɋ@�B�̃��Y���ɏ]���K�v���Ȃ��A���R�́A�����w�I���Y���ɏ]�����B�����ł��邪�䂦�Ɏ��Ԃɂ��čl����K�v���Ȃ��A���ԂɈ�������邱�Ƃ��Ȃ������B�A�����E�R���o���^�n�Ӌ��q��w���W���[�̒a�����V�Ł��x(�������X�A2010�j
���̂悤�ɗ]�ɂ��Ȃ�������J�����s���A���Ԃɔ����邱�Ƃ��Ȃ������̂ق���I�Ԃ��A�J���Ƃ���ȊO�̎��Ԃ�������Ă��āA�]�ɂ������Ă�����ǂ��g�������l����K�v�̂���A���J������ʓI�ł���悤�Ȍ��㐶����I�Ԃ��B���͂��łɂ��̓�ґ��ꂩ�玩�R�ȔN��ɂȂ��Ă��邪�A���������U��Ԃ�A�T�����[�}���Ƃ��āA���ԂɍS������A���������̂�����ł��������A�������Ƃ����āA���Ԃ̋x�e�͂����Ă��A�]�ɂ�x���̂Ȃ��J�������̐�����I�Ԃ��Ƃ͍l�����Ȃ������B���́A���������J�����s����ꂽ��x�����邾���Ƃ����������́A���R���ԂƗ]�ɂ������āA�J��/�d���ȊO�̍D���Ȋ��������邱�Ƃ̂ł���A����Љ�̂ق����D�ށB
������J�����A�u���Ԃ̈����v���Ȃ��u�����w�I���Y���v�ɂ����]���������A�����A�J�����y�������̂ł���A�]�ɂƗV�т͕K�v�Ȃ��Ɗ�������Ȃ�A�傢�ɖ]�܂����Ǝv���B�������A�`�N�Z���g�~�n�C�̂悤�ɂ��ׂĂ̘J�����y�������̂ɂ���Ƃ����̂͋�z�I�ł��낤�B�����̑����̘J���͊y�����Ȃ��A��莞�Ԃ��܂ē�������Ȃ��B�Ƃ���A�E�J���̎��R���ԂƗ]�ɂ����߂�͓̂��R�ł���A�܂����肳��Ă���]�ɂ��v��I�Ɏg���̂��܂����R�ł��낤�B
��Ћ߂̍��ԂɁA���d����������G��`�����肵�āA��������������邱�Ƃ͗]�Ɋ������Ƃ����₢���A����N�w�I���ł͑S���Ȃ��B���R�́A�J���Ƃ́A�ݕ��Ƃ��Ď�邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�����邽�߂ɍs���i���邢�͂����R�̍l���ɑ����Č����A�u�������v�y�����j�����ł���ƍl���Ă���悤�Ɏv����B���������āA�u�E�J���v�̗]�Ɋ����͎����ƌ��т��͂��͂Ȃ��ƍl���A�]�ɂ̊����Ŏ����������邱�Ƃ�����Ƃ�����������̂ł͂Ȃ����A�Ƌ^����o����̂��낤�B�����A�]�Ɋ����Ƃ���ɂ������̗L���Ƃ͑S���W���Ȃ��B
���̐l���_�Ƃ��s������G��`�����肷�邱�Ƃ��A���Ћߣ�̔�����₤���߂̃A���o�C�g�Ƃ��āA����������Ό��Ɣ_�ƁA���Ɖ�Ƃ̎d���̈ꕔ�Ƃ��čs���Ă���̂ł͂Ȃ��A�D���ŁA�y���݂̂��߂ɍs���Ă���̂ł���A����͗]�Ɋ����ł���A�������瓾����앨���i���A���ׂĎ����ŐH�ׁA�����̉Ƃɏ��邱�Ƃɂ��邩�A�]�������������Ď����邩�A���邢�͂����ʂ肪����̐l�ɂ܂��͒m�荇���ɂ����ŏグ�邩�A����Ƃ��A������i�����Ĕ�������j�����c�̂Ɋ�t���邩�A���X�͂��̊������]�Ɋ����ł��邱�ƂƉ��̊W���Ȃ��
��ނɂ�邪�A�������^���Y���銈�����A����Ƃ����������A����ɐ������������Ă���Ƃ����̂łȂ���A�܂�A�ꍇ�ɂ���Ă�߂邱�Ƃ��ł��鎩�R�Ȋ����ł���Ȃ�A�܂�V�тƂ��čs����Ȃ�A�ƂĂ��y���������ł���B������]�Ɋ����Ƃ��āA�܂�V�тƂ��āA���ō앨�����A���邢�͊G��`���A���邢�͊C�ŋ���ނ�A�����̎Y����Ƃ������Ƃ́A�]�ɂł��邱�ƂƂȂ�疵�����Ȃ��B
���̗F�l�ɗD�G�ȋZ�p�҂ňꗬ��ƂŖ�E�ɂ����ȂǗ��h�ɋ߂Ă������A�w������Ɋo�����}�[�W�������߂��ۂ������A�]�ɂɂ͂����ΐ����ɍs���q���}�[�W���������Ă����l��������B�ނ͏������������ԉ҂����͂����B�������A����͓q���}�[�W�������ʔ����������Ă����̂ł���A��������₤���߂̃A���o�C�g�Ƃ��Ă���Ă����̂ł͂Ȃ��B�ނ����������ł͑��肸�A�A���o�C�g���������Ǝv������A�m�̍u�t��ƒ닳�t�Ȃǂœ��ӂ̐��w��������Ȃǂ��āA�A�\�r�Ȃ���i�܂聃�]�T�Ł��j�����҂����Ƃ��ł����B���̏ꍇ�ɂ̓}�[�W�����ɕ����đ�������댯�͂Ȃ����܂��d���ł��邪�䂦�ɋx�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�V�тƎd���̈Ⴂ�͂͂����肵�Ă���B�ނ̃}�[�W�������]�Ɋ����ł���i�������j���Ƃɂ͋^���]�n���Ȃ��B
����ȒP���Ȃ��Ƃ�N�w�҂̓��R���₢�Ƃ��Ē�o����Ƃ������Ƃ́A���ꂪ�A�����Ɂu�J���̃X�X���v������l���Ă��āA�]�ɂɂ��čl�������Ƃ��Ȃ��������������悢�؋��ł��낤�B
���āA�����ҁA�d���ɏA���Ă���҂̑啔���́A�����ĕS���̖������������Ƃ͂ł��Ȃ��J���ɏA���Ă��āA�ł���ΘJ�������炵�A�]�ɂ𑝂₵�����ƍl���Ă���Ǝ��͎v���B�]�ɂ̂Ȃ��Ɋy���݂����o���l�X�́A��Ƃɂ���āA�J���ɂ���čS������Ă��邱�Ƃɕs���R��������B�]�Ɂ����R�Ȏ��Ԃ��Ȃ���A�y�������ƁA���������Ƃ������Ă��A�����ł��Ȃ��B������A�����̂��������Ƃ����邽�߂̊�{�I�����Ƃ��āA�]�ɁA���R�Ȏ��Ԃ��܂��~����̂ł���B�e�l�͂��̂Ȃ��ŁA�����̂��������Ƃ�����B�d�����������ꂽ���Ɗ����Ă���ЂƂ͗]�ɁA���R�Ȏ��Ԃɂ̂�т肷�邩�A�V�Ԃ��A���X�|�[�c��|�p�ɑł����ނ��A���邢�͎q�ǂ��Ɖ߂������Ԃ𑝂₷���A�Љ�^���ɎQ�����鎞�Ԃ𑝂₷�����邾�낤�B�d�����D���Ȑl�͗]�ɂɂ����Ă��d�������邩������Ȃ��B�]�ɁA���R�Ȏ��Ԃɉ������邩�́A�e�l�̍l�����A���l�ς�l���ρA�D�݂ɂ䂾�˂���B���ꂪ���R�Ȏ��ԂƂ��Ă̗]�ɂł���B
�Ƃ��낪���R�́A�]�ɂ͎��R�Ȏ��Ԃł���A�]�ɂ̊g��͘J���҂̎��R�̊g��ɂȂ�Ƃ����A���̗]�ɊT�O��ے肷��B�J���҂̎��R�Ƃ͎��R�ȘJ�����s�����Ƃł���B�u�ǂ�ȁu�d��������Ƃ��v�A�J���͂�莩�R�Ȃ��̂ɂȂ肤�邩�v�������Ɩ��ł������̂ɁA�u���̍����炩���R�ƌ����Ӗ��̒��ɁA�]�ɂ̊g�傪�����悤�ɂȂ����v�B
�������A�u�]�ɂ��g�傷��A�l�Ԃ͎��R�ɂȂ�Ƃ͎��͎v���Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ玩�R�Ƃ́A���Ԃ̔z���k�܂�]�Ɏ��Ԃ̒����l�̖��ł͂Ȃ��A���̓��e�̖�肾����ł���v�B�u�Ƃ��낪������ݍ���Ŏ��R�ȗ]�ɂƂ͉��Ȃ̂����l���悤�Ƃ���ƁA���̍l���������ł͓����͌�����Ȃ��v�Ƃ����B
���R�������u���R�v�͒ʏ�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�Ӗ��ŗp�����Ă���B��ʂɁA���R�̈Ӗ��ɓ�ʂ�̈Ӗ�������B�������\���ɂ���A�]�ɂɁA���͎��R�ɔ��������ł���B���Ƀt�����X��̔\�͂��\���ɂ���t�����X�f������R�Ɋy���߂�B���R�ȘJ���Ƃ͎�̓I�Ɏ��Ȃ̋Z�\���ł���悤�ȘJ���̂��Ƃł���B�l�X�ȏ����������Ύ��͘J����]�ɂɂ����Ď��R�ł���A�l�ԓI���R������ł���B���R���l���鎩�R�́A�ʏ�͂��܂�g���Ȃ��A������ϋɓI�ɍs�����Ƃ��ł���Ƃ����A���̂悤�ȈӖ��̎��R�ł���B
������̎��R�͒ʏ�̈Ӗ��ł̎��R�ł���A�s����v�z������(�l���邢�͖@���Ȃǁj�ɂ�萧���A�����A�S������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B��������������\�͂�����A��������悤�ƍl���Ă��A���̍s�ׂ��ւ����Ă���A���͂�����������邱�Ƃ��ł����A�s���R�ŕs�K�ł��낤�B���҂Ɋ�Q���y�ڂ��s�ׂ͖h�~����˂Ȃ�Ȃ����A����ȊO�͌X�l�̎������d���ׂ��ł���Ƃ����l�����Ɋ�Â����R�ł���B�����ł��邩�Ƃ������Ƃɂ��Ă͂��̎��R�͌��Ȃ��B���̈Ӗ��ŏ��ɓI���R�ƌĂԂ��Ƃ��ł���B���Ƃ��A�����ɂ�����悤�Ȍo�Ϗ�Ԃɂ���A�s���ɐ�����S�����Ă��Ȃ��Ă��A�܂���ɓI�ȈӖ��Łu���R�ȁv����A�x�����^�����Ă��Ă��A���̐l�͓�������������A�ϋɓI�ȈӖ��ł̎��R�͎����ł��Ȃ��B
���������āA���ɓI���R���F�߂��邾���łȂ��ϋɓI�Ȏ��R����������邽�߂̏����𐮂��邱�Ƃ��K�v�ł���B�����܂��o�ϓI�ɖL���ŁA���N�ł���A���X�̏�����������Ă��Ă��A��O�̂悤�Ɏv�z��s���̎��R����������A�����������ɂ���Č������Ď������Ȃ�A��͂莩�R�ł͂Ȃ��s�K�ł���B�������ď��ɓI���R�ƐϋɓI���R����ʂ���邪�A���R�̎����̂��߂ɂ͗������K�v���ƌ�����B
�O�Ȉ�≹�y�Ɓi�O�͑�S�ߎQ�Ɓj�A���邢�͌����҂ȂLjꕔ�̐l�X�̎d���������A�����̎d���i�J���j�̑����͊y������肪���̊���������̂łȂ��B�����ŁA�������Ƃ̒��ɖ����A�K���������������Ƃ��ł��Ȃ��J���҂��������āA�J�����Ԃ̒Z�k�A�]�ɂ̊g������߂Ă���B�]�ɂ̊g��́A���Ȃ��Ƃ����ɓI�ȈӖ��ł́A�J���҂̎��R�̊g��ł��낤�B
���R�͗]�ɂɂ����Ăǂ�Ȋ������s���u���R�Ŗ������肽�]�Ɂv�������ł��邩��₤�B�����āu�]�ɂ͎��R�Ȏ��Ԃ��v�Ƃ����l�����̒��ɂ͂��̓����͌�����Ȃ��A�ƌ����B�������ł���B�ǂ̂悤�ȗ]�ɂ��߂������͊e�l�̎��R�ɂ䂾�˂��Ă��邩��ł���B�e�l�͗]�ɂɂ����āA�����̍D�ފ����������̂��o�ϓI�����Ɣ\�͂ɑ����čs���A�l�X�Ȓ��x�̏[�����邾�낤�B�Љ�����̎�ނ��ƂɈ��̃C���t����p�ӂ��邱�Ƃɂ����R�̌����u���R�v���I�ɂ͕⊮���邱�Ƃ͉\�ł��邪�A�u���������v���ǂ�������ʓI�A�q�ϓI�Ɍ�邱�Ƃ͍���Ǝv����B
�Ƃ��낪�A�ނ͗]�ɂɂ����āu�����Ȃ��ׂ����v���O�����璍�����悤�Ƃ���B�ނ́u���R�Ŗ������肽�]�ɂ��߂������Ƃ���Ȃ�A�]�ɂƂ͂܂��A���Ɏd���̍��Ԃ̋x���łȂ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�v�B�u��d���I�����[�����ƂƂ��Ɍ���Ă���]�T�ɖ��������ԁA�]�ɂ͂����������̂łȂ���A���R�ȂƂ��k���ԁl�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�B�u�����đ��ɂ��̋x���́A���R�őn���I�ȂƂ��łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�B�n���I�ł��邪�䂦�Ɋy�����Ƃ��ł�����B�������n���I�ł��邩��ƌ����āA�����Ɋ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��B�u����x�߂�v�Ƃ��u���x�߁v�Ƃ������t���̂��炠��悤�ɁA�u��v��u���v���������悤�ɁA�ڂ���Ǝ����߂����Ȃ��琶���͂����߂Ă����̂��A�l�ԂɂƂ��Ă͂܂��n���I�ȉc�݂ł���v�B
�u�������A���R�őn���I�ȗ]�ɂ���ɂ��邽�߂ɂ́A�J�����ǂ�Ȃ��̂ł����Ă��悢�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B----�����炭�A�y������[���������J��������Ƃ��A���̍��ԂɖK��Ă���x�����܂��A�l�ԓI�Ȏ��R�������炷�̂ł��낤�B---�K�v�Ȃ��Ƃ͘J���Ƌx���Ƃ̍K���ȘA�����ł��낤�B�Ƃ��낪��������Ă���]�ɂƂ͂����������̂ł͂Ȃ��B�����̗]�ɂ͒E�J���̎��Ԃł���A�J�����S�g�̏��Ղł��邩�炱���A�]�ɂ��K�v���ƍl�����Ă���v�B
�J�����u�y������[���������v���̂ł�����̍��Ԃ̋x�������̂��Ɗy�����K���Ȃ��̂ƂȂ�B�ǂ�ȗ]�ɂ����Ƃ����ƍl����K�v�͂Ȃ��B�u�y������[���������J���v�ɏA���Ă���l�́u�����Ɋ�������v�K�v�̂���]�ɁA�܂背�W���[�͕K�v�Ƃ͂����A�Ƃ��ǂ��u�ڂ���Ǝ����߂��v���A�u���x�߁v�̋x�����Ƃ邾���ł悢�B�x���͒E�J���̗]�ɁA�d����Y��A�d������������邽�߂̎��Ԃł͂Ȃ��A�u�����͂����߂�v�܂�G�l���M�[�����Ċy�����J���ɍēx���A���邱�Ƃ��\�ɂ���u�n���I�Ȏ��ԁv���ƌ����̂ł���B
�܂��A�E�J���̗]�ɂ��K�v���Ƃ����l�́A�u�J���͐S�g�̏��Ղ��v�Ɗ����Ă���̂�����A�J���ɖ�肪����̂ł���B�܂�A�]�ɂ����߂�l�́A�J�����[���������̂łȂ������̂ł�����̂łȂ��悤�Ȏd���ɏA���Ă���l�ł���A���̂悤�Ȑl�̗]�ɂ��邢�͋x�����悢���́A�[���������̂ɂȂ�͂����Ȃ��B
�������āA�y�������R�ȘJ���ɏA�����Ƃ̂ł������͎̂d���Ƌx���̗����ŁA���R�Ŋy�����u�A�������v�K���Ȏ��Ԃ����邱�Ƃ��ł��A���������āA�E�J���̗]�ɂ͕K�v�Ȃ��B�����A�d���ɖ����ł����A�]�ɂ�K�v�Ɗ����Ă���l�́A�y�����[�������x�����]�ɂ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂�����A�]�ɂ������Ă����ʂł���Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂪ�ނ̗]�ɘ_�ł���B����A�]�ɖ��p�_�ł���B���̗]�ɖ��p�_�ɔ[������̂́A���̌I�c����̂悤�ȗ]�T�̂���o�ϓI��Ղ��������_�Ƃ��A�`�N�Z���g�~�n�C�����Ă���O�Ȉ�≹�y�Ƃ��A���邢�͎��X�������Ƃ�����u�d������v�ŔN����N���d���������Ă��čK���ł���悤�ȁA���������̐l���������ł��낤�B
�]�܂����]�ɂ̂��肩���ɂ��Ă͑傢�ɋc�_���Ȃ����ׂ����Ǝv���B���͑�Q�͂ł́A�ቻ�̕K�v�ƌ����ϓ_����A���Z��̂悤�ȓ���̏ꏊ�ɑ吨���W�܂��āu�y���������v�Ő���オ������A�R�����̂悤�Ȃǂ��炩�Ƃ����̂�т�Ƃ����]�ɂ̉߂������̂ق����]�܂����Ƃ����ӌ����q�ׂĂ���B�������A���R�̗]�ɂɊւ���c�_�́A�J���ɂ�����[���̕K�v�����A�x���ɂ���đn���������߂�̂��]�ɂ��Ƃ������Ƃɂ��Ă���B�]�ɂɂǂ̂悤�Ȋ������Ȃ����̂��]�܂����̂��Ƃ������Ƃɂ��Ă͑S�����Ȃ��B�ނ̗]�ɂɊւ���c�_�́A�J���҂��邢�̓T�����[�}�����J������������Ď��R�Ȋ������y���ނƂ����]�ɊT�O���̂��̂�ے肵�Ă���B
���́A��Q�͂ŁA������ɂ����ẮA��͕K�v����Ƃ������ʔ����Ɗ�����ꂽ����s��ꂽ�̂��Ƃ������ɂӂ�A�܂���R�͂Ńz�C�W���n�́A�Ñ�Љ�ɂ����Ắu���ׂĂ̊����͗V�т̕��͋C�̒��ōs��ꂽ�v�Ƃ������t�����p�����B�������A����Љ�ɂ�����E�ƘJ���́A�Ñ゠�邢�͌��n�̎Љ�̐l�X�̂悤�ɗV�є����Ȃ����ʔ������̋C�����ł����Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B�E�Ə�̎d���́u���ቻ�v���ꂽ�d���ŁA�܂�A��������e�Ɋւ�����Ⴆ�邱�ƂȂ��A�����I�ɁA�K���ɏ]���āA���m�ɍs���邱�Ƃ����߂�B���̂悤�ȐE�ƘJ���̐��s�́u�V�т̕��͋C�v�̂Ȃ��ł͕s�\�ł���B
�d���^�J���̎��Ԃ́A�������Ԃ������P���̑啔�����߂邪�A�d���ɃX�g���X�������Ȃ��Ƃ����l�͂��������ł���B�������āA����l�́A�L�Ӌ`���Ɗ������A�[�������E�Ɛ������������Ă���ɂ��Ă��A�g�̓I��J����̉��K�v�Ȃ����ł͂Ȃ��A������̐��_�I�ȃX�g���X�������������Ƃ������Ƃ����ЂƂ��K�v�ł���B�G���A�X�������Ă���悤�ɁA�]�ɂɂ�����X�|�[�c��V�тɂ���āA�u���_�I�Ȓ��Ɋׂ��Ă��܂����Ƃ�h���A���_������������v�K�v������B�]�Ɋ����̑����́u��]�ɓI�����ɂ�����S�ʓI�ȗ}���̏d�ׂ��y������v���߂ɕK�v�Ȃ̂��ƍl����ׂ��ł���B
�������A���̂悤�ȕ⏞�I�A���邢�͎��ÓI�ϓ_���炾���łȂ��A�l�́A���邢�͐l�ɂ���ẮA������̂��Ƃ����ł͖����ł����A���낢��Ȃ��Ƃ���肽���ƍl����B
�G���A�X�͗]�ɂƔ�]�ɁA���ቻ�Ɣቻ�̃o�����X�����Ȃ̂��ƌ����A�]�Ɋ���������s���Ă����炻���Ŋ��ቻ���N���邩������Ȃ��Ƃ������Ă���B�������A����͞X�J���Ǝ��͎v���B���ׂĂ̐l���K�v�ȘJ����S���s��Ȃ��ōςނ悤�ȎЉ�͖����i���ɂ킽��������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���邩�炾�B�����Ď��́A�P���ɂP�`�Q���ԂȂ�A�K�v�ȘJ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ��Ă��A�����Ă���͢���ቻ���ꂽ�v�������ōs���邱�Ƃ��K�v�ŁA�䖝���Ȃ���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ɂ��Ă��A���ꂭ�炢�Ȃ�A���܂�Ȃ��Ƃ��v���B
���͎����ʂɘQ��A�n���S�̂�j�A���Y�������グ�A���Y�傳���A�����Ď��{�̊g������ȖړI�Ƃ��Ă���悤�ȋ�������������w�x�܂��邽�߂ɁA���_�����茸�炵�A�J�����S�A�d�����S�̐����𑱂��Ă��邱�Ƃɂ���B�d���ł͂Ȃ��A���R�ɍs���邳�܂��܂Ȋ������A���܂ɂ͎v���苻�������肠�邢�͑S���̂�т肵���肵�Ȃ���A��������܂ł���悤�ɂ���ׂ��ł���B������������A�d����ʔ����Ǝv���Ă��邩������Ȃ��B�������A�ق��ɂ����Ɗy�������Ƃ����邩������Ȃ��B�����āA�d������łȂ����낢���肽�����Ƃ�����Ă݂����l����������ł��낤�B�l�X�������Ǝ��R�ɂ��܂��܂Ȋ�������������Ɍ����悤�ɎЉ�̎d�g�݂�ς���ׂ��ł���B
�X�|�[�c��������s�����肷�邱�Ƃ͑��i����Ă���悤�Ɍ����邪�A����ȊO�̎�A���R������Љ�A���j�T�K�╶�w�̌�����{�����e�B�A��������p�≹�y�Ȃǂ̊������s���₷�����邽�߂ɁA�}���ق��w�⢓Ɨ��@�l�v�Ȃǂ̌����@�ւ�{�݂��I�[�v���Ȃ��̂ɂ��A�l�I�ɂ��s���̊����ɋ��͂��₷���̐��ɕς��Ă������Ƃ����̈���ɂȂ邩������Ȃ��B
�]�Ɋ������y���ނ��Ƃ́A�o�ϓI�Ȉ����A�悢�Ƒ��W��A���N�E���S�Ȑ����ȂǂƂƂ��ɁA���K�ōK���Ȑ������\������ƍl������B���́A�L�Ӌ`�ŏ[�������J���Ƃ���ɂƂ��Ȃ��[�������x���������K��������������̂��Ƃ͍l���Ȃ��B
�]�ɂɑ�������M���V����̓X�R���[�Ѓԃ̓Ƀłł���B�p���leisure��spare�]time�Ɠ��`�ŁA���R�̌����悤�Ɂu�]�����ɂȎ��ԁv�ł���B�p�ꌗ���邢�̓L���X�g�����ł́A����̂����l�Ԃ������ׂ����Ԃ�����A�c�肪�u�]�������ԁv�ł���ƍl�����Ă���B�������A�Ñ�M���V���̃|���X�ł́A�o�ϊ����͓z�ꐧ�Ɉˋ����Ă����B�Ǝ����z�ꂪ�s���Ă����B����䂦�A�s���͈�ʂɁA�����K�v���Ȃ������B�܂�A�|���X�́i�j���j�s���͐������ԂȂǂ������āA������A�u�Ɂv�������̂ł���B �ŋ߂̓��{�̎q�ǂ������́A��l�畉���ɂ��܂��܂Ȏd���i�m�ʂ��A�X�|�[�c�N���u�ł̗��K----�j�������Ă���A�V�ԉɂȂǂȂ��悤���B�������A�����甼���I�ȏ�O�Ɏq�ǂ��ł������A���Ɠ�����̐l�́A�w�Z�ɍs���Ă��鎞�ȊO�A���ɉċx�݂Ȃǂɂ͒�����ӂ܂ōD���Ȃ��Ƃ����ĉ߂������Ƃ̂ł��鎩�R�Ȏ��ԁA�u�Ɂv�������Ă����B�Ñ�M���V���̃|���X�ł͑�l�̎s��������Ɠ��l�̉ɂ������Ă����̂ł���B
�M���V���N�w�̏����̖M��ł́A�X�R���[�́u�]�Ɂv�ł͂Ȃ��A�u�ՉɁv�Ɩ�Ă���B�Ñ�M���V���́u�Ɂv�͘J�������]��̎��Ԃł͂Ȃ�����ł���B�|���X�̎s���͒j�����Ɍ����Ă������A���̎��R�Ȏ��Ԃ��g���āA�����̂��������Ƃ������B�X�R���[�̓A�e�[�i�C�Ŏs���S�����Q�����钼�ږ��吧���\�ɂ��������̈�ł������ƍl������B�s���͌��I�����I�Ȋ����Ɍg��邾���̎��Ԃ������Ղ�����Ă����B�j�Ղ̂Ƃ��ɉ�������ߌ��̐������������A�\�[�N���e�[�X�̂悤�ɁA���Ȃ��ő��̐l�X�Ɛ���ɑΘb��������A���邢�͐e�����F�l�ƏW�܂��ċ������J���ēN�w�I�c�_�������l���������B���ɂ͐E�l�I�Ȏd���A���邢�͏��Ƃ��c�ގ҂��������B
�������A���R�ȃ|���X�s���̑����́A�E�l�I�d�����܂߁A�J���ɂ��҂����Ƃ������ɁA���R�Ȑ����_�c���s������A�����Œm�I�ȉ�b���y����A�w�⌤���������Ȃ�����A���邢�͍ՓT�ŋ��������X�|�[�c�≹�y�⌀�Ȃǂ̌|�p���y���ނ��Ƃ̕���I�B
�z�ꐧ�̎Љ�łȂ��Ă��A�啔���̎Љ�́A���Y�͂̌���ɂ���ĘJ���͂ɗ]�T��������ƁA��m�̊K���A���E�ҁE�w�҂��l�����̊K���̂悤�ȁA���Y�J���ȊO�̎d���Ɍg���K���ݏo���Ă����B�����A��������J�����y�����Ɗ�������A���̂悤�ȊK���͐��܂�Ȃ������ł��낤�B�ߋ��̂��ׂĂ̎Љ�ɂ����āA�͂̋������́A���ʂ̔\�͂��������҂������A�͂����Ől���x�z���邩�A�J��̏��Ȃ��d���ɂ��Ƃ�����������ɓ���悤�Ƃ������A����́A�J������ʂɂ炢�A�ꂵ�����̂ł��������炾�ƍl������B
���R�͐l�Ԃ̖{���͘J���ɂ���ƍl���Ă��邪�A�i���̐l�Ԃ��]���ɂ����Ɂj�J�������Ȃ��čςނȂ�A���邢�́A���Ȃ����Ԃōς܂��邱�Ƃ��ł���Ȃ�----�����Ă��̂��Ƃ́A���łɂ��₨���Ȃ��ɔ��B���Ă��܂��Ă���@�B��I�[�g���[�V�������l������A�u����v�ł͂Ȃ������ł���-----���̊����ɏ[�Ă����ƍl����̂͂���߂Ď��R�ł���B
���R���Љ�Ă��鑽�p�o�c���y���ޔ_�Ǝ҂��k�^�@���g���āA�J�����Ԃ����炵�Ă���B���̔_�Ǝ҂͗]�ɂ������Ƃ��ł���B�ނ͔_��ƘJ�������ɏ[���������A���ɂ͉��̎�������Ȃ��̂��낤���B�_�Ƃɂ����閞���Ƃ͂܂��ʂɁA�ނ���������Ƃ͂��肤��̂ł͂Ȃ����B�l�Ԃ͏����ȃz���E�t�@�[�x���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȏ���͂Ƃ������Ƃ��āA�_�Ƃ����ׂĂł���A��ȂǑS�������Ȃ��Ƃ����l�����A�]�ɂ̎��Ԃ����A��������Ȃސl�̂ق����u�l�Ԃ炵���v�̂ł͂Ȃ����B
���R�́A���{�̘J���҂́u�J���ɔ��Ă���̂ł͂Ȃ��A��Ƃ̂��ƂŃT�����[�}�������Ă��邱�Ƃɔ��Ă���v�̂ł���A�u���{�̘J���҂͘J������̗]�ɂ����߂Ă���Ƃ������́A��Ƃ̃T�����[�}���ł��邱�Ƃ���̗]�ɂ����߂Ă���v�Ƃ����B�ނ̌����u���{�I��J�v�͊m���ɂ���Ǝ����v���B�������A�u���ہA�ł��邱�ƂȂ��Ƃ����߂����Ǝv���Ă���҂͂������邯��ǁA�Ƃ����Ĕނ炪�J�������Ȃ킯�ł��A�J�����������Ȃ��Ǝv���Ă���킯�ł��Ȃ��B�ނ���----�����ƗL�Ӌ`�ɘJ�����������Ɗ����Ă��邾���ł���v�i�w���R�_�x�j�Ƃ܂ł�����Ɣ��_���Ȃ��ł͂����Ȃ��B
�u�ł��邱�ƂȂ��Ƃ����߂����Ǝv���Ă���v���{�̘J���҂��u�����ƗL�Ӌ`�ɘJ���������Ɗ����Ă��邾���v���ǂ����́A�����ĉ҂����ɁA���y���������A�D���ȃX�|�[�c�ɑł�����A�D���Ȃ��Ƃ����ĕ�点��Ƃ��Ă��A��͂蓭���������Ɛq�˂Č��Ȃ���킩��Ȃ��͂����B���̗\�z�ł́A���̂悤�ɖ����A�����̐l�͂Ƃ��ɓ��������킯�ł͂Ȃ��Ɠ����邾�낤�B
�ق��ē����l�̂قƂ�ǂ́A���l�̎w����w���A���邢�͖��߂ɏ]���ē����B����ɑ��āA��҂�ٌ�m�A���邢�͔_�Ǝ҂́A�����̂�肽���悤�ɁA�����̂�肽�����Ƃ�����B���̂悤�Ȍ���ꂽ�����̐E�Ƃł́A�������Ƃ̃}�C�i�X�v�������Ȃ��B�����҂̏ꍇ�ɂ��A�T�����[�}���Ƃ��Ă̍S��������A�܂����̌����҂Ƃ̌������������������Ă��邪�A�d���̓��e�͎����ōl�������Ō��߂鎩�R������B�������A�ق��čs�Ȃ���ʓI�Ȏd���ł͂����������R���ɂ߂ď��Ȃ��B���R�������Ă���y�����d���͔_�ƂȂǎ��c�Ƃ����ł���B
�����A���c�Ƃ́A�ٗp����ē����J���҂ɔ�ׂĎ��R�̓x�����͑傫�����A�K�v�ȉ҂���Ƃ����_�ł͕s��������B��҂�ٌ�m�Ȃǂ������A�V��Ȃǎ��R�̉e������������A���邢�͌o�ς̔g���₷�����c�Ƃ́A���肵�Ă���Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������Ƃ���A�J���̒��Ŏ����̒m�b��H�v�����邱�Ƃ͘J�����y�������邾�낤���A���ʁA���肵�����������Ƃ߂�Ȃ�A�K�������A���c�Ƃɓ]�E����Ƃ����I�����悢�Ƃ͌����Ȃ��ƍl������B���c�Ƃւ̓]�E���l����l���ŋߑ����Ă���Ƃ������邪�A�J���̑��̖ړI���u�y���݁v�邱�Ƃɂ���̂łȂ��A�u�����̎�i�v�邱�Ƃɂ���Ȃ�A���c�Ƃ�I�Ԑl�����A�ٗp����Ă����Ȃ��J����I�Ԑl�̂ق��������͓̂��R�ł���B
����̊�ƘJ���҂̒��ɂ��A�Z�p�҂Ȃǂ̂悤�ɁA�����̎d���ɂ�肪���A���������Ɩ��������o���Ă���l�����邾�낤�B�������A�����̎d�����u�����̎�i�v���ƍl���Ă���l�̂ق��������Ƒ����͂����B
�Ƃ��낪�A���R�ɂ��A���̂悤�ɂ����������Ȃ��Ƃ���ΘJ���͖��Ӗ��Ȃ��̂��ƌ����̂Ɠ������ƂɂȂ�B������u���{���Љ�̂��ƂŘJ���͐l�ԂɂƂ��ċ��J�ȊO�̉����̂ł��Ȃ����낤�B�J�����̂ɉ��̈Ӗ����Ȃ��A���̌��ʓ����邨�������ɈӖ�������Ƃ�����A�����������̂��߂ɐl���̑唼���S������邱�Ƃ͋�ɂł���B���������Ȃ�J���҂͂Ƃ����Ɋv���̓���I�ю���Ă������낤�v�Ɠ��R�͂����B���������ɂ͓��{�ɂ����Ă͊v���͋N����Ȃ������B���̗��R�͘J���҂��u�҂����߂̘J���ɕʂ̈Ӗ���t�^�����Ȃ���v�A�u�҂����߂̘J�����d���Ƃ��Ă̘J���ɓ]���Ȃ���v�����Ă��邽�߂��Ɠ��R�͌����i�w���R�ƘJ���x�j�B
�܂�命���́A�v���s���ɗ����オ��Ȃ��J���҂͎����̎d���ɖ����������������Ƃ��A�����̔\�͂����Ă��邱�ƁA�܂����̌��ʂ��Љ�ɖ𗧂��Ă����Ƃ��m���߂����ƍl���Ȃ���d�����s���Ă���A�Ƃ����B�Ƃ��낪�A�u�����Љ�I�ȗL�p���������Ă��邩�ȂǂƂ������Ƃ́A���������J���ɂ��������҂̗�������̂ł���v�B�u�J���҂ɂ͎����̘J������ƂɂƂ��Ă͗L�v�ł��邱�Ƃ͂킩���Ă��A�Љ�ɂƂ��ėL�p�ł��邩�ǂ����킩��Ȃ��v�B�����ŘJ���҂́u�Љ�ɂƂ��ėL�p�Ȑl�Ԃł��낤�Ƃ������قǁA��Ƃ̒��ł̃��[���c�T�����[�}���ɂȂ��Ă������v�B���ꂪ���x�������̓��{�̘J���҂̌����ł������Ɠ��R�͌����B
�O�ɓ��R�̋c�_�́A�s�s�ƎR���A�����Ǝ��R�A���X�A������P�������A�I�Η��̂Ȃ��łƂ炦��X�����������Ƃ��w�E���Ă��������A�����ł��������Ƃ�������B�l�Ԃ͘J����a�O�A��l�ԓI�Ŗ��Ӗ��Ȋ����A���J�Ɗ����A�v���s���Ɍ��N���邩�A�����łȂ���Ύd���Ɏ��Ȏ����A�Љ�ւ̍v���ȂǁA��̓I�i��ϓI�j�Ӗ���t�^���A���ۂɂ͎Љ�ɍv������ւ��Ɋ�Ƃɍv������A���[���c�E�T�����[�}���ɂȂ��Ă����A���̂ǂ��炩���Ƃ����B�ނɂ́A����߂āu��̓I�ȁv���������������Ȃ��B�v���s���Ɍ��N���悤�Ƃ͂��Ȃ��������A�܂��u�J���ɂ���ĎЉ�̂��߂ɖ𗧂Ƃ��v�Ƃ͕K�������l�����A�����ƉƑ��́u�����邽�߂̎�i�v�Ƃ��Ďd���������ƂƂ��ɁA��Аl�ԁA���[���c�E�T�����[�}���ɂ͂Ȃ炸�A���ʂɁA�����Ɏd�����s�����Ƃ��u���J�v�Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ������������Ă��鑽���̘J���҂̑��݂͖ڂɓ���Ȃ��̂ł���B�ނɂ́A�d���Ȃ��䖝����i�Ƃ����Ă��A�Z���^����A�s���^���ɉ����A�f����W��ɂ͎Q�����邩������Ȃ��j�Ƃ����������͌����Ȃ��B�����A�����܂߁A���̕��}�ŁA�u���̓I�v�Ȑl�X�͘J���̒��ɖ����ƍK���������������Ƃ͍l�����A�]�ɂ�K�v���ƍl����B
���́A�d���E�J���͂�ނȂ��u�����̎�i�v�Ƃ����������A����͂���Łu�J���̈Ӗ��v�ł���ƍl����B�����͐����邽�߂ɁA�܂��Ƒ��̂��߂ɁA�Ȃ�ׂ������̔\�͂�����ƂƂ��ɁA�Ȃ�ׂ��J�������̂悢�d�����݂��A�����̗]�ɂ��y���݂Ȃ���A�䖝���ē����B���ꂪ�J���̈Ӗ��ł���B
����͘J��/�d�������������邱�Ƃł���A�l���̈Ӗ��͂����ɂ����Ȃ��Ƃ����l���Ƃ͈قȂ�B�������l�Ԃ͂܂����������Ǝv���B�Ȃ�ׂ��ǂ��A���邢�͑P�����������Ǝv���B�����āA�����邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ������̎Љ�ɂ����ẮA���ʂ̎��Y�Ƃ̉Ƃɂł����܂ꂽ�̂łȂ���A�����K�v������B�N���D���Ȑl�ƈꏏ�ɕ�炵�����Ƃ��l����B�����Ďq�ǂ����ł��邱�Ƃ�����B�����Ŏ��͂��̈ꏏ�ɕ�炷�Ƒ��̂��߂ɂ��i��l�łƂ͌���Ȃ����j�����K�v������B���͓����Ȃ���A���̗]�ɂɁA�Ƒ��ƂƂ��ɂ��邢�͎��X�͎��������̂��߂ɁA�X�|�[�c�₻�̂ق��̍D���Ȋ������y���݂����ƍl���邵�A���N�ň��S�Ȑ�����j�Q����Љ�I�����Ɠ����A�܂����̎Љ�̒��ŋꂵ��ł��鑼�̐l�X�̂��߂ɖ𗧂������s�������ƍl����B���͘J�������i�ƍl���A�]�ɂɂ��܂��܂ȗǂ��A���邢�͑P�����������������邽�߂̊������s�������B���ꂪ�����܂ޑ����̐l�ɂƂ��Ă̐l�ԂɂƂ��Ă̘J��/�d���̈Ӗ��ł���A�Ǝ��͎v���B
�ŏ��͓��R�́u�ނ�͘J�����v�Ƃ����u�ނ�N�w�v�ɔ��_���悤�Ə����n�߂����A�c�_���L�����Ă��܂����B�����Ȃ��������R�ւ̔��_�͂���ŏI���ɂ��A�u�l�X�Ȓނ�v�ɂ��Ă̏͂��I���邱�Ƃɂ������B ���̏͂ł́A�ނ肪��Ŏv���o���Ă�������s�����Ƃ��Ɠ������炢�y�����Ƃ������Ƃ������B
�������w��̓��x���ދ������V���[�Y���i���[�A���a�T�P�N���Łj�Ƃ����{������B1907�N���̐��܂�̏����͖����V���̋L�҂ŁA���A�O�n��������グ�Ă��ē����ɏZ�݁A�ނ���ĊJ�����B
���M�̒��ɎU�����ƁA���̐l�̍�����Z�̂⎍�i������ׂĒނ�A���邢�͊C���ɂ��Ă̂��́j���}�����ꂽ�A����ꂽ���M�W�ł���B
�u��l�̎l�G�v�Ƃ������M�̒��ɂ́A�ނ̈ȑO�̍�u�l�����y�v�Ƒ肷�鎍�������Ă���B
�@�u �V�l�͊Ƃ�S���Ł^ �ߋ���ނ�^���y���ς�
�@ �s�҂̓��[���𑀂��ā^���݂�ނ�^���l���ւ�
�@ �N�̓����b�N�����Ɂ^������ނ�^���z�݂�
�@ �͊C�Ώ��^���Ă͌k���Ɂ^�j���V��́^�y���݂���܂�Ȃ��v
�����͌���
�u�����Z�����T�����[�}���͒�N���}������Œނ�ł��n�߂悤���ƍl���Ă��邾�낤���A����ł͂��łɒx������B----�Ⴂ�Ƃ��ɂ��Вނ���o���Ă����Ȃ����B��������ނɌ��炸�A�ł���Ƃ��ɂ��܂��܂̒ނ���o���Ă������Ƃ��B�N������Ă���ł́A�̂̕����Q���Ă��܂��B
���A�[���\�A�g���[�����O�I�[�P�[�A�����ނ��낵���A���ł�����Ƃ��ɂ��A���낢��̒ނ�����ڂ��Ă����A�ł��邾����������̒ނ���K�����Ă����Ȃ����B---�ЂƂ����ɒނ�Ƃ����Ă��A���z�̔�p�̂�����ނ������A���̂�����ʒނ������B�����Ă����������Ȃ��Ă��A----�H�v����œ����悤�ȁA���邢�͂���ȏ�̊y���݂𖡂키���Ƃ��ł���̂��B����ɑ厩�R�̂ӂƂ���ɖv�����Ă���A���Ƃ��A���ɂ�����ʃ^�i�S��C�A�ނ�グ���Ƃ��Ă��A���̒ނ薡��18�L���̃J���_�C���������Ƃ��̊����Ə������ς��Ȃ��B---
���N�͐N�ƂȂ�A�N�͑s�N�ƂȂ�A�s�N�͕K���V�N�ƂȂ�B������A�Ⴂ���ɘV��̒ނ��p�ӂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��v�B
��̏����̎��́A�J���ɕ���Ď������́w�G�b�Z�[�x�̍ŏ��Ɍf���������̌Ì��Ō����Ă����u�i���ɍK���ɂȂ肽��������A�ނ���o���Ȃ����v�Ɠ������Ƃ������Ă���B�ނ�͘V�N�ɂȂ�܂Ŋy���ނ��Ƃ��ł���A�����\�ȗV�тł���B
�����̘V�l�́u�Ƃ�S���ŁA�ߋ���ނ�A���y���ς�v�Ƃ�������A�����ނ�����Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B�����̒��ŊƂ��o���A�ނ�̎v���o�ɐZ���Ă��邾���Ȃ̂�������Ȃ��B�h�g�炩����ۂɊƂ��o���Ă͂��邪�ނ邱�ƂɏW�����Ă���Ƃ������A�ߋ��̑務�̂��邢�͑�^����ނ������̎v���o�ɐZ���Ă���̂�������Ȃ��B���͎����̏͂ł́A�S���ނ肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă���ł��A�ߋ��̒ނ���y���ނ��Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��������Ǝv���B