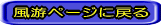内海(宮城)恵美子「安里清信さんの思想――金武湾から白保、辺野古・高江へ」(『けーし風』№76・201209)
崎原盛秀さんインタビュー「現在に引き継がれる『金武湾を守る会』の闘い」(『情況』2010年11月号)
上原こずえ「施政権返還後の沖縄における住民運動と裁判-石油備蓄基地建設反対闘争(1973-1985)における裁判をめぐって」
「戦後50年 人間紀行 そして 何処へ/第2部 闘い 立つ」(沖縄タイムス1995年5月16日~23日)
金武湾を守る会「提訴にあたっての声明(1974年9月5日)」
安里清信さんの思想
――金武湾から白保、辺野古・高江へ
内海(宮城)恵美子
はじめに
私は本土から1975年に沖縄に戻り、金武湾闘争に参加した。まずは、那覇の若者グループ「CTSを阻止する会」を作り闘いに参加したが、活動の多くは「金武湾を守る会」(以後、「守る会」と呼ぶ)の若者たちとともに行動をしていた。安里清信さん、屋慶名区長伊礼門(いれいじょう)さんを訪ねたり、自治会館行事に参加、時には崎原盛秀さん宅あるいは「中頭教育会館」で行われる中部地区労との連絡会等にも参加させてもらっていた。照間区では平良良昭さん、前川美智代さんからは考え方を、花城清繁さんから農業・漁業についてお話しを伺うこともよくあった。援農運動は各地・職場から馳せ参じた「金武湾闘争労働者連絡会」等のメンバーと「ウージ倒シ闘争」を行った。
那覇では「くらしの公害を追放する会」事務所(石鹸ハウス)を拠点に、会報『公害ぬ無ん世ど(どくねんゆ)』の発行、記録映画等の上映、キャンペーン活動等を行っていた。また「守る会」の県庁行動(実に100回を数えた)等那覇での行動、自ら設立した印刷会社で「守る会」機関紙『東海岸』や裁判の準備書面等の作成の協力を行った。製本作業は「金武湾を守る会」の前川さんらも交えてワイワイガヤガヤと楽しい活動であった。そしてCTS設置の影響で衰退を余儀なくされた藪地島の畑作を復活させようということで、「守る会」の手ほどきを受け、小舟で島に渡り、「藪地島開墾」も始めていた。今にしてみれば無謀に思えるが、0歳の赤子3人も連れて、その母親である照屋房子さん、佐伯恭子さん、私らと他の若者たちが、一緒に船で渡って芋作付等を行った。
「守る会」運動の中から始まった「琉球弧の住民運動交流合宿」は事務局として10年間活動した。金武湾からは少し外れるが、守る会の前川美智代さん、照屋房子さんらと「ベラウの女性を招く会」を読谷村の財政支援を得て開催し、ベラウと金武湾の平和運動を広め、同じ太平洋の島として協力する運動を行ったこともあった。
金武湾闘争が触発した運動は、その後も復帰後の沖縄に思想的なインパクトとダイナミズムをもたらし続けている。多様な視点で見ることができるが、私はその中から四点について述べていきたい。実は現在展開されている沖縄の闘いは、金武湾闘争当時の担い手たちの多くが今も闘い続けているし、運動の内容も金武湾闘争の中で展開されていたものを継続している。つまり、金武湾から白保、辺野古・高江と40年間も続いている。したがって金武湾闘争はまだ終わらず、途中の状態にあるといえよう。
第1章 金武湾に石油備蓄基地(CTS)を置いた国・県の構想の時代背景
沖縄経済は復帰後数年の混乱期を経て、それ以降はマクロ経済的には日本経済と同調する動きをしている。しかし、完全失業率は全国の2倍近い高さ、有効求人倍率は全国一低い状況にある。ところで、復帰前は違っていた。1970年の失業率は0・70%(全国0・85%)、1971年0・8%(全国1・2%)で全国平均よりも悪くはなかった。雇用する企業はあまりなかったが、生業としての就労条件が地域に存在していたのである。失業問題は、復帰後の大論点でありつづけているが、通常の経済学的立場からはその解決は困難をきわめている。
かつては自立的に存在し、住民の生活基盤となっていた共同体。その基盤である海と大地を基礎に、老若男女、障がいの有無にかかわらず、共生できていた地域社会を壊し、市場経済における金銭関係のみに収斂させるのは限界ではなかろうか。
金武湾闘争では、沖縄の生存の根っこはなにか、なにが大切で次世代に残すべきかを訴えていた。では金武湾闘争ではどのような主張があり、その主張の基盤である「海と大地と共同の力」とは何なのかを見ていきたいと思う。
現在沖縄は、グローバル経済の中に組み込まれ、日本の問題点を共有している。経済の低迷、1億総中流社会の消滅、少子高齢化、不安定雇用などである。今後沖縄はGNP神話という既成価値観から抜け出し、自らの生活基盤の価値を見つめ直さないといけない。それは金武湾闘争の中で語られた「海と大地と共同の力」、「生存権」という言葉の意味をとらえ直すことから始まると考える。
沖縄振興開発計画の流れ――カンフル剤効果
金武湾闘争とは、政府が海洋博で海を「賛美」する一方、金武湾に巨大石油備蓄基地を計画し、そのために湾を埋め立てたことから始まった。ここで、金武湾を埋め立てた、復帰前・後の時代の流れを押さえておく。
1960年代、日本は外国の石油資本が入ってくるのを規制していた。しかし、沖縄を日本に返還しようという話が浮かび上がったころから、国際的な石油資本が沖縄に注目しはじめていた。沖縄がもし日本に返還されるならば、返還される前に沖縄に足がかりを作ろうということであったと思われる。沖縄島東海岸にガルフ、エッソ等の石油業界が進出を始めた。日本はそういう進出は好ましくないという勧告を出したが、琉球政府は石油企業を受け入れた。松岡政保主席時代に本土との経済的格差是正の観点から石油企業を中心にした外資導入政策が打ち出されていた。しかし、行政計画であり、一般市民には関係がないこととして計画作成時に案の公表も意見聴取もなかったのである。
屋良主席になって「沖縄長期経済計画」が練られ、1972年復帰時に策定された「沖縄振興開発計画」へと引き継がれた。その中核は金武湾・中城湾の大規模埋立てと石油企業及びその関連企業誘致にあった。つまり琉球政府の構想を屋良知事も踏襲したのである。当時、高度経済成長に陰りがでていたにもかかわらず、石油は重化学工業等の基礎であるとして、まず石油備蓄基地(CTS)を作って、次にコンビナートのタンク群を作り沖縄を工業地帯として発展させようとした。
西海岸は観光、東海岸は工業地域と考えた。東海岸に位置する金武湾では、1972年当時、すでに石油備蓄基地(CTS)のための埋立てが進行していた。しかし、当時、地域の開発について住民に意見や希望を聞くことなく、日本政府と琉球政府(復帰後は沖縄県庁)は情報公開もせずに地域ボス(村長や漁協長等)に図って進めていた。
実は、開発計画は60年代後半から次々と出ていた。大石油コンビナート建設計画は琉大教授・久場政彦さんらがつくった報告書の中にもある。沖縄は石油産業が有望で、東海岸大型タンカーが停泊しやすい地形であるなどと、大工業地帯建設の夢が描かれていた。
当時は、「雇用対策」という建前もあった。復帰直後、米軍雇用員が大量解雇され、新たな雇用機会を作るために工業立地が必要と言われ、CTSは雇用を生む優良企業のように言われていた。
その一方で1973年8月に沖縄県は東京都公害研究所に石油備蓄基地の設置が環境面でどのような影響を及ぼすか調査を依託し、報告結果を受け取っている。その内容は「石油備蓄基地は沖縄の美しい海を汚すので、もし大規模に立地すれば取り返しのつかないことになる」というもので、既にある備蓄に対しても、今後の新たな石油基地に関しても反対する内容であった。このような住民にとって判断基準になる情報を沖縄県はひた隠しにしていた。これを金武湾を守る会は東京大学の自主講座の情報で知って、県を追及したこともある。
金武湾の埋立て計画は、当初1000万坪で石油備蓄2000万キロリットルの膨大なもので、その情報も、通産省の外郭団体である日本工業立地センター及び「国際工業を誘致するための臨海工業地造成について」(琉球工業連合会)という報告書に明らかである。東海岸の工業開発のため、福地ダムを作り、火力発電所を設置することも書かれている。なんと金武湾の埋立地に原子力発電の計画まであった。これらの情報を沖縄県は決して住民に開示せず、追及されて認めた。その報告書には、安上がりな沖縄の浅海を埋立て、工業用地を作るのが得策のように書かれている。建設コストの比較であり、決して沖縄のために考えていたわけではない。
このように金武湾CTS計画がまず先に立地した。しかしそれに続く関連企業の進出はなかった。工業地域になるには、製造業界の利便性など立地条件が課題になる。つまり商品搬出機能や市場の近接性、豊富な水・電力等の諸条件が必要で、沖縄にはそういう条件はない。糸満に松下電器が工場を設置する案があったが、条件が整わなかった結果、計画中止となった。復帰後、製造業は伸びていない。
復帰後さらに続く沖縄振興開発計画
ところで本土各地で敬遠される油の汚染源、CTSのような企業は沖縄に来るメリットがある。そして企業・政府は一体となって沖縄に押し付けてきた。沖縄側には、復帰後をどのように構想していくのか、という構想の誤りがあり、それが様々な開発計画と住民の考え・価値観との違いを露呈させてきた。住民から見れば生活基盤を破壊して生業の場を奪うことは認められない。しかし、土木建設業界等からは「振興開発計画」は、金の効果がある。一種のカンフル剤みたいなものである。CTS計画、中城湾整備計画、国体関連施設計画と、どこかに何かを作ることが目的で、何らかの計画を提案すればお金が落ちる。落ちたお金が本土企業に還元されるにしても“おこぼれ”が県内に落ちる。金が落ちている間は何とかなり、なくなったら次の計画を考えるという連続が見て取れる。その最初の計画がCTS計画であった。政府財政依存による開発優先政策は歴代県政に引き継がれている。ただし、それを克服しようとする大田県政では「沖縄国際都市構想」を自力で考え作ったことはあったが稲嶺県政以後、放棄されている。基地経済に代わる新たな「自立経済」の構想は今も問われている。
第2章 安里清信さんの思想
沖縄は既に自立しているVS自立を邪魔し破壊しようとする国家
安里清信さんの主張はダイナミズムにあふれていた。「沖縄はすでに自立している」。
戦中・戦後、“焼け野が原”であってもそこで生きてこられた。海と大地を活かし「共同」性を発揮すれば、人々はみんな生きていけると。「海と大地と共同の力」により「生存権」を享受できるシステムが機能しているのが沖縄の地域なのである。沖縄の既に自立し自律的に生活できている地域に対して、邪魔し破壊行為をしているのは国なのだ。「生存権」を踏みにじるな。沖縄人の主体的な生き方を邪魔するな。これが安里清信さんの主張である。
よく知識人が言う経済の「自立」を目指したいとか、こういう条件が備われば「自立」できるといった発想にも問いかけを行っている。「既に沖縄は自立・独立している。それを邪魔し、破壊しようとするのが米軍基地であり、それを固定化しようとする日本政府である」。国・県の地域破壊による影響が大きい。戦争後、人々は魚介類によって生存が保障された。地域自体の海・大地が健康であればどれだけ「豊か」なのかと安里清信さんは問いかけている。以下、安里清信さんの言葉を思い出してみる(直接のお話、記述から)。
屋慶名の人々は農業の合間にはよく「海アサリ」に行った。長老たちはみな海を大事にしていて、潮のぐあいを見て、付近一帯の女たちも連れだって海に行った。モリ、水鏡、ザルを背負って、30人くらい一緒に行った。海人草はサントニ(回虫駆除剤)の原料になるので探ってきて業者に売る。ひもじければ海に行けばよかった。かかとで砂をグルグルとすると車エビが群れをなして湧いてくる。それを生のまま食べた。潮が引くと、逃げ遅れた魚などがくぼみにたまっている。干潟は子どもにとっては憩いの場。紋甲イカ、クジラも流れてきた。潮が満ちるとカニをもぐって捕まえた。生モズクの最適地と太鼓判が押されていた。その理由は北風が当たらないという点、そして海水が清らかであるという点で、知念、泡瀬、金武湾、大浦湾が最適地であると水産試験場は指摘していた。
ハマウリー(浜下り)は盛大で、人が集まって、鍋で貝、磯のものを炊いた。いたるところから人がきている。互いに交流が始まる。健康を回復するために来ている人も、デートのカップルもいる。海は全ての人を育てる役割を持っており、“海は人の母”である。
干潟は生態系のエネルギーの集積所で、ここで大きくなったエビが外洋に出て、孵化した小さなエビがまたこの砂に戻ってきて大きくなる。(生態系)自然が維持されていく。
金武湾は白イカ漁の本場だった。一軒ごとにみな網をもっていた。“スク(アイゴの稚魚)ドーイ”と誰かが叫ぶと皆「すくい網」をもって駆けてきた。ほとんどの家庭がそれで1年分の蚕白源を手に入れることができた。チクラ(ボラの稚魚)も跳ねていた。人々は総出でつかまえて、屋根の上に広げて天日で干した。
平安座島には「ナンジャ岩(銀の岩)」がある。浜比嘉島の人々は周囲の海を「ジングラ(銭蔵)」と呼ぶ。“海が銀行”である。戦争で家が焼けて、家屋を再建するためには、海で採った魚を漁業組合に入れ、そのお金で材木を買った。
伊計島はイチガツー(鰹)の名所。金武湾の入り口から入ってくる鰹を、網を仕掛けておいて3000キロぐらいとった。それを伊計の部落全体で処分する。3分の2が漁民のもの。3分の1が売上金を部落に納めて子供の教育などに使う。モズク漁もある。自給自足はまずは自分たちのための漁獲を得ることが基本なのだ。普通、2人でサバニ漁をやるが対象によっては1人でやる。白イカなどは1人でもやった。だから船は小さい。
今は漁業権が設定されているが、昔は海には境界線はないから、津堅島の漁民たちも慶良間、宮古に行った。巨大漁船団で乱獲するのではなく人間の身の丈にあった漁業をしておれば漁業権を設定する必要はないはずだ。各地域の漁民は互いに知り合いであり、今の漁業権を超えて互いに夏冬場所を共有して使用していた。今は漁業権が設定されて「ウミアッチャー(海歩く人)」たちも小さなところに閉じ込められている。もともと海には線引きなんかできない。
屋慶名は牛の名所で「徳之島トウクヌシマー」や「与論牛」などを屋慶名でまずは闘牛用に育て、後に阪神で売られ神戸牛となった。青い草を食べ運動をしっかりさせており肉質がいいからだ。
宮城島は農業も盛んだった。東海岸の漁業の一大拠点は津堅島で、津堅島の漁業が滅びると東海岸、ひいては沖縄の漁民が滅びるのと同じであると言ってよい。津堅島には大きな干潟があるので、台風があろうが何があろうが、そこにいけば生活ができるという好漁場をすぐ眼の前に持っている。海岸にザルを置いて一日中生モズクをとっていた。シャコ貝、巻貝、トビイカなど、島のまわりには豊富に魚がいた。そして漁民の気風も非常に剛気であったのは物質的な生活基盤がしっかりしていたからでしょう。(安里さんのお話終了)
以上、安里清信さんが述べられた「豊かさ」を具体的にイメージできるように記述してみた。安里清信さんは農産物、漁獲類、牛、家畜、人のつながりの中で人々が成長していく。人間らしい感性を育むことをとても誇り高く、お話しされた。また名波さんという方が甥の健一さんという目の見えない方とともに安里さんの自宅前の道を農作業に通われる様子もたびたびお話しされていた。健常者のみならず障がい者も自立する基盤があった。老人クラブ「かりゆし会」の農産物展示会も盛んであった。まさに「地域は既に自立している」ということが実証されていると言えよう。そのうえで不足している分野のために金銭の出番があるが、基礎的な基盤を見据える視点こそ大事である。通常の経済論からは見えないことが実は尊いものであることを資本主義経済、GNP主義者は見落としてはいないだろうか。多様な人びとが既に自立できているのにそれを壊し、GNP指標の市場経済に移行する必要性があったのだろうか。「自立」を売って買ってという購買の「量」で測る考えのみに陥ってはいないだろうか。
しかし、すでに在る基礎を破壊して地域から住民を追いだし、都市で従属した生き方に仕向ける攻撃は今もつづいている。金武湾闘争ではCTS計画だが、白保では飛行場建設であり、辺野古では米軍基地計画であり、高江ではヘリパッド実はオスプレイパッド建設という計画で、国策という大義をふりかざして、住民の生業を破壊し、国家に国民を従属させる手法・発想は全く同じ根っこであり、復帰後、ずっとそのような国策の大義対県民の生存権・人権の闘いが続いているのである。我々沖縄ではその闘いを一刻でも手を緩めてはいけない。
サブシステンスという考え
世界中の各地で、特に先住民の住む地域をグローバル資本主義経済の中に組みこむ経済理論に対して、この地で生きていく権利があると主張せねばならない。地域で不安なく、生き生きとした生活を営むことはできる。これはサブシステンスという考え方である。
経済成長と生活の豊かさは決して比例関係にはない。
現在、原発事故で経済成長が高まったといわれている。事故前にはほとんど野菜を買わなかった人たちが、放射能汚染を心配し、地域の野菜を食べなくなった。しかし、以前は「野菜の半分は近所・親戚からもらっていた」とか、「事故後、野菜や果物を買うようになっている。月に2~3万円は負担が増えた」と福島やその近辺の方々が証言している。もらう野菜は無償だからGNPに反映されないが、買えばGNPが高まる。結果的に原発事故後、経済成長したのである。ではGNPが高まって豊かになったのか、誰もそう思う人はいないだろう。
ところで、多くの人々は、経済は成長しなければいけないと固定観念のように考えている。GNPこそが信頼に値すると思っている。しかし、大切なのは決して経済成長ではなく、無償のやり取りを含めた。安心して暮らせる生活の営み、生業にある。
かつての金武湾のように、伝統的な農漁業を中心とする自給経済(サブシステンス・エコノミー)の中で「持続的」な生活が営まれてきた。しかし、そのような地域も資本主義的な開発やグローバル化の進展に伴い、また近代化による貨幣経済の浸透で伝統的・持続的な営みが難しくなっている。それに対する攻撃はすさまじい。その結果、都市で就職先を探す人びとの不安は大きい。まして沖縄の狭い地域の中で住民は増加の一途をたどっている地域では、作った就職口では賄うことは難しい。
ところが、金武湾のような地域の生業・就労の場があれば、かなり基本的な生存は可能である。その喪失によって、いまだに、沖縄の雇用問題の解決の糸口も見い出せていない。多くの若者の生活は不安定で、非正規雇用で低賃金である。学卒後の「初職」では正社員になるのは三割に過ぎない。就職不安は30代、40代にもひきつがれている。
さて、改めてかつての金武湾、そして今も離島の各地に点在して残る豊かさを活かさねばならない。そして金武湾を蘇らせる闘いをしなくてはならない。東海岸の辺野古、高江の生業を持続させる意義を自覚しなければならない。それはとりもなおさず、現在、国から仕掛けられている攻撃をはね返すことにつながる。
サブシステンスとは耳慣れない言葉であるが、とても重要な概念だと考えるので、少しくどいが説明させてほしい。マリア・ミース(ドイツの社会学者、Maria Mies)は「人びとの営みの根底にあってその社会の基礎をなす物質的・精神的な基盤」という。ミースは地域や女性の自律する力の確保と向上を目指し、サブシステンスを近代産業社会に対するオルタナティブな生産・生活様式であると位置づけるとともに、それは生活の楽しみや幸福感や豊かさを示す概念であるとも定義している。また自家消費のための生産・消費活動のみならず、ローカルな市場に販売するための食糧生産や販売活動も含まれ、ローカルな地域の内部において生産-流通-消費を完結させ、なおかつ自らの手でその経路をコントロールできる、という広がりを持った意味あいで、サブシステンスを定義している。そしてこのようなサブシステンスは、グローバル化などに起因する。さまざまな社会的・地域的な圧力に対して対抗する力を生み出す場のひとつとして捉えられている。
自給自足的な営みの意義を問うことで見えてくる「豊かさ」を考える。サブシステンスを支える主体性について考えてみたい。
安里清信さんの立ち位置・戦争体験がもたらした国家からの独立思想
安里清信さんが「住民が自分たちの住んでいる土地を支配しているか否かは、その地域社会が存続しうるかを判断する上で、もっとも主要な指標である」というアメリカの文化人類学者の言葉を言われた。これは自決権に通じると思えるが、安里さんはそれを「生存権」と表現された。そして自決権、自律権、生存権は実は根っこは同じ独立心から発するものであると考える。
安里さんが裁判の中で、証言台に立たれて身振り手振りで裁判長に向かって語られた様子が私の脳裏を離れない。安里清信さんは、軍隊に徴兵され、朝鮮を経て、中国で悲惨な戦闘を経験されるが、再度朝鮮に行かされ敗戦となった。しかし、沖縄に戻ると妻子は亡くなっていた。証言台から言われたのは「背に妻、胸に子、左右に戦友や……。十字架を背負って、苦悩して生きてきた私……」と。
戦争で妻子を失い、苦しみぬいた生活の中から、それでも生活の営み、地域の人びとに乞われて、二度と就きたくないと思っていた教員になった。地域の学校建設、と言うものの文字通り土木工事、校舎建設から学校再建を成し遂げ、焼野と化した戦場跡を開墾し、住民の生活基盤を立てなおしてこられた。そこに踏み込んできた行為が海の破壊であった。海を埋め立て、埋立地の材料には海底の砂地を採取、それにより海は汚泥化、棲みついていた魚介類は逃げる。海中道路によって湾内の流れが変化、各地に浸食作用を発生させた。国家こそが沖縄の自立を阻んでいる。それを認識された安里清信さんは、屋良知事を含めて多くの教職員が持っていたような「国家」が住民を守るという幻想を持っておられなかった。だから、屋良さんと安里さんはかつて、同じ教職界のリーダーであったが、まったく別の思想に向かっていった。安里清信さんは戦争・戦中・戦後体験から多くを学んでいた。実際に起こっていることを真正面に見すえ、考え抜く、本質を探る、それこそが安里清信さんから我々が学ぶべきことである。
そして、安里さんは個々人の主体的な生き方についても口酸っぱくおっしゃっていた。「CTSの勝利というのは個人個人が石油と戦争について、核について、国策の中味について考え、それに対処していく決意が生まれなければ、本当の勝利にはならないと思う。」個人個人の自覚の重要性、そのために守る会には代表を置かないこと。自覚的生き方をしてほしいと。こうもおっしゃっておられる。「(戦争で)20万人の犠牲者を背負って、体験のなかから世界を見抜いて、世界に呼びかけていく責任を、いま沖縄人が問われている。」「一人一人の沖縄人の歴史をなしくずしにしてしまうようなことがあっちゃいかん。」沖縄人としての世界の中で果たす役割まで述べておられる。国家の住民に対する権力支配構造との闘いについて、沖縄人は世界に率先して発信すべき内容を持っていること。それを伝え、世界の民衆に貢献する役割を持っていること。
さらに沖縄の将来の在り方についてこうおっしゃっておられる。「これからの沖縄が生きる道は、底辺から“自分たちの持っている良さ”を発見して、つきあげていくところにある。」「今はアメリカに支配された形だが、しかし、沖縄の未来というものはまだ未知数だ。世界情勢を見れば、いつどうなるか分からない世界だと考える。だからこそ、いついかなる“世”に変わろうと、沖縄人自身がウチナンチューとして“生きうるだけの強さ”を、普段の生活の中で厳として“養って”おく必要がある。」
「自分たちの持っている良さ」とは何か。それは今まで述べてきた「豊かさ」であろう。そして、「ウチナンチューとして生きる強さ」とは何か。その強さを「養う」とはどういう方法で可能なのか。
「養う」側面は行動の中にある。「金武湾を守る会」の県庁行動は実に100回にも上った。多数の住民が一日丸ごと家をあけて那覇にバスで向かった。那覇の闘いの場で「守る会」の県・国への訴えを直に聞く。逆に県側の意見・態度を見る。その双方をすり合わせながら自分の考え、立場を明確にしていく。住民は闘争の現場で、“養”っていった。またその基盤は日常的にももたらされていた。農産物展示・試食あり、失われた行事の復活、チクラマチの復興、うた・踊りのイベント等。野菜つくりとその商いをしておられた大城フミさんは、いくつもの琉歌を作り、みんなで歌った。歌は機動隊を攻めていく武器にもなった。そしてそれらの共通体験が住民をさらに元気づけた。文化活動は常に連帯感を強め続けた。これ程、高度な質を備えた大衆運動は、金武湾闘争以外ではまだ見たことがない。「養う」関係性はあらゆる場面で発揮されていた。これが個々人の主体性を高めたのである。
「ウチナンチューとして生きる強さ」は沖縄の現実、国家との関係で生じている問題やそれを乗り越えていく経験、考え方を深く掘り下げて、世界に発信し、世界の真の平和に貢献する自覚的生き方に向かって歩み出すことであろう。沖縄の薩摩侵略以来の400年の歴史、あるいは戦争・戦中・戦後の生き方、基地問題、自衛隊問題、金武湾、白保、辺野古、高江の地域闘争など、いかに表現していくか、それぞれに問われている。
今後も国家の沖縄への攻撃が止む見通しはないのであり、金武湾闘争が人を育んだように、攻撃の現実から目をそらさないこと。沖縄には自立する基盤があり、自立できると確信する人々がいる。国家に振り回され、一方的に支配される存在から主体的に国家に立ち向かう、誇りをもった生き方に向かいたい。
侵略と対抗領域
沖縄には行政の末端組織として区がある。行政の通達や取り組みを地域の中で直接住民に伝え、また業務も行うもので、一種の行政の外部委託組織である。
例えば、キビ刈りの時の農地の刈り入れ順を決め、ユイマール(共同作業)の手配や調整を行う。区長は行政からの任命制で、その地区が開発をめぐり反対運動がある場合などは、行政から任命された区長が、開発賛成派に有利なように手続きや順番を決めたりする。そこで、金武湾を守る会では公正な行政運営を求めて自分たちで区長を決め、例えばキビ刈りなどを自主的に運営した。その結果当時の屋慶名には2名の区長が存在した。
区長を決める権限がなくとも、必要ならば自分たちで区長を選ぶ。行政の上からの流れに対して、住民から湧き上がる自主・自決の思想を対抗させ、実質は行政の制約を乗り越える自治体制=対抗領域を作っていた。伊礼門区長が扱うキビの数量は、行政が任命した区長よりもはるかに多くを、また援農等を活用して農家に負担なく処理した。
第3章 金武湾闘争は今も続く――金武湾闘争から白保、辺野古、高江への闘いへ
金武湾闘争は次々と新しい運動に点火してきている
今、沖縄の現場の闘いを担いっている方には中高年が多い。その多くは実は金武湾闘争時代からの担い手たちでもある。人によっては闘病生活等で中断を余儀なくされる時期等をはさみながら、しぶとく継続している。30、40年金武湾闘争から連綿と闘いが続いているという気持ちである。辺野古、高江で互いの話にも出たりするのが「金武湾闘争からずっと同じように闘いは続くねー」と。復帰後、あいも変わらず、年中である。
沖縄の地域の生存基盤の破壊、生活者を追い出し、国策に従わせようとする攻撃を許すわけにはいかないのである。本質が金武湾闘争と同じだからである。
金武湾闘争の認識に立てば、あの時上げた拳は降ろす状況になっていない。復帰、40年の歴史、闘争の歴史である。金武湾闘争からの継続者、その白保からの継続者もおられるし、辺野古から参加された方々もおられるが、崎原盛秀さん、伊波義安さん、新崎盛?さん、弁護士さんら、池宮城紀夫さん、三宅俊司さん、照屋寛徳さんら、宮城節子さん、照屋房子さん、平良修さんご一家、高良勉さん、豊見山雅裕さんらの市民・文化人。城間勝さん、当山栄さん(故人)らの「金武湾闘争労働者連絡会」の方々、有銘政夫さんら「中部地区労」の方々は金武湾闘争からの同じ顔ぶれである。多くが「沖縄平和市民連絡会」等に参加し現在も運動の中心におられる。私も一時がんを患ったが回復し、闘いに復帰できた。地域の基盤「生存権」を守る闘いは金武湾、白保、辺野古、高江と新たな国の押し付けが増したことで、新たな参加者も加わり据野は広がっている。金武湾闘争の特徴は、沖縄の復帰後、ずっと闘い継がれていることである。
また、海を壊しての辺野古新基地建設、ヤンバルの森を破壊しての高江ヘリパッド建設、日米安保条約を盾に強行配備しようとしているオスプレイ、いずれも沖縄の自立基盤の破壊のみならず、沖縄から、飛び立つ軍事力によってアジアの人びとが生命と生活を破壊される、その加害性を黙認しない闘いでもある。アジアへの加害行為を止めさせていかねばならない。
金武湾闘争の中から生まれた運動として1988年まで継続された「琉球弧の住民運動合宿」運動を紹介しておきたい。第10回で閉じた「琉球弧交流合宿」運動を列挙する。金武湾闘争から産声を上げたこの活動も各地の運動を活性化する役割を担った。
・1979年8月24~26日:第1回目(金武湾の屋慶名と照間の浜)
・1980年7月26~27日:第2回目(奄美大島宇検村平田)
・1981年7月25~27日:第3回目(西表島。安里さんも参加されたが翌年死去)
・1982年8月22~24日:第4回目(宮古島・与那覇前浜)
・1983年8月27~29日:第5回目(石垣島・白保)
・1984年:第6回目(石垣島・白保。金武湾漁民と白保漁民の交流もあった)
・1985年:第7回目(読谷村。金武湾闘争関連参加者は減る)
・1986年:第8回目(伊江島)
・1987年:第9回目(読谷村)
・1988年:第10回目(那覇市・教育福祉会館)
安里清信さんは西表合宿にも参加され、「綱引き」には力を込められておられた。石垣金星さん他、西表の方々と島の自立、将来像について議論に花を咲かせておられた。そして安里さんは1982年10月19日死去された。その後、運動の流れの中心は「白保の海を守る」闘い、「一坪反戦地主会運動」等に向かっていった。そして現在も辺野古、高江、オスプレイ……。運動・闘いは日本国家が今のスタンスである限り、沖縄は永続的闘いの現場であろう。誠に悲しいことである。早く人間らしい営みの場として取り戻せるよう「沖縄人とし生きる力を養うことが大事です」(安里清信の言葉から)。
「インテリがするように机の上で議論」しているだけでは見えない、という言葉を安里清信さんから頂いた。それを自戒のメッセージとして今後も大切にしたい。金武湾闘争とは歴史の彼方にあるものでもなく、日々の闘いそのものの中で息づいている。
第4章 まとめ――沖縄の「自立経済」像の提案
沖縄地域に内在する“豊かさ”を“対抗経済”の土台に
GNP指標でみると沖縄の経済は脆弱である。復帰前には殆どの人がサブシステンス、生業の基礎が備わっていた。沖縄の根っこにある良さ=価値を大事に基礎に置きつつ、不足部分を外部から補う、という発想に立てないだろうか。ある面では、海と大地は今も残っている。それを活かす共同の力という共生の在り方を意識化し、拡大していくことで我々の生存基盤を復興させることである。サブシステンスを基礎に、沖縄の経済を再構築する。国家からの独立精神を培い、「海と大地と共同の力」により「足るを知る」ことを主として据える。そして競争原理は従属的に位置づける。不足部分の補填を外部から自律的に行う、という地域経済の発想である。
今までのように日本経済の後追いを続けることで、沖縄の未来は開けるのだろうか。日本はグローバル競争市場が前提で米金融界が主導し、その影響は世界に波及しつつある。しかし、金融資本のもたらす「強欲」への反発もある。とはいえ、金融資本主義者の矯正は簡単ではない。したがって簡単に金融市場に翻弄されない立ち位置をつくることが必要である。金融資本主義と一線を画するのである。
米国は自国の農産物から軍需品まで世界市場で売ることが戦略で、そのために軍事上の「抑止力」論をかざし、グローバル市場の拡大を目指している。日本国家は、米主導の方向に際限もなく巻き込まれている。豊かさをGDP(国民総生産)という単一指標のみで計り、高収入=進んだ地域、低収入=遅れた地域という色分けがなされた。沖縄振興開発計画は「進んだ」日本に対し「遅れた」沖縄を前提に「格差是正」による資金投入がなされてきた。だがその方向では地域経済システムが破壊され、多くの人が就業機会を失っている。
安里清信さんは「(漁業などの)こういった自然にできた流通機構を有効に整理していけば、農業行政もきちっとしたものになる」と言われた。沖縄は亜熱帯で広大な海があり、皆が生きられる場所なのである。価値観を見直すヒントは、70年代に名護市が提唱した、沖縄は、「遅れ」ておらず「逆に」豊かであるという「逆格差論」にもある。金武湾闘争にもサブシステンスの考え方にもある。
現在の沖縄でその視点に立って考えると、グローバル市場経済と一部はつながる場面があるとしても、基本は沖縄内部の地産地消、サブシステンスを軸にすえながら、外部から不足を補う経済を組み立てて、外部に振り回されない生き方ができるであろう。外部とのつながりは、観光産業、感性産業、健康産業の得意分野で収入を図れば良い。つながりつつも「海と大地と共同の力」による生業を成り立たせて基本的な就業者を増やす。
対抗経済――共生分野と競争分野
数年前に訪れた、エコツーリズム発祥の地コスタリカでは協同組合が設立され経済的自立を模索していた。数百件の農家でチーズ工場が運営され、チーズ生産の上澄み・廃棄物は豚の飼料で、養豚場の汚水は池で沈没を繰り返して川に流し循環させ、女性たちは作業所を設け、森で生息する動植物をデザインした工芸品を製造、その場所だけで販売するなど、森を守れば仕事は受け継がれるという。観光産業では地域の生態系を熟知した登録ガイドが行い、地域に収入が落ちる。域内の動植物の調査分類に住民が半専門職として従事し地域資源の維持と生計を支えている。
日本では、新自由主義政策の結果、利益追求には適さない医療や介護や教育等の分野にまで競争原理が支配的になっている。沖縄でも「共生」分野にまで「競争」による仕組みがみられる。最低限の生活保障をすべての人が享受できるようにすべきである。
沖縄の基礎が持つ豊かさを活用すれば、沖縄の全ての人の健康で文化的な生活は可能である。具体的な「外貨」獲得策としては、中国では刺身・魚介類の需要拡大が見られ、沖縄近海の排他的経済水域200海里で取れた鮮魚を、中国に水揚げできるようになれば漁業は伸びる。また東北大震災後、食の安定性に関心が高まっており、沖縄の農産物は評価されるだろう。
抗酸化物質の農産物を「健康産業」に活かせる。歌・踊りや染め織り等の「感性産業」、観光産業は今後も有望であろう。医療・福祉現場の雇用の安定策も重要である。地産地消、その生業に厚みをもたせ、「自立」的基盤への国の妨害・破壊をやめさせることである。つまり、それこそが最も大変だが、やらねばならない闘争である。
一方では、「世界のウチナンチュー」とのネットワークを生かした交流事業も有望であろう。彼らは沖縄人としての生き方の発信を共に行う仲間・主体である。そして沖縄の地域自体を、彼らも含めた共有財産として次世代にまで特続的に活かす。「海と大地と共同の力」は人びとに希望をもたらす、それに向けた行動が問われている。
(琉球歴史研究会、うちなーぐちティーダぬ会主宰、琉大教員)
(『けーし風』№76・201209)
崎原盛秀さんインタビュー
現在に引き継がれる「金武湾を守る会」の闘い
この七月、崎原さんのご自宅の近く、篤志によって維持されているという、「金武湾を守る会」の資料を収蔵する事務所でお話をうかがった。少し高台に登れば、与勝半島が見える。海中道路は観光スポットのひとつかもしれないが、一歩踏み込めば、今もなお人々の闘いの息づく場所であることを教えられた。闘いの記録『金武湾を守る会闘争史』はほぼ完成とのこと、刊行が待ち望まれる。インタビューからも受け止めていただけるようにご本人も矍鑠、金武湾反CTS闘争は依然として現在形である。貴重な資料、記録『闘いの足跡Ⅰ・Ⅱ』をいただき、当時の写真なども拝見しながらお訊ねした。
― この金武湾周辺は、非常に豊かな海だということが安里清信さんの本(『海はひとの母である』晶文社)にも書かれています。私は東京育ちなもので、実感としてわからないのですが。
崎原 まだ金武湾が破壊されないときの海は、豊かでしたね。それから二〇年余り、汚染も進みましたが、最近では海が再生してきて、四月になると人々が浜下りして、海の幸がいっぱいとれます。やんばるでも見られない光景ですね。とくにスヌイ、テングサ(このあたりではそう呼ぶ海藻で、こりこりして酒のつまみにも良いものです)があるところとか、知っている人は知っている。やんばるからもテングサとか、海豆腐といって海藻でところてんのようなとうふをつくるのですが、その材料になる海藻とか取りに来る。どこの海でも取れるというわけではない。今でも金武湾はそういう意味では豊かですよ。モズクを採って歩く人もいますが、ほとんどテングサ採りですね。春先、大潮の時期、月に二回は確実に海は人でいっぱいになる。その間に中潮もありますので、一週間に一回は海は人でいっぱいになる。四月、五月はそんな状態です。海藻はさんごのかけらに生えますから、慣れている人は岩場を探して歩いていますね。海中道路の右側は砂地ですが、そこに水の流れができていて、水路みたいになっている。干潮になっても流れが速い。砂をかぶってテングサもあまり見えないけれども、掬ってみると、たくさん出てくるんです。行くたびにかごいっぱいとれますから、自家用で一年分まかなうだけでなく、近所に配ったりもします。
少年期のヤマト体験で沖縄差別を知る
― ところで、崎原さんは、お生まれは何年になりますか。
崎原 一九三三年一一月、七十六歳になります。西原町生まれです。小学校の三年までは西原にいました。八人兄弟でしたが、私は一九四二年頃、小学校三年のとき、子どものいなかった大阪の叔父にもらわれて、育てられました。まだ幼く物心がつかない時期でしたので私が行くということになりました。沖縄では「ヤマトかい、いちゅん」と言って、なにかすばらしいもの、珍しいものがたくさんあるというような話を聞いていました。その日になって、末っ子ですので、親も手放したくはなかったのでしょうが、迎えの人が来ていますので連れて行かれました。
小学校六年のときに敗戦を迎えました。八月敗戦の前に、叔父(おやじとよんでいましたが)が、牛の密殺をしたということで―つぶした訳ではなく肉の販売をしただけですが―、刑務所に入り、栄養失調で、獄死した。だから八月敗戦の頃から六年生で中退し、学校に行くことなく、煙草を巻いて売ったり、買出しをしたりして叔母と一緒に生活をしました。私がほとんど稼いでいました。そのうちに寿重工業という泉大津の会社の職工の人たちに雇い入れられました。会社でなく、職工さんたちが金を集めて、私を雇って、昼飯を炊く、買い出しに行くとか、用足しに使われた。あとは紡績工場に入ったりして、一九四六年一二月に沖縄に帰ってきました。叔母が、「こんな小さい子を働かせるのは大変だ」というので、沖縄に帰されました。帰ってみると、母親は戦争で亡くなっていました。貧しい家でしたので、兄たち五人のうち四人はパラオに出稼ぎに行っていた。日本の植民地政策によって南方に労働力として供出されたというところではないかと思います。私は、兄に引き取られました。そこで中学、高校、大学までいた。
そういう環境で育ち、いろいろ考えさせられました。小学六年のころ、おやじが刑務所に行く前、岸和田署に繋がれているときに面会に行き、だんだんやせていく姿を見ていた。刑務所に入り二ヶ月にもならないうちに、やせ衰えて、死んでいった。裸で、毛布一枚を与えられ、コンクリートの中に閉じ込められていた。岸和田では先生にも相当いじめられた。沖縄からきたばかりですから。教科書を朗読させられると、「ちんちろまつむし」が「つんつろまちゅむし」になる。一回読むと教室中が「わーっ」と笑う。二回目には先生も面白がって聞いていた。松田先生という女の先生で、いまだに忘れられないですね。三度目に「もっと読め」といわれて敢然と拒否した。それですんだが、その時にすごく異様な感じ、差別を感じました。だから小学校の間、近所に同級生がいなかったこともあって付き合いもほとんどなかった。近くに朝鮮部落があり、成田くんと金くんがいて、この2人とは話をしていました。小さいながらにも、色々な意味でウチナンチュウとして差別されているのを感じた。叔父の死を見て、「おとし入れられた」という思いをもった。何かに対する反発、反骨心みたいなものをわりと持っていました。
沖縄に帰って、小学校中退だからということで中学を一年落とされました。同級生は高校に行っていたのですが。学生のころはほとんどバイトでした。ガーデンボーイをやって米軍の生活はよくわかっていました。メイド(家政婦)さんが各家庭に一人ずつはいた。今の那覇の新都心のあたりです。うらやましいというよりも、なぜこんな生活が違うのか。アメリカ人は、広いきれいな家に住み、自分たちは元の住んでいたところにも帰れない。自分のところには、米軍の兵舎がありました。同じ西原村内に、避難民として八か所の部落から集められている。畑は原始共産制のように村が、家族の人数に合わせて、割り振りました。とにかく、食べるために芋をつくって生活をしなければならない。そういう生活状態でしたから、米軍の広大な住宅地を見て、沖縄の人たちがいじめられているのを感じた。夜になると、米兵が各家庭で造っている芋焼酎を買いに来ますが、それを口実にして「女あさり」の目的もある。青年たちは、よく「もあしび」をしましたが、これは村の警備でもありました。それでも遠くの畑に行く際になど、事件は何度か起きました。常に危険な目に直面していると感じていました。
復帰運動から金武湾を守る会結成へ
高校、大学では、沖縄とはいったい何なのか。日本にとって何なのか、考えるようになった。まだ発想として弱いものを持っていて、日本に帰れば解放されるのではないかという幻想もあって、高校生ぐらいから復帰運動にものすごく関心をもっていました。大学のときには、人民党と当時の社会党が結成した民主主義擁護連絡協議会(民連)に興味を持った。一九五六年ころの「民連ブーム」ですね。五六・五七年は土地闘争が大きく盛り上がった時でもあります。その時に運動にかかわるようになった。
― 大学は琉球大学ですか。
崎原 そうです。一九五四年入学、五八年卒業でした。
復帰運動をやっていくわけですが、一九六七年、八年になると反復帰論も出てきて、外資もどんどん入ってくる。大きいのは石油産業です。エッソ、ガルフ、カルテックスとか。なぜ外資が入ってくるのかと考え始めました。さらにそのあとから日本の資本も入ってくる。復帰を前後しての動きに、疑問が一つ一つ浮かんできた。日本には憲法がある、人権が尊重されるところに帰ろうやという。ちょっと待てよ、と。六〇年代後半に色々な情報が入ってくる。学生が、渡航証明書を焼いたりする。なんで我々は米軍の認可を受けて渡航証をもたされるのか?それを認めるヤマトの政府とは何か?そのようにして、実は沖縄を放置したのは日本ではないか?話によれば日本はものすごく繁栄しているという。その一方で沖縄の苦しい状態がある。私たちにとってヤマトは何か。基地問題や復帰運動の中心は基地のない平和な沖縄。六八年には屋良県政が登場しますが、これは、ヤマト世という社会を、何の疑問も持たず全面的に受け入れていくものではないか?幻想を県民に与えているのではないか。もっとヤマトを相対化する視点を持つべきではないかと考えた。復帰運動というよりも、そのことを考え、一九六八年には「反戦教師の会」を組織しました。私たちも復帰運動の流れを汲んでやっていますから、この辺で立ち止まって自分たちの活動を総点検し、自分自身を見つめながら、ヤマトを相対化する必要があるのではないか。そう考えました。
石油基地を作る問題が起こったときに、関心があったので、集会に行ったり、学習会に出たりしました。近くの中城でも石油基地反対運動が始まりました。集会に参加して、石油基地建設に反対することの意味を考え、外資の侵略について考えた。はじめて水俣や四日市などのヤマトの公害の問題も学び、沖縄ではまだまだ知られていないが、ひどい人間的差別が起きていることを知りました。四界海に囲まれた沖縄が海を失うことは生きる展望を失うことではないのかと。そういう中で、沖縄を問い直す、自分自身を見つめ直す運動が六八年ころから七〇年にかけてあって、ますます復帰に対する疑問点が沸いてきました。
一九七三年九月に金武湾を守る会を結成しましたが、もうそのときには人がごく自然に集まってきた。中心は石川市内のアルミ精錬工場(アルコア)の反公害闘争をした、石川高校の先生たちでしたが、宇井さんの東大自主講座との交流もあり、資料をいっぱい持っていました。日本の公害の闘いや実態を学び、環境破壊に対する抵抗意識が強くなりました。
同時に、それは反基地の問題と繋がります。朝鮮戦争でも、ベトナム戦争でも、沖縄の基地から出撃して、他国の戦争に出て行く。沖縄の米軍基地がどういう意味を持っているのか、考えざるを得ない。沖縄戦の悲劇が今でも続いている。これはなぜなのか。これを中学の子どもたちに平和授業で語りかけた。自分自身の学びの旅でもあるんです。沖縄が侵略基地としてあり、基地を返せといっても、日本政府が金を出して米軍にいてもらっている。これは何なのか。
― 当時の教職員会では、日の丸を振って、復帰運動をやったと聞きますが。
崎原 一九六一年くらい、ですね。一九五八年くらいから私も教員しています。六一年までは私立の高校教師でした。六一年に中学の教師になり、子どもたちの家に日の丸があるかどうかの調査をしました。心情的にはアメリカへの反発もあって、日の丸振ってなぜ悪いのか、という気持ちがありました。これに対する自己批判めいたものが六七年、八年ころから出てきました。その中で、復帰とは何かを捉え返していきました。当時、復帰とは何かを子どもたちと話している写真が「アサヒグラフ」に撮られたことがありました。
― 安里清信先生はもう六〇年代後半は退職されていたのでしょうか。
崎原 いや、校長をしていました。安里先生が退職されたのは六八年です。六八年には、主席選挙、立法院選挙、那覇市長選挙という、いわゆる三大選挙がありました。彼は与那城・勝連という選挙区から立候補しました。屋良朝苗のブレーンでしたから。と言うのは教職員会(まだ組合ではありませんでした)で中部(当時は中頭です)の情宣部長か何かをなさっていたのではないかと思います。教職員会が組合になったのは七〇年ごろだったと思います。地域でのものすごい信頼がありますから、厳しい選挙区から立ちなさいということになって、それを受けたのでしょう。その時には私はまだお会いしていませんので詳しいことは分かりません。私はいまの沖縄市周辺で教員をしていました。
安里先生とは金武湾を守る会を作ってから初めてお会いしました。他の人たちは、その地域で先生をしていましたから以前から知っていたようです。
金武湾闘争を振り返る
― 金武湾闘争そのものについて、お聞きしたいと思います。最初にガルフ石油が平安座島への海中道路を作りますよね。
崎原 石垣を簡単に積んで、砂を取って入れて盛り上げてトラックが通れる程度の道路にした。現在のものとはまったくイメージが違う。台風が来たら壊れてしまうようなものでした。それが七一年。場所は現在と同じです。当初、屋慶名の人たちが、海中道路を作るならば、海流の変化が起きますので、今のようには作るなと言っていました。引き潮のときの渡り道をルートにと要望しました。元々潮が引いたときには、平安座から与那城までトラックも荷馬車も人も通っていた。現在の場所に作ったがために海流が変化し、水路ができてしまって、藪地島にも橋を渡さざるを得なくなってしまった。ガルフが平安座に石油基地を作るために、自然を無視して現在のルートにわずか三ヶ月で仕上げました。
― 西海岸は観光、東海岸は産業開発というのは、いつごろからでしょう?
崎原 金武湾開発は一九六七年ころからです。松岡政保琉球政府主席が「本土との格差是正」の観点から外資導入政策を打ち出していました。というよりもアメリカが石油資本を当時の外資規制をかいくぐって、日本に導入する為の足がかりとして沖縄に投資をもくろんだのが真相でしょう。
― 外資と結びついて日本資本も入ってきた。
崎原 エッソが西原町に南西石油、中城村の東洋石油(日本石油)、ガルフが与那城村に沖縄ターミナル原油基地、三菱石油(沖縄石油基地)と入ってきました。用途は米軍への供給です。沖縄はガソリンスタンドのことを「カルテックス」(外資の社名)と呼んでいました(笑い)。
― 七三年九月に守る会結成になるわけですね。東京にいた私も、「石油危機の中で、一年分の備蓄基地を作る」と言われていたことを覚えています。
崎原 世界の石油支配の一環として日本に入ってきた。経済的な支配と同時に軍事的な支配を目的とした。備蓄はある意味では、産油国に対する支配にもなる。沖縄は生産手段を持たないので、企業配置に向けてアメリカ資本の石油備蓄で先導するというのが松岡の政策だったのではないか。
― 第一次振興開発計画については、沖縄内に工業立地も考え、総合的な産業基盤の形成がうたわれた。そのあたりから総てだまされてしまったのかなと感じます。
崎原 第一次振計の誤りをどのように認めさせたかということですが、これは金武湾闘争です。それ以前のものは、全部石油を戦略産業としてコンビナートの配備です。具体的に言えば、格差是正を目標とした外資導入政策、一九七〇年代になって、屋良県政になって、金武湾中城湾開発計画が出てくる。作成は工業立地センターです。これを要請したのが、与那城村。その中身は、金武湾一千万坪埋立計画、石油精製、電力(これには原発も含みます)、石油化学、アルミ精錬です。これがその後の金武湾の開発構想の基本になります。
― 一千万坪と言うのは金武湾のほとんどを埋め立てるという計画です。この恐ろしい計画を運動で押し返した。破壊の被害はこうむりましたが、金武湾は残った訳ですから。
崎原 そうです。金武湾闘争は敗北であると同時に、一面では勝利だった。
― 一般的には、金武湾闘争は敗北してCTSも作られたが、その闘いの精神は残った、といわれていますが、実際はかなり勝っている…。
崎原 ま、どういう評価をするか(笑い)。第一次振興開発計画では「東海岸の開発を行う」と言っているだけだが、その中身は工業立地センターの計画と七〇年の「長期経済計画」。これには屋良政権も関わっています。ここにも石油とか鉄鋼・アルミ産業がある。総てその原型は与那城村の工業立地センターの開発構想です。
住民自治の原則と革新行政の矛盾
崎原 この開発構想を巡って、屋良県政を支える与党「革新」の部分と守る会との激しい理論闘争が出てきます。例えば、総ての大衆運動は革新政党を先頭にしなければ作れないとか、そういう考え方が強い。住民運動は革新政党の指導の下に置かれるべきだという発想がある。とんでもない。地域から起こったところの考え方に基づいて、運動はあるべきだということです。住民運動を無視したところに双方の対立が出てきて、一九七四年二月二二日にもたれる予定だった反CTS県民大会が、中止に追い込まれる。
七三年の九月二二日に金武湾を守る会が結成され、二五日から直接行動が始まっています。守る会は屋良革新県政の金武湾中城湾開発構想の誤りを指摘しました。埋立が自然破壊であり、沖縄の未来をなくすものだ。海は宝だと。沖縄の世論も自然破壊は許せないということになった。世論の高まりが運動の支えになりました。文化人知識人の「一〇〇人委員会」からも自然破壊への警告が出されました。こうして追い詰められ、一九七四年一月一九日に屋良知事の「CTS誘致撤回声明」が出ました。私たちはそこに止めを刺すために「県民大会を持とう」と民主団体に呼びかけたところ、「革新政党を交えたものでないとだめだ」と言ってきた。私たちの基本は、住民運動はあらゆる思想信条を超えたところに存在するものであり、一人びとりの個の運動の主体的な結合体なんだ。それに政党政治という思想が入ることは住民運動の本来の意思ではない、政党は別の形で支えるべきで中心に位置するものではないと主張しました。
― これは金武湾闘争の大きな教訓ですね。
崎原 そうです。この県民大会を、政党と労組団体で私たちと別に作ろうとした。これでは分裂になるから、反公害の認識、自然保護の認識、CTSへの認識、沖縄開発の認識のすり合わせをしようと提起して、議論しました。県政与党は、「金武湾開発は報道で知ってはいるが、金武湾開発構想・中城湾開発構想を持っているとは考えられない」と言った。これに対し私たちは、「工業立地センターの計画があり、県の職員も参画している長期経済計画もある。間違った認識の元に一緒になれることはない」と、こういった。労組は、「沖縄の大衆運動は革新政党の指導で作られてきた」といって来ました。そして結局話し合いは決裂し、三月五日に三政党と労組が「物価高騰反対・反CTS県民大会」を開催し、我々を排除しました。そういう政治的に運動をゆがめ、つぶしにかかる革新与党と、革新県政。そのあと私たちは裁判に訴えるのですが、その時、平然と「受けて立つ」と言ってのけたのが革新県政です。実は、その裁判に先立って、革新弁護団は、与那城村の漁協総会において漁業権の放棄が手続き上きちんとなされて決定されたのかを事前に調査していました。調査すると、実にずさんなやり方であったことが分かり、弁護団は県に対して「法的瑕疵がある」とはっきり伝えてある訳です。これが裁判の中で明らかになります。もともと革新弁護団は、法律家としての良心に基づいて、県のやり方の誤りを改めさせる立場であっただろうと思います。にも関わらず県は堂々と「受けて立つ」と言ってのけた。
そして革新弁護団の弁護士は、私たちにこう言いました。「みなさんの運動論、組織論には問題がある。まず代表がいない。責任を持って共闘できない。」これは違うよ、一人びとりが責任を持って会の一員になることで本物の闘いになる。誰も命(いのち)を代理することはできない。この原則は曲げられない。我々には世話人という集約機関はあるよ、と議論した。実は県との交渉には「代表六名と会う」ということを認めさせたかったのです。何回議論しても、平行線。一人びとりの意見を無視する革新とは、何か。民衆の個々の意思を把握することから民主主義の政治が成り立つのではないのか。今後の運動のあり方に関わる事だからこれは譲れない。もう一つ。革新県政に開発を強制しているのは政府・自民党と三菱資本だ。これを拒否すればよい。なぜ先導役をするのか。さらに開発計画は沖縄の側からの要求という実態がある。ため息が出たのは、「革新県政でなければねえ・・」と言われたときです。これはおかしい。住民運動は革新県政とも革新政党とも緊張関係にあるのは当然ではないか。こう考えました。
― 結局その議論は、その後どうなったのですか。革新三党と労組との修復は・・・
崎原 その修復はないですね。
― 運動の側に原則を残した、現在に至る教訓を残したということでしょうか。住民が自治を基本に闘うという原則は、現在も引き継がれている問題だと思います。そこは様々な住民運動に生かされているように思います。
崎原 もう一つは、政治的に分断を強いられ、大きな力で運動を押しつぶされようとする、けれども一方では、運動としての理念をしっかり持って行動していくことによって、住民運動が何であるかが一般の人にも理解されるようになる。その正しさが認識されるようになる。政党・労組との癒着は、大衆運動の中でも出てきますが、一般の青年労働者は違う、と感じ始める。住民運動が理念を持って続け、地域の中でしっかりと根を張っていけば、労働運動・大衆運動の中に流動化が出てくる。金武湾闘争が大きかったのは、地域に根を張り―屋慶名では約三分の二くらいの、照屋では半分ぐらいの人が支持してくれる―、運動の広がりがあった。漁民たちは裁判とは恐ろしいもの、お金もかかるし負ければどうなるか不安だとおもいます。もともと寡黙な人たちです。その漁民たちから「おかしい」と最初は六人が立ち、さらに誘致派の圧倒的多数の中から二人が出てきて、後はほかの島から四〇人がごそっと原告に入ってくる。運動の広がりが実感されました。
弾圧に耐えたたかいを支えた生産と文化
崎原 もう一つ。金武湾闘争は、険悪な状況もあった。白昼、鉄パイプで誘致派に襲撃されるとか、警察官の前で殴られるとか、夜、火炎瓶を投げられるとか、色々ある。誘致派の連中が、反対派の家の中まで入って脅したり、暴力を振るったり、今にも殺されるという危険を感じたり。そんな中で、地域の若者たちが、そんなこと許されるの、といい始める。誘致派の集まりに、度重なる暴行に我慢できず抗議するため押しかけると、「反対派の暴力事件」などと警察発表をそのまま報道されたり。私自身も毎日のように警察に出頭を要請されたりしました。無抵抗の抵抗、と言っても防衛もせざるを得ない。誘致派の若者のヘルメットを取り上げたこともある。色々な形で厳しい面もあったが、それを乗り越える組織の生活ぐるみの力を維持してきました。
― 生産もやり、闘争もやり、文化も、と安里さんも言っています。
崎原 特に屋慶名という部落は地域文化の行事が多いところです。それを担っているのが、女性。女性が多い。例えば、綱引きのときに太鼓をたたいたり、歌ったり。その中心をつかさどっているのは、女性です。ウスデーク(豊年祈願、方策感謝を趣旨とする女性だけで行われる奉納集団舞踊)をになっているのも反対派の皆さんです。厳しい闘いがあればあるほど、連帯を強める為に、アシビといって、三線や踊りや、いまを語り合いながら、展望も語ろうと。綱引きとか地域の伝統行事を復活させた。それだけでなく、農作物の品評会をして交流する場を一ヶ月に一回開催するとか。援農運動もありました。藪地にわたれなくなってしまってからは毎週土曜日と日曜日、労働者に呼びかけて、島に渡って耕作運動を展開した。一月から三月にかけてはキビ倒しで農家は大変です。援農運動として反対闘争をしている人たちの畑を手伝う。キビ倒しの畑作業が総て終わると、シースビーと言ってヤギ汁を作り、お酒をのみながらお祝いをする。運動の輪を広げていく。全体で集まるアシビもありました。喜納昌吉のバンドが入ってお祭りをしたこともある。演劇集団・創造(1961年に知念正真、中里友豪、幸喜良秀らが、沖縄の新しい演劇運動の創造を目指して、コザ=現沖縄市=で結成したアマチュア劇団。代表作は「人類館」「アンネの日記」「コザ版どん底」など)が劇をしたり。そういうことをしながら、楽しく一日を過ごす。金武湾ハーリーも一九八三年にやりました。漁民の中で反対運動はしていないが、行事には参加してくる人もいます。こちらは門戸は常に開いておく。
― 金武湾闘争の概要と大事な点をお話していただきました。辺野古とか高江の運動は、金武湾闘争を原型として、その精神が繰り返し貫かれているという気がします。
崎原 金武湾の運動の中での労働者と私たちの認識合わせがあったからできたところがありました。自分たちが運動に参加できる範囲はどこかということ。例えばカンパをきちっとやるとか、新基地建設反対を組織として確認するとか。行動に毎週参加するとか。どこまで労働者、労働組合として闘争に参加するのか、すり合わせをする必要がある。そうすれば参加しやすくなる。認識合わせをするのが大事ではないか。そう思います。
私たちの運動は常に今ある問題を大衆的に、労働組合に申し入れをして、呼びかけをしながら、話し合ってきた。共通の認識を持ってもらわないといけない。例えば裁判闘争のときに、あまりにも裁判官が酷いものだから大声で批判して退去命令が出る。「裁判官への印象を悪くする、大丈夫なの」言われる。でも裁判は手段であって、こちらは正当な反論はする。その広がりと密接な交流が大事です。認識のすり合わせをしなさいということです。
安里清信さんの人がらと思想
― 安里さんと、屋良さんとの対比を考えるのですが、安里さんの本には叔父さんが、「沖縄も朝鮮も植民地のようなものだからよく考えてやりなさいよ」と言われたという話が出てきます。沖縄は植民地だという認識があったのかなと思います。屋良さんの場合はそういう見方は乏しかったのかなという印象を持ちますが、どうでしょう。
崎原 安里さんとは七三年から守る会の世話人になっていますから、一緒に動いてきた。安里さんは泡盛がお好きで、自分の家ではなく、私の家などで会議をやっていた。自分の家ではやれないんですよ(笑い)。屋良さんはどちらかというと、大学教授みたいな方で、台湾高等師範の先生だけれども、台湾に対する侵略という認識はほとんど持たない、まさに戦前の教師で、国威を高める為の運動に積極的に加担していった。その証拠に、戦後も靖国奉賛会の呼びかけ人でもあるわけです。戦争責任の認識はなかったでしょう。
もうひとつは、沖縄教職員会の天皇と言われたわけです。あの人の一存で方針が決まってしまう。私が中学にいる一九六五・六年ころに教職員会の労働組合移行の話があった。当時はだいたい会長は校長、青年部長は教頭と言うような教職員会の仕組みでした。その私の地域(中部)の中頭教職員会の大会で、組合移行が決定された。その時に来賓で来ていた教職員会会長の屋良さんが、「いまの決定は認めません」と言った。私はまだ若いころですから、「民主主義の手続きで決まったことを会長の一存で拒否できるのか」と問いかけた。私が逆に教頭のみなさんに「黙れ!」と言われて会場から追い出されました。だから、天皇はえらいものだと思いました。そういうことをやりながら、「子供の教育権は米軍に押さえつけられるものではなく、日本国民を育成しているのだから、日本国家が守るべきだ」という主張もしていた。米軍への抵抗が評価され、復帰協議会の会長にもなります。ところが体質的に持っているものは、やはり戦中の自分の位置を総括せずに、戦後も引きずっている。米国への抵抗は強いが、それは国粋主義者でもあるでしょう。戦前の教育の誤りを自分の中で整理しないで戦後もそのまま持っている人だと若い人の中では言われていました。
安里さんはこう言っていました。「朝鮮人と日本人は対等だ」と思いながら教鞭をとっていたが、自分が植民地朝鮮に教師として派遣されているということは侵略者の一員で加担者になっているのではないか。この思いが、自分の中に苦悩としてある。常にそのことを反省しながらまっとうな生き方をしたい。戦中の自分を省みて慙愧に耐えない思いを持っていた。こういうことは、常に言っていました。
例えば、運動の中で、沖縄でも色々な党派の人が来ていて、新聞も送ってきた。安里先生は「この新聞は誰が持ってきたのかね」と私に聞きながら、「よその国の理論を自分の国に生かそうとしているが、生きるものではない。もっと自分たちの地域の中に底辺の中に自分たちの生き方を発見しろ」これを常に言っていましたね。そして、常に自分の周囲に学ぶべき人がたくさんいる。漁民であれ、農民であれ、そこからどれだけ学べるか。思想は土着だ。こういっていました。土着の思想を自分なりに生み出せ、と。借り物、よそ者で運動できるわけはない。そして人をいつくしむ。特に先輩たちをものすごく大事にする。その人たちの発する一言一言の中に真理がある。借り物の思想では運動にはならない。常に現場主義。眺めるだけではダメ。現場に行き点検し、考え、行動する。
お話は、季節の移ろいと自然と常に結びついている。スルルグワー(キビナゴ)の大群が打ち寄せているとき、漁師の目は常に海を見ている、海の色が変わると漁師は一瞬のうちに飛び出していく。だから、その時期になると漁師はほとんど高台にいるんだよ。海の魚と陸の花、自然を繋ぎ合わせ季節の移ろいとともに、沖縄の自然を語っていく。いかに沖縄の人々が自然とともに生きてきたか。『海はひとの母である』ですし、自然と大地の共同の力の中に自分たちがある。それを見失うと大変なことになる。
泡盛を飲みながら、そんなすばらしいお話をしていました。とても優しく、叱ったり、人に指示するということは一切しませんでした。全て自分の考えでやりなさい。人間としての偉大さと哲学的な思索を持った人だった。
― 当時、若いときには、環境問題についてはほとんどわからなかったけれども、今この『海はひとの母である』の文章を読んでみると、すごいなと思いますね。
崎原 こういうはなしがあります。新任の先生が、与勝中学に行き、まず校長・教頭に挨拶をしようと思って事務の人に所在を尋ねました。安里さんは当時教頭でした。事務職の人は「教頭先生はその近辺にいらっしゃいます」と言いますが、それらしき人は見当たりません。しばらく玄関口に立っていると「いらっしゃいませんか?」と事務員が出てきました。「あのかたです」。笠をかぶって、上はランニング、下は作業ズボンという格好で一生懸命花壇を掘り返していらっしゃったそうです。用務員かと思ったと。それからがまた大変です。集まれというので職員室に行ってみると車座になって酒が出てきた。教育の話は関係ない、一人びとり人間の生き様の話をするという。生き様の話が子どもと接するときの大事なことだと。酒が進んで暑くなるとだんだん裸になってしまいます。「教育現場」だろうとお構いなし。「学校だから世間体から外れてはいけない」と言うと「ここも一家庭なんだ。子どもたちが見ていようと、家庭で大人が酒を飲むのは当たり前、当たり前のことを当たり前にしないからおかしくなる」。そういうところに安里さんのもうひとつの教育というものを感じたといいます。安里さんにそんな話を聞くと「そんなこともあったかなあ」という具合です。そういえば教頭・校長の時は、あまり外に出なかった、「教頭会・校長会」などに行ってもつまらない話ばかり、…。時間がある時は、緑化運動をしていました。藪地島―学校とは全く関係ありませんよ―の海岸べりにあるモクマオウはあの人が植えたものです。高校のときには、農業を教えていたそうですが、「沖縄には樹がない、緑を増やそう」と教えられ、実習もしていたとのことです。戦後沖縄に帰って、焦土となった沖縄の状況を見て、まず自然を復興させることを考え、海と大地と共同の力を感じたのではないでしょうか。
青年に継承される金武湾闘争の教訓
― 沖縄の戦後は、間断なく、世代から世代へと運動が続いているという実感を持ちました。日本で言えば、七〇年前後までありましたが、それがパタッと途切れてしまっていて、それは僕ら自身が考えるべき大事な問題かなと思っています。沖縄の土地闘争は、奪われたもの、奪われようとするものの切迫した状況があったのかなと思います。生きていく上での土地を守らないといけないという闘い。その経験を持った人たちは、また沖縄戦の厳しい経験をもち、さらにその後の闘いの経験とつながっているのかなと思います。記憶と体にしみこんでいるのかなと。
崎原 今回、民主党が普天間の移設先を「少なくとも県外」と言った。ところが、今年の三月になってから、与勝沖案が急浮上してきた。その時、うるま市議会の基地対策委員会を傍聴に行ったが、「公開できない」という。これは「市民が立ち上がらないといけない」、と呼びかけてみんな集まってきた。一七日に会合を持ちました。議員が当時の平野官房長官に呼ばれた話もあり、これはあぶないと、その場で市民協を結成しようということになりました。議会に押しかけたところ全会一致で反対決議が出た。これでも危ないというので、議長と市長に要請行動をした。三月二五日に市民大会やろうと準備に入った。市長からメッセージをもらった。一週間の準備期間でしたが、ホールが満杯になった。その前の二二日、二三日にダイバーを頼んで与勝沖の海底を調査したところ、珊瑚がいっぱい。市民大会で映像で披露したところ、これはすばらしい!この海を埋め立てるなどとんでもない!となった。国会要請行動もやり、国会の外務委員会メンバーも調査に来たので、市と交渉して一時間のうるま市の説明時間の半分をもらい、三〇分説明した。映像を見てみんなびっくりしていた。
漁民たちも反対決議をした。勝連の平敷屋でスヌイをやっている若い漁民とも話しました。彼らは、ここは私たちの生活の場、そして後輩たちに受け継がなければならないところとも言っていました。なんで埋め立てを許せますか。また、あるところの年輩の漁民に聞きました。金武湾闘争の事も知っている世代です。私たちの事も知っています。「昔私たちはだまされた。埋め立てても漁業に影響ない、補償金をもらうだけ得と言われた。しかしそのあとものすごく苦しんだ。ようやく回復した宝の海をどうして手放しますか?」漁民たちはこの海を「ジングラ」と言います。「銭蔵」=銀行です。貯金をおろしに行くように海から恵みをもらうのです。金武湾闘争の過去の教訓が、漁民たちにも引き継がれていっている。若い青年たちにも受け継がれているものがある。「自分は四年間、ヤマトに就職した。向こうの生活はあれやれこれやれで、まるで奴隷。人間の心の豊かさが感じられない。いま僕の心の中には豊かさがいっぱいあります。」こういっていた若者がいた。豊かさを、いまどう感じることができるのか、考える必要がある。沖縄の漁民が政治家に、企業にだまされることはない。一つの教訓がつながっていったことは、金武湾闘争で残したものがあったということ。与勝沖案に反対した漁民たちに金武湾の闘いが受け継がれていったことがうれしかったです。
― とてもいいお話でした。ありがとうございました。
(『情況』2010年11月号)
施政権返還後の沖縄における住民運動と裁判
石油備蓄基地建設反対闘争(1973-1985)における裁判をめぐって
上原こずえ
はじめに
1.金武湾闘争と裁判
1970年3月:日本工業立地センター、与那城村からの依頼に基づき「金武湾地区開発構想」を策定
1972年3月:琉球政府、三菱開発に対し公有水面埋立免許を交付→10月:平安座島―宮城島間の埋立工事着工
1973年9月:「金武湾を守る会」結成→現地、県庁にて集会やデモ、座り込み、直接交渉
1974年9月:金武湾公有水面埋立免許 無効確認請求訴訟を提訴
1977年4月:危険物貯蔵所等 建築工事禁止仮処分申請を提出
2.先行研究
①反CTS裁判
*反CTS裁判の経緯を整理(⇒崎原、1978年)
*技術論・法律論的な問題を指摘(⇒小川・水上、1977年;安里、1979年)
②司法権力に対峙する戦後の沖縄における抵抗運動
*日本国憲法獲得要求としての違憲訴訟(⇒新崎、1965年)
*自治権拡大闘争としての裁判移送撤回闘争(⇒新崎、1966年)
③抵抗する「住民」にとっての裁判経験(⇒家中、2006年)
④抵抗運動の方法としての裁判
*日本国憲法に解放の論理を見出した復帰運動と連続性をもつものとして(⇒Tanji, 2002)
*米軍再編に伴う基地建設に反対する名護市辺野古や東村高江の<座り込み=不服従の直接行動>と対比される方法として(⇒阿部、2011年)
3.本報告における問題関心
*金武湾を守る会が、司法権力に訴えることの問題を認識していながら、それでも裁判を展開するに至った背景を明らかにする
*裁判の過程において金武湾を守る会が直面した問題や、金武湾を守る会内部に生じた迷いや葛藤を探る。また、金武湾闘争が裁判の経験から得たものを明らかにし、裁判が金武湾闘争においてどのような意味をもっていたのかを考察する
*金武湾闘争に続く復帰後の反基地・反開発の住民運動における、司法や裁判闘争の意味を探る
Ⅰ.戦後の沖縄における司法制度と権利要求の動き
1.米軍統治下の司法制度とその問題
①法令:米大統領による行政命令、米民政府によって制定・公布された布令・布告に絶対的な優位性がおかれる
②司法体制:米国民政府裁判所と琉球政府民裁判所の二元制(※後者が前者に従属)
→米軍人などによる被害の賠償や土地接収に対する補償・救済を要求することが認められない(⇒日本弁護士連合会、1968年)
2.権利要求の動き
①二つの違憲訴訟(1965年)
対日講和条約第3条と日本国憲法第95条の矛盾―「住民投票を経ない対日講和条約第3条は無効」
→憲法第22条が定める居住・移転の自由の権利、原爆医療法が定める医療費請求権の侵害を違憲であると訴える
②裁判移送問題(1966年)
民裁判所で係争中の「友利・サンマ裁判」について、「米国の行政の妥当性に合法性を審査する権利が米政府当局以外ない」、という理由で高等弁務官が民政府裁判所に移送命令
→移送命令の撤回、大統領行政命令の撤廃を求める島ぐるみの運動へ (⇒新崎、1965年;1966年)
3.「日本国憲法」という幻想が崩壊した復帰
①司法の反動化と裁判所の管理強化
②在日米軍基地の恒久化のための日米関係再編成としての復帰
*「沖縄返還政策粉砕」を貫けない復帰運動の限界→矛盾を抱えたままの復帰(新崎の指摘⇒新崎・金城、1982年)
Ⅱ.反CTS裁判
1.漁民原告団と原告代理人弁護団の組織化
1974年6月:金武湾を守る会、革新共闘弁護団が県に提出した「CTS問題についての見解書」を入手
*県が三菱に与えた埋立免許の法的瑕疵が明らかに→提訴に向け、漁民原告団の組織化へ
*革新共闘弁護団は屋良知事を被告とすれば革新県政を窮地に陥れると判断、裁判支援せず
*県内の弁護士、「自主講座」を通じて参加を呼びかけた弁護士らが原告代理人に
2.「漁業権」裁判
1974年9月:6人の漁民原告団、那覇地裁にて金武湾公有水面の埋立認可無効確認のため屋良知事を提訴
1974年10月の第1回公判?1975年7月の第7回公判:
*煤煙の雨で枯れた野菜や原油流出事故で汚染された海水、異臭魚を法廷に提出
*漁民自ら法廷に立ち、合意手続きの問題、悪臭・騒音被害、海の汚染、魚介類の減少を訴える
*金武湾を守る会住民ら、貸し切りバスで駆けつけ傍聴
*与那城村漁協・勝連村漁協から新たに42人の漁民が原告団に加わる
1975年10月:山口裁判長「訴えの利益なし」を理由に、漁民原告団の訴えを却下
→漁民原告団、控訴(控訴審:1976年1月の第1回公判?1976年7月の第4回公判)
→屋良知事は埋立竣工を認可(「無公害企業」の誘致を求める、と示唆)
1976年6月:屋良知事、石油タンクの設置を許可
3.「生存権」裁判
1977年4月:1,250人の原告団「危険物貯蔵所等建築工事禁止仮処分申請」を那覇地裁に提出
→当時大阪空港騒音訴訟で争われていた人格権や環境権に基づく県内初の公害裁判に
1977年8月の第1回公判?1978年6月の第5回公判:
*日本各地の研究者や技術者が証人として参加―埋立地の脆弱性、タンク構造の問題、火災の可能性を指摘
→技術論でCTSの危険性を訴える
1979年3月:稲盛裁判長は「危険性はない」を理由にCTS工事差止仮処分請求を却下
4.裁判闘争の終わり
1978年12月:「革新」から「保守」へ:自民党の西銘順治が県知事に就任―79年、80年にタンク増設を認可
*頻発する事故?1981年2月:喜屋武岬沖合での石油タンカー爆発、11月:沖縄石油基地で原油流出事故
1982年10月:「漁業権」裁判の上訴請求を福岡高等裁判所那覇支部から取り下げる
Ⅲ.裁判をめぐって
1.反CTS裁判の評価
「我々は敗北したのか?否である。十年近くのCTS反対闘争によって、孤立無縁であった石油企業による金武湾破壊に対する我々の告発が、やがて県民に理解され、CTS反対が今や世論となっていること。」(池宮城紀夫「CTS裁判の終結にあたり」『東海岸』第32号、1982年12月)
→提訴を機に拡がる理解、各地の反開発・反公害の住民運動とのつながりが、孤立する金武湾を守る会の支えに
2.金武湾を守る会内部の裁判闘争批判
①革新政党・労組からの支援や連帯の欠如のなか、「唯一残された最悪の手段として」踏み切った提訴
「いつ竣工認可がうちおろされるかも知れないという、時間的制約を受けた緊迫した情況の下で、それを歯止めしていく唯一残された最悪の手段として不本意ながらも、守る会は訴訟へと踏み切らざるを得なかった。」(死角・蹉跌を撃て編集委員会『死角:蹉跌の歴史を撃て』創刊号、1976年1月、23頁)
②「誰の為のどのような意味をもつ闘いであるのか」?
「裁判に規定された形で、単に量的運動への拡大へと、本質的な視点の対象が歪められていく。」
「運動の無原則的な展開は、根拠地闘争としてのある住民運動そのものの本質と対立するものであり、こと沖縄あるが故の特殊的な歴史と運動体内部の矛盾の止揚を一般的な通念に解消することになる。」(『死角』25頁)
③裁判によって奪われる住民運動のエネルギー
「裁判というのは僕らが直接交渉する場じゃない。原告代理人である弁護士らを通じてしかやれないでしょう。ぼくらの怒りとか気持ちは直接ぶつけられない。しかも裁判というのはスケジュール闘争。だから住民運動のエネルギーが、だんだん無くなってしまう。それから裁判は権力側の土俵でしょう。そこで勝てるはずないけど、僕ら一般の人は、裁判では正しいものが勝つという幻想を持って、裁判だけが主目的な運動になってしまう。時間も金も、エネルギーも使うわりには、裁判で勝てる可能性はない。」(伊波義安、2011年3月)
「実際の裁判では「訴えの利益なし」判決に見られるような論理のすり替えがなされ、金武湾を守る会が一方的につぶされていった。控訴も進めるが、現場では埋立やタンクの建設が進行する。仮処分申請をしてからは、争点は技術論となり、タンク論、地盤論、それに対する風圧、鉄板の厚み。そういった技術論になると、一次訴訟の意見陳述で代表して訴えを述べ闘った漁民も住民も出る幕がないといった状況が出てきた。」(崎原盛秀、2009年12月)
3.どのように自らを表現するか?
「じゃあどう自らを表現しうるか、課題を含む闘いのなかでどう問題を是正し運動を拡げていくかが重要なのではないかを考えるべきだと思っていた。」(崎原盛秀、2009年12月)
①沖縄戦を経験した住民の「生存権」の思想の主張
*金武湾の住民や漁民にとっての「生きてきた現実」―人間の「生存」が自然と不可分であること
*「海のおかげで生きてこれた」沖縄戦経験―「生活」の基礎に「生存」があるという認識
*沖縄戦で「死」をもたらすものでしかなかった国家―「民衆の生存にとっての国家・文明の役割」の相対化 (平良良昭「安里先生晩年の思想―沖縄の自立・独立」『琉球弧の住民運動』第22号、2?3頁)
→沖縄戦中、戦後経験の証言集「海と大地と共同の力―沖縄民衆の生存権の原像」(1978年2月、準備書面)
②「生存」をささえてきた海や土地とともに生きる行動へ
*開墾運動と援農、共同体の豊漁・豊作祈願としての伝統行事・文化の復興運動
⇒「実態を明らかにして世論に訴えていく手段」としての裁判闘争は、復帰後の住民運動に受け継がれていく
(石垣島新空港建設反対運動、嘉手納爆音訴訟、泡瀬干潟埋立反対運動、辺野古の米軍基地建設反対運動‥‥)
→しかし、裁判は「あくまで反対運動の一環」であり、「法廷外の運動と裁判は車の両輪である」(池宮城紀夫「公害・環境裁判」『法と民主主義』第211号、1986年10月、33頁)
Ⅳ.おわりに
*革新県政のもとで孤立した金武湾を守る会は、日本本土の反公害運動とつながり、漁業権や生存権に依拠した裁判闘争を展開した
*行政の決定に追随する司法のあり方を目の当たりにした金武湾を守る会の住民らは、司法の問題を改めて認識し、司法権力が下す判決に屈せず、海や土地とともに生きるという権利を自ら行使し要求する意志を育てた
*国家が規定する権利を相対化し、沖縄戦の経験にもとづく「生存権」の思想をうちたてた*司法権力による反基地・反開発の抵抗運動に対する弾圧は強化されており、運動が対峙している司法権力のあり方を改めて問い直していくことが必要
参考・引用文献
阿部小涼「繰り返し変わる:沖縄における直接行動の現在進行形」『政策科学・国際関係論集』第13号、2011年.
安里悦二「金武湾CTS基地の建設を断固として拒否する」『開発と公害』第5号、1979年.
新崎盛暉「<日本の潮3>沖縄からの二つの訴訟」『世界』第240号、1965年11月(『未完の沖縄闘争 沖縄同時代史 別巻1962?1972』凱風社、2005年所収).
新崎盛暉「<日本の潮4>沖縄裁判移送問題のゆくえ」『世界』251号、1966年10月(新崎、2005年所収).
新崎盛暉・金城睦「対談・沖縄復帰10年の歩みと展望」『法律時報』増刊、1982年.
小川進・水上学「沖縄CTS建設が裁くもの」『技術と人間』第6巻7号、1977年.
崎原盛秀「沖縄は拒否する-反CTS金武湾住民闘争の経過」『季刊労働運動』第17号、1978年.
日本弁護士連合会「沖縄報告書」『法律時報』第40巻4号、1968年.
家中茂「実践としての学問、生き方としての学問:解題と論点の整理」新崎盛暉・比嘉政夫・家中茂編『地域の自立・シマの力』コモンズ、2006年.
Tanji, Miyume. (2002). The dynamic trajectory of the post-reversion ‘Okinawa Struggle: Constitution, environment and gender.’ In Glenn D. Hook and Richard Siddle (2002). Japan and Okinawa: Structure and subjectivity. London: Routledge. Pp.167-187.
日本平和学会2011年度春季研究大会(2011.06.04)・自由論題部会報告レジュメ
金武湾・CTS建設阻止闘争
提訴にあたっての声明(1974年9月5日)
金武湾を守る会
はじめに
私たち金武湾を守る会は、昨年9月以来、金武湾・中城湾の一切の埋め立てとCTS建設に反対して、血のにじむような激しい闘いを展開してきました。
今日私たちは、「革新県政」を被告として訴訟を起しました。私たち、守る会に結集する住民は、そのほとんどがかつて屋良知事を革新知事として立てるため一票を投じてきたのであります。その私たちが、自ら立てた「革新県政」をその底辺から告発せざるを得ない現実は、皮肉というには余りに苦い現実といわねばならない。しかし、この現実がどのように苦いものであろうと、私たち住民はそれから眼をそむけることを許されない立場に立たされているのである。
私たち金武湾を守る会に結集する住民は、金武湾を守り、それと密接に結びついている私たち及び私たちの子孫たちの生命とくらしを守り抜くという原点に立って、その破壊を推し進めている県の「開発」行政の誤りを告発し、是正するために、さらには沖縄を東南アジアへの経済侵略の拠点にしようと企む国と、そのもとで金力と暴力をもって住民を支配し、CTSを核とする公害企業建設を強行しつつある三菱ヤマト大独占と闘うために、今日提訴にふみ切ったのである。私たちは、私たちが自ら立てた革新県政を被告としたこの訴訟の不可避性・必然性と意義を訴え、あわせて全県民の力でこの闘いを勝利に導くためいくつかの提言を行いたいと思う。
国家の論理に包みこまれた復帰の現実
思えば、沖縄の日本への復帰が現実の問題となりつつあつた1967年を境として、「開発」の問題がにわかにクローズアップされることとなった。松岡琉球政府が、ガルフ、東洋石油、エッソ等のかけ込み資本の金武湾・中城湾への石油基地建設を認可するや、世界アルミ独占であるアルコアをはじめ、沖縄アルミKK、アラビア石油、三菱等が相ついで企業立地の申請をなしてきた。
69年に誕生した屋良革新政府は、松岡政府の公害企業誘致政策を何のためらいもなく踏襲し、しかもそれら戦略産業としてのアルミ・石油産業を「平和産業」と位置付け、積極的な誘致政策をとってきた。その結果が、今日みられる金武湾・中城湾の汚染、漁業の破壊、地域住民の生活環境の破壊となってあらわれ、死の商人といわれ日本軍国主義とともに歩むといわれる三菱ヤマト大独占を私たちの沖縄に導き入れようとしている現実となったのである。
しかしながら、このような現実は、単に屋良県政のみに問題があっただけではないであろう。その基因は、あれほど熾烈に闘われた復帰運動のもつ思想的・理論的弱点にあったことも見逃してはならない。「異民族支配をたち切り平和憲法の下でその思索を日本国民として平等に享受する」という復帰運動は、沖縄の位相、即ちサツマによる暴力的沖縄併合をはじめ、その後の差別と被支配という辛酸と痛苦をなめつくした歴史、日本の占領体制からの脱却とひきかえにした沖縄の米軍への提供、沖縄人民の米軍基地への隷属化等に見られる国家としての日本がとり続けてきた数々の暴挙をなんら歴史的に検証することなく、「母なる国への復帰」という感性的発想で日本人への同化を急ぎ、「28年の長い米軍統治下に置かれた沖縄県民の御苦労に対し、深くお詫びし、復帰のあかつきには暖かく迎え入れたい」という佐藤の偽装をこらした言辞の前にもろくものめり込み、結果的には国家の冷徹な論理に屈服していったのである。
そのような内実をもつ復帰運動であったが故に、「復帰」を「反戦復帰」と手なおししてみたものの、なお帝国主義国家としての日本を対象化し、それと闘って自らを解放していく運動になり切れなかったのである。こうして5・15返還は、スムースに体制の論理のうちに吸収され、包摂されるものとなり、今日の沖縄の現実として具体化しつつあるのである。
あやまった格差是正論
さらにもう一つ提起しておかねばならない復帰運動の一側面・根本的弱点は、本土との経済的「格差是正」論にあったことも見逃してはなるまい。国民総生産世界第二位にのしあがった日本の繁栄は、沖縄の犠牲の上になり立ったのだから復帰後の沖縄に対して、国は当然その責任を負うべきだという発想が生まれたのである。この発想の弱点は、帝国主義段階に突入した日本資本主義国家の繁栄が、その実、国内における労働者人民の世界にもまれな適当な収奪・搾取にもとづくものであり、一方、東南アジアをはじめとするいわゆる第三世界人民からの労働と資源の収奪にもとづくものとして成立している点を見ないことにあった。復帰運動は戦後28年、沖縄の人々を苦しめてきた米軍支配に対して、それを打倒し解放をかちとる方向ではなく、いみじくも「脱却」と表現された様に、それとの対決をさけ、日本国家権力を通して解放を展望する根本的誤りを犯したのである。このような復帰運動が現実の日本国家を見ず、「平和憲法の」「繁栄」した日本という幻想を拡大していったのはけだし当然であった。この幻想は、国政参加選挙において、最も特徴的に表出したことを想記してみるべきである。
基地経済からの脱皮を合い言葉にした平和産業論は、事実上「基地撤去」の闘いを後退させたのである。そして米軍支配下で集積した沖縄経済の矛盾(それは基地の存在そのものに起因しているのだが)を、日本独占資本を導入することによって糊塗するものであった。それは公害を激発させることによって住民の厳しい抵抗にあい、本土を追い出された公害企業の絶好の誘因となったのである。アルミ、石油産業が真先に沖縄に眼をつけたのはこの様な素地故であった。
公害の共犯者─平和産業論
屋良県政の「平和産業論」の実体は、本土ではもはや立地の展望を閉ざされたCTSを中核とする石油コンビナートの誘致であることはかくすことのできない明白な事実である。70年に出された「長期経済開発計画」は新全総の立役者である下河辺淳氏の指導によってなされ、その中心は企業優先であり、その立地場所として金武湾・中城湾を設定し、それを受けて72年に出された「沖縄県振興開発計画」は業種として、CTS、石油精製、アルミ精錬、造船などの公害産業をあげ、その誘致方針を明確に打ち出している。さらに、74年5月、CTS・埋立反対の住民運動が労組・民主団体に拡大され、全県的な反対の嵐のなかで県が日本工業立地センターに策定を依頼し発表した「中南部工業開発基本計画」の中に於いても同様に記載されているのである。それらは70年から71年にかけて出された「日本工業立地センター」「三菱総合研究所」「伊藤忠商事」「通産省」等の金武湾・中城湾開発構想とも、その内容はほとんど一致しているのである。
これらの事実からも明らかなように、屋良県政の開発行政は、すでにその発足時点からして、国策としての石油備蓄、公害独占企業の沖縄侵出の積極的な補完者であり、完全に誤った住民無視の公害路線を突っ走っていたのである。
金武湾沿岸住民は、70年に操業を開始した沖縄ターミナルKK(ガルフ)からの度重なる油漏出事故やバラスト水による慢性的汚染の進行、沖縄石油精製からのガスの発生等により、海と大気が汚染され、海が死に、油臭魚が発生し、人体への影響すら懸念されている現在、更に三菱のガルフに倍するCTS建設におびやかされている。昨年9月、三菱のCTS建設を目前にして、私たち住民は自らの生命とくらしを守るため敢然と起ち上り、金武湾を守る会を結成、公害の元凶CTSを積極的に誘致している屋良県政、住民の反対を押しきって強行に工事を進める三菱に対し、果敢な抗議行動を開始したのである。
既定方針化をはかる県側
ところで屋良県政は、金武湾を守る会の住民の数十度に及ぶ大衆団交・大衆対話の申し入れを、「金武湾を守る会には代表者がいない」とか「5名となら会う」などの口実でことごとく拒否してきた。県が守る会住民と会うのを拒否する真の理由は、県がCTSの誘致、それを核とした金武湾「開発」を既定方針として貫き通そうとする意志を、1・19談話以後も頑なに固執していることにある。
私たちは、知事が既得権を有している金武湾・中城湾内約1050万坪の公有水面埋立免許権が1月31日をもって効力を失うことから、県としても1月いっぱいでCTS問題に決着をつけなければならないという情況にあって、1月20日前後を山場と見て、1月18日に県庁前座り込み闘争へ突入した。そして、1月19日、「CTSの各社配分はしない」という知事談話が発表されたのである。
ところがこの知事声明は、欺瞞に満ちた大衆を愚弄するものであった。それは現在の情況──即ち、CTSに反対するといいながら、CTS建設用地を三菱の所有物にしようとする、埋立竣工認可の県の方針に最も端的に表れている。理念においては反対だが、行政の立場からはそうもいかないという1・19以後の県首脳の発言は、県のかくされた真の意図を明らかにするものではないだろうか。1・19の知事声明以後も、三菱は埋立工事を続行し、シーバース・パイプラインなどを昼夜の突貫工事で完成を急ぎ、既定事実のつみ上げにやっきとなっている。県は、こうした既定事実の進行を黙認してきた。いや、これこそ県の意図だったのである。既定事実を黙認し、それを進行させ、その進行を理由に、CTS[建設を拒否することがますます困難になったとして、公害防止対策を厳重にする方向で認める──これが県の筋書なのである。恐るべき世論操作・大衆操作といわねばならない。県が今なお金武湾・中城湾の工業開発を強力に推進していることは、先の漁業権区域設定に於いて、金武湾開発の一環である具志川地先への造船所誘致を前提にした埋立計画区域を、現に漁業が営まれているにもかかわらず漁業区域からはずしていることにもうかがえるのである。
県はCTS[に反対すると称しながら、現実にはCTS建設を既定方針として押し通そうとしている。6月定例議会における「埋立認可をするかしないかは政治的立場からではなくあくまで法的立場に立って判断する」という発言や、「消防法」と「県土保全条例」で阻止するという明確な世論操作、さらに、革新弁護団の意見書で「三菱に埋立免許を与える時点で県は法的瑕疵を犯している」ことを指摘されながらこれを無視した件、これらのことが、県の姿勢をものがたっている。県は今なお公害開発行政の道を固執している。これは許されるべきことではない。これは沖縄をヤマト独占資本の支配下に積極的にくみ込み、自然破壊・生活破壊・沖縄破壊への道である。
一方、屋良県政を支え、裏の革新行政を守り育てるはずの革新与党は、県執行部のCTS[誘致政策に対し、なんら有効な対応策を持ち得ず、意志の統一をもかちとり得ない現状である。
また、県の行政的に先行している金武湾・中城湾関係計画に対しても、何らの対応策を持ち得ていない。それは、2月23日に予定されていた「CTS阻止県民総決起大会」が、守る会と県与党との認識の違いから流産したいきさつからして、明瞭になっている。
CTS反対闘争の要点
2・23県民大会を開催するにあたっては、社大党控室で、県与党・労組団体・民主団体及び金武湾を守る会の参加で12、14、16日と延々3日間に亘って話し合いをもった。「政党、各労組、各民主団体、守る会が共催する」ことについては議論の末確認されたが、「大会スローガン」の点で、与党と守る会との間に深い認識の違いが生じた。すなわち、守る会が提起した「金武湾・中城湾開発構想に反対する」と「具志川市造船所誘致に反対する」の2点に対し、与党から「金武湾・中城湾開発のプランは、民間団体が出していることは新聞で知っているが、現実に県にあるとは思わない」とか「造船所に公害があるかないかは、調査してないので分からない」という理由で、これをスローガンに掲げることには責任が負えないという発言から紛糾した。
この件に対する守る会の立場は、
① 列島改造論の中で金武湾・中城湾が、それぞれ中規模コンビナートとして位置づけられていること。
② 現に三菱の埋め立てがなされ、CTS建設工事が急ピッチで進められていること。
③ 泡瀬南港の建設がすでに具体化されていること。
④ 72年の「沖縄県振興開発計画」で、明確に述べられていること。
⑤ 1・19声明から一週間後に「国家として金武湾にCTSを建設する」との中曽根通産相発言からもみられる。
⑥ 同じ時期に「沖縄県の振興開発計画を練り直さなければならない」と困惑しきった沖縄開発庁の発言。
⑦ 現に右と同様のことを県与党が主張している
点などをあげ、具体的に反論し、金武湾・中城湾開発構想について目隠ししようとする県与党の欺瞞性がスローガンの項にいたって暴露され、金武湾・中城湾の開発構想の粉砕なくして、実質的なCTS阻止闘争の勝利はあり得ないとする認識の違いで、大会が流産したというのがその実相である。また、この態度が県与党の実態でもある。
この大会が流産したことで「守る会は政党を排除している」とか「労組団体を排除している」と誹謗や中傷がとびかっているようだが、金武湾を守る会は政党を排除したこともなければ、労組・民主団体を排除したこともない。むしろ、これまで積極的に対話する中で共闘を申し入れ、反CTS闘争に決起することを何回となく各団体に要請してきたのがその実状である。
自らの生命の代表としての運動
たしかに守る会の運動には、その出発において確認された組織原則と運動原則がある。それは「金武湾を守る会はここに結集する住民ひとりひとりが、自らの生命の代表であり、自らの自覚と責任に於いて行動することをふまえ、会長(代表者)は置かないが連絡世話人は置く」であり「この運動は保守、革新、イデオロギー、セクトの別を問わず生存の原点に立って広汎な運動を展開していく」と確認されているように、「代表者」は置かないし、住民運動である以上、政党との間には常に一定の批判関係を保ちつつも、共闘をし連帯して闘うことに、勝利への展望を持つ意味と、現在沖縄のすべてにかけられてくる国家からの攻勢は、現象的に変わっていても、常に紙の表裏をなす関係にあり、労働者、農民、漁民は一体となって闘うこと自体が、自らの解放をかちとる道でもあると信じる。
私たち守る会は、今回の訴訟にあたっても、これが死の商人三菱を沖縄から追いだす唯一の手段とは思わないし、また県を窮地に追い込もうとするものでもない。県が自らなした誤った開発行政を反省し、埋立て竣工認可を却下し、埋立て免許を与えないという保障があれば、今すぐにでもこの訴訟を取り下げることもやぶさかではない。しかしながら県がこれまでとってきた埋立て竣工認可の姿勢に変更がないかぎり、私たちは三菱をたたきだすまで、この訴訟をはじめあらゆる手段と戦術を駆使して闘うことをここに明らかにするものである。
運動への参加をよびかける
さらに、与党をはじめ各労組・各民主団体・全県民に対して要請をする。私たち金武湾を守る会は、自らの生存の原点が奪われようとすることに対し、これを告発し、また独占企業管理社会を目論み、住民を企業の論理に従属させ隷属支配を貫徹しようとする国とその先兵としての企業に対し、激しい怒りを感じるが故に、闘いに力強く突入しているのである。それらを沖縄から排除し、住民が安心して生活できる自然環境を守るため闘っているのである。
しかしながら、現在の沖縄の政治的、社会的に混沌とした情況を政治的、経済的、軍事的に悪用し、農・漁民の生活基盤を破壊し、労働者の生活権をも破滅においやる現実が全沖縄をおおいつつある。
私たち県民がこのような「開発」と公害企業を先導にした独占企業の侵出を許していくならば、沖縄の将来はまさに悲惨な現実となって出現するであろう。それらを阻止することは、労働者、農・漁民を中心とする全沖縄県民に課された大きな歴史的課題である。この課題をにないつつ提訴にふみきった金武湾を守る会の闘いに積極的な参加を呼びかけるものである。
上記、声明する。
|
「戦後50年 人間紀行 そして 何処へ/第2部 闘い/立つ」
① CTS阻止闘争に10年
1981年、安里清信は金武湾を守る会代表世話人として、相変わらず忙しい毎日を送っていた。1月のベラウ、グアムを振り出しに、西表、水俣、宮古、東京と住民運動がある所、あらゆる所へ足を運んだ。係争中の裁判、守る会の定例会議でも安里はなくてはならない人だった。
水俣から帰った夏の終わりごろ、安里は会のメンバーに体の不調を訴える。「ご飯がのどにつかえる感じがするな…」
多忙な安里は住民検診も受けておらず、食事もろくに取っていなかった。集会で演説する際、声がしわがれるようになっていた。
年の瀬、体調を崩した安里は琉大付属病院で検査を受け、2日後に入院する。入院してからも、数々の見舞客に加え、守る会の報告や相談は続いた。
安里は守る会の一連の運動を記録し続けたように、病床で体温や血圧、その日の感想を日誌に細かく記録した。
2・16 第8回公判。バス1台、感激。見舞に全員見える。涙が止まらなかった。
3・12 負けるな。不屈の金武湾の闘いのために。人の道を求めるために。水俣の子らを思えばまだまだはるかにましだ。
5・9 今日はゆうな荘で同志達が討論集会を持っている。成功を祈って12階からゆうな荘を眺めて心はかり立てられる。
CTS(石油備蓄基地)建設阻止闘争を始めて10年。しかし、それも空しく、石油タンクは建設され操業は始まっていた。タンクの建設禁止を求める裁判は2審で争われていたが、その行方は思わしいものではなかった。
妻の芳子は主治医から相談を受ける。食道がんを告知すべきか。すでに手遅れではあった。安里は早く体を治して、入院前、漁民とともに取り組んでいた浜比嘉島のCTSの影響調査を目指していた。芳子は結局、病名を知らせない。7月の手術後、病床の日誌は家族が交代でつけた。家族以外は面会謝絶となっていた。
9月10日、安里は38度の高熱にうなされながら話した。「もう体がちょとも動かないだよ。もう10日もまたないと思うよ」
9月15日。「フランスやアメリカ、ソ連等の超大国(に)本当の幸せがあると思えない。私の思想にただ固執するのではなく、反対でもよいから本当の幸せとは何なのかよく考えてもらいたい。そして行動してもらいたい」
その後、安里の言葉はノートにない。せきが増え、血の混じったたん、赤い尿、熱、足のむくみなどの症状が顕著になる。頻繁に汗をかくようになり、10月18日、体温が36度を割った。
10月22日午後2時、臨終。長い闘いは終わった。69歳。正式な遺書も遺言もなかった。
死の3、4日前、安里は浜比嘉島の方角に向いてベッドの上にひざまずき、「もう少し、浜比嘉島の漁民のことをやりたかった」とつぶやいた。妻の芳子はその姿が今でも忘れられない。
(沖縄タイムス1995年5月16日)
② 「海は生活の基盤」と説く
安里清信が本格的に反石油基地闘争に取り組み始めたのは1973年の5月。生まれ育ってきた屋慶名の海に「異変」が起き出してからだ。
そのころ、海中道路で本島と結ばれた平安座島では、石油精製工場と石油備蓄基地(CTS)が既に操業を開始。「沖縄石油基地」も、平安座島と宮城島の間の海、約64万坪を埋め立て、CTSを建設する計画を進めていた。
すでに8割が埋め立てられていた。
これらの石油企業を誘致したのは、与那城村(当時)であり、琉球政府(同)だった。60年代後半、琉球政府は、米軍基地依存経済からの脱却を図るには第2次産業の振興が不可欠として、当時本土でも花形産業であったCTSの誘致を決めていた。
「事故や公害の心配はない。税収や雇用も増え、村は潤う」と村や社側は説明していた。実際、ガルフ社は70年に海中道路を完成、「離島苦解消」に島民はわいた。
しかし71年以降、原油流失事故や工場からの悪臭騒ぎが発生。漁民は一時、操業を停止した。住民の不安が高まってきたころ、金武湾もまた、海中道路によって分断され、潮流の変化などを見せていた。
安里は「与勝の生命と自然を守る会」会長として、闘いを続けた。73年9月には金武湾沿岸の具志川、宜野座など5つの団体が安里らと共同歩調を取り、「金武湾を守る会」が発足した。
守る会はCTS建設の白紙撤回を求め、県庁での座り込み、公開質問状、村民総決起大会など幅広い闘いを展開していった。
守る会は抗議行動だけでなく、教職員らが中心となって「水俣病」などの公害の実態を伝える映写会も開いた。現与那城町議の花城清繁(50)は「まだ沖縄にはほとんど公害がなかった。おじー、おばーたちには公害の意味を含め、1から教えていかねばならなかった」と振り返る。
そのお年寄りたちが守る会の原動力になった。安里は彼らを大事にし、よく話を聴いた。与那城の歴史、戦争、農漁業-多岐にわたる先人の知恵を克明にメモし、闘いの中に、自分の思想の中に、取り入れていった。
泡盛の好きな安里は、守る会のメンバーらと飲むと、よく昔の海について語った。イカやエビが苦もなく採れた時代。住民の暮らしが海と共にあった時代。「海はジングラ(金の蔵)、いわば銀行なんだ。大量に採るのではなく、その日の生活を満たすものを下ろしにいくための銀行」。生活の基盤である海の大事さを説いた。
安里らがつけた火は、瞬く間に広がった。屋良朝苗知事の支持母体である県職労、高教組、県労協など革新団体がCTS建設中止を求めた。さらに県議会経済労働委員会は73年11月12日、守る会の陳情を革新与党の賛成多数で採択、CTS反対に回った。
翌74年1月19日、ついに屋良知事は「CTS撤回」を表明する。闘いは大きな前進を勝ち取ったかのように見えた。
(沖縄タイムス1995年5月18日)
③ 屋良知事相手の闘い
屋良知事の「CTS撤回」発言があってからも、沖縄石油基地の用地埋め立て、シーバース(海上桟橋)建設は続けられた。
CTS以外の建設を求める知事に対し、同社は「既に500億円近い投資をしている」などと工事推進の方針を崩さなかった。国や沖縄開発庁も屋良発言に難色を示した。第1次石油ショック(73年10月)後、石油の安定供給・確保(備蓄)は重要な国策だった。
安里清信は1913年(大正2年)に生まれ、県立農林学校卒業後、36年から日本の植民地だった朝鮮(当時)で教師となる。現地で戦争が始まり、召集され戦闘にも参加。先妻と2男は敗戦後、汽車に飛び込んで自決した。
破壊された沖縄に帰った47年、皇民化教育の反省から、二度となるまいと思っていた教職に復帰する。米軍政権下で十分な予算のない中、校舎の建築から始め、イモ、米の食料作りや植樹など復興に力を注いだ。
知事と安里は、復帰前の主席公選と立法院議員選(1968年)をともに戦った先輩、後輩の仲である。津堅小中学校校長で退職後、頼まれて出馬した安里は落選。知事の引き上げで、翌年から観光開発事業団(元県観光開発公社)理事に就任する。
3年間の激務で体を壊し、退職後は養蚕をしていたが、CTS建設に驚き、闘いに立ち上がった。敗戦、米軍統治、そして本土復帰の歴史の中で、「国策というものは、いつも沖縄を犠牲にしてきた」。そんな思いが安里にはあった。
埋め立て工事は終了し、74年5月、沖縄石油基地は竣工(しゅんこう)認可を県に申請した。認可は埋め立て地の登記に必要で、焦点は、屋良知事がこれを認可するかどうかだった。
守る会の抗議団は連日、県庁まで足を運び、申請の却下を強く求めたが、知事は「団体では会わない」と交渉に応じなかった。守る会は74年9月、漁民6人を原告に、「知事が72年に同社に交付した埋め立て免許は、漁民の同意などの点で手続き上のミスがあり無効である」として、屋良知事を相手取り、法廷闘争に入った。
安里は著書「海はひとの母である」(晶文社)で、知事との認識の違いについて述べている。「大きな組織の人間で、志向は東京の指導者と変わらない」。日本の1県としての復帰を果たした屋良、「植民地解放」を唱えた安里。CTS問題で対立するとは予想だにしていなかった。
75年10月、那覇地裁は「埋め立て工事は完了しており、元通りにするのは困難」として訴えを却下した。
竣工認可を阻止せねば-。安里は仲間3人と県庁前でハンストに入る。このとき62歳。新聞の取材に「県民の資産である海を大企業に売り渡すのだから、首里城明け渡しと同じだ」と訴えている。
「裁判の結果も出た。企業の認可手続きは法律上の問題はない」。ハンストから6日目、屋良知事は竣工を認可した。
(沖縄タイムス1995年5月21日)
④ 「新たな支配」への反発
小さく細い体、ふろしきに書類を包み、げたを好んで履いていた。日に焼けた柔和な表情が、企業や行政と渡り合うときには「金武湾を守る」闘士の顔に変わった。
政党、セクトも含め、安里清信の元には多くの人が集まった。彼らが参加するのを拒まないかわり、観念的な理論やイデオロギーを排除し、徹底した「住民主導主義」を貫いた。
「対自民党」「対大資本」といった既成の理論や、外国の思想は、歴史と文化の異なる沖縄の住民運動には決してプラスにならない、保守も革新も、右も左もない、との考えがあった。住民1人ひとりが責任を持って動くべきだと。
戦時中に勤務した朝鮮で、日本の侵略のひどさを目の当たりにしてきた安里は、沖縄もまた「植民地」でしかないと感じていた。守る会の崎原盛秀に話していた。「ヤマトは戦後になっても変わらん。沖縄がヤマトの支配を捨てて自立するしかない。できるなら、独立だと思っている…」と。
生存の基盤である土地と海を奪われ、沖縄に集中する米軍基地と石油基地。期待された税収・雇用効果もなく、赤字に転落した村財政。こうした状況を安里は「新たな沖縄支配」「政府の棄民政策」と、とらえていた。補償金や補助金をもらって食いつなぐ生き方を否定し、自立のために必要な自然を守るべきだと主張し続けた。
一方で安里は賛成、反対に分かれた地域住民の対立を危ぐしていた。地域生活、文化までも破壊されることを恐れた。そこで長期化する闘争に、チクラマチ(屋慶名の棒術)など伝統文化の復活や綱引き、村芝居、金武湾ハーリー大会の開催など「遊び」を融合させていった。「かりゆし会」という老人のサークルも結成し、農産物の展示会を開いたりもした。
埋め立て地の竣工(しゅんこう)を認可された沖縄石油基地は、タンク設置の許可を県に求めた。手続きや設置基準に問題がない以上、県はこれを拒否できず、屋良知事は任期切れ直前の1976年6月22日、設置を許可した。
守る会は控訴していた「埋め立て免許無効確認訴訟」を一時休止し、77年4月、タンク建設工事の差し止めの仮処分を求める新たな裁判を起こす。生存権と環境権を柱に、CTSタンク設置に伴う公害や危険性を訴えた。原告は与那城、勝連、具志川市の農・漁民ら計1250人。しかし、勝ち目のない裁判だった。守る会から離れる人も次第に出てきた。
79年3月、那覇地裁は「タンク設置でたとえ火災などが発生しても、原告住民の生命、身体、健康に被害を与える危険性はない」として訴えを却下。翌80年3月には、海上デモなど強硬な反対運動にもかかわらず、完成したタンクに油が入れられた。
長年の反CTS闘争は実らず、「タンク完成」「操業開始」と、積み重ねられていく既成事実の前に、安里らは闘争方針の転換を余儀なくされていく。
(沖縄タイムス1995年5月22日)
⑤ なお生き続ける遺志
安里清信は、CTS建設の話が浮上した多良間や与那国島、新空港建設で揺れる石垣島・白保にも飛び、精力的に講演していた。カンパを集めて白保漁民を金武湾に呼び、埋め立ての影響を潜って見てもらったりもした。
安里だけでなく、若手メンバーも白保の運動を支援していた。「白保の運動もせねばならず、人材が手薄になっていった」(花城清繁与那城町議)。もはや「金武湾を守る会」に、かつての勢いはなかった。
1981年12月、安里は食道がんのため入院。初めは見舞いも兼ね、闘争の報告などもあったが、面会謝絶などの病状の悪化に伴い、それもなくなった。
守る会と弁護団は82年10月20日、「タンク建設差止め仮処分」裁判の控訴を取り下げた。「10年に及ぶ闘争は、CTS建設に対する県民世論を喚起し、多くの賛同者を得た。企業の安全に対する意識を変えた」。安里が死ぬ2日前だった。安里の死は、そのまま「金武湾を守る会」の終わりにつながった。
守る会代表世話人として安里とともに闘ってきた崎原盛秀(61)は、今年3月で沖教組を退職した。「自然を守ることがいかに大切なことか、多くの人に認識してもらったと思う。また、守る会のメンバーも無農薬農法の実践など、闘争の中で得た知識や物の考え方を実生活で生かしている。安里先生の思想は、白保などその後の住民運動にも受け継がれている」
91年、米石油会社ガルフが造った屋慶名と平安座島を結ぶ「海中道路」は、県道「伊計平良川線」に移管した。2車線から4車線に拡幅し、これまで長さ30㍍の1本だった橋の部分も、280㍍と96㍍の2本にする工事が進められている。
橋の部分が広がることで、「潮の流れがよくなり、金武湾の浄化につながる」と地元の期待は大きい。道路の途中には駐車場も造られ、将来的には売店やトイレも設置し、リゾート地として発展させようとの計画もある。
また花城によれば、CTS建設で反目し合っていた人たちも、町の発展のためにと、一部で「雪解け」が進んでいるという。
橋は97年度、道路は98年度に完成する予定だ。
安里の死後、生前の「教育功労」で叙勲の話が舞い込んできた。妻芳子が崎原に相談を持ちかけると、崎原の答えは「安里先生が勲章を喜ぶと思いますか」。家族で話し合った結果、辞退した。
安里は反CTS闘争に全精力を注いだ分、ほかのことにはまったくむとんちゃくだった。教員をして家計を支えた芳子は「選挙の借金、CTS運動のときの借金もようやく返済しましたよ」と笑って話す。
自宅の書庫には、安里が集めた多数の資料や文献が眠る。資料に交じって、今はもうほとんど見なくなった、直径15㌢ほどの「廃油ボール」が無造作に置かれていた。安里の家には、環境問題や住民運動の勉強のため、今も県内外の大学生が訪ねてくる。
(沖縄タイムス1995年5月23日)(この項 社会部・平良秀明) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
このページのトップに戻る
THE SEVENTH EMIGRANT に戻る