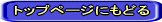「沖縄経済自立の構想」
(『新沖縄文学・48号』沖縄タイムス社1981.6)
沖縄経済研究会〔文責 原田誠司・安東誠一・矢下徳治〕
はじめに
第二次沖縄振興開発計画(以下、二次振計)の策定作業が開始され、すでに県当局の「素案」が公表された。復帰特別措置の延長事項も収約されはじめた。また、公用地法の期限切れにともなう「強制使用」などの声も上がり出した。こうした様々な動きは、すべて1982年5月の沖縄復帰=返還10年という節目をめざしたものであり、いわば、復帰10年の決算が問われる時期に入ったことを示すものといえよう。
われわれは、この間、経済自立論議が72年復帰それ自体を洗い直す契機となり、文字通り経済自立が沖縄の自立にまで及ばざるをえないことを提起してきた。復帰10年の決算が問われようとするにあたって、いよいよ具体的な経済自立とその条件を構想しなくてはならない。だが、それは同時に日本経済と日本国家のあり方をどう変革するかという問題でもあるところからわれわれのよくなしうるところではない。あえて非力を承知の上で、以下の順序で沖縄自立の構想にむけていくつかの問題提起を行いたい。
第一章 復帰10年と沖縄経済
第二章 日本の開発政策と二次振計
第三章 72年復帰と沖縄の位置
第四章 少数民族と自決権・特別自治権
第五章 沖縄経済自立-政治的自立の構想
一、一次振計は未達成
復帰後の沖縄は「沖縄振興開発計画」(注1)(以下、一次振計)にもとづいて経済・社会各分野の振興・開発が進められてきた。この一次振計の目標は、①本土との格差是正、②自立的発展の基礎条件の整備、をもって「平和で明るい豊かな沖縄県」の実現をはかることにあった。復帰9年の今日、この目標ははたして達成されつつあるだろうか?
すでに一次振計が破綻したことは「振り出しに戻った沖縄経済」として牧野浩隆氏によって鋭く指摘された(『沖縄経済を考える』)。われわれは、現状把握のためにふたたびこの点に立ち戻ってみたい。
県当局の資料(『総点検資料』)からも明らかなように、①人口では77年段階で目標をこえたが、②生産所得は33パーセントしか伸びず、その結果一人当り所得は全国平均の70パーセント弱の水準に低迷し、③自立的発展のメルクマールとされた産業振興も二次産業が伸びず、逆にマイナスと考えられた三次産業の比重が高まり所期の目標とは反対の結果となってしまった。しかも、計画当初予想もされなかった高失業状態(失業者2.1~2.8万人、率にして5~6パーセント)をも生み出した。
一次振計はたしかに、破綻したといってよいだろう。では、その原因はなんであろうか。県当局(沖縄振興開発審議会総合部会、専門委員会報告)は、①一次振計策定当時高度成長であったこと、②73年石油危機以降の影響を受けたこと、③人口増が予想以上であったこと、などに原因を求め、三次産業のウェイトが高いことは跛行的だとの考えをあらため、国内分業のなかで位置づけ直すべきとすら指摘している。これら三つの原因は、現象的にはその通りであろう。だが、この説明は日本経済の低成長に責任を押しつけた以上ではない。一次振計は、放置されたのではなく計画に沿って実施された結果、こういう事態を招いたのである。われわれは原因を探るためこの沖縄経済の現実を、一つには復帰前との関係で、二つには本土各地域との関係で比較検討してみたい。
(注1)一次振計の政治的目標の問題点(基地撤去の削除)については、比嘉良彦「沖縄自立経済論の問題点」(『沖縄経済自立の展望』所収)を参照。
二、復帰と沖縄経済の周辺化
まず前者の視点からみると、復帰後の沖縄経済は復帰前にくらべ明らかにより畸型化(注2)されたといえよう。
(1)基地経済の構造は弱化するどころか拡大再生産されている。
基地経済の構造とは、基地依存経済という意味ではない。それは、①沖縄は日本とアジアの中継点に存在し、②その沖縄の島嶼としての位置の価値が外生的(帝国主義的)に「軍事基地」に特化されたため、③自立的経済発展を剥奪された経済構造であると言うことができる。この島嶼としての沖縄の位置を利用したのは言うまでもなく世界資本主義システムの中心部分たる米・日両帝国主義であった。復帰によっても沖縄の位置の利用は変らないばかりか、一層多様に展開されているようになった。軍事基地は日本政府による軍用地料の大幅アップによって維持され、米軍・米政府援助・収入にかわって日本政府の財政資金撒布が登場し、CTS=石油備蓄基地の恰好の適地として選定され、さらに観光地としても評価されるに至っている。その結果、復帰前の米政府援助と米軍関係収入に依存しつつも維持した高成長と均衡(完全雇用状態)が破壊されてしまった。日本政府への依存、日本資本主義の体系のなかでの沖縄の位置の積極的利用によって、沖縄の非自立的経済構造は、一層拡大・深化させられたのである。
(2)また、日本資本への系列化、従属のなかで沖縄経済の「非接合性」がさらに拡大した。
一般に経済構造が非自律的であることがそのまま非接合的であるとは限らないが、沖縄の場合は、軍事基地を維持するための経済(基地経済)であったため一個の国民経済としての接合性は当初から存在しなかった。復帰前の農-工関係は<きび生産-きび加工部門>という形での一定の接合性の上に成立した。だが、きび生産への特化は、日本の甘味資源確保政策(日本資本主義のアジア進出の一環)に規定されて成立し、パインとともに日本および世界の一次産品市場に左右され続けた。沖縄農業は沖縄人の食糧供給部門への発展をはばまれ復帰後は低迷するばかりである。
他方、工業はきび加工部門(原料糖加工)が日本の糖業資本に系列化されつつも主流(60年代の二次産業の60パーセント)をなし、これに基地関連部門として建設業が成長した。工業の自律的・内発的発展の条件は明らかに欠如し、軽工業への特化=偏向から沖縄の工業はきわめて部分的・周辺的であった。復帰後は、保護措置の撤廃、本土資本・商品の進出・流入および世界不況により、①激しい倒産と本土資本への系列化、②糖業の低迷と公共事業に従属した建設業の増大、③石油備蓄産業の拡大、などがもたらされた。結局、糖業中心の産業構造が崩壊し、建設業が二次産業の軸になったが、基礎・機械部門の欠如(大手本土資本の進出はゼロ)、つまり、産業構造の非接合性のゆえに沖縄工業は衰退・周辺化・崩壊へと向っているのである。
(3)沖縄の過剰労働力構造が明らかにされた。
復帰前(60年代)は就業人口35~40万人弱、一次産業から三次産業への大量の労働力移動、失業率1パーセント未満(2~3000人)という状態であり、それなりの均衡を保っていた。ところが、復帰後は、就業人口が伸びず、三次産業の比重が高まっただけではなくまったく新たな事態が出現した。復帰と不況にからんで大量の失業者の発生(失業率5~7パーセント、2.2~2.6万人)、本土への若年労働力の流出増、Uターンの増加(年に2000人)、さらには沖縄内部での都市部(那覇市)への労働力移動・集中などである。
この新しい事態は、基地経済下で表面化しなかった沖縄の過剰労働力構造が顕在化したものとみることができる。もちろん過剰という意味は、絶対的に扶養人口が過大だということではない。沖縄経済の発展構造との関係における過剰労働力問題である。かつては三次産業の肥大化のなかに過剰労働力が吸収されていたが、復帰後日本資本主義に組み込まれることによってもはや不可能となり、「還流的移民」状態(Uターン)や都市への失業-半失業層の滞留などに表われているように、いわば沖縄の労働力が日本資本主義のなかで「マージナル化」を強いられつつあると言わなくてはならない。
以上から明らかなように、沖縄経済は「本土との格差是正」や「自立的発展の基礎条件」の成就どころか逆に復帰によってより畸型化したのである。それは、世界資本主義システムの中心部のなかで米から日本国内への編入によって、いっそう周辺資本主義化が進んだこと、「低発展の発展」状態が強まったことを意味する。
(注2)詳細は、原田誠司「沖縄経済の独自構造」(『沖縄経済自立の展望』所収)を参照。
三、周辺化する諸地域の構造
では、日本本土諸地域と比較して沖縄の周辺化はどのように把握できるだろうか。これを次に検討したい。(注3)
本土内でも戦前から国内植民地的「後進」地域として存在した東北地方の開発とその周辺化の特徴は次のようにまとめられる。
(1)東北は戦後、もっとも徹底した農地改革と財政投資の展開によって、戦前の東北がもっていた生産関係の非近代性、資本の過小という発展阻害の要因を相当程度除去した。その後、高度経済成長の波にのって東北地方の経済的地位は急速に高まり戦前からの貧困問題は解決したかにみえる。南九州より上位に立ったのである。
(2)しかし、東北の経済構造をみると地域経済の解体現象とでもいうべき現象が顕著となっている。
第一に経済の非接合化である。つまり、先進工業地域からの工場進出による工業化は、「飛び領土」型の工業化であり産業活動は中心地域で担われている基幹的経済活動を支える周辺部分の、相互連携を欠いたたんなる寄せあつめと化している。
第二に労働力の価値分割が常態となったことである。賃金水準と必要生活費とのギャップから兼業や家族多就業が広汎化し労働力の価値分割を強制されている。つまり、東北地方の生活は細切れの労働、細切れの収入の寄せあつめで成立している。
第三に自然や土地の急変である。工業的に土地や自然が改変され、かつその管理が粗放化あるいは放棄され、風土が廃棄されつつある。
第四に財政資金のテコ入れなしには成立しない経済である。直接雇用(公務員)、公共事業の波及効果、米価維持政策などの財政依存状態は東北経済を主導するものが財政資金であることを物語っている。この財政的効果も地域経済の循環・接合性の弱さから中心地域への資金の還流というかたちで減退させられる。
このような地域経済の解体現象は、国内の周辺地域にも共通しており、いわば、国内に「ゆたかな低開発経済」が存在していることを示している。
(3)では、東北経済の日本資本主義経済のメカニズムのなかでの役割をどうみるべきか。
まず第一に縁辺労働力の貯蔵庫である。東北は、安価で良質でかつ弾力的な利用の容易な労働力の貯蔵庫としての役割を日本経済にたいして担っている。この労働力の主力は、農家が生み出す兼業労働力であるが、これは大都市圏=中心地域の基幹的労働力の縁辺=周辺を形成している。
第二に弾力に富む市場=財政資金撒布政策を展開する場であることである。耐久消費財などの消費財市場、農業・生産財市場であるとともに公共事業を媒介にした大都市圏企業の市場(投下資本の還流)となっている。
第三に「場所」と「位置」の貯蔵庫であることである。東北をはじめ周辺地域は、さまざまな産業施設の選択的な立地空間というだけでなく、大都市圏に立地困難あるいは不経済な諸施設(大規模産業施設、公害発生・危険施設)のそれとしての役割も負っている。むつ小川原開発、原発、CTSなどはその典型である。これは個別企業だけでなく、国家の経済戦略にそって進められ、各周辺地域の新たな「場所」「位置」を発見することによって逆に地域経済の解体を早めることにつながっている。
以上から明らかなように高度成長を経た東北をはじめとする本土周辺諸地域経済は、一言で中心地域とその資本蓄積にとってマージナル(縁辺=限界的)な経済単位として存在させられているといってよいだろう。これら周辺地域は中心地域とその資本によって、その発展の方向を左右されコントロールされる補完的役割を担わされているのである。しかも低成長経済を余儀なくされる80年代においてこの周辺地域のマージナル性は、国際的な(アジア・太平洋圏の)基準において決定され、周辺地域の価値は第三世界のそれとの比較における選択に委ねられよう。
(注3)詳細は、安東誠一「東北開発と沖縄開発」(『沖縄経済自立の展望』所収)を参照。
四、復帰10年の決算――国内植民地
以上を総括してみると復帰10年の決算はほぼ明らかになる。
(1)まず、沖縄経済は日本資本主義経済の一環に組み込まれたが、それはマージナルな経済単位、つまり周辺地域経済としてである。しかも、復帰8年の現実は東北のような工業化過程を欠如したまま(大手資本による工業立地はゼロ!)周辺経済化を強制されているところに東北とは異なった沖縄経済の特質があるといえよう。もちろん工業化したところで東北の再現以外にならないこともたしかであろう。
(2)沖縄が非工業的周辺地域として存在させられているのは、日本の辺境のなかでも、特異な「位置」とその利用の歴史によっている。沖縄は地理的には日本本土とアジアとの中継点に位置する島嶼であるが、その位置がアジアにおける資本主義的帝国主義システムの<中心―周辺>構造の連結点として利用されてきた。沖縄の第一次併合(1879年)は明治政府の対清政策からであったし、第二次世界大戦での敗戦では切り捨てられ、戦後は米帝国主義の属領とされアジア防衛の一大軍事拠点として利用された。復帰後はこの軍事機能を変更しないまま石油備蓄拠点としても位置づけられ、日本のアジア・太平洋への中継点(南進拠点の方向にむかって)となりつつある。このような沖縄の位置の利用が構造的に周辺資本主義的発展を強制し沖縄経済を非自律的・非工業的周辺経済たらしめたのである。
(3)では、島嶼としての沖縄の位置はなぜこのような帝国主義的資本システムの中心部(米・日)に利用されたのか。歴史的にみれば明らかに沖縄人が「島嶼民族」として存在しながら自らの島嶼=地域にかんし無権力状態にあったからである。「島嶼民族」という規定が積極的に主張されたことはないにしろ、沖縄学や皇民化教育さらに日本の資本と国家の対応批判からして沖縄人が「島嶼民族」として存在しつづけていることは明らかである。
沖縄の位置利用の決定権が明治以降一度として沖縄人に委ねられなかった、という意味での民族的疎外が根本的原因であろう。
(4)このようにみてくると、沖縄はたしかに復帰によって日本国家の平等な一構成部分として他地域と対等な法的・政治的・経済的地位を確保した。しかし、民族的疎外を基底においた沖縄経済の非自律的・非工業的周辺経済化の進行は、その質において沖縄の位置と沖縄人総体を収奪・抑圧・差別のもとにおいていると言える。この意味で沖縄は国内植民地化されているのである。
かくして、一次振計破綻の原因はここまで深められなくてはならず、安易に格差是正や自立的発展の条件を呼ぶのではなく、格差とは何か? 自立とは何か? が客観的に再把握されなくてはならないのである。このように一次振計の決算がなされる必要があろう。
第二章 日本の開発政策と二次振計
一、日本資本主義の開発政策
沖縄の日本への併合は、同時に沖縄の経済社会や労働者が日本資本主義の開発政策のなかに包摂されることを意味する。日本政府の沖縄への開発政策は、沖縄への個別的、特殊的な対応であると同時に、その基底には、高度成長過程で試され、磨かれてきた開発政策がある。ここで、その政策のひとつの帰結である新全総と、その修正版である三全総の性格規定を行い、批判のあり方について明らかにしたい。
(1)新全総と三全総
新全総(1969年閣議決定)の計画論理は明確である(「『資本の論理』の結晶」――宮本憲一)。資本の強蓄積を効率的・持続的にすすめるための国土デザインであり、国土幹線ネットワーク、大規模生産基地、広域生活圏等の主要プロジェクトは、国内資源、労働力を効率的に動員・再配置して、生産のスケール・メリットと社会的分業のメリットを最大限追求するという一点の目的から発想されている。
新全総は、一定の「成果」を達成したが、しかしその途上で矛盾を露呈し、結局棚上げの形でその役割は一応形式的には終息した。その要因として、住民の抵抗、国内外の経済環境の変化が通常あげられるが、しかし、開発政策自体のもつ政策技術の限界、すなわち資源、環境や労働力、地域社会等の社会的資源の管理体制の不十分さ(甘い認識)をあげることを忘れてはならない。この点は、政府自体の一定の「総括」として次の三全総の計画論理につなげられる。
三全総(1977年閣議決定)の性格は、基本的には、成長のスピードダウンと経済環境不安定化にともなう調整機能であり、次の階段へのつなぎであるといってよいだろう。従って「開発」より、資源管理、社会管理など「管理」を前面に打ち出している(具体的には定住構想)。三全総独自の開発プランはなく、新全総の計画枠組を継承した上で、むしろ手法的には行財政等いわゆるソフトな手法の方に関心が向けられている。
(2)三全総批判の特徴
新全総はその論理が明確だっただけに、広汎な批判と抵抗を喚起し、政治的争点を結びえた。新全総の一定の路線修正のうえにたつ三全総にたいしては、批判に大きなバラつきと揺れがみられる。そして批判力そのものが弱くなっている。典型は次の二つである。
ひとつは、路線修正への一定の評価、受容である。たとえば新全総をめぐる対立状況を「資本の論理」と「生活の論理」との対決と規定した宮本憲一氏は政府開発政策への、氏の今もかわらぬ鋭い批判にもかかわらず、三全総の生活・環境政策については一定に評価可能とし、新全総の尾をひく産業政策とが整合のとれない「混迷の産物」としている(「『福祉型開発』よそおう三全総」、『住民と自治』1977年11月号所収)。
もう一つは、批判の視座が現実から遊離し、理念化した批判である。それはいわゆるエコロジスト的地域主義の主張者にみられ、現実に進行する資本の政策との具体的な対抗の軸を設定することができない。
この二つの典型は、いずれも「資本」と「地域」とのダイナミックな対立関係を浮きぼりにすることができず、結局市民主義的な対応に帰結する。
政府・資本の開発政策批判の足場は、資本の論理によって具体的に進行する「地域の周辺化」にもとめられねばならない。日本資本主義は、地域の急速な周辺化(すなわち地域独自の生産関係の解体、中央地域への従属化)を不可欠の要因として強蓄積=高成長を行ない、財政政策によって、地域の急速な周辺化から生じる矛盾・危機の露呈化を回避してきた。しかし、このような政策は高成長と国際経済関係の安定の条件のもとでのみ、成果があがる。三全総や田園都市国家構想にちらつく危機管理的視点は、政府・資本の危機認識の路線の模索の跡を示している。
(3)地域政策の今後
これまでの地域政策、すなわち企業の旺盛な投資活動とケインズ的財政政策を土台にした地域政策は、①成長のスピードダウン(投資、とくに能力増につながる投資の鈍化)、②財政問題(財政膨張、硬直化)、③国際経済環境の変化(貿易摩擦、海外への工場進出の要請)、エネルギー問題(エネルギー・コストの上昇)、の諸問題に直面して、その遂行が困難になりつつある。
今後の地域政策を5~10年くらいの期間で展望すれば、次のようにいうことがてきるだろう。
第一に「開発」より「管理」が前面に出てくる。三全総の定住構想や田園都市国家構想は、低成長の不安定化時代の長期化に向けた、地域の労働力や土地・資源の管理強化のプログラムにほかならない。
第二に、国際分業化(とくに海外での直接生産体制)の推進と地域振興策(すなわち国内での分散化政策)との矛盾の調整が深刻な課題になる。結局は、日本資本主義全体の利益の追求のため、地域へのいっそうの周辺化の強制がすすむだろう。
第三に、地域経済社会の特定分野の部分的「自立化」が、財政負担を軽減する安あがりの地域づくりとして、政府・資本によっても試みられるだろう。その意味から、政府、資本によって周辺的機能に限定した一定の「分権化」「自主管理」が提起されてもいっこうに不思議ではない。
第四に、地域とくに資本にとっての遠隔地域の利用価値が変動するだろう。企業の投資活動からみると「後進」地域は、労働力やエネルギーの面からその利用価値は相対的に低下し、今後の長期的傾向として大都市圏への投資のウェイトが高まると思われる(大都市内部での労働力プール機能の拡大、輸送コストの上昇などから)。沖縄や九州、東北、北海道などは、たとえばエネルギー基地など特定の(地域の望まない)役割を強いられる状況になっていくだろう。
(4)批判の視点
われわれはこの事実をふまえて、これまでの批判論を的確に批判継承しつつ、開発政策批判の基本的視点を確立していかねばならない。
宮本憲一氏は、沖縄開発にたいする優れた批判や問題提起をされているが、われわれは氏の批判の基底にある「生活の論理」の限界性について再度触れておかねばならない。氏の生活の論理、そして自治体改革論は、国家ないし国民経済の枠のなかでの投資や所得の配分、あるいは財源や行政権限の配分の問題の次元をどうしても超えることができない。政府・資本が労働者の生活過程や地域社会をもその計画の射程範囲に明確に包摂しつつ市場拡大や危機管理にとりくもうとしているとき、その論理は攻勢的な位置を占めえず、防衛的・後追い的な役割にとどまるだろう。
西川潤氏は「内なる南北問題」論を提起している。しかし、この概念はきわめてあいまいであり、氏の論理の混迷を示していると思えてならない。結局、氏の限界は沖縄問題に南北問題的視点を適用しようとしつつ、最後まで「国家」「国民経済」の相対化の視点が欠落しているところにある。多国籍企業を主導者とした、国内外を通じた周辺化メカニズムの中に沖縄を位置づけることこそ、沖縄問題と南北問題の結合の真の意味がある。またここにこそ沖縄とアジア諸国との連帯の根拠がある。西川氏については、その論理の混迷を喝破する必要がある。
政府、資本の、生活や地域社会をも包摂した経済政策、地域政策の展開を前にして、もっとも求められる視点は、政策によって地域の政治、経済、生活、文化が急速に周辺化する事実を的確に認識し、そのメカニズムを透視できる視点である。しかもその周辺化は、周辺地域、海外周辺資本主義諸国を通じて国境を超えて無差別にすすめられる。だからこそ、日本運命共同体としての地域や住民への管理=一体化政策が不可欠となる。周辺地域住民が政府・資本の周辺化政策と対抗しうる視点は、日本資本主義と利害を共有した一構成員であるという当然視されてきた前提を疑い、国家、国民経済と地域との関係を相対化する視点である。
二、 二次振計とその批判
(1)二次振計(素案)批判
さきごろ二次振計(第二次沖縄振興開発計画)の県「素案」の内容が明らかにされた。「素案」でみる限り、二次振計は、一次振計の成果にたいする評価や沖縄経済のもつ問題にたいする視点が明確でなく、その政策内容も一次振計の延長上にあるものが主体であり、「素案」策定者の視点・意図自体がはっきり伝わってこない。しかし、あいまいながらひとつの方向性を「素案」のなかにかいまみることができる。それは、ひとつは産業振興への重点の設定であり、ひとつはそれを、沖縄の地理的・自然的特性を利用しつつ日本経済のなかでの沖縄の「役割」を積極的に見出そうとする姿勢である。
「素案」は、計画の理念を「平和で明るい活力ある沖縄県」としたうえで、総括的な目標を次のように述べている。「安定的に増加する人口に対応した就業の場を確保するとともに、県民の所得を増大させ豊かな県民生活を実現するためには、産業の振興をはかる必要がある。このため産業の振興開発にあたっては、県の有する地理的・自然的特性を積極的に活用するとともに基地依存経済から早期に脱却し、財政依存経済を漸次縮小して自立経済化へ向けて長期的な産業政策を展開するに必要な基盤を整備する」。そして、国際経済化、エネルギー・資源問題等日本経済のおかれた新しい経済環境の座標のなかに、沖縄のもつ地理的、自然的特性を位置づけ、さまざまの開発・振興プランがうち出されてくる(亜熱帯性気候を利用した低コストの野菜・花卉、肉用牛の供給基地、南方漁業中継基地、フリーゾーン=自由貿易加工基地、観光レクリエーション基地、国際交流基地等である)。
問題は、このプランの是否を問うまえに、現在における沖縄と日本の政治的・経済的関係のなかで、しかも現行の政策手段の枠のなかで、このプランが沖縄側の望む形でそもそも実現しうるのかという点にある。「素案」でみる限り(そこにはなんら新しい方法の提起がみられないため)、結局は、沖縄の特殊性を売り物に政府・資本の投資を呼び込むしかない。新しい交渉力(バーゲニング・パワー)の組織手法の創出でもない限り、現在の政治的力関係のもとでは、当初の構想とは似ても似つかぬ結末を帰結するだろう。いっそうの周辺化である。
「素案」の構想が実現に動いたとき、沖縄住民が手にするのは、自立化の跳躍台となりうる構想の具体化でなく、かわりに、中継貯蔵基地、CTS、核燃料再処理基地、低コスト農業基地等、一層の周辺化をおしすすめる「成果」である可能性の方が現実味がある。これは、これまで沖縄、本土を通じて日本の周辺地域がいくどとなく経験してきた不幸な事実である。
現在、バラ色の色調で語られている「フリー・ゾーン(沖縄自由貿易地域)構想」がその典型ではないだろうか。政府のうち出す開発計画の「初期構想」は多くの場合、政治的な役割を果す。「うまい話」が突然降ってわいてくるはずがない。かりにこの構想が実現したとしても、はじめの期待とは大きくかけはなれた、たとえば雇用効果もほとんどない中継貯蔵基地、すなわち「フリー・ゾーン」ならぬ「倉庫ゾーン」に終る可能性が強い、はじめの「構想」とまったく異なった「結末」へと変質していくメカニズムは「むつ小川原開発」で証明ずみである。
(2)反面教師―北海道自立経済論
二次振計「素案」のなかでも「自立経済化」の目標は高らかに謳われている。現在、「本土」においてもさまざまの地域で自立経済論議が交わされている。だが「自立経済」の意味はあいまいで混乱したままである。
最近、自立経済の意味を考える上で恰好のテキストが発刊されている。北海道未来総合研究所編『自立経済への挑戦――北海道開発への新視点』(日本経済新聞社、1980年10月刊)である(この報告をまとめた委員会の主査は、戦後日本の経済政策、地域開発政策の立案の多くに参画してきた稲葉秀三氏である)。
同書によると、北海道の自立経済化とは、域際収支の改善、均衡化である。つまり民間経済では北海道の対外収支が大幅な赤字になるが、これを財政がカバーし、その傾向はますます強まっている。そこで北海道経済の課題は財政依存体質から脱却することである、とするのである(同書12ページほか)。
では何故、財政依存からの脱却が必要となるのか。稲葉氏の説明によると、政府の財政再建の必要上、これまで優遇されてきた北海道への財政資金の配分がしぼられてくる。したがって財政に頼りにくくなるから民間主体の「経済自立」が不可欠になる、とするのである(同書35~36ページ)。
そして、そこから具体的政策は、域際収支悪化の主因となっている工業化の遅れの解消(同書12ページ)に重点がおかれ、そのため北海道の地理的・自然的条件のプラス面を活用して、①北方諸国を市場とした工業開発(同書14~15、17ページ)、②その主要な条件のひとつとして石炭火力と原子力を主体とした安い電力供給基地化(同書52~53ページ)、③進出企業へ売り渡す用地価格を下げるために、道債発行等自治体による相当部分のコスト負担(同書51ページ)、などである。
この書は、官製の自立経済論の本質を具体的に示した貴重なテキストである。
前にも触れたように、第一に、政府・資本にとって、財政撤布を基本とした地域政策は桎梏となりつつある。財政の膨張と硬直化を防ぐため地域の民間経済自体による一定の「自立」が必要とされ、それを地域に要請(強制)する段階になっている。第二に、安いエネルギーを前提に急速な重工業化をめざしてつくりかえてきた国土構造を新しい経済環境に即して再編する必要が生じている。
同書による北海道の自立経済構想は、その意図の有無にかかわらず、右に述べた政府・資本の要請に応えたものになっている。それは「自立経済化」の名のもとに、地域経済・社会の維持コストを下げ、さらに「国家」、「国家経済」の要請に応じて地域経済・地域住民の体質転換をすすめようとする、新たな「従属経済化」の政策にほかならない。
現在さまざまに主張されている自立経済論や地域主義などの論理は、冷徹な現状認識と具体的な対抗軸の設定に成功しない限り、政府・資本による地域への「自立」の強制、すなわち、新たな地域従属化の政策攻勢を前にして、その大半が政府・資本の地域支配=周辺化政策の枠組のなかに包摂されていくのではないだろうか。
沖縄の自立経済論はどのように志向していくのだろうか。現状認識と争点をあいまいにしたまま心ならずも政府・資本の新しい地域政策に吸収されてしまうのか、あるいは(先の北海道自立経済論のように)自ら率先して地域再編の片棒をかつぐのか、それとも反周辺化の論理に支えられた対抗的な自立経済の構想か、その選択が迫られている。
この選択を規定するのは主体の条件である。われわれはさらに主体の問題に論をすすめていかねばならない。
第三章 72年復帰と沖縄の位置
一昨年(79年)の日本平和学会のシンポジウム「1980年代の沖縄-平和と自立、内発的発展の展望」の討論をふりかえって、新川明氏は次のような鋭い提起を発した。
「経済自立論や地方分権論を考えるに際して要求される長い射程の発想のバネとして、あるいは文化論における思想の可能性を追求する想像力の豊かなひろがりを獲得するためにも、“独立論”にかかわる議論は、もっと深められてよいと思う。この問題は、そのまま日本の国家体制のありよう、さらには日本を含めた新しい国際関係についての将来構想にかかわる問題を提起せずにはおかない筈だからである。」
われわれも、経済の自立の展望が、このような政治的自立の構想と不可分であると考える。以下、政治的自立にかんする問題点を検討したい。
二、復帰論と独立論
(1)復帰運動の政治理論的陥穽
沖縄の政治的自立の構想を考えていくことは、戦後沖縄の闘いのすべてを象徴している復帰運動のとらえかえしから出発しなくてはならないだろう。
すでに多く指摘されている通り、沖縄の祖国復帰運動とは、きわめて心情的なものとして展開された。逆にいえば、政治的・政治理論的レベルではきわめて脆弱であったといえる。そこでは、戦後における日本からの分離という事態を、歴史的な日本・沖縄関係、当時沖縄のおかれていたきわめて不分明な国際(法)上の位置等からとらえかえし、沖縄の自らの進路を議論し、決定することは、沖縄人=日本人、沖縄=日本との心情の前に一貫して不十分であったということができる。
そうした復帰運動の主情的性格は、サンフランシスコ条約三条にたいする理解の誤まりとして60年2月の「立法院2・1決議」に典型的に表現されている。国連の植民地解放宣言を援用してのこの決議には、<サン三条によって、沖縄にたいする日本の領土権が否定され、意志に反する不当な支配が行なわれている>との認識で貫かれている。
しかし、サン三条は、「日本国は、北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)孀婦岩の南方諸島(小笠原郡島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」と述べているのである。すなわち、カイロ宣言・ポツダム宣言で帰属が未定であった沖縄を<沖縄住民とはなんであるからどうするのか>という首尾一貫した論理を欠落させたまま、<国連にたいする米国の信託統治提案に日本が同意する>といったひねった論理操作を行ったうえで、はじめて、日本の「潜在主義」論なる領有権主張の根拠を形づくったのである。一言でいえば、日本国家は、沖縄住民を切り捨てることによって領土としての沖縄を手に入れたということである。論理的に言って、沖縄が「植民地」状態にあり、沖縄人民が「住民の意志に反して、不当な支配がなされている」という認識にたつならば、沖縄住民の意志の頭上でとりかわされたサン条約そのもの(三条だけでなく)を否定し、沖縄の進路があらためて問われるべきであったと思われる。
(2)復帰論と沖縄学・日琉同祖論
では、沖縄の法的・政治的位置、言いかえれば、日・沖関係はなぜ論理的に明らかにされなかったのか。
このような復帰心情の奥底には、薩摩侵略による民心の荒廃を収撹した羽地朝秀以来の、とりわけ、日琉同祖論を実証せんとして伊波普猷によって集大成された沖縄学が横たわっていることは新川明氏、新里金福氏ら多くの人々によって指摘されている。
伊波普猷は、薩摩以来の日本による歴史的支配と抑圧、そのなかで形成された沖縄人の日本にたいする異質感からの脱却を日本との同化・一体化に求めた。伊波の出発点は沖縄を「異民族」視する当時の傾向にたいし、「沖縄人は日本人である」という命題をあらゆる学問的考証により証明することによって、差別からの脱却と沖縄人の日本人としての覚醒を喚起するところにあった。それゆえ伊波は、第一次琉球処分を「迷児を父母の膝下に連れて帰った様なもの」として賛美し、ついには、彼の沖縄学が皇民化→沖縄戦の悲惨へと至る戦前沖縄史の悲劇にたいする大きな思想的支柱となったことは周知のことである。
戦後、伊波が遺著『沖縄歴史物語』の末尾で「沖縄人は日本人ではない」というマッカーサーの談話に触発されて、「沖縄人」が「自分の運命を自分で決定することができなかった境遇におかれて」きたことをふりかえりつつ、独立の方向を示唆していることは、伊波の日琉同祖論の事大主義的本質と、なによりも日琉同祖論の自己破産を示すものであった。
にもかかわらず、復帰論と復帰運動は、この沖縄学的発想に依拠してなされていったと考えられる。
(3)初期独立論とその限界
他方、人民党をはじめとして、戦後主張された独立論も、この沖縄学的発想をこえるものではなかった。
人民党は、日本共産党の第5回大会における「沖縄民族の独立を祝う」メッセージを受けて、明確な少数民族論にたっており、公然と掲げないまでも、「自主沖縄」、少なくとも「人民自治政府の樹立」、「全沖縄民族の解放」のスローガンに示されるように、事実上独立論の主張を掲げた。この主張は、51年2月に帰属問題にたいする「琉球の帰属は全琉球人民の意志によるべき」との態度表明にみるように、50年群島知事選を経て後の51年までつづく。
しかし、群島議会での復帰気運を追認してこの立場は清算された。ここにおける米占領軍にたいする解放軍規定、あるいは、機会主義的発想の誤りは事実である。だが、そのことによって少数民族規定まで清算することは正当ではない。むしろ、問題の根本は、この少数民族規定を、日本国家の構想との関係においてつめきれなかったことにある。当時の共産党において、自らが主導する新しい日本国家にあって、沖縄をどう位置づけるか、という点を欠落させていたということであろう。だからこそ、情勢の激変によっていても簡単に清算されるという構造にあったといえる。
すべて日本ナショナリズムの枠をこえることのなかった沖縄学--復帰思想にたいして、初期独立論は一見すると、これをこえたかにみえるが、じつは、沖縄における思想的基調、否、感情ともいえる日本ナショナリズムの内在的批判・否定を通して自らを確立するところまではいたっていなかった。復帰論と独立論はメダルの表裏であったといえる。
つまり、戦後初期の独立論的主張は、たんなる機会主義的対置にとどまり、日琉同祖論的な感情に突きささる日・沖関係の根本的再検討を通じた沖縄人としての政治-国家構想への回路を閉ざしていたということができる。
(4)復帰論-初期独立論の限界をこえる視点
比嘉良彦氏は、1951年当時の群島議会の議論を紹介して次のように述べている。
「『琉球が日本を中心としたアジア経済圏から独立して存在することは恐らく不可能であろう。かく経済的に日琉の分離が不可能とするならば、寧ろ琉球の日本復帰が琉球人の経済福祉上望ましいことは当然である』という論議を経て『日本復帰』が選択されている。ある意味では、『復帰論』というのは『自立論』を捨てたところから出発しているともいえるのであり、『復帰』の問い直しなくしては、いかなる『自立経済論』も論者の意図は別にして、政府の沖縄統治政策を手直し的に補完するものでしかないであろう。」(「沖縄自立経済論の問題点」、『沖縄経済自立の展望』所収)
ここに指摘されるように、復帰-初期独立論の限界は、日・沖の国家的関係を客観化することによってのみ、克服されるのである。
二、反復帰・自決論と特別自治権論
(1)反復帰論と自決論
沖縄人民の「復帰」願望を逆手にとった日本帝国主義の「返還」政策が暴露されるにつれ、強要された復帰を拒絶し、反復帰の主張が展開された。新川明氏、川満信一氏らの主張である。新川氏らは、沖縄が本土にたいして所有する異質感=異族性を「否定すべきマイナス面」として退けるのではなく、プラス要因として「国家権力に対する<加害者>へと転化させる契機」とするという鋭い視座を提起した。「反復帰」とは「すなわち、反国家であり、反国民志向である。非国民として自己を位置づけてやまないみずからの内に向けたマニフェストである」と氏は規定した(『反国家の兇区』)。
この視座は、沖縄学-復帰運動を貫いてきた日琉同祖論を軸とする思想を根本的に転換し、沖縄自立への思想的発展を示す価値ある提起であった。しかし、同時にこうした反復帰の主張は、思想的レベルから、現実の経済・政治、とりわけ沖縄の日本国家にたいする具体的構想にまではふみこむものではなかった。いわば、沖縄の帰属、つまり新たな選択の問題において、沖縄人としてのアイデンティティーをどう貫くのかという領域は、国家そのものを否定する「反国家の兇区」という一般的なレベルになおとどまったといえる。
この時期、日本の地においても、在日沖縄人知識人の間から、復帰思想を根底から把え返す主張が展開された。新里金福氏、金城朝夫氏らの日・沖関係の歴史的総括にふまえた鮮明な沖縄自決の政治主張であった。新里氏の自決論は、復帰運動における「科学的国家論の欠落という最大の欠陥をのりこえ」、沖縄の分離・独立というレベルをこえた日本人民との新しい平等な結合関係を求める主張である(『沖縄解放闘争の未来像』)。金城氏の主張もほぼ同様のものであった(『沖縄処分』)。
ここには、72年「返還」=併合をこえて進まんとする沖縄人民の闘いの方向と構築さるべき日・沖関係の原理的起点が記されている。
このように、沖縄、日本双方において開始された復帰運動をこえる思想的、政治的主張の展開は、沖縄においては、中部反戦等の運動に多大な影響を与え、国政参加選挙紛砕闘争としてはじめて反復帰、さらには、自決の質をはらんだ政治行動を生み、一方日本においては、沖縄青年同盟の結成、70年10月の反日自決を掲げた国会内決起を媒介に、在日沖縄人の闘争を形づくった。復帰という選択が破産するなかで、新しい沖縄の政治的選択の基本方向を提示した意義は画期的なものであった。これらはいぜんとして沖縄自立の構想の出発点でなくてはならないだろう。
(2)特別自治権論
また、この時期、主要に復帰運動の中心にいた知識人の間から、特別自治権の主張が提起された。比嘉幹郎氏、久場政彦氏らの主張である(比嘉幹郎「沖縄自治州構想」、『中央公論』71年12月号所収、久場政彦「なぜ『沖縄方式』か」、『中央公論』71年9月号所収)。野口雄一郎氏の主張(「復帰一年 沖縄自治州のすすめ」、『中央公論』73年6月号所収)もこの系譜に属するものといえる。
これらの主張は、反復帰・自決の主張が思想的・原理的なものであったのに比べて、(復帰運動・思想の総括には直接はふれないかたちでの)現実論的な政治主張であった。それは、固有権説的自治権にたっていることが示すように、沖縄の日本国家にたいする向き合い方を原理的に考えるというところから出発するというより、復帰の実相が明らかになるなかでの失望と危機感からとりあえずの対応策として提起されたという性格が強い。
しかし、なかでも比嘉氏が、「軍事・外交を除くすべての権限をもち、軍事・外交の分野でも沖縄住民の意識を反映する沖縄州」を提案し、「沖縄の将来を決定するのは究極的には沖縄住民」であり、「自治州構想は……沖縄住民の要求を実現するための政治姿勢に立脚」すると述べていることは重要であろう。そこでは、沖縄人民の自決権が、異質の法論理としての地方自治権という回路を経由して主張されているのである。
たしかに、この主張は、「平等・対等な新しい結合」を求める新里氏らの自決論との間に大きな断層をもっている。そしてなによりもそれは、これらの主張が復帰運動と復帰思想を根底から批判、否定して立論されていないという限界に由来する。ここに、反復帰・自決論とこれら特別自治権論が緊張関係をはらむ議論として当時なしえなかった事情がひそんでいると思われ、両論が、72年復帰を前にした情勢のなかで交点をもつことなく終わったことは、その双方の立論の発展にとっては不幸なことであったといえる。
しかし、復帰思想の総括の欠落、地方自治論への原理的依拠という大きな限界をもつものであったが、こうした特別自治権の主張は、反復帰-自決の観点から、今後の日・沖関係、日本国家と沖縄のあり方を具体的に構想していく場合の重要なたたき台としての意義をもつものであるといわなくてはならない。
第四章 少数民族と自決権・特別自治権
一、日本国家と沖縄
(1)平恒次氏の「日本国改造」論
沖縄の日本国家にたいする向き合い方--日本国家との関係における沖縄の位置づけをはじめて具体的に構想したのは平恒次氏であった。氏は、『日本国改造試論』において、独自の(少数)民族としての沖縄人の日本国家との対等合併の理念にもとづく連邦的結合論を主張した。
氏の提起の鋭さは、たんに日・沖関係のあり方を構想するにとどまらず、日本国家自体を対象化し、その構成原理の変更を提起した点にある。つまり、多民族国家としての日本国家という現実を照らしだし、沖縄人、アイヌ人、在日朝鮮人の少数民族から構成されるおのおの「新琉球国」、「新アイヌモシリ」、「新朝鮮国」と旧日本国残部および新自由州から成る連邦国家--「日本連邦」を提起したことである。復帰そのものを“一つの選択”として相対化し、沖縄人のナショナリティーの問題を突き出しつつも、それを単純に分離、独立の方向において自己完結させてしまうのではなく、日本国家との対等な新しい結合の具体的あり方として連邦制を提起したこの平氏の主張は、これまでの日・沖関係をめぐる議論を具体的レベルにおいて大きく一歩前に進めるものであった。
また、平氏の提起は、沖縄問題がたんに沖縄人にとっての問題であるのみならず、多数民族集団としての日本の側の問題のとしても存在しており、日本の側における闘いが、単一民族国家の擬制を解体する構想をもつものでなくてはならないことをあらためて鮮明に迫るものとしても大きな意義をもつものであった。
このような氏の提起は、琉球国、南朝鮮、北朝鮮、アイヌ自治州と旧日本からなる対等で平等な連邦国家--「東アジア連邦国家」として現在の日本民族国家の解体を展望する松浦玲氏の提起(『続・日本人にとって天皇とは何であったのか』)とともに、沖縄の政治的自立の構想、そして日本民族国家解体の展望を論じているうえでの貴重な素材としていかなくてはならない。
(2)西野照太郎氏の「島嶼住民自決権」論
このほか、西野照太郎氏の業績についてふれておかなくてはならない。
氏は、72年復帰を前にして、「本土復帰は選択された一つの途であって、必然的な沖縄の運命ではないこと、また、日本にとっては失地回復的な返還の実現ではないこと。この点を看過するところから、『琉球処分』がくりかえされる危険性が生まれる」というまったく至当なモチーフから、沖縄と類似した島嶼地域における自決権と自治権の国際的な比較研究を行った。そこでは、キプロス、アイスランド、マルディブなど独立を選んだ島嶼の存在をあげ、「これら島嶼が本土と一体化して、一つの地方自治体となることなく、独立したという経緯を論ずる理由は、沖縄島民にもその意志さえあれば、政治的な独立を選びうる可能性がかつてあったのだということに関連している」と喝破した(「国際環境からみた沖縄復帰--島嶼住民の自決権と自治権--」、国立国会図書館調査立法考査局『沖縄復帰の基本問題』所収)。
氏のこのような精力的な国際比較研究ならびに「この報告で論じたどの島嶼とも異質な政治的地位にあったことはいうまでもない。しかし非植民地化の問題としてではなく、日本の領土の一部に復帰するばあいの沖縄県という島嶼群の住民が、行使しうる筈であった自決権や、これからも主張しうる筈である自治権について、考えてみたい人たちのために、私はこの報告を執筆したわけである」という報告末尾の文章が示す、現実には実らなかったことへの無念の想いをこめつつも表白される、ひかえめな、しかし鋭い沖縄人民の自決権の主張は、今まさに、沖縄自立、日本国家解体の政治構想をめぐる議論のなかで生かされ、継承されなくてはならない。
二、沖縄少数民族論の登場
72年復帰以降の苛烈な現実は、復帰幻想をしだいに突きくずし、沖縄問題の新しい角度からの把握がなされはじめた。
(1)中野好夫氏の「民族解放」論
その象徴的なひとつに、復帰運動の中枢にいた中野好夫氏のいわば「民族解放」論ともいうべき立場への転進がある。
氏は、「もう沖縄のみなさま方もそろそろ本土にサジを投げる、愛想づかしをする日が来ているのではないか、いや、少なくとも近い将来にくるのではないかということです。もちろん究極的にはみなさま自身の選択であり、私など外部人間のとやかく申すべき筋ではありません。……しかしこの問題、必ずや近い将来においてみなさまの選択を迫ってくる日があるに相違ないと確信しています」(「小国主義の系譜」、『新沖縄文学』44号)と述べ、明らかに復帰、返還論からの転進を表明している。そして氏は、沖縄民衆が「植民地的隷属の状態から長い民族運動の結果、ついに独立を達成した諸国家の歴史を勉強していただきたいと思うのです」とアイルランドをはじめとする海外の民族解放運動の歴史からの教訓をうることを呼びかけるのである。
中野氏のこの発言は、かつて復帰運動の中心を担った部分でさえ、沖縄問題が民族問題として存在し、その解決の方向が民族解放闘争として追求されねばならないことを示唆・確認せざるをえなくなったことを象徴するものとして注目される。
(2)大田昌秀氏のマイノリティー論
だが、もっとも注目されるのは、大田昌秀氏の提起である。
氏は、最近の著書『沖縄人とは何か』のなかで、沖縄人を明確にアイヌ人、朝鮮人、中国人とならぶ日本における支配社会(社会の多数派)の抑圧をこうむる少数民族集団として把握し、日本への同化を見直し、沖縄人としてのアイデンティティーと国家および国家的アイデンティティーとの対決の相促的展開のなかに新しい沖縄の展望をみいだそうとしている。
このように大田氏は、単一民族国家として擬制化されてきた日本国家の多民族国家としての実相に焦点をあて、沖縄問題が「南北問題」的性格をもつものであるとともに、沖縄人が日本国家とその民族主義と対決することなしには解放されぬ少数民族集団として存在していることを明らかにしたのである。いわば、氏は、平恒次氏や西野照太郎氏とは異なる方法ではあるが、しかしながら、領土問題としての沖縄問題という把握をこえて、マイノリティー・少数民族問題として把え直すという点においては同一の地点に立ったということができる。
もちろん、氏の復帰運動ならびに反復帰、自決論への評価、また、氏のアイデンティティー論が文化的領域に限られているように思われることなど、問題点を残してはいるが、復帰運動、復帰思想からの転換を促し、沖縄の政治的自立の構想、日・沖の民族的・国家的関係を考究することを迫る非常に貴重な提起となっている。
このように、今日における沖縄問題への新しい視座の提起は、72年復帰が結局は沖縄人民の意志に反した日本国家による併合として存在したこと、そして、このなかであらためて問われる復帰とは異なる沖縄の新しい選択は、日本国家内部におけるマイノリティー=少数民族問題としての沖縄問題という認識を基軸として、反復帰論、連邦論をよりいっそう具体的な政治構想へと発展させるものでなくてはならないことを明らかにしたのである。
三、国際的にみた自決権・特別自治権と連邦制
(1)国際的なマイノリティー問題
沖縄問題をマイノリティー問題、少数民族問題と把握して沖縄自立の政治構想を論議することにおいて、国際的視野からのアプローチは不可欠である。
とくに、現代世界において、ひとたび近代民族国家として確立したかにみえた先進資本主義国内部にあって、少数民族問題が鋭い矛盾として噴出していることが注目されなくてはならない。すなわち、長くマイノリティーとして抑圧・収奪・差別を蒙ってきた少数民族集団によって自らのアイデンティティーの確立、さらには自決を求める闘いが発生しているという現実である。
イギリスにおける、北アイルランドはもとより、スコットランド、ウェールズ、フランスにおけるブルターニュ、コルシカなど、スペイン・フランスにまたがるバスク、スペインにおけるカタロニア、ガルシア、アンダルシア、カナダにおけるケベック等々がそれを代表する存在である。また、今日では、民族闘争的色彩は薄いが、イタリアにおけるシチリア、サルディニアなどもこの類例に入れることができる。日本における沖縄問題も、本質的にはそのような位相にあることは明らかであり、その将来的政治構想は、これらのなかに多くの教訓をみいだすものとなろう。
また、たとえば、植民地本国における環流的移民集団にみられるような、特定地域に集団的に居住するものではないにせよ、独自の歴史的、現在的な抑圧・収奪・差別を受けている民族集団の自決を求める闘いも次第に強められつつあり、これは在日沖縄人問題への基本的視座を与えている。
こうした事態は、いうならば、先進資本主義国(もちろん、既成の社会主義諸国家において基本的には同様であるが)が、いちようにあらためて多民族国家としての現実を承認し、少数民族の自決、本質的な平等の実現の要求に応えないかぎり、国家的崩壊に直面せざるをえないことを示しているといって過言ではない。
これら現代世界の少数民族問題、なかでも先進諸国におけるそれの位相は、おのおの具体的であり、いちがいに論ずることは困難であるが、その所属国家との関係のとり方においてみてみるならば、
(1)、特別な高度の自治権を求めるもの(特別自治権)
(2)、完全な分離、独立を求めるもの(独立)
(3)、独立しつつ、残存した現存国家との対等な連邦を求めるもの(連邦)
の三つに分けることができる(もちろん、これは当該民族闘争の発展段階および主体の側の戦略によって、(1)から(2)もしくは(3)への移行等の流動する可能性をはらんでおり、また、現在においてすら主体の間で選択が分岐していることが留意される必要がある)。
(1)に属するものには、スコットランド、ウェールズ、およびブルターニュ、コルシカ、バスク、カタロニア、ガルシア、アンダルシア等における多数派がある。このうち、バスク、カタロニアについてはすでに内政上の特別自治権が付与されており、(スコットランド、ウェールズは、中央政府の提案を拒否)、また、シチリア、サルディニアは戦後以来すでにこのレベルにある。さらに、やや位相を異にするが、米国の自由連合州とされる現在のプエルトリコの状態もこの範疇に属するといえる。当該主体において特別自治権は、多くの場合、究極的な分離・独立へと至る過程において経由する中間的なもの、とされることが、ここにおける特徴となっている。
(2)に属するものの代表は、ETA(「祖国と自由」)に体現されるバスク内少数派である。このほか、コルシカをはじめ多くの地域で、それぞれ少数派がこの方向を求めている。
(3)に属するものの代表は、住民投票の結果多数を獲得することに失敗したが、ケベック(ケベック党州政府)の追求した立場である。このほか、ブルターニュ等においても連邦の主張が少数ながら提起されている。
(2)自決権と特別自治権
このようにみてくると、先進国における少数民族が現時点において求めている所属国家にたいする関係のとり方の多くは特別自治権の方向をとっている点が注目される。したがって、特別自治権と自決権との関係性をおさえておくことが重要となる。
通常の地方自治権をこえる特別自治権の主張も、法理論的にいえば、基本的には自治権の枠内にあり、それがたとえ固有権説に依拠するものであったとしても、地方行政上の自治、すなわち地方分権の主張を意味するにすぎず、政治的な自決権を意味するものではないことはいうまでもない。しかしながら、独占資本主義と官僚制の強大化が行政的自治を空洞化し、また、連邦制をとる諸国にあっても、それが実質的には、連邦各支分国が自治権を有するにすぎない、という現状にあって、この特別自治権=自治・分権を求める下からの運動は、たんに地域主義にとどまることなく、とくに、さきに挙げた地域におけるように民族闘争と結びついて主張される場合には、国家の構成原理の変更を必然化させる革命的な質をおびる可能性のあることを確認せねばならない。もちろん、これにたいしては、所属国家の側から先取り的な防衛策がつねに用意されるのであり、激しいヘゲモニーの角逐が不可避となる。したがって、革命的に運用される場合には、民族自決に至らざるをえず、改良的に運用される場合には、高度自治という形式を通した中央集権の新たな貫徹、民族闘争エネルギーの吸収を招くという二重性をもつものである。この意味で特別自治権とは、自決権の視点からみるならば、中間的・過渡的な概念であり、それが民族自決へと突きぬけるものたりうるか否かは、これを運用する主体の質にかかっているといえる。
なお、今日における連邦制の実態は、これをもっぱら自決権の行使を事実上封殺する用具としているソビエトや事実上の地方自治制への退嬰化を進めている先進国の実情をみるならば、たんなる形態的な模倣によっては、沖縄の政治的自立の実質を保証するものたりえず、批判的な比較分析的考察となによりも原理的考察の蓄積が要求されていることが最後に確認される必要があろう。
以上みてきたように、沖縄の政治的自立の具体的構想は、島嶼地域としての独自性にふまえつつ、帝国主義国家内部の少数民族としての自決、本質的・絶対的同権の主張を基軸として、単一民族国家の擬制を突破し、日本国家の構成原理の根本的な変更を促す、そのようなものとして構想されなくてはならない、ということができる。
第五章 沖縄経済自立-政治的自立の構想
一、経済自立-政治的自立の基本視点
以上の検討をふまえて、まず沖縄経済自立――政治的自立の構想の視点をまとめておこう。
(1)復帰と返還の矛盾
第一に、復帰9年の現実はなにを示し、沖縄がどのような岐路に立っているのかという点である。
われわれの検討のなかからは、一口に言えば、72年復帰=返還自体の問い直しが迫られていると結論づけられよう。日本国家-日本国憲法下に入ることによって沖縄はたしかに本土と法的、形式的には平等な存在となったが、質的には、沖縄経済は格差是正どころか周辺化がいっそう進み、軍事基地も日・米共同管理のもとに維持され、日本本土からの系列化も果たされ、沖縄人総体の民族的疎外状況は逆に深まった。この現実は、沖縄人のめざした復帰と日本帝国主義の返還とが、じつは、まったく相反するものであることを示してはいないだろうか。
とくに、沖縄人民が復帰を選択したのは、究極的には、人間的に豊かな生活と経済生活の確立(“食うため”)であったとすれば、復帰後の事態は、その目的とは明らかに背反していると言わざるをえない。経済自立論議がここ数年たたかわされ、今また一次振計の総括が問われ、二次振計が策定されようとしているのは、その反映だとみることができる。つまり、経済問題は、復帰という選択自体の政治問題と密接不可分であり、この点の評価こそが俎上に乗せられなくてはならない。再び政治的選択が問われていると思われる。
(2)経済自立の三つの視点
第二は、肝じんの経済自立をどのような視点から構想するかである。
少なくとも次の三つの視点は不可欠であろう。
一つは、日本資本主義経済の周辺化(独占資本主義の空間構造の再編成)のうえに成り立っており、80年代に予想される世界市場競争の激化のなかでこの周辺化傾向はますます強まるであろうことである。日本の多国籍資本による蓄積は、政府の産業政策と相まって世界的基準で展開され、諸地域経済はこのなかに位置づけられよう。したがって沖縄の非工業的周辺地域化は構造化されているとみなくてはならない。この資本主義的周辺経済化の構造との対決が自立経済の第一の条件であろう。
二つには、沖縄人総体が沖縄の位置利用にかんして決定権を剥奪されてきた歴史的現実=民族的疎外を脱却する方向である。基地依存経済といわれ基地が撤去されれば経済が発展するかのように発想されてきたことが、逆転されなくてはならない。つまり、歴史的に形成された非自律的経済構造は基地撤去によっても解消されないのであり、沖縄人総体が沖縄の位置をどう自らのものとして獲得するかという方向性においてはじめて基地問題の解決のしかたが明らかになるのである。
三つには、これら二つの条件を満たしたとしても、その経済自立が「北海道自立経済論」にみられるように80年代の日本資本主義経済を補完する道か、それとも日本資本主義経済との「断絶」を含む人民的自立経済の道か、が問われざるをえない。これまでの自立経済論議は、この点をまったく不問とし、じつは、前者の道を歩んできたことは疑う余地のないところであろう。二次振計の策定に際して、この点が明らかにされなくてはならない。
(3)マイノリティー自決の三つの視点
第三は、経済自立の展望は、復帰論と経済論が一体的であったように、不可避的に政治的条件の新たな確立にまで及ばざるをえないという点である。
この政治問題についても三つの視点から検討されるべきであろう。
一つは、マイノリティー(少数民族)という自己規定とその自立の展望が日本国家をどのように変革するのか、という点である。マイノリティー規定が、日本人か否かというかつての沖縄学的なレベルではなく、復帰幻想の現実的崩壊のなかから現れたことは、明らかに沖縄人の立場から日本国家を相対化しはじめたことを意味する。それは、日本国家が民族国家としてどのように形成され、かつどのように死滅すべきかまでにも論を及ぼすとともに、経済的側面からみた民族的疎外をマイノリティーとしての主体性において克服する起点を与えるものであろう。
二つには、マイノリティーとして沖縄人が自らの政治的、経済的生活を確立する場合、日本国家の具体的変革をどのような視点と理論によってはかるかということである。国際的にみてもマイノリティーの自立には多様な形態があるが、その理論的・基本的視点は、連邦論に求められる。つまり、民族問題の解決は、国家構成原理の変更によってしかできないのである。
三つには、マイノリティーの自立は、政治、経済的決定権の確保なしにはありえないが、その選択の形は多様に存在することである。沖縄の新たな選択は、自決の観点から分離・独立、特別自治権確立などとしてもさまざまに具体化されようが、それは経済自立の構想と一体的なものでなくてはならない。
以上、明らかなように経済自立-沖縄自立への基本的視点は、民族的疎外からの脱却をマイノリティーの自立・自決において克服することにあるといえよう。
二、経済自立の構想
(1)経済自立の概念
沖縄の経済自立を構想する場合、まず経済自立の概念について検討されなくてはならない。
われわれはかつて経済自立の意味を抽象的ではあれ次のようにとらえた。「経済自立とは……一定の社会的経済単位とくに民族集団が自己発展力の主体と体系を内在させ、固有の経済発展の軌道をみいだし、それへの動態を開始している状態である」(「沖縄自立経済のために――沖縄経済の現状と自立経済の方法的一視点――」、『沖縄経済の自立にむけて』所収)と。この抽象的規定を沖縄の経済自立にまで具体化するために二つの側面から深めてみたい。一つは「固有の経済発展の軌道」、もう一つは「一定の社会的経済単位」である。
前者については、すでに周辺資本主義構造の特質を部門間の「非接合性」「不均衡性」にみたS・アミンによって提起された。大衆消費財部門と基礎的生産部門を基盤とした自立的中枢的発展(輸出および奢侈財部門は周辺的・従属的関係)=拡大再生産軌道の設定である。近代経済学においても「統一的経済体の構造的変化の達成度」(詳細は、中村丈夫氏「島嶼経済と特別自治権」を参照)に経済自立の指標が求められるべきとしている。いずれにしても固有の経済発展軌道を自主的に生み出すことが不可欠である。
しかし問題は、後者の「一定の社会的経済単位」を島嶼として考えたとき、「固有の」とは何を意味するかである。島嶼性は自然的・原生的条件に起因する(西野照太郎氏)にしても資本主義的システムの変動によって変化するのであり、島嶼の位置を利用した本土への従属性と島嶼内部のその従属性との関係における「凝集力」として表現される。とすれば「固有の経済発展の軌道」とは島嶼の「凝集力」に支えられその位置の固有性を体現した経済発展の方向性であると言うことができる。
(2)資本主義的周辺化との対決
第二に、このような「固有の経済発展の軌道」は、多くの島嶼がそうであるように、沖縄の場合も資本主義システムによって強制される周辺資本主義化との闘いを通して構築されることである。S・アミンの言う「世界資本主義経済からの離脱」とはこの「中心-周辺」構造の抜本的転換のための闘いをさしているものと思われる。自立的中枢的経済発展はこの闘いを媒介にしてはじめてその道が明らかになるが、その場合、当該島嶼経済にとっては本源的蓄積と本来的蓄積の軌道をどのように敷設するかが中心的問題となる。
本源的蓄積とは言うまでもなく本来的蓄積のための“立上がり条件”であり、賠償や援助がそれにあたる。問題は、本来的蓄積である。島嶼の経済的諸条件――地理上の位置、風土、資源、人口規模、労働と労働力、産業の歴史的伝統など――と上部構造的・主体的諸条件――政治権力の形態、階級構成、文化的・知的蓄積など――との有機的結合がなくては、均衡的・接合的経済発展の構造を創り出すことはできない。なかでも重要なのは、周辺化、従属化にたいし島嶼自身の位置利用を逆手にとって島嶼住民の決定権を拡大すること(沖縄の場合であれば基地を“人質”にした闘い)である。
この闘いは、経済発展プロパーというより政治的・上部構造的条件の確立が先行するといわなくてはならない。つまり、島嶼住民の権利が反画一化・同化と特別自治権など政治的自治の諸条件に収約される過程が即本来的蓄積の条件確立の過程でもあるとみるべきであろう。
また他方この周辺化との闘いは、当該住民(沖縄人総体)が島嶼(沖縄)の位置を見直す過程でもあり、周辺資本主義的分業を拒否し新たな国際分業(アジア太平洋圏における)を築くことである。S・アミンの言う世界経済との「断絶」とは、もちろん自給自足経済(アウタルキー経済)ではないのであって、沖縄の反周辺化の闘いは、新たなかつアジア・太平洋に開かれた分業・結合関係の構築にむかうのであり、政治的関係も当然新しくうちたてられるのである。
(3)経済自立への契機
第三に、では80年代の沖縄においてどこから自立経済への展望をきりひらけるであろうか。
まず、二次振計にたいする政治的批判と闘いがあげられる。ごく最近の日本政府による「国際交流センター」設置決定は、二次振計にたいする日本政府の立場をもっとも鮮明に示している。沖縄をアジア・太平洋地域にたいする情報・知識交流・蓄積の拠点とはしても、二次振計総体には保留の態度に出ているのである。この現実は、これまでの二次振計「素案」が日本政府との取引力になっていないこと、つまり一次振計の総括が不明のため確乎たる二次振計の目的・性格を固められていないことを示した。基地・CTS・情報拠点という沖縄の位置の帝国主義的利用を許すのかどうかが、大きな焦点となろう。
また、復帰特別措置法や公用地法について、この9年の現実をふまえ経済自立の観点から新たな政策が構想されるべきであろう。すでに述べたように復帰9年の現実が周辺的経済構造の拡大・深化ということであるとすれば、特別措置という発想と方法が根本から見直されなくてはならない。あらためて賠償の問題が浮上せざるをえない。しかも、公用地法による土地の「強制収用」=「強制使用」という政府の方針とからみ合せてみると取引力形成の点からみても、豊かな構想をえがくことができると思われる。
まさに帝国主義的経済自立か人民的経済自立か、82年に向かって、その構想が根底から問われようとしている。
三、沖縄自立の政治構想
沖縄の経済自立は、日本資本主義経済の「断絶」をも含む緊張をはらむものであるだけに、日本民族国家の変革とも不可分の関係にある。以下、政治的自立の構想の基本的骨格について検討していきたい。
(1)民族国家の擬制と沖縄自立の射程
明治維新によって確立した近代日本国家は、ただちにその北辺国境をアイヌモシリの略取(「旧土人保護法」)によって拡大したが、対外膨張と民族国家としての形成は、1879年の沖縄併合(第一次琉球処分)を画期に(本格的に)開始された。以降、台湾、朝鮮をつぎつぎに併合、ここに今日における沖縄人をはじめとする少数民族集団を日本国家内部につくり出す根拠を記した。
しかしながら、日本国家は、事実として多民族国家として存在しながらも、戦前においては天皇制帝国主義民族国家として、いわば天皇制を軸に単一民族国家の擬制をつくり出し、また、戦後憲法を軸とする戦後日本国家は、天皇制をふりすてることによってかえっていっそう民族主義的紐帯を強め、世界に比類なき単一民族国家の擬制を今日に至るまで強固に保持してきた。
まさにこのようななかにあって、72年復帰=併合とその後の国内植民地化の進展を経るなかで、沖縄において、従来の復帰選択を根本的にとらえ返しうるマイノリティー=少数民族としての自己確立の視点が提起されつつある。
この視点は、これまで保持されてきた日本国家の単一民族国家としての擬制を解体し、日本国家の構成原理の根本的変更に結びつかざるをえない。最近の反中央集権の主張(地域主義)は、この日本国家の構成原理の転換と結合し、それによって主導されるものでないかぎり、中央集権国家=日本国家の論理の合理的貫徹を誘導するものとならざるをえない、といわなくてはならない。
主体的にいえば、このような沖縄のマイノリティーとしての自立と自決は、他の国内少数民族あるいは社会的マイノリティーおよび日本国内の国際主義勢力との協働・結合関係の確立と相互促進的関係にある、ということができる。
沖縄自立の政治構想は、今日において、そこまでの射程が問われているのである。
また、このような沖縄自立-自決の主体的水路は、沖縄の社会構造の質的相違にふまえるならば、現存共同体の抵抗共同体としての新生を原基とする「沖縄共同体社会主義」(中村丈夫「沖縄経済自立の展望・序説――地域・共同体・社会主義への一考察――」、『沖縄経済自立の展望』所収)の方向たらざるをえない。この「共同体社会主義」は、その本旨からして、否、社会主義の真実の姿として、地域主義の唱える分権的質を完全に内包することは言うまでもない。
このように考えるならば、日本国家の構成原理の根本的変更とは、じつに、「沖縄共同体社会主義」との間の絶対的同権の確立を意味するものにほかならず、したがって、日本国家にたいするすぐれて社会主義的変革たらざるをえない。
(2)連邦の理論
このように、沖縄の自立、政治的自決のための構想は、日本国家との関係の完全な断絶=分離・独立として構想されないかぎり、それは日本・沖縄間の国家的な相互関係のあり方として、連邦制を問題とせざるをえない。また、かつて比嘉良彦氏は、「真の沖縄解放……は“沖縄人が日本人になりきる”ことによってではなく、“沖縄人のまま日本国民になる”ことによって実現されるのである」と述べ、「日本と沖縄という視野の中で沖縄の主体性・自立性」を具体的に考究していかねばならないことを提起された(「社大党の変遷と展望」、『青い海』79年6月号所収)。この提起も、明らかに日本と沖縄の連邦的結合の方向を示唆している。その意味で連邦制をめぐる理論の検討と再構築は不可欠である。
だが、日本における連邦理論は、多民族国家の現実を隠蔽する単一民族国家の擬制の強固な形成に規定され、小森義峯氏の『連邦制度の研究』等の著作を除いてはまったくの貧困である。また、小森氏の研究自体も、比較法制度的考察であって、この作業の第一次素材たるの位置以上にはない。またさらに、現存の連邦制自身も、第四章で若干述べたように、事実上、地方自治のレベルへと退嬰化し、この作業にたいしては否定的媒介の域をでるものではない。
したがって、やはり、この連邦理論再構築の作業は、諸民族の融合と国家死滅の二つの理想の実現という観点から、それに至る過渡的国家(=半国家)間相互の関係性について、連邦制を積極的に擁護・推進したレーニンの理論を出発点とせざるをえない。レーニンは、1922年から23年にかけて、ロシア社会主義連邦ソヴェト共和国と独立の諸共和国間の相互関係にかんして、「独立共和国」を「自治共和国」としてロシア連邦に包括することを構想し、あまつさえ、そのためにこれに反対するグルジアの党組織を抑圧したスターリンにたいし、死の床から敢然と「最後の闘争」を挑んだ。民族間の本質的平等の実現を通してしか民族主義の克服、民族融合の理想の実現は果たせず、また、国家死滅の理想も実現できないと確信するレーニンは、スターリンの「自治共和国」案に「平等な権利を享受する諸共和国の連邦」、「ロシアとの正式の連合による、ヨーロッパとアジアのソヴェト諸共和国の連合体」を対置、スターリンの「民族的自由主義」の非難をうちやぶって自らの主張を貫いたのである(M・レヴィン『レーニンの最後の闘争』)。
われわれもまた、真の民族間の平等の実現にむけてこのレーニン的連邦理論から出発しなくてはならないだろう。そして、このようなレーニン的観点とは、たんに現存日本国家内部の民族間においてのみ貫かれるものではなく、中心部資本主義=日本の新植民地主義支配のもとで「低発展の発展」を強いられているアジア、太平洋諸民族とその国家との間の現在的な関係性をうちやぶり、真に平等な結合関係の確立へと至る今日的起点でもある。
(3)自決-連邦の構想
以上、沖縄自立の政治構想の諸前提について考えてきたが、これにふまえて次に沖縄自立の政治構想の骨格をなすと思われる点を三点にわたってまとめておきたい。
第一は、沖縄自立の政治構想の基本方向は、少数民族としての自決、とりわけ連邦的結合の方向であろうということである。
分離、独立、または日本国家との対等・平等な連邦的結合の二つ(あるいは、中間的・過渡的な形態としての特別自治権を含めれば三つ)の選択肢のいずれを自決の内容として選択すべきかは、沖縄人民自身の選択でなくてはならない。
ただ、分離・独立を選択する場合、沖縄民族国家の樹立にとどまることなく、日本国家解体=過渡的半国家への展望が不可欠となろう。そこにおいてはじめて、日本国家内部における他の少数民族、さらには社会的マイノリティーの自立、自決の展望と有機的関係を創造できると思われる。その意味で、連邦的結合の方向がもっとも今日の情勢から要求されているのではないだろうか。
第二は、沖縄共同体の抵抗共同体としての新生を導きとする「沖縄共同体社会主義」こそが、その基本的内容たらざるをえないだろうということである。
すなわち、そのような自決-連邦的結合の担い手は、すでに中心部=日本資本主義に従属的に再編成された「沖縄民族ブルジョアジー」、あるいは、併合によって特権を享受する官公労働者たりえず、併合と国内植民地化によってマージナル化を強いられる諸階層、とりわけ、現存共同体から抵抗共同体への新生を担うべき共同体民衆として想定され、したがってその質は「沖縄資本主義」たりえず、社会主義的社会変革を伴なう「沖縄共同体社会主義」たらざるをえないと考えられる。また、こうした認識によるならば、日本国家との連邦的結合の実質は、社会主義共和国連邦(より正確には社会主義半国家連邦)としてあると考えることができよう。
第三は、そのような沖縄自決と連邦的結合自体のもつ国際的意味についてである。
つまり、沖縄自決と連邦的結合自体は、沖縄の地理的位置を指摘するまでもなく、日本国家内部の他の少数民族を介して直接的に、あるいは間接的に、韓国・朝鮮、台湾、アジアおよび太平洋島嶼人民の自決と社会主義の展望を明らかにし、なによりもこれら変革された諸邦とのアジア・太平洋規模における連邦的結合へと開かれたものとして発展せざるをえない、ということである。
(4)むすび
以上述べてきた沖縄経済自立の構想ならびに沖縄自立の政治構想の骨格にかんする考察は、いまだ基本的視点として展開されているにすぎない。現時点において肝要なことは、破産した復帰という選択に替わる新しい選択を基軸的に確定しないかぎり、沖縄のおかれている現実はなんら変更されることはない、という認識であろう。
復帰10周年としての1982年を、この新しい選択の転機たらしめることこそがさし迫った課題であろうと思われる。
このページのトップにもどる