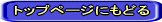江上能義
「Ⅷ55年体制の崩壊と沖縄革新県政の行方-『68年体制』の形成と崩壊-」
『年報政治学1996・55年体制の崩壊』(日本政治学会編・岩波書店1996.12)
はじめに
55年体制は、<保守>対<革新>という大きな対立軸の下で、保守側が日米安全保障条約によってわが国の安全保障を基本的にはアメリカに依存しながら自衛力を着実に整備し、復古的伝統的価値を追求する立場に立ったのに対し、革新側は反米、中立かつ社会主義的立場で日本国憲法でうたわれた平和的民主的価値を主張する対抗姿勢を示した。国内政治では自民党優位の自社二大政党制(一カ二分の一政党制)と特徴づけられるが、1972年に日本に復帰した沖縄では悲惨な沖縄戦の後、建設された巨大な米軍基地が今もなお、日米安保体制の要としてそのまま存続したことで、この米軍基地をめぐって厳しい保革対決の政治が展開されてきた。
復帰4年前の1968年11月、沖縄では長年にわたる自治権闘争が実って、米軍統治下で初めて行政主席の公選が施行された。この年には立法院選挙と那覇市長選挙と合わせて三大選挙が実施されたのだが、これらの選挙戦で本土との一体化を訴える自民党に対して反基地反安保、即時復帰を主張する革新共闘体制が確立され、革新共闘対保守勢力という対決型の政治構図がスタートした。そして本土の保革対立の一大争点でありつづけた日米安保体制のキー・ストーンとして米軍基地との共存を復帰後も強いられてきた沖縄ではその過酷な現実から保革伯仲もしくは革新優位の政治構造が持続して今日にいたっている。本稿では国内の55年体制に対比して沖縄でしばしば主張される「68年体制」を中心に、保革対立の沖縄政治の推移を55年体制の動向と関連づけながら考察する。
一 戦後初期の沖縄の政党
敗戦直後の沖縄の統治機構は、米民政府(USCAR)の支配下で群島政府と群島議会、琉球政府と琉球政府立法院へとめまぐるしく移行し、その間、諸政党の消長再編劇が各地で展開されたが、1950年に平良群島知事の与党として沖縄社会大衆党(社大党)が結成された。また52年、民生クラブを母体として社大党脱党組や旧共和党および宮古革新党などの支持者が合体して琉球民主党が結成された。琉球民主党は保守合同の要となり、59年10月に沖縄自由民主党となり、立法院の第一党となった。第二党は社大党だった。(1)沖縄の独立を主張する政党もあったが勢力を拡大できず、またたく間に消失していった。
琉球民主党や沖縄自由民主党などの保守政党は、いくつかの基本的理念を堅持していた。第一に、沖縄住民の福祉と安寧は米国の施策に積極的に協力することによって増進すると考えていた。第二に、政治を現実から遊離させてはならないと絶えず主張した。沖縄の現実は米施政権下にあるので、この現実主義的観点から米民政府との協力が説かれ、任命主席を総裁に選出して政治に参画した。第三に、“現実的”政策を重視し、段階的かつ穏健妥当な政策を指向した。第四に、自由企業の原則に基づく自立経済の発展をはかることを公約した。これは保守政党と実業界との結びつきが強かったこともあって、社会主義に反対することをも意味していた。(2)
社大党以外の主要政党は本土の政党と公然あるいは隠然たるつながりをもつようになった。沖縄自由民主党と沖縄社会党は最初から日本自民党と日本社会党の県組織となることを強く望んでいたし、沖縄人民党は日本共産党の基本的指導原理から離れたことはない。このことは本土の政党の政策と消長が、沖縄のそれぞれの友党に影響を与えたことを意味する。だが本土とのつながりのない地域政党(土着政党)である社大党は「ヒューマニズムを基底とし」、イデオロギー的には右と左との間の広い中間地帯を、その時々の状況に応じて揺れ動いてきた。(3)社大党の基本的性格をきわめて的確に表現しているのは、結党宣言の「時代の要請する革新的政策を具現する政党(4)」であろう。すなわち時代と環境によって政策を変更する弾力性のある政党をめざしたのである。こうした壮大党の性格は強みともなり、弱みともなった。流動性と曖昧さをもつ社大党の活動範囲は広く、時には保守勢力と組み、時には人民党と共闘した。“沖縄の心”が最も似合う政党でもある。
(1)宮里政玄編『戦後沖縄の政治と法 1945-72年』東大出版会、1975年、234-247頁
(2)同右、255-256頁
(3)比嘉幹郎『沖縄--政治と政党』中央公論社、1965年、110-112頁
(4)沖縄社会大衆党史編纂委員会編『沖縄社会大衆党史』1981年、215頁。
二 「68年体制」の形成
1 革新主席の誕生
米国の軍事支配の下で日本政治への参政権、主席公選、労働基本権をはじめとする基本的人権など、自治権要求への闘いは復帰へ向けた闘争の本土や世界への活動の広がりをみせながら高揚していった。そしてアンガー高等弁務官は68年2月、同年11月の立法院議員選挙と同時に主席公選を実施すると公表した。この年の12月に那覇市長選挙も実施され、沖縄のなかで保守対革新の政治対立の構図がスタートした。日本政治の自民・社会両党を軸とする保革対立の構図が55年体制とすれば、沖縄の政治において類似の構造をこの「68年体制」に見い出すことが出来る。なぜなら、この「68年体制」は復帰後はいうまでもなく、今日まで持続し、沖縄の政治過程において決定的要因であり続けたからである。
この「68年体制」に先んじて準備体制に入ったのは保守側だった。67年12月9日、那覇市の国映館で第五回民主党定期大会が開かれ、三千人余の代議員で館内は埋まった。同大会で「返還に備えた本土との一体化促進」を決議した。その約一ヶ月前、佐藤・ジョンソンの共同声明で施政権返還が現実的課題となったので、返還をスムーズにするために経済・文化・教育など本土との格差を是正しようという一連の一体化政策の必要性が、沖縄内外で主張されるようになった。保守陣営はこの本土との一体化政策を基本政策の要とした。本土の自民党と沖縄の保守政党は50年代後半から友党関係になったが、この大会で沖縄民主党は「沖縄自由民主党」に改称して政治の世界でも一体化が図られた。「本土自民党と沖縄自民党との関係は、日本政府の沖縄への財政支援をきっかけに一段と深まった」と当時、琉球政府の財政担当だった翁長助裕は語っている。(1)本土の自民党は沖縄の三大選挙に備えて対策本部を設置、政府や党の要人を沖縄に送り込んだ。米民政府は中立の立場に後退し、それに変わって自民党が全面的に介入することになった。だが選挙情勢は革新有利に展開していった。1952年に琉球政府が設立され、比嘉秀平が行政主席に任命されて以来、16年間にわたって保守党が行政主席の地位を掌握し続けてきたが、主席公選の実施に臨むにあたって、復帰運動と反基地闘争のうねりの中で保守陣営は危機感を募らせていった。候補者の人選で自民党は公選実施の高等弁務官発表以前から西銘順治那覇市長に的を絞り、着々と準備体制を進めていったのも、その危機感の現われと見ることができよう。折しもタクシー汚職事件が発覚し、現職の行政副首席や会計検査院長までも巻き込んで松岡政保主席は苦境に立たされ、保守体制の・黒い霧・は革新政党の絶好の標的になった。
一方、革新側は社大、社会、人民の野党三党の役員合同会議を開き、「復帰勢力を結集して共闘体制を確立し、保守勢力の打破」に向けて意見が一致した。これがいわゆる「革新共闘体制」への第一歩となった。同年4月、革新統一候補として沖縄教職員会会長の屋良朝苗を決定した。そして6月5日、革新共闘会議(社大、社会、人民の三政党と教職員会、県労協など)は、五つのスローガンのほかに七つの統一綱領(即時無条件全面返還、反ベトナム戦争反基地反安保・B52と核基地の撤去、国政参加・自治権の拡大、民主的本土法の適用・沖縄県復興特別措置法の制定、経済振興政策、平和的民主教育の推進と教育環境の整備、清潔で明るい政治)を決定した。(1)この段階での安保条約や軍事基地に対する革新側の統一見解は、「安保反対・基地反対」であって「安保廃棄・基地撤去」ではなかった。統一綱領は当初、「安保廃棄・基地撤去」だったが、屋良候補が「基本理念は大切だが、選挙戦であまり現実から遊離すると保守政党を利することになり、幅広い支持が得られない」と注文をつけ、「安保反対・基地反対」にとどまった。(3)三政党の政策にはかなりの相違点があり、最初、革新共闘体制の確立を疑問視する見方も少なくなかった。そういった意味で政党に属さない屋良朝苗の人選は、政党間の調整の幅をもたせる結果となり選挙戦勝利への一因となった。ちなみに革新の統一見解が「安保廃棄・基地撤去」に変わるのは、この年の三大選挙で革新側が勝利した直後に起こった、嘉手納基地でのB52墜落炎上事故の後だった。(4)
「明るい、明るい、沖縄は……」、6月5日、会場の琉球新報ホールに大合唱が鳴り響いた。革新共闘会議・明るい沖縄をつくる会・の結成大会に県内の政党や労組、学生など105五団体から約1500人の代表が詰めかけ、舞台まで人があふれた。大会で合唱された歌は、主席公選に向けて公募したテーマソング『明るい沖縄をつくる歌』。この選挙ではシンボルマーク、イメージカラーも公募で採用し、県内の選挙がこれまでのスタイルとは一変した。このイメージ選挙は、・美濃部方式・に倣ったものだった。(5)実は、屋良は立候補を表明した2日後に上京して美濃部都知事、飛鳥田横浜市長、それから京都へまわって蜷川府知事に会って意見を交換した。その際、革新行政や美濃部方式の選挙戦が大いに参考になったと回顧している。(6)
沖縄教育界の大御所で、沖縄は当時、きわめて影響力の大きかった教職員会の会長が知事選に出馬したのも、学者出身が多かった当時の本土の革新知事と似通った点があった。後援会も美濃部方式に倣って「屋良さんを励ます会」を結成した。革新共闘会議は立法院議員選挙や那覇市長選挙とのセット戦術にも成功し、とくに立法院選挙では、革新勢力は小選挙区制の全選挙区で競合しないように候補者を擁立した。また前述したように統一綱領によって戦うという共闘体制を確立した意義は大きかった。注目を集めたのが公明党の動向だった。同党は当初、「中立堅持」の方針だったが、8月下旬、「本土公明党の本質は野党であり、自民党の西銘支持はありえない」と、反西銘の姿勢を明言した。この後、公明党幹部が沖縄を訪れ、屋良、西銘両候補と個別に会ってこの・面接試験・で公明党の屋良支持が確定的となった。(7)全沖縄軍労働組合(全軍労)が即時無条件返還を掲げて革新共闘に加わった意義も大きかった。
この選挙ではまた、沖縄の経済問題とりわけ“基地経済”と称されるように、米軍基地に依存して歪んだ経済特質の是正や日本政府の財政支出などが大きな焦点となった。保守陣営は、一体化政策と沖縄経済の基地依存体質を結びつけて、「基地反対」論は生活を破壊し、イモ、ハダシの昔に戻ると主張した。この主張は、「米軍基地が縮小もしくは撤去される場合、沖縄はイモと魚に依存した裸足の生活になる(8)」というアンガー高等弁務官の発言に由来した。基地反対論に対する基地の経済的効用論は、現に基地と共存している沖縄の住民にとってかなり強力なスローガンとなった。だが「今回の主席選挙は、単なる与野党の対決ばかりでなく、県民と米国政府との対決なのであり、沖縄の復帰は米国の施政に対し協調的であるよりも、批判的であり反対である勢力が強くならないかぎり、実現は望めない(9)」という平良辰雄(初代沖縄群島知事)の言葉が、当時の民衆の間に広がっていたムードを要約していた。本土自民党との一体化が急速に進展していた沖縄自民党に、自民党政府は閣僚や大物政治家を投入しただけでなく、芸能タレントまで次々に送り込んだ。一方、革新陣営も党首または党首級の大物幹部や労組代表、革新首長や革新系タレントが続々と来沖し、本土保革の代理戦争の様相を呈した。
要約すれば、自民党の西銘候補は一体化策の強力な推進、本土なみ返還、国政参加、革新共闘の屋良候補は即時全面返還、B52撤去、基地・安保反対を各々、掲げて戦ったのだが、11月10日投票の結果、屋良候補が大差で勝利を収めた。89%という高い投票率は、いかに沖縄の有権者の関心が高かったかを明示している。同時に実施された立法院議員選挙の全32議席中、自民党の過半数支配(18)は揺るがなかったが、革新側は社大党が1、人民党が2議席増やし、結果的に革新勢力が伸長した。12月1日の那覇市長選挙でも平良良松革新統一候補が勝ち、68年の三大選挙は革新が完勝した。ちなみに県都の那覇はそれ以来、今日までの革新市政を守っている。
勝利の喜びもつかの間、屋良革新主席は少数与党の議会運営に直面しながら数多くの難問を処理していかねばならず、前途を危ぶむ声も多かった。また革新共闘の主柱となった3政党が今後も足並みをそろえて協力し合っていけるのか、先行きが不透明だったが、屋良が出馬を受諾する前提条件として「全県民的立場に立って党利党略を超えて協力する」ことを申し入れ、念を押していたことが功を奏したのか、その後、自民党(後に民社党が加わる)に対する革新共闘体制は、もちろん波風は立ったが持続して沖縄の政局の主軸を担ってきた。なかでも復帰政党といわれた沖縄固有の地域政党、社大党は、結党精神がイデオロギーにこだわらず、ヒューマニズムを基底として幅広い大衆の支持を結集させることを本旨としていて、とかくイデオロギー論争で対立しがちな社会、人民両党の間で柔らかなバッファ政党として革新共闘の要に位置し続けたことも、この体制の形成と持続に不可欠であった。
B52の沖縄駐留は革新諸派の急進化を促進した。「黒い恐怖」「空の殺し屋」と忌み嫌われたB52は沖縄から直接、ベトナムに発進して北爆を続けた。B52撤去運動は「島ぐるみ」で展開され、立法院も即時撤収を要求する決議を採択した(68年2月10日)。そして前述したように、屋良革新主席選出直後の11月19日、嘉手納基地を発進しようとしたB52が爆発した。核貯蔵庫付近への墜落事故は県民を戦慄させた。彼らの記憶に生々しくよみがえったのは、59年6月、米軍ジェット戦闘機が石川市の宮森小学校に墜落炎上、死者17名、負傷者121名の犠牲を出した大惨事だった。この爆発事故で軍事基地の存在自体が直接、生命の危機を招くという現実をあらためて沖縄県民は実感させられた。10万人規模で嘉手納基地を包囲して基地機能を麻痺させようというゼネストは翌69年2月4日に設定され、そのための準備が急ピッチで進められていった。2・4ゼネストの中核部隊である全軍労(上原康助委員長)は圧倒的多数で24時間ストを決めた。共闘会議議長の亀甲康吉は、スト権も認められていない中でゼネストを提起した理由として、日米両政府の沖縄県民に対する態度を挙げている。「アメリカ側に抗議すると沖縄人はアメリカ国民ではないとつまはじきにされるし、問題を日本政府に持ち込むと施政権がないとはねつけられる。まさに日米両政府のはざまでまるでピンポン玉のようにはじき返されている。こういう状況の中で沖縄県民が生命の危機を感じた場合、ゼネストを打って抗議する以外にない(10)」と。屋良は主席就任早々、B52撤去とゼネストの収拾に取り組むはめになった。「主席、知事を通じて約7年7ヵ月の私の任期が激動の連続だったことを思うとまさに象徴的なスタートだった」(11)と屋良自身、述べている。
このゼネストへの動きに対して米民政府は1月11日、布令63号「総合労働布令」(Comprehensive Labor Ordinance)を公布した。これは2・4ゼネストに向けての<治安維持法的規制>を目的とする沖縄民衆弾圧の布令だった。(12)そして全軍労に対してスト参加者は解雇を含む懲戒処分に付すと警告し、熾烈な切り崩し工作を行った。屋良主席は予想される混乱を懸念し、ストを回避するために、日米両政府に対してB52撤去の保障を求めた。事態を重視した日本政府は沖縄県民の不満を宥めるために、対沖縄援助を示唆する一方で、米国側に総合労働布令の施行の延期を要請、さらに滝川同盟会議会長、重枝書記長、堀井総評議長らを通して県民共闘会議への説得を試みた(13)(だが亀甲自身はこうした圧力があったことを否定している(14))。本土から駆けつけた安恒総評政治福祉局長や同盟・総評単産幹部は6、7月撤去の感触を語り、革新主席を守ることの必要性を説いた。(15)そして木村官房副長官は屋良主席に、5月にはB52が撤去される見通しであることを示唆し、この不明瞭な言質をてこに主席はゼネスト回避を呼びかけた。
1月24日、共闘会議主催の県民総決起大会が開かれ、約4万人が参加した。この大会で「本土の皆さんへのアピール」が採択された。それは、B52撤去を求めるこのゼネストが安保廃棄、沖縄返還へと発展する重要な闘争であり、そのために沖縄と本土の全民主勢力が力を合わせていかねばならないと訴えたのだが(16)、総評や同盟は沖縄のゼネスト闘争を支持し連帯したものの全国的な規模のゼネストを実行する気は毛頭なかった。この頃から緊迫化する基地の島の現実から沖縄の革新勢力は急進化していき、こうした急進化に本土の革新勢力が当惑するようになり、次第に両者間に溝が生じていった。我部政男教授は「このアピールには沖縄闘争と70年安保闘争との統一的な把握と展望が示されていたが、これを受け止める力量が本土革新には不足していた」(17)と指摘している。共闘会議の幹事会では回避派の社大党や県労協(全軍労を含む)と決行派の間で意見が対立したが、県労協は、ゼネストは誕生間もない屋良政権を窮地に追い込み、全軍労では大量解雇と組織の分裂が予想されるとして、ゼネスト回避に踏み切った。共闘会議の中核だった県労協の脱落でゼネスト態勢は崩壊した。この背景には、もしゼネストを強行すれば、米国側を硬化させて沖縄の本土復帰が遠のくのではないかという懸念が日本政府以外にも根強くあったことも見逃せない(B52部隊が嘉手納基地から撤退したのは翌年10月だったが、その後も随時飛来している)。
返還のあり方をめぐって日米両政府が国際情勢をにらみながら、「核つき」か「核ぬき」かの交渉を続けている間に、屋良主席の基本姿勢は平和憲法のもとで日本国民としての諸権利を完全に回復する、つまり「核基地の撤去、即時無条件全面返還」となり、日米両政府が「核ぬき本土なみ」返還を決めた佐藤・ニクソン共同声明(69年11月)とは著しいギャップを生じた。72年復帰を目前にして日本政府の要請を大筋で受け入れて、早急に準備態勢を整えていかねばならない行政上の現実的対応と、「核も基地もない平和な沖縄」をスローガンに叫ぶ反戦復帰の革新内部からの批判との板挟みとなって、屋良行政府はしばしば窮地に立たされた。
2 国政参加選挙
沖縄の国政参加への要求は、復帰運動の柱のひとつとして1961年、立法院が全会一致で要求決議を行って以来、繰り返し要請されてきた。いうまでもなく沖縄の施政権が米国にあることを理由に認められなかったのだが、業を煮やした社大党の安里積千代は、沖縄住民でも国政に参加できるはずだとして、66年の参院選に全国区から超党派で立候補、沖縄住民の国政参加を全国民に訴えた。だが惨めな結果に終わった。(18)70年5月「沖縄住民の国政参加特別措置法」が公布され、衆院5、参院地方区2の議員定数が決まった。参院全国区は復帰まで見送られたが、沖縄県民の念願のひとつがかなった。
70年前後の沖縄で革新勢力は急速に成長し、10市のうち7市までが革新市長となった。またこの国政選挙で本土系列化に拍車がかかった。沖縄自民党が70年3月に自民党沖縄県連に移行したのをはじめ、沖縄の諸政党は社大党を除いて系列化の波に洗われた。社大党は同年1月の定期大会で本土政党への系列化問題で、「本土政党の対立抗争にかかわりなく、あくまで県民の立場から県民を主体とし、民意を政治の場に反映せしめる使命をおびた政党として独自の活動を展開しなければならない」という新運動方針を採択していた。平良幸市書記長は採択に先立つ審議のなかで「72年返還は合意されたが、依然として差別や沖縄の特殊性は残っている。この沖縄の特殊性を解消し、本土と差別なき取扱いを受けるまでは、沖縄の立場を主張する特殊な沖縄の政党があってもいい。そうすることが即ち日本を正し、1億国民を正しい姿に立ち返らすことだと信じている」と答え、社大党の独自路線の意義を強調した。(19)
革新側の社大、社会、人民、公明の各党が共通して訴えたのは、反基地・反安保の反戦路線の推進と公害のない平和産業の開発だった。一方、自民党は、日本は安保体制によって経済大国になりえたのであり、また安保は世界平和に通じる故に、安保体制による豊かな県づくりが必要であると強調した。保守、革新ともに国会議員やタレントを多数、送り込んだ。自民党候補者を応援にやってきた倉石農相の発言が沖縄の世論を刺激した。その発言内容は、第一に、今回の選挙は国会議員の選挙だから、B52や米軍基地問題を地域的観点から取り上げてとやかく言うべきではない、第二に、沖縄の基地は米国から押しつけられたものではなく、講和条約によってわが国が自らの国家意思で設定したものであるというものだった。(20)これをきっかけに、日米共同声明路線の評価をめぐる論争が激化し、「安保路線」か「反戦路線」かの争点がより明白となった。
11月15日投票の結果、衆院は革新の瀬長亀次郎(人民)、上原康助(社会)、安里積千代(社大)の3名、自民の西銘順治と国場幸昌の2名が当選、また参院地方区は喜屋武真栄(革新統一)と稲嶺一郎(自民)の保革1名ずつが当選し、保革が拮抗するなかで革新優位の印象を与えた。この選挙で保守対革新の対決の構図が定着したといえよう。選挙後、自民党は安保路線を掲げて激しい革新批判を展開し、立法院では多数支配を背景に、ほとんどの対立案件について単独もしくは強行採決を重ねて、対決姿勢を全面に打ち出した。(21)
3 “歪められた返還”
復帰協は69年3月、それまでの「基地反対、核基地撤去」を「基地撤去」に改め、新たに「安保条約の廃棄」を打ち出した。復帰協の運動方針として「基地撤去」を明示したのは、これが初めてだった。「基地撤去」や「安保条約の廃棄」を基本目標に掲げることについては数年来、論争を繰り返してきた。この時も全日本海員組合、全繊同盟(各支部)の右派と社会、人民系の左派が激論となったが執行部の主張が通って、ついに「基地撤去」「安保廃棄」となった。この背景にはいうまでもなく、日米合作の安保路線に対する危機感や不安感があった。(22)しかしながら「基地撤去」を基本目標に掲げるにあたって、復帰協は結成以来、統一を堅持してきた組織を分裂させた。それは復帰運動の急進化を象徴する事件でもあった。(23)
だが69年11月の佐藤・ニクソン共同声明以後、沖縄復帰の主導権は日米両政府の掌中にあることが自明となり、復帰勢力は「72年返還の幻想」のために混迷状態を続けた。返還のあり方に希望よりも失望と不安が民衆の間に広がり、この挫折感が爆発したのが「コザ暴動」だった。70年12月20日末明、コザの街で米軍人の交通事故への憤りがきっかけで、民衆の反基地感情が爆発した。群衆は5000人に膨れ上がり、米人車両70台以上を焼き打ちにした。さらに群衆は現場に近い嘉手納基地になだれこみ、コザ市の中心街は一時、無政府状態となった。自然発生的で無秩序に見えた暴動に奇妙な統制と秩序があり、約6時間の騒ぎは午前7時半、平静を取り戻した。この「コザ暴動」の根底には、米軍の占領意識から生じた人権無視の長い歴史があった。25年間、基本的人権を奪われ忍従を強いられてきた沖縄住民のうっ屈と怨念が復帰への不安と重なって暴発したのだった(24)。71年5月19日を、復帰協は「返還協定粉砕」をスローガンに、2・4ゼネストを上まわる「全県民ストライキ」の日に決めて準備を進めた。復帰協から離脱した沖縄地方同盟の反対や官公労のスト権確立失敗などがあってゼネストには及ばなかったが、それでも右翼団体の挑発のなかでデモ隊は軍用道路一号線(現在の国道58号線)を二時間近く遮断した。
71年6月17日、東京とワシントンを宇宙中継で結び、沖縄返還協定が調印された。11月、屋良主席が“県民最後の声”を盛り込んだ建議書を握って東京に到着した時には、すでに沖縄返還協定は衆院特別委員会で、予定されていた沖縄選出議員の質問を無視して強行採決された後だった。沖縄県民の意向が十分に反映されない“ゆがめられた返還”を象徴するかのような暗転だった。社大、人民、社会の革新政党や労組は怒り、自民党や経済界は安堵と、反応がはっきりと分かれた。
(1)『沖縄タイムズ』1995年1月10日。
(2)沖縄社会大衆党史編纂委員会編、前掲書、103―104頁。
(3)屋良朝苗『屋良朝苗回顧録』朝日新聞社、1977年、102頁。
(4)沖縄社会大衆党史編纂委員会、前掲書、105頁。
(5)『沖縄タイムス』1995年1月14日。
(6)屋良朝苗『激動8年』沖縄タイムス社、1985年、17頁。
(7)当山正喜『沖縄の舞台裏―政党政治編』沖縄あき書房、1987年461頁。
(8)沖縄タイムス社『沖縄年鑑』(1970年版)、674頁。
(9)中野好夫・新崎盛暉『沖縄・70年前後』岩波書店、1970年、100頁。
(10)琉球新報社『世替わり裏面史―証言にみる沖縄復帰の記録』、1983年、561頁。
(11)屋良朝苗『屋良朝苗回顧録』、111頁。
(12)宮里政玄、前掲書、192頁。
(13)同右、89頁。
(14)琉球新報社、前掲書、566頁。
(15)中野好夫・新崎盛暉『沖縄戦後史』岩波書店、1976年、188―189頁。
(16)宮里政玄、前掲書、192―193頁。
(17)同右、193頁。
(18)琉球新報社、前掲書、240頁。
(19)沖縄社会大衆党史編纂委員会、前掲書、113―114頁。
(20)沖縄タイムス社『沖縄年鑑―復帰特集号』(1972年版)、379頁。
(21)同右、421頁。
(22)沖縄タイムス社『沖縄年鑑』(1970年版)、218頁。
(23)宮里政玄、前掲書、199頁。
(24)同右、205頁。
三 復帰後の沖縄県政
1972(昭和47)年5月15日、沖縄県民は不安と期待が交錯した複雑な思いで、この世替りの日を迎えた。東京では武道館で、沖縄では那覇市民会館で復帰記念式典が催された。一方、復帰協主催の5・15抗議県民総決起大会が雨の降りしきる中で与儀公園で開かれた。いうまでもなく米軍基地がそのまま存続したことへの抗議だった。また通貨切替えによる物価高騰などで県民の生活は混乱していた。日の丸を掲げて復帰を祝う人、憤懣やるかたない顔で抗議県民大会へ向かう人など、街の表情はさまざまだった。日本政府は復帰にあたって、「沖縄を平和の島として、アジア大陸、東南アジア、さらに広く太平洋諸国との経済的文化的交流の新たな舞台とすることこそ、沖縄戦で生命をささげられてきた多くの人たちの霊を慰める道であり、沖縄の祖国復帰を祝うわれわれの道でなければならない(1)」という声明を発表した。
だがこの声明とはうらはらに、5月9日、米国はベトナム戦争で新たな攻勢に転じ、アジア地域で最大の支援能力をもつ沖縄の米軍基地は、連日、緊迫した空気に包まれ、B52をはじめとする戦闘機や空中給油機が昼夜の別なく飛びかっていた。「平和憲法の下で、基地のない平和な沖縄を」と叫ぶ県民の声は空しく、核の疑惑の消えない米軍基地の存続は新たな重荷となってこの日を重苦しいものにした。屋良主席は、「多くの問題が未解決のまま残されており、県民の立場からすると決して満足できるものではない……沖縄問題は、復帰の時期が到来したことによって、すべてが解決したというものではなく、むしろその完全な解決へ大きく一歩を踏み出したというのが、いつわらざる実感だと思う(2)」と語った。
1 革新県政期(屋良・平良)
本土復帰の余韻も冷めやらない同年6月、復帰に伴う最初の県知事選と県議会議員選挙が実施された。復帰の是非を問う選挙選でもあった。結果は両選挙とも革新側の勝利に終わった。知事選では屋良候補が圧勝し、県議選でも社大党、人民党、社会党などの革新側が過半数を制し、社大、社会、人民ともに躍進した。なかでも社大党は立候補者の全員当選を果たし、7議席から11議席へと4議席増やした。社大党は本土系列化の波に洗われながらも、沖縄の地域政党として復帰後も存続することを決定したのたが、「この選挙結果はその決定が正しかったことを証明した」(3)と自己評価した。結局、本土化を急ぎ経済開発に重点を置く保守よりも、平和(反基地)と沖縄独自の主体性(地方自治)を強調する革新側を、沖縄県民は支持したのである。米軍統治下の長い苦難の道のりにおいて沖縄県民は自分たちの生活を守るために、反基地闘争や自治権獲得闘争をたたかって数多くの成果を収めてきた。復帰後も日米安保条約下の米軍基地を拒否し“平和の島”を回復する努力を県民は屋良県政に託した。それは「5・15沖縄復帰」への96万県民の総括でもあった。同年11月の那覇市長選挙でも革新共闘の平良良松が圧勝した。
屋良知事は「平和の島の回復に政治生命を賭ける」と言い切った。そして県民福祉と反戦平和の自主県政、基地問題の解決、経済の再開発、市町村自治、三大事業(記念植樹祭、沖縄国体、海洋博)を推進する豊かな県づくり、を強調した。これに対して野党自民党は、政治理念と現実政治のギャップが大きいと批判した。3割自治どころか1.5割自治と酷評される自主財源の貧弱さゆえに国庫に大きく依存せざるをえず、“地方自治の確立”というスローガンとはかけ離れていた。沖縄開発庁を発足させた日本政府は同年12月、「沖縄振興開発計画」を発表した。10ヵ年計画で沖縄の自立的発展を可能とする基礎条件の整備をめざし、全国平均の58%にすぎない県民所得を目標年次には80%に到達させる計画だった。
屋良県政の三大事業は立ち遅れた沖縄の基盤整備の一環として企画されたのだが、不慣れや資金難などで難航した。350万の入場者を迎えた海洋博も、地価の高騰や相次ぐ企業の倒産を招いた。こうした三大事業を中心とする基盤整備は、革新県政の「反戦平和」の旗印を大きく揺さぶる結果となった。抗議の嵐のなかで自衛隊が配備されCTS(原油中継・備蓄基地)建設が認可された。事故や事件が頻発する米軍基地では軍雇用員の解雇が相次ぎ、緊張が続いた。このように本土復帰の余震は予想以上に大きかった。
復帰後二度目の県知事選挙(1976年6月)で、平良幸市社大党委員長は革新共闘候補として勝利を収め、屋良革新県政を継承した。無所属だった屋良と異なり、沖縄の地域政党であり革新共闘の要である社大党委員長の県知事当選は、沖縄の革新共闘の健在ぶりを浮き彫りにした。保守候補の安里積千代が「中央政府の協力による自主県政の確立」を訴えたのに対して、平良は「中央支配を排した地方自治の確立」を主張した。平良県政は基地問題に対して、反戦平和の立場から積極的な打開策を打ち出していった。その結論が翌年11月、「軍用地転用特措法案要綱」としてまとまった。軍用地返還のあり方をただし、計画的な返還と有効な跡地利用を進めるために、軍用地転用行政に国の責任を引き出していこうとするものであった。だが具体化への細かな作業や国への働きかけを始めようとする矢先、平良知事は病に倒れ、辞任した(78年11月末)。平良県政では県民に期待を抱かせた振興開発計画も後期に入っていたが、石油ショック後の余波などがあって、経済不安は深刻化する一方だった。いずれにせよ2年5ヵ月の任期はあまりにも短すぎた。
2 保守県政期(西銘)
平良知事の病気辞任に伴なう1978年12月の県知事選挙は、県政の潮流を革新から保守へと変える分岐点となった。前年の参院選挙や地方選で台頭してきた保守化への流れは、革新県政10年の節目でついに保守県政を実現した。保守側が衆議院議員であった西銘順治の出馬にいち早く成功し、自民、民社、新自由クラブ、社民連の推薦を取りまとめることができたのに対し、革新側は共闘体制の乱れと候補者決定の遅れが選挙結果に大きく響いた。西銘は、イデオロギー論争に明け暮れる革新県政の雇用・失業問題への責任を追及し、積極的な企業誘致と中央直結による開発を提唱した。これに対して革新の知花候補は有事立法問題で応酬したが、68万の有権者は経済問題の解決を最優先し、その解決を保守県政に託した。本土復帰のあり方を革新県政に委ねてきた県民は、復帰後、本土の経済への急速な系列化や深刻化する経済不況などで混乱が続く沖縄経済の建て直しを、中央政府との協調に依拠する保守県政の施策に託したといえよう。その結果、反戦反基地と自治主義から基地・自衛隊の容認や中央直結へと基本路線が変わった。西銘県政は大型プロジェクト主導型の地域開発に着手した。
その反面、基地行政が後退し、自衛官募集業務を開始した。80年の県議選で保守が過半数を占め、社大党の衰退が目立った。また西銘県政は「沖縄をわが国南の交流拠点に」とする国策に沿う形で、79年10月、「国際交流拠点」の形成基本案を発表した。一般消費税問題で「国難を救うことは、国庫依存度の高い沖縄を救う道である」と言い放った西銘知事は、中央直結、中央との協力もしくは国策優先を打ち出し(4)、国庫資金の極大化をはかることで積極的な開発行政を推進していった。国政レベルで衆議院の議席配分は革新3(社会、公明、共産)・保守2(自民)で革新優位は変わらず、参議院は一対一で推移してきた。また県都の那覇市長は革新が守りつづけた。だが宜野湾、浦添、名護などの市長は保守が占めるようになった。84年の県議選でも保守系は前回を上回る安定多数を獲得し、西銘県政の基盤はより強固になった。度重なる選挙で革新の要の社大党は低落の一途をたどり、その減少分を社会、共産、公明が補う傾向が続いた。知事選では西銘知事が再選を果たした82年に、革新は復帰運動で名をはせた喜屋武参議院議員を担ぎたして接戦となったが及ばず、86年選挙では、革新側の足並みの乱れから大差で西銘三選が決まった。
企業誘致の成果は上がらず、数々の大型プロジェクトの具体化も、頼みとした中央政府の財源難から決してスムーズには運ばなかった。県民所得は依然として全国最下位である。しかしながら、社会基盤は着実に整備され、また観光客は300万をめざす勢いで増大し、基地依存経済を脱却して観光業を主柱とする第3次産業中心の経済へと転換していった。ただ西銘県政下でも基地の演習やトラブルが相次ぎ、抗議や対立が頻発した。また土地改良事業は赤土汚染を日常化し、リゾート・ラッシュは地価の高騰と自然環境の破壊をもたらし、過度の観光開発が沖縄の美しい自然を次々に消し去っていくのではないかという不安を県民は抱きはじめた。新石垣空港建設予定地をめぐる混乱や論争は、地域開発か自然保護か、その選択を迫って国際世論をも巻き込んだ。
3 再び革新県政へ(大田)
県政は保守化傾向にかげりが見え始め、逆に守勢一方だった革新が勢いを取り戻し始めた。88年6月の県議選で、革新側は2議席増やして保革伯仲に持ち込み、同年11月の那覇市長選では、革新の親泊市長が大差で再選された。89年、参院選で革新統一候補の喜屋武真栄が再選され、90年早々に革新は県知事選統一候補として大田昌秀琉大教授の擁立を決定、その直後の衆院選で革新側は反自民で結束を固めて三議席を守り、保守側の内紛をしり目に県知事選への共闘体制を固めていった。社大党は久しぶりに革新の要役を強く印象づけた。同年11月の県知事選は世界中が湾岸危機で揺れるなかで行われた。平和協力法案を支持する西銘発言をめぐって、再び「基地の島・沖縄」が論点となり、沖縄戦と平和研究の学者、大田候補が「反戦平和」「公平、公正な政治」を訴えて当選し、革新陣営は12年ぶりに県政を奪還した。
少数与党の県議会でそれまでの保守県政とは打って変わって「基地の全面返還」を掲げ、平良県政同様、返還軍用地の利活用に向けた軍用地転用促進特別措置法(略して軍転特措法)の制定を急いだ。また大田知事は再三にわたって渡米し、国務省や連邦議会などに沖縄の基地問題の実情を訴え、理解を求めた。未契約米軍用地の強制収用に伴う公告・縦覧代行問題でも三ヶ月余りも沈黙を守って国政への抵抗の姿勢を示した。だがいずれも、日米両政府の壁は厚く、選挙公約であった「反戦平和」の具体的成果を実現することの難しさを県民にも実感させた。その他、沖縄を平和の発進地として、国際平和に関する文化活動、交流、研究の新たな拠点形成を目指した「国際平和創造の杜」構想を大田県政の目玉として推進し、95年6月、国籍を問わず沖縄全戦没者23万余の名を刻んだ「平和の礎」が完成した。21世紀に向けて「平和で活力に満ち潤いのある沖縄県」をめざす「第三次沖縄振興開発計画」が、92年9月に沖縄振興開発審議会の答申と関係行政機関との協議を経て決定された。計画の決定に当たっては、米軍基地の取扱をめぐって「全面返還」の記述を盛り込んだ県案が「安保条約という国の施策と合致しない」という理由で削除され、「縮小」へと変わった。(5)
(1)『沖縄タイムス』1972年5月15日。
(2)『琉球新報』1972年6月15日
(3)同右、1972年6月27日
(4)『沖縄タイムス』1989年3月9日
(5)『琉球新報』1992年9月29日
四「68年体制」の崩壊
沖縄の「68年体制」は平和憲法と日米安保体制をめぐって保革が対峙した55年体制の縮図でもあり、またその支柱でもあった。本土の政治における自民党対社共プラス公明という対決の構図は、沖縄の「68年体制」でも同様であった。ただ前述したように、沖縄独自の社大党が社会、共産、公明などの革新勢力を束ねる重要な役割を果たしてきた点が本土とは異なる。また沖縄の保革双方が主張した政策は、本土の両者の政策を色濃く反映していた。本土の55年体制と沖縄の「68年体制」における保革の対立軸はほぼ一致していたからである。ただし復帰闘争にみるように、沖縄革新の主張や行動はしばしば本土革新の枠をはみ出したのであるが。
本土の55年体制においては革新側は次第に多党化していき政権を獲得する可能性は生まれなかった。だが60年代後半から70年代にかけて地方自治体の選挙では、東京、横浜、大阪などで革新自治体が次々に誕生し、保守勢力に代わる統治主体として注目すべき諸政策を実施した。こうした革新自治体運動の一翼を沖縄の革新自治体は担っていた。70年代後半になって行財政の状況が大きく変化したことなどによって、本土の革新自治体が急速に後退していくのと歩調を合わせるように沖縄の革新自治体もいったん姿を消した。
沖縄の本土復帰が日米両政府間で決定した直後の69年12月の総選挙で自民党は圧勝し社会党は大敗、公明党と共産党が躍進した。この後、自民党と社会党は長期低落傾向をたどる。一方、沖縄では復帰6年目に保守県政が実現した。西銘知事は・イデオロギー論争に終始する革新勢力・を真っ向から批判して、経済開発を最優先する政策を次々に打ち出した。西銘県政の80年代は、安保闘争直後に登場した池田内閣が、所得倍増計画などを打ち出して経済主義へと路線転換をはかった60年代の状況と類似している。しかしながら復帰後、20年が経過してもほとんど変わらない基地の重圧への不満や苛立ちが鬱積していき、とりわけ冷戦構造崩壊後、平和の配当を願う切実な県民の要望は、米軍基地の縮小撤去と日米安保体制の見直しを再び、緊急の課題として革新県政を再登場させたのである。
ところで過去3度、野党共同提案で審議未了・廃案の経過をたどった軍転特措法案が94年6月、沖縄県案を踏まえて連立与党と社会党が中心となって議員立法として国会に提出された。だが7月に羽田政権が崩壊して村山自社さ連立政権が誕生、社会党は自民党との共同提案をめざして調整に入った。そのさ中、村山首相は自衛隊合憲を言明し、さらに日米安保条約についても「冷戦終結後もわが国の安全確保とアジア太平洋地域の安定要因として米国の存在を確保するために必要不可欠だ」と強調し、従来の社会党の安全保障政策を根本的に転換する考えを表明(1)、社会党も追認した。この政策転換は日米安保ゆえに米軍基地を抱える沖縄に大きな衝撃を与えた。55年体制を担う主力政党として与野党に分かれ、これまで対立してきた自民党と社会党が連立政権を組み、さらには主たる対立軸であった日米安保体制と自衛隊に対する政策を社会党が大きく劇的に転換して自民党に歩み寄ったことで、名実ともに55年体制は終焉したといえよう。
社会党沖縄県本部は「首相の発言は納得できない」と一時、社会党本部との一切の関係を凍結した。その煽りを受けて9月の統一地方選で社会党は沖縄で敗北し、苦境に立たされた。基地視察のために来沖した防衛施設庁の宝珠山長官が、「沖縄はアジア戦略の要地であるから基地と共生、共存してほしい(2)」と発言し、これを基地固定化を当然視する発言として沖縄県議会は一斉に反発、抗議を表明した。この発言は村山首相の政策転換を受けた日本政府の本音と沖縄では受け止められ、発足当初は期待した村山政権から沖縄県民は立て続けに冷水を浴びせられる格好となった。反発の強さから結局、宝珠山発言は撤回せざるをえなくなった。自民党との調整が焦点となった軍転法案は自民党の修正案をめぐって合意に達せず、年度内の成立を断念した。
94年11月の県知事選で社大、社会、共産、日本新党推薦で再選をめざした大田は、自民推薦の翁長助裕候補を大差で破り、革新県政をいっそう強固にした。だが自民党政権崩壊後における中央政界の液状化はこの選挙にも大きな波紋を生じた。68年以来、各政党と労組が統一綱領を掲げて一体となって戦ってきた革新共闘体制が崩壊、知事サイドと各党が個別に政策協定を結ぶ「ブリッジ共闘」というゆるやかな協力体制で選挙戦に臨む結果となった。社会党の政策転換や自社政権に対する共産党の反発は大きく、これが共闘体制を断念させた大きな要因となった。自民党県連は従来の「基地縮小」から県益優先の立場で「基地撤去」へと踏み込む姿勢を見せて選挙戦に臨んだが、それまで保守系だった新生党や民社党の支持を得ることができず、自民党の退潮を浮き彫りにした。「68年体制」の一方の主役であった自民党県連は、今では保守系市町村議員や保守支持の有権者をかなり新進党に奪われ、党基盤を弱体化させている。そしてまた「護憲・反安保」を・錦の御旗・として掲げる革新陣営に対して、翁長候補は「保革の枠を超えた新しい政治潮流」を訴えつづけたのだが、自民党県連内からも日米安保の見直しや米軍基地の全面撤去が主張され始め、確実に保革の対立線がぼやけ始めた。(3)
95年1月、日米首脳会談では日米安保体制の堅持を確認し合った上で、クリントン大統領は「沖縄の米軍基地の整理、統合に努力する」と表明し、沖縄県民に希望を抱かせたが、基地の整理、統合とは結局、沖縄内での基地のたらいまわしにすぎないことがわかり、何ら具体的な進展はなかった。軍転法案の方は、原案から国の責務が軽減され、さらに原案にはなかった日米安保条約の条項などが付け加えられた末、衆参両院で全会一致で可決され、6月から施行されることになった。7年の時限立法である。55年体制崩壊後の自社連立政権がこれまで幾度も阻止されてきたこの法の成立にともかく有利に作用したといえる。度重なる譲歩を強いられながらもこの法律の成立が返還軍用地の跡地利用の促進に大きく寄与すると受け止められ、戦後50年の節目に返還へのひとつの手ががりがようやく実現した。平良知事が着手して実に20年を経過してやっと日の目をみた法律だった。
「68年体制」の崩壊は、7月の参院選でいっそう顕著となった。自民党推薦で返り咲きをめざす大城真順候補と社会・社大推薦、公明支持の照屋寛徳候補、共産党公認の外間久子候補の三つどもえの選挙戦となり、これまでの保革一騎討ちの選挙とは一変した。この選挙でこれまで革新共闘体制を支えてきた社会党と共産党が初めて全面対決した。結局、照屋候補が勝利を収めたために、自民党は比例代表区の一議員が引退し、一議員が落選した結果、参院ですべての議席を失った。
(1)『朝日新聞』1994年7月21日。
(2)『琉球新報』1994年9月10日。
(3)『沖縄タイムス』1995年1月7日。
展望にかえて
95年9月初旬、明るみに出た三米兵による少女暴行事件をきっかけに沖縄県内で激しい怒りが渦巻き、わが国のみならず世界中に報道されて大きな反響を呼んだ。この事件を契機にこれまで抑制され、蓄積されてきた基地問題への怒りや不満が一挙に爆発して沖縄は今、復帰後、最大の転換点を迎えつつある。復帰後も米軍基地の重圧は変わらず、基地に起因する事故や事件が頻発して沖縄県民を脅かし続けてきた。ちなみに米軍人・軍属・家族に関する犯罪は復帰後で約4,700件、米軍機墜落事故は36件、そして県道104号線を封鎖して行われる実弾演習は87年から急増して付近の住民を危険にさらしている。犯罪をおかした米兵は日米地位協定を楯に基地内に逃げ込み、そのうち帰国するといったケースは枚挙にいとまがない。こうした“植民地状態”がいまなお継続している現実があるから、「日本に主権はあるのか」という批判の言葉が出るのである。また男中心の軍隊組織は女性にとって構造的暴力組織であるという、女性の人権擁護の立場からの批判は沖縄県民の共感を呼んだ。(1)
抗議運動は日一日と広がりと激しさを増し、次第に大きな波となっていった。10月21日、基地に隣接する宜野湾市で開催された抗議の県民総決起大会には、5万人の予想を大きく上まわる8万5000人の人々が参加した。地位協定や安保条約の見直し、そして米軍基地の具体的かつ大規模な縮小計画を要請する代表団に対して、河野外相などの対応は拒絶するだけの極めて冷淡なものであり、それでまた沖縄の怒りを買うと、地位協定の見直しまでせず、その運用面の検討だけで切り抜けようとする。事が起きるたびにこのように小手先だけでかわす日本政府の手法を沖縄は幾度も経験し、そのたびに言い知れぬ不満が蓄積されていった。今回の大規模な抗議行動は復帰後23年間、沖縄の基地問題に対して日本政府が無為無策であったことへの怒りの表明であり、根は深いといわざるをえない。冷戦構造が終焉した後もなぜ沖縄に巨大な米軍基地が居すわり続けるのか、西欧からは米軍は大幅に撤退しているのに、なぜ沖縄から撤退しないのか、日本政府の思いやり予算は米軍を引き留めるためなのか、半世紀にわたって米軍基地と共存を押しつけられ続けてきた沖縄県民は、21世紀を目前にしても一向に変わらない基地の現状にこうした疑念を深めている。
このような沖縄の世論を背景に、大田知事は未契約軍用地強制使用手続きに伴う土地・物件調書への「代理署名」を拒否すると公表した。その理由として同年2月に米国防総務省が発表した東アジア戦略や日米安保の再定義などで、沖縄の基地機能が強化、固定される危険性が十分あるからだと知事は説明した。(2)一時は代理署名する方向に傾きはじめているかに見えた知事が逆の方向に転じたのは、事件以降の沖縄世論への配慮がある。復帰以降、ほとんど聞かれることのなかった沖縄独立論までささやかれるようになり、米軍基地問題への日米両政府の対応次第では今後、予断は許さない。
96年4月、橋本・モンデール会談で普天間基地の全面返還が決まった。那覇市に隣接するこの基地の返還を県民は強く要望していたので、この決定は大きな朗報として最初は受けとめられた。だがこの合意は嘉手納基地と岩国基地への機能移設が前提条件となっており、とりわけ東洋一の基地を誇る嘉手納周辺の住民は、今でも爆音禍や事故などで忍耐の限界にあり、これ以上の基地強化への反発は非常に大きい。単なる“基地ころがし”ではないかという批判の声も根強い。9月8日、沖縄県は「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位定の見直し」の賛否を問う、わが国で初めての県民投票を実施した。その結果、自民党県連の棄権表明などが響いて投票率は59.53%にとどまったが、賛成票が約48万2000で投票総数の89%に達し、棄権を含めた全有権者の過半数(53%)を超えた。大田知事は、賛成票が圧倒的多数を占めたこの投票結果について、「基地問題を解決しなければ沖縄に明るい未来は作れないという認識の表れ」と評価した。(3)
在日米軍基地の75%が全国土面積の0.6%しかない沖縄に集中している。沖縄本島では面積の20%が基地に占有されている。そして沖縄の米軍基地の特色は約3万人の沖縄の地主が存在することである。三沢や横須賀の米軍基地は88%までが国有地である。だが沖縄では国有地は34%にすぎない。(4)なぜなら基地建設のために米軍は強制的に住民の土地を奪ったからである。現在、その地代を日本政府が支払い続けているが、契約の更新に応じようとしない地主に対して、政府は強制使用の手続きに入ろうとして大きな政治問題となっている。さらにまた沖縄県の国際都市構想などのように沖縄の将来計画を策定していく上で米軍基地はどうしても最大の障害になる。広々とした基地のフェンスの外で沖縄の住民は息苦しいほど密集した生活をよぎなくされている。読谷、嘉手納、宜野湾など大きな基地を抱える自治体では基地撤去後の跡地利用を織り込んで都市計画を作成しており一部施行されている。要するに、米軍基地の撤去もしくは大幅な縮小がなければ沖縄の21世紀に向けた未来像は描きようがないという限界状況にあるのである。
沖縄の政治構造は日米安保体制の要である在沖米軍基地への対応政治をめぐる保守と革新の対決に基地的特徴があったが、そうした沖縄政治の「68年体制」は、日本政治の55年体制の崩壊現象に大きな影響を受け、さらに全県民一致して米軍基地問題に取り組もうとする姿勢にかつてのイデオロギー性が薄れて徐々に保革の大枠も崩壊しながら新たな方向を模索しつつある。沖縄の政治は今後、「保革対決」から「非自民・非社民」になるのか、それとも米軍基地への憤怒が沖縄ナショナリズムを高揚させ、社大党を中心に諸政党が結束を固めて溝を深めつつある日本政府と対峙していくのか、大田知事の采配と社大党や新進党の動向が大きな鍵になると思われる。いずれにせよ沖縄は米軍基地問題を通して、これからも戦後日本の民主主義を正面から問い続けていくことになるだろう。
(1)『沖縄タイムス』1995年9月15日。
(2)『琉球新報』1995年9月29日。
(3)『沖縄タイムス』1996年9月9日。
(4)『アエラ』1991年10月22日号、7頁。
このページのトップにもどる