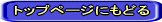|
自立解放をめぐる参考資料4/安良城・西里論争 |
★安良城盛昭『天皇・天皇制・百姓・沖縄』(吉川弘文館1989年4月)より
★西里喜行「琉球=沖縄史における『民族』の問題―琉球意識の形成・拡大・持続について―」(『新しい琉球史像』榕樹社1996.10)
☆安良城盛昭「琉球処分論」(『新・沖縄史論』沖縄タイムス社1980)
天皇・天皇制・百姓・沖縄
(吉川弘文館1989年4月)
安良城盛昭
P208~212〔附記①〕
1986年地方史研究協議会大会討論の折に西里喜行氏から、琉球王国は「島津の琉球征服・明治維新期の<琉球処分>の二段階を通じて日本社会のうちに包摂された」と安良城は主張するが、徳川期の琉球はなお「琉球王国」であって、どんな意味内容で日本社会に包摂されているとみなせるか、と問われた。大会討論の折に簡単に答えておいたところであるが、徳川期の「琉球王国」は、島津の琉球征服によって、徳川期日本経済の一環にはっきりと組みこまれ、その構造的一環に定置させられていた史実を私は重視しているのである。
この点は、従来の琉球・沖縄史研究ではこれまで全く看過されていたので、西里氏のような疑問が生じたのであろう。
徳川期における琉球王国は、島津に対する貢納(米)と貢糖(砂糖)の義務負担の故に、琉球経済について、沖縄本島の北部(山原)を米生産地、南部(島尻)を砂糖生産地、という二極の地域構造に編成替し(この編成替=二極構造は、沖縄県になっても定着しつづけた)、日本より昆布を筆頭とする素麺などの消費物資を移入するという、徳川期日本経済の一環に組みこまれる経済対応を行なっている。
「琉球王国」の進貢貿易も、「長崎口」「対馬口」とならぶ「琉球口」として幕府の公認と規制の下に行なわれており、中国より輸入された前期の白糸、中後期の漢籍・漢方薬・奢侈品等は、基本的には日本本土に移出することを前提とした輸入であった。
島津の琉球征服という、「琉球王国」の日本社会への政治的包摂は、実質的な経済的包摂を徳川期に必然化し、これを基盤に、「琉球処分」は、琉球の全面的な日本国家・社会への政治的・文化的包摂を、上から他律的=強圧的に完了したのである。二段階的包摂とみなす所以である。
西里氏にはこういう経済史的視点が全く欠落しているが故に、西里「琉球救国運動と日本・清国」(法政大学沖縄文化研究所編『沖縄文化研究』13・1987年、所収)といった、私からみれば、不可解としかいいようのない論考が生まれてくると思うのである。
西里氏はいう。
たしかに、明治政府の旧慣温存政策によって、琉球士族層のなかの有禄士族は琉球処分後も「寄生的な特権」を保障され、「非常特別ノ優待」を受けたのであって、個人的な利害関係だけから云えば、なにも「ぼう大な反権力的・反政府的エネルギー」を投入して「寄生的な特権を守る」運動を展開する必要などはなかったのである。にもかかわらず、琉球士族層のなかには、明治政府の保障する「寄生的な特権」にはあえて目もくれず、波涛を超えて清国へと亡命し、清国当局者へ執拗に琉球救国の嘆願を続けるのも少くなかったので、陳情通事・林世功のように、琉球救国のために一命を投げだし、自刃して果てるといういわゆる琉臣殉義事件さえ現出しているのである。琉球士族層を琉球救国運動へ駆り立てたものは、なんであったのだろうか。 ここに、解明されなければならない重要な問題があるように思われる。(29頁)
この論考は、徳川期の「琉球王国」が一個独立の国家として存続していた、というような錯覚を前提としないかぎり成り立たないと考えるのは、私だけの僻目だろうか。
なるほど、史料の上では、亡命士族は、国家、国家と騒ぎ立てているけれども、それは一体、社会科学的にいって、あるいは、歴史科学的にいって、どんな国家だったのだろうか。西里論文は、亡命士族が、「琉球王国」の滅亡の不可を声高に論じているから、それは「琉球救国運動」である、などとその言動を歴史的に評価するが、それはまったく奇妙な判断としか私には思えない。
大体、亡命士族の「琉球王国」の存続・維持運動は、「琉球民族体」(庶民をふくめた)のヤマト抵抗運動などと判断できる根拠は一切ないのである。亡命士族には琉球の庶民や琉球文化を守ろう、などという意識は一切ないのであって、だから、仮に「ある種の」という限定をつけたにせよ「民族運動」ではありえない。あるのは唯一つ「琉球王国」存続によって、その士族的特権を永遠に維持したい、というアナクロニズム的な有禄士族の利己主義的意識を、中国を中心とする冊封体制的秩序肯定の下に儒教的に粉飾したものである。大江健三郎氏によってもてはやされてきたために、過大評価されてきた林世功の言動も、琉球文化・琉球民衆を無視した儒教的志士・仁人以上のものではない。
私は、「琉球処分」は「上からの・他律的な民族統一」(安良城『新・沖縄史論』1980年・沖縄タイムス社)というかつての見解を今もなお堅持するものであって、このような西里氏の見解には到底賛同できない。
西里氏が「救国運動」と評価される一部士族の「脱清活動」が、多数の士族と全庶民という「琉球民族体」(もしそうよぶとするならば)の基幹に全く見はなされてしまった歴史的現実を、西里氏は一体どう考えられているのだろうか、とあえて問いたい。
西里氏のこの論考の発想の原点がそもそも誤っている。西里氏は先に指摘したとおり、次のようにいう。
明治政府の旧慣温存政策によって、琉球士族層のなかの有禄士族は琉球処分後も「寄生的な特権」を保障され、「非常特別ノ優待」を受けたのであって、個人的な利害関係だけから云えば、なにも「ぼう大な反権力的・反政府的エネルギー」を投入して「寄生的な特権を守る」運動を展開する必要などはなかったのである。にもかかわらず、琉球士族層のなかには、明治政府の保障する「寄生的な特権」にはあえて目もくれず、波濤を超えて清国へと亡命し、清国当局者へ執拗に琉球救国の嘆願を続けるものも少くなかった
冗談ではない。明治政府が認めている現在の「非常特別ノ優待」=「寄生的な特権」が一時的なものであって、遅かれ早かれ消滅することを「脱清士族」は知っていたが故にこそ、彼らの「寄生的な特権」を永続的に保証する「琉球王国」の恢復を願う階級的運動に彼らを駆り立てたのであって、階級をこえた「琉球民族体」(もしそういうものがあるとするならば)の「ある種の民族運動」などと評価するのは、没階級的視点から必然的に生みだされた幻像以外のなにものでないのである。
西里見解は、①その「琉球救国運動」という歴史認識における「救国」の対象となる「琉球王国」は独立の国家であったかどうか、という徳川期「琉球王国」の政治・経済実態に関する歴史認識に欠け、②亡命士族の言動が「琉球民族体」(もしそうよぶことができるとすれば)の反ヤマト民族運動であることを何ら論証していない、没階級的視点にもとづく見解であり、③亡命士族を駆りたてたものは、旧慣存続期における彼らに対する「非常特別ノ優待」がかりそめのものであることを、その階級的本能によって察知できた(士族が馬鹿でない限り、旧慣存続期の政治過程を通じて身にしみてこのことを十分に実感できたはずのことを、前掲安良城『新・沖縄史論』で詳論したところである)からである、というごく素直な歴史理解を、何の検討も説明もなしに、あっさり無視して否定し、「ある種の民族運動」といった短絡的謬見を強調しているが、「ある種」とは一体どんな種類の「民族運動」なのか、全く説明されていない。④こういう短絡的謬見については、すでに1983年に比屋根照夫氏の『自由民権思想と沖縄』(1982年・研文書院)について「朝日ジャーナル」1983年2月11日号の書評欄で私は厳しく批判しておいたところである。にもかかわらず、これを無視して勝手な議論を展開するのは、独善的というほかはない。
「琉球処分」の《上からの・他律点な民族統一》の強圧的性格に対する批判は、このような西里的な感性的な仕方ではなく、歴史科学的になさるべきであって、亡命士族の階級的言動を没階級視点的に、「民族的」(?)視点から再評価などすべきではない。
琉球=沖縄史における「民族」の問題―琉球意識の形成・拡大・持続について―
(高良倉吉・豊見山和行・真栄平房昭編『新しい琉球史像』榕樹社1996.10)
西里 喜行
Ⅰ はじめに――問題の所在――
1970年代の後半、琉球=沖縄史研究に旋風を巻き起こした安良城盛昭氏は、通史としての琉球=沖縄史を叙述することはなかったものの、「琉球処分論」のなかで琉球=沖縄史の大きな枠組みを次のように提起している。つまり、同一の種族に属し同一の言語を使用しながらも、日本とは別に独自の国家を形成した琉球社会は、薩摩の琉球征服と明治政府の琉球処分という二段階を経て日本国家へ組み込まれたのであって、その最終局面としての琉球処分は「上からの・他律的な・民族統一」と規定すべきである、という枠組みである(『新・沖縄史論』198頁以下)。
このような安良城氏の枠組みを踏まえながら独自の琉球=沖縄史像を構成したのは高良倉吉である。高良氏は琉球=沖縄史を次の五つの時代、すなわち①先史時代(数万年前の旧石器時代から12世紀頃まで)、②古琉球(12世紀頃から島津侵入事件まで)、③近世琉球(島津侵入事件から琉球処分まで)、④近代沖縄(琉球処分から沖縄戦まで)、⑤戦後沖縄(沖縄戦から日本復帰を経て今日まで)に区分しつつ、琉球=沖縄史の基本的特質を次の3点に要約している。第一に、「原日本文化ともいうべき文化複合を有した人々によって担われた歴史であったにもかかわらず、日本列島における歴史形成とは異なり、みずから独自の国家を成立させ」たこと、第二に、「独自の王国をもった地域が、近世初頭および近代初頭に惹起した二つの事件――島津侵入事件・琉球処分――を契機に段階的に日本社会の一員に編成された点」、第三に、戦後の「アメリカの直接統治を体験し」、復帰運動を通じて「日本社会への復帰を選択・要求し」、実現したこと、以上である(『琉球王国史の課題』14頁以下参照)。
以上のような安良城・高良両氏の琉球=沖縄史像の枠組みについて、ここで注目しておきたいことは、第一に安良城氏が民族統一の視点からアプローチしているのに対して、高良氏は必ずしも民族統一の視点に固執せず、歴史的局面の変化を経験的に捉えて時代区分していること、第二に琉球処分を民族統一の最終局面として位置づけた安良城氏は、近代以後の琉球=沖縄史における「民族」の問題を視野の外に置き、従って戦後のアメリカの直接統治や「日本復帰」も歴史的体験の特殊性として捉えていること(「沖縄の地域的特質」『現代と思想』33号)、第三に琉球=沖縄史における国家形成の主体について、高良氏は「原日本文化の所有者」とか「独自の王国をもった地域」と称して国家主体の名称を回避し、安良城氏もまた「琉球社会」と規定しているだけで、「琉球社会」を構成する「人々」の結合体を明示する特定の呼称を用いていないこと、これである。
要するに、安良城氏にしても高良氏にしても、歴史的「独自性」をベースにして琉球=沖縄史像の枠組みを提示しているにもかかわらず、琉球=沖縄史の担い手がどのような独自性を有する「人々」であるのかを明確に規定してはいないのである。琉球=沖縄史における国家の形成を問題にするのであれば、国家形成の主体をどのように捉えるのかという問題を回避することはできないであろう。それは同時に、琉球=沖縄史における「民族」の問題を検討の対象に据えることを意味する。
琉球列島に住みついて国家を形成した「人々」を、明確に「琉球民族体」と規定したのは藤間生大氏である。藤間氏は1970年代の初頭、独自の民族理論を琉球=沖縄史へ適用し、「琉球民族体の日本民族への転化」という視点から薩摩の「琉球入り」を「転化」の第一段階と認め、琉球処分を「転化」の第二段階と評価しつつ、逸早く二段階民族統一説を提起することによって、琉球=沖縄史の全体像の枠組みを構築している(『近代東アジア世界の形成』第三章)。確かに、注目すべき問題提起ではあるけれども、スターリン流の「民族体」の概念には、歴史的な特殊性が付着しているために、近代以後の「琉球民族体の日本民族への転化」=「同化」を無条件に肯定してしまいかねない問題性を内包していることに留意すべきであろう。もっとも、「民族体」を近代以前に限定して理解するのではなく、近現代においても多民族国家の構成要素として位置づけられるエスニシティの概念へ連結させて捉えるならば、琉球=沖縄史像を構築する上で一定の積極的意義を持ち得るかも知れない。民族体と民族の関係をより柔軟に捉えることはできないであろうか。
いづれにせよ、日本民族とは別の民族集団が前近代において独自の国家を形成したとすれば、その民族集団を特定する呼称が必要であろう。ここでは、とりあえず伊波普猷以来の慣用に従って琉球民族と称することとし、その自己意識を琉球意識と概括した上で、琉球民族の民族的結合の強弱を計測するための重要なバロメーターとして、琉球意識の内実に注目したい。その際、琉球列島が広大な海域の多数の島々から構成されていることを考慮して、琉球=沖縄史における中心と周縁の関係が政治的・経済的・文化的にどのように規定されたのかという視点から、琉球意識の内実へアプローチする必要があるであろう。
かくて、本稿の課題は次のように設定される。即ち、琉球=沖縄史における中心と周縁の関係を視野に置きつつ、とりわけ周縁に位置する道の島と先島に視点を据えて琉球意識の形成過程の特質と内実を問うとともに、琉球=沖縄史の歴史的局面の転換が琉球民族の自己意識=琉球意識をどのように「変容」させたのかを検討することによって、二段階民族統一説を再検討すること、これである。
Ⅱ 王国形成期の「琉球」と道の島・先島
一、王国の成立とその自己意識・国際意識
言語学的研究によれば、同一の日本祖語から「本土方言」と「琉球方言」が分離したのは3世紀から6世紀の間であるとされる(外間守善『沖縄の言語史』)。考古学的研究によっても、縄文文化・弥生文化が琉球列島のかなりの部分に展開していたことが実証されつつある。先史時代に遡れば、琉球列島に住みついた人々が日本列島の人々と共通の文化をもつ集団であったことは、もはや疑問の余地はないように思われる。とはいえ、琉球列島を固有の生活圏とした人々は「日本」と共通の文化をベースにしながらも、12世紀から16世紀までの間に独自の文化を創造しはじめ、一方で日本の中世社会の影響を受けつつ、他方でアジア諸民族との交流のなかで独自の国家を形成したという認識が、伊波普猷以来多くの研究者によって強調されていることも周知の通りであろう。琉球=沖縄史において古琉球の時代と称されるこの時代をどのように認識するかが、琉球=沖縄史像全体の構成を決定的に左右することは言うまでもない。
もっとも、12世紀から16世紀までの5世紀の間に、すなわち古琉球の時代に形成された琉球王国の評価については、ほぼ三つの見解がある。第一は琉球王国を日本の中世社会の枠組みのなかで捉え、この時代の琉球=沖縄史を「東国史」「奥羽史」と同質の日本中世史のバリエーションとして理解しようとする見解(仲松弥秀・高城隆等)であり、第二に琉球王国の形成過程で久米村の「華僑」が果した役割に注目し、明国の出先機関(朱明府)に操られた交易のための人工国家とみなす見解(太田良博・生田滋等)であるが、いづれも琉球王国の独自性・自立性を否定もしくは過小評価する点において共通している。伊波普猷以来の認識を継承した第三の見解は、日本祖語から分離した琉球語を使用する民族集団が日本の中世国家の圏外に独自に形成した自立的な貿易国家であることを強調する(藤間生大・高良倉吉等)。
琉球王国の実体をどのように評価するにせよ、14世紀後半以来、東アジア世界の中に「琉球」「琉球国」という呼称で明示される地域・国家が存在し続けたという事実を否定することはできないであろう。むろん、その呼称は中国大陸の明王朝から与えられたとはいえ、琉球王国の形成過程において、それが王国の担い手たちの自己意識として定着していったことは歴代宝案や琉球薩摩往復文書などの外交文書によっても十分に確認される。また、周知のように、15世紀中頃のいわゆる「万国津梁の銘」には、「琉球国は南海の勝地にして、三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車となし、日域を以て唇歯となす」とあり、王国の担い手たちは東アジアの一国としての自国の位置と役割を明確に自覚し、隣国を唇歯輔車の関係にある貿易相手国として位置づけている。この時期の琉球王国の外交には、京都五山の僧侶や久米村の三十六姓の系統が深く関わっていたとはいえ、外交主体としての王国の担い手たちが自立的な自己意識すなわち琉球意識と、東アジアの国際情勢をベースにした独自の国際意識を確立していたことは否定できないように思われる。
明国や日本・朝鮮などの東アジア諸国とシャム・ジャワ・マラッカなどの東南アジア諸国を結ぶ仲介貿易を展開した琉球王国は、16世紀に入ると、国際社会においても広く認知されるに至る。ポルトガル人のトメ・ピレスが「レケオ〔琉球〕人はゴーレスと呼ばれる。かれらはこれらの名前のどちらかで知られているが、レキオ〔レケオに同じ〕人というのが主な名前である」(『東方諸国記』)と記録して世界に紹介したのは周知の通りである。自他共に琉球人・琉球国の存在を認知したこの時代に、王国の担い手たちの自己意識は琉球意識として確立したと見なしてよい。もっとも、その琉球意識が王国支配層の対外的な自己意識であったとすれば、琉球王国を支える民衆の自己意識は沖縄(ウチナー)意識というべきであるが、両者は王国支配層の意識においても往々にしてオーバーラップしていること、しかもその琉球意識あるいは沖縄意識は王国の中心地(沖縄本島地域)の人々に限られていることに注目すべきであろう。
琉球を東アジアの一国とみなした諸外国の人々も、この時期には琉球列島全体を包括する名称として「琉球」という呼称を用いたわけではない。1453年に博多僧の道安が作成したといわれる「琉球国之図」には「与論島は度九(徳之島)を去ること55里、琉球を去ること15里」とあり、与論島や徳之島は「琉球」の範囲に含まれていないが、朝鮮人の申叔舟もその説明をそのまま受け容れている(『海東諸国記』)。しかし、15世紀後半から16世紀後半までの1世紀の間に、琉球列島全体を政治的に統一した琉球王国の担い手たちは、固有の政治制度や社会組織・宗教組織を産み出し、王国を支える民衆は「おもろ」に代表される独自の精神文化を創造し、自生的な世界観・他界観を共有したわけであるから(伊波普猷『古琉球の政治』『全集』2巻参照)、王国の領域の拡大に比例して琉球意識が列島内に一段と拡大・浸透する条件も形成されたと思われる。それならば琉球王国の統治領域において、琉球意識はどの程度拡大・浸透し得たのか、やや立ち入って検討しよう。
二、王国の道の島・先島支配と琉球意識
道の島や先島の首長たちが沖縄本島の政治勢力と接触したのは13、4世紀に遡る。記録によれば、1266年に英祖王のもとへ朝貢した奄美大島の首長も、1390年に中山王へ朝貢した宮古・八重山の首長たちも、最初から自主的に「朝貢」して政治的従属関係に入ることを希望したかのようにいうけれども、これは近世期の琉球型中華思想にもとづく記述であって、この段階ではいわゆる首長制社会の対等な交易関係であったと解すべきであろう。
ただ、ここで注目したいことは、最初の政治的接触において、相互に言葉が通じず直接の意思疎通ができなかったという事実である。大島の「北夷」は「重訳」して、つまり通訳を通じて意思疎通を図ったが、宮古・八重山の首長たちが中山王と接触した当初の状況についても、次のように伝えられている。「昔大明の洪武年間、与那覇勢頭豊見親といふ人、宮古島の主長たりし時、(中略)船を艤し艮の方を望みて出航す。諸神擁護して順風意の如く翌日中山に到る。然れども言語通せず只手を振って心中を訟ふるのみ。中山王察度深くこれを憐れみ、寓居を泊村に賜い居ること三年にして言語初めて通ず。(中略)当地はもとより八重山島と唇歯の好みあり、是に因りて洪武23年(1390年)庚午、彼の島の酋長等を導きて、相共に方物を捧げ中山に朝見す云々」(『宮古旧記』)と。
13、4世紀には琉球列島内の沖縄本島と道の島・先島の間でさえ、地理的・言語的条件等に阻まれて互いに意志疎通できないほどの懸隔が生じていたわけで、道の島や先島では独自の言語圏を基礎に独自の首長制社会を形成しはじめていたことが窺われる。しかし、15世紀に入ると、沖縄本島を基盤として形成された琉球王国は道の島や先島の政治的従属化を志向しはじめる。たとえば、15世紀前半の築造とされる座喜味城は「国中並びに鬼界・大島抔寄夫にて作立て」られたと言われるように(『毛氏元祖由来伝』)、道の島の人々も琉球王国の支配下に組み入れられつつあった。むろん、政治的従属化の過程において道の島の人々は頑強に抵抗した。『中山世譜』巻5には「奇界島は畔して朝せず、連年兵を発し、屡々征するも功なし。王怒りて曰く、ただに功なきのみならず、反って侮辱せらる。吾宜しく親ら軍兵を領いて以て賊乱を平らぐべし、と。」云々とあって、第一尚王朝の尚徳王が自ら奇界島を「征討」したのは成化2(1466)年のこととされる。この年「大島・徳島・鬼界島・与論島・永良部島の年貢等を掌る」泊里主が置かれ(『琉球国由来記』巻2)、道の島全体が琉球王国の領域に組み込まれたけれども、道の島の人々の抵抗はなお持続したようで、第二尚王朝の尚真王・尚清王代にも奄美大島を「征討」したという。この間の事情については、『おもろさうし』にも「おぎやか思いに/笠利 討ちちへ みおやせ」とか「喜界 大みや/直地 成るへ みおやせ」などと詠われている。
かくて、道の島は名実ともに琉球王国へ組み込まれ、「世之主のような琉球の血縁者や地元の豪族が大親に任命されるとともに、各島に首里の聞得大君からノロが任命され、トウール墓、琉旋法民謡や舞踊、蛇皮線、琉球焼など、各種の琉球文化が奄美文化に深い影響を与えた」といわれる(長澤和俊「南島文化論」『ヤポネシア序説』)。国王の血縁者を送り込む直接支配とともに、地元の豪族=首長を通じた間接支配の方式も採られたにせよ、「那覇世」と称される琉球王国の支配の時代に、琉球文化の強い影響を受けた道の島の人々が琉球意識を自己意識として受け容れる条件は拡大したものと思われる。
先島(宮古・八重山)が琉球王国の領域に組み込まれる過程においても、ほぼ同様の事態が現出している。15世紀後半、宮古諸島と八重山諸島には各々独自の首長制社会が形成されつつあったものの、宮古の首長(仲宗根豊見親)は逸早く琉球王国の配下へ入り、王国の後援を受けて八重山の政治的統一過程へ介入した。八重山の最も有力な首長(オヤケアカハチ)の「反乱」を鎮圧するという名目で、王国軍と宮古軍からなる連合軍が八重山へ「遠征」したのは1500年のことである(『中山世譜』巻6)。これ以後、八重山は琉球王国の領域に組み込まれ、宮古もまた次第に政治的自立性を喪失することとなる。
琉球王国は遠征の後、暫くの間、宮古の首長の一族に八重山の戦後処理を委任したが、一族の真列金豊見親は「自恣」「暴虐」で八重山人民を心服させることができないとの理由でまもなく免職され、「故郷に撤回」されている(『球陽』巻3)。これを契機に王国は宮古の従属化を強めるとともに、八重山へも満挽与人と称する役人を送り込み、直接統治を試みた。しかし、外来者の支配に対する八重山民衆の抵抗はなお続いたようで、満挽与人もまもなく引き上げられる。直接統治に失敗した琉球王国は、八重山民衆の抵抗を緩和するために、「遠征」の際に首里へ連行した竹富島の西塘を帰郷させ、武富首里大屋子の職位を与えて八重山統治に当たらせることにした(『琉球国由来記』巻21等)。
首里に滞在中石工として名声を博していた西塘は、王国支配層の期待を担って帰郷するや、竹富島に蔵元を創建し、行政機構の整備に着手した。まもなく八重山「諸島の酋長は尽く竹富島に赴き、もって法令を聴く」ようになったので、西塘はその配下の「酋長」=村役人たちを指揮監督しつつ、八重山の「琉球化」を推進するための政治的・経済的条件を確立したと思われる。とはいえ、八重山民衆の王国への反感は全く払拭されたわけではなかったから、沖縄本島と八重山の結合を強めるための精神的措置も必要であった。かくて、新たな信仰上の対象を創出する必要に迫られた西塘は、竹富島の国仲御嶽に首里の園比屋武御嶽の神を勧請して祭ることとし、毎年「正月朔日・十五日・冬至ニ、諸役人相集」り、「悪鬼納ガナシ(琉球国王)」の長寿と王国の安泰を祈るよう義務づけた(『琉球国由来記』巻21)。国仲御嶽こそは八重山の役人層の琉球意識を醸成する聖域であり、八重山の「琉球化」を推進するセンターであったといえる(拙稿「西塘考」『琉球大学教育学部紀要』32集)
要するに、15世紀の後半から17世紀初頭までの1世紀余の期間、琉球王国は道の島から先島に至る琉球列島全体を領域に組み込み、行政制度や宗教制度を整備し、官僚機構を確立することによって都出氏のいう成熟国家の段階に入ったわけであるが(「国家形成の諸段階」『歴史評論』551号参照)、この間に琉球意識が王国の統治機構に吸収された列島内の各共同体の首長レベルまで拡大・浸透し、一つの自立した国家のもとで政治的・経済的・文化的共同体意識として定着しつつあったことに注目すべきであろう。では、この時代すなわち古琉球時代の琉球意識は薩摩の琉球侵攻以後どのように変化したのであろうか。
Ⅲ 「両属」下の琉球王国とその周縁の自己意識
一、日琉・中琉関係と王国支配層の琉球意識
1609年の薩摩(島津氏)の琉球侵攻を契機に、琉球王国も日本型華夷秩序の一環に組み込まれたことは周知の通りであるが、その後の2世紀半にわたる近世期の日琉関係の特徴は次の点に要約されるであろう。
①島津氏の琉球侵攻事件以後、江戸幕府は琉球を島津氏の領分として認めながらも、明国の要求を考慮しつつ対明講和交渉の窓口として琉球王国体制を存続させたこと(紙屋敦之『幕藩制国家の琉球支配』等)、
②対明講和交渉の失敗と琉球・明国関係の正常化=国王尚豊の冊封(1633年)を経て、幕府は島津氏の領地判物へ琉球石高を明記し、島津氏を通じて琉球を幕藩制的知行体系へ編入するとともに、琉球使節の江戸上りを制度化することによって、近世琉球の「異国」化を推進したこと(荒野泰典『近世日本と東アジア』等)、
③明国から清国への交替の時期に、琉球の領有権を公然と主張して対清開戦を覚悟するのか、従来の明国・琉球関係と同様の関係を容認するのかという二者択一を迫られた幕府は、対清開戦の危機回避の必要性と琉球の要望を考慮し、日琉関係の隠蔽を前提として後者の方針を選択したものの、万一の場合には琉球を切り捨て可能な「異国」として位置づけ、琉球問題の処理を薩摩藩に一任したこと(上原兼善「琉球の支配」『講座日本近世史二 鎖国』等)、
④幕藩体制内の各藩とは異なる「異国」として位置づけられた琉球王国は、幕府や薩摩藩の裁判体系の枠外で独自に裁判権を行使し、薩摩藩が裁判権に介入した場合にも極力抵抗して主体性の確保に努め、他方では清国との宗属関係によって独自の国家体制を保証されたこと(菊山正明「琉球王国の法的・政治的地位」『沖縄歴史研究』11号等)、
⑤近世期の琉球は日本市場と中国市場を結ぶ貿易ルートの一つに位置づけられたが、琉球の中国貿易や糖業経営は日本市場を前提として成立し、琉球内で消費される必需物資さえも日本市場からの輸入に依存したことによって、琉球経済は日本経済の一環に従属的に包摂され、構造的に定置されたこと(安良城盛昭「琉球・沖縄と天皇・≪天皇制>」『琉球・沖縄―その歴史と日本史像』、荒野・前掲書)、これである。
要するに、薩摩侵攻以後の琉球王国は幕藩制国家の中に組み込まれ、政治的・経済的に包摂されながらも、明・清王朝との宗属関係にある「異国」として位置づけられたことを確認し得る。薩摩の琉球侵攻が琉球王国の幕藩制日本への政治的経済的従属を決定的にした重要な画期点であったことについては、すでに研究者の共通認識となっていると言ってよいであろう。けれども、16世紀後半以降「自立の経済的地盤」を喪失しつつあった琉球王国に対する薩摩の侵攻が「琉球王国の自立の喪失を、最後的に仕上げ」「『琉球民族体』から日本民族への転換に大きな機能をはたしている」(藤間・前掲書)といえるのかどうかという点については、議論の余地があるように思われる。
確かに、薩摩藩の琉球侵攻以後、いわゆる「琉球民族体」の幕藩制日本への従属意識は強まったものの、それは他方で王国体制の存続とそれを支える琉球・明国間あるいは琉球・清国間の冊封進貢関係の継続によって相対化され、近世期全体を通じて存続した「琉球民族体」は両属意識のバランスの上に、自立意識=琉球意識を確立したことも確認すべきであろう(拙稿「前近代琉球の自己意識と国際意識」『地域からの国際交流』参照)。
琉球王国の自立化=主体性回復への志向は清国の展海令をテコとして漂流民を直接福州へ移送し、幕藩制日本の送還体制から離脱したことにも示されており(豊見山和行「近世琉球の外交と社会」『歴史学研究』586号)、あるいはまた17世紀後半から18世紀前半にかけての自国史の編纂事業の推進(『中山世鑑』『中山世譜』『琉球国由来記』『琉球国旧記』『球陽』『歴代宝案』等)にも反映されている。『中山世譜』を編纂した琉球の政治家蔡温が「国の国たるや、容貌言語、衣服礼服等の類、各々能く処に随て宜きを取る、…而して諸国の斉しからざる所なり。必ず之を斉しくせんと欲するは愚の至りなり」(蔡温『図治要伝』)と宣言し、琉球の独自性を強調したことに注目しておきたい。近世期を通じて、琉球王国の幕藩制日本への政治的経済的包摂は進展したにもかかわらず、琉球民族は解体されることなく存続し、従ってその自己意識=琉球意識はむしろ強化され定着したと言えるのである。
もっとも、王国支配層の自立意識=琉球意識は両属意識=事大意識と不可分の裏表の関係にあったことにも留意すべきであろう。17世紀の後半、向象賢(羽地朝秀)が「唐大和の暦用うべき由、申し達し」たり、「此の国(琉球国)、人の生まれ初めは、日本より渡りたる儀、疑い御座なく候」と日琉同祖論を展開しながら、他方では「琉球の儀、前代より唐へ往来商売仕り、着用雑具等に至るまで、相い続く躰候」と中国との関係の重要性を強調しているのも、その一例である(『羽地仕置』)。18世紀の前半、蔡温も「偏小の国力をもって唐・大和への御勤め」を果たさなければならない琉球の立場を強調しつつも(『独物語』)、「御国元(薩摩)の御下地(支配)に相い随い候以後、国中万事思し召しの通り相い達し」云々(『御教条』)と薩摩の支配を賛美し、他方では「唐は大国にて、…若し表奏咨文の内、よろしからざる儀これあり候ハバ、国土(国家)の御難題に相い係り」云々(『独物語』)と清国との外交関係に細心の注意を払っている。このような両属意識のバランスの上に、王国支配層の自己意識=琉球意識が定着したわけで、両属意識の強化は琉球意識の増幅とパラレルの関係にあったといえよう。かくて、近世期を通じて「両属」下の王国支配層の自己意識が琉球意識として定着・増幅したとすれば、道の島や先島の人々の自己意識は薩摩の琉球侵攻以後どのように変容したのであろうか。
二、道の島・先島の自己意識と琉球王国観
薩摩の琉球侵攻を契機に、与論島以北の道の島は薩摩の直轄支配のもとに置かれたものの、明国ついで清国に対する日琉関係の隠蔽策にもとづいて、対外的には依然として琉球王国の領域下にあるかのように偽装せざるを得なかったことは、周知の通りである。道の島を直轄するや、薩摩はまず古琉球時代に各島の首長層に浸透した琉球意識の排除にとりかかった。1613年、大島代官職を置いて年貢の徴収を開始した薩摩は、24年に道の島の役人が「冠簪衣服階品を本琉球(琉球王国)に受る事を禁制」し(『南島雑話』4)、1706年には道の島役人の系図や旧記類を取り上げて焼き捨て、32年には与人・横目等が琉装することさえも厳禁したという(伊波普猷「渡琉日記を紹介す」『全集』7巻)。
寛永元年の禁制の中には、「能呂久米年々印紙を本琉球官寮に請ることを止」める措置も含まれていたが、奄美大島のノロクモイ(能呂久米・神女)たちの抵抗が強く、享保以前までは「本琉球」へ赴き琉球国王に謁見してノロの辞令書を受け取ることを、薩摩も黙認せざるを得なかったようである(『南島雑話』4)。古琉球以来の琉球意識を排除して薩摩との精神的結び付きを強化するために、薩摩は積極的な方針をも打ち出したが、道の島の役人たちに「日本国中六十余洲大小神祇」に誓って薩摩藩への奉公・忠誠を義務づける起請文を読み上げさせたのも、その一環といえよう(『伊仙町誌』142頁)。
しかし、薩摩の琉球意識排除策はさほど成功しなかったようである。というのも、薩摩は他方で道の島を琉球王国の領域であるかのように偽装しなければならなかったから、琉球国王冊封のため清国から冊封使が渡来する度に、道の島から貢ぎ物を差し出し役人を派遣することを黙認せざるを得なかった。たとえば、1719(享保4)年「琉球国王尚敬様御即位、大清国ヨリ冠船勅使就御渡来、諸入目島々ヨリ被差渡候故、東間切与人義宝・西目指池安・面南和目指喜大知、宰領被仰付度」(『道之島代官記集成』217頁、以下『代官記』と略称)との要請を容認している。また、1838(天保9)年の尚育王の冊封の際には、沖之永良部島から貢ぎ物の運搬責任者として饒覇とその弟のノ葉(えつよう)らが派遣された外、他の島々からも貢ぎ物の運送人や観光客が多数那覇へ赴いたことを、伊波普猷はノ葉の『渡琉日記』をもとに詳細に紹介している(『全集』7巻)。冊封使の来琉は道の島と沖縄本島の人々の接触・交流の機会となり、双方の琉球意識を確認し合う場を提供したことに注目すべきであろう。那覇滞在中の饒覇やノ葉らは琉球役人の豊見城按司や板良敷里之子らと漢詩・琉歌・和歌の応酬を通じて深い親交を結んでいることから、冊封使の来琉を機会に道の島の役人たちの琉球意識は増幅されたものと思われる。
道の島の人々の琉球意識は台風などの災害時の救援米を通じて醸成される場合も少なくなかった。たとえば、1755(宝暦5)年の飢饉の際、「拝借米本琉球ヨリ両度ニテ五百石申請候、…御国許(薩摩)ヨリ御米三百石被下候得共、時分後ニ相成候」と報告されているように(『代官記』227頁)、災害・飢饉時には「本琉球」からの救援米に頼ることが多く、その後も62年、66年(180石)、73年(800石)、77年(500石)、81年、83年と災害の都度救援米が送られている。それが無償の救援米であったのかどうかは明らかでないけれども、「国許(薩摩)よりも『本琉球』に対する借入れ度数が多かった形跡のあるのは、…歴史的一体感があったからであり、自給米に余裕のない琉球であっても道之島は感情的には異国ではなかったのである」(宮城栄昌「本琉球と道之島との歴史的関係」『南島文化』創刊号)。
このような「歴史的一体感」すなわち琉球意識を背景として、圧制に堪えかねた人々が道の島から「本琉球」へ逃亡する事件も少なくなかったようで(『代官記』377頁)、1736(元文元)年には伊仙村の栄文仁らが「百姓多人数」を引き連れ、貢租の出米徴収の件で役人の不正を訴えるため、「本琉球」へ向けて出航する直前に連れ戻されるという事件が起こっていることに注目すべきであろう(『代官記』221頁)。琉球意識は道の島の民衆レベルまで浸透しつつあったことが窺われる。もっとも、薩摩は道の島を「本琉球」から切り離す方針を変えたわけではなく、六月灯や八月踊り、ヤマト民謡、芝居などを「政策的に相当強力に普及」させたから(長澤・前掲論文)、琉球意識の浸透には自ずから限界があったと思われる。しかし、19世紀の20年代においても、道の島の役人は次のような歴史認識を表明している。――「海南の中、吾か大島は、中山国の属島にして小琉球と称し、明朝萬暦のむかしは首里帝より命して、親方及親雲上なる人をしてこのしまの政要を執らしめ、在島の内出生の氏族七家繁栄して顕然たり、…倭の下知に従いしより、…万民一に帰し飢寒の労を忘れ太平の晨に遊びぬ」(『代官記』374頁)。
自らを「小琉球」と自覚し琉球王国を「本琉球」と意識する道の島役人たちの自己意識の底流には、古琉球以来の琉球意識が潜在し続けたように思われる。では、薩摩侵攻以後も琉球王国の領域に留まった先島(宮古・八重山)の場合はどうであろうか。
薩摩侵攻以前にあっては、琉球王国は先島の首長層を頭職以下の役人に任命して徴税等を委任する間接支配の方式を採ったが、薩摩侵攻以後、王国から直接首里在番を派遣して蔵元・番所の頭職以下の土着役人を監督させる統治方式へ転換した。その上、薩摩も大和在番を派遣して監督したから、先島は薩摩と王国の二重支配を受ける特別行政地域となる。かくて、先島の役人層は大和在番や首里在番を通じて大和文化や首里文化と接触する機会が増大し、また毎年の貢租運送などで王国の首都を訪れる機会も増大したことから、琉球文化への憧憬、王国との一体感を抱くようになり、琉球意識を自己意識として受容することにさほど違和感を感じなくなったと思われる。海運の発達にともない、物資や情報の移動・伝達が頻繁となったこともその傾向を助長したであろう。
しかし他方で、移住の禁止を前提とした人頭税制は、民衆の視野を村落共同体の外部へ拡大させる可能性を減じたから、民衆レベルの自己意識は複雑な様相を呈することとなる。王国や薩摩の政策が過酷・非情と受けとめられたことも、先島の民衆の自己意識に複雑な陰影を刻む要因であった。たとえば、王国の寄人政策(強制移住)によって1732年に黒島から石垣島の野底へ移住させられた若者が、故郷の恋人を慕って歌った「久場山越路節」の一節に、「黒島に居るけい/先島に居るけい/島一つやりをり/里一つやりをり(中略)別れ欲しや無いぬその/ぬき欲しやこれ無いぬその/沖縄から美声/美御前から御差図/島別れで言うられ/国別れで言うられ(中略)」とあり、黒島・先島の外の「沖縄」に居る「美御前(国王)」の命令で強制的に移住させられたことに対する怨念が詠い込まれている。沖縄=琉球の国王を圧制者として告発する八重山民衆が琉球意識を自己意識として受容するには、まだかなりの距離があったというべきであろう。
先島社会における士族と平民の対立構造も各々の自己意識に複雑な陰影を刻む要因の一つであった。19世紀も後半を過ぎると、先島の士族(役人)と平民との対立は顕著となり、平民の抗租運動が頻発する。宮古諸島では人頭税の割り増し徴収をめぐって、1848年以来数年間、民衆の蜂起寸前の事態が繰り返され、1855年には多良間島の「蒲戸砂川等五名、小舟に坐駕して内地(首里)に到来し」島役人たちの不正を訴えたため、王国から直接査察官が派遣され島役人を詰問処罰するという事件が起こっている(『球陽』原文編513頁)。平民の砂川等が「性命を惜しまず、跋渉して」王国政府へ直訴したのは、王国に対する期待感があったからであろう。その限りで、砂川等は琉球意識を共有し得たものと思われる。
ところが、人頭税の割り増し徴収事件で免職された下級役人の波平景教は、1860年に薩摩の出先機関=在番奉行へ王国政府の悪政を非難し救済を訴える次のような嘆願文を投書している。――「一、琉球は小国にして、大国の間に介在し、諸政行ひ難く、(中略)偏に大国に帰趨附庸の急なる覚ゆる也。一、当島(宮古島)は往古自立の政を行ひ来りしものにて、与那覇勢頭、中山に服属の途を講ぜしより、其の属領となりしも、用語と云ひ、先祖の由来と云ひ、寧ろ大和に近きものなれば、下々の者皆大和を以て親国と云ひ、これに帰するを喜ばずと云ふ者あらざる也」(慶世村恒任『宮古史伝』229頁以下)と。波平の内面には、大国の間に介在する小国の琉球への帰属意識=琉球意識と、宮古島の「自立」時代への復帰願望=自立意識と、王国の「属領」より「大和」への「附庸」を希望する事大意識が混在していることに注目すべきであろう。先島の役人層や民衆の琉球意識は、19世紀後半の時点でも、定着しているとはいえず、なお流動的な状態であったのである。
以上、要するに、薩摩の琉球侵攻から2世紀半の「両属」期=近世期に、王国支配層の琉球意識は消滅へ向かうどころか定着・増幅し、道の島や先島の役人層をはじめ民衆へも琉球意識は浸透しつつあったものの、琉球列島全域の各階層に共有され得るような単一の運命共同体的自己意識として定着するには至らないまま。未曾有の民族的危機=琉球処分に直面せざるを得なかったといえる。民族的危機のなかで、琉球意識はどのように機能し、どのように変容するのかが次の問題である。
Ⅳ 琉球処分期の救国運動と琉球意識
一、道の島返還要求と救国運動の意義
「両属」下の270年間に定着した琉球民族の自己意識=琉球意識は、琉球処分の時期に最も鮮明に表出される。1872年の「琉球藩」への格下げは琉球処分の開始を意味したけれども、薩摩藩(鹿児島県)の管轄から明治政府の直轄へ変わるだけのことと理解した王国支配層には、まだ存亡の危機として意識されることはなく、むしろ薩摩藩の管轄から「解放」されるという期待感をもって受けとめられた形跡がある。たとえば、琉球国の慶賀使として上京した伊江王子らは明治政府の副島外務卿へ次の二点を要求している。第一に、琉球は薩摩の支配下に入って以来「その賦税の重斂に堪へず、国民疲弊」しているので、「天朝(明治政府)の直轄となりたる以上は、特恩を垂れ」租税を軽くして貰いたいということ、第二に、「大島・徳之島・喜界島・与論島・永良部島は固より我琉球の隷属」であったのに、慶長年間に薩摩に「押領」されたのであるから、この際返還して頂きたいということ、これである(喜舎場朝賢『琉球見聞録』)。第一の減税要求において「琉球国民」の疲弊の原因が薩摩支配にあることを告発しているのは、「琉球国民」意識をベースとした王国支配層の歴史意識の表明として注目すべきであろう。第二の道の島返還要求についていえば、薩摩の琉球侵攻によって奪取された道の島も本来琉球王国の領域であるという潜在意識が、薩摩の管轄を離れた途端に顕在化したことを示しており、王国支配層の自己意識=琉球意識のなかには道の島も包括されていたことを確認し得る。古琉球時代への強烈な復帰願望を、時代錯誤の迷夢として一蹴するわけにはいかなかった副島外務卿は「同僚の協議を経て宜しく琉球の為めに処置すべし」と応えて期待感が抱かせたが、周知のように、王国支配層の期待は完全に裏切られたばかりでなく、まもなく廃琉置県への動きが加速化する。
1875年、明治政府が清国・琉球間の進貢・冊封停止を命ずるや、王国支配層は存亡の危機を感じ取り、救国運動を開始した。国王から藩王へ格下げされた尚泰は「皇国(日本)・支那(清国)の御恩」に感謝し、両国を「父母の国」と仰ぎ奉っていると称して、日清「両属」の現状維持を要請した(『琉球見聞録』25頁)。しかし、現状維持が困難となる情勢のなかで、自らの「国家」維持の方策を模索した王国支配層は日本・琉球・清国の各地で救国運動を展開する(拙稿「琉球救国運動と日本・清国」『沖縄文化研究』13号参照)。
救国運動の展開過程で、王国支配層は自己意識=琉球意識をより一層強調した。たとえば、79年4月の廃琉置県直後、琉球士族層の総意を結集して松田処分官へ提出された請願書の中では、「当藩(琉球)ハ自ラ開闢シ、素ヨリ君主ノ権ヲ有シ、御内地旧藩トハ相替リ候処、廃藩被仰付候テハ、君臣ノ名義相廃リ、仮令万民身上ハ如何程御撫恤ヲ蒙リ候共、何共安着不罷成、憂心焚ルガ如ク」云々と強調されている(『琉球処分』224頁)。要するに、独自の歴史を歩み日本の各藩とは異なる主権国家を維持してきたという強烈な自己意識=琉球意識に立脚して、廃琉置県反対の意思を表明しているのである。また松田処分官に協力した親日派下級士族の「探訪人」たち(大湾・松島・久高等)でさえ、「国家の危難」を救うための琉球国王の「保国の神策」に期待していることに注目すべきであろう(『琉球見聞録』142頁)。
廃琉置県を契機に、琉球内部では一時期農村の地方役人層まで新県政反対運動=救国運動へ参加する情勢となり、宮古島では血判誓約書にもとづく県政ボイコット運動が県政加担者の殺害事件(サンシー事件)へ発展したことは周知の通りである。明治政府=沖縄県当局の弾圧によって琉球内部の救国運動は表面上沈静化したけれども、清国への亡命・請願運動はなお執拗に繰り返された(前掲・拙稿参照)。とりわけ、日清両国の間で、沖縄本島以北を日本へ、先島を清国へ属させる琉球分割条約が妥結した1880年前後に、琉球から清国への政治亡命者が急増し、清国内では亡命琉球人の分割反対運動が広範に展開されている。たとえば、天津では向徳宏(幸地朝常)が李鴻章に分割反対を泣訴し、北京では毛精長・林世功・蔡大鼎が連名で80年9月18日付の請願書を総理衙門へ提出し、「敝国(琉球国)内に三府あり、…外に三十六島あり。その中、八島は業に前明の萬暦年間に倭の占去を被る。…夫れ三府二十八島を以て国を立つること尚お難し。況や国土を割き島を分かてば、将た又何を以てか国を立てん。既に以て国を立つるに足らざれば、名は存国と曰うと雖も、何ぞ亡国に異なるあらんや」(拙編『琉球救国請願書集成』)と訴え、断固たる分割反対の意思を示していることに注目すべきであろう。
日清両国は琉球側の反対を無視して80年10月21日琉球分割条約を妥結するが、亡命琉球人の激しい抵抗、とりわけ林世功の抗議自決に衝撃を受けた清国政府は遂に条約の調印を見送り、辛うじて琉球分割の危機は回避される(拙稿「琉臣殉義事件考」『球陽論叢』参照)。とはいえ、80年代を通じて日清両国は琉球問題決着の一手段として琉球分割案の実現を繰り返し志向し続けた。琉球分割の試みをその都度阻止したのは亡命琉球人たちの執拗な反対運動に外ならなかったのである(拙稿「清国(洋務派)の対日外交と琉球問題」)。従って、80年代の救国運動は琉球分割反対運動としての歴史的意義を帯びていたというべきであろう。
80年代の琉球士族層の前には、①全島返還か、②分割案の受諾か、③廃琉置県の黙認か、以上三つの選択肢が提示されていたけれども、亡命琉球人たちが自ら同意すれば実現する可能性の高かった②の琉球分割案の受諾を拒否し、最も困難で実現性の少ない①の全島返還に固執したのは何故であろうか。清国政府当局への請願書のなかで、道の島から先島に至る琉球列島全体を琉球国の固有の領域として絶えず確認していることからも窺われるように、琉球士族層は「琉球」の国家・民族としての一体性、不可分性を強く意識していたのであって、それ故に琉球分割案には最後まで抵抗せざるを得なかったのである。琉球士族層が自らの階級的利害よりも琉球民族総体の利害を優先させたことに留意しておきたい。もっとも、この時期の琉球士族層の自己意識=琉球意識のなかに道の島や先島がどのように位置づけられていたのか、また先島士族の自己意識=琉球意識が琉球処分のなかでどのように変容するのか、という問題は別に検討されなければならない。
二、先島士族の救国運動と琉球意識
日清両国の水面下の外交交渉によって琉球分割条約調印の可能性が最も高まったのは1882年の前半であるが(前掲・拙稿参照)、再度分割の危機に直面した琉球内の士族層は協議して「必ず全島を取戻されんことを嘆願すべしと決定し」(『琉球見聞録』)、毛鳳来(富川盛奎)を清国へ派遣する。毛鳳来は途中宮古・八重山へ立ち寄り、先島士族たちと分割条約への対応を協議しているが、八重山では10年前に公務で知り合った憲英演(神村英演)と再会し、救国運動への参加を呼びかけたものと思われる。八重山士族たちは翌83年6月、協議して憲英演らを福州へ派遣し、琉球救国=全島返還を訴えさせた。当時、毛鳳来はすでに北京滞在中で、福州における救国運動のリーダーは向徳宏(幸地朝常)であったから、憲英演らは八重山士族の要請を福建当局へ取り次ぐよう向徳宏へ依頼した。かくて、向徳宏は83年7月30日、請願書を提出して次のように言う。
「琉球国の陳情陪臣紫巾官向徳宏等、…国を回復せしむるを賜わらんことを泣懇せんが事の為にす。窃に、本月初八日、敝国(琉球国)に属するの八重山島の官吏憲英演、土小船に坐駕し、飾りて漂風の為めとして■[ビン=モンガマエ・ムシ]に来る。…念いめぐらさんことを乞う。敝国、前明の洪武五年の間に、誠を輸して中国へ入貢せり。八重山・太平(宮古)の両島もまた、王化を慕いて敝国に貢入し、久しく敝国の管轄と為れば、即ち共に天朝の覆■(保護)の中にあり。…茲に以えらく、僻処の島の官吏、君民の日本の毒楚に逢うを痛念し、目撃心傷したれば、奮発して■[ビン]に来たれり。並びに聞く、太平山島の官吏、日ならずしてまた将に?に来たらんとす、その余の各属島も均しく日本に屈服せず、と。上は内地(沖縄本島)より下は外島(先島)に至るまで、…仰ぎて天朝(清国)の日本を征し琉球を救うを望むこと、大旱に雨を望むより切なり」と(拙編『琉球救国請願書集成』)。
ここで注目すべきことは、まず第一に日本の「毒楚」=廃琉置県に憤慨して琉球国の回復を要請するために、八重山の官吏憲英演らが福州へ亡命しただけでなく、宮古島の官吏もまもなく亡命して来るという情報を福建当局へ伝えていることである。事実、まもなく宮古島官吏の白川恵伊外9名が海賊の掠奪を受けたと称して漂流を装い、福州へ到着している(拙稿「清代光緒年間の琉球国難民漂着事件について」)。琉球分割条約において清国への割譲対象となっていた先島の士族たちも自主的・主体的に救国運動=分割反対運動へ参加する動きを示していたのである。第二に注目すべきことは、首里士族の向徳宏らが「敝国(琉球)に属するの八重山島の官吏」といい、あるいは「八重山・太平の両島もまた、王化を慕いて敝国に貢入し」云々と説明しているように、琉球型中華思想にもとづいて先島を属島・外島と位置づけていることであろう。琉球士族層の自己意識において、先島はなお周縁的位置に留まっていたのである。もっとも、救国運動の過程で、両者の運命共同体的一体感は強化される。その典型的な事例を紹介しておきたい。
八重山官吏の憲英演らが福州へ亡命する1年前に、同じ八重山の下級官吏梅孫著(竹原孫著)ら32名を載せた城間船が台風に遭遇して浙江省へ漂着し、福州へ送り届けられている(竹原孫恭『城間船中国漂流顛末』)。梅孫著は文字通り遭風難民であったが、福州の琉球館に滞在した9ヶ月間、救国運動の指導者向徳宏らと寝食を共にして思想的に強い影響を受け、琉球分割の危機的状況の中で救国運動へ参加する決意を固めたといわれる。上級官吏の憲英演らが亡命してきたことも梅孫著の決意を強めたであろう。琉球内部で救国運動に従事する使命を帯びて福州を出発するに当たり、梅孫著は向徳宏・馬必達(国頭必達)らと次のような琉歌や漢詩を贈答している(竹原・前掲書106頁以下参照)。
向徳宏の贈歌「たち別る袖にことの花つつて 浮縄から八重山匂い移す」(いま、たもとを別つが、別れにあたって、その袖に<ことの花>を包んで持ち帰り、沖縄本島から八重山まで、その花の匂いを流し伝えて徹底させてくれ)
梅孫著の返歌「拝もことの花肝に染つつて 菊の花匂ひ移しあげら」(承った<ことの花>を心に深く刻み、染め包んで持ち帰り、この目出度い菊の花の薫りを、きっと、沖縄本島から八重山まで流し伝えましょう)
漢詩や琉歌の贈答を通じて琉球意識を覚醒させられた梅孫著は、帰国後の救国運動の宣伝文書として活用するために、向徳宏らが福建当局へ提出した請願書をも丁寧に筆写している。帰国後、梅孫著は向徳宏らから与えられた任務を果たすべく、暫く沖縄本島に留まり、首里・那覇の士族層(御殿・殿内)と接触して向徳宏らの救国運動の状況を伝えたり、八重山の役人たちへ救国運動への参加を呼びかける書簡を発送するなど、懸命の努力を傾注した。ここに、八重山士族が「琉球」との一体化を自覚し、琉球意識を自己意識として定着させるプロセスを伺うことができる。
しかし、梅孫著の場合は民族的危機意識に促迫された特異な事例であり、民衆のレベルではまだ「琉球」と「先島」の間の溝は埋め尽くされたわけではなかった。しかも廃琉置県後の事態はもはや挽回し難い段階へ進んでおり、梅孫著の努力は何の成果ももたらさず、琉球士族層を救国運動へ結集することさえ困難となりつつあった。最後の国王尚泰自身が明治政府への恭順を呼びかけていたからである。とはいえ、琉球内の救国運動の指導者の一人・津嘉山親方などは「仮令、君ノ命ナレハトテ、国家ノ為メニハ従ハサル事モアルモノナリ」(『沖縄県史』15、377頁)と主張し、なお救国運動を継続したことに注目すべきであろう。
Ⅴ 結びに代えて――琉球王国の滅亡と琉球民族の「蘇生」――
日清「両属」下の270年間に琉球経済が日本経済に従属的に「包摂」され、「日本」と「琉球」の経済的「一本化」が進行したにもかかわらず、廃琉置県を契機として琉球民族の内部から自主的・主体的に「日本民族への転化」を促進する動きは表面化せず、むしろ逆に強烈な琉球意識をベースにした救国運動が展開されたことを、どのように理解すべきであろうか。いわゆる「琉球民族体の日本民族への転化」が「完了」したと言えるのかどうかが当面の問題である。
むろん、廃琉置県すなわち琉球王国の滅亡には二つの側面がある。第一には「日本」と「琉球」の「統合」を促進し、両者の「一体化」の客観的基礎を強化する契機となったこと、第二に琉球の民意を配慮しない強権的措置が採られたことによって、「日本」と「琉球」の双方に歴史的に存在してきた自他意識を定着させたこと、これである(拙稿「近代沖縄の課題と差別問題」『論集・沖縄近代史』参照)。第一の側面の「統合」「一体化」の内容自体にも多くの検討すべき問題点が内包されているけれども、ここでは主として第二の側面に焦点を合わせつつ、近代以後の「日本」と「沖縄」の自他意識の特徴、とりわけ琉球意識の諸相を素描しておきたい。
琉球の民意を配慮しない強権的措置が、琉球側の自己意識を増幅させたことは前述の通りである。「日本」側では、明治政府の強権的措置を「国中一般の例に従って廃藩の命を下したるのみ」(福沢諭吉)と受け止めつつも、救国運動に奔走する琉球士族層を「頑迷固陋」と批判し、「琉奴伐つべし」と恫喝する論調がジャーナリズムを風靡した。もっとも、「日本」側の世論のなかにも、琉球分割論を痛烈に批判し、琉球の「衆心」が「独立自治」を欲するのであればその独立を承認すべしと主張した植木枝盛の琉球独立論があり、また「沖縄県民ハ我々ト同シク日本政府ノ治下ニ在ル良民ナレバ、即チ同胞兄弟ニシテ他国人ニ非ザルノ意ヲ記念シ、苟クモ交際上ニ奴隷是レ視ル等ノ事ナカランコト」を希望すると訴えて同胞意識を表明する論調もあったことに留意すべきであろう。(『近事評論』188号)
しかし、このように琉球の意思を配慮したり、あるいは同胞として受け容れようとする論調は大海の一粒であって、「日本」の民衆一般は「沖縄県民」を「頑迷固陋」の「亡国の民」とみなして劣等視した。たとえば、廃琉置県から10年後の明治21年、沖縄を旅行した「内地人」旅行者は「当節内地人ノ沖縄ニ入込ミ居ルモノ、凡ソ二千名ニ近シトノコトニテ、其内鹿児島県人十分ノ九ヲ占メ、余ハ大抵京阪地方ノ落武者ナル由。当地ニテ内地人ノ威張ル有様ハ、丁度欧米人ノ日本ニ来テ威張ルト同シ釣合ニテ、利ノアル仕事ハ総テ内地人ノ手ニ入リ、引合ハサル役廻リハ常ニ土人ニ帰シ、内地人ハ殿様ニテ土人ハ下僕タリ、内地人ハ横柄ニシテ土人ハ謙遜ナリ、肝心ノ表通リハ内地人ノ商店ニテ、場末ノ窮巷ハ土人ノ住居ナリ、内地人ハ強ク土人ハ弱ク、内地人ハ富ミ土人ハ貧シ」と指摘しつつ、このような状況を「優勝劣敗ノ結果ニテ、如何トモスヘカラサル訳ナレドモ、亡国ノ民ホドツマラヌモノハナシ」と、肯定的に受けとめている(「琉球見聞雑記」『沖縄県史』14)。
廃琉置県から沖縄戦に至る66年の近代史を通じて、「日本」側の自他意識が「内地人」の「土人」に対する優越意識として表出したことによって、「琉球」側の自他意識は「沖縄人(ウチナンチュ)」の「大和人(ヤマトンチュ)」に対する劣等意識として定着せざるを得なかった。沖縄の内部からこのような自他意識を克服する努力が始まったのは日清戦争前後からである。明治政府=沖縄県当局の強力な「皇民化教育」政策が起点となったものの、日清戦争前後には東京留学から帰った謝花昇や太田朝敷らが「日本民族への転化」の先導役を果たした。しかし、謝花は県政を私物化する奈良原知事との対決に敗れて以後、「大和人」の沖縄支配を呪いつつ不遇のまま短い人生を終え、太田もまたオピニオンリーダーとして「日本」への「同化」を強力に推進しつつも、政府や「日本人」の沖縄差別を糾弾して止まなかった。
日清戦争、日露戦争を経て、徹底的な「皇民化教育」の推進により琉球の歴史や文化が排除されていく状況の下で、かつて琉球分割条約に抗議して自決した林世功の33回忌が沖縄のジャーナリズムで大々的に取り上げられたのは、「皇民」意識に覆われながらも、琉球意識がなお沖縄の人々を捉え続けた証であると言えよう。たとえば、「沖縄毎日新聞」や「琉球新報」は1913(大正2)年の11月、「林氏の祭典は同情者多し」などの見出しで数回にわたって林世功関連記事を特集し、「故林世功追悼詩文集」などを掲載している。追悼詩文集のなかの「国のため身をつくしたるかひなきも よのいさをてふ名はくちせし」(兼島景福、沖縄毎日、11月20日)という一句などは、林世功の自決を悼む琉球民族のレクイエムというべきであろう。
この時期、沖縄学の創造に意欲を燃やしつつあった伊波普猷や東恩納寛惇らも、一方で林世功の政治的選択の誤りを批判しつつ、他方で琉球民族の存亡を賭けた林の決死の行動に哀悼の意を表している。日琉同祖論の立場から琉球処分を肯定的に評価していた伊波普猷や東恩納寛惇にしても、「皇民化教育」によって押し潰されようとする琉球の歴史と文化を研究の対象とすることによって、自らの内面に琉球意識を保持し続け、琉球民族の運命に無関心ではいられなかった。「琉球人の祖先に就いて」という論文を発表して以来、琉球・沖縄史における「民族」の問題に執着し続けた伊波は、「琉球処分の結果所謂琉球王国は滅亡したが、琉球民族は日本帝国の中に這入って復活した」(『全集』第1巻、493頁)とか、「所謂琉球王国は滅亡したが、瀕死の沖縄民族は日本帝国の中に這入って、蘇生した」(『全集』第2巻、439頁)と繰り返し強調している。
伊波の強調する「琉球民族」もしくは「沖縄民族」という概念の中の「民族」とは、現在の民族学で提起されているエスニシティ、あるいは藤間生大氏の提起している「琉球民族体」に近い概念と考えてよいであろう。とすれば、琉球王国は滅亡しても琉球エスニシティあるいは「琉球民族体」は消滅せず生き残ったという理解も可能であり、藤間氏流に言い換えれば、「琉球民族から琉球民族体への転換」ということになる。国家を形成していた琉球民族が国家滅亡後も「日本帝国」という多民族国家のなかで一民族として兄弟民族たる大和民族と共生し得る(共生せざるを得ない)という認識を、伊波は生涯を通じて主張し続けたわけであるが、同時にまたその生涯の最後の著作『沖縄歴史物語』の結びにおいて「地球上で帝国主義が終りを告げる時、沖縄人は『にが世』から解放されて、『あま世』を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することが出来る」と強調していることも周知の通りである。第二次大戦の結果「日本帝国」は崩壊したが、沖縄戦から今日に至る現代史の中でも、帝国主義はなお猛威を振いつつあるという冷厳な現実を直視する時、琉球民族の過去・現在・将来を見据える伊波の視点は、現代史における「沖縄問題」を洞察するためのキーワードとして見直されるべきではなかろうか。とすれば、琉球処分を民族統一の「完了」とみなす二段階民族統一説を受け容れて、琉球=沖縄史における「民族」の問題は既に過去のものとなったというわけにはいかず、まさに今日及び将来の問題として存在し続けると言わざるを得ない。
(付記)1985年10月、浦添市民開館で開催された第36回地方史研究協議会大会において、安良城盛昭氏は沖縄と天皇制に関する興味深い報告を行われた。安良城報告に対して、私は二段階民族統一説の問題点を提起したが、時間の制約等もあって十分論議することができなかった。後に安良城報告を収録した論文集(『琉球・沖縄-その歴史と日本史像』)が刊行された際に、安良城氏は後注においてかなり詳細に私の問題提起を批判されている。安良城氏の批判には傾聴に値する点も少なくないが、私の問題提起の核心が把握されていないため、論点がかみ合っていない。従って、私はさらに論争の必要性を感じたものの、その機会を得ない内に、安良城氏は忽然と他界されてしまった。本稿は安良城氏の批判に触発されて構想された私の試論であるが、もはや安良城氏の再批判を頂くことができなくなったことに一抹の不安を覚える。しかし、常に安良城氏の厳しい批判を意識しつつ、今後も批判に堪え得る議論を続けたいと思う。学問的訓練の場を提供して頂いた安良城氏に感謝し、ご冥福を祈る。
参考文献
①『伊波普猷全集』第1巻、第2巻、第7巻。
②安良城盛昭『新・沖縄史論』(沖縄タイムス社)、『天皇制と地主制』下(塙書房)、『天皇・天皇制・百姓・沖縄』(吉川弘文館)。
③高良倉吉『琉球王国史の課題』(ひるぎ社)。
④藤間生大『近代東アジア世界の形成』(春秋社)。
⑤西里喜行「前近代琉球の自己意識と国際意識」(『地域からの国際交流』、研文出版)、「琉球救国運動と日本・清国」(『沖縄文化研究』13号、法政大学)。「清国(洋務派)の対日外交と琉球問題」(『琉球大学教育学部紀要』第45集)。
このページのトップにもどる
<風游・図書室>にもどる