(8/30)
サイクル理論
サイクルとは一定の間隔で定期的に生じる測定可能な現象である。
だが、それは必ずしも100%の規則性をもって起こる訳ではなく、一定の間隔で80%以上の確率で起こる。
例えば、「6週サイクル」という場合、それは毎回6週間ごとに起こる訳ではなく、
5〜7週サイクルが80%以上の確率で起こることをいう。
サイクルにはオーブ(許容範囲)と中心がある。
サイクルの中心とは、そのサイクルの平均的な時間の長さを言い、
オーブとは、そのサイクルの中心からの距離を言う。
一般的にサイクルのオーブはサイクルの中心の6分の1である。
したがって、「6週サイクル」は前後に1週のオーブがあるので、実際には5〜7週ということになる。
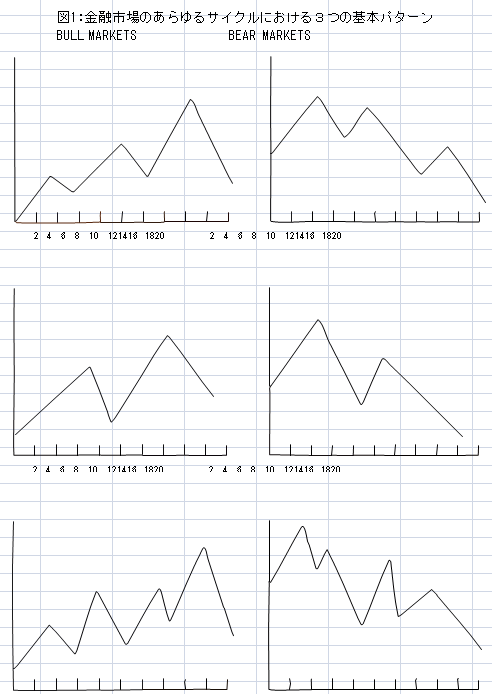
サイクルがオーブを含む時間帯の80%未満の状態で終了した時、「短縮」されたと言う。
短縮は通常、長期サイクルが終了する時に起こるが、
長期サイクルの中間地点でサイクルが短縮されることは希である。
また、オーブを含む正常な時間帯に入る前にサイクルの短縮が起こった場合、それは「歪み」と言う。
サイクルがオーブを含む正常の時間帯を超えて終了する時、サイクルが「延長」されたという。
サイクルの延長は長期サイクルの終了する時に延長される傾向があるが、「短縮」の場合ほど頻繁には起こらない。
長期サイクルの「支配性」は通常、短期サイクルを延長させるケースよりは短縮させるケースのほうが多い。
サイクルがオーブを含む正常な時間帯を超えて終了する時、それは短縮された時と同様、「歪み」と言う。
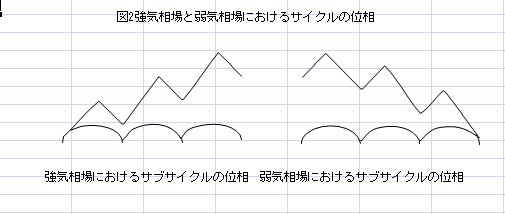
全てのサイクルはより小さなサイクルにより構成される。
18週サイクル(オーブを入れて15〜21週。プライマリーサイクルと呼ばれる。)
には通常、3個ないし4個の「6週サイクル」が入っている。
どのサイクルもより大きなサイクルの一部であり、例えば、
3個ないし4個のプライマリーサイクルが50週サイクル(38〜62週)を構成する。
強気サイクル(上昇トレンド)の場合、最安値はサイクルの開始時につける。
また、サイクルの最高値は通常サイクルの中間地点を過ぎてから出現する。
即ち、サイクルの中で相場が上昇する期間が長く、下降期間が短い。
サイクルの最高値がサイクルの中間地点を過ぎてから出現することを
「ライト・トランスレーション」と言い、強気相場の特徴である。
弱気サイクル(下降トレンド)の場合、最安値はサイクルの終了時につける。
また、サイクルの安値と安値の間に出現する最高値(天井)は、サイクルの前半部分に出現する傾向にある。
この場合、相場は上昇する期間よりも下降する期間が長い。
これは「レフト・トランスレーション」と呼ばれ、弱気サイクルの特徴である。
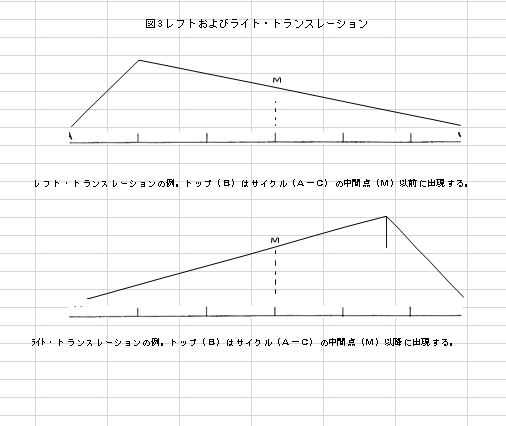
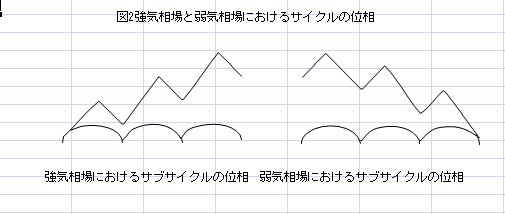
同じ長さのサイクルは、より大きいサイクルが支配性を発揮するまでは同じ特徴を持っている。
大きいサイクルが支配性を発揮すると、それまで規則正しく繰り返されていた小さいサイクルに歪みを与える。
歪みは強気相場では大きいサイクルの終末の位相で起こり、
弱気サイクルでは大きいサイクルの初期の位相で起こる。
サイクルは呼吸のように間隔が長くなったり、短くなったりするので、
一定の規則正しい間隔で繰り返し起こる訳ではない。
以下に、いくつかの商品の平均的なサイクル(プライマリーサイクル)の長さとオーブを週単位で記す。
米国株式指数 17(13〜21)
日本株式 16(13〜19)
金 18(15〜21)
銀 17(13〜21)
銅 18(15〜21)
穀物 17(13〜21)
Tボンド 23(18〜28)
スイスフラン/米ドル 26(21〜34)
独マルク/米ドル 26(21〜34)
米ドル/日本円 33(26〜40)
代表的な長期優越サイクルには下記のようなものがある。
各長期サイクルはそのサイクルよりも短い長期サイクル、
あるいは少なくともプライマリーサイクルの倍数により構成される。
米株式指数 50週(38〜62週)
米株式指数 4年(42〜54ヵ月)
米株式指数 8年(7〜10年)
米株式指数 20年(17〜21年)
米株式指数 54年(45〜63年)
日本株式 54週(10〜15ヵ月)
金 48週(42〜54週)
金 118週(102〜124週)
金 4.25年(42〜60ヵ月)
金 8.5年(7.5〜10年)
米ドル/円 14.45ヵ月(11〜20ヵ月)
米ドル/円 20.56ヵ月(15〜29ヵ月)
米ドル/円 64ヵ月(60〜68ヵ月)
穀物 4.5年(3.5〜5.5年)
穀物 9.25年(8〜10年)
穀物 18.5年(16〜20年)
長期サイクルが終了する時には、含有する短いサイクルに対し支配性を発揮し、
プライマリーサイクルのパターンと長さに歪みが生じる。
もし長期サイクルがトレンドを示した場合、次に続く同じタイプの長期サイクルも、
それより大きなサイクルのボトム(終了)が同時期に到来しない限り、同じトレンドを継続する可能性が高い。
プライマリーサイクルより短いサイクルを短期サイクルという。
中でも、「ハーフプライマリーサイクル」、「メジャーサイクル」、「トレーディングサイクル」
の3つの短期サイクルは、相場サイクルの分析に最もよく使用される。
ハーフプライマリーサイクルの長さは、プライマリーサイクルのおよそ半分である。
メジャーサイクルは、その長さの中心時間帯がプライマリーサイクルの3分の1(時として4分の1)である。
トレーディングサイクルの長さは、メジャーサイクルの半分(時として3分の1)である。
強気相場では、サイクル内での上昇期間が長くなり(ライト・トランスレーション)、
プライマリーサイクルの中の小さなサイクルのボトムも徐々に切り上がる。
天井の場合も同様で、同タイプのサイクルの天井は徐々に切り上がる。
しかし、これらの小さいサイクルは、プライマリーサイクルの終了時には、
プライマリーサイクルの支配性により歪みが生じる。
弱気相場のサイクル内では、
下落する期間が上昇する期間よりも長くなる(レフト・トランスレーション)。
このタイプのサイクルの天井とボトムは、共に毎回切り下がる。
しかし、プライマリーサイクルがボトムをつけた後の最初のメジャーサイクルでは例外が起こることもある。
強気相場におけるプライマリーサイクルのボトム、
あるいは弱気相場におけるプライマリーサイクルの天井の直後は、極めて特別な期間である。
この期間は、現実のトレンドの反対のポジションを取ることで、短期間に大きな利益を上げることができる。
ただし、この取引手法はプライマリーサイクルないし長期サイクルのボトムあるいは天井の時に限られる。
プライマリーサイクルないし長期サイクルのトレンドに対する反転の動きは、
関連する大きいサイクルの長さの6分の1から3分の1の期間続く。
それは、より大きいサイクルの半分以上続くことはない。
もし、その長さ以上に反転の動きが続けば、それはトランスレーションの変化を表し
(弱気相場では左から右、強気相場では右から左へ)トレンドが変わったことを示す。
長期サイクルがボトムをつけた直後の最初のプライマリーサイクルは、
しばしば「ライト・トランスレーション」あるいは前のプライマリーサイクルの天井を更新する等の強気の特徴を示すが、
この場合に、相場が弱気から強気に変化したと思うのは早計である。
相場は単にサイクル論の基本原則に従って動いているに過ぎない。
即ち、トレンドに対し相場が大きく反転して動くと、
その動きは関連する大きいサイクルの長さの平均の一定の割合の期間続く。
強気相場においては、プライマリーサイクルの天井からの下げは、最低2〜5週間である。
この期間より長い場合もあるが、長期サイクルのボトムの到来と合致しなければ、
前のプライマリーサイクルのボトムを下回ることはない。
プライマリーサイクルのボトムは通常少なくとも3週間ぶりの新安値となる。
弱気相場においては、相場は前のプライマリーサイクルのボトムを更新する。
下げの期間は通常、プライマリーサイクルの天井形成後、少なくとも8週間である。
プライマリーサイクルのボトムはプライマリーサイクルの後半に出現する。
それは通常、3番目か4番目のメジャーサイクルの位相に現れる。
下げは通常、3番目ないし4番目のメジャーサイクルの天井から2〜5週間続く。
強気相場においては、天井はプライマリーサイクルの後半に出現する。
プライマリーサイクルの中の3番目か4番目のメージャーサイクルの位相で天井になりやすい。
ただし、長期サイクルのボトムの到来と合致すると、このプライマリーサイクルは
弱気タイプの「レフト・トランスレーション」に変化する可能性がある。
弱気相場においては、相場は「レフト・トランスレーション」を示す。
天井はプライマリーサイクルの前半に、ボトム形成後2〜5週間の間に出現する。
通常はプライマリーサイクルの最初のメージャーサイクルの位相で天井になる。
ただし、長期サイクルのボトムの到来と合致すると、
このプライマリーサイクルは「ライト・トランスレーション」(歪み)を示す可能性がある。
