ベートーヴェン後期作品群への過渡期的作品の考察
序論
本論文は、ベートーヴェンの中期と後期の重要な作品群の狭間の 寡作期に作曲された、ピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102‐2との類似性を分析し、ベートーヴェンの後期作品群の作曲に移行していく過程を主として演奏者の立場から明らかにするものである。
ベートーヴェンの作品区分は、初期、中期、寡作期、後期と4つに分けられることが多いが、寡作期の作品が特に注目されることは少ない。1813年〜1816年は、多くの音楽学者 *1) も述べているように、ベートーヴェンの生涯において、「寡作期」といわれている。この時期は、ベートーヴェンの私的な生活環境にさまざまな困難が山積しており、ヨーロッパの社会情勢やベートーヴェンの社会的地位にも変化が見られ、ベートーヴェンの耳の疾患の悪化なども顕著になるなど、寡作になった原因はいくつか発見できる。
ベートーヴェンのピアノソナタの中で、第28番作品101は、演奏会のプログラムに載ることが極めて稀であり、ベートーヴェンソナタ全曲演奏やCDの全集の中で取り上げられることはあっても、演奏会の主要なプログラムには登場しない。この事は、現代においても一般の人達にはわかりにくい難解さを持っているということを意味するだろう。一方、演奏家の立場から言えば、演奏技術が特殊であり、演奏に困難さを伴う事にも一因がある。ピアノソナタ第28番作品101は、1816年、ベートーヴェンの寡作期の終わりころ、つまり、傑作といわれる後期作品群が生まれていく過程の過渡期に作曲された作品である。寡作期のこの作品は、ベートーヴェン中期の作品、いわゆる、ベートーヴェンらしい力強さを持った楽曲と、後期の深い内面性を持った楽曲に挟まれ、注目されにくい位置にある。
その反面、このピアノソナタ作品101に先駆けて、1815年に作曲されたチェロソナタ第5番作品102−2は、チェロソナタとしては、ベートーヴェンの最後の作品となるためか、前記ピアノソナタと同時期に作曲されたにもかかわらず、注目されることが多く、さらに、後期作品群の代表とも言えるピアノソナタ第29番、作品106「ハンマークラヴィーア」のフーガとの類似性が指摘されることもある。しかし、ベートーヴェンの寡作期に書かれた、楽器編成の異なるこの二つの楽曲には、多くの類似性があり、それらを研究、分析することは、ベートーヴェンの後期作品群への移行期の特徴を明らかにする重要な意味を持つ。
後期作品群の大きな特徴である、フーガ(ポリフォニー)への傾倒、自由な形式、長大な楽曲構成、深い内面性などが、この寡作期といわれる時期に現われ始めていることは、ベートーヴェンの晩年のさらに難解な楽曲の特徴を研究する上でも重要である。
本論文は、楽曲分析による形式の考察や、ベートーヴェンの内面的な思想の検証だけではなく、演奏家が、演奏技術上の問題点や経験的に感じる技術的な違和感について考察する。演奏家の観点から、この2つの作品の比較検討をおこなうがそのことは、理論だけでは説明できない、ピアノという楽器特有の技術的特徴にも視点を広げ、ベートーヴェンの後期作品群の特徴の萌芽を実証することになろう。さらに、寡作期にベートーヴェンが作品を書かなくなった原因と、後期作品群に向けて作曲を再開していく過程を知ることで、内面的にさらに深まっていくベートーヴェンの晩年の音楽をより深く理解できると思われるため、寡作期当時のベートーヴェンの社会的立場、ヨーロッパの情勢、ウィーンにおける音楽の傾向などにも言及する。
第1章 寡作期におけるベートーヴェンとその作品
ベートーヴェンの作品は、一般的に、初期、中期、寡作期、後期の4つに区分される。詳細な年代による分類では、研究者 *2) によって多少の差があるが、その区分は、おおよそ次のようになっている。
初期 :1792年頃〜1802年頃 ウィーンに移住した22歳から32歳まで
中期 :1802年頃〜1814年頃 32歳頃〜44歳頃
寡作期:1813年頃〜1816年頃43歳頃〜46歳頃
後期 :1916年〜1827年(没年)
46歳頃〜没年
ベートーヴェンの作曲技法の発展や内面性の研究は、この区分によって行われており、この分類によってベートーヴェンの作曲活動をわかりやすく見渡すことができる。ベートーヴェンの楽曲は、交響曲やピアノ音楽を始めとして、オペラ 、歌曲、弦楽器、管楽器など多岐にわたっており、それらの楽器編成や形式の異なる楽曲が互いに影響し合いながら芸術性が高められてい る。初期、中期の作品は、特に楽器編成に偏りがなく、交響曲、ピアノ曲などをベースに、さまざまな楽器による作品が生み出されている。曲の長さも、聴衆の集中力が途切れない程度の長さの楽曲が多い。その中で、後期作品群は、それらの作品群とは、明らかに異なる特徴が見出される。寡作期の作品は、後期作品群の特徴の萌芽がすでに見え始めており、演奏者として後期作品群のこの特徴を考慮する事が重要である。
後期作品群の楽曲は、長大で難解であり、演奏頻度も多いとは言えない。後期作品群を発表する頃のベートーヴェンは、耳の疾患が決定的に悪化して、彼の耳はほとんど聞こえなくなっていた。作品を実際に耳で確かめることができないということは、ベートーヴェン自身が自分で演奏をすることがなくなったということを意味する。そのため、演奏技術を考慮することへの配慮が希薄になり、演奏のための具体的な事柄よりも、作曲そのものに対する想いが大きくなっていたと思われる。その具体的な技術上の問題点については、後述する。このことから考察すると、ベートーヴェンの後期作品群の音楽は、初期、中期と比較すると、さらに内面的に深く掘り下げられ、高い芸術性を持っていると考えられる。
その後期作品群の創作に入る数年前に、ベートーヴェンの生涯でただ一度の寡作期がある。その時期は、ヨーロッパ史においても時代の転換期であり、ベートーヴェン自身の地位や立場も変化してきた頃で、ベートーヴェンが寡作であった理由は、いくつか挙げられる。これは、次節に示す。その時期に作曲された楽曲は、現在、芸術的価値が低く見なされているものもあり、注目されることが少ない。しかし、その中でピアノソナタ作品101やチェロソナタ作品102−2などは、芸術的にさらに高まっていく後期作品群の特徴が見られる。本章ではその点に注目し、ベートーヴェンの寡作期という時代に作曲された二つの重要な楽曲を比較研究し、後期作品群の音楽的特徴の萌芽が、すでに寡作期にあったことを示す。
ベートーヴェンは、貴族社会の中で、自我を明確に主張し、音楽を芸術として高めた最初の音楽家である。この事は、当時のヨーロッパ社会が、疾風怒涛(シュトルム・ウント・ドランク)の時代を経て、啓蒙主義やフランス革命によって、自由平等という思想が受け入れられてきた時代であったことに大きな関連がある。1792年、ボンでは、すでに啓蒙主義君主が現れており、ボン大学も設置されていた。ベートーヴェンがウィーンに移るまでの青年期に、彼は、すでに、自由で新しい思想の雰囲気の中で生活してきた。そのような時代背景があったため、貴族ではないベートーヴェンが、音楽の才能を高く評価され、ボン在住の貴族からの紹介状を持ってウィーンに行くことができた。この頃ウィーンでは、地理的にヨーロッパの極東にあったため、フランス革命の直接的な影響も少なく、依然として貴族社会は機能していた。
しかし、婚姻によって全ヨーロッパに姻戚関係を持ち、事実上ヨーロッパの中心的存在となっていたハプスブルク家は、啓蒙主義の精神を取り入れ、君主自らその思想を推し進める傾向にあった。ベートーヴェンがウィーンに来た1792年は、王制の終焉期にもあたり、王族、貴族などの身分がなくなり、自由平等の世の中になる動きがすでに見え始めていた。ベートーヴェンの新しく斬新な演奏技術や作曲法がウィーンで受け入れられたのも、そのような時代背景の影響によるものが大きいと思われる。
さらにベートーヴェンがウィーンで活躍した時代は、文化が貴族社会から市民社会へと移行した。市民階級における家庭音楽( Hausmusik )が普及し、そのため楽譜出版業者も繁栄を見せていた。裕福な市民たちは、新しい楽器、ピアノフォルテを買い、習い始めるようになった。 *3) そのような時代に、ベートーヴェンは、貴族にも一般市民にも受容される作曲家となっていった。ベートーヴェンの初期、中期の作品は、新しさと保守的なものが混在しており、一般市民でもある程度の理解ができる音楽形式であった。その中で、ベートーヴェンは、ハイドンやモーツァルトとは違った音楽に対する新しさを持っていた。彼の音楽は、音楽が単に「味わわせるもの」、「心を癒すもの」、「人々を楽しませる」ものではなく、「生の根源的なもの」で、ベートーヴェンの新しさの特徴の一つとして、彼の音楽全体にエネルギーが満ちていることである。この新しさが、貴族階級にも市民階級にも受け入れられ、認知されたのは、民主主義的な新しい思想がその時代と合致していたからである。
この後、ベートーヴェンはウィーンで広く知られるようになり、中期の傑作を次々と発表していた。寡作期に入る1813年頃までは、すでに第8交響曲まで作曲されており、ピアノソナタは、作品81 a 「告別」や作品78「テレーゼ」、さらにヴァイオリンソナタは、第10番まで、弦楽四重奏曲 は、第11番「セリオーソ」が完成している。ベートーヴェンは、181 3年頃からの寡作期に入るまでに、社会的にも音楽家としての地位を確立していた。上記の背景を基に、1812年以降1816年までの寡作期の社会的状況を考察する。
ベートーヴェンの生きた時代は、全生涯を通して、ヨーロッパの激動期と重なる。特に、ベートーヴェンの寡作期でもある、1814年秋から1815年春まで開催された、「ウィーン会議」がその象徴である。フランス革命のあと、ナポレオンによるヨーロッパ侵略によって、今までのヨーロッパの秩序が大きく乱れた。今までの封建主義社会が、自由主義によって衰退しようとしていたが、ナポレオンの侵略、それに続くナポレオンの失脚により、自由主義は崩壊する。自由主義の流れの逆行は、オーストリア政府にとって歓迎すべきことであった。オーストリア帝国外相メッテルニヒは、あらゆる民主主義を排除し、半封建的な絶対主義を推し進め旧体制を維持することに努めた。ウィーンでは、新聞、小説などの検閲を行うなど、近代思想を排除しようとした。そのため、急進的な思想を持つベートーヴェンも秘密警察の監視下にあったことも知られている。
しかし、当時のベートーヴェンの音楽家としての地位はほぼ確立しており、全ヨーロッパにも知名度があるほどであった。* 4) そのためか、「ウィーン会議」の余興としてベートーヴェンがステージに立つこととなる。* 5) ベートーヴェンを一目見ようと大勢の人々が集まり、その演奏会は一見、大成功に見えた。この「ウィーン会議」の際には、ベートーヴェンの音楽の他に、舞踏会のための音楽、つまり、ウィンナワルツも共に人気を集め、本来のベートーヴェンらしい音楽とは正反対の軽音楽に聴衆の興味は移って行ったといわれる。このように、ベートーヴェン自身の知名度は高まったが、彼の音楽が演奏される機会は少なくなっていった。
この時期になると、ベートーヴェンの耳は、ほとんど聞こえなくなり、ピアノ独奏は、不可能となった。ベートーヴェンは、突然の熱に侵されたり、胃腸疾患になるなど、体調もすぐれない状況になった。* 6) さらに、1815年、ベートーヴェンの弟カールが肺結核のため死去し、甥のカールについて未亡人と親権を争そうことになる。この訴訟は、5年間続きベートーヴェンの生活を落ち着かないものにさせた。そのことについて、ベートーヴェンは、法律家ヨハン・ネポムク・カンカ(Johann Nepomuk Kanka 1772〜1865)に次のような手紙を送っている。
『こんな訴訟がおしまいになることをどんなに渇望しておりますことか、ほとんどあなたにはご想像になれぬほどです。(中略)またこの事が生活を幸福にしてくれるいろいろなことから私を遠ざけているのです。私の性向であり、また自らの義務ともしておりますことは、わが芸術を貧しい人々に役立たせるということです。しかし、この事件のため、それらを抑制しなければなりませんでしたし、現に今も差し控えなければならないのです』 *7)
このようにベートーヴェンの寡作期における、ヨーロッパ事情とベートーヴェンの生活は、ベートーヴェンの後期作品群の精神性に影響を与えたと思われる。寡作期において、ベートーヴェンの音楽は、正当に評価されなかったり、政治に利用されたりした。自由思想を持っていたはずのベートーヴェンが、オーストリア帝国の封建制度を後押しするような形で利用されたことは、不本意であったし、また、そのような形でベートーヴェンの音楽がもてはやされたことについてベートーヴェンがのちに回想し、虚しさを感じている。* 8) 元来、 ベートーヴェンは、当時では急進的ともいえる自由な思想を持ち、その音楽は力強く、活力に満ちたものであり、音楽形式は理論的で、一般の人々にもわかりやすいものだった。しかし、ベートーヴェンの後期の作品は、内面的で難解になり、聴衆の理解を得られないものになっていった。寡作期に起こったさまざまな背景を考察することで、後期作品群が、難解で内面的になっていく経緯が理解しやすくなる。後期作品群には、明確な特徴として深い内面性と難解さがあげられるが、その特徴は、この寡作期に徐々に形作られたと考えられる。短い期間ではあるが、人生におけるさまざまな変化があった寡作期を経てベートーヴェンは、晩年、ロマン派のさきがけといわれるような、古典派音楽とは、ある意味で別な方向に向かって、さらに新しい音楽を制作していくことになる。
寡作期には、以下の作品が作曲されている。年代順に記す。
1813年
ウエリントンの勝利<戦争交響曲> 作品91
交響曲第7番 作品 92
クフナーの悲劇のための勝利の行進曲 WoO2a
クフナーの悲劇の第2幕への導入曲 WoO2b
リート<ナイチンゲールの歌> WoO141
リート<吟遊詩人の亡霊> WoO142
20のアイルランド歌曲集 WoO153
12のアイルランド歌曲集 WoO154
26のウェールズ歌曲集 WoO155
カノン<苦しみは短く>第1作 WoO163
1814年
オペラ<フィデリオ>第3稿 作品72
<フィデリオ>序曲 作品72
ポロネーズ ハ長調 作品89
ピアノソナタ 第27番 ホ短調 作品90
<悲歌> 作品118
カンタータ<栄光のとき> 作品136
トライチェケのジングシュピール<よい知らせ>の終曲<ゲルマニア> WoO94
<連合君主に寄せる合唱> WoO95
<別れの歌> WoO102
田園カンタータ<楽しい乾杯の歌> WoO103
リート<恋人に寄せて> WoO140
リート<兵士の別れ> WoO143
リート<メルケンシュタイン>第1作 WoO144
カノン<友情は真の喜びの源> WoO164
<私は場所 zu の殿、貴方は身分 von の殿> WoO199
手紙に書き込まれた言葉つきの音遊び<ひとりで、ひとりで、ひとりで> WoO205b
1815年
リート<希望に寄せて>第2作 作品94
二重唱<メルケンシュタイン>第2作 作品100
チェロソナタ第4番 ハ長調 作品102-1
チェロソナタ第5番 ニ長調 作品102-2
オーケストラ伴奏付き混声合唱のための<海の凪と成功した航海> 作品112
序曲<霊名祝日> ハ長調 作品115
ドゥンカーの悲劇<レオノーレ・プロハスカ>のための 4 つの音楽 WoO96
トライチェケのジングシュピール<凱旋門>の終曲<成就せり> WoO97
リート<声高な嘆き>第2稿 WoO135
カノン<新年おめでとう> WoO165
カノン<苦しみは短く>第2作 WoO166
カノン<ブラウフレ、リンケ> WoO167
1816年
連作歌曲<遥かな恋人に寄せて> 作品98
リート<約束を守る男> 作品99
ピアノソナタ第28番 イ長調 作品101
軍楽のための行進曲 WoO24
リート<秘密> WoO145
リート<憧れ> WoO146
リート<山からの呼び声> WoO147
パズル・カノン<沈黙を学べ> WoO168-1
カノン<語れ、語れ> WoO168-2
パズル・カノン<私は貴方にキスする> WoO169
カノン<芸術は長く、人生は短し> WoO170
寡作期の作品をすべて見渡してみても、これらの作品の中で現在も芸術的な価値が認められているのは、ピアノソナタとチェロソナタ、交響曲第7番、フィデリオ序曲、歌曲集<はるかなる恋人に寄せて>などである。それ以外のほとんどの楽曲は、ベートーヴェン自身も述べているように* 9)、 人によっ ては、よい評価が得られていない。 それらの楽曲は、大公や貴族からの依頼によって作曲されたものが多い。しかし、ピアノソナタとチェロソナタは、ベートーヴェンの意思により作曲され、音楽的な技術や理解が高い人物に献呈されている。寡作期とはいえ、この時期にこれだけ多くの作品を書いていたにもかかわらず、ピアノ演奏家の立場から見て、現在も芸術的なベートーヴェンの代表的な作品となっているのは、ピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102ということがいえるであろう。
第1節では、ベートーヴェンの寡作期における時代背景とウィーンにおけるベートーヴェンの社会的位置を考察し、寡作になったいくつかの原因を調べた。第2節では、ピアノソナタ作品101を中心に楽曲分析を行い、チェロソナタ作品102−2との類似点を検討する。同時代に書かれたこの二つの楽曲を比較検討することで、後期作品群の特徴の出現を見出していく。 第2節 ピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102−2の楽曲分析
A:ピアノソナタ作品101
この曲は、寡作期である1816年に作曲され、ドロテア・フォン・エルトマン男爵夫人に献呈された。エルトマン男爵夫人は、1803年以来、ベートーヴェンの弟子でアマチュ アであるにもかかわらず大変優れた演奏技術を持ち、ベートーヴェンのピアノ曲を最もよく理解して演奏したと言われている。ベートーヴェンは、彼女に演奏法を数多く指示して演奏させた。*10) 演奏技術が高く、ベートーヴェンの感性を伝えることのできる人物に曲を献呈することは、後期作品群に表れる1つの特徴である。このことは、晩年に一般大衆から自ら隔絶したベートーヴェンが、音楽性の優れた貴族を自 己の音楽の受容者とみなしていることを意味すると考えられる。寡作期におけるベートーヴェンの社会的地位は、一見最高潮に達し、ベートーヴェンが世界的に音楽家としての名声を手に入れていたことは、前章で述べたが、その外見的な華やかさとは反対に、ベートーヴェンが、大衆に理解されるわかりやすい音楽から離れていくことを、このピアノソナタ作品101から見出すことができる。このことは、以下の楽曲分析と演奏家による技術的な困難さの二つの観点から論ずる。まず、この作品を音楽的内容や作曲技法的な観点から検証する。この楽曲の楽曲分析は次のようである。
ピアノソナタ作品101の全体の特徴は、形式的には中期に作曲されたピアノソナタ作品27−2の「幻想風ソナタ」とよく似ている。 *11) 「幻想風ソナタ」 の 楽曲の構成や内容は、きわめて自由であり、幻想的である。しかし、作品27−2とは異なり、作品101では、各楽章が一貫して楽想が綿密に発展していく方法がとられている。その上、各声部が室内楽風に運行し、そこに和声の色づけと強弱の陰影が綿密に行われている。そのため、全曲にわたって温和で暖かい印象を与える。この楽曲の発想記号は、イタリア語ではなく、ドイツ語で表記している。自国語による発想表記によって、内面性をさらに明確にしようとする表れといえる。
第一楽章 Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung(やや活気を持って、そして強い内面的な感情を持って)
ソナタ形式ではあるが、厳格な古典的なソナタ形式とは異なる。
この楽章は短く、全体で、102小節である。
第一部(提示部) 1小節〜34小節
第一主題の提示 1小節〜6小節
*譜例1 ピアノソナタOp.101第一楽章 提示部 1小節〜6小節)

第二主題の提示 17小節〜25小節
*譜例2 ピアノソナタOp.101第一楽章 提示部 17小節〜25小節)
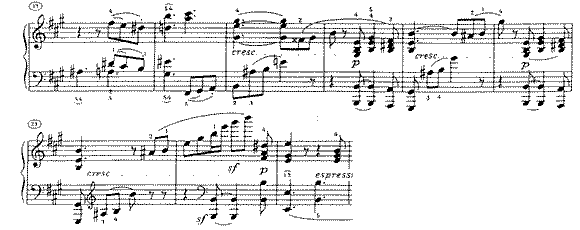
終止 26小節〜34小節
*譜例3 ピアノソナタOp.101第一楽章 提示部 26小節〜34小節)
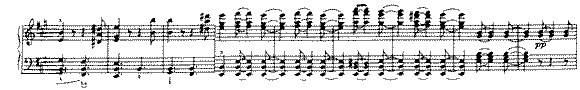
第二部(展開部) 35小節〜57小節
譜例4で示した、二つのモティーフが絡み合いながら、第一部との明確な区切りなく第二部に進入する。第二部の終わりも明確な終止がなく第三部に移行する。
第三部(再現部) 58小節〜102小節
第一主題の再現 58小節〜68小節
第2主題の再現と確保 69小節〜77小節
終止 78小節〜102小節
この楽章は、古典的なソナタ形式とは異なり、提示部、展開部、再現部の区分性が希薄であり、力強い第一主題という古典的特徴もない。カール・ダールハウス(Carl Dahlhaus 1928〜1989)によれば、ベートーヴェンの晩年様式の特徴として、「サブ・テーマ法」を挙げている。それは、ソナタ形式の楽章で、古典的なソナタ形式では、男性的な第一テーマ、女性的な第二テーマが配置される事が多いが、ベートーヴェンの後期作品群には、第一テーマに女性的ともいえる、歌曲のようなカンタービレ的特徴があるというものである。特に作品101にその特徴が現れていると述べている。 *12) 作品101の冒頭のテーマは、室内楽的なやわらかさを持ち、内声には、シンコペーションを伴った第2動機により緩やかな動きを内包している。このように後期作品群の特徴がこの第1楽章には顕著に現れる。その上展開部が大変短く、各主題の間には、対立や区切りが希薄である。第2主題は、エピソードのように継ぎ目がわからないように現れる。展開部と再現部の区切りも明確ではなく、第1主題は断片のみであり、それも変奏されさらに主調の平行調 ( イ短調 ) である。この部分を展開部の終止ととらえるか、再現部の始まりと捉えるかは、解釈が分かれるところであるが、その区分は明確ではない。イ短調部分を再現部の導入とも考えられるが、演奏者の立場から見ると、原調に戻った58小節から再現部が始まると思われる。この部分にも示されるように、この作品101の第1楽章は、ソナタ形式でありながら、従来の厳格なソナタ形式のようにな明確な区切りがない。このように、この楽章は、ソナタ形式とはいえ、その枠組みは、 大きな自由性を持っていることがわかる。
第二楽章Lebhaft,Marschmassig(生き生きと、行進曲風に)
古典的なソナタの場合とは異なり、スケルツオではなく、行進曲という形式が、ベートーヴェンの音楽の中ではまれである。全32曲のピアノソナタの中で、行進曲風にという表記は、作品26に現れるのみである。その点を考慮して考察すると、スケルツオの代わりに行進曲をおいたと考えるより、古典楽曲の対位法的作風を用いて書かれたとする方が妥当である。 *13) 園田高弘は、その説を支持しており、その根拠は、その後に来るトリオ部分のカノン風展開を見たとき、その関連を見出せると述べている。カノ ン風とは、ルネッサンス時代に生まれた多声部音楽であり、古典楽曲的な趣を感じるからである。
全体は3つの部分に分かれている。
行進曲 1小節〜54小節
第一部 1小節〜11小節(8小節の主題と3小節の終止)
*譜例4 ピアノソナタOp.101第二楽章 行進曲 第1部 主題)

第二部 12小節〜40小節
第三部 41小節〜54小節
中間部(トリオ) 55小節〜94小節
60小節からはカノンであり、対位法的手法がすでに現れている
*譜例5 ピアノソナタOp.101第二楽章 トリオ 対位法的手法)
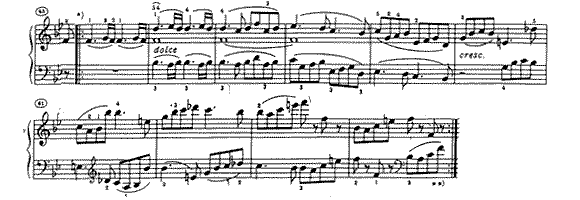
行進曲 1小節〜54小節の反復
この楽章は、行進曲風リズムの部分が、のちのローベルト・シューマンの幻想曲作品17の第2楽章に大きな影響を与えたことは、明白である。このリズムの特徴は、両曲で大きな類似性が見出せる。
*譜例6 シューマン 幻想曲Op.17 第二楽章)
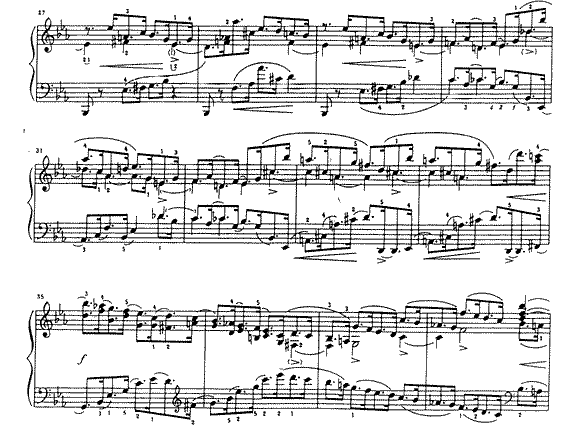
このことについて、吉田秀和は、「行進曲」と命名されていても、明朗で晴朗な一般に言われる「行進曲」の概念とは異なっている、と述べている。*14) つまり、ロマン派において好まれた形式をすでに先取りしていると見ることができる。
第三楽章 序奏〜終曲Langsam und sehnsuchtvoll(ゆっくりと憧れに満ちて)〜Geschwind,doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit(迅速に、しかしあまり早すぎず、そして決然と)
ベートーヴェンのスケッチには、第二楽章のあとに「このあとイ長調で」と記されている。そのため、この緩徐序奏は、当初書かれないはずだったが、全楽章のスケッチが出来上がったあと、書き加えられた。この緩徐序奏の低音進行は、第一楽章の第一主題の短調的出現となっている。第2楽章から、第3楽章のイ短調の序奏に演奏を進める時、その表現は、第一節で述べた当時のベートーヴェンの心的苦悩の表れのように感じる。序奏の後に来る、 mit Entschlossenheit( 決然と ) という表現の前の苦悩的回想と見ることができる。この楽章を、序奏と回想がついた1つの楽章ととらえる分析が一般的であるが、のちに分析するチェロソナタ作品102−2の緩徐楽章との類似性を発見する。チェロソナタの緩徐楽章も完全に終始せず、 attacca で終楽章のフガートに入っていくため、その点においても、この序奏を1つの楽章または、緩徐楽章の代用とみなすこともできる。*15) しかし、一般的には、次のように分析される。
序奏と回想 1小節〜28小節
後に述べるチェロソナタ作品102−2に演奏家として大きな類似性を感じた部分である。演奏してみると、その音型、拍子感、音楽的雰囲気が、酷似している。その詳しい分析は、第2節Bで行う。
第一部(提示部) 29小節〜113小節
第一主題の提示 33小節〜40小節
*譜例7 ピアノソナタOp.101 第三楽章 提示部 第1主題 33小節〜40小節)
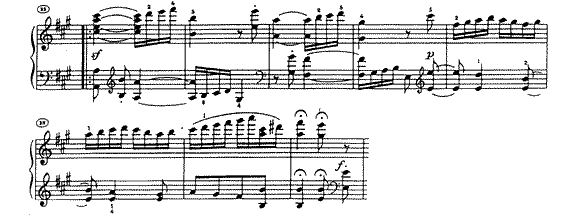
第二主題の提示 81小節〜87小節
*譜例8 ピアノソナタOp.101 第三楽章 提示部 第2主題 81小節〜87小節)
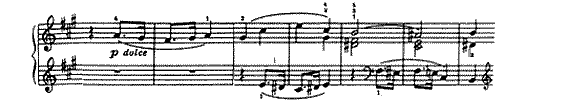
終止 107小節〜113小節
*譜例9 ピアノソナタOp.101 第三楽章 提示部 終止 107小節〜113小節)

第二部(展開部) 114小節〜231小節
第一群 114小節〜121小節
第二群 122小節〜182小節
*譜例10 ピアノソナタOp.101 第三楽章 展開部 低位法的手法 122小節〜182小節)

第三群 183小節〜208小節
第四群 209小節〜231小節
この展開部は、四声のフーガで書かれている。特に第二群の譜例10で示した部分は 四声体フーガである。一般的なバッハのフーガにおける対位法的手法の法則にすべてのっとっているとはいえないが、変則的ではあるが、まぎれもなく対位法的手法によってフーガ的に作曲されている。主題もバス声部から始まっており、次に5度ではなく、3度高くテノール声部にかつヘ長調に転調して現れる。その後、主題はアルト声部に原主題の4度高い位置に現れ、1小節の間奏の後、原主題のオクターブ上にさらに4つ目の主題が原調ではなく、その平行調、つまり、イ短調の和声付けをされている。この時点で、4つの声部がすべて現れたが、正規のフーガの応答とは異なり、各声部は自由に配置されている。そのため、演奏者は、元来周知しているフーガの法則性とは違った演奏法を強いられるため、非常に演奏が困難になっている。この部分も、チェロソナタ作品102−2の終楽章フガートに類似している。第一群には、第一楽章の第一テーマの断片が上声部に現われ、バスには、第三楽章の第一テーマの要素が含まれており、第二群の導入ともなっている。この展開部は、後期作品群の特徴の先駆けとなっており、ベートーヴェンの対位法への傾倒が顕著な部分である。
第三部(再現部) 232小節〜361小節
この構成は、第一部とほぼ同じで、大規模な楽章終止がつく。
第一主題の再現 232小節〜239小節
第二主題の再現 270小節〜276小節
終止 280小節〜302小節
楽章終止 330小節〜361小節
*譜例11 ピアノソナタOp.101 第三楽章 楽章終止 330小節〜361小節)
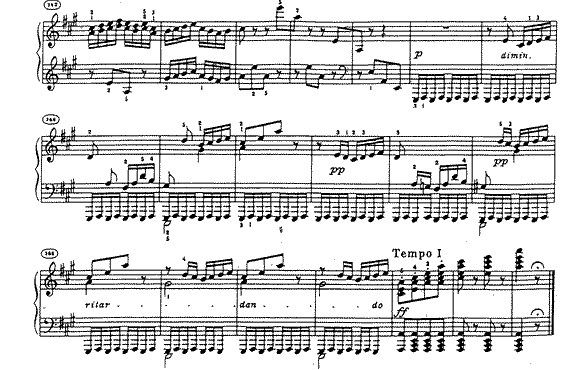
第三楽章は、序奏的緩徐楽章から切れ目なしに奏され、第一主題は、同期の対位法的展開によって扱われていく。主題の提示構成は、展開部のフーガに向かうためのものであることがわかる。展開部が、後期作品群の対位法的作風の先駆けとなる部分であり重要で注目される部分である。 この曲は、多くの音楽家に内面的でロマン性を先取りしたような音楽として捉えられている。 *16) しかし、 ベートーヴェンの対位法の作曲法は、バッハに代表されるような古典的で厳格な規則性を持った対位法とは異なっていることがわかる。それは、最晩年に書かれた、弦楽四重奏にあるように、形式の自由さを持ち、ロマン派の先駆けともいえる新しさを持ちながら、古典的なイメージを持つ対位法を多用するという特徴、つまり、新しさと古さの同居ともいえる作曲法に向かっていくことの前ぶれであるともいえる。
以上が、ピアノソナタ作品101全曲の楽曲分析である。
テオドール・W・アドルノは、この作品101について次のように述べている。
「第一楽章は『トリスタン』の前奏曲のモデルではあるまいか。音こそまったく異なるものの、いわば抒情詩としてのソナタ形式である点、完全に主観化され、魂によって浸透され、構築解体が行われている点で、両者は共通している」 *17)
このように第一楽章の第一テーマが、かなり叙情的であることを指摘している。それは、ダールハウスの「サブ・テーマ法」とも一致している。その上、ヴァーグナーの作品と比較していることで、ピアノソナタ作品101のロマン性を示している。さらに、アドルノは、最後期のベートーヴェンの作品群とそれ以前の作品群を分ける境界をなす楽曲は、ピアノソナタ作品101と述べている。その際、最後期の作品は、「直接的ではなく」、「すべては屈折しており」、「指示的で現象から引き出された抽象となっている」と定義している。*18)
このピアノソナタ作品101の分析から導き出される特徴は次のとおりである。
1.抒情的な第一テーマを持ち、ロマン的な傾向を示している。
2.ソナタ形式が厳格な古典様式ではなくなり、提示部、展開部、再現部の明確な区分がなくなる。
3.対位法への強い傾倒が見られる。
4.各楽章のソナタ形式が自由なだけではなく、全楽章を通して、構成が自由になっている。
以上が作品101の楽曲分析から見出される特徴であるが、さらに演奏実践から導き出される特徴がある。それは、音域の拡大である。演奏技術上困難を伴う、広域にわたる跳躍が挙げられる。
*譜例12 ピアノソナタ Op.101 第二楽章 広域音程部分)

この点をアドルノは、「古典主義的な動的形式を犠牲にする」*19)と表現している。つまり、意外性を持った跳躍は、抒情性と相反するものであるが、あえてその相反するものの融合によって、両者を結びつけ表現する方向に向かっている。この技術的困難については、第2節Cにおいて、改めて取り上げる。 B:チェロソナタ作品102−2
この作品は、2つのチェロソナタ作品102−1、2として、1815年に作曲された。ピアノソナタ作品101より1年ほど先になる。作品102−1は、7月、この作品102−2は、8月と自筆譜にあることから、ほぼ同時期に2つのチェロソナタは書かれたことがわかる。
1814年〜1815年は、第一節で述べた ように、ウィーン会議が行われた時期で、ベートーヴェンは、ピアノソナタ作品101が作曲された1816年より、さらに落ち着きを失っていた頃であった。それにもかかわらず、ベートーヴェンは、自らの様式に変化を求めており、その結果として、この2つのチェロソナタが創作された。この楽曲は、当時、一般聴衆にほとんど理解されず、奇妙なもの、異常なものとしてとらえられていたことが、当時の新聞評からもうかがえる。*20)
このチェロソナタ作品102の2曲は、後期作品群の創作に入る前の寡作期における数少ない芸術作品であり、ピアノソナタ作品101と同じように後期作品群の特徴がすでに明確になっている。作品102−1の草稿の上書きには、“ピアノとチェロのための自由なソナタ”とあり、作品102−2には、ただ“ソナタ”とのみ書かれている。後期作品群の特徴 である自 由な形式は、 1番目のソナタの第1楽章が顕著である。Aの分析で特に取り上げたさまざまな特徴が第1番目のチェロソナタには備わっている。第1番のチェロソナタにも、後期作品群の特徴のその先駆けを見ることができる。
本来なら、この2つのチェロソナタを同時に分析し、ピアノソナタ作品101との類似性を論じるのが妥当と思われるがピアノ演奏家の立場からこの2つのチェロソナタを演奏した際、作品102−2の第2楽章(緩徐楽章)と作品101の緩徐序奏に強い類似性を見出した。そして、フーガ部分の難解さにも、共通するものを感じた。チェロソナタ作品102の2曲は、両方が後期作品群の特徴を合わせて備えていることは、明確であるが、ここでは、演奏家が 感じた 、楽曲の持つ内面性の共通点に沿って、作品101と作品102−2を比較することとした。この比較対象の選択は、音楽が本来持つ 感覚 の多様性から発したもので、理論だけでは測れない、実際の音楽表現の中から生まれたものであった。そのような発想から、まずは、作品102−2のチェロソナタの分析を行う。
作品102−1 ハ長調に比べると、この作品102−2は、全体は三楽章形式で、第一楽章はソナタ形式によるアレグロ(急)、第二楽章が歌謡風のアダージオ(緩)、第三楽章は、第二楽章から切れ目なく演奏されるアレグロ(急)・フガートであり、一見、古典的なソナタの形式を踏襲している。 さらに、 全5曲のチェロソナタの中で唯一、緩徐楽章を採用している 。このことは、古典的作曲技法への回帰とも見ることができる。その点においては、ピアノソナタ作品101との類似性は感じられないが、この緩徐楽章は、ピアノソナタ作品101の緩徐序奏に強い類似性を見出すことができる。形式は異なっていても、内面的なイデーにおいて、共通点を発見することができる。さらに、難解なフーガを終楽章に持っていることも、ピアノソナタ作品101との共通点である。その点も、演奏家としてそれらの楽曲を演奏する時、同様のイデーを感じる。技術的な複雑さや困難さは、演奏してみた時、その共通点が明確になる。このチェロソナタ作品102−2は、古典的な形式で書かれているように見えるが、A.で述べたベートーヴェンの後期作品群の特徴をその類似性によって見出す事ができる。
第一楽章 Allegro con brio(早く、生き生きと)
提示部 1小節〜53小節
第一主題提示 1 小節〜13小節
*譜例13 チェロソナタ Op.102-2 第一楽章 提示部 第1主題)

第二主題提示 29小節〜34小節
*譜例14 チェロソナタ Op.102-2 第一楽章 提示部 第2主題)

終止
展開部 54小節〜88小節
第一主題の素材のみで展開される。
再現部 89小節〜128小節
第一主題は完全には再現されないものの、第二主題は形式どおり原調で再現される。
終止 129小節〜147小節
第二主題から完全終止へ向かう。
第二楽章Adagio con molt sentimento d'affettoso
チェロソナタの中で、唯一の緩徐楽章である。三部形式であるが、深い抒情性と瞑想的雰囲気を持つ。
第一部 1小節〜24小節
ニ短調主題(譜例15)のコラール風主題によって諦念さえ感じられる穏やかな旋律が現れ、その後チェロによって新たな旋律が登場し変奏されながら第一部を終える。
*譜例15 チェロソナタ Op.102-2 第二楽章 提示部 ニ短調主題)

第二部 25小節〜50小節
ニ長調に転調し、ニ短調の暗さが払拭され、明快で幸福な音楽が展開される。チェロとピアノの穏やかな対話が行われる。
第三部 51小節〜85小節
再びニ短調となり、第一部の再現を行うが、付点リズムや3連 符により変化を見せるが、最後はニ長調属七和音によって不完全終止し、第三楽章に途切れずに入っていく。
この楽章は、ピアノソナタ作品101とさまざまな点で類似性を持つ。
*譜例16 ピアノソナタ Op.101 第三楽章 序奏)

使用されているリズムも音価は異なるが、まったく同じである。
*譜例17a チェロソナタ Op.102-2 第二楽章)

*譜例17b ピアノソナタ Op.101 第三楽章 冒頭)

このことは、第2節Cにおいて詳しく述べる。
第三楽章Allegro Fugato
ベートーヴェンが晩年盛んに用いた対位法的書法の重要な出発点といえる。この曲のこの楽章を以って、それ以降の後期作品群には、盛んに対位法的書法が現れる。フガートの主題を暗示する4小節の導入のあと、フガート主題(C omes)*譜例18)が提示される。その6小節後にピアノによりDux主題が現れ、さらに声部を増やし、四声のフーガが展開される。その後、チェロが第二主題*譜例19)を提示し、新たなフガートを展開する。その7小節後には、第1フガート主題が再び現れ、二重フーガを構成していく。さらにピアノによって持続低音をトリルによって奏させ、第1フガート主題がストレットで繰り返され高揚するうちに全曲を閉じる。
二重フーガという複雑な対位法は、当時の聴衆には、まったく理解されなかった。その事は、トーマス・マンの「ファウスト博士」の中でも次のように述べられている。
「チェロソナタ・ニ長調作品102の終楽章は、《アレグロ・フガート》と名づけられているのだ!(中略)人はその全体を、難解で味わうことなどできないと非難した。しかし少なくとも二十小節くらいのあいだはめちゃくちゃに混乱しているから―主としてあまりに激しい転調のためである―それによって、この人は厳格な様式を築くことができないのだと案じて断定することができる」「かくしてベートーヴェンは、フーガが書けないという噂をたてられた」*21)
トーマス・マンは、「ファウスト博士」のこの部分を書く際、アドルノの解説を参考にしたといわれており、アドルノさえも、このフガートを難解なものとして捕らえていたことがわかる。そのことは、ベートーヴェンの生きた18世紀のみならず、 20世紀に入ってからも、ベートーヴェンの難解な対位法が理解されにくかったこともうかがえる。このチェロソナタ作品102−2は、形式こそ古典的なソナタ形式、フガートも規則的な対位法によって書かれているが、第2楽章の深い内面性をたたえた、ピアノソナタ作品101と共通する音楽的イデー、そして、第3楽章の難解なフガートを見出すことにより、後期作品群の特徴を備えている事がわかる。
A,Bにおいて、寡作期に作曲されたピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102−2を分析することで、この2つの楽曲が、後期作品群の先駆けとなり、さまざまな特徴の萌芽が見えることが確認された。次に演奏家としてこの2つの楽曲の類似性を見出した根拠と演奏上の問題点に焦点をあて、さらにこの2つの楽曲を比較する。 C:ピアノソナタ作品101とチェロソナタ 作品102−2の類似性とピアノ演奏技術の観点からの考察
前節ABにおいて、ピアノ演奏家が実際の演奏から、この2つの楽曲に類似性を見出したことについて簡単に述べた。Cでは、その類似性を演奏技術の観点からも含め、詳しく考察する。
C−1:第2楽章の類似性について
ベートーヴェンは、この二つの楽曲の緩徐楽章および緩徐序奏において、同じイデーを持ち、内面的な深い感情を表現した。第2節Bで述べたように、この2つの楽曲の緩徐楽章、および緩徐序奏には、以下の類似点がある。
1.リズムがほぼ同型である
2.始まりが各調の?度和音で開始されている
3.ターン型音型は上行し、バスが下行する
4.発想表記がほぼ同じである
・チェロソナタ Adagio con molt sentimennto d'affetto
・ピアノソナタ(ドイツ語表記と同時にイタリア表示もある) Adagio,ma non Troppo,con affetto
5.以下の表に示したように調性の長調−短調−長調という変化と拍子が同じである
|
|
調性 |
拍子 |
|
チェロソナタ |
ニ短調−ニ長調−ニ短調 |
2/4 |
|
ピアノソナタ |
イ短調−ハ長調−イ短調 |
2/4 |
C−2 第3楽章の対位法と演奏技術の観点からの考察
ピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102−2の終楽章には、難解な対位法によるフガートがある。その難解さは、先に述べたトーマス・マンの文章にも顕著であるが、演奏を通しても、その難解さが感じられる。それは、あとに述べる後期作品群の特徴でもある幅広い音型にも大きな原因がある。ピアノを演奏する際、2オクターヴ以上の両手の遠隔は、バランスをとりにくく、演奏しづらい。そのため声部の連結も集中を欠く。ピアノによる対位法楽曲の演奏は、規則的なフーガであっても、演奏者一人による多声音楽の表現は困難である。しかし、規則性のあるバッハのフーガなどは、音域がある程度自然な範囲にあり、声部の連結も比較的緩やかで、聴く側も音楽美と形式の明確さによって、難解さをさほど感じない場合が多い。しかし、この2つの楽曲の対位法的作曲技法は、ピアノ演奏法上の困難を伴うことから、ベートーヴェンが自ら演奏することを想定しておらず、観念的に書かれたものといえる。はなはだしい跳躍や中声部がはなはだしく高音で書かれたりしている。このように、前項で分析した2つの楽曲の対位法の演奏における不自然さは共に共通しており、演奏技術上の困難も同様に感じられた。このことから、これらの楽曲は、ピアノで演奏することを想定せず、晩年の弦楽四重奏に代表される楽曲のイデーをも感じさせる。
このことは、後期作品群の大きな特徴であり、この2つの楽曲は、少なくとも、演奏上において、この2つの点に類似性を持つ。つまり、ベートーヴェンの寡作期においての数少ない芸術的作品である、ピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102−2には、さまざまな類似性があることがわかる。全体像としてこの2つの楽曲には、類似性を検証した文献は、ほとんどないが、演奏家の立場から、細部を検証することで、類似性を見出すことができた。このことから、ベートーヴェンの後期作品群の特徴の萌芽は、寡作期にはっきり現れていることがわかった。 第2章 ベートーヴェン後期作品群の作品とその特徴
第1章第2節において、ベートーヴェンの後期作品群創作に入る前の寡作期に現れた重要な二つの作品を分析し、そこに内包する晩年様式の表出を明確にした。第2章では、寡作期と後期の関係を比較し、難解といわれるベートーヴェンの晩年の作品へのアプローチを行い、芸術的音楽表現の実現の方向性を考察し、明らかにする。
第1節 後期(晩年)におけるベートーヴェンの生活環境の背景
ベートーヴェンは、寡作期を乗り越え、1818年から死にいたる1827年まで、再び、創作を始める。1817年は、まだ、体調不良や甥の訴訟問題で悩み、意欲がありながら、実際は楽曲を一つも完成させなかった。*22)
この時期は、すでにベートーヴェンの耳の疾患はさらに悪化し、筆談に頼るようになる。晩年の創作期は、いわゆるビーダーマイヤーの時代*23)とも重なる。ビーダーマイヤー時代には、ベートーヴェンの後期作品群の重厚で長大な音楽は、一般には受け入れられないものになった。妥協をせず、苦悩に立ち向かうベートーヴェンの生き方とその音楽は、すでに時代遅れのように受け取られて行った。ビーダーマイヤー時代の典型的な人気音楽は、ヨハン・シュトラウスに代表されるダンス音楽などであった。他にも、ジョアッキーノ・ロッシーニ(Gioacchino Rossini 1792〜1868)などの大衆的なオペラがもてはやされた。ベートーヴェンの晩年の作品は、一般の人々の理解を超えたものとなり、楽譜は売れなくなりベートーヴェンの孤独をさらに深いものとしたと思われる。このような環境の中で、ベートーヴェンは、後期作品群を書きつづけ、1818年、ピアノソナタ作品106「ハンマークラヴィーア」が完成する。この「ハンマークラヴィーア」の完成によって、ベートーヴェンの創作活動は、再び甦る。ピアノソナタ作品106は、第2節で述べるが、さまざまな点で後期作品群の特徴を持っている。1817年以降に作曲された、後期作品群の楽曲を以下に記す。
ピアノソナタ 第29番 作品106 1817年〜1818年
ピアノソナタ 第30番 作品109 1820年
ピアノソナタ 第31番 作品110 1821年〜1822年
ピアノソナタ 第32番 作品111 1821年〜1822年
11のバガテル 作品119 1820年〜1822年
ディアベッリの主題による33の変奏曲 作品120 1822年〜1823年
ミサ・ソレムニス ニ長調 作品123 1819年〜1823年
交響曲 第9番 ニ短調 「合唱」 作品125 1823年〜1824年
6のバガテル 作品126 1823年
弦楽四重奏曲 第13番 作品130 1825年
弦楽四重奏曲 第14番 作品131 1826年
弦楽四重奏曲 第15番 作品132 1825年〜1826年
これらの楽曲は、現代、芸術的価値の高い作品として高く評価されており、寡作期の作品と比べると、比較にならないほど、演奏される機会が多い。しかし、音楽的内容や作曲技法が複雑化し、演奏技術的に困難な部分があり、この後期作品群は、現在においても、難解で一般に理解されているとはいい難い。本節で明らかにした時代背景でも、ベートーヴェンの後期作品群の難解さの原因を探ることができる。ベートーヴェンの生活環境や、そこから生まれる、精神性を知ることで、内面からその難解さ理解する一端になるだろう。本節では、ベートーヴェンが、晩年、ウィーンにいて、孤独的、内面的になっていった事実を明らかにした。次節では、さまざまな研究者による後期作品群の特徴を系統的に分類する。 第2節 ベートーヴェンの後期作品群の特徴
ベートーヴェンの後期作品群は、ロマン派の作曲家たちに影響を与えた。それは、形式にとらわれない自由な発想へと続き、ベートーヴェンの後期作品群は、ショパン、シューマン、メンデルスゾーン、ブラームス、さらにワーグナーやひいてはシェ−ンベルクに至るまで、さまざまな音楽的発展を刺激した。そのような、ロマン派的といわれるベートーヴェンの後期作品群の特徴は、形式、テンポ、テーマの扱い方、作品の規模、音域の拡大などに顕著に現れる。
カール・ダールハウスは、晩年の作品の概念を次のように述べている。「精神史的、作曲史的に晩年の作品群は、成立的に所属している時代の埒外に出てしまう」*24) つまり、ベートーヴェンの場合、古典派に属した作曲家でありながら、後期作品群は、その先のロマン派に属しているようで、また、それも明確にロマン派とも言えず、結果的に、どの時代にも属さないような、中間的な独自の世界を形成しているということである。その意味においても、後期作品群の特徴は、古典派とロマン派の中間的無時間性を感じさせる。
さらに、ダールハウスは、ベートーヴェンの晩年様式の特徴を次のように述べている。*25)
1.いくらか破格の自由さを持ったフーガ ( 対位法 )
2.抽象化の傾向
3.魔術的関係付け
4.カンタービレ的要素とモティーフ操作
次に、テオドール・アドルノは、「音楽の哲学」でベートーヴェンの晩年の様式について、次のように述べている。
1.メロディ形成:音の繰り返しが多い。
2.神秘的なものの表現についての技術面での確認
3.幅広い音域
4.シンコペーションとアクセントの原理は強化される
5.剥き出しの音楽表現。無機的なものとの関係。
6.和声進行を無視した対位法
7.和声のありかたは、存続はしていても忘却されている。
このように、形式にとらわれずに自由な音楽表現をした結果、難解でわかりにくくなっていることを強調している。*26)
また横原千史は、後期様式について、次のように述べている。*27)
1.ソナタの弱体化
2.作品の中に解決を求めていく構造上の終局性 ( フィナーレ ) の衰退
3.作品概念の解体
4.作品の連作
門馬直美によるベートーヴェンの最晩年の音楽的志向は以下のようである。*28)
1.変奏曲とフーガへの傾倒
2.“自由化”の展開
3.幻想の飛翔と緊密な構成
4.カルテット志向
5.革新の歩み
後期作品群の特徴について検証すると、上記のようなほぼ一定した見解が現れることがわかる。それの特徴は、シューベルト、シューマン、ブラームスにいたるロマン派への先駆けといえる。特に、シューマンの音楽傾向には強い影響を与えており、フィナーレの衰退、形式の弱体化、音域の広さなどは、まさしくロマン派の音楽の特徴とも一致する。ベートーヴェンの前期、中期に現れる、堅牢な形式、循環方式による作曲法、力強い前進的音楽、苦悩からの再生というベートーヴェンの明確な表現法は、表面に現れず、内 的なものになっていく。耳の疾患で、観念的な音楽となり、厳格さの象徴である対位法に固執し、その中で和声法を変容させていると思われる。ベートーヴェンの後期作品群は、このように、古典派でもロマン派でもない独自の世界を形成するに至った。演奏家の立場から見ても、後期作品群を演奏する場合、古典的なソナタ形式とは異なりロマン的な自由さを持つ内容であるため、テンポのゆれ(テンポルバート)のをどの程度にしなければならないか、レシタティーヴォをロマン派のようにまったく自由に感ずるまま演奏するべきかなどの問題点が発生する。技術的にも音域の拡大による左右の腕のバランスの悪さなど、ベートーヴェンの中期の作品とは明らかに異なる演奏技術を要する。これらの後期作品群を演奏しようとする時、その違和感が、明らかにロマン派に向かっていくことを表していると感じる。 結論
ベートーヴェンの後期作品群は、第2章で述べたように、音楽史の分類区分には当てはめることのできない、独自の音楽としてとらえられることを示した。これは、ベートーヴェンの生きた時代の時代背景に大きな関連があった。ヨーロッパの激動期に重なるベートーヴェンの生涯は、封建主義と自由主義の狭間にあり、新しい社会常識が生まれつつある時期であった。その中で、独立した芸術家の地位を確立し、才能を認められ、一時は、貴族のみではなく市民階級に至るまでベートーヴェンの音楽が浸透した。その後、ビーダーマイヤー時代、ウィーン会議のあった時代から、いわゆる芸術音楽と大衆音楽が、明確に分かれていく。その時点でベートーヴェンは、聴衆の音楽への好みの変化、時代背景、生活上の環境の変化によって寡作期に入っていく。寡作期の作品は、当時、大部分が芸術的価値を認められておらず、現在も一部を除いて、ほとんど演奏されない。しかし、後期作品群に明確に現れる特徴をすでに持った作品が、この寡作期に現れていることは、注目に値する。その楽曲は、特にピアノソナタ作品101とチェロソナタ作品102であり、その作品は相互に類似点を見出すことができる。その特徴が、後期作品群の特徴を備えていることを楽曲分析により明白にした。後期作品群の難解さを深く理解するためには、それに先駆けて現れる、寡作期の芸術作品を改めて調査する必要があることを示した。またこの調査によって、ベートーヴェンの作曲法の変化の過程を知ることができた。この調査は、後期作品群を理解するために、重要な役割を果たしたと考えられる。 【注】
*1) 多くの音楽学者が以下のように―貫して,ベートーヴェンの寡作期を認めている。
・平野 昭:「創作面では大きな収穫がなかった」『ベートーヴェン』新潮社 1992,p.123
・F.ツオーべライ:「三,限界への挑戦」『ベートーヴェン』理想社 1983,p.215-245
・J.N.サリヴァン:「1810年から17年にかけて間、ベートーヴェンは創作的不毛に陥った」『ベートーヴェン』禰生選書4 1959,p.197
・A.ブークーレシュリエフ:「5年間というものベートーヴェンはほとんど何一つ作曲しない」「12 超克(1812〜1827)の章」『ベートーヴェン』白水社 p.231
・小松雑一郎編訳:「1813年の項 解説 この年の前半はベートーヴェンは何も書いていない。どんな楽想も頭には浮かんでいなかった」『ベートーヴェンの手紙(下)』岩波書店 1982,p.11
*2) 前田昭雄によるベートーヴェンの創造の時期区分研究によれば、19世紀には、A.シントラーの「ベートーヴェン伝」、W.V.レンツの「ベートーヴェンとその三様式」、A.V.ウリビシェフの「ベートーヴェンその批評と解釈」、W.J.V.ヴァシェレフスキーの「ベートーヴェン」によって,3つの区分に分けることが多い。その後、20世紀に入り、3つの区分では、分類しきれないという研究が一般的となる。E.ビュッケン「ベートーヴェン」やE.シェンクのウイーン大学における、ベートーヴェン講義において、4つの区分に分けることが、より理解しやすいといわれるようになってる。「ベートーヴェン研究の基礎的な諸問題」『音楽芸術(別冊)』1969,p.122
*3) 渡辺護:『ウイーン音楽文化史 上』音楽之友社 1989,p.220
*4) F.ツオーべライ:『ベートーヴェン』理想社 1983,p.243
*5) アレグザンダー・リンガー編:『西洋の音楽と社会7 口マン主義と革命の時代』音楽之友社 1987,p.100
*6) A.ブークーレシュリエフ『ベートーヴェン』白水社 1985,p.232
*7) 小松雄一郎編訳:『ベートーヴェンの手紙(下)』1982,p.21
*8) 小松雄一郎編訳:『ベートーヴェン音楽ノート』岩波書店 1957,p.89,181
*9) A.ブークーレシュリエフ『ベートーヴェン』白水社,1985,p.234
*10) 園田高弘・諸井誠共著:『往復書簡 ベートーヴェンのピアノ・ソナタ 分析と演奏』音楽之友社 1971,pp190-191
吉田秀和:『ベートーヴェン奏鳴曲集第3巻』春秋社 1965,p7
*11) 伊藤義雄:『ベートーヴェンのピアノ作品』音楽之友社 1962,p.221
*12) カール・ダールハウス:『ベートーヴェンとその時代』西村書店 1997,pp.308-309
*13) 園田高弘校訂:『ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第28番』2003 作品解説 p.2
*14) 吉田秀和:『ベートーヴェン奏鳴曲集 第3巻』春秋社 1965,p.8
*15) 吉田秀和:同上
*16) 伊藤義雄:同上
*17) 平野 昭:『ベートーヴェン事典』東京書籍 1965,p.413
*18) T.W.アドルノ:『ベートーヴェン 音楽の哲学』作品社 1997,p.218(分類番号:282)
*19) T.W.アドルノ:上掲書 1997,p.201
*20) T.W.アドルノ:上掲書,1997,p.257(319)
*21) 平野 昭他編:Fベートーヴェン辞典』東京書籍 1999,p.272によれば以下の記述が見られる。
「1818年11月11日付けの『総合音楽新聞』には、『この二つのソナタは,この種の形式だけではなく、およそピアノのために書かれたこれまでの作品の中で、最も異常で奇妙なものである。(中略)耳を魅惑するものはすべて退けられ、意味関連ばかりか、技巧的な関連に関しても、奏者や聴衆にわかりにくく、旋律は耳に不快で随所に堅い和音がある』」
*21) トーマス・マン:『ファウスト博士(上)』岩波書店 1974,pp.102-103
*22) A.ブークーレシュリエフ:『ベートーヴェン』白水社 p,236
*23) 渡辺 護:『ウイーン音楽文化史(上)』音楽之友社 1989,pp.242-243に以下の記述が見られる。
「ビーダーマイヤー時代:ウイーン会議(1814年〜15年)から二月革命までの時代に、独特の生活様式や芸術様式が起った時代。威嚇の誇示、過剰な装飾を排し、材料の実質的な性格を隠さず、使用日的に合致している。美の表現は、節度を越えず穏やかでやさしい印象の文化。この時代の市民生活の特色でもあった」
*24) カール・ダールハウス:『ベートーヴェンとその時代』西村書店 1997,p.320
*25) カール・ダールハウス:上掲書,pp.323-347
*26) T.W.アドルノ:上掲書,pp.205-206(267)
*27) 横原千史:「後期四重奏曲における〈終局性〉」大宮眞琴他監修『鳴り響く思想、現代のベートーヴェン像』東京書籍 1994,pp.343-371
*28) 門馬直美:『ベートーヴェン』春秋社,2000,pp.258-267 【使用楽譜】
Beethoven:"Sonaten fur Klavier",G.HENLE VERLAG MUNCHEN,ed.by B.A.WALNER,1980
Beethoven:"Sonaten fur Klavier und Violoncello",G.HENLE VERLAG MUNCHEN,ed.by Bernald van der Linde,1971
