序論
第1章 18世紀、啓蒙主義の台頭
第1節 啓蒙主義以前の音楽家の身分
第2節 啓蒙主義の時代
第3節 ドイツの啓蒙哲学 〜カント〜
第2章 ゲーテの作品とベートーヴェンの評価
第1節 文学におけるシュトゥルム・ウント・ドラング(疾風、怒涛)とその発展
第2節 ゲーテの音楽感とベートーヴェンの評価
第3章 ベートーヴェンの作品とゲーテの評価
第1節 ベートーヴェンの精神性と革新性
第2節 ゲーテとの関わり
結論
序論
ベートーヴェン研究を進めていくと、彼の生きた時代、つまり、18世紀〜19世紀初頭の社会情勢に深く踏み込まなければならない。バッハ、ハイドン、モーツァルトまでの作曲家とベートーヴェンの音楽は、特に、力強さ、音楽構成の複雑さにおいてもも、比較にならないほど変化がみられ、作曲技法も発達し精神性が深まっている。モーツァルトやハイドンは、若きベートーヴェンの指導者でもあり、実際にベートーヴェンとのかかわりがあるため、ベートーヴェンと同世代の作曲家だと思われがちだが、モーツァルトやハイドンが実際に活動していた時期は、ベートーヴェンの活躍した時代の10年ほど前になる。その僅かな時間差が、ベートーヴェンとそれ以前の作曲家との間に大きな変化をもたらしたことは、疑う余地がない。その僅かな時間でなにが起きたのか。ベートーヴェンが生まれた1770年は、すでに、中世的社会情勢が、徐々に近代社会の方向に向かっていたことが知られている。フランス革命に代表される新しい思想は、1770年代には、機を熟しつつあった。音楽家の身分は、貴族の使用人の一人という立場から、自己表現のための芸術としての作品制作を担うものとしての意義を持ち始める。その新しい思想の中で、いわゆる芸術としての音楽を実践したのが、ベートーヴェンである。
音楽家(演奏家)、音楽学者、音楽愛好家などと呼ばれるカテゴリーに分類される人々は、とかく、その作曲家の生涯や同世代の作曲家との比較など、音楽という枠の中だけでの考察にとどまっている場合が多い。それもある意味で、重要な観点ではあるが、人間の生活は、一般的に見ても、同じ職業の人々とのかかわりだけでなく、あらゆる分野との接触があり、すなわち、読書などから来る知識、教養などが複雑に絡み合って、人格を形成してゆく。そのような幅広い観点からベートーヴェンと彼の音楽を考察する時、啓蒙主義時代の、文豪ゲーテ、哲学者カント、フランス革命の落し子ナポレオンなどの偉大な人物が浮かび上がって来る。今揚げた人物は、ベートーヴェンの人生に大きな影響を与えたことは、文献によりあきらかであり、個々の人物像、各人の業績、ベートーヴェンとのかかわりを追うことには、大きな意義がある。
ここでは、1749年〜1832年の、まさしく啓蒙思想の只中に人生を送ったゲーテと、ゲーテより21歳年少のベートーヴェンの関係を考察する。ベートーヴェンとゲーテは、テープリッツでの出会いを含め、手紙のやりとりがあり、ベートーヴェンは、作品などを献呈するなど実際的な付き合いがあった。その点に着目し、啓蒙思想を軸とする芸術の方向性をベートーヴェンとゲーテの比較により明らかにする。そして、私たちが現在、コモンセンスとして捉えている近代思想の原点となっている、18世紀の啓蒙主義を再考し、ベートーヴェンの音楽の本質を思想的観点から検討し、音楽解釈の理解を深める。
第1章 18世紀 啓蒙主義の台頭
第1節 啓蒙主義以前の音楽家の身分
啓蒙主義が台頭するまでのヨーロッパの社会情勢は、どのようなものであったか。それを解説するためには、多様なアプローチの仕方があるが、芸術的な観点から見ると、バッハやハイドン、モーツァルトなどの音楽家や宮廷に仕えた画家などの立場の考察から説明することができる。現代では、偉大な芸術家として認知されているバッハ、モーツァルト、ハイドンなどの作曲家は、当時、封建貴族からは職人および召使と同等の待遇しか受けていなかった。音楽に対する認識も、単に舞曲の寄せ集め、または気持ちを紛らわすための音の出るもの、という今の感覚から見れば低俗なものであった。内容と形式が優れたものでも、それを芸術として理解されず、余興の一つとしての認識しかなかった。
バッハ(Johan Sebastian Bach)は、ワイマール候やアンハルト・ケーテン候などのドイツ宮廷に仕え、他方、ライプツィヒのルーテル教会に仕える音楽教師、オルガニストとして生涯を過ごした。ある面で職人的召使であっても、大衆に話しかけるブルジョア的芸術家という認識を持っていた。それらの相反する立場の間で生涯を過ごした。そのような認識は、当時の社会では認められておらず、彼が生きている間に出版された作品への批評や反駁は、厳しいものだった。
1737年、批評家シャイベ(Scheibe)は、バッハを、「音曲師(Musikant)」および「音楽芸人」と酷評し、彼の作品はあまりにも複雑で難しすぎるため演奏できにくいこと、その上、彼は演奏すべき音譜を一つ残らず書いているので、他の人が即興演奏する余地をなくしてしまったことなどをあげて、彼を攻撃した。(*1)
ハイドン(Josef Haydn)は、農民の出身でありながら、音楽の才能を認められ、オーストリアのエスターハ−ジィ公に仕えた。エスターハージィ公は、ハイドンの音楽を賞賛していたが、個人的な召使い以上には認識してなかったため、封建君主の暴政にも我慢をしなければならなかった。
モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)は、ハイドンとは対照的な立場、つまり、貴族と宮廷社会に生まれた。有名な宮廷音楽家を父に持ち、幼少から宮廷の中で活動した。しかし、モーツァルトは、腐敗し、非合理な封建的秩序を軽蔑していた。モーツアルトが25歳の時、相変わらず音楽家の認識を召使いとしか考えられなかったザルツブルクの大主教のもとを離れたことは、芸術の独立に対する歴史的宣言でもあった。しかし、当時は、封建社会はゆるぎないものとして存在し、モーツァルトの芸術家、思想家としての自負は、貴族たちには認められなかった。しかし、一般大衆は、モーツァルトの音楽を愛し、大流行となり、「フィガロの歌は、街や庭園にこだまし、ビヤホールのハーピストは、人々に聴いてもらいたければ、“もう飛ぶまいぞこの蝶々(Non piu andrai)”を弾きはじめなければならなかった」と言われている。(*2、譜例1)それほどの人気があっても、生活のためには、王侯や貴族の援助を求めなければならなかった。それを裏付ける手紙が残っている。その手紙には、「王妃様は火曜日に私の演奏を聞きたいと言っていますが、でも、私はあまり報酬を貰えないでしょう。」「私の演奏会は、名誉と栄光という点からいえば非常な成功を修めましたしかし、金銭に関する限り、それは全く失敗に終わりました」とある。(*3)
このように、作曲家自身は、自信と誇りを持って、音楽家、芸術家または哲学者と思いながらも、封建制度が当たり前だったこの時代に生きた音楽家は、屈辱的な待遇に甘んじなければならなかった。
第2節 啓蒙主義の時代
啓蒙主義に代表される事柄は、フランス革命であり、封建制度、王政などが崩壊し、農民や市民が貧困から開放され、自由と平等を勝ち取ったことである。このヨーロッパの大変革期が、18世紀〜19世紀初頭に起こった。18世紀の啓蒙思想の発芽は、17世紀後半に、イギリスにおいて、各国に先駆け「名誉革命」として市民の政治的地位を確立し、経済的にも商業資本主義から産業資本主義を形成した。その流れは、ヨーロッパ大陸、まずは、フランスに大きな影響を与えるようになる。ダランベール(1717〜1783)、ディドロ(1713〜1794)、啓蒙思想家、つまり、「百科全書」編纂に尽力した人物であるが、無神論、唯物論を唱え、生命論的自然科学としての実験哲学であり、それに加え、エルヴェシウス(1715〜1771)は、社会論政治論を展開させ、一種の啓蒙思想的体系を作り上げていた。しかし、その後、ルソー(1712〜1778)は、17世紀の形而上学的を根底に、18世紀の問題を考察し、学問、文化主義に対して批判を行う。ルソーの思想は、18世紀を超え、19世紀の思想に先駆するものとなり、その思想が、やがてフランス革命へと導いてゆくことになった。ルソーの思想、すなわち、第2章、第3章で述べる、ベートーヴェンやゲーテに与える啓蒙思想となった。具体的な内容を端的に表現した文章は以下の通りである。
「百科全書学派の文化主義に対して、批判する。学問芸術は道徳を純化したどころか、それを腐敗させた。無学にして粗野なる民衆の中にこそ真の徳がある。アテナイよりスパルタがルソーの理想であった。“社会”の成立と“国家”の成立は同時であり、国家権力の根底は、平等な個人の間の協定によって成立した人民主権にある。こういう原理上の“民主主義”“共和国”の理想をもとにして、行政府のさまざまな形態(政体)」、すなわち、いわゆる君主制、貴族制、民主制が分けられるのである。」教育の原理もこれに基づき、「自然人の教育」と唱えた。まず、幼児は、「事物の必然性」を学び、少年期には、「技術の教育」を与え、青年期には、他の同胞との感情的共同がきざせば、はじめて道徳、宗教(自然宗教)が学ばれる。このようにして、正しい平等社会の人民活主権者となるべき人間が形成される。と考察した。(*4)
啓蒙主義の思想にも、このような流れがあり、学術的啓蒙と人間的啓蒙にわかれて行くのであるが、それらの思想の発現から次章で述べる、カントの哲学が大きな意味を持つことになる。哲学は、カント以前、カント以後といわれるほど、カントの思想が近代思想と古典的思想を分けるといわれる。その大きな思想的流れの変換期が、18世紀であり、ベートーヴェン、ゲーテが活躍した時代であったことは、象徴的である。
譜例1 モーツァルト作曲「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」(Non pin andrai)
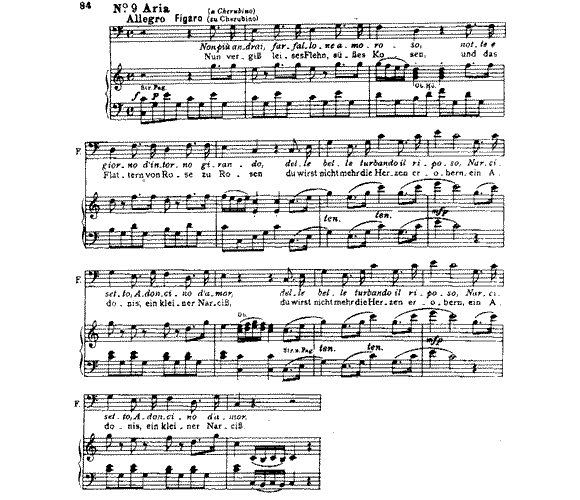
第3節 ドイツの啓蒙哲学 〜カント〜
第2節で述べた、イギリス、フランスの啓蒙思想とドイツの啓蒙思想の形態は、異なっている。17世紀における30年戦争荒廃のあと、ドイツは、政治的にも近代国家の統一には至らず、多数の小候国に分かれたままだった。啓蒙思想も、市民の政治的経済的自己主張にはならず、市民の日常生活の合理化という形をとる。つまり、ドイツ思想は、17世紀依頼の形而上学的思考を持ちつづけたのである。この状況が、ドイツ観念論につながり、大きな哲学の体系を築くことができたのである。ドイツ啓蒙哲学のみでなく、哲学全体に大きな影響を及ぼした哲学者は、カント(1724〜1804)である。カントは、理性を斥ける懐疑的自然主義に対して科学的理性を確保しニュートンの自然学を肯定する知識論を求め、そのような科学的自然の基礎となる形而上学的真実在を、道徳的信仰の内容と説く。この二つの統合の成果が、「純粋理性批判」と「実践理性批判」となるのである。カントは、第2章で述べたフランス啓蒙思想の文化主義とルソーの道徳主義の両方を受け入れることができた。つまり、カントは人間の歴史を、倫理的目的論によって解釈した。それは、人間はまず、自然の粗野で無知な状態から現れ、社会と文化を作り文明に至るが、そこからさらに進んで、真に道徳的な社会、世界市民の共同態にまで至らなければならない、と考えた。そして、世界平和を世界連邦状態によって理想化した。カントは、霊魂不死と神の理念にも、道徳的意味を与えた。神、すなわち、世界を支配する全能なるものの存在を要請する。神の存在は、理論的に証明されないが、実践的には要請されると説いた。その後、この神の摂理の信仰を背景に、神の技としての美的対象と有機的生命を認めるとし、美や生命に対して、「判断力批判」を著した。カントは、芸術についても哲学的に論じている。芸術、つまり、「美」について次のように述べている。
「美は、一つの快楽であり、美的判断は感情の判断である。しかし、単なる経験的な快感の判断とは異なって、主観に対する普遍妥当性を要求している。美的判断が感情に基づく判断でありながら、普遍妥当性を要求し得るとすれば感情そのものが単なる経験的性格において成り立つものではなく、先験的原理を有しなければならない。感情は、アプリオリな作用との直接結合を構造原理として成立する」(*5)
このような考えは、同世代に生きた、ベートーヴェンとゲーテにも彼らの創作に多大な影響を及ぼし、各作品に反映される。18世紀のドイツ啓蒙主義は、第3節冒頭で述べたように、小候国に分かれていたドイツにおいて、大きな市民革命に発展することはなかった。なぜなら、小候国の君主の中には、新しい思想を率先して推進する、啓蒙君主と呼ばれる君主が、大学を設立し、学問を推し進める政策を行ったからである。そのような啓蒙君主が治めた典型的な場所が、ベートーヴェンの生地、ボンを含む、ケルン候国であり、ボンには、ケルン選定候が住んでいた。ケルン選定候は、オーストリアのハプスブルク家の君主、ヨーゼフ2世の弟で、プロシャのフリートリッヒ国王と並んで、啓蒙思想を積極的に取り入れた。しかし、ドイツの啓蒙思想は、ここで、フランスやイギリスにおける啓蒙主義の発展とその経過、つまり、産業革命やフランス革命など市民革命に至るような、一般市民の啓蒙という形を取らなかったことに注意しなければならない。革命は、あらゆる点で、社会情勢が大きく変化し、実生活に大きな変化をもたらすが、ドイツの啓蒙主義は、君主のもと、学問の推進、精神的な開放というような、ゆるやかな発現をする。
ベートーヴェンは、そのドイツ啓蒙主義の只中に生まれ、その中で育ったという点で、作品解釈にもその思想的影響を考慮しなければならない。モーツァルト、ハイドンもすでにその新しい時代の流れを感じていながら、結局は、社会情勢に目立った変化が起こらなかったため、新しい考えは受け入れられず、封建貴族たちの使用人としての立場から、脱却できなかった。オーストリアの強大なハプスブルグ王家が統治する首都ウィーンは、イギリス、フランスと距離的に比較的遠かったため、革命の実際的な状況の伝達も、フランス革命のような過激な行動も、市民に深く浸透するのに時間がかかった。そこにいた、モーツアルト、ハイドンは、思想的には先んじていても、結局は、封建主義の因習の中からは脱却できなかった。しかし、ベートーヴェンが育ったボンは、フランスに距離的に近く、ベートーヴェンが、ウィーンに移った直後、フランス軍に占領され、ケルン選定候の時代は終焉を迎える。そのような地理的な環境を持ったボンの啓蒙主義とウィーンの啓蒙主義の影響力は、異なっており、その点を見ても、ベートーヴェンの思想は、新しい方向により近かったと考えられる。
ベートーヴェンが彼の作品に傾倒し、尊敬したゲーテも、ベートーヴェンと同じく、ルソー、カントの影響を強く受けた。しかし、ゲーテは、21歳もベートーヴェンより年長という背景から、この二人の基本的生活態度、思想的行動が違う形で表れるのが興味深い。第2章では、その相違点を意識しつつ、ゲーテの思想、人格について述べる。
第2章 ゲーテの作品とベートーヴェンの評価
第1節 文学における、シュトゥルム・ウント・ドラング(疾風、怒涛)とその発展
ゲーテは、1749年にドイツ、フランクフルトで生まれ、1832年、83歳の生涯を閉じた。このゲーテの生きた時代は、まさしく啓蒙主義の発芽から成長、発展のすべてを見とおすことのできた時代であることは、注目しなければならない。啓蒙思想は、ダランベールなどが、学問を広く広めようとする動きからはじまり、百科全書編纂が、人々を啓蒙するという動きの基となった。その動きが、フランスでは、一般市民の社会情勢を変革させるフランス革命へと進んでいったが、ドイツでは、そのような市民活動には至らず、まもなく、知識層のあいだで、特に、思想と文芸の領域で、啓蒙主義に対して、強烈な反対運動が沸き起こった。それが、<シュトゥルム・ウント・ドラング>と呼ばれる流れである。その代表的な文学者が、若きゲーテと若きシラーであった。シュトゥルム・ウント・ドラングを生んだ有力な基盤は、ルソーである。第1章第2節で述べた、啓蒙主義の流れは、ドイツに渡り、知識層の内面に作用した。ルソーは、人間存在の根源としての自然への復帰を説き、個人の情感と意欲の尊厳を目覚めさせたのであるが、ドイツでは、この悟性の専制や作為への反逆、自然な感情の開放として受け取られた。当時の小君主国によって分断され、現実生活におのおのが共通の活動権を持たなかったドイツにおいて、中産階級は、公的な中枢には入れず、政治に関与はできず、君主や旧勢力の閉鎖的な貴族たちに生活を保証される状態が続いていた。若きゲーテなどの中産知識階級もまた、モーツアルトやハイドンと同様の立場だった。そこにルソーの思想が到来し、精神的独立のための創作としての活動をはじめた。シュトゥルム・ウント・ドラングは、ゲーテの表現によれば、「私が生まれた文学上の時代は、抗議、抗言によって、それに先行する時代から展開したもの。」であった。その精神を今一度要約すれば、悟性に対し感情、合理主義に対し非合理主義、外的に規制された形式に対し内発的で根源的な生命力の自己主張ということであった。そして、その具体的な活動は、冷ややかな理論の展開ではなく、文学的作品によってなされた。ゲーテのシュトゥルム・ウント・ドラング時代の代表作は、「若きヴェルテルの悩み」である。ドイツ文学は、この策によって世界文学の舞台に登場し、フランス、イギリスなどにロマン主義の要因となった。ゲーテは、この「若きヴェルテルの悩み」によって、若者が能動的な意欲持ち、虚飾を排し、事故の内部から涌き出る感情を重んじ、本来の自己の本質を重んじて生きようとすることを主張し、しかし、体面や慣習や利己心を持つ現実のドイツ社会がそれを許さず、その旧体制の犠牲となって滅びるという、反旧体制へ抗議したのであった。この「若きヴェルテルの悩み」をナポレオンが7度も読み、エジプト遠征にも持参し、ピラミッドの下でも読んだという事実は、当時の能力ある若者たちの希望の書でもあった。
このような、文学革新の形を取った、激しい旧体制への否定の爆発が、本来の意味の啓蒙思想による、新しい時代の道しるべとなった。ゲーテは、ベートーヴェンより21歳年長である、という事実には、大きな意味がある。ベートーヴェンは、シュトゥルム・ウント・ドラング時代を過去のものとして受け止め、その爆発的文学活動を冷静に見ることができる時代に生まれた。その点、ゲーテは、大きな社会情勢の変化の過渡期に、社会的に大きな影響を与え、ヨーロッパ全体にその存在を知られていた。
その後、ゲーテは、爆発的で刺激的な作品から徐々に抜け出し、古典主義を確立して行く。晩年の教養小説「ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代」の中に、次のような文章を見出せる。
「徳の最高のものとみなされているのは、<畏敬>であり、それを象徴して挨拶の形式も定められている。われわれの上にあるもの、天への畏敬、下にあるもの、地への畏敬、そして、われわれと共にあるもの、運命や苦労の畏敬である。この3つの畏敬から、自分自身への畏敬という最高の畏敬が生じます。また、この畏敬から前の3つの畏敬も出てきます。そして、人間は、その達しうるかぎりの最高のこと、つまり、自分自身というものを、神と自然が生み出した最高のものと考えることに到達するのです」(*6)
この思想こそ、カントが「実践理性批判」の中で、無窮の星空と共に自己の内部の道徳律を畏敬するといった理想主義の思想と、一致するものである。ゲーテの生涯を通じての彼の仕事は、近代精神に目覚めた人間のあり方を大きなスケールで見定め表現したことにある。自然を尊び、調和の精神を持っていたゲーテは、どんな時でも一面的な片寄りにおちいらず、人間の創造性、生産活動を重んじ、多くの知識階級に多大な影響を与えたと考えられる。
第2節 ゲーテの音楽感とベートーヴェンの評価
ゲーテと音楽についての著述は、思いのほか多い。ベートーヴェンの音楽をどのように評価していたかという問題の前に、ゲーテが総合的に音楽とどのように関わっていたか考察する。
まず、ゲーテは、音楽の主権を認めている。「音楽こそいかなる理性の近づきえない高みに立っている。そして、あらゆる物を支配しているが、その効果は何人も説明できない」(1831年)と述べている。その他、ベッティーナ・ブレンターノ(*7)との書簡やエッカーマンの対話集などから、ゲーテの音楽感や音楽体験は、次のように要約できる。
1. 騒音を嫌い、犬の鳴き声や騒がしい音楽を嫌った。
2. 詩作する時、口ずさんで歌っていた。その声も美しいバスであった。
3. ピアノとチェロを学んでいた。
4. 音楽を聴いた時が、いつも仕事がはかどる。と述べている。
5. 自ら作曲した。
6. 歌劇やオラトリオを愛した。バッハ、ヘンデルの宗教曲やロッシーニの歌劇をよく鑑賞した。
7. 理性的傾向の強い音楽を愛した。特に、バッハの作品は、実に簡単な問題と壮麗な詩的効果をもった、数学的作品であると言った。
8. 「色彩論」の他に「音響論」を書いた。物理学的音楽の源は人間性にあるとして、音楽家の耳があらゆる自然現象を支配する。と考えた。(*8)
1818年、若き神学者でアダルベルト・シェプケがゲーテの詩に作曲し、ゲーテにその作品を送り批評教示を求めた。特に、「音楽における模倣の限界」について質問したことに、ゲーテは、それに次のように答えている。「音楽家が直接に外的感覚を通じて受けるかぎり、音楽家が絵を描いてよいかという問いは無意味である。しかし、この外的感覚の力を通じて受けた感じを表すなら、描写してよろしい。音楽で雷鳴をうつすのは芸術ではない。雷鳴を聞いたときの感じを表すのは大いに結構である。同様に、安静、沈黙、否定なども音響で表し得る。心のうちを平凡な外的手段を用いることなしに気分に変えることは音楽の特権である」(*9)
ここで、このゲーテの音楽感とベートーヴェンの音楽感が完全に一致している点をみいだすため、ベートーヴェンの第六交響曲“田園”についてのベートーヴェン自身の記述を紹介する。(譜例2)
「この交響曲は、絵画的再現よりも感情の表現である。(Mehr Ausdruck der Empfindung als Mahlerei)つまり、音楽の主なる表現範囲は感情であり、音楽が現実なるものを写す場合、それが感情を用いて、そのできた作品が知らず知らず農地に、その根源を暗示するような特徴を帯びる場合は、絵画的要素が許される。音楽は、決して自然の音を模写してはならない。これが、自然の音に近ければ近いほど、芸術から遠ざかる」(*10)
ゲーテとベートーヴェンの音楽感の一致が、おのおの別な場所で語られていることは、興味深い事実である。この点において、根本的な音楽感は、この二人の芸術家において、同じであるということは重要なことであり、音楽美学上でも、強調されるべき事柄である。
譜例2 ベートーヴェン作曲 交響曲第6番“田園”より
第1楽章“田園に近づく喜び”より(小鳥の鳴き声)
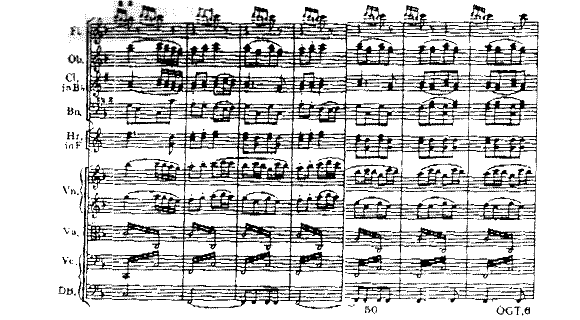
第2楽章“小川のほとりで”より(うぐいす、うずら、ほととぎす)
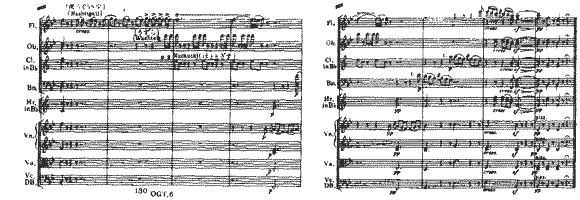
第4楽章“嵐”より(嵐)

第4楽章“嵐”より(閃光、驟雨)

ゲーテは、ベートーヴェンの音楽に対して冷ややかであった。音楽感は、似ていながら、ベートーヴェンが、ゲーテの作品を非常に高く評価し、ゲーテに対しても一生、尊敬の念を抱きつづけていたのとは対照的に、ゲーテは、ベートーヴェンの音楽に対しては、沈黙をし続けた。ベートーヴェンは、ゲーテの詩にいくつもの音楽を作曲し、それがベートーヴェンの歌曲の中での傑作にもなった。ゲーテがベートーヴェンに宛てた、「エグモント」についての表面的な書簡が残っているが、音楽の真髄に迫る内容ではない。理論的に考える時、ゲーテとベートーヴェンは、お互い才能を認め合い、良好な芸術のパートナーとなり得るはずであった。しかし、このベートーヴェンのゲーテへの尊敬と畏敬は、決して受け入れられることはなかった。
第3章 ベートーヴェンの作品とゲーテの評価
第1節 ベートーヴェンの精神性と革新性
ベートーヴェンの作品には、強い個人主義が見出される。個人主義とは、社会奉仕のための芸術ではなく、芸術のための芸術という概念、つまり、大衆に望まれた作品ではなく、芸術家が聴かせたい作品を書くということである。ベートーヴェンは、まさに、この概念を確固として持った作曲家であった。ベートーヴェンが活躍する10年ほど前の社会情勢は、ハイドンやモーツァルトの音楽を、一種の娯楽、あるいは典礼のためにあるという概念があたり前であった。注文によって仕事をする芸術家的職人であった音楽家の地位を、自由な自己表現をする教養ある芸術家まで高め、それを、ベートーヴェン自身の態度と作品の内容によって示し、それを定着させた。それは、それまでの音楽家とは、全く異なる芸術へのアプローチであった。ベートーヴェンの作品は、音楽家として特に悲劇的な事柄として扱われる難聴、金銭面や考え方の相違から来る兄弟との確執など実生活の困難から解釈されることが多い。ベートーヴェンを追求する上での資料として、難聴であったための筆談帖、「不滅の恋人」に宛てた物に代表される数々の手紙、ハイリゲンシュタットで書いた遺書などが残されている。それらの文献に現れる物語性のあるエピソード以外の部分に、ベートーヴェンの精神性と革新性の根源を見出す思想的観点を発見することができる。
ベートーヴェンの日記帳、筆談帳、スケッチ帳の中には、当時、ベートーヴェンがあらゆる書物を読んでいたことを示唆する書き込みが散見される。それらは、クローズアップされることが少ないが、ベートーヴェンの精神性、革新性の思想的根源を発見することができる。その中に、カントの書物からの抜書きがある。そのいくつかをあげると次のようである。
「原始の偶然の集合体が世界を形づくっているのではない。最も懸命な理性に源を発する、根源的力と法則が、世界秩序の恒久的な源となっているのである。世界秩序は偶然的ではなく必然性を持って理性に源を発しなければならぬ。世界秩序と美について明らかにされるものがあるとすれば、それは神である。美も神を基とすることでは世界秩序と少しも変わるものではない。世界秩序が一般的な自然法則に源を求めることができるのは、それは、全自然が最高の叡智の働きであるからである」(*11)
「いろいろの異なる諸惑星の住民たち、それだけでなくこれらの惑星上の動物や植物さえもが、それを形成している素材は、結局それらが太陽から遠く離れていればいるほど、それに正比例して、それだけ軽くまた繊細な種類のものでなければならぬ。またかれらの構造に特徴的な繊維の弾力性はますます完全でなければならぬ」(*12)
「考える自然の優秀さ、彼らの表象の機敏さ、彼らが下界の印象によって得る概念の明確さと活発さ、それに加えるにこれらの概念を合成する能力、最後にまた実践行動の機敏さも、要約すれば彼らの完全性をすべて包括する一定の規則のもとにあり、この規則に従って、これらの性質は、彼らの住んでいる場所が太陽からの距離に比例してより優秀になり、また完全になる。惑星の精神世界と物質世界の完全性は、水星から土星に至るまで、あるいは恐らくさらに土星を越えて(なお他に惑星があるかぎり)ひとつの正しい級数的な続きをなしており、太陽からの距離に比例して増加し前進して行く」(*13)
「二つの力、双方とも同じ大きさで、同じように単純で、同時に根源的で普遍的である力、すなわち求心力と遠心力」(*14)
上記のカントの著書からの抜書きから、ベートーヴェンは、カントの自然科学的概念に強い関心を寄せていることがわかる。この抜書きは、1817年頃の物と考えられる。同世代の新しい思想と哲学を著したカントを早速受け入れ、小さな世界観ではなく、宇宙にまで視点の幅を広げている。ベートーヴェンは、ボン時代の最後の数年、つまり、18歳〜22歳頃、ボン大学でこれらの新しい哲学を学んだと考えられる。当時のボン大学のシュナイダー教授、フィッシェニッヒ教授が講義をしていたが、彼らは二人とも、カント哲学に精通し、カント倫理学を講じている。それらの事実と筆談帖への抜書きから考察すると、ベートーヴェンの音楽の革新性は、当時のフランス革命などの実際的な事実からより、自己を高め普遍的な道徳の原理に至るというカント的思想から起こったものと考えられる。ベートーヴェンの作品は、常に「革新的」または、「革命的」といわれるが、その思想の根源には、カントに代表される啓蒙思想からの影響が大きいのである。
第2節 ゲーテとの関わり
ベートーヴェンは、年上のゲーテを深く尊敬していた。21歳の年齢差があるため、ベートーヴェンは、幼少の頃からゲーテの作品に親しみ(*15)、心の糧にしていた。1810年5月、ベッティーナ・ブレンターノとの会談の際、彼女に語った言葉が残っている。
「ゲーテは、生きている。そして、われわれは、彼と共に生きなければならぬ。彼の作品は、実によく音楽になるのだ。彼ほどその作品が音楽になるものはいない」(*16)
その他にも強い口調で、ゲーテとの会談を、ベッティーナに依頼している。
「私のことをゲーテに話してください。是非、私の交響曲を聴く必要があると彼に言って下さい。音楽こそ、人間を覆い包んいて人間には、補足することのできぬ知識に、いっそう高い世界に入る唯一の形なき入り口であるという、私の意見にゲーテは賛成するでしょう。精神が感覚によって音楽から受け取るものは具象化した精神的な啓示です。私のことを理解してくれるなら、ゲーテに私のことを書いてください。そしてまた、彼から教えを受けることを心から願っているのです」(*17)
ベートーヴェンは、音楽になるすばらしい文学的な台本を探し求めており、その理想的なものとして、ゲーテの作品を音楽への近親感を持ってとらえていた。1808年には、ゲーテの「ファウスト」を劇に改作できる人物を探していた。結果的には、他の交響曲やオラトリオに時間をとられ実現しなかったが、ゲーテの傑作「ファウスト」にも音楽化に強い関心を寄せていた。その他にも、たくさんのゲーテの詩に音楽をつけている。
ゲーテに実際会うことができるなどとは思いもよらない若い時期、1796年以前にもすでに「五月の歌」(Maigesang)を書いているし、1808年には、「ミニヨン」(Kennst du das land)、ゲーテの小説「ヴィルヘルムマイスターの修業時代」第三部の冒頭、ミニヨンの歌にも作曲している。(譜例3)ベートーヴェンは、1795年のこの小説の初版本を持っており、この小説全体も読んでいた。1809年には、宮廷劇場から、ゲーテの悲劇「エグモント」を依頼される。このような時期に、ベッティーナ・ブレンターノとの出会いがあり、ゲーテとの会談が、現実味を帯びてくる。
1812年7月、チェコのテプリッツで、ベートーヴェンとゲーテは、実際に会談する。ベートーヴェンは、ゲーテの作品から、自分と同じ思想を持ち、同じ精神性を備えた人物として大きな期待を持っていた。二人は、同年7月19日に、ゲーテがベートーヴェンを訪問するという形で、はじめて出会い、翌20日も共に散歩をしている。21日も、23日もゲーテはベートーヴェンを訪れ、その際ベートーヴェンは、ゲーテのためにピアノを弾いている。(*18)ゲーテが妻に宛てて書いた手紙には、ベートーヴェンについて、「私はこれまでに、これほど強い集中力を持ち、これほど精力的で、これほど内面的な芸術家を見たことがなかった」(Zusammengefasster,energischer,inniger habe ich noch keinen Kuenstler gesehen)(*19)
このように残された手紙や日記によって、ベートーヴェンとゲーテは、同じ精神性を持った偉大な芸術家同士として親交を深めたように思われるが、その後の人間関係は、良好とはいえない事実が浮かび上がる。ゲーテは、ベートーヴェンの音楽を、ベートーヴェンが感じてほしいようには理解しなかった。そのテプリッツでの会談の後は、彼らは、二度と会うことはなかったが、ゲーテのベートーヴェンに関する記述は、辛辣なものとなり、反ベートーヴェンの音楽愛好家のベートーヴェン批判に同調したり、(*20)ミサ・ソレムニスについてのベートーヴェンの依頼にも、全く応じなかった。(*21)
一方、ベートーヴェンは、ゲーテに対して、非常に革新的な、まさに、新しい思想を持って、貴族や王族に毅然とした態度を取るべきだと諭した。啓蒙主義の時代とはいえ、ウィーンの社会情勢は、まだ貴族たちが、歴然と存在しており、フランスのような市民運動には発展していなかった。しかし、ベートーヴェンは、そのような旧体制に対し、貴族の使用人の立場であることは、実際的にも精神的にもなかったため、優れた芸術家は、王族、貴族にへつらう必要はないと確信していた。ゲーテは、そのようなベートーヴェンの態度を無礼と感じ、傍若無人であるといっている。ベートーヴェンとゲーテは、作品のみでなく、人間同士の付き合いとして、思想や芸術性には関わりない「性格」や「人間性」の部分で相容れないことになってしまったのである。ベートーヴェンが一生尊敬しつづけた人物という観点から、ゲーテを見なおした時、そこに現れる事実は、ベートーヴェンの一方通行の尊敬ということばかりであった。
結論
ベートーヴェンとゲーテは、同世代に生きた偉大な天才である。250年経った現在も、この二人の業績は、輝かしいものである。その個々の作品は、社会において広く受け入れられ,人間の生きる糧になっている。考察をした彼らの生きた啓蒙主義時代というヨーロッパの思想的大変革の時代を深く研究する必要があった。
啓蒙主義の発芽は、18世紀の初期であり、発芽期の新しい思想は、徐々に熟成し、カントからドイツ観念論に至るわけである。この間、100年もかかっていない。ゲーテは、83歳まで生きたので、その思想の発芽期から成熟期のすべての流れを体験することになり、若きゲーテは、反啓蒙主義の流れといわれる、シュトゥルム・ウント・ドラングの中心的活動をした。その思想は、やがて啓蒙思想が市民階級まで浸透し、結果的には近代思想と呼ばれるようになる根源となる。ドイツの旧体制の中で、抑圧された精神状態を体験し、その抑圧からの脱却として、自然の感情を素直に表現する文学を創造した。
近代思想の入り口の時代に生まれたベートーヴェンは、シュトゥルム・ウント・ドラングの時代が終わり、社会は近代国家に向かう時代に生き、芸術家として独立した存在を主張することができつつある体制で、独自の生きかたを推し進めることができた。皇帝にも貴族たちにも、けっしてへつらうことなく、芸術家の尊厳を持ちつづけた。若きベートーヴェンは、ハプスブルク王家が統治するウィーンではなく、フランスに近いボンで、啓蒙思想が花開いた時代に、大学でカントを学ぶこともできた。最も感受性の強い青年期に、そのような思想の中で教育を受けたことは、後のベートーヴェンの創作に多大な影響を与えた。ボンから、音楽の才能だけを持ってウィーンにやってきたベートーヴェンは、最初から、王室や貴族の内部に入りこまず独自の活動を始めるのである。この行動は、それまでの音楽家の地位を、根底からくつがえすもので、決して権力に屈しないベートーヴェンの生き方は、自然と社会に受け入れられるようになったことを述べた。
このベートーヴェンとゲーテの社会情勢の僅かな差が、お互いの人格や性格的な部分に違和感をあたえた。その上、21歳も年少のベートーヴェンは、ゲーテの権威に屈するような振る舞いを非難し、意見を述べている。年長のゲーテは、それに対して、ベートーヴェンを無礼な人物として、敬遠してしまう。このようなすれ違いによって、結局、同じ新しい感覚と思想を持った、才能ある芸術家は、わかりあえることがなかった。
ベートーヴェンとゲーテの比較から、芸術の本質が見えてくる。ベートーヴェンもゲーテも全世界を代表する芸術家であることをあげた。芸術作品を創作し、その作品は、高度な技術と高い思想的観点からの裏づけがあり、人々の人生の糧となるような社会的にも意義の深いものである。そのような選ばれた才能を持つ芸術家でさえも、別な分野の芸術や、当時は新しいといわれる、進んだ芸術表現に対して、単なる感情的な受け止め方をしたことをあげた。ゲーテは、新しい芸術の先駆者として自認しながら、こと音楽に関するかぎりは、保守的で牧歌的な音楽から抜け出ることができなかった。つまり、ゲーテは、ベートーヴェンの音楽を、彼の才能は、認めながらも、進歩的な音楽形式、音楽表現などをよく理解していないと考えられる。ゲーテ自身が文学の分野では、最も前進的であった事実とは矛盾するが、この矛盾は、現在でも、芸術鑑賞、芸術批評にも見ることができる。ゲーテが、当時、ベートーヴェンを正当に評価しなかったことは、現在の楽聖ベートーヴェン像に、全く影響はなく、むしろ、文豪ゲーテは、音楽がわからなかった、という定説ができあがっている。
このベートーヴェンとゲーテの芸術を比較する時、カントの音楽美学の概念が、重要な意味を持つ。カントは、広義の美的判断(規定の基盤が主観でしかありえない判断)を趣味判断(美を対象とする判断)や芸術判断(趣味判断を越えて芸術作品の文化価値へ向かう判断)から区別している。音楽と哲学を結びつける音楽美学は、哲学的に基礎付けられた音楽史的現象と考えられる。音楽をめぐる直感としての音楽美学は、哲学の問題設定からから生まれ、文化体系の中で音楽の位置を新たにした。ゲーテは、カントの音楽美学の概念に近いものを感じていたと思われる。カントは、音楽美を「感覚の単なる遊び」ではなく、「音楽の躍動における比率という数学的なもの」と「音階における緊張の多様性による質的な変化の知覚」と考えた。音楽を形式美が高度でない場合、感覚的に快適な作用として解消されているかぎりは、文化になり得ないと説いている。しかし、芸術に対するとき、カントが言うような概念や理論が正しいということはできない。芸術も哲学も、正しい答えなどないからである。
旧体制から、近代思想への大きな時代の変化の時期に現れた、二人の偉大な芸術家が、新しい思想、新しい社会情勢の中で、革新的な創作活動をしつつも、芸術の批判や受ける感覚は、現代と変わりなく、普遍的な評価などはどこにもないということなのである。
原注
* 1 音楽はどう思想を表現するか フィンケルシュタイン著 田村一郎訳 三一新書
* 2 同上
* 3 Mozart Alfred Einstein
* 4 西洋哲学史 野田又男 ミネルヴァ書房
* 5 芸術哲学(形式と理想) 木村 素衛 河出書房
* 6 ヴィルヘルムマイスターの遍歴時代
* 7 ベッティーナ・ブレンターノは、ゲーテのかつての成就しなかった恋人の娘であ り、18歳の時ゲーテと会い、その後、後に絶縁するまで、親蜜な交際をする女性である。ゲーテは、若きかつての恋人の面影をベッティーナに見て、数多くの手紙のやりとりをしている。ベッティーナの意見や願いをゲーテは、いつも聞いていた。1810年、ベートーヴェンをウィーンに尋ねてから、ベートーヴェンの音楽に傾倒し、ベートーヴェンが尊敬するゲーテとの会見を実現させようと努める。
* 8 音楽芸術論 村田武雄 音楽文庫
* 9 ゲーテと音楽 石倉小三郎 堀書店教養叢書
*10 同上
*11 ベートーヴェン音楽ノート 小松雄一郎 岩波書店
*12 同上
*13 同上
*14 同上
*15 ゲーテとベートーヴェン ロマン・ロラン 潮文庫
*16 同上
*17 同上
*18 ゲーテの日記 ゲーテ全集 潮出版社
*19 同上
*20 ゲーテの信望者で音楽教師だったツェルテルは、ベートーヴェンの音楽を全く理解せず、常に、ゲーテに対して、ベートーヴェン批判をした。一説には、ツェルテルの助言が、ゲーテのベートーヴェンに対する態度の影響を与えているといわれる。
*21 1823年、ベートーヴェンは、ミサ・ソレムニスの出版に際して、ヴァイマール大公とゲーテにこの曲の予約を依頼してほしい旨の、長文の手紙をしたためる。内容は、尊敬と敬意に満ちたものであったにもかかわらず、ゲーテは、それに対して、一切返事を書かなかった。ヴァイマール公も予約者にはならなかった。
参考文献
ベートーヴェン音楽ノート 小松雄一郎 岩波書店
ベートーヴェンの手紙 小松雄一郎 岩波書店
ゲーテとベートーヴェン ロラン 潮出版社
音楽の発見 ピゲ ムスルジア全書
音楽社会学序説 アドルノ 平凡社
芸術哲学入門 ラコスト 白水社
西洋哲学史要 波多野精一 角川書店
芸術の哲学 オルドリッチ 培風館
芸術哲学 植田寿蔵他共著 河出書房
西洋哲学史 野田又男 ミネルヴァ書房
音楽芸術論 村田武雄 音楽之友社
音楽はどう思想を表現するか フィルケンシュタイン 三一書房
ドイツ文学史概説 上村清延 福村書店
音楽と思想 シクラ 三一書房
学生と語る 阿部次郎 角川書店
鳴り響く思想 大宮眞琴他共著 東京書籍
ドイツ文学案内 手塚富雄 岩波書店
西進し押しての音楽史 野村良雄 ムスルジア全書
ベートーヴェンの美学 グリーン 剄草書房
ベートーヴェン辞典 平野昭他編 東京書籍
ゲーテ的世界観の認識論要網 シュタイナー 筑摩書房
ゲーテとの対話 エッカーマン 岩波書店
ゲーテの世界観 ジーベック 理想社
古典的・ロマン的音楽美学 ダールハウス
純粋理性批判 カント 岩波書店
