|
|
設立の趣旨 | 全作品目録 | 精選作品目録 | 紫花人形作品目録 | 編者 |
 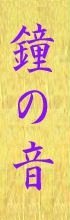  |
| 「白梅」の琴演奏で物語が始まり,次に場面は歌舞伎「京鹿子娘道成寺」舞台の幕が上がると登場(道行き)する白拍子の華やかで綺麗な姿と成っています。一途に純粋に燃える女心を明るい舞台を連想さす端正な姿で表現しています。桜満開の春に萌え上がる女性の情念が赤紅色の着物に純白の裏地、桜の模様に伝統的な品格が伺えます。着物に対比して黒色の結び下げた長帯、頭に戴く金色の小さな立烏帽子が前に傾き可愛いです。腕に持つ桧扇を前に突き出す白拍子の姿に強い意思を感じました。凜とした淑(シト)やかで美しい人形での表現は、演劇や映画でも及び難い作者の胸中に映じた雅な姿でした。女性は憧(アコガ)れる
相手に対して変幻自在に優美で品格が有る姿として表現されています。 芝居では一人の役者が早変わりで衣装を着替えて登場するのと同じです。源氏物語に書かれた女性も同様に求められた麗しい幻影です。生得の素養と資質を兼ね備えている人物こそが作者で、紫式部なのです。人形を虚像でなく現世の優しく美しい女性の姿として観たいものです。舞台伴奏の長唄から「諸行無常、寂滅為楽」の歌詞が響きます。 僅か三寸の美しい人形は腕を伸ばせば触れる程に顔を近付け凝視するものでした。人形の着物や小道具も全てが優雅で高尚な品格ある女性を表現しています。着物は作者の家系に伝承された高雅で貴重な時代を経た生地を素材として使っていました。 「鐘に恨みは数々ござる」という道成寺からの表現です。女性の生命の火が妖しく燃えるようです、それは一つのドラマです。 その情念は妖しく変わっていくものです。ここから物語が始まります。これ一場面だけで全部を表現しています。女性の喜びや悲しみを萬空の想いの内に 表現しています。踊りの姿を表現する事は難しいものです。静から動へ移りゆく姿を描かなければなりません。それから、再び静へ戻るような動きを表現しなくてはなりません。 悲しみの中に耐えていく姿が文学(人形)になるのです、悲しみを慰めてくれるのが文学です。このような生活の中で作品(人形)が創られているのです。 展覧会は正月ですから、道成寺から始めます。きっと人を泣かす作品になると思います。人形の衣装には百年以上前の布もあります。祖母の集めた布も在りますから、三代懸かりになっています。出品は十七許りですが、本当は三十位で女の一生を表現したいものです。夏なら、いろいな表現が出来ますが、冬はたくさん着込みますから、表現が限られて難しいものがあります。 展覧会では、多くの人々の心を受けました。それに対しても今後も精進しなければならないと、決意をしています。名も知らない人からも随分と心を戴きました。人形には清らかな魂を捧げて参りました。夜中人々が寝静まった、一時を、身も心も清めて作品を創って参りました。日本女性の魂を喚(ヨ)び起こす使命を帯びて生きています。この深い願いを理解してほしいものです。私の生涯は多くの人々に守られて参りました。 |
