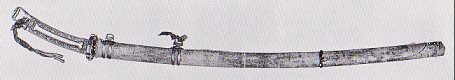
| 拵あれこれ |
拵(こしらえ)の役割や、各部名称については「拵と白鞘」で書きましたが、ここでは特徴的な拵について、少し触れてみましょう。
※甲冑と武器にも各時代の武用の拵の解説があります。
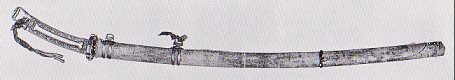
平安時代に衛府(えふ)の役人が帯びた太刀です。衛府とは皇居護衛の役所のことです。別名を「毛抜形太刀(けぬきがたたち)」と言います。図で見える柄(つか/握り手)の真ん中の透かしが毛抜形になっています。毛抜を左右からくっつけたような形からこう呼ばれます。
この太刀の特徴は、刀身と柄(つか)が一体になっていて(共柄/ともづか)、鮫皮(さめがわ)や柄巻きを施さず、中心(なかご)自体に毛抜形の透かしを施している所です。中心の両面に唐草彫りを施した銀板(これも真ん中は毛抜形に透かしてある)を当て、銀などの縁(ふち)、頭(かしら)、覆輪(ふくりん)で固定します。
中心に透かしを施したのは、刀身とのバランスを取るため、柄が直接中心なので、打ち下ろした際の衝撃をやわらげるためなどと言われます。また、この太刀は中心自体にも反りがあり、これは馬上から地上に居る敵を斬り倒すのに適した形になっています。
鎌倉時代になると、どうしても敵に打ち下ろした際に手に響くのか、実用の座からははずされ、奉納刀などに使われました。江戸時代にも形式は受け継がれ、五位以上(江戸考 武家の世界 参照)になると、狩衣(かりぎぬ)に太刀を許され、儀式時には公家の佩く(はく)蒔絵の太刀に真剣を入れて衛府太刀と呼びましたが、中心を毛抜形に透かすのではなく、普通に中心に柄(つか)を入れ鮫皮を巻き、毛抜形の目貫(めぬき)を据え、柄巻きは施さず、幾つか俵鋲(たわらびょう/頭の大きなクギのような留め具)を打って鮫皮を固定してあります。
太刀とは違って、刃を上にして帯に差す式の拵です。時代劇で武士が腰に差しているものです。太刀は甲冑の隙間から突くのを主としていますが、打ち斬ることを主眼に置いた刀の拵で、室町頃から流行しました。
打刀拵に太刀拵を加味した様式のものです。足金物(あしかなもの)と足緒(あしお/太刀の鞘にある、帯から吊り下げるための金具と紐)を取り外し、帯に直接差せるようにしています。冑金(かぶとがね/柄の先にある金具で刀で言う頭)、石突(いしづき/鞘尻にある金具)、責金物(せめかなもの/鞘の補強用の金具)などが付いています。後にこの様式から道中差し(どうちゅうざし/庶民が旅行中などに持つことが出来た脇差し)になっていきます。
室町時代に生まれた打刀拵の発展版です。室町末期から江戸初期にかけて流行しました。立鼓形の柄(りゅうご:目貫側から見たときに、真ん中が細く、頭、縁側が太くなっているもの。輪鼓とも書きます)で、鮫皮を巻いて黒漆をかけ、皮で柄巻きしたものが多く、柄が鐔(つば)の所で急に曲がっているので、「へ」の字形になっています。栗形(くりがた)や返り角(かえりつの)も大きめです。
江戸時代の武士が、公式の場で指す大小で、裃指(かみしもざし)、殿中指(でんちゅうざし)とも言われます。柄(つか)は鮫皮で包み、目貫は金無垢(きんむく)などの豪華なものを使い、頭(かしら)は水牛の角製、柄紐は掛巻き(頭に筋違いに掛けて巻く)、縁(ふち)は赤銅魚子地(しゃくどうななこじ/数の子のような小さなつぶつぶを打ち込んである)、もしくは磨き地で無紋または家紋を入れ、鞘は黒呂色(くろろいろ/ツヤのある真っ黒)塗りとなります。
鐺(こじり/鞘のおしり)は大刀は角製で一文字形(いちもんじけい/まっすぐな形)、小刀は丸鐺(まるこじり)となります。鐔は赤銅地(しゃくどうじ)の碁石形(ごいしがた/碁石のように真ん中に厚みがある)、大刀には小柄(こづか)と笄(こうがい)、小刀には小柄のみを付けます。小柄、笄、目貫は後藤物(ごとうもの/室町から江戸時代までの将軍家お抱え金工)を使用します。上級武士は、高価な鮫皮を見せるために、柄巻きの菱を少なくしたりしたようです。
江戸時代の武士は、格式によって服装や、指料(さしりょう/身に付ける刀)が変わります(江戸考 武家の世界 をご覧下さい)。直垂(ひたたれ)には出鮫合口拵(でさめあいくちごしらえ/上の写真参照)、狩衣(かりぎぬ)には無腰(むごし/何も帯びない)、大紋(だいもん)・長袴(ながばかま)には小さ刀(ちいさがたな)を使用します。小さ刀というのは脇差で、柄巻きを施し鐔も付けますが、番指と違って鐺は一文字とし、小柄・笄を付けます。小さ刀という名から短刀と誤解されますが、様式が違います。なお、有名な『忠臣蔵』で、浅野内匠頭(あさの たくみのかみ)が江戸城の松の廊下で吉良上野介(きら こうずけのすけ)に斬りつけた時の服装が長袴で、その時内匠頭が使ったのが小さ刀です。
肥後藩主細川三斎の創作拵で、茶道の感覚と居合の実用性が兼ね備えられた堅牢を主とした作りになっています。寸法的には二尺二寸くらいの短い物が多く、柄も七寸くらいの短い物が多いです。これは抜き打ちに適した寸法で、柄が短いので片手打ちに向いています。片手で切り込むと、両手で切り込むよりも刀の届く距離が延び、居合に有利となります。
金具は肥後の金工作の鉄物が多く、柄は短く立鼓を取り、頭(かしら)は縁(ふち)側より小さく、鮫皮でくるんで黒漆を掛けます。柄巻きは紐ではなく鹿の皮で巻き、漆を掛けることもあります。
鞘も鮫皮でくるむことが多いのが特徴です。ただし柄の場合と違い、粒々を残さずに研ぎ出しています。鐺(こじり)には鉄の泥摺りという金具を付けます。返り角も栗形の上側を向くように角度が付けられています。小柄は希で、馬針(ばしん/小柄の形に似た共柄で、馬の足の鬱血を取る時に用いる)を用います。
他国の武士もこれを見習う物が多く、幕末には江戸を中心に流行し「江戸肥後拵」と呼ばれ、区別されるようになります。肥後拵には「信長拵」、「歌仙拵」、「希首座拵」、「清正公網代鞘短刀拵」、「宮本武蔵の和泉守兼重の拵」などがあります(下記をご覧下さい)。
肥後藩主細川三斎の愛刀・越前国信長の刀に付けた拵です。田村宗徳作の金具に、はばきは銀と金無垢の二重はばき、鞘の鐺には鉄の泥摺が付いています。小柄は千利休に相談して作ったそうです。鐔は藩工である西垣勘四郎作で、鉄地に海鼠透かし(なまこすかし)になっています。
細川三斎の脇差「歌仙和泉守兼定(之定)」の拵です。三斎隠退の際に奸臣(かんしん/悪だくみをする家臣)三十六人を斬ったことから、三十六歌仙にちなんで付けられた名前です。肥後拵の典型作として有名です。鞘は鮫鞘で中央近くまで印籠刻み(いんろうきざみ)になっています。
希という京都大徳寺の首座(高僧)を、熊本藩主細川忠興が手討ちにした脇差の拵です。
加藤清正所持の短刀拵です。豊臣秀頼が二条城において、徳川家康と会見の際に、清正が懐に忍ばせていたと言われる短刀です。熊本本妙寺蔵で中身は「備州長船祐定作 天正十年二月日」です。目貫は金銀赤銅の土筆(つくし)が二本の図です。鞘は腰刻みで下は網代(竹を細かく剥いで網状に組んだもの)を着せて漆付けにしてあります。返り角は四分一(しぶいち)の木瓜(もっこう)形という高尚で精巧なものです。
宮本武蔵晩年の差料(さしりょう/愛刀)、和泉守兼重(のち上総介)の拵です。1645年没後、二天流を継いだ寺尾信行が武蔵の養子である小倉藩重臣宮本伊織に大小を送りましたが、脇差のみを受け取り、大刀を送り返してきました。明治期に寺田家はこれを戸下温泉主人である長野某(なにがし)に譲りました。元は柄巻きは馬の革で巻いて漆を掛けてあったのを、この長野某が糸巻きに変えてしまっています。鐔は武蔵作と言われる素銅の海鼠透かし(なまこすかし)鐔(写真右)です。
薩摩島津藩の拵です。島津家の刀装に使われる赤銅(しゃくどう/銅に鉛、亜鉛、金を加えたもの)は金性が良いと言われ、いざというとき金を吹き分けて軍資金にするためなどと言われます。島津家の伝来品は愛好家の垂涎の的となっています。
ところが、島津藩の薩摩拵は実用一点張りのものです。薩摩藩は示顕流(じげんりゅう)であり、これは一撃のもとに敵を倒すというすさまじい剣法ですが、これに適した造りとなっています。
柄は太く長めで立鼓はあまり取らず、鮫皮の代わりに厚い牛革で巻き、黒漆を掛けます。巻きは紐または革で巻き目貫はほとんど使いません。縁頭(ふちがしら)はほとんど鉄製で、特に縁は深く作られています。栗形も変わっていて、下の写真のように凸形になっています。また鐔は小さくなっています。これは示顕流の特徴である刀の物打(ものうち/刀で斬る時、最もよく使う刃の切先寄り部分)に重心をかける工夫だと言われています。
薩摩藩では平常は決して刀を抜かず、やむを得ず抜いたときは必ず相手を仕留めよという戒めがあり、薩摩拵の鐔には小さな穴が2個空いていることが多く、これは「拵と白鞘について」の鐔で説明した手貫緒(てぬきお)ではなく、これに針金(後に元結/もとゆい)を通して栗形と結び、鞘走り(さやばしり/うっかりと刀が抜けてしまう事)せぬようにするものです。凸形の栗形もいざという時、鞘ごと抜いて敵を打ち据えるということを想定したための形になっています。
尾州徳川家の剣術指南、柳生連也斎(やぎゅう れんやさい)の差料の拵です。柄巻きは浅黄色(あさぎいろ)の紐で大は十三菱、小は八菱に巻きます。目貫は大が「かごつるべ」の文字の容彫り(かたちぼり)で、逆目貫(ぎゃくめぬき/表を頭寄りに、裏を縁寄りに置き、普通とは逆にする)とし、小は「笹露」という文字の容彫りを普通に置いています。鞘は黒呂色塗りの三分刻みとなっています。
ちなみに、「かごつるべ」とは連也斎の愛刀である大小拵の大刀である「肥後守泰光(以下切れ)」であり、その中心裏に「かごつるべ」と切ってあり、「笹露」は同作の脇差しで中心裏に「笹露」と切ってあることから来たものです。
図版は小窪健一著「刀装のすべて」(光芸出版)より抜粋。