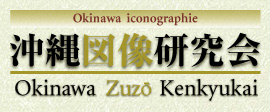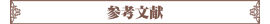【図像解釈学 イコノグラフィー/イコノロジー】
図像解釈学はイコノグラフィーとイコノロジーの両方に宛てられる日本語である。一般的にはイコノグラフィーが「図像の分析/分類」であるのに対してイコノロジーは「図像のより深い概念的、象徴的解釈」であるとされるが、現時点でもその二つの間の区別は必ずしも厳密ではない。
寓意的歴史的研究においては、イコノグラフィーの第一の限定的な意味は、図像(イメージ)の記録である。古代のメダルや貨幣などの肖像は、近現代における写真や映像記録と同様のドキュメントでありうる。
19世紀後半には考古学の発展により諸古代文明に関する知識が増大し、イコノグラフィー研究はそれに伴って、美術史の中でより歴史的、科学的厳密さを獲得する分野として発達した。19世紀の時点でイコノグラフィー研究は、特に概念的内容に満ちている初期キリスト教美術の分野では、主題の叙述や分類にとどまらず象徴的、寓意的解釈にまで広がっており、現代的意味でのイコノロジーやイコノグラフィーその双方を包含するようなものになっていた。
20世紀初頭には、美術史の中で急速に擡頭していた「純粋可視性」の概念や純粋な「形体主義(フォーマリズム)」批評の流れに対抗する形で、芸術作品の美的価値だけでなく、それが属する文明の宗教的歴史的価値に注目し、内容をより深く理解しようとする複雑な研究へと進める動きが生まれた。これが近代的概念のイコノロジーであるが、その発生にはドイツ語圏の学者たちの大いなる寄与があった。
ヴァールブルク文庫という私設図書館をハンブルグに設立したヴァールブルクがイコノロギー(Ikonologie)という言葉を現代的意味で最初に使ったといわれている(「イコノロギー的分析」という形容詞の形であったが)。彼の目指したものは民俗学、民族学、人類学、心理学など様々な学問分野を横断してイメージというものを考察することであった。ヴァールブルクの助手を勤めたザクスル、ビング、ヴィントなどによって文庫は引き継がれたが、ナチの迫害により、1933年ロンドンに移り現在はロンドン大学附属のウォーバーグ研究所となり、思想史研究、図像学研究の中心地となっている。次世代のエルヴィン・パノフスキーは、イコノロジー研究を独立した一学問分野にまで高めようとした。パノフスキーはナチの迫害を逃れ、1933年アメリカに移住する。ヴァールブルクをはじめとするイコノロジーの研究者のほとんどがユダヤ人であり、そのためにイコノロジー研究は、研究者が移住したイギリス・アメリカなどのアングロ・サクソン系の国々へとその中心地を移した。第三世代のエルンスト・ゴンブリッチは2001年に没するまでウォーバーグ研究所所長を務めた。パノフスキーが最後に教鞭をとったプリンストン大学にはキリスト教図像研究のためのインデックス・オブ・クリスチャン・アートが置かれている。また同様に広範な図像分類のシステム「イコンクラス」はアムステルダムで編纂された。
歴史学の分野からも、図像資料を単なる記録(ドキュメント)として扱うのではなく、積極的に図像解釈学研究へアプローチしようとする動きがある。まずフランスのアナール派の研究者たちは、より広い意味でのイマジネールの世界、心性(マンタリテ)の世界を扱う多くの研究を行っている。イタリアのカルロ・ギンズブルグやキアラ・フルゴーニなどの歴史家もアナール派やウォーバーグ研究所への接近を通して積極的に図像解釈的研究を行っている。日本ではまず黒田日出男氏などを中心に主に中世史家たちによる図像学的な試みがなされている。また多木浩二氏なども思想史の分野から、主に近現代を中心にイメージ分析を行う先鋭的研究を行っている。
【沖縄図像研究会の図像学的アプローチ】
本研究会は、従来沖縄研究の中で重要視されてこなかった図像に光を当て、まずはそれらの存在を広く知らしめ、それを美術史の観点から研究することを目的としている。これらの図像の多くはたとえば王家のお抱えの絵師などによって描かれた傑作だけに限らず、美術的価値の面や様式の面からの研究よりは、それらが担ってきた機能や意味とその変遷を探ることが研究の中心になるため、図像(解釈)学的なアプローチが取られることになる。
現在まで調査してきた図像は、先述のように、観音を含む仏教系のもの、関羽などの道教/儒教系のもの、神道神や大和の信仰にかかわるもの、沖縄固有の信仰に関するもの、吉祥図像、その他の部門に分類してきたが、これらを分類、解釈をする図像学的研究に際して、従来のいわゆる図像学の方法がそのままの形で採用できるのかどうか、いくつかの点について再考の必要がある。民間信仰の場合にはありがちなことであろうが、特に沖縄の場合は、拝所に置かれる図像が、その図像の本来の持つ意味において正しく理解され、信仰されているとは限らず、また、沖縄の伝説などに基づいて新たな図像が制作されるような創作系の図像の場合には、図像の着想の源泉を意味内容にかかわらず既存の他の図像に求めていることも多く、それらの要素を解きほぐして正しく図像メーキングの実態に迫るのは容易ではない。ある意味で図像解釈学の耐用性が問われる場でもある。
【沖縄の図像の解釈学的研究の方法について】
西洋美術研究においても、イコノロジーもしくはイコノグラフィーという名で呼ばれる図像(解釈)学研究は、様々な形で修正を加えられ新しい動向が示されている。
たとえばロマネスク彫刻についてのマイケル・カミールの論文中では、従来のロゴセントリックなイコノロジー・イコノグラフィー研究を越えるようなアプローチが試みられている。その一つは、図像プログラムを作成する側とそれを受容する側の間で共有されていた意味のコード体系の枠外にある鑑賞者の存在をも考慮するということである。彫刻のように特に三次元的でそれに対峙したときのインパクトがより直接的に五感に訴えるようなものでは、図像の表すもの、意味するものとはまた別の、「恐ろしい、可笑しい」などの感情が呼び起こされる。多くが農民であったり巡礼者であったり必ずしもキリスト教の教養を身に付けているとは限らない鑑賞者にとっては、たとえば教会堂の扉口に施された丸彫のライオンなどが哀れな動物を今にもその歯牙にかけんとする様は、必ずしもキリスト教の教義に則った意味コードに照らし合わせて理解されたのではなく、そこに呪術的な意味が見いだされたり、ライオンの牙に切り裂かれ、飲み込まれる痛みという身体感覚などが呼び覚まされたかもしれない。
拝所などに安置されている沖縄の図像群は、それが重要であるという認識やそれらが家の守り神であるというような認識があることを除いては、その意味するところや由来などについて正確な伝承がなく、図像本来の持つ意味が正しく理解され、伝えられ信仰されているとは限らないようである。その意味で、外在するあるテキストにその図像解釈の根拠を求める従来の「ロゴセントリック」な図像解釈学では信仰の実情が捉えきれない。図像だけは次々に継承されながら、それを守り伝えてきた共同体が、正確で十全な意味を伝えてこなかったがために、図像から別の感情を引き起こされたり、あるいは自身や共同体のイマジネールの世界に照らし合わせて意味の再解釈を行なったり、テキストと図像との不一致などを招いているケースが見られる。
また、沖縄では夢などでお告げがあった内容を図像化したり、ユタなどの指示に従って図像を制作すること、大戦中に消失してしまった軸や額などの図像を戦後に記憶を頼りに描き直させるということが頻繁に行われてきた。それゆえに、沖縄の図像研究は共同体、ユタの信仰、組織体系などのイマジネールの世界をも解き明かす鍵にもなると思われる。沖縄の図像は、その本来の意味と現在賦与されている意味との間にズレがあり、また沖縄の現在の信仰の中でそれが果たしているアクチュアルな役割は、仏教、道教、儒教、あるいはキリスト教の教義に基づいて図像体系を読み解くといった狭い意味の図像解釈では捉えきれない。「言葉」と「イメージ」の関係という根本的な問題にまで発展しうる沖縄の図像研究は、ある意味でヴァールブルクが目指したような、民俗学、民族学、人類学、心理学など様々な学問分野にまたがるような広い意味でのイコノロジー研究の格好のフィールドであると思われる。
copyright (c) 2009 沖縄図像研究会 All Rights Reserved.