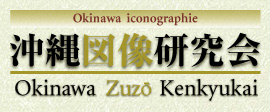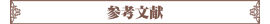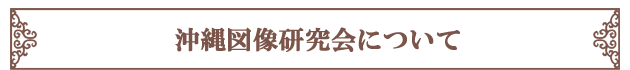
沖縄図像研究会は、沖縄県立芸術大学芸術学専攻所属の教員二名、当時の同大大学院修士課程比較芸術学専攻学生、科目等履修生を中心に1999年に発足した。
メンバーはそれぞれ日本近代美術、西洋中世美術研究、中国・韓国の民間図像研究、美術製作・沖縄の美術状況研究などを専門としているが、
沖縄の歴史文化研究、民俗学研究などの成果において図像がほとんど資料として扱われていない状況に、皆多少なりとも疑問を抱いていた。
沖縄の文化を語る際にしばしば引用され、沖縄の視覚文化を定義するある種の常套句ともなってしまった岡本太郎の「何もないことの眩暈」という言葉がある。
岡本太郎は確かに沖縄本島や久高島の御嶽などに、建築物などの何もない空間を見いだしたのであった。
しかしながら、御嶽以外の沖縄の拝所などには実は様々の形態の図像が数多く存在する。
それらをまずは広く紹介し、それらの機能や意味などを美術史の立場から調査・研究しようという主旨で沖縄図像研究会を立ち上げた。
沖縄民族、歴史の研究者にもアドヴァイザーとなっていただき、手始めに今帰仁を中心とする山原(ヤンバル)を主なフィールドとして、様々な拝所や個人の家庭の仏壇などに安置、保存されている軸物、額装などの絵画、彫像などの図像をできるだけ多く見てまわり写真資料を作成する作業から出発した。
これらの図像は主に、観音を含む仏教系のもの、関羽などの道教/儒教系のもの、神道神や大和の信仰にかかわるもの、沖縄固有の信仰に関するもの、吉祥を表す図像などに分類されることがわかってきた。
同研究会は平成12年度、13年度と継続してうるま財団より受けた助成金によって、これまでに収集した図像とその分類、解読などを含めた現在までの成果を本サイトで公表する。多方面からのご批評、ご指摘、ご指導を賜れると期待している。
copyright (c) 2009 沖縄図像研究会 All Rights Reserved.