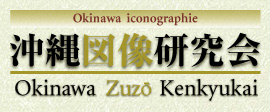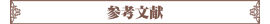本研究会は沖縄の「図像」を調査、研究するものであるが、本研究会が対象とする図像の種類について限定する前に、まず「図像」の定義をしておく必要があるかもしれない。
(図像とは)
「単数あるいは複数の作られたイメージが、いろいろのレベルでの対応関係に基づいて意味することmeaningにかかわっているとき、そのイメージを図像という。したがって図像においては、そのイメージの形式よりは内容のほうが主として問題とされる。イメージはその生成において無限定な地groundに対立するものとしてみずからを特徴づけ、さらに他のイメージとの関係の中にみずからを位置づけて視覚的体系を形成する。このときイメージは第一次的意味を産出し、図像的対応を準備する。図像的対応とは、狭義には概念、命題、言術、言語による体系等とイメージとの対応をさすが、広義には機能、観念のような非言術的対象との対応をも含む。これらの対応は一見必然的、強制的に思われるが、じつは恣意的arbitrary、約束的conventionalであり、基本的には特定の文化、社会、歴史的条件にその成立を負っている。図像の解釈、すなわちその対応づけの解明を行うには、まずもってその文化、社会、歴史的文脈が明らかにされていなければならない。さらに加えて、その対応関係を証すべき同時代の解釈を示す文献などの証拠資料が要請される」。
上は平凡社大百科事典の「図像」の項の一部抜粋である。「イメージ」という言葉がこの中で使われているが、これはその語源であるギリシャ語のimagoが意味していた「目に見える形として現れている形姿」と共に、現在では「頭の中に思い描かれた像」の両方を意味するものである。そこで「図像」を、「ある意味内容に対応する視覚的(可視的)イメージ」と言うことができるかもしれない。
「イミジャリーimagery(英)」「イマジネールimaginaire(仏)」という言葉もしばしば使われるが、これは、個人あるいは共同体の有するイメージ・表象体系の総体というような意味で使われており、人間の想像世界を目に見える形で顕在化したもので、ある形体をもつものが「図像」である。
次に「図像」という語の語源、意味について、西洋、東洋の場合を概観してみたい。
(西欧美術)
図像学あるいは図像解釈学と一般に訳されるイコノグラフィーiconography、イコノロジーiconologyなどの言葉は、ギリシャ語のeikon(肖像、像)とgraphein(記述)あるいはlogos(言葉、学問)を組み合わせたものである。ギリシャ・ローマ時代にはIkonographeinは肖像画集を表していたように、ギリシャ語のエイコーンは狭義には肖像という意味でも使われるが、そもそもは、何かの物事の「影」=像を表している。
西欧では図像集、図像のハンドブックなどとして、チェーザレ・リーパの著した寓意集「イコノロジア」(1593年)や17世紀を通して数多く制作されたエンブレマータ(標章エンブレム集)などがある。
(ビザンチン美術)
ビザンチン美術における「イコン」は、ギリシャ語の原義よりその意味が限定されており、聖像にのみ使われる。
ビザンチン美術にはHermeneia(図像釈義)などの図像集がある。
(日本美術)
日本美術における「図像」は、広義には、本来姿形なき仏・菩薩を視覚的な形を持つものとして絵画や彫刻などに表現した「像」そのものを表す。釈迦は本来象徴的表現によって表象されていたが、仏像が出現し、釈迦と仏弟子、梵天・帝釈天などを区別し、また仏伝図中の釈迦の事跡や意味を区別して表現するために、表現上の個々の規範が求められ、仏教図像が成立した。そして各種経典に説かれるさまざまな仏たちを一つ一つ区別して表現するために、相好、印相、持物、姿勢などの異同の識別のため、仏教図像はさらに複雑化した。
一方狭義の「図像」とは、さまざまな仏たちの識別のため、相好、印相、持物、姿勢などを図解する手本である「図」そのものである。平安時代初期には入唐八家などによって請来されたこれらの図像の多くは、彩色を伴わない白描画(白描図像)、あるいは彩色を伴うものでも墨線による素描が主で淡い彩色が施されるにとどまり、信仰の対象となる本格的な仏像画とは区別されていた。しかし図像は密教において教義の理解のために重要視され、東密、台密各派の間では師質相承の伝授の証とされ、各阿闍梨はみずからの寺僧研究のため図像を収集、書写した。平安時代後期以降、図像研究にいそしむ阿闍梨や画僧が輩出し、その典拠や儀軌の研究が盛んになった。専門の画師による図像制作も行われ、その芸術的価値も高まった。
図像という言葉は中国では古くより「像を描く」という意味で使われていたが、平安初期に円珍が唐より請来した白描仏画の平安末期の転写が「胎蔵図像」と呼ばれていることから、中国ですでにこのようなものが図像と呼ばれていた可能性はある。しかし平安末期に鳥羽上皇の命を受けて仁和寺の僧永厳(ようげん)(恵什という説もある)が選集した図像辞典とも言えるものが「図像抄」と呼ばれることから平安末期にはより図像という言葉が一般化し、その呼び名が定着したと考えられる。
それ以前には中国でも、また日本でも「様」もしくは「図様」といった言葉が、下図や手本の意味で使われていた。
(本研究会が対象とする図像)
本サイトでは、「図像」という言葉を「ある意味内容に対応する視覚的(可視的)形体」という意味で使っている。それらは絵画や彫刻などに表されたものあり、また、たとえば演劇や祝祭、パレードなどにおいて使われる仮面や装束そのもの、またそれらを伴って演じられる役割の形姿、あるいは舞台装置、道具、建築物、装飾などの形などをも含む。それゆえに、本研究は非常に簡単なシンボルや記号のようなものも対象にする場合もあり、絵画、彫刻などの美術的作品に関しても傑作ばかりを対象とするわけではない。
現在のところは、純粋な芸術作品として鑑賞されてきたものものよりもむしろ、なんらかの形で信仰の対象であったり、また信仰の場に置かれ、民間レヴェルで継承されてきたもの、制作されてきたものを主な対象としている。その中には近現代の作家が、要請や注文によって描いたもの、あるいは夢のなかなどでお告げを受けて描き寄進したものなども含まれている。
調査はほとんど山原地方で行ったが、一部那覇、首里、南部地方でも行っており、今後はより調査地域を広げていきたいと思っている。
copyright (c) 2009 沖縄図像研究会 All Rights Reserved.