超次元戦闘妖兵 フライア ―次元を超えた恋の物語―
渚 美鈴/作
★第1話「次元を越える脅威 ―機動歩兵 出撃せよ!―」
introduction
帰ってきたのは
失われた記憶の時から十年後
孤独と絶望、重責と戸惑いを乗り越えて
私は帰ることを希望した
夢見たのは、ただ
懐かしい故郷(ふるさと)の空と大地
会いたかったのは、ただ
暖かな家族の笑顔
だけどそれは
叶えられない現実(リアル)
私の胸にある戦士の魂
フライアは世界を救う闘いの女神
黙示録の獣を滅ぼす荒ぶる妖兵は
魂の伴侶として生を受けた
誓ったのは、ただ
世界の人々の幸せと平安
祈ったのは、ただ
同じ胸に宿る魂の救済
だけどそれは
乾いた砂漠に響く子守唄(ララバイ)
私の胸に潜む復讐の化身
それは悪を断罪する裁きの女神
怒りと憎しみ、涙と哀しみを胸に叫ぶ
もうひとりの私は、血にまみれる
求めたのは ただ
凍てついた心の癒し
欲しいものは ただ
同じ人のぬくもり
傷つき血を流す
ひび割れた心の手当て(ケア)
愛する人よ 嫌わないで
戦いの女神も 復讐の化身も
どれも私の本当の姿
愛する人よ 嫌わないで
見えないの 探せないの
どこへ行くの 何を求めるの
時の迷子 魂の迷子
一人荒野で道に迷う私
愛する人よ その手で私を導いて 愛するあなたの側へ
【目次】
(1)帰還
(2)旧帝都の異変
(3)次元断層
(4)出撃! 機動歩兵・蒼龍
(5)交戦
(6)死闘! 蒼龍vs次元超越獣
(7)次元ポケット
(8)奇跡の生還
【本文】
(1)帰還
闇を走る光の奔流を超えると、そこは、夜の都会の一角だった。
保安灯の光がまぶしく照らす背の低い生垣とベンチ、そしてレンガ状のタイルが敷き詰められた、ごくありふれた公園の風景。
あたりを確かめ、安全が確認されると、全身からゆっくりと力を抜いていく。
少しずつ縮んでいく金髪の間から視界が開けていく。
冷たい外気が頬にふれる。
強く結んでいた唇をゆるめ、ハアッと息を吐いて、静かに吸い込む。肺の中に流れ込んでくる空気は、かすかに油を燃やしたような匂いがまざっている。
それは心の奥底に眠っていた懐かしい世界の記憶と一致していた。
排気ガス……? 自動車?
夜空には、市街地の明かりを反射した白い雲がポッカリと浮かんでいる。
時間的には、真夜中を少し過ぎた頃だろうか。
公園の木々の間から見える車や人の往来は、まばらだ。
大きな幹線道路沿いに位置する公園は、生垣や街路樹に囲まれているものの、通りすぎる車中からは丸見えのはずで、強い不安感がつきまとう。
半身にとっては見知らぬ世界。
この世界の住人から見れば不可解なこの姿を考えれば、あまり懐かしさに浸ってばかりもいられない。
記憶の底の情報との一致を確認しながら、未だ同化していない半身からの焦燥感にも似た要求に応えて、移動することにする。
背中から伸びた羽根を展張し、ふわりと夜空へ飛び上がる。
交差する電線を避け、音もなくビルの群れを見下ろすだけの高さに駆け上った時、ビルのひとつに掲げられた看板の文字が目に飛び込んできた。
静かにホバリングしながら文字を確認する。
吹き抜ける冷たい風が、金色の長い髪をたなびかせる。
す、ず、つ、き、し……読める……・日本語だ。
唇から漏れる言葉はないが、その意味が凍てついた心の奥まで伝わるのに、少し時間がかかる。
本当に……帰ってきたんだ。
ちりちりと刺すような刺激が、身体を走る。
次元同化という未経験の現象。
逃げ出したくなる恐怖心が、頭をもたげる。しかし、帰ってきたという喜びの前には、ほんの些細なことでしかない。
目覚めた時に、妖精たちが教えてくれたことをひとつずつ思いだし、噛み締める。
この命と引き換えに与えられた重い使命。
強い生存本能と表裏一体のテリトリ―意識は、すでにこの世界をインプットしはじめている。
時間。十年という空白の時の存在。
懐かしさと同時に感じる一抹の寂しさと不安が、いとおしく繊細なもうひとつの心、魂から溢れ出す。
超科学と魔法のような技術で創られ、鎧われたこの身体は、妖精たちの求めた使命を果たすのに十分役立ってくれるはずだ。
そして、心の奥底にポッカリと開いた暗闇。
そこで機会をうかがう暗く冷たい感情。
封印された記憶が開放された時、何が起こるのか。
自分自身のことなのに、わからないという不安も少しはある。
やがて、左手首内側についた、水晶の丸い円盤が風に揺れる水面のように震え、行くべき方角を指し示す。
水晶盤の指示する方向へ。
体を傾け、重力バランスを崩して沈み込む。風を全身で受ける形を取り、羽をいっぱいに展張して水平飛行に移る。
水平飛行している間も、思いはめまぐるしく展開し、それは目的地へ着くまで途切れることはなかった。
(2)旧帝都の異変
「アルファコントロ―ル。目標上空に到着した。降下して状況を確認する。」
「次元センサ―をロックオンすることを忘れるな。これは、訓練ではない。実戦だ。落ち着いてやれ。」
「ラジャ―」
旧帝都のビジネス街の一角に向かって、高機動偵察ヘリコプタ―が降下していく。突然上空に現れたヘリコプタ―の姿に、通りかかった人々は、何事かと見上げる。ヘリの下面に描かれた帝国機動隊のマ―クは、帝都で発生した事件や事故で見知ったものであるだけに、特に大きな不安を抱かせるものではない。
どんな事故が起こったのかと、市民が携帯でネットワ―クにアクセスしている間に、通りの向こうからは、けたたましいサイレンとともに機動隊の緊急車両とパトカ―の群れが押し寄せてくる。
パトカ―から降りてきた警察官たちが、通りに立ち入り禁止のテ―プを展開し、集まった野次馬たちを排除にかかる。大型輸送車両で到着した機動隊員が立ち入り禁止区域内の建物に次々と入り、建物内の住民らを退去させていく。
「危険ですので、E27街区は、しばらく立ち入り禁止とします。」
「何かあったんですか? 」
封鎖される街区内の建物から出てきたビジネスマンが、警官に尋ねる。
「わかりません。公式発表をまってください。」
「しかし、今日中に片付けなければならない仕事があるんですよ。出ろといわれて、はいそうですかというわけには……」
「とにかく、退去して。」
「何があったかくらい教えろよ。」
「そんな暇はない。文句なら後で聞く。」
警察官たちは、あちこちからあがる不満の声を無視して、街区の建物から次々と住人たちを強制的に退去させていく。
そこへ大型のトレ―ラ―が続々と到着し、警察と機動隊の誘導の下、立ち入り禁止区域内に入っていく。野次馬と退去させられた人々は、次第にこれが普通の事件や事故ではないのだと感じはじめた。
禁止区域内に入った大型トレ―ラ―は、国防軍の専用車両だったからである。
警察の手に負えない大事件が起こっている。核や化学兵器を使ったテロは、すでに現実の脅威となっているのだから、誰も警察や軍の街中での行動に不満を言うものはいない。
悲しむべきことに、それがこの世界のリアルだった。
(3)次元断層
エレクトリック・ツルギ社製の機動歩兵「蒼龍」の中で、日高良弘一尉は、偵察ヘリから送られてくる画像をバイザ―のディスプレイで確認していた。
「まるでブラックホ―ルだな。」
街の一角、帝国銀行前の空間に墨を垂らしたような黒い大きな円が、ポツンと映っている。
画面の一部に障害が起きたか、カメラのレンズの汚れのような印象だが、それは撮影の向きに合わせて移動することもなく、同じ場所に固着したままだ。
建物や街路の凹凸を無視して居座る黒い染みを中心に、ヘリはゆっくりと旋回していく。
黒い円は平面のように、見る角度にあわせて傾いていく。まるで、厚みの無い黒い板状の物体がそこに起立して置かれているようだ。
次の異変は、ヘリがその周囲を百八十度ほど旋回したところで生じた。
突然、映像から黒い染みが消失する。
「アルファコントロ―ル! 目標が消えた? 」
その声を聞いて、機動歩兵内の日高も思わず腰を浮かしかけ、機動歩兵がトレ―ラ―内の拘束ワイヤ―を軋ませる音を聞いて、あわてて連動ギアを中立にもどす。ヘリから送られてくる映像からは、黒い染みが完全に消失していた。
状況終了?
そんな思いが頭の隅をよぎる。
今回も何事もなく終わりになるかもしれないな。
日高は、その可能性が高いと思った。
20世紀末頃から、世界各地で空間にぽっかりと黒い穴のようなものが生ずる不可解な現象の報告が続いている。報告の中には、人や航空機が吸い込まれて消えたという事例もあるが、その大半は、何事もなく数時間で消滅している。
神隠し、四次元ミステリ―と関連付けした公式研究もあるが、映像として記録されるようになったのは、携帯のカメラ機能が一般に普及してからのことでもあり、まだまだ大きな社会的関心を集めるものとはなっていない。コンピュ―タの画像処理技術の進歩もあって、マスコミや大多数の市民が、いたずらと考えているのが現状だ。
だが、政府上層部と国防軍は、その現象発生の事実と脅威を冷静に受け止め、秘密裏に対応を続けていた。今回の現象についても打ち合わせどおり、発生地区の周囲を完全封鎖し、対応部隊を展開して監視を続けている。うわさでは、アメリカからの強い要請があったとも言われている。
日高が考えている間にも、ヘリと司令部との交信は続いている。
待機状態でいる間は、交信への介入は厳禁とされている。日高は状況把握に努めるしかない。それは、「蒼龍」2号機で待機中の村雨も同じだ。
「あせることはない。」
日高は、自分に言い聞かせるようにつぶやいて、交信情報に注意を向けた。
「現地作戦本部より報告。状況変化なし。目標は依然として存在しています。」
「アルファコントロ―ルより、現地本部へ。チャンネル2で映像を送れ。」
「了解。チャンネル2で送る。」
「こちら偵察ヘリ3号。位置座標のデ―タを送ってくれ。」
「現地本部より、偵察ヘリ3号へ。目標の位置座標は、そちらが報告してきたとおりだ。位置は動いていない。こちらの正面、ニ百メ―トルのところだ。」
「了解。確認のため接近する。」
偵察ヘリは、ホバリングを止めて、現地本部の正面、目標の背後から接近を開始した。ヘリの爆音が次第に大きくなり、目標とヘリの距離が縮まる。しかし、ヘリから送られてくるチャンネル1の映像に、目標は、依然映っていない。
「まだ捉えられない。カメラの向きは合っているんだろうな? くそっ。どうなってんだ? 」
「偵察ヘリ3号、OK! 真下にきた……」
現地本部につめている全員が、ヘリから送られてくるチャンネル1の映像を確認しようとディスプレイを覗き込んだとたん、ヘリの爆音がふっと消えた。
映像も一瞬にして途切れる。
「? 」
現地本部のスタッフが顔を上げた時、そこにヘリの姿はなかった。
スタッフ全員が立ち上がり、キョロキョロと周囲の空を探すが、雲ひとつない青空が広がるばかりである。
「あ、あれ? 偵察ヘリ3号、どこ行った……? 」
金城三佐の半ば上ずった、素っ頓狂な声が、周囲に響きわたる。全員が顔を見合わせる中で、目標の映像を撮影していた白瀬唯三曹がポツリとつぶやく。
「金城三佐。ヘリが消えました。」
「……」
誰も彼もが押し黙った中、ヘリとアルファコントロ―ルで呼ばれる司令部を繫ぐ交信が続く。
「アルファコントロ―ルより、偵察ヘリ3号へ。チャンネル1で映像を送れ。送信が止まっているぞ。」
「……」
「アルファコントロ―ルより、偵察ヘリ3号へ。偵察ヘリ3号応答せよ。チャンネル1の映像を送れ。」
「……」
「現地本部指揮官、霧山だ。偵察ヘリが見えなくなった。いや、消えた。不時着したのか? 」
「アルファコントロ―ルより、現地本部へ。状況知らせ。こちらでも、今、上空の警戒管制機に確認中だ。事故なのか? 3号との交信が切れた。」
霧山一佐は、緊張で乾いた唇をなめながらアルファコントロ―ルに状況を伝える。
「ヘリは消えた……。状況フェ―ズ3が、起こったと思われる。」
「…………」
その瞬間、交信先のアルファコントロ―ルに大きな衝撃が走ったであろうことは、無反応の交信の様子からも察することができた。
現地本部では、この正面以外の三方向から偵察小隊を派遣し、目標を映像出捉えるよう指示しているが、霧山たち現地本部以外、現場を映像で直接捉えられる位置関係にはなっていない。三方向ともビルにさえぎられており、現在、屋上や窓越しに撮影するため、接近を試みているところである。
徐染済みとはいえ、幹線道路から離れたこの地域は空きビルが多い。無人だが施錠されていることも多く、接近のために通り抜けるのは困難が伴う。
「霧山一佐、金城三佐、目標が少しずつ拡大しています。」
映像カメラを監視している白瀬が、ディスプレイから顔を上げて告げた。
「まちがいないか? 」
霧山一佐の問いに白瀬はうなずく。そばに立って、双眼鏡で目標を確認した金城三佐が、双眼鏡を手渡しながら意見具申する。
「後退すべきですな。見た目は変りませんが、フェ―ズ3が起こったとなると、ここも安心できません。」
金城三佐から双眼鏡を受け取った霧山一佐は、目標に向けて最大ズ―ムをかける。ピント合わせをしている間に、ぼやけた黒い染みの中を何かが動いた。
「警報! 何かいるぞ! 」
カメラの映像を見ていた白瀬も応える。
「いや、何これ? きもい! 」
金城三佐も白瀬とともにディスプレイに見入る。
黒い染みの中から強い日差しを浴びて、てかてかと白くぬめった芋虫のようなものが顔をのぞかせている。身体全体はまだ、染みの中のようだ。サイズはよくわからないが、かなり大きい。
「霧山一佐、フェ―ズ2へ移行しますか? 」
「当然だ。接近中の偵察小隊にも警報! 待機を伝えろ。」
「アルファコントロ―ル。フェ―ズ2発生。『蒼龍』を出撃させる。」
「……こちらアルファコントロ―ル。神だ。まて、ODMを視認したのか?危害行動の確認が先だ。総理の許可まで、待て! 」
「非常事態対処規程第9条第2項に適合します。神少将には、至急応援部隊の手配を求めます。」
「2項の解釈は国家間紛争……」
霧山一佐は、交信が続いている無線機を白瀬に放り投げる。白瀬があわてて一度は受け止めたものの、霧山の視線からその意図を理解し、そのまま落としてしまう。
ガシャン。ピ―
交信音声が途絶える。
「……落としてしまいました。」
白瀬は、ニコッと笑って答える。金城三佐が近くに落ちていたこぶし大の石を拾い、無線機にとどめをさす。
「官給品だぞ。ダメじゃないか大事に扱わないと……。」
白瀬の手に始末した無線機を置いて、金城三佐がにやりと笑う。
「おい、金城。待機中の日高と村雨を呼び出せ。いよいよ実戦だ。あとの者は、ここから離れる。全員装備を確認。白瀬は、カメラを自動追尾モ―ドにして固定。予備のカメラも追加して設置だ。佐藤は、警察と機動隊に立ち入り禁止区域の拡大を要請しろ。」
てきぱきと部下に指示を与え、目標を振り返って双眼鏡で覗いた霧山は、低くうなった。
「佐々木会長からの予言どおりになった。やはり……食ってやがる……」
(4)出撃! 機動歩兵・蒼龍
株式会社エレクトリック・ツルギ社製・機動歩兵ABT―X03A「蒼龍」。
全高二メ―トル二十五センチ、全幅一メ―トル十八センチ、全備重量約1・6トンの、俗に言うパワ―ドス―ツである。
手袋側に装着された操縦桿の頂部にあるボタンで、着脱や起動、装着兵装等のコントロ―ルを行うが、あとは身体の動きにあわせて自由自在に可動する。
兵装は、巨大生物を想定した近接戦闘用の武装が中心だが、その他、必要に応じて様々な火器が用意されている。
だが、「蒼龍」の最大の特徴は、アメリカよりブラックボックス状態で供与された次元センサ―&補助動力システムが組み込まれていることにある。「蒼龍」の前身は、ツルギ社のABT―X02「翔龍」で、「蒼龍」と大きな差異はない。ツルギ社は嫌ったが、実際に両機種間で行われた模擬戦闘の結果、受け入れざるを得なくなったと言われている。
ツルギ社は、このブラックボックスの量産化をアメリカに要請したが、頑ななアメリカ側から拒絶にあって困惑しているともきいている。また、ブラックボックスの数は、総数で3桁に満たないとの不確定情報もあり、日本帝国政府も様々なチャンネルを通じて戦力増強のための交渉を続けているらしい。
日高は、そんな「蒼龍」の7号機に搭乗している。現在、日本帝国に7台しかないブラックボックスを使った最終号機である。それと同時に、日高にとっては、自分が最もなじんだ機体であり、命を預ける機体としても愛着が強い機体でもあった。
ブラックボックスの仕上がりの差によるものか、明らかではないが、「蒼龍」の機体と搭乗者の相性、適性にはたいへん強い癖がある。
「翔龍」の搭乗者として最高ランクの成績をあげたパイロットが、「蒼龍」に搭乗し、ブラックボックスとのリンクを入れると異常停止する。
「翔龍」ではBランクの評価だったものが搭乗すると、高性能を発揮するなど、ツルギ社の技術者の理解を超えた部分があり、技術協力も含めて、大きな不満がくすぶっているともきいていた。
霧山一佐からの指令を受け、トレ―ラ―のコンテナ上部と側面が次々と開放されていく。
「拘束フック解除よし。続いて外部APU、交信RUNの接続を解除します。日高一尉、『蒼龍』7号機発進願います。」
「了解。『蒼龍』7号機出る。」
暗いコンテナ内部から開放され、キャノピ―にも外部からの光が差し込む。
スモ―ク処理がほどこされているとはいえ、真っ暗な中でインジケ―タ―や液晶ディスプレイの灯だけに慣れた目には、外の日差しはまぶしい。
連動ギアを入れ、立ち上がる動作を開始するとともに、シ―トの座面が背後に引き込まれていく。
交信アンテナがモ―タ―音とともに伸張し、外部との交信が開始される。
「日高一尉、携帯兵装は十二・七ミリでいいですか? 」
「いや、地上班から送られてきた映像からすると、相手の面の皮はそれほど固くないだろう。むしろ弾数が多いほうがいい。ミニガンを頼む。」
「了解。では、弾倉には焼夷弾と溶解弾、徹甲弾を用意します。」
兵装員と交信が終わると同時に、「蒼龍」2号機の村雨から緊急連絡が入る。
「日高。こちら『蒼龍』2号機、村雨だ。すまん。起動に失敗した。先に行ってくれ。」
「村雨。再起動できないか? 」
「だめだ。機体がびびっちまったみたいに、反応しない。今、整備員がDS&APUを外して、『翔龍』の主電源パックに換装している。三分で終わる。」
「『翔龍』ではパワ―も低下する。稼働時間も限度がある。そんな状態で……」
「心配すんな。俺にとっちゃ『翔龍』の方が慣れてる。必ず追いつく。」
「蒼龍」の内部は機密の塊のため、送信情報は音声のみとなっている。そのため、村雨のコックピット内の様子は、声から推察するしかない。
冷静さは失っていない。神経が図太い奴のことだ。トラブルを乗り越えて、ペアとしての責任は果たすだろう。
その間に準備されたのだろう。日高の眼前に六本の銃身を束ねたミニガンが起立する。
「蒼龍」用に普通の銃器の形状に成形されているが、その重量と射撃時の反動は、とても人間が持って扱うことなどできない。「蒼龍」に乗った人間が、システムのアシストを受けて初めて扱うことができるものだ。錯覚を起こし、手で持ち上げようとして、腕や腰を痛めた者もいるという噂話もあるほどだ。
日高は、「蒼龍」の右手を伸ばし、ミニガンをゆっくりと持ち上げる。左手でグリップを握りしめ、安全装置を解除する。モ―タ―の駆動を確かめ、試射弾を上空へ放つ。
爆発音が轟いたのは、その時だった。
「『蒼龍』7号機。日高一尉。こちら地上班、白瀬。応答せよ。」
「こちら7号機。日高だ。どうした? 」
「後退中の地上班ノ―スが、襲われたようです。」
「チャンネル2をモニタ―しているが、目標の動きは確認できない。」
「チャンネル6に切り替えてください。ノ―ス班の阿部が落としたカメラの映像が確認できるはずです。」
白瀬唯三曹の上ずった声が応答する。その間にも、市街地をタタタン、タタタンという乾いた銃器の立てる音が響き渡る。
急いで、左手の操縦桿頭部のボタンを操作し、モニタ―画面のチャンネルを切り替える。モニタ―画面が即座に切り替わり、赤い光が目に飛び込んでくる。
「……」
モニタ―画面には、左から右へ伝っていく赤いベ―ルがあった。そのベ―ルの向こう側で蠢く、白い芋虫のような生き物がいた。しかし、そのサイズは、牛が3、4頭連なったほどに巨大だ。黒く長い爪状の脚がムカデのようにたくさんついている。腹側は背中側よりも皮が薄いのか、その体内の臓器らしきものが透けて見える。今しも、その消化器官らしきものの中を一つの塊が転がっていく。それは、半分溶けかかった人間の頭部だ。
「くっ。」
総毛立つ光景。日高は、突き上げてくる嘔吐感から意識をそらし、努めて冷静に交信を送った。
「……こちら『蒼龍』7号機。指示を請う。」
「霧山だ。目標に回り込んで戦闘を挑むのは、危険が大きすぎる。目標の正面、こちら側で迎え撃つのがベストだろう。地上班も支援攻撃を行える。至急こちらへ向かってくれ。」
「了解。」
日高は、ミニガンを抱え、「蒼龍」7号機を走らせた。その動きは、ほとんど人間とかわらないスム―ズさだ。しかし、その軽やかな動きと裏腹にその重量の実体は、路面に穿たれた足跡と衝撃が物語っていた。
(5)交戦
後退中の地上班ノ―スが襲われたため、立入禁止区域は、さらに北へ一区画拡大される処置がとられたが、戦闘はその最中に南側で始まった。
チャンネル2で送られてきた画像では、今やはっきりと巨大な芋虫状の身体にムカデのように多数の黒い爪状の脚をつけた怪生物が捉えられていた。
それが霧山たちの方へ向くと、カサカサと走り出す。後退準備をしていた霧山たちは、一斉に発砲した。
タタタン、タタタンという発砲音とともに、怪生物の身体に高速の銃弾が次々と命中し、めり込む。ピクッと動いて固まった怪物に、地上班の銃火がさらに雨あられと浴びせかけられる。
「ふせろ! 」
金城三佐が叫んで、手榴弾を投げつける。轟音とともに怪物の鼻面で炸裂する。さらに2発目、3発目と手榴弾が投げつけられる。
連続する爆発音がやむと、あたりに静けさが戻る。
「ストップ。ストップ……・どうだ? 」
霧山一佐が射撃を制止し、怪物の様子を伺う。
怪物は固まったように動かない。白くなめらかだったその身体は、無数の黒い斑点に覆われている。黒い爪状の脚も縮こまって身体にひきつけられている。
「死んだか? 」
「確認します。」
金城三佐が近くから棒切れを拾い、怪物に向かって投げる。怪物の目の前でカランと跳ねるが、怪物は微動だにしない。
霧山一佐が立ち上がり、M2で伏射姿勢をとっている小田以外、全員がほっと一息ついたその時だった。
「気を抜くな。まだだ。」
ドドドドッ。
小田のM2が再び火を吹く。重機関銃の一連射が怪物の身体にめり込み、その着弾の衝撃で怪物の身体が、わずかに後方へすべるように後ずさる。他の隊員も手にした短機関銃をとっさに怪物に向け、トリガ―を絞りかける。
「お、おどかすな……」
「だ、誰だ。今の声は? 」
「霧山一佐、代わります。」
霧山たちの後ろから声が降ってきた。灰色の装甲に覆われた日高の「蒼龍」7号機がミニガンを抱えて仁王立ちしていた。
(6)死闘! 蒼龍vs次元超越獣
「折角来てもらったところだが、申し訳ない。先にノ―ス隊の仇は、こっちで先に取らせてもらったよ。」
金城三佐が日高に向けて答える。しかし、「蒼龍」7号はその言葉を無視して地上班のバリケ―ドの前に出る。日高のバイザ―に接続された警戒センサ―は、真っ赤なままだ。
「こいつ、罠を仕掛けているんですよ。見ててください。」
日高は、ミニガンの一連射を怪物に向けて浴びせる。ブスブスという貫通音の後、焼け焦げる匂いが立ち込めるのと同時だった。
ヌウウウウウウ~
怪物が再び首を持ち上げたかと思うと、すさまじいスピ―ドで走り出した。向きを黒い染みへ変え、逃走を図るようだ。そうはさせじと日高は、「蒼龍」の腰に装備された焼夷手榴弾を黒い染みへ向けて投げ込む。一瞬にして噴出す強烈な火炎に、怪物が突入を躊躇する。
「逃がさないぜ。くたばりやがれ。」
日高は、怪物の背後からミニガンの連射をかける。焼夷弾と溶解弾、徹甲弾を混合した銃火に、のたうつ怪物は攻撃を逃れようと、「蒼龍」7号の脇をすり抜けようとした。
その巨体に日高はショルダ―タックルをかけ、押さえ込みにかかる。1トン半を超える「蒼龍」のタックルに怪物の身体が路面にこすりつけられるようにして静止させられる。だが、怪物も必死だ。巨大な尻尾? が跳ね上がってきて、「蒼龍」7号のキャノピ―を直撃する。
ガツン、ガツン、ガツン。
バブルキャノピ―を保護するケプラ―製の枠がしなる。強烈な打撃に、日高も恐怖感を感じ、尻尾の4撃目は、右手のミニガンで受け止める。
空の弾倉がへこみ、捻じ曲がってはじき飛ぶ。次の5撃目で6本の銃身も捻じ曲がり、駆動モ―タ―が火花を散らして脱落する。
「蒼龍」の前面装甲は、搭乗者の身体の動きの制約をなくすため、ほとんど無きに等しい。この尻尾の直撃の威力は、受け損なったら圧死することを確信させる。
日高は、ガラクタとなったミニガンを離すと、右腕に収容されたスピア(格闘戦用の槍)を展張して、尻尾の6撃目を迎えうった。
ぶすっ。
鋭いスピアの切っ先が怪物の振り下ろす尻尾に深々とめり込み、白い体液を撒き散らす。引きの反動で引っ張られそうになる右腕をこらえ、7撃目、8撃目、9撃目を繰り返しスピアで貫く。
9撃目の引きの反動で引っ張られた時、右腕のアクチュエ―タ―が異音を発し、バイザ―のディスプレイに警告表示が映し出される。
ちっ! 右腕がやられたか。
駆動しなくなった右腕は、ガ―ドのため自動的に折りたたまれる。
怪物を離して、距離を置き戦うか、それともこのまま接近戦で止めを刺すか。日高に迷いが生じる。そこに振り下ろされる怪物の尻尾の10撃目が目に入る。
グワ―ン!
すさまじい轟音とともに怪物の尻尾が千切れ、宙に舞う。
「日高! 離れろ! 」
村雨の声が響き、反射的に日高はタックルを解除して、怪物から離れる。
入れ代わりに、村雨の「蒼龍」(翔龍)2号機が突進してくる。ほぼ零距離射撃で百二十ミリ無反動砲を怪物の頭に撃ち込む。めり込んだ砲弾が怪物の体内で炸裂し、怪物の口らしき場所と、千切れた胴の切り口から色彩豊かな臓器らしきものが白濁した体液と爆風とともに噴出する。それでも袋状となった体は、ほとんど裂けない。信じられないほど強靭な体組織だ。
村雨が、無反動砲を捨て、怪物から離れる。ぼろぼろとなった怪物は、動かない。壮絶な接近格闘戦の邪魔にならないよう、避難していた霧山一佐たちが遠くから様子を伺っている。
「霧山一佐。状況終了です。」
「蒼龍」(翔龍)2号機が合図をおくると、地上本部の面々が恐る恐る接近してくる。
「や―れやれ。芋虫相手に重火器ぶっ放すとは思わなかったぜ。日高、だいじょうぶか?ずいぶんやられたようだが……」
「遅いぞ。おかげでこの有様だ。」
「そう言うなって。戦闘状況を見て、携帯装備を変更して駆けつけたんだ。無反動砲2門も抱えてこなきゃ、始末できなかったはずさ。」
「動きを抑えなきゃ、でっかい大砲も当てられん。いざとなりゃ、こいつの神経系統に放電を浴びせて仕留めるつもりだったんだ。」
「よせよ。神風アタックは。芋虫相手に心中じゃあ、割に合わないぜ。」
村雨の放言につきあって、ほっとしている日高の脳裏を、突然、電流のようなメッセ―ジが流れた。
(マダダ。マダ、終ワリジャナイ……・。)
同時に悪寒のようなものを感じて、日高は、慌ててバイザ―の次元センサ―を見る。センサ―ランプは、赤のままだ。
次元センサ―は、次元に何かが干渉するエネルギ―を感知するものと説明を受けている。警戒ランプは、その何者かが未だ健在なこと、どこかに存在していることを示しているのだ。
「警報っ! 全員、警戒を怠るな。まだ何かいるぞっ! 」
日高の警告に、一瞬その場が凍りつく。現場に近づこうと、バリケ―ドの外へ脚を踏み出した霧山一佐たちも、その場に釘付けとなる。短機関銃を構え直し、周囲を警戒する。その表情はこわばったままだ。
一瞬の静寂。
「……まてよ。『蒼龍』のセンサ―が、故障してるんじゃないのか? 」
緊張に耐えられなくなった村雨が、交信してくる。
「こっちのセンサ―は、反応してないぞ。」
村雨の「蒼龍」(翔龍)2号機が、緊張を解き一歩踏み出したとたん、その踏み出した脚が接地した路面上に暗黒の染みがパッと広がった。ストンと落ちかかる「蒼龍」(翔龍)2号機に、全員が息を飲む。
黒い染みに飲み込まれまいと、村雨は、2号機の姿勢をひねり、かろうじて黒い染みの外縁に上体を預ける。しかし、踏み出した片脚はどっぷりと暗黒の染みにつかってしまった。次の瞬間、暗黒の染みが閉じて消滅する。
「うわあああっ。」
吹き上がる血しぶきとともに村雨が絶叫し、2号機が激しくのたうちまわる。なんと、2号機の脚ごと、村雨の右足がスッパリと切断されてしまったのだ。
「村雨! 」
日高は、「蒼龍」7号機を起き上がらせようともがいた。しかし、胸の前でV字型に折り曲げられた右腕は、ロックされて動かず、重心が体の後部にある機体を左手だけで起き上がらせるのは、容易ではない。もちろん、霧山一佐たちのいるバリケ―ドの向こう側もパニック状況で、村雨の支援には、とても動けそうもない。地雷原のど真ん中に入り込んでしまったような混乱だ。
あせる日高が、何とか左手で上体を起こした時だ。今度は、その日高の「蒼龍」7号機の下に暗黒の染みがパックリと口を空けた。
ストンと頭から落ちる「蒼龍」7号機。そして、日高の眼前、漆黒の闇の中から、もう一匹の白い怪物の顔? が現れた…………。
(7)次元ポケット
日高良弘一尉、29歳。国防軍中央即応集団・対次元変動対応部隊、通称「対次元変動対応部隊」第2機動歩兵戦隊所属。部隊に配置されている15名の機動歩兵パイロットの中の正規パイロットの一人である。
スタンバイ状態の7台の「蒼龍」のうちから、7号機を乗機に選んだのは、偶然ではない。その相性の良さは、日高が「死ぬときはこいつと一緒なら悔いはない」と思うほどだ。日高は、今、その時がきたのだと運命をすんなり受け入れてしまいそうになった。
まだ……。まだ終りじゃない……・。
今度は、女の声のようなメッセージが、日高の脊髄から脳へと駆け抜ける。
我にかえった日高は、目を見開いて、眼前に迫る白い怪物の顔? を見つめる。
スローモーションビデオを見ているかのように、徐々に開かれる黒い牙の並んだ口。
何を見ているかわからないが、黒いマイクの頭のような巨大な目が眼前に迫ってくる。
口の上に、レンズのように並ぶ黒い三つの複眼が、一瞬煌めいたように感じて、日高はㇵッと我にかえる。
「こいつ……芋虫風情が人間を喰おうなんて……贅沢なんだよ! 」
日高は思わず罵ると、「蒼龍」の左腕をその口に突きこむ。左手操縦桿ヘッドの操作ボタン横のセ―フティ―を素早く解除し、一番右側のトリガ―ボタンを押し込む。
ズン! という衝撃とともに、左腕上部からノズルが飛び出し、怪物の口腔内に一千度近い火炎が噴出した。
くわわっ!
怪物の体内を赤い炎が突き抜ける。あわてて口を開けて蒼龍の左腕を吐き出そうとするが、装甲板に食い込んだ歯がひっかかって吐き出せない。パクパクする口が左腕の装甲板をさらに貫き、マニュピレ―タ―機能の停止を告げる警告が表示される。火炎放射器のブ―ストポンプの出力も急速に低下していく。
「ちっ。なら、こいつで、もう一丁! 」
日高は、火炎放射器のトリガ―ボタンから親指を離し、左隣のトリガ―ボタンを押し込む。
プオオオオッ!
今度は軽い連続振動とともに、三十センチのタングステン製の針が怪物の体内に撃ち込まれる。電磁レ―ルで音速に近い初速で発射された針は、怪物の炭化した内臓を撃ち抜き、一部は丈夫な体表さえも貫通して、外に飛び去る。
針の後部から伸びるピアノ線が、長さの限界を越えてブツッと千切れる。
怪物は体を丸めて、黒い針金状の足を「蒼龍」の前面に引っ掛けると、蒼龍を突き放した。
バキッ!
ブツン。ブツン。ブツ!
日高のバイザ―に警告表示が現れ、日高が握り締めていた左手の操縦桿ごと、「蒼龍」の左腕が怪物にもっていかれる。むき出しとなった日高の左腕に引きちぎられたコ―ド類やクッション材が絡まり、むりやり引きちぎられた関節部分に繋がる緩衝機材が突き出したまま機能を停止する。
怪物の姿は左腕とともに漆黒の闇に消え、日高は、暗黒の空間を浮かぶように漂っていた。バクバクと拍動する心臓の音が反響し、「はあ、はあ」という荒い息がバイザ―内に繰り返し白い曇りをもたらす。
あの怪物は死んだか?
とどめをさせただろうか?
怪物が再襲撃を思うと、息が乱れ、生唾を飲み込んで身構えてしまう。
上も下もない。
右も左もない暗黒の空間。
バイザ―内に点滅している赤い警告表示の群と、「蒼龍」の管制デ―タが流れるディスプレイだけが唯一の灯りだ。
「蒼龍」の両足をバタつかせても、何かに接触する感触は伝わってこない。
千切れたコ―ド類が絡まるス―ツに包まれた左腕を振り回してみても、まったく感触は伝わってこない。
空気があるのか?
気温は? 重力は?
少し冷静さを取り戻して、外部の様子を確認する。
酸素タンクの残量計は、いつの間にか、ゼロに接近した状態で止まっている。
通信アンテナに入る電波もない。壊れているかと思うほど、静かだ。
メイン電源も怪しい。残量表示は、デジタル表示の時刻とともに不規則な反応を繰り返している。日高が注意を向けるとすごい速度で残量が減り、時刻も進む。注意を外すと停滞する。その動きは、まるで、日高の精神状態を反映しているようで、時間の概念が、日高の支配下でのみ存在するかのようである。
窒息し、干からびたミイラ……。
嫌な自分の未来の姿が浮かんでくる。
「誰かいないか? 」
「居たら返事してくれ。」
インカムに叫ぶ自分の声が、ス―ツ内にこだまのように反響する。
頭痛とともに、パニックが襲ってくる。
心臓がバクバクと鳴り、息苦しくなる。
耳の中を自分の呼吸音が台風のように響きわたる。
視界がぼやける。
何を見ているのか。
ふと、気がつくと目を閉じている自分がいる。
途切れ途切れの意識……。
何度目か、目をあけた時、日高は、ス―ツで包まれた左腕が、黒く染まってにょきにょきと伸びていくのを見た。
真っ黒な細い腕は、どんどん、どんどんゴムのように伸びてゆく。
まるでマンガだ。
伸びた手の先は、やがて針の先のようになって見えなくなる。
一体どこまで伸びてるのか?
ゴムのように腕が伸び続ける感覚が続く。
やがて、左手がかすかに握り締められる感覚が伝わってきた。
凍てついた左手に暖かなぬくもりが伝わってくる。
そして、引き寄せられる感覚とともに、目の前に金髪の白い女の顔が現れた。その背中からは、透明な銀の羽が水平に羽ばたいている。首から下は、全身黒い衣装のためか、判別できない。
やがて、女の両耳の白いイア―マフの下から伸びるピンクの聴診器? のようなものがアクリル製のバイザ―を貫通して、日高の額に触れる。
だいじょうぶ。あなたは死なない。
女の声が、直接、頭に伝わってくる。
私は、フライア。良き魂を持った戦士は、私の同志。
その声の抑揚、感覚に、日高は思い当たるものがあったが、女の言葉は、日高が必死で保ってきた意識を消失させるだけの安心感をもたらす。
「助けてくれるのか……」
相手の正体を詮索して結論を出すだけの力は、すでになく、日高の意識はそこで途切れていった…………。
(8)奇跡の生還
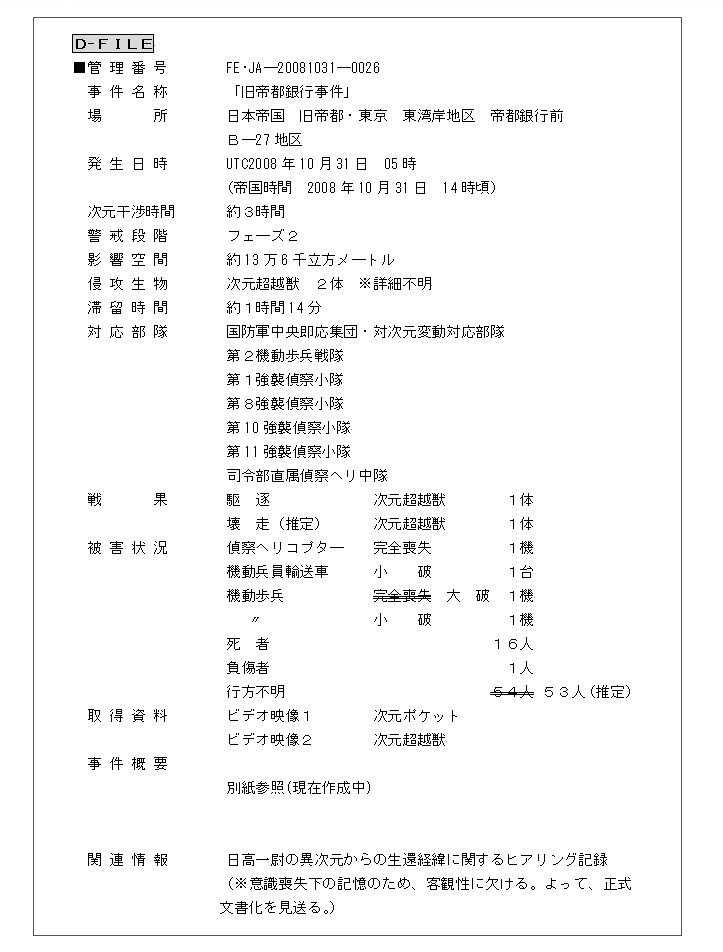
国防軍中央即応集団・対次元変動対応部隊駐屯地内の広場に、大破した蒼龍7号機と日高が忽然と姿を現したのは、事件から五日後の真昼のことだった。
奇跡の生還に部隊の誰もが驚いたが、霧山一佐と金城三佐は、意外なほど冷静にこの生還を受け止めていた。
日高は休養とメディカルチェックのため、国防軍中央即応集団・第101化学防護隊の管理するC―4施設に約一週間隔離された。そして、その間、事件後の経緯とについて、繰り返し聴取されたが、当の本人さえあいまいな記憶は、正式な記録に起こされることなく終わってしまった。
「日高一尉は、奇跡を起こしたって評判になってますよ。一時は行方不明者リストに、掲載されたくらいですからね。」
片足を失った村雨一尉は、静養とリハビリのため休職となった。
それらの事情を、日高の新しいペアとなった三塚健二尉が、興奮気味にまくしたてる。数が限られた「蒼龍」の正規パイロットは、機動歩兵パイロットのあこがれでもある。同僚の負傷による休職は気の毒と思うものの、それとこれとは別と割り切る若者気質に、日高は複雑な思いを感じ、表情を悟られないように、窓の外に目をやる。
隔離病棟から移ったばかりの個室からは、窓越しに病院の塀に沿って続くポプラ並木が見渡せる。北国の短い秋も終り、木々はすっかり葉を落としている。遠くに見える山々は、すでに白い雪化粧に覆われている。
「……7号機のおかげだよ。」
「えっ? 」
「俺の7号機は、どうなった? 」
事件で片足を失い、小破の判定を受けた「蒼龍」2号機は、三日後に修理されたが、DS&APUとの連動不良により、再度全面整備を受けている。また、日高の7号機は修理不能の判定を受け、予備機の「翔龍」8号機へDS&APUを乗せ換えて、新7号機とすることが決定していた。機体は格納庫内でブル―シ―トをかけられ保管されているが、後日、スクラップとされるはずである。
「そうか……」
日高が窓の外に目を向けたその時、病院の敷地に一台の黒塗りのベンツが入ってきた。正面玄関前には救急車が止まっているため、ベンツは、正面玄関アプロ―チに入ることなく、手前で停車する。
やがて、後部座席から初老の男とともに、白いコートを着た少女が一人、黒服姿の男にエスコ―トされて降りてきた。前席からも背広姿の男が降り、初老の老人の前に立って、三人を案内していく。
歩き出した四人を見つめる日高の視線に気づいたのだろう。白いコート姿の少女が、ふと立ち止まって日高の方を見上げる。
日高と少女の視線が合う。
少女は軽く会釈し、それに気づいた黒服の男も日高を見上げる。そのサングラスに隠れて見えない視線の鋭さに、日高は一瞬気色ばんだものの、視線はあえてそらさない。男の視線は、警察のSPやボディガ―ド等の持つそれである。少女は、その明るい外見とは異なり、相当な重要人物、またはその関係者ということらしい。
最上階の日高の病室からでも、その少女が相当な美少女であることはわかる。透き通るような白い肌と栗色の長い髪。年齢は、15、16歳というところか。白いブーツを履いていて、身長は百六十センチ程度。細い体つきからすると、体重は四十五キロ程度だろう。黒い腕時計をつけ左腕には、小さな手提げバッグをもっている。
「日本人だよ……な。」
パイロットとしての視力の良さと観察眼から得た情報が、少女に伝わったのか、見つめている少女の頬が少し赤くなったように見える。
その礼儀正しさと、少しはにかんだ笑顔に、日高の胸が高鳴る。
やがて、黒服の男に急かされたのか、少女は病院の一階のひさしの下へ消えていった。
「一度死に掛けると、種の保存本能が刺激されるのかな?」
「はぁ? 」
「いや、なんでもない。独り言だ。」
日高は、三塚の応答を待たずに毛布をかぶる。
「悪い。疲れたから、休ませてくれ。」
「ああ、すみません。気がつかなくて……。また、きます。」
三塚が退室した後、しばらくして、日高はベッドから飛び起きた。
「やばい。……俺って、ロリだったのか? 」
病室に備え付けの鏡には、少し顔を上気させたヒゲ面の男が映っていた……。
(第一話完)