 |
音楽家インタビュー・アーカイブ・シリーズ1 阿部 寛さん(ギター・バンジョー奏者)p.1
|
2001/05/18掲載
(2007/08/27一部改訂)
interview&text by Ikuko Asai |
簡単なことしかやってないんだけど
与えるインパクトが大きい、
僕はそっちになりたい。 |
〔プロフィール〕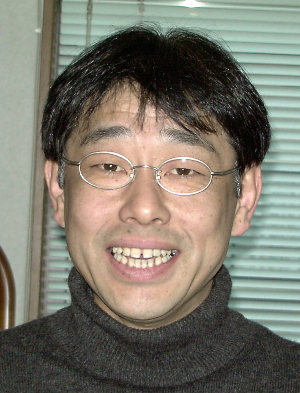
神奈川県出身。10代の頃より、クラブ、キャバレー等で演奏する。知友に恵まれ、各地でライブ演奏活動をして現在に至る。スタジオではジャンルを越えた音楽制作に参加、多くの録音で様々な音楽家と共演している。クラシックの世界では、NHK交響楽団、東京フィル、大阪フィル、新日フィル等の公演に参加している。また、約20年間に亘って、谷 啓&スーパーマーケットのメンバーでもある。一方、趣味が嵩じて15年ほど前より、ギター、バンジョーなどの弦楽器を自ら製作する。昨年は、自己のCDもリリースし、トラディショナルなアコースティック・ジャズの演奏に力を注いでいる。
▼Guitar,Banjo奏者、阿部寛・Web Site |
|
| ゲストはギタリストの阿部寛さん。スタジオ・ミュージシャンのギタリストの第一人者として多忙な日々を送りながら、ご自身が最も愛する音楽は「トラディショナル・ジャズ」。ライブ活動やCD制作でも活躍中です。 |
◆譜面を読む勉強は、完全な独学
―阿部さんがプロになったきっかけを教えてください。
「僕は16歳くらいの頃から仕事をしてるんですよ。昭和40年代の話ですが、当時は、新宿、府中、国分寺、立川、八王子など演奏する場所がたくさんあって、お店(キャバレー)があれば必ずバンドが入っていた時代があったのです。今の若い人がかわいそうなのは、そういう場所がないことですね。僕は、楽器を持っているというだけで仕事を頼まれ、いきなり生演奏をしてました。それが今、身になっています」
―お店ではいろんな曲を弾いいてたのですか。
「その頃流行っていた流行歌が多かったけど、どんな曲でも弾きましたよ。僕はまだその頃10代で、エレキバンドしかやってなかったから当然、譜面なんて読めないわけ。だから最初は言われるがままに適当にやってたんだけど、そのうちにメインのバンドに行かされるようになって、そこではショーがあるので、譜面が読めないとダメ。そこから譜面を読む勉強を始めたんです」
―独学ですか。
「そう、完全に独学。もう20代の前半だったね。・・・・・あのね、なんにもわからないうちからドレミファソラシドを読まされる音楽教育もいいんだけど、ある程度方向性が決まってから、自分がやろうと思ってからやった方が身につくというかね。どっちが良い悪いじゃなくて、僕はそっちかなと。勉強のしかたがわからないから、当時の歌謡曲の本(「歌謡曲のすべて」)に載っているメロディーを、1曲目から弾くんです。弾くことだけなら簡単なんだけど、ちゃんと休符を休むとか、タイをちゃんとのばすなんてことをきちんと考えながら弾くんですよ」
―クラシックの練習みたいですね。
「そう、まるでクラシック。弾いていて途中で間違ったらまたはじめからやりなおして。結局、1冊最後まで行ったのは何回かしかないんだけど、そういう練習をとにかく毎日していたら、3ヶ月で譜面は読めるようになりました。譜面を見てわからないところを調べるためには、楽典なんかも見ましたよ。譜面の読みかたを知るまでは、ギターのどの部分になんの音があるかがわからないで弾いてたわけです。今でも耳で聴いてやっている人はそうですよ。ドがどれでレがどこにあるか。ギターの人はそんなことはわかってなくてもコードの形で覚えてるんですよ」
―音を聴いて「この形はこの音だ」ということですね。
「そう。若くてギターをやっている人のなかにはそういう人がいっぱいいると思いますよ。でも僕は、当時既に仕事をしていたから、毎日譜面が来るわけです。周りの慣れている人はもう平気で弾いてるんだけど、僕は、ワン、ツー、スリー、フォーって始まった瞬間に、どこやってるかわかんないわけですよ。譜面を追っていけないわけ。だから毎日先輩やバンマスから、あーだこーだ言われる。自分でも1日でも早く譜面が読めるようになりたかった。3ヶ月でだいたい読めるようになって、最後まで譜面を追えるようになりましたよ。読めるようになると自信がついてくるんだね。最終的には、Bフラットで書いてある譜面をCに読み変えるとかが平気でできるようになったね」
―実践だから、転調などのパターンもどんどん身についていくわけですね。
「そう。当時の現場では実際、“Cメロの楽譜忘れちゃった”とか言われるわけですよ。“Bフラットしか持ってきてない”とね。そんな時は、“いいですよ、Bフラットの楽譜を見ます”と言って、1音下げて弾いたりね。仕事の場合は、いかに集中するかだから。でもこれは“慣れ”だね。今の若い人にはこういう経験の場所がないからかわいそうだということです。けれども、もちろんこれは、職人的な世界の話をしているわけで、自分のなかになにかいいものがあって、他のことが出来なくてもそのいいものがちゃんと表現できるのなら、それでもいいけど」
―いろんなプロがあるということですね。
「そう。いろんなスタイルがある」
|
| P.2 / 3 / 4 |