|
先生や友達に支えられて歩んで来た事を書き綴ってきたが、進路については僕ほど中途半端な人間はいない。
音楽が好きといっても、ピアノは弾けないし、音楽大学には行けない。
体操が好きといっても、国体の予選で落ちるようではアスリートにはなれない。もし国体に出場できていたら、
日体大に推薦でいけただろうが、それも叶わぬ生徒だった。医者に診てもらったら「心臓肥大が少し気になる。スポーツ選手には向いてないだろう」という助言もあった。
唄が旨いといっても、上京して有名な歌手あるいは先生の弟子になるほどの勇気はない。
英語が好きといっても、久山君のように一発で東京外国語大学に受かるほどの実力はない。
宇宙が好きといっても有名な国立神戸大学物理学部には受からなかった。受験勉強もしないで受かるわけがない。
残るは電気工学、電子工学だ。「これからは真空管から半導体へと変わる時代だ。今がそのチャンスだ」ということは知っていた。アンプ製作は好きだったし、電子工学の道に進むことが、これで決まった。東京電機大学電気通信工学科に受かった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大学の卒業論文については、大学編で述べるのが真っ当であろうが、簡単にまとめた記述がMJ誌の1995年3月号に掲載したのがあるので、ここで、こういう内容だったという事だけ紹介しておこう。
§17に小生宅の当時の部屋が非常に美しいカラーで載っているが、このほかにも巻頭グラビアなので、数えると全8枚も掲載されている。この時はカメラマンと編集長が来宅。
余計な話はこれくらいにして、卒論内容はどういうものだったかを紹介しておこう。
・・・この頃は徐々に真空管からトランジスターへと移り進もうとしていた時代で、私も当然時代の流れに沿って歩むことになるが、それでも自作アンプは真空管が主だった。私の卒論はテープレコーダーの製作だったが、オール真空管だったように、まだまだトランジスターには信頼性や特性上に問題があったのである。この拙論は単なる製作記事ではなく、FMのステレオ放送の実験が開始されていた頃だったので、パイロット信号とバイアス周波数のビートにメスを入れ、バイアス周波数は150kHz以上にしたいという提案をしたものだった。・・・と、こういう内容です。
卒論全文は長大なもので、回路図や特性図、写真も付加していた。「パイロット信号とバイアス周波数のビート」というのは、いわゆる “干渉” です。高次調波が発生して左右のステレオ音声にひずみが生じる現象です。パイロット信号の周波数は既に規格で19kHzと決まっていたので、問題は録音機側のヘッドのバイアス周波数です。これとのビートが問題になるわけです。使用する録音ヘッドにも左右されるので、僕は神田にあった電気堂という店で買ったものだった。これでテープレコーダーを製作し、バイアス周波数をいろいろ変えて行き、それをグラフにして、最も低ひずみになる周波数を見つける。学校の実習室で測定器をいくつも借りて、特性を取っていった。助手の先生には随分と迷惑をかけただろう。
結局、その後の高級テープレコーダーの録音ヘッドのバイアス周波数は殆どが200kHzくらいになっているようだった。
恥ずかしながら、あとで分かったので、当時は知らなかった事を白状すると、FMステレオ放送の帯域は電波法で1局あたり100kHzと決まっていたそうです。だから私の提案150kHz以上というのも、上記200kHzくらいというのも理にかなっているわけで、当たり前の話である。受信している周波数スペクトラム以上だから、絶対にビートは起こさない事になる。
いやはや、そんな事を知らないで、上記のような卒論を書いたのだから、無駄だったのだ。若気の至りというのか、一生懸命にやったのに。(^_^;)・・・
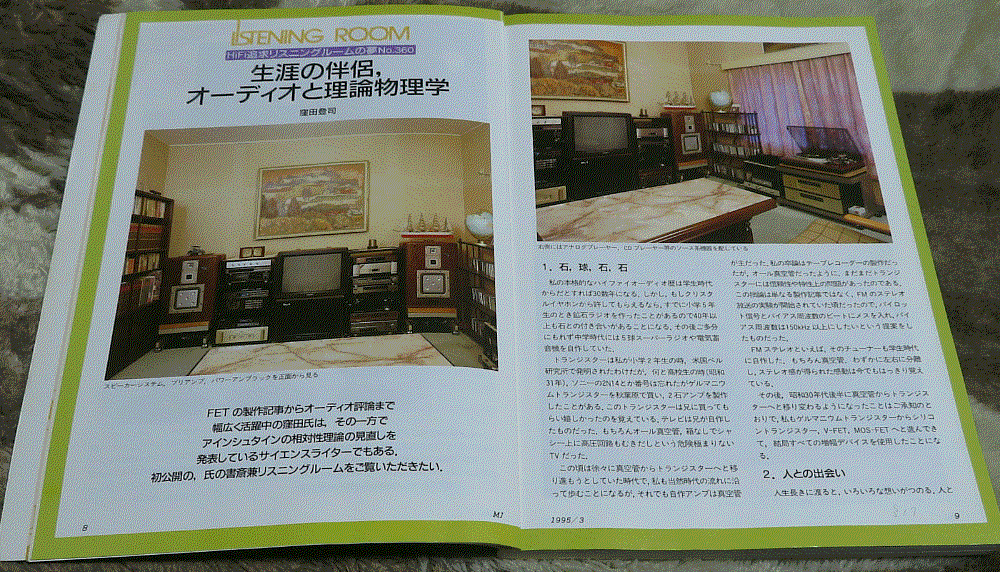 MJ誌 1995年3月号巻頭グラビアより MJ誌 1995年3月号巻頭グラビアより
(2001年10月以降は、この部屋は書斎兼寝室になっている。階下の半地下に約12畳のオーディオルームを造った。スピーカーも代わって、B&Wマトリクス801になった。写真のソニーの平面スピーカーは位相特性が抜群に良い)
|