|
更新したのでコントロールキーを押したままF5を押してください
§18 オーディオ、カメラ、カーマニア 追稿:日本全国プリメーラでドライブ旅行
オーディオ、カメラ、カーマニアと言えば男性の持つ3大嗜好であろう。私もご多分に漏れず、これらにハマッた人間である。この章では相対論とは離れて少し気休めをしよう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(1)オーディオは「オカルトオーディオをやっているトンデモ窪田」とネットで拡散されたが、この件はのちほど述べる。
最も親しかった評論家は長岡鉄男さんだった事を記しておきたい。メーカーの新製品発表会では、必ず私を見つけて、つかつかっと寄ってきて「やー」と話しかけてくる。大先輩であるため挨拶一つにしても気を遣う。それが嬉しい思い出となっている。1980年代の中頃だったか、某社某工場の見学会に出席したとき、長岡さんと二人で工場の広い庭のコーナーに “記念植樹” をしたことがある。
また日本屈指のレコード評論家であられた若林駿介先生も、講師として音響芸術専門学校にお勤めになっていたので、講師室で、近寄りがたい大先輩である事を忘れるほど親しくお話に弾んだ(はずんだ)のを思い出す。
ルーカス・フィルム社の取材にもご一緒した。娘さんはピアニストであり、リサイタルに招待されたこともある。
空前の大ヒット実話映画『南極物語』の監督兼チーフプロデューサー貝山知弘さんも、ご一緒したルーカス・フィルム社の取材映像を編集したものを贈ってくださったし、上記メーカーの新製品発表会でお逢いした際は気さくにお話できた事も特記しておきたい。「窪田アンプを聴いてみたい」と仰って、私のアンプに特別な興味を示されていたが、いつもプロダクションの事務所通いであるため、お忙しくて実現出来なかった。
オーディオテクニカの初代社長・松下秀雄さんがのちに会長になられた頃、「入力インピーダンスがゼロである窪田さんの逆相型MC用EQアンプを作ってくれないか」と頼まれて製作している最中であった。亡くなられたのは。悔やまれて、悔やまれて、悔やみきれない。お元気だった頃「腹式呼吸すると身体にいいんだ」と言われたのが私にとっては最期のお言葉となっている。・・・・・
1988年にMJの取材で、ご自宅に伺った時からの知り合いで今田智憲(いまだちあき)会長も私のアンプを聴きたいと仰っていたお一人である。今田さんは東映動画の元社長で「銀河鉄道999」や「ドクタースランプアラレちゃん」などヒットを飛ばし、日本のアニメ界を牽引された方である。Wikipedia で検索すると、そのご活躍が詳しく載っているが、書かれてない事がある。取材の時、仰ったのだが、会長は広島県のご出身で、「原爆の被爆者である」との事であった。
すっかりオーディオ仲間の知り合いとして、都営三田線の白山から近いご自宅に何度も行ったことがある。二階の屋根を突き抜ける二本の大型コンクリートホーンドライバーを目印に豪邸が建ち並ぶ住宅街を歩く。部屋に入るとオールホーン型の4ウェイスピーカー群に圧倒される。「このスピーカーを窪田さんのアンプで駆動すると、どんな音になるかな」と仰ったことがあるが、私は「いや〜、このままの方がいいんじゃないですか」と返したが、「窪田さん宅のオーディオルームでB&Wのマトリクス801を聴きたい」と何度も仰っていた。2006年6月にお亡くなりになって(享年82)夢と消えてしまった。
私の考案したオーディオ回路は特許を取っているわけではないが、著作権保護で守られているのでメーカーが勝手に使用する事はできない。そのため回路を買ってくれたメーカーが3社ある。
○アメリカのカウンターポイント社。「パワーアンプの終段をNO−NFBにする」もの。これは私としては満足のいくものではなかったが、さすがメーカーは特性のよく揃ったNchとPchのペアーデバイスを使用しただけあって、安定なアンプになっていて音質も良かった。
ところが、なぜ私がNO−NFBにしたかの回路上のメリットや工夫など全く知らないで、私を含めて数人を『トンデモ』と小馬鹿にした「トンデモ本の世界」(トンデモ学会のY.H著)がベストセラーになり、Y氏は何百万円もの収入があったことは有名である。高校卒の筆者で、これだけの収入を1冊の本で得たのは前代未聞である。「オカルトオーディオをやっているトンデモ窪田」というのがネット上で拡散したのは、まさにこのY氏が本家である。
○デンマークのオルトフォンは私の回路をそのまま使用したもので、例の「抵抗1本で上下のFETのバイアスを同時に掛ける」というヒット作だった。MCカートリッジ用EQアンプである。ヘッドトランスを使用するより遙かに良い音がする。オーディオテクニカの松下秀雄会長が私に依頼されたのが、これであった。
○もう一件は日本のアキュフェーズ。終段のパワートランジスターのバイアスを掛ける回路に「温度特性が負になる中型MOS−FETを使用して終段の動作の安定化を図る」というもの。私の製作したパワーアンプは殆どこれである。真夏の暑い日でも、真冬の寒い日でも、電源投入時からファイナル段のアイドリング電流が変動しない。
最近のアキュフェーズの高級アンプはファイナル段のバイアス安定化はもっと工夫してあるようだ。
面白い思い出がある。それはパワーアンプであるが、「小音量の時はA級動作をし、大音量にしたら自動的にAB級動作をする」というパワーアンプ。電波科学に発表直後、NHK放送技術研究所から「そのアンプを1ヶ月ほど貸してくれないか」との依頼があって御貸しした事がある。どういうことをしているのか、詳しく分析したようである。「な〜んだ」とお笑いになったと思う。きわめて単純な発想であるからだ。ファイナル段の電流を検出して、ある値以上になるとバイアスを深くするだけ。
これには欠点がある。A級からAB級に変わる時、プッシュプルの上下の波形の繋ぎ目にスイッチングひずみ(クロスオーバーひずみ)が生じる事である。そんな事はオシロスコープを見て分かっていたが、「通常はA級動作で音がいい。AB級になる事はまずない」という気持ちで試作的に発表したものである。メーカーも何社か同類のアンプ(回路は異なる)を発売したが、人気がなく、廃れて(すたれて)しまった(^_^)。オーディオマニアは聴覚に優れている!
(2)カメラは父がカメラマニアだったこともあり、長女が生まれた時からカメラは手放すことはなかった。アンプやスピーカーなどの製作記事の過程を写真に撮って編集部に渡すためにも貴重な存在だった。何台の、そして何本の交換レンズを持っていたか数知れない。これらはすべて新宿スタジオアルタ横の中古カメラ店に売って、現在はデジカメオンリーになっている。
フィルムカメラの最後は NikonのF4であった。このF4は日本中を沸かした超絶カメラとしてよく知られている。某新聞社のカメラマンが普賢岳の火砕流を撮影している際、呑み込まれて死亡したが、のちに火砕流の中から発掘した焼死体の手にF4が握られていた。メーカーがF4を遺族から譲り受け、蓋を開けると、何とフィルムが焼けないで残っていた。現像したら、迫り来る火砕流をしっかりと捉えていた! 驚愕と涙の実話である。
(3)車は25歳の時からだ。最近の常識からすれば遅いとも言える。NTTdocomoに入社した娘は19歳で普通車免許を取ったし、日本で最も自家用車の所有台数の多い群馬県では車の免許の取得年齢の平均は二十歳だと聞いた事がある。
私の話に戻そう。オートバイ(自動二輪)の免許は大学2年生の時、アルバイトで東京電力で働いていた際、鮫洲試験場で獲った事は大学時代編で述べたが、普通車の免許は武蔵小金井に住んでいたので、府中試験場だった。二度落ちて三度目に受かった。私たち受験者グループは25名だったが、そのうち5名が受かったのを覚えている。
ちなみに教習所には行ったことはない。そんなお金はすべて相対論の書籍代になっている(^_^)。
免許が取れたらすぐにセドリックの中古を買った。それからカーマニアに突進。結婚するときも岡山の実家に往復していたが、まだ東名高速道路はなく、名神高速道路は出来たばかりだった。山陽道に繋がるあたりは工事中だったため、途中で国道2号に降ろされる。殆ど車はいない。私たちの専用道路(?)だった(^_^)。
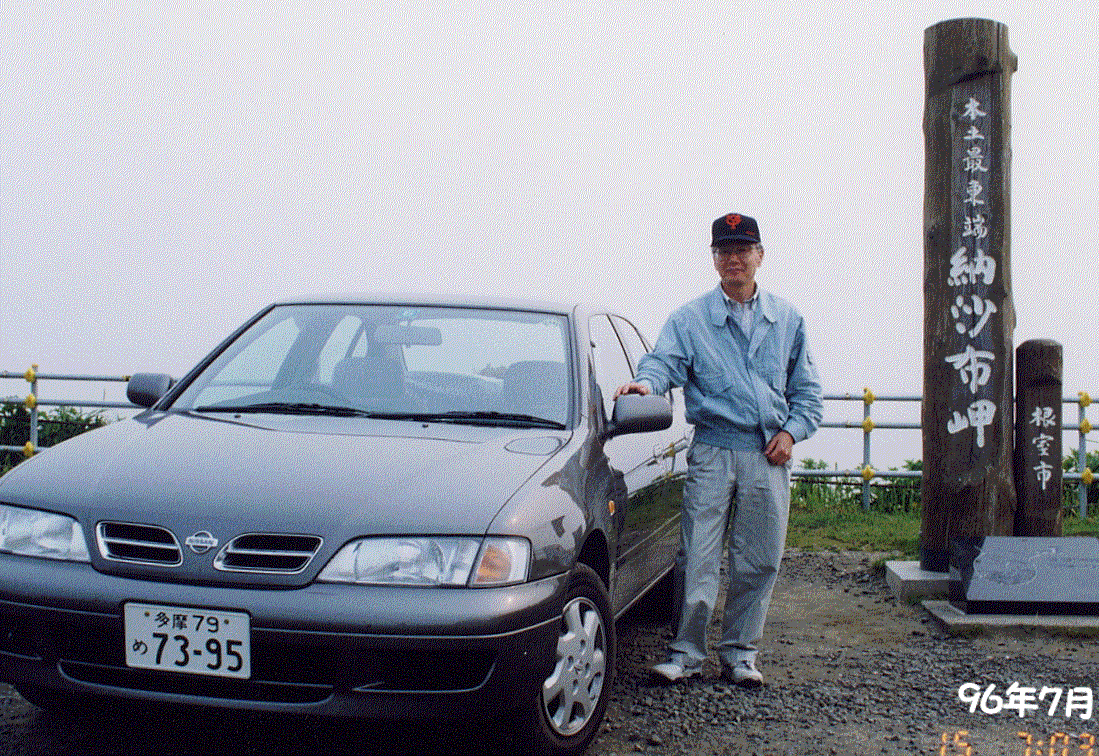 初めて買ったクルマ・中古のセドリック/§11にこの車が写っている 初めて買ったクルマ・中古のセドリック/§11にこの車が写っている
ハンドルが最近のものより大きいですね。気が付きましたか
また当時はエヤーバッグはなかった
63歳で車をやめるまで38年間、安全運転の模範みたいな(?)カーマニアだった。
車をやめたのは、“吹割の滝”を見に行こうと家内とドライブしている途中、正面衝突の事故が私たち(妻と)を襲った時だった。相手は19歳の少年で居眠り運転。スーッと私たちのレーンに入って来た。左側は歩道との境でガードレールがあるし、右にハンドルを切って逃げるわけにはいかない。どうする事も出来なかった。なぜって相手が居眠りかどうかは、まだ分からないのだから、相手が急ハンドルで自分のレーンに戻るかも知れない。もし戻ったら、私の方から右車線の相手にぶつかって行くことになる。だからである。瞬間の私の判断は正しかったと思う。もちろんブレーキは踏んだが、よける事は出来ない状況だったということである。
真っ正面からドカーンとぶつかった。
私の車はプリメーラの新車だった。この車は北欧に輸出するもので、車体が非常に強硬に出来ている。余計な話だが、プリメーラは普通のオートマ変速機ではなく、スポーツカーと同じ無段階変速で、発進して時速80kほどになるまでエンジンの回転数が変わらない。なぜ、こんな無段階変速が出来るのか、その構造を知っている人は、かなりのクルマ通である(^_^)。
逆に言うと、時速100kで走っていても、そのままローに落とすことが出来る。レーシングカーではエンジンブレーキでコーナーを回るとき使うが、あれと同じだ。私も何度かやった事がある。時速100kで走っているとき、急ブレーキなんてやったら地獄行きだから。
話を戻すが、上述のようにプリメーラは車体が非常に頑丈にできているので、フロントバンパーが壊れてボンネットが少し持ち上がった程度だったが、相手のサニーはぐじゃぐじゃ。ガソリンがどーっと流れだし、付近がガソリンの川になった。どなたが110番したのか知らないが、まもなくパトカー2台、救急車2台、消防車1台が駆けつけて、警察官がメガホンで「タバコは吸わないでください!火の元は消してください。蒸発したガソリンに火が付いたら車ごと爆発します!」などと叫び続けていた。消防車から白い粉が広範囲に蒔かれて付近の住民には事なきを得たが、サニーの中には、まだ運転手がいた。運転手に怪我がなかったのは、多分エヤーバッグによるバッファー効果と衝突時の運動エネルギーが車のぐじゃぐじゃエネルギーになったからだろう。
あとで警察官に聞いた話では、運転手はしばらく、何が起こったのか分からなかったそうだ。余っ程(よっぽど)ぐっすりと寝ていたんだろう(^_^)。笑い事ではないですね。
この時、奇妙な現象を見た。衝突して1分か2分後、私の車の左側、つまり家内の目の前のフロントガラスが、目の前の1点から四方八方にミシミシっとヒビが入った。救急車の隊員が「奥さん、頭を打たなかったですか!」と叫んでいたが、家内は「いえ、大丈夫です。安全ベルトをしていたので、窓の方には手も頭も行ってはいません」と説明した。
おそらく車全体に異常なストレスが発生し、それに耐えきれなくてヒビが入ったのだろう。
まア、そんなこんなで、もし相手が大型輸送トラックだったら、さしものプリメーラもペチャンコだろう。私たちは今頃天国だ。怖い、もう車はやめようと思ったのが、その時だった。車はその日のうちに買ったディーラーに引き取ってもらった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(4)こんな事になる前まで、毎年一人で、各一週間程度の国内ドライブ旅行を楽しんだ。第1回目(1996年)が北海道、その後、東北、北陸、東海&紀伊半島、中国地方、四国、九州(2度行った)と計8回。これらは綿密な計画を立てて実施したもので、じつは、その前にプリメーラの新車を買ったとき、嬉しくて大阪、京都、奈良をドライブした事がある。その時の写真をここに掲載しておこう。有名な「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」に立ち寄ったときのもの。
なお、余談だが、当時はまだデジカメは無かった頃なので、使用したカメラはすべて上述(2)の NikonのF4 である。

その後の日本全国ドライブ計画での無謀運転を一つ白状すると、朝7時にウチを出発して、昼食をどこかのSSで食べて、休憩も取らず、午後3時には淡路島の野島断層記念館の中に居たこと。
でも、この程度のスピードなら普通かな?淡路島に降りたら一般道だが、それ以外はすべて高速道路だったから。
この年は四国探訪をしたときだ。ご存じの吉野川は何億年前か巨大断層地震で四国が真っ二つに割れたと言ってもいいほどの地形だった。吉野川を挟んで、北側と南側では所によっては何十メートルもの段差がある。南側の方が高い。北側の方が低地だ。ということは、この巨大断層地震の時に瀬戸内海が出来た、という説を何かの本で読んだ事があるが、まんざら想像だけでもあるまい。この吉野川の景観を見ていると、実証しているようにも思えた。そんな事を考えながら私は徳島本線に沿って南側の道路をゆっくり走って池田経由で国道11号に出た。
こんな事を書き始めるとキリがないので(^_^)、旅の途中での人との出会いについてだけ述べておこう。一人旅では殆ど人との出会いはなく、孤独なものだ。初めに小学生に道を尋ねた時の楽しい思い出を3点書いておきたい。
1つは九州の高千穂峡に行った時のこと。観光ガイドブックと道路地図によってプリメーラを走らせた。地図を見ると、どうもこの辺だ。しかし、いっこうに、それらしき案内もなく、判らない。ちょうど小学生数人と出会った。
「すみません、高千穂峡って、どこにあるんですか?」と訊いてみた。数人の子供達が一斉に「この下だよ」と言う。「え?何も見えないじゃないの」、「だから、この下だよ」と指さす。「どうやって行くの?」、「行き過ぎているからバックして看板を見て!」。
バックは無理。大型バスは通れないほどの幅の狭い道路だから(この道は農道だったかも知れない)、バックは危険だと思って前方を見ると、左側は段々畑になっていて車が入れる舗装してない道がある。そこまで行って、坂を少し上り、バックしてUターンした。
ゆっくりと看板があるか探しながら走ったら、<矢印>があって、斜め下を向いている。「これか」と思い、左に曲がると急な坂になっている。100m以上か、かなり長い下り坂だ。この辺でやっと気が付いた。子供達が言う通りだ。この下が高千穂峡なんだ。降りて行ったら、目の前に高千穂峡の絶景が見えた。ただ観光本に載っている滝は見えない。ボートに乗って奥の方にもっと行かなければならないのだ。しかし、ボート乗り場もボートも無かった。
大きなお店が1軒だけあった。
今から思い出すと、ここは同じ高千穂峡でも、いくつかある、その一つだったのだろう。上を見たら、樹木が生い茂っていて、高千穂峡の天井とも云える景観だ。これでは確かに道路からは見えない。一人旅のいい経験をしたと思っている。
2つ目は四国の日本一綺麗な水の四万十川と、その橋の一つ、沈下橋(沈降橋)という橋を渡りたいと思って車を走らせた。地図を見ても判らない。おろおろしていると、ちょうど小学生が3人歩いて来た。学校の帰りのようだ。
「すみません。沈下橋はどう行けばいいんですか?」と訊いてみた。女の子が「ああ、沈降橋は、この道を真っ直ぐ行ったら、左に行く道があるから、そこを曲がって行けばあるよ」と教えてくれた。土地の人は沈降橋と言うようだ。
「ありがとう」とお礼を言って、その通りに左に曲がって行った。両側に背の高い葦(と思う)が茂っていて何も見えない。小型車が1台通れるだけの道だ。不安になったが、そのまま進むと、パッと開けて小型車なら2〜3台は止まれそうな空き地があった。そこから一直線に向こう岸まで橋があった。これだ!確かにガイドブックにある橋だ。橋の両側には欄干がない。大雨などで水かさが増しても、これなら水流に負けることはないだろう。そろそろと渡ってみた。中腹まで行った所で止まって、来た方向と行く手の方向の写真を撮った。行く手の方に橋を渡りたい小型車が待っている。これは!と思い、急いで渡った。待っている人に会釈をして国道441号に出た。
3つ目は山形県真室川の梅園。真室川音頭と共に日本中に知られている有名な所だ。ここに行った時の事。ガイドブックの地図に沿って坂道を上がって行った。この辺が頂上付近だという所まで行ったが、まるで梅園とは無関係な風景だ。ちょうど、その時小学生5人ほどが向こう側の坂を上がってきた。帰宅途中のようだ。「ちょっとすみません。真室川梅園という梅の木がある大きな公園を探しているんだけど、どこかな?」と訊いたら、「ここだよ」と言って、右を指さした。「え?塀で囲まれてて中が全然見えなかった。どこから入るの?」と言うと、「坂を登って来たんでしょう。坂の下に橋があるのを見た?」、「ああ、そう言えばあったような気がする」、「その橋を渡ったら駐車場があって、梅園に入るには石段を上がっていくんだ」と教えてくれた。お礼を言ってUターンをし、降りて行って橋を渡ったら、なるほど広い駐車場があった。大型観光バスが何台か駐車できる広さだ。石段を上がって見た。さっきの塀が見えない広〜い梅の木の公園だった。僕が行ったのは7月だったから、当然、梅の美しさを観ることは無かったが、土地の子供達との触れ会いには一時(いっとき)の疲れを忘れさせる良い思い出となっている。
一人旅の寂しい途中、土地の人との触れ会いは、こよなく良いものだ。以下、いくつかの出会いを回顧してみよう。
北海道・襟裳岬に行った時の涙の話を一つしておきたい。ご存じのように襟裳岬は北海道を象徴する太平洋に突き出た三角形の半島の先端である。舗装などしてない自然のままの広場であるが、何十mもある断崖絶壁の表層大地である。しっかりしたコンクリートで作られた柵はあるが、見下ろすだけで身がすくむ。キタキツネが1匹10mほど僕から離れた所でじっと見つめて<餌を欲しがる>顔をしたが、そばに「えさを与えないでください」という看板があった。周りを見ると誰もいない。僕とキタキツネだけである。珍しいのでキタキツネの写真を撮ってきた。
広場の中程に一軒のおみやげ店があった。2本の電線があったので電気は来ている。家内が「北海道に行ったら出し汁にする昆布を買ってきて」と言っていたので、それを思い出して入って行った。いろんなおみやげが並んでいたが、そういう昆布があるかどうかを店員さんに聞いた。40代のおばちゃん一人である。「ありますよ、これです」と丁寧に包んでくれた。その時の会話である。
「今日は天気が良いです。こんな、風のない良い天気は、1年に10日ほどしかないんですよ。太平洋からの吹きさらしで、観光客は殆ど来ません。・・・こんな所で一人で店番しているわたしなんぞ哀れみを持って軽蔑するでしょうね」と。
僕はびっくりした。「なんて事をおっしゃるんですか。そんなことないですよ」と、思わず昆布の包みの上から、おばちゃんの手を握った。その時の嬉しそうな優しいまなざしは、現在でもまぶたに涙と一緒に浮かんでくる。
お店と別れて坂を下り、来た道に出て(国道336号)、右に曲がり、釧路方向にドライブした。途中で<ナウマン象発掘の地>と案内板が見えたので、左折して入って行った。2〜3百メートルか、すぐ近くだった。碑があって囲いもあり、説明文の看板もあった。北海道にはマンモスなどの骨も発見した場所が多数ある。大陸続きだった古代にやって来たのだろう。
国道に戻り、釧路方向に再び向かっていた途中。夏祭りだろう、トラックの上に踊り場が造られていて、大音量の囃子と共に、何人もの若い女の子が法被(はっぴ)を着て踊りながらやって来た。男性たちはトラックの前後に数人づつ歩いて笛や太鼓、摺鉦(すりがね/チャンチキ)である。ゆっくりやって来た。車を左端に止めて子供の頃を思い出しながら観た。
窓から手を出して大きく振ったら、一斉にこちらに向かって、燥ぐ(はしゃぐ/飛び跳ねる)ように手を振って応えてくれた。心底楽しそうだった。こういう場面も一生忘れられない思い出となる。
釧路湿原を展望台から観た絶景も忘れられない。日頃の苦労や悩みが吸い込まれる思いだった。降りて行ったら湿原の中に歩ける道があり、そこから川でカヌーの練習をしている(遊んでいる?)若者たちも見えた。また珍しいトロッコ列車も通ったのが見えた。1日に一回か二回ほどの列車である。殆ど観光客を乗せて走るのだろう。
その後、屈斜路湖、摩周湖、裏摩周、厚岸、根室半島、納沙布岬、野付半島、知床半島(知床五湖にも行った。たった一人。誰もいなかった。熊が出るから用心との看板があちこちにあった)となるが、知床半島を去る頃が、ドライブ旅行一週間の半ばを過ぎた時だったので、全身の疲れとストレスがかなり溜まっていた。
もう少し前、人との出会いの話にしよう。
根室半島は太平洋側ではなく、北側の根室湾側を走った。もう少しで納沙布岬に着くという直線道路で、私を猛烈なスピードで追いかけて来るような乗用車がバックミラーに映ったので、左側に寄って左のサイドランプを点滅させた。私は60kくらいで走っていた。
ププっとクラクションを鳴らしてびゅーんと追い越した。ご夫婦か、男の人が運転していた。やがて私も半島の先まで着いたので、写真を撮った。このセクションのラストに、その写真を載せた(96年7月15日朝7:03となっている)。この写真のすぐ右側に観光客用の大きなお店があったので、入って行き、例の「出汁昆布」を買った。かなり寒かった記憶がある。ストーブが焚かれていた。この時のおばちゃんとの会話。
「さっき、追い越した時のお客さんだね」、「はい、そうです」、「多摩ナンバーって東京だね」、「そうです」、「一人で?」、
「はい」、「まア」、「でも楽しいです」、「そう・・・きょうは霧が立ち込めていて歯舞諸島や国後島が見えないね。ここに写真があるから、観ていって」と天井の方を指さした。見ると側壁の上部にずらっと大きな(幅50cmくらいか)写真が何枚も掲載されていた。「写真撮ってもいいですか?」、「ええ、いいですよ」
せめて、これくらいはと思って写真を撮ってきた。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
四国の佐田岬半島に行った時の “人との出会い” で終わりにしよう。
地図で見ると平坦だが、実際には断崖絶壁の半島であった。井方という所だったかナ。ここから山に登るようにぐんぐんと上がって行くと頂上から平坦な道路になる。舗装してある。景色がいい。右側は瀬戸内海、左側は太平洋。
まさしく台形型の、いや殆ど垂直の断崖絶壁。多分、上述の何億年か前の巨大断層地震の時に出来た瀬戸内海の名残の半島であろう。
やがて、その約50kmほどの舗装道路が終わったら、今度はやっと乗用車程度の車1台が降りられる下り坂となる。
“わだち” があるし、<この先、通行止め>などの標識はないので、降りて行った。ちょっとハンドルを切り損ねたら真っ逆さまに海に落ちるか、松林に引っかかる。
無事に降りたら多くの民家があった。天然記念物に指定されている “あこう樹” の前で写真を撮っていたら、土地の人が「多摩ナンバーということは東京から来たのかね」と話しかけてきた。「そうなんですよ」と返事をして、30分ほどか、親しく話をした。その人は、この土地の出身だが、30年ほど大阪に出てサラリーマンをしていたそうである。帰ってきたら、すっかり村が変わっていた事を “あこう樹” を指さしながら「木がバッサリと切られているだろう、わしが子供の頃は、海の方まで木はあったので、あそこから飛び込んで、よく遊んだものだ」と懐かしそうに話をした。そういえば、いま立っている写真の所は道路になっている。昔はここまで海だったのだ。
「わしの姉は大分に嫁に行ったんだ」とも話して、普段は船で九州に買い物に行くなど話があった。「四国本土には滅多に行かない」とも言っていた。・・・帰りは今度は登り坂だ。無事に “四国本土” に戻った。
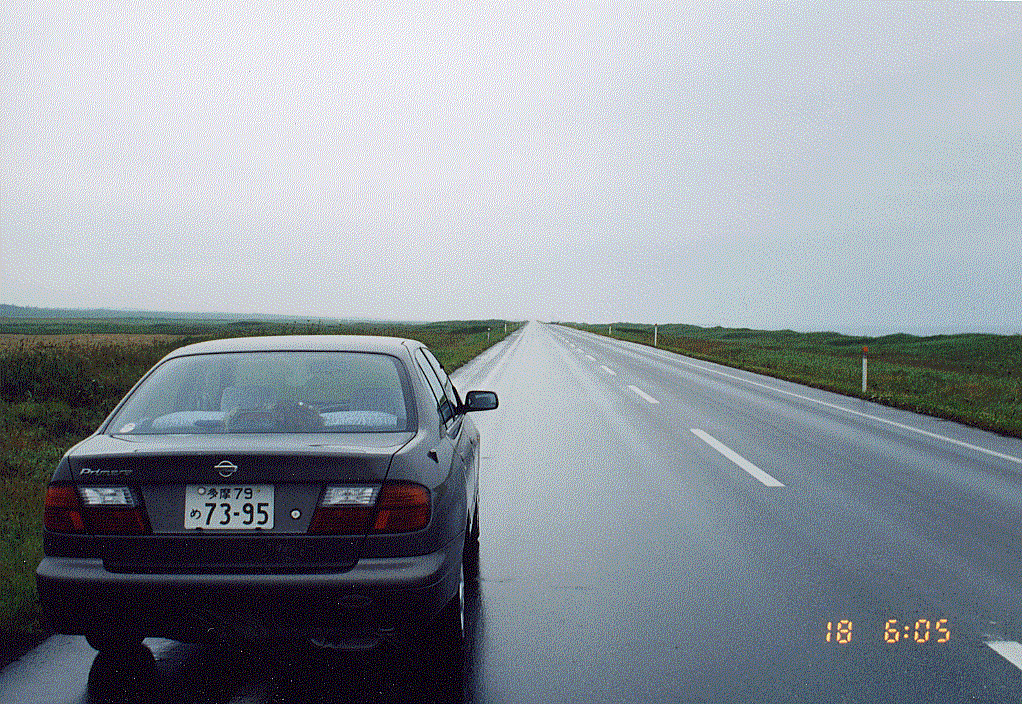
次の写真は内之浦ロケット発射場内でのひとこま。現在は種子島に移っているがJAXAの仕事を一部担っている。
入場する際、住所と氏名を書く。入場料無料
次の写真は北海道サロベツ原野。同じ場所から前方(旭川方向)と、後方(稚内方向)を写した。
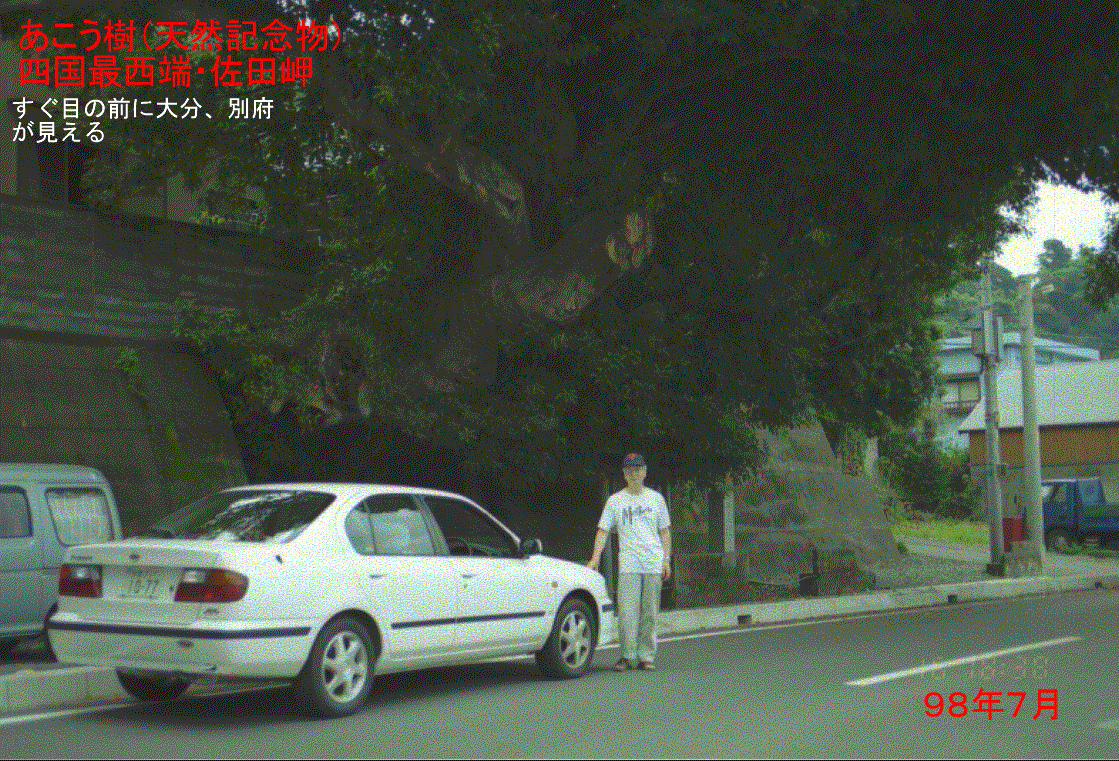 左側が日本海(運転席から言うと右側が日本海) 左側が日本海(運転席から言うと右側が日本海)
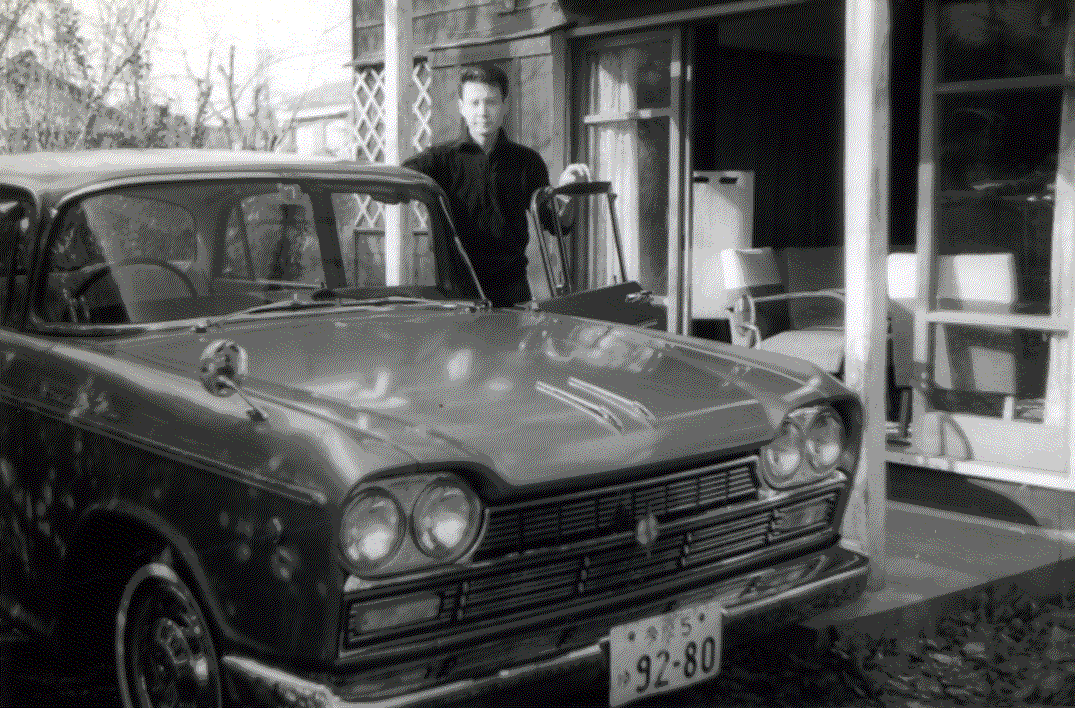 右側が日本海(カメラは Nikon のF4) 右側が日本海(カメラは Nikon のF4)
私のクルマ人生で最高速度を出したのが、この直線道路です。160km/hを超えたあたりで減速(エンブレ)
しました。
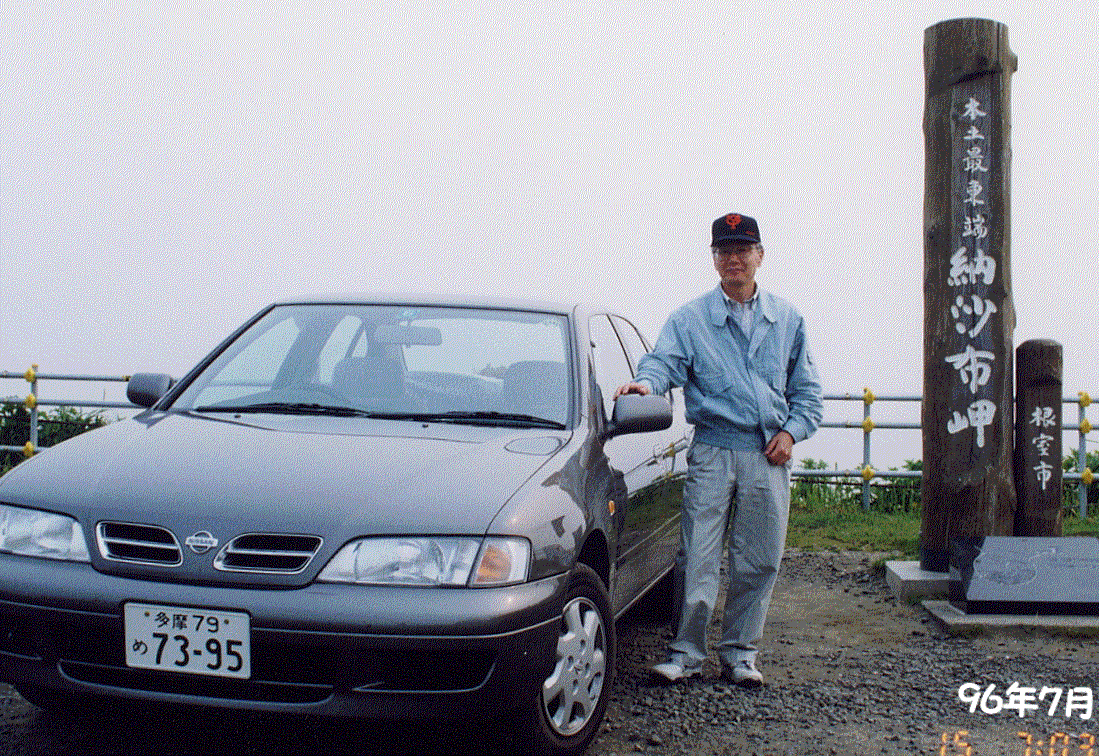 夏なのに、お土産屋店ではストーブを焚いていた。すぐうしろにハボマイ諸島があるのだが、霧が立ち込めて見えなかった。 夏なのに、お土産屋店ではストーブを焚いていた。すぐうしろにハボマイ諸島があるのだが、霧が立ち込めて見えなかった。
この年は知床峠に雪が残っていた。峠の頂上は広くて観光バスが1台、乗用車数台あったが、閑散としていた。
登る途中の坂道で車が滑らないようにと、雪かきをしていたおじさんがいた。挨拶をして、10分ほどか話に弾んだ。
峠で “焼きイカ” を買って食べた。新鮮でおいしかった。お店は、このテント張り1軒だけだった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
読者からの質問:このご旅行で事故はなかったですか?
窪田:厳しい質問ですね(-_-;)。事故にはならなかったですが、普通なら<ほぼ即死>という場面がありました。
第1回目の北海道旅行の時です。このルートは大きく分けて1週間の前半が北海道の右半分(十勝平野側)で、後半が左半分(石狩平野側)となっていました。
最終日「これで終わりだ」と江差を探索、松前を堪能、そして一気に函館から〜大間岬へフェリーで、というルートを取りました。函館は何度も行ったことがあるので、長い時間居たわけではありません。フェリー乗り場で身体を癒していました。
問題は松前から函館への帰路で起きました。どの辺かは全然覚えていません。“終わった” という1週間分の疲れが出たのでしょう。運転中寝てしまったのです。道路の中央車線上を走りながら、目を開けて寝ているんです。
もの凄い警笛でバーバーバー、ブアブアと大型輸送トラックが近づいて来た、と夢の中で聞きました。突然、そのトラックは左側の歩道に片側だけ乗り上げて、危機一髪で私の車を避けて通ってガクンと走行車線に戻りました。
この辺で僕は目が覚めたのです。
エ〜!僕は寝てたんだ!もし、あの歩道にガードレールがあったら、完全に即死だったろう!体中が震え上がりました。
広い草むら空き地があったので、そこで休みましたが、とてもじゃない寝られなかった。この道路は幹線道路ですが、その後、1台も会わなかった。僕の命を救った、あの大型トラックだけです。
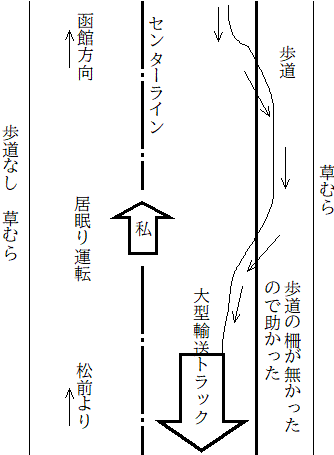
二度目のお便り:最も楽しかったのは?
窪田:これには、いろいろあって<最も>には答えられませんが、最初の北海道は、どこに行っても楽しかったです。
じつは北海道には後年、家内と一緒にツアーで行ったので、二度行った場所がいくつもあったことになります。
オシンコシンの滝や、摩周湖などです。ただし、この摩周湖湖畔は観光用に開発された場所です。観光バスが何台も駐車していた。
私の一人旅では裏摩周にも行きました。原生林の中を通る立派な舗装道路があり、かなりのスピードで突っ走って行きました。駐車場もあり、トイレもあった。誰もいなかった。湖畔から眺めた裏摩周も透明度の高い湖だった。
北海道以外では、最も印象に残っているのは高校1年生の時、学校祭の演劇で<五木の子守歌>をやったのですが、その五木村に行ったのが良かったです。九州のど真ん中、山また山の中でした。「ここが五木の子守歌、発祥の地か」と思うと感激しました。こぢんまりした山間の村という印象でした。ここで無料の温泉に入りました(*^_^*)。
二度目の九州旅行では、ここも山また山の奥深い山の中にある「椎葉村(しいばむら)」が良かった。ちょうど
『道路が土砂崩れで通れないので迂回せよ』との看板があったので、迂回して行ったが、昼なのに薄暗い鬱蒼とした山中をライトを点けて、そろそろ走った。1台しか通れない狭い道路だったので、カーブでは『クラクションを鳴らせ』との看板があちこちにあった。やっとの思いで椎葉ダムを探して行けた。
その近くに何軒かの家があり、洗濯物を干していた奥様が居て広場があったので、「こんにちは。ここに駐車していいですか?ダムを見学して来ます」と言ったら、「もちろんいいですよ」と快く承諾してくれた。ここでは駐車違反にはならないだろうと思われる道路わきである。
何時間ぶりかの散歩である。気持ちが良かった。「庭の山椒の木 鳴る鈴かけてよ ヨーオホイ 鈴の鳴るときゃ出てヨーオー おじゃれヨー」と、ひえつき節を唄いながらダムを見学した。回りを見ると誰も居ない。僕一人だ。
戻って来たら、おばちゃんが「どこから来たのかね」と訊いたので、「東京です」、「え〜?一人で?」、「はい」、
「マ〜」。
庭の隅の方にちょっとした崖のような斜めになっている石垣があって、そこまで行って「おいで、これが山椒の実だよ。都会の人は見た事ないだろうね」と言って、葉っぱをちぎって何枚かくれた。「いい匂いがするよ。嗅いでごらん」、「ホントだ、いい匂いがする」。・・・こんな出会いと会話があった。手元に、おばちゃんが山椒の実を取っている写真がある。
その他、この旅行で「行きたい!」と計画した場所は殆ど踏査したように思うが、映画に出てきたシーンで記憶にあるものでは『高原の駅よ さようなら』という映画で、ラストシーンで香川京子が恋人と別れる「信濃追分<しなの おいわけ>」の駅のホームと、その看板を見たくて、車を降りてすぐ近く迄行った事です。ここで撮影したのかと思うと感動しました。
映画のシーンでは、北海道夕張市で探した『幸せの黄色いハンカチ』の現場。矢印があって坂の上でした。撮影現場そのままの家とロープに掛かっている黄色いハンカチがありました。夕張市が保存しているのでしょうか。
他には三橋美智也も出演した映画『おんな船頭唄』の “潮来” や “あやめ園橋”、安井昌二と堀恭子が赤ちゃんを連れてお参りした “香取神宮” にも行って、「ここを歩いているシーンがあった!」など。
また、『伊豆の踊子』(1963度日活作品)で吉永小百合、高橋英樹などが歩いた旧天城トンネル。ここは「伊豆の踊子」の映画では、殆ど登場していると思うので珍しくないかも知れませんが、私は実際に見たら感動しました。
また、ファンタジック長編小説『少女コビの千年ワープ』を書く出発点となった埼玉県の『ヲワケの臣』の古墳がある稲荷山古墳を初め、出雲や熊本県の江田船山古墳などを見て回ったのも懐かしい。この日は雨が降っていて、靴がずぶ濡れ。
国外では小説を書くための取材旅行では長編科学小説『火星消滅』もありますが、これは“プリメーラ”とは関係ないので、拙著拙筆の目次をご覧ください。
以上、プリメーラで国内一周旅行は、取材しながらの計画旅行でもあった。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
旅行記最大の思い出を書いておきたい。大学1年生のとき、夏休みに一人で東北一周旅行した。この時は国鉄の東北周遊券を買って行った。旅館やホテルに泊まるお金はない。寝袋だった。最も多く利用したのは国鉄駅舎の切符売り場(待合い室)だった。どこの駅員さんも親切で、蚊取り線香までくれた。僕も持っていたが、お礼を言って貰っておいた。ほかには公園の東屋(あずまや)とか、お寺の境内など。
多くは語るまい。一点だけ。秋田県男鹿市にある寒風山に行ったこと。現在はネットで調べると、大きな回転展望台があり、観光地として大々的な宣伝を見られるが、当時は丘の上にポツンと直径5mくらいかの円筒形ガラス(プラスチック?)張りの雨よけ程度の展望台があっただけだ。そして、登ってくる途中の丘の下の方にテント張りのお店が三軒あった。
ぼくはどこから登り始めたのか全く記憶にないが、登っている途中で、土地のおじさんが畑に行く途中らしい馬車が来た。
おじさんが止まって「どこに行くんだ」と訊いてくれた。「寒風山に行きたいんです」と言うと、「乗れ」とぶっきら棒に言った。馬車の後部の空いている所に座った。ガタコン、ガタコンと狭い農道を30分以上か、登った所で、
「俺の畑はここだ。降りろ」と言う。降りたら「この道を真っすぐに行けば寒風山に行ける」と、これまた、ぶっきら棒に言った。「ありがとうございました」と言うと「あゝ」と応えた。このおじさんは馬に乗っているのではなく、馬を引いて歩いてきたのです。
何と親切な人なんだと心の中で泣いた。東北の人は人情に厚いと、よく謂われるが、地でいった話である。そういう思いを馳せて上記丘に登ったのだった。
そして、このガラス張りの展望台に入って行った。誰もいない。たった一人。
ここで唄ったのが林伊佐緒の『高原の宿』であった。・・・寝袋と蚊取り線香で寝た。
あれから何十年も経た、ある日、立派な観光道路を通って、プリメーラでここに来た。ガラス張りの展望台は無かった。だが、土台だけは残っていた。懐かしい!『高原の宿』を唄った場所だ。
・・・回転展望台が見えた。・・・しかし、そこへ行こうとする足は動かなかった。
質問:三度目です。これで失礼します。『高原の宿』はいい曲です。私も好きです。この歌詞には「君呼ぶ心」、「面影恋し」、「切ない心」が出てきます。ひょっとして窪田さんは、東京に残してきた恋人を思いながら唄ったのでしょうか。
大学1年生の時ですね。
窪田:もう勘弁してください(-_-;) 思い出すと泣けてくるんです。その通りです。友達がいました。とても可愛い子でした(東京都出身)。・・・ある日「わたし、オーディションを受けようと思うんです」。
ある番組に出演する俳優を選ぶオーディションがありました。受かったのです。あっと言う間に、当時人気番組
**に出演し、注目されて有名になりました。
当時<平凡>という雑誌がありましたが、大々的に大きな写真が可愛さ抜群のポーズで載っていました。現在も、その写真が載っている記事を切り取ったのが手元にあります。記事の冒頭に芸名と本名が両方載っています。
その後はタレントとして活躍するようになりました。こうなると僕なんかからすると高嶺の花、会う事すらできません。
よしんば会えたとしてもマスコミが追いかけて来るでしょう。週刊誌では格好のスクープになります。そして彼女には大きな迷惑を掛ける事になります。
だから会うことは無かった。・・・その頃です。あの展望台で『高原の宿』を唄ったのは・・・
あれから二人は別々の人生の道を歩む事になった。彼女は俳優、一人ぽっちになった私は生涯を掛けた相対性理論です。
そして60年以上経った。僕と同じ歳だから現在80過ぎです。お元気だろうか。・・・
ネットで探したら当時デビューした時の番組(日テレ)の出演者一覧に本名で載っていました。
Googleサイト/2025.5.17
§19 音響芸術専門学校で講師
|