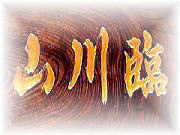山切の地に住う人々を慈しむ地蔵尊
お地蔵様が信仰されてきたわけは、子育て(子供を丈夫に育てる力)、安産(安産させる力)、抜苦(この世の苦しみを和らげる力)、衆生済度(誰にも御利益を与える力)など霊験(不思議な力)があると言われてきたからです。今あるこの世の大地の中に、総てのものを育てる力が内蔵されているように、人々を慈しむ心を無限にもっておられることから「地蔵」の名が付いたとされております。
時代の流れと共に、さいの河原の信仰と結びついて、親子の所縁が薄く旅立った幼児、また母の胎内から出ずに逝った嬰児達の苦しみを救ってくださるのが地蔵尊であると言われています。
山切の地蔵尊は、江戸時代の中期に山切川の氾濫や川遊びでの水死、また水害によって命を落とした、多くの子供達を里人が哀れみ、浄財を寄せ合って、歓料寺の住僧(元文4年7月示寂)の世代に建立したものと伝承されています。
一説には、青木家或いは土肥家の寄進だとも言われており、始めは川の近くに建立しましたが、江戸末期の洪水で流失の恐れが出たため、山の中腹に移転し、山切部落を見守ってくれていました。その後、山切部落で維持管理してきましたが、戦後建物がいたみ、交通の便も悪いことから、昭和47年に当寺境内の地蔵堂に移し、納められました。
それからは交通の便も良くなり,当寺現住職を始め多くの人達から、お地蔵様を元の場所に戻したらどうかという意見が出たことから、平成9年3月に現在の場所(峠)に再度移転されました。(地区内多数の皆さんから寄せられた浄財によって、立派な地蔵堂が再建されました。)
地蔵尊の霊験を今一度思い起こし、山切の歴史を大切にすると共に地域が平安でありますよう願いたいものです。 |
 木質座像二尺大 作者不祥
木質座像二尺大 作者不祥