|
仁杉家の祖となった幸通は伊東六郎祐通の子として生まれた。(本朝武家諸姓分脉系圖)
伊東家代々の通字は「祐」であり、長男には必ずこの字が使われている。幸通は父祐通の「通」を受け継いでいるので長男ではないと思えるが、父と同じ「伊東六郎」を名乗っているので家督相続者であろう。
生国は駿州鮎沢郡仁杉邑とある。仁杉邑には幸通が初めて住んだのではなく、5代前の朝光の代から住んでいた。
武士が本貫とする地名を名乗る当時の習慣から、幸通は伊東から仁杉に改め仁杉伊賀守を名乗り、仁杉家の始祖となった。 天文年間(1540年代)のことと考えられる。
過去帳や墓所に生まれた年の記述はないが、天正20年(1592年)に71歳で没とあるので逆算すると大永2年(1522)と推定される。
幸通は北条家に材木奉行として仕え、65貫文の知行を受けていたと小田原役帳にあり、その他にも多数の北条家文書に幸通の名が残っている。北条家朱印状参照
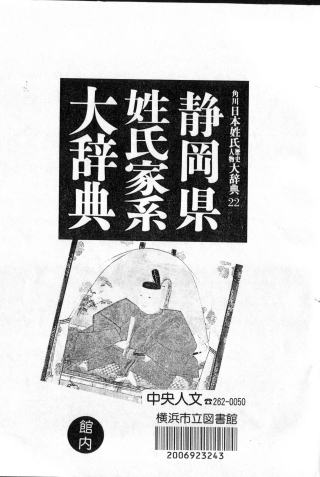 |
角川書店 刊 「静岡県姓氏家系大辞典」
(原文のまま)
仁杉 にすぎ
伊豆国出身と見られる土豪に仁杉氏がいる。
小田原北条氏の家臣で、永禄2年の「役帳」によれば、仁杉五郎三郎(馬廻り衆)が伊豆奈古谷(韮山町)などに20貫文、仁杉伊賀(伊豆衆)が60貫文の所領役高を有している。
仁杉伊賀は名を幸通といい、小田原北条家の材木奉行であった。
天正14年北条氏朱印状・北条家朱印状(森六夫氏所蔵文書)からも伊東山、狩野山の材木を仁杉氏や大川氏が管理していることがわかる。
また同17年の北条家朱印状(大川文書)は、伊豆長浜の大川氏が購入した東海船を伊東まで運び、仁杉氏に渡すよう命じられており仁杉氏が伊東の湊に住んでいたことがわかる。
同18年には、仁杉幸通は白井加賀守とともに、40人の鉄砲、弓足軽への出陣の触れを命じられている。(北条家朱印状/伊豆順行記)。
同18年相模小田原城開城ののち、幸通は熱海に移って商人になった。 |
下記ホムページの北条家家臣団の名簿に仁杉幸通の名が見える。
北条五代とその家臣
http://homepage3.nifty.com/houzyou-kotaro/Q12-Kasin-top.htm
また仁杉幸通については
北条家家臣=家臣団2
http://homepage3.nifty.com/houzyou-kotaro/Q12-kasin-kasin2.htm
に下記のような記述がある。
| 仁 杉 幸 通 |
| 生没年不詳。『小田原衆所領役帳』の「伊豆衆」にその名が伝えられ、西清寺分として50貫、御蔵出から10貫の知行を持つが、西清寺の所在については不明。材木奉行として伊豆の伊東山や狩野山の管理を努めていたため、知行役は免除されていたと言う。また伊豆郡代笠原氏の触口も努めていた。幸通の子孫は熱海の商人となり、伊勢屋を称したと伝える。 |
関連ページ
北条家臣
北条家朱印状
幸通の生涯
父祖の地に墓所建立
仁杉家の出自(室町・戦国時代)
|