
バリ島ハンダラ・コウサイドー
の18番ホール |

バリ島レギャン・ビーチ
の夕日
|

バリ島レギャン・ビーチ
でのスナップ |
(1) 設計部門へ復帰
新事務所建設の任務が終ってからの数ヶ月は、新設された不動産開発部に所属して、些か暇を弄ぶような日々を送ることになったが、会社は長くは遊ばせてくれない。海外(インドネシアのCAPC向け案件他)の大型ジョブの受注が見込まれて忙しくなり、現業部門の要員不足が心配される事態になると、1991年には、詳細設計本部副本部長兼土建設計部長として現業へ復帰することとなった。会社員としてスタートした時に所属した部署の部門長としての復帰で業務面では何の戸惑いも無く移行することが出来た。また忙しい日々が戻ってきて、その多忙の中でも、シンガポール、マレーシア、インドネシアへなどの東南アジアの現場への出張も頻繁(特に、CAPC向けのエチレンプラントでは客先の呼び出しも多かった)に繰り返すことになる。また、国内でも、三菱化学殿向けエチレン・プラント、丸善石油化学殿向けの大型エチレン・プラント(当時としては世界最大規模)などの大きなプロジェクトでTECも忙しい時期であった。
この時期には、ライン長としての種々の管理業務に加えて、国内外の建設現場からのクレーム対応、社内の各種委員会への参画、会社としてのISO9000シリーズの認証取得に向けた社内体制の整備(その目的のための一つの分科会をリーダーとして主催)などなどの業務をこなしながら、1年間(1991年〜1992年)は「部課長会の会長」も勤めさせてもらった。体力的にも何ら問題のない時期で、忙しい中でも楽しく仕事が出来た年代である。
(2) 設計屋から工事部門(建設本部)長へ
種々の業務を経験してきたとはいえ、プラントの建設工事を管轄する部門に所属したことは無かった(多くのTECの役員達が、隠居のその風貌からか「隠居は工事やである」と思い込んでいることは感じ取っていた)が、突然の社命で1994年6月には工事部門長を担うこととなった。当時は、国内プロジェクト、海外プロジェクトの両方の工事を統括することで、人員の大幅増員もはかり本部に昇格してのスタートであった。
1996年には、ライン職はそのままで理事(役員待遇)に就任、更に2年後には専任理事へと昇格。この間の主要プロジェクトは、国内では幾つか(日石殿、昭和石油殿、三菱化学殿、ゼネラル石油殿など)の深度脱硫プラントその他、海外ではマレーシア、インド及びタイの3大のエチレン・プラント、クウェートのPPプラント、インドネシアの塩ビ・プラント、カタールのガス関連プラント、インド及び韓国の石油精製プラント、インドネシアのパイトンの大型火力発電プラント
等々と多様であった。TECの年間売上高の最高値(約3,000億円)を記録したのもこの時期であったように記憶(調べればすぐ分かることであるが)している。従い、工事部門長としての現場出張も多国に亘る事となる。
1998年の春に現場工事着工予定であったサウジアラビアのヤンブーに建設するモービル殿向けのEOEGプラントの工事業者との契約ネゴのために、1997年の年の瀬も押し迫りつつある12月22日から年越しも覚悟してサウジアラビアへ出かけていた時に、またもや我が身に変化の兆しが迫ってきた。当時の副社長(後の社長)から電話が入り、「急ぎ相談したい事があるので、何としても年内に帰国して欲しい」との要請があった。何となく予感するものがあったが、12月29日早朝に成田に到着し、出社してみると予想は的中、「先々のスケジュールが見えず、客先から強いクレームのあるインドネシアのパイトンの発電プラントの現場建て直しために自ら陣頭指揮をとってほしいという要請であった。
(3) インドネシアの1年半、パソコンにも目覚める(?)
ライン職はそのままでという条件(ただし、1998年6月には 工事部門のライン長は離れて、「先任理事 プロジェクト統括本部副統括本部長」という立場となる)であったが、長期間会社を留守にするとなると引き継ぐべきことも少なくなく、年が明ければその準備にかかった。1月3日(土)、4日(日)を使って兄の町長選挙の応援で田舎へとんぼ返りし、9日から18日までは工事業者からの追加コスト請求でもめていたタイのエチレン現場でのネゴを兼ねて、タイ、インドネシアへ出張。1週間だけ日本に滞在して、25日の夕方に日本を発ってシンガポール経由(26日にインドネシアの長期ビザ取得のため)で本格的に乗込んだ。
1999年の5月に予定通りに業務を完了して帰任(1、2ヶ月に1回は会議、報告のために一時帰国はした)するまで、1年半弱のインドネシア暮らしが始まった。パイトンのプロジェクトにはそのスタート時から業者との契約を含めて殆どの場面で深く関与していたし、工事業者も以前から付き合いが深い韓国の「信和建設」、日本のマリンコントラクターの「東亜建設」、発電所建設の実績の多い「太平電業」、コールヤードやアッシュヤードを担当した「三菱重工業」、高圧の変圧器を担当した「日立製作所」などの力ある企業が主体であり、更に、PM,APM,複数のCMらを中心とする優秀な社員も多く配属されており、何らの戸惑いも無く現場組織に入り込むことが出来た。ただ、信和建設に経営上の問題が起きつつあったことと、客との契約形態が複雑でそのことに起因したコスト問題の紛争には大いに苦労した。
この間、1998年の5月に、公共料金の値上げに端を発した首都ジャカルタの民衆のストが大暴動に発展し、世界一の長期独裁政権を保持していたスハルトが辞任してハビビ副大統領が大統領に就任するという歴史的な出来事もあった。この時は、各国ともに自国民のインドネシアからの引き上げのための救援機をジャカルタ及びバリ島に飛ばし、3万人以上滞在していた日本人も95%近くが引き上げる(各企業とも連絡要員1名だけを残して)という事態になった事件であるが、日本での新聞やテレビの報道は実際以上に大袈裟なものであったようで多くの人達に心配をかけることになった。我が現場は、TEC独自の組織として日本人、イギリス人を主とする約200人以上の外国人を抱えており、コンソーシャム・メンバーとしてこのプロジェクトに参画したアメリカのDFWのメンバー等が約50名、それに三菱重工、日立製作所、太平電業、その他の工事業者の要員が数十名、信和建設の韓国人社員約170名が滞在中で、内部では些かの同様はあったが、殆どの要員が残留して業務に励むことになった。帰国したのは、家族帯同していたメンバーの夫人・子供、強い本社指示に従わざるを得なかった一部の日本企業(彼らはスラバヤの日本領事館がアレンジした数台のバスに分乗して陸路でバリ島へ向かい、バリ島で救援機に乗込んで帰国した)、以前に働いた国の大暴動で危うく命拾いをしたが未だにその恐怖が頭から離れない(当人の言)というTEC直接雇用のイギリス人2名(再び現場に戻ってくることはなかった)だけであった。特に、韓国人については、総てのメンバーが軍隊経験者であり、非常事態が迫ってきたら武器を準備してくれたら一個中隊が編成できるという意気込みまで見せてくれて頼もしい限りであった。
インドネシアは、隠居の訪問国で最も訪問頻度も多く期間も長い国で、インドネシア人も好きな人達が多い。個人では穏やかで、人なつこい人が多いが、徒党を組むと想像できないような凶暴な行動に出ることがある。特に、10代の若い人たちが暴徒化するようである。また、イスラム教を冒とくするような言動に対して強い反動(TECが雇用していたキリスト教のインドネシア人がそのような言動があったということで「追放しなければ、事務所に焼き討ちをかけるか、彼を殺すという脅迫の手紙を受け取ったこともあった)のがあることも念頭においておかねばなるまい。この大暴動後も、意味不明の「黒忍者殺人事件」と称する殺戮が繰り返されていたが、何時しかそれもおさまっていった。
このインドネシア駐在中に、遅ればせながら「パソコン」の利用頻度が高まって(と言っても、ワード機能に限定されているが)、1999年2月からは日記もパソコンを利用して書くようになった。ただ、その後も手帳に隙間無くびっしりとメモをする癖は変わらず、今でも続いている。
(4) 欲求不満気味の調達本部長
1999年5月初めにパイトンの工事完了(M/C達成)を契機にインドネシア駐在を終えて帰国、6月からは「調達本部長」を拝命することになった。この任務は約1年で終ることになるが、これがTEC本体における最後のお勤めとなった。
当時の主たる調達先は、塔曹類が韓国、回転機器は日本(しかし、コンプレッサー類はヨーロッパも多かった)などで、調達ネゴに関連した出張は韓国とヨーロッパに止まった。ただ、1年間という短期間であったことと、不得手の英語力に起因してネゴに十分力を発揮出来なかったという思いが残ったことで、些か欲求不満気味の調達部門であった。
また、この1年間は、会社も不況の最中にあり種々の再建策が検討された一環として、海外調達拠点(韓国、ヨーロッパ、アメリカ)を含めた組織のあり方(社内組織の統廃合を含めて)に対しての社内検討会を繰り返し実施することを強いられた。そして、還暦を迎えた年2000年の4月には、調達本部長を退いて次の任務として、2000年の6月から前年に会社再建策の一つとして設立された子会社TMEC(TEC Masters Engineering Co.)の社長職を担うことを命じられた。更に、次年度にはTMECの社長のままで、検査業務を主たる生業とする子会社PIM(Plant Inspection and Maintenance)の社長も兼務するよう命じられ、二束の草鞋を履くことになる。
(5) 余談
会社員になってからは、これまでは仕事にまつわることだけを記録してきた。ここらで、話題の方向転換を図り、趣味の話(詳しくは、「思いつくままの雑記」の中の「ゴルフのあれこれ」および「趣味」の中で書き綴ることにしたい)に簡単に触れておきたい。
<趣味1:ゴルフ>
職場の先輩達に勧められて最初のクラブ他のゴルフ道具を購入したのは1970年1月、前年末に生まれた娘の出産祝い金として会社から貰った金を総てはたいてのことだった。ただ、当時は釣りという趣味がゴルフ以上に面白いと感じていたのと、生後5ヶ月くらいの娘を乳母車に乗せて散歩中に「ぎっくり腰」(重症の椎間板ヘルニアと診断されて長期に苦しめられ、今でも「腰痛」は持病となった)を発症したこともあって、道具は揃えたがプレイは10年間封印。危険な海釣りをやめさせたい母と妻の強い要請を受け入れて、安全(彼女らの言)なゴルフに本格的に取り組んだのは40歳になった2000年である。
以来、釣りからは完全に足を洗いゴルフに熱中することになる。凝り性の自分の性格を認識しているので、安い金額の会員権を購入して環境を整えると、初年から年間約30回のプレイをこなした。以後、ブレーキがかからず、今では年間110日前後(一番多かった年は136日)もコースに出ていて、数年前にはハンディキャップもシングルとなったが、このところ不調に悩まされ、シングルと称するには恥ずかしく、力の限界を強く感じている。
ゴルフに関連した交友の輪が大きく広がって(真名CCでは、「千葉真名会」、「球道会」、「ニ木会」、「真名マスターズ会」という複数のグループのメンバーとなっており、千葉国際CCではコースのメンバーとなっているTECの社員達と、更にコースに関係なく会社のOBのゴルフ会「新桜会」の仲間と、大学の柔道の七大学対抗戦の仲間、と数え切れないほどのグループに所属)いるので、1年間の大方の休日がゴルフで消える「ゴルフ馬鹿」の状態である。また、ここ数年は、心筋梗塞の再発を気にしながらも、年末年始はバリ島でゴルフに明け暮れるなど、ゴルフ中心の生活である。体が動く間はこのような状況が続くことになるだろう。
<趣味2:釣り>
幼い頃に手作りの釣り道具を使って、川でフナや手長えびを釣ったのに始まり、大学時代にも下宿の近くの川でオイカワなどを釣ったり、松島湾や塩釜近郷で海魚を釣ったりと、その嗜好は途切れることは無かった。会社に入ってからは、内房、外房の海岸線からの投げ釣りに始まって、富浦(春の「のっこみの真ダイ」や「イサキ」、秋の「イナダ」や「カンパチ」など)、大原(ハナダイが中心)、外川(ハナダイ、アイナメ、ソイなど)などの釣り船を利用した海釣りが主体で、時折新島の磯釣りなどにも挑戦した。1970年ごろには、会社の同僚達と船外機つきの5人乗りボートを購入して釣りに励んだこともあった。
2000年までの10数年間の出張のない週末の殆どは、金曜日の夜から船宿に泊って早朝に出船する釣りに出かけていた。ただ、当時郷里の近くの海に関西方面から来ていた釣り人が遭難する事故が続くようになり、初めに母が、続いて妻が、最後には二人が組んで「危険な釣りは止めて、安全なゴルフを!」という合唱が始まったのを契機に釣りからゴルフへ乗り換えた。以後、釣りの興味が無くなった訳ではないが、二つを追いかけるには時間が足りないことと釣り道具を処分してしまったことこともあり、釣りに出かけたことはない。たまに、「釣り情報」に関する新聞や雑誌は今も求めていることなど、釣りの興味は薄れてはいない。また、「体力が許せば海の近くに住んで半漁師的生活をしてみたい」という夢も完全に無くなった訳ではない。
<趣味3:盆栽、庭いじり>
高校生及び大学生の頃の春休みや夏休みに、実家の庭の模様替えを庭師と一緒になって計画し、木々の植え替えなどの作業するなど庭については執着した。当時、魚を飼うことも考えて、自分ひとりで「池造り」を何回か試みたが、水漏れを防止できずにこの試みは総て失敗に終った。とにかく、草花や木々を育てること、庭をいじることは生来好きであったようだ。
会社に入って間もない頃から、公団の賃貸住宅の1階に住みながら、ベランダはサツキの植木鉢で溢れていた。初めて持ち家に住んだ1975,6年頃から、サツキを中心に、山野草や松なども加えて一時期には約400の鉢物を育てていたこともあった。国交回復後に頻繁に訪問した中国出張時には、古い植木鉢を探して持ち帰る(妻に土産はいつも植木鉢と嘆かれた)ほどの熱の入れようであった。しかし、海外出張が多かったことと、ゴルフが忙しくなってしまったことで、鉢数は徐々に少なくなり今はサツキ、松、藤その他で20鉢足らずとなってしまった。「隠居したら盆栽の復活を!」という思いは続いていたが、未だに実現はしていない。徐々に体力的なことも考慮しなければならないので、「ミニ盆栽」などが適していると考えるが、一日に何回も水遣りが必要で、旅行もままならないので容易に手が出せない。
庭についても興味は薄れていない。初めて家を持った時も、転居後の今の家を購入する時も広い庭が確保(75坪の敷地の半分近くをオープンの駐車スペースと庭で活用)できることを条件にして、そこそこに庭いじるが出来る環境は整えてきた。最初の家では、水の浄化装置も備えた4,5平方メートルほどの池も作って鯉も飼ってみたが、病気の予防が上手くいかず、途中からは睡蓮用の池と化してしまうという失敗もしているが、退屈しのぎの玩具としての効果は十分にあった。今の庭も、娘からみれば手入れや草取りに不満(当人も十分に自覚している)はあるようであるが、隠居はそこそこに満足している。庭の植木は松や楓などの他に、花物はサツキ、ツツジ、石楠花、ギボウシ、えびね、あやめ、クレマチス、アジサイ、水仙、バラ、ヒマラヤ雪ノ下、百日紅、ツワブキなど、果実をつける木は大きな柿の木、びわの木、石榴の木、金柑の木など、実付き楽しむ小木はピラカンサ、南天、マンリョウなど、実に雑多な物が所狭しと植え込まれている。ただ、柿や松などの高い場所での手入れは危険性も伴うことであり、ボツボツ難しくなってきており、何時まで続けられるか疑問ではある。
<趣味4:絵画>
小中学校時代に熱中したことは先に記したとおり。興味は続いていて、月刊誌を購読したり、絵の具や筆などの道具を買い揃えたりと、いつでも再開できる準備は進めているが、最初の一筆がなかなか進まない。兄と弟を見習うべきと思うが、最大の問題はゴルフに時間がとられ過ぎていることであろう。このまま筆を握ることなく終ってしまう可能性も大きい。もはや、趣味とは言えないのだ。
|
*
|
 
|
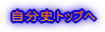
|
|