  |
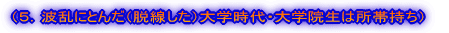 |
(1) 春なお寒い学生の街・仙台で些か浮かぬ生活がスタート
仙台での大学生活のスタートは順調なものとは言い難い。この大学に入学することが心から望んだという選択でもなかったこと、親しい友人が一緒に入学することにならなかったこと、春なを寒い仙台の気候(落葉樹が少ない暖かい鹿児島から新緑には遠い仙台へ来た当初は、緑も無く寒々としたその風情が好きになれなかった記憶がある)にすぐには馴染めそうになかったこと、などから、心弾む学生生活のスタートとはほど遠い感触であった。この精神状態がその後の学生生活の挫折に影響を与えたことは間違いない。
当時の教養部は、広瀬川の西側に広がる川内という町(当然、仙台市内)の米国駐留軍のキャンプ跡地にあって、建物も大部分は米軍が使っていた古いものを改造して使っていた。当時は、些かみすぼらしい建物にはエアコンなどのようなしゃれたものは無かったが、寒い地方だけあって暖房用のストーブは設置されていた。ただ、ストーブの燃料は、亜タンと言って石炭の出来損ないみたいなもので、近くの「伊達藩の城址がある青葉山」から採れる安価なものが使われていた。斯様な環境下で学生生活は始まったのだ。
入学して早い時期に「柔道部」に入部した。入部して1年もしないうちに痛めた足首の捻挫ががなかなか完治せず、退部するのも早かったが、この柔道部で知り合った友人には今でも親しく(月に1回のゴルフを含めて)付き合っている貴重な友人が幾人かいて、柔道は中途半端であったとしても、入部の選択は良かったと今でも思っている。退部したあとでも、この中の特に親しい友人二人(今はゴルフ仲間である工学部機械学科の野澤君と今は気象庁勤務後九州在の理学部地球物理・宇宙学科の神原君)とは「山秀会(3人の「三」にもかけて)」と名づけて、彼らが仙台を離れるまでは三人で山登りにも励んだ。
この年の昭和34年5月には、父が49歳の若さで東串良の町長選に挑み、当時の現職と当時は県議であった元町長との三つ巴戦に勝って、初当選した。自分にとっても、家族にとっても順調に動き出した年であったと言うことである。
(2) 日本一周旅行、喫煙の始まり
夏休みは、鹿児島大学に入学していた幼馴染の孝一君と北海道旅行と洒落こんだ。この旅は、少し(大いにか?)変わった旅程を辿ったユニークなものであった。仙台を出発して、北海道をほぼ一周したあと、青森から日本海側を南に下り大坂を経て九州に入り、九州を一周してから仙台に帰るという有効期限27日間(途中で交差する駅が出てくるので切符は3枚位に分割されていたように記憶している)の切符を買った他は、細かな日程を決めずに出かけた旅であった。
今で言う、「バックパッカー」の旅で、宿泊はテント、北大の学生寮、知人の逗留先などが殆どで旅館に泊ったのは夕張、岩三沢と遠軽での3泊だけという貧乏旅行である。
この記録は、「隠居の気ままな旅の記録」に整理することとしたが、概略の旅程は次のようなものであった。
・・仙台を普通列車で出発し、夜の青函連絡船で「函館」を経て「洞爺湖」(テントで2泊)へ到着
・・ここから「有珠山」を歩いて越して「洞爺駅」(昔は虻田駅か?)へ出て列車に乗り、「追分」を経て今は「財政再建団体」になって連日新聞・テレビを賑わしている「夕張市」(当時は石炭産業が盛んな頃で町も隆盛を極めていた。ここを訪問したのは、将来は鉱山学科へ進もうかということも選択肢の一つにあったので、鉱山とはどんなところか見てみたいという思いからである)へ
・・翌日、炭鉱を訪問(北炭の好意によって、案内役つきで炭鉱の模擬鉱へ潜る)後に、「岩見沢」へ出て時間調整で映画をみてここで宿泊
・・「滝川」を経て「富良野」を通過して「帯広郊外の音更」(養蜂業の孝一君の叔父さんが花を求めてこの地に逗留中であったので、ここで一宿の恩義をこうむることとなる)に移動
・・バスで、「士幌」、「足寄」、「阿寒湖」、「弟子屈」と移動して、「摩周湖」(幸運にもガスが晴れて美しい湖面を眺めることが出来た)の観光後に「屈斜路湖」の湖畔キャンプ場(テントで1泊)へ
・・また、バスで網走へ出て、原生花園やトウフツ湖を散策後に列車で札幌方面へ向かう。「遠軽」という町で終点となったので、駅前の安宿に宿泊
・・翌日、「上川」から「層雲峡」へ出て、大雪山系の「黒岳」まで一気に登り、頂上の山小屋に宿泊。ここでは、お花畑の素晴らしさと鳴きリスを初めて経験。
・・翌日は、ガスが立ち込める中、「熊よけ」の鈴も笛も無いままに「旭川方面」(ユコマンベウ温泉?)に下りて、バス、鉄道を乗り継いで「札幌」まで。甲南高校の先輩が入寮していた北大の「学生寮」に泊めてもらう
・・昭和34年の春に東京で、日本で始めて開催された「ホリデイ・オン・アイスショー」がこの時期に札幌へ移動(日本の主要都市5,6箇所で開催された)していたので、これ幸いと見に行った。札幌に着くまで知らなかった。これが札幌の唯一の思い出。
・・さて、ここから郷里の鹿児島への道程がすごいことになってしまった。札幌を夜の8時前後に普通列車で出発。青函連絡船で青森に着いたのが昼過ぎてから。当時、日本海側を大坂まで走るその名も「日本海」という急行列車があったが、出発時間がうまくない。同じく日本海側を大坂まで行く「普通列車」があることが判明したので、疲れたら何所かで下りて宿泊すればよいという思いもあって、それに乗ってしまった。ところが、孝一君と意見が合わないままに列車で一晩送り次の夜の8時前後(?)に大坂まで来てしまった。また、そこで休むということをしなかったのだ!ホームを変えれば30分前後で鹿児島県の出水行きの普通列車があるではないか。大坂には用事がないので、乗ってしまえということになった。ここまで来れば、あとは蛇足!とうとう終点の出水に次日の夜10時過ぎに到着するまで、札幌を出てから3泊4日計74時間余の休みナシの長旅が続いたのだ。列車を下りても、体が揺れている感じは暫く続いた。誰も信じないような本当の話なのだ!当然のことであるが、長距離普通列車の乗客は頻繁に入れ替わり数え切れないほどの人々との接触があるのだということを実感した旅でもあった。
この旅のスタート時点の青森へ向かう列車の中で、初めてくわえたタバコは旅の間に習慣づいてしまって、これから心筋梗塞の発症で禁煙に至るまで43年間続いた長い喫煙生活(知る人とぞ知る超ヘビースモーカー)の始まりとなってしまった。また、この旅を終えて思ったことは、「日本は何所へ行っても日本であり、大した変わりはない!」、「日本全国の殆どをみてしまった!」など、全く独り善がりのものであった。このことが、のちに南米移住ということを発想する一因になったことは否定できない。
なお、当時の鹿児島・東京間の急行列車は、鹿児島本線経由で27時間、日豊本線経由で29時間、更に上野・仙台間の急行列車が約7時間という長旅で、しかも何時も席の確保に苦労するくらい混雑していたが、大学院へ入るまでの夏休み、冬休みおよび春休みの殆どの休みに欠かさず帰省していた。若さゆえに苦にもならない長旅であったと言うことか!
(3) 初めての蔵王、紅葉の美しさに感嘆
東北に来て、新しい発見の一つは「紅葉の美しさ」である。それに初めて接したのは、昭和34年の初秋に、当時、農機具製作・販売会社の東北支店長として仙台に駐在中の祖母方の遠縁の人(子供のいなかったこの夫妻には我が子のように可愛がってもらった)に連れられて訪れた「蔵王」である。鹿児島では、決して目にすることも無かった美しい光景に驚かされた。どんな花よりも美しい光景という表現が決して大袈裟とはいえないという思いであった。教養学部時代には学業には燃えるものを見出せなかったが、東北の秋の景観には感動した。このことが、その後の登山の趣味へと繋がっていった。
主として、休学・復学を経験したあとになるが、この項の頭書に記した「山秀会」の仲間と、仙台から近くて日帰りが出来る「泉岳」を初めとして、「蔵王連峰」、「磐梯山」、「朝日連峰」
、「飯豊連峰」、「栗駒山」、「八幡平」および「岩手山」などの東北の山々を歩き回った。特に、蔵王と二口峡谷では、特注(注記*参照)のテントを担いで、極寒期の冬山の経験もした。これらの冬山登山は、1年間近く下宿の部屋も一緒であった柔道仲間の神原君と二人で行動を共にしたのが殆どである。彼は、山にかける情熱は突出していて、総ての小使いを山のために投資するという状況にあった。当時の下宿代の2か月分に相当する値段のした、しかもその性能の高さから登山家の憧れの的であった高橋製の特注の登山靴を購入するほどの熱の入れようであった。
注記* :仙台の「宮帆」という店で帆布を購入して、当時婚約中の妻に依頼して作った「手製のテント」。このテントは、栗駒山麓でキャンプ中に携帯コンロ(ホウェーブス製)の燃料に無謀にもガソリンを注入しながらタバコに火をつけたがために起こした火災で一部損傷(穴あき)し、冬山では雪が入り込んだりしたが、他に代わるべき物もなく長きに亘って重宝した。
(4) 60年安保闘争・休学でブラジル行きを画策・挫折
1960年には、世に言う「60年安保」でいずこの大学も大きな学生運動で揺れ動いた。6月15日には東京大学の女子学生であった「樺美智子」さんが参加した全学連のデモ隊が国会に突入した際に、警察隊と衝突して大混乱となり彼女が死亡するという大きな事件も発生した。この事件は、その後の学生運動に大きな影響を与えることとなった。 東北大学でも、連日のように学生の集会があり、安保に関しての議論を繰り返したり、街中をデモすることが頻繁に行なわれた。隠居も、確固たる信念に基づいていた訳ではないが、身の回りの学生達に引きずられるようにして、この動きの中に身を置いていたのは言うまでもない。旗を掲げてデモ隊の先頭を行く隠居の姿が、仙台の地方紙「河北新報」の紙面に出たこともあった。
この安保闘争がきっかけとなった訳ではなく、たまたま時期がこの時になったというだけであるが、以前から描いていた夢を実現しようと、大学には休学届けを出して田舎へ帰ることにした。夢とは、何と南米移住である。何か燃えてこない学生生活の中で、東大の新入生が陥ると言われていた「五月病」的なものであったのか、「大学で学ぶことと将来の自分の姿が具体的に繋がってこない」という状況にあった。そのような中で、何をすべきか探すうちに、愛読書の「ノンフィクション全集」などの影響もあって「ボヘミアン的な生活」への憧れも嵩じてきており、しかも学内に「南米移住研究会」なる少人数の同好会があったので、それに入会して密かに南米移住の調査・準備はしてきていて、そこそこの知識も身についていたので、一気にその方向に走ってしまった。
このことを相談された父は、特に反対することも無く、「親として応援できることはしてやるから、とにかく、自分でよく考えて行動するように!」という前向きの(?)対応であった。先ず、この計画を鹿児島大学に入学していたM・K君と県庁の職員となっていたN・K君の二人の幼馴染に話したら、行動を共にしても良いということになった。周囲では、安保闘争で大学に居づらくなって帰ってきているらしいとの無責任な噂もあったようだが、三人での移住計画は、資金面の準備も含めてすぐさま開始された。
ただ、事は思うように進展しなかった。当時の南米は、ルートにもよるが、船(飛行機は頭にも浮かばない時代)で20日〜40日間を要する遠い国であった。一度行ったら、何時帰ってこられるのか分からないというふうに思う人々が多かった。メンバーの中(当然、隠居自身も含めて)の家族、特に母親からの反対、周囲からの忠告などなどが続くうちに、3人の結束も少し緩んできたようであった。その後も、6ヶ月間余に亘って紆余曲折があって、最終的には断念ということになり、3人の家族が安堵するということに落ち着いた。このあたりの詳しい経緯は、不確かな点も多いので割愛したい。一時行動を共にしようとした両君が、この騒動でその後の進路に影響を受けることなく、所期の目標に向かって邁進され、それぞれの職場で定年まで立派に勤め上げられたことは、隠居にとっても喜びであり、彼らを惑わした事に対するお詫びの気持ちも消えていない。<同窓会で会っても、約50年前のこの話を口にすることもない>
*蛇足であるが、この騒動中に、「移住するのであれば、一人ではどうなるか不安だから、結婚して行ってくれ!」という母の強い希望があって、それを理由に思い切って告白し、両方の家の両親の了解も得て婚約(大学院入学後に入籍・同居)に至ったのが妻のR子である。南米移住計画で妻を得たということだ!
また、隠居は会社に入ってから仕事に関係して約30カ国に出張する機会を得ながら、南米には一度も足を踏み入れていないが、父は現役引退後に、義弟(隠居の妹の連れ合い)の現地の工場勤務のためにブラジル駐在中であった娘家族を訪ねて約2ヶ月間滞在したという何とも皮肉な巡りあわせになっている。南米は、隠居には縁のない国々であったということか!
(5) 大坂での放浪生活・復学
この移住騒ぎの中で、父は鹿児島出身の大実業家である岩崎氏(岩崎産業の創業者、鉄道の枕木で巨万の財を得て日本一の山林王と称されていた)に相談していたらしい。彼のアドバイスは、「将来を見極めないうちに、いきなり工学部を選択したことに、迷い又は間違いがあったのかも知れない。俺の所(世田谷の大邸宅内に「岩崎寮」という郷里の鹿児島県出身の学生の為の大きな寮を提供していた)に預かるから、将来のつぶしが利く東京の大学の法学部(東大という意味であったかどうかは定かでない)に再挑戦させては!」というものであったようだ。父から、この話は聞いたが、自分としては「東北大学」へ復学するという道を選ぶことにした。
「ほとぼりの冷めるまで」という意味合いもあって、復学前の半年くらいは大坂で浪人生活を送った。大阪外語大に通っていた甲南高校のクラスメートのアパートに同居させてもらい、時々はアルバイトに精出したり、大阪外大の柔道部で一緒に練習させてもらったりして、時間を潰した。復学のために仙台に帰ったのは昭和36年の夏前であったように記憶している。
復学後は、学習欲が出てきて勉強に励んだということもない。大学まで足を運んでも、終日校舎外の芝生の上でタバコ(この頃には、立派なヘビ−スモーカーに変身していた)を吸いながら文庫本を読み漁るという生活が繰り返されていた。学業以外では柔道部にも戻ったが足の捻挫の回復が思わしくなく、早いうちに練習から遠のいてしまった。山登りだけは「山秀会」の活動として、継続していた。このような緊張感のない生活の報いか、年度末になって数学の単位不足が判明し、1年の留年を味わうこととなる。
(6) 落ち着いた専門学部時代、恩師との出会い
2学年の3学期から始まる専門課程の授業で、ようやく勉強に興味が出てきて落ち着いてきたように思う。当時の東北大学では、入学時は工学部として纏めて試験が行なわれ、2学年に進んだ直後か、夏ごろに専門課程の決定が行なわれるというシステムで、隠居は希望通りに「建築学科」へ進むことが出来た。この頃になって、ようやく大学に進学した意義を見出していたように思う。些か遅きに失したという感もあるが!
ここからは、並みの学生らしい生活が始まった。専門の授業内容に興味が湧き、授業への出席率も急激に高まった。3年生の後半になって、卒業論文の課題(「コンクリートブロック塀の耐震強度」、これが耐震設計の道に進むきっかけとなった)を選ぶことで構造講座の志賀研究室(志賀先生には、大学院修了後も現在に至るまで何かと指導を仰ぎ、親しくお付き合いを続けさせて頂いている)への所属が決まり、夏休みを減らしての実験所での泊り込みの実験や、卒業設計などのも課題を処理するために休日も返上するという忙しい充実した生活が続いた。そして、志賀先生に教えられた学問の面白さが少し理解できるようになり、この忙しい生活の中の4年生の夏休みを前には大学院への進学を最終決断した。なお、余談になるが、設計の課題をやるために大学内の製図室で友人(ゼネコンの藤田工業へ就職)と二人で徹夜した夜の明け方に携帯ラジオを通して、若きアメリカ大統領ジョン・F・ケネディーの暗殺事件(1963年11月22日)を知ることとなった。
この頃には、「山秀会」の仲間は卒業・就職して仙台を去ったので、山登りに出かけることも無くなった。新しく仲間となった建築学科の友人達とは、山登りや旅行などの遊びは殆ど無く、3年生の修了する春休みに九州一周の旅をした二人の友人に一時合流したほかは記憶にない。酒を酌み交わすために集まるということは多かった。学部卒業直前に同居したI・K君とは下宿で晩酌と洒落込んでいた!
(7) 大学院へ進学
当時、大学院の建築学科の定員は4人(実際には6人の入学がが認められた)ということで、試験前は緊張の日々が続いた。特に、二ヶ国語の選択が義務付けられていた外国語のうちでドイツ語は全く駄目であったが、受験対策に長けたO・J君のアドバイス(山掛けが的中)で何とかクリアーできたことは幸運という以外にない。無事に入学出来てからの、2年間は志賀研究室の一員として先生や先輩諸氏の指導を仰ぎながら、学会での論文発表も東北支部大会、全国大会共に欠かさず参加でき充実した日々が続いた。また、大学院での研究テーマは、昭和39年6月16日に発生した新潟地震で多いに話題となった「砂質地盤の液状化現象」を勘案した「砂質地盤の動的支持力」で、当時はこれを研究して学者も少なくて興味を持って評価してもらえた。その成果の集大成である「修士論文」は、志賀先生と共同発表の形で、「建築学報」という建築学科の論文集にも収録してもらい、他の研究者の参考資料として利用していただくという栄誉にも恵まれた。
この大学院生活は、「東洋エンジニアリング」の紐付きであった。学部の4年の時の就職活動時に、当時の人事担当役員が大学を訪問されて直接に声をかけていただいたので、とりあえず会社を訪問したが、直後に大学院進学を決断しその旨を知らせたところ、「新たに、大学院生を対象とした委託研究制度を設定するので、大学院終了後に就職することを前提に、その初めての対象者として処遇したい」という話を頂いた。元来、この分野の仕事には強い興味を持っていた(具体的に仕事の内容に接したのは大学院時代の昭和40年の夏に大阪の東洋高圧<現三井化学>の建設現場で実習させてもらった時であるが)し、技術的にも専門とする振動・耐震設計に関連するテーマが転がって居そうで喜んで受けさせていただくことにした。当時の学部卒の初任給を上回るような額で、お陰さまで親からの仕送りを受けずとも何とか生活できる道も開かれた。会社には感謝!
(8) 結婚、妻の病と出産
大学院に入ると間もなく、婚約中であった妻を入籍し仙台での同居も始まった。新居は、仙台市内の北部の岩切地区で、三浦さんという昔の豪農の10畳間の離れである。塀で隔離された中庭も美しく、静かな環境であったが、部屋の周囲を総ガラス戸付の廊下が囲っていて、明るいが些か寒い部屋での新婚生活は、時折志賀研究室の先輩や仲間も訪問してくれたりして、貧しくても楽しく賑やかなものであった。所謂「学生結婚」であったのだ。生活費は、会社からの委託研究社員としての給与(奨学金とも呼ばれていた)と妻の洋裁での収入で、また大家の三浦さんや以前の下宿先の佐藤さんには何かとお世話になった。今でも感謝の思いは薄れない。
妻の妊娠が判明したのは、結婚後数ヶ月が過ぎた頃である。しかし、血圧が異常に高くて「妊娠中毒症」の疑いがあるということで、注意深く経緯を見守る必要があるという診断であった。国立病院に通院しながら、様子を見ることとなったが、血圧が異常に高い状態が続いて、なかなか正常値に近づかない。最終的には、「妊娠中毒症」の症状が治癒せず、8ヶ月での早産となって仕舞った。非常に残念なことであったが、我が長男は1日だけの生命力しかなく、この世を去ることとなった。この子の遺骨は、未だに千葉に墓を持つことを隠居が躊躇っているために、妻(彼の母親)の遺骨と共に鹿児島の実家の墓に納骨してあり、父親の墓参りは一年に一度だけとなっている。なお、後日談であるが、その後もなかなか下がらない妻のこの高血圧の原因は、長期間に亘る金沢大学医学部付属病院での入院による精密検査の結果、副腎の肥大によるものであることが判明し、昭和43年に同病院で8時間に及ぶ手術で四分の三を除去することとなった。
(9) 息抜きのスキーで骨折、
大学院では、授業のほかに修士論文のための研究を続けながら、欠かさず出席した学会の発表論文の作成や発表のための出張などもあって、忙しい日々が続いたので、大学を離れたことでの記憶は少なく、長期の山登りや旅行なども殆ど記憶に残っていない。研究室の仲間たちで、冬が終わりに近い(初春と言ったほうが妥当か)頃に、息抜きのための「蔵王山頂の山スキー」に出かけたのだけは鮮明に記憶している。ここで、出かける数日前に来訪した父親に貰った小遣いをはたいて新調したスキーを履いて、忘れられない足の複雑骨折をやってしまったのだ。
鹿児島ではスキーは見たこともなく、当然ながら、仙台にきてから始めたが、熱心にやったと言うこともなく、時折近場のスキー場へ出かけたのと冬山に登る時に雪上を歩くために必要なためにスキーを履いたに過ぎないために、腕前は初級の域を出ていなかった。大学の山岳部の山小屋を利用させてもらっての山スキーであったが、この程度の腕前では、アイスバーンもみられる初春の蔵王山頂でのスキーは無謀と言うものであったのだろう。 初日の夕方に頂上近くで事故発生、その日は何とか山小屋に担ぎ込んで貰っただけ、翌日に全員へバスのある場所まで運んでもらい、バスを利用して大学病院に辿り着いたのは翌日の昼は既に過ぎた時間帯であった。痛さに苦しめられた丸一日で、結果的には約2ヶ月以上もギブスの世話になることとなった。
(10) 蛇足ながら、どうでも良い話を幾つか! <追加予定>
・鯖の味噌煮が得意!
・何故か美味しかったブツ肉!
・大町のトンカツを食べるのが夢!
・登山靴を抱いて寝る冬山のテント内は寒かった!
|
*
|
 
|
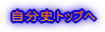
|
|