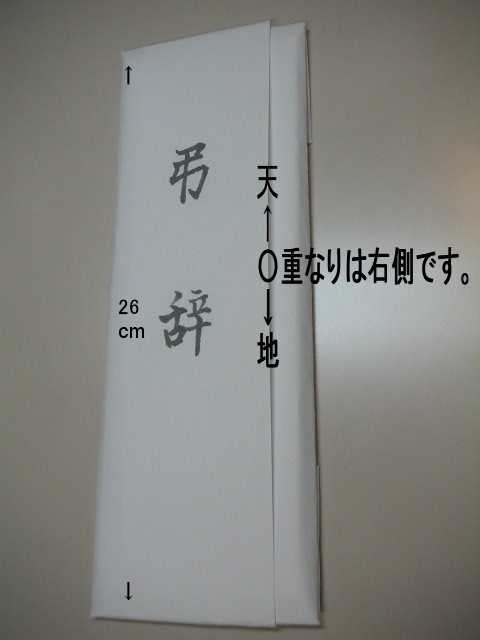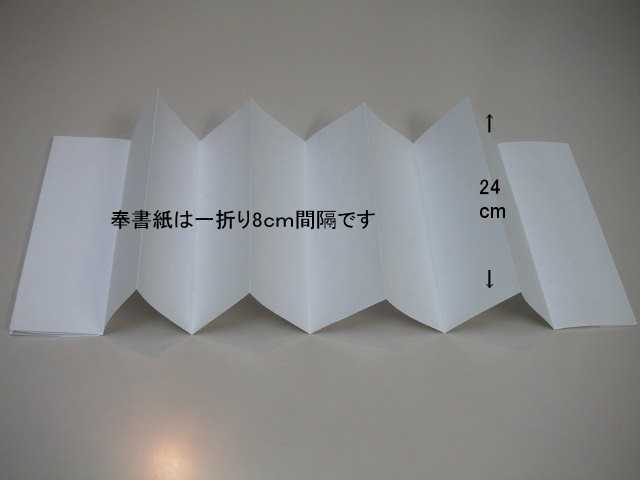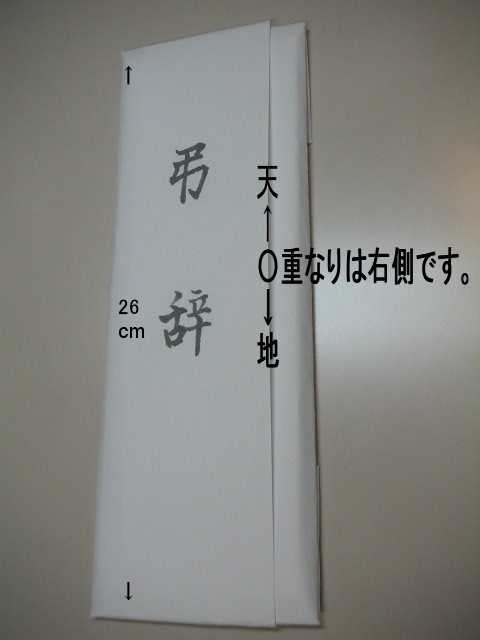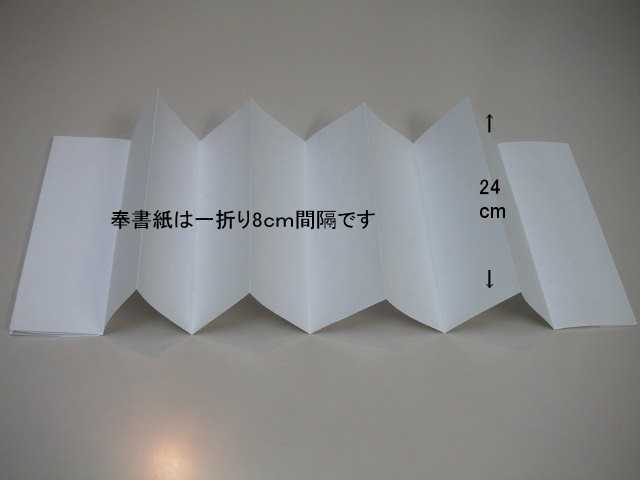謝辞の書き方ポイント
謝辞には色々な種類があります。「お祝いの言葉」「感謝の言葉」「祝辞」「御礼の辞(お礼のことば)お礼の言葉」等々。読まれる方の立場によってタイトルが違います。(保護者代表・後援会会長・園長などなど)の立場からの目線で文章を考えなければなりません。また出しゃばってその立場のおかぶを奪うような文章もつつしまなくてはなりません。
もって文章はご自身で考えなければいけません。ご来賓の方に感動を呼ぶ文章でなければいけません。
- タイトルについて
- 通常,タイトルは「謝辞」ですが,仏教の幼稚園では「感謝の言葉・感謝の辞(かんしゃのことば)」とするところもあります
- 句読点は必要なしです
- ●謝辞は,基本的に句読点を外した文章にします
- (※句読点を外して,「福が入り込むように」という意味合いからです)
- 改行の一文字下げは,しません
- 文章の頭ラインは揃えて書きます
- いろいろと書きたいことはわかりますが
- 1200文字内に収めたいものです。
- 特に幼稚園の謝辞は,保護者もお若い方が多いので,まだ,学生気分の延長のような会話調作文が見受けられ,文章が長くなる傾向ですが,
- しかし,謝辞を聴衆される方は,老若男女の幅広い年齢層なので,言葉の選び方に大変,気をつけなければいけません。
- 普段の会話でしたら「若いからね」で理解して年配者は聞いていますが,謝辞となると,その幼稚園に,永久保存される
- モノです。下手な字は一生の恥になります。ので,代筆をおススメします。
-
文書ですが,まず,会話の文と文書の文は違うことを理解して下さい。
-
会話は,声の抑揚とその人の個性でしゃべって相手に伝達しますが,
-
文書は,声を出さない場合,目で読んで頭にイメージを浮かべて理解するモノです。
-
わかりやすく言えば,目で読んで頭の中に映画のスクリーンが浮かぶ文書が理解しやすい文書です。
-
来賓の方の感謝,園長先生と先生の感謝,保護者の感謝は,始めと終わりに必ず入れなければいけません。
保育所と幼稚園とこども園と小学校の言葉の使われ方
| 保育所では卒園は「修了式」と「入所式」です。児童福祉法に基づく「児童福祉施設」の為 |
| 幼稚園では卒園は「卒園式」と「入園式」です。学校教育法に基づく「学校」の為 |
| 認定こども園は卒園は「修了式」と「入園式」です。学校教育法に基づく「幼保一元化施設」の為 |
| 小学校では「卒業式」と「入学式」です。学校教育法に基づく「学校」の為 |
- 仏教幼稚園でしょうか?キリスト幼稚園でしょうか?
- 保護者が一番わかっていることですが,仏教・キリストでも宗教を敬い讃えるフレーズを文書に入れてください。
- 様を使ってください。では殿とは・・・
- 殿は,「○○会社社長××殿」と,官公庁,公務員が事務的な手紙を個人に出す場合に使っていた言葉である。
- つまり「お上」が「庶民」に対して上から目線で宛名に使っていた。最近では,様に移行変更しています。
- 現在でも公用文では一般に「殿」が使われています(省庁の公文書で,あて先の敬称には「殿」)古い体質の民間会社では,社内でまだ使われていますが,様に移行変更になってきています。
- 今でも社内の同僚同士で殿は使われていますが,できれば様を使う方が無難です。でも,年下には,殿を使ってもよいでしょう。
- 様〜経理部長 姓名様,民間では,様を使う方が一般的になってきている。
- 例外事項:「園長」と「様」の二つを付けると二重敬称となりマナー違反です。
しかし、「殿」は「園長殿」「先生殿」「社長殿」「部長殿」などの肩書きに付けたりします。
- 保護者を使ってください
- 父兄(ふけい)とは〜私の時代は父兄という言葉を使っていました。私も子供ときから疑問だったですが,父兄参観では,母ばかり来ているのに,どうして兄?と書くのか?ちょと調べてみました。現在は禁止用語です。1947年に廃止された家長制度(男性を長とする考え)に由来する言葉で、
子どもを保護するのは「男」、つまり家長としての父、その継承者としての兄である・・・という意味を含んでいます。民法の規定により、女性は独立した人格とはみとめられず、父兄、夫に従属するもの、いつも頭のあがらないものという地位に属していた時代の用語です
- 父母(ふぼ)とは〜字のごとく父と母の両親を示しているわけですが,昨今,震災などでお亡くなりなった家族が増えました。また時代の反映で離婚も増えてきました。かつて看護婦が看護師に,スチュワーデスがキャビンアテンダントに言い方がなったように父母から保護者に変更する方が学校関係にはよいのでは思います。しかし,歴史の長い幼稚園では今も父母(保護者という意味で)を使っています。
- 幼稚園児の服装用語について
- 帽子〜赤白の体操帽,制帽〜毎日の登園用の帽子
- スモック〜幼稚園児の男女が着る上着の一種。基本的には丈の長めの身頃に、長袖がついた形のデザインです
- 僭越(せんえつ)ながらとは言わないでください
- 辞書では「自分の身分や権限を越えて、出過ぎたことをする」と書かれていますが,昨今のイメージでは
トップでふさわしい方が謙遜して言う言葉になっています。しかも酒席とか宴会の会場とかで使われることが多いので,幼稚園ではふさわしくありません。
- ご苦労とご足労の違い
- 謙譲語を知らなくて育った世代なのか?以外と知らない人が多いです。ご苦労とご足労は
ちゃんと使い分けをしなければ恥をかきます。使い分けは簡単です。
ご苦労は年下か同僚に対して言う言葉です。下から目線もあります。
ご足労は,お客さま,先生など敬ったり,謙譲語,丁寧な言葉です。もって
先生には,いくら若くても「ご足労」と言わなければいけません。
- 3月の季節用語
- 3月
早春の候/春暖の候/花便りの聞かれる今日このごろ/春まだ浅く/春色にわかに色づき/日増しに春らしくなり
- 佳き日か?良き日か?
- 私も未だ迷っています。でも日頃,目にする感じは「良」です。ちょと調べてみました。
-
佳き(うつくしい)・良き(よい)・嘉き(よろこび)・吉き(しあわせな)・懿き(うるわしい)
でした。漢字から行くと「佳き日」がよいと思いますが,私の好みからいくと「良き日」がいいのではと
園児の旅立ちの区切り日という意味あいです。結婚式では「佳き日」がいいかもしれませんね。輝いていうつくしい花婿,花嫁という意味です。「結婚を佳き日から良き日になる」
- 「先生がしゃがみ込む」か「先生がかがみ込む」か
- 子供の目線に先生がしゃがみ込んで合わせた。後ろの子供に舞台が見えにくいので先頭の先生がかがみ込んだ。
- 「先生は子供に手を貸す」と「先生は子供に手をさし出す」
- 竿がのびるように手を出す場合は「さし出す」舌がペロっと出るような感じの場合は「貸す」です。貸すは本人自ら言う場合で
,他人が言う場合は「さし出す」の方が敬いがある
- 「先生に感心する」と「先生に学ぶ」
- 上から目線が「感心する」で下から目線が「学ぶ」なので,親は先生から「学ぶ」がよい。親が子供に感心する。これなら良い。
- 初めてと始めての使い分け
- 以下,例文を列記しておきますので読めば理解できると思います。生まれて初めて水泳をする。今年の水泳を始めてする。
初めて北海道にきた。掃除を始める。英語で(初めてfirst,New)(始めbeggining,Start)(副詞)初めて(動詞)始める
- 園長先生,卒園証書,卒園児
謝辞の骨組み
| タイトル(謝辞) |
| 季語 |
| 学校に対してお礼の詞 |
| 入学から卒業までの思い出 |
| 学校に対して最後おお礼の詞 |
| 学校の繁栄を願う詞 |
| 先生に対して健康を願う詞 |
| 日付,●●幼稚園,卒園児保護者代表 ●●●● |
| ●●●幼稚園 園長殿(この場合は様は,間違いで殿がよい) |