第15話 コラボレーション&インタープレイ
前回のコラムで、ソロとバックの音が重なってはいけない事を説明しました。
この様に相手の演奏を良く聞き、全体をサウンドさせる事は=その瞬間瞬間において全員が作りあげる即興演奏とも言え、これを”コラボレーション”(collaboration=合作、共同作業)と称しています。
たぶん即興演奏を主とした音楽が発生した時点から、このような試みは(程度の差こそあれ)行われていたでしょうが、さらに一歩進めて、ソロとバック(主と従)という垣根を取り払ったのが、JAZZピアノの詩人、ビル・エバンスと言われています。
「ただひとりの演奏を他の人が追従するような形ではなく、トリオが相互にインプロヴィゼーションする方向で育って行けばいいと思う。たとえば、もしベース・プレイヤーが自分の演奏で応えたい音を聴いたとする。それなのにどうして4分の4拍子をただ弾き続けている必要があるんだ?」(ビル・エヴァンス/ピーター・ペッティンガー著・水声社)
旧来の役割からベースを開放する為に、まず彼はコードからルート(基音)を抜いたりして工夫をこらしました。かち合いを避ける意味と同時に、対等奏者であるベースの為に自由に動ける空間を用意し、その存在意義を明確にした訳ですね。彼曰く、「もし私がただ座ってルートやフル・ヴォイシングを演奏するなら、ベースはタイムを刻むことしかできない」(前出)
そして演奏者同士が、お互いの空間に入り込み、互いをインスパイアさせながら音を作り上げて行く演奏を”インタープレイ”(Interplay)と称しています。
ビル・エバンスのその後のアルバムの題名に「Interplay」(そのまんま!)とか「Intermodulation」などがありますが、”相互の”を意味する、”Inter”という言葉を好んで使っいる所に、彼のこだわりが見て取れますね。
さて、コラボレーションができているからこそインタープレイが成り立つのか、インタープレイがあってこそ真のコラボレーションと言えるのか?
鶏と卵の関係にも似て、視点や考え方の違いでどうにでも取れるので断言は難しいですね。
私的には「他人の演奏をよく聞いた上で、自分の音を重ねる」作業があり、その上で自らの演奏が昇華していくのが自然の流れかと。
良いブドウがあってこそ、素晴らしいワインができる。
よきコラボレーションがあってこそ、素晴らしいインタープレイが味わえるのではありますまいか?
文:
クリフォード・伊藤
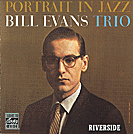
ポートレート・イン・ジャズ / ビル・エバンス トリオ (OJCCD-088-2)
ビル・エバンスと言えども、誰とでもインタープレイが成立する訳ではない。稀有のベーシスト、スコット・ラファロの参加を得て、彼の理想としたインタープレイが初めて実現したのだが、これは(トリオとしては)その記念すべき第1作目。
実は、ちょっとひねって彼の他のCDを紹介しようとも思ったのだが、それすら出来ないほどのインタープレイの金字塔的存在。一家に一枚の必帯盤。(私はLPとCDとで2枚持っているゾ!)
アマゾンで購入
Portrait in Jazz
ジャズコラムトップへ戻る
