| 里の風 小柏氏 | ||||
 |
今昔余話 小柏氏系譜と 戦国武将 御荷鉾山の つむじ風 神サマ常次郎 城和泉守と小柏氏 高天原の侵略 八咫烏のくりごと あまのじゃくの 羅針盤 時の丸木橋 あぜ道 ブログ コメントを書く 
|
|||
| 鎌倉時代から戦国時代を生き抜き、江戸時代までを駆け抜けた西上州の武装勢力 小柏氏。鎌倉時代には京都勤番、戦国時代には 北条に仕え小田原籠城、江戸時代に は御荷鉾山一帯の支配者になる。 その800年の軌跡を追う。 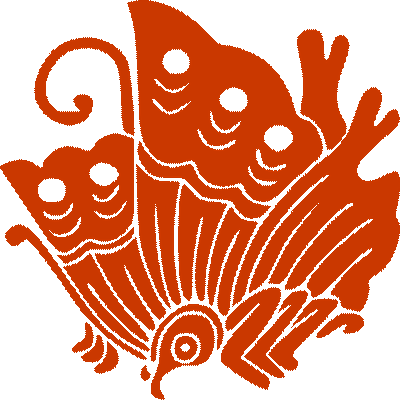 table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
||||
     |
||||
小柏氏800年の軌跡

里の風 里に風が吹いている
住む人は変わっても
里はずっと変わらない
風もずっと変わらない
風は里の歴史を見つめてる
風は過ぎたあの日を知っている
人は誰も風を見ない
風は皆を見ている
風は花を見ている
風は川を見ている
風は山をみている
風の流れが見えるとき
風で青葉のさざなみができる
風は雨の中を渡って行く
風は雨の飛沫を連れて行く
風は空を渡って行く
風は川を渡って行く
風は田畑を渡って行く
人は風の力を忘れてる
風は雲を運ぶ
風は木の葉を運ぶ
風は種を運ぶ
風は波を運ぶ
風は時に木も倒す
風は時間 時間は風
風が通り過ぎる時、時間が見える
風は時間をまたいで吹いている
風のひと吹きは里に流れる百年
風は今日から明日へと吹いていく
春の風は希望
秋の風は寂寥
風は春を呼んでくる
風は雪を連れてくる
目 次
平家の凋落
平氏の末裔 5
清盛の孫・娘たち 6
平家最後の戦い
9
平家落人伝説
11
安徳天皇は生きていた 12
維盛の「青海波」 14
惟盛伝説 17
御前岩の六代丸 21
小柏氏800年の軌跡
第一章 高政 鼠喰城で千人斬り 23
小柏氏の始祖 23
維基 鹿島神社建立 28
鎌倉北条氏と小柏氏 29
上杉氏と小柏氏 鼠喰城 29
関東管領・平井城の落日 34
豪族 高山氏 39
豪傑 小柏高政 血糊の宮
42
織田家と宝積寺の確執 49
菅原神社・妙義神社の鰐口 51
生島足島神社の起請文と養命寺 56
竹花城と小柏城 58
第二章 豪族 小幡氏 61
小幡氏の領地 61
国峰城落城 落武者信秀 62
秀吉攻め 小田原籠城 65
宝積寺合戦 67
幡氏旧領弁録について 71
小幡図書助の実像 76
定重長篠の合戦に出陣 80
定政小幡孫一を救う
82
第三章 お菊伝説 85
宝積寺のお菊伝説 85
因果の水鏡菊が池 87
二本木峠と小柏峠 94
上毛菊婦伝 96
上野国甘楽郡中里村菊女事 100
市川氏 春山大明神の記 103
第四章 江戸時代の小柏氏 106
大阪冬の陣に出陣
106
小柏家の権勢 名刀むかで丸 106 107
重高 黒滝山不動寺の開基となる 108
潮音 重高に誌偈を贈る 111
先代旧事本紀大成経 113
徳氏と吉次兄弟の足跡 118
三波川妹ヶ谷の開拓者 竹野(小柏) 120
妹ヶ谷の地名由来
120
「村上」とは何処か 121
竹野の妹ヶ谷入植期 127
妹ヶ谷城と小柏氏 131
三波川の柔術指南と血判状 135
南牧衆市川氏 138
焙烙峠の伝説 御荷鉾山の山元 141
當重 養命寺の中興開基となる 142
小暮市右衛門 「大神」となる 143
切支丹宗門改め 144
御荷鉾山(みかぼやま)騒動 146
重基 秩父山で金を掘る 148
第五章 風梅年代記
150
好文堂風梅と芭蕉塚
158
上日野の獅子舞 160
第六章 小柏舘最後の当主 八郎治重明
162
御鉾神社の建立と祭祀 163
明治政府 地租大増税 165
小柏常次郎と秩父事件 167
武士の商法敗れる 168
小柏家 落魄の風 171
小柏氏正系図 作成者 175
第七章 小柏氏の末裔 176
日野地区・三波川の小柏氏 176 178
甘楽天引の小柏氏 180
小柏徳氏の天引移住 184
熊野堂の磨崖仏 191
天引の笠塔婆 192
天引黒渕古墳群の塚 193
亀穴峠・鳥屋峠は昔の街道 195
中山道坂本宿の小柏 198
第八章 小柏舘の発掘調査
199
二回目の文化財発掘調査 201
あとがき
205
補 稿
小柏氏の墓所について 207
墓碑の分析 208
天引の小柏氏の墓所・墓碑 209
小柴氏と川邊氏 213
平氏伝承 小柏氏と武士団 215
小柏氏 年表
217
参考文献 224
小柏氏家系図 225
平家の凋落
平氏の末裔
一般に平氏は滅亡し子孫は絶えたと言われる、本当に平氏の子孫は絶えたのか?ここでは主に伊勢平氏・平清盛系を検証してみる。古文献などになかなか現れない平氏一族の行く末・末路を探ってみよう。まず清盛の弟たちの子(甥)であるが、経正、経俊、敦盛、通盛、教経、業盛、為盛など多くの者が一の谷の合戦などで討死している。
![]()
清盛 家盛 経盛 教盛 頼盛 忠度
経正 経俊 敦盛 通盛 教経 業盛 忠快 光盛 保盛 為盛 忠行
![]() 重盛 基盛 宗盛 知盛 重衡 知度 清房 清定 清邦
重盛 基盛 宗盛 知盛 重衡 知度 清房 清定 清邦
女子 徳子 盛子 女子 女子 女子 女子 女子
![]()
行盛 清宗 能宗 知章 知忠
維盛 資盛 清経 有盛 師盛 忠房 宗実
六代丸 夜叉御前 盛綱
勢観
源氏との合戦で討死が伝えられていない、その他の平氏の末裔の行方を追ってみる。
清盛の甥たち
忠快
平教盛の子忠快は出家して青蓮院の慈円の弟子になり、後に能福寺住職になり阿闍梨にまでなったという。その後なぜか、平家の都落ちの際には還俗したのか同行している。そして壇ノ浦の合戦に加わり、囚われの身となり伊豆に流された。
1189年に許され、また慈円の元に戻って僧としての生活を始め、父の所領であった三条白河小河が忠快の手元に戻された。その後、源実朝・北条政子の主催する仏事に協力し1227年に没した。
僧から武士に戻り合戦し、また僧に戻るという一見不可解の人生を送った。一時武士に戻ったが、僧であったため子孫は残していないと思われる。
二
平保盛
平頼盛の長男。右兵衛・越前守・尾張守・左兵衛佐。従四位下・中宮亮・正四位。1183年7月、平氏の都落ちに同行せず。正三位に列せられた後出家した。親鸞に教えを受け、福井県武生市の城福寺の開基となったとされる。河内守に補せられ小谷城を築城し、小谷氏の祖となったとの説もある。子には頼清(庶子説有)・保教ありとする。
平光盛
平頼盛の三男であり清盛の甥になる。母は仁和寺法印寛雅の娘。正五位下に補せられた後、寿永2年(1183)讃岐介となる。平家の都落ちの際には同行していない。左近衛少将・従四位下・備前守・正四位下・非参議・従三位等に列せられ、後に大納言となった。その後、正三位となり源実朝の任右大臣の勅使になり、更に従二位に列せられ、寛喜元年(1229)7月に没した。
子には教性、娘二人、源通忠室、松殿基嗣室がある。詳しい記録は少ないが、平家一族が皆、没落した後もしぶとく生き残り、公家として出世を重ねていった光盛は後世にその子孫を残している。
清盛の弟、平忠度の子忠行については伝えられている文献が見当たらない。足跡を残す間もなく早世したものか。
清盛の子供たち
重盛 病死 基盛 戦死 宗盛 刑死 知盛 入水 重衡 刑死 知度 戦死 清房 戦死 清定(養子) 戦死 清邦(養子、戦死か)不明。
清盛の孫たち
維盛 入水 資盛 戦死 清経 自害 有盛 戦死 師盛 戦死 忠房 刑死
行盛 戦死 清宗 刑死 能宗 刑死 知章 戦死 知忠 自害
平宗実(むねざね)
宗実は波乱の時代の波に翻弄された悲運の公家である。重盛の子にして維盛の末弟。生まれてまもなく2才(3才説あり)の時に左大臣藤原経宗の養子になった。土佐守には任ぜられていたものの、藤原氏として文字通り公家の生活を送った。
平氏が滅亡した年には18才になっていた。宗実に特に罪と言えるものはなかったが、経宗は周囲の者が鎌倉に密告し罪を問われ、一族に災いの類が及ぶのを恐れ宗実を追い出すようにして縁を切った。
この後、宗実は聖俊乗房を訪ねて弟子にしてほしいと申し出て、髻を切り鎌倉へ連絡してもらっても構わないとまで言いきった。その際に鎌倉から何らかの沙汰があれば、それに従うとまで覚悟を披瀝したので、俊乗房も断りきれず出家することを認めたのであった。
その後、俊乗房は念のため鎌倉へ報告したところ、一度鎌倉へ出頭するようにとのことで、宗実は鎌倉へと送られる事になった。すっかり公家になってしまっていた宗実は、武家のように強い心を持っていなかった為に、道中では食が細くなり遂には飲食を断ってしまった。
これまでの鎌倉の処置を思うにつけても、命が助かるとは思えなかった。そして足柄山を越えて、相模の国に入った所で遂に息を引き取った。
織田親真(ちかざね)
平資盛の子といわれている。平家滅亡後には近江の津田庄に逃れ、後に越前国丹生郡織田神社の神官、斎部親澄の養子になり神職についた。才覚があり、覚盛と名乗っていたと伝わっている。後に姓を織田と改め信長を生んだ織田氏の祖になったという。
平盛綱
平資盛の子(孫説有)。平家の系図上に名前の記載があるが、父の名前に関して諸説あり、謎のある人物といえようか。平家滅亡後に北条氏に仕えた。侍所所司となり、承久の乱の時には北条泰時と共に上洛している。
伊賀氏の乱を鎮圧し、御家人同士の争乱を鎮めるなどの実績を残し、御成敗式目の制定に関わった。北条家の家令になり政治力を発揮したが、北条泰時の死亡後に出家した。子には長崎時綱、平盛時、平頼綱、長崎光綱、長崎高光、長崎高泰が居る。(長崎氏の祖)多くの子孫を残しているが、鎌倉の追討を受けた形跡がないことから資盛の血は薄いのかもしれない。
源智(げんち・勢観)
平師盛の子。平家敗戦後は母と共に遁世していた。出家し慈円の弟子となり、勢観坊となり賀茂の上人と呼ばれた。知恩院(寺)二世となり多くの信者が集まったという。後に浄土宗法然上人(源空)の近くで片腕的存在になったという。著書も数巻残している立派な僧であったが56歳で没している。
その他
平盛国
平季衡の七男(孫説有)といわれている。平家一族ではあるが傍系である。右衛門尉、左衛門尉、検非違使に任じられ、富士川の合戦にも参加した気骨のある武将であり、清盛に意見する事もあったと言われている。
平家の都落ちに同行し、捕縛された後鎌倉へ送られ、軟禁状態にあった時に出家し毎日法華経を読経していた。自ら断食を強行し命を絶った。享年74才であったと伝えられるが、老人にして強靭な意思が感じられる。
関氏にあっては盛国は資盛の子としてあり、母は鈴鹿の関庄の女となっていて盛国が関氏の祖となったとある。盛国は源氏の追討を受けなかったものか、平家滅亡後には北条時政に降りその臣となった。盛国の子実忠は幕府御家人として鈴鹿郡の関谷の地頭に補せられ関氏を名乗ったとしている。
資盛には他にも妾が居たと伝えられており、その子孫が他にも居ると思われる。
清盛の娘たち
清盛の長女
藤原信隆に嫁ぎ、信仰心が厚かったと言われている。隆清という子をなして隆清は後に参議になった。都落ちには同行せず、和歌や絵画などの貴族の生活を全うしたようだ。
清盛の二女・徳子(三女説あり)
17歳の時に11歳の高倉天皇に嫁した。24歳になった時親王を生み、親王は清盛に擁立されて後の安徳天皇となった。徳子は安徳天皇と共に平家の都落ちに同行し壇ノ浦で入水した。
ところが源氏の平氏によって髪の毛を熊手に掛けられ引き上げられたという。後に都に送られ出家して建令門院徳子と呼ばれた。時を同じくして二位の尼も壇ノ浦で入水した。安徳天皇を胸に抱いて、三種の神器と共に海に沈み剣は失われた。鏡と勾玉は見つかったとされる。
清盛の三女(二女説あり)
左中将の藤原通憲の子成海範の許婚となったが、成憲が流人となった為、婚約は解消され後に左大臣藤原兼雅に嫁いだ。数人の子宝に恵まれた。都落ちには同行しなかった。子の忠経は右大臣となり、家経は中納言となったが詳しい事は詳らかになっていない。絵の上手。
清盛の四女・盛子
近衛基実に嫁いだ。器楽の演奏に長けていた。基実は24歳で急逝したため子はなしていないようだ。
清盛の五女(母は時子)
藤原隆房に嫁ぎ、隆衡を生んだ。都落ちには同行していない。指折りの琵琶の名手だったという。
清盛の六女・完子
関白藤原基通に嫁いだ。男子をなしたが都落ちに同行し平氏敗戦の後、都に戻ってきた。
清盛の七女・廊の御方
母は常盤御前で有名な義経の妹である。都落ちに同行して、平氏敗戦の後、都へ護送されて帰ってきた。仕えていた主で義兄でもある藤原兼雅の娘を産んだという。「書」に堪能だった。
御子姫
清盛の八女、母は厳島神社の巫女(内侍)だったと言われ、この為か「みこ姫」となったとされる。後白河法皇に18歳で嫁いだが19歳で短い生涯を終わった。入内後僅か1年で没しているため子孫は残していない模様である。
この他の娘たちの多くは若くして亡くなっている。
平の姓を名乗る氏族は非常に多く、源姓と並び二大姓ともいわれる。有名なのは桓武平氏であるが、この他に任明平氏、文徳平氏、光孝平氏がある。古い氏族であり、後世に多くの有名子孫を残し栄えたのが桓武平氏である。平の名前の由来は平安京の平(たいら)から取られたとする。また平の地名は若狭に平庄がある他、武蔵
常陸 上野 磐城 陸前 肥前 薩摩などが主なところである。こうした土地に住む平氏ゆかりの者たちは平姓あるいは多比良姓を名乗っている。
藤岡市上日野の小柏氏が本拠とした小柏村の近辺にも平の地名は幾つか散見される。小柏村の隣には上平があり、同じ上日野岡本の近くには芝平、下日野には塩平があり、日野小学校の近くには大平がある。
一山越えた吉井町には多比良(たいら)があり、多比良氏が勢力を張っていた。この他、関連は不明ながら、平井、向平、平石、栗木平、小平、琴平(神社)が見出される。この地方の平の地名は坂東平氏との関わりが類推される。多比良氏、小幡氏、高山氏も坂東平氏の流れを汲んでいる。古い地名は多くの場合、その土地の有力豪族・武士団と結びついている。
白倉には白倉氏があり、高山には高山氏、小幡に小幡氏、神保に神保氏、富岡に富岡氏、一宮に一之宮氏、高田に高田氏、長根に長根氏、庭谷に庭谷氏、奥平に奥平氏、安中に安中氏、秩父に秩父氏、新田に新田氏、足利に足利氏、千葉に千葉氏、三浦に三浦氏数えていくときりがない。
「多野郡藤岡地方史総説編」に南毛伝説として以下の話が掲載されている。
平井村(藤岡市)に後家畑と呼ばれる所があった。城の内に平良文が築いた城があった。子孫の城主が家臣の妻に懸想し、夫を無実の罪で打ち首にした。その怨霊が祟り城は滅びた。その後、首切り場の畑を耕作する者は必ず妻をなくした。畑の中の首切り台にした大石を、ある人が運んで庭石にしたら、まもなく妻がお産で死亡した。石はやがて寺の持ち物になった。
「平良文は小幡氏の系譜にその名前が見られる事から、小幡氏の先祖であるとみられる」とする者があるが今は見つからない。平良文の生没年は886~953(952)年とされている。
平安期の武将であり、三浦氏・千葉氏・秩父氏などの坂東平氏の祖と言われている。中でも秩父氏との関連が強いとみられる。平将門の伯父にあたり武蔵・下総に勢力を有していた。
平家最後の戦い
平忠房は維盛の末弟であり、「丹後侍従」と呼ばれていた。生年は不詳であるが同じ藤原家成の娘を母に持つとされる弟・宗実の出生が1168年である事から、是より先1166年の出生と仮定すると、1184年の壇ノ浦の戦いの頃は18才くらいと推定される。屋島の合戦で敗れた後、ひそかに陣営を抜けて紀伊国へ入った。
当地の豪族・湯浅宗重を頼ったが、協力者を募って態勢を立て直す積りだったと言われている。湯浅氏は有田の強力な武士集団で、南北朝時代まで300年にわたって活躍し湯浅党と呼ばれていた。
頼朝の残党狩りは厳しいものであったが、各地に潜伏していた平家の残党、悪七兵衛ら猛者が500余名も忠房の元に集結した。これだけ集まれば鎌倉に情報が届かない訳がない。源頼朝が阿波成長に命じ、成長は千騎余りの軍勢をもって攻めたが湯浅氏は岩室城に籠り、激しい戦いが3ケ月も続いた。
忠房の一党は宗重と共に防戦し退くことはなかった。だがこれに業を煮やした頼朝の、「重盛殿には旧恩あり、そのお子は助命する」との言質を得て、忠房は周りの反対を押し切り降参人となった。
この頼朝の言葉を伝えたのは文覚上人であったという。忠房はその後、鎌倉へ出向後、京都へ送還される途中で、頼朝の命により後藤基清によって斬られたが、妻に藤原脩範の娘を妻にしていた事から、その子孫がなかったとは言い切れないものがある。
白糸浜長者・岩井左衛門の娘(白拍子花松)との間に、女の子が居たとも伝えられている。また一説には忠房の潜伏を湯浅宗重が鎌倉へ密告したとしているものもある。
「紀伊続風土記」の青木村の条につぎのようにある。
小松殿の御子丹後侍従忠房八島の軍より落ち、紀伊国住人湯浅権守宗重を頼んで
湯浅の城にそ籠られける。是を聞て平家に志し思ける越中次郎兵衛、上総五郎兵衛悪七兵衛、飛騨四郎兵衛以下の兵共附奉りしかは、伊勢伊賀両国の住人等我もわれもと馳集究竟の者とも、数百騎盾籠山聞しかは熊野別当鎌倉殿より仰を蒙りて、両三月の間に八箇度寄て責戦城の内兵命を不惜防きけれは、毎度に味方追散る熊野法師数を盡
し討れにけり。
熊野別当鎌倉殿へ飛脚を立、当国湯浅の合戦の事両三月の間に八箇度寄て責戦ふされども城兵命を不惜防く間毎度に味方散れ敵をしへたつるに及はす。近国二三箇国を
も給て責落すへき由、申たりけれは鎌倉殿其條国の費へ人の煩なるへし。盾籠所の兇徒は定めし海山の盗人にそ有ん、山賊海賊きひしう守護して城の口を堅め守へしと、そのたまひける其定にしたりけれは、けにも後には一人も無りけると云々。或記曰永和四戌午年南方宮方蜂起し、湯浅権守搆城国民を追捕し国中の野伏山族強盗の溢者共馳集り、其勢二三千計国中に打出と云。
依之将軍家義満より是を退治せんと、同年十二月山名修理太夫義理舎弟、陸奥守氏清佐々木冶部太夫高詮本郷左近将堅詮泰一万七千余兵そそ向ひけると云々。去程に山名以下の諸将湯浅の城に押寄たるに、要害最嶮にして進退自由ならさりけれは先向ひ城を取り、二三日の程敵の位を見て未戦と云々。寄手城を守徒に見物すへきに非す、大手搦手手分を定め一万騎山名義理同氏清軍勢一度に進責上る。
残り七千の勢は城中援兵の押とす、山名の軍勢攻上ると云とも土地嶮難にしてたやすく進むへき様なかりけるに、城兵厳しく矢炮を以て防きたれは寄手是に辟易し乍ち敗し引退く。
依之十二月二十六日の夜、山名義理舎弟氏清と計り夜討を以て勝利を得んと七百余人丑の刻計り、忍やかに打立ける城内には兼て忍の者を以て今宵の夜討を計り知りて敵の寄来る道路に伏兵を設け、不意に起て散々に戦けれは又寄手敗軍して討るゝ者敵不知は詮方なく、そ見江にける義理氏清又計議を回らし此上は水手を断切渇しさせは自ら落城なすへしと、案内者を以て水手の通路を尋軍士六百余人を以て昼夜番をなし、十二月二十七日より翌正月十六日迄城を囲み水手を取斬りたり。
今は城兵水に渇し防戦の術盡て同月十八日の夜半に、城兵潜に城を落河州へ落行ける寄手は是を知らす。十九日迄守り居しか人有とも不見けれは、若落行たるや責て見よと山名氏清か朗徒二千終に城を乗取り陣ゝに火を放し霞と共に焼立けり。
(句読点は付加)
微にいり細に亘って記述されている。本文中に古記録があったとの記述があり、史実に近いものであろうか。多くはこの伝説を史実であったと捉えている。忠房は祀り上げられただけであったと思われるが、平家最後の戦いともいえる岩室城攻防戦で、平氏一門の武将は失いかけていた武家としての意地を見せ気を吐いたのであった。忠房の最後については平家物語別本「延慶本」「四部合戦状本」には次のように記されている。
「屋島ノ軍ヨリイヅチノ落給ケン行方ヲ不知。」
平家落人伝説
九州佐賀市に落人伝説があり蓮池町には小松神社がある。「復刻佐賀市の文化財」によれば、平重盛を祭った小社であるとの口碑が伝えられている。
壇ノ浦の戦いに敗れた後、数艘に分乗し海岸伝いに南下して来て、山地に身を潜めながら逃亡を続け、長い日数を掛けて、一部の者は筑後川沿いに下り佐賀市蓮池町に土着したという。
荒れ果てていた田地を開拓し時が経って源氏が滅びた後に、社を建立し人徳者の重盛を祀り、小松社と名付け落人たちの信仰の的となった。
人々はいつしかここを小松の里と呼ぶに至った。
小松神社に春秋の2回奉納される踊り「小松の浮立(ふりゅう)」は佐賀市の重要無形文化財になっている。この踊りの楽器には笛がなく、別名笛なし浮立とも呼ばれるという。一の谷の合戦の際、一門が船で沖に逃れる時に平敦盛は愛用していた笛を、館に忘れ取りに帰ったために撤退が遅れた。
この時、はせ寄ってきた源氏の熊谷次郎直実に呼び止められ、討死してしまった事から、楽器の中からあえて笛を除外しているという。小松部落では今でも、家の新築の際には「小松の浮立」が演奏されている。
この他、松阪市には六代丸の伝説がある。三重県松阪市のホームページには次のようにある。
三重県松坂市に六代丸の墓と伝えられている物がある。落人が美しい山間部に隠れ住んだという。当地の日川寺は源平合戦の後、平家の落人が隠れ住んでいたという。
なめり湖から南へ細い山道を奥深く入った所で、人目を避けてひっそりと暮らすのには絶好の場所であるという。
そこは山々に囲まれて、清流が流れ今でも非日常的な別世界を形成しているという。
この山の中腹にひっそりと佇む石塔が六代丸の墓と伝えられている。
|
|
六代丸の墓と伝えられている。
また、白山一帯の白川郷、飛騨、五箇山にも平家落人伝説が伝わっている。戦いに敗れた平家の敗残兵が、国境の山沿いに逃れてきて白川郷に住みついたという。これ等の地域では平維盛伝説が中心であり、白山信仰と関連しているものとみなされている。白山の坊数は6,000余もあったとされ、天台宗比叡山の3,000余の倍程もあった事から白山信仰の広がりが分る。
このほか悪源太が遁世していたとする福井県の町、平家落人の里、平家の子孫を名乗る町は熊本県や北関東にある。これ等の町の多くは、谷川や山に囲まれた山村で温泉などもある。こうした土地では産業も少ない為か、主として観光客誘致に積極的に活用しているようである。
観光地として売り出すための目玉・看板として案出され、演出で作りだされ、それなりの規模と格式を、取り揃えて整備されている所も見受けられる。
安徳天皇は生きていた
安徳天皇は壇ノ浦で二位の尼に抱かれて、入水して果てたとされている。二位の尼は平清盛の正妻・時子である。従二位の位にあり清盛の死後は尼になっていた為、二位の尼と呼ばれた。
宇佐神宮の宮司家・宇佐家の伝承によれば、同家は神武天皇が東遷の際に立ち寄った時に、足一騰宮を建立し当主の妻を差し出し供応したという。そして神武の兵士たちには土地を与えて屯田制として生活させた。
この神武部隊の滞在期間は4年に及んだという。
都落ちして大宰府にくだっていた安徳天皇が、源氏方に加担していた緒方惟栄の圧迫を受け宇佐神宮宮司・公通の館に逃げ込み一時ここを皇居と定めた。この時に公通は、宇佐神宮にて斎戒沐浴・断食して七日七夜祈ったところ神託を得た。
それは嫡男・公仲を安徳天皇の身代わりとして、天皇を守護し奉れというものだった。
公仲の母は清盛の娘・浄子であり建令門院の妹であるから、天皇と公仲は従兄妹の関係であり年齢も同じ8歳であった。
かくして天皇は宇佐に残り、身代わりの公仲が安徳天皇として讃岐の屋島に移った。この後、平家は山陽道を制圧し勢いを盛り返したが、義経が下向して参戦した事により、たちまち劣勢になり壇ノ浦で亡ぶ事になる。こうして宇佐公仲は、天皇の身代わりとして二位の尼と共に壇ノ浦の藻屑となった。
安徳は30年ほど遁世し、公通の先妻の子公房の庇後を受けていたが、やがて宮司職を譲られた。
1214年に大宮司に補任され従五位下に列せられ、男子三人をなしたが宮司は長男に譲り出家した。実母である建礼門院や、平家一門の菩提を弔って晩年を過ごしたという。
この後、宇佐神宮の宮司職は安徳天皇の子孫が勤めた。真実かどうかはともかく、可能性として充分にあり得る事ではある。恐らくは事実なのであろう。宇佐公仲となった安徳は、宇佐家の系図上では公通の孫となっている。
三種の神器
三種の神器は、安徳天皇と共に都落ちに随判されていたが、二位の尼が携行して壇ノ浦に沈んだ。剣は見つからなかったが、鏡と勾玉は見つかって、義経が京都へ持ち帰り後白河法皇に返したとされている。
池や湖ならともかく、潮流のある海に沈んだ物が当時の技術で見つかるとは信じ難いものがある。それとも、鏡は二位の尼が小脇に挟んで入水したといわれているので、潮に流されて沈むのに時間がかかったのか。
徳島の安徳天皇
一説には清盛の弟教盛の二男国盛が、安徳天皇を擁護して徳島県吉野川奥地の粗谷山に逃れたという。国盛は百騎ほどの部下を連れて吉野川を遡行して、粗谷に入りその地の名主・喜多氏を殺し占拠すると共に周辺に支配地を広げたという。
後に阿佐庄に移り阿佐氏を名乗った。同家には向い蝶紋のある平家の赤旗と宝刀が今に伝わっているとされる。
事実とすればこの「宝刀」と呼ばれる刀が、壇ノ浦で失われた三種の神器の一つである可能性が高くなる。しかし国盛の伝説と阿佐氏の伝承が話の中心であり、安徳天皇のその後の動向・子孫にまつわる伝承は伝えられていない。
安徳天皇の事績・名乗った名前、改名したであろう後の名前・子供の有無・死因・死亡地などは一切伝わっていないのである。
この事から、ありそうな話ではあっても、今ひとつ真実味に欠けてしまう嫌いがある。また「国盛」の名前は平氏の系図上に見えないが、教盛の二男「教経」の別名としているものがある。
この他、栗枝渡神社に安徳天皇の火葬塚がある、安徳天皇の御典医(堀川家)がいた等の話しが別々に伝わっている。
維盛の「青海波」
横笛の優雅な調べがさやかな風に乗り、その場に居合わせた高貴な人々の胸を打つ。その音色は寂しく愁いを帯びて、時には悲しさを込めて切なく胸の底に響いてくる。舞っているのはきらびやかな衣装に身を包んだ平維盛である。
ただでさえ維盛の女人をも凌ぐ優美な面立ち、日本一ともいえるその美男子ぶりは宮廷女の羨望の的であり、何人か寄れば口の端にのぼり噂話は耐える事がなかった。
安元2年、後白河院五十賀のこの時、維盛が烏帽子に桜の枝、梅の枝を挿して舞った、「青海波」は後々までの人々の語り草となった。「安元御覧記」は次のように記している。
左右互いに舞いを奏す、、、、、、青色のうへのきぬ、すほうのうえの袴にはえてる顔の色、おももち、けしき、あたり匂ひみちみるひとたゞならず、心にくゝなつかしきさまはかざしの桜にぞことならぬ。、、、、
野迫川村歴史資料館HPより
女院からお衣下賜があり、父の大将重盛が座を立ってきて、これを受け取り女院に拝し奉った。「県礼門院右京太夫集」には、
――法住寺殿の御賀に青海波舞ひての折などは、光る源氏のためしも,思ひ出でらるゝなどこそ、人々いひしか。花の匂ひも、げにけおされぬべくなどきこえしぞかし。――
とあり、維盛はこの頃源氏物語の光源氏になぞらえて、語られる事が多かったのである。この舞により維盛は大変な賞賛を浴びたが、一人維盛の名誉にあらず、平家一門の貴族的な優美さも改めて認識されるにいたった。青海波は雅楽の曲のひとつであり、管楽や舞楽などに用いられている。その文様は中国の青海地方の民族模様・山岳文様である。代表的な吉祥紋のひとつとされていて、波が左右に交互に重なる文様であり、色は藍と青の中間位の優美な色合いである。舞楽の衣装に使われている他、絵にも好んで描かれた。舞楽の装束にあってはこの曲の服飾ほど、「秀美なるものはあらじ」と言われるほどであった。
この他、今でも青海波の模様は古き町並みを残すための、石畳などにまで使われている。維盛の父平重盛は太政大臣平清盛の嫡男にして、権中納言 権大納言 大納言 内大臣を歴任し、1179年に出家し、熊野に参詣後まもなく病気になり41歳で没している。
名もない官女との間に惟盛を設け、側室の下野守藤原親方の娘、少勇輔掌侍との間に資盛を設けている。正妻の中納言藤原家成の娘経子との間には弟たち、清経、師盛、忠房、宗実が生まれている。その他、母名不詳ながら重真、行実、重遍、清雲、他二女の子供たちが居たとされている。
さて惟盛ほど伝説の多い人物はいない。その伝説は熊野沖入水・その後の遁世についてのものが多いが、以下は浮名を流した伝説である。維盛が妻と妾である白拍子(巫女)とで三峰川(今の伊那市)の浦の地に一時住んでいたという。
ところがこの白拍子は生活に疲れ、世を儚んで川の深みに身を投げたという。そして維盛は白拍子の霊を祀った。
この場所は「巫女淵」と呼ばれている。光源氏の再来ともてはやされた惟盛に、側室が居たという事は充分考えられるところである。世の女性からは、引く手あまたの状態であったであろう事から、他にも女性が居たと考えるほうが自然であろうか。一の谷の決戦の時、小松一門は三草山の守備についていたが、義経の勢いに乗った軍勢に、態勢を崩され敗走を余儀なくされた。
一説には維盛は重病で三草山には布陣せず、屋島で療養していたとあるが、維盛は出陣したものの体調が優れず、大将軍には弟の資盛を立てていた事からこうした話になったと思われる。
この三草山の戦いの後、師盛は一の谷の助勢に廻り討死、資盛、有盛は屋島へ撤退して行った。平家の時代は終わったと考えていた惟盛は、部下を連れて三十艘ばかりの船を用意させ一時四国へ退く事にした。
「玉葉」によると、維盛卿三十艘ばかりの船を率いて南海を指して去りおわんぬ云々とある。
この後、惟盛は暫く屋島に逗留していたが、時代の趨勢を見極め劣勢を挽回し、有利な条件で講和を結ぶためには、形だけでも援軍が必要と考え熊野へと渡った。援軍を獲得できる僅かな望みが絶たれた場合には、身の処し方を父に仕えていた滝口入道に相談する積りで、数名の従者を連れただけで熊野に入った。
「高野春秋」に次のように記されている。「小松維盛、従者阿波守宗親及び二三の輩を拘引し、屋島内裏より来奔し、戒を心蓮上人(東禅院の元祖なり)に受説す」
熊野権現は朝廷との繋がりも深く、公家や庶民にも広く信仰され熊野詣は行列を作るほどだったという。
維盛が頼みとしていたこの熊野三山は、従来からの源氏との関系、また時代の趨勢が源氏の世に傾いていく流れを読み取り、維盛の話には耳を傾けなかった。
維盛は平家の嫡流であり、本来であれば統帥権を握ってもおかしくない立場にあったが、今は叔父である宗盛が兄弟たちと計り方針を決定していた。
維盛の母の身分が低かった事も原因していた。弟たちは身分も名もある母の腹によっていた。長い間の公家的な生活が沁み込んでしまった維盛には、武士の棟梁としての才覚と気迫が不足していた。
このため、維盛の平家一門での立場は清盛亡き後から、次第に微妙なものになっていたのである。これまでの合戦で取り立てて、功績を挙げていなかった事も一因になっていたかもしれない。
世の中が大きく変わろうとして時間は急速に流れていた。平氏が例え九州勢を糾合して、反攻に移ったとしても京都から東国一帯までを固めている頼朝を、排撃できるとは思えなかった。
熊野で援軍を得ることを諦めた維盛は、次善の策と考えていた滝口入道に会うため高野山に向った。滝口入道は元は重盛に仕えていた武士であったが、父の反対にあい失恋し、結果として出家した者であった。
滝口入道と夜を徹して語り合った維盛は、自分は反抗の首謀者でもなく一門のしがらみに引きずられただけであるので、出頭するゆえ助命の儀お許しありたいと院の御所へ使者を送って伺いをたてた。
院(法王)も気の毒に思われ頼朝へ伝えたが、頼朝の返事は取り合えず鎌倉へ参れとの命令であった。維盛はこの期に及んではやむを得ずと、従者と共に出家する道を選択した。
従者の与三兵衛重景と石童丸が、先に滝口入道に剃髪してもらい維盛がその後に続いた。入道の案内により、維盛は高野山の峰ゝ、お堂を巡礼し父重盛及び先祖の供養をした後、那智の浜へ出た。
維盛は沖の島へ渡り松の木を削り、辞世を綴り終えると小舟から海へ飛び込み、波の下の補陀落の世界を目指した。この頃には夕闇が迫り、陸の方からはしかとは確かめられなかった。観音信仰の補陀落渡海を演じたのであり、入道が全て計らった事である。那智には今も補陀落寺がある。
この後、京の都では維盛入水の話が噂となったが、弟の清経も瀬戸内海において入水しており、人々はさして奇異な事とも思わなかった。
惟盛伝説
十津川村(奈良県吉野郡)に惟盛の墓がある。十津川村のホームページに次のようにある。
「平惟盛は平清盛の孫で、“桜梅少将”と呼ばれるほどの当代随一の美男子だったといわれています。平家一門の滅亡を前に寿永3年(1184年)那智の海に入水、27才で果てたと伝えられています。
奈良県野迫川村には平家盛衰の物語を題材にした資料館、平維盛塚などがありますが、十津川・五百瀬(いもせ)にあるこの墓が本物だという根拠は、廃仏毀釈前にこの地にあった寺の過去帳に、維盛の戒名が記されているところからきています。」
ちなみに野迫川村と十津川村は、十津川を挟んで向こう側とこちら側との位置関係にある。平家物語、源平盛衰記では維盛の入水があたかも真実のごとく、記述しているがこれ等の話は、あくまでも物語であり史実の記録ではない。
仏教僧、高野聖、熊野行者などが語り物として、創作し仏教の布教に利用していた側面も強く持っている。(勿論史実を記載している部分も多いが)
いかに命の軽い時代背景があったとしても、民衆を助ける主命を担っている、仏教の高僧が必ず成仏できるからと自殺を勧め、しかも同じ船に乗りその脇から海に飛び込ませ、死ぬのを見ていたという事は全く考えられない。
世話になった主家の嫡子であり、貴人でもある惟盛を助けこそすれ、自殺するのを手伝う僧など居ようか。
この頃、絶大な信仰を受けていた熊野には、焚身捨身して熊野の沖にある補陀落へ渡る「補陀落渡海」という信仰があった。海に入水し、死んだ事にすれば全く別の人になって、残りの人生を生きられるというものである。
これは現代でもよく言われる「死んだ積りになれば、何でも出来る」という事にも繋がっていようか。
また別の伝説はいう。維盛は熊野沖での入水を演じた後、行者たちに案内されて、那智大社の北の山を越えた色川郷という所に身を隠し蟄居していた。後世この地に残した子孫は、畑などを開拓し繁栄したという。
この地では「香」を作り、毎年那智大社に香を一荷収める他、行事は何も行われなかった。この地は「香膠」(こうばた)と呼ばれた。この地の小松姓、色川姓がその維盛の子孫とされている。この説は「大日本史」にも採用・記述されている他、現地にも伝説が残っている。
「大日本史」には維盛は熊野に入り、船に乗り夜の那智の海に漕ぎ出し、偽って海に赴いて死んだ事にし牟寠郡藤縄に隠れる。子孫は後に香を那智大社に貢ぐようになり、その地は香膠と呼ばれるようになったとある。維盛はこの地で蕗を食べて死んだという口碑が今に伝わっている。
「平家物語全注釈」によれば、この「大日本史」にいう伝承は「高野春秋」元暦元年三月十五日の条にも次のような説明記事があるという。
「この補陀落渡海の演出は滝口入道の計らいであり、入道が熊野山那智の海浜に誘引し、入水して往生すると称して二十八日の夜船を出した。
同行の信者たちが声を合わせ、高く念仏を唱える中を漕ぎ出して沖に消えた。世に入水と称すといえども、実は忍び姿となり深山の中に隠れ天年を終わる。その時、行年二十七才なり。この末裔保田庄のうち小松氏が是なり。下湯川・杉原・板尾・三个村を領して守護も介入しない所の領主なり。」
また「太平記」巻五「大塔宮熊野落事」にも同様の記事があるという。十津川竹原宗規入道の一族・戸野兵衛が、大塔宮護良親王を匿う時の言葉として、「平家の嫡孫維盛と申しける人も吾らが先祖を頼って、此処に隠れ遂に源氏の世につつがなく候けるとこそ承り候へ」と言ったという記事である。
「源平盛衰記」には、「維盛は熊野三山の参詣を終えて高野山へ入り、どうしても遁れられない身ならば、都へ行き院の御所へ参り我が身は首謀者の中にも入らねば、罪は深くもなし命は助けられたしと申し入れた。
院は殊の他、気の毒に思われて鎌倉へ仰せ遣わされけり。頼朝の返事には彼の卿を下し給いて、家来に従って下向し自分で申し立てるべしと申してきた。したがって院は鎌倉へ行くべしと仰せられた。
維盛はこれより飲食を絶っていたが二十一日も経つのに、鎌倉へ到着せず相模の国湯下の宿にて死亡したという記事が「禅中記」にあり、ある説では那智の客僧などが憐れんで滝の奥に庵を作って隠した。其処は今広い畑となり、子孫は繁栄して那智へ香を贈り、行事なく今は香疁という、入海は偽り。」
とある。
和歌山県在田郡に上湯川村がある。ここに旧家の小松家が今もあり、維盛の子孫と伝えられている。維盛が日高郡龍神村の奥杉谷山中に、隠れ住んだ後その子孫が上湯川村に来て、近隣一帯を支配し仕える村民も多かったという。「紀伊続風土記」に次のようにある。
旧家 地士 小松弥助
伝え云う小松内大臣重盛紀公の嫡男三位中将維盛卿の後なり、維盛卿熊野にて入水と偽り、日高郡龍神村の奥杉谷山中に蟄居し、後子孫当地に移りこの地一円を支配し、村民も其の召抱えの者の末多しとそ代々小松弥助といふ元和五年よりりん米を賜り地士となる。今杉谷山に小松屋敷の跡並びに小宮三社其よ古跡ありとそ
同じく紀州の熊野本宮の近くの、熊野街道に沿っている湯峰川渓谷の湯峰に伝わっている伝説がある。熊野沖で入水すると見せかけて、生き延び山を伝わって来て熊野本宮に詣で、近くの湯の峰に遁世していたとする。
ここは話のみで、物証は何もなく墓があるわけでもない。また寺に位牌や棟札があるという事もなく、子孫が何処其処に居るとも伝わっていない。このようにひっそり語られているのには、近くにある熊野本宮が源氏方に近かった事と関係があるといわれている。
少しでも噂話などが外部に漏れると、鎌倉殿にお伺いを立て維盛一党を、誅せねばならない事態になってくる事を恐れたのである。
奈良県吉野郡野迫川村にも維盛伝説が残っている。ここでは維盛は壇ノ浦合戦の前に、援軍を頼むために屋島から熊野に入った事になっている。そして山中を転々として生涯を終えたと伝えられている。
野迫川村には維盛塚があり、ここを中心として、歴史資料館などの平維盛歴史の里を大々的に整備している。
維盛塚

維盛歴史の里 野迫川村HP
悲運の六代丸
六代丸は父維盛の容姿を受け継いで成長したため、一見美しい娘にも見えたといわれている。平家滅亡後は、遁世生活を送るため母に女装させられた事もあった。そのため、後に六代御前と呼び習わされるようになったとされている。
六代丸は京都の草深い山里に、母と妹と一緒に隠れ住んでいた時に、賞金の為に密告する人が居て囚われの身となった。
あわや鎌倉に送られようとする時に、これを聞きつけた文覚上人が、鎌倉に伺いを立てるからそれまで待つよう申し入れた。頼朝は文覚上人の手紙を受け取り、上人が自分の弟子にして出家させるからと、あまりにも熱心に助命を願っていたので、小松内府のこともあり当面、上人に預ける事を了承した。
維盛の父重盛が、池の禅尼の使いとして、頼朝の助命嘆願をしてくれた事は忘れていなかったのである。六代は上人の下で、暫くひっそりと暮らしていたが、数年もたつと鎌倉の空気がやや剣呑になってきた。このことを感じた上人により出家する事を余儀なくされた。
栄枯盛衰は世の習いといわれるが、この時代の波は急速に動いていた。頼朝の恩人として権勢をみせた上人も、やがて罪を得て流人の汚名を蒙ることになる。高野山をかわぎりに熊野山にこもり、名のある山・寺を訪ねて修行を重ねていた六代は、これを聞き、上人が逗留していた大覚寺近くの宿所に戻ってきた。
知人などから情報収集しながら、思案している時に北条四郎が踏み込んで来て囚われの身となってしまった。
鎌倉に送られた六代はややあって、頼朝に面会し鎌倉の小さな寺に軟禁状態に置かれたのであった。頼朝はこの面会の時の印象を、心憎からず思ったとの事である。六代は元服前の公家の美少年であり、しかも今は僧でありながら凛とした気品は全身から漂っていた。生まれながらに、その身に備わった気高さが、その居住まいの中に自然に現れていた。
六代は兵を起こして、鎌倉に叛くなどは微塵も思っていなかったので、頼朝の思いはむしろ当然であり、自身が清盛の前に連れて来られ面会した時の事を思い出し、哀れにも思えたのではなかったか。
軟禁状態もほぼ解かれて、ある程度は自分の意思で外を歩き回れるようになっていた翌年、六代は許可を貰って上野国の名刹を訪れた。
寺男を二人同道することが許可の条件になっていた。六代は生きる当てもなく、一日一日を生きてそして死んでいた。その心は朝生まれて夜には死んだのである。頼朝の気分しだいで、何時首を斬られるか分らない状態で、生きていくのには心の拠り所が必要だった。
平家の嫡流として、公家の華やかな生活しか知らなかった六代である。子供の頃に置かれていた環境・習慣から、全く別の質素な生活をおくるのには、相当な心の葛藤を抑える強烈な理性が要求されていた。
関東の名刹浄法寺(緑野寺)を訪ね、住職に生きる当てのない自分は、心の置き所を何処に求めればよいのか教えを請いたかった。都で別れたきりの、弟の維基にも一目会って別れを告げておきたい。
上野国鬼石にある浄法寺は、伝教大師(最澄)が信仰を広めるために、末寺を立てたうちの一つで創建は815年頃といわれている。
本寺が延暦寺で、本尊は阿弥陀如来であり、東国の天台宗の拠点になっており武家にも広く信仰されていた。
維基は六代の異母弟であり、年も一つしか違わなかったが、六代と違って逞しく、野性的なところがあり、野武士のような風格を発散させる男で、弟なのに何故か頼もしいところがあった。
維基の母は武勇で鳴らす秩父平氏の娘であり、その血を引いている維基は着る物にはとんと無頓着で、言われなければいつも同じ袷を着ていた。維盛とは別居していたため、一人で山へ分け入って、鳥やウサギを捕まえたり、川に潜って魚を取っているような子供であった。
維盛の叔父知盛が永暦元年(1160)に武蔵守に任じられ、武蔵国に滞在した折に、人手が足りなくなり秩父党に申し付けて娘を出仕させた。仁安二年(1167)知盛は武蔵守の任期を終え都へ戻った。
この時、知盛室の請いにより都に同道してきた娘を、維盛が見初めて貰い受け、帰京した翌年嘉応元年(1169)維基の誕生となったのであった。源氏勢が上京し都が戦乱に、巻き込まれそうな情勢になった折に、維基は母と共に武蔵国へ帰っていたのである。
御前岩の六代丸
新緑を揺らせて爽やかな風が吹いてきて、六代丸の頬をなぶっていく。足下に見える鮎川の清流の、せせらぎが心地よく響いてきて、うたた寝を誘うようだ。時折、鶯の鳴き声が聞こえてくる。
鶯はこちらで音を立てていても、よほど傍に近寄らない限り鳴くのをやめない。やがて六代丸の後ろで響いていた槌音がやんだ。
近在の石工親子が、今仕上げたばかりの石碑を首を左右に傾けては、ためつすがめつ角度を変えて出来栄えを確認していた。上日野や三波川は石を産出する為、この辺りには腕の良い石工が何人も居るのである。
断崖になっているこの岩壁にはところどころに、躑躅(つつじ)の花が咲いていて六代丸のお気に入りの場所だった。
ここの岩壁の僅かな岩棚に腰掛けて、鮎川のせせらぎの音を聞きながら、あっという間に過ぎていった華やかだった日々、やがて訪れるであろう自分の最後の時に思いを廻らせていた。
六代丸は、傍らで鮎川の河原を眺めていた弟の維基を振り返った。維基は、ほんの少しの岩の出っ張りに生えた、躑躅の木の根元に跨って背中を岩壁に持たせかけていた。維基はひょっとしたら誰か来るのでは、そんな気がして河原とその上に続く叢と、雑木林をぼんやりと眺めていたのである。
ここからは見えないが、雑木林の上には曲がりくねった小道があり、左へ行けば名無村から峠を越えて秋畑村、右に行けば下日野村を通って金井村となる。上日野小柏村からも小半刻ほどの距離がある、この渓谷に人などが来る筈がなかった。六代丸は今仕上がったばかりの、父の追悼碑の前に立ち僧衣の袂で、碑に僅かに残った石砂を払って維基を促した。
用意してきた酒と線香を供え、惟基と並んで額ずき法華経を誦し始めた。六代丸は半刻ほど身じろぎもせず、先に逝った平家の一族の霊を弔った。今生きているのは妹の夜叉御前を別にして、自分たち兄弟の二人きりだった。
この断崖・絶壁は後に御前岩と呼ばれるに至った。幼名六代丸は平正盛から数えて六代目にあたる事から命名された。正盛、忠盛、清盛、重盛、維盛、六代丸の順である。出家してからは妙覚と名乗り、三位中将維盛の子だった事から三位の禅師とも呼ばれた。
禰寝氏の系譜によれば、六代丸の名は「高清」になっている。高清の子とする清重が建部氏となり、後に禰寝氏を名乗り大隈国の禰寝院南俣に入り、源頼家により地頭に補任されたという。
清重の名は清盛の清、重盛の重をとって清重としたという。禰寝氏の系図を見ると、その子たちの名前の頭には清をつけ二文字にしている。大隈半島で勢力を拡大し、後には島津家に仕え長く繁栄した氏族である。
実在が確認されている人物「高清」は頼朝に許されたが、反逆を恐れた頼家により斬られたとされ、この点は確かに六代丸に類似している。
「小柏氏800年の軌跡」
第一章 高政鼠喰城で千人斬り
小柏氏の始祖
上州は古くは上毛野国・上野国と呼ばれ、武蔵国とならび大国に列せられ、上毛野氏が国造として任じられ東国一帯と共に支配していた。上毛野氏は古い氏族で崇神天皇の皇子の豊城入彦命を祖としている。
また上州には有名な多胡碑があり、多胡郡の新設に伴い711年に設置された物とされる。この多胡碑から南西に直線距離でおよそ11キロの所に、西上州の秀峰・御荷鉾山がある。東御鉾山・西御鉾山の北麓には、鮎川の清流が西から東に向かって流れている。
鮎川は決して深い谷ではなく、何所にでも見られる普通の小川であるが、上日野の西部から上流は渓谷の趣き・景観をなしている。この鮎川の一帯、下日野・上日野は古くは日野谷と呼ばれた。
上州日野谷に君臨していた武士団・小柏氏は伊勢平氏の系譜を継いでいる。その系図には桓武天皇より、連綿とした系譜が記されている。平清盛の子重盛の嫡子、維盛の子維基が小柏氏の始祖である。維盛の嫡子六代丸は出家している。また清盛は天皇のご落胤との説もあり、妊娠した女(むすめ)を父の忠盛が娶らせられ清盛が生まれたという。
別の説には、これは清盛サイドが意図的に作った話という。小柏氏正系図によれば同氏の祖「平維基」は六代丸が生まれた翌年に出生している。
小柏氏系図は代々の継承者の名前が載っているだけではなく、主だった人には事跡が添え書きされている。
この添え書きには別記ありと書かれていて、系図の他に詳細な記録があったことを示している。
この系図は太い巻物となっており、タイトルは汚損して読み難くなっているが、かろうじて「平姓上野国小柏氏正系図」と読む事ができる。
系図に名前の記載はないが、妹の夜叉御前は維基の次に女子と記載されている。一般に系図には女子の名前は記載されない、○○の女(むすめ)とか○○の妻○○の妹と記載されている。夜叉御前は維基が生まれた翌年の出生ということになる。
系図によると維基は幼名平太郎といい、上野国小柏(現在の藤岡市上日野町小柏)に移り住み、後に土地の名を採り小柏氏に改称したという。
藤岡市が刊行した「ふるさと人ものがたり」の小柏氏の項には、
「身分を隠した伊勢平氏の直系とあり、上日野小柏の高台に『小柏様』と呼ばれる屋敷があり、集落を眼下に一望できた。
半ば伝説化したこの一家の活躍の跡を尋ねる。小柏氏は伊勢平氏の末裔で、始祖は父維盛が武蔵国司在任中に生まれた平維基であり、壇ノ浦合戦後は源氏から逃れ日野の奥に隠れ住んだ。
そして身分を秘して、小松姓を小柏姓に変え、建久7年(1196)には鹿島神宮を創建したという。」
と記されており小柏氏の事跡の説明が続いていくが以下は略す。
「藤岡市史」では「小柏」は豪族小柏氏が居館を置いたところから命名されたとしている。その屋敷跡は現存している。
清盛の嫡子・平重盛一族は京都付近の小松谷に住み、小松姓を名乗っていたが、源平合戦に敗れたあとその子孫の小松維盛が日野谷に落ちのび、隠れ住みついた時、「小松」を「小柏」と改姓したといわれている。(市史通史編・近世)
父の中将維盛が、武蔵の国司の時に東国の諸士に甚だ崇敬されていて、この頃に妾があり、ある時懐妊し維基が生まれたという。
「公卿補任」等によれば、維盛が武蔵野守に任じられた記録は、見受けられないようであるが、或いは目代であったか又は一時的な任官であり、辞令のないままに赴任したのか定かではない。
上日野小柏(村)から鮎川をさかのぼった所に御前岩がある。ここに六代丸と弟の維基の足跡が残っている。
「群馬懸多野郡誌」によれば、「小柏を隔てること十数町、人家のなくなる所に鮎川の源流がそうそうと音を立てて、断崖の岸を洗う所がある。ここを名づけて御前岩という。高さ二十丈で絶壁の頂は天高く、中空に聳えており、岩壁の腹には躑躅(つつじ)や楓が彩っている。
遥かに御荷鉾山の秀峰に対峙・向き合うようであり、足元を見れば水石の粼ゝ(りんりん)としているのを弄ぶかのようである。」と形容している。更にこの岩は平家維盛の子息六代御前が、弟の維基と共に小柏村に蟄居していた折に、ここに碑を建てた旧跡という。
そのとき建てた碑は、嘉永年間の山崩れの時に何処かへ流されてしまい、今は崖の中腹に石の階段のみが残っている。と記されている。
(* 一町は109mか。十五町として約1.6キロか。)
「多野藤岡地方誌・各説編」には小柏から1キロ余の所の断崖の景勝である。として平維盛の長子六代が弟・維基と共に小柏村に隠れ住み、その時ここに碑を建てた旧跡であると伝えている。その碑は嘉永年間(1850頃)の山崩れの時に流失したといい、岩の中腹に石段だけが残っている。
とある。
資料として購入した国土地理院発行の、二万五千分の一の地形図は何度も目を通していた。「上野吉井」と「万場」の2枚である。御前岩の痕跡らしきものを探してつぶさに見ていたところ、小柏村より上流の地点に墓石状の小さな記号を見つけた。この記号は昭文社の三万分の一の地図にはないものだ。記号一覧を参照するとこの記号は記念碑と書いてある。
この記号の少し下流の所は両岸から崖が迫っているように等高線が密集している。両岸は急斜面で川幅が狭くなっているように見える。とすれば急流となっているのだろうか。「多野郡誌」の記述と一致する。
これはてっきり御前岩の記念碑に違いないと思ったが、現地調査に行く機会がなかった。数ヶ月も経ってから漸く現地を訪れた。山へ入るのは、やはり木の葉の落ちて見通しの利く冬が良い。
小柏から上流へ向い注意深くそろりそろりと進み、やがてこの辺りかと思った地点を少し過ぎた辺りに石碑を見出す事が出来た。それは川に向って少し路肩の部分がせり出した安全地帯に設置されていた。
これだなと思って近づくと、なんとそれには「県道昇格記念碑」と書いてあった。群馬県はこんな碑も建てるのですね。小柏から1.6キロはとっくに過ぎていたが、念の為に更に会場(村)の方へ向って行って見たが何もない。
紛らわしいと思いながら、もと来た道をゆっくり引き返した。右手に鮎川をじっくり眺めながら行くと、蒼い水を湛えたお釜があった。青と緑を混ぜ合わせたよぅな吸い込まれるような、手をつければ冷たくて千切れそうな色をしている。深さも3m以上ありそうだ。
この渕に見とれながら少し上流へ戻ると同じように深いお釜があった。対岸からは大岩が迫って渕を作っている。お釜の上は小さな滝状の流れを作って急流となっている。手前には雑木や弦状の木が生えておりよく見えない。覗き込みながら更に近づいて行くと、対岸は屹立した岩盤状になっている。
これがそれらしいと思いながら何枚か写真を撮った。高さはおよそ20mくらいか。水面近くは大岩が何枚か重なっているように見えるが、上部は断崖状で直角に近い角度でそそり立っている。御前岩なら中腹に石段が残ると聞くが、目を凝らして探してみても潅木や弦状の木が垂れ下がっている他、草なども付いていて判別は出来ない。
しかし小さな橋の反対側から、上流の方を覗くと流水域は2mほどに狭まって急流となっている。やはりこれは御前岩だ。
戻ろうかときびすを返した時ふと欄干の端に目が留まった。橋の名前のプレートが貼り付けてある。近寄ってみると「御前岩橋」としてあった。翌日、休日明けで開館した市立図書館に行って、住宅地図を検証したところ同橋は「御前岩橋」と記載してあった。
鮎川の渕 
午前岩 



藤岡市の旧美九里村は、古くから開けた村落でありさまざまな伝説が今に残っている。美九里の龍田寺の屋根裏から見つかったという、「神明縁起之覚え」にも文覚上人が信州善光寺への参詣の際に立ち寄った時の状況が記されている。
資料の文字は薄くなっており、詳細の意味は判然としないが、本郷・神明村の境に明神の社があり、頼朝公の時に建つたとされる社という。
地頭高山遠江守の時にこの周辺に困りごと(冰嵐)が発生し難渋していた。名僧と呼び声高い、文覚上人が中里弾正の家に宿を取っていた時に、高山殿が祈祷を依頼したという。
上人は弾正をお供に参宮し内宮、外宮、土主明神、瓶子明神、飯玉明神など十二社を建立したようである。
そして地頭が社領として十二社に百石を寄進した。同社は地頭が替わっても諸役免除となり、その証文が神明の宝物となっていたが、火災により焼失してしまったという。このため、右の通り先祖代々の申し伝える事を書き記し置くものなり。この時、天正十二年。
かろうじて判じられる部分は以上である。同文書は高山家系図と一緒にあったので同家所蔵の物であろう。
「多野藤岡地方史総説編」によれば、美九里村(藤岡市本郷)の葵八幡の近くに、「文覚上人の垢離(こり)の水」がある。直径が約91センチ,深さが約1.9メートルの井戸である。
旱魃の時に文覚上人がここで水垢離をとって、雨乞いをしたところ雨が降ったといわれている。上人が袈裟をかけた楓の木もあった、という。文覚上人は六代丸の助命嘆願をして、一時は六代の命を救った高僧である。元は北面の武士であったという。出家してからの荒行はつとに有名である。
藤岡の本郷から道を西に取れば、東平井・平井城を経て下日野から上日野に至る。
この地に文覚上人の足跡があるという事は、六代丸の伝承がある事と併せて考える必要があるかもしれない。
日野の地名は相当古くからあったものらしく、「群馬懸多野郡誌」によれば和訓栞、和漢三才圖會に「日野は上野の邑名なり」とあり、上野名跡考には「日野は多胡(郡)の南部なり。属邑十二、或いは火野なるべし。
上古防人と烽(とおひ・とふひ)とを置きて蝦夷に備えられしといへり」とある。
また日野大宮社天文十七年の棟札に「穎野」とあるが、火野は仮説であり、穎野は音を当てたものではないかとしている。
なお、同社後代の棟札は「日野」と記してあり、他の古書、旧記には皆「日野」とあるとのこと。よって関東平野の西部に始めて山脈の起こる所であり、御荷鉾山の峻峰より朝日を迎え、夕日を送るところから日野と呼ばれたのではあるまいかと推測している。
平井以西が日野谷(ひのやつ)であり、鮎川に沿って東西に十里あると言われ、西南部には西御荷鉾山(1300m)東御荷鉾山の秀峰がそびえている。所々に集落が出来るにつれ、日野郷と呼ばれた事もあった。
和名抄に見える多胡郡俘囚郷が上日野に当るとされる。天正年間に至り、上日野、下日野、金井となり、寛永年間に入りこれを三村として名主を置いた。そしてこの形は明治二十二年の町村施行まで続いたが、三村合併して日野村と改称した。
また古くは日野は鼠食郷(ねづはみ)、井池庄のなかとして記載されたものもあるが詳細は不明なりとしている。
井池は多胡にあり鼠食は日野にある。(同郡誌)鼠食の名は今は鼠食城(跡)として残っている他には見当たらないようである。あまり良い名前ではないため、他の名称に変わったものか。
「群馬県姓氏家系大辞典」(角川書店)に、次のような記事がある。
「小柏・おがしわ(藤岡市)日野谷から南の三波川谷にかけて、小柏姓があり、上日野字小柏が発祥地とされる。
平清盛の子小松内大臣重盛の子に維盛があり、重盛(ママ)が武蔵国司の時に、妾腹に生まれた維基は、のち鎌倉幕府を恐れて上野国小柏に隠れ、小松姓を小柏に変えて始祖になったという。(小柏氏系図)
子孫は鎌倉幕府執権北条氏に仕え、幕府滅亡後は山内上杉氏に属し平井城に出仕したという。
小柏高政の時、国峰城主小幡重貞と姻戚関係を結び、武田氏方として子息定重と共に長篠合戦で戦死。なお、定重は菊女伝説に登場する。後は弟定政が継ぎ、代々日野谷を支配した。」
維基 鹿島神社建立
小柏維基は上日野村鹿島に鹿島神社を建立している。現在、鹿島神社は別名を「日野お天狗」といい、またお天狗様とも上の天狗とも呼ばれている。同社の祭祀は、氏子や村民によって連綿と続けられ今に至っている。
夫婦和合の信仰もあるらしく、境内の端にそれと分る石碑が幾つかあり、男女抱擁の石碑「陰石」と呼ばれる物もある。
「多野藤岡地方誌・各節編」及び「群馬懸多野郡誌」によれば、同社は延享元年(1744年)に火災(祝融の災)により消失し、村民により再建されている。この際に(延享二年)奉納された棟札によれば、願人酒井與惣左衛門とあり、この人が発起人代表であったと見られる。
棟札に「当社は小松内大臣平重盛の末裔、小松平太郎維基が上野国小柏村に蟄居し、建久7年9月(1197年)に本姓を小柏と改称した際に創建した」とある。更に「所蔵していた甲冑・武具を奉納したところなり」との記載がある。「翌二年八月村民相計り、これを再建す」と続いている。
「藤岡市史・通史編」では、上野国神名帳には登載されていないが、鎌倉幕府の神社保護政策の時期と一致する事などから、社伝の通り中世には存在していたと思われる古社であるとしている。
鹿島神社は旧村社であり、(明治九年に上日野村社となった)諏訪社、八坂社、天神社、熊野社が合祀された。
慶応三年には神祗伯王家、駿河守藤原朝臣より正一位鹿島大神宮神璽及び副翰を下賜された。祭神は「武甕槌命」であり、宝物には鏡二面(径四寸・三寸三分)、古刀一振り(相州住友光作)、古槍一筋(天国藤原吉次作、穂先一尺二寸)、扁額二面(鹿與紅葉乃賦、寛延二年東都空門子覚胤撰と源義恭筆)春には太太神楽、秋には山車と獅子舞が行われているという。
「甘楽町史」にもほぼ同様の記事がある。祭神は武甕槌命であり、小松内大臣平重盛苗裔小松平太郎維基が、本姓を転じて小柏と改称の際を持って、創立し所蔵の甲冑戒具を納めたる所なり。としている。
「上野雑記」にある小幡伝説によると、天正18年(1590年)の小幡国峰城落城の折、城主上総介信貞の嫡男信秀が供も連れず一人で峰伝いに逃れてきて、疲労困憊の果てに鹿島神社を見つけ、これ幸いと本殿のうちに隠れ一夜を過ごしたという。
城を攻める寄せ手は大勢であり、果敢に戦ったが防ぎようがなくなったと家臣の浅香民部により、落ちて行くよう進言されたものという。
しばし時間を稼ぎ、信秀が自害したように見せかけ、城には火を放って後を追いかけて行くので、安全な秋畑の山伝いに落ち延びるようにとの言を入れての事だった。
同社で一夜を明かした信秀は、翌朝参拝に訪れた天引村向陽寺の和尚と顔を会わせる事となり、仔細を話しひとまず向陽寺において保護される事になった。
この向陽寺の和尚はその昔、武田の家臣であり、豪の者であったそうな。この時、信秀はまだ十代の若者であった。後に出仕の機会を得ている。
鹿島神社 


鹿島神宮の石碑
鎌倉北条氏と小柏氏
小柏維基は成人するまで、産衣のままで暮らしたと記載されている。(於襁褓之中為成人)おそらくは掻巻に帯一本締めただけの格好で通したという事であろうか。鎌倉殿を恐れて諸所を流浪し、上野国小柏村に至り遁世していた。
ここで小松の称号を小柏に転じたという。(小柏氏正系図)松の木が柏の木になっただけの改姓で、ありそうなことではある、柳にすれば小柳、杉にすれば小杉となり栗なら小栗である。
半分は元の本名を残しており、世を忍ぶ仮の姿であればよく用いられそうな変名スタイルといえる。井戸氏には同系統に熊井戸氏、古井戸氏、大井戸氏などがあり、小柴から分かれた姓に、文字を分解したと言われる小此木氏がある。
関連は不明だが小幡氏が居城としていた国峰城の近く、南側に小松という地名がある。系図には維基が小柏の始祖となり、子孫が連綿と相続しているとある。
維基の子維里は通称小柏太郎と名乗って小柏村に住んだ。維里の子時基は世襲制でもあったのか、やはり小柏太郎とされている。
1221年に後鳥羽上皇が、鎌倉幕府倒幕の軍を起こし承久の乱が勃発した。この後、六波羅探題が設置され朝廷は監視を受けるようになった。小柏時基の子維仲は市太郎を名乗り、北条陸奥守時村に従って鎌倉に住み、後1278年時村が六波羅探題に任じられ、京都六波羅入りした時に同行している。
維仲の子重胤は右衛門太郎と名乗り、六波羅探題となった北条左馬介基時につき従い京都に住んだ。
基時はこの後1315年に鎌倉将軍執権となった。小柏重胤の子時實は市次郎を名乗った他に事績の記録はない。時實の子實親は與市と名乗り、鎌倉で奉仕していたが、守邦親王の治世に執権、北条相模守高時(宗と号したと云う)の時、元弘三年(1333)に新田義貞に攻められ、鎌倉が陥落した時に討死している。弟の實季(小柏兵庫助)もこの時一緒に討死した。義貞が上野国から鎌倉へ侵入した時点で北条高時は自害して果てた。
同じ頃、高山越後守時重も同じく北条氏に属していて、武州関戸に新田義貞軍を迎え撃ち、粉骨砕身して働いたが同所で討死した。
高山(藤岡市)の高山氏は、南上州一の名族と言われた大氏族であり、小柏氏よりも古くから記録が現れ、「吾妻鏡」にも名前が記されている。その子孫は連綿と続き現在に至るも各方面で活躍されている
小柏氏は「ふるさと人ものがたり」に、維仲の時から北条氏に仕え、弘安元年(1278)時村の六波羅探題就任に従い、数年間京都大番役を勤めた、重胤も20年後に同じ役を果たしたとの記述がある。
上杉氏と小柏氏 鼠喰城
上杉氏は藤原家の出であり、天皇家とも縁続きの日本史上の名族中の名族である。足利氏とも濃い縁戚であるが、ある意味では足利氏よりも上位にランクされる血統・家柄であった。
南北朝時代には足利尊氏によって、上杉憲房が上野守護に任じられた。憲房の子が憲顕でありいわゆる山内(鎌倉)上杉氏の祖となった。山内上杉は扇谷上杉、侘間上杉、犬懸上杉とは元々兄弟であるが後に相戦う事になる。
憲房が京都で戦死した後、憲顕は新田義貞が国司を勤めていた上野国に入り高崎南部の八幡の庄を与えられた。
この頃は南北朝の争乱が顕著であり、双方の勝敗もめまぐるしく入れ替わった。上杉憲顕は越後の守護も兼務となり上野支配は安定した。しかし尊氏は弟直義と対立し、直義方についた憲顕は武蔵野の合戦で敗北して越後に逃れた。
10年後、待望論が湧き起こり憲顕は再び上野に戻り関東管領に就任した。小柏實親の子重親は平太夫とあり、宮内少輔、従五位下とある。
鎌倉管領足利左馬頭基氏に属し、基氏の執政を勤めていた副将軍上杉民部大輔憲顕は鎌倉山内に住んだ。上杉憲顕に従い、小柏重親も近くに居を定め勤番していたが延文五年(1360年)に没した。
重親の子重家は小柏庄司を名乗り、上杉に仕え幾つもの手柄を立て頭角を現した。
重家の項には、歴代日野庄小柏村に住んだとあるので、本拠は小柏村に置いたまま鎌倉に勤番していたようだ。
小柏重家は第八代の関東管領上杉安房守憲方(右京亮)に従い、鎌倉に勤番していて数々の武功を挙げた。貞治6年十一月(1367年)には上日野小柏村に宝塔を建立している。応永年中に没して同所の嶽ノ本に葬られ、その墳墓は今もあると系図の添え書きにある。
嶽ノ本とは小柏屋敷跡の、西南の隅にある墓地のことであろう。この墓地には小柏氏歴代の石碑・供養塔などの石造物群があり、今も静かに木漏れ日のあたる木立の中に眠り続けている。
小柏屋敷に最後に住んでいた「逸」の墓碑もここにある。群馬懸多野郡誌によれば、この宝塔は九輪の塔であるとしている。その碑文を次に示す。
謹募衆縁造立貞治第六丁未霜月日謹記 (1367年)
「藤岡市史・通史編」ではこれを小柏家墓地内、宝篋印塔と記している。宝篋印塔は、その内部に宝篋印塔陀羅尼経を納めて供養すれば、一切の罪業が消滅して寿命延長福徳無尽となるとの信仰により造立された物である。
もう一塔の碑文は
逆修□阿庵 應永二十七巳年二月日 (1420年)
とある。どちらも一族の結束を強める目的で建立された結衆塔である。造立の趣旨は生前に死後の安楽を願うものであり逆修供養の物である。
重家は小柏館の下を流れる鮎川を渡った所、西御荷鉾山に鼠喰城を築造している。山崎一著になる「上野国古城塁跡の研究」などを見ると、尾根筋を利用した山城であったと思われるが、高低差を持ちかなりの規模を有しているようだ。
標高700mから950mに亘って四つの土塁・砦・本丸などに分れている。
「多野郡誌」に次のようにある。
鼠喰城址 大字上日野村字御荷鉾山内にあり東西弐拾五間(45mか)南北四十
五間(81mか)ばかり、二段にして平坦なり貞治六年未年小柏荘司重家ここに築き住いすと上野鑑に見えたり。
鼠喰城(ねずはみじょう)はなんとも奇妙な名前・命名ではある。芋や食物でもない城がなぜ鼠喰みなのか。卑下・謙遜したとしても、築城した本人の名づけたものではなさそうである。
一説には鼠喰城に敵勢が押し寄せた時に、敵軍の野営陣地に白鼠が大挙して現われ弓の弦や刀の柄の糸を齧って切ってしまったという。
この為、さしもの大軍も戦闘能力を低下させてしまい散々に打ち負かされたという。(ふじおかふるさと伝説)
御荷鉾山の北面、標高九百mの所にあり、城(じょう)と呼ばれて南北六百mほどある。
南端は山頂に程近い。貞治六年(1367)小柏庄司重家が築いたものという。(群馬県古城塁址の研究下巻参照 多野藤岡地方誌・各説編)
鼠喰城 図 
明治8年頃の編集とみられる「上野国郡村誌」を見ると、上日野の項に古城嶽ノ城址、本村南釜伏山岳の中腹にあり、東西二十五間、南北四十五間、山を穿ち平坦に段になす。
今に至り土を穿つ者、古城具・軍器等を得る。貞治6年未年当村平民小柏八郎治祖先小柏荘司重家築き、居住する事五年にして小柏へ転住すという。と記載されている。
西御鉾山を釜伏山岳と呼ぶ事は、種々ある文献でも一顧だにしないものである。かつ鼠喰城を嶽ノ城と呼ぶ事も同様であるが、その城の規模からいってこの記事の城は間違いなく鼠喰城の事を指している。
更に重家が同城に5年居住していてその後、小柏(村)に転住したという記事も初見のものであり、ちょっと奇異な感じも受けるが参考までに揚げておく。
小柏重家の跡を継いだ重徳は六郎を名乗り、鎌倉将軍足利基氏の第11代関東管領上杉安房守憲定に仕えた。この時代、小柏氏正系図では当初南朝の元号を使い後に北朝の年号を使用している。
1392年には南北朝間での和議が整い、朝廷は合議により統一された。上杉氏の守護国は上野、武蔵、伊豆、上総、下野の五カ国になり関東管領として支配を確立していた。
山内上杉は憲顕のあと五人が関東管領の職を勤めた。憲定の子、憲基の時に、上杉氏憲(禅秀)の乱が起こり、憲基は一時越後に逃れたが、寺尾、小幡、小柏(高家)、白倉氏を従え犬懸上杉(禅秀党)を打ち破った。上杉憲基は従兄弟の憲実を養子として、憲実は第14代の関東管領となった。
関東管領・平井城の落日
小柏重徳の後継者高家は平太郎であるが後に庄司と改名した。関東管領上杉安房守憲基およびその従兄弟憲実(後に養子となった)に属した。永享10年(1438)に後にいうところの永享の乱が起こり、この際に高家は軍功を挙げた。
これより先、憲実は養父が死亡した為に、僅か9歳で(1419)上野・伊賀2カ国の守護となり、関東管領に就任した。関東10カ国を支配する鎌倉公方の補佐となったのである。
この時代足利幕府将軍と、関東を治めていた公方とはその権力の範囲をめぐって時々対立していた。また公方と管領との間にも時によって微妙な対立があった。幕府の将軍人事に、不満を持っていた公方の足利持氏に諫言していた憲実は持氏に憎まれ、一時上野国平井城に戻った。
しかし持氏が兵を差し向けた為、これを迎えうつべく憲実は上野国、越後勢を率いて武蔵国に進出した。分倍河原において合戦となったが、持氏側の鎌倉の氏族の多くが憲実側につき、持氏は捕らえられた後、永享11年永安寺にて自害させられた。
憲実は自分の主君であるとして、幕府に命乞いをしたが入れられなかった。これにより、憲実は関東管領の職を辞任し剃髪して出家した。憲実は「賢人才知勇の人」と評価されていたという。
この後、憲実は多くの貴重な書籍を寄付して足利学校を再興している。出家していた憲実は、持氏の子供たちが兵を挙げた時には、一時俗界に戻り采配を振るって鎮圧した。その後は引退し諸国を巡歴した後、山口県長門市の大寧寺に住み1466年に没した。(ふるさと人ものがたり)
小柏高家の後継者重行は平治左衛門尉である。父の高家と共に上杉安房守憲実に属した。
重行を継いだ顕重は小柏宮内少輔で法名浄山である。当時関東管領の職にあり、上野国平井城に住いしていた上杉民部大輔顕定・兵部少輔房顕(前管領)に仕えた。
平井城に出仕している時に、上杉顕定から顕の一字を賜りこれにより顕重と名乗った。
この事は小柏氏が代々忠臣として仕えた結果だとの記載が小柏系図にある。しかし、小柏顕重は永正元年(1504年)武州立河原の合戦に出陣し討死してしまった。この頃、小柏家が属していた山内上杉と扇谷上杉との抗争が激しさを増していた。山内の上杉顕定、養子憲房は合戦下手だったのか、武蔵国須賀谷で敗れ(両上杉氏の戦死者七百余)、同国高見原で敗れ、相模国菅生原でまたおくれをとった。
翌年には相模真巻原での合戦にも敗れ、続く同国須賀谷原の合戦では漸く勝利を手にした。
その後、相模国菅生原での合戦にはまた敗れてしまった。10年後の9月23日、上杉顕定は立河原において、扇谷上杉、駿河今川、北条長連合軍との合戦に望み敗れた。小柏顕重はこの戦の時に戦死したものと思われる。9月27日、同所で再び対陣した両軍は今度は扇谷上杉朝良軍側が負けて朝良は川越に退いた。顕定は川越城を包囲して長期戦になったが、翌年には和睦がなり顕定は平井城に帰還した。
関東管領は古くは、足利尊氏が二代ほど勤めた事もあったが、代々上杉家が任じられていた。その殆どが山内(鎌倉山内)上杉であった。
犬懸上杉からは朝房・朝宗・氏憲が飛び飛びに任じられた他は、山内上杉が31人の内18人を輩出している。詫間上杉からは2人が任じられている。1363年より1578年まで実に214年にわたり、上杉家だけで連綿と関東管領の職を奉じているのである。
小柏顕重の後継となった顕高は小柏駿河守であり、後に剃髪して浄印入道と号した。父が戦死した後も上杉顕定・上杉兵庫頭憲房に仕えて、顕定から顕の一字を使うことを許されて顕高と改名した。毎日、関東管領居城の平井城に出仕した。後、上杉兵部少輔憲寛に仕えた。
顕高の後継者は高道である。又の名を小柏大學といい法名は道徹である。管領の上杉兵部少輔憲政に属し、幾度もの軍功を挙げた。天文14年(1545年)川越合戦の時にも戦功を挙げた。
高道の代においても合戦が多く繰り広げられた。第21代の関東管領の憲寛は憲政に家督を譲り、憲政は第22代の関東管領となった。この頃、北条氏(後北条)が急速にその版図を拡大していた。
北条氏綱は川越城を攻略し、松山城をも落として上野国に迫る勢いを見せていた。憲政は川越城を奪回すべく扇谷上杉と手を結び、天文14年(1545)川越城を包囲した。
北条氏康は川越城を救援すべく入間川で憲政軍を破り、憲政は平井城に退いた。この時の合戦において小柏高道は戦功を挙げている。その後、北条氏康・氏政親子に攻められ、平井城は落城の憂き目にあい憲政は越後へ落ち延びた。この平井城攻めでは氏康は大金を投じて、忍びの者を使い上杉方の家老や武将を抱きこみ城下をも攪乱せしめたという。
憲政は越後へ落ちて行く時に清水峠を越えるため、暫く水上町付近に滞留した為、現地には多くの憲政の伝承が残っている。(ふるさと人ものがたり)
後、憲政は越後の長尾景虎(後の上杉謙信)に管領職を譲り後を託した。こうして上野国は武田氏、北条氏、上杉謙信の三つ巴となった抗争の時代に突入していく。この頃の有力武将と在地武士集団の関係は、完全な主従関係ではなく緩やかな同盟ともいえるものであった。それゆえ、その時々の力関係、情勢によって離合集散が繰り返された。
上杉憲政が越後に落ちて行った後、小柏高道は小幡尾張守重定に招請を受けたが応じなかった。やがて重定の姪を息子の高政が娶ることになり、これにより小幡重定と和睦した。
「ふるさと人ものがたり」によれば、上杉氏の平井落城後、主を失った小柏高道を国峰城主小幡重貞が招いた。しかし小田原の北条氏に内通して憲政から離反、その先駆けとなって上杉氏を没落させた重貞を許せず応じなかった。
小幡氏と後に和睦し小幡家に内紛が起こった時には、孫の命を救いこれを援助して小幡本家存続のために働いたとしている。
高道には高景という弟があり、その幼名を小柏小次郎といった。高景は管領の上杉憲政に属し、兄と供に平井城に出仕していた。高景の力量は群を抜いていたとされる。豪胆で且つ大力があったらしく、後に駿河守を名乗った時には鬼駿河と人をして言わしめた。


平井城 土塁

上杉一族の碑
高景の子は景氏であり幼名を小柏新吾という。景氏もまた大柄の体躯をもち、その力は父の高景に劣らないものだった。そのため、叔父の高道にも一目置かれ、本家の後見役として重きを成した。
西城州の諸士は上杉憲政が越後に退いた後、一時は長尾景虎に従ったがすぐに進出してきた武田信玄に従った。
景氏の弟は高治でありその幼名を小柏新助といった。高治は、上日野の細谷戸の地守に任じられていたが、やがて武田信玄より信州佐久郡田ノ口村の、代官を命じられ赴任して行った。今にその子孫が田ノ口相木村に残っているとされる。
小柏景氏の子は高元であり、若年の頃は宮内介を名乗っていた。母は本家当主の高道の娘である。
高元の子は高久・小柏加兵衛であるが、その実は養子であったらしく、大塚村の何某の男と記されている。高久の後継者は光氏・小柏作重郎であるが、やはり小柏弥五兵衛の嫡男を養子にしたのである。
光氏の子は高次・小柏武兵衛であるが、実は堀口氏の次男を養子に迎えたものであった。武兵衛は後に一無という号を名乗った。(養母の弟なりとも言うが詳細は不明である。)高次の子は高連・小柏浅次郎であり後に武兵衛と名を改めた。
(以上は小柏氏の傍系である。)
小柏高道の長女は従兄弟の小柏新吾景氏の妻となった。法名を貞範尼という。この女子も男子に負けず、力持ちと評判をとった。その委細は別に記録があるとされている。高道の次女は、上日野小柏の奥隣の奈良山の後藤新太郎基道の妻となった。後藤家は古くから、奈良山に住みついていた有力武家である。
基道の子、道兼は姓を改め小柏新左衛門となり、以後小柏本家を脇から支える重責を担った。新左衛門は後に、「奈良山竜源寺」の開基となり、小柏氏の祖、平維盛の墓を建立して供養している。
母方の先祖をたどっていき、供養したのである。
「宝積寺史」に次のようにある。
上日野奈良山「奈良山竜源寺」、創建不詳、本尊不詳、開山芳谷永磨、開基小柏新左衛門道兼。沿革、奈良山の領主、小柏新左衛門道兼は小柏氏の祖、維盛(平)の墓所を建立し、宝積寺12世芳谷永磨を請じて開山とする。
同地の春日神社には、奈良山小柏氏の始祖、後藤大和守基明を祀る。後藤氏は基道の代に小柏氏と改称したという。現在は廃寺であるが、跡地には歴代住職の墓石三基がある。
寺地の上の方に、小柏氏の屋敷跡および墓地が残っている。この他、宝積寺の小幡氏の墓地の隣に歴代先祖の墓地がある。27世万仭道坦は進山披露のため、宝暦八年(1758)一月二十三日に当寺を訪問した。
その記録に「奈良山に赴く、殊の外難所なり、竜源寺にて喫茶、次に新左衛門にて吸い物、終りて麺子を出す、次に安五郎方にて吸い物、新左衛門より僕三人にて荷物を送る。薄暮れに本山に帰着す」
とある。宝暦六年の進山記録には、
二十四日 石原の利済寺方丈尊来入院祝賀なり、他門故に応対入念を入る。蕎麦切を出す。同日小柏八郎左衛門子息を名代に〆入院の祝賀を勤む、旧例は五百文三本入なり、今度は三百文三本入なり□□なり。
二十八日 小幡屋敷より熊井戸園右衛門を使者と〆去する比口屋敷にて出頭の検察あり、副寺チンキンの間にて応待す。
とある。この八郎左衛門は小柏祝重と思われる。名代としたのは長男の重簡であったのだろうか。また別の進山記録では当時の宝積寺の住職が養命寺に来て、小柏八郎宅へ泊まったとの記述もある。
七村城
上日野御荷鉾の名無村にその城跡がある。鮎川の水源に近い峰にあって、東端の郭(春日神社がある)から山頂の本丸まで二百七十m。小田原の北条氏の家臣後藤基明が同氏滅亡後、十余名を従えて来住して築いたと伝えている。
基明は後、奈良山に移って小柏と称した(奈良山小柏家)その跡を後藤屋敷と呼び、基明の墓がある。(多野藤岡地方誌・各説編)
「多野郡誌」には本村住民小柏喜伊三郎の祖先後藤基明、北条氏康の家臣たりし時、同家落魄以後この地に来たとある。全然酋長の如く何れへも納租せず耕作をして生活をなし、その後間もなく同地に移住し、その姓を小柏と改め今なお古墳があるとしている。
山内上杉氏が関東管領の職を代々勤めていた時代は,平井城下町が最も繁栄を極めた時代である。京都が打ち続く戦乱により荒廃していた為に、多くの人が地方へ流れそれに従って文化も分散したという。
上杉顕定は連歌でも名を成して、戦乱の中にも歌会を開いたりした。関東管領のお膝元は比較的平和との事で人と物資が集まった。このため、東平井一帯の城下町は一時は鎌倉にも劣らないとまで言われる繁栄を見せた。
「甲陽軍艦」に平井城には相模、武蔵、下総、安房、常陸、上野、信濃、越後、佐渡、出羽、陸奥、飛騨の国の諸侍が勤務していたとある。「上野伝説雑記」には十五カ国とある。これならば正に鎌倉を凌ぐものがある。
京都からも白拍子が多く下ってきて賑やかに栄え、武士たちは軟弱になって武を忘れた為に滅びてしまったとの記述がある。(多野藤岡地方史・総説編)
豪族 高山氏
西上野きっての名族、高山氏は古くから記録に現れ「吾妻鏡」「源平盛衰記」にも名前が現れる。上杉家の筆頭家老であったとの説もあり、戦国時代には既に高名の存在となっていたと思われる。
桓武平氏の系統の秩父重綱の三男重遠が、秩父郡高山村(飯能市)で高山氏を名乗り祖となったとされる。重遠は後に緑野郡山高郷(金井、高山)に移り、その一帯は高山の庄・御厨と呼ばれた。
重遠の子重久は木曾義仲軍に加わり、信濃横田河原での平氏との合戦(1181)に参陣しその後、源頼朝に属し奥州藤原攻め(1189)にも参加している。重久の子重治は、和田義盛と執権・北条泰時が対立した和田合戦において討死した。南北朝時代には高山時重が、新田義貞を武州関戸において迎えうちこの時に討死している。時重の子重栄・遠江守は義貞に従い、義貞没落後は足利尊氏方に転じた。その武功は「太平記」にも記されている。
高山重栄の孫の重康・重直兄弟は、足利義満軍に加わって山名氏の乱の時に共に討死した。重康の子頼重は、上野国の旧領を回復し上杉氏に属し同氏との絆を深めた。重秀・重友父子は結城合戦(1440)の時に反幕府軍と戦った。
顕定(山内上杉)に属していた重友の子、高山盛重は、扇谷上杉氏との武州菅谷原(嵐山町)で行なわれた合戦(1486)で討死した。憲重・重員兄弟も顕定と共に越後六日町長森原の戦いで、敵長尾為景との合戦において討死した。
平井城落城後は行重・定重兄弟は武田信玄に属した。武田氏滅亡後は織田信長や北条氏に属していたが、江戸時代に入りその子孫は帰農したものとみられるという。
江戸中期に重寛は金井の稲荷神社の別当に千体地蔵を寄進した。(ふるさと人ものがたり藤岡)
高山憲重・重員兄弟の討死については、「長森原古戦場史上杉顕定公」にやや詳しい記述がある。同紙によれば憲重は日野金井東城主で遠江守、弟の重員は甚二郎で平井城主、上杉顕定公の側近(重臣)として永正六年(1509)上州兵八千名と共に越後に進撃した。越後国の三分の二を制するも翌年六月、長森原(南魚沼郡下原新田)の戦いに於いて顕定公と共に討死を遂げる。
顕定公の墓は立派な多宝塔で管領塚に祀られ、討死した家臣の憲重や重員ほか三百余名の墓は管領塚近くの寺西珠院門前に祀られている。後、憲重の養嗣子重純は顕定公の四女を嫁に迎えたという。
尚、同史の別項によると長森原で対陣した人数は、顕定軍八百余騎、為景軍五百余騎であり、最初は顕定軍が優勢であったが、横合いから高梨勢七百余騎が突撃して来た為、顕定軍の敗走が始まったと言う。(鎌倉九代後記、鎌倉管領九代記、関東管領記)
幕末の頃に生まれ、明治時代に養蚕事業に多大の貢献をしたのが高山長五郎である。
長五郎は養蚕事業の改良・研究に取り組み、日野村の父の隠居所で飼育した蚕が豊作だった事にヒントを得て、天候に左右されない養蚕の方法を造り出した。後に「養蚕改良高山社」を設立し養蚕を指導した。また新道開設に私財を投じたり、貯蓄の奨励など農村振興にも貢献した。(ふるさと人ものがたり)
現在、高山氏の主な子孫・旧家は三家(金井・東平井・高山)あり、その何れもが系図・古文書・領地を所有しており何れが嫡流か本家か判然としないという。系図上では金井東家が嫡流で、満重が拠った山城跡を所有していて、栗須・神田の神明宮の祭祀を営んでいた。
高山にある南家は高山氏が在城した金山西城近くに邸があり、古文書を最も多く所有している。高山重遠が始めて住んだ清水山城や高山氏の菩提寺の興禅院も高山にある。
平井家は満重が建立したという満重山高源寺が近くにあり、満重の子定重は法号を
高源寺殿という他、高山氏の住んだ城跡も同寺の所有地になっていた。(多野藤岡地方誌・各節編)
高山氏と小柏氏の関わりの詳細は明らかになっていない。高山氏は頼朝に属し、後上杉に属し更に武田信玄に属し、その後織田、北条にも属した。この流れは小柏氏の航跡と殆ど一致している。この為、同じ合戦に参加したり行動を共にしたりする事もあったと思われる。
小柏氏系図には所々に主な事跡が記載されているが、高山氏に言及した箇所はない。また高山吉重文書の高山氏の二つの系図を精査しても、小柏氏に言及している部分は見られない。高山家は小柏家の主家筋に当ると言った人がいるが、それは的を得ていないようだ。
小柏氏が、高山氏の指示で行動した形跡が全く見られないのである。また日野七騎の小柴氏・小此木氏と小柏氏は縁戚関係を結んでいるが、高山氏とは縁戚関係になかった。高山氏は小幡氏とは縁戚関係を結んでいる。
この点は小柏氏も同様である。近代に至り八郎治の妹才の長女が、高山村の高山武十郎の後添えとなっておりこの時点では縁戚関係が生じている。更に才の二女さとは金井村の高山菊次郎に嫁いでいる。
小柴氏と小此木氏は同祖で平氏の落人とも、源氏だったが平氏と婚姻を結んで一門と同格の待遇を得ていた、ともいわれる。源平の大乱により御荷鉾山山麓に隠れ住んだという。「小此木」は鎌倉の追及を受けて「小柴」の柴の字を分解したという。小此木氏は長篠の合戦に出陣して戦死したと云われている。(藤岡市史通史編)
はっきりしている事は後代の高山長五郎(近世の世襲名か)が、昭和10年に小柏家にて小柏系図を筆写した事、上日野小柏家墓地の前に立っている小柏家の家系図・同由来の板碑に高山長五郎が文章を書いている事だけである。
高山氏系図 

豪傑 小柏 高政
血糊の宮
小柏高道の三女は早世であったが、後に長男の高政が生まれている。小柏氏800年のうちでも、もっとも勇名を馳せたのがこの高政である。高政は当初小柏左馬介を名乗り後に六郎右衛門と改めた。
高政は父と共に上杉憲政に属していた。天文二十年(1551年)に北条氏康・氏政父子の攻略により、上杉氏の居城平井城が落城し憲政は越後に敗走した。この後、西方から勢力を拡張してきたのが武田信玄である。
西上野国の諸氏は誓詞を差し出すなどして、ことごとく武田信玄に属すことになった。永禄十年(1567年)武田信玄に捧げた起請文(誓約書)の中に、小幡親類中として小柏左馬助高政の名前がある。
高政も小幡氏と共に武田家に仕える事となり、後に信州佐久郡田ノ口(現在の臼田町か)を俸地として賜った。そして伝来の揚羽蝶の家紋・幕紋を定丸ノ内釘貫紋に変更した。一部では丸に三つ柏の家紋も残し平行して使われたようだ。
その他の事績・詳細一切は別に記録をとってあるという。(小柏氏正系図)系図には簡単な紹介しか書けないので、別に記録した文書があるとの趣旨である。或いは逆にこの古記録から系図が組み立てられたものかもしれない。
この記録は今のところ探索・閲覧するまでには至っていない。本家子孫の方に聞くしかないが….。ぜひ見たいものである。
上日野小柏(村)の南側に流れる清流鮎川を渡り、左に行くと西荷鉾山の山麓、奥ノ反から流れ落ちてくる小川がある。この小川を渡って行くと、すぐ右側に野宮神社(或いは野々宮神社ともいう)がある。
この道は、ここからは緩い登り坂の林道となる。「藤岡市史」によれば、高政はこの神社の二キロメートルほどの上流で敵勢のうち十人を斬ったという。このため川が血の流れとなり数日間、赤い川となったという。このため、血の宮神社、野宮神社と呼ばれるようになったという。
明治12年調査の神社明細帳によれば、無格社、野々宮神社、由緒は不詳、相殿7座は明治10年12月合祭、祭神は鹿屋野比売神、宇迦之御魂、大山津見神、火産霊神、建御名方神、大物主神、須佐之男命、菅原道真であり、末社は御鉾社(大和建命)、八幡社(品陀和気命)、琴平宮(金山毘古命)であるという。
このうち、御鉾社は小柏屋敷内にあった御鉾神社のことであろう。祭神も同じである。
「群馬懸多野郡誌」によれば、小柏(村)をさかのぼること約2.2キロメートル(約二十町)の渓谷に千ヶ滝という滝がある。投石通りの左側に高さ約9m(三丈許り)の二段の岩盤の滝がある。永禄年間(1558~1570年)に武田信玄に属していた高政が、小田原北条の軍勢をこの地に迎え撃ち、敵千人をこの滝に斬り落とした遺跡と伝えている。
この為、千ヶ滝と名付けられた。この時に七日七夜にわたって、血の川となりこの下流、鮎川と合流する所にある社が、血(のり)の宮(野宮神社)と呼ばれるようになった。という。
この神社、今は野々宮神社と呼ばれる事のほうが多いようだ。この千人という数字はあまりにも多く、当初これを読んだ時には、伝承されるうちに誇張された数字が出来上がったものと考えた。
しかし、かなり経ったある時、ふと思いついた。野宮神社の上流には重家(庄司)が築城した鼠喰城があるではないかと…城攻めとなれば、千や千五百の軍勢を揃えて当ってきても少しも不思議ではない。
この二十町ほど遡るというくだりを、私はてっきり鮎川のことだと決め付けていたのだった。
上方は大谷川 右方は鮎川

よく読めば「渓谷」とある、鮎川は渓谷というほど深い谷になってはいない。したがってこの渓谷は、鮎川の支流で野宮神社の西側を流れ、神社に沿って北側へ廻り、そのすぐ下で鮎川に合流している現在の大谷川の事であろう。
この川は、小さい清流であり草木などにより、川幅は判然としないが、およそ3mほどであろうか、水流のある部分は幅が約1.5mほどか。鮎川沿いであれば合戦の記録や、戦場となった形跡・影も感じられなかったので、ただの伝説ではと思っていたのだった。
しかし最近になって、何の根拠もないが、私は近在の歴史に詳しい好事家から、鼠喰城で合戦があった、というような趣旨の話を聞いたのだ。
長く関東経営の中心をなしている平井城を攻め、さらにその足を少し伸ばせば小柏(村)に至る。
ここは山中領や下仁田を通って、信州に抜ける要衛の地でもある、鎌倉街道(古道)もこの地を貫いて通っている。(今でも古老の話によく出てくる。)
鼠喰城は西御荷鉾山の北麓にある山城であり、かなり高低差がある細長い城である。
これを鮎川を渡って下から攻めたなら、上から大石や大木、水や油を落としたり、長槍などで突けば将棋倒しに、数百人は渓谷に向けて落ちて行くだろう。
平井方面から攻め上ってきたなら当然、下から上の城に向かって攻めるこのコースになる。
楠正成も要害の金剛山に籠り、この戦法で十倍以上の軍勢を迎えうち、半年以上に亘って落城を許さず死守したのだった。
さすれば城主高政が指揮して何波にも亘り、攻め登る敵を繰り返し谷に突き落としたのではあるまいか。鼠喰城は標高900mの位置にある。
鼠喰城はいま杉や奈良の木立に覆われているが、当時は登山道などが整備されていて、砦としての用途の他に、鮎川沿いの街道などに対処する役目や山の管理などの目的をもって築かれたものであろう。
したがって小柏館(城)と別に、対岸の山に築城の運びとなったのではあるまいか。同城の守城軍が、渓谷に突き落とした敵勢を数百人と解釈しても、高政が直接手を下して斬ったのが、十人であったとすればこの伝承も無理ではなくなるように思う。
或いは撃退した敵勢の人数が千人であったのであろうか。この後、「多野郡誌」に次の記事を見い出した。
千ヶ瀧 御荷鉾山鼠食城ノ直下ニ位シ高二丈幅五尺許往昔小柏某ナル者武田家ノ臣タリシ時北条氏康ノ軍勢トコヽニ戦ヒ鼠食城ヨリ敵兵千人ヲコノ瀧ニ切落シタルニヨリ千ヶ瀧ノ名ヲ得タリトイフ
鼠喰城には、西御荷鉾山頂上の不動明王を本社とする不動明王の社が祀られている。
「奥ノ反」の奥にある鼠喰城の登り口には、不動明王の大鳥居が鎮座しておりその足元には立派な御影石の碑が設置されて、今なお地元の人たちの手によって大切に鎮護されている。
その碑文には、御荷鉾山不動明王は古代より小柏城城主小柏八郎ほか地域住民の願望により開山され今日に至る。昭和7年八月落雷によりご本尊が焼失されたが、住民有志により昭和八年十月復興された。
その後、荒廃が激しく地域有志一同の発願により参道・鳥居・境内地の修復・美化を遂行する。
とある。この碑は平成三年に設置された物である。
鼠喰城登山口 不動明王の大鳥居

不動明王の大鳥居下 石碑

野々宮神社

野々宮神社境内奥の橋 (大谷川)
「多野郡誌」を引き継いだであろう「多野藤岡地方誌・各説編」は、野宮社は上日野小柏にあって、祭神は日本武尊。永禄年中(1558~70)の事、当社から半里ほどの谷合で、小柏左馬助高政が十人の敵を斬ったという。
そのため社前の沢の流れが七日七夜血に染まったので、血(のり)の宮といったのが野宮になったと伝えている。祭神を鹿屋野比売命ともいう。槻三本野宮にあり。一本は目通り一丈九尺六寸廻り、一本は一丈九尺廻り、一本は一丈ニ尺廻り。杉十六本。(慶長三年御用木帳)明治初年の修築の時、鏡二面、刀一口、土器などが発掘されたという。社地は古墳であろう。 としている。
地方史に十人斬りは永禄年間とあるが、更に資料をつぶさに検証したところ、多野藤岡地方誌の付記に、北条五代記に天文二十年三月十日小田原より三万余騎にて上州平井へ寄る。とある記述を見つけた。
これによれば平井よりも途中へ出て防戦、上杉方敗れ憲政厩橋へ遁れる。平井城は悉く焼払云々。としている。
憲政は途中まで軍勢を出して北条方を迎えうったがひどく敗れた為、平井城を放棄して戻らずそのまま前橋へ落ち延びた事が分る。
平井城を落とした余勢を駈って周辺の鼠喰城にも押し寄せたのであろう。小柏系図にも「天文二十辛亥年氏康・氏政父子の為に平井城落城、憲政敗走」との記載がありこれを裏付ける。
「豆相記」にも「天文二十年辛亥年十月北条氏康・氏政父子囲山内上杉憲政居上州平井城攻敗。 中略 山内憲政出奔北越矣。」
とある。
また「箕輪軍記」に憲政愚将にて長野業政の諌を不用 中略 上原兵庫之助が巧言に迷、非業の政道多かりしかば諸士背民恨て終に北条氏康に国を被奪、天文二十年平井を落城後に走云々。とあり、他の諸武士団と共に高政も憲政に愛想をつかしたのかもしれない。
勇猛で鳴らした高政にとっては、長年本拠地とした城をほっぽり出して一気に遠い前橋まで逃亡する事など考えられなかったのかもしれない。
小幡氏系図が「鷲翎山宝積寺史」に収載されている。
![]()
![]()
![]() 第十三代小幡顕高 十四代憲重 十五代信真
第十三代小幡顕高 十四代憲重 十五代信真
![]() 女子(小柏高政室)
女子(小柏高政室)
![]() 女子(白倉道左室)
女子(白倉道左室)
(国峰小幡氏に集う会作成系図)
となっている。これを信じるとすれば高政の妻は、憲重(重貞)の妹となる。よって高政は重貞の義弟という事になってしまうが….。
他の文献は重貞の姪を妻とした事になっている。
小幡龍蟄の著した「上毛菊婦傳」の末尾に、小柏高政について次の記述がある。
覚性浄林居士 小柏左馬介高政
光岩智明大姉 同人妻 小幡尾張守重貞姪女
こちらは小柏系図と同じ重貞の姪である。
小柏系図にある小幡重貞は誰なのか?憲重か?他の小幡家系図を見ると
旧領弁録の小幡系図
![]()
![]()
![]() 顕高 重定 信真
顕高 重定 信真
(播磨守) (尾張守憲重・新龍斎) (尾張守信貞 上総介)
上野人物誌の系図
妻長野娘
![]()
![]()
![]() 顕高 憲重 信貞
顕高 憲重 信貞
(一に重定) 尾張守泉龍斎 憲景 信定 上総介、尾張守
更に「甘楽町史」によりやや詳しくみていく。
小幡正系譜
![]()
![]()
![]() 顕高 重定 信真 (旧領弁録と同じ)
顕高 重定 信真 (旧領弁録と同じ)
安中市野殿 木村氏所蔵系譜(信秀 江戸小幡氏の子孫)
![]()
![]()
![]() 顕高 憲重 信真
顕高 憲重 信真
上野伝説雑記
新龍斎 妻長野妹
![]()
![]() 実高 重定 信真
実高 重定 信真
吉井町史
![]()
![]()
![]() 実高 重定 信定
実高 重定 信定
顕高 憲景 泉龍斎 信貞 忠甫斎
![]() 弾正忠信長
弾正忠信長
一宮神主志摩所持系図
![]()
![]() 重定(尾張守後上総介 信真 新龍斎)
重定(尾張守後上総介 信真 新龍斎)
![]() 信氏
信氏
![]() 昌高
昌高
寛政重修諸家譜
![]()
![]()
![]() 顕高 憲重 信真
顕高 憲重 信真
播磨守法名宗顕 尾張守法名新龍 上総介
以上の小幡氏系図の中で最も信頼出来るのは、最後に記載した寛政重修諸家譜であるという。重貞はやはり憲重であり、少し混同が見られるが時に信定、信真、顕高、憲景、新(泉)龍斎を名乗ったようだ。
起請文などでは信真を、同じ「のぶざね」読みの信実と記載している。
小柏氏系図では高政の室は重定の姪であるので、寛政重修諸家譜、旧領弁録と同じである。やはり高政の妻は小幡憲重の妹ではなく姪である。
甘楽町史の「小幡氏関係の社寺ならびに縁故者の一部」によれば、小柏高政の妻は小幡信貞の姪であり、高政は小幡定政(源助)と同一人であるとしている。
出典は不明であるが、小柏正系図とは不一致であり高政とその子の定政を混同している。
尚、小柏正系図では定政は高政の二男であり、左馬助後源重郎であり、源助と名乗った記録はない。ただ宝積寺の位牌名の写しには定政初号源助とあり、一時名乗っていた可能性もある。
後述する菅原神社寄進の、鰐口記載の名前の順も新龍斎、信真、高政の順であり、旧領弁録と一致する。
小幡龍蟄によれば、泉龍斎は新龍斎の誤りであろうとしている。さもあろう。ただ高政が、信真と近しく行動を共にしている形跡が見られる事から、その妻は憲重の妹であった可能性も残されている。
妹であれば信真にとって高政は義理の叔父に当り、高政から見ると甥という近い縁者になる。
西上州の白倉氏
永禄三年(1560年)長尾景虎(後の上杉謙信)が、関東に出陣した時に従った諸将の陣幕を調べた「関東幕注文」に、下野国足利衆として小幡次郎の次に小幡道左の名前があるが、白倉道左と同じ人物で白倉氏であろう。
「上野人物志」に白倉氏に関しての記述が見える。これによれば、白倉道佐の碑として、城(白倉城であろう)の西南、一丁ばかりの所にありて、野石を刻み、碑面に「捐官白倉院殿天漢道佐大居士神儀」とあり、さらに「天正八壬戌暦林鐘三日」と刻まれているという。
白倉氏については、「上野人物志」に「白倉五佐衛門」という項があり、次のような説明が記されている。甘楽郡白倉村の人なり、西上州四家の一つにして、山内上杉氏四宿家老の一人なり、碓氷峠の戦いに武田の勇将、板垣信形の馬を射て勇名を顕わす。後、北条氏に属して、天正十八年白倉掃部之助、小田原に入城し(後、落城)白倉氏滅ぶ。(関東古戦録)
別説では、白倉周防守、白倉左衛門佐、白倉左馬助などという(名乗った)。白倉氏、鎌倉(時代)以後、代々ここに住む。永禄六年、武田信玄が侵略してきた時は、上杉氏の武将、白倉左衛門慰宗任、五十騎を率いて降参を申し出た。以後、白倉源左衛門慰、上杉氏の兵を導いて天引城を攻めたが勝てなかった。
と記述している。
戦国時代の武将は、仕える大名が変わると自分の名前を変えたりしたので、後世、少し混乱するところである。源左衛門慰を別にして、いずれも白倉氏を代表する人物、白倉道左のことであろうか。
「甘楽町史」の白倉城の項目に、白倉氏について触れている所がある。それによれば、白倉城は仁井屋城と麻場城の二城からなる。白倉氏は小幡氏と並んで上州八家の一つであったという。関東管領の山内(鎌倉)上杉氏の重鎮で、小幡・白倉・安中・倉賀野・桐生・由良・山上・沼田氏がそれである。白倉氏は四宿家老(長尾・大石・小幡・白倉)にも名を連ねていた。
小田原の役の時には、掃部助重家が小田原に籠城し、居城は弟の重高が守っていたが、北国勢により落城しその後廃城となったという。
織田家と宝積寺の確執
「甘楽町史」に収載の幡氏旧領弁録(小幡龍蟄著述)によると、富岡市妙義町の菅原神社に、小幡氏一族が奉納した鰐口に、一族の名前が彫りこまれている。その中に小柏高政の名前もある。
小幡新竜斎全賢(重定、尾張守憲重)の次に子息の信真(のぶざね)の名前があり、その次に高政の名前がある事から、かなり重く用いられていたものと推定できる。高政の次には信直の名前がある。
史家によると関東幕注文にある、この小幡次郎が鰐口に記載された高政であろうとしているが、宝積寺の史料なども参酌して考えると、どうもそのようには思えない。この鰐口に記載されている地名は、上野州高田庄菅原郷(妙義町菅原)とあり、現在の妙義町高田の包含地であったようだ。
続いて「大神宮御神前鰐口寄進部類眷属一味和合祈」とあり、一族が結束して鰐口を奉納したことが分る。この際の趣意を奉じて祈願した者は、小幡新竜斎、高政、信直であり、一族の安全、子孫繁盛、武運長久祈願とある。
尚、源勝頼の名があり、一族が結束して武田勝頼に従い助けることを誓約した物でもある。続けて敵を打ち破り、住まいを安泰に、たとえ七難が降りかかってもたちまち消えるように、小幡一門が息災延命であるよう祈願文を刻んでいる。
鰐口は仏塔や神社の拝殿の前に縄で吊るし、参拝者がその太縄を持ち鰐口にぶつけ鈴をならす為の物である。
この鰐口は寄進された後、火災にあいその背面は焦げてしまったという。「幡氏旧領弁録」を著した、松代藩士(中老職)の小幡龍蟄によれば、新龍斎は信竜斎と書く事もあり上総介重貞であり、全賢は入信してからの道号であろうとしている。(甘楽町史収載)
大族の小幡氏の系図は幾つもあり、少しずつ違う物もあればかなり違う物もある。龍蟄は伝え言うところでは、背面になお次の三十七文字がある。「妙法華経如来神力品第二十一諸仏救也者住於大神通為悦衆生故神力現無量天正元年」。
寺僧が作った模型板の旧記には天正五年とあるが今、元年に訂正するという。
織田家の城下町、甘楽町のはずれの秋畑に、関東の名刹宝積寺がある。宝積寺史が語るところでは、小幡上総介は初め信実で信真、信貞、信定と四回にわたり改名した事になっている。
甘楽町では今でも華やかな、武者行列のお祭りがある。宝積寺は古い寺で伝統・格式を有している。寺史によれば現職の住職が、公用で外出する時は輿にのり、供ぞろえが十数人つくことに決まっていた。衣装や供の持ち物などに至るまで細かな規定があったという。
正規の寺名は後ろにある山を、鷲翎山というところから「鷲翎山宝積寺」という。この宝積寺は小幡伝説やお菊伝説などでも有名な寺である。檀家である小柏氏と同寺は深い繋がりがある。小幡家の墓地の隣に小柏家(奈良山小柏)の墓地がある。
宝積寺は住職が代替わりするたびに、その披露・供養を目的として「進山式」を行っている。
この進山式は曹同宗の各寺にも行く他、同寺内でも檀家を呼んで盛大に執り行われた。ある進山式のときに小幡家、小柏家、織田家が参列した。
その時に寺が用意した席次は上記の通り、織田家が三番目だった。これに感情を害した織田家は、後に崇福寺を再興してそちらへ菩提寺を移したといわれている。
これを宝積寺史でやや詳しく見てみると、東昌寺と宝積寺との間で本寺、末寺の紛争があり、織田四代の信久がこの仲裁に入った。
和解を画策していたが、両寺とも聞き入れず裁判沙汰にまでなってしまった。その以前に信久はこの裁判で、宝積寺が敗訴したなら檀家を離檀すると警告していたが、案の定宝積寺の敗訴となってしまった。
感情を害した信久は、小幡(村)の真言宗崇福寺を改築し、臨済宗に改めて織田初代から三代までの墓碑を移した。
別の説では先にあげた進山式の席次の不満である。宝積寺は宝徳二年(1450年)の開山以来、国峰城の小幡氏の菩提寺であり、竹花城主・小柏氏と共に大檀越(援護者)をなしていた。
織田氏は時の領主とはいえ、檀家としては新参でありその為、式宴の席次は第三席となった。この処遇が信久の不満となり、離檀に拍車をかけただろうとしている。
時代が移り、後に崇福寺が廃寺の憂き目にあい、先祖の供養もなかば打ち捨てられているのを、見かねた時の宝積寺住職が供養を申し出て、織田家もまた檀家として戻ってきたとされる。
この宝積寺が編纂したのが、先に挙げた「鷲翎山宝積寺史」である。装丁も立派な分厚い本である。同寺の歴史や収蔵品、伝説、寺に関わった士族の歴史などが、詳細に著述されている。
菅原神社・妙義神社の鰐口
「幡氏旧領弁録」は、小幡氏の直系の子孫で当時、信州の松代藩士(中老職といわれる)小幡龍蟄の著である。
龍蟄が先祖の遺蹟を訪ね、細かく調査した記録を著述したものである。丹念に調査・取材・収集され、客観的に細かく分析されている。
安政六年(1859年)の成立である。(翌万延元年に巻の弐を著している)鷲翎山宝積寺史にも、その幡氏旧領弁録が詳しく収載されている。この弁録によれば、再考として鰐口の分析考を記載している。
江戸時代の文章なので、一部の意味は正確に把握し難い面もあるが、下仁田村近戸明神と、隣村の菅原村天神の鰐口は、小幡重定君の寄進した物であろうとしている。系譜や諸書に記録されている新龍斎は誤りで、重定は始め新龍斎と称したが甲斐公(信玄)より信の字を拝借して信龍斎に改めたという。
詳細は不明ながらも証拠もあれば「信」の字のほうが正しいとしている。重定の没年は未年であるが、鰐口の銘文によって考えれば、天正五年には存命であったが、天正十八年の小田原の役には在陣していたとは記録がない、故に天正十一年(1583年)である、この事疑うべからず。万延元年 龍蟄識 とある。
同史収載の旧領弁録は、この記事のあと数項を挟み、また鰐口寄進の記事になっている。
補遺 前巻に記した下仁田村近戸明神へ、永禄九年重定君が鰐口を寄進したの
は事実である。いまも同社の旧記にはその記録があるとはいえ、その後、同社
は火災にあい、鰐口を焼失して今跡形もないのは残念である。
(追記再考)上総介信真君は永禄の初め頃、尾張守信真と称したと由緒書きに
見えるので、近戸明神の鰐口は永禄九年なので信真君が寄進した物である。
と書いている。この近戸明神の物については、重定が寄進したというのを信真が寄進したと訂正したもののようである。重定の嫡男・信真は天正二十年(1592年)に没している。旧領弁録は続けて菅原天神(神社)の鰐口の記載に移っている。
前巻に記す菅原村天神鰐口は、天正五年重定君がご寄進したのは事実である。
だが寛政八年(1796)同社の火災により、鰐口も三個ほどに砕けてしまったので鋳掛けなおして重宝とす。かつ古い物なので焼失した後は、その図を板に彫って希望する人には刷って与える。略図次の如し。
鰐口略図 
次に鰐口の図が記載されていて、次のように彫られた文字も記載している。
鰐口表径一尺四寸三分程 右の鰐口の銘が前に細い字で書いてあり、読みずら
いので左に記す。正面(に)字数三 天神宮 右(側に)字数三十弐 大日本国上野州高田庄菅原郷天神宮御神前鰐口寄進部類眷属一味和合所 同内(側に)字数十九 源勝頼魂情追月倍増喜悦累月出来皆令満足 左外(側に)字数参十壱 右意趣者小幡信龍斎全堅信真高政信直并一類安全子孫繁盛武運長久所 同内(側に) 字数二十 怨敵滅却住所安泰七難即滅小幡一門息災延命

この鰐口は概ね円盤であり、古の銅鏡を思わせる。円のてっぺんの所に縦書きで大神宮とありそこから時計回りに、真下の部分まで「大日本」から始まる文字があり、「和合所」で終わっている。
大神宮の所から左へ反時計回りで、「右意趣」の文字が始まり、真下まで「長久所」で終わり真下の余白となる。
その内側の同心円部分に、右上から右下にかけて「源勝頼」から始まる文字があり、左上から左下にかけて「怨敵滅」で始まる文字となる。同心円の真ん中には紋章があるが、小幡家が幾つか使っている家紋には、どれも合致しないので、何の紋章かは今のところ不明である。
旧領弁録では先に彫られた文字を、説明した後に次のように解説に移っている。
鰐口の裏は焼失の際微塵に砕け、散乱したため不便だが次の文字が、有ったというのでこれもまた板にした。 妙法華経如来人力品第二十一諸仏救也者住於大神通為悦衆生故神力現無量天正元年 「金石私志」には天正五年とあるが、ここに天正元年とあるので思うに、これは焼失のあと板にした物だから、「金石私志」にいう天正五年のほうが事実であろう。
鰐口名の全堅は重定君の御号なるべし、高政・信直の両氏はまだ不明であるが、ここに来て宝積寺から事績の研究の参考になればとして、次のように覚性浄林の牌名(位牌か)の中から書き抜いて送って来てくれた。それによれば重定君には姪があって小柏氏に嫁いたようだ。
これは、はっきりとは判らないが、本当の事であろう。よって先に記された銘の高政は、すなわち御姪婿の小柏高政であろうが、なお研究の余地を残す。小柏氏は小松重盛公末孫の由也。今現在も日野村に小柏を名乗る郷士があり、この家が菊女伝説に記す源介は次の定政であろう。
覚性浄林居士 小柏左馬介高政
光岩智明大姉 同人妻 小幡尾張守重貞姪女
昌室浄久居士 小柏左馬介定政 初め源介と号す
右者小柏八郎左衛門 牌名之内
としている。ここの八郎左衛門は定政の孫の小柏重高であろう。
上記、鰐口の図は旧領弁録のものであるが「上野国郡村誌」に収載の鰐口の図は少し趣を事にしている。下記の如くの物で、文章末尾の「所」という文字が「祈」となっているが、他の説明文章などは旧領弁録とほぼ同様である。
柄はなく全体が円盤状になっている。見たところでは旧領弁録の物の方が精巧であり真実味がある。

菅原神社

菅原神社 鰐口 郡村誌より
下仁田(町)と妙義町の菅原村に鰐口の寄進があり、この地域で一番大きく由緒ある妙義神社に寄進がないのは何故なのか、不思議に思っていたが、よくよく読んでみると妙義神社にも寄進したとの記事があった。
それは先の文章に続けて記された次の小さな記事であった。
この記事は菅原村も妙義山の麓で妙義町に属している事から、菅原神社の追加説明と理解していたが、妙義山とは妙義神社の事を指している。
天正五年妙義山金皷の銘に小幡□信龍斎全賢信真高政信直云々とあり、今この皷 甲州古府(甲府)塩部八幡宮之社檀にある由。江戸の人黒川春村という者が先年甲州に行った時に、自ら摺り取りて所持せる由。旧臣新居又太郎がいう。
追記 金皷とは鰐口の事なり。□の中に入るのは恐らく平の字か。
『金石私志』は市川寛斎が著述した歴史書である。龍蟄がこの記事の後に、記した系図では重定は初め尾張守憲重であり、後に剃髪し新龍斎と号し上野国国峰城、宮崎城の城主であると記している。
重定の子が信真であり、初め尾張守、後に上総介であり剃髪し忠甫斎と号した国峰・宮崎両方の城主であるとしている。
信真は3~4回改名(信実―信真―信貞―信定)しており、父も改名している他、尾張守も共通しているため、この二人の事跡は混乱をきたしているところである。
特に戦国時代は仕える武将が、何度も変わった時代であり、変わるたびに主人の名前を一字貰ったり、前の主人の名前を一文字使っているのが、気に入らないなどの理由から、何度も改名するのが一般的だった。
小幡氏の先祖は村上天皇から出ている。二十六代目の祖、赤松播磨守則景は,広島に住んでいたが源氏だったことから、頼朝の挙兵に呼応し関東に来て、児玉党と縁を結んだ後、子孫が児玉忠行の養子になり武州児玉の庄を領したという。
後に上州、奥平之郷を領し姓を奥平と改め、更に甘楽郡小幡郷の郡司となり、再び姓を小幡に改めたという。
この後の嫡子の吉行が奥平郷を与えられ、源姓奥平(別家)の祖となり、小幡郷は次男の崇行が継いだとしている。
小幡重定の子、信真(定)は武田信玄・勝頼二代に仕え、二十四将の筆頭としてその名を馳せた人物である。その軍勢は赤備えの騎馬軍団として勇名を轟かせた。小幡氏は本城の国峰城(現甘楽町)を本拠として白倉城(仁井屋城・麻場城)、庭谷城を代々有しており、他にも宇陀城、宮崎城等の支城を持っていた。
小幡景憲は、ことに有名な甲陽軍鑑の最終的な編集者と見られているが、景憲も上野国小幡氏の一族とする説もある。
実際は景憲は甲州小幡氏であり、上州小幡氏よりも古くから武田に仕えていた別族と思われ、後に上州小幡氏から姓を譲られたようだ。
甲陽軍鑑の品第十七にある「武田法性院信玄公御代惣人数の事」には、ご親類衆として
1、勝頼公 旗白色に大文字、、二百騎、、、、中略、、、
信州先方衆として
1、真田源太左衛門 旗色黒四方 二百騎、、、中略
西上野衆(五十七名略)
1、小幡上総守 五百騎
1、和田 三十騎
1、たいら 四十騎
とある。小幡氏の五百騎というのは群を抜いて多い人数である。
二番目に多い高坂弾正(譜代家老衆)で、四百五十騎であり、あとの殆どの将が率いる人数は二百、百五十、五十、三十騎などである。一騎の武者が四人の供を連れ参陣する事を想定しており、総人数を四万五千六百五十人と見積もっている。更に旗本足軽八百八十四人、総家中の足軽五千四百八十九人を合計すると、軍の編成人数は五万二千二十三人になるという。
武士と農民が、はっきりとは別れていなかった時代であるから、殆どは農民とも言える。先方衆とは占領地の軍勢を組み入れたものという。(甘楽町史・歴史読本)
生島足島神社の起請文と養命寺
「甘楽町史」に小幡弾正信高が、武田氏宛てに出した、従属を誓約する起請文が記載されている。
敬白起請文
1、為始長尾輝虎自御敵方以如何様之所得申旨候共、不可致同意事。
1、甲信西上野三ヶ国諸卒雖企逆心於某者無二奉守信実御前可抽忠節之事。
1、甲州之御前悪儀不可批判事。
上ニ者奉始梵天帝釈四大天皇下ニ者堅窂(ママ)地神殊ニ者八幡大菩薩、摩利支天諏方上下大明神、天満大自在天神、甲州一二三大明神、忽而日本六十余州之小神祗各可蒙御罰候。此旨可預御披露候。仍如件。
永禄十年丁夘
八月七日 弾正左衛門慰信高(花押血判)
左馬介 高政 (花押血判)
自徳斎 道佐 (花押血判)
能登守 行実 (花押血判)
熊井土対馬守 重満 (花押血判)
金子与三郎 (殿)
永禄十年(1567)小幡信真の親類で、家臣となっている者が、信州の生島足島神社に捧げ、信真(実)に忠節を誓う事により、武田信玄への服従を誓った起請文。戦国の時代にあっては、このような文書が数多く作られた。あらゆる神を引き合いに出して、やや大げさに誓約しているように見える。
同史は信高は弾正忠信氏(信真の弟)と推定している。信氏はこの起請文を奉納した二年後の、永禄十二年(1569)に駿河蒲(神)原で討死している。高政については関東幕注文にある、小幡次郎がこの人か。としているが、これは左馬介(助)という名前からいっても時代からいっても明らかに小柏高政である。
道佐は鰐口に記載のある白倉道佐であろう。記載順も信真と信高が違うだけで、鰐口と同じ並び順である。熊井戸(土)氏はこの時、小幡氏の家老クラスの重職にあったと思われ、縁戚関係もあった筈であるが、何故か親類衆の後方の順位になっている。ずっと後代になってからは、小柏氏の子孫が熊井戸氏に従って大阪夏の陣に加わっている。
同じ永禄十年に、小幡信真の家臣団中別格の三氏(松本、友松など)が、やはり生島足島神社に捧げて、信真への忠誠を誓った起請文があるが、宛名が熊井土対馬守殿御中となっている。
これも熊井土氏が重職にあった裏づけとなる。「甘楽町史」では、生島足島神社に奉納された起請文中の、小幡氏の一族・家臣団を合計すると、二十四名にのぼり同様文書中に、これ程の大集団を擁する者は他に見られない。
これをもっても小幡五百騎が、武田軍団の中心兵力であったと肯定できよう。と結んでいる。小幡氏と武田氏との間で、交わされた多くの文書は旧家などに今も残されている。
「群馬県の地名」の国峰城の項を見ると、巨大な山城であった事が詳しく紹介された後、小幡一族を紹介している。小幡氏の当主信真(実)は小幡一族の信高・高政・道佐・行実や有力家臣の熊井戸重満、鏑川筋とその縁辺高瀬・上条・武河・南蛇井・伴野・尾崎・湯浅・山口の各氏。
南牧衆の小沢・市河・懸河・高橋らの諸士を家風・同心として従属させ、彼らも信実への忠節を媒介に武田信玄の領国支配に服している。とあり、小幡氏に属し協力或いは行動を共にした周辺の武士団の名前が良くわかる。
小幡一族の中の高政とあるのは小柏高政である。
高政は小柏館のすぐ下に、養命寺(曹洞宗)を建立・開基している。同寺は宝積寺の末寺の一つとなった。同寺は小柏山と号し、本尊は十一面観世音菩薩である。天正年間(1580頃)に小柏氏の開基で、甘楽郡小幡町の宝積寺を本寺として、その十世魯嶽林誉禅師が開山。小柏氏とその家臣の菩提寺とした。
その後荒廃したが、天保の頃(1680頃)宝積寺二十一世祥山寂瑞禅師を中興開山として再興した。宝物は涅槃像 一軸 十六善神画像 一軸 二十五菩薩画像 一軸 大般若経 六百巻
茶釜(銅) 壱個 梵鐘(元禄十五年) 一口 (多野藤岡地方誌・各説編)
「宝積寺史」によれば、小柏山養命寺、藤岡市上日野464、創建天正年間(1573~92)、本尊十一面観世音、開山魯岳林誉、開基小柏高政となっている。
そして沿革として、天正年間に竹花城主・小柏高政が開基し、宝積寺十世魯岳林誉を請いて開山とする。小柏氏の祖は小松内大臣重盛の子維基で、小松を小柏と改めた。鎌倉幕府滅亡後は、山中郷を領し平井城主上杉氏に出仕していた。当寺は小柏氏とその家臣の菩提寺である。
天和年間(1681~84)に宝積寺21世祥山寂端が、中興開山として再興する。との記事である。
養命寺

「多野藤岡地方誌・各説編」の年表を見ると、1575年の長篠の合戦で討死した者の中に小柏高政を入れている。これが事実とすると、同誌は養命寺の開基を1580年頃としているので、養命寺を開基したのは二男の定政という事になる。しかし先に述べたように、宝積寺はその末寺養命寺の開基は小柏高政としている。
養命寺は、碑名の内の抜書きとして高政や定政の名前・法名を書いて小幡龍蟄に送っている。大檀家である小柏家の位牌や過去帳があった事になり、その他の記録もあったものと思われる。
その宝積寺が、自分の寺の住職が開山した養命寺の開基者の名前を間違えるはずはない。したがって「多野藤岡地方誌・各説編」の年表にある長篠の合戦での討死にの記事は何らかの誤りと考えられる。
他に古文書・古文献はない事から、同誌はおそらくその典拠を「小柏氏正系図」に求めたのであろう。だが同系図をよく読めば、高政が長篠の合戦で戦死したとの記事は載っていないのである。
嫡子の定重には子供がなく弟の定政が後継者となっている。この事から、定重は長篠の合戦で討死した1575年には21歳であったと推定すると、父の高政の年齢は46歳と推定する事が可能である。
当時としては高齢でもあり、長篠の合戦には出陣せずに息子の定重が陣代として、出陣したのではなかろうか。養命寺が開基されたとする1580年には高政は51歳となり無理のない仮説が成立する。
この仮説が間違っている時は、養命寺の開基は6~7年遡った1574年頃となる。いずれにしても「多野藤岡地方誌・各説編」のどちらかの記事に誤りがある事になる。
竹花城と小柏城
「竹花城」の名前は他の文献には見られないものである。藤岡市教育委員会の「小柏館跡(2)埋蔵文化財発掘調査報告書」を見ると、「館南西(裏鬼門)嶽ノ本~嶽ノ鼻には、小柏氏累代墓所及び掘切が残り、館の東西外周付近には科人断罪の伝承が残る」とある。
したがって、小柏館、敷地に隣接し低地に向って、突き出ているような墓所の部分が「嶽ノ鼻」と呼ばれていた事が分る。そこに隣接する所が「嶽ノ本」という地名で呼ばれていたのである。
してみると、「嶽ノ鼻」が美字で簡略された「竹ノ花」に変わり、呼び易い詰めた音の「竹花」に変わったとみる事が出来る。とすれば小柏館が「竹花城」と呼ばれていた事になる。一山を隔ててはいるが隣村にあり、小柏氏との繋がりが深かった、宝積寺ならではの知識、呼び方であったのだろう。また地元の人のみがそう呼んだのではなかったかと思われる。
この頃は、重家が築いた、西御荷鉾山の山麓に踏み込んだ鼠喰城よりも、街道沿いに位置していて、周囲の山や集落の支配にも便利な、小柏館の方に主な拠点を置いていたのだろう。
小柏氏墓所の前に、高山長五郎が筆を取った板碑が二つある。その一つには桓武天皇以来の小柏氏の家系図が書かれていて、もう一つの板碑に小柏氏の由来が書かれている。そこに小柏舘の東側の山は、城山(しろやま)と呼ばれているが、城山(じょうやま)と呼び習わすべき。とある。
更にその横に立つ石碑の碑文に「小柏八郎を主とし小柏城を中心に今日に至る――中略――三本木より小柏城までは日向組十戸の――後略。」と、小柏舘を小柏城と呼んでいた事が明確に記載してある。
また奥ノ反の鼠喰城の入口にある石碑にも「小柏城主小柏八郎…。」とあり、上日野地区では小柏舘、或いは城山の保塁を小柏城と呼んでいた事が分る。
これにより、その時期によって竹花城又は小柏城と呼ばれていた事が分る。小柏(村)の交差点に「小柏」というバス停がある。このバス停の北側は雑木林の斜面になっていて、南傾斜の小高い丘となる。
この小高い丘が城山(じょうやま)と呼ばれ砦が築かれていたようだ。私も最初に現地を訪れた時には、小柏舘跡はこの丘の辺りであろうと見当をつけたものだった。したがってこの砦を含めた小柏舘が小柏城と呼ばれていた可能性がある。

![]() 小高い丘の頂上に城山の文字が見える
小高い丘の頂上に城山の文字が見える
近年では城山の北の道を隔てた天神山に小柏城があったとする説も出ている。
上日野板碑 

上 上日野 板碑 下 石碑 小柏氏由来

第二章 豪族 小幡氏
小幡氏の領地
小柏氏を語る上で、上杉氏或いは武田氏の元で行動を共にし、縁戚関係にあった小幡氏の動静も知らねばならない。「甘楽町史」から小幡氏の足跡を概観してみよう。
「小幡村郷土史」に次のようにあるという。小幡氏の所領は十八万石といわれ、東は多胡、緑埜(みどの)の境まで、西は西牧・南牧に及び、南は神流川を越えて武蔵の国境に接し、北は碓氷川を境として、磯部あたりの地域全てを古代小幡の里といった。
かなり広い領地を持っており、他の大名に比しても遜色はない。地名は小幡氏からとった説、上毛野氏の家臣名、織機説、小墾田説、その他諸説がありはっきりしない。小幡氏の祖についても幾つかの説がある。
「上野名跡志」の武蔵七党の系図、児玉氏の中に小幡平四郎輔行の名前があり、「東鑑」(吾妻鏡)には小幡三郎左衛門慰の名前がある。七党には児玉、横山、猪俣、野与、村山、西、丹党とするものと、児玉、丹治、私市、猪俣、西野、横山、村山党とするものがある。
また安芸国藤松朝臣貞行が、勅命により小幡羊太夫宗勝を誅して、その功で小幡の姓を取得し、羊太夫の領地を貰い同時に字を小幡としたという説もある。その祖を甘楽郡司だった小葉多連とするものもある。
「上野人物志」では小幡氏の祖を、児玉党、秩父平四郎行高として、次に行頼とする。小幡氏正系図では、平姓畠山(秩父)――氏行――崇行としている。安中市木村氏所蔵の、小幡氏系譜では具平親王をその祖とし、「上野伝説雑記」には祖、実高――重高――信真とあり、一宮神主一ノ宮志摩所蔵の系図では、重貞(信真)から始まっている。
吉井町史では小幡平太行頼――氏行――崇行となっている。氏行は始め安芸国に居たが、秩父に来て畠山氏となりついで山を越え小幡に来て小幡氏を唱えた。小幡の地は水清く、土地が肥えており、桑の木の養生に適していたため、早くから養蚕が盛んだった。国峰城を居城として、宮崎城を第二の城として上総介信貞の弟信秀を守将としていた。
国峰城は大城郭であり、南北2.5キロm、東西2.5キロmに及び、山頂は標高434mである。麓近くに小幡城、内匠城を配し国峰城直衛堡としていた。小幡城は熊井戸対馬守の舘城であった。
吉井の長根衆も一族であり、庭谷、八木連、高田氏も小幡の騎馬衆として、その旗下に連なっていた。
小幡配下にあって連携した城・砦は、日の谷(上日野)の七村城から始まり、甘楽・富岡・高田・菅原(妙義)・下仁田に及び、六十一にものぼった。
小幡氏の研究書として、定評を得ている「上野国小幡氏の研究」には、上州小幡氏は鎌倉以来の名家であるが、永禄年間に入り、甘楽一帯に安定勢力を樹立し、その後は甲斐武田軍の有力武将として、先方衆の西上野衆に属し後武田二十四将にも数えられた。
武田滅亡後は、織田の武将滝川一益に従い、滝川氏西上の後は、小田原北条氏の勢力下に入り、天正十八年の北条氏没落と時を同じくして、本貫の地、甘楽より姿を消している。とある。
そして武田には以前から、別の小幡氏が従属しているが、この甲州小幡氏は、上州小幡氏とは別の系統(縁戚関係はない)であるとしている。
甲州小幡氏の、山城守虎盛は武田二十四将の一人に、数えられていてその孫が「甲陽軍鑑」の著者と見られている勘兵衛景憲であるとしている。
小幡伝来記など幾つかの系図は、甲州小幡氏の祖を上州小幡氏の系譜に、繋いでいるが同伝来記は、信真を小田原で切腹を仰せつかった(史実とは違うようだ)と、記載しているなどの事もあり、「上野国小幡氏の研究」の言うように、両小幡氏の血縁関係はなかったように思える。
小幡龍蟄が著した「幡氏旧領弁録」の中にある系図にも、甲州小幡氏の系譜は書かれていない。甲州小幡氏は始め、葛俣と称し後、小畠さらに小幡と称したという。
先の「羊太夫」という人は、天引城辺りに居住していた豪族であり、天馬を駆って従者の「八束の小脛」と共に、大和朝廷へ毎日出仕を欠かさなかった、という伝説の人物である。
その碑が今に残る有名な「多胡碑」として吉井町に残っている。羊太夫の姓は、藤原或いは小幡とするものがあるが、いずれにしても小幡氏の祖にはならないのではないか。多野郡に八束村という地名があり八束山という山もある。
八束の小脛の名と共に、出雲風土記に出てくる国引きをした神、八束水臣津野命との関連性を考える人もいる。古墳時代の舟形石棺は確かに出雲と上野国と共通している。舟形石棺はこの他、丹波・讃岐・肥後などに見られ、大和文化とは無縁とされている。
出雲の国譲りの際に、建御名方神が逃げて来た諏訪も隣県にあり、上野国にも諏訪社が数多くある事も関連があろうか。
国峰城落城 落武者信秀
「上毛伝説雑記」巻の十一に「上野志料集成」が収載されて、「小幡傳來記」が載っている。少し読み易く修正し次に大略(抄)を紹介する。
小幡家譜の事
尾張守重定は實高の嫡男。後に新龍斎日永と号す。上総介信貞は重定の嫡男、長野氏の妹婿。風山宗家居士と号す。弾正忠信氏は信州神原で討死。播磨守昌高は長篠にて討死。又八郎昌定は遠州三方が原にて討死。
小田原攻の事附國峯城合戦の事
天正十八年関白秀吉公、小田原の北条氏政を滅ぼさんと思し召され、三十万騎を引率し、氏政と対陣す。また御加勢には、徳川家康公、織田信雄公、都合五十万騎と聞く。
小田原城中に相詰める人々には、武州忍(藩)の城主成田下総守長康、岩槻の城主太田三楽、新田金山の城主由良信濃守国繁、足利の城主長尾顕長、佐野の城主宗綱、松井田の大道寺駿河守、鉢形の城主北条安房守氏邦、これは小田原へ子息を遣わし、
その身は北国の押さえとして、
鉢形に在城し桜沢八幡前に砦を築き、藤田正龍寺の後ろの大山の上に、楼閣をつくり大鐘を釣り北国勢が攻めて来て、藤岡八幡山に見えたなら、この大鐘を鳴らし相知らすべしとの約束なり。
今に至りそこは撞鐘堂と名付けられた。国峯の城主小幡上総守、これも同じく小田原城に相詰める。城代に子息左衛門佐信秀を置いて、宮崎城には小幡左衛門・同彦三郎が参百余騎にて相守る。
その他前橋、倉賀野、松山、川越、沼田、古河、関宿、平井、八幡山、館林、宇都宮も催促されて小田原城に相詰める。
文明、応仁以来の大合戦である。北条氏も早雲より五代続いて、八カ国の管領となっているので一族も増え、何十万人とも数知れぬ籠城となり、五年、十年では落城するはずはないと見えた。
これにより、関白秀吉公は長陣の支度をして、七十間に渡って陣小屋を作らせ、京都、大阪、奈良、堺より町人どもを呼び寄せ町を作り、店を出させ何でも不足のないように、種々の品物の商売をさせた。
金銀銅鉄の細工職人まで悉く、呼び寄せたのであたかも京都、大阪のようになり急に賑やかになった。このとき、北国よりも秀吉公へ加勢として、加賀の国守菅原の朝臣利家、越後の太守上杉景勝、両大将が北陸道七カ国の勢を率いて笛吹き峠(碓氷峠)を、攻め破り坂本を焼き払い、松井田を十重二十重に取り囲み、昼夜息をもつかせず、攻めたればこらえられず落城す。
それより先には宮崎城をなで斬りにし、国峰城へ押し寄せ鯨の咆哮の如く、鉄砲を撃ち矢を射掛け喚き叫んで攻め戦う。この城は追手北向きで山はなく、南は秋畑山、
秩父まで連なる高山、西は岩染・五賀・高瀬まで、屏風を立てた如くの険山なり。城山は遥かに秀で続く峰なし。
寄せ手大軍にて取り囲み、数日戦うといえども、基より名城にて要害なり。殊に浅鹿民部という智謀あり、武勇を兼ね備えた士である。
計略を廻らし、戦わずして勝利を得、大敵を滅ぼしければ、流石の大軍も呆れ果てて控えたり。さりながら、この城は山上に水がないので、東の方の谷の水を汲んでいる。ここに加賀大納言利家の家臣、山崎勘斎という者がこれを見つけ、大勢の番人を付けたので、これにより城中渇きに苦しむ。
数日のことなれば、梅林を指すに術なし。時に浅鹿は思案し、馬を数多く高い所へ引き出して、白米を流しかけ、水がたくさんあるように見せかけた。寄せ手これを見て、城中に水不足はないから馬どもを洗っている、無駄骨折りて益なしと水番人を引き上げた。
しかし寄せ手多勢なれば、入れ替え入れ替え、息をもつかせず攻めたので、今は門を一つ押し破り、櫓も塀も引き倒し、えいやと声を上げて攻め上る。城中からも矢玉を透間もなく射かけ、ここで死ぬ積りで防いだ。
ここにおいて、寄せ手の軍兵、二町ばかり引き退く。浅鹿民部は五十騎ばかりを従えて、逃げる敵を追いかけ此処の谷、あそこの落とし穴に追い込み、大勢打取り引き返し、太刀の血を拭い本丸に上がり、左衛門佐殿に軍の次第を申し上げ、涙をはらはらと流し、君の御武運もこれまでにて御座候。
随分城中の者共、防ぎ戦い候といえども、敵大勢の事にて候へば大水の堰を切ったる如くにして、防ぐべき術なし。君には早々後ろの山より、ひとまづ何処方へもお落ち下さい。某は城中に踏み留まり、おっつけ日暮れたなら城に火をつけ、殿は御自害のように見せかけ御跡を慕い参るべし。
はや得々と諌めれば信秀是非もなく、暮れ方に供をも連れずにただ一人、城中を忍び出て南の方、秋畑山は大山のことなれば、敵の入る懸念はなく、樵の通路ありて、草深く九十九折のような所を、ようよう辿り鷲翎山の峯に上りて、国峯を見れば民部は、はや城に火をつけたと見え、炎天に登り日中と異ならず。
屋形、櫓焼け崩れる音に、敵の勝どきの声夥しく聞こえける。信秀は民部が来ないが、峰を伝い鹿島という所に下り給えば、夜は東雲になりにけり。
信秀思し召す様は、おっつけ夜も明ければ、日野谷の者共、我が身の態を見るならば、必定咎め捉え置き敵陣へ注進すべし。
もしそのような事になれば、逃れ出て来た甲斐もなく、莫大の恥辱也。如何せんと思し召し案じて、煩い給いしに傍らを御覧ずれば大なる森あり。この中へ立ち寄らせ給い、見れば大社ありて鹿島明神と額あり。
これ究竟の隠れ家と思し召し、戸を押し開き立ち入らせ給う。それ鹿島明神は往古よりも軍神と、申し伝え候へば、信秀行く末安穏に守らせ給へと祈念して、勿体なくも神殿の内に隠れ居させ給へば心細い事なり。
大澤不動の由來附信秀向陽寺に入り給ふ事
さるほどに、信秀は既にその日も暮れければ、鹿島の神殿を立出でさせ給い、暗夜に紛れ、細道を谷川の流れの音を頼りにして、方角も判らぬ山中をあなた、こなたと踏み迷い、谷より峰また峰伝いに、そこはかとなく行くほどに、ようやく三里の所を十里ばかりにも歩き給うぞは憐れなる。
向こうを見給へば、ほの暗き中に堂と思しき物見えたり。近くに立ち寄り見させ給へば、不動明王のお堂なり。信秀幸いと喜び給い、日野にては鹿島明神の社に通夜し、いままた計らずもこの堂に来たり、明王を拝し奉る事、不思議の因縁と末頼もしく思し召し、拝殿に跪き出世の事を御祈誓なされた。
まだ夜も明けざれば、暫く御堂の柱に寄りかかり眠らせ給う。そのうちに日はほどなく三笠に落ちたり。
その所へ雨(天)引村の向陽寺の傳州和尚、この不動へ参詣なされ、順礼読経の事終わりて、傍らを見給へば十八、九なる容貌清やかなる士一人、御堂の柱に寄りかかり前後も知らず眠り居たり。
傳州この有様を見給うに、羽二重の黒き小袖に、軍配団扇の中に七五三笹の紋をつけ、大広口の裾を高くさしはさみ、黄金つくりの総巻の太刀を帯し、糸の草鞋召されたり、傳州不審に思し召し立ち休らい、伴僧の行者を頻りに呼ばせ給う、
その声に信秀うち驚き目を覚まし、顔を押し拭い両膝押立てもの申さんとし、少し遠慮の態に見えければ、傳州のほうより申されけるは、愚僧の儀はこの隣里、天引村向陽寺の住持にて候が、毎月二十八日この明王へ参詣仕り候。
今日おりしもまた二十八日故、参詣をいたし候なり。貴公には如何なる人にて、此処に渡らせ候ぞや。いぶかしと申されければ信秀聞召し、さては向陽寺にておはするか、しからば事情を話しましょう。
某(それがし)の事は定めし聞き及びでしょうが、国峰の城主小幡上総介の愚息にて候。北国勢と戦い、寄せ手多勢故、終いに打ちまけ落城に及びし、是非もなく此処へ落ち延びて参りたる。
お目にかかるこそ幸いの儀に候へば、暫く貴寺に隠し置き給われと、慇懃に述べ給う。傳州聞きて驚き入り、近くよりて手を束ね、さてさて如何なる人ぞと思いしが、御物語を承りては、聊か疎かにすべき儀ではなく候。
これと申すも偏に不動明王の、お引き合わせと覚え候。よくよくこの不動明王は春日の作にて、霊験いま以ってあらたかに候。
由来を申せば、昔此処の城主、羊太夫という人は神変奇異の名将にて、奈良の都まで百五六十里の行程を、日々参内怠らず。また家僕に八束小脛といい、権化なる者ありて主人に従い往来す。
この者の脛は八束ある故、八束小脛と申すなり。その頃羊太夫、奈良にてこの不動を求め来たり、堂を建立し安置し治世安民を祈らせ給うと、古老この事を語り伝える。それ春日の作と申す事は、ある説に藤原政純の刻みたるを申すなりと。
この政純は、春日明神より柄に鹿を彫りたる小刀を、お社参のとき申し受け、奇妙に細工を刻み浮かべ給うとなり。
即ち春日の化身といへり。さるによりてこの作は別して霊験に候なり。よくよく御祈念なさるべし。ご出世疑い候わず。まづ愚寺へお立ち入り候へと、伴い寺へ帰りたる。この傳州忠的和尚は、俗姓を尋ねれば、甲斐信玄公のご一族にて先年信玄公と、上杉憲政公と笛吹き峠にて合戦の節も、向陽寺より打って出て甲州勢に加わり、幾多の手柄を致されたる人なれば、甲斐甲斐しくも情けを懸け時節を待たせ給いけり。
秀吉攻め 小田原籠城
武州鉢形の城合戦の事附小田原落城の事
国峰の城、既に落城せし故、直ちに武州鉢形の城へ押し寄せ、勝負を決せんとす。平井八幡山の者共、早馬にて鉢形へこの事を注進す。
柳澤砦の者、慌て騒いで鉢形へ逃げ籠る。高根山の後なる大鐘を打ち鳴らし、事の急を鉢形へ知らす。
城中にては安房守氏邦、諸軍勢に触れて手分け手配りし給い、城の北なる荒川を、末野という所で土俵を数多積み重ね、また大石も重ねて水を締め切り、敵が川下を渡るならば、一度に水を切り落とし流す知略なり。
既に北国勢、平井八幡山を踏み破り、広木・大仏・用土などを乱取し、二手に分かれて押し寄せる。大手小前田の方へは、加賀利家八幡余騎にて向う。
一手は越後の景勝五万余騎、用土より分れ飯塚にかかり、寄居の方へ攻め寄せる。ほどなく、越後勢桜澤に着きければ、八幡山を本陣として幕打ち回し、合戦の手合いは明日と議定し、人馬を休め居たるところへ、越後勢の中よりも糸井川平六という勇士が、ただ一騎一族二百人ほど言い合わせ、兵糧をつかい馬に草飼い、明日の陣ぶれはなかなか遅かりし、この方、追手小前田よりも道のりも近くして、加賀勢に先を越されては越後の者の油断なり。
今日、未だ八つ時なり続けや一族家来共と、多勢の中を乗り抜けて、荒川端に臨みてあれば、さしもの大河思いのほか水浅くありければ、この間の旱魃に水少なくなったと覚ゆるなり。
心安く渡らんと一度にさっとうち入れければ、敵方時分は良しと湛え置きたる水を、土俵をどっと切り流せばたちまち、大水漲り来て二百人の者供一度にどっと、押し流され浮きつ沈みつ流れけり。
糸井川平六は馬を流しけれども、その身は越後の海辺にて育ちし者なれば、水にも溺れず岸に上がり、本陣に立ち帰り面目を失い居たりけり。景勝大いに立腹し、糸井川がいらざる抜け駆けして、敵の計略に乗りて戦わずして流れ死にする事、味方の恥辱言語道断也、抜け駆けすべからずと陣中に触れられけり。
既に明日になりければ、二手の勢い東西より押し寄せ散々に相戦う。寄手は道すがらの合戦に勝ち、勢い盛んに振舞いければ、城中の甲兵も随分防ぎ戦うといえども、多勢に無勢のことなれば、弓折れ矢尽きて過半のもの落ちて行き、籠城持ちがたく見えたり。
ことに小田原も落城近かるべしと、風聞が諸兵の間に蔓延し、氏邦も仕方なく降参するか、和睦するかと案じ煩いおられし所へ、菩提所の藤田正龍寺、布州和尚が参られ軍労の程を述べられ、その上にて申されけるは、公には如何思し召し候ぞ。
最早御武運も末になり、落城近かるべしと相見え候、早急に開城なされ、敵の幕下に属す事を請い、籠城の兵士女人子供までお助け候はば、これに過ぎたる御慈悲は更に之あるまじく候と。
言葉を尽くして諌(いさ)め給へば基より、氏邦も降参の心掛けありければ、布州の諌めを幸いと思われ、某も左様にとは存ぜしが、人口の程(意向か)は如何と思い候也、然らば尚、会稽山(中国の山)を下るの旨趣、敵陣へ至ってよくよく取り計らい給はれと、ありければ布州その意を了解候と、城外へ出でられ両大将に面会せられ、さても氏邦、両大将の大軍に囲まれ、籠鳥の如くにて遁るべき様なし。
之によりて氏邦も討死と思い定め、今一度命限りの合戦いたし腹切るべしと申し候を、愚僧諫言仕り候。氏邦も思い定め候へば城兵必死の合戦いたしなば、御軍士大勢亡び申すべく候へば、曲げて降参お許しあるべし、
囲みを解いて、籠城の者共をお助け給うべしと、言葉を尽くし申されければ、両将得心ありて然らば降参の印に、髭髪剃らせご同道あるべしと申されけり。
布州喜悦致され城中に立ち帰り、両将の申越されし趣、氏邦へ手立てを尽くして演説致されければ、氏邦も降参の上からは、兎も角もとて剃髪染衣の姿となり、布州を伴い降人に出でられけり。
それより寄せ手、城を巻きほぐせば城中の軍兵は、群鳥の籠より放されたる如くにて、万歳を謳いけりこの時、氏邦よりも布州東播和尚へお礼として、徽宗皇帝の鷹の絵の掛け物、毘首が達磨に東坡が竹・恵心僧都十三仏を進ぜられけり。
即ち正龍寺の宝物となり、宝蔵に秘し之あり。さて両将は、松山・川越をば破竹の如く攻め負かし、小田原に着陣し秀吉公に対面あり。
上州・武州の城共、悉く攻め破りし事共を申し上げられければ、秀吉公御喜び限りなく、両将の武功比類なしと御賞嘆なされ、御盃をくだされその上種々饗応、結構を尽くされけり。
既に北国勢の大軍、小田原に着きければ、五里・十里の中には尺寸の地もなく充満せり。氏政父子も、種々計略を廻らすといえども、大軍に囲まれ長陣のことなれば、兵糧も次第に乏しくなり、八カ国の大名数多詰める中には、今は退屈し敵へ心を通じ城中に引き入れんとする者も之有りと、
風聞も確かのように語るについて、氏政父子も諸大名に心を置き、用心厳しく城を堅固に保ちけるが、舎弟安房守氏邦は鉢形にて降参し、大納言菅原の朝臣利家の手に属し、小田原への先陣致しけるを、秀吉公召しだされご対面の上、種々馳走ありて近く召され仰せられけるは、いかに氏邦、舎兄氏政には籠城堅固也といえども、秀吉策を持って亡ぼさん事、義経が一の谷を落とし、義貞が鎌倉を滅せしよりも尚、以って易かるべし。
速やかに降参せば武蔵・相模を宛て行う(与える)べし。この趣を申し遣わし降参を致さすべし。この言葉に少しも相違あるべからず、と誓約を立て仰せられければ、氏邦肝に銘じ忝く存じ、委細畏まり奉り候と御前を立ち、使者を以って城中へ申し遣わせければ、
舎弟氏邦の申し遣わしたり事なれば、相違あらじと心得、父子供に喜悦して、早々幕下に降らるれば、氏政をばその夕暮方切腹を致させ、子息氏直をば御家人参百人つけられ、高野山へ遣わされ、後には大阪へ召され一万石を給はりけり。氏政、秀吉の策に乗りて終いに小田原落城す。
北条の家運五代にて終わる。実に盛衰興亡は世の習いといいながら、浅ましかりし事どもなり。
小幡上総介は、子息信秀が居城国峰にて降人に出でずして、合戦いたし候間、その怨敵ことさらその身小田原へ相詰めたる科により、これも切腹仰せつけられ、成田永康は降参を請われければ、金子千両に唐の頭あり次第、差し上ぐべきの由、仰せられけるによりて、忍の城中皆、詮議しけるに、金子ようやく九百両これあり、うち百両は御訴訟申されけるにご赦免なり。
唐の頭は三、差し上げ命ばかりお助け城地召し上げられ、浪人の身となりけるが、後に下野鳥山の辺にて、永銭三百貫文の所を拝領せられけり。嫡子、別府太郎・二男奈良次郎いずれも浪々の身となり、奈良次郎康光は奈良村集福寺開山也、法名を貞岡宗廉居士という。
家譜は大織冠鎌足公の末裔也。新田金山城主、由良信濃守国重はその身は病気と称し、小田原へは家老小金井四郎左衛門・鳥山浄三に三百騎を添えて、遣わしけるによりて、罪の軽重を計りて、国重をば十五万石を召し上げられ、千石にて常州関宿へ遣わされける。
宝積寺合戦
小幡一家の菩提所宝積寺の事
小幡権頭平朝臣実高は、もと勢州の人也。甲州信虎へ十九歳の時出勤せられ、諸所において手柄を致しその後、上州へ来たりて国峯へ住まいし、また小幡に久しく住まいす。故に在名を称し今に小幡という。
実高後に、入道して円城と号す。宝徳二年、庚午三月宝積寺を建立し、即庵宗覺和尚を請じて開山とす。即庵は小田原より来たりて、轟村鷲翎山の奥天寿庵に住す。一つの牛を飼われけり、この糧なければその牛の角に、一つの袋をかけて山を出さるれば、その牛、轟村に下り家ごとに廻る。
村里の男女これを見て、角より袋をおろし米を入れ、またもとの如くに懸ければまた他の家に行く。かくのごとくして、袋に満つれば牛、庵に帰る。諸人これを聞きて呼び寄せ即庵牛という。
即庵和尚は最乗寺了庵和尚より三世の孫、春屋和尚の嗣子なり。宝積寺は元律寺なり。そのときの石碑今にあり。延慶と年号を記し梵文あり。開基小幡上総介というは誤り也。
宝徳庚午は、人皇百三代後花園院の年号也。将軍は足利尊氏八代の孫源義政公なり。上総介は、人皇百七代正親町院の御世にて、永禄・天正時代の人なり。既に上総介は、天正十八年小田原陣に氏政へ加勢す。是をもって見れば、円城入道中興の開基たること明らかなり。即庵和尚の伝記にも開基実高とあり、実高法名華翁栄仲居士と号す。
宝積寺合戦の事附釣鐘淵の事
永禄六年の事とかや。
宇田城主小幡図書と宮崎の小幡彦三郎と異論の事ありて、合戦に及ぶ。図書、謀に乗りて終いに打ち負け、夜中に妻子諸共に宝積寺へ落ち来たり、魯岳和尚をお頼みありければ、魯岳一世の大事と思われ、如何せんと思案いたされ、流石、檀縁の事といい殊に又尸毘王の鳩の袂に入りたるを、助け給いし事を思い出され、見捨てがたく早々寺中へ入れ申し、前後の門を固めさせ図書殿に対面あり。
夜中に不慮のご入来お頼みの趣、何とも大難に存ずれども、檀縁を慕いお頼み候へば異議に及び難し。
お心安く御合戦なさるべし。当寺の儀は山高くして、西一方口なれば、要害は河内の金剛山にも劣りは致さじと、おっつけ彦三郎寄り来たり申すべし。お支度あるべしと、魯岳和尚も方丈に入り、衣の袖引き結びて肩にかけ、上帯締め裾を取りて差し挟み、練り絹にて鉢巻し、寺に伝えし小長刀を左手の脇にかいこみ、図書殿出で給へ言いながら、山門に走りのぼり、
四方を下知してありければ、五六十人の大衆も我劣らじと、進み出て褊袗の紬を結びて肩にかけ、裳をば手巾をもって括りあげ、もとより寺の事といい、殊に俄かの合戦なれば太刀も槍もあらばこそ、ただ山にある物は、樫の木沢山なりければ、我も我もと樫の木を手頃に拵へ、敵乱れ入らば無二無三に打ち殺さんと控えたり。
図書殿の装束は、白糸の鎧敷目に拵えたるを、草摺長に着下して、同じ毛の甲の緒を締め、大立物の脛当てに三尺八寸の太刀を帯し、重藤の弓横たえ、魯岳と同じく山門に上がり、矢束解いて押しくつろげ寄せ手の来たるを待つ。
宝積寺は東面にて、南は鷲翎山の大山西へ連なり、北は山なけれど大木数多く茂りあい、矢玉もなかなか通り難き要害なり。
総門の前は鷲翎山の奥より漲り出る谷川深くして底見えず。水が岩石に当たりて激する事雷の轟くが如し。大門上がり八町は谷を右にして、霧の中を行き岩石所々に横たわり、中々進み難き峽路なり。図書に従う侍二十四人、僧俗あわせて七十余人、今夜限りの討死と思い定めて待ち居たり。
案に違わず彦三郎、透き間もなく襲い来たり門外に馬を立て、参百余の勢を前門、後門に手配し、馬上に伸び上りて大音あげ、いかに図書、何とて居城を落ち去って、山林に入りけるぞや。ただし、妻子諸共に尼入道になりて、降参せん為の存念か。しからずば早々出でて勝負をせよ。
さなくば踏み込み狼藉せんと呼ばわりけり。図書山門にてこの言葉を聞き、弓杖ついて申す様、只今の雑言は彦三郎にてありけるか。
その不運にして汝が謀略に乗りて打ち負け、是までひとまず落ち来る。更に尼入道して降参の心なし。
汝もし来たらば快く一戦し、汝が首を取るか、我運命尽きて腹切るか、是非の勝負を決し、その広言を止めんとて、寺衆、大衆諸共に相待つなり。珍しからず候へども、合戦の習いならば一矢仕らん。
受けてみよ彦三郎と、二人張りに十二束打ちつがへ、切って放せば門の上を鳴り渡り、彦三郎が鎧の袖にばっしと立つ。彦三郎驚いて馬の手綱引き返し、遥か遠くに控えたり。
侍供に言いつけるは寺中に、さのみ人大勢あるべからず。門扉を押し破り乱れ入れと、しきりに励まし、ののしれば畏まり候と、我も我もと斬ってかかる。図書は山門よりさしつめ引き詰め矢種限りに射る。
侍供は門を開きて斬って出づれば、大衆も続いて打ち出で、入り乱れて戦いけり。寺中の僧俗は命を惜しまず、斬り伏せ討ち伏せ、火を出して戦いけれども、寄せては大勢こなたは小勢、ことに大衆は太刀・長刀も持たざれば皆悉く討死す。
彦三郎喜び勇みて、門の内へ馬を乗り込み図書はいずくにあるぞ。
侍供ただ生け捕れという所へ、図書・魯岳此処にありと、回廊の陰より飛んで出て、十文字巴の字に斬って廻れば、彦三郎この勢に恐れをなし、門外さして引き返す。また寄せての者供、一息ついて取って返し中庭まで乱れ入る。
ここにその丈、六尺ばかりなる法師一人、樫の丸太一尺四五寸の径と見える、一丈余なるを、軽々と引き揚げ、大勢の中へ打って入り、東西南北、四維八荒、乾坤宇宙も翻すべき勢すれば、この棒下にて死する者、何十人ともその数しれず。寄せ手是に恐れて、この坊主はよも人間にはあらじ。
如何様この山に住む天狗なるべし。まずこの陣引けというを幸いに、我先にと下村さして引き退く。その後の門へは、丹生五郎という者大将にて向いけるが、門塀を押し破り庫裏の方、廊下際まで乱れ入り、ここあそこに火を懸けさせければ、魔風忽ち吹き来たって諸堂一時に灰燼となる。
図書、力及ばず妻子をまず刺殺し、自身も頑(とみ)て腹切って炎の中へ飛び込みけり。魯岳和尚も合唱し結跏趺坐して焼け死にけり。大力の法師は、本堂の後に大磐石のありけるに、飛び上がりて大膝組み、腹掻き切って死にけり。
この石をその時より、天狗腹切石と申すなり。
宝積寺 腹切り石 
釣鐘は総門の上に釣置き、鐘楼門といいけるが、山門の下ゆえ急に火が移って焼け崩れ、鐘は谷へ倒れ落ちると見えたが、また撥ね返り終いに谷へ倒れ入る。
その所、即ち淵となり、今に至って「釣鐘が淵」と言いてあるなり。鐘は竜頭ばかり見ゆるときも有り、また見えざる時もあり。
嗚呼、一挙に焦土となりて後、僧堂燈消え、秋の虫なく音を添え、実に哀れかな、伽藍、土地変じて武士の戦場となり、数多の屍、仏教を汚す、魯岳は宝積寺十代なり。 石室和尚寛永七年に諸堂建立の時、大門を轟村の方へ廻らし、寺もこの向きに建てられたり。この時、織田兵部大輔、越前国よりこちらへ来たりて領す。
小幡石室に帰依し檀越となる者なり。
「小幡伝来記」にはこの他に、孫市郎直好(直正嫡子)實高九代末孫、小幡御一族の事、菊女の池扞煎胡痲生ずる事、佐野城の事附戸澤砦の事、西牧落城の事、小幡左衛門佐信秀御出世の事、国峰城異説の事、という項目がある。一部は紹介したところもあり、重複する所もあるので今は省略する。
向陽寺に匿われた信秀はその後、同寺を訪れた奥平美作に傳州が推挙を依頼し、美作が秀忠(徳川)にとりなし、安中(市)野殿にて一千石を与えられ、取立てられた。
「甘楽町史」に小幡信定(信真・国峰城主)参加の、小田原城攻防の合戦概況が載っている。
これを見ると、籠城側は本丸に氏政旗下の三千人、氏直旗下の五千人の計八千人が詰め、信定は渋取口を相模津久井城主、内藤景豊と共に、八千九百人で固めたとある。他の上野衆も信定と一緒に、ここの配置に付いたのだろう。
渋取口にはこの他に、岩槻城主太田氏房・北条氏ら一万八千三百人が守備に付いたとあり、相当重要な守備所だったと思われる。
「甘楽町史」・「旧領弁録」にも国峰城の記事がある。長文なので、概略を紹介しよう。
国峰城は峰城ともいう。「箕輪軍記」(長野氏)の云うところでは、国峰城に小幡重定が千騎で立て籠っていた。
弟の鷹ノ巣城主、図書之介とは同じ長野業政の婿同士である。兄弟は不和となり、重定が草津へ湯治に行っている間に、図書は兄の悪口を舅の業政に吹き込み、それによって業政は国峰城を占領し図書之介を入城させた。
重定は帰る事ができずに、仕方なく甲州へ行き信玄を頼った。信玄は大日向に五千貫の所領を与え砦を築いた。後に信玄は上州に侵攻し、国峰城を取り返し重定を入城させた。
「関東古戦録」では重定が憲重(同一人物)に変わっていて、熱海に湯治に行っていたとあり、図書之介が上杉景虎を欺き、国峰城を占拠し重定を入れなかった。とある。
このため重定は信玄に拠ったという。
「和田記」にも同じような記事があるという。甲陽軍鑑にも同様の記事が見える。
小幡龍蟄は、二人が長野氏の婿というのは誤りで婿は信真であるとして、既出の重定も信真の誤りとしている。そして鷹ノ巣は下仁田の鷹ノ巣であろうとしている。また砦を築いたのは南牧であるとしている。
信玄・信真の攻略により、長野氏の箕輪城落城の後、信真は信玄から上総介の名を貰った。また長野氏の娘である妻を離別し、武田譜代の者と縁組するよう命令を受けた。
信真は、二十七年も連れ添った妻であり、沢山の子供も育てたが実家には勘当されていて、今となっては行く所もなく、路頭に迷うだけであり、そうなれば自分の恥ともなり、他の事なら何でもするが、こればかりは成敗されるとも出来まじき候、ときっぱりと断っている。
信玄は怒りもせず、その意気で義理堅い故、信頼して先陣も申付けられる、甥の武田典厩を婿に仰せ付けると言った。(実際には典厩の子供)
この信真が長広舌を振るったくだりは、「鎌倉公方九代記」に詳しく載せられている、名調子の名文となっている。
龍蟄は有名な赤備えもこの頃、命ぜられたのではと推測している。小田原落城後、小幡信真はその所領を追われ、真田昌幸を頼って信州上田へ落ちて行った。甘楽に覇を唱え約400年間、十五代に亘ったその栄華の日々はここに終焉を告げた。
この後、真田軍の赤備えが殊に有名になっている。小幡軍の赤備えを受け継いだものとみえる。
幡氏旧領弁録について
龍蟄が著して、名文でもある旧領弁録を少し要約し現代語訳で示しておこう。何故、「幡氏」であって「小幡氏」ではないのか、謎である。「小」は冠詞・接頭語とでも言うのであろうか。
美辞麗句を取り去り謙虚に表示したという事ではなさそうだ。それなら本姓が「幡」であったのか。その「幡」は古代氏族の「秦」氏から来ていることを示唆しているのであろうか。
この事はどの文献でも論じていないし判然としない。近年、伝説の「羊太夫」が秦氏であり、小幡氏もその子孫であるとの説が出ている。羊太夫は有名な多胡碑の「羊」の人名に結び付けられている。
羊太夫の伝説は、ストーリーが完璧に完成されている感を受ける。古代の伝説によくある矛盾した部分・筋がなく明瞭であり、異なる伝承がないようで殆ど同じ筋書きで伝えられているようだ。
この事が何を意味するのか。私は何か後世的なものを感じる事を禁じ得ない。だが火のない所に煙は立たないように、伝説が大きく膨らませて伝えられたとしても、その中に核となる真実が含まれている事も大いにありうる。
出自のよく分らない小幡羊太夫宗勝は初め秩父にいたが、その有能さを疎まれて甘楽・多胡郡に移された有力な豪族であった。多胡碑に見られる「羊」名の人物と同一人とする説が有力視されている。
しかし現存する伝承では、小幡氏が羊太夫宗勝を討ったとするものであり、羊太夫宗勝が小幡氏の祖先である可能性は低いと思われる。
渡来氏族とされる秦氏は大和や河内を拠点としていたが、小幡氏は安芸国をその原点とする説が有力で、これを採ると両者に接点はないように見える。
今となっては、秦氏が小幡氏の祖先かどうかを検証するのも難しいものとなってしまったが、心証では小幡氏の出自を秦氏に採る説は成り立ち難く思える。
地名の由来として伝えられる「小畑」「小墾(治)田」「小葉多」「織機」の何れの「小」をとっても「幡氏」には結びつかない。
そこで、小幡龍蟄がわざわざ「小」を削除して「幡氏旧領弁録」と銘打った意図は、秦氏との関わりを示唆して子孫による今後の研究を、期待すると言外に述べているようにも受け取れる。
龍蟄自身はその系図の先端を村上天皇に繋いでいる。
近年の研究により、旧領弁録の記載には一部誤りがあるとの指摘もあるようだが、批評・批判はさほど難しい事ではない。
確かに史料批判は必要なものであり、その批判に耐える裏づけを持った文献史料に整える事が重要と思う。例え一部に誤りがあったとしてもその価値は減じられない。
幡氏旧領弁録 抄
序文
上毛野は吾、祖先歴世の旧領地故、その墳墓あり、然るに絶えて拝する事なし。志が適う事を得て、去年四月二日宝積寺に行き、累代の墳墓を拝し、国峰・宮崎の城跡及び、古戦場、旧跡を訪れた。
然れども今、所々にその旧名が残るとはいえ、或いは松柏繁茂の地となり、或いは、僅かにその証の残るもあり、あゝ哀れ也。
栄枯盛衰定めなく、世をもって数えれば僅か十一世、年を持って数えれば二百六十四余年、広々したる堅城も名のみにして今は荒野となる如くか。ここにおいて懐古の情、涙湧きて衣を濡らす。
高瀬村新居又太郎、轟村田村助左衛門、琵琶窪村中野吉兵衛(名主)、竹の内村斉藤喜兵衛、中里村藤井仲衛門など、皆吾家の旧家の旧臣なり。なかんずく又太郎家に宿して、彼が家に風山領室両君の尊毫を数枚所持してあるを拝見す。
その筆勢吾家にあるものと同じにして、実に真筆であり真に貴きものなり。上毛野に止宿する事、僅か七日にして古跡を見聞する事少なからず。
いわんや数十日留まりて、聴取すれば祖先の兵器、或いは遺書または平素玩弄の器などを伝え、所持する人あれば嘆きは止まらぬほどになる。
尚、子孫にいたり旧跡を尋ねる共、年を経るに従い伝承も少なくなり、判然としない事多くなるべし。
故に今見聞するままに記し、また誤伝を正し幡氏旧領弁録と名づける拙文とし、不弁なれど、その他(者)に示すにあらずして、(我)子孫たる者に祖先の事を忘れぬように、かくのごとく己が知る所を記す。
尚、新たな見聞があればまた増録すべし。
小幡郷国峯城之事
国峰城周辺の地形、位置関係が詳しく記述されている。
国峯は遠祖累代の居城なり。左右の山陰に民家あり、この辺は都で昔は囲いの内にあり、一円を国峰村といった。御殿平の後ろの辺りから中野吉兵衛が、長さ五寸ばかりの槍を掘り出し今も所持している。
古戦場の後も今は広々とした畑になっている。畑の中に七八間四方で高さ二間位の墳が所々にある。いずれも墳の上に自然石の庚申塔二十本~三十本くらい建ててある。
天正の時の戦死者を埋めた所なり。
安政五年四月二日より八日まで、宝積寺にて旧領古跡を訪ね同三日国峰城跡を弔い、七日峯城跡を弔い、八日宝積寺にて祖先の法事を行う。当寺は四十一世孝道和尚という。小幡は羊太夫の末という、また国峰城は藤田氏の居城という説があるが、いずれも誤りなり。
宝積寺の事
宝積寺合戦は天正十五年、彦三郎が籠り、図書介が焼却せしめた説、永禄六年、図書介が籠り、彦三郎が焼却せしめた説の二つがある。同寺でもこの両説を伝えているだけで、どちらが真実かは判然としない。
ただ上野伝説雑記が伝えるところは図書介が籠り、彦三郎が攻めたとあり、寺が伝えている永禄六年説と全く同じである。
(「因果の水鏡お菊が池」では、上野伝説雑記とは違い彦三郎がこもり図書介が攻めたとしている。)
時代を考えると永禄(上野伝説雑記)の頃では、彦三郎の年齢は子供となるので、天正十五年の事なのであろう。これならば魯岳和尚の年代に合致する。図書介が籠っていて、彦三郎(関東古戦録に景純とあり、伝説雑記に景定とある)が攻めたのであろう。
「上野志」にも彦三郎は宮崎城にありて小田原の役の時に落城とあり、図書介は宝積寺にて討死し、彦三郎はその後天正拾八年、小田原の役の際に宮崎城にて、戦死したのであろう、この事疑うべからず。
(龍蟄の言うように時代背景などは合致しても、時の住職魯岳が、開基であり大檀家の重貞の甥の彦三郎と戦い、自分や寺僧達の命までかけて遠縁(?)の図書介を庇いだてしたのかという疑問は残る。
龍蟄は同書の中で彦三郎に君を付けて彦三郎君として、尊崇の念を顕わしているが図書介については図書介と表記しており呼び捨てである。
宝積寺合戦を天正15年(1587)の事としているのは、宝積寺の過去帳記載の魯岳和尚の没年と同じであり、小柏氏正系図の記載とも一致する事から説得力がある。)
この戦いのさなか大法師が現れ暴れまわって、天狗といわれ進退窮まって大石の上で腹を切った。この時、石に血がかかり流れ落ちた如くの赤黒いしみが出来た。鐘楼は焼け落ち、釣鐘は川に落ち釣鐘淵となった。
その後、小幡の領主(織田侯か)がこの鐘を引き上げようとしたが、なかなか上がらなかったという。そこの滝に打たれるなどの目的で、人が入ると天気が風雨などになり荒れる事があるといわれ当時は入る者なし。
三四十年前までは、この滝壺に入れば鐘の竜頭が足に触れたという。先祖の墓所は長年法事もせず、ほったらかしになっていたのでかなり荒れていたが修復し尊牌を奉納した。
次に墓石の形状・寸法図などの記載あり。

宝積寺 小幡氏の墓所
この後、重定の二男、弾正忠信が開基となったという永隣寺の事、重定の五男、左衛門尉信秀の開基という宗泉寺の事、播磨守顕高が開基したという興巌寺の事、の記事が続くが略す。次は鰐口再考の記事。
再考 菅原村天神鰐口 天正五年小幡信龍斎置
更に考えるに同社の鰐口、重定君のご寄進なるべくこの如くなれば、信龍斎と称せしなるべし、然るに系譜並びに諸文献新龍斎と記載するは誤りか。もしくは始め新龍斎と称し、後甲斐候より信の字を御拝借ありて信龍斎に改め給えしか、未だ不明なれどこの如く証拠もあれば信の字のほうを然りとすべし。
(菅原村は甘楽郡ナリ)またいわく重定君未年八月十五日御卒去あり、既に尊牌に記す如く年号不明、然るに前文、鰐口の銘によりて考えれば天正五年まではご存命なる事疑うべからず。
その後十八年小田原の役には君、居ますを聞かず故に未年とあるは天正十一癸未にて八月十五日の御卒去なる事疑うべからず。
万延元庚申年八月上浣 龍蟄識
この数項後に、高政の項で述べた補遺 追記再考の記事が記載されている。
家系大略左の如シ 二十六代の祖、源則景は芸州に住まいせしが、頼朝公の挙兵により関東に来たり、児玉武蔵守朝行の娘を娶り二子を産む。二男氏行が後に児玉氏の養子になり児玉氏を名乗った。武州児玉の庄を領し新児玉という、後に上州奥平の郷を領し、姓を奥平と改める。
また甘楽郡小幡郷の郡司となり再び小幡氏と改める。奥平は嫡子吉行に与え奥平氏の祖となる。
信真君御改名の時代を考えるに御父尾張守憲重君の、憲の字は上杉候より御拝借なるべし。よって信龍斎重定とお改めは上杉候没落(天正二年)後なるべく、尾張守の御名はそのみぎりお世継ぎの信真君へお譲りなるべし。
同君その後上総介と甲斐候より御拝借は甲陽軍艦にいう、永禄十一戊辰年なり。お諱信真とお改めも同時なるか。また尾張守の前は甲陽軍艦並びに上野伝説雑記にいう藤五郎と称せしか。なお正すべし。
且つ信真君御年十八歳、甲斐候へ御随身是また永禄元戊午年なり。また考えるに藤五郎は信真君御幼名にあらず。
旧領弁録はこの他に、小幡系図、昌禅寺の事、乗願寺縁起抜書、書簡、家紋等諸々の記事が書かれているが、長文となるので略す。
旧領弁録の執筆にあたっての参考文献などは次の通り。
上野志 後上野志 上野名跡考 上毛伝説雑記 小幡伝説 箕輪軍記 関東古戦録
甲陽軍艦 武田三代記 徳川歴代記 小幡氏系譜 奥平氏系譜 一の宮氏系図
寺社 宝積寺 最興寺 乗願寺 安楽寺 貫前神社 妙義神社 菅原神社
旧臣 轟 田村家 高瀬 新居家 国峰 斉藤家・中野家 妙義 藤井家
一の宮志摩家 (宝積寺史)
「仙洞院記」
仙洞院は「因果の水鏡菊が池」によれば、宝積寺の末寺にて小幡信真の奥方が蟄居した寺である。
宝積寺が所蔵する「仙洞院記」(以下)は筆者不詳、作成年月不祥という。
国峰の城主小幡上総介内室の建立なり。その所以(ゆえん)を尋ねるに、箕輪の城主長野信濃守業政の娘にて相婿図書介の讒言により業政と不和になり、終いに甲斐の信玄に属し、かねて箕輪を退治の心がけありければ、甲州方箕輪の城に押し寄せ、数度の合戦ありけるに甲州方の手に入らず。
忠功の小幡なればとて帰る際に甲州勢国峰城へ押し寄せ、図書介居城を乗っ取り、本領なればとて上総介へ下さる。
敵の長野の娘を妻に致す事、無用の由申し聞かされけるに、上総介申し返さるには元来貞女にて父長野に勘気をうけ、国峰落城してより数多の子供を引き連れ漂白流浪艱難の苦を厭わず、今公の御厚恩にて本領安堵の思いをなし数年の愁眉を開きしを、今更離別を致さば困窮路途に餓死せんより他事なかるべし。
さ候えば公のお名までを汚し貞女の道を乱し候。義に相あたりし処を不便に存じ何分ご賢察くだされと申し上げれば、信玄公上総介義も有情もある者なればとて一家の好みを結ばる。
近郷轟村曹洞宗宝積寺六世格翁禅師を□□して師匠と頼み、夫婦ちはつ染衣の身となりて花萼山興岩寺を建立し格翁禅師を開山とす。法名興岩宗見と号す。
ついに国峰の城に卒る後に妙意当地の山水絶景なるを見立て退隠せらる。格翁禅師を勧請開山として当院を建立あり。
禁裏に「仙洞御所」あり如何の故と昔物語に言い伝えるに、武田小幡の両家好みを結ばるる、時天下に三つあり琴の仙洞代と云う物を武田の重宝となるを引手に贈らるる。故仙洞の院号とす。
花萼は往古の琴の歌の題なり。故に是を山号とするか、近辺にガキヤマというのがあり、文字は判らず楽器山と書くなれば花萼仙洞院の縁に叶うなるべし。本尊虚空蔵は妙意の内持仏なり。 小幡上総介信定 紋は七五三竹軍配円ワトハリビシナリ。
いずれ小幡の関係者が書いた物のようである。当主或いは当主に近い家族ででもあろうか。仙洞院は小幡家の開基であり、記事中の上総介は信真のことである。
信玄が砦を構えて重定を入れたのは、南牧の砥沢であり現在の羽沢小学校の所という。重定はここから上州の高山、多比良、天引(甘尾)氏を武田方に引き入れたとしている。
国峰城を取り返す時に、信玄は重定から図書介は慌て者と聞き、夜間に馬一頭につき提灯一個をつけさせ、徒歩の者は松明を持ち、旗竿の先にも小提灯を結びつけ城に迫った。
合図と共に一斉に提灯をあげ、松明に火をつけ鬨の声をあげると、図書介は大軍の夜襲と思い、慌てふためき城を捨てて逃れたという。これにより重定は元の如く国峰城に入った。(上毛古戦記)
別の文献ではこの国峰城攻めのとき、重定は先陣を勤めている。ここに記載の「重定」もやはり信真のことである。
宝積寺の脇に白倉神社に登る参道がある。白倉神社は古い創建であり由緒ある神社である。白倉神社の縁起書には小幡氏の名前が見え、その伝説にも小幡宗綱が登場している。白倉神社の創建は775年といわれ、祭神は大和武尊、大山祇命、金山彦命である。
兄たちに蛇塚に投げ込まれて殺された、群馬大夫の末弟が大蛇に変身し周囲に災いを及ぼしていた。年に一回生贄として娘が大蛇に捧げられる事になり、小幡権頭宗綱の娘が捧げられる事になり、判官宗冬が同情し恋仲となり二人は共に蛇塚に入りお経を唱えた、すると大蛇の怨念は消えた。
後に宗冬は辛科大明神に祀られ宗綱は白倉大権現に祀られた。白倉神社は熊倉山の頂上近くに奥宮(旧社)があり白倉郷に里宮がある。国道沿いには大きな鳥居があり天狗の面が飾られお天狗様とも呼ばれる。
小幡図書助の実像
旧領弁録所収の小幡系図を見ると、彦三郎は信真の弟信氏の子則信(諸説あり)であり龍蟄が言うように甥である。彦三郎は小幡氏の中にあって、主要な継承者ではなかった為か上野人物志の系図、木村氏所蔵の系図、上野伝説雑記の系図、一ノ宮氏所蔵系図等には名前の記載が見つからない。
これら系図は主に当主を継承した人物名を記した物で、系図を抜粋したものもあるので断定は出来ないが…。
小幡図書介或いは景純、景定の名前は、吉井町史の系図、寛政譜の系図、旧領弁録の系図の中にも見られない。「甘楽町史」所収の旧領弁録の系図だけに、信真の三番目の弟に景定の名前がある。
ところが「宝積寺史」所収の旧領弁録系図では、景定の所は昌定となっている。宝積寺史では昌定の別名及び法名まで記載しているので、甘楽町史の方が誤植であろうと思われる
吉井町誌の系図やその他の系図もこの部分はみな「昌定」と記載されている
「北甘楽郡史」に小幡家一族の事として、小幡図書景定は甘楽郡宇田城主であり、後に神成(城)に住み下総国で討死したとある。
その子孫は神成氏を称したとある。小幡氏傍系譜としては盛次を筆頭として次に虎盛があり、数代置いて信定・信秀・女子・景純の四兄弟の名がある。信定の定は一に貞に作るとあり本名重貞・尾張守とある。
これは全く直系と混同しているようだ。そして景純は図書助で板倉鷹巣城主としている。
ついで高山氏系図を見ると、高山満重の二男・光重の長女が小幡図書の養子神成城次郎に嫁ぐとある。
嫁于小幡上總介信定末子次郎信之後為神成城主小幡図書之養子即在于神成城次郎母長野信濃守業正之女也 ――略――
これを見ると図書助の妻は業正の娘で、信定(真)の末子信之を養子にした事になっている。しかし、信真に実子はなく弟の子供を養子にしている。
ここにある信定は重貞の事と思われるが、重貞の末子或いは子に図書・次郎・信之などの名前はない。
高山系図のこの部分には有力な異説があり、一概に鵜呑みにする事はできない。
龍蟄が宝積寺に奉納した小幡氏歴代法名記録には、初代氏行から二十四世龍起までが記載されているが、彦三郎の父の信氏の法名は載っているが、彦三郎らしき人物名は記載されていない。
同じく図書助の名前も見当たらない。
図書介は一般に信真の弟とされるが、それは長野氏の長女を信真が娶り、二女を図書助が娶っているところから推測されたものではなかろうか。諸文献の殆どが(小幡氏の)「一族の図書助」と表記しており、明確な系譜については触れていない。
「上毛古戦記」を見ると、憲重泉龍斎の子が尾張守重定(上総介信貞)であり、長野業政の長女の婿であり、一族の図書介景純は丹生・宮崎両城の城主で業政の二女の婿であるとしている。
丹生城は新田氏の影が強く、宮崎城も代替わりがあるが彦三郎が居住したとする説の方が有力と思われる。また箕輪軍記には国峰城主図書助景定とあるが、これは図書助が一時同城を占領した時の事であろう。
諸文献に重定(憲重)と同時期に、図書の名前の記載が見られるので重定と同時代の人物である。重定の兄弟の名前は系譜として伝わっていないが、おそらくは重定の弟であったのだろう。
一ノ宮志摩所蔵の系図には重定の弟は五人居たとあるが、この重定は信真の間違いである。重定と同時代に宇多城・神成城二城を有していたのなら、しかるべき系統の者である事は疑いを入れない。
先に触れたように「箕輪軍記」に、重定国峰城に千騎で籠り…..舎弟図書介も(鷹巣城主)長野業政の相婿なり、兄弟不和にして….とある。「箕輪軍記」は必ずしも正鵠を射ていないとの評もあるが、状況的に見ると図書助は重定の弟に見えてくる。
やはり重定の何番目かの弟であったと推測されるが、これ等の諸文献は信真の事を重定と記載している。重定も信真も共に尾張守を名乗った事から混同しているとみえる。信真は先に触れたように4回改名しており、初め尾張守を称して後に信玄のよって上総介を授けられている。
父重定の名前と似通っていた事もあり、多くは重定と混同され記録されている。茂木家系譜にも、小幡尾張守重定後上総介信真亦号新龍斎也男子依無実子而以弟為子とあり、重貞が信真のように思えるが実子無くとあればやはり信真であろう。
新田吉重の後裔、新田景純(主水正)は北条政時を滅ぼして、丹生城から後閑城に居を移し長野業政に属し後に姓を後閑氏と改めた。(景純の子の信純の時に後閑に移ったとの説もある。)
この謎の多い新田景純を小幡図書助と同人物とする説もある。確かに宇田城と丹生城は、隣接しているのでこの可能性は捨てきれない。
鷹巣城主小幡三河守(図書介)貞政は図書助と混同される場合もあるが、龍蟄は別人であるとしてこの説を否定しているが、もしかしたら三河守が親で図書助が子供なのかもしれないと言っている。
この事は、先祖の研究と供養を後半生のライフワークとしていた龍蟄さえも、図書助の素性を把握できなかったという事である。「上野武士団の中世史」によれば、代々(小幡)三河守を称する系統は下仁田鷹巣城(板鼻にも鷹巣城がある)を本拠とする系統であるとしている。
また「結城戦場記」に上杉氏の被官として、小幡三河守の名前があるという。「上野人物志」では図書助と三河守は明確に別人として構成している。
いずれにしても三河守貞政の別名は員政・景宗・信尚であり甲州小幡氏とみられる。しかし「吉井町誌」所収の小幡系図には、重定の二番目の弟として三河守貞政の名前がある。
尚、同系図にすぐ下の弟として記載されている虎盛は、甲州小幡氏であり当初は小畠虎盛であったとされている。この系図に虎盛の名前がなければ、信用に足る系図のように思えるところである。
図書助の死亡地についても、宝積寺合戦の際の宝積寺説と下総で病死・討死説がある。ここまで見てきたように、多くの文献に重定と記載されているものの殆どは信真である事が分った。
ここで小幡彦三郎と小幡図書助が、戦った宝積寺合戦を検証してみよう。図書助が重定の弟とするなら彦三郎とは二世代違う事になる。彦三郎にとって重定は祖父であり図書助は大叔父という関係になる。
彦三郎の叔父の信真は1540~1592年の人であり、重定の没年代は1583年である。この二人の年代を基準として考えると、宝積寺合戦があったと見られる天正十五年(1587)には彦三郎は18~19歳である。
対して図書助の年齢は64歳位と推定される。戦国時代の年齢では寿命を過ぎていると思われる高齢である。19歳と64歳の血縁者が命をかけて戦うとは考え難い。ましてこの合戦の原因は分っていない。「異論があって」という程度の事しか伝えられていないのである。
この事は些細な原因であったと想定されるから、尚更可能性は薄くなる。やはり重定と伝わっている人物は信真というところに帰結する。
図書助は信真の弟であり、叔父と甥・彦三郎とのいさかいが宝積寺合戦に発展してしまったとみられる。しかし信真の弟四人の没年齢・法名は龍蟄によって明らかにされており、図書助らしき人物は見当たらない。信真の知られていない異母弟でもあったのか。
信真はお菊事件を初めとして国峰城を不意に奪われ、武田に属し二十四将に数えられ、信玄との妻離縁問答、小田原城籠城・後に鉄砲傷により死亡と波乱万丈の生涯を送った。そして多くの伝説を残し、小幡氏の中では最も高名を馳せた武将であったといえる。
図書助の実像に指呼の間に迄、迫ったかとみえたが、結局のところ図書助の素性を示す確たるものは見つからず、その出生と系譜は霧に包まれている。古文書や手紙の中に小幡○○あるいは小幡○○守として、沢山の武将の名前が登場するがその多くは小幡系譜のどの位置に当るのか不明である。
今に伝わっている小幡系図は沢山あるが、そのそれぞれが一部を異にしている為に真実は見えてこない。異説や伝説と相まって、小幡氏の系図は複雑怪奇な物となってしまっている。
小柏定重長篠の合戦に出陣
高政の後継者(嫡子)、定重がお菊伝説で有名な小柏源六である。定重は庄司・源六と呼ばれた事もあったようだ。定重は父高政と共に武田信玄・勝頼に仕えていた。小柏系図を見れば、お菊の事は次のように記載してある。
小幡信定の奥に召し仕えていた女、その名を菊というが小さい過ちを犯した。これを重罪となし、家来が桶に入れてかつ蛇、百足を入れて菊を責めた。
この時に定重は軍事の用件にて二本木峠を馬で通りかかり、その山中に女の悲鳴を聞きつけ、不思議に思い山林の中に駆け込んだ。
見ればお菊がその苦痛に悲鳴を上げている、定重は忍び難く不憫に思いすぐにお菊を助けた。このとき菊女は苦痛の中から声を絞り、定重に告げて吾の苦痛を救ってくれた厚き恩を、幾度生まれ変わっても忘れないと言った。この縁によって、あなたの子孫を必ず長く守る事を誓うとしてこときれた。
これによって小柏家をはじめ、小柏村出生の者まで皆蛇の害を免れた。もし蛇の災いがありそうな時は、“小柏氏のお通り”と唱えていけば蛇も寄ってこないと云う。
その他の事跡の詳細については別に記録がある。
以上が小柏氏系図に記載されているものである。「藤岡市史」には小幡伝来記にもお菊伝説が収載されているが、内容の違いなどから小柏系図の方が古いものであり、小幡伝来記から取られたものではないとの趣旨を記載している。
宝積寺史収載の「幡氏旧領弁録」では、お菊を助けたのは小柏源介定政となっているが、宝積寺史には正しく記載されている。二本木峠は現在の小柏峠のすぐ北側に位置する峠と思われる。(別項に記述。)
定重については「多野郡誌」に次のような記載がある。
小柏源六は甘楽郡小柏村に生まれた。小柏家は小松内府重盛の嫡子三位維盛の一子維基を始祖として、この地の郷士となり鎌倉北条に属し、後平井上杉に従いまた甲州武田に属した。江戸時代には土地の名主をして現代に至った。
維基から十八世定重に至った。定重は左馬助六郎右衛門高政の嫡子で、すなわち庄司源六と称した。父子ともに武田の武将で、諸所の合戦に武功を顕したが、天正三年遂に長篠役で戦死した。
長篠役後勝頼から定重の功を賞し、甲冑及び武具を添えて感状(感謝状)を寄せられた。これが今同家に存している。それより前、小幡信貞の女中菊女蛇責の事によって世に知られている。
「甘楽町史」にもほぼ同様の記事があり、その次に定重が関わった「お菊伝説」を紹介している。(「多野藤岡地方誌・各説編」の記事もほぼ同様。)
小柏氏系図には次のようにある。
定重 小柏源六 父子共に武田信玄同四郎勝頼に従う。天正三乙亥年五月二十一日未だ黎明の時、武田勝頼の命を承り、小幡大膳亮と共に小斥候に出て敵陣に忍び寄りし時、敵これを知り足下に起き上がり囲まれた。
定重性質、大力あり武勇無双の者にして度々の戦功あり。事此処に至っては今更逃れ難く、いまその時節に望みても、その場において聊かもその猛気隕(おち)ず、比類なき働きをなし、三州長篠にて終いには戦死してお訖(おわりぬ)。
長篠の合戦、殊に設楽原の決戦では多くの西上州の武士が討死している。特に安中城主安中忠成の軍勢は、殆ど全滅し帰還する者なしと伝わっている。鉄砲隊の正面から突撃した小幡勢には、何故か比較的生存者が多かったともいう。
長篠の合戦で討死した西上野国の将士には、小幡信貞、大戸丹後守幸宗・信茂兄弟、松本縫之助定吉・右衛門重友がある。
「信長公記」は「三番手の小幡の一党は赤色の具足を揃えて、入れ替わって攻めかかって来た。
関東の武士たちは馬を巧みに乗りこなしたから、小幡一党もまた騎馬で突撃する戦術で、攻め太鼓を打って突進してきた。
味方は鉄砲を揃え、盾に身を隠して待ちうけ撃たせたので、小幡隊も過半数が撃ち倒されて兵力少数になって退却した。」としている。
だが、歴史考証家の名和弓雄によれば、騎馬軍団での突撃はなかったという。その著書「長篠・設楽原合戦の真実」の中において、合戦当時は梅雨時であり、水田は満水の状態であり、低湿地帯の設楽原は進撃する部隊により踏み荒らされて、泥濘の海原となっており、馬は足を取られて走れるものではないとしている。
同書は[長篠日記]「三州長篠軍記」「当代記」「武徳編年集成」「三州長篠合戦記」「信長公記」など多くの古文書を検証している他、実際に合戦の現場に当時の馬防柵や空堀を設置して、鉄砲の連射までを再現し実地検証している。
同書に拠れば武田勝頼は小幡大膳亮に命じて、八剣山(竹広弾正山)の敵陣地を偵察させたという。
小幡大膳亮は天王山をくだり偵察に行ったが、闇夜であり暗くて様子が判らないため傍らの、人気のない大きな家に放火させその灯りによって敵陣の様子を見ようとした。
この時、監視に当っていた徳川軍の内藤金一郎家長らが、火事に気づきその火光で大膳亮らは発見され銃撃を受けた。
大膳亮は危ない所だったが逃げ帰り、警戒が厳重で偵察は不可能と報告した。勝頼は怒って再び偵察を命じた為、大膳亮はやむなく再度敵陣に接近したが、銃撃され二弾を受けて傷つき、従者に助けられて明け方近くに漸く本陣に戻った。
大膳亮は勝頼に攻撃の中止と、敵から討って出るのを待ち受けて戦うよう諫言した。
――としている。
諸文献を探索しても、この記事が載っている原典の古文書はまだ見つかっていないが、この記事が事実であれば定重も敵の銃弾に倒れたのかもしれない。
この小幡大膳亮は小柏氏が同道して、共に戦っているところから上州小幡氏と見られるが、小幡氏の系譜の中にそれらしい名前は見られない事から、甲州小幡氏という線も排除しきれない。
ただ甲州小幡氏の系譜にも大膳亮の名前は見つからない、改名したものか、傍系だった故に記載されていないのか、今は詳らかにする事ができない。長篠で討死したのは小幡上総介信真の弟(重貞の三男)昌高である。
「信長公記」によれば武田軍の攻撃は第一波が山県正景の部隊、第二波の突撃が武田逍遥軒信廉の部隊、第三波が小幡一党(西上野の赤備え隊)第四波が武田典厩信繁の部隊、第五波が馬場美濃守信房の部隊であった。
これ等の諸部隊が、それぞれ何波かに分けて突撃したものとみられる。織田徳川連合軍側は、その陣地を空堀や馬防柵、身隠しと銃眼など三段構えに作り、これが二重、三重、四重に構築してあった。
待ち構える鉄砲の数は三千挺弱とされている。長雨が上がった翌朝のことであり、
朝靄が立ち込め、靄が晴れても風はなく鉄砲の硝煙で視界は全くなかったという。馬を乗り入れれば、馬の腹まで泥田の中に埋もれてしまう泥濘の海である。
赤具足を着けた小幡隊は徒歩にて這うように進み、長槍と大刀で銃弾の雨の中を突撃して行ったとされる。
名和弓雄は設楽原合戦の際の武田軍の人数は18,600人、突撃して銃撃され戦死した人数は12,000人と推測している。この時武田勝頼は三十歳であった。
「信長公記」は信長の家臣太田牛一が書いた物であり、自身の日記を元にして書いたとの説もある。
「三州長篠合戦記」は設楽原の近くの乗本村の名主、阿部四郎兵衛忠政が書いた物で、阿部四郎は織田徳川連合軍に協力し、野戦築城に従い奇襲攻撃の案内もしたという。
長篠城攻撃と設楽原合戦を、織田軍の陣営の中にあってつぶさに見聞していたとされる。「徳川実記」を見ると勝頼は血気の勇者とあり、短気で合戦好きな若者という印象を受ける。同書によれば、武田勢は二万余騎、徳川・織田連合軍は七万二千とあり、五月雨が強く降っていたとある。
「備えの前に堀を穿ち塁を築き、柵を二重三重にかまへ鉄砲数千丁を撃たす、血気の勝頼夜中より勢を繰り出す、山縣昌景、小幡上総貞政、小山田兵衛信茂、典厩信豊、馬場美濃信房、眞山、土屋、穴山、一條など名ある輩入れ代わり入れ代わり柵を破らんと烈戦する。」
と記している。しかし鉄砲の威力により人塚が出来るほどに敵を打ち倒したという。ここに信玄の時より、名を知られた武田方の信玄の弟兵庫頭信實、山縣、内藤、土屋、眞田、望月、小山田、小幡などが死にもの狂いで戦い討死していった。
武田方の戦死者一万三千余騎、連合軍側は六十人ほどだったとしている。
定政小幡孫一を救う
定重が戦死したため弟の定政が家督を受け継いだ。定政は当初左馬助を名乗り、後に源重郎と改めた。法名は浄久である。小柏系図には
父、兄と共に武田に属した。兄定重戦死により家督を相続した。天正十壬午年織田信長のため武田家が没落し終わりぬ。
然る後、信長公西上野を統一し是を治める。その家臣滝川左近将監一益が管領となり、上野国に来て厩橋城に住む。然る処、同年六月二日信長公父子明智光秀のため、京都において生(殺)害さる。故に一益本国に帰る。是によりて当州の諸士悉く小田原の北条家に属す。
同十五丁亥年夏小幡上総介の甥小幡三郎叛逆を企み宮崎城を陥れる。折から小幡上総介は小田原城に詰めていて、宮崎城中は無勢にて防戦叶わず。上総介の妻子は宝積寺へ落ちのびた。
この時、宝積寺は敵勢のために焼かれる。この時僧侶が上総介嫡、孫市を介抱し小柏定政の舘に逃がした。定政は大喜びし是を深く隠しおいた。然る後、上総介の留守中、小幡三郎の時、定政は忠勤し戦功も挙げた。
その後、定政は宮崎城に孫市(郎)を送り届け、宮崎城は丁重に受け入れた。上総介はこの時大喜びし、感謝すること一方ではなかった。
同十八庚寅年七月小幡信貞旗頭共定政籠城于小田原。此処にいたり、太閤秀吉のため北条家没落す。
故に定政浪々の身となり小柏村に住む。尚、委細の記録は別記に記してある。
とある。この記載には彦三郎が三郎とあり、孫一郎が孫市としてある。
彦三郎の彦は別記から系図に写す際に脱字したのか、系図を書き写していく際に脱字したのか、或いは名前が三郎と呼ばれていた、もしくは三郎と思っていたなどが考えられる。
両名の名前の字が他の諸文献と異なっているのは、小柏氏正系図が他の古文書を参考にしなかった事になり逆に真実味が籠っている。これらの事は、小柏家には別の古記録が伝わっていた事を裏付けるものである。
やはりこのエピソードの骨格をなす事実が存在したと考えられる。孫一郎は上総介信真の弟の子であり後に養子とした。
子孫の小幡龍蟄は言う。孫一郎は孫一・孫一郎と書かれた両書簡があり、始め孫一と称し後に孫一郎とお改めありしなるべし。
さらに龍蟄はその著書「幡氏旧領弁録」の中で、宝積寺合戦を天正十五年の出来事としているので、この系図の記事と合致し異なる点もない。
尚、小幡伝来記には孫市郎と記載されている。この他、小柏系譜の「上総介嫡孫市介抱之」の部分を孫と市の間で切り「市介」としている文献を見かけるが、市介という名前はどの小幡系図にも記載されていない。
宝積寺住職、西有穆堂はその著書「因果の水鏡菊が池」の中でこのエピソードが宝積寺合戦であるとしている。同書にも母子で小柏舘に落ちのびたとある。確かに小幡方面から、敵が押し寄せて来たら寺の裏山に逃げるのが理に叶っている。裏山は懐深く、土地の者でなければ不用意に踏み込めない。
また近隣を見渡しても裏山から峠を越えて、小柏舘へ逃げる他に適当な城舘もない。
末尾の方は少し意味が判り難いが、小幡信貞が一方の旗頭として小田原籠城に参加して、定政も共に籠城したとの意であろう。小幡上総介信貞(真)は天正十五年には軍議があり小田原城に詰めていた。
その後一度上野国に戻り、再度天正十八年に小田原城に入ったのであろう。定政が小田原城に入ったのはこの時である。
定政の長女は小柴与兵衛兼行に嫁ぎ、二女は三波川の飯塚彦衛門常清に嫁いでいる。三女は小此木吉左衛門兼佳に嫁いでいる。
何れも日野七騎と云われた武士団の面々と思われる。三波川の飯塚家は大変に古い旧家であり、代々名主を務め戦功をも顕わした名家である。近世においては政治家になっている。
その倉に所蔵されていた三万点ほどの、大量の古文書は県に寄贈され文書館において整理されている。研究者や関係者にとって貴重な歴史資料となっている。三波川に飯塚姓は多いが、三女の嫁ぎ先も飯塚名主家の親戚である。
第三章 お菊伝説
宝積寺のお菊伝説
お菊伝説は幾つかありそれぞれ少しずつ違っている。また全国各地に伝わってもいるが、この各地に伝わっている伝説は、各地に散って行った小幡氏の子孫や家臣、関係者によってもたらされたものという。当事者の一端とも云える宝積寺が著した宝積寺史によって詳しくみてみよう。
宝積寺史には大略次のように記されている。
宝積寺の菊女伝説は有名で、群馬県で「お菊さん」を知らない人はいない。この伝説を最初に記録した本は不詳だが、知られているのは1743年の序がある「小幡伝来記」である。この本は「上野志料集成」(大正六年)の中の上毛伝説雑記巻十一に
「小幡伝説」という題名で収録されている。
これによれば
国峰城主小幡上総介信真は、侍女菊が据えた食膳の椀に針が一本落ちているのを見つけた。信真はおのれ、自分を殺害しようとする曲者として菊を蛇攻めの仕置きにした。大きな桶に菊を裸にして入れ、蓋に穴を開けて多数の蛇を入れ、宝積寺奥山の池に沈める。
小柏源介(宝積寺史は源六)は猪狩りに来て池の辺を通ると、桶の中から女の泣き叫ぶ声がする。源介は弓の弭(はず)で桶をかき寄せ、蓋を破って菊と蛇を助け出す。菊は「今からお家に蛇が入っても怨みをさせません。このご恩は忘れません」という声とともに死んだ、このことから小柏家はたとえ毒蛇を踏んでも刺されることなく、その子孫は繁栄した。
菊の母は「無念だお前が死んでも、霊魂があるなら小幡家へ祟りをなせ。その印を見せよ」と懐から煎りゴマを取り出して蒔くと、三日の後に芽生えた。母は「万願成就即現怨霊」と喜んだ。それから菊の怨霊は小幡家へ祟りをするようになる。ゴマは年久しく経った今でも池の辺に生えている。
小幡家は露地にも園にも菊を植えない因縁はこれから始まった。その後、菊の怨霊を慰めるために、宝積寺は母と姉妹姪と菊を入れて五大姉にまつり、朝夕回向したという。―――としている。
小幡伝説は信真(のぶざね)の没後百五十年経って成立した本である。小幡伝説を典拠として、菊女の伝説を書いた代表的な本は次のものである。上毛菊婦伝、因果の水鏡菊が池、上野人物志、群馬県北甘楽郡史、小幡町郷土読本、甘楽町史、行田史譚、諸国百物語。
信真(1540~1592年)は実在の人物である。菊女の出生地は上毛菊婦伝(小幡龍蟄)では、甲斐国巨摩郡藤井庄の菅根正治の娘としている。そして「予が家の菩提所宝積寺の和尚は、菊の引回さるるを見物し、命乞いをもせざる故、その後寺へ祟りをなし、また予が家にも祟りをなす由、既に序に弁ずる如し。」
としている。
「春山大明神の記」(南牧村星尾仲庭の市川家伝説)もこれに従っている。上野人物志では多野郡神川村生利(万場町)新井右近の娘としている。また信真夫人が実家の箕輪城から連れて来たという説もある。どの本も実在の人物としている。
菊女を助けた小柏氏の名は、小幡伝説、上野人物志では源介。上毛菊婦伝、因果の水鏡菊が池では源助。群馬県甘楽郡史、小幡町郷土読本では源六としている。小柏源六(定重、高政の子)は、天正三年(1575年)長篠の役で戦死した実在の人物である。
「因果の水鏡菊が池」は、宝積寺の四十六世住職が書いた脚本であるが、蛇の他に百足を入れたとしている。「ヘビもムカデもどーけどけ、小柏どんのお通りだ」のわらべ歌は有名である。宝積寺の山門は建ててもすぐ燃えると、山門のないことが寺への祟りのシンボルとなった。
しかし、山門連続焼失の確実な資料はない。行田史譚では、松平忠明の家老山田大隈守が侍女の菊を刑に処したとある。山田家は庭にお菊稲荷を祀ったという。諸国百物語に見える菊女伝説は、兵庫県の姫路城の話となっている。前橋藩、安中藩にも同様の伝説がある。
宝積寺 
上毛菊婦伝を著した小幡龍蟄(りゅうちつ)は信真十一代の孫であり、自分の先祖は伝説のような、残忍な武将ではないという同族の絆もあって、菊女の仕置きは信真の出陣中に、妻が自分の下女を仕置きしたものと考えた。
安政五年(1858年)龍蟄は、妙義町中里村の菊女の墓に添碑を建てた。
「小幡伝説」成立後三年の後、二十六世乙禅叵甲が記した文書には五つの法名が記され、右は菊女の法名なりとしている。次に一つの法名があり、右菊女の母の法名なり、右五大姉は当山開基の小幡上総介殿の下女なり。
幽怨代々小幡家の奥方へ祟り候由、折々申し来たれば、すなわち毎度遺し贈る大姉号なり。延享二年。とある。祟りのあった都度、江戸から使者が来て回向を頼む。時の宝積寺住職は、その都度読経して改めて贈った法名が五度になり、菊女のことを五大姉と称したという。
後に宝積寺は菊女を金毘羅大権現として祀り、熊倉山菊が池の傍らに石祠を建てて寺の鎮守とした。こうして宝積寺の守護神となり、祟りはなくなった。各地に散在する小幡氏も、色々な形で菊女御霊をまつり供養している。例えば江戸小幡氏、松代小幡氏、榛名小幡氏。
明治からは宝積寺の菊縁日は四月二十八日となり、白倉神社(宝積寺が別当職)の春祭りと重なり、宝積寺から白倉山への峠道は参詣者の列が途絶えなかった。この行事はその後、太平洋戦争で中絶した。昭和63年には全国の小幡氏が宝積寺に参集して「国峰小幡氏に集う会」を発足させた。
平成2年には集う会は小幡氏四百年供養法要を営み、菊女金毘羅大権現ならびに小幡氏歴代の大供養を行った。平成5年には本堂前に菊女観音菩薩立像が建立された。
「甘楽町史」によれば、宝積寺住職西有静観氏が過去帳・書類に従って書いた「菊ヶ池」という芝居があるとして、他に幾つかの説を紹介しているがいずれも大差ないものとなっている。「妙義町郷土史」に、妙義町大字中里五輪平の菊女の墓の記事がある。妙義の菊女の墓は安政五年四月に、小幡氏の十一世孫・信州松代藩士の小幡長左衛門が建てたと墓碑に記されている。(同町史)
宝積寺 お菊様 
因果の水鏡菊が池
次に大正十年に宝積寺住職・西有穆堂によって、書かれた「因果の水鏡菊が池」を概観していこう。原文は長文なので筋のあらましを記す事にする。尚、原文では小幡家は「小旗」の表記になっている。
第一幕は妙義山参詣の場である。主役は小幡上総介信真である。お菊は妙義町中里村の庄屋菅根正治の娘となっている。山桜に飾られて美しい妙義山麓の妙義神社の紹介から物語に入っていく。
妙義神社 
神社には何百段もの階段があり、社殿そのほか立派に壮麗な建物があり、裏山の妙義山は奇岩、怪石が、ががたる絶壁を織り成している。信真は家老の森平策之進他十数名の供侍を連れて、通り道の一ノ宮貫前神社の参詣を終え、領内の妙義神社へ参詣にやって来る。
時代は秀吉の小田原攻めの少し前である。武田信玄の二十四将の時代を経て、今は北条氏直に仕えている。この時、妙義神社へ参詣を終えて帰路についていた菅根正治夫妻とお菊は、領主のお通りと聞き平伏していた。信真はこの時ちらりと見ただけであったが、お菊の輝くような美貌は心情に響くものがあった。
信真は家老を通してお菊の素性を問いただした上で、一両日中に殿中へ罷り越すよう申し渡した。
第二幕は城内酒宴の場である。お菊は既に侍女として、城内に奉公し一年が過ぎていた。はや、一目ぼれしていた信真の寵愛を受ける身となっていた。
菅根正治は甲州巨摩群藤井の庄の出身であり、信真が信玄に仕えていた頃からの旧臣としている。
信真はお菊に黄金一封を与え、正治を重い役に取り立てて用いる旨を伝えた。この後、お菊のお酌で酒宴に移っていく。この時お菊は十九歳。信真は世継ぎの信直が五歳で早世し世継ぎの子がなかった。侍女たちは別間に下がってからお菊に嫉妬し、あたりちらす。
やがて信真は、またお菊を呼び寄せ奥方も下がらせる。
第三幕は小田原出陣の場である。国峰城からは赤城山、妙義山、榛名山の秀峰が望める。信真の妻は箕輪城の長野業政の娘である。お菊は、子供のない時には観音様を振興すれば子供が出来ると聞いています。
宝積寺の住職からも、大本山総持寺の螢山禅師の母が観音様を信仰し、一日に観音経を三十三編も読み、南無観世音菩薩と三万三千参百参十三編唱えて、長い間信仰を続けたところ螢山禅師が生まれたという。宝積寺の観音様は霊験新たかな、観音様で小柏源助定重公の守り本尊と聞いています。
この観音様に殿様の武運長久を祈り、奥方様にお子様が出来ますよう祈っています。と出陣前の信真に話した。この後も二人きりで酒を酌み交わすが、信真が奥方に子供が出来なくても菊に出来ればよいと言うと、お菊は実は妊娠して既に五ヶ月であると打ち明けた。きょう言おうか明日言おうかと思案していたが、明日は出陣との事、思い切って申し上げますと言う。
信真はあっぱれあっぱれ、世継ぎに致すとして、正宗の短刀とお墨付きをお菊に与えた。
第四幕はお菊折檻の場である。信真は小田原へ出陣し留守である、奥方八千代の君は侍女の初代を呼び寄せ、菊女に与えた短刀と墨付きを奪い返すよう指示する。初代は機会を捕らえて、お菊の留守にその居間へ忍び込み、手文庫より短刀とお墨付きを盗み出す事に成功した。
嘆き悲しむお菊を、お殿様より拝領の品を盗み出されるとは油断千万、御殿奉公が勤まらぬぞと奥方は責める。今朝ご飯の中に、縫い針が二本入れてあったのもお前のやった事だろうと更に責め続ける。
拝領の品を無くしたとは嘘で、隠し男子がありその男に渡しておき、自分を殺して国峰城を乗っ取る積りであろうとした。
殿様の子とは偽りで、その隠し男の子供であろうと無実の罪を着せるのであった。必死に弁解するお菊の話は聞かないで、集まって来た他の侍女と共に散々に殴ったうえ、山田軍兵衛に命令して蛇責め百足責めにする事とした。
この時、柴田外記が現れて自分は菊の守護を命じられている者であり、この処刑は承知出来ぬと反対した。奥方は殿の留守を預るは自分であるとして、山田と共に柴田を叱咤し、奥方は閉門を申し付けた。山田は更に、腹の子はあの柴田の子であろうとお菊を責め続ける。
第五幕は宝積寺門前の場である。
時は天正十四年九月十九日である。東に赤城山、西に妙義山が望め、七堂伽藍が完備している曹同宗の古刹宝積寺門前である。国峰城からは約二十町の所、駕篭に載せられたお菊が来る。宝積寺の後にある熊倉山を一里ほど登ると、池がありそのほとりに篭岩と呼ばれる石窟がある。
この中に石櫃をこしらえ、蛇や百足を入れてお菊を責め殺そうとする。宝積寺は十万石の格式を持ち、末寺五十三寺、孫寺を含めると百寺ほどになる。開基は国峰城主小幡実高である。
お菊は一縷の望みを持って、住職への面会を山田に懇願する。山田は許可しなかったが、他の侍たちの意見を入れて住職に会わせる事にした。
女人禁制の山なれば、第十世魯嶽禅師が山門まで出て、直々に山田に会い助命を取り計らう事となった。魯嶽はお菊に向い、当山は小幡家の開基なれば、なにかある時は一肌脱がねばならぬ、そなたに無残な刑罰を行う事はお家の為にもならぬ早速、国峯城へ行き奥方に助命の儀をお頼み申す。と言う。
尚、山田他同行の侍たちに向って、これから城に上がって奥方へ七つの膝を八重にも折って、お頼みすれば宝積寺と深い縁の小幡家のこと、きっと聞いて下さるに違いないしばしお待ちくだされと言う。
この後、寺側と侍衆の間で押し問答が続くが、暫くの間この場所で住職の帰りを待つ事になった。
第六幕は熊倉山蛇責めの場である。熊倉山の頂上に周囲七、八町の池がある。青く澄んでいる水が満々と湛えられて、そのほとりに岩石が峨ゝと聳えている。日が暮れるまでは山門の前で住職の帰りを待っていたが、山田が痺れを切らして池の所まで移動して来たのであった。
この時、急を聞きつけたお菊の母たまが、狂気のごとく髪を振り乱してこの場所へ駆けつけて来た。無実の罪で蛇責めにあい殺されるとは、あんまり無慈悲です。後生ですから助けてください。叶わぬのなら私を身代わりに蛇責めにしてくださいと、山田を伏し拝み懇願する。
お菊に会わせて貰ったたまは、「いまはの際に会えたのはせめてもの慰め、菊死んでもこの怨みは忘れるな、丁度ここに親類から貰った煎りゴマがある、これを池のほとりに蒔くから花を咲かせて見せなさい。」と言い、お菊は「蛇や百足にこの身が食い荒らされようと、恨みに思うのは無実の罪に陥れた奥方や侍女、この後はゴマに花を咲かせ、小幡家と宝積寺に祟りをなします。」と答える。
居合わせた寺僧を初めとして、同行して来た侍の中にも処刑を躊躇し反対する者もあった。殿の留守中に、その寵愛する侍女を処刑しては、後の処分が恐ろしいという者もあった。
たまは夫の正治と日頃仲が悪く、しかも侍女初世の父親でもある山田に最後の恨み言をいう。菊がおってはお前さんたちの邪魔になるので、謀を廻らし菊を無実の罪にでっち上げた張本人であろう、言い訳はあるかと詰め寄る。
住職もいまだ帰らず、山田は矢庭にお菊親子を石櫃の中に押し込み、外から鉄の錠を掛けてしまった。その時、一人の侍が先ほどの煎りゴマに花が咲いているのに気がついた。
ここに、熊倉山に鉄砲を担ぎ猪狩りをしていた小柏源助定重公が、お菊親子の悲鳴を聞きつけて駆けつけて来た。
一旦下がった柴田外記も、この時になって再び駆けつけてきた。定重公は、吾こそは、武田信玄二十四将の一人、小幡上総介信真公とは親友にして、平重盛の末孫、小柏源助定重なるぞ、汝らは何者ぞ、鏖(みなごろし)にしてくれん。
とのたまう。
山田他、侍衆は敵わないとみて、逃げ惑うがたちまち定重公と柴田に皆殺しにされてしまった。定重公が鉄砲のこじりで、石の櫃を打ち破り既に虫の息のお菊親子を助け出す。小柏公は腰の印籠より薬を取り出し手当てをする。
石の櫃よりニョロニョロと這い出す蛇と百足を、ハッタと睨みつけ汝等虫類の分際にして、万物の霊長たる人間を食い殺すとは何事ぞ、汝らを皆悉く皆殺しにしてくれん。と大音声で、鉄砲を振り上げれば蛇は鎌首を下げ、百足はうなだれ逃げ去ってしまった。お菊親子はかわるがわるお礼を申し述べる。
お菊は最早この世の見納め、私の亡き後は小柏様のお家繁盛を守護いたします。無事息災にお暮らしなされて下さいませ。この後、私を信ずる者あれば何事によらず、願いを聞き届けんと言い残し、息を引き取った。
定重公を中心にして柴田、寺僧は遺骸をかたずけ、お菊親子の遺体は宝積寺へ運んだ。
第七幕は宝積寺戦争(合戦)の場である。時は天正十五年に移っている。この合戦譚では、寺の立場を考慮したものか、小幡伝来記などの通説とは違って、彦三郎と図書介の立場が入れ替わっている。
将軍家より御朱印として五十石を賜り、山林一里四方を所有し山林、田畑一切無税であり、門前百姓三十戸を擁する関東の巨刹宝積寺。奥方八千代の君は仙洞院に入り、尼となっており侍女一同も、これに同行してそれぞれ尼となっていた。
信真は小田原落城の憂き目にあい、甥の彦三郎と奥方の兄、小幡図書介は不仲になり不穏な空気が漂っている。
図書介の家来,丹生五郎景義が宝積寺を訪ねて来て、彦三郎とその妻子を匿っていると聞いたが、事実ならば渡して貰いたいと申し入れる。この時、寺はそのような事実はないと突っぱね、五郎は弓矢を持って再来すると一旦引き下がった、
魯嶽は方丈の間で彦三郎と会し、今夜にも図書介の夜討ちが入るであろう事を告げる。彦三郎は、宇田城主図書介と戦い、武運拙くここまで逃れてきたが、残兵もいることだし、一戦交えて打ち破る存念です、ついては寺にも迷惑を掛けるけれども力添えをお願いしたい。と言う。
魯嶽も今は覚悟を決め、寺衆七十名をもって加勢いたし、寺が焦土となるまで戦うので安心くださいと彦三郎を励ます。彦三郎は、図書介は八千代の父の二男なれど、腹黒い者で、八千代をそそのかしてお菊を蛇責めにしたと聞いている。小柏公が助けた時には、無念の形相悪鬼羅刹の如きで、小柏公の厚い手当て・介抱もむなしく最後を遂げたとの事、拙者小柏公より聞きました。
この事があってより、小幡家によくないことが続きます。と言う。魯嶽は、拙僧も奥方に因果の道理をお聞かせし、小幡家に必ず悪果をもたらす、助命の事が適わないのであれば、拙僧もこの場で自害いたすとまで申し上げたが、お聞き届けなく時間ばかりが無駄に過ぎてしまったのでした。と言う。
別れの杯を汲み交わした後、魯嶽は彦三郎の一子、玉太郎を山道伝いに、二里ほど離れた多野郡日野村の小柏にまします、小柏源助定重公館へお預けなさればと薦める。続いて魯嶽は文智和尚を呼び、玉太郎と母(弥生)を小柏舘へ案内し、このたびの合戦に御加勢を致し下さるようお頼み致せ、と命じた。
文智も小柏殿は当寺の大檀越なれば、当寺の危急を思し召し、一刻も早くお越しくださる事と存じます。と彦三郎を励ます。
第八幕は小柏舘の場である。御荷鉾山を前に眺め、清流そうそうと流れるほとりにある小柏源助定重公の、屋敷は広大なる構えにて家来の屋敷数十棟を数え、立派なる欅の門構え。平重盛公末孫らしく山林八百町歩を有し、田畑数百町、土地の百姓は皆悉く小柏家の領内にありて、家来同様に召し使われ小柏公の権勢は大名と同じであった。
夜は遅かったが、門番は家老の山崎覚太夫へ取り次ぎ、早速小柏公の居間へ通された。文智は図書助が五百の軍勢で夜討ちに来る由、ご出陣・御加勢願わしゅう存じますと述べた。小柏公、家老一同に出陣の準備を命じ、小柏源助定重公が大将となって一散走り、二本松峠まで至れば遥かに紅蓮の炎が見える。
この頃、図書介は巌空坊覚禅に討ち取られ、丹生は彦三郎に討たれ劣勢になっていたが、小柏勢が攻めかかり余すところなく討ち取ってしまった。彦三郎は小柏公の手当てを受けながら、加勢かたじけなく存じまする。
魯嶽禅師は群がる敵兵の中にて戦っていましたが、丹生が本堂の裏手より火をつけるに至り、紅蓮の炎に包まれ、禅師は釣鐘を背負って鐘が淵へ飛び込みました。天狗と言われた七尺五寸の大入道、巌空坊覚禅は開山堂側にある一枚岩の上に、立ちはだかり立腹斬って果ててござる。と言う。
そしてこれより小幡家を再興し、お菊親子の亡霊の供養を営み、宝積寺も小柏様と相談いたし再興いたすでござろう。と言う。文智へ後片づけを託し、彦三郎と小柏公は小柏屋敷へと移動する。
第九幕は宝積寺の末寺仙洞院庵室の場である。
小幡町の仙洞院は小幡家の開基なり、仙洞御所より琴を賜り、その琴を仙洞院に納めてその名を寺号とする。後ろに山があり、前には雄川のそうそうたる流れの音を聞く。八千代の君はお菊親子を無実の罪にて、蛇責めにしてからというもの、毎夜のごとく、お菊親子の亡霊に悩まされていた。
安らかな日は一日もなく、黒髪を断ち黒衣をまとい、尼となった侍女と共に仏道を修行し供養に勤めている。侍女たちも八千代と同様にお菊の亡霊に悩まされている。八千代はしきりに反省し、魯嶽禅師が助命嘆願に来て、因果の道理を説いてくれた時に何故、聞き入れなかったのか悔やまれてならぬ。
あの時は、わらわは嫉妬の炎が燃え立っていて承服できなかったが、このままではわらわたちは皆狂い死にしてしまうだろう。思えばお殿様も小田原の役で戦死遊ばされ、宝積寺も合戦で悉く灰燼となり、魯嶽禅師も相果てなされた。今日はお菊親子の月命日、お位牌を安置して供え物を捧げ、回向を致そう。と侍女たちと経を読み追善回向を行った。
その夜、庵室に現れたお菊の亡霊に八千代は狂気となって、まだ足りぬかと長刀を手にし斬りかかる。驚いて止めに入ってきた侍女初代も、八千代には亡霊に見え、突き殺してしまい、更に他の侍女も皆、斬り殺したうえで自害してしまう。
第十幕は園枝取殺しの場である。時は延享二年、百六十年後である。常に雲水五~六十人が修行し、住職は三十六人の供ぞろえで道中する宝積寺の場である。寺は再興されているが、山門は何度建築するも焼失すとして今も山門はない。
小幡家の家老、神成仙右衛門が住職へ面会に訪れる。
殿様のひとり娘、園枝様が病気になり一向に快方へ向わない、夜中にむっくり起き上がり、わらわは百六十年前蛇責めにあいし、菊女の亡霊なるぞ、汝ら我母たま殿の墓を無縁となし、供養も怠りたる段、真に不届き至極なり、我母親の石碑は小幡家廟所の左側にあり、ゆめゆめ追善供養を怠る事なかれ、怠るなれば一家親族、残らず皆殺しにしてくれん。と言う。
言い終わるとばったり倒れて死亡されてござる、その際お菊親子の命日は九月十九日なりと申せし故、追善供養・園枝様の葬式をお願いしたい。という。
副寺、道智は神成をお菊親子の墓地へ案内し説明する。初めに仏心大姉と戒名をつけ、葬儀しましたが仏果圓成致さず、亡霊が夜も昼も寺に現れる故、今もお菊親子の座敷があります。
それより歴代の住職が進山式のたびに戒名をつけかえ、五度の葬儀を行いましたが、未だにその怨霊は退散しませぬ。石碑に仏心大姉、妙心大姉、蓮心大姉、仏蓮大姉、心仏大姉とあるはこのためです。と言う。この後、本堂においてお菊親子のため、大施餓鬼の大法要が行われた。
第十一幕は菊女金毘羅大権現大祭の場である。
時は明和五年である。熊倉山の菊が池の辺に、菊女金毘羅大権現の碑がある。その両側には眷属夜叉、菊が池山神との彫刻がある。左横には宝積寺鎮守と掘られた石碑がある。この場所は菊女親子が蛇責めにされた所である。石碑の前には小幡家奉納の華表があり、新しく建立された鎮守堂の周囲には、旗やのぼりがたくさん立てられている。
子供たちは「小柏どんのお通りじゃ、蛇も百足もどーけどけ」と歌っている。小柏源助公が、お菊様蛇責めの時、お助けなされたというので、こう言いながら歩くと蛇も百足も寄ってこないと言い伝えられている。
今日は菊女金毘羅大権現の初めての大祭であるので、老若男女が朝から一万名ほども参詣に訪れている。曹洞宗の名僧知識、万仭禅師が宝積寺へ住職せられ、菊女を金毘羅大権現に祀られ、大般若の大法要を行われこの引導によって、成仏得度を致した。
かつ、小幡家・宝積寺は言うに及ばず、菊女金毘羅大権現に心願をかける者は、何事も成就すると言い伝えられている。
菊女の石塔を粉にして飲めば、万病平癒するとも言われ、妙義山の麓、中里村にある菊女の墓にはいつも、白蛇が住みお菊様を守っていると言い伝えられている。お菊様に願を掛ければ、子供の虫封じが出来るといって願掛けする人も多い。
宝積寺本堂においては、お菊様親子の為、万仭禅師が導師となり、一山の大衆五十名大施餓鬼法会を行い、参詣人一同の所願成就の為、大般若法会が営まれた。
そして万仭禅師は駕篭に乗り、大衆五十名、檀徒総代、檀徒数百名を連れて熊倉山、菊が池へ登り、大法要を営む。
小幡孫一郎真之公も参詣し、法要に列席せられた。
参考文献 宝積寺宝物小幡静氏著菊女一代記、過去帳、書付類。
とある。
お菊母子の墓所

尚、大正十一年に小幡町で開演した東京大歌舞伎、藤森座の広告が載せられている。要略を次に示す。
中央に縦に印刷されたタイトルが「菊女金毘羅大権現一代記」であり、副題のようにして最上段に横一列、右から「お待ちかねの菊女神霊劇開演」とある。
口上を述べた後、由来として「この狂言は、天正年間北甘楽郡小幡の城主小幡上総助、城内に起こりし愛妾菊女悲惨の最期なせし、大大悲劇にして本郡日野村小柏八郎右衛門の義勇を奮いし、実説を骨子としたるものにして、当地方としては尤も因縁深き劇なり。
この劇の主人公菊女の霊は、いまなお小幡村宝積寺に菊女金毘羅大権現と祀られ、その守札は、商売繁盛家内安全子供の虫除養曩(さき)には最も不思議のご利益あり、今尚、参詣者引きも切らさる有様なり。
◎特に開演中御信仰の御方には、御守札五百枚限り毎夜差し上げ候。」
との記述がある。
源六定重が八朗右衛門と名乗った事は、記録には見当たらない。小柏氏にあっては、世襲名ではないが、近世になって八郎左衛門を名乗る人は多かった。それ以前に六郎或いは六郎右衛門を名乗った人は三人ほどいるが、伝説の文献などに見かける八郎右衛門を名乗った人物は幕末の重基だけである。
八郎左衛門と混同したのではないかと思われる。
二本木峠と小柏峠
前述の第八幕の文中に「二本松峠」の地名が出てくる。この峠名は現在の地図上に見当たらないが、何処であろうか。
みやま文庫発行の「群馬の峠」によれば「上日野の小柏から山を越え、甘楽町白倉・轟・小幡町へ行く途中に二本木(にほうぎ)峠がある。標高は820m。」とある。
これだけ読むと接続する両町の位置関係から、二本木峠は現在の小柏峠と思える。
しかしよく読むと、次に「中峠」の紹介がありその説明に
小字名調書の甘楽郡小幡村に「中峠」がある。「甘楽町地名考」によると、二本
木峠の北、白倉神社の西方にあり、中峠を通る道は小幡・轟から入り、二本木峠で白倉から至る道と合流した。
と記載がある。また同書には二本木峠の隣の項に「水越峠」が紹介されていて、標高800mで、小柏~甘楽町白倉とある。水越峠もまた現代の地図には現れない。
「小柏峠と天狗山」(天野H・P)によれば、小柏峠には近代に置かれた「小柏峠」という手書きの標識があり、一体の石仏があるという。更に峠から少し小柏側に降った所に一体の道祖神があるとしている。
そして無名峠から小柏峠は徒歩で10分という、標高もさしたる違いはない。無名峠もまた地図には出ていない。しかし、以上の資料を総合的に検証して、何れの記述にも矛盾しないよう峠の位置を比定してみる。
甘楽町の小幡・轟側から入り山道を登って行くと、旧白倉神社の西にあたる場所で左右に分かれる分岐がある。ここが中峠である。左に行くと旧白倉神社に行き、右に行くと上日野小柏方面である。
中峠で右に道をとり少し行くと二本木峠である。ここで(中峠で左へ別れて行った)旧白倉神社から来る道が左方から合流する。更に山道を小柏方面に進むと、稜線の少し手前にY字路の分岐がある。
ここを右へ行くと登山者が無名峠と呼ぶ峠に至り、無名峠から左に降りれば上平を経て小柏に至る、降りないで稜線をまっすぐ行けば焙烙峠に至る。
先のY字路の分岐点で左の道を辿ると小柏峠に至る。小柏峠から更に杣道を進むとまた分岐がある。右へ降りるとやはり上平へ至る、左へ進むと小柏へ至る。この左の道を降りた地点は、小柏舘の東の辺りへ繫がっている模様である。
これ等の杣道は国土地理院の古い地形図に全て破線で示されている。
また「小柏」の現在の道路から小柏舘へ向かって、舘の左端・西側に当る所に良く見ると細い杣道が見つかる。この杣道は北側の裏山へ登って行く道である。幅は50~60センチほどの物であるが、登って行けば小柏舘の東側から来た道と合流しているものと思われる。(途中に社が設置されていたか?)
「群馬の峠」には二本木峠と水越峠が併記されている。
したがって、この二つの呼び名は同時に存在していたと推測して差し支えない。
結論となるが、この水越峠が現在小柏峠と呼ばれているものであろう。「因果の水鏡菊が池」に記載の「二本松峠」という名称は、二本木峠の誤植、または誤りではなかろうか。松の字と木の字は似通っている。
登山者が呼ぶ無名峠の名称は文献にも地図にも現れていないが、小柏側から登って小柏峠を左に行った所である。(先に述べた場所)
正に名前のない峠である。二本木峠は先に述べた場所にあるので、上日野の中心地であった小柏から小幡・轟に行く時には必ず通る事になる峠であった。また逆コースの場合も同様である。
小柏氏が大檀家であった宝積寺との往来も当然にこの道を通った。江戸期以前はこの道が街道然として使われていた。会場から秋畑那須へ行く遠回りのルート(小峠)はあまり使われていなかった。上日野地区から甘楽地区へ行くルートは、他に奈良山から焙烙峠を越える道、矢掛から亀穴峠を越える道(ちちぶ道)、鹿島から小梨峠を越える道などがあったのである。
山名・地名などは何らかの由来(伝説や豪族名など)に、基づいて付けられる事が多いが「水越峠」については水越という地名もなくその由来が不明である。標高800mもある高い所を水が越すわけもあるまい。
とすると「三越」が転訛したものと考える事も可能になる。甘楽轟から登ると中峠、二本木峠、水越峠となり三つ目の峠が水越峠となる。峠を三つ越せば上日野に出られる。三つ越す峠、の三つめを誰言うとなく便宜的に「三越峠」と呼んだ事が考えられる。この呼び名は養命寺や小柏家に時々来ていた宝積寺の僧や轟の人、つまり甘楽側からの呼び名ではなかったか。
道が整備され、この峠道が使われなくなると次第に水越峠の名前は忘れられて、峠の直近の里・小柏の人たちが呼んだ「小柏峠」の名前だけが残ったとも考えられる。
また口頭で「三越峠」と耳から聞いた誰かが、「水越峠」と受け取り何かの文献に書いて、以後その表記が踏襲されていた事もあり得る。
いずれ解明されるまでの一仮説としておこう。
上毛菊婦伝
小幡龍蟄が著した「上毛菊婦伝」の序には、同氏の考え方が記されている。大略次のような記事である。
菊女は我十一代の祖、国峰城主小幡上総介平信真君の妻、長野氏の侍女なり、菊罪をなした事により罰するに、桶に入れ首を出し、桶の中に蛇数匹を入れて、熊倉山の池に浮かばす。
事実は菊の過ちではなく、同僚の中に菊を憎む者ありて、罪を着せようとして巧みにやった事という。この故に菊は罰を下されても、納得せずその後、五、六十年以前まで我家に祟りをなした由。龍蟄考えるに、菊は平日の事で知らなかったとしても、ご飯中に針があった事は罪になる。
時は戦国時代といえども、領主たる者は下の者を慈しむ仁の心を持たねば、一日も国家を治める事は適わない。これをもって考えれば、ご飯中に針が落ちてる事は、あるべからず。
もっとも、今の時代で考えれば、例え重罪であっても、このような罰はあるべからず。しかし、戦国の世なれば、重罪の者には蛇責めの類もあるべし。また実に、針の一事だけの事で法に照らして、過重な罰ならば例え君は怒りに任せて、蛇責めの事を命じても、諸臣が止めに入り諌めて罪を軽くするべきである。
それがなかった事を考えると、君は他国に出陣中での事で、夫人のご飯中に針があって、夫人が命じた事なので止められなかったのではあるまいか。
老臣ばかりの戦いであって、この為に後の世まで長く君の悪名とされたものか。実に菊の過ちではなかった事が、後日判明した時は、ひとたび厳罰に処せられたとしても、何らかの回復処置が取られたであろう事は疑いない。
昔より、そうした例は少なくない。してみると、小田原の役に出陣していた事は疑うべからず。嗚呼、時を得ざるものか。子孫は泰平の世に生まれ、これ等の事情を知らずして、世評を信じ一重に殿の御一矢(指示か)と思うべからず。
故に去年四月、上毛に行き、祖先の旧領古跡を弔い、累世の墓碑にお参りした時に、菊女の墓所を尋ねて行き、その墓に添碑を建て菩提を厚く弔ったのは、龍蟄は不肖だが君の意思を引き継ぐ意地であり、且つ見聞したところを記し、これを説明するは、子孫のためにする事なので失うべからず。
安政六巳未三月中浣 平信真十一代の孫 小幡内膳龍蟄識
「上野人物志」に記されるお菊伝説は少しだけ色合いが違う。次に紹介しておこう。
タイトルは「小幡氏侍女菊子」となっている。
小幡氏侍女菊子
菊女は甘楽郡国峰城主小幡信貞の領内、多野郡神川村生利の里正、新井右近の娘なり容色美しく、女の道にも優れたれば、遂に領主信貞の知るところとなり召されて侍女となった。
主君の覚えもめでたくなっていたが、ある時、菊女主君信貞に御膳を据える時に、平素、菊女の出世を羨望、嫉妬していた朋輩女中のために謀られて、御食椀中に一本の針があるのを、気づかずに膳を整えたのがお菊の運の尽きるところなり。
主人、信貞食椀の中に針があるのに気づき、大いに憤り針を取り出し、菊女を責めていわく、おのれ私に針を飲ませ、殺害せんとするか、身を寸ゝに切り裂いても飽き足らぬ、言語道断の曲者なり。
さんざん苦しませて、なぶり殺してやると下郎に命じて、蛇をあまた取り集めさせて、大きな桶に菊女を裸体にして押し込め、その桶の蓋に穴を一つ開けて、蛇を一匹ずつ入れて穴をふさいだ。
その中で、蛇は上になり下になり、カジリあい潜りあいしてそのうち菊女の身体の中へも食い入って、桶の中の動揺することすさまじく、菊女の泣き叫ぶ声、恐ろしく聞こえ人々肝魂を失いける。
そしてその桶を、国峰城付近の、宝積寺山の奥なる池に沈めたり、折から、小柏源介(ママ)なる侍、猪狩りに出ていて池のあたりを通りかかり、桶が浮かび女の首だけが出ているので、源介不憫に思い弓の弭(はず)にてかき寄せ、桶の蓋を打ち破れば、蛇が夥しく出て菊女は喜び、誰さまにてまします、と問いければ小柏源介なりと答える。
菊女申して、このご恩には今後お家の中に蛇が入っても、怨みごとは致させ申すまじ蛇も助けられ奉る、ご恩を忘れなく仕りますお心安かれ、と言う声と共に死亡した。この為に、小柏家にては例え毒蛇を踏んでも刺されることなく、子孫今にても栄えているという。
菊女の母、悲嘆に堪えず池の辺に来て、我娘の入りたる桶に向かい泣いて、言いけるは、汝、如何なる業因にてか、殺害の方法多くある中に、かかる無残な蛇責めにて、死亡するとは口惜しき次第にて、実に前代未聞の残虐なり。
千日の仕官、一朝の過ちとて、歴々ある習わし、飯に埋めた針不調法なる小科なるに、大科を以って、責めらるるは主人ながらも怨みあり。我娘、死してもし霊になりてあらば、一念の魂女となり小幡殿へ祟りをなせ。
我言葉が判るのならその印を見せよとて、煎りゴマを懐中より取り出して、我娘、小幡殿に祟らんと欲せば、このゴマに萌芽を出すべしと、池辺の土砂中に蒔き置きて、泣く泣く胸をさすりつつ、我が家に帰りぬ。
三日を経て、かの池辺に来てみると、そのゴマ、悉く発芽しており母は大いに喜び、我娘の霊に向って、手を合わせ愚願成就即現怨霊と唱えその菩提を弔いける。それより怨霊、小幡家へ祟りをなし天正十八年信貞、小田原に入城しその陥落するや秀吉の怒り甚だしく、十月二十八日切腹を命ぜられる。
その前、居城国峰城は前田・上杉の両将に陥れられ、嫡子信秀は一時浪々の境に沈降するに至る。ゴマは今に池の辺りに生ずる事、不思議というべく、また小幡家にては露地にも苑にも、菊を植える事はならざる因縁ここに起こるとか。
その後、菊女の怨霊を宥める為、菊と母、姉、妹、姪の五人を大姉に祀り、宝積寺祠堂に位牌を立て、五大姉と称し、朝暮回向に怠りなかりしと云う。
因みに云う。お菊がゴマ年々その株より若芽が生じ、ゴマの如き物が実るという。新井家、連綿今にあい伝え大正十一年お菊三百五十年忌法要を営めり。よって惨殺は天正元年の出来事なるべし。新井家当主、新井一郎と云う。
(小幡伝説、松田□氏 南毛名迹)
「北甘楽郡郷土史」では、次のような記事になっている。
「菊女の墓、妙義町大字中里字五輪平にあり。永禄の頃、甘楽郡国峰城主小幡上野介平信貞の配、長野氏の侍女、父は甲斐国巨摩郡藤井之庄より出でて、小幡氏の臣となりし菅根正治の娘なり。
一日、菊女主君の飯に侍する時、飯中に針あり、讒者の舌頭にかかり、蛇責めの刑を受く。本郡熊倉山中に池あり、桶中に蛇をいれ菊をその中に入れ、蛇集まりて菊女の肉を噛む。
悲鳴久しゅうして死すという。安政五年四月小幡氏十一世の孫、品濃国松代藩士小幡長左衛門、古墳の側に碑を立て、菊女の墓、九月十九日没す。」
お菊様の命日
|
菊女の墓 |
|
|
|
国峰城の菊ヶ池伝説には幾つかの説があり、疑問も多いが、この墓は妙義町にある。 その悲しい物語のヒロインに多くの共感者が出、人々の記憶に残り、その結果各地で語り継がれ、伝説となって残ることになったのではあるまいか。 |
* 写真と文、国峰城(小幡城)HPより
お菊の命日には幾つかの説がある。宝積寺46世住職の西有穆堂の「因果の水鏡菊が池」では、天正14年9月19日として救出したのは小柏定重とする。小幡龍蟄は、信真が小田原出陣の留守に起こった出来事と考えたため、天正17年と推定している。(龍蟄は当初、天正15年以前と考えたが後に訂正した)
「上野人物志」では、新井家が連綿として伝えてきて、三百五十年忌の法要を催した事から、逆算して天正1年の出来事としている。天正1年のことであれば、お菊を救出した侍は小柏源六定重であり、小柏氏正系図の記載と一致する。
「因果の水鏡菊が池」の記載は、救出した侍が小柏氏正系図の記載と同じく、定重であるが年代的には合わないものとなる。天正14年、或いは天正17年の事であったのなら、救出した侍は兄の後を継いだ定重の弟、左馬助定政、後源重郎となる。定重は天正3年の長篠の戦いで、小幡大膳介と共に討死しているからである。
小幡龍蟄の著した「上毛菊婦傳」の末尾に、小柏高政とその二男定政の記述がある。龍蟄の研究の一助にと宝積寺が、同氏の元へ送ってきた資料の中にそれがあった。小柏氏の牌名(位牌)の中から抜書きをした物という。
覚性浄林居士 小柏左馬介高政
光岩智明大姉 同人妻 小幡尾張守重貞姪女
昌室浄久居士 小柏左馬介定政 初号 源助
寛永十二乙亥正月四日
右者小柏八郎左衛門 牌名之内
と記された資料である。小柏系譜には定政が源助と名乗った記録はなく、後に源重郎と改めたとある。左馬助を名乗る前の幼名が源助であったという事はあり得る。
向陽寺の話では、位牌や過去帳は住職が変わったり、読み難くなったりすると、書き換える事があるという。
この際、一部の文字が変わったりする事も否定はできない。この資料に、何ゆえに長男の定重の名前がないのかは不明のままである。
ここにおいて龍蟄は次のように考察する。かくの如くなり、菊の一件は天正年間の事と、口碑にも伝えられていて、かれこれ考えると、山で猟をしていた小柏源助というのは、この定政なるべし。と書いている。
この後には、松代清野村龍泉寺に安置してある鎮守は菊を祭る所なり、(我)曽祖父義正君の代の書面に、年来安置の鎮守とあるのでその以前、更に古くから祀っていると見える。と記述している。
上野国甘楽郡中里村菊女事
小幡龍蟄は「上毛菊婦傳」の中で、お菊の素性について更に詳しく検証している。「上野国甘楽郡中里村菊女事」と題された一項がそれである。次に大要を記してみよう。
上州妙義山より、辰の方角にあたる向かいの山を大桁山という、この大桁山の卯の方角の麓の村を十二村という、その小名に中里村という村がある。妙義より、一宮へ行く街道を左の方へ、百間(約180mか)程踏み込みし所の山麓に村がある。
すなわち中里村なり。
また街道よりおよそ十間程右へ踏み込みし畑の中に、墓あり、これが菊女の墓なり、東向きにて、左に槻(榎)の大木あり、この槻の木の左に高さ一尺ばかりにて、小さき石碑の如き物二つ程あり、
この石碑の如き物は、この辺の者が菊の墓へ立てて願事致すなり、成孰の節に納めし品であろうとの言い伝えがあるが定かではない。
当時この辺の畑は、中里村弁蔵という者の土地なり、且つ槻の木、枝が多く畑に支障が出て迷惑につき、近頃切り取ったが、弁蔵一家ならびに切り取った者の一家が罰を蒙り病気が絶えない、よって神職に頼みお詫びをしたところ、追々全快にいたる由。
木は若芽が出て格別、年経ずして大方、元の如く大木となったという。
この墓の辺は中里村にて、誰となく常に掃除され大切にされ、疎かにすれば罰が当たる由。中古は中里村は家数が百七軒ほどあったが、今は多くは死に絶えて今は漸く二十軒足らずの家数の由。
全く菊の墓を疎かにした罰と人々恐懼す。また近村の人々癪を煩うは、この墓石を削りて飲めば、全快するとして諸人削るため、文字の有無が判じられない。ただ菊女の墓と言い伝わっているのみで、法名を知る者なし、この辺今尚、霜雨等の夜は怨火が出る由、また諸人疎かにすれば罰を蒙り、散するれば霊験ある由、大いにこれを尊敬す。
寛永14年小幡候縄張りの節、菊女の墓所弐畝十五歩除地、その頃この辺は助兵衛才十郎の所有の畑の由なり、徐地は旧例に従っただけである、考えるに、前に言われていた石碑の如きものは、古いものにして文字の有無は判らず、いずれにしても近代のものにあらず、恐らくは菊女一家の葬地にて家内の者の墓なるべし。安政五年四月二日この墓所に謁す。
この墓地に添碑を建てんと、中里村名主、仲右衛門・地主弁蔵へあい話し、御領主にては子細ある間敷か、承りしに一村大いに喜び、小幡領主松平玄蕃頭殿、お役人へ仲右衛門一存の趣にて申し立てしに、もとより徐地の事ゆえ子細(支障か)なき由につき、添碑の下書きは宝積寺考道和尚に頼む事として、
その下書きは四月五日仲右衛門へあい渡し、添碑建立の段取りを同所へ任す。菊女は中里村出生の者の由、遠祖、信真君の国峰城ご在城の頃、甲斐国巨磨郡藤井の庄より召抱えた菅根正治という者、中里村に住まうという。
同人に娘二人ありその一人の由。姉か妹かは今だ判らず、国峰城の奥に勤めていた時、上の思し召しに叫ぶという共、同僚の中に菊女を憎む者ありて、ある時菊女、君に御膳を上げるそのご飯中に針があり。
これ同僚のした事なりて、菊女の過ちにあらずと云共、申し訳なく罪に落入、お仕置き仰せ付けられるという。一説に最初はお詫び申し上げ、それで収まったがまた続けて同じ事があり、その節にお仕置き仰せ付けられたと云う、二度とも同僚の仕業の由。
お仕置きは御領内引き回しのうえ、菊を桶に入れ首だけ出して、桶の中に蛇数匹をいれ、轟村宝積寺の裏の熊倉という山の中ほどにある池に浮かばす。死せし後、一家の者身体を故郷中里村に葬るという。
その頃、菊女菩提寺は、菅原村管応禅寺であった筈と仲右衛門はいう。何故このように言われるか今だ判らず。且つ予家の菩提所宝積寺の和尚、菊の引き回さるるを見物し命乞いをしなかった故に、その後、寺へ祟りをしてまた予家へも祟りをなす由。
既に序にて論じたところなり。
考えるに、菊お仕置きは天正年間の事で、宝積寺十世魯岳和尚の時か、既に天正十五年の魯岳討死・寺の焼失などの事は菊の祟りであろう。又いわく、お仕置きの場で、当人に望みはあるかと聞いたところ、宝積寺の中を通り国峰御殿の見える所でお仕置きになりたいと言ったと云う。
それで熊倉山でお仕置きになったと云う。当人がそう言ったのは、上の御菩提所の中を通れば、必ず命乞いの願いも聞いてくれると、思っていたが和尚は命乞いもしなかった故、寺へ祟り又、後世拠り所無きゆえ小幡城主へも祟りをなし、宝積寺にて絶えず朝暮読経し改めて贈る法名は五度に及んだ。
その法名は仏心大姉、妙心大姉、連心大姉、仏蓮大姉、心仏大姉の五大姉となった由。お仕置きのことが宝積寺に伝わっているところでは、前に言ったように菊を桶に入れ首だけ出して、桶の中に蛇を入れ、熊倉山中ほどの池に浮かばせし時、小柏源助とういう者が山狩りをしていて、通りかかりその叫ぶ声を聞くに堪えず、桶の蓋をこじ開けて、菊女は源助に一礼を述べて直ちに死すと云う。
また別説では、桶ではなく石櫃に入れ、前にいう如くにしたところ、蛇共菊女の肉を食べつくし後、石櫃の中にて共に食い合い、その声甚だ悪く小柏源助山狩りに通りかかり、声を聞き不思議に思い石の櫃をこじ開けたところ、蛇共は散って行ったと云う。
菊女が死せし後、母が来て嘆き悲しみこの如き責めに遭うとは口惜しい事なり、これより小幡家へその子孫まで祟りをなせ、我もまた同じようにする、言う事が判るならこれを発芽させよと煎りゴマを池の辺に植えた。
そのゴマは発芽したと云う。今に至りても、年々生えて花は咲けども実はならぬと云う。熊倉は高山にして、中ほどにある菊女お仕置きの場所まで登るのには、一里余あるなり、この辺は昔は池だったか。今はおよそ百間四方ばかりの平坦地で水はない。
またこの山稜・山続には格別石もないが、菊池の辺りには六、七尺四方くらいの、大石が多くあり。そこより六、七町左のほうに昔、天寿庵と言う庵があった由、故に今この辺を菊が池と云う。また天寿庵の淵とも云う。ここより北西の隅にあたる所に、国峰(城)御殿裏山の高い所が少し見える。
また曰く、お仕置きのとき石櫃に入れたという説があるが、桶のほうが事実なるべし、小柏源助は小松重盛の末孫の由。今上州日野村の郷士に小柏源助という者があり、これ小柏の家なり。安政五年熊倉山に登り菊が池を見た。案内の者がゴマ草はこれなりと云うので、それを見ると松代にて小車という草に似ている。花はどんな物かは知らない。
菅根正治の子孫は今は耐えて居ないが、正治の兄弟に治部右衛門という者が有る由、その子孫が即ち仲右衛門の由と同人が云う、また同国、下仁田村の字の、大崩村に菊女の親類筋の者が居る由、それは同、八木連村太右衛門の父出雲という神職へ、十五、六年以前に、自分は菊女の親類筋なりと話して来た事があるが、名前までは聞かなかったと、父出雲の話だった。と太右衛門が云った。
今はこの他に縁者あるというのを聞かない、また同州で山田を名乗る者の家にはとかく良くない事が起こると云う。菊女もしくは山田を名乗る者に讒言されたものか、その故に今尚、山田家を怨むものか、と高瀬村、旧臣新居又太郎が云う。
仲右衛門家より山沿いに、百間ほど東へ行ったところの山に、八幡の社ありその社,石段の前の左の方に、並んで五輪の如き石碑二つあり、これが菊女の両親の墓との言い伝えがある。
毎年九月十五日は八幡祭日の節として、村一同が祭っている由、仲右衛門の弟太平が云う。考えるに宝積寺の旧記によれば、菊女の母の葬地は宝積寺になるべし、両親
の墓というのは信じがたし。石碑二本とも文字の有無は論ぜず、もしや一家の者の墓かなおの研究が待たれる。
十二村の字、崎保村に正国寺という真言宗の寺あり、安中市の明光院の末寺なり、近頃この寺に欲深い和尚が居て、菊女の墓は諸人が尊敬するので、その墓所は正国寺の中に有と云う。
古い時代に川の洪水があった事により、やむを得ず崎保村の現在地に寺を移した、よって菊の墓は正国寺の所有なりと言った事があるが、この寺は天和年間に建立した由で、したがってこの事は事実ではないと仲右衛門は云う。
菊女、とかく宝積寺に祟りをなすので、同寺二十七世万仞和尚菊を金毘羅に祭り、寺の鎮守となすにより、以来寺への祟りをしなくなったと云う。鎮守は熊倉山菊が池より、五町ほど左の方に小さき石の社あり北東の隅へ向いている。
またいわく小幡城主にてもこれを恐れ尊い、この社の鳥居は白木にて粗末なれど、当時小幡城主より寄進にて修復の度、宝積寺へ依頼して石社へ次の文字を彫った。
正面 眷属夜叉 金毘羅大権現 菊池山神
右 明和五年万仞立
左 宝積寺鎮守
以下、石碑、添碑などの形状・文字・寸法などの詳細な説明が続いて、長文となっている。この他、松代の屋敷内にお菊を祀った二社について説明し、忍之藩の小幡氏、江戸小幡氏の領する安中市中野殿の、小幡氏の供養について触れているが省略して巻末の記事だけを次に示す。
松代清野村龍泉寺寺内に、安置の鎮守は菊を祭る所なり、毎年九月十九日を祭日とす、同村字鳥見塚裏に、かねて所有の土地のうち、四斗二升三合の畑を安永二年にこの社に寄付をした。
吾曽祖父義正君の御代なり、その書面に年来安置の鎮守とあれば、その前より古くから祭りたまえしと見ゆる。且つ母の玉女は後に祭りたまうと見ゆる。恐らくは仁寿君の御代の文化の時か。 比壱巻先年納置候処不相見由ニ付猶又うつし納置物也
明治廿八年二月 六十九叟 小幡龍蟄
市川氏 春山大明神の記
「甘楽町史」に、南牧村の市川家が伝えている、春山大明神の伝説が収載されている。あまり知られていないこの伝説を最後に紹介しておこう。
以下は南牧村星尾出身の市川氏の調査によるものである。
春女並びに菊女の伝説(春山大明神の記)
春山大明神(甘楽郡南牧村星尾仲庭、地蔵堂敷地内)祭神(春山大明神=春女)例祭(9月13夜の当日=旧暦)天正十五年頃(1587)国峰城主小幡上総介の家臣に甲斐国巨摩郡藤井の庄よりお召抱えの菅根正治という者がおり、才色兼ね備えたお春、お菊という二人の娘が居た。
ある時二人は、殿様の侍女として仕える事となった。
美しい姉妹は殿様に、格別に可愛がられたので、同輩たちがこれを妬み、殿様に差し上げる食膳の中に縫い針を入れられて、二人の姉妹の仕業として疑われ、殿を害する心ありと妹菊女はとらわれ、領内引き回しの上、桶に首だけ出して桶の中に蛇数匹を放ち、これを小幡藩主の菩提寺である宝積寺の、熊倉という山の中ほどにある池(菊が池)へ投げ入れた。
のち、この池のまわりに蒔いた煎りゴマの花が咲いたので、お菊の怨念ならんといわれた。菊女の処刑の際、何か言う事はないかと問われ、国峰の舘の見える宝積寺裏の熊倉山を処刑の場にしてくれと願った。
これは熊倉山へ行く途中、宝積寺境内を通るので、その際、和尚が必ず命乞いを願ってくれると思ったが、命乞いをしなかったので以来寺が全焼したりなど、宝積寺へ祟ることしばしばで、寺の山門は何度建てても火災にあい、名刹でありながら今だに山門のない寺である。小幡藩滅亡もまたよりどころない二人の怨霊の祟りと言われている。
くだって明和五年(1758)お春、お菊二人が、とかく宝積寺に祟りをするので、同寺二十七世万仞和尚は二人を金毘羅に祭り、石の祠を造りお春とお菊両名の名を刻み、寺の鎮守としてからは寺へ祟らなくなったと言う。
石祠の文字は次の如くである。
眷属夜刃 明和五年万仞立
金毘羅大権現 宝積寺鎮守
菊池山神
姉のお春は逃れて、一路西の方へ向った。そして、ようやくのはて辿り着いた所は、山深い里、南牧村星尾仲庭の市川勘解由の屋敷であった。お春が救いを求めたので、主は屋敷内にある厩の、干草の内深く隠し入れたが、槍を手にした追っ手の者たちの手にかかり、干草が怪しいと見られ干草の上から盲刺しに突き刺されて、哀れにも殺害された。
その日は9月13夜の月の夜であった。お春は絶えんとする息の底から、私が死んだら骸の上に煎りゴマを蒔いて下さい。必ずゴマの芽を出して、無実の証としますと未練を残してこの世を去った。
お春の骸を埋葬し、言い残した言葉どおり、そのまわりに煎りゴマを蒔いたところ、ゴマの芽が生えてきたのでその不思議さに驚いた。
またその後、お春の殺されたあたりで、女の悲しい泣き声がする事があったので、仏の霊が浮かばれずにいるのであろうと哀れに思い、手厚く供養してきたと伝えられてきた。
後年、病人が続き、また直りにくい事があったので、神職に病い平癒の祈願をお願いしたところ、お春様を大明神に祭り社に安置すればよいとのこと故、早速お祭り申し上げたところ、霊験きわめてあらたかに、今までの難病もたちまちに治ったという。
以来、毎年9月13夜の日を祭りの日として、この日は社にお神酒、供え物等し、また赤飯を炊き村の子どもたちに分け与えて春山大明神の功徳とした。
なお市川家では(現戸主、十三代喜義)代々、ゴマを栽培する事とお春、お菊の名を子どもにつけることを禁じられている。
昭和53年10月家祖市川勘解由13代孫 市川盛敏(茂)調記
(注)宝積寺古文書を参考にする事多し、現在も星尾あたりでは、墓参の時、墓地及び墓碑などに、生米など穀物を播き供え供養する風習がある。
以上
お菊伝説は諸人のうちに広まり語り継がれ、やがて宝積寺の鎮守となり霊験新たかと信仰され、多くの人が参詣するようになった。いかに諸人の中に浸透していたか、歌が唄われるようになり、その歌の数が多い事からも読み取れる。歌は長文なので、『宝積寺史』の中からタイトルと作者だけを列記してみる。
述懐 反歌 作詩 新井守村 (長歌)
お菊一代記八木ぶし 作詩 水沢天外散人 校訂 西有穆堂
お菊さま 作者 不詳 (甘楽町史収載)
菊女伝説 作詩 田村貞雄
「述懐」は国学者守村が、龍蟄が妙義町中里の菊女の墓に添碑を建てた時に、その霊前に捧げたものという。お菊一代記は、小冊子として刊行されたという。お菊さまは念仏講で、女衆が唱えて甘楽町秋畑では、昭和50年代まで歌われていたという。
どの歌もこの稀代なるストーリーを織り込んで、お菊の悲しみを歌っている。小幡龍蟄は明治維新後、明治四年に岩手県権知事に就任している。
祖先の足跡を生涯に亘って調査し、多くの史料・著書を残し、明治29年に70歳で没した。松代藩(真田家)の中老職にあり五百石を給されていたとされる。
「宝積寺史」によれば、永久保貫一が同寺に調査に来た他、全国に伝わる[お菊伝説]について研究し本を出版しているという。その説によるとお菊伝説の根源地となった松代、姫路、行田、江戸、彦根などに伝わるお菊伝説は小幡一族やその家臣が伝えた物という。
また皿屋敷伝説もお菊伝説と一緒に、或いは同伝説が発展した物としてか同時に伝えられた物のようだ。
三波川小柏氏から頂いたコメントによると、三波川の竹野が来たと伝えられている小柏家の墓地には小幡家の女中の墓と伝えられている墓が二つあるという。
また三波川の小柏氏では胡麻の栽培が禁止されているとの事である。食材の胡麻を煎る時も、一粒でもこぼれたらその胡麻から芽が出るとして慎重に扱っていたようだ、という。
これ等の伝統・伝承はお菊伝説を如実に物語っているかのようである。お菊伝説に
は骨子となる事実があった事を窺わせるのに充分である。そしてこの二つのお墓はお菊とその姉のお春の物であるのか。
三波川には小柏姓の家が今、十二軒ほどあるが何故ここに小幡家関係者の墓が存在するのか?この謎を解明するには更なる探求が必要となるが、後述する別項において少し考察してみたい。
第四章 江戸時代の小柏氏
大阪冬の陣に出陣
小柏定政の長男は重氏(1592~1671)であり二男が貞景である。貞景は小幡郷の堀口家の養子となって同家を相続し堀口伝内と改めた。法名は浄無である。
三男が貞實であり福島の住人友松家を継承し友松傳左衛門となっている。法名は半無である。
長男の重氏は六郎右衛門であり、七十九歳で没し法名を浄安という。系譜に拠れば
妻は城和泉守永盛の娘である。慶長十九甲寅年冬摂州大阪のご陣の節、重氏生年二十二歳にして、関東方の御使い番役の永盛に従い大阪表に随行し大いに働いた。この戦では数多の武功を挙げた。
また永盛の従臣、熊井戸久兵衛永正は老体であり殊にこの時嬰病痾なり。かつ娘ありて男子なく、よって軍役も勤めがたくなっていた。重氏は永盛の婿・永正のためにその陣代を勤めた。この他、事績の詳細を記した別記あり。
有名な大阪冬の陣に参加した記録である。熊井戸氏は小幡家の家老格にあった熊井戸対馬守の一族であろうと推測される。同氏は小幡城を館城としていた近隣の武将である。
城和泉守は武田勝頼の侍大将として活躍したが、武田家滅亡後は家康に属し七千石を与えられていた。大坂冬の陣には軍監(戦目付)として参加していたが、軍令違反があったとして改易された。(後に復帰)
和泉守は名刀「正宗」を所蔵していた事でつとに知られている。この頃、元和二年(1616)家康に領地を与えられ、信長の二男織田信雄が小幡城主として入国してきた。
小柏重氏は城和泉守が改易となった時点からか、戦に赴いた記録もなくなり上日野において、その所領の管理・発展に努めていたと思われる。
小柏家の権勢
日野谷(ひのやつ)には戦国時代から「日野七騎」と呼ばれた旧家があり、代々名主などの村役人を勤めてきた。日野七騎は小柏(小柏村)、酒井(鹿島)、小柴(岡本他)、黒澤(駒留)、高山(金井村)、栗崎、飯塚の七家で、地主として強大な権威を持っていた。
「群馬県多野郡誌」では栗崎・飯塚の替わりに柴崎・笠原(後原氏)を挙げて、小柴氏と小此木氏は同一視している。
七騎といわれる家には、代々「家抱」(けほう)といわれる半隷属民がおり、10戸から多いものになると、小柏家のように約50戸も家抱がいた。家抱は大家といわれる地主の屋敷内に住み、労役を提供していた半隷属民であった。
衣服に対する制限も厳しく、絹などを用いれば皆取り上げられた。したがって、日野七騎は江戸時代にわたり絶対的な権威を持って君臨していた。上日野村の名主小柏家は、農民を自宅に呼び出し家抱にする旨を申し渡した。家抱は笠は竹張笠、下駄は切附下駄以外は厳禁であった。
小柏家は見渡す限り一面の山をすべて所有し、一説には三千町歩もの山林を所有していたといわれ、その権威を示す「おえんが荷場」「若宮八幡の由来」などの“小柏伝説”がいくつも残されている事に象徴されている。(多野藤岡地方誌・各説編)
御荷鉾山は古くは八束山と牛伏山とで多胡三山と呼ばれていた。特に御荷鉾山は三山中の最高峰であり、その秀峰ぶりは万葉集にも歌われている。
「群馬県多野郡誌」を見ると御荷鉾山には三峰あり、西御荷鉾山(釜伏)が最も高く(1286)、次いで東御荷鉾山(1246)、亜ぎをどけ(オドケ山1191か)と続くとある。
江戸時代には村民がたびたび登山して、雨乞いの祭祀を行なっていた。その跡は今にして窺う事が出来る。別名雨乞山(雨降山)と呼ばれた事もあったようだ。
御荷鉾山の頂上には不動明王の石像があり、鬼が住んでいたが弘法大師に調伏され、この時に大石を投げて去ったという。
その石の落ちたところが今の鬼石町であるとされ、その石は今なお村の中にあるという。江戸時代は木材の需要も多く、小柏家は山の支配権を背景として強大な権勢を持っていた。
山間の地にあっては、やはり山が生活の基盤をなしていた。これらの山仕事は「山稼ぎ」と呼ばれ、山元或いは元締めと呼ばれた小柏家が統轄していた。
山はすべて元締めが支配しているので、山に入るものは元締めを通して申し込むものとされていた。
山の中での事で元締めが承知していない事があれば、不取締り(吟味できない)になるので、全て元締めに報告せよとの公文書も今に残されている。
「家抱」とは耳慣れない言葉だが大名家の中間、商家の下男、寺の作男みたいな者であったろうか。屋敷内に住居などを与えられ、税金は大家が負担したが労働力として使われた。家族で住み込んでいる者も多かったようだ。この地域独特の制度であったようだ。
藤林伸治によれば、吉井藩も小柏家の自治権を承認し一種の同盟関係にあったとする。そして小柏家の隷属的主従関係や上・下日野村の支配体制を積極的に利用したとしている。
家康は武田家(信玄)をかっていた為、同家の旧臣の優遇策をとったといわれる。この政策も後押しをして、小柏家も大地主としての権威を徐々に身につけていった。既に江戸時代の初期の頃には、家抱を数十人も抱えていたという。
幕府の政策により権力を築いていったとしたら、約二百六十年後の明治政府の財政再建政策により、没落のきっかけを蒙ったのもまた廻り合わせの成せる業か。
名刀 むかで丸
ごく大まかにこの頃の時代設定かと思われる伝説がある。小柏八郎右衛門は「むかで丸」という名刀を所持していた。ある時、峠の大石に座して一休みした時に赤い鞘のその刀を置き忘れて来てしまった。
これに気づいた八郎右衛門は後から峠を降りてきた町人に、峠の石の上に刀がなかったかと聞いた。町人は刀はなかったが、大きな大きなムカデが石の上にいてこっちを睨んでいたので、恐ろしくなり慌てて逃げて来たと言った。
八郎右衛門が峠の大石の所まで戻ってみると、刀はちゃんと石の上に置いたままになっていた。この名刀「むかで丸」は所持する本人が見ると刀であるが、他の人が見るとムカデに見えて脅威を与えたという。(ふじおかふるさと伝説)
小柏定重がお菊を助けた故事から生まれた伝承といえるかもしれない。八郎右衛門という名前は幕末の頃まで小柏系図には現れない。
八郎左衛門と六郎右衛門の名前は時々世襲された名前である事から、「左」が「右」に誤記されたものであろうか。ちなみに同伝説には小柏氏の記事が4箇所に登載されているが、名前は全て八郎右衛門になっている。
小柏重高と名僧潮音の黒滝山
重高 黒滝山不動寺の開基となる
小柏重高については「甘楽町史」に次のようにある。
「定重(小柏)から六代に八郎左衛門重高がある。重高は一燈居士、妻は妙香大姉と号して、深く仏道を信じ上州館林なる潮音和尚について、禅を学び後、潮音を迎えて村内に草庵を建て、此処に居らしめたが、潮音の志望により親戚なる甘楽郡(下仁田)砥沢の市川氏と共に開基となって、甘楽郡黒滝山に一宇を建立した。これが今の黒滝山不動寺である。
同寺には一燈夫妻の像が今に存している。一燈の子一柱は黒滝山二世月浦和尚について学び、和尚が浅間山に普賢寺を開いた時、梵鐘を寄進した。その鐘は今も同寺に残っている。」(同家系図及び古文書、小幡伝説)
不動寺開山堂に鎮座する重高像
左から一桂(吉重) 妙高 一燈(重高)の小柏一族 右は丸に釘抜き紋の一燈位牌

穏かな表情に“和尚さん“の雰囲気が漂っている。 いつでも好日H・Pより
小柏重氏の嫡男が重高である。重高は四代目でありなぜ六代と記載されているのかは不明である。重氏の弟二人を入れたものか、さすれば確かに六代目となる。重高は小柏甚平と名乗り後に八郎左衛門と改めた。
上日野の小柏舘跡にある石碑・板碑や、鼠喰城への登山口にある石碑には「小柏城城主、小柏八郎を中心として・・」等の文章が彫り込まれている。小柏氏で始めて八郎左衛門を名乗ったのは、重高であるので碑にいうところの「八郎」はこの重高ではあるまいかと推測される。
「ふるさと人ものがたり」によれば、この頃には小柏家は既に数十戸の家抱や広大な私有地を持っていたとある。
小柏系譜には次のようにある。
この時代は自ずから泰平の御世となり、重高は仏道を信じ上州館林に行き、臨済三十三世隠元禅師の弟子の潮音和尚に拝す。夫婦とも弟子になるため法体となる、重高は一燈と号し妻は妙香と号す。
然る後、上州黒滝山に於いて一寺を建立す。延宝年中、彼の和尚を招待す。今もって、拵えた夫婦の影像(木像)がこの寺に存しているなり。詳細は拵えた別記に記録してある。
「群馬県の地名」に不動寺の記事がある。少し長くなるが、下記に引用する。
不動寺 南牧村(下仁田)大塩沢、黒滝 黒滝山(870m)の南東側中腹にあり、背後に日東巌・星中巌・月西巌の三巌が聳え、前方には五老峰が迫る。黄檗宗で黒滝山緑樹院と号する。
本尊の不動明王像は行基の作と伝え、寺名は本尊によるという。古くは嵯峨天皇の勅願の道場であったとも伝える。中興は館林広済寺二世の潮音道海。
「国志」には「開山潮音道海和尚、潮音和尚館林の広済寺を辞して後、南牧に遊歴す。これより先、黒滝山に山居の僧あり、師を招いて山居せしむ。
師乃ち僧と共に往きて巌窟の中に禅座す。その為地甚だ霊区なり」
とあり、「名跡志」にも「後上野志に南牧黒滝山不動寺開山潮音道海和尚という」とある。また「大日本名跡図誌」には延宝三年(1675)の創立として「市川半兵衛、小柏八郎、白石六郎、市川清平等の開基也、時に隠元禅師の法孫たる潮音和尚を帰依して開山となす」とある。

不動寺 山門
潮音は広済寺在住の延宝七年に偽書とされる「旧事大成経」を編纂、同書で伊勢の皇太神宮を別宮とし、本当の天照大神の本宮は同地の伊雑宮であるとしたために、伊勢神宮から告訴を受けたが裁判の結果、将軍の母が帰依僧ということで流刑を許され、黒滝山へ転住させられた。(広文庫)
「潮音年譜」の天和三年(1683)の項に「師かって官寺を厭うの志あり、万徳を辞して補陀に入らんと欲す。諸檀護黒滝に住せんことを請う。七月一日、黒滝に入る」と記され、さらに「南牧に隠れてより南牧樵夫と号し、偈を作りて志を示す」とあり、ここで三年の謹慎をしたという。
この三年を過ぎた後、再び活動を開始、百数十寺の末寺を持つ名刹とし、黄檗宗黒滝派を開いた。(磐戸村郷土誌)潮音は天和三年より元禄三年(1690)まで在住して中興に力を注ぎ、堂塔伽藍を整えた。
遠国からの入山僧も多かったとみえ、彼らの不自由さを見ていた塩沢村の市川好等は、宝暦十二年(1762)祠堂金五両を寄進し、年二分と定めた利金を与えるようにしている。(「祠堂金寄進状」市川文書)
現在の山門は寛政十年(1798)の再建で、潮音筆の「東海禅窟」の額が掲げられ、不動堂は天保四年(1833)、開山堂は明治二十一年(1888)の再建である。不動堂の裏は、岩が削り取られたように内曲し、上方から黒滝泉が落ちている。
開山堂の裏には「潮音海老和尚寿塔」と刻まれた岩窟があり、潮音の分骨が納められている。また境内には目通り6.6メートルの県指定天然記念物の大杉がある。
潮音 重高に誌偈を贈る
「多野藤岡地方誌各説編」には次のようにある。
小柏源六の項 定重から六代の八郎左衛門重高(一燈居士)は妻(妙香大姉)と共に、館林の潮音和尚に禅を学んだ。
村内に草庵を建て潮音を迎えたが、潮音の志望によって甘楽郡黒滝山に不動寺を建立し、夫婦の木像が同寺に現存している。一燈の子一柱は同寺二世の月浦和尚について学び、和尚が浅間山に普賢寺を開いた時に梵鐘を寄進した。小柏氏は江戸時代には名主を努めるなど土地の名家の一であった。
潮音庵跡 上日野小柏火口山(ひのくちやま)にある。小柏八郎左衛門重高の師、潮音が数年間在住した草庵跡であるが、遺蹟保存のため観音堂を造り大正十三年九月に黒滝山から潮音の彫刻という正観音像を移して入仏式を行った。
重高は一燈、妻は妙香と号して仏教を信じ、当時館林の広済寺潮音和尚について禅を学んだ。
潮音が故あって、同寺を焼いて跡を暗ませ一燈家に隠れた時、潮音のために寺を建てようとして草庵を造ったが、潮音が南牧村黒滝山を希望したので、一燈が開基となって不動寺を建立した。潮音が小柏に在住した事は次の史料で明らかである。
維持延宝五丁巳年過小柏梅屋元香居士曇華室
法王示現曇華室 頂礼帰依作雁行 一語分明須記得
慈悲直実子孫昌 臨済正伝三十四世 万徳潮音書印
貞享丙寅之孟秋栄三道婆一燈居士及了源幽斎ニ老翁登山省侍偈以志喜
寿星遠聚黒滝峯 山色増光映疎林 禅脈永流弥勤会 莫忘扶法護宗心
黒滝潮音老人手書 花押 (小柏家蔵・偈)
潮音が小柏におったのは延宝(1673~)から貞享(1684~)の間で、貞享三年には黒滝に行っていることが偈でわかる。正面観音に添えて潮音の位牌がある。
黒滝山開祖上潮下音海老大和尚覚位。
-中略―― 。
多野郡誌によれば、当時火口滝壺の洞穴から湧き出る泉は酒となり、潮音の毎夜の食膳に不自由はなかったという。
先の文章中の「小柏家蔵・偈」の偈とは経文のような物とされている。おそらくは潮音が重高のために薄い木板に手書きして、感謝の気持ちを表したのであろう。その大意は、仏法は生き様を教え示してくれる。
(我々)仏弟子は五体投地の精神を持って、御仏の後ろを雁行のようにして、ひたすら奉じて行きましょう。黒滝山に久しぶりに、登山され訪れて来てくれて嬉しく思う。いま秋となり黒滝山の峰の木々の色は増えて、林は光があたり映えている。法を守り援けてくれた事は忘れない。
と解しておこう。
一燈居士は小柏重高・了源幽斎は白石六郎左衛門である。現在までにその偈の所在の確認は取れていないが、こうした偈や別記と称する古文書が存在していた事であろう。他に法政大学や県立文書舘などに所蔵されている、小柏氏の古文書は虫食いなどでの傷みが激しくその数も多くはないが、小柏家に伝わっていた古記録の一端が窺われる。
潮音は卓越した詩人であったらしく事あるごとに、詩作をして偈に記し漢文調の誌を多数残している。語彙が大変に豊富であり、見た事も聞いた事もない言葉がかなり含まれている。或いは仏教独自の用語も含まれているのだろうか。
その作品は「誌偈集」として纏められている。重高に偈を贈った時の事は次のように記録されている。
一燈玄照居士に示す
鬢髪を削除して 緇流と作す 謂う可し 世間出格の儔と
心眼豁開して 浄穢なく 一燈の照徹す 萬千秋
潮音は重高の妻「妙香」の事を、清潔極まりなくその身心は雪・霜のごとく真っ白であると、その誌偈集の中で次のように述べている。
剃頭戒を受けて 餐由いず 皓潔の身心 雪霜のごとし
忽ち人間 塵世の夢を覚まし 清涼国裡の 真常を楽しむ
(「関東の仙境黒瀧山」)
先代旧事本紀大成経
潮音は臨済宗の高僧であり、黄檗宗黒滝山派の開祖となり、不動寺は多くの末寺を造り隆盛を極めた。「謎の根元聖典先代旧事本紀大成経」(後藤隆)によると、潮音は延宝三年(1675)に「聖徳太子の五憲法」という本を出版したという。
同年は上日野小柏村に滞在していた年である。とすれば潮音は重高が建立した草庵で執筆したものか。
この本を出版した版元は江戸の戸嶋惣兵衛であり、「先代旧事本紀太成経」七十二巻本の版元と同じという。
先代旧事本紀は多くの人が潮音の著作と考えているが、後藤隆氏によれば、潮音が出版に関わっていた事は事実であるとしている。後藤氏はこの七十二巻本が十巻本、三十一巻本の原典となったという。
「先代旧事本紀」は学会からは無視され、幕府によって発禁処分となったりしたが、好事家や研究者の間で論争を巻き起こした書物である。
七十二巻本を信奉する人たちは、これこそ聖徳太子が著した「先代旧事本紀」の原典であるとする。確かに「古事記」や日本書紀」には書かれていない事柄なども、詳しく書かれていて真実味が伝わってくる本である。心情的には真実が書かれていると思いたいところである。
正編三十八巻・続編三十四巻からなる「先代旧事本紀大成経」は延宝七年に木版本として刊行された。七十二巻本が潮音の著作になると見られるのは、同書に「聖徳太子の五憲法」の内容と全く同じ記述がある事によるという。
伊勢神宮の訴えを受け幕府は戸嶋惣兵衛を追放、神道家永野釆女、潮音、伊雑宮神官を流罪とした。永野采女は箕輪城主の永野業政の子孫で、いづれかの宮に秘蔵されていた先代旧事本紀七十二巻本を潮音に貸したという。
高名である潮音が来ているとの噂は、近在に広まっていたのではあるまいか。そして永野采女も訪れて来て、一緒に「先代旧事本紀」の出版に関わったとみられる。
永野采女は神道家であるが、当時は寺と神社は混在しており比叡山も高野山も神道を否定せず、むしろ肯定していたのである。
皇學館大学の学長を勤めた田中卓は「先代旧事本記大成経」は潮音が伊雑宮の祠官長野采女と議り、同社に伝えた若干の古記録を基に多く無稽の説を付会した物と思われる」として更に「聖徳太子の御撰でもなければ内容また信ずべき限りでもない」と断じている。
しかし先代旧事本記大成経は、発行されるとすぐにベストセラーになったと言えるほど多くの人に読まれた。神代からの日本の歴史・出来事が人名を含めて事細かに綴られている上、伊雑宮が日神を祀る宮であり、伊勢内宮は月神、外宮は星神を祀っているとしている事が何よりも注目されたと思われる。
内宮と外宮は以前からの確執を抱えていたが、此処に伊雑宮が参戦し三つ巴の論戦が開始された。長谷川修は将軍綱吉の師匠格に当る潮音が、自信を持って世に出した先代旧事大成経がそんなに凡庸なものとは到底思えない、焚書にされるだけの価値を備えていたに違いないと論じた。
潮音の先代旧事本記大成経(神代皇代大成経)が、世に現れるおよそ百年ほど前に伊雑宮から幕府に「伊雑宮旧記」「五十宮伝来秘記見聞集」が提出された。この目的は伊雑宮を再建する事にあったが、幕府は内宮・外宮の主張するところにしたがい偽書と断じた。
この古記録・二書の主張するところは先の大成経と同じであった。伊勢の皇學館大學は潮音・采女の論敵にして天敵であり、歴代の学長は容赦ない批判を浴びせた。
大成経事件は数百年に渡る複雑で根の深いものであるが、その骨格は伊勢内宮と伊雑宮の対立に起因している。
潮音の大部「大成経」に書かれた事は、或いは事実と異なっているかもしれないがその史料価値は決して減じるものではない。日本書紀でさえ事実と異なる記述が沢山あるではないか。更に潮音の多くの詩作からは、その高潔な人物像がほのぼのと浮かびあがってくるのである。
潮音は不動寺の山門を入った参道の右側に、饒速日命(ニギハヤヒノミコト)の石碑を建立している事から「大成経」への思い入れがいかに深いものであったかが窺われる。 原田実によると、采女の弟子の仙嶺が著した長野采女伝が「旧事大成経に関する研究」に収録されているという。その采女伝によると長野采女の姓は在原で性は男であるという。
上州沼田の生まれで箕輪城主の子孫と称していたという。幼少の頃から神童の誉れ高く家には代ゝ物部之家伝という神道奥義が伝わっていた。それは七十余巻あり、巻名は大成経の本紀名と共通しているという。仙嶺は采女が久しく神庫に秘匿されていた神史経教を世に広めたと称えている。
この事から、どうやら先代旧事本記大成経の原典となった古記録は、采女の家ではなく伊雑宮にあったものらしいと推測する事が可能である。ちなみに采女は天海僧正の直弟子だったという(采女伝)
近代まで養命寺の山門前に不動堂があった。養命寺に向かって参道の右側に古いお堂があった。(別掲写真)潮音が開山した黒滝山の不動寺にも同じ名前の「不動堂」があり、時代にはずれがあるもののその関連性には注目される。

養命寺の不動堂 左奥が養命寺 (藤林伸治資料)
「藤岡市史通史編」にも潮音と小柏氏の次のような記事がある。
山岳霊場の地、黒滝山不動寺は潮音道海が中興開山となった。開基となったのは南牧村の市川半兵衛、白石六郎左衛門、小柏の郷士小柏八郎左衛門重高(六代)らであった。
小柏氏は日野小柏に土着した郷士、日野七騎の筆頭で、当地の名主を代々勤め「小柏様」と呼ばれた在郷地主であった。小柏氏は「小柏系図」によると平維基を開基とし、代々北条氏、管領上杉氏、武田氏に属していた。
特に十八代小柏定重は庄司源六と称した「大力無双」の士であった。小柏源六親子は武田氏の武将となり戦功を立てたが、天正三年(1575)の織田信長・徳川家康との長篠の戦で奮闘し討死している。
また小柏源六は小幡お菊伝説で知られており、その名は童歌にも「蛇もムカデもどーけどけ、小柏殿(どん)のお通りだ」と歌われた有名な武将であった。
この童歌は小幡氏の側室お菊が蛇責めの刑を受けたものを、源六が助けてやったのでこの歌を唱えて行けば、決して蛇(マムシ)に噛まれないという蛇よけのマジナイであった。
源六(定重)から六代目に小柏八郎左衛門重高がいた。重高は砥沢の市川宗家と縁続きであり、しかも信仰が篤く黒滝山の潮音禅師に帰依した。
重高夫婦は剃髪し、重高は一燈居士、妻は姉高大姉となって開基に加わった。小柏氏の菩提寺養命寺で出家した行者「祖源」が、黒滝山で修行し潮音の弟子となって高源と改めた事も、黒滝山との結びつきをより深いものにした。
なお、上日野の小柏家の西方の火口山に滝があり、延宝年間に潮音禅師が在住した滝壺のほとりの草庵跡には今も石垣が残されている。
仏教に深く傾倒していた重高はこの頃、養命寺の本寺でもある宝積寺にも半鐘を寄進している。
「宝積寺史」には小柏重高が寄進した半鐘について、貞享四年(1687)四月作、高さ五十九センチ、口径三十五センチ、鋳造人西宮四郎兵衛。この鐘は20世仏舟海代に小柏一燈居士が寄進した物である。としている。
重高はいま、不動寺の奥まった位置にある開山堂の中央に、木像として黙然と端座している。そのたおやかな表情はお参りに訪れる人々を迎えて、祝福を与えているようにも受け取れる。
開山堂の内部は土間造りで敷石畳になっている。広さは五間四方というから25坪ほどになる。正面には等身大の潮音の寿像があり、両脇に三十センチほどの開基者の木像が鎮座している。
小柏重高・吉重父子(実は兄弟)の象と位牌が並び、重高室妙香・市川半兵衛・白石六郎左衛門の開基となった四人(吉重を除く四人)の木像が鎮座している。六郎左衛門は黒滝山の土地を寄付し、半兵衛は重高と縁戚であり、かつ六郎左衛門の仏道に掩護を与えていた。
この四人が開創・開基となり潮音を請じて、黒滝山不動寺を開山したのである。開山堂には、後に一切大藏経を寄進した栄三禅尼と、御代田の普賢寺に梵鐘を寄付した吉重の木像が安置された。
この六体の木像は1852年の山火事で、開山堂が類焼した時も寺僧と近隣の人々によって一時避難し類焼を免れた。
白石六郎左衛門は、小柏山養命寺において出家し祖源の法号を唱えていた。後に黒滝山に戻り、巌窟にこもって20年間の修行を重ねていた。近在で開かれた潮音の説戒に現れ、問答を仕掛けその結果潮音に師事し、名も高源と改め黒滝山の土地を寄進した。
小柏重高・白石六郎左衛門・市川半兵衛そして潮音の四人は奇しきも不思議な縁で結ばれていたのである。(「関東の仙境黒瀧山))
黒滝山不動寺にはこの他、黄金色に輝く金体不動明王があり行基の作と伝えられている。「不動堂」に安置され十二年に一度、開帳されるだけである。平素は小柏重高・吉重両人の寄進した厨子の中に納まっていて、その扉は固く閉ざされている。
小柏吉重と古文書
小柏重高の弟(重氏の二男)、重弘は白倉村の山田家を相続し、山田與惣右衛門を名乗り後に全當と号した。妹(重氏の長女)は榎谷戸村(坂野)の小柏彌五兵衛光高の妻となり法名を慧観という。
その長子の光氏は中俵家を継ぎ中俵作重郎となり、二男高行彌平治が榎谷戸家の家督を相続した。
小柏彌五兵衛光高の長女は重氏の二女(養女)となり、高崎城主安藤右京進重長の家臣金井重兵衛勝光の妻となって法名を妙林とした。
重氏の三女は藤岡の住人、桜井五兵衛勝行の妻となった、法名は逞心とする。
重氏の四女は始め沼田城主、真田伊賀守信利の家臣、堀田九兵衛近忠の妻となり、後に藤岡の広瀬左源太季孝に嫁ぎ法名を光心とした。
小柏重氏の四男徳氏は丑之助と称し後に宗莫と号した。真田伊賀守信利に仕えていたが、真田氏が改易となり沼田を去る前に同家を辞して小柏村に戻った。
五男の常氏は三波川の飯塚家彦右衛門の名跡を継ぎ、飯塚平右衛門と名乗り、法名を了真とした。
六男、吉次は小柏権右衛門であり、後に又兵衛と改めた。摂州尼崎の城主青山大膳亮幸利に仕えていたが、後年浪々とした暮らしを送った。後に甲斐の徳本流の医師となり露休と号し小柏村に住んだ。
重氏の五女は村上の住人、飯塚惣兵衛春猶に嫁ぎ、法名を貞真とした。(竹野か)
六女は松枝(松井田)の松本勘兵衛清房の妻となった。重氏の長男重高には嗣子がなく、本多家に仕えていた弟(重氏の三男)の吉重が養子となり、小柏家の家督を受け継いだ。
吉重は初め平吉と名乗っていたが後に権兵衛と改めた。その法名を一桂といい、不動寺には吉重の建影像が残されている。
「群馬懸多野郡誌」によれば、吉重は黒滝山二世の月浦和尚について禅を学び、和尚が浅間山に普賢寺を開いた時には梵鐘を寄進した。その鐘は今も同寺に残っている。(同家系図及び古文書、小幡伝説)と記述している。
同誌では小柏家に伝わっていた系図以外の古記録「別記」を、ここで「家系図及び古文書」としている。この表現は家系図と古文書が一繋がりになっており、家系図と古文書がセットであった事を示している。
文書舘や他の旧家にあった古文書であれば「家系図、古文書、小幡伝説」と記述する筈である。もしくはただの「古文書」では、何が何だかさっぱり分らず真偽の程が疑われるので、題名や所蔵家の名前を記すのが当然である。
史書を編纂するほどの歴史研究家であれば尚更の事、その責務ともいえるところである。したがって、題名のない古文書は同系図に記載のある「別記」にほぼ間違いないとみられる。
家系図と密接な関係を持っている古文書であったから、題名を記さず「家系図及び古文書」と二つを一つの物(セット)として表現したのだろう。
系図と関係のない古文書であれば「人別帳」とか「宗門改め帳」とかその文書の題名を必ず記す筈である。或いは表紙の付いた冊子にはなっていなくて、多くの古文書と同じように、ある年代(又は事跡を遺した人物)ごとに一塊になっていたのかもしれない.
この記述によって小柏家に、系図を補填する先祖の事跡を記録した「別記」があった事がほぼ明らかとなったと言えようか。この正系図が縦糸となり、「別記」が横糸の役目を担って小柏家の歴史を連綿と伝えてきたのだろう。「多野郡誌」の、この項を執筆した担当者は自分の目で「別記」を閲覧し執筆したものであろう。
「甘楽町史」も「多野藤岡地方誌各説編」も吉重を一柱と記しているが、小柏氏正系図では一桂となっている。よく似ている字なので誤写であろうと思われる。
徳氏と吉次兄弟の足跡
天引に移住した可能性のある、徳氏と吉次兄弟の時代と足跡を少し追ってみよう。
小柏重氏の四男・重高の弟・徳氏が沼田城主の真田伊賀守に出仕した経緯は不明だが、すぐ上の姉の夫・廣瀬左源太季孝が伊賀守に仕えていた事からその関係と推測される。
或いは伊賀守には同時期に小幡氏の係累も仕えていたから、その関係で仕える事になったのかもしれない。
真田氏は清和天皇を始祖として、松代藩・沼田藩を有する巨大氏族である。真田伊賀守信利は幸村の兄・信之の孫であり、父は新吉である。信利は明暦二年(1656)に沼田領を相続した。
その後、信利は本家松代藩の相続権は自分にあるとして、従兄妹の幸道と争ったが幕府の裁定では認めてもらえなかった。信利は検地を実施して、三万石(実質六万石)を十四万石として幕府に報告したという。
天和元年(1681)には、幕府から両国橋の改修を命じられたが工期までには完成せず、増税に苦しむ領民は一揆に訴えた。
殊に有名な磔・茂左エ門が一身を投げうって、将軍綱吉に直訴に及び磔刑に処されたとされる。しかし茂左エ門の話は伝説であり、真偽の程は定かではないとする異説もある。
幕府は信利の不手際を許さず、所領の沼田藩を没収し山形藩・奥平家にお預けとした。信利が46歳の時であった。
小柏徳氏は明暦の伊賀守信利の改易前に、同家を辞して小柏村に戻ったと正系図に記されている。沼田藩は、信利の沼田城の改修・江戸藩邸の改修・実石高の水増し報告などにより、領民は窮乏に苦しんでいた。
徳氏はこうした信利の失政・悪政に愛想をつかして辞職したものであったか。寛永五年(1628)~天和元年(1681)の「沼田藩真田氏家臣総覧」には徳氏の名前は見られない。
53年間に亘っての名簿なので、この間の全ての藩士の名前を書いているのか、それともある一時期・特定の年度の物なのか細かい事までは分らない。○○同心○○人等とある記載の中に紛れてしまったものか。短期間の出仕であったから名前が残らなかった可能性もある。
いずれにしても、父子共に属した上杉家や武田家とは違って、小柏家と沼田真田家との関わりは強いものとは思われない。したがってごく短期間の出仕であって、帰農して大地主としての権益を拡大していた兄の重高の元に帰ったのだろう。
徳氏と同じく、堀田九兵衛近忠・廣瀬左源太季孝の名前も先の総覧に見つける事は出来ない。
これは如何なる理由によるものだろうか。小藩にあって徳氏も季孝も近忠さえも全くの無名で無役であったとは考え難い。かなりの漏れがあるようだ。
小柏吉次が仕えた青山氏は藤原姓であり、祖先は上野国吾妻郡青山郷の出身であり家康の譜代大名である。掛川藩から尼崎藩四万八千石に転封となり、四代に亘って尼崎城に住んだ。
寛永二十年(1643)父の死により、青山大膳亮幸利は尼崎藩の二代目藩主となった。東京の青山霊園は青山家江戸屋敷の跡地であり、今の「青山通り」は青山氏にちなんだものという。
吉次は青山家を辞して帰路の途中、各地を旅して甲斐に入り当代の名医と謳われていた永田徳本(とくほん)に出会い、師事する事になったと思われる。徳本は、戦国時代から江戸初期にかけて活躍した人物である。
永正九年(1513)に三河で生れ、寛永六年(1630)に没したとされるが生年没年・生国共に異説がある。医術は出羽の山伏に手ほどきを受けて、後に鎌倉で中国の李朱医学を学び、後に独自の医学を確立し徳本流と呼ばれた。一説には紀州の山中で修行した名僧ともいうが、これは江戸後期の高僧徳本上人(行者)の事績と混同したものと思われる。
徳本は奇特な人で何所でも往診して、特に貧しい人々を慈しみ、後には各地を転々として医術を施していた。「梅花無尽藏」など数点の著書も残している。当時の医者はお金持ちの人からは沢山診療費をとり、金のない人には安くしていた。これを徳本は安くしてしかも均一料金にしていたという。このため常に貧乏していたが、一向に気に留めなかった。
徳本の医術は投薬が中心だったらしく、薬籠を背負って牛に乗り「甲斐の徳本、一服十八文」と声を挙げながら気ままに行脚したという。中でも伊豆から武蔵国の間を主に行き来していたようだ。
徳本流の医師でもう一人名医と謳われた人物に、小島蕉園が居るが蕉園は江戸後期の人なので、吉次はやはり徳本の直弟子だったとみられる。
現在、湿布薬「トクホン」でお馴染みの株式会社トクホンも、永田徳本にちなんで名づけられたものである。
三波川妹ヶ谷の開拓者 竹野(小柏)
妹ヶ谷の地名由来
群馬県姓氏家系大辞典(角川書店)の鬼石町の項に次のように出ている。「三波川字妹ヶ谷の小柏氏は、藤岡市上日野の小柏氏の妹、竹野が分家したと伝え妹が新たに開拓した谷なので、妹ヶ谷の地名が起こったという。」
「竹野」は八郎左衛門の妹と伝えられている。「多野藤岡地方誌・各説編」を紐解けば、日野村小柏の小柏八郎左衛門の妹、竹野が開拓したので「妹ヶ谷」と名付けたという。
とある。八郎左衛門は江戸時代以降に時々世襲された名前である。一番可能性の高い八郎左衛門は、黒滝山不動寺の開基となった一燈居士・重高である。その逞しかった妹とは重氏の五女(重高の妹)ではあるまいか。
小柏氏正系図にある五女が嫁いだ「村上」とは何処なのか、いまだ判明していないが、同系図には遠隔地であれば、武州とか松井田の庄とか藤岡の住などと頭につけて記載してあるが、村上の住としてあるだけで頭につける町名の記載はない。
この事から上日野の近くであって、誰もが知っていた地名・村名であったのだろう。してみると「飯塚家」に嫁いだとあり、近隣で飯塚家といえば、かねてより縁戚となっている三波川の飯塚家とするのが必然の結果となろう。
現在の藤岡市鬼石町である。妹ヶ谷は三波川の少し上流の地であるので、その近くに分家した家であった可能性も考えられる。
伝統に基き、系図にはその名前がなく、女子とのみ記されているのが口惜しいといえる。小柏家の女子は大力があったと、何人かの逸話が残されており、後世に伝説を残すほどであった事から、この五女も自ら鋸・鍬を取って開拓にいそしんだものと推測はされる。
飯塚家文書1(県立文書館収蔵目録)の三波川の概要によれば、同村は三波川に沿って東西に長く、18の耕地が点在する山間部の村落である。面積は広いものの地形は丘陵地或いは山地で起伏に富み、急峻であるため水田はなく、僅かな畑地は傾斜地を利用しているとある。
明治13年の戸数は248戸、人口は1,099人である。その他、社13戸、寺1戸となっている。
「鬼石町誌」には徳川初年の割付石高芋萱村33石6斗とあり、譲原村などでは1728年に「満水愁作水損災害」と記されていて、洪水で相当の被害が出たようである。また天明年間の1783年には浅間山の大噴火があり、妹ヶ谷一帯にも40センチほどの降灰があった模様である。この当時の時代背景を考える上において注目するべき記事ではある。年貢は各戸の生産高の半分とあり、現代の税金と比べてもかなりきついものであった事が分る。
三波川における1733年の人口は1,511人とある。明治8年頃の編集と見られる「上野国郡村誌」によれば、三波川の字地に、下妹ヶ谷、竹谷戸、上妹ヶ谷の名ありとしている。戸数は248、社13、寺1、計262戸、人口1,990人。(先の記述と出典は同じ物のようだ)
民業は猟業23戸、製茶8戸、薪炭180戸と出ている。また諏訪社は四社あり、村の中央に2、村の西に2あり祭神は建御名方命、祭日は7月25日。鹿島社は村の西にあり祭神は武甕槌命、祭日は9月19日。と記載がある。
妹ヶ谷は古くは芋萱と書き、芋ヶ谷と書いた事もある。現在は妹ヶ谷になっている。
この事から芋・萱が採れた場所という事が推定できる。また萱は江戸時代などには、大事な資源であった事から、萱が採取できる萱場は耕地同様で重要な意味を持っていた。
飯塚文書 目録 
「村上」とは何処か
八郎左衛門を最初に名乗った重高の兄弟は11人もいたので、近隣に嫁いだり移り住んだりして小柏氏の影響力を広げたものと考えられる。
鼠喰城を築城し宝篋印塔も建立した重家の時代が、小柏氏の第一期の黄金時代であったとしたら、小幡一族と共に戦国の世にその名を轟かした高政・定政父子の時代が第二期の黄金時代。
そして黒滝山に名僧潮音を招請し、不動寺を建立し開基となった重高の時代は第三期の黄金時代にも相当すると考えても良い。重高の次に八郎左衛門を名乗ったのは記重権八郎である。記重の妹は二人居るが、一人は早世しており、もう一人は藤岡の庄田家に嫁いでいて竹野となる可能性は低い。
また時代もかなり降ってきてしまい年代的にも合わなくなる。したがって多野藤岡地方誌のいう八郎左衛門はやはり重高という事になる。
重高の跡を継いだ弟・吉重も仏教に深く帰依し、同寺二世の月浦和尚に教えを受けており、不動寺に今なおその建影碑が残されている。三波川小柏氏は現在も、不動寺との深い縁由を保っている。重高・吉重・竹野の兄弟であるから、結びつきが深い訳も十二分にうなずける。
これより重氏の五女・重高の妹を「竹野」と呼ぶ事にする。竹野の二つ上の兄、常氏は三波川の飯塚彦右衛門の養子となって、平右衛門を名乗り飯塚家を継いでいる。
彦右衛門家は戦国期以来の系統を引き継いでいる、三波川名主家の飯塚家の一族であろう。
「飯塚家文書(1)」には近世の行政文書、約6,000通の目録が収載されている。同文書の目録を丹念に見ていくと「組頭彦右衛門」の名前が何箇所にも出ている。公文書の差出人となっている物が多く、1688年から1717年頃の約20通ほどの文書に関わっている。
時代が新しいので後代の世襲名の組頭彦右衛門であろう。同時期の三波川の名主は与市(飯塚)である。また平右衛門(常氏)の名前は、畑質物手形のやり取りの文書として1695年(元禄8年)に記載がある。
私の仮説では平右衛門の出生年は、竹野より4年早い1642年となり、1695年にはその年齢は53歳となる。したがって此処に記載されている平右衛門とは同一人物の可能性が高い。
もう少し詳しく「飯塚家文書(1)」の記載を見ると、質物として山之はな大道下の畑と植木を取って金子六両を貸している。五年季とあるので、これがおそらく返済期間であろう。
地主市左衛門、証人太兵衛他六名、組頭二名、名主市太夫と書かれている。これを遡る1680年には逆に畑を質物として供出し、金三両を借りている。此処の記載では下いもかや(妹ヶ谷)村平右衛門となっており、住所地が下妹ヶ谷であった事が分る。
常氏が養子に入った飯塚彦右衛門常清家には以前、重氏の姉が嫁いでおり常氏にとっては叔母に当る。
つまり常氏は叔母が嫁いだ飯塚家を継いだのである。これ等の縁由から竹野は飯塚家に嫁ぐ事になったのであろう。昭和中期に長く鬼石町町長を務めた名主家の飯塚馨の前々代にあたる、三波川村長の飯塚清は下日野の小此木家から養子として飯塚家に入った。
この小此木氏との関わりは不明ながら、小柏定政の養女が小此木吉左衛門兼佳に嫁いでいる。さらに近世において小柏舘の最後の住人となった「小柏逸」が、三波川の飯塚時五郎に嫁いでおり、小柏氏と飯塚氏との縁由は深いという事が出来る。
こうした事から竹野が嫁いだ村上の住人、飯塚惣兵衛春猶もまた三波川の飯塚氏であろう事は疑えないという事になろうか。
「飯塚家文書(1)」を見ると惣兵衛の名前は9箇所に記載があるので、三波川の住人に「惣兵衛」なる人物がいた事は間違いない。その文書の確認されている年代は1666年から1834年までに及んでいる。
この間168年間に亘る。やはり世襲名であって、父子数代にまたがって名乗られたもののようだ。竹野の出生年を1646年と推定すると、1666年の同文書に記された惣兵衛はひょっとすると竹野の良人になるかもしれない。飯塚家文書(1)には次のようにある。
一札の事(午夏中御本丸様へ指上ヶ候小麦代鐚百六十四文御公儀様より被下候を貫納之割ニ指引請取)寛文六年六月十日 惣兵衛、太兵衛、三右衛門、三右衛門、(ママ)三郎左衛門外芭地名八名
十名の連名で惣兵衛が筆頭・代表者になっている。文政十年(1827)に、奉行役所へ提出した文書には「三波川村百姓代(代表)惣兵衛」と記されている。また享保十七年(1732)の文書には「小平村惣兵衛」と記されている。
したがって、この惣兵衛は下三波川の小平村に居住していたもののようである。(小平村と妹ヶ谷では三波川の西端と東端とになってしまう。)
尚、後年小柏八郎治の娘逸が嫁いだ飯塚時五郎は、時の三波川村戸長の飯塚与一郎の親戚である。
時五郎は秩父事件が勃発しようとして風雲急を告げる頃、藤岡警察によって没落農民を纏めるよう「雑商人世話役」に任命された。警察は没落農民を村単位の組合に纏めて監視する政策を採ったのである。
さて「姓氏家系大辞典」に記載の「妹が新たに開拓した谷なので、妹ヶ谷の地名が起こったという。」という文章の意味するところ・行間を斟酌すれば、妹ヶ谷にはそれまで地名・字名がなかったと解釈するのが一番自然である。
「多野藤岡地方誌・各説編」に記載の文章も、家系大辞典とほぼ同様である。妹ヶ谷の地名が起こるまでは、その地はただの山であり山林原野の類であったと考えられる。
私の田舎では集落の前にある名のない里山を「前山」と簡便に呼んでいた。また北側に山のある所は「北山」と呼ばれていた。開拓前の妹ヶ谷もそんな風にとられ、呼ばれていたのではなかったか。「竹野」が開拓して「妹ヶ谷」の地名となっていった可能性が高い所以である。
ところで次の問題は、現在の地名には見つからない竹野が嫁いだ「村上」は何処であるのか?という事になる。明治14年の地理雑件による「群馬県小字名索引」を見ると、邑楽郡の田谷村と日向村に字名として「村上」がある。
邑楽郡は太田市と栃木県の足利市の間に位置しており、これはあまりにも遠すぎる。そこで間違いを恐れず大胆に比定してみれば、その村上の地は現在の下妹ヶ谷ではあるまいか。
先述したように竹野の兄、常氏平右衛門の婿入り先の飯塚家も下妹ヶ谷と見られる。
「奥ノ反」付近に村上の字名があればとも思うが、これら近隣に同字名は見つからない。状況を総合的に見ると「村上」は下妹ヶ谷の地にあったとする事が一番しっくりくる。
此処では、新資料が発見されるまでは「村上」は下妹ヶ谷にあった字名としておきたい。三波川の清流は東御鉾山にその源を発し、上妹ヶ谷を通って下妹ヶ谷を経由して桜山の麓を流れ、神川町に向かって流れている。
妹ヶ谷付近の北方から滝の沢が合流する辺り、上姫神社・東養寺のある辺りまでが、開拓され耕地があった限界ででもあったのだろう。
その辺りから上流が村のうえ、川の上を意味する「村上」と呼ばれていたと想像できる。そこは村の一番上流に当たり、そこから上に登って行くと東御鉾山の山腹に突き当たり、道は行き止まりとなってしまう。
「村上」の辺りでは芋(自然薯)や萱が取れたので、その季節になると下流の村から村民が採取に来ていたのだろう。このため時に「芋・萱」と呼ばれた事もあったかもしれない。しかし入植者が増えるにつれて、萱場は畑へと変貌を遂げて芋萱の面影はなくなってしまった。
やがて小柏氏の妹が来た..妹が切り開いた谷..と人々の口の端に上るようになり、幕府へ提出する公文書などにも「妹ヶ谷」と記載されるようになった。そして村上と呼ばれていた土地は、いつしか「妹ヶ谷」という名と文字に定着していったと考えられる。
小柏氏正系図の中にその子女の嫁ぎ先として、記載されていた「榎谷戸」という小字名も今では使われていない。
そこは現在の上日野「坂野」である。「榎谷戸」も「村上」と同じように、町の名前の記載はなくただ単に「榎谷戸」と書かれている。してみると、この「村上」も小字名であって現在は消えてしまったものであろうか。
さらに、以上の比定・仮説の傍証を支え得るものになるかもしれない絵図がある。飯塚家文書の中に見い出したものである。役人が“地境”を調停し、絵図として交付した物と見えるその絵図には、雨降山と思える山の峰が三つ描かれている。
そしてその麓にラフな線が引かれ、東小柏新三郎、北新井徳治郎などと書かれている。なお、絵図と別項との両方に次の字名が記されている。字「熊燈釜」字「思火久保」字「二タ木釜」字「臼倉」の四字名である。
妹ヶ谷のブナン沢辺りだけで、これ等多くの字名があったという事である。近隣の人もこれ等の字名を、いま覚えている人は少ないのではあるまいか。ただ三波川小柏氏から、頂いたコメントでは「熊焼釜」と「二木釜」は今でも使われているとの事であった。
この他、飯塚家文書(1)を見ると、三波川には数多くの小字名があった事が分る。次に列記してみる。
かんばきちょうご沢 かつきくね 上之くぼ かきのくぼ わせくり沢 おノくぼ(尾之久保) たき山(瀧山) はりまがいと 柳のくぼ 西くぼ 長くぼ 竹ノはな よこ鳥 龍之沢(たきの沢) ねこかいと はた沢 大平 高之内 はんにゃ塚 高辻 松山 坂本坂 若社 中之久保 中林 牛之平 ししなご山 よしの入
しおなし 明か沢 久保之背戸
沢入 長畑 中之久保 上之山 若林 宮之沢 なみ木 みやえ之沢 かき之木平 矢のたわ あかけ沢 山之鼻 馬之平 宗沼 高石 久保之畑 とかけ場
うへえ(之)山 鬼岩之畑 たちう場 天狗岩 神なら 大門 宮向 丸畑
長とろ はまへ場 堂之うえ さい之神
中山 宿長 赤岩 小すち 芝原 ふがめ 沼之平 長久保 松山 坂本 木おとし 中之平 森脇 松之久保 ささ山 上之平 まみね 堂のうえ おじ久保
明らかに小字名と思われるものを挙げたが、この他にも屋敷前とか堂下とか向平岩、横道下など、かなりの小字名があったようだ。これにより江戸時代の三波川では場所を示す(話す)時はこれ等の多くの字名で示していた事が判明した。
「村上」という字名も、このように自然消滅していった一つであった可能性がある。

飯塚家文書より
そして、竹野が清流に恵まれた小川沿いの「竹谷戸」へ入り、耕地或いは萱場を開拓したので、そこは「竹の谷戸(かいと)」と呼ばれた。
折からの不景気でここにも人がやって来るようになり、竹野は更に上流に向かい上妹ヶ谷に耕地を開拓する。
この時には移住してきた人や家抱たちに手伝ってもらい、その経験から竹野が指揮をとったのではなかろうか。三波川の家抱は上日野地区よりも早くに解放されたが、この頃は本百姓一家で平均して3人の家抱を抱えていた。
小柏氏の妹の「竹谷戸」の上だから、そこは上妹ヶ谷と呼ばれ、竹谷戸の下流にある耕地付近は、村の(いちばん)上(うえ)の意味が薄れ「村上」から次第に下妹ヶ谷と呼ばれるようになっていったと推測する。
なぜ飯塚の名前でなく妹(妹ヶ谷)になったかといえば、その頃の小柏氏の影響力が大きかったからと考えられる。
「村上」の候補地をもうひとつ挙げるとすれば、「小野上村の村上」になろうか。この地の「村上」には飯塚姓の家が20戸ほど現存している。かなりの勢力を持っていたらしく江戸時代には名主を勤めてもいる。
群馬県内の殆どの飯塚氏は、源氏車の家紋を使用しているが村上の飯塚氏も同紋である。仮に「竹野」が嫁いだ村上が小野上村とすると、どんな縁でこんな遠方に嫁いだのか、どんな事情で三波川に移ったのかの説明が難しい。
上日野周辺では「村上」はおろか「小野上村」の村名も知られていない。当然小野上村の地理や歴史・風俗も皆目知られていない。
こうした場所に嫁いだとしたら「村上ノ住人」という表現ではなく「小野上村惣兵衛の妻」と記録されてしかるべきと思われる。
小柏氏の縁戚は奈良山・細谷戸・坂野・上日野(小柴・小此木)・箕輪・三波川・天引・塩沢・多比良・小幡・福島・白倉・藤岡・南牧・高瀬・倉賀野などの近隣であり遠くても松井田である。
また小柏氏と縁由の深い三波川の飯塚氏は、軍配団扇の家紋を使用していて他の県内の飯塚氏の家紋とは異なる。
竹野の妹ヶ谷入植期
開拓が進み、山を越えた小柏村からも時に応援が来たという事も十分あり得る。おそらく三波川の飯塚家を継いだ兄の常氏の協力も得られたのであろう。そして小柏村から、小柏姓の人や常氏の二男、三男などの子孫も移り住んで来て、小柏集落を形成したと考えられる。
現在も諏訪神社を中心として小柏姓の家が8軒も集中している。妹ヶ谷の地名・由来について「鬼石町誌」は黙して何も語ってはいない。伝説の項を見ても妹ヶ谷の地名についての言及は見られない。
妹ヶ谷には現在11軒ほどの小柏姓の家が存在しており、竹野の子孫も分家などして、由緒ある小柏姓を名乗ったものと推測できる。
江戸時代の地境を調停した絵文書を見ると、小柏姓の人が何人か山などの土地を持っていた事が分る。この絵図は小学生が描いた絵のようなものであり、一枚の和紙に描かれて、これ以上はない大雑把な物である。
芝地などの区分は墨の濃淡によって区分されている。ここに現れる小柏姓の人は先述した新三郎の他には小柏平治郎の名前が見える。他には新井徳治郎の名があり、この三人の地境を調停したもののようである。
三波川小柏氏の話では、この小柏新三郎は「おそらく竹野の子孫である」としている。これで広大な土地を所有している理由も頷ける。新三郎は飯塚家文書(1)を見ると、明治5年に質地にとった畑の境書き書を受け取っている他、同年中に畑質物証文を受け取ったとの記載がある。
先の絵図の作成年代も明治5年とそうかけ離れてはいないと思われる。
竹野は後年小柏家に住まいしていたもののようであるが、二男か或いは三男の家に子守などを頼まれて居ついてしまったものか。または自分は離婚して分家した二男の家に身を寄せたのかもしれない。
現在も妹ヶ谷の小柏氏が居住しているエリアの、隣接地に4軒の飯塚姓の家が存在している。余談になるが昔の女性は何度も結婚したものである。子育てや食事・家事の役割を担い、働き手としても大いに必要とされたのである。現代よりも少ないが離婚も相応に存在していた。
資料もなく知る人もない時は、傍証を積み上げる作業によって、ある程度真相に近づく事が出来るのではなかろうか。
竹野が移住した時期をやや強引に推側すれば、1686年頃になるかもしれない。320年程前の事になる。推測してみると竹野の出生年は、1646年頃と考える事が出来る。父の重氏が1602年生れであり、10人目の子となる竹野が生れた時、重氏の年齢を46歳と考えてみた結果である。

妹ヶ谷不動尊
三波川小柏氏の話では、妹ヶ谷不動尊の再興が1695年であるとしている。この事から移住して9年ほど経過して、暮らしも落ち着いてきた頃に不動尊を再興したと考えられ、移住年代に大きな誤差はないものとみる事が出来る。また江戸時代初期のこの頃は各地で盛んに新田開発が行なわれている。
また「群馬県の地名」を見ると、寛文郷帳には「芋萱」と記載があり、元禄郷帳になると「竹谷戸」の記載がある事になっている。寛文は1661~1672年、元禄は1688~1703年である。
1672年にはまだ芋萱であったが、元禄期(1688~1703)の調査には「竹谷戸」が登場している。したがって1673~1688年の間に「竹谷戸」の字名・地名が出来たとみる事ができる。先に挙げた入植時期1686年説を補強するものといえようか。
飯塚家文書(1)に三波川の絵地図が収載されている。この地図には「芋萱」ではなく上妹谷・竹谷戸・下妹ヶ谷と記載がある。
地図の作成年代と、時代がやや近接してくる可能性もあるが、同文書は1716年頃の文書が多く収載されており、矛盾はしないものと考える。
この約320年前というのは、小柏定重の三兄弟の子孫が天引へ移住したといわれており、その時期を推測してみると340年程前となり、双方の時代差は20年となり近接している。
これによっても重高の兄弟たちが近隣に移住して行った気配が窺える。この時代には士農工商の下に、エタ・非人が置かれるなどの厳格な身分制度があった。武士の中にあっても侍士、徒士、足軽などの厳然たる身分差があった。
幕府の財政は逼迫し享保の改革が行なわれたのもこの頃である。また新田開発が進められた反面、飢饉や洪水も多く農村の崩壊もあったという。この頃から各地での激しい一揆が起こるようになった。

三波川 野々宮神社
三波川小柏氏に、妹ヶ谷にある野々宮神社と諏訪神社には、小柏氏の家紋、丸に釘抜きの紋があると聞き現地において確認した。
この紋は小柏定政が武田信玄より領地として、信州佐久の田ノ口を賜った時から使われるようになった家紋である。それ以前は平家と同じ揚羽蝶の紋を使っていたので、この事も年代が矛盾していない事の一つの証左となる。
また、上日野にある野々宮神社の横を、大谷川に沿って登って行き妹ヶ谷峠(720m)を越えて、妹ヶ谷側に降りて行く道沿いを流れる渓流は「野々宮沢」である。
上日野から来た竹野が、野々宮神社にあやかってそう呼んだ可能性が垣間見えてくる。
先述の三波川小柏氏の話の中に、妹ヶ谷小柏家の墓地と上日野の小柏氏の墓地とは、石塔や祠などが良く似た造りになっているとの指摘があった。更に上日野小柏(村)と妹ヶ谷の地形・景色がそっくりであるとしている。
同氏は共に街道をきっちり抑える要所を占めており、狼煙で山から山へと合図を送って緊急の連絡をとっていたのではないかと推測している。
これまでに見てきた幾つかの傍証から、妹ヶ谷に小柏氏のうちでも有力な子弟が移り住んできた事が髣髴(ほうふつ)と浮かび上がってくる。

三波川 諏訪神社
妹ヶ谷小柏家の墓地にある、小幡家の女中の墓と伝えられている二つの墓は、お菊・お春のものである可能性は低い。その推定する理由は明瞭である。三波川小柏氏とお菊は直接の関わりを持っていなかったのだ。また年代的にもかなりの開きがある。
お菊をここに葬るとなると熊倉山から、その遺体を降ろして二本木峠を越えて小柏(村)に出て、更に山に登り妹ヶ峠を越えて来なければならない。困難を極める作業となる。
供養塔を建立するのなら納得できる面もあるが、大叔父(竹野の)が救出したかもしれないという、そのくらいの縁の人の墓を作っていたら畑は全て墓になってしまう。戦国時代から江戸初期には周囲の人が死ぬのは、まったくもって日常茶飯事の事だったのである。
人が生れて死ぬ事、その事こそが日々の暮らしだった。外科手術の技術が、格段に進歩を遂げた現代とは生命価値観も違う上、童子・童女のまま亡くなる人も大変に多かった時代である。
妙義町の中里にあるお菊の墓も、宝積寺や熊倉山からは間に富岡市を挟むなどかなり距離があるが、同地にはお菊の実家(藤井家)があったとされているので矛盾は生じない。
小幡家の女中の墓であるとの伝承に真実味が見られるとすると、江戸小幡氏・安中野殿小幡家との関連性が注目される事になるかもしれない。小幡氏(信真)は小田原籠城から解放されると、信州真田家を頼って上州を退去しているのである。
小幡信秀・直之父子は幕府から1,100石を給されており厚遇されていたといえる。その「野殿」の地名は今も安中駅の南に残っている。或いは小幡氏の分家がある法久小幡氏との関連か。
妹ヶ谷城と小柏氏
藤林伸治は、妹ヶ谷城の麓に位置する妹ヶ谷不動尊を中世の山城と見ているようだ。
同氏の取材ノートに、不動尊の詳しい配置図が描かれて「中世、山城の構え」とメモが付されている。
妹ヶ谷城を築城したのは誰か?そしてその城主は誰か?という命題はなかなか興味のあるところである。ここでは一つの小考察を述べさせて頂く。
野々宮神社近くにある妹ヶ谷城と、小柏氏との関連性は色濃く漂って来ているが、これを明らかに出来るものを今は提示出来ない。
或いは飯塚氏が関わった物かとも考えられるが、同氏の本拠地琴辻からはかなりの距離があり、正面の前進基地でもない山腹の後背地となるような位置に砦を築いたとは考え難い面がある。
妹ヶ城の位置は不動滝の西南、野々宮沢の南の山上になる。標高は200mくらいの所で、長さ30m、幅12m二段の保塁である。妹ヶ谷不動尊は下曲輪である。(山崎 一 稿「奥多摩地区の故城塁址」)
曲輪とは、自然の地形を利用して築いた砦状の石壁や土塁・保塁等を指しており、不動尊までが妹ヶ谷城の一部であった事になる。この研究結果を読むと砦のような物が浮かび上がってくる。
上日野の小柏氏が鎌倉方面からの侵攻に供えて、鼠喰城の出城とした可能性も高いのではなかろうか。何故なら妹ヶ谷から山を越えて来れば、すぐに小柏村となり侵略される危険性が高まる事になる。
小柏氏はその舘の東、約200mの所に砦を築いていた。ここは街道を見下ろす位置にあり、小高い丘・山のような場所であり、其処は城山(じょうやま)と呼ばれていた。
砦状の物も城(しろ)と呼ばれていた事が分る。妹ヶ谷城もその役割から見て砦のような物であったと考える事が出来る。その規模にもよるかと思えるが、先に見たように砦であっても城と呼ばれたのである。
この城山の砦と妹ヶ谷城の関わりが考慮されるところである。城山と妹ヶ谷城との間で、狼煙などによる連絡方法を確立していた可能性に注目したい。小柏氏は西御鉾山の頂上近くにも鼠喰城を築城している。
見渡す限りの山を所有していたと伝えられており、この辺り一帯の山の支配権を有し、配下の者や農民たちも山は自分の家の庭のように歩き回っていたと考えられる。したがって妹ヶ谷城のある山にもその影響力があった事は否めないものとなる。
更に小柏重高は舘の西方の火口山(上平)に草庵を建てて、そこに潮音を招じている。私はこの草庵の場所に思いを馳せる。そこは何もない、ただの山で潅木や萱が生い茂っていたのであろうか?否である。
そんな所にいきなり草庵を建てるとは思えない。してみると其処は以前から小柏氏にとって周知の場所であったのだ。伐採や炭焼きなどで時々足を踏み入れる場所であったからこそ、南傾斜で良い場所だと熟知していたと考える。
そして其処が草庵の場所に選ばれたのではあるまいか。こう考えてくると草庵を立てる前にも、その場所は何らかの用途に利用されていた可能性がある。炭焼き小屋・番小屋・椎茸栽培の建屋なども考えられる。
その他、少し飛躍するが見張り所・信号所があったと考える事も出来る。こう仮定すると小柏(村)を通る街道を、城山と共に東西両方で監視できる事になる。そして南側には鼠喰城と妹ヶ谷城がある。
これ等の施設が相互に連絡をとっていた可能性を考える所以である。築城年代を考えると、まず江戸時代には合戦はなくなり平和な時代が長く続いている上、この時代の事ならば何らかの記録・伝承が残っている筈であるのでこの線は消える。
次に想定されるのは上杉氏・平井城の時代である。その後の上杉・武田氏・北条氏が覇を競って、合戦に明け暮れた時代の可能性も僅かながら残されている。しかし近隣の土塁・山城の築城年代からみて、更に時代を遡るものとみられる。
近隣の諸城・砦には三波川譲原に「真下城」があり、その西には尾之窪城、枇杷尾根城、塩沢城、諸松城がある。諸松城の西に位置するのが妹ヶ谷城である。これ等の諸城は、上杉の平井城の外周を守る防衛線を形成していたという。
真下城は別名下山城といい「上州の史話と伝説その二」によれば、承平五年(935)の築城としている。かなり古いものである。
平将門が平貞盛を追って、この地に来た時に要害の地と見て城を築いたという。「上州の苗字と家紋下巻」によれば、真下城は真下伊豆守吉行の築城としている。「日本城郭全集3」も真下城は真下氏の築城説をとっている。いずれにしても、真下氏が移り住んで来てから真下城と呼ばれるようになったのであろう。
下三波川の尾之窪城は「上州の史話と伝説その二」によれば平貞盛が築いたものという。更に同誌によると、山崎一の調査により東小学校の所が、枇杷尾根城跡である事が判明した。
戦国時代の物であり、近くに貞和二年(1346)銘のある板碑や、室町時代の五輪塔などがある。塩沢の塩沢城については詳しい資料がないが、「日本城郭全集3」には「塩沢砦」として次のように紹介されている。
標高三百六十メートルの山頂に、東西45メートル、南北25メートルの本丸がある。東斜面に幾つかの小郭が認められる。本丸は東縁に堀があり北縁を除く他、高さ1.5メートルの土居をめぐらす。
諸松城の出城であったと考えられる。――
「土居」とは土を積み上げた土手・土塁のような物であろう。この表現を読む限り本格的な城のような印象を受けるが、築城者・築城年代などは不明のままである。
諸松城は諸松にあり「日本城郭全集3」では、本間佐渡守の城と伝えられていると紹介している。本間佐渡守が佐渡の守護代・本間家であれば16世紀後半の人となろう。すると築城年代かなり新しいのかもしれない。
この他「三波川地域城」は土塁・平山城であり、南北朝時代のもの(1392頃)として、飯塚氏の築城と伝えられているとしているものがある。しかしこの三波川地域城が前記のどの城を指しているのか判然としない。
また尾之窪城、枇杷尾根城、塩沢城の全ての別名を「三波川地域城」としているものもある。この他、尾之窪城、枇杷尾根城、塩沢城、諸松城、妹ヶ谷城とは別に「三波川地域城」という城があるとしているものもある。
これ等各種の資料を突き合せて検証した結果、「三波川地域城」は平滑・大内平の保塁六箇所を指している事が分った。飯塚屋敷の近くである。されば、これは飯塚氏の築城に間違いあるまい。
前記の5城とは別の城である。さて収集した資料を全て披瀝して分析したところで、結論を誘導してみよう。
小柏氏は鼠喰城に不動明王を祀っており、西御鉾山の頂上にも不動明王を祀っている。その他黒滝山の不動寺にも不動明王があり小柏氏の守護神ともいえる。三波川小柏氏の話では、妹ヶ谷不動尊・妹ヶ谷城の山・野々宮神社などの土地も小柏氏の所有との事である。
こうした事から、妹ヶ谷城はやはり小柏氏に関係した城址であると考えたいが、この地域は多くの武将が跳梁跋扈したエリアであり、色々な可能性を秘めている。
また飯塚家にはそれこそ厖大という言葉が、ピッタリなほど古文書が残されているが、多くは江戸期などの近世文書である。
記録などは戦国時代からあるようだが、その記録の中に妹ヶ谷城を築城したという記録はないようである。(この資料は整理されていないので断定は出来ない)すると妹ヶ谷城は更に古い年代の築城だったのか、或いは飯塚氏とは別の武将が築城したという考え方が出来る。
ではそれが誰かという事になるが、残念ながら現時点では詳らかに出来ない。城の様式・年代など更なる研究が必要なのである。
「真下城」の築城が935年と見られ、三波川地域城の築城が1392年頃とすれば、この地域での築城は457年間に亘っている事になり、あまりにも長い期間になりすぎる嫌いがあるのだ。
鼠喰城の築城は「日本城郭全集3」では1367年としているが、様式からするともう少し年代が降る(15年程か)可能性もあるとしている。いずれにしても三波川地域城の築城年代と鼠喰城の築城年代は近接している。
真下城と尾之窪城とは同時代の人物が築いたと伝えられており、これからすると両城の築城年代は近接しているとみる事が出来る。
地理的・配置的な面から考察すると、真下城は神流川入口の抑えとみられ、尾之窪城は山上に有る事から砦・出城・見張り所的な意味合いを持っていたと考える事が出来る。
三波川侵攻の抑えの役目を担っていたのが、川の北岸に設置された枇杷尾根城・南岸に置かれた塩沢城・諸松城であり、枇杷尾根城が三波川の入口を守る前進基地のように映じてくる。
塩沢城と諸松城とは近接しているので、おそらくは築城年代にかなりの開きがあるのではないかとの推察が成り立つ。両城は1キロメートルと離れていないので、塩沢城を諸松城の出城と見做す事は危険があるように思う。
諸松城から、その西方に位置する妹ヶ谷城まではかなりの距離がある。実質的・直接的に三波川の領土を守備する枇杷尾根城・塩沢城・諸松城の三城の築城年代・築城者を明らかにする研究が待たれる。
この三城の関わり合い、性格などが分かってくれば、その奥に位置する妹ヶ谷城の姿・輪郭も次第に見えてくるのではなかろうか。
三波川流域の諸城だけではやや史料が少ない感もあるので、この他のやや離れた所に位置する三ッ山城・浄法寺城についても見ておこう。三ッ山城の内城とされる浄法寺城は舘跡・保塁であり、1566年以前に長井豊前守信実が居たという。したがって築城推定年代は16世紀初頭頃になろうか。しかし浄法寺城は1350年頃の築城といわれておりかなりの開きがある。
総花的に概観するとこの地域の城の築城年代は、14世紀後半のものが多いといえようか。14世紀は新田義貞が大いに活躍した時代である。義貞は楠正成の千早城を攻めた後、上野に帰国し準備を整え倒幕の兵を挙げている。
鎌倉を落して京に上った義貞は足利尊氏の勢力討伐を目指し、鎌倉に向かったが箱根の戦いに敗れている。尊氏は鎌倉にいた弟の義直とも血みどろの戦いを繰り広げている。
1355年には新田義宗が上野国に挙兵し、鎌倉を目指して武蔵国の各地が戦場となっている。上野国守護や関東管領の職にあった上杉氏も、またこれ等の戦乱の中に巻き込まれている。
14世紀後半から15世紀前半には、上野国の武士集団によって各地に宝篋印塔が建てられている。この後も結城城合戦が勃発し関東の大動乱へと戦乱は続いてゆく。南北朝の動乱期から関東の大動乱と続く、この時代に幾つもの城が造られたとすればその世相から自然の成り行きであろうか。
ちなみに関東管領の拠点、平井城は1438年・長尾忠房の築城、1467年・上杉顕定の築城の両説がある。
妹ヶ谷城の築城年代が、近辺の諸城と同じように14世紀後半(或いは13世紀後半~14世紀後半)と類推するならば、ほぼ同時期に鼠喰城を築いた小柏氏の影が強くなってくる。
上日野小柏から峠一つを越えれば妹ヶ谷である。北に位置する小柏村を頂点として、鼠喰城と妹ヶ谷城を結ぶとほぼ二等辺三角形の形になる。(妹ヶ谷城の部分がやや右下に長くなるが)
妹ヶ谷城を小柏氏が築いたとすると、竹野にとってこの地は先祖が足跡を残した縁由のある処であり、愛着もあり近くに住んでいて土地勘もあった事から入植したと考えればさほど無理が生じないと言えようか。
なお、三波川小柏氏によれば、飯塚氏は源姓、小柏氏は平姓で地域や役割を分担していたようだとしている。小柏氏は三波川上流の山や水源の管理を行なう傍ら、祭祀や行政の一端を担い、猟民・農民の取り纏め・調停などに力を発揮していたと推定される。上流の方までは目が届き難く、飯塚家は主としてそれ以外の土地を管轄していたのであろうか。
三波川の柔術指南と血判状
県立文書舘の資料の中に血判状と思しき近世文書がある。文書と言えるのか綿布に書かれている物である。後半部分は千切れて失われてしまっているが、千切れた部分の字は「血判状」と解読できる。血判状の字の上の部分に「気楽流」と解釈できる字があるので、門弟たちの間で交された血判状と判断できる。
「剣槍柔術指南、上野国緑野郡三波川住 小柏新左衛門 源計昌」とある。道場で柔術の稽古・教授をして、尚且つ剣術と槍をも教えたのだろう。今でいう総合格闘技がこの時代にもあったのである。
当時人気のあった「気楽流柔術」は柔術・剣術・棒術・鎖鎌術・鉄扇術・縄術・組打術・山谷歩行術・忍術・接骨術・指圧術を教え、上日野にも沢山の道場があった。(「火の谷)藤林伸治)
気楽流柔術の創始者は藤岡美土里村の飯塚臥龍斎である。臥龍斎は戸田流柔剣術の第11世となったが、後に気楽流の流名を名乗って各地に出向き指導した。時に江戸時代の後半・文化の頃である。
いうまでもなく小柏氏は平姓であるが、この新左衛門は源姓を名乗っている。三波川小柏氏の子孫の人の話では飯塚家から三波川小柏家へ来た養子が居たとの事である。
三波川の飯塚家は源姓を名乗っていたとの事なので、この柔術指南の新左衛門も飯塚氏の出身であろう。剣槍柔術とは山岡鉄舟が明治17年に創立した「剣槍柔術永続社」と同祖・同流のものではなかろうか。推測ながら「剣槍柔術」と四文字までが同じ流派が幾つもあるとは思えない。
しかしながら年代的に合致する傍証を今は示せない。だが、血判状だとしたら、そうそう何回も血判を取り交わす事はないと考えるのが自然である。とするとこの血判を取り交わした時期は、もしかしたら明治初期の群馬事件・秩父事件と関わりのあるものかとの推測が成り立つ。
同事件とこの血判状が関係しているとすれば、年代的には無理のないものとなってくる。そして後半の、名前を連ねて血判を押したであろう部分を、千切ってしまった理由も無理なく理解する事が出来るのである。
当時は秩父事件は反乱であり暴徒・犯人と当局から決め付けられ、また新聞報道などもその論旨に同調したのである。しかし今日では秩父事件は見直されるようになり、特に同事件の百周年を契機として評価も変わってきているようだ。民権運動のはしりであった、民衆の自由・権利を勝ち取るための行動とも評されるようになったのである。
秩父事件に関わりのあった各地においても、各種の記念事業・講演会などが催されている。上州困民党と秩父困民党を結びつけたのは、小柏常次郎といわれている。
「秩父事件」井上幸治によると、常次郎は明治17年8月までは三波川に居たとしている。
妻ダイとの仲人であった横田林太郎の家で養蚕を手伝っていたとしている。しかし仲人は小柏菊次郎と横田林太郎で、常次郎は箕輪にかなりの面積の耕地を所有して、上農クラスであった事から、同誌の記述には若干の疑義があると思われる。
私には常次郎が謙遜の意味でそのように供述したもののように思える。常次郎の妻ダイは同志に頼まれて、三波川に鉄砲を借り出す為に行っている。
「秩父事件のおんなたち」は、秩父事件に加担した各村では村ごとに連判状を作ったとしている。
また三波川では山林博打も盛んに行なわれていたようだ。丁半長屋などもあり他に気晴らしになる娯楽もなかった事から、農民も金が入るとよく博打を打った。剣術・柔術の道場もある事から、結構鉄火の気質・風土もあったように見受けられる。
ところで先の柔術指南の小柏新左衛門という名前は、上日野の奈良山小柏氏と偶然に同じものである。奈良山小柏家では新左衛門は世襲の名前であり、代々その当主が名乗っていた。
小柏新左衛門という名前は同じではあるが、同家と三波川小柏氏との関わりは薄いようだ。

血判状
三波川の小柏新左衛門は地主でもあり、飯塚家文書(1)には土地境書き証文を受け取った記録が載っている。
安政6年(1859)に山を質物にとった時の文書である。同様に弘化3年、嘉永2年(1846)にも畑の質物を受け取ったとの記録がある。この他、安政3年に金を貸した記録があり、更に文久1年(1861)に不動尊の積金として村民に十両を貸している。
この記録は妹ヶ谷不動尊の修理(復興)積立金らしい。してみると新左衛門は不動尊の祭祀を司っていたか、或いは修理に際しての施主・世話役であった可能性が強くなる。
また文久2年の文書として、竹谷戸耕地新左衛門との記載があるので、住いが竹谷戸であった事が知れる。
南牧衆市川氏
小柏氏とは黒滝山の開基を一緒に行なうなど、縁由の深かった南牧の市川氏について概観を示すのも意義があろうか。
「藤岡市史通史編」には、不動寺に関連した記事のところに「小柏重高は砥沢の市川宗家と縁続きであり」とある。記録を見る限りでは重高の時代には、既に縁戚を結んでいたとの確証はない。小柏氏正系図は小幡氏に招請された高道の頃から縁戚関係がやや詳しくなっている。
したがってそれ以前は主に当主の記録・事跡を中心として編纂されている。同系図では重高の四代目に当る記重の六女が南牧の市川氏に嫁いでいる。その後、同六代目にあたる重簡の長女が市川帯刀眞直に嫁いでいる。
更に重簡の二代後の重基の二男真太郎(八郎治の弟)が、南牧砥沢村の市川家に養子に入り後継者となっている。更に八郎治の五女が砥沢の市川虎義の妻となっている。
また寛政十二年四月(1800)の上日野村禅宗門改帳を見ると「謙治郎女房 歳三十七 吉川栄左衛門様御支配所南牧砥沢村半兵衛娘」とある。
砥沢村半兵衛とは当然の如く市川家の市川半兵衛と思われる。謙治郎は重簡の弟重方であろう。このように近世にあっては濃い縁戚を形成してきている事が確認できる。
南牧村
甘楽郡に属す。山林及び原野が70%を占め集落は川に沿って形成されている。戦国期には高橋氏、小沢氏、市河氏ら南牧衆と称した国人層がいた。砥沢村には幕府の御用砥(石)を切り出した砥山が大規模に開発された。
南牧道は中山道の脇往還(下仁田道)の下仁田より分岐し、南牧谷を経て信州・甲州に通じる。(「群馬県の地名」)
砥山は徳川家康より朱印状により、市川半右衛門が採掘の権利を与えられていた。採掘された砥石は主に鎌を研ぐのに用いられ全国に流通したという。「群馬県の地名」を見ると砥沢村の記事は大略次のように記載されている。
村の中央を南牧川が東流し、その川沿いに南牧道が通っている。
生島足島神社の起請文に南牧衆として連署している市川氏は、当地に居住し元和九年(1623)より砥山請負人となり、分家筋に当る羽沢村の市川家は南牧関所の関守となっている。
この羽沢の市川氏からは、佐久郡の五郎兵衛新田の開発者が出た。砥沢の村名は砥山に関係しており、当山は幕府の手厚い保護を受けていた。
安政五年の家数は117戸、人口456人、明治10年には砥石880万本を生産したとある。
羽沢村は南牧川の少し上流にあり、砥沢村の奥隣になる。同じく「群馬県の地名」には大略次のようにある。
北西は信州佐久郡田野口村と接し近年は概ね幕府領。砥山普請人足の御用を承っていた。天保九年の家数109戸、人口365人。
羽沢村市川氏が関守を勤めた南牧関所についての要約を次に示す。
中仙道の脇往還、富岡・下仁田線の下仁田街道から分岐する南牧道に設けられた関所、文禄二年に開設され同時に市川氏が関守に命じられた。この市川氏は五郎兵衛の代に至り、信州佐久郡に居を移し七百町歩の新田(現浅科村)を開拓した。関守はその実子の四郎兵衛が羽沢村に戻って勤めている。
南牧関所に常駐していたのは、他に足軽1人、中間2人で、常備の武具に弓二挺・矢50本、鉄砲2挺、鑓二筋、熊手3本、鳶口5本、突棒1本、刺股1本、手錠3組、提灯4張、松明20本、火消し道具、病人籠1台等があった。
関所が通れるのは明け六つから暮れ六つまでで、南牧の女は出る時に手形は要らず、他所の女は手形を必要とした。一度洪水で流失しその後、少し下流に移転したという。
天明三年には浅間山焼けで流失した土砂により再び流失した。修理代は南牧二十一カ村が負担している。通過する者は上下合わせて一日12人程だった。
下仁田から磐戸を通って南牧川に沿って登っていくと砥沢村がある。その少し上流の隣村が羽沢村である。砥沢村と羽沢村の間の道を、北に向かって荒船山の方に入ったところが星尾村である。
同村には先述した「春山大明神」の伝承が残っている。星尾村は西は佐久郡内山に接し、御巣鷹山も同村に含まれる。耕地は全て畑で山畑と切畑で生産性は低かった。 名主は砥沢村名主が兼務した。農閑期には男は紙漉き手伝い、薪採り、砥山普請、砥石運搬で手間賃を稼いだ。
天保九年の家数107戸、人口388人。市川氏は時に市河氏と表記された。羽沢村の、市川五郎兵衛が開発した新田は広大なものであり、そこには集落が出来て「五郎兵衛新田村」と言われた。
また新田開発には農業用水が絶対的に必要となるが、五郎兵衛は約20kmに亘る用水路を掘削し完成させた。これは五郎兵衛堰と呼ばれ今も残っている。この堰は山はトンネルを掘って通し、沢も渡って通過している。(長野県の文化財H・Pより)
市川家の古文書
「上野国郡村誌」によると、羽沢村、市川真英所蔵三通、砥沢村、市川真太郎所蔵八通の古文書(近世文書)が存するとして、次のように記載している。
○ 日向つふらこ之内十三貫文之処進置者也、仍而如件
天文十六年未二月廿三日 虎満 判
市川右近助殿
○ 如前々知行津布羅子不可有別条者也
天文廿二年辛亥五月二日 貞清 判
市川右近助殿
右二通係砥沢村市川真太郎所蔵、市川右近嘗属小幡氏、居砥沢村、食村中三拾貫文中所載日向津布羅子盖砥沢村地名、今村中有日向砥沢日影砥沢等之処
武田氏文書
○今度内山辺移討手之処通路馳走之由本望候、於于自今以後者猶可被致忠信事、可為祝着候、謹言追而雖軽微候木綿遣候也
六月五日 晴信 判
市川右近助殿
右一書市川真太郎所蔵
条目
一 番手之者主本城在陣之事
一 市川衆閣自余之山小屋新地在城之事
一 赤岩之橋場番不可有疎略事
以上
五月六日 南牧
右真太郎真英並蔵之、第二条山小屋盖山上置戌之処、新地未詳、何所新城、
疑是三代記所謂信玄新置一城居小幡信定者乎、第三条赤岩橋場番今砥沢村有赤岩橋
虎満は上杉氏、貞清は村上氏と見られるものの不確かであるとしている。つふらこ・津布羅子とは、あちこち調べているが未詳である。絹布のある工程での呼び名であったのか、或いはコンニャクに関するものででもあろうか。どうも方言が入っているように思われる。
市川真太郎の先祖・右近助が小幡氏に属していた時に受け取った書状である。この真太郎は小柏八郎治の弟で、市川家に養子に入った真太郎であろう。
「郡村誌」は明治8年頃に編纂命令が出ており、数年かけて編纂した物と思われるが年代的にも一致している。砥沢村で市川真太郎という人物が、近い年代に二人居たとは考え難い。
三番目の古文書に押印してある晴信の判は、言わずもがなの武田信玄である。信玄は羽沢村の市川家(右馬助宛)にも殆ど同文の書状を送っている。これにより信玄が南牧の市川衆に眼目を置いていた様子が知れるのである。
砥沢村は信濃から甲斐へ行く街道の要衛にあたり、信玄がこの地を重視していた事が良く分る。
南牧は信越国境にあたり、田口峠を越えて信濃佐久へと繫がっている。西上野国への進入口として、真っ先に抑えておかなければならない戦略上の拠点であったのだ。信玄は赤岩橋の守りを固めて、油断するなと細かい指示まで出している。信玄は南牧に砦(城説あり)を築いて、国峰城を追われた小幡信真を入れて守らせてもいる。
小柏高政は信玄から佐久郡田ノ口を俸地として賜っており、従兄弟の高治は同地の代官を勤めている。これ等の事から小柏氏は上日野小柏の本貫地と田ノ口との間を何度か往復したと思われる。
したがって砥沢村・羽沢村は通り道となり、同地を差配していた市川氏との関係が生じたとみる事も出来る。共に小幡氏に属していたので旧知の間柄であり、戦場に於いても共に行動した事もあったかも知れない。
焙烙峠の伝説
鮎川(あいがわ)沿いの奈良山の北側稜線上に焙烙峠がある。ここは上日野と秋畑村との境界であり、北側へいろは坂のような曲がりくねった道を下っていくと秋畑村の雄川に出る。
この焙烙峠は小柏館に奉公していた下女が、仕事の厳しさに耐え切れず焙烙がなければ仕事もしなくて済むのではと、焙烙を持ち出して逃げてきた場所と言われている。このため焙烙峠という名前が付いた。
「群馬の峠」によれば、焙烙峠は標高860m、別名大峠とも奈良山峠ともいう。焙烙を伏せたような形に見えるのでその名が付いたとしている。何か当たり前すぎて物語性もなく、古くからの山里の歴史や人々の息吹きが感じられない由来ではある。
上日野の北側にあるのが同峠であるが、地図を見ると上日野の南側神流町との境にも「焙烙峠」がある。
塩沢峠の西隣である。「群馬の峠」のいう焙烙峠は、個人的にはこちらの方の由来と思いたい気もする。鮎川と上日野を挟んで北と南に同名の峠があるのだから、もしかすると混同したのかもしれない。
御荷鉾山の山元
江戸時代の小柏家の権勢は絶大であり、飛ぶ鳥をも落とす勢いがあった。同家は小柏の高台にあるが、そこから見渡す限りの西御荷鉾山・東御荷鉾山からオドケ山・赤縄山あたりまでを所有していたという。山の元締めとしても君臨し山に入る時は一々“山元”の許可が必要であった。
時の藩主も山行政には関与せず、全て山元に采配を任せていた。広大な御荷鉾山は、
水田の少ない山間の者たちにとって資源の宝庫である。茸とり椎茸作り、山菜、筍、木材、竹材、薪、炭焼き、萱、馬草、鹿皮などにより生活を支えられるのである。
この他、楮(こうぞ)を栽培し紙を漉き、和紙の生産も盛んに行なわれていた。この紙は「日野紙」と呼ばれかなり知られた存在であった。
然るに江戸中期の頃になると、その支配下にあった近隣の農民たちの意識が微妙に変わってきた。平和の時代が続き合戦はなくなり、武力や刀にものを言わせる時代は静かに遠のいていた。
商品が各地に流通するようになり、農民たちにも金銭と他国の情報が入るようになった。名主家が村役所となり村役人を兼ねて、村落の行政・支配を行なう時代が続き、ある種の腐敗が進んでいたのだろう。この体制に農民たちは次第に不満を持つようになっていた。
特に御荷鉾山を巡っては論争がたびたび起こるようになり、秋畑村との間では裁判沙汰も起こった。
そして寛文四年(1664)に御荷鉾山論争、宝暦七年(1757)には御荷鉾山騒動が引き起こされた。近在の旧家には藩役人へ訴えた訴状や御荷鉾山騒動を記録した古文書が残っている。
これ等の古文書はひどく長文であり、江戸時代独特の言い回しや、今では全く死語となっている言葉などがあり、書いてある事は分るが言わんとしている趣旨を正確・的確に捉える事は難しい。
同じような表現を繰り返しており、当て字、脱字がある他、漢文のように戻り読みもあり相手がした行為なのか、自分がした行為なのかなど微妙な部分が判じがたいところがある。
名主や小柏家を訴え帳面(年貢の)を見せてくれと農民が藩役所へ訴えたところ、役人は村役所に申し出ろという。
これにより、農民代表が小柏八郎左衛門に要請した。八郎左衛門は趣意書を示し、帳面を見せる事はならないが読み聞かせる事は良いとする。翌日、組頭は農民の総代ら11人を呼び出し、訴えを取り下げる書面に一旦は署名しながら、また別の連判をするは不届きと農民たちを叱り付けた。
訴えを取り下げなければ、逮捕し家族ともども引き回しにすると言って、持っていた扇子によりある百姓は打擲され、縄をかけられ連れ出されるなどしたが、その身は後に組合の者を呼び出し組合へ預けられた。
この際、ある組頭はキセルで打ちかかってきたという。事実かどうかは判然としないが、当時の役人と農民、支配者と農民の関係の一端を垣間見るような、このような状況もあったと記されている。
當重 養命寺の中興開基となる
小柏吉重の跡を継いだのが當重である、始め萬太郎と称し後に武太夫と号した。吉重には嗣子がなく、山田貞弘の嫡男を養子にしたのである。當重は後に六郎右衛門と改め法名を浄榮とした。
當重は父祖の意思を継ぎ深く仏法に帰依し、小柏山養命寺の中興開基となった。享保十乙巳年夏、解江湖(不肖)の施主となった。また法華経を千部読み伝える会の主催者となった。(転読・斜め読み)
「宝積寺史」によれば、
正徳年間(1711~16)知海(住職)代に、小柏六郎左衛門は寺の護持を図って山林・畑を寄進する。当寺の規模は、「上野国寺院明細帳」(明治12年)によれば、境内288坪,檀徒247人であった。
とある。
六郎左衛門とあるのは六郎右衛門(當重)の誤りであろう。小柏氏の世襲名は六郎右衛門か八郎左衛門であり、六郎左衛門を名乗ったものは居ない。同様の記事が「多野藤岡地方誌・各説編」にも載っている。(正徳年間知海和尚のとき、小柏六郎左衛門が山林や畑を寄進して寺の興隆を図った。)
表現が類似しており、出典は同じ物と思える。
當重の長女は早世し法名を知春という。二女は藤岡の諸星七左衛門貴郁に嫁いだ。
小柏當重の後を継いだのは長男の記重であり幼名平吉である、後に権八郎と改め更に八郎左衛門とした。法名は有象という。宝暦二壬申五月二十四日卒。(1752)
當重の三女は早世し法名を昌桂童女という。當重の二男俊棋は政右衛門であり、須藤家を継ぎ、加納城(岐阜市)主安藤対馬守信尹に仕えた。
當重の三男一要は幼名を源六といい、十七歳の時に出家し宝積寺・智海和尚の弟子となった。
四女は藤岡の庄田新兵衛淵信の妻となった。四男、松次郎は早世し法名を了香童子という。
記重の跡を継いだのは祝重である。始め権八郎といい後に八郎左衛門と改め、法名を躰寿という。寛政癸巳五月十七日卒。(1793)
記重の長女は高瀬村の新井清蔵に嫁ぎ、法名を妙薫という。二女は福島村の根岸伊之助政命に嫁いだ。三女は早世し法名を理心童女という。四女は倉賀野の須賀弥七郎の妻となった。五女は藤岡の庄田彦七郎に嫁ぎ、六女は南牧の市川氏に嫁いだ。七女、九女は早世、八女は消息が記載されていない。
記重の二男惣次郎は須賀角右衛門知春の二男を養子にしたものである。(小柏系図)
小暮市右衛門 「大神」となる
この頃、小柏家の強引な家抱政策に対し、近隣の農民が立ち上がり吉井藩松平公をも巻き込む大事件が起こった。
宝暦七年(1757)吉井藩(松平氏・一万石)から小幡藩(織田氏・二万石)への編入により、名主“小柏様”への隷属になる事に強く反対した農民は、その代表として、旅慣れていた修験僧(世間師)の百姓小暮市右衛門を選んだ。
小暮は田本で「権律師」の僧位を死後送官された修験僧で、全国をよく巡回していた。そこで、小暮市右衛門は総代となって江戸へ直訴したが、吉井藩の江戸屋敷へ預けられ入牢の身となった。
この時、松平家の親戚の水戸藩主から「吉井候は百姓を難儀させるな。」と諭され、市右衛門は無罪となり帰される事となった。ところが、市右衛門は牢を出る際に役人から毒を一服盛られ、腹の痛みを押さえ籠に乗り、村人に無罪の喜びを一刻も早く知らせるべく急いだ。
彼は念仏を唱えつつ籠を急がせたが、ついに下日野・駒留の大宮様(地守神社)の前で倒れ水を求めたが、ついに絶命して果てた。これは宝暦七年二月十八日の事である。
農民らは市右衛門の残した遺徳を偲び、田本の臨川院「権大僧都本岩大徳院」の墓石を建てた。
なお、小暮家には市右衛門が諸国巡礼に出かける時に着た行衣が残されていた。それには、
西国巡礼三十三番 為二世安楽也
享保十六年
上州多胡郡上日野田本村
小暮 市右衛門
と記されている。更に臨川院の屋敷内に若宮八幡の祠を造って「小暮大神」として祭り「小暮様」と崇め、毎年二月十八日の命日に「先祖祭り」と称して小暮家総本家
に集まった。そこで神官の祈祷を受け、参加者の氏名を記して小暮様の神前に納め、先祖の遺徳を偲んだ。
小暮の家抱反対越訴は江戸中期、西上州の山間奥地の経済的に遅れた地域に起こった、名主小柏家の「家抱」再編成に対する一般農民による反対越訴であったと位置づけられている。
諸国を巡り旅慣れた「世間師」でもあった小暮市右衛門は、民衆の代表に選ばれ修験僧として反家抱の立場から法を犯して吉井藩へ直訴したのである。より民衆側の立場に立った農民であった。
江戸時代後期の代表越訴型の義民が上州では磔茂左衛門に代表されるとすれば、小暮の越訴は平百姓による民衆宗教(修験者)に基盤を置く、「衆生救済」のための義民の反権力闘争であったと言えよう。(多野藤岡地方誌・各説編)
小柏祝重の跡を継いだのは重簡である。幼名を右馬介といい、後に内藏之丞とした。後の六郎右衛門である。重簡の弟には重方がいて兄弟共に名主を勤めた。
切支丹宗門改め
徳川幕府により禁教とされていたキリスト教。これを取締るため時に宗門改めが行われた。これは上日野村においても例外ではなかった。
寛政十二年四月(1800)の、上日野村禅宗門改帳を見ると「上野国多胡甘楽両郡上日野村禅宗門御改帳」と題され、キリシタン宗門の儀は毎年絶え間なく仰せ仕る処にて、村中百姓、男女、子供、召仕えの者、門屋、借屋、抱え者、出家、社人、村に住む者全てを調査するよう指示が出ている。
更に他所から出入りした者に至るまで調べて報告するように、禁教の信者が居れば速やかに注進した者に褒美を出すとある。怪しい宗門の者が居ても報告しなかった時は、五人組、名主、組頭に至るまで罪に落とすとしている。
油断無く吟味して禁教の者が居れば、その家族にまで印をつけ報告せよと固く申し付けている。このため、村全員の名前と宗派、旦那寺を記載・押印して報告している。
上日野村
名主 六郎右衛門 印 (小柏重簡であろう)
組頭 軍蔵 印
〃 市之介 印
〃 房右衛門 印
〃 弥五右衛門 印
〃 熊太郎 印
禅宗
旦那寺
六郎右衛門 歳四十八 宝積寺
女房 歳三十二 〃 松平右京太夫様家中大河友左衛門妹
男子幸三郎 歳三 〃
女子あき 歳六 〃
弟謙治郎 歳三十七 〃 (小柏重方であろう)
謙治女房 歳三十七 〃 吉川栄左衛門様御支配所南牧砥沢村半兵衛娘
〆十八人内 男八人 女十人
伝左衛門 歳六十七 養命寺 六郎右衛門家抱
男子金之介 歳四十 〃
金之介女房 歳三十八 〃 同家抱介七孫
庄之介 歳五十四 〃 六郎右衛門家抱
平右衛門 歳六十七 龍源寺 禅宗新左衛門家抱 (奈良山小柏家)
女房 歳六十 〃 当村柳兵衛家抱六兵衛娘
男子久米之介 歳三十三 〃
同峯吉 歳二十二 〃
久米之介女房 歳三十四 〃 当村柳兵衛家抱定七娘
〆五人内 男三人 女二人
中略
惣人数 千二十五人 男五百四十五人 女四百七十一人 出家八人 道心一人
(藤岡市史資料編・近世)
全ての百姓・町人はいずれかの寺に檀徒として所属しなければならなかったという。
緑野郡大塚村の大雲寺の弟子、五十九歳は六郎右衛門方取置候とあるので預りの意か。〆ての総人数は計算が合わないが、欠落部分でもあるのか定かではない。組頭に名を連ねる熊太郎は「風梅年代記」に出てくる岡本熊太郎と思われる。
この宗門改めから10年後に箕輪山に大熊をうつとの記述がある。更にその翌年に名主になっている。
小柏重簡は「風梅年代記」の筆用者の項に天明(年間)小柏六郎とあり、名主になる前に寺子屋か手習いの師匠などをやっていたものとみられる。寛政十二年の宗門御改帳には48歳とあるので逆算すると1752年生れである。
六郎右衛門重簡は「風梅年代記」に拠れば、文化四年(1807)に隠居したとある。隠居時の年齢は55歳となる。組頭の房右衛門も風梅年代記に出てくる小柏房右衛門であろう。
小柏重簡の跡を継いだのは重方である。「宗門改帳」には弟謙二郎と記されている。重簡に嗣子がなく弟の重方が相続した。重方は幼名を右膳司といい、後に八郎左衛門と改めた。天保三壬辰年正月十九日卒、(1832)法名を一法寿山という。
「宗門御改帳」と「風梅年代記」から生没年を計算すると1764~1832年となり、44歳で名主になり68歳で没した事になる。
重方には妹が一人いたが早世している。小柏系譜には謙二郎の名前は見られず、重方とのみ記載されている。
古記録は残っていたが、近世に至り別記の記録を怠ったものか。記録が残っていれば謙二郎の名前が重方の下方に記されていた筈だ。同じく「宗門改帳」に現れる重簡の嫡男幸三郎と長女あきも小柏系譜には網羅されていない。早世したものか、いまだ判然としていない。
御荷鉾山(みかぼやま)騒動
小柏重方の代にも大事件が起こっている。御荷鉾山の騒動の一件が持ち上がったのである。「多野藤岡地方誌・各説編」に事件の要約が以下の如く載っている。
文政・天保年間(1818~1843)に上日野・下日野・金井三村の百姓による哀訴事件。御荷鉾山は元禄年中に日野と秋畑の境界論争があって、日野分と決し、吉井藩主松平弾正から御印附裏書絵図面を与えられた。
ところが文政五年、(1822)日野三か村の村役人と吉井役所の役人が共謀して、これを吉井宿・俵屋清兵衛に二百両で売却したことが百姓に知れた。そこで、上木を売ったとか、入質したなどと偽りその代価は百両であるとし、内八十四両を百姓方へ割渡した。
「風梅年代記」に文政八年(1825)岡本助左衛門の計にて、御荷鉾山を吉井俵屋清兵衛へ百両で売る。と記されている。
藩主公許の稼山の入会権を守るため、百姓方は文政十一年からたびたび吉井役所へ訴えた。しかし役人の吟味も正当でないため、総代四人が江戸へ出訴した。甘楽郡上日野村百姓総代常吉、多胡郡下日野村同馬之助、緑野郡金井村同作右衛門・繁右衛門の四名で、一時入牢のちに宿預けとなった。
吟味中金井村寅五郎、幸右衛門(繁右衛門の子で多胡村に養子となる)も入牢となった。文政十二年、寅五郎、幸右衛門は獄死、繁右衛門も宿預け中病死し、常吉・作右衛門も病気になった。
馬之助は宿預け中脱走し、帰村して策略の後、三村百姓連印哀訴状を持って自首の上再び哀訴した。勘定奉行曽我豊後守の裁きによって、天保二年(1831)村役人方、名主二人江戸払、組頭十二人過料銭十貫文宛、百姓代三人同三貫文宛、山買主同十貫文。百姓方総代三人軽追放、百姓三百三十九人御叱。の処分が下された。
訴人たちは宿預けの最中に役所へ時々呼び出されて吟味されたという。あとから江戸表へ出向いた村役人もあった。漸く勘定奉行の曽我豊後守によるお白州が開かれ、上日野村名主助左衛門、金井村名主助太夫は江戸払いとなり、この騒動に参加しなかった家抱十八人には褒美が出された。
この名主助左衛門は風梅年代記によれば、岡本熊太郎、後の助左衛門である。文化9年に小柏名主が退役し、熊太郎が助左衛門と改め名主になったとある。岡本名主は江戸払いとなった年に退役している。
小暮市右衛門が死亡してから10ヵ月後、農民たちは更なる行動にうってでた。上・下日野村は元禄までは天領であったが以降吉井藩領となっていた。村役人は小柏家など日野七騎と呼ばれる旧家が代々勤めていた。
宝暦七年(1757)両村の百姓代表は、何度も村役人の不正を追及する訴状を吉井藩に提出していた。しかし村役人と藩役人の間に馴れ合いがあり、一向に取り上げて貰えなかった。
かえって藩役人から横暴な仕打ちを受けた為、ついに幕府へ訴え出た。訴状に記された内容は概ね次のようなものであった。日野村は寛永五年に検地帳を焼失して以来、年貢は毎年永銭で納めていた。村役人の不正で費用がかさむので、惣百姓は反別による持高に見合った年貢上納を願い出た。
村役人は身勝手で年貢以外の税を余分に取り、入用銭として納めていたが、受け取りも出さないので、納得いかない税金は納めない事にした。宝暦二年に「脇差帯刀禁止令」が出され村全体がさびれて困っている。
村所持の切開畑が幾つかあり、それに見合う年貢を納めたいと村役人に訴えたが、取り上げてくれない。
御荷鉾山は天領で入会山として薪を取り炭を焚き出してきた。ところが山元(小柏家)が山の木を伐り出し、山は荒れ果ててしまった。村役人と山元が馴れ合って不正があるが、村役人は取り上げてくれない。
村民は御荷鉾山で芝秣を取り下日野村はそこで干していた。ところがこの地は山元で名主の小柏家の所有地であった。そこでその川原は入会地同様なので、小柏家にかけ合ってくれないかと村役人に相談したが取りあってくれない。
以上の事どもを農民は藩役人の代官へ訴えたが、村役人への取調べはせず訴人やその家族を調べるだけで訴状への回答はなかった。
農民が更に問いただすと藩役人は二人ずつ手鎖をかけて、縄をかけ不届きと大声で怒鳴りつけ無理やり印を押させた。
これにより農民は幕府への訴えを起こすに至り、旧家小柏家の支配から自立する道を模索し始めた。開墾畑が広がり、日野絹が流通し、炭・紙なども売れるようになり、ある程度の経済基盤を持った農民たちが山の元締めの支配に抵抗を始めたといえる。
(藤岡市史通史編・近世)
天保二年の「御鉾山騒動記(写し)」の上日野の項を見ると、農民たちが養浩院に大勢集まり悪口致し河原に押し出した。
別の日には名主を呪詛する為、猪狩りの時に大栗河原に於いて大勢一所に鉄砲撃ち放し気勢を上げたと記されている。同文書は長文であり公文書の体裁をとっている。
この文書は金井村の組頭他百姓77名、下日野村組頭・百姓235名、上日野村組頭・百姓244名、吉井宿の組頭・名主、問屋などの連名として吉井藩に提出した文書とみられる。
重基 秩父山で金を掘る
小柏重方の跡を継いだのは二男の重基である。重基は後に八郎左衛門と改めている。重方の長女は市川帯刀真直に嫁ぎ、法名は春生院松厳妙智大姉である。文政七申年正月卒。二女は早世。長男徳明は法体となり武州今井村長興寺に住いす。重方の三男方義は幼名を泰吉といい二十三歳で没した。法名を一天総梅居士という。
四男治平は前原村の松下氏を継承した。
「風梅年代記」によると重基は天保十三年(1812)に名主になっている。嘉永三年(1850)には、秩父山にて金の採掘(秩父山に金を掘る)を試みて失敗し、かなりの散財をしたという。重基は安政三年(1856)に没している。この後の名主は奈良山小柏新左衛門が勤めている。
奈良山小柏家の世襲名は新左衛門である。三波川では飯塚家が代々の名主を勤めていたが、上日野地区ではいつの頃からなのかは不明だが、年番制も導入されたようである。
上日野村、下日野村、金井村の三ケ村で代々名主を勤めた役人家(名主家ともいう)は、上日野村は小柏・小柴(細谷戸)、下日野村は黒沢(駒留)・柴崎(印地)、金井村の高山の五氏である。
名主・組頭・年寄の役を交代で勤めていた。他に組頭家という組頭のみを交代で勤めた家があった。これらの家はいずれも旧家で先祖は帰農武士である。(多野藤岡地方誌・各説編)
黒沢氏は奥州安倍貞任の子孫という。姓を黒沢と改め鎌倉時代には既に上日野に住んでおり、戦国時代には上杉氏に属し、平井落城後は小幡氏に従い黒沢玄蕃允・源三(後出雲守)父子は小幡氏より感状を数通受けた。(同家系図)
聖天社は同家の屋敷神である。源三は先祖代々の墓地に阿弥陀堂を建てた。(多野藤岡地方誌・各説編)駒留城は同氏の築城とされている。
日野七騎の一騎、黒沢氏は戦国期には同地の小柏氏とほぼ同一の軌跡を残している。
藤林伸治の調査によれば、小柏(村)には「小柏13騎」と呼ばれる私兵・農兵のような存在があったという。幕末の頃か明治初期の頃の事なのか、その時代は判然としないが今もその伝承が残っている。(藤林伸治のメモ)
第五章 風梅年代記
上日野に号を風梅という俳人・粋人がいた。元の姓は小柏であるが後に宮沢姓に転じ弁蔵とした。その批評を受けるところは佳作が多いとされている。「多野藤岡地方誌・各説編」には幼時より学を好み、特に俳諧にすぐれ、好文堂風梅、野雲亭、青柳舎と号したとある。
藤林伸治資料の中にある風梅の子孫という宮沢滋の書簡には、風梅は小柏氏から分家していて、滋の祖父で小柏家第十四代と称していたという。風梅が残したものに「風梅年代記」がある。また上日野年代記と呼ぶ人もいる。
上日野の出来事を112年間に亘って綴ったもので貴重な民俗資料である。伝説的な面白い記事もあるので「藤岡市史資料編・近世」に収載のものに少し注釈を入れて次に掲載する。
「むじなの化物出る」
安永元年辰
下日野掘込惣右衛門吉井(藩か)の用達となる、十月千両開きをなす
同二巳
箕輪小柏市郎左衛門生まれながらにしてだみ(荼毘)をなす、観音堂に入り念仏者となる
同三午
小柴利右衛門の指図により江戸屋敷(吉井藩か)へ始めて蕨を貢、御荷鉾山運上永十八貫十八文と定む
同四未
絹運上大騒動、日野金井高山氏つぶす
同五申
日野坊藏宝院山伏の位を請く、日野村々祈願所始まる
同六酉
江戸へ紫蕨を納む
同七戌
以三和尚を以って養浩院住持となす
同八亥
細谷戸の堂へむじなの化物出て夜な夜な踊る
同九子
細谷戸米吉と申す座頭コウトウに任ず、十一月妙音講を行ふ
天明元丑
潮来節始めて流行す
同二寅
細谷戸伴藏、馬盗人の科にてはりつけにかかる
同三卯
七月九日浅間山焼砂降る、細谷戸平六寸余といふ
同四辰
穀物大高価、人飢死す、野老葛根掘り尽くす
同五巳
細谷戸磯右衛門、猪にかけられきずを請く
同六午
弥惣渕河原に火の柱、夜な夜な見ゆ
同七未
細谷戸小柴氏、火事あり
同八申
細谷戸小柴氏、車の元へ家を建つ、小此木彦市退転す
「おたか夫の男根を切る」
寛政元酉
さんご節といふ唄流行る
同二戌
秋大洪水、所々川荒れ見分を請く 鹿島大ぐえ、酒井与惣左衛門の家くえつぶる
同三戌
板谷戸、定衛門退転する
同四子
平仁田の大道を釜の沢へ廻す
同五丑
小柏に病犬流行、人を多く喰ふ
同六寅
下鹿島、兼五郎酒店を開く
同七卯
矢掛にて太郎といふ男、見世物を出す、三十五歳にて二尺一寸の丈
同八辰
鹿島に人形始まる 一人へ三人がかりにて大芝居あり
同九巳
細谷戸薬師堂にて真心という僧侶、金春流の古謡を教ふ
同十午
全阿和尚、養浩院住持となる
同十一未
小柏房右衛門退転す 小柏奥ノ反吉田氏百姓となる
同十二申
庚申塚村々に立つ 大厄病流行 村々百万遍の数珠を拵ふ
享和元酉
全阿信州より願王和尚請待 百日の大結制を行ふ
同二戌
養浩院に釣鐘を鋳る
同三亥
養浩院大門に大きなる石地蔵建つ
文化元子
鹿島斉藤武右衛門、医師をなす、小柏に日野出山谷八と申す角力あり三段目になる
同二丑
鹿島忠作といふ者、女房を屠す
同三寅
鹿島大火、人形焚く、奈良山新左衛門千本杉形と狂歌人となる
同四卯
小柏六郎右衛門隠居、小柏郎吉六郎右衛門と改め名主となる
同五辰
秋田村(秋畑村か)にて九之助といふ者を殺し奈良山の地獄谷へ捨つ、大騒動となる
同六巳細谷戸、松田秀右衛門宅碁将棋の会をなす、大人数集まる
同七午
箕輪小柏伝益、医師となる、塩平に冨屋藤八酒造を始む
同八未
矢掛の寺に木々庵と申す俳諧者住む 岡本熊太郎、箕輪山に大熊をうつ
同九申
小柏名主退役、岡本熊太郎、助左衛門と改め名主役仰付けらる
同十酉
風梅生る よしこのといふ唄流行、田本の滝の沢、小柴兵右衛門、大橋流の書を教ふ
同十一戌
細谷戸、飯塚常五郎天徳清水井の上に酒店を出す
同十二子
細谷戸、富八酒造を始む、梵悦和尚を以て養浩院住持となす
同十三子
田本、髪結大騒動、火方役人高村出役有り、地頭役人広瀬小右衛門之を鎮む
同十四丑
上日野村髪結所を禁止す 日野坊女房おたか夫の男根を切る
「気楽流柔術」
文政元寅
坂野、円蔵酒店を出す大藤場并天流行る
同二卯
細谷戸、天徳川原に新田を開く 大塚村、臥竜斉気楽庵の柔術を弘む
同三辰
(田)政蔵酒造を始む 又地蔵佐養を施す 箕輪神道御荷山を開く為、白河役人来る 助左衛門之を防ぐ
同四巳
田本に大神楽始まる 乙右衛門曲の名人なり、小次郎跡冠不向 (獅子舞か)
同五午
(田)政蔵、細谷戸天神祭に人形を奉納す 御改革厳敷、絹縮緬の掛切并半襟袖口を止む
同六未
田本、馬渡戸両村より天神祭練り奉納す 角太郎、熊吉猿まはしの名人なり
同七申
私(秋か)洪水、所々川荒れ小柴氏表門崩る
同八戌
岡本助左衛門の計にて御荷鉾山を吉井宿俵屋清兵衛へ百両で売る (御鉾山騒動)
同九戌
御荷鉾山一件に付、日野三村大会合、大宮にて連判、江戸へ出訴、総代金井作右衛門、下日野午之助、上日野常吉
同十亥
八木良助、松田雪七、気楽流の目代となる、細谷戸上ノ山ノ庭に大芝居あり、松田豊八家を建つ
同十一子
御荷鉾山論につき日野三ヶ村江戸へ不残御門訴、風梅田本乙右衛門の弟子となり桶屋を習ふ
同十二丑
梵悦和尚出走
「大飢饉で飢死にす」
天保元寅
岡本名主退役、田本常吉ケッショ、名主組頭も預り御荷鉾山論相済
同二卯
細谷戸、七郎右衛門名主と定る 風梅江戸へ逃げ酒井の屋敷へ足軽となす
同三辰
臨渓和尚を以て養浩院住持と定む 田本常吉空家へ化物夜な夜な出て左(だけ)の足跡付あり
同四巳
二月初午大宮へ日野三村祭りを出す かまやせぬの唄流行る
同五午
養浩院立替普請始まる
同六未
松葉村弥十郎といふ男、おかばみに出会ふ、驚きて一月を過ぎず死ぬ
同七申
大飢饉穀物高値、飢死にす、地頭より籾老人に付四升宛下さる、小柴七郎宅にて之を渡す 舛取風梅
同八酉
去年より家々葛を掘る 麦壱駄三両なり、米百文二合五勺買出し更になし
同九亥
小柏に達磨岩流行、万五郎のりきと成る 小柴与三郎木屋をなす 代人木曾の木右衛門
同十亥
風梅始めて俳諧の会を企てる 田本森に額納む 小柴与三郎蚕種屋となる 風梅代人に出る
同十一子
杉原八左衛門家を売る 本年博打騒動、吉井より出役 人を多くたたく 作右衛門弥惣渕を干す
同十二丑
亥年より三年間、風梅御年貢勘定なす 賃金三両と定む
同十三寅
細谷戸七郎右衛門退役 小柏八郎右衛門名主となる 全阿和尚死す
同十四卯
杉田豊八弥々屋敷を建つ メクリの定宿をなす 塩平冨屋退転 又山六店を開く
弘化元辰
下日野小柴吉右衛門名主となる 臨渓和尚富岡へ隠居、月払いの金を貸す
同二巳
養浩院無住寺世話人持となる 芝平新道となる 細谷戸大神楽始まる
同三午
細谷戸より三波川不動へ新米奉納、又手桶をなす 小柏重好といふ歌人となる
同四未
細谷戸にて一の谷の芝居を習ふ、不出来
「小柏氏秩父山にて金を掘る」
嘉永元申
大仏村永明寺、養浩院の住持と定む 坂野乙右衛門の祖母、狢と交合す
同二酉
細谷戸に百庚申建つ 戸川丑太郎、藤岡の絹市を止む
同三戌
小柏氏秩父山にて金を掘る、大損す 細谷戸、矢掛村論にて分る 鹿島友吉天狗と剣術を遣ふ
同四亥
風梅外五人、博打の科にて入牢す
同五子
番場川原丑松鯉池を拵へ酒店をなす 鹿島卯市、天狗の乗気となる
同六丑
風梅、田本万三郎の店を借りて酒店を出す、夏ひでり、御荷鉾山へ雨乞上る
西嶺に不動立つ
安政元寅
地頭より人馬言付く 日野にて五十人江戸詰る 越中島のかためをなす 悦道和尚、養浩院に入り、おこうと申す美女も連れ込む
同二卯
万三郎、風梅、駒蔵 田本にて操興行す 地頭より科めを蒙る 小柏より桧大木、川流多金たたく
同三辰
小柏名主死す 村役人にて 名主預り、戸川久蔵鏑川にて水死す
同四巳
奈良山新左衛門、田本万三郎年番名主 片山郡藏組頭となる 小幡山大猪狩
同五午
井田不二太郎、養浩院大門に横死、ノウ千代さん唄流行 七兵衛と申す者田本にて常磐津師範す
同六未
大水、鯉屋流る 平仁田大ぐえ、所々川荒検分あり 妹ヶ谷と栗拾論に及ぶ 藤八ケン流行
万延元申
細谷戸天神組を村中と定む コロリ風行人死す 吉井殿様養浩院旅館
文久元酉
名主万三郎死す 奈良山一人名主となる 臨川院出張所立つ 源三郎茶製造を始む
同二戌
田本芝居 友信玄 悪徒者を亀屋にてしばる、小柏祭組二つに分かつ 田本亀屋へ押込み入る
同三亥
博打騒動四十人に及ぶ 過料七十貫奈良山へ納む
元治元子
吉井より農兵三十人日野村被仰付、下仁田軍あり 農兵並百姓不残吉井へ詰る 片山氏火
慶応元丑
村々番所を立て昼夜番人出る、八日市端巌寺を養浩院となす
同二寅
風梅田本去る、天徳に亀屋新築、岡本名主見習いとなる、御荷鉾道普請 フギリに御小屋新築す
同三卯
井田馬蔵、天徳に寄火花を成し大損す 吉井農兵三国峠に戦ふ 小柏村源吉病犬を伐る
「明治時代 金札・学校 小柏戸長」
明治元辰
徳川氏亡ぶ 諸国強談質家品物只出す 又十月残なく返す 利吉宅に押入る 田本万三郎火、井田馬場土蔵の作り売りをなす
同二巳
奈良山名主退役、岡本名主となる 金札始めて通用す 信士法名居士となる 穀高値、南京米安値あり
同三午
二分金通用止る 旧役人を廃止す 風梅太々伊勢納む、田本芝居、芭蕉塚立つ 法正塚定橋落る 小柏九人百姓になる
同四未
鹿島大芝居、岡本梅二鹿島の川で死す、岡本曾市屠さる 農兵不残免職 井田馬蔵薬師を立てる 小幡山花見あり
同五申
吉井陣屋畑となる 富岡製紙始まる 平井三島大神村社と定る
同六酉
去年より地券改、岡本副区長、小柏戸長となる 一月より太陽暦となす 日の丸旗立つ。冬岡本火
同七戌
千万吉坂野に屠さる 春学校開く 十月小柏分校す 秋岡本大芝居、三十六人大損す、市五郎立会人となり森三郎家を売る
同八亥
金井新道開く 岡本小柴家を建つ 天朝より学校へ金を給ふ 柳三郎立会人となり室静厳住職となる
同九子
一月大雪五寸降る 去年より酒店官許となる 小柏村中百姓となる 三村合併願不叶 旧役人不残廃止 三月投票なし 戸長小川 副戸長福田・喜月両人地租改正を始む
同十丑
風梅去る秋より中症病、下日野村芝地論、春地位等定む、春諸供養塔合併す
同十一寅
小柴連三郎、小暮峯吉家新築、春畑収穫帳なる 神風護免許下る 小柏天狗加持流行、鹿島大神(神宮)村社に定む 藤岡に郡長置く 大小区戸長廃止す
同十二卯
藤岡に区役所を置く 戸長堀越市五郎 用掛新井喜善治、養浩院に仮役場を置く 春山林地租をなす 南甘楽より大量人を雇ふ 秋村会を置く 坂野甚三郎屠服不死
同十三辰
春辺見杢太郎家新築、夏村史廃止す 又投票戸長堀越市五郎
同十四巳
この秋下田本川岸に村内製紙場器械を設く 福田種蔵酒店を藤岡長屋を借り開店す 鹿島祭日に大煙火、その日雨風寒し、商人不印なり
同十五午
旧冬より器械生糸大下り 商人中大不印又博打刈込みにつき福政大観風梅宅六十日舎る 本年は十一年ぶりにて旧来を用ひ、十六年末の二月八日の夜より雪降り出し九日を以て元日とし その雪深く三尺余なり
同十七申
八月榛名坂道長さ百間、幅五十間崩れ、川瀬深さ五丈余となる
「上日野美人リスト」
上日野筆用者
天明 小柏六郎 小柏伊之助 酒井与惣左衛門 小柏房衛門
寛政 小柏卯善二 小暮常八 小柴兵右衛門 斉藤武右衛門 松田秀右衛門
文化 小柏助在衛門 井田富右衛門 矢掛端伝坊
文政 戸川皆二郎 小柴与三郎 小暮善之助 小暮勘二郎 小暮友吉 新井甚八
天保 千手印 小柏才三郎 片山郡蔵 新井七蔵 最乗院 小柏五市
弘化 宮沢風梅 小柏新左衛門 戸川丑太郎 小暮久三郎 新井喜善二
嘉永 小柴重太郎 山田倉吉 堀越市五郎 片山郡蔵 新井友吉 小柏一甫
明治 福田伝十郎 清水竜三郎 斉藤清三郎 堀越慶二郎 清水勝太郎
上日野酒店
天明 細谷戸伊右衛門 田本繁様
寛政 小柏弥右衛門 田本半左衛門 田本文治 田本倉吉 鹿島兼五郎
文化 細谷戸富八 細谷戸常五郎 鹿島三之助 馬渡戸八十八 田本政蔵 田本三八祖母
文政 細谷戸多茂八 田本代吉 田本繁八 田本おかよ 坂野国蔵
天保 鹿島おかつ 鹿島高八 小平繁太郎 峯熊五郎 田本勘兵衛 中上主馬吉
中上藤兵衛 坂野伊右衛門 日向幸二
弘化 小柏兼吉 田本わたや太平 坂野長之助後家
嘉永 番場鯉屋 田本新井屋 岡本才吉 下府飯塚 小柏倉吉 田本かめや
矢掛万太郎 鹿島藤吉 小柏八十八 坂野角蔵
明治 田本年太郎 田本喜善治 細谷戸風梅 坂野おこと ミノハ泰吉 井田万蔵
矢島喜三郎 田本藤四郎 小柏佐五郎 坂野おゆき 鹿島八五郎
小柏八郎治 福田種蔵 小柏利平
駒留上り別品美玉
文化 田本おとよ 芝平おなか
文正 岡本おふさ 小川おたみ 釜ノ沢おもと 釜ノ沢おうめ
天保 小柏おとせ 小柏おきた 岡本おくま 田本おふで 岡本おすま
駒留四王天
天保末 鹿島おたか 小柏おなか 駒留おとく ミノハおこと
マカブおふじ 駒留おきぬ
弘化 釜ノ沢おせい お寺おこう
安政 細谷戸おいと 細谷戸おふみ 田本おそは 田本おるい
明治 坂野おさと 田本おとり

法政大学 藤林伸治資料より
好文堂風梅と芭蕉塚
「年代記」とタイトルにある通り日記ではなく、一年の記事をほぼ一行にまとめてある年代記である。気持ちが後に引きずられるような大事件でもさらっと簡潔にまとめている。
何の感慨も持たず事実だけを述べているようにも見受けられる。安永元年(1772)から明治十七(1884)年までの記録である。
風梅は自身の記録によれば文化十年(1815)の出生であり、没年は明治十七年、七十二歳とされている。
風梅が生まれる前の記録が43年分もある事から、何らかの古記録がありそれを元に書き足して「風梅年代記」をなしたと思われる。
「風梅年代記(上日野年代記)について」(塚越篤江、群馬歴史散歩90号)によれば、風梅は学者であったという。
以前は田本に住んでいたと思われる節があるが、同誌によると細谷戸に住んでいたようだ。(晩年になり戻ったのか?)
宮沢滋によると同家が宮沢姓になったのは、同氏の曾祖父が信濃から婿入りして宮沢姓を名乗った事によるという。家の宗旨は黄檗禅宗としている。黄檗宗は重高が帰依していた黒滝山不動寺の事であろう。
風梅年代記は風梅翁の蔵書「和漢年契」(安政版)の巻尾に綴じ込まれていたという。上日野馬渡戸の高桑市蔵家に保存されていた、原本を郷土史家の松田毛鶴氏が借りて写本を作り、この写本から更に清水丈夫氏が写本を作ったという。
「風梅年代記」の冒頭には、「如何なる事あろうともこの書物破るべからず、最も大切に後世の参考として保存すべし」とあったという。
更に「亦貸しは奈良の都の八重桜今日ここで見ておいてくだされ」と唄が添えられていたという。
風梅は酒屋、宿屋を営む傍ら手習いの師匠として、多くの弟子を育て中風を病み死去したとしている。辞世の句に「世の中に毒ほどうまきものはなし」があるという。私などは若輩にてまだこの翁の心境は分らない。
天保六年の意味不明の「おかばみ」の記事は、「おはばみ(うわばみ)」として紹介している。うわばみなら大蛇の意になろうが、上日野にニシキヘビがいたとも思えぬ。
いずれにしても貴重な記録であり、百年以上に渡る庶民の暮らしなどが良く分る。他の古文書・文献と照合すれば裏づけ史料としても使えるのではないか。
明治以降は、実際に風梅が見聞したであろう事件など、より詳しい記録となっている。
印象に残る記事としては、養浩院を大切にしている事、浅間山噴火の被害があった事、物価高騰により葛の根を食した事、飢饉により餓死者が出た事、時々洪水があった事、名主交代の記録。
ひでりにより御荷鉾山に登り雨乞いをした事、(同山頂には今も祭祀の跡が良く残っているという)農兵の徴兵と実際の戦い、芝居が好まれていた事などがある。坂野乙右衛門の祖母が、狢と交合したとの記事は一概には信じられない。狢とは狸の一種と思われるが、戯れにした事であろうか。風梅が生存中の記事でもあるので、恐らくはこれに類する行為があったのだろう。
また小柏祭組が二つに分かれた事、これにより伝統ある獅子舞も、獅子頭と秘伝書が二つの村に分かれてしまい、更には獅子舞の行事自体が休止になってしまっている事は残念な事である。
明治維新については「徳川氏亡ぶ」とだけ記されているのは、極めて意外というかあっさりし過ぎているようだ。上日野の村落までは大した影響がなかったという事なのだろうか。
巻末の「筆用者」リストは筆の達人・転じて知識人とでもいうべきものだろうか。
筆用者は「寺子屋」や手習いの師匠をやっていたと思われる。
酒店のリストがなぜ作られているのか、その意図は分らないが幕末や明治に酒店が多くなっている。
名主の息子であり、戸長であった八郎治までが酒店をやっている。誰が作ったものやら美人リストまでが添えられている。風梅は文化の生れであるから、少なくとも文化の年代の美人リストは風梅の手によるものではない。粋人であった事から、老翁などから聞き取り取材でもしたのかも知れない。
年代記に現れる箕輪・ミノハは、「鹿島」或いは「岡本」から三波川方面に向って山を登った所にある小さな集落である。箕輪には秩父事件と関わりを持ち、その名を馳せた小柏常次郎が住んでいた。
風梅が俳句を当地に広めた影響であろう。上日野の人たちによって「芭蕉塚」が建立されている。
明治五年に芭蕉の故地、伊賀上野を訪れ墓参を行い、金二円を寄進して墓土を受け俳塚の形をとった。昭和50年に県道沿いから養浩院に移された。筆は枯れて配字もよく筆勢は雄健という。
彫刻の技術もすぐれ、仕上げの丁寧な事は類例が少ない。高さは二百七十三cm。下日野駒留にも同好者八十人が建てた芭蕉碑がある。
上日野の獅子舞
上日野の獅子舞については「多野藤岡誌帳」に記事があり多くの頁を割いている。その由来は古く飛鳥時代に遡る。正倉院に大陸から伝来した獅子頭が九面伝わっているという。
神聖なものとして宮廷や大寺院、神社などの行事に用いられ、後に地方の民俗芸能化し多くの流派が生まれたと推測している。多野・藤岡地方の獅子舞は稲荷流であり、同流の本家は秋畑村那須とされ、山を越えて上日野・三波川妹ヶ谷などに古くから伝わっていた。
秋畑村那須に伝わる稲荷流の奥義を記した巻物「神代獅子由来」は、日本の獅子舞の起源を書いたものとされ、那須、小柏、上平、妹ケ谷、神田に筆写本が伝わっている。
このうち小柏本が最も首尾一貫しており、原本に近いと思われるとしている。小柏と上平は隣接していて、一緒に獅子舞を演じていたが、ある時不和となり小柏が巻物と太鼓、上平が獅子頭を取って分裂したという。
同誌収載の「神代獅子由来」の冒頭部分の大意は次のようなものである。
そもそも獅子の由来を尋ね奉るに 天竺の獅子国と申す国の主なり
孝徳天皇の御代の大化の元年乙巳八月十五日に、獅子の頭と身体を日本へ移し取り
国土の泰平のために獅子を神社の祭礼に仕え奉り候条
1 天つ神二神が海の中を矛を以って探るに、矛に触るは何者とお尋ねあり
地主の日吉権現が葦と答う よって葦原の国と申すなり
1 イザナギの尊・イザナミの尊は出雲の国の大社のスサノオノ尊の父母なり
この神に一女三男あり、伊勢大神宮 日の神・月の神・西の海の宮の蛭子三郎殿なり
1 スサノオノ尊がこの国を取らんとて、大和の宇多野に一千の剣を掘り立て城郭
をかまいたもう 天照大神は一千の剣を蹴破り捨てたまう 之により千剣破
(ちはやぶる)る神ともうすなり
1 八咫の鏡は天照大神の御霊なり 今の伊勢内宮の神体なり
よって鏡は尺八寸なり
1 住吉大明神がいる国を平らげ候時 御衣装あこめ袷を筑前国極井ノ浜にぬぐすてたまう 即ち石となり その後は社なり
1 稲荷大明神は山城国紀伊郡に明神あり 和銅年中に「始めて稲荷山に鎮座なる一説に弘法大師が東寺の門前にて」稲を荷なえる老翁に逢えるをもって
大師が東寺の鎮守とす 十二月に配当する 別に律する所は七月に当るなり
七月の霊なり
1 稲含大明神は天竺より稲を含み取る 即ち稲の神なり
1 崑崙山に崑崙国という国有り 南の海の諸州の拾余国の中の傍遊羅国という国の東にあたるなり
1 補陀落山は布咺落迦山にあり、天竺の観自在菩薩の遊舎する所なり
1 天竺の霊鷲山はこの山の形が鷲に似れば名付く 即ち釈迦如来の説法の所なり
1 天竺の獅子は天竺一の獣なり
1 大唐の竜は唐一の獣なり
1 日本の狐は日本一の獣なり
1 日本の葦原国は鬼の国なり 神の力・仏の力が之有りて天下泰平なり
よって狐の老翁は天竺の獅子の形を写して、獅子鳳神として祭礼を企て候
1 神社の祭礼の始めは田の百姓からと言えり 泥を掻くに似るを神前の祭礼の
始めとするなり
1 天竺の遊羅国の菩薩並びに布咺落迦山にある観自在菩薩なり
1 天竺の霊鷲山の釈迦如来と右の菩薩並びに如来ご免の獅子鳳神の祭礼なり
笛は天下泰平 豊葦原の水穂とお救い息学は 但し口伝之あり
以下略
以下は笛の吹き方、歌の歌詞などになり、陰と陽の戦い、夏と秋の戦い、女獅子・男獅子のめぐり会い、歴代天皇名、在位年数などが出てくる長い物語となっている。
獅子舞は如来と菩薩の免許としている他、日本の起源にまで言及している。イザナギノ尊・イザナミノ尊と同時代に日吉権現が居たとあり、日吉権現が居た国を占領し葦原国と名づけた事を示唆している。
また住吉大明神の住む(治める)国を征服したとしている。日本書紀・古事記とは一味違った記述であり、近世の成立とはいえ興味の持てるところでもあるので紹介した。
第六章 小柏舘最後の当主
八郎治 重明
270年ほども続いて、平和の時代をかこってきた徳川幕府の命運も尽きて、明治時代の幕開けが近づいていた。
小柏重基の跡を継いだのは長男重明である。重明は幼名を民之助といい後に八郎治と改めた。神習教(神道)の中教正を務めていた。大正十一年五月八日卒(1922)。法名を寿翁柏英居士という。重基の長女貞は三本木村浦部元之助に嫁いだ。二女嶋は日野岡本の小柴重太郎に嫁いだ。
三女才(重明の妹)は三本木村の浦部助太郎に嫁いだ。助太郎は浦部元之助(姉の夫)の舎弟で、豪商・原善三郎の経営する横浜の生糸問屋に勤務した。この縁で重明と善三郎の共同事業・取引も始まったものと推測され、ここから重明のひいては小柏氏の悲劇が始まったとみられる。
「才」の長女シマ子は高山村高山武十郎の後添えとなった。才の長男辰吉は幼くして父をなくし、原商店(生糸問屋原善三郎「亀善」か)に勤務し後にアメリカに渡った。二女さとは金井村の高山菊次郎に嫁いだ。二男泰次郎は東京へ居を移した。才の三男英治は中浜光司と改め横浜に住んだ。(高山家蔵小柏系譜)
この「才」以下のくだりは小柏家の系図には記載がない。高山長五郎が筆写した後で小柏家で記載事項を修正し、家系図を書き直したものか、或いは高山家では周知の事実であったので書き加えたものか。
両者の系譜の記載状況を子細に見比べると、必然的に後者となり論を待たない。一般に系図では、他家に嫁いだ女子についてはその子供たちまでは記載しない。「○○の室」までの記載で済ませる。系譜が膨大になり紙数が足りなくなるからであろう。
小柏重基の四女「代」は武州下奈良村正五位吉田市十郎宗載に嫁いだ。二男真太郎は下仁田砥沢村の市川市を相続した。重基の四男重義は幼名を倉太郎といい、明治九丙子年七月徴兵令により応募、入営し同十丁丑年三月、西南の役に従軍するため「西京丸」に乗り込み肥前国長崎港に着いた。
倉太郎(八郎治の弟)は東京鎮台の歩兵第三連隊に属し、小柏倉太郎重義一等ラッパ手として戦争に加わったが、明治十丁丑五月、熊本県下の内照角山の麓において、右前槫及び右胸より背部に貫通する敵弾を受けた。
大築村大包帯所より八代軍團支病院を経て、六月二十二日に長崎軍団病院に入り治療するも、段々に衰弱し遂に十月四日死去する。(小柏系図)
高山長五郎が筆写した(昭和10年に)小柏系譜によれば、重明の妻は武州小平村根岸孫右衛門の娘とある。この頃、根岸家とは縁が深かったとみられる。
また同系譜によれば吉明の母は登江(光江と思える)となっていて、武州下奈良村吉田嘉三郎に嫁ぎ、後に武州小平村根岸担二に嫁いだとあり、(小柏)吉明は嘉三郎の息子とある。
御鉾神社の建立と祭祀
小柏舘の敷地内に同氏が建立した御鉾神社があった。同社の祭神は日本武尊で小柏氏が源平合戦以来使用した武具を祀る所という。宝物に次の物がある。
麻陣幕一張 五反幕に揚羽蝶紋を五箇記してある。幕には矢の当った跡が所々にある。これは川中島決戦にも使った物という。
槍9本 神輿一座 (群馬懸多野郡誌)
小柏氏が川中島の合戦にも参陣していたというのは、いまだ他の文献・古記録で確認出来ていない。何か他に古文書があったのか、或いは口碑・伝承があったものか今は判然としない。
御鉾神社は「ふるさと人ものがたり」によれば、小柏当主が祭祀していた、その祭典には小柏・上平から獅子舞(16獅子)を奉納するしきたりが戦後まで続いていたという。
当時は伊勢講、御岳講などが盛んに信仰された。御鉾神社は御岳様の分社という。御岳講は木曾の御岳山を霊山として祀る、御岳教で今もなお信仰されている。神道家が資格を与えられて布教に努めた。
藤岡市神田に御岳大神の碑があり(明治十五年建立)、立春に火渡り、四月に例祭を行ない三方荒神の幣束を配った。鬼石町雨降山には御岳大神を祭った。三波川の桜山の登り口にも御岳様を祭った。(多野藤岡地方誌)
御鉾神社は「多野藤岡地方誌・各説編」に、小柏氏の屋敷内であり祭神は日本武尊で、小柏氏が源平合戦以来使用した武具を祀るという。
御鉾教会については、小柏にあった神道神習教会であり小柏氏と消長を共にした。小柏氏が邸内に祭る御鉾神社と一体不離のもので、明治二十年五月三十一日設立許可になった。
大正末期には担任教師一名、信徒総代三名のもと三百四十一名(女八)の信徒を有していた。その後は小柏氏の衰退に伴って信者は激減の一途をたどり、昭和の初めになると、小柏家の老女のほかには信者は見られなかった。
とある。
上日野の人口は寛政十二年(1800)の宗門改帳に1,025人とあり、藤林伸治資料には、明治10年代の戸数は229戸(下日野は199戸)とある。229戸とすると一家につき1.5人が参加していた事になる。
女の参加者は殆どなく、子供は対象外であろうからかなり多い人数である。義務のような形で、一戸あたり一人以上が名を連ねていたのであろうか。
下日野には日高野分教会があり、大正十二年天理教本部に認可され、担任教師が常駐した。当時の信者数は173人、内女30人だった。昭和期には信者数は31人となった
上日野には神社が多く、寺を別にして鹿島に鹿島神社、坂野に厳島神社、駒留に聖天社、黒石に諏訪社、上日野に野々宮神社などがある。これほど神社がある中で341人の信徒を擁するとはその権勢が窺われる。村の人口のおよそ33%が信者だった計算になる。
御鉾神社は何時誰が建立したかは定かではない。鼠喰城を築城した重家ではなさそう。(時代が古すぎる)上杉家に仕えた顕高は剃髪して浄印入道を名のっており、これも違う。
小柏氏の長い歴史の中で恐らくは、最も権勢を誇ったであろう高政、だが高政は生島足島神社に起請文を奉納しているが、養命寺を建立しており御鉾神社をも建立したとは考え難い。
定重・定政の頃は戦国時代で戦いに明け暮れていたと見られるほか、宝積寺との繋がりも深い。重高は仏法に傾倒し不動寺を建立、弟の吉重も同寺に帰依している。心証としてさほど古くはなさそうというのがあり、江戸末期の頃かと推測する。すなわち八郎治の父か祖父の建立した可能性が髣髴と漂ってくる。
小柏舘がなくなっている今、御鉾神社は失われているが、かっての舘・敷地の東端の北側に祠がある。
裏山の雑木林の下端に位置するその祠には、注連縄が張られて現在もお守りされている。この祠がかって隆盛を極めた御鉾神社の名残りではなかろうか。(ただし舘の裏山に社があった形跡もある。)

「小柏舘跡の祠」
小柏学校
「風梅年代記」によると重明は明治六年(1873)に戸長になっている。名主に替わる村長みたいなものだろう。同七年に小柏分校すとあるが、養命寺を仮校舎として小柏学校が設立されたのは明治九年である。
(多野藤岡地方誌では明治7年、養浩院に上日野学校が設立され、養命寺に小柏支校設立とある。)後に(同年のうちか)小柏八郎治宅に移る。と記載している。
明治十三年には学校の保護役を廃止し、学務委員を選挙とする事になり小柏八郎治が当選した。
「藤岡市史資料編・近世」によると、当時の就学生は二十八人、男十五人、女十三人であったという。十五年の項には十一月第十一回定期試験において受験生徒十七人、同時に小柏イツ初等小学を卒業す。とある。
このイツは「逸」であろう、後に小柏舘の最後の住人となっている。十六年には、人民挙げて貧困に陥り日々の生活に苦しむ、幼年といえども家事に使用せざるを得ず、昇校を怠る者多くなり。就学生徒四十五人、内男二十五人女二十人。このような大意で学務委員の小柏八郎治が報告書を出している。
更に十七年には次の意見書を役所に提出している。
意見書
当校を維持するの計画は至難といわざるを得ず、何となれば本村の如きは山間の僻村にして、地勢狭長戸数僅少にして人民資産に乏しければなり。
然るに生徒は日進月歩するに随い費額相嵩むにもかかわらず、昨年以降世間非常の不景気にして、金融塞塞物価低落のために士人家を破り産を傾く者往々これあり。これによりて、これを観るに目今一時に定額金を増加し維持の方法を計る。
よくば他日物価旧に復し聊か不景気を挽回するを待ち、然る後相当の金額を増加せば従いて学事隆盛を来たすべき也
明治十七年六月
多胡郡第十三学区日野村
小柏学校学務委員 小柏八郎治 印
重要なのは、大正八年4月に校舎を焼失し、養命寺を仮用、翌年正月再建する。という記録がある事だ。藤岡市教育委員会が、実施した小柏舘の発掘調査の時に出土した焼土層と附合するのである。してみると小柏舘が焼失したのはこの時か?時代が新しすぎるからそれ以前にも火災があったものか。
「宝積寺史」に収載の明治18年の上日野村「曹洞宗護法会姓名録」には、筆頭に小柏八郎次(治)の名前があり、以下58人の名前が記されている。
この中には、小柏喜伊三郎、小柏幸太郎の名前もある。この姓名録で目立つのは黒澤姓の人が多い事である。
明治政府 地租大増税
明治政府は金がなかったと言われているが、税金の制度が徐々に出来上がってきたものか、同十年には地租改正が行なわれた。八郎治の所有地山林・原野の税金も大幅に増額され、数十倍以上に跳ね上がった。
このため一度では払いきれず、八郎治は明治十六年に大蔵卿松片正義に延納願いを提出し許可を得ている。
これによれば、八郎治は明治10年から14年までの地租を滞納しており、同年に約半分を支払い、残りは何と40年の年賦としている。許可書案文を見ると、八郎治ほか十二名の所有地の未納地租は、1,435円余であり同地の税金増額は従前の149倍にものぼると認めている。
年賦期限表には極度五十年とあり、せいぜい説諭を加え出来るだけ上納させ、残りは徴収が非常に難しいゆえ、特別の許可をするべきとしている。松方が太政大臣三條實美あてに意見を添えて伺い書を出している。
その後松方は、伺之趣、特別を以って聞届候条、年賦納額各年度限内訳を取り調べて申し出る事。と大層な文言で許可を出している。(法政大学藤林伸治資料)
また同資料の中に次のような記載がある。
明治十年ヨリ同十三年迄四ケ年分
金弐千七百九拾五円五拾八銭四厘 上日野村地租
金六拾七円八拾弐銭六厘 是ハ納済ノ分
金七百弐拾五円五拾七銭弐厘 本年二月祖甲第廿三号 以□
内 小柏八郎次外拾弐名延納相同候□
金五百拾弐円九拾八銭四厘 今般延納相願候分
金千四百八拾九円弐拾銭弐厘 十五年度一時上納ノ分
また「上日野村地税年賦延納之儀伺」によると渡辺政信外五名持地の地租として
(約)478町で地租(約)143円
(約)427町で地租(約)128円
(約) 50町で地租(約) 15円 (いずれも山林・萱場)としている。
これを計算すると1町あたり0.3円の地租である。八郎治の所有地も同じ上日野で原野となっているのでこの算式が当てはまる。
2,795円÷4年=699円 (1年分の地租)
699円÷0.3円=2,330町 となる。
「多野藤岡地方誌・各説編」では、小柏氏の所有地は一説に三千町歩とされているとある。明治初期はメートル法は導入されていないが、1町歩は3,000坪と見て良いのではないか。
3,000坪×2,330町=6,990,000坪 となる。
約700万坪(ミニマム)である。文字通り見渡す限りの山々である。これを八郎治他十二人の所有となっているが、おそらくは家族・一族の名義の物が多いのではないかと考察する。
たかが山とはいえ凄い大地主・山元であったといえる。八郎治の別の地租延納願いの文書には、前は僅か10円の地租が1,250円になったと書かれている。藤林伸治はこれを八郎治の地租闘争と呼んでいる。
延納になった40年の各年度の地租はどうなるのだろうか。一回こっきりの税金とも思えず、毎年課税される筈と思うが詳細は不明である。
八郎治の筆

正にこの頃明治17年には、革命と言っても差し支えないような事件・秩父事件が勃発している。同事件には日野谷から多数の者が参加しており、特に小柏耕地(集落)は全戸参加ともいわれた。一戸当り一人から三人参加者を出したともいわれる。
八郎治は福澤諭吉の自由・独立思想や自由党の思想にも共鳴していたが、近代的で大量生産できる養蚕の研究、小学校の運営、地租闘争等に多忙を極めていたようだ。
大地主であった八郎治が秩父事件の際、困民党と呼ばれた農民たちの運動にどのような態度を示したのかは伝わっていない。
秩父事件に事実上の参謀格として参加し、重要な役割を担った小柏常次郎も、八郎治には好意的中立者としての立場に、留まっていて貰うよう動いた形跡がある。ちなみに八郎治と常次郎は同い年である。
小柏常次郎と秩父事件
常次郎は信州の生まれであるが、三波川の豪農、小柏菊次郎の世話で箕輪の小柏家の養子となり、桑栽培・養蚕などで近隣の人の世話も積極的にしていたという。畑や山林もかなりの規模で所有しており、妻にしたのはかの女闘士とも言われる自由党員「ダイ」(別名なか)である。
常次郎が養子となったのは箕輪小柏家の総本家小柏伊勢二郎である。親戚であった三波川の菊次郎が絶家となるのを惜しんで、見込んでいた常次郎を養子に迎えさせた。(「秩父事件の女活動家」大沼田鶴子)
また常次郎は剣の達人でもあったという。北海道のエピソードでは川の流れを算盤で斬ったという。おそらく早業により、水の流れが一瞬二つに割れたのだろう。養女にも剣技・薙刀を教え、養女は剣道上級者4・5段の男性と試合しても負けなかったという。
常次郎は北海道でも自作の神社を建てて、土地の人の相談役・世話役を自認していたがやがて樺太に渡りその地で生涯を閉じた。
秩父事件も当時は政府やマスコミにより反逆・大罪であると喧伝され、加担した者たちは犯罪人として厳しい刑を受けた。
このため当時の世相・世論も加担した人たちを冷たい目で見ていた。二十数人もの人がこの事件に参加した上日野地区でも、秩父事件の事を口にするのは憚られるような風潮があったのである。
(藤岡市史では上・下日野村で44人参加。)
なんとなく肩身が狭かったのであろう。しかし近年に至り秩父事件の研究も進み、色々な事が明らかとなり、見直されるようになってきた。一部に事件の参加者を闘士・英雄に見立てる人もあるようだ。
困民党はまず高利貸し(10ヶ月で元金の2.6倍にもなったという)の打倒を念頭に置いたとされ、近代史上の大衆運動・自由民権運動の一環であった側面をも有していた、と見なされるようになってきている。
最近では、常次郎が移住した北海道や地元の秩父界隈に於いて、秩父事件百周年の記念講演などが行なわれている。これ以前に釈放された常次郎は北海道で講師として招かれ講演も行なっている。
地元に貢献していた所以であろう。常次郎は小柏村・箕輪で金策の相談にのったり、多くの者を自宅に止宿させるなど世話役となっていた。こうした事から藤林伸治は、常次郎の人となりが分ってきて、これまでのやたらに人を煽動して騒動を引き起こした張本人、という見かたは変ってくるだろうと言っている。
武士の商法敗れる
ここに詳細を極める資料がある。長年に亘って、秩父事件や近隣の村の研究を続けた映画監督の藤林伸治のノートである。講演か投稿用の取材ノートと思える、或いは映画のシナリオ製作用ででもあったのか。
「秩父事件と旧日野村」と題して1983.5.15 藤林伸治とある。次に示そう。
土地所有および生産様式にみる小柏耕地の特質
隷属的主従(大家と家抱)関係が13世紀初頭から、明治初年の「家抱解放令」まで続いた特殊の山村共同体で、所領の吉井藩も小柏の自治圏を承認し幕末革新期にはその影響下(同盟関係)にあった上・下日野村□(落?)を最大限に利用した。
横浜開港以後の原蕾期、小柏の当主八郎治は福澤諭吉の啓蒙思想に傾倒し、生糸の輸出生産に情熱を燃やし、在来の封建的生産様式を最大限に活かした村落ぐるみの大規模生産方式を編み出し、横浜市場に進出した。
しかし士族の商法さながらに商敵・原善三郎に父祖伝来の、小柏の山林を明け渡す羽目になった。こうして600年来の山村共同体であった小柏耕地は、幕藩政下では考えられなかった冷酷な資本の倫理に直面する。
もともとこの地域は良質の蚕卵原紙、蚕糸の他、茶、白炭、生漆、屋根板、木材、蝋石、砥石などの商品生産が盛んであった。松方財政の強行下で大規模な土地収奪が開始される。横浜商人原善三郎(亀善)の取得した土地は、
「山林160町5反、畑3反7畝9歩、宅地7畝20歩」
星野長太郎は宅地、畑、山林の別なく120町歩余
さらに群馬事件前段の農民側世話役に登場する、小幡の茂原百一郎(蚕種・質屋)も加わって、実に山林の60.5%、畑の31.4%が外部商業資本の手に渡るのである。
宗家小柏家の手元に残された山林は小字小柏を中心に、
「山林原野39町9反7畝、畑2町9反3セ、宅地7反9セ1分、その他4畝10歩であった。
これ等は経営能力を失った小柏八郎治に替わって、事実上村落ぐるみの共同体利用に委ねられ、代償として良質の漉紙が小柏家に形式的に上納されるという両者の新しい関係をもたらす。
既に明治9年旧家抱の賦役地は全て無償で「譲与」されていて、各戸の生業は盛んであった。炭焼き、山稼ぎも活気を取り戻す。かっての封建的統治下の下層農民の急速な自立化、旺盛な商品生産活動と意識の変革――米作、出稼ぎ地帯とは異なる秩父事件参加地帯の性格。 (法政大学大原研究所蔵 藤林伸治ノート)
藤林によると小柏耕地の土地台帳の名義人は79名で内、旧家抱が47名、残りは耕地外の地主や外部資本であるという。
ちなみに同ノートの明治17年の土地台帳の、集計の項目にある数字をざっと集計すると、上日野で2330町(歩)になる。藤林資料集の中にある「火の谷」(1977年刊)の記事には、秩父事件に参加した人数は上日野56人、下日野38人とありかなり多い数字になっている。
そして日野谷で注目されるのは、維新前後まで多くの村民を家抱として隷属させていた“殿様”(日野七騎)のうち柴崎豊作、小此木峯太郎、黒沢金四郎、山田房吉と4人までが、小柏常次郎らの自由党員として参加し処罰を受けているとしている。
金四郎と房吉は耕地の組織者として活動した。いずれも明治に入ってから没落した豪農であるという。
「火の谷」は秋に御荷鉾山が耀く“火野谷”になり、古代に火ノ谷(ヤツ)と呼ばれた所以によるという。(「火の谷」は「秩父困民党に生きた人びと」に収載された。)同誌の藤林伸治の言葉を借りれば、「小柏耕地の生活山の60%は短期間に収奪され、それはまるで死屍に群がるハイエナのようだった。」という。この藤林資料の中には絶対年代を特定できる記載がないのが残念だが、これにより色々な事が明らかとなって浮かび上がってくる。
「風梅年代記」に明治15年生糸大値下がり、商人皆大損とあり、この相場の大崩や松方大蔵卿の政策による家抱への土地の下げ渡しなどが大いに八郎治を苦境に陥らしめたと考えられる。
旧家抱が耕作に当っていた土地は全て、無償・無条件で家抱に譲与・下げ渡されたとしている。「生糸」や「乾繭」「小豆」は現代でも先物取引とされ、プロ中のプロでも先を読めず大損する事がたびたびである。(横浜に商品取引所がある)ましてや素人では絶対に儲ける事はできまい。特に小豆は近年まで「赤いダイヤ」といわれ激しい投機対象となっていた。
いま現にある商品ではなく、半年・一年先に入る商品の売買をするのであるから、どうしても経済状況などが大きく変わったり、災害などの不確定要素がふんだんに相場に盛り込まれるのである。
したがって、ちょっとした噂話でも相場が乱高下する事がある。またイギリスの国内事情により生糸が暴騰した事もある。このように諸外国の天候異変、国内の経済の動向、世情の不安定からも相場は乱高下する。
明治13・4年は生糸価格は高止まりしていた為に、好況の観を呈していたが16年には暴落し17年には14年の半値以下となり不況の波が襲ってきた。西南戦争の出費に喘いでいた政府・大蔵卿松方正義が、採ったデフレ政策により農作物の価格は暴落し、農民の現金収入は激減し逆に税金は大幅に増えた。農民は高利貸から金を借りるようになり、返せなくなり集落からの離脱・一家離散などが目立つようになっていた。
各地方でも地租改正反対運動が持ち上がっていた。高利貸の連帯責任として、戸長は田畑を手放し貧農へと転落する者が相次いで現れた。
政府の地租改正・生糸の取引所を通さない直接輸出の奨励策などに揺籃され、原善三郎・星野長太郎・茂原百一郎などの明治の怪物たちの競争相手との狭間で、八郎治が日夜苦しみぬく姿が髣髴と浮かんでくる。
善三郎は生家が生糸問屋であった事から、生糸の取引には幼年の頃から関与していたらしく、裏事情にも精通していたとみられる。また長太郎も生家が金貸しも営んでおり、海外に何度も留学し製紙所を立ち上げるほどの生糸のプロであり、修羅場を何度も切り抜けてきた傑物である。
これに対し八郎治は先代から、綿々と引き継がれてきた山と土地の管理、御鉾神社を通じての農民たちの取りまとめなどに、多忙を極めていたと思われる。また小学校の管理・運営にも心を砕かなければならなかった。
季節ごとの林業の仕事、畑の管理、神道教会の集会・勉強会の主催などに加えて戸長として、村全体の行政をも見ていかなければならなかったのである。国際的な相場を睨んで、生糸の鬼ともいえる売込み人を向こうに廻して、対等に渡り合えるような状態にはなかったといえる。
まして善三郎も長太郎も、後に伝記本が何冊も出版される程の傑物であり、とても誠意だけで通用するような世界ではなかった。文字通り潰すか潰される世界がそこに展開していたのである。この点では当時の財閥、三井・三菱などの競争と同列に論じられるものであったろう。
横浜生糸取引所で購入する相場は、世界の相場の二分の一ほどであった、その事が分った各地の生糸売込み人たちは、アメリカなどに直接輸出が出来るよう奔走に明け暮れたようだ。
原善三郎の生糸問屋には八郎治の義弟が勤めており、その長男(妹の長男・甥)も勤務していた関係から、当初、八郎治は上日野で生産した生糸を善三郎に売り渡していたと見られる。
横浜の有力な売込み人(問屋)は例え良質の生糸であっても、数量がまとまらなけらば購入しなかった。このため生産者にとっては人件費・機械の設備投資・運搬費などが膨大な金額に達したという。
このために八郎郎治なども設備投資費用を、善三郎から売上金の前借として借りていたという事も大いにあり得る。生糸相場の暴落によりこの借金が返せなくなり、担保としていた山や畑を渡す事になったのではあるまいか。
この間の詳しい事情は分っていない。長い時間をかけてこの事を解明する資料を探したが、遂に見つかる事はなかった。思い余って藤岡図書館にお願いしたところ、文化財課や過去に歴史を執筆した先生にも問い合わせて頂いたが、資料は出て来なかった。
特に他の生糸商人との関わりや、取引の状況を知りたかったのだが、口頭でなされたものが多いのか、いまは霧の彼方へと遠ざかって行ったようだ。
星野長太郎の家は名主家であり、後に銅山経営や金貸しまで手広く事業を展開していた。
一時、一族が逮捕され親類中の金をかき集め釈放に奔走したりして、家屋敷そっくり手放した事もあったが長太郎はいつも不死鳥のように立ち上がっている。
海外に何度も留学や視察に行き、水沼製紙所を設立し、横浜正金銀行の幹部となり、明治政府の要人にも深く食い込んだ
文字通りの明治の動乱が生んだ怪物といえようか。
上日野小柏に富源産業㈱がある。木材を切り出し加工し横浜方面へと搬送するのには恰好の場所である。同社は元の名前を原林業部といったが戦後に改称した。本社は横浜にあるという。
何時の時点かは分らぬながら従業員は7~8人という。(昭和中期?)製紙・生糸・絹などを取り扱っていたようだ。考えるまでもなく亀善・原商店の関係会社であろう。製材部は藤岡に持っていたというが、こんにゃく・りんごの栽培・販売にも手を広げていた。
明治初期から中期にかけての頃か、小柏家の持ち山を大量に買い占めていた。地券は箱詰にして富岡の原製紙へと運んでいた。小柏氏は惜しげもなく原家へ地券をくれていたという。(藤林伸治のメモ)
地租が上って厖大なものになり、山林・土地の所有にも嫌気が差していたのか。
小柏家 落魄の風
秋の夕日は釣瓶落しという。御荷鉾山の鮮やかな紅葉が終わると、冷たい木枯しが舞い降りて来る。御荷鉾山の麓に位置する小柏村は標高550mほどである。山間の里に吹く冷たい北風が、小柏家の柱の隙間から襖の隙間を吹き抜け、屋内を寒々とした広い空間に変えてしまっていた。
以下は哀しい没落史となるが、これもかって繰り広げられた歴史の一コマとして記さざるを得ない。
小柏氏没落のきっかけを作ってしまった悲運の士、「八郎治」その名は長く歴史に残る事となった。藤林伸治のメモには、小幡町のシゲハラ質店が大正初期から15年頃にかけて、小柏家の刀剣その他多数を買い受けていたとある。その多くは質流れとなった模様である。
この売却を誰が指図したのか、八郎治は大正11年5月に80歳で没している。老齢であった八郎治が直接断を降したものか、或いは「逸」であったのか。八郎治の死後にも売却しているようなので、当然相続人か身内の誰かが関わったのだろう。
小柏八郎治(重明)の長男武之助は早世した。長女美代は武州奈良村の吉田保三(之?)の妻となった。二女の逸は三波川村の飯塚時五郎に嫁いだ。三女濱は信州臼田町の井出久定に嫁いだ。四女光江は児玉町小平の根岸坦二に嫁いだ。(二児を連れて再婚)
五女光志は下仁田町の市川虎義に嫁いだ。この五女は高山家所蔵の小柏系譜には市川虎義室登志、早世とある。小柏家で筆写した系譜に分っている事を書き加え、より詳しく記述をしたのであろう。
二女の逸は晩年には小柏村に戻って舘を守っていた。袴をはき、馬を走らせ村長や村の者を呼び捨てにしていたという。栄光が翳るその瞬間、落日が一瞬の輝きを見せるように最後の空しい、そして涙にも似た悲しみの光を放ったのだろうか。激動の時を生きて昭和22年その生涯を閉じた(80歳?)。
重明の跡を継いだのは吉明である。
吉明は重明の四女光江の長男である。大正十一年五月、祖父重明の死去によりその家督を継ぎ第三十五代の当主となった。この時、吉明は24歳、妻は芳江である。この相続の時点での吉明の住まいは小柏であったのか、児玉町であったのか不明だが後者の可能性が強い。
大正十二年三月大宮市に居を移した。高山家蔵小柏系譜には、吉明は日野小学校の教師を経て埼玉県警に奉職したとあり、その妹は兄と共に根岸担二の家に入り児玉町で育ったとある。
藤林伸治が、小柏吉明から聴取した時のものと思われる取材メモがある。断片的なものなので、正確な事情は読み取れないがかなり重要な内容を含んでいる。
このメモは次のようなものである。
細谷戸 戸川タケキ 八郎治代理人
根岸担二・児玉(町)の銀行へ(八郎治の土地を)担保に入れた。
![]() ∴訴訟を起こした。 臼田町の井出久弥
∴訴訟を起こした。 臼田町の井出久弥
戸沢の市川 が一緒に小○(原?厚?)へ行った。
奈良の吉田保三
ところが示談となり、約5,000円くらいで処分されてしまった。(昭和2年頃)
担二の妻女は高山長五郎の妹で、担二が一時製糸で破産した時高山家に移っていた。
その時八郎治の土地は全部処分してしまった。[(八郎治は)実印を預けてあった。]
( )内は筆者
以上のメモから分った事は
1.八郎治に代理人がいた。?
2.根岸担二が土地を担保に入れていた。
3.訴訟が起こされていた。
4.この訴訟は根岸担二を相手方として、義理の兄弟三人が訴えたものらしい。
井出久弥(定)は弥と読んだのが、正確ではないかもしれないが八郎治の三女濱の嫁ぎ先。
戸沢の市川(虎義)は同五女光志の嫁ぎ先。
吉田保三は同長女美代の嫁ぎ先である。
5.八郎治の二女逸の嫁ぎ先の飯塚時五郎の名前がない。他は全て相続人。
6.やや安い値段で処分しただろうと思われるが、5,000円程度の土地であった。
7.昭和2年頃、相続について揉め事があった。
8.根岸担二は一時的に?製糸で破産したらしい。
9.根岸担二の妻は高山長五郎の妹だった。
10.土地の処分に高山家が関わった可能性があるのか?
高山家は相続人の立場になく関わった可能性は極めて低い。実印を誰に預けてあったのか不明であるが、文脈からは担二に預けていたと思われる。
おそらくは担二が資金繰りに困り、八郎治を保証人に立てたのか又は担保の提供を頼んだのだろう。
この際、一番上にメモされた「細谷戸、戸川タケキ 八郎治の代理人」が関わったのか、そして代理人が任命された時間の前後関係などは一切不明だ。この訴訟に飯塚時五郎の名前が見られないのは、この時点で離婚していたか或いは既に死亡していたかどちらかになろう。
資産家だから訴訟に参加しなかったという事は、同じく資産家の市川家も訴訟に参加しているため考え難い。ちなみに八郎治の母は戸沢の市川半平の二女である。そして妻は児玉町小平の根岸孫右衛門の長女である。
同じ児玉町小平の根岸担二は、嫁いだ四女光江とは従兄妹同士だったと思える。こうしてみると、市川家も根岸家も八郎治家とは非常に近しい関係にあった事が分る。 さらに下奈良の吉田家も八郎治の妹、代が市十郎に嫁いでおり、八郎治の長女が嫁いだ吉田保之とも従兄妹同士の結婚であろうか。
昭和2年当時は、既に家督相続していた筈の当主である吉明の年齢は29歳である。既に大宮市に居を移していたが、この時点で結婚していたかどうかはわからない。昭和6年に長女が誕生している事から、まだ結婚していなかった可能性が強い。
仕事が忙しく、また担二は養父であった為に、傍観していたのではなかったかと思われる。
おそらくは大正十一年に八郎治が亡くなった後も、家督相続を誰に継がせるか正式にはまだ決っていなかったのだろう。昭和二年の頃はまだ吉明の代理人を養父の担二がやっていたのだろう。
この時に処分する土地がなくなって、吉明が家督相続したものと推測できる。高山家の系図で確認すると、長五郎の三女と思しき多勢子が根岸太平に嫁いでいる。
太平の名前の下に、担二 児玉郡会議員秋平村長ヲ勤ム秋平製糸所の創立経営ス。と記されている。藤林伸治のメモと合わせて考証するに太平が後に担二と名乗ったもののようだ。そして担二が一時製糸で破産とのメモは秋平製糸所の倒産を意味しているのだろう。
これ等の記録をつき合わせると、次のストーリーが脳裏に浮かび上がってくる。児玉町小平の根岸担二は郷士であり、郡会議員を勤め製糸会社を経営するなどの土地の有力者だった。
担二の叔母が八郎治の妻であり、初め高山多勢子を嫁に貰ったが何らかの事情で離婚した。後妻に貰ったのが八郎治の四女光江である。その後自身が経営していた秋平製糸所が糸価の低落により倒産した。
同製糸所は、資金繰りの度に八郎治に保証人になってもらっていたから、実印も預ったままになっていた。
八郎治には保証人と共に担保を提供して貰って、銀行の抵当に入れていた。そして借金返済を迫られ、やむを得ず八郎治の土地を処分した。
光江が最初嫁いだ吉田嘉三郎は吉明の実父であるが、昭和二年の訴訟の時までに離婚(死別ではなさそう)していて、籍を抜いていたので訴訟には参加しなかった。この嘉三郎は光江の姉美代が嫁いだ吉田保三の弟と見られる。
下奈良村(現熊谷市)の吉田家には、これ以前に八郎治の妹・代が市十郎宗載に嫁いでいる。
吉田家は旧家であり、初代市右衛門宗以から五代目宗載までの約200年間に渡り、慈善公共事業に尽くした家柄であった。特に三代目の宗敏は天災や凶作の時に近在の農民などの救済に力を尽くした。
その善行は育児資産を献上するなど枚挙にいとまがなかったという。また同家は名主を勤めていたようだ。吉田家の累代の墓所は、下奈良集福寺にあり県の指定文化財となっているほどである。
つとに有名な高山長五郎は明治初期に刻苦研鑽し、合理的な養蚕法を編み出し養蚕改良社「高山組」を創立した。広く養蚕の指導をした他、後に星野長太郎などと共に生糸の直接輸出の途を開いた。(別項)
「細谷戸 戸川タケキ 八郎治代理人」というメモの意味するところは謎である。ここまで八郎治の事績の探求を続けてきたが、戸川もタケキもどの文献・記録にも記載されていない。
民生委員・公証人のような立場の人ででもあったのだろうか。多くの縁戚があるなかで、他人と思われる人が代理人になる事があるのだろうか。今の時代ならばあり得ない事である。
小柏(村)のすぐ近くの細谷戸に同族の小柏氏があるが、八郎治の兄弟・子供で細谷戸に嫁いだ女子はいないので、祖先は同じだが近世の縁戚関係はない。
吉明の長女尚江は大宮市大和田の大木広美に嫁いだ。
吉明の長男は敏明である、妻はヤイである。二男は勝明である。
敏明の長男は秀一郎である。(ここまで小柏氏正系図)
原 善三郎
八郎治の商敵とも共同事業者とも言われる原善三郎について少し触れておこう。善三郎は横浜の美しい三渓園に関係した事で、原三渓(富太郎)と共に良く知られている。同氏の出身地は児玉郡神川町(旧渡瀬村)であり、そこの旧家で文政10年(1827)に生まれている。
家業として機業家などを相手に生糸を売買していた。渡瀬村は昔から秩父絹を江戸の呉服問屋へ送る中継点であったという。
横浜開港の翌年には秩父提糸を野沢屋(現在の百貨店か)と吉村屋へ出荷する事になり、横浜の弁天通に店舗兼住宅を手に入れ生糸店の屋号を「亀善」と称した。時に「亀屋」と呼ばれる事もあったようだ。
翌年には居留外国人へ生糸を売り込む仲介人となり、蕎麦屋を買い取って開店した。
そして委託販売人となり商売を拡大し、慶応元年には横浜第一の生糸売込み商人と言われるほどになった。同氏は明治二年には政府の為替方となり、横浜為替会社の頭取になった。
当初官営であった富岡製糸場も三井家に払い下げられ、三井から原家が買い取って経営に当った。
明治六年の生糸改会社には社長の一員に名を連ねた。翌年には為替会社を改組して第二国立銀行を設立し頭取になった。横浜開港後、多数の生糸売込み商が出店して慶応二年には131人となっていた。
しかし生糸の値動きは激しく、明治六年の生糸改会社への加入者は僅か16人に減っていた。残りの売込み人は潰れてしまったのである。(新しく加入した者は17人、計33人)生き馬の目を抜くような激しい競争に打ち勝った、少数の売込み人に生糸の流通が集中する事になった
明治二年夏の時点では流通量の三分の一以上が原・茂木両人に占められたという。明治七年には流通量の74%が上位五人(小野善三郎、原善三郎、三越得右衛門、茂木惣兵衛、吉田幸兵衛)が占めていた。その後、善三郎は神奈川県議会議員、横浜商法会議所頭取となり、横浜蚕糸貿易商組合の組合長となった。また横浜市議会議員、議長を歴任し市参事会員となった。
明治25年には埼玉県から出馬し、衆議院議員に当選、明治28年には神奈川県の多額納税者で貴族院議員に選ばれ、横浜商工会議所初代会頭になった。横浜野毛山の邸宅には珍樹泉石の大邸宅(レンガ造りの洋館)を造り、隣接の茂木別荘と並び称される名園となった。
この大邸宅は現在の横浜市中央図書館の裏手から、野毛山公園にかけての広大な土地に建てられていたが、関東大震災によって潰れてしまった。建物はイギリスの貴族の邸宅のようにも見え、当時としてはひどくハイカラな物だった。
また渡瀬には天神山と称する別荘を築庭し、明治初期には横浜本牧に後に三渓園となる山林・田圃を20万㎡を購入した。明治32年に72歳の生涯を閉じた。
(神川町HP)
原善三郎邸・茂木邸の跡地は、今は横浜野毛山公園・野毛山動物園として整備されて、往時を偲ばせる物は何も残っていない。
小柏氏正系図 作成者
現存する小柏氏正系図を作成したのは誰か?
筆跡などから考察するところ八郎左衛門重方ではないかと考える。重方は1764年生れと見られ、1832年68歳で没している。小柏家に代々伝わっていた古記録(別記)と系図を元に整理・作成したのではあるまいか。
小幡龍蟄が書いた幡氏旧領弁録の中に「歴代法名記録」がある。小幡氏の始祖氏行から15代信真までの法名を書いて、位牌と共に宝積寺に納めた物である。この法名を新たに書く際に、参考にした物は「古伝する記録」としている。
これにより同家に古記録が伝わっていた事が推察される。この他、宝積寺所蔵の過去帳をも参考とした。
現存の小柏氏正系図が制作されたのは近世であるが、古い時代の事も記載が正確(藤岡市史)であり、余人が知るはずのない事跡も記載されており、古記録があった事が納得できる。
或いは、それまで保存していた系図が老朽化・汚損・焼失などの事があり、新しく書き直したものである可能性もある。
和紙は丈夫で筆跡は消え難く、破れづらく長持ちするが、それでも150年も経てば虫食いが激しくカビの害も発生するので、作り直したという事も充分あり得る事だ。
私も先祖の約270年に亘る家系図の作成を試みたが、完全に繫がる物にはならなかった。
位牌・過去帳・お墓などの調査で分った名前は26人ほどあり、家族の中での横のつながり、縦の関係が判然としないのである。何回も作り直してみたが、21歳で後継者を生んでいる事になる部分が二つ出来てしまう。
間違っていないかも知れないが、正確ではない確率の方が高いと思われる。
このように家に伝わる記録がないと、300年も系統が繫がらないのである。まして小柏氏は800年に亘って続いており、江戸中期の人物が正系図を作ったとしてもそれ以前の600年ほどの記録がなければいい加減な物にならざるを得ない。したがって小柏氏正系図は何回かに亘って、書き直された物と考察する。
現存する系図は江戸中期に新しく書き直された物である。それ以前の物は虫食い、水濡れなどによって判読も難しくなり再作成したのであろう。
和紙を侵食する虫食いなどについては、県立文書舘などに保管されている古文書であっても、ひどい状態になっている物が多くあり、これを見ても理解できると思う。
小柏氏系図は高山氏の系図と書式・構成・表現などが良く似ている。次世代に結びつける直線の描き方が同じである他、主だった人物名の横にその事績が記されている点もおなじである。
また誰々に属すとか軍功ありとか、大力ありなどの表現もそっくりであり、改名した名前や法名も記されている点も似ている。
また高山氏も小柏氏とほぼ同時期に、鎌倉北条氏の京都六波羅入りに供奉・勤番しており両氏は共に鎌倉武士だった事が窺える。これ等の事から、骨子において小柏氏系図は信憑性のあるものと判断できる。
第七章 小柏氏の末裔
日野地区の小柏氏
「上野国郡村誌」に載っている上日野の概要を見ると、戸数229戸、社10戸、寺7戸、計247戸、人口1,001人とある。神社と寺の多いのが目立つ。諏訪社は村社であり祭神は建御名方命、祭日は8月27日。野々宮社は村社で祭神は草野姫命、祭日は10月25日とある。
民業は農桑業140戸、薪炭79戸、生糸(女)330人。との記載があり、桑の木を栽培し、蚕を育て繭から生糸にするまでの事業に従事する人が多かった事が分る。日野谷の生糸は日野絹と呼ばれ珍重されたという。上質の物であったのだろう。
現在、上日野においては小柏家本家の嫡流子孫の影は見られないが、鮎川の向かい側の,細谷戸小柏氏は小柏本家からの古い分家であろう。今も小柏姓の家が数軒存在している。
千人斬りと伝説にも謳われた、小柏高政の従兄弟の高治が細谷戸の地守であったとの記録がある。高治は後に信州田ノ口の代官になっている。(小柏氏正系図)
「地守」という事が何をさすのか、どんな事をやる役職なのか今は判然としないが、村民を取り纏める村長のような、小代官のようなものと想像できる。江戸時代になると、町内の世話役を「地守」という事があった。おそらくこの頃から小柏氏の分家が細谷戸に存在していたのであろう。
高治はおよそ1550年代頃に活躍した人物である。高治の父高景の兄高道が、小柏本家を相続しており、高景が細谷戸に分家をした可能性が大いに考えられる。その時期は大まかに言って1500年頃と推定しておきたい。すると約500年も前の古い時代からの継承を持っているという事になる。
同じく、その系譜の中に見られる榎谷戸の小柏家は現在の上日野坂野である。今も6軒ほどの小柏姓の家が集中している。小柏重高の妹が榎谷戸村の小柏弥五兵衛光高に嫁いでいる。この事から戦国時代末期には同村に分家が出来ていたと見ても差し支えないと思われる。
この他、秩父事件の常次郎が養子として来た事で、有名になった箕輪にも小柏姓の家が数軒ある。
箕輪小柏氏は、上日野小柏村の本家からの分家の可能性が高いと思われるが、三波川小柏氏との繋がりも深く三波川から移住した可能性も残されている。
奈良山小柏氏は元後藤姓であるが、小柏氏から妻を迎えてその子から小柏氏に改称した。その時期は細谷戸に分家が出来たとほぼ同時期、或いは一代後くらいの年代に当たる。
奈良山小柏氏は宝積寺に墓地を有していて、檀家として今も猶 同寺と深い繫がりを持っている。同氏は丸に対い蝶の家紋を使用している。(本家は揚羽蝶)
小柏氏本家は埼玉市に移っているので、上日野地区にあってはこの四地区が小柏氏の足跡を伝えている。
大沼田鶴子の「秩父事件女活動家」によれば、三波川の豪農、小柏菊次郎と箕輪を開拓した小柏家の総本家・小柏伊勢次郎は親戚筋であったという。菊次郎はまた常次郎とも親戚筋であって、常次郎の人柄を見込んで菊次郎の養子に世話をしたという。血縁が絶えるのを惜しんでの事だった。
下日野に「鈩沢」の地名がある。鈩遺跡があることから付いた地名であろう。平安期から鎌倉期にかけて銑鉄を精錬した遺跡である。周辺は古くから「かなくそ」が散乱していて「金山」の地名もあったという。
古代の大鍛冶用「たたら」であり、全国的にも稀有の物であるという。この遺跡の東方、金井にも上野国分寺瓦を製造した金山瓦窯跡があり、鮎川流域には製鉄や製瓦に関連する集団が居住していたと考えられる。(「群馬県の地名))
この集団は誰で、何所に消えたのか?近くには土師神社もある事から土師部に属する一族であろうか。
お菊伝説の項で述べた、小柏様のお通りじゃ、の別版に「蛇もムカデもど~けどけ鍛冶屋の婿どんのお通りじゃ」とする童歌も残っている。この事から小柏氏と製鉄一族との関連性に注目する必要があるかもしれない。
製鉄で財を成し更に鮎川の上流に、良い鉄を求めて入って行ったものか。或いは小柏氏の一族のうちの誰かが製鉄に従事していたのか。配下の者が製鉄をやっていたのか、製鉄氏族の子孫が小柏氏となったのか。
今後の研究課題であろうか。
小柏小学校は明治十八年に多胡第二小学校の第二分校となり、後に日野第五尋常小学校となり、明治40年には校舎を新築している。
日野西小学校の歴代校長の中に小柏達三(明治40年)の名前が見える。また日野第五尋常小学校の歴代校長の中に、小柏達三(明治21年)、小柏辰五郎(昭和13年)の名前が見える。
日野中央小学校PTAの歴代会長の中に、小柏磯吉、小柏美佐雄、日野西小学校PTAの歴代会長の中に小柏行平の名前がある。小柏小学校は戦後の昭和24年4月に廃校となり、地域の教育をになったその長い歴史に幕を閉じた。
地元の古老に聞いた話でも、戦後まで小柏館の隣に小学校があったとしていた。
平成18年の電話帳を見ると小柏姓は日野・藤岡地区で27軒の名前がある。これをごく近隣の上日野・下日野だけに絞ると僅か9軒になってしまう。少し寂しい数字ではある。勿論、昨今の社会情勢から電話帳に記載していない人もあるだろう。
平成12~13年頃の物と思われるが、家の歴史社によれば、群馬県の電話帳には藤岡鬼石町を中心にして、128軒の小柏姓があるとしている。全て上日野の小柏家を源流としているという。
平成18年4月現在の電話帳では三波川・鬼石町地区に22軒、甘楽・天引地区に21軒、藤岡・日野地区と合計しても70軒しか見えない。埼玉県や東京都・神奈川県に移った人も多いとみられる。

上日野 小柏氏家系図 高山長五郎筆
800年に亘って血を流し、涙を流し築きあげて守ってきた山と屋敷地、歴史に名を刻んできたその所領ともいうべき上日野。先祖代々の霊が眠る墓地もそのままに、この地を去る事になった小柏氏の末裔の気持ちはどんなものであったろうか。
小幡氏にあっては二百五十年後に中興の祖とでも言うべき、小幡龍蟄が出て歴代祖先の事蹟史、系図を作り位牌を作り各地の墓碑と墓地を整備し、ねんごろに供養を行なった。
近年では全国の小幡一族が参集し400年大供養を行なっている。
小柏氏は栄枯盛衰の時も過ぎて歴代の勇者は今、木漏れ日の差し込む木立の中に静かに眠っている。何時の日か小幡氏のように中興の祖が現れ、また祭祀の行なわれる日が訪れるのであろうか。
三波川の小柏氏
三波川は慶長三年まで同地、郷士の飯塚和泉守の領地であったが、同年から幕府代官伊奈備前守の支配となり、明治まで幕府直轄領となっていた。飯塚家は名主を代々勤めた。
三波川に小柏姓は多い。「群馬県姓氏家系大辞典」では、日野谷から南の三波川にかけて小柏姓があり、上日野小柏が発祥地とされる。と記載して、以下は平清盛からの小柏氏系図を紹介して、重盛が武蔵国司の時に妾腹に生まれた維基は小柏に隠れ、姓を小松から小柏に改めた。としている。
定重は菊女伝説に登場、長篠で戦死。代々日野谷を支配。重高は黒滝山に不動寺を建立。八郎治は小柏支校を自宅に移す。…..と長々と記載している。(半分以上略した。)
三波川小柏氏は明治から大正にかけて、仲重郎・実五郎が三波川村会議員・郡会議員を務め、義夫は昭和四年から村会議員などを歴任した。
三波川に小柏姓の家は13軒あり、その内の11件は妹ヶ谷にあり更に8軒の家は一箇所ともいえる近隣に集中している。小柏氏やお菊の伝承を引き継いでおり、現状を鑑みると,ある意味でこちらが小柏氏の本流を継承していると言えるかもしれない。
「多野藤岡地方史・各説編」を見ると、三波川西小学校の歴代校長の中に小柏勤悟の名前がある他、三波川東小学校PTA歴代会長の中に、小柏宗一、小柏安太郎、母親学級長の中に小柏くに子の名前が見える。
同じく三波川中学校PTA歴代会長の中に小柏求、保護者会歴代会長の中に、小柏昇、婦人会三波川支部歴代支部長の中に小柏えいの名前が見える。
青年会歴代支部長の中に小柏英雄、学務委員の中に小柏仲重郎、小柏実五郎の名前がある。

三波川墓地
甘楽天引の小柏氏
群馬県姓氏家系大辞典(角川書店)に次のように出ている。
「天引に小柏姓がある。桓武平氏で、平維盛の子維基が甘楽郡小柏村(藤岡市)に隠れ住み、後裔は日野谷の支配者となり、のち小幡氏とともに武田氏に属したという。
源六定重は菊女伝説で知られ、天正三年三河長篠の戦いで戦死。天引にはその三兄弟の後裔が移り住んだとの伝承がある。」
甘楽町天引にはお菊を助けた定重の三兄弟の子孫(或いは三兄弟)が移り住んだという口碑・伝承が今も残っている。
天引という地名は広い地域に亘っていて、天引城・倉内城の二城もあり重要な戦略的位置を占めていた。小柏姓の家が集中している所は天引の外れ、字名「久保」である。
明治8年頃に編集された「上野国郡村誌・9」を見ると、天引村字地久保あり、東西一町三十八間、南北一町四十五間、戸数200戸、社戸5、寺3戸、計208戸、人口825人とある。
民業は商19戸、工9戸としている。「村社は諏訪社で祭神は建御名方命、祭日は9月15日。他に熊野社が村の西南にあり、祭神は伊邪那岐尊・速玉男命・事解男命で祭日は9月15日。向陽寺は天文年中に僧・道巌の開基。これは信玄(武田)の叔父という。」と記載している。
諏訪社は信州の諏訪大社を本社としている。諏訪社を置いている点は上日野も三波川も同じである。また熊野社はその祭神名からして古いものを感じさせる。
諏訪大社は初め狩猟の神様を祀っていたという、後に武人の神様、武神となり、北海道から九州まで約五千社以上の末社が数えられる。
これら諏訪大社を勧進した各地には「諏訪」の地名が残っている所が多い。本社は長野県諏訪市の上社と諏訪町の下社の二社である。
建御名方命を祭神としているのは、天照大御神が派遣した武御雷之男神に、出雲(大和の出雲か)を追われ信濃まで逃げたとする「古事記」に由来するのだろう。
天引の小柏姓の旧家(政美家)で聞いた話では、小松と言う人が小柏村に来てその(子孫の)三兄弟のうちの一人、右近(或いは左近)が天引に移り住んだという事であった。(祖父から聞いた話との事。)
同家では過去帳から判明している先祖で、一番古い人は延亨3年(1746年)没であるが、名前は不明でその次の人が宝歴年中(1751~1763)の没であり、その次が権大僧頭(都?)八之丈であるとのこと。
菩提寺の向陽寺が三百数十年前に火災にあい、それ以前の過去帳が残っていないが向陽寺に墓を作る前の墓は近くの別の場所にあり、石碑は二基あって一基が代々の当主の物でもう一基がその他の家族の物であるという。
この形式は宝積寺にある奈良山小柏氏の墓所と同じものである。天引の小柏一族は寺への信仰・帰依が厚いように感じられる。それぞれ立派な墓地を持ち先祖の供養も欠かさない。
その姿勢からと思われるが、法名に寺への貢献度が高い人に贈られる格の高い戒名が多く見受けられる。
天引の小柏鶴吉(故人)家は私の本家筋に当たる家であるが、その家には代々伝わる位牌が残っていて、判っている先祖だけでやはり283年程さかのぼる。当主は代々勘右衛門と称していた。
墓は近くの畑と丘(里山)の麓との境の小さな野辺の道にある。本家の墓碑、分家の墓碑がずらりと並んでいる。近世に到り墓は向陽寺にも新設したが、同寺の大火災で過去帳は300年を遡れない事は先の旧家と全く同じである。

ご先祖様の墓碑 合掌

天引の小柏一族は、小柏氏が信仰していた宝積寺と同じ曹洞宗の向陽寺の檀家である。他に寺がないという訳ではない。上日野小柏氏とのこの他の共通点は、墓地は自己所有地に設営して、法事は寺に依頼し位牌を祀り供養を行っている事、などでありこれ等の類似点は、両者の間に何らかの関係があった事を窺わせる。
向陽寺にお尋ねしたところ、鶴吉家の約284年間に渡って護られている位牌を、調査してくれた上に、過去帳とつき合わせて精査して頂けた。その結果26人ほどの先祖があり、その戒名などが判明した。過去帳は戒名と没年代、小字名の物が多く生前の本名までは調査しきれなかった。
その戒名の多くは「山」の字がついた物が多い。やはり山の権利を持ち、山の関係の仕事をしていたものと考えられる。現在小柏姓が密集している集落の北側にはゴルフ場がある。昔はこのゴルフ場が里山であったのだろう。
そしてこの山をはじめ周辺の山において、林業・炭焼き・シイタケ栽培などの山稼ぎが多かったと思われる。判っている一番前の先祖が284年前の没であるから生年は60年ほど遡ると考えられる。さすれば344年前になる。
小柏氏と掘口氏
伝承では上日野村の、小柏源六定重の三兄弟の後裔が天引に移り住んだとされているから、この三兄弟を定重の弟の定政の子、重氏・貞景・貞實と考える。系図上、他に三兄弟はいないし、定重は長篠ノ戦いで討死しており子供はいない。
定重の没年は天正三年(1575年)である。重氏の没年は1681年であり、79歳であったから当時としては長命であった。二男の貞景の没年は明らかでないが、小幡郷の堀口家へ養子に入っている。
貞景は堀口家を継ぎ堀口伝内と名乗った、法名は浄無である。貞景の長男が後を継ぎ、二男が分家して父の旧姓であり、由緒ある小柏の姓を名乗ったという事は充分考えられる。
ただ先の天引の旧家の話では、小柏氏と堀口氏は関係ないようだとの事であったが、一人だけの話では断定する事もできない。
系譜に記されている「小幡郷」の範囲は判然としない。天引(村)の堀口家ではなかったのかもしれない。だが天引の堀口家は25軒ほどあり同一の姓では断トツである。その密集度では全国一としている文献も目にした。
三人兄弟の末弟、貞實は上州福島(吉井町)の友松家を継ぐことになり、友松伝左衛門と名乗った。貞實の二男・三男が分家して天引に入り、小柏の旧姓を復したという事もあり得る。
三兄弟の長男重氏の生年が1602年であり、次に一女子が生まれている事から、弟の貞景の誕生を4年後の1606年と仮に推測してみる。
二男・貞景の長男出生を貞景28歳時の1634年、次に女子が生れたとして、二男の出生を6年後の1640年と仮定して考える。
この二男が結婚して天引へ分家したのが27歳の時と、仮定してみると1667年となる。これは今から約340年前の事になる。
先ほどの小柏鶴吉家の判明している一番古いと思われる、先祖の出生年が344年前の1663年と推測できる。先の仮定では貞景の二男は1663年には23歳である。4年の誤差があるがごく大雑把な見方をすれば、貞景の二男が鶴吉家の始祖という説も成り立つ事になる。
極端な推測ではあるが、これを否定できる材料もまたないのが実情である。
この後、小幡町で最も古い家ではと思われる堀口中庸家で話を聞いてみた。上日野の小柏氏とは、縁戚関係があったような事は聞いているが、何代くらい前の事なのかは分らないとの事だった。
代々の当主名は分っているが、貞景或いは伝内という人は居ないと明確に答えて頂いた。中庸家は現在の当主で26代になるとの事である。18代までは曹洞宗であり宝積寺を菩提寺としていたが、19代からは神道に改宗しているとの事であった。
また天引の小柏氏とは関係がないという。
上日野の小柏家から養子を貰ったのは、小幡町の他の堀口家の可能性については否定的なお答えだった。この結果には頷けるところもあり、矛盾しているところもあり謎が更に深まった感もある。
ちなみに同家では「織田様代々覚書」を所蔵しており、他の古文書も所有されている事と思われる。またこの堀口家との関連は明らかではないが、小柏氏は堀口家から養子を迎えている。
近隣にあって小柏本家の後見として、同家を支えた小柏景氏の四代目の、高次がその人であり堀口家の二男とされている。系図には「為養母弟矣」と記されているが、その正確な関係は不明である。
向陽寺
宗旨 曹洞宗 本尊 釈迦牟尼佛 宗祖 道元禅師 瑩山禅師
本山 大本山永平寺 大本山 総持寺 由来 天長年間(824~834)に鎮護国家の寺として、現在地よりも約500m東方の入木屋の地に創建されたと伝えられる。
天文年間(1532~1555)に武田氏一族の望月三郎氏が開基となり、所領9石を寄進して当地に移し、新たに曹洞宗の寺院として再興された。
開山は吉井町多胡の仁叟寺四世・荘山道厳大和尚で、俗名は武田信綱と云い信玄公の親族であったとされ爾来、寺紋には武田菱が用いられている。
当寺は天文年間の再建以来幾度の火災にあい、特に正徳3年(1713)の火災では諸堂の全てを失い、翌正徳4年に再建された。
現今の本堂はその時のものであり、概ね300年の風雪を経ている。
(向陽寺パンフレット)
「北甘楽郡史」に記されている向陽寺の紹介文の概略を次に示す。
友月山 曹洞宗 大字天引字岡平にあり、背後は連峰遠く城山に達し前には天引川を距え小丘西より東に走る。境内いと広く、幽遂閑静にして本堂のほとり小池をたたう。
少しく離れて年経る枝垂桜あり、伝えていう。此寺開山の手植なりと。近辺之に比肩すべき大樹なく、花時にありては万朶彩雲空に叢り韲くが如し。本尊は釈迦如来、脇仏は普賢、文殊の両菩薩なり。
天正の頃、武田信玄の家臣望月三郎が寺領九石を寄せ自ら開基となる。開山は信玄の第四子信綱にして、法名を荘山道厳大和尚という。故に当時は武田菱の紋を用いたという。
徳川の時代になって三代家光、先規寺領を改めて朱印とせり。境内に武田家に縁ある古碣六基あり、弘治、文録年間の物なれど、字体明らかならず。僅かに年号の頭字認め得るのみなり。
信綱の叔母、望月三郎夫妻の墓なるべしと。傍に天長三年七月八日建立の碑あり、大梵字一字を刻し年月を記す。その真意詳ならず。

向陽寺
小柏徳氏の天引移住
先の仮説が成り立たないとすると、次に考えられるのは文字通り三兄弟の子孫となる徳氏が移り住んだものか。
小柏徳氏は定重の弟・定政の孫であり重氏の四男である。系譜によると真田伊賀守に仕えていたが、沼田城が落ちる前に辞職して小柏村に住んだとある。幼名丑之助、号を宗莫としたとされている。
兄である二男は山田家を継いでおり、三男の次兄は長兄の後継となっている。弟である五男は飯塚家を継いで、その下の弟・六男は医師となってこれも小柏村に住んだ事になっている。
いわば部屋住みであり兄の居候ともいえる。父の後を継いだ長兄に子がなく、すぐ上の兄が長兄の後を継いだので、兄が二人となり更に弟の六男も居たので兄弟4人が一つ屋根の下に住んだ事になる。
となると当主の兄二人は別として、また医師の弟は収入もあったであろうから、一番居心地の悪いのは四男の徳氏という事になる。当時の小柏家の権勢からいって経済的に困る事はなかった筈であるが、兄弟が4人も居て無役となれば結婚なども難しいものがあったと思われる。
そうなれば考えるのは当然、分家・移住である。徳氏の兄弟は女子も含めて11人である。他に父が養女にしてから嫁がせた女子が二人おり、これも含めれば13人の大所帯となる。
この兄弟はみな近隣に移り住み、小柏家の影響力を周囲に拡大していたであろう事から徳氏も当然、移住がし易かったものと推測できる。近隣にいれば手助けをしてくれる縁戚がいっぱい居るので心強い事となる。
徳氏の父の重氏は大阪冬の陣に出陣しているが、重氏の後継者、徳氏の兄である重高の時代になると徳川の天下となり戦乱はなくなった。
この江戸時代初期には新田開発が奨励されて、各地において山や林の開墾が行なわれている。徳氏の妹と見られる「竹野」も妹ヶ谷を開拓し耕地を拡大している。羽沢村の市川五郎兵衛が、この時期に広大な新田を開発した事跡は殊に知られているところである。
しかして、この重氏の四男、重高の弟・徳氏が天引に移り住んだ事が考えられるのである。この仮説であれば小幡町の堀口家のいう天引の小柏氏とは関係ないとの言にも合致する。同じく天引の小柏姓の旧家で言う堀口氏とは関係ないようだとの言にも合致する事となる。
口碑・伝承では主として定重の三兄弟の子孫と言われているが、定重は若くして戦死した為か、弟の定政と混同されている例が見受けられる。ここも混同されて伝わっていたとすれば、定重の名前は定政に置きかえられる事になる。
定政の三兄弟は重氏・貞景・貞實であり、徳氏は嫡男重氏の四男でありまさに口碑・伝承に合致することから、これも傍証の一角を形成する事になる。
住宅地図を見るとはっきりと分るが、天引川に沿った字名「久保」には小柏姓の家ばかりが11軒も集中していて、これはすっぽり長方形の線で囲む事が出来る。
これだけ隣接した一箇所に密集している事から、やはり四男が分家し来て此処に一家を構えたという事に留まらず、小柏氏の有力者が何人か移り住んで来たと考えるほうがすんなりと受け入れられる。
徳氏の弟の吉次も同じ頃にここに居を構えて、医師の仕事に専念したのではなかったか。医師ならば何処にあっても収入が得られると思うが、上日野よりも小幡・吉井に向かって開けていて、平坦地の天引の方がより良い立地である。
東から西へと藤岡から吉井・富岡を通り、下仁田経由で佐久市に抜けているのが国道254号線、通称信州街道(姫街道)である。
この信州街道を「上州新屋」の駅前、金井の交差点から南へ入る道が中世の「ちちぶ道」である。この道は天引川に沿って天引村の倉内を通り、同村の久保を通り向陽寺の前辺りを通って上鳥屋を経由して亀穴峠に至る。
亀穴峠からは上日野の矢掛に降り、小柏村を経由して投石峠に至る。投げ石峠からは神流町・万場町に降り秩父市に至る。この「ちちぶ道」を通って上州と武州の交流が盛んに行なわれていた。(「火の谷」)
小柏吉次の別名は権右衛門であり、政美家に伝わっている移住して来た「右近」の名前に少し似ている。
こじつけになるかもしれないが、「権右・ゴンウ」の音と「右近・ウコン」の音は似ているので、いつの間にか上下の音がひっくり返った可能性はないだろうか。
吉井町は信州街道に沿った長い町で江戸時代には吉井藩があった。当時の時代背景としては、幕府は財政難から享保の改革を行なっており、目を覆うような不景気な世の中であったと思われる。
してみると庶民は、近隣に新たな耕地を切り開く必要に迫られ、近場に移り住んで行ったのであろう。
父重氏の出生年と兄弟の出生年から、徳氏の出生年を推定すれば1642年となり、24歳の時に移住して来たと仮定すると1666年となる。
鶴吉家の古い先祖の推定出生年は先に述べたように、1663年となったのでその出生年の差は21年である。徳氏或いは徳氏の子が鶴吉家の284年前に没した先祖であると、やや強引に繋げるといった事も可能な範囲に入る。
ここにおいて、この徳氏が天引小柏氏の始祖となった事が充分に考えられる事となった。小柏徳氏の別名は傳右衛門である。鶴吉家の世襲名勘右衛門とは一字違いである。
また鶴吉家の一番古い位牌に書かれている戒名は「頓證了覚大徳」(1723没)である。「徳」の字が共通しているのは偶然だろうか。普通は下の二字は信士・居士などをつけるがそれがない。
お寺で付けたものではない可能性もある。親族・遺族が生前の俗名から「徳」の字を採って付けた可能性も僅かながらあると思われる。仏教では戒名を付けない浄土真宗を除いて、信士・居士・清士・禅定門などを位号として、下の二字に付ける。
この戒名の意味するところを向陽寺にお尋ねした。戒名はつける人によって様々なので判らないが、名前の可能性もありお寺で付けたものではない可能性もあるとの事だった。
「大徳」の意味として考えられるのは、文字通り徳が篤かった・大きかったととれる。そして昔は戒名もなく葬式もなかったという。
更に1781年没の当主の戒名は「徳翁忍光」であり、ここにも「徳」の文字が使われている。位号のないところも共通している。この場合の「徳」は名前のように見える。
藤林伸治の現地調査によれば、上日野小柏村では伝統的に戒名に院号(○○院)をつけず、権大僧都・権僧都と刻印して葬ったという。これは特に栗崎一覚の栗崎神道による神道葬祭のようだ。
この点も小柏村と天引では似通っている。おそらく天引に移住してきた当初の葬祭は、寺に依存していなかったのではないか。
系図を作って考証を重ねた結果、徳翁忍光は76歳で没したと推定される。すると当時でも翁と呼ばれるのにふさわしい年齢である。戒名は「徳○翁は忍耐強く周囲からは一際光って(輝いて)いた人だった」と解釈できる。
年代は違うが、1880年没の先祖の戒名は「徳聲常圓」であり、また「徳」の字が用いられている。
「頓證了覚大徳」の次代の戒名は「前山覺庭信士」でその次代が「長山清閑信士」その次代が「理山玄性信士」である。そして二代はさんで「権大僧都喜山秀悦信士」の戒名の位牌がある。
向陽寺に過去帳も存在している。「山」の付いた戒名が四代に亘ってつけられていて、伝世・世襲的なものが感じられる。
鶴吉家では名前が判明している近世から、今に至るまで僅かの例外を除いて一文字が世襲されている。

常吉(高祖父)が分家・隠居したという屋敷跡の門と倉。
近年まで敷地の周囲に塀が廻らしてあった。

ゼンリン 住宅地図
位牌と過去帳から、年齢などの整合性を勘案して作った系図の概要を示したのが下記である。1831年に64歳で亡くなった事が明らかとなっている、勘右衛門の年次を絶対年代・基準値として出生年・没年齢を算出した。
78才? 頓證了覚大徳 1723ー1645生?
![]() (小太郎父)
(小太郎父)
83? 前山覺庭 1749―1666?
![]()
![]()
![]()
91? 長山清閑 1778―1687?
![]() (太郎兵衛父)
(太郎兵衛父)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 73? 理山玄性 1780―1707? 76? 徳翁忍光 1781―1705?
73? 理山玄性 1780―1707? 76? 徳翁忍光 1781―1705?
![]() (太郎兵衛) (八三郎父)
(太郎兵衛) (八三郎父)
66? 権大僧都月潤浄心 1791―1725?
![]() (勘右衛門父)
(勘右衛門父)
57? 権大僧都喜山秀悦 1804-1747?
![]() (勇蔵養父)
(勇蔵養父)
64 勘右衛門 実参徹温 1831-1767
以下 略
先に「頓證了覚大徳」の没年齢を、ごく大雑把に60歳くらいと仮定して論じてきたが、系譜前後の繋がりなどを詳細にかつ時間をかけて慎重に検討して、系図上では78歳と推定しここに訂正する。
20歳で次代の嫡子を輩出しているところや、91歳の長寿年齢などが現れ少し奇異に感じられる部分がある様にも見えるが、何人か養子が含まれていると推察されるので、その部分は年代が縮小しその他の部分が広がるので、さほどの無理は生じないかと考察する。
現に私の祖父とその祖父は養子である。祖父と曽祖父との年齢差は僅か14歳である。直系ばかりで数百年も家系を繋げるのは無理というものである。徳川家を例にとって見ればよく分る。
鶴吉家は同じ家との間で婚姻を繰り返し、嫁を出したり嫁を貰ったり養子を貰ったりしている。これは家と田畑を守り繋ぐ為に何所の家でも行なわれていた事なのだろう。
同家には曽祖父を含まずその前代までの老若男女の名前が30人も伝えられている。高祖父(祖父の祖父)は養子であったが、妻に先立たれた為に後妻を迎えて更に3人の子をなした。
そして血の繫がる子に家督を返す為か、自分は分家して居を近くに移している。その土地は「久保」の外れにあるが、平坦な角地で元は畑であったのか広い土地である。
残してきた本家は自分の二男に継がせて、他の家族は連れて行ったようだ。分家した土地は後に三男が家督相続し、長男は高祖父の養父(本人から見れば祖父)の家督を相続している。
これにより高祖父の子供のうち、男・三兄弟の三家が出来た事になるが、その子細は子孫でも良く分らない複雑なものになっている。
近世にあってもこんな状況であり、先の30人を完璧に縦横の系図に組み込むのは至難の仕儀となってくる。過去帳も、住職が変った時や虫食い・水濡れなどによって書き換えられ、近世だけでも明らかに間違いと思われる物も存在するのである。
先に鶴吉家の始祖は、徳氏の子供かも知れないと仮定して論を進めてきたが、もしこの系図が本筋において、間違いがないとすれば同家の判明している、一番古い位牌の「頓證了覚大徳」は、小柏徳氏本人の物という可能性が出てきた事になる。
先に推定した徳氏の出生年次は1642年であり、「頓證了覚大徳」の推定出生年次が1645年であり、その差は僅か3年しか認められないからである。
法名の「頓證」は経巻にも出ている仏教用語で、仏道の真理を悟ったという意であり、ここでは接頭語として使われていると思われる。仏道に深く帰依して法体の在家僧となり、不動寺の開基となった重高・吉重の弟・徳氏にはふさわしい冠詞のようにも見える。
したがって「頓證」の下の「了覚大徳」の中に生前の名前が一字含まれている可能性がある。「了」を名前と仮定してみると、徳の大きな了さんの意味となるが、この場合「覚」の字がいかにも唐突に感じられ、文章の体裁が奇異なものになってしまう。
「覚」を名前と考えると、今度は「了」の字が唐突に出てきた印象を受け、やはり文章の体裁が悪くなる。すると「大徳」の二字の内に名前が含まれているとみる事ができる。
「徳」を名前とすると、その意味するところは「読んだ事・学んだ事を覚えてすぐに了(さとる)徳氏は大人のような人だった(大きな仕事を成し遂げた)」との理解が成り立つ。
「頓證了覚大徳」の下に居士をつけて考えると分り易くなるかもしれない。あくまでも可能性の一つであるが、徳氏が上日野から移住して来て久保一帯を開拓したのであれば、「大徳」の称号は真に似つかわしいものに思えてくる。
徳氏の兄弟は13人もいて、その妹と見られる「竹野」は妹ヶ谷を開拓しその名を今に残している。
小柏氏の二男・三男・四男はその殆どが養子に出ている。その養家は掘口・友松・山田・飯塚・須藤・松下・市川家である。養子になった記録がない二男・三男は徳氏・吉次の他には見当たらない。
両人の長兄・重高と次ゝ兄・吉重の墓碑は上日野小柏家の墓所にある。ところが系図上の記録で、上日野小柏に戻ったとしている徳氏・吉次両人の墓碑は見当たらない。この事は後に両人が何処かへ分家・移住した事を示している。
天引に両人の墓碑が見つかれば、一番はっきりするのだが今のところ確認できていない。両人の法名が不明な上に未踏査の所も多く、300年ほどの時間が経っている事が大きな障害となっている。
鶴吉家は小柏一族が、11軒ほど密集している一角のほぼ中心になる位置に居住している。この辺を中心として隣地に、分家が建てられて広がっていったとみる事が出来る。(或いは隣接する旧家からかその両方からか。)
現状を見ると、中心地にある二つの旧家からそれぞれ西と東に広がったとの推測が成り立つ。
現に西隣の小柏家は近世に鶴吉家から分家した家であり、鶴吉家の墓地に隣接している。分家の西側の畑を挟んだ数十m先は、同家の高祖父が分家した広い角地であり、久保の集落の西端になっている。
もしも心証を披瀝する事が許されるならば、この両家の始祖は徳氏と吉次になる可能性を秘めている。鶴吉家の始祖と思われる人の没年次が1723年であり、政美家の始祖と思しき人の没年次が1746年である。
この間に23年の開きがあるものの近接している。何歳で亡くなったのかにもよるがほぼ同年代の人であった可能性が高い。兄弟であったとしても、状況的にさほどの違和感は生じない。
結論めいたものが思わぬところへ導かれた。これは決して意図したものではなく、諸資料の検討、現地調査・取材、年代の考証などを総合して書き進むうちに自然と帰着したものである。
先述したように当初、私は天引小柏氏は堀口氏経由で派生したものと漠然と考えていたがこれは間違っていた。
「甘楽町史」を紐解くと、「鉄砲とピストル所持者(明治十八年 白倉村連合戸長役場調)」という項目があり、天引の欄に私の曽祖父・嘉市とその兄の定吉の名前が見える。他に小柏姓の二名の名前が記載され、天引村全部で30人の名前が記載されている。
天引は明治10年頃は家数が208軒あり、人口は1,012人であった。(「群馬県の地名」郡村史)先に示した資料よりも人口が多くなっている。この中に小字名・久保がある。小柏姓の家はこの久保の中の狭いエリアに密集していて、その中には他の姓の家は全くないのである。
天引川に沿って、長方形に展開している小柏姓の集落の右隅に、一軒だけ別姓の家があるが小柏姓の家と接合していて、いずれ縁戚に繫がる家と推測できる。
昔は洗濯もしたという小さい川、天引川を挟んだ対岸にも小柏姓の家が一軒ある。
この他、少し離れた所に天引の小柏姓のうちでも、古いほうと見られている小柏家が一軒ある。また向陽寺の近くに小柏姓の家が2軒ほどあるが、周囲に畑があり畑の近くに分家して出て行ったのではないかと思われる。
天引の小柏家はこの他には1~2軒あるだけである。久保(小柏)集落の前を流れる天引川を挟んで、向かい側に位置しているのが向陽寺である。

久保の集落
平成13年出版の「郷土氏姓録」(日本姓氏出版)は、分厚い立派な装丁の本である。同本には鶴吉家は次のように掲載されている。
[家暦] 当邑草創小柏一門の旧家で家紋は「丸に三つ柏」を用いられる。遠祖を辿り現存する位牌を精査するのに、享保八年八月三日歿(1723年)――頓證了覚大徳が判明、累代に亙り護持されている。
菩提寺は当地の向陽寺である。*小柏姓出自~~別項参照。――小柏家の中興系譜――勘右衛門氏(世襲)勘右衛門氏は天保二年64歳歿。――
以下は略すが現在に至るまで連綿とその系譜と略歴が記されている。冒頭には家紋の写真が掲示されている。先代の当主は戒名に俗名の1字が用いられている。
熊野堂の磨崖仏
この地域が、江戸時代に発展していたであろう事を喚起させる物に摩崖仏がある。この江戸初期の製作と推定されている摩崖仏は、小柏集落のある「久保」の少し先の熊野堂にある。
天引川の最上流部にあたる。甘楽町指定の重要文化財である。文化財係によると、凝灰岩に薬師如来一体が彫られていて、舟形光背を持っている。眉間の百毫から発する頭光と身体から発する身光がある。
この二つを合わせたものを挙身光といい、この挙身光を光背に表現したものが舟形光背であるとしている。銘はなく像は高さ55cm、幅44cmで浮き彫りしてある。
この摩崖仏を囲んで堂宇があり、摩崖仏を本尊として春と秋に祭礼が行なわれていたとしている。
また熊野社があったが、明治41年に諏訪社に合祀されたという。地元では「おくまさま」(熊野様)と呼ばれている。この信仰は今も引き継がれているようだ。この他、隣村の白倉にも平石摩崖仏がある。
熊野堂の摩崖仏がある所からは、400mほどしか離れていない場所であり、天引川とほぼ平行して流れている白倉川の近くである。
堂の入の石仏 
天引の笠塔婆
鮎川の奥に位置する上日野小柏氏には800年以上の歴史がある他、近年立てられた碑文に同地では縄文時代からの歴史があると記されている。
街道の通る吉井町や小幡から平坦な道を通って、すぐの所にある天引は更に古い歴史があると思われる。
「群馬県の地名」によれば、中宿に正安四年(1302年)銘の、板碑一基と笠塔婆三基があり、倉内に笠塔婆一基がある。笠をかぶっている物は非常に珍しい。
信州街道から天引川と平行に走る道を入って行くと、天引川が細くなる辺りに県指定の重要文化財となっている笠塔婆三基と板碑一基がある。
板碑の上に、大きい蓋のような笠のような平らな石を載せている事から、笠塔婆と呼ばれている。
甘楽町文化財係によれば、その材質は地元で産出される天引石(砂岩)である。
笠塔婆は群馬県全体でも20基程しかなく、まとまって3基もあるのは珍しいとしている。碑の高さはおよそ1.2mほどである。同係によると蓮の花や阿弥陀如来、観音菩薩の種子が刻まれている。
正安四年(1302)の銘があり、近郷の豪族によって建てられたとしている。
またこの場所から西方に約1.5km離れた白倉川の近くにも笠塔婆一基がある。
同係によれば、全長1.74mで角柱状であり、デザインは先の笠塔婆とほぼ同じであるとしている。主尊の阿弥陀如来が蓮の花をかたどった中に配され、脇侍は向かって右が観音菩薩、左が勢至菩薩である。
右側面には不動明王、左側面には愛染明王の種子が薬研彫りで刻まれている。鎌倉時代の仏教文化を知る上で貴重な物であるとしている。鎌倉時代は仏教文化の花が開いた時代であったので、同時代の信仰を反映させているのだろう。
正安元年(1299)の銘があるのでこちらの方が先述したものより3年程古いものとなる。
笠塔婆三基と板碑一基

白倉川近くの笠塔婆 (一基)

天引黒渕古墳群の塚
甘楽町指定史跡の古墳である。堂の入川に沿った東向き斜面の黒沢家の、畑の中に立地している。盛った土・封土(ホウド)が現存しておらず、当地産出の天引石で構築された石室が露呈している。
形態は円墳と推定されている。埋葬施設は、南に開口する横穴式石室(石を積んで石室を造り、羨道から奥の玄室に通じ、ここに遺骸を安置する)で、平面形は両袖型である。
石室の全長は495cmを測る。羨道入口部の羨門は、向かって右側が、幅50cm、高さ85cm、奥行50cm。左側は幅30cm、高さ85cm、奥行45cmで、鳥居状に長さ160cm、高さ55cm、奥行85cmの一枚岩がのっている。この構築技術はすばらしい。
羨道は、長さ285cm、高さ100cm、幅75~90cmを測る。
玄室は、長さ210cm、高さ175~180cm、幅75~90cmを測り、奥壁、左右壁とも一枚岩で構築されている。
天井石は、長さ370cm、幅約160cm、厚さ70cmの一枚岩である。
直刀13本が出土したとのことであるが、その所在場所は不明である。
数基の古墳より構成される古墳群のうちの1基であり、年代は古墳時代後期の7世紀後半頃と推定されている。(甘楽町H・Pより)


古墳のお部屋H・Pより
亀穴峠・鳥屋峠は昔の街道
向陽寺の東方、旭岳の北方の峰には天引城跡がある。郷山城、八束城と一線に結ばれる山城である。標高は約450mとされる。この天引城は「群馬県の地名」によれば、永禄六年の箕輪城攻めに際し、落城した小城としての記載があるという。(箕輪軍記)
箕輪城は群馬郡箕郷町にある戦国時代の雄・長野業政の居城である。私の母は上日野と山を隔てて、背中合わせの位置にある秋畑の出身であり、菩提寺は近くにある宝積寺だった。物心がつくかつかない頃と思うが、家で母が小柏伝説の話をしているのを一~二度聞いた記憶がある。
母は上日野の隣、秋畑村の出身であるから子供の頃から耳に入って来ていたのだろう。母の話は近所の主婦相手の茶飲み話しででもあったろう。
小柏様のお通りだと言うと、ヘビもムカデも道をあけた。という大意であった。その時は何という事もなく、聞き流していただけであった。
およその意味は判ったがその話のいわれや、どんな状況でその話が生まれたのかなどは全く判りもしなかったし聞きもしなかった。この他に、やはりお菊伝説も同様にして耳にした事だったが、幼かったためか特にこの二つを結びつけて考えた事はなかったようだ。
小柏系図の冒頭に、家紋は揚羽蝶或いは丸の内に釘貫、丸の内三ッ柏葉とあるが、私の家でもこの丸の内に三ッ柏紋を使っている。
三波川小柏氏は、小柏氏からの男子の分家(天引・箕輪)が丸に三ッ柏の家紋・女子の分家(三波川)が丸に釘抜き紋、本家が平家の丸に向(対)い蝶、場合によって丸に釘抜き紋、又は裏紋で丸に三つ柏と推定している。
「甘楽町の地名」によれば天引の久保は窪であり、谷や川の中の平らな所で窪の美称「久保」の表記になったのでは…...。10戸で構成さるとある。
久保の位置するエリアは、平坦である。周囲には畑などがあり里山も近くに見える。甘楽町の方へ少し行くと水田も広がっている。
このあたりの里の風景は、おそらく300年後となっても、そんなには変わらないのではと思わせる。これ以上過疎化が進む様子もなく、周囲の畑や山などを維持、耕作し町場へ勤めに出るなどして家と土地を護っていくのだろう。
その時々により薄くなり厚くなり,脈々と流れる系譜・血筋の承継は現代まで続いている。現代では戦国時代のような英雄はいない、従って英雄譚もない。多くの歴史は庶民の中に埋もれている。
庶民こそが歴史を作り、歴史を積み重ねていく。庶民が日頃営んでいる生活が伝統を作り、文化を生み出していく。庶民が創り出していく世相こそが歴史そのものなのである。
そして庶民の中から一握りの豪傑が生まれていく。百年という時間は、とてつもなく長いようにも思えるが、ある意味で別の角度から見ればきっと僅かな間の出来事なのだろう。
二百年、三百年も前の話が今に伝わっているのだから。二百年、三百年も昔の出来事が口碑・伝承で今に伝えられ、それは多少歪んでいる事もあるが、事実そのものの事も多く、文書や石碑、奉納物、埋蔵物などにより裏づけが取れる。
上日野小柏氏と天引の小柏氏との、繋がりを示す明確な物証はいまだ見つかっていない、今後の研究・探索を期待したい。法政大学大原社会問題研究所所蔵の、明治十七年調べの「上野国多胡郡上日野村戸籍控」を見ると、当時天引から上日野に二人の嫁が来ている事がわかる。
この事は更に古くから上日野と天引に交流があった事を窺わせる。昔は同じ家から何度も嫁を貰ったり、嫁にやったり養子を貰ったりしていたのである。鶴吉家でも曽木村・君川村などの家との間で同様の事が繰り返されている。
「群馬の峠」を見ると次のような事が載っている
鳥屋峠 標高680m 藤岡市上日野矢掛~甘楽町天引の上鳥屋を結ぶ。本峠は新屋峠ともいう。小字名調書の北甘楽郡天引村に「上鳥谷北(岳ノ谷)」という小字名がある。本峠、或いは亀穴峠に関わるかとみられる。
亀穴峠 691m 藤岡市上日野矢掛~甘楽町天引、本峠は元禄国絵図にある「杉峠」にあたるとみられる。同図には数本の杉が描かれている。
「藤岡市史」の民族編には、「明治大正の頃は、上日野で病人が重くなると亀穴峠などの峠を越えて、小幡の医者を迎えに馬を引いて行き、医者を馬に乗せてきた。村の人は提灯を持って迎えに行った。」
「奈良山をはじめ上日野の人は、峠を越えて富岡の銀行へもよく行った。」という記事がある。
「ちちぶ道」を来て、久保で右折すると「堂の入り」を経由して亀穴峠に至る。この道沿いには道祖神が多く、通行人が多かった事が窺える。明治期までよく利用された「ちちぶ道」の支道・旧道と思われるが、現在の地図を見る限り、こちらの方が本道のように見える。尚「ちちぶ道」の標識・碑は今も吉井町に残っている。
久保の石仏 
「甘楽町地名考」にも、日野と富岡・吉井を結ぶ主要な峠道であったという内容が記されている。当時の人は現代人と違って、山道をさして気に掛けなかったのか、今ある環境を受忍していたものか。回り道をして良い道を行くよりも、最短距離の山道をいつも使ったという事になる。
この記事を見ると上日野と天引村の間には、思っていたよりも活発な交流があった様子が浮び上がってくる。
両村は山一つ隔てただけの隣村に位置しており、尚且つ珍しい「小柏」という苗字の集落があるという事は、上日野からの移住者があったという伝承にまず間違いないとみて支障はない。
アメリカの青年が、自分の先祖はアフリカから来たとの、祖母の話を信じていなかったが、後に何代も前に遡る先祖の「キンタクンテ」が、奴隷としてアフリカで拘束され、アメリカまで連れて来られた事が判明した。
アフリカの現地を訪ねると、現地にもほぼ同様の伝承が伝わっていた。
このように伝承には何らかの火種・真実が含まれている事が多い。厄介な事に伝承には往々にして、尾ひれがついてしまい誇大に人から人に伝わる習性がある。
非日常の、特に珍しい出来事が語り継がれ易いからであろう。誇張されているから、信じ難いと言っていては、その中にある、小さな核となっている真実に気づかないままとなってしまう。
自分で誇張された部分を探し出して、それを削ぎ落としていけば良い。
この他、小柏朝光は高崎市商工会議所の第9代の会頭を務められ、昭和21年10月から27年10月までその職にあった。同氏は甘楽郡新屋村の出身で高崎において製紙会社を経営されていた。
新屋村は天引に隣接している隣村である。いずれ天引小柏氏の一党ではないかと思われる。
その他の小柏氏
平成14年頃の群馬県の電話帳には、藤岡市を中心に小柏姓が128軒載っていたというが、平成18年の現在では電話帳に掲載する家もかなり少なくなっている。
日野地区に27軒、三波川地区で23軒、天引に22軒あり、この三地区に集中しているように見えるほか、三地区で均等・拮抗しているかのように見える。
日野を流れる鮎川を中心として、山を南に越えれば三波川、北に越えれば天引であるからやはり、上日野の本家から分家などの形で双方に派生していったとみる事が出来る。
本庄市と合併前の児玉町町長は小柏儀一である。藤林伸治によれば、児玉町の小柏善司の先祖は長野出身だが、上日野の小柏氏に繫がっているという。善司の父親は元海軍大佐としている。
前の鬼石町の助役は小柏姓の人である。
万場町の前助役の名前に小柏姓の人が見える。
鯖江藩の小柏氏
「姓氏家系辞典」に鯖江藩の家臣に「小柏栄」の名前が見られる。とある。鯖江藩は遠隔地ではあるが、同藩の本貫地は新潟であり藩主は一時群馬に領地を得ており、その後新潟に引き上げ、更に福井へと移ったものである。
上野国高崎藩5万石を領していた譜代の間部氏がそれである。したがって群馬に居た折に小柏の一族が仕えたものであろう。
中山道坂本宿の小柏
松井田町坂本に「小柏」という字名がある。どの地図にも記載されている。一度訪れてみたが、何の変哲もない山麓の村里という印象である。碓氷峠へ向かう碓氷バイバスの脇道沿いに展開している。
一見したところ人家は殆どないように思える。地元の人に話を聞きたかったが、歩いている人は全く見かけなかった。地図を見ると諏訪神社と入山神社がある事になっている。
諏訪神社は上日野にもあり、三波川妹ヶ谷(三波川小柏氏)と天引にもあり、この点は小柏氏との共通項となり関わりが更に強まる。
松井田町史はこの「小柏」については黙して何も語っていない。
日本地名大辞典によると「坂本」は上毛野氏であり、坂本君であるとしている。大変に由緒ある有力な豪族である。「小柏」という地名・名前はありそうにも思えるが滅多にない名前である。
偶然に付いたり、自然発生的に付いた地名とは考え難い。やはり上日野の小柏氏の系統で、山稼ぎを生業とする衆人が移り住んで来たと考えるのが一番自然であろうか。
良木を求め、獲物を求め、椎茸の栽培地を求めて何度か訪れる内に何時しか住みついたのではなかろうか。
そして、この地を本貫地の地名にちなんで「小柏」と呼び次第に地名として定着した。その時期を推測するに、高政が武田信玄より佐久郡田ノ口を領地として賜った頃と考える事が出来る。武田氏が西毛一帯・信州を抑えていた時代は、高政も領地の経営に専念していたと思われる。
佐久郡と松井田町坂本は、妙義山を間に挟んではいるが遠い距離ではない。小幡氏の支城のあった西野牧を経由して、南野牧を通れば佐久の地へ入って行く。小柏氏は下仁田の市川氏とかなり濃い縁戚関係にあり、この辺は立ち回り先の山であったともいえよう。
更に高政から二代目(孫)に重氏がある。重氏の五女は松井田の松本家に嫁いでいる。この五女の二男・三男が分家して小柏姓を名乗った可能性も充分ある。或いはこの五女自身が離縁して小柏姓に戻った事も考えられる。
こうした例は同氏の中で他にも見る事が出来る。現在、松井田町は安中市であるが、隣接している原市(安中市)に3軒、板鼻に1軒小柏姓の家が電話帳に見える。何らかの関連があるのではなかろうか。
第八章 小柏舘の発掘調査
埋蔵文化財の調査
藤岡市教育委員会により、上日野の小柏家館跡の発掘調査が行なわれた。第一回目は平成10年12月である。「県営ふるさと水と土ふれあい事業」の一環として、上日野に農道が建設される事になり、その農道が小柏舘の敷地を通る事となったので、埋蔵文化財の調査として実施されたのである。
建設予定地には、平維盛の一子太郎維基を始祖とする小柏氏が中世より居住したと伝えられる小柏舘跡が存在し、文化財課では小柏舘跡の現状保存措置及び記録保存となった場合の手順を説明した。(文化財課)
7月14日、文化財課は現地踏査を行い、遺蹟地の現状と農道の建設範囲を確認し、該当地に埋蔵文化財が存在することがほぼ確定的となった。土中の遺構を確認するため試掘の必要がると判断した。
これにより12月8日から12月17日まで試掘調査を行なった。その結果、礎石を伴う掘立て柱建物跡、溝状遺構、石列が検出され二面の遺構面を確認した。また出土物として陶磁器・古銭が検出された。
以上から小柏舘の存在が再確認され、開発にあたり保存の措置が必要になる事が判断された。高崎土地改良事務所に保存を望んだが、他に農道建設の適地がないことから、やむなく記録保存を目的とした発掘調査を行なう事になった。
調査範囲は小柏舘跡を中心として、910㎡で実施する事になり、期間は平成11年9月10日~平成12年2月29日までとなった。(埋蔵文化財発掘調査報告書)
その後延長され実際には3月10日迄調査が行われた。
調査を行なった後の石垣は破壊せざるを得なかったが、巨石は人力で除去できなかったため、重機を使ったという。では築造時の石を積む作業は人力で行なったのではなかったのかとの疑問が残る。
遺蹟全体の空撮はラジコンヘリを使った。
対象地は明治期以降、日野第五尋常小学校が建設されており、遺構の保存状態の悪化が懸念されたが、石垣などの保存状態は比較的良好であった。同遺蹟は鮎川左岸の山腹南側の標高370mのところにある。
周辺は耕地拡大に伴って新たな居住域が設けられ、しだいに拡大していった。箕輪においては、平安時代の集落が確認されている。鮎川流域では国分寺瓦窯跡など、幾つもの窯跡がある他,炉遺蹟・製鉄炉や製鉄工房跡もあり、奈良・平安時代の生産力・技術を持っていた事がうかがわれる。
中世に入ると戦時に備える城館は砦が多くなり、平井には関東管領上杉氏の平井城、金山城、飛石の砦、東平井の砦が築かれた。高山には日野七党の一つ高山氏の高山舘、東日野金井城が所在する。
日野地域では小柏氏の居館である本遺蹟の他、後藤屋敷、小柴屋敷、黒澤屋敷、柴崎屋敷が鮎川沿いにある。これ等の居館・城館は律令制崩壊後の地域支配の拠点としての役割を担っていたと考えられる。(埋蔵文化財発掘調査報告書)
日野地域では他に山地尾根上などに、駒留城、子王山城、三ッ山城、清水山城などの城郭が築かれ、自然の地形を最大限に利用している。
第一回めの発掘調査報告書は「まとめ」として次のように報告している。
小柏舘跡の存在については、近年まで小柏氏が居住していた事もあり、古くから確認されていた。まず最初に舘の所有者である小柏氏についての概略を記すと、小柏氏は平清盛の嫡男である重盛の子、維盛が妾腹に生ませた維基を始祖としている。
維基は源平の大乱の後、鎌倉幕府を憚って上野国小柏に隠れ、重盛から伝わる小松姓を小柏姓に変えたとされている。
永享の乱に際し、小柏高家が上杉憲実に仕えて戦功を挙げるなど、上杉氏との関係を深めたが、天文二十一年(1552)に上杉憲政が越後に走った後は、甲斐の武田氏に降っていたが小幡氏と婚姻関係を結んで武田氏配下となった。
また小柏氏は上日野名無村・奈良山の後藤氏と婚姻関係を結んでこれを吸収しており、日野地域における積極的な勢力の拡大を謀っていた。
近世に至ると小柏氏は大家と呼ばれ、農業経営や村落共同体の中心的な役割を果たし、「家抱」と呼ばれる隷属農民を従えるようになっていた。
今回の発掘調査では、小柏舘跡の南部分を構成していると考えられる石垣の一部を検出した。調査範囲が狭い範囲に限定されているため、舘跡の全体像を掴む事は不可能であり、特に舘の出入り口を特定する事は困難であった。
舘跡の構造全体を把握できないために「矢掛け」などの個々の石垣についてもその機能を明確に解釈する事が出来なかった。
個々の石垣は石材の規格にやや違いが認められるものの、基本的には緑色片岩を使用した乱石乱積の石垣である。舘跡が築造されている平場は、南側に緩やかに傾斜しているが、整地を行なう事で傾斜を極力なくし、石垣を築造している。こうした自然地形を克服し、背後の山々から産出される石材を利用した石垣は、現在も日野地域の各所で散見される。
石材の加工技術に若干の差異は認められるものの、基本的には石垣の築造技術に小柏舘跡の石垣と現在認められる石垣との間に大きな差はない。また調査範囲内は、近代以後における攪乱の影響を著しく受けており、遺構の保存状態は余りよくなかった。
したがって、石垣の築造技術や土層の断面から築造年代を特定する事は困難であった。
今回の調査における焦点の一つは、小柏舘跡の築造年代を確認する事にある。舘跡の西端に位置する小柏家墓地内には、貞治六年(1367)銘、応永二十七年(1420)銘の宝篋印塔が存在する事、また山崎一氏が指摘しているように、墓地と舘跡の間に堀切状の遺構が認められる事から、小柏舘の起源が中世に遡ると想定された。
しかし、今回の調査では検出された石垣の年代は、出土物から少なくとも近世の所産である事が明らかとなった。
内耳鍋や焙烙等、中世の所産である遺物は少なからず出土してはいるものの、石垣の築造過程において近世陶磁器片と共に混入したとみられ、石垣の年代を直接反映する資料ではないと判断した。
勿論今回の調査結果をもって中世舘跡の存在を完全否定する事はできない。今後の舘跡とされる中央部分についての発掘調査の結果を待って結論付けることにしたい。
この他、出土物として炭窯跡、染付椀、内耳鍋、石垣を記し各写真を付している。この時、発掘された石垣は現在では道路の下になってしまったようだ。
空撮写真 小柏舘跡 全景 (藤岡市史)

二回目の文化財発掘調査
第二回の埋蔵文化財発掘調査は緊急発掘調査として、平成13年2月1日から行なわれ、整理作業が終わったのは10月10日であった。対象面積は300㎡である。
その報告書から関係のあるところを抜粋・要約してみる。
第Ⅲ章地理的環境と歴史的環境
本遺蹟およびその周辺は桓武平氏維盛流を称する小柏氏の城館(屋敷)が、中世~近世、近代にわたり営まれた地である。
小柏舘を含む鮎川上流域には、中世~近世にかけて「日野七騎」(小柏・黒沢・後藤・小柴・小此木・柴崎・高山)の城館(屋敷)が点在し、それらの多くは小田原北条氏没落後、領主の帰農に伴い、中世末期の城館を近世豪農屋敷として転用されたものである。
小柏舘は通称「日向」付近に所在し、三方を谷に囲まれ、北側背後に山を擁し、南斜面には腰曲輪をめぐらす。
舘南西(裏鬼門)「嶽ノ本」~「嶽ノ鼻」には、小柏氏累代墓所および掘切が残り、舘の東西外周付近には科人断罪の伝承が残る。また菩提寺の小柏山養命寺は幾度かの移転伝承を持つ。
小柏氏は鎌倉~室町期には鹿島、鼠喰城などに拠点を持ち、建久年間に始祖・小柏平太郎維基による鹿島神社の建立、貞治年間に小柏庄司重家の鼠喰城の築城伝説を残している。
嶽ノ本の小柏氏累代墓所に残存する貞治六年、応永二十七年銘宝篋印塔は小柏地区の金石文では初見のもので、重家により建立されたとの伝承がある。
室町~戦国期には山内上杉氏、武田氏、小田原北条氏に仕え、盛衰を繰り返しつつ、周辺の小幡氏(国峰城)市川氏、(南牧砥沢)飯塚氏(三波川妹ヶ谷)後藤氏(七村城・七村後藤屋敷)、小柴氏(岡本・小柴屋敷)などと婚姻関係を結び、小柏峠・焙烙峠・温石峠を通る秩父~小柏~小幡~南牧の甲斐・武蔵・信濃交易ルートをおさえ、日野谷周辺の権益拡大を図ったとされる。
高政の時、武田氏に従い、信濃国佐久田ノ口に移り、定政の時、小田原北条氏没落に伴って小柏の地に帰農したといわれる。
その後、重高・吉重・富重が当主であった延宝~享保期には、徳川綱吉の甲斐武田旧臣優遇政策の影響を受けてか、大地主として経済的に成長し、黒滝山不動寺(南牧)及び菩提寺の小柏山養命寺の建立・再興に寄与したとされる。
第Ⅴ章 確認された遺構と遺物の章では、西側の石組み遺構付近で中世末頃の内耳土鍋・羽口が出土した。
同嶽ノ本・嶽ノ鼻にある堀切には埋蔵金の伝承があったとしている。この為下部は破壊されていたという。
誰かが宝探しをしたものらしい。また近世において小柏屋敷に火災があったらしく、焼土層があったという。この焼土層を切って江戸末期から明治期の石垣が東西に走っていた。この焼土層からは焼けた肥前陶磁器・桟瓦が出土した。南東側の畑には小柏屋敷の居住者伝承があった。
西側隣接地には、寛政六年銘の緑泥片岩製庚申供養塔が所在する。出土した軒丸瓦には小柏氏の家紋である「丸ノ内釘貫紋」があしらわれていた。版築部分には中世の志野焼皿・中国渡来銭が混入していた。
小柏氏在居時、科人断罪伝承があった「インゴウバタケ(インドウバタケ)の南側では出土物はなかった。東側には近世の廃寺伝承が残っている。
まとめとして、(A区)東側は小柏墳墓と近く、中世~近世の要素を多分に含むが性格は不明である。(今回調査の対象地域が狭いため)中央部は近世小柏屋敷南端部に含まれ、入り口状遺構・暗渠遺構が検出された。
西側は焼土層が厚く堆積している。小柏屋敷火災時の物であろう焼土瓦礫が投棄されていた。南側は石垣を中心とした複合遺蹟と考えられる。対象地域が300㎡と狭いためであろう、小柏舘(屋敷)跡の広がりを示す遺構は本調査では確認できなかったとしている。
また南側は素堀をした跡があり、後に再掘削を行い石垣を築いたと見られるとしている。前回の調査及び本調査により、中世小柏舘期、小柏氏信濃移住期、中世~近世小柏屋敷期の3時期に大別される事が判明したと報告をまとめている。巻末には現場の写真及び空撮写真、出土物の写真を掲載している。
以上の教育委員会による報告書で目新しいのは次の5項目である。
1.南側石垣部分辺りに埋蔵金の伝承があった。
2.舘の東西外周付近に科人断罪の伝承があった。その辺りはインゴウバタケ(因業畑か)と呼ばれていたらしい事。
3.近世において小柏屋敷に火災があった。(江戸後期?)
4.B区北側の畑地に小柏屋敷の従者居住伝承があった。
5.中国渡来銭が出土した。
この5項目を考察する。
1.の埋蔵金伝承は実際に破壊した跡がある事から現実味を帯びてくる。税金や山稼ぎの上納金、炭や木材・椎茸や山菜などの売上金で、残った金は火事になっても安全な土中に隠したという事は充分考えられる。
2.の科人断罪は家抱などの自家に従属した者が何らかの罪に問われ、主人の名の元に独自に断罪し罪を償わせたものか。
3.の火災については藤岡市史に大正八年4月に校舎を焼失したとする記録がある。この時に同敷地にあった舘も一緒に焼失したのであろうか。(時代が違う。)
4.の屋敷従者の居住とは誰の事であったろうか。この文面・表現からは家抱ではないように思える。小柏家の支配・行政に協力する直属の家来(番頭)のような者がいて、家抱の管理・監督などの仕事に携わっていたものか。
5.の中国渡来銭とは何を意味するものであろう。明治期に生糸売り込み人と呼ばれた生糸問屋が勃興した。
八郎治も大蔵卿に土地を簒奪され、別の収入の道を確保すべくあせったのであろうか。明治初期に横浜に進出している。生糸を売り、中国商人から受け取った銭であったのか。或いは(おそらく)もっと古い時代の中国銭なのか、今は詳らかに出来ない。
現在の小柏舘跡 道路が貫いている。

小柏舘跡 右端

藤林伸治が小板橋善三に聞いてメモ書きにした絵図がある。これを見ると舘跡地の西側に屋敷があり、南北に長い建物になっている。屋敷と書いてこれを南北に長い長方形の四角で囲っている。
東西の横幅は7間となっている。この長方形の右上に15-16間という数字が書き込んである。これが縦方向(南北)の建物の寸法とすれば、小柏屋敷の大きさは1階だけでゆうに100坪を越える大きな建物になる。
屋敷の長方形の左上に、3階と書き込みがあるので屋敷は三階建であったのか。もし総三階であったとすると、300坪~330坪にもなりこれは巨大な城の様な建物であったと想像される。
この屋敷の北東の所にもう一つの建物の図が書き込んであり、厩か納屋のような物があったように窺える。納屋の南、屋敷の庭に当たる中央付近に枝垂桜が植えてあったようだ。
この枝垂桜を挟んだ向かい側に、旧屋形があったが後に小学校となっている。小学校の南側に小柏門があり櫓門と記載されている。
西は墓地、西南は養命寺と書かれている。屋敷と墓地の間に火の見櫓と思しき絵も描かれている。屋敷の西北の山中には稲荷社とおぼしき図があり、メモの説明が付されているがこの文字は正確には読み取れない。
舘敷地の東端の辺りに、土地の人が「柏姫の井戸」と呼んでいる井戸がある。この柏姫とは誰なのか、いまだ不詳だが江戸初期の小柏重高の妹の一人であったのではないか。
重高の代からは合戦に出陣する事もなくなり、地元に腰をすえて足元を固めていたとみられるうえ6人の妹がいる。
あとがき
上日野小柏氏の足跡は記録などに見えるだけでも、群馬・京都・埼玉・長野・尼崎・岐阜・福井(鯖江)・北海道など広範囲に及んでいる。
また三波川小柏氏の集計(平成14年頃)によれば、全国の小柏姓の家は北海道から九州に及び342戸になるという。
この内、明らかに上日野小柏氏の流れを汲むと思われる上記の県に、東京をプラスすると259戸になる。これは実に76%を占めている。この傾向から見る限り小柏姓の一族は、全て藤岡市上日野の小柏にその源流を求める事が出来るようだ。
残りの83戸は他府県に2戸、5戸と散らばっている。但し徳島県には纏まった数がある。その19戸についてはその出自・性格は不明である。
徳島を除いた中国から九州にかけて21戸の小柏姓の家があり、集計した同氏は平氏の縁に繫がる土地に多いと見ている。
小柏一族の男子が養子となって家督を継いだ堀口氏・友松氏・山田氏・飯塚氏・中俵氏・須藤氏・松下氏・市川氏などの二男三男が父の旧姓の小柏氏を名乗った事もあるのだろう。
系譜に記録のないこれ以前の300年間にも、色々な氏族に養子に入っていると思われる。また奈良山小柏氏のように、小柏氏の子女が嫁いだ先で生れた二男三男が分家して小柏姓を名乗った可能性も大いにありうる。
ところで小柏氏正系図には、桓武天皇から始まる長い系譜が連綿と記されている。この系譜について殆どの文献は疑義を論じていない。平家から上代はともかくとして、平氏に繫がっているのかというテーマは残る。
繫がっていないとする場合は、小柏氏が揚羽蝶の家紋を使用した経緯について言及する事が望まれる。平家の一門に連なっていたからとするだけでは、少しもの足りないか。
小柏高政は、それまで370年程に亘って使われていた揚げ羽蝶の家紋を変更している。その時期は高政が武田信玄により、佐久の領地を貰い同氏が代官に任じられた時である。
してみると武田氏は甲斐源氏の流れを汲んでいる為、主家におもんぱかって平家の紋所を変更したと考えられる。
小柏氏正系図にあえて異質な物を探し求めると、維盛の庶子・維基のところからの二代にしかあるまいと思われる。維基の後継者維里は太郎、次の時基も太郎と添え書きがある。
維基以下の三人の内に架空の人物が1~2人いる可能性が考えられるのである。
藤岡市内の旧家に所蔵されている戦国期の古文書は、東京大學の史料編纂所長・所員によると真実の物はごく僅からしい。旧家を歩いて検分した結果、殆どの文書に両人は首を横に振ったという。
しかし偽書だからといって使えないとするのは少しおかしい、たとえ偽書であってもそれには何らかの意味がある筈だという意見も出されているという。
確かに戦国時代の文書は戦乱にあい、その混乱の中で焼失したり移動したり、保存状態が悪く湿気や虫食いなどもあり、残っている物はごく僅かであろう。これ等の事から筆写した書や、記憶を辿って書き直された物などが多いのではあるまいか。
してみれば偽書であっても、真実を伝えている場合があるという事になり、史料としての価値が存在する事になる。
これをどういう形で使い利用するかという点に留意すればよい。傍証として使い、そこから別の史料にたどり着いたり、ある種の結論を引き出す事が出来るかもしれない。
郷土史の研究は、やはり住所地の近くの物を扱うのが良い。出身地などの歴史などを調べる際には、図書館・公文書館などに所蔵されている古文献が門外不出となってしまう事がある故だ。
現地調査も二度三度、或いはもっと多くの訪問が必要になってくる。検索自体はインターネットで各地の物を検索し有無を調べる事ができ、図書館同士での書物の送付・貸出しも受けられる。
また簡単なコピーも取り寄せる事ができるが、発行部数の少ない古い郷土の記録・古文書などは貸出し不可となっているものが多く、現地まで出向く必要がある。
二部所蔵して一部を館内閲覧用、一部を館外貸出し用としてくれると良いのだが….。
地方の小さい出来事や氏族の事などの文献は国会図書館でも所蔵してないので困る。
「小柏氏800年の軌跡」は小柏氏の家系・歴史・事績を縦糸として、関連した文献・記録・伝説などを横糸として構成した。物足りない部分は残るものの小柏氏の歴史に関連するものは、ここに一通りまとめられたのではないかと思う。
今ひとつ核心に迫れず悔いが残った処は、小幡大膳之介の出自を明らかに出来なかった事、八郎治と原善三郎のせめぎあい・経過・因縁についての資料を見つけられなかった部分である。
特に、八郎治と善三郎の関わりは小柏氏没落の契機となったものであり、真実を知りたい欲求が燻ったままである。向後の解明に期待したい。
そして小柏一族の数箇所の墓地・墓碑の調査もいまだ不十分のまま今後の課題として残されている。
本編が小柏氏一族の方々が歴史をふり返り、語る時に少しでも参考になれば喜ばしいと思う。自分のルーツはいつか知りたくなるものである。偉大な先祖とその事績に、思いを馳せる時がくるのではあるまいか。また郷土史研究などに少しでも参考になるのであれば猶の事喜ばしい。
上日野小柏にある小柏氏の顕彰碑のうち、二つは高山長五郎の協力によるものとみられる。同氏が縁戚に連なる小柏氏の事績を偲び、後世に伝える為に労をとってくれたのだろう。小柏氏の末裔の一端に繫がる者として謝意を表します。
文中の敬称は略させて頂きました。
柏 宮沢賢治の宇宙H・Pより 
補 稿
小柏氏の墓所について
藤林伸治によると小柏家最後の番頭は、小沢弥五郎の四男・兵三であり同家の現地管理人(兼)墓守をしていたという。(昭和53年頃の事か)弥五郎は気楽流の使い手で秩父事件の参加者である。
事件後は行方不明であったが、時効が成立するのを待って帰郷して、破産していた家を再興したという。その間は木挽きの仲間に入り腕を磨いていたらしい。また石積みの名人、山田小太郎に弟子入りして石積み職人になった。
自由党員でもあった弥五郎は、常次郎そっくりの切れ者とされる反面、ホラ吹きとの評もあったもようだ。
口伝として上日野に残っている村のしきたりは、次のようなものである。
男だけの念仏講 16日
戒名に院号を付けない(八郎治も院号を付けていない)
土蔵を作らない(現在も土蔵はない)
獅子舞は草鞋をはかない隠れ獅子(室内用・長く隠された家抱村)
等である。(藤林伸治の取材メモ)
小柏氏の墓所には貞治年間の宝篋印塔があるが、江戸時代以前の墓碑が見当たらない事を不思議に思っていた。江戸時代以前の約600年間の墓碑が見られないのである。
中世は墓制がなかったのか水葬や土葬が行なわれていたという。墓碑や墓石についても一般庶民は禁止されていたともいう。この事から多くの人は、墓碑や墓石を建てる習慣がなかったのか、或いはこだわらなかったものか。意外と知られていないが、どんな墓でも造っていいという事はない。今でも墓石の大きさや形状を、条例や施工規則で規制している都市も多い。
家紋は平安時代以降に使用されるようになり、主として武士が戦場に於て目印となる旗印として用いられた。墓石を建て、家紋を刻むようになったのも江戸時代以降の事とされている。江戸時代にはキリシタン対策もあり、檀家制度が確立されていった。
三波川小柏氏の協力を得て、連絡先が分らなくなっていた小柏氏の現当主に話を聞く事が出来た。まず系譜にまつわる別記や古文書についての質問には、今現在は残っていないとの事であった。
先代の当主・吉明氏が全て処分してしまったという事である。残されているのは現存の系図のみであるそうな。
御鉾神社に祀られていたとされ、川中島決戦の時にも使われて、矢弾の跡が残っていた揚羽蝶紋の幕についても残っていないとのお答えだった。上日野小柏にあった建物を取り壊す時に、全て焼却処分したとの事である。
最後の住人「逸」さんが、なくなった時の事のようだ。其の際、葛篭(つづら)があったという。どんな葛篭だったのか、中に何が入っていたのかは今となっては灰に聞くしかないようだ。
また逸さんが三波川から帰って来て、小柏舘へ住む事になった経緯についてはご存知なかった。また小柏氏の墓地について私が江戸時代以前の墓碑がないようだが…とお訊ねすると古いものは壊れてしまったのではないかと言っておられた。
そして前は板の塔婆があったという。土葬であったとされるが正確なところはご存知ないようだった。現在は墓地の管理は地元で行なっているとの事で、最近は現地に行ってないと話してくださった。
鹿島神宮の、向かい側に墓地を移したのではないかと聞いたところ、その話は知らないないとのお答えだった。
墓碑の分析
|
俗 名 |
没 年 |
法 名 |
|
|
|
|
|
没年齢 |
|
貞治六年銘宝篋印塔 |
謹募衆縁造立貞治第六丁未霜月日謹記 |
伝小柏庄司重家 1367 |
重家建立の宝塔 |
|
応永廿七年銘宝篋印塔 |
逆修□阿庵□応永27年2月日 |
1420 |
伝 庄司重家墓所 |
|
|
|
|
|
|
|
1600年代 5 |
|
|
|
俗名不詳 |
寛永18年5月23日 1651 |
清雲芳永大姉 |
重氏室 墓碑? |
|
俗名不詳 |
延宝6年11月18日 1678 |
松窓妙喜大姉 |
|
|
小柏重高室 |
貞享1年6月23日 1684 |
妙高元志大姉 |
|
|
小柏八郎左衛門重高 |
貞享5年8月4日 1688 |
一燈元照居士 |
75歳 |
|
小柏権兵衛吉重 |
元禄5年10月14日 1692 |
一桂宗貫居士 |
|
|
|
1700年代 9 |
|
|
|
小柏六郎右衛門 當重 |
享保11年9月18日 1726 |
一峯浄栄居士 |
66歳 |
|
俗名不詳中宿村須藤氏娘 |
享保16年3月18日 1731 |
尊昌妙徳尼大姉 |
80歳 吉重室? |
|
小柏 當重室(嶋方氏) |
享保17年1月29日 1732 |
安窓寿昌尼大姉 |
66歳 |
|
小柏八郎左衛門記重 |
宝暦2年5月24日 1752 |
一氣有象居士 |
64歳 |
|
小柏 幼名源六 17歳出家 |
宝暦5年7月2日 1755 |
一要玄峰上座 |
60歳 當重三男 |
|
俗名不詳 |
宝暦7年10月? 1757 |
華崇□□□□ |
|
|
小柏記重 室と旡(小柴氏) |
明和1年12月10日 1764 |
松岳玄寿大姉 |
72歳 |
|
小柏八郎左衛門 祝重 |
寛政3年5月17日 1791 |
一叟躰寿居士 |
67歳 |
|
俗名不詳 |
寛政7年3月初3日 1795 |
春暁栄心大姉 |
|
|
|
1800年代 12 |
|
|
|
小柏祝重室 茂與(小柴氏) |
文化1年3月9日 1804 |
壹窓妙圓大姉 |
75歳 |
|
小柏るう?六郎右衛門 (重簡?)娘 |
文化10年1月4日 1813 |
孝顔王忠大姉 |
19歳 |
|
ふさ |
文政2年10月10日 1819 |
祖室貞勇大姉 |
|
|
小柏六郎右衛門重簡 |
文政7年12月10日 1824 |
一精密晋居士 |
72歳 |
|
俗名不詳 |
文政8年7月20日 1825 |
智□妙林童女ヵ |
|
|
小柏八郎左衛門重方 |
天保3年3月19日 1832 |
一法寿山居士 |
69歳 |
|
小柏重間室多美 |
天保4年3月18日 1833 |
白峯妙花大姉 |
64歳 |
|
小柏重方室於峯? |
天保13年8月28日 1842 |
柏室妙操大姉 |
73歳 |
|
小柏八郎右衛門重基 |
安政3年1月9日 1856 |
一量道鼎居士 |
55歳 |
|
小柏角次 |
慶応4年1月2日 1868 |
春月了性孩兒 |
1歳 重基子息 |
|
小柏武之輔墓所 |
明治7年1月16日 1874 |
柏永道葉居士 |
10歳 重基子息 |
|
小柏倉太郎重義 |
明治10年10月4日 1877 |
勇猛院重賢忠義居士 |
22歳 八郎治弟 |
|
満佐墓所角次武之輔と合葬 |
明治22年12月12日1899 |
栢葉梅幻嬰児 |
1歳 吉田保三娘 |
|
市川保太郎 |
明治32年10月23日1899 市川虎義登志子息登志・志津合葬 |
松山康秀孩子 |
2歳 |
|
|
1900年代 5 |
|
|
|
小柏重基室以與(市川氏) |
明治34年4月9日 1901 |
一心妙鼎大姉 |
82歳 |
|
市川登志墓所 |
明治36年11月26日1903 重基娘市川虎義室保太郎・志津母 |
梅屋妙俊大姉 |
23歳 |
|
市川志津墓所 |
明治36年11月26日1903 虎義・登志娘 登志・保太郎合葬 |
静安禅童女 |
3歳 |
|
小柏八郎治重明 |
大正11年5月8日 1922 |
寿翁柏英居士 |
80歳 |
|
小柏重明室多勢(根岸氏) |
大正11年7月13日 1922 |
寿室妙英大姉 |
77歳 |
|
小柏逸子墓所 |
昭和23年頃 1948? |
俊室妙逸大姉 |
飯塚時五郎室 |
|
計 |
31 基 |
|
|
参考:藤岡市教育委員会の調査
天引の小柏氏の墓所・墓碑
墓碑は畑の西端で竹林の麓に横一列に並んでいる。この後ろの潅木の中にも二つ以上の墓碑があるが、細い潅木がびっしりと茂っていて足を踏み入れる事は出来ない。この一列に並んだ墓碑群と、数メートルしか離れていない畑の仲にもう一つの墓地がある。
この墓地には古い墓碑が四列に並んでいる。この最後列が最も古い墓碑なのか倒れている碑、割れて倒れている碑があるなどで一番荒れている。この中に長山清閑信士と理山玄性信士の墓碑がある。
両墓碑は共に屋根付位牌形であり、笠塔婆のようにも見える。この最後列の墓碑の前に「角型前置灯篭」が三基ほど置かれている。この灯篭は一見すると墓碑のようにも見えるが、碑文が刻されていないようなので供養塔・庚申塔として置かれたもののようである。
灯篭と後ろの墓碑列の間隔が狭いのもこの事を窺わせる。灯篭の列とその前の墓碑列(後ろから二列目と三列目の間)との間隔は広くとってある。

灯篭の列 その左には観音様らしき石仏がある
天引の小柏氏 墓碑
(太字は確定)
|
卒年齢 |
卒 年 |
名 前 |
墓所 |
墓碑形 |
|
(推定) |
|
|
|
|
|
82 享保7 |
1723 |
小太郎父 頓證了覚大徳 |
未詳 |
|
|
61
延亨3 |
1746 |
傳六 母 安窓貞心 |
|
|
|
87 寛延2 |
1749 |
前山覺庭信士 |
|
|
|
7 |
1751 |
青銭童子 |
|
|
|
7 |
1759 |
不秀童子 |
|
|
|
7 |
1764 |
慧淳童子 |
|
|
|
7 |
1767 |
智陽童子 |
|
|
|
57 明和4 |
1767 |
傳六 妻 梅黄雨林 |
|
|
|
91 安永7 |
1778 |
長山清閑信士 太良兵衛の父 |
後列 横の墓 |
屋根付 |
|
76 安永9 |
1780 |
理山玄性信士 太良兵衛 |
後列 横の墓 |
屋根付 |
|
76 天明1 |
1781 |
徳翁忍光 八三良 父 |
向陽寺 |
灯篭形 |
|
7 |
1781 |
涼薫童子 |
|
|
|
22 |
1781 |
貞倫智永 |
|
|
|
64 寛政3 |
1791 |
勘右衛門父権大僧都月潤浄心信士 |
向陽寺 |
卵塔 |
|
61 8 |
1796 |
定室了禅 善治朗 母 |
後列 横の墓 |
方形 |
|
72 8 |
1796 |
勘右衛門祖母丹丘妙仙 判読不能 |
天引? |
方形 |
|
57 文化1 |
1804 |
勇蔵養父 権大僧都喜山秀悦信士 |
後列 横の墓 |
卵塔 |
|
61 文化2 |
1805 |
勘右衛門 母 月舩妙皎 |
天引 |
|
|
61 文政1 |
1818 |
勇蔵養母 清蓮知浄 |
|
|
|
22 文政5 |
1822 |
定吉 收林常然 |
天引 |
方形 |
|
61 天保1 |
1830 |
勘右衛門 妻 寒相貞温 |
天引 |
|
|
64 天保2 |
1831 |
勘右衛門 実参徹温 |
向陽寺 |
卵塔 |
|
36
弘化3 |
1846 |
寅吉 妻 安室休穏 |
天引合葬 |
五輪塔 |
|
60 嘉永 |
1850 |
林次郎 陛岳良忠 (寅吉倅) |
天引 |
方形 |
|
61 安政4 |
1857 |
覚室明圓 萬吉 母 (70代) |
|
|
|
75
明治12 |
1880 |
寅吉 徳聲常圓 定吉祖父 |
天引? |
五輪塔 |
|
77
明治23 |
1891 |
定吉 養母むら 夏雲清涼 |
天引合葬 |
五輪塔 |
|
79 37 |
1905 |
常吉 徳翁常圓 |
天引 |
方形 |
|
計 大人 23人 童子 5人 (高祖父以前) |
||||
|
|
墓碑数 |
判明 |
不明(除童子) |
備考 |
|
天引 |
13 |
7 |
6 |
|
|
後の潅木の中 |
2~□ |
|
2~□ |
|
|
横の墓地 |
6 |
4 |
2 |
最後列(除前列) |
|
向陽寺 |
3 |
3 |
|
|
|
向陽寺 石仏 |
2 |
|
1 |
一体は庚申塔? |
|
計 |
26~□ |
14 |
11 |
|
時代の変遷による墓碑の形状
五輪塔
石造りの五輪塔は平安時代から造られるようになり、広く親しまれている。時代によって塔の高さが変ったり、やや形状が変ってきている。その五層の塔は上から「空」「風」「火」・「水」・「地」を顕わすとされる。
この五要素は人体を顕わす事にも繫がるという。
天引墓碑 
無縫塔
卵形をしているので俗に卵塔と呼ばれる。野球のバットを縦方向に縮小したような形である。鎌倉時代に中国から禅僧によって伝えられ、僧侶の墓碑として広く用いられた。
多くは卵塔の下に蓮座を敷いている。江戸時代には大名も好んで用いるようになった。
上日野小柏氏 1795 天引小柏氏 1791・1804


角石燈篭型
上日野小柏重高墓碑 1688 天引小柏氏 1781


角石型墓石
江戸時代になり、現在の墓石に近い位牌形の物が多く作られるようになった。方形の板碑で、武士はこの上部に笠を置いた物を好んだ。一般では屋根付がよく用いられた。
上日野小柏氏 1757 天引小柏氏 1780


合掌
ここでは代表的な物を挙げたが、両者の年代は近接していて形状も似ている。
平氏と小柏氏・武士団
小柴氏と川邊氏
西上野国の武将・地侍の多くは平氏の系統に属し或いは桓武平氏を称えている。そして先祖伝来の落人・平氏伝承を備えている旧家が多い。これ等の諸家の先祖は京都に在番していた経験があったり、近世では名主を勤めたりしている。三波川小柏氏からお借りした書籍を基に平氏伝承を考証してみる。
上毛新聞社の「上州の苗字と家紋」を見ると、
上日野の小柴家は小此木氏と共に古くからの名家。江戸時代には名主を勤め、領主から定紋入の宝物などを拝領している。両氏とも源氏の流れであるが、平重盛の一族と婚姻し平家全盛の頃はその一門として京都にあった。
平氏滅亡後、小柏氏と共に上野国多胡郡日野谷の奥地、御鉾山裏に隠遁し小柴摂津守は日野地区の柴平に、雅楽頭は塩平にそれぞれ居を構えた。雅楽頭は鎌倉幕府の詮索を恐れて「小柴」の二字を分解して「小此木」にした。
戦国時代には甲斐の武田に属し、長篠合戦で両氏共に討死した。小柴家では「天正三年五月二十一日・小柴与兵衛兼行」の霊を祀っている。京都時代の文書は焼失したが江戸時代の文書は数多く残されている。家紋は「雪輪揚羽蝶」。
としている。小柴家に伝わるこれ等の伝承は、次の四点からその信憑性は低いものではないと思われる。
1.小柏氏と共に隠遁したという点。
小柏氏は平重盛の孫が始祖と伝えられており、小柴氏も重盛の一族と婚姻していたとあれば、縁戚ゆえに行を共にしたものと考えると違和感がない。
2.「柴平」の地名は小柴平家から採られたと見る事も出来る。
今は「芝平」と表記される事が多いようだが、小柴屋敷がある岡本の事であろう。そしてその下流に位置する「塩平」の地名にも平家の由来が感じられる。この鮎川の上流から下流までの三地点、すなわち「小柏」「柴平」「塩平」はごく大雑把に見てほぼ等間隔に距離をとっている。
この三地点を地図上で凝視して見ると、藤岡・平井方面からの侵入に備えての布陣・配置と思えてくる。小柏を本城、芝平を詰城、塩平を出城と見る事が出来るようなのだ。
小柏より西は杣道(往時)となり通行不能、北は秋畑山などの山塊に守られ南は鮎川に守られ、豊富な山の幸と水のある要害の地として映じてくる。
3.小柴氏・小此木氏は小柏氏と同じく長篠合戦で討死している。ここでも生死をかけて共に行動している。長篠合戦で討死した小柴与兵衛兼行の妻は小柏定政の長女である。
つまり同じ戦場で討死した小柏定重(定政の兄)の姪である。記録は見当たらないが、これ以前にも小柏氏と小柴氏は婚姻関係にあったとの想像は難くない。
更に定政の三女は小此木吉左衛門兼佳に嫁いでおり、この三家は血縁で固く結ばれていたものと思われる。
4.家紋が小柏氏・平氏と類似の「丸に揚羽蝶」である。雪輪とは蝶を囲む円に所々切れ目が入り、雪の結晶のように見える円の囲いである。
川鍋巌著「北武蔵・西上州の秘史」によると、薩摩・川邊郡司の川邊氏は941年、藤原純友の乱に加担した為、薩南地方に逃れ桓武平氏を称えていたという。伊作氏は川邊郡を領有しその氏を「川邊」とした。
薩摩川邊氏の末裔川邊氏は京都で朝廷守護の勤番中、1221年の承久の乱に巻き込まれ、鎌倉源氏軍に敗退、信濃から十国峠を越えて秩父郡矢納郷へ落ち延びて来たという。
この落人武士団は金澤氏・川邊氏合わせて十二人であり仏像を携えていたという。金澤氏は「矢納」に土着し川邊氏は「鳥羽」に土着し、国人領主になった。「矢納」は承久の乱の時の京都方の武将・矢野次郎左衛門」に由来し「鳥羽」は京都「鳥羽」に由来があると川鍋巌は推定している。
以降、金澤・川邊両氏は一体の武士団を形成し、金澤城・智禅寺舘を築き中世に活躍した。金澤氏はその邸内に宝積寺を建立し、川邊氏は邸内に延明寺を建立してそれぞれ墓地を造っていた。
更に前進基地として、藤原砦・観正寺屯所を設置したという。
金澤氏は矢納西部国人領主として西部を支配し、川邊氏は従者と共に東部国人領主として東部を支配した。
川邊氏は館内に三家老(飯塚・塚本・浅見)を置き、宇那室に野口氏を配置した。
その地は鎌倉長尾氏領や足利長尾氏領になり、戦国期には武田に属した。
その後は鉢形城の北条氏に属していた為、秀吉軍の前に敗退した。家康は鉢形城の残党狩りを厳しくした為、江戸時代には鉢形の残党の足跡・記録を村ぐるみで徹底的に排除・消滅させて今日に至ったとしている。
昭和27年に川邊舘跡から1500年造立の、逆修五輪塔二基と地蔵菩薩画像板碑が出土した。
更に明治41年に近在の人によって、智禅寺横の南沢で小さな「金鋳仏」が発見された。この高さ約8ミリの仏像は、博物館の鑑定により十二世紀作「銅造如来形座像」とされた。火災の為に行方不明となっていた智禅寺の本尊だったという。この事により落人の伝承が裏付けられたとしている。
この川邊氏の由来・伝承は小柏氏と小柴氏の由来・来歴に酷似しているように思われる。両者共に平氏の一門であり、縁戚に連なる合同の武士団が西国から落ち延びて来た。
落ちて来たルートは、東海道を避けて東山道に沿ったものであったろう。古代に信濃・諏訪まで敗走してきた「建御名方命」と同じルートだったかもしれない。谷川沿いに土着して、その川沿いに城・砦を配置している事も同じである。
その時代の文化であったのだろうが、屋敷内に氏寺を建立し墓地を設置している点でも全く同じである。逆修塔を建立し自分と一族の安泰・繁栄を願った事も一致している。
武州・上州のこのエリアは日本武尊の東征のルートにあったとして、同尊の伝説が数多く残されている。その伝説から生じた地名がいま尚幾つも現存している。
「矢納」は日本武尊が自分の矢を納めたところからその名が付いたとされる。「御鉾山」は日本武尊が鉾を担わせた所から生じた山名としている。(「上州の史話と伝説その2))それぞれ変った名前であるが、この由来であれば さもありなんと納得出来るものがある。
平氏伝承 小柏氏と武士団
「藤岡市森」の岡本氏の先祖は、甘楽郡岡本に住んでいた岡本兵部少輔持村で,伊勢平氏の流れを汲んでいるという。箕輪城主長野氏の一門であったが、長野氏滅亡後は武田氏に従った。神流川決戦では滝川一益に従って出陣し討死したという。江戸時代には名主を勤めた。家紋は丸に揚羽蝶である。
富岡市妙義町に十数軒ある関氏は本家・関三重一氏家に伝わる系図によると平氏の末裔である。
伊勢国の亀山の関屋の地頭に任ぜられていたので、その時の「関屋」の関を取って関姓を名乗った。実忠の嫡子盛信は織田信長と戦って敗れ、敵対していた武田信玄の元に逃れたという。
その後、武田氏の滅亡により小幡氏を頼って上野国甘楽に来たが、小幡も同じように織田氏に追われていた為、菅原城主の高田氏に関氏を託した。高田氏は自領内の諸戸の佐藤氏に関氏の身柄を預けたという。
三重一氏は第十五代目で、江戸時代には名主を勤め多くの古文書を有している。家紋は丸に揚羽蝶を使用している。
富岡市蕨(一の坂)に新井姓がある。この地は小盆地で隠れ里とも言われるが、交通の要衝でもあり吉井・甘楽町との繋がりが強い。ここ新井家の墓地に応永年間の宝篋印塔があるのが確認された。
この地の南に位置する根古には城跡があるが、築城年代・築城者などはいまだ判明していない。土地の古老の話では新井家の先祖は小松少将の一族で、鎌倉幕府の目を逃れて来て世の中から身を隠し農業をしていたという。
そして「新井」という新開地の名を取り姓にしたという話である。一族が増え後賀や蕨に移った者も出たが、再び戦乱の世となり蕨城に籠って戦ったがこの城も敵の手に落ちたと古老は語っていた。家紋は九曜である。
富岡市藤木を中心に白石姓があり、江戸時代には名主を勤めていた。「白石家家図」と古老の話では遠祖は平氏である。初め土肥氏を名乗り後に白石を名乗った。白石老兵衛盛久の時に安芸国に移り、久知は同地の小幡尾張守に仕えた。
小幡候は、朝廷から上野国天引城の朝敵を征伐するよう命を受け、平定した功により小幡庄を与えられ久知以下の十八人の武将も従って来た。
小幡落城後、時の家老・白石出雲守も身を隠し放浪していたが、小幡信秀が野殿に千石の領地を与えられると、久知兄弟は藤木と野殿へ家を構えた。家紋は丸に九枚笹。
富岡市瀬下の黒沢氏の先祖は桓武平氏の出である。下総国相馬郡黒沢村に住んでいたという。後に国峰城小幡氏に仕え、更に武田氏、滝川氏、北条氏に従った。小田原の役での国峰城落城の時には、黒澤の先祖が若君を連れて多野の上野村に逃げた。折を見て若君を伴って瀬下村へ来て農業を営んだ。
後に砥石問屋を営み名主をしていたという。家紋はつなぎ駒。
以上「上州の苗字と家紋」から類似の伝承を抜粋してみた。
平氏の出であると伝承されている家が7家あり、その内の4家が伊勢平氏或いは桓武平氏を称えている。
家紋もそれぞれ揚羽蝶を用いている。これだけ多くの氏族が平氏末裔伝承を持っているという事は何を物語っているのであろうか。これらの諸家はみな嘘の伝承をもっともらしく作りあげたのか?
そうではあるまい、先祖から子孫へと連綿として語り継がれていく家の事績が、嘘で塗り固められたものであったとしたらどうだろう。その嘘が暴かれた時、子孫は恥をかき、侮られそしりを受けるかもしれない。
してみると、小柏氏や諸家に伝わるこれ等の伝承、或いは伝承の骨格を形作る部分は事実であったと見做す事も出来る。
何れも明確に否定できる文献や古記録は、いまだ現れていない事もその証左であろうか。一様に平氏一門の使う揚羽蝶の家紋を今だに用いている事も、一つの傍証となり得るものと考える。
平維盛が牛車に蝶の紋を付けていた事はつとに有名であるが、桓武平氏がみな一様に揚羽蝶の紋を使っていた訳ではないのである。坂東平氏は鎌倉源氏に従って平氏と戦ったゆえか蝶紋を使用していない。
公家では桓武平氏高棟流が蝶紋を使用した他、高望流伊勢平氏の一派が蝶紋を用いている。
三波川小柏氏にも、平氏に結び付く可能性について話を聞いてみたが、そのお答えは次のようなものだった。
三波川とその周辺の地域はみな平氏だった。唯一、三波川の飯塚氏だけが源氏である。自分の家は母から犬を飼ってはいけないと言われていた。(六代丸が犬を追いかけて源氏の将に見つかった故事の戒めか。)
(遠い西国から鎌倉の近くを通って、さほど遠くもない上野国に居ついたとは考え難いが…..」東海道は通らず信州を経由して来た。上日野辺りは地政学的に見て御鉾山の連山が、埼玉・神奈川方面からのエッジ(壁の意)となっている。と話しておられた。
川鍋巌は父から、鳥羽はみんな平氏だ、うちの先祖は馬に乗ったいい侍だった、父などから聞いて良く知っている。と聞いたという。今も土地の古老に良く聞いてみると、戦国時代の話でも自分が見ていたように語る人が居る。
その話の多くは事実に沿っていて、問題となるほどの矛盾は包含されていないのである。
小柏氏 年表
平安時代
1100年 上野国国司 介藤原敦基 目代平周真
1157 平維盛 出生
1168 維盛嫡子六代丸(午前) 出生
1169 六代丸弟維基(姓を小柏に改称) 出生
1170 六代丸妹 夜叉御前 出生
鎌倉時代
1185 文覚上人 六代丸の助命嘆願
1190 頼朝 入京
1194 六代丸 鎌倉で頼朝に面会
1194 六代丸 鎌倉で没(斬) 26歳
1196 小柏維基 鹿島神社建立 (上日野)
維基の後継 維里 小柏太郎
維里の後継 時基 太郎
1252 上杉氏 鎌倉で侍家大将となる
1278 時基の後継 維仲 (市太郎) 北条時村に従い京都六波羅入り
1301 維仲の後継 重胤 (右衛門太郎) 執権北条基時に従い六波羅入り
重胤の後継 時實 (市次郎)
時實の後継 實親 (與市) 執権北条高時に属す
1333 新田義貞鎌倉没落時 實親戦死 弟實季も兄と共に戦死
南北朝時代
1335 上杉憲房 上野国守護となる
1355頃 實親の後継 重親 (平太夫宮内少輔) 鎌倉管領に属す (北朝)
重親 足利基氏・上杉憲顕に属し鎌倉勤番(在住)
1360 重親没
重親の後継重家(庄司)歴代小柏村住す 管領上杉憲方に属す(在鎌倉)
武功有
1367 重家 上日野小柏(村)に宝篋印塔を建立す
1367頃 重家 西御鉾山に鼠喰城を築城
1410頃 重家 没
この頃 重家の後継 重徳 (六郎) 管領上杉憲定に属す
1416 小幡氏 上杉氏に属す
室町時代
1428頃 重徳の後継 高家 (平太郎後庄司) 上杉憲基・憲實に属す
1440 足利持氏生害の時 高家軍功あり
1441 上杉氏 小幡氏 結城城を攻撃
この頃 高家の後継 重行 (平治左衛門尉) 上杉憲實 に属す
重行の後継 顕重(宮内少輔) 法名 浄山 上杉房顕・顕定に属す
1504 顕重 武州立川原合戦にて戦死
1504頃 顕重の後継 顕高 (駿河守) 浄印入道 管領上杉顕定に属す
上杉憲房から顕の一字賜る 顕高と称える
1511頃 顕高 平井城出仕 上杉憲寛に暫く属す
顕高の後継 高道 (大學) 法名 道徹 管領上杉憲政に属す
1545 高道 川越合戦出陣 数度の武功あり
1552頃 高道 小幡重貞より招致あるも応ぜず のちに和す
1545頃 高道の弟 高景(小次郎 後 駿河) 兄と共に上杉憲政に属し
平井城出仕 力量優れ鬼駿河と呼ばれる
高景の後継 景氏 (新吾) 本家後見役 (妻 高道長女)
1583頃 景氏の弟 高治 新助 細谷戸村の地守を勤め後 田ノ口の代官
子孫有 田ノ口相木村
景氏の後継 高元 (宮内助)
高元の後継 高久 (加兵衛)
高久の後継 光氏 (作重郎)
光氏の後継 高次 (武兵衛)後 一無 (実は堀口氏二男)
高次の後継 高連 (浅次郎 後 武兵衛)
高道長女 景氏に嫁す 力量大いにあり誉れ高い為別記有
二女 後藤新太郎基道に嫁す 基道の後継 道兼(小柏新左衛門となる)
1551 高道の後継高政 (左馬助 後六郎右衛門) 浄林庵主 上杉憲政に属す
1551頃 高政は鼠喰城に北条氏康軍千余人を迎えうち、千(十)人斬り。(撃退)
1551 上杉憲政北条氏康に追われ越後へ退く
1552 憲政逃亡後 高政武田に属す 佐久郡田ノ口代官となる 家紋変更す
1561 武田信玄、西上野へ進出 氏康と謙信の倉賀野城を攻める
1566 信玄により箕輪城落城 長野氏亡ぶ
1567 高政 小幡弾正忠信氏と白倉氏・熊井戸氏と生島足島神社に起請文奉納
高政の弟 定重(源六) 兄と共に武田勝頼に属す お菊を救助する
1570 新陰流祖 上泉信綱(大胡城主・長野旧臣) 足利義昭に兵法を教える
1575 定重長篠の合戦に出陣 戦死 別記有
1577 高政小幡重貞・信真と共に菅原神社及び妙義神社に鰐口奉納
1580頃 高政 養命寺建立 開基となる
1582 織田信長 没
高政の後継 定政 後源重郎 浄久
1587 定政 小幡信貞 嫡男(養子)孫市(直之)を匿う 定政武功有
1590 定政 小幡信真と共に小田原籠城 (秀吉攻め) 別記有
定政 長女 小柴家に嫁す
二女 飯塚家に嫁す
三女 小此木家に嫁す
1592 定政の後継 重氏 (六郎右衛門)出生
定政二男貞景 (傳内)堀口家に養子・後継
三男貞實(傳左衛門)友松家に養子・後継
江戸時代
1614 大阪冬の陣に重氏出陣 22歳 数度の武功有
1616 織田信雄 小幡城主となる
1660 吉重後継 當重出生
1662 沼田藩主真田伊賀守信利 領内に過酷な検地をする
1671 重氏 没 79歳 法名 浄安 別記有
重氏弟 貞景 堀口家(小幡)を継ぐ 堀口伝内と称す 法名 浄無
重氏弟 貞實 友松家(福島)を継ぐ 傳左衛門を称す 法名 半無
重氏の後継 重高 (甚平 後八郎左衛門)
1675 重高夫婦で潮音に帰依 不動寺建立開基となる 不動寺に木像有 別記有
重高 弟 重弘 與惣右衛門 号は全當 山田家(白倉)を継ぐ
妹 小柏光高(榎谷戸)に嫁す
光高 長男光氏 (作重郎) 中俵家を継ぐ
光高 後継 二男 高行 (彌平治)榎谷戸小柏氏
重高 妹(実は光高妹)金井家に嫁す
重高 妹 桜井家に嫁す
重高 弟 吉重 後 重高の後継者となる
重高 妹 堀田家に嫁す 後広瀬家に嫁す
1646生? 重高 妹 飯塚惣兵衛春猶(村上)に嫁す 法名 貞真
竹野か? 1686頃?妹ヶ谷入植?
重高 妹 松井田の松本家に嫁す
重高 弟徳氏(丑之助)号は宗莫 沼田藩真田信利に属す、後小柏に住む
後、天引に移住?
重高 弟 常氏(平右衛門)飯塚彦右衛門(三波川)を継ぐ 法名 了真
重高 弟 吉次 (権右衛門) 後又兵衛 尼崎城主青山幸利に属す
後 医師露休 となる 小柏に住む
重高の後継 弟 吉重 (平吉 後権兵衛) 初め本多家に属す
後 重高の後継 法名 一桂 不動寺に建影像有
1681 潮音「旧事大成経(神代皇代大成経)」の出版に関わり幕府より謹慎処分を受ける
1684 小柏 重高室 没 妙高元志大姉
1688 小柏八郎左衛門重高 没 75歳 一燈元照居士
當重後継 記重出生
1692 小柏権兵衛 吉重 没 一桂宗貫居士
1713頃 吉重の後継當重 養命寺の中興開基となり山林・畑を寄付する
萬太郎後武太夫と号す
1724 記重後継 祝重出生
1725? 當重 解江湖の施主となる 法華経一千部 転読施主 法名 浄榮
1726 小柏六郎右衛門當重 没 一峯浄栄居士 66歳
1732 小柏當重室 没 安窓寿昌尼大姉 66歳
1752 小柏八郎左衛門 記重 没 一氣有象居士 六十四歳
記重の姉 諸星家に嫁す
弟 俊棋(甚平後政右衛門)須藤家を継ぎ六右衛門を名乗る
弟 一要(源六)17歳で出家す(宝積寺)
妹 庄田家に嫁す
記重の後継祝重(権八郎後八郎左衛門)
祝重の姉 新井家に嫁す
姉 根岸家に嫁す
姉 須賀家に嫁す
姉 庄田家に嫁す
姉 市川家に嫁す
弟 惣次郎 (実は須賀角右衛門智春の二男)
1752 祝重の後継重簡 (右馬介後内藏之蒸 六郎右衛門)出生
1757 (第二次)御荷鉾山騒動
1757 小暮市右衛門 刑罰受ける
1764 小柏 記重室 没 松岳玄寿大姉 七十二歳
1764 重簡の弟・後継重方(幼名は右膳司 謙治郎 郎吉? 後八郎左衛門) 出生
1784 国内冷害飢饉
1786 関東大洪水
1787 数年飢饉 物価高騰 農民脱走
1791 小柏八郎左衛門 祝重 没 一叟躰寿居士 六十七歳
1800 幕府 切支丹宗門改め
1800~1807 重簡 名主を勤める
1801 重方の後継重基 (八郎右衛門) 出生
重基の姉 市川家に嫁す
兄 徳明 出家 武州今井村長興寺
弟 治平 前原村 松下家を継ぐ
1804 小柏祝重室 茂與 没 壹窓妙圓大姉 七十五歳
1807~ 重簡の後継・重方 名主を勤める
1809 富岡正忠 上野名跡考を著す
1815 宮沢(小柏)風梅 出生
1824 小柏六郎右衛門重間 没 一精密晋居士 七十二歳
1828 日野村の農民、役人の不正を越訴する 御鉾山騒動
1832 小柏八郎左衛門重方 没 一法寿山居士 六十九歳
1833 小柏重簡室多美 没 白峯妙花大姉 六十四歳
1837 重基の弟方義(泰吉) 没 23歳 法名 一天総梅居士
1842 重基名主になる (八郎右衛門)
1842 重基後継 八郎治 重明(民之助 八郎治)出生
重明の姉 貞 浦部家に嫁す
妹 嶋 小此木家に嫁す
妹 才 浦部家に嫁す
妹 代 吉田家に嫁す
弟 真太郎 砥沢村の市川家を継ぐ
1850 重基 秩父山で金堀り 失敗
1850頃 寛永年間の山崩れで御前岩の碑が流失したという
(多野藤岡地方誌各説編)
1856 小柏八郎右衛門重基 没 一量道鼎居士 五十五歳
1867 念流(間庭)道場を建てる
明治時代
1868 上野諸藩兵 三国峠で会津軍と戦う
1869 岩鼻県 貫前神社に廃仏命令を出す
1871 廃藩置県
1872 逸 出生
1872 富岡製糸創業 民間信仰禁止令
日野村の俳人 芭蕉の墓参 芭蕉碑を建てる (風梅)
1876 星野長太郎 自家製生糸をアメリカへ直輸出 地租改正
1877 重明の弟重義(倉太郎) 西南の役に徴兵で従軍 熊本県にて戦死
勇猛院重賢忠義居士 22歳
重明の長男 武之助 早世
長女 美代 武州下奈良村 吉田家に嫁す
二女 逸 三波川 飯塚時五郎に嫁す
三女 濱 信州臼田町 井出久定に嫁す
1884 秩父事件 発生
1885 風梅 没 72歳という(70歳?)
1894 日清戦争 高崎連隊へ動員令
1898 重明の後継(孫)吉明 出生 (後第三十五代の当主となる)
1901 小柏重基室以與 没 一心妙鼎大姉 八十二歳
1904 高崎連隊に日露戦争の動員令
1909 浅間山大爆発 郷土史編纂令
1910 「多野郡誌」なる
大正時代
1922 (大正11年)八郎治重明 没 寿翁柏英居士 80才
1922 小柏重明室 多勢 没 寿室妙英大姉 七十七歳
昭和時代
1948頃 逸 小柏にて没す 76歳?
* 年次には数年の誤差がある場合があります。
参考文献
大日本地名辞書 吉田東伍
群馬県の地名 平凡社
徳川実記
秩父事件 井上幸治
秩父事件のおんなたち 保高みさ子
秩父事件の妻たち 新井佐次郎
秩父事件の女活動家 大沼田鶴子 (文芸秩父)
上野国郡村誌
鬼石町誌
甘楽町史
藤岡市史 通説編
藤岡市史 各説編
藤岡市史 資料編
藤岡市史 民族編
藤岡地方の中世資料
多野藤岡地方誌総説編
多野藤岡地方誌各説編
群馬県北甘楽郡史
群馬県多野郡誌
小柏舘跡 (発掘調査報告書) 藤岡市教育委員会
上野人物志 岡部福蔵
小柏氏正系図 小柏吉明蔵 県立文書館
小柏氏正系図 高山吉重蔵 ゝ
県立文書館収蔵文書目録11 (飯塚家文書)
群馬の峠 須田茂
ふるさと人ものがたり 藤岡 藤岡市
群馬歴史散歩 90号 塚越篤江
甲陽軍艦
鎌倉公方九代記 文化資料館
関東管領上杉一族 七宮涬三
長森原古戦場史「上杉顕定公」
鎌倉大草紙
上毛古戦記 みやま文庫
上野志料集成
宝積寺史 宝積寺
現代語訳信長公記 新人物往来社
長篠・設楽原合戦の真実 名和弓雄
郷土氏姓録 日本姓氏出版
地理雑件 小字名調書 明治14年
藤林伸治資料 法政大学
上州の伝説 角川書店
ふじおか 「ふるさと伝説」 (関口正巳)
関東の仙境 「黒瀧山」 あさお社
上州の苗字と家紋 上毛新聞社
上州の秘史と伝説 上毛新聞
北武蔵・西上州の秘史 川鍋 巌
日本城郭全集 3 人物往来社
上野武士団の中世史 久保田順一
藤林伸治の取材ノート 藤林伸治
住吉大社神代記の研究 田中 卓
先代旧事本記と大成教 原田 実
謎の根元聖典先代旧事本紀大成経 後藤隆
群馬県姓氏家系大辞典 角川文庫
風吹きて 歴史は廻る 日野谷を 花は散りいて 草ぞ哀しき
著 者
小柏 正弘 1949年生 (群馬県)
完稿 2007.12.4
「平姓上野國 小柏氏 正系圖」 (巻物表紙)
小柏系圖 平姓 家紋 揚羽蝶或丸ノ内釘貫丸ノ内三ッ柏葉
神武帝五十代 諱山部 太宰大貮 安藝守 小松内大臣 母二位尼 小松伊豫守 正三位中将法名浄円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 桓武天皇 中略 平清盛 重盛 維盛
桓武天皇 中略 平清盛 重盛 維盛
従一位 太政大臣 治承三巳亥年 七月廿八日出家号浄連 欲入水干熊野那智海遂不果
同八月一日 薨四十二歳 其望而遁世隠干十津川
![]()
![]()
![]() 家盛 早世 基盛
資盛
家盛 早世 基盛
資盛
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 頼盛 宗盛 清経
頼盛 宗盛 清経
![]() 有盛
有盛
![]()
![]() 忠房
忠房
![]()
![]() 六代午前 法名妙覚
六代午前 法名妙覚
小柏平太郎 太郎住上野國 太郎 市太郎 右衛門太郎 市次郎 與市 平太夫 庄司 六郎
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 維基 維里 時基 維仲 重胤 時實 實親 重親 重家 重徳
維基 維里 時基 維仲 重胤 時實 實親 重親 重家 重徳
宮内少輔 従五位下
兵庫助
![]()
![]()
![]()
![]() 女子(夜叉御前) 實季
女子(夜叉御前) 實季
平太郎後庄司 平治左衛門尉 宮内少輔 駿河守 大學 有大力量
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 高家 重行 顕重 顕高 高道 小柏新吾景氏妻
高家 重行 顕重 顕高 高道 小柏新吾景氏妻
奈良山 小柏新左衛門
![]()
![]() 後藤新太郎基道妻 道兼
後藤新太郎基道妻 道兼
早世
![]() 女子
女子
左馬助 後六郎右衛門 源六 お菊救助
![]()
![]()
![]() 高政 定重 長篠合戦討死
高政 定重 長篠合戦討死
左馬助後源重郎
![]()
![]()
![]() 定政
定政
小次郎後駿河 新五
宮内助
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 高景 景氏 高元
高景 景氏 高元
新助
![]()
![]() 高治
高治
甚平 後八郎左衛門
![]()
![]() 重高 中俵作重郎 新井清蔵妻
重高 中俵作重郎 新井清蔵妻
![]() 山田與惣右衛門 光氏
山田與惣右衛門 光氏
![]()
![]() 重弘 継山田家 継中俵家 根岸伊之助政命妻
重弘 継山田家 継中俵家 根岸伊之助政命妻
榎谷戸村 彌平治 早世 早世
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 小柏彌五兵衛光高妻 高行 女子 法名知春 女子 法名理心童女
小柏彌五兵衛光高妻 高行 女子 法名知春 女子 法名理心童女
継榎谷戸家
![]()
![]()
![]() 小柴與兵衛兼行妻 金井重兵衛勝光妻實小柏光高妹
須賀弥七郎妻
小柴與兵衛兼行妻 金井重兵衛勝光妻實小柏光高妹
須賀弥七郎妻
![]() 諸星七左衛門貴郁妻
諸星七左衛門貴郁妻
![]()
![]() 三波川 桜井五兵衛勝行妻 庄田彦七郎妻
三波川 桜井五兵衛勝行妻 庄田彦七郎妻
![]() 飯塚彦右衛門常清妻 平吉改権兵衛 萬太郎号武太夫 平吉後権八郎 八郎左衛門 南牧
飯塚彦右衛門常清妻 平吉改権兵衛 萬太郎号武太夫 平吉後権八郎 八郎左衛門 南牧
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 吉重 継兄重高 當重
記重 市川氏妻
吉重 継兄重高 當重
記重 市川氏妻
後六郎右衛門 権八郎 八郎左衛門
![]()
![]()
![]() 六郎右衛門 水戸殿臣何某妻 実大田氏女 早世 祝重
六郎右衛門 水戸殿臣何某妻 実大田氏女 早世 祝重
![]()
![]()
![]() 重氏 女子 法名昌桂童女 早世
重氏 女子 法名昌桂童女 早世
![]()
![]() 広瀬左源太季孝妻初堀田九兵衛近忠妻 女子
広瀬左源太季孝妻初堀田九兵衛近忠妻 女子
實兼行妻養女 丑之助後傳右衛門 号宗莫 甚平 須藤六右衛門
![]()
![]()
![]()
![]() 小此木吉左衛門兼佳妻 徳氏 俊棋 後政右衛門 女子
小此木吉左衛門兼佳妻 徳氏 俊棋 後政右衛門 女子
![]()
![]() 飯塚平右衛門 三波川 継須藤家 早世
飯塚平右衛門 三波川 継須藤家 早世
![]()
![]() 常氏 継飯塚彦右衛門 源六 女子
常氏 継飯塚彦右衛門 源六 女子
![]() 堀口傳内 権右衛門 後又兵衛
一要 十七歳出家
堀口傳内 権右衛門 後又兵衛
一要 十七歳出家
![]()
![]()
![]()
![]() 貞景 継小幡郷堀口家 吉次 医師露休
惣次郎
貞景 継小幡郷堀口家 吉次 医師露休
惣次郎
村上ノ住 竹野? 實須賀角右衛門知春二男
![]()
![]() 友松傳左衛門 飯塚惣兵衛春猶妻 庄田新兵衛淵信妻
友松傳左衛門 飯塚惣兵衛春猶妻 庄田新兵衛淵信妻
![]()
![]() 貞實 継友松家 松枝ノ住 法名 貞真
貞實 継友松家 松枝ノ住 法名 貞真
![]()
![]() 松本勘兵衛清房妻 早世
松本勘兵衛清房妻 早世
![]()
![]() 松次郎 法名了香童子
松次郎 法名了香童子
加兵衛(養子) 作重郎 實彌五兵衛嫡男 武兵衛号一無 浅二郎後武兵衛
![]()
![]()
![]()
![]() 高久 光氏 高次 高連
高久 光氏 高次 高連
實堀口氏二男
高山長五郎重業書系図 (昭和十年)
三本木村浦部元之助妻 高山 高山武十郎後妻
![]()
![]()
![]() 市川帯刀眞直妻 貞 才 シマ子
市川帯刀眞直妻 貞 才 シマ子
原生糸店勤務後渡米
![]() 民之助 八郎治 母砥沢市川半平二女 早世 辰吉
民之助 八郎治 母砥沢市川半平二女 早世 辰吉
![]()
![]()
![]() 早世 重明 武之助 金井 高山菊次郎妻
早世 重明 武之助 金井 高山菊次郎妻
![]()
![]()
![]() 女子 妻武州小平村根岸孫右衛門長女 さと
女子 妻武州小平村根岸孫右衛門長女 さと
小柴重太郎妻 吉田保之妻
![]()
![]()
![]() 嶋 美代(みゆう) 泰次郎 住東京
嶋 美代(みゆう) 泰次郎 住東京
右馬介改内藏之蒸六郎右衛門 出家武州長興寺
![]()
![]()
![]()
![]() 重簡 徳明 浦部助太郎妻(元之助舎弟) 三波川 飯塚時五郎妻 英治 改中浜光司住横浜
重簡 徳明 浦部助太郎妻(元之助舎弟) 三波川 飯塚時五郎妻 英治 改中浜光司住横浜
![]()
![]() 才 逸
才 逸
横浜原善三郎生糸問屋勤務
(謙治郎)右膳司 八郎左衛門 八郎右衛門 吉田市十郎宗戴妻 井出久定妻
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 重方 重基 代 濱 尚江
重方 重基 代 濱 尚江
継兄
砥澤村市川氏継 (武州下奈良村吉田嘉三郎妻)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 早世 泰吉 真太郎 光江 吉明 敏明 秀一郎
早世 泰吉 真太郎 光江 吉明 敏明 秀一郎
![]()
![]()
![]() 女子 方義 二十三歳卒 後児玉町小平村 根岸坦二妻
女子 方義 二十三歳卒 後児玉町小平村 根岸坦二妻
![]()
![]() 倉太郎 砥澤村 市川虎義妻 女子
倉太郎 砥澤村 市川虎義妻 女子
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 重義 光志 勝明
重義 光志 勝明
前原村松下氏継 西南役戦死
![]()
![]() 治平
治平
