|
海神・アマテラスの誕生
神話の舞台は黄泉の国出雲から一転、九州へと移っていく。イザナギは筑紫の日向に行き禊祓いをする、この橘の小戸の所在には諸説はあるが素直に読めば宮崎県になる。田中卓は綿津見の神と筒男命出現の所伝は架空の場所ではなく、現実に存在するある地点を中心に伝えられていたらしいと述べている。
宮崎県には信憑性はともかく、神話をそのままになぞる伝説地が全て完備されている。今も「橘」や「小戸」「阿波岐原」の地名が存在している。
梅原猛は宮崎市の橘や小戸の名前は古い地名であり、小戸は薩摩にあったとみられる綿津見の神の国との貿易港であったとみている。小戸神社はイザナギ・イザナミを祀っている古い由緒のある神社である。江田町にはやはりイザナギ・イザナミを祀る江田神社がある。
阿波岐原のあおき遺跡は日向でも突出して古く、出土物から弥生前期中期の遺跡であるとされる。このような状況からも、イザナギが禊祓いをし、三貴神が生まれた橘の小門は日向の宮崎市になろう。(天皇家のふるさと日向を行く)
江田神社の北に位置するところに、塩路の地名があり塩土の神との関連を窺わせる。さらにその北には住吉神社が鎮座している。
田中卓は禊祓いで生まれた綿津見神が、祀られている志賀海神社が筑前にあり、しかも社家は綿津見の神の後裔の安住氏であること。
更に住吉神社やヤソマガツヒの神、カムナオビの神、オホナオビの神が祭られている警固神社の存在などから博多・那珂川付近に求めている。安曇氏の本貫は筑前粕谷郡安曇郷であり、応神天皇の頃に畿内に進出した。禊祓いで生まれた綿津見の神と筒男命は共に神功皇后の新羅征討に加わっている。
この新羅征討の際に神功皇后は、博多湾で髪を洗い禊をしているが、イザナギが禊祓いした橘の小戸も北九州に比定できる。
皇后の新羅征討に参加した綿津見の神と筒男命の史実が、イザナギの禊祓いと両親の誕生に投影されている。(神話と史実))
田中卓はこの他にも幾重にも傍証を取り上げて、思わず納得してしまう見事な論理を展開している。
神皇正統記ではイザナギが禊をしたのは、日向の小戸の河・檍が原としている。福岡市の姪の浜に小戸神社がある、古田武彦はこの地をイザナギが禊をした地でありアマテラス誕生の地と論証している。
記・紀の記述からイザナギが禊祓いをして、三貴神が生まれた場所を探して特定する考証は楽しくもあるが、「筑紫日向」の日向は一定の場所ではなく、九州や日向などのどこかという意味に解する向きもある。
つまり日向の神話であるから名辞的な表現で「日向」とした、或いは日に向かう良い場所などの意で用いた表現とみる説である。同説に立てば現実の場所を探し求めることは無駄な事となる。
しかし様々な角度からその場所について考証を重ねることは、日向神話の根本を考えることであり、神話や古文献の理解を深めることにも繋がり意義のあることと思われる。
天照大神はアマテラスオオミカミと読まれているが、果たしてそう読んで正解なのだろうか。「アマテル」と読めば天が照り輝くという意味になる。天が照るに大神を繋いでいる。
この場合個人としての神を特定する固有名詞がなくなり、神名の中身が薄くなり、一般的な広い意味の太陽神・日神の意味で用いられていることになる。
現にアマテルと読む天照神社はいくつか現存している。弥生時代は文字通り太陽と共に生活していたのであろう。明るくなれば起きて活動を始めて、日が沈み暗くなれば家の中に入りやがて眠りについた。
日照時間により作物の出来不出来も決まり、猛獣からも守ってくれる太陽は自然と信仰の対象となったのであろう。太陽を神格化し神の名前として、皇祖神と一体のものに仕立てたと考えられなくはないか。
こうした太陽崇拝はインドネシアに広くみられるように、農耕民族により多く崇拝されていた。
また天照大神は「オオヒルメノムチ」とも呼ばれたと言われているが、オオは大きなという意味でムチは貴人という意味を持っている。そして残されたヒルメは「日の女」即ち巫女のことと解釈される。してみるとこの名前も「日を祀る偉大な巫女」という意味になり、個人名ではなくなってしまう。
オオヒルメノムチが一人しか居なかったという保証はなく、年月を隔ててオオヒルメノムチと呼ばれた人が他にも居た可能性が浮かび上がってくる。
播磨国風土記には、アマテラスが乗っている船に猪を献じる説話が乗っている。天神は天の磐船にのって天下って来たと古文献に散見され、このことは宇宙船でない限り海を渡って来た事を想定させるのである。
従って天とは空のことではなく、海の事と考えるのは必然の帰結であろう。アマテラス」もまた空を照らすのではなく、暗い海を照らすという意味に受け取れる。沿岸航法でも日が暮れた海を航海するのには危険が伴う。
当然照明が必要であり、そんな暗闇を照らす灯台のような効果を生む方法があれば神の助けとも思えたであろう。
そこで「海照らす大御神」となったかもしれない。古代氏族の多くが海部族の出自であることも何らかの関連性を持っているのだろう。アマテラスには太陽神のイメージが定着していることから、「天照す」といえば空が照っているかの如くの現象として捉えがちであった。
しかしアマテラスとは「晴れてる」という意味ではない。明らかに「天」を照らすということであろう。よく考えると空を照らすことなど出来はしない。東京タワーのライトアップでも、空のほんの一部しか光が当たっていない。
広大な空を広い範囲で照らし出すことは無理な事である。天上界から下界を照らすという意味だとしたら、表現は「天ヶ下(を)照らす・大神」とならなければおかしいのである。
上の数行を書いた数日後に似たような論説を目にすることになった。「日本神話と神々の謎」の中の一項目がそれである。この本は買っておいた物で、まだ目を通していないままだった。
この本ではアマテラスは元は海神であったとしている。やはり天照すの意味は元々は天を照らすためのものではなく、海を照らすものであったと述べている。そしてアマテラスという言葉自体は太陽神をあらわすものではないと言っている。
イザナギとイザナミは重要な神であるが、宮廷祭祀の中には現れず天皇家は両神を祀った形跡がない。朝廷は四、五世紀には三輪山の大物主を祀り、六世紀以降にはアマテラスを重んじていた。(武光誠)
言語学の立場から神名を考証している川崎真治は、対馬の「阿麻氐留神社」の名前を「アマテ」と助詞の「ル」であるとして、「ル」は「ノ」と同じと解釈できるという。この場合の「テ」は方角のテではなく、「先手」の手で広義には部族を指すと捉えている。
「アマ」は海人族となるとしている。この考証方式をアマテラスに当て嵌めることができるだろうか。やや強引に当て嵌めてみると「海人族のテラス」ということになろうか。テラスという名前は奇異にみえるが、それをさておくとアマテラスは海人族の支配者層であったことが想像できるのである。海を照らすように航路が読める、航路を知っている海人の代表、それがアマテラスだった。これは案外、当たらずとも遠からずの説となり得る。
三貴子の中の月読命は三神の中では一番影が薄い。月読命のエピソードは取ってつけたかのように一回しか語られていない。早くに亡くなってしまいこれといった事績がなかった為なのか。
それとも太陽と月として陰・陽を顕す必要から設定されたものなのか。ツクヨミとは月齢を読んだり、暦を数える事と言われている。山城国葛野郡の月読命は壱岐から勧請された神である。
この辺一帯は帰化人、秦氏の根拠地である。松前健は月読命は渡来人がもたらした亀卜の神だったようで、大陸的色彩が強い神であると論じている。
月読神社は壱岐や山城や伊勢などに存在している。松本清張はこのアマテラスと月読命の誕生話は、中国の「五運歴年記」の盤古の説話からとられたことは明らかであるという。
そこには「左眼は日となり、右眼は月となる」と記されている。月読命は月を読む神ではなく月そのものであるとしている。しかし同時に生まれたアマテラスは巫女をモデルにしているという。太陽(神)であるならば天地開闢の項に生まれていた筈であるとする。
ではなぜ、月である月読命は天地開闢の項で生まれていないのであろうか。松本はこの矛盾については何も語っていない。スサノオと月読命は同神であったとする説もある。紀の異伝には海原を治めるのは、スサノオとする伝と月読命とする伝の二つがある。
また記ではスサノオが大気都比売を殺しているが、紀では月読命が大気都比売と同神とみられる保食神を殺している。以上の二項目と先に述べた月読命の事績が殆どないことを考え合わせると、スサノオと月読命は同一人物であった可能性が高まってくる。
更に近江雅和はスサノオと月読命の、モデルであったらしい二神の話が「契丹古伝」の中に出ている事を紹介している。(逆説としての記・紀神話)
出雲の佐太神社に伝わる「佐陀大明神縁起」によると、天竺の鳩留国にあった小山が波に浮いて流れてきて、島根山になったという。
またイザナミは妊娠し、イザナギと別居して加賀潜戸に住み、この地でアマテラスを生んだ。そこの岩窟中に乳房の形の岩を作っておいた。イザナミが潜戸を出ないときは天下は暗く、潜戸を出ると天下は明るくなった。その時にイザナギが「嗚呼赫赫」と言ったので、その地は加賀となった。としている。他書には見ない不思議な伝えである。
新編古事記
イザナギは吾は汚い国に行ってしまったので、禊をすると言い筑紫の日向の橘の小門に阿波岐原に至り禊をした。杖を投げるとツキタツフナトの神になり、帯を投げるとミチノナガチワの神となり、袋を投げるとトキハカシの神が生まれた。
衣を投げるとワズライノウシの神となり、褌を投げると道俣神となり、冠を投げるとアキグイノウシの神となり、左の腕飾りを投げるとオキザカルの神、オキツナギサビコの神、オキツカイベラの神がうまれた。
右の腕飾りを投げるとヘザカルの神、ヘツナギサビコの神、ヘツカイベラの神が生まれ、ここに十二神の誕生となった。
体を洗うと穢れから、ヤソマガツヒの神、オオマガツヒの神が生まれ、次にカムナオビの神、オオナオビの神、イズノメの三神が生まれた。
水底からはソコツワタツミの神、ソコツツノオの命、中ほどからナカツワタツミの神、ナカツツノオの命が生まれた。
水の上からはウワツワタツミの神、ウワツツノオの命が生まれた。この三柱のワタツミの神は安曇の連の祖先である。
三柱の男神は住吉神社の三座の大神である。次に左の目を洗った時に天照大神。次に右の目を洗った時に月読命、鼻を洗った時にタケハヤスサノオノミコトが生まれた。
イザナギは天照大御神に汝は高天の原を統治せよといい、月読命に夜の食国を治めよ、スサノオに海原を治めよと指示した。
住吉大社神代記
ウワツツノオ、ナカツツノオ、ソコツツノオ、気息帯長足姫の、四神を祭神とする住吉大社が伝える住吉大社神代記は記・紀とならび重要な資料である。ウワツツノオ、ナカツツノオ、ソコツツノオ、三柱の神名は海の深さを象徴するような奇妙な名前の不思議な神である。
「ツツノオ」は津の男を言うとする説がある。三神が誕生したとき、それぞれの神とセット・ペアで生まれた綿津見三神は安曇氏の祖先とされ、住吉三神は住吉に祀られ子孫はいなかったことになっている。後に住吉三神は、神功皇后の新羅征討の際に託宣を下している。
綿津見の神三神は武光誠によると、奴国の航海民が祀っていたという。この三神は志賀島の志賀海神社に祀られている。同時にペアで双子のように生まれた六神のうち、三神が住吉大社に祀られ、三神は志賀海神社に祀られた訳である。なぜ引き裂かれて西と東に分かれることになったのかは謎である。
武光は綿津見三神と住吉三神は元々無関係であったが、安住氏が大阪湾の安曇に本拠地を移したことにより、兄弟とされるようになったとしている。住吉三神を祀る津守氏は長門から摂津に移り安曇氏の監督を受けた。
大和朝廷は四世紀の初頭に九州を制圧した。志賀島を本拠地とする航海民は大和側に従って安曇氏と呼ばれるようになった。安曇は「あまつみ」が訛ったものである。綿津見三神は元は一柱であったが三柱に変えられた。(日本神話と神々の謎)
神代記はそれまでに、大社に伝わっていた二つの書物を一つにまとめたものであるという。神代記は神代の誕生から筆を起こし、大筋では紀と軌を一にしているが、祭神の神宮皇后の記事に多くを割いている。
編纂したのは大社宮司家の津守氏であり、天平三年(731年)に奉られている。
したがって成立年度は更に遡り、大宝二年に原撰、養老三年勘注したものとされる。だが田中卓はその末文などから、更に古い斉明五年・659年にはある程度の形(旧記)が出来ていて、天平3年に言上されたと推考している。
これならば記・紀よりも古く最古の歴史書になってしまう。神代記には紀を参照し引用したと見られる個所もあることから、原資料はともかく編纂が終了したのは紀・紀の成立後まもなくのことであろう。
神代記の内容について、田中卓は紀にはない記事や表記が見られることから、津守家の独自の古伝が多く取り入れられたとみている。そして紀の方が神代記の原資料を参照したのではないかという。
神代記と記との関係では、記の文章は取り入れ、または引用されていない、記と一致しない内容もあり、構文・用字の点からも、両書の間に直接の史料的親子関係は全くないと断じている。しかしながら、紀と説を異にし、もしくは欠けている内容に関して、記と説を同じくする事例が少なからず存する、と分析している。(住吉大社神代記の研究)
最古の英雄スサノオ
「神皇紀」にはスサノオの元の名は「多加王」であったと記され、タカミムスビの曾孫となっているが父名の記載はない。豊阿始原を占領するべく、大陸から千三百人余を率いて高天原へ攻め込んだという。この時に大巳貴命は八千人の軍勢を編成してスサノオ軍を皆殺しにしたとしている。
アマテラスは多加王を出雲に追放し、スサノオは出雲を平定した。スサノオは作らせた剣、鏡、置物を持って各地に巡行し、平定した後に剣をアマテラスに奉じた。アマテラスは多加王に「スサノオ」の名前を与えた。(古代文書の謎)
三輪高宮家系譜によるとスサノオは、紀伊国牟婁郡熊野大神なりとして、またの名を八束水臣津野神としている。八束水臣津野神は記紀には表れないが、風土記において出雲の国引きをした神として有名である。
記・紀では同神の功績などをスサノオに転化したものなのか。同系譜では更にスサノオの別名を、遊美豆奴神、熊野加夫呂神、熊野加夫呂神櫛御気野神、気都御子神と伝えている。「出雲国造神賀詞」では熊野大神(櫛御気野神)を「いざなきの日まな子」と呼んでおり、イザナギの子スサノオと同神と分かる。
記ではスサノオノミコトは出雲勢力の代表・首長として描かれている。「須佐」の地名は今も島根県に存在する他、スサノオノミコトを祀る「須佐神社」は同地に数多くある。「須佐の男」にミコトをつけ名前としているのは、明らかに天孫族の対抗勢力と解るように設定したかのようでもある。
スサノオが渡来神であったかどうかはともかくとして、出雲国風土記には同神の伝承が豊富に語られている他、記紀に現れない同神の子の名前が幾つも記されている。
このことはスサノオが出雲の地方神、或いは出雲に先着した神であったことを窺わせる。
スサノオの影響力下にあったのは出雲を始めとして、大和や北九州に亘る広大なものであったとも考えられる。大和にも「出雲」の地名がある上、出雲神社が幾つもある。スサノオは息子と共に新羅に行き、暫くソシモリに居たとの伝承もあり、新羅や北九州に縁が深いことが窺われる。スサノオノミコトの娘である三女神も宗像大社に祀られている。
関係は不明だが、松江市の忌部神社の「忌部大宮濫觴記」には「韓山」の地名も見えている。紀の一書では、熊成の峯から根の国に渡ったと記載している。この熊成は朝鮮の地とみられ、任那の熊川もしくは百済の熊津は、いずれも古くは久麻那利と呼ばれていた。
松前健はスサノオと朝鮮との結びつきが深いことは認めるが、スサノオの前身が全くの渡来神とすることには疑問を持っているという。スサノオと韓土の結びつきは5~6世紀の頃、盛んに韓土と往来し交易や征討に従事した紀伊の海人の活動によるとしている。
また「宇佐宮劔玉集」には、豊葦原中国之宇佐嶋は云々、スサノオは天降りて筑紫宇佐州に居て、今の小椋山の頂に大神として祭られたとしている。このスサノオの治める芦原中津国に、アマテラスは天のオシホミミや天のホヒノカミ等の征討軍を次々に送り込んで来たようだ。
スサノオは原出雲系の神ではなく、朝鮮半島から渡来した神であるとする説も多く唱えられている。一名を牛頭天皇といい、紀が朝鮮のソシモリに行ったと記す、その「ソ」とは古代朝鮮語で牛のことだという。
ソシモリとは江原道・春川府牛頭州のことで、ここに牛頭山がる。京都八坂神社の社伝では、」斉明天皇二年に新羅の牛頭山からスサノオの神霊を迎えて祀ったとしている。石見で「韓」ないし「辛」の字がつく地名のところには、必ずと言ってよいほどスサノオ伝承がある。
とすると何故大国主と結びつけ、その祖先としたのか、考証を急がねばならぬ。出雲国風土記ではスサノオは侵略者とし登場している。
スサノオは牛族でその神紋は十字紋であった。播磨国風土記に新良訓と名づくるは新羅の人来て、新良訓と名付けた。山の名前も同じ。とあり白国神社には牛頭天皇(スサノオ)を祀っている。
大国主の末裔・富氏の伝承では、同氏の祖神はクナトの大神で何世かの後に大国主があり、また何世かの後に富のナガスネヒコや伊勢津日子に繋がっている。出雲の熊野神社にはクナトの神を祀っていたが、後に全国の熊野神社と共に祭神はスサノオに変えられてしまった。(記紀解体)
クナトの神との関係は不明であるが、「クナト」とは「来な」と「門」を合わせたもので、悪いものが入ってくることを防ぐ門の役目を持つ者を指すという。この点、道祖神信仰に繋がるものとみられる。衝立船戸神の船戸はクナトが訛ったものと言われている。
スサノオはアマテラスの元では乱暴者の悪神であるが、出雲に行ってからは民衆のヒーローになっており、正と悪の二面性を持っている。出雲風土記では大衆の中に溶け込んだ平和の神として描かれている。
この二重人格のような矛盾について、松前健は全く別な二つの神格が結びつけられた同一神と考える。スサノオは出雲や紀伊で祀られた地方神で本来は平和な神であったという。
彼が犯した悪行は後世の大祓に、列挙される罪の名と同じである事から、この悪い事をする例(者)としてスサノオが挙げられたとみているようだ。つまり悪のキャラクターとしての役割を担わせられている。
松前は出雲の東西各地にスサノオの崇拝や口碑があり、その崇拝は紀伊、備後、播磨、隠岐などの広い領域で行われていたとしている。紀伊国在田郡の名神大社「須佐神社」がスサノオの原郷ではないだろうかと言っている。
スサノオは高天原から根の国へ行き支配者となった。その足跡は韓半島にも及び、韓の神とも出雲の神とも言われている。スサノオは須佐の男であり、この名前だけを取れば文字通り須佐(出雲)の男である。
古事記の言うところの建速須佐之男命の建は勇猛な意味の籠められた敬称であり、速も同様の接頭語とみられる。
書紀の第一の一書にはスサノオの子は清(すが)の湯山主三名狭漏彦八島野であり、この神の五世孫が大国主命であると記している。この伝承は須佐神社資料と一致している。
清(すが)は須賀の宮・須我山(川)に通じ、ここにスサノオと出雲との関わりが色濃く反映されている。スサノオの足跡を線で綴ると韓半島からの航路となり、渡来人の足跡とも重なるようだ。
新編古事記
スサノオノミコトは指示された国の統治をせずに、その髭が長くなり胸元に垂れる頃になっても泣いていた。
その泣く事により青山を枯らし川や海は干上がり、悪い神が台頭し蠅の大軍が現れ様々な災い事が起こった。
イザナギが理由を問いただすと、スサノオは母の根の堅州国に行きたいのだと答えた。イザナギは怒って、ではこの国には住むなと言って追放した。
そのイザナギは死去して今、近江の多賀神社に祀られて居る。
スサノオ軍が迫ってきた時、高天原の山川は揺り動き国土は振動した。アマテラスはスサノオが吾国土を奪う積りに違いないと言った。髪を解いて男髪のみずらに結い、左右のみずらとみかずらにも左右の手にも八尺の勾玉を多く巻き、背に大きな矢筒を負い脇にも矢筒をつけ、左の手に鞆をつけ武装した。
弓をふりたてて庭の土を踏みしめ、淡雪を蹴散らし雄叫びを上げ、すっかり戦の準備を整えてスサノオを待ち構えた。
天の安河の停戦交渉
人類の祖先神イザナギはここに亡くなり、これ以上登場する事はなくなるがその御陵については詳しく触れられてはいない。記では淡海(近江)の多賀としているが、紀ではイザナギの御陵は淡路としており、淡路島の神話・海人族の伝承が浮かび上がって来る。
松前健は近江の社は古い記録に見えず、延喜式では小社となっているとして、イザナギは5、6世紀頃は単なる島の神であり、皇室との関係はなかったであろうと言っている。
イザナギの陵については宮内庁が作成した「陵墓要覧」にも記載がない。イザナギは神代の神様であったから当然の措置か。
「陵墓要覧」の陵墓の記載・位置などは、降臨してきたニニギノミコトから始まっている。高天原は記・紀に記載記事の状況証拠から、必然的に北九州・博多湾付近に比定することができる。田中卓も高天原は筑後国山門郡の辺りにあったと論じている。
それを原ヤマト国と呼び、その本拠地から移転したのが皇室の祖先であり、九州に留まったのが後の邪馬台国であると推考している。
「秀真伝」では高天原を仙台地方にあったとしている。神代文字で書かれている同書を論じる学者は殆どと言ってよい程いない。また同書はアマテラスを男神として12人の妃があったと述べている。
北九州の沖ノ島の近くの大島には宗像神社中津宮がある。ここには天の川と天の真名井があり、神官は天の真名井で禊をしている。天の川の両岸にはそれぞれ牽牛、織姫を祭る神社がある。
七夕祭りの時に男女の出会いの場所となる。これらの事柄はスサノオとアマテラスの誓約の場面に酷似している。(神々の流竄)アマテラスとスサノオは誓約して子を作ったとあり、両神は一時期夫婦の関係にあったと考えられる。
二ギハヤヒの項で後述する熊野連の和田家系図には、熊野加夫呂櫛御気野命とアマテラスの二人は姉弟であり、夫婦であり天忍穂耳命を産んだと記されている。神皇正統記によると、安河の誓約でスサノオは「まさやあれかちぬ」と言ったとしている。
新編古事記
アマテラスの高天原に征西軍を率いて到着したスサノオは、高天原軍と対峙し優勢のうちに小競り合いを繰り返した。この戦いは長びき、高天原の田畑は荒れて農民は戦に駆り出され収穫も出来ない状態に陥った。
アマテラスは降伏を申し出た。スサノオは高天原人心の掌握のためアマテラスを妃に迎えた。スサノオは十握剣をアマテラスに献上し、アマテラスは八尺の勾玉、みすまるの玉を差し出して交換とした。
二神は天の安河の近く、天の真名井に宮を建てて住まいとした。やがて生まれた神は多紀理姫命、またの名は奥津島姫命、次に市寸島姫命、またの名を狭依姫命、次に多岐都姫命が生まれた。
また次に正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命、天之菩卑能命、天津日子根命が生まれた。
更に活津日子根命、熊野久須毘命の二神が生まれた。
多紀理姫命は今宗像の沖津宮に祀られ、市寸島姫命は宗像の中津宮に祀られ、多岐都姫命は宗像の辺津宮に祀られている。
三柱の神は宗像の君の祖先である。多岐都姫命の子の建比良鳥命は出雲国造、武蔵国造、上総国造、下総国造、対馬県直、遠江国造などの祖先である。天津日子根命は紀の国造、倭の田中直等の祖先である。
スサノオノミコトの勝利
天の安河の誓約で、スサノオの物実であるとされた十握の剣とは精子を象徴しているように思われる。スサノオの種を貰って生んだのが三女神ということになる。その後生まれたのが五男神である。
この勝利により、三女神が祭られている宗像の辺津宮、沖ノ島と韓半島へ続く壱岐をスサノオが領有することになったのではないか。宗像氏はスサノオの後裔三輪氏と同族である。
スサノオは、出雲の支配地を侵食するアマテラス軍を放逐するべく、北九州に大軍を持って上陸した。戦いに勝利したスサノオは妻問いの慣例に従って、敗軍の旗印となっていたアマテラスを娶って妻とした。
こうすることによって完全制圧するのではなく、吸収合併した形を取り一体となり領土を一緒に統治する姿勢を領民に見せることが必要だったのであろう。
「新編古事記」
侵略戦争に勝利したスサノオは慣例により、当地支配者層の娘アマテラスを妃にして、高天原の統治・経営に専念した。だが農民は静かな抵抗を続け統治はうまくいかなかった。
スサノオは見せしめとして、抵抗した農民の田の畦を切り離し溝を埋めた。アマテラスは、神事だけを司る立場に追いやられ咎め立ては出来なかった。スサノオの悪行はやまず、アマテラスが機屋で機を織っているときに、屋根に穴を開け斑馬を投げ込んだ。
機を織っていた織女は驚いて杼にホトを付いて死んでしまった。やがて水面下で、勢力を立て直していた高天原の高木神の策略によって、出雲へと撤退せざるを得なくなった。スサノオは出雲を経由して、紀伊に入り山の権利を掌握し支配した。スサノオが親権をとった三女神は北九州に残り、後に宗像神社や沖ノ島に祀られた。
天の石屋戸隠れ説話
アマテラスが石屋戸に籠ってしまい、世の中は真っ暗になってしまった。研究者によるとこの頃に日食があったという。祭祀の途中に日食が始まった事があり、これが一部に伝承されていたのではなかったか。
そして古事記編纂の際に、アマテラスと日食とを結び付けられるストーリーになった可能性が高い。この日食神話のモチーフは西はインド、東はカリフオルニアにまで及んでいるという。特に内容が似ているのは中国南部からインドアッサムにかけての地域の神話である
この他、天の石屋戸神話を、鎮魂祭(みたましずめまつり)・冬至の祭りであったとみる説も古くから存在している。
田中卓は天の磐戸隠れはスサノオ等の、オオナムチ系氏族に対する大和朝廷側の敗北という史的事実が投影されている史的神話である。
大巳貴命系氏族の元来の本拠地は畿内・大和を中心としていたらしい。このことは大物主を含む三輪山と畿内の信仰と伝承が、この氏族と密接に結びついている。神武天皇の東征により出雲へ敗退・転出したとみられると言っている。
この説に従えば時代は遡るが、スサノオが出雲斐の川上に降臨したことと辻褄が合うことになる。
アマテラスの別名は大日女命とされているが、この名前は当然のように今まで太陽・日神を祀る祭祀を司ることによると考えられていた。しかし中国の南朝の最後の大王陳の娘の名前が大比留女だという。
このことからは何が考えられるのだろう。単なる偶然なのか。それとも日本語読みが全く同じ名前なので何らかの関連があるのだろうか。
鹿児島県隼人町の鹿児島神宮の縁起によると、大比留女は七歳で懐妊し生んだ男の子が二歳の時に自分は八幡だと名乗った。
後に母子を船に乗せて流したところ、大隅の海岸に流れ着いたという。大比留女は日本に来ていたということになる。(海を渡った人びと)
渡来伝説といえば、徐福は秦の始皇帝の命によって前210年頃、三千人の男女を引き連れて渡来したという。五穀の種も持参して辿り着き王になったが帰国はしなかったとされる。
日本各地には徐福の墓や伝説が残っている。船が難破したとしても千五百人くらいは日本にたどり着いた可能性がある。
アマテラスは男神であったと唱えているのは、津田左右吉や折口信夫であるが、この説にもそれなりの理由が存在している。折口は「日女」は「日妻」であるとして、即ち太陽神の妻であるという。
アマテラス男神に仕える巫女がヒルメであり、代々の巫女のイメージが祭神の姿に重なり、いつしか巫女がアマテラスになったと考証している。仕える者が主の名前で呼ばれることはままある事である。ある神を奉じて戦う武将や氏族が、年月を経るとその代表としての神の名前で伝承されていくこともある。
神事などでの巫女の振る舞いは一種神秘的に見えるものであり、神意を告げる巫女そのものが次第に神へと昇格していった可能性は十分存在している。
敏達紀には宮廷内に日祀部を設置したと記載されている。これは神祗官以前の宮廷の祭官であり、太陽神の祭祀を司ると言われている。
敏達帝の宮があった大和の他田には、他田坐天照御魂神社があるがその祭神は天照御魂・火明命である。アマテラス男神説はこれらの内容とは混同していないであろうか。
松前健はこれらのことから、敏達帝当時の宮廷にアマテラス崇拝はなかったと言っている。また上田正昭は伊勢の渡会氏の奉じる日神の地に、皇祖神アマテラスを祀ったのは伊勢と宮廷の交渉の記事の多い雄略朝であろうという。
松前はこの説を肯定し、最初は守護神程度に祀った時期が長く続き、継体朝頃から中臣氏や忌部氏を送り込み皇祖神化していったとみている。(日本神話の謎)
アマテラスが岩屋に隠れて、世の中が真っ暗になったとする現象をアマテラスの死、或いは一度死んで復活する儀式と捉える論者も少なくない。松前健はアマテラスの岩屋戸隠れは「死」を象徴するものであったらしいという。
実際に紀の一書では、機屋の中で杼にホトを付いて死んだのはアマテラスであったとしている。
鎌倉時代の「年中行事秘抄」の神楽歌を見ると、日神の死が歌われており、冬至には太陽が一旦死んで生まれ変わるというのは、世界的な信仰であるとしている。(日本神話の謎)
吉田大洋はアマテラスという神はいなかったと断じている。延喜神明式によると、宮中で祀っている神は、ムスビ系の八神でありアマテラスやスサノオはいない。伊勢神宮におけるもっとも重要な、新嘗祭の祭儀は豊受の神を祀る外宮優先である。アマテラスが伊勢の神となったのはかなり後世であり、神宮の形を整えた天武天皇の頃であるという。
松前健の主張でも、宮中のアマテラス祭祀は固有と思われるものは一つもなく、みな後世、ずっと後の平安時代になって神話の影響などにより成立したものである。としている。(謎の出雲帝国)
アマテラスが、古くから宮廷内に祀られていたという証拠は何一つなく、アマテラスに天皇が礼拝するなどは平安時代中葉に始まった。タカミムスビは八神殿の主神として古くから宮廷に祀られていた。
この八神はタカミムスビ、カミムスビ、イクムスビ、タルムスビ、タマツメムスビ、ミケツカミ、オホミヤノメ、コトシロヌシで天皇の守り神であり、鎮魂祭や祈年祭、月次祭などにも祀られた。タカミムスビとは本来、田の傍らに立てた神木に降臨する田の神なのである。(日本神話の謎)
住吉大社では今も天の香山の埴土を取りに行く行為を続けている。もっとも、江戸時代以降は天の香山から畝傍山に変更されている。(住吉大社神代記の研究)
出雲の佐太神社に伝わる「佐陀大明神縁起」よると、天竺の鳩留国にあった小山が波に浮いて流れてきて、島根山になったという。
またイザナミは妊娠し、イザナギと別居して加賀潜戸に住み、この地でアマテラスを生んだ。そこの岩窟中に乳房の形の岩を作っておいた。イザナミが潜戸を出ないときは天下は暗く、潜戸を出ると天下は明るくなった。
その時にイザナギが「嗚呼赫赫」と言ったので、その地は加賀となった。としている。他書には見ない不思議な伝えである。
古田武彦は、高天原を紀の一書日本旧記にある「天国」として、その領域を北九州の北方、日本海中の対馬を含む島々であったとする。天石屋戸は「天国」の中心に位置していて、全島岩で覆われている沖の島と断じている。
新編古事記
アマテラスはスサノオ軍と戦った際に、傷を負いその後遺症が元で死んでしまった。
天の石屋戸を開き一時その中に埋葬した。高天原の人心は暗く沈んでしまった。毎日民衆のさざめきは蠅の大群のようになり様々な犯罪が起こった。長老たちは天の安河に集まり、アマテラス復活の祭祀・儀式の段取りを相談した。
タカミムスビの子のオモイカネが指揮を執ることになった。鶏を集め鳴かして、天の安河の川上の天の堅石と天の金山の鉄を取って、鍛冶のアマツマラに鏡を作らせ、タマノオヤに八坂の勾玉の御すまるの玉を作らせた。
アメノコヤネ・フトダマに天の香具山の、鹿の肩骨と波波迦木を採って占なわせた。
天の香具山の真賢木を根こそぎとって、上の枝に八坂の勾玉の御すまるの玉を架け、中枝に八尺の鏡を架け下枝に白丹寸手・青丹寸手を架けた。
これ等をフトダマが持ち、アメノコヤネが祝詞を称えアメノタジカラオは石屋戸の脇に隠れ、アメノウズメが天の香具山の蔓を架けて、天の真折を葛として、天の香具山の笹葉を結って石屋戸の前に桶を伏せて踏み鳴らした。
神がかりして乳房をむき出して、衣を臍の下まではだけて踊り続けた。人々は笑い、二代目のアマテラスが石屋戸から覗いた時に、タジカラオが手を取り一気にアマテラスを引き出した。
すかさずフトダマがその後方に縄を張り巡らした。人々の顔は明るくなった。長老はスサノオの髭と手足の爪を切り武器を取り上げて新羅へと追放した。スサノオは息子のイタケルとともにしばらく新羅のソシモリにいたが、なかなか勢力を伸ばせないので出雲へ帰った。
イタケルは新羅から多くの樹種を持ち帰り、筑紫から大八島にまで播いてことごとく青山にしてしまった。楠や杉檜槇等の木がそれである。このことからイタケルはイサオシの神と及ばれ、紀の国、伊太祁曽神社に大神として祀られた。この後アマテラスは高木神と結婚し、二人で様々な命令を出し国土の発展と経営に努めた。やがてアマテラスは日神の祀りごとに専念するようになり、オオヒルメノムチと呼ばれ政治・行政面は高木神が務めるようになった。
五穀の起源
追放されたスサノオがいきなり大気都姫に会うシーンから始まる。伊手至(古事記・角川)は後から挿入した説話かと言っている。
むろん古事記は一つの伝承・歴史だけではなく、各地に伝わる色々な伝承をモザイクのように織り込んでいる。当然天皇家に関係のない伝承をも、いかにも関係あるかのようにそれらしく記述して構成しているのである。
どの箇所が皇室・系譜に関係のない挿入なのか慎重に見極めなければならない。
スサノオは書紀では海原ではなく根の国を治めよとなっている。スサノオはアマテラス以前に漢半島から来て出雲を支配していたと考えられる。越に出雲の神々が式内社として祭られており、出雲の支配地域ないしは影響力を及ぼしていたのは、越から北九州福岡の沿岸地域(大和を除き)までのエリアとみられる。
沿岸航法で小さな船でも往来できる日本海沿岸の地域である。
後に進入してきたアマテラスは北九州で勢力を拡大し続けていた。新撰姓氏録には宗像氏は、「大国主の六世孫の吾多片隅命の後なり、大三輪朝臣と同祖」と記されている。
しからば、出雲系のスサノオの子である三女神を祀っていても違和感なくとらえられる。また宗像大菩薩縁起には出雲簸河上より筑紫宗像に移ると記されている。(神話と史実)
これに対しスサノオは出雲から進軍して反攻を試みて一時は勝利を収めた。アマテラスの直轄地まで支配する勢いだったが、施政・行政に失敗し民衆の反感には抗えずまた出雲へと撤退したのではなかったか。
この時にスサノオは屈辱的な降伏の条件を呑み、携えていた草薙の剣をアマテラスと高木に簒奪された。スサノオと大気都姫の説話は、書紀では月読命と保食神との物語になっている。
新編古事記
撃退されたスサノオは、出雲へと帰還する途中で会った大気都比売神に食物を乞う。比売はスサノオの汚さを詰って食べ物を与えなかった。スサノオは怒って大気都比売を殺した。
大気都比売を埋葬したその土地からは、小豆や大豆が取れるようになりカミムスビが種を保存・利用するようになった。また後には粟や麦や稲が生産されるようになった。
ヤマタノオロチ伝説
出雲系神話か。島根県大原郡大東町須賀にスサノオと稲田姫を祭る須賀神社がある。櫛名田比売と少し名前が違うが「櫛」は「奇し」で尊い・神秘的という意味の美称であろう。
ヤマタノオロチ退治の説話は、勿論大蛇を退治した時の伝承ではない。出雲の斐伊川流域には古くから蛇神信仰があった。斐伊川の川の神は肥長比売であり、蛇の化身であったとする伝承もある。渓谷には蛇が多く棲息し山や田で作業している村人を害し恐れられていた。
こうした危険な動物を恐れ敬い、祟りのないように守り神として祀ったのである。古事記では高志のヤマタノオロチとしているが、これは勿論「越」ではない。越との間には鳥取や福井もありいかにも遠すぎる。出雲市に古志町があり、ここなら斐伊川とはさほど遠くない距離となるが…。
福井県三国町に河口を持つ九頭竜川の上流に日野川がある。日野川は鯖江市の西方に位置するが、ここに八岐大蛇伝説があるという。九頭竜川は文字通り九つの頭を持つ竜であるが、名前のようにたくさんの支流をもっている。ちなみにこの近くには越廼村(こしの)や国見岳の地名が残っている。
オロチの形は背に桧・杉が生え、体長は八谷・八峡に亘るとある事からやはり谷川のイメージを表現したものであろう。水田の生命線となる川が急流であり治水が難しかったと思われる。
ヤマタノオロチの神話はギリシャの「ペルセウスーアンドロメダ神話」と言われる。大蛇と処女の人身御供の話であり、若者が大蛇を退治するというもので非常によく似たストーリーになっている。
中国南部やインドネシアにもこれとよく見た神話が伝えられている。田中卓は八岐大蛇退治の神話を、出雲風土記に見える、大巳貴が越の八口一族(あるいは川の激流)を平定した話と捉えている。この卓越した推論には諸手を挙げて賛意を表したいと思う。
「豊受太神宮禰宜補任次第」には、越国の荒ぶる凶賊阿彦を平定するために標剣
を賜って出征したと伝えられている、大若子命の祖先が天牟羅雲命であるとされている。(伊勢神宮の創祀と発展)また出雲国風土記にある大国主が越の八口を討った話を、記の編纂者が八十神に変えたと言うのは武光誠である。
梅原猛はオロチ伝説の土地は大和である。三輪山の神は蛇であり、大蛇はこの三輪山のシンボルとして書かれている。三輪山にはいまでも全山に酒が供えられている。そして大蛇は大巳貴のイメージであり、大蛇の死は大巳貴の死であるとする。
草薙の剣は三輪山のふもとに居たナガスネヒコが持っていたものとしている。
新編古事記
一度は高天原に攻め込み、天の安河で勝利をものにしたものの、次第にスサノオ一族は高天原勢力に筑紫を追われて出雲へと撤退を余儀なくされた。
出雲には越の八口一族が収穫物の簒奪を狙って季節ごとに襲撃して来ていた。スサノオ一族の大巳貴がこれを征伐するべく部下を引き連れて、出雲の肥上の河上の鳥髪の集落に来た。そこで泣いている老人夫婦と少女に会った。老父は土地の豪族オオヤマツミの子でアシナズチ、妻はテナズチ、娘は奇稲田姫と名乗った。
老父は年毎に越の山賊八口が来て、今年も収穫の時期になり山賊が来る頃になったので困っているという。
八口の目は酒に酔って血の如くで、腹は常に血にただれていると言う。大巳貴は助けてやるから、汝の娘をくれないかと持ちかけると老夫婦は承諾した。大巳貴は少女を櫛に変身させおのが鬟に差した。
大巳貴はアシナズチに強い酒を造らせて八口を宴会で歓待させた。八口は酒を飲み酔って寝てしまった。この時、大巳貴は十握剣を抜いて八口を斬った。
八口の持ち物の中から、つむはの大刀が見つかった。後に言う草薙の大刀がこれである。大巳貴は「須賀」に到りその地に宮を建て、アシナズチに「稲田の宮主」「須賀之八耳」の名を与え仕えさせた。
スサノオの神裔
スサノオは土地の豪族の娘、櫛稲田姫と結婚した。この地に水田があったことを窺わせる名前である。稲田に櫛を冠しただけなので、個人を特定する固有名詞のようなものは見当たらない。
スサノオとは関係が深い熊野三山の「新宮神社考定」には、イザナギの日真名子、加夫呂伎熊野大神、櫛御気命、出雲風土記に熊野加武呂之命とあるこれなり、と出ている。
そしてスサノオの別名は熊野坐神、家津御子大神、櫛御気野命とも称え奉られていたとしている。この伝承は三輪高宮家系譜を裏付けるものであり、相互に傍証を形成している。
出雲と紀伊の類似神社
|
出雲国
|
紀伊国
|
|
名神大社 熊野坐神社
|
名神大社 熊野坐神社
|
|
名神大社 速玉神社
|
大社 熊野速玉神社
|
|
須佐神社
|
名神大社 須佐神社
|
|
加多神社
|
加太神社
|
|
神社坐韓国伊太氐神社
|
名神大社 伊達神社
|
大国主は記の系譜上では、スサノオの六世の孫となっているが二人は何故か同世代として行動している。
紀によれば大国主はスサノオの子供である。(第二の一書では六世となっている)また出雲国須佐の国造家の末裔で須佐神社の宮司家・須佐家の系図では大国主はスサノオの孫になっている。(吉田大洋)
三輪高宮家系譜では、大国主はスサノオの子供となっている。そして他所には見えない大国主の別名を次のように記している。「八島士奴美神、三穂津彦神、玉垂彦神、今三輪大神是也」
この他、記では大国主の子となっている八重事代主は、高宮系譜では孫と記載されている。不思議な事に、記も同系譜も母は共に神屋楯比売命(神)としている。
よりしっくりはまるのは高宮系譜の方となる。もっとも同系譜では事代主が二代続いている。また大田々根子命は記では大物主の五世になっているが、同系譜では十二世(十世)になっている。
血統をより有益なものに糊塗することもなく、その間に六世代もの名前を入れていることが却って系譜の信憑性を高めているようである。
同系譜には建甕槌命の名が現われており、記に登場する建御雷と同名であるが世代的にはかなりのギャップがある。表記の用字は異なるものの「タケミカズチ」と六音までもが同じということは、どう見ても同一人と思えてくる。
大物主を祀る由緒作りに気を取られすぎて、別の名前を付けるのを疎かにしてしまったのだろうか。
いずれにしても高宮系譜は各当主の名前にも欠損がなく、別名や母親の名前も記されていて明治まで連綿と続いている。
何回も紙幅を加え書き継がれたと思われ、全く遺漏がない完璧な系図に仕立てられている。何はともあれ宇佐郡菱形山「比義」など、重要な名前が多く含まれており更なる研究と考証が必要であろう。
三輪高宮家系譜を整理して要点だけを次に掲げる。
三輪高宮家系譜
 建速素盞烏命 建速素盞烏命
 大国主 (和魂大物主神 荒魂大国魂神) 大国主 (和魂大物主神 荒魂大国魂神)
 味鉏高日子根命 味鉏高日子根命
 都美波八重事代主 (猿田日彦神・大物主神) 都美波八重事代主 (猿田日彦神・大物主神)
 天事代主籤入彦命 (事代主 玉櫛彦命) 天事代主籤入彦命 (事代主 玉櫛彦命)
 奇日方天日方命 奇日方天日方命
 飯肩巣見命 飯肩巣見命
 建甕尻命 (建瓶尻命 建甕槌命) 建甕尻命 (建瓶尻命 建甕槌命)
豊御気主命
 建飯賀田須命 (建甕槌命) 建飯賀田須命 (建甕槌命)
大田々根子命 (大直禰古命)
記の系譜にあるスサノオから、大国主の間に挟まれた五人の神は記紀上では殆ど記事に現れていないことから、この五世代は後にはめ込まれたとする説がある。(日本国家の成立と諸氏族)合理的な論理で納得できる説である。
しかし、ここに有力な反論がある。スサノオの系譜が記載されている、和銅元年(708年)の撰とされる「栗鹿大神元紀」によるものである。系図を文章で説明する書法には古くは二通りあったと田中卓はいう。
この読み方によって一番最初の語句を主客とするか、途中で随時主格が変ってゆくかの違いである。つまり前者の方式で読めば大国主はスサノオの六世になるが、後者の読み方で読めば、大国主はスサノオの子供になるとしている。これが二つの説の生じた理由であるという。
「栗鹿大神元紀」は用字法や形式に古形を残しており、なおかつ記・紀と類似の記事もあるが、記紀や旧事紀に伝えられていない神部氏の古伝をも伝えている。ちなみに同書に見える系譜文では、大国主はスサノオの六世である。この神部氏は祖を大国主として、大田田祢古命の後裔としている。
また因幡の「伊福部氏」の系図では、大巳貴はスサノオの子供とされている。また
饒速日は大巳貴の八世として記載されている。
ただ同氏の系図は綺麗に整理されていて、各世代の名前に遺漏がなく完璧なものになっていることが少し気になる点である。古い系図では海部氏系図と双璧とされている、和気氏の系図では所々虫食い状態のように名前が欠損している。そのことが却って古さを伝えているように思える。
スサノオの子・五十猛を葬った場所が、鬼神神社になり後に伊賀多気神社に移転したというのは「風土記鈔」である。(神々の里)
新編古事記
スサノオと奇稲田姫は、ヤシマジヌミを産んだ。スサノオとオオヤマツミの娘カムオオイチヒメとの間には、大年神、ウカノミタマが産まれた。
ヤシマジヌミはオオヤマツミの娘コノハナチルヤヒメをめとり、フワノモジクヌスヌを産んだ。
フワノモジクヌスヌとオカミの娘ヒカワヒメは、フカフチノミズヤレハナを産んだ。
フカフチノミズヤレハナはアメノツドヘチネを娶ってオミズヌを産んだ。オミズヌはフノズノの娘フテモミミを娶って、アメノフユキヌを産んだ。
アメノフユキヌが、サシクニオオの娘サシクニワカヒメを娶って産んだのは大国主、又の名は大巳貴又の名は葦原色許男、又の名は八千鉾、又の名は宇都志国玉といい五つの名有。
アマテラスとスサノオの人物像
天皇家の祖先とされるアマテラスではあるが、注意して記を読んでみるとその記事は驚くほど少ない。
|
アマテラス
|
スサノオ
|
|
日向の橘で誕生
|
日向の橘で誕生
|
|
スサノオを待ち受ける
|
海原へ行かずに泣いていた
|
|
天の安河で誓約
|
天の安河で誓約
|
|
服織りして後に天の岩屋籠り
|
田を荒らす
|
|
オシホミミ・次にホヒを降す
|
大気都比売を殺す
|
|
ワカヒコ・鳴女を降す
|
大蛇を退治する
|
|
タケミカズチを降す
|
大国主を苛めて後に許す
|
|
ニニギを降し宇受売に問わしむ
|
|
|
(高倉下の夢に現れる)
|
|
上記の表を見るとアマテラスの伝承は、ほんの僅かしかなかったことが窺われる。
独自の説話は訪ねてきたスサノオを、警戒しながら待ち受ける姿と服屋で服織りをしていたこと、天の岩屋に籠った事だけである。その他の説話は全て高木神と共同で行ったものである。
困ったことがあると隠れてしまう女らしい気の弱さ・気難しい一面を持っている他に、一朝事ある時には武装して戦陣に立ち、指揮を執る勇ましい面とをあわせもっている。だが作戦会議では配下の武将の意見を採用して、自分の意思を示さない優柔不断の側面をも有している。
人類の始祖神イザナギの子であることを除けば、普通のおばさんのようにも見える。占いを行ったこと、託宣を行ったことなどの神事に携わったことは一片も語られていない。
その事績や功績については一切記されていないことから、古事記著述以前にアマテラスのキャラクターや、ストーリーが設定されていなかったことが分かる。紀においても月読命を怒り別居したこと、稲を初めて植えたという事が述べられているが基本的な違いは見出せないようだ。
記の方が紀よりも古く素朴な伝承を伝えている、ということは多くの先学が言っている事である。古田武彦も紀にあって記にない記事は、大いなる疑いを持って臨むべしというような主旨を述べている。
こうした考え方を持っている論客は少なくないようだ。日本にいた先住の農耕民族が信仰していたのがアマテラスであり、後に渡来してきたのが高御産巣日神一族であるとする説がある。またその逆を唱える識者もいるが前者の説をとると違和感を感じない。
農耕民は太陽を軸として、日々の暮らしを立てている。その太陽の神が「天が照らす神」であり、やがてアマテラスと同一視されていき、太陽神とそれを祀る巫女と共にアマテラスと呼ばれていった可能性を考えたい。
ある時期から「アマテラス」は固有名詞ではなく、普通名詞となっていたかもしれないのである。
このことは大気都比売を殺したり、大蛇を退治して土地の人を助けたりしたスサノオとは対照的である。良いにしろ悪いにしろ、スサノオは活き活きとした説話となっているが、アマテラスに至っては一向にその人物像が伝わってこない。
松本清張はスサノオは狂言回しとして、無性格に作られている。記・紀の作者がスサノオに与えた役割はただ一つ、大巳貴の舅になることだけであったという。このようにスサノオが、天孫族と出雲を結びつける役割りを担ったと見る論者は少なくない。
アマテラス像は、はるか遠い過去の記憶の片隅、一握りの伝説を膨らませてようやっと、少しの物語を形作ったという印象が否めない。とても高貴な至高の極みにある天皇家の祖先とは到底眼に映じないのである。
このことは何を意味しているのだろうか。どこかの一地方に辛うじて、伝えられていた伝承だったのか、その土地の地神だったのか。古田武彦の言うように対馬の神様であったのか。
更なる探求が必要であるが、残念ながら今は詳らかにできない。松本清張はアマテラスは太陽神として、元々性別のなかったものを記・紀が構成される間に物語の都合次第で、男になったり女になったりしたと思うと述べている。
「アマテラス」の名前には「アマ」がついているが、高天原関連の名前には全て「アマ」がついている。アマを取れば「照らす」となり、行為か事物の神格化になりそうである。だとすると太陽の光を照らす鏡の神名化と考えられる。と言っている。(古代史疑)
武光誠は七世紀後半に天皇家はアマテラスを、国全体の守神として位置づけようとした。そのため「大宝律令」によって豪族たちが、アマテラスの祭祀に強制的に参加させられるようになったとしている。
アマテラスが始めて伊勢に移り住んだところはただの祠にすぎなかった。井上宏生は、天武とその妃・持統の時代になって皇祖神に昇格したと述べている。
由緒がいま一つはっきりしない「ホツマツタエ(秀真伝)」では、アマテラスは男神であり96カ月もイザナミの胎内にいたとしている。またスサノオは紀伊で生まれたと述べている。
同書ではイザナギの亡骸は淡路の伊佐奈伎神社に葬られ、その魂の緒が近江の多賀神社に戻ったとしている。更にニニキネが茨城県に最初の都を作り、後に富士山麓に広大な土地を開墾したとある。その関東の国を「ホツマの国」としている。
また宮下文書(徐福の項で後述する)にあっては、スサノオはタカミムスビの血統であり、大陸から眷族千三百人を引き連れてきて、瑞穂の国・高天原を占領しようとしたと述べている。
この時にアマテラスは山奥の岩穴に籠り、スサノオは大巳貴命によって捕縛され忠誠を誓い、出雲(隣国の信濃という)へ追放された。後に各地を平定し三種の神器を作りアマテラスに奉った。ちなみに同書では高天原は富士山の北麓にあったとしている。
スサノオは戸隠山で死去して、鳥上山に葬られたという。鈴木貞一はスサノオの陵を長野市の伊豆毛神社と想定している。
|
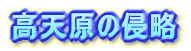 神々の降臨
神々の降臨










