| 〜GIFT〜TOPへ |
| 「亮輔〜!!」 相棒を追う拓真の後姿 そして追いかけられる亮輔を見守る日樹に懐かしい記憶が蘇る 今だからこそ客観的な自分の姿を見い出すことができ、 胸にきざみ付けられた、もはや塗り替えることはできない鮮烈な残像と重ね合わせる 芽吹いた若木は健やかに育つはずだった 見上げた蒼穹はどこまでも永遠に続くものだと信じていた だがそれは、摂理に背くことなく消え行くものだと あまりにも突然の出来事に受け入れ難かった 少年時代の一瞬を駆け抜けた 遥と過ごしたあの過ぎ去りし夏が再び |
 |
激暑(GEKISYO)2 晩夏、そして初秋へ・・・ |
| 教室でたったひとつ主のいなくなった机が ポツンと寂しげに物言わず存在している それは遥のものだった わかっていながら日樹は毎日その場所へ瞳を移す もしかしたら遥が戻ってくるかもしれない 気づいたら遥がそこに座ってこちらに笑いかけているかもしれない それなら見逃すことなく応えなければ 有り得もしないことに期待を持ちながら 何度も、何度も繰り返す 中学1年とはいえまだまだ子どもだった 願えば必ず叶うと心のどこかで信じていたのだから “またいつか逢えるよね” 小梶を通じて残していった遥の伝言が、小梶から遥の声に差し替えられて耳に残っていた 肌を射す強い陽差しも心なしか低く傾き、高くなったと感じられる空はもう秋の気配を運んでくる 孤独感に苛まれ、日樹は何もする気になれなかった 遥と一緒に通った美術室へも数日間足を運んでいない もともと自主性に任せた部活動 しかし日樹の傷心を思いやってか、部への出席を強要しなかった小梶がいよいよ日樹を誘った できるなら手を貸さず、自らの力で自身を再起させたかったが 繊細な少年には衝撃が大き過ぎたようで、時間に解決を任せるのはいよいよ無理であろうという判断を下したのだ 「放課後、私の処へいらっしゃい」 たまたま職員室で出くわした小梶にそう告げられたのが三日前のこと 約束通り美術室へ向おうとしていた日樹は 美術教室のある校舎手前の『風の広場』に差し掛かるとそこから足が進まなくなっていた 握り締めたこぶしを小さな体の胸元へ、そして瞳をかたく閉じた日樹 緑の木々は優しく日樹を迎えているのに ここまで何度も足を運びながら遥との想い出に押しつぶされそうになり、そこから引き返していた いっそこの木々の中に吸い込まれ、自分もここから消えてしまえば良い そうすれば遥のいる場所へ行かれる、そんな錯覚にも誘い入れられていた まして美術室には遥との想い出だらけだ たった一人の親友 遥がいなくなってしまった現実をまだ受け入れたくない、目を背けたいという気持ちが 今日も日樹を足止めする 戻ろう・・・ 「諸藤、待つんだ!」 踵を返した日樹を引き止めようとする声がした その声と声の主は“風の広場”を挟む一番北寄りの校舎、三階の美術教室からのものだった 見上げれば緑葉を縫い、開け広げた美術教室の窓に小梶の姿があったが 日樹と視線が合致してからすぐ、その姿はそこから消えていた 息を切らした小梶が日樹の目の前へ現れるまでに経過したのはわずかな時間 室内履きサンダルの足音を遠慮なしに廊下へ響かせ、 いつもなら生徒達に注意する 「廊下は走るな」 の決まり文句を無視し、 三階から一階までの階段を数段飛ばし、全力で走って来たからだ この数日、ここまで来ながら先に進めず引き返していた日樹 この機を逃せば二度と訪れて来なくなってしまうかもしれない 呼び止めたことが原因で、自分がたどり着くまでに立ち去ってしまうのではないか なんとしても掴まえなければと 切羽詰った小梶は形振りかまわず一気に駆け下りてきた 「諸藤・・・・・・・ハァ・・」 体力の無い体が情けない 三階からここまでの距離は美術教師の呼吸を乱すには十分だ 「先生・・・」 「来て・・・いたんだな・・・ここへ・・・・フゥ・・」 体育科の教師でもなければこうして全力疾走する機会もそうそうなかろう もしここで逃げ去られては、追いかける体力もわずかしか残っていない 小梶は日樹から目を離さず前屈みで息を整える |
待っていてくれて良かった・・・ 天に一度大きく息を吐き、やっと呼吸を落ち着かせた 「ここまで来ていたのに、引き返していたのか?」 どんな思いを抱き、ここで人知れず “風の広場” を見渡していたか 悲しげに伏せた日樹の瞳に小梶の胸がひどく締め付けられる 「・・・・・・」 ぎゅっと固く結んだ唇をかみ締め、微かに頷く日樹 小梶に言われた通り、毎日ここを訪れていながら遥との想い出が残る美術室までは足を踏み出せずにいた どんな些細なことでも全てが遥に結びついてしまう 日樹は遥がいなくなった事実を認めることに堪えられないのだ 悪い癖で、また手を差し伸べてしまう 教師が生徒に個人的思い入れを抱くのはあるまじき行為 だがそれは世間一般論 教師もただの人間、意識していながら境界線が途切れ、時にプライバシーに立ち入ってしまうこともある それが遥や日樹でないにしても 相手の痛み苦しみを受け入れてしまえば見過ごすわけにはいかない たとえ他の生徒であろうが、間違えなく同じような行動を起こしていただろう 特別扱いをしていたわけではない 入学当初から家庭の事情に苦悩していた遥の相談を受け 小さな胸に抱える不安を和らげ、精神的支えになれればと願っていたのに 結局は無力な自分が悔やまれてならない 日樹のことが “好き” だった 想いは届かないまま、答えは確かめないままで良いと最後まで強がっていた遥 遥に伝えてやりたい・・・ その答えはたった今、この目で己が確認したと “遥・・・、お前がいなくなってしまい、諸藤はこんなにも胸を痛めているんだ・・・” ずっと見守り続けていきたかった 彼らを守ることで、同時に自分が癒され救われていた 喪失感で溢れた心の渇きを潤す二人から得た心地良い時間を手放したくなかったのは自分かもしれない 神が引き逢わせてくれた純真無垢な二人は、天使のようだった 「諸藤、気づかなくてすまなかったな・・・」 そっと肩に触れた大きな手のひら 日樹を思いやる小梶の声はとても穏やかだ 初めて小梶の元を訪れた日樹は遥に手を引かれていた 人なつこく、いつもリードする遥の後を何も言わずにくっついていた 教師という立場は、しぐさや言動でその生徒の家庭状況がある程度推察できる この西蘭に入学するには並み以上の学力が要されるが、それもクリアし 少々内向的だが、何の不安もなく将来を約束されている良家の子息 それが日樹に対する小梶の印象だった まだまだ成長過程にある少年は、やがて幾多の挫折や経験を積み重ね一歩一歩、大人へと成長していくのだが 告知されていなかった親友との突然の別離は 覚悟の猶予もなく、あまりにも衝撃的な門出になってしまった 「私と一緒なら・・・大丈夫かな?」 自分と一緒なら美術教室まで踏み出せるかもしれない、と 小梶は日樹が自分に同意する確率に、ほぼゼロに近い確信しか持てないまま問いかけをしてみた “ 美術部を退部させてください ” もし、日樹がそう答えてしまえば 本人が選択することである以上、その先は強要できない 日樹の性格をふまえれば、こちらの確率がはるかに高く、 遥に続き日樹も自分の前から去ってしまうのでは寂しさが続き、小梶も痛手を受けることになる できればこの返事は聞きたくない しばらく間を置き、小梶へ瞳を向けた日樹はまだ影を帯びている ここを去るか・・・ 小梶の微かな期待が全くなくなった瞬間 嬉しくも予想は裏切られた “先生と一緒に・・・ 行きます” 別れを認めたくない、どこか逃避的な自分にも 事実を受け入れなければならないと、現実的な別の自分が存在する 何も告げずに行ってしまった遥の本心を知る手がかりを探すため 遥が日頃慕っていた小梶なら、自分の知らない遥のことまでも深く理解している そして彼が籍を置く美術教室、準備室には遥との想い出ばかり 何かを見つけられるかもしれない そう承知していながら、未熟な自分は足を運ぶことができなかった タイミング良く小梶が呼び止めてくれた以上、これを機にいよいよ自分が前に進まなければ そんな気がしてならならない 二人の足音は乱れず一定で廊下に反響する 階段を昇っていく小梶の足取りが少々滑稽な動きをするのは 先ほどの疾走で日頃使わない筋肉を驚かせてしまったからだろう その後ろ、距離を離さず日樹は追って行く 芸術家というのは気難しい人間が多いと思われる中 とつきにくい様子はなく、いつでも遥と自分を受け入れてくれた小梶の後姿が義兄、朋樹の姿に重なる 今は毎日顔を合わせることもなくなってしまった義兄と歳、背格好もちょうど同じようで 振り返っては日樹を気遣い笑顔を向ける小梶が、義兄のような錯覚を起こし その度に自分の目を疑った 北側に配置する階段は、踊場の窓から差し込む外光だけで日中の陽差しを受けることがないせいか、 心なし涼しく他との気温差を感じる 美術教室へ着くまで小梶は終始無言だった 遥がいなくなってしまってから初めて足を踏み入れる美術教室 心の準備をする間もなく、次々と視界に飛び込んでくる現実 教室後ろのロッカーに積み上げられたスケッチブックは 遥と一緒に覗き見しながら片付けた記憶がまだ鮮明だ 蘇る想い出が悲しみを充填させるばかりで 遥との別れは薄れるどころか、日ごと増して留まらない 遥と最後に過ごした日からまだ数日しか経っていないというのに、この教室が懐かしく感じてしまう 「さぁ・・・」 「・・は・・・い」 小梶に促され日樹は歩みだす 部員それぞれが自由な活動をしているせいか、今日もここ本拠地に誰一人としていなかった これで成り立つ部に、少々首を傾げたくなることもあったが かくて遥と二人で小梶を独占することができたのだ 静かな空間 いつものようにひょっこりと、遥が何処からか笑顔で顔を出しそうだ 『諸藤君っ!』 その声はもう聞こえるはずもないのに・・・ 笑顔の奥の悲しみを吐き出すことなく 遥はとうとう最後まで隠し通してしまったのだ もしわかっていたら・・・ 自分に何かできたのだろうか? 問いかけの答えを見つけようとすると 『これでいいんだよ』 触れて一瞬まとわり離れ過ぎていく風に、笑顔で黙した遥の幻影を見る 先ほど小梶が自分を呼び止めたと思われる窓辺に真っ直ぐ歩く 放課後、開け放たれた窓から入り込む風はどこか秋めいて そこからは緑の木々生い茂る “風の広場”が一望できた 見下ろす“風の広場” 遥が一番好きだったというこの場所 木々の影も長く伸び 季節は時間とともに少しずつ流れていることを知る 夏の間にグンと伸びた桐の葉が窓の下に、手を伸ばせば届くすぐそこに姿を見せている この階下の生物室はすっかり葉の陰に陽射しを遮られ 遮光カーテンも不要なぐらいに、ちょうど良い庇になっていることだろう 「二学期は行事が多いからな、いつまでも夏休み気分ではいられないぞ」 外の景色に見入る日樹の背中へ囁くと、続き部屋になっている準備室に姿を消した小梶 カチャカチャと音がするのは、食器棚からカップを出しているようだ ここに来る生徒に珈琲をもてなす 人生相談、心のケア、それが生徒達から慕われ信望の厚い小梶の日課だ 準備室から珈琲の香りがここまで漂ってくる まだ残暑厳しいこの季節にホットコーヒーというミスマッチな組み合わせに眉をしかめたくなるが そのスタンスはいまだ変わることがない “暑いからといって冷たいものばかりは体に好ましくない” 小梶がそういえば、遥が間髪入れずに 『先生、年寄りくさいな』 遠慮無い物言いの遥をただ受け流し微笑む、この美術教師になんの疑問を抱くことなく その後、少年二人は堪えていた笑いをついには我慢できなくなった 遣る瀬無い想いが蘇る 何度も薀蓄(うんちく)を聞きながら遥と一緒に口にした大人の味は少々苦い 間違いなく他の生徒も同じく感じているだろう “この残粉は乾燥させて脱臭剤に使えるんだぞ” 本来なら当然あるべき画材などの芳りがさして気にならないのは小梶が小まめに脱臭を気遣かっていたからだった もっとも小梶自身もよほど近くに寄らなければ美術担当とはわからない 彼から芳るのはやはり珈琲の薫りだったからだ 小梶が挽きたての珈琲を運んでくる 認めなければいけない事実がここにも・・・ そこに違和感を覚え、続いて悲しみがこみあげてくる 机の上に置かれたカップが三個ではなく、二個だった 小梶と自分の分だけ 遥がもうここにはいないということを一つ二つ・・・認めさせられている あんなに拒んでいたことなのに そうしているうちに全て認めていかれるのだろうか 「先生っ・・・」 「今月の体育祭が終わると、来月は文化際だ」 まるでこちらの心中を察したのか、差し障りのない会話に切り替えられた 二学期に主要行事が集中することは入学当初の説明で承知していたが イベント行事が待ち遠しく思うどころか、忘却のかなたに押しやった小さな胸は現状認識だけでいっぱいっぱいなのだ 「文化祭には美術部も勿論参加だぞ 一人作品1点以上がノルマだからな」 「・・・ノルマ?」 この自由な活動の美術部にも強制されることがあったとは初耳だ 「諸藤は初めてだな 造形でも絵画でもなんでもいい、好きなもの1点前日までに仕上げること」 小梶はあくまでも遥の話を持ち出さない 「上級生達はそろそろ取り掛かっているだろう 早い奴は夏休み中に完成させてしまうんだよ」 文化祭は日頃地味な活動を続ける美術部には、作品を公に発表できる大変有難い場 教え子たちの作品を披露できる小梶はとても満足そうだ 珈琲をひとくち飲むと 「心の眼を開くんだ 諸藤」 小梶は窓辺に佇む日樹に背を向けて座った 先ほど、義兄と間違えそうになった小梶とは異なり、寂しげな背中が彼の体を小さく見せた 「先生は・・・全部知っていたんですね」 |
|
遥の意思は小梶に継がれているのだろうか 訊ねたところで事実は何も変わらない 日樹は続けるつもりの言葉を飲み込んだ 「諸藤・・・忘れなくて良いんだよ」 日樹に、そして自分に言い聞かせるような小梶の言葉だった 日ごと短くなっていく陽射しはもう西に沈みかけ、辺りは薄っすら夕闇を迎える どこからか “風の広場に” ヒグラシの鳴き声が響き渡った |
| 「そこはそうじゃない」 すーっと背後から伸びてきた指先が筆を奪っていく それは大人の男性のものでありながら決してゴツゴツしていない繊細でしなやかに動く指先 振り返ればそこに小梶の姿があった 「先生・・・」 「いいか、ここはこうして」 小梶はペロっと舐めてから筆先を日樹のスケッチブックに走らせた 「先生・・・・絵の具が」 絵の具がついたままの筆先を口に含んだ小梶を案じた言葉だった 「大丈夫だ、・・・ただし白の絵の具だけは舐めては駄目だぞ」 スケッチブックに描き巡らせた生い茂る木々 そこに細やかなタッチで絵の具を重ねていく 「どうだ、こうすると自然な感じになるだろう?」 さすが美術教師だ、日樹は小梶の滑らかに動く指に操られる筆先に惹きつけられていた 日樹の描きかけの風景画もそこそこのものだが やはりプロの手にかかってしまえばその比ではない みごと立体的に浮き上がった"風の広場"の木々たちは命を吹き込まれる 「やっぱり、ここにいたんだな諸藤・・・」 スケッチブックを見つめる真剣な眼差しを、優しげな視線に変えて日樹を包む 遥がいなくなったという事実を全てではないが認め以前と変わらず美術部に身を置く 選んだ道は強要されたわけではなく自分で決めたこと 遥と過ごした時間に戻れる、この “風の広場” が大好きだ ここが一番落ち着く・・・ 文化祭への出展作品はこの “風の広場” のスケッチにしようと決めたのは 『忘れなくて良いんだよ・・・』 小梶にそう教えられてからだ 認めなければいけない、遥の存在を抹消してしまわなければと 自分の思いと裏腹な行動をとろうとしていたがために、心のバランスを失いかけていた そんな折に小梶のたった一言が、がんじがらめの心を解き放ってくれた 忘れなくても良いのだと 遥がどうして別れを伝えていかなかったか “ いつかまた逢えるから ” それは確実なものではなく、ただ漠然とした遥の願いだった “ いつか ” それが明日か、それとも三年後、あるいは十年後になるのか、 永遠に続く、限りない月日のたった一部であり、叶わない思いかもしれない それでも遥はあえてその少ない確率に希望を託した 日樹の隣にゆっくりと腰を下ろす小梶 そこは注意を払わなければうっかり見落とす、人には気づかれにくい木陰 小梶はなおも筆を動かし続ける 「体育祭は何か競技に参加するのか?」 「・・・クラス対抗のリレーに」 二学期に入りクラスの中にも少しずつ変化が見られ 他人には無関心だったはずのクラスも、ひとまとまりになろうとする意気込みが見受けられ出した 「ん、選手に選ばれたのか?」 小梶の問いへ気恥ずかしそうに頷く日樹 もともと家柄も成績も優秀な生徒ばかり、物事を公平に判断する能力も優れている 係や種目選手、クラスの意気込みは入学当初の教室内と同じとは考えられないほど 活発になっている 「そうか、それは大したものだ」 「・・・そんな・・・」 褒められて少々照れくさいのか、自分には身に余る大役というところなのか 日樹はスケッチブックへ視線を逸らしてしまった 体育の授業で好タイムを出したか、そのきっかけで日樹はリレー選手に推薦されたのだろう 立候補という意志の強さとは異なる積極性は、内向的な日樹の物陰にわずかしかないのだから 「という私も・・・職員レースに借り出されてしまった」 「先生が!?」 「そんなに驚くことか?」 運動とはまったく無関係の教師が、無理やりと思われる選出に困惑する姿が目に浮かび 失礼だとは承知しながらつい笑みをこぼしそうになり 「・・・い・・いえ・・」 「何か言いたげだな、諸藤」 感情を押し込めてしまう日樹の本心を自然に引き出してやれるチャンスだ トーンを上げた日樹の反応に、しめたとばかりに小梶が食いつく 「そんなことありません」 「さては、私が走れないと思っているんだろう?」 実はその通り 先日の全力疾走の後の筋肉痛に悩む小梶を、数日間気の毒でならなかった だが・・・ 「違います、先生」 「言っておくが、美術教師にならなければ私は体育科の教師になっていたんだぞ」 「それ・・・本当・・ですか?」 信じ難い あまりにも畑が違いすぎる双方の教科だが、もしかすると・・・ 好奇心いっぱいの日樹の瞳が小梶を見つめれば 「いや・・・あり得ないだろう・・・」 真っ直ぐ向けられた視線が眩しすぎ 筆を返すと同時に、信じてしまう前に有り得もしない事実を苦笑いでさっさと否定してしまった 「え・・・」 意外性に期待を膨らませていた日樹はどう反応していいのか戸惑う 小梶なりに気を使ってくれた冗談で、遥がいればきっと 『先生・・・それ究極のオヤジギャグって言うんだよ』 教師である小梶を容赦なくなじり、会話が途切れることもないのだが・・・ 互いの顔を一度見つめ合い、なんだか気抜けしてしまった二人はぼんやりと視線を同じく緑のなかへ埋めた 穏やかに過ぎる時間 やはり少し物足りなく感じるのは遥がいないせいだろうか・・・ 「正直言って、お前は美術部に残らないだろうと思っていた」 「えっ?・・・」 自分から好んでというより、勢いで入部してしまった成り行きは、小梶の目の前での出来事だった 遥がいなくなっては部活を続ける意味が見当たらない それゆえに、てっきりあの日を境にここを去るものだとばかり思っていた 「・・なんとなく・・・」 微かに囁く声は自分の思いを伝えようとしている 「なんだ、諸藤?」 「なんとなく・・・こうしていることで遥が喜んでくれるような気がして・・・」 「そうだな・・・」 アドバイス通り筆を動かす日樹へ、小梶は静かに返した |
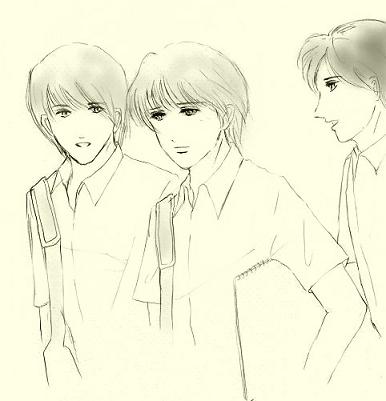 |
| まだ夏の名残りある蒼穹のもと 文化祭に並ぶ今学期の二大イベントに向けて全校生徒達が同じ志を抱く 体育祭は中等部、高等部と全校一斉のせいか、校内は否が応でも盛り上がり、 中等部の1年生にとっては始めての大行事 未知のものへ不安ながら心は沸きあがる この二つの行事が終わるころ、幼さ残る面影はひと回りもふた回りも逞しく成長するのだ ただひたすら無邪気に駆け抜ける青春の日々 今は誰も気づくことが無くて、もやがて大人になった時 それは懐かしさとともに、永遠に消え去ることの無い“心のアルバム”の1ページとなる 体育祭の練習で小麦色に日焼けした色白な日樹も、ことさらに頬、鼻の頭と薄っすら赤らめていた 互いに親交を深めることのなかったクラスメイト同士が誰彼とうちとけ それまでの様子が信じられないくらいに気心許せる仲になっていた 一致団結奮起し、目指すはチーム、クラスの勝利 全力を出し切れば結果はどうあれ満足だ 彼らはまだ若い たとえ敗れ去ろうとも屈辱感と悔しさの経験は長い人生において後々必ず生きてくる グラウンドいっぱいに響く生徒たちの応援や掛け声が空に吸い込まれて行く・・・ そんな折、小梶は美術教室に一人 一冊のスケッチブックに目を留めていた そよぐ秋風、天高く限りなくどこまでも広がるこの空は 間違えなく遥のいる場所と繋がっている |
| 「諸藤君、運動部に入部しないの?」 「そうそう、3人抜きしたクラス対抗リレーの活躍は中等部中の評判だよ」 日樹の横にはいつしかクラスメイトが肩を並べるようになっていた それは遥のことを忘れてしまったわけではなく 自分が傷つかないように、相手を傷つけないように いつの頃からか張り巡らした護身用の自壁の殻がぽろぽろと崩れ落ち、諸藤日樹という人間を 完全にさらけ出すことができたからだ そのきっかけを作ってくれたのが他でもない 殻の中に小さくうずくまる日樹に手を指し伸ばした遥だった 「ううん・・・」 放課後、教室を後にした数人のグループの中に身を置く日樹は 気軽に声をかけてくるクラスメイトへ照れくさげに答える 偶然が偶然を呼び、1つのことが好転し始めれば、不思議に二つ、三つ・・・のことが連鎖しだす 運動部に所属しているわけでもないのに体育の授業で皆から注目を浴びるようなタイム成績を出した日樹は そのままクラス対抗リレーの選手に抜擢され、着順こそは上位入賞を逃したが、 最下位から巻き返した最後の追い込みは、ギャラリーの目を釘付けするほどみごとな走りだった 何においても優れた義兄をもつ日樹 物心ついたころから歳が離れた義兄との間に闘争心が芽生えることは無く その背を越えることもなく、才があり褒められる機会があっても それは義兄を通してだと踏まえ、決して思いあがることは無かった 義兄が6年間過ごした学び舎を同じく志望校とし、難関を突破合格した時には 尊敬する義兄に少しでも近づけたような満足感に胸溢れさせた この西蘭学院に義兄の影は存在しないにもかかわらず 一個人とし栄誉を讃えられることは光栄ながら、それが自分へのものだという自覚が持てず 喜ぶべき状況になぜか心がくすぐったかった 取り囲んだ人垣は日樹と歩調を合わせて進む 「もったいないなぁ・・・」 クラスメイトは少々不満なようだ 「美術部ってあんまり活動してないよね だったら掛け持ちしちゃうとか?」 無責任な提案を持ちかければ 「それはできないよ」 もちろん校則には部活の掛け持ちが不認可とはうたわれていない 活動内容ではなく心地よい空間に身を預けていたいがために美術部に所属している日樹は あっさりと否定した その返答がきっぱり潔いため、クラスメイトもそれ以上は執拗に触れない 躊躇わず自然に意思表示ができるようになった日樹だが、自己主張とは話が別だ 目的の場所へ行き着くまで何人の視線が体育祭のヒーローへ向けられたことか 一時のブームだから、しばらくすればほとぼりも冷めるであろうが それでも困惑するばかり 「美術部の顧問って、高等部の小梶先生だったよね」 「うん」 「知ってる!その先生って凄く評判良いんだっけ」 年齢も兄と慕うにほど近く、堅い教師イメージとかけ離れた美術担当教師 熱血風でもないのになぜか生徒の信望も厚いと中等部にまで名が知れている 「良いよなぁ〜担当教師で授業への意気込みが変わるもんね」 「中等部の美術担任ってさ、おじいちゃん先生だし・・・」 小梶の噂は遥から聞き、その真意のほども承知している 体育祭の偉業を讃えられるより、こうして小梶の優功な評価を耳にする方が名誉でならない 「諸藤君が美術部を離れられない理由はそこかなぁ?」 「え・・・?あ、・・・そんなわけじゃないんだけど・・・」 深い意味も無く訊ねられただけなのに もしかしたら、口元にうっかり笑みを漏らしていたのかもしれない 日樹は慌てて否定をする 「僕も美術部に入ろうかなぁ」 「やめときなよ、キミのセンスじゃ美術部は無理、無理 医大志望らしく生物部でカエルを解剖している方が良いんじゃない」 「医大志望って・・・?」 「こいつの家は代々医者の家系だから、必然的に進路が決まっちゃうんだ」 「そうそう〜 選択肢がないのは進路のことで悩む必要もないから楽だけど、決められたままっていうのも つまらない気がするよ」 「そうなんだ・・・」 西蘭は一流大学への進学率も高く、このクラスメイトのように入学時既に将来の進路が決まっている生徒も 少なくない 義兄と同じ西蘭に入学しただけで自分の今後の進路についてまったく考えていなかった日樹は 名門校の現状をあらためて思い知ることになる 殻の中に居たままではこうした詳細を知ることもなかった 日々のさりげない会話から多くを学び、それが今までと違う自分へ導く 目の前には吸収することばかり、 真っさらな心はそれを全て受け入れる、まるで遥と過ごした時間のようだ 「じゃ、ここで・・・これから美術教室に寄って行くから・・・」 3人は話題尽きずに高等部の校舎、体育館、昇降口への起点になる 中等部のはずれまで来ていた 「あ、そうなんだ」 「じゃね、諸藤君」 それぞれの場所へ スケッチブックを小脇に抱えた日樹はクラスメイトを後にした |
| 体育祭の練習に明け暮れ 文化祭への出展課題がすっかり遅れていた日樹 当日の本番が終了し、やっと提出することができる 小脇にスケッチブックを抱え、北のはずれの校舎三階、美術教室まで来ていた日樹 いつのもように美術教室から続きの準備室へ向おうとしたが、入り口の前で躊躇し足を止めた 誰かいる・・・ 先客だった 顧問小梶を含め二、三人の声が混じる そろりそろり近づき気づかれないように顔半分で準備室を覗く こちらに背を向け腰掛けているのが小梶、そして向かい合わせに座っている数人の生徒は高等部の生徒だろう 大人びた表情や体格が中等部の最高学年の生徒と比べ明らかに差がある いつもは小梶に対面して自分が座っている簡素な応接セットのイスに腰掛けている三人 そのうちの一人が日樹に気づきこちらへ視線を向けた 「あ・・・」 見つかってしまった 日樹は条件反射で身を後ろに引いた 「先生、後ろ」 新たなお客を察したその生徒が目配せをして小梶に知らせれば、いつもの優しげな面持ちで出迎えてくれた 「諸藤か?」 ここへ来れば心安らぐ時間を保障されている この上級生たちも、日頃の吐き出し場のない悩みを打ち明けに来たのだろう 先ほどクラスメイトと話題にした将来の進路、高等部ともなれば否が応でも付きまとう話題 自分と同じように容赦ない大人の味の珈琲で持て成され小梶と談話する上級生 真剣な面差しはまず進路の相談に違いない 担当教科を教えるだけではなく、小梶は自部活以外の生徒を誰となく受け入れる その噂が人づてに校内へ広まり、かつて遥や自分がそうだったように足を運ぶ生徒が後を絶たない 「・・・提出課題が・・遅くなってしまったんですけど・・・」 それでなくても期限をすぎているのに、更に今日は第三者の視線まで感じ、 少々気まずくスケッチブックを差し出す日樹 「そうか、お前が最後だったな 悪いが隣の部屋にパネルがあるだろう それに入れて多目的ホールへ掲示しておいてくれないか? お前のスペースは空けてあるからすぐにわかると思う」 「はい」 まだ談話途中のようで、小梶は簡単な指示だけをし 日樹が頷くと先客の方へ向き直ってしまった それが嫉妬ではないにしろ蚊帳の外の自分がちょっぴり寂しく感じた 週末の文化祭へ向け、校舎のいたるところで準備が進められている 美術教室は授業で使用されるため、前日ギリギリまでは美術教室並びの多目的ホールに 展示品を収納してある 進路・・・ そういえばつい先ほどもクラスメイトが自分の将来を早々と決めてるとことに驚かされたばかりだった 将来・・・まだ漠然とも浮かばない 父親の後を継ぐのは義兄であろうから自分は家督相続に束縛されず自由な道を許されることになる だが、自由ということが逆に選択を難儀させるのだ このまま流される日々を送りながら、果たして高等部へ進級するまでに将来への兆しが見えてくるだろうか・・・ 美術教室を出た日樹は廊下を道なりに進み、多目的ホールの前にたどり着いていた ホールは教室二部屋分のスペースがあり、その室内にはすでに作品を掲示した キャスター付きのボードが何台か配置されていた 当日、この掲示板は美術教室へ移動される 展示済みの作品はどれも個性豊かなものばかりで、この中には美術関係の進路を考えている生徒もいる 『素晴らしい』、と賞賛しようにも、今の自分にはまだ理解し難い作品もあったが 今後本格的に学べばその作品の持ち味も納得できるようになるかもしれない 小梶と同じ道、安易ではあるが たった今選択肢の一つにそれが加えられる 傾げていた首を戻し小梶に指示された通り自分の掲示スペースを探す 一列目、その裏面、二列目・・・順に作品に目を通しながらゆっくりと進む あった・・・ 「・・・・・これは!?」 自分用に空けられたスペースの直ぐ隣、そこには作成者の名も記載されていない一枚の風景画が飾られていた 日樹のように期日に間に合わなかったのだろうか 日樹の描いたものと、とてもよく似ているまだ作成途中の絵は どうやら“ 風の広場 ” のようだ そして、それが誰のものか・・・ 日樹にはすぐにわかった さぼってばかりで 他人のものばかり覗き見をしていた彼のスケッチブックはいつ見ても真っ白だった それでも限られた時間の中でここまで描き残したのか 遥・・・ 「他校の生徒の作品を無断で掲示するわけにはいかないからな」 「先生・・・」 声に振り返れば、背後には小梶が立っていた 「名無しだが、それなら掲示しても良かろう」 西蘭学院に在籍していたとはいえ、 今や転校してしまった生徒の作品を無断で展示するわけにはいかない 小梶や日樹の心の中で遥はまだこの美術部の一員だとしても、それは学院のルールに反する 名無しだろうが、諸藤 お前にはこれが誰の作品なのか、わかっているよな? 小梶の瞳が日樹にそう問いかける これが小梶の計らいだ 答えはもちろん・・・ 「・・・ええ・・・」 日樹はその名無しの作品の隣に自分の絵を心勇み立たせながら並べた ずっと友達だよ・・・ |
 |
| 激暑1 |
| 激暑3 |