|
|
| 解説記事 |
安元家は、門註所氏の支流にあたる。
問註所氏の祖は、鎌倉幕府発足の際設けられた門註所執事に三善朝臣康信が初代長官となり、その子孫三善加賀守康持の代に姓を三善より問註所に改めた。
問註所氏が鎌倉領を出て九州へ西下したのは、康持の三世孫康行が正和二年(1313年)に筑後国生葉郡・竹野郡の地頭に任ぜられたことによる。長巌城を築城し始祖となり、問註所氏の始祖となった。 |
 |
長巌城に関連した、うきは市H.Pへリンク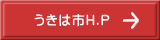
安元家は、三善朝臣清行の第八子浄蔵貴所(891-964)の第九世孫町野右馬頭三善朝臣康倫の三男問註所左近太夫真伸真行(-1185)が姓を安元に改め、若宮八幡宮の神主となる。これが安元の祖となる。
元来安元家は、生葉郡今丸村に住し、家録千石を領した小名の格に列していた。
|
 |
今から三百十年前、安元市右衛門真信は、社職を辞して医業を営み今丸村に住し、今丸安元の祖となる。二男安元宣庵玄通が有馬藩主頼元公(慈源院)側近奉仕(1688)となる。その子孫安元玄琢真淳(-1788)が生葉郡今丸村より三百五十石を持し、生葉郡朝田村中川原に分家、初代朝田安元となる。玄琢真淳の弟安元玄磋真磋(-1771)が三百石を持し、生葉郡原口村に分家、初代原口安元となる。
今丸安元家・朝田安元家・原口安元家の御三家の創立をもって現在に至っております。
私は,朝田安元家の支流にあたります。祖父哲保眞は、明治15年分家し、千足に医業を開業しました。(千足安元家)
|
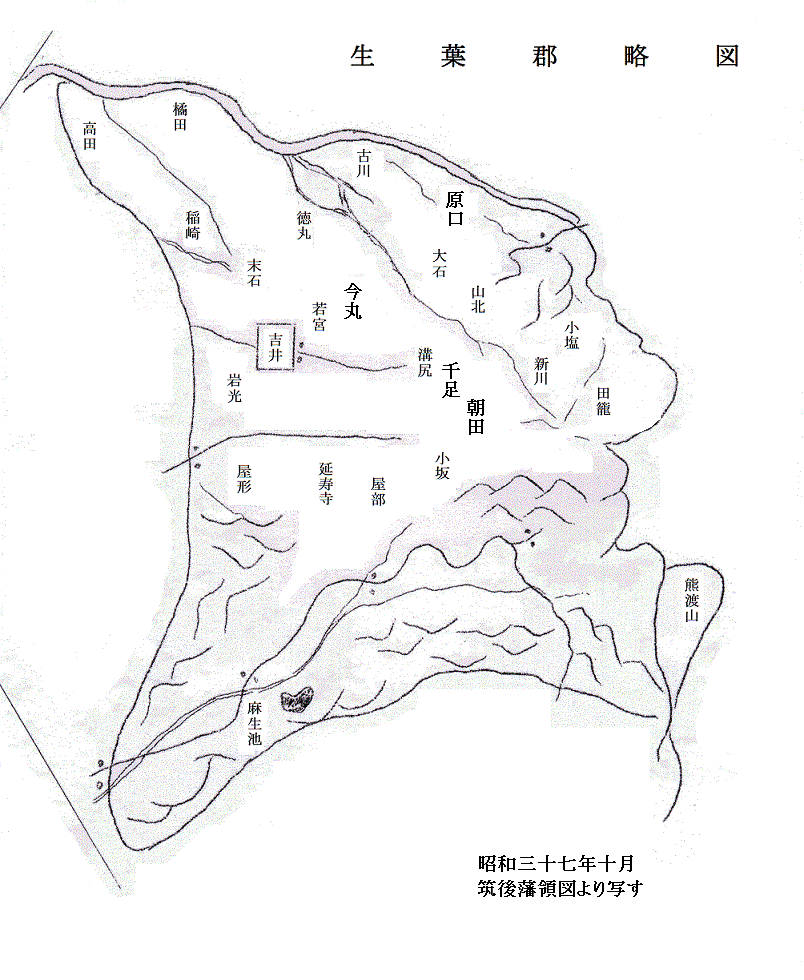 |
|
|
|

