|
|
うきはの伝説 (福岡市 古賀 勝氏のご厚意により転載させて頂きました)
筑紫次郎の伝説紀行H.Pへリンク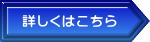
|
筑紫次郎の伝説紀行 第323話 茶畑のお地蔵さん 「流川」地名の由来
門註所家の鑑景・鑑豊2家に別れた内紛から双方数千の兵が入り乱れての斬り合いが巨勢川べりの茶畑で、いつ果てるともなく続いた。
そこから流れる血潮は、巨勢川の清流を真っ赤に染めた。この時”血の川”と化した様子から「流川」の地名がついたそうだ。
戦い終わって村人たちは、犠牲になった子供を含め、多くの屍を無残に荒らされた茶畑に集めて弔った。夜更けになると「うぉ〜ん、うぉ〜ん」と不気味な音が地べたを這うように村中に響いた。「いや〜ん」とか「うらむ〜」などとも聞こえたという。困った村人たちは、大生寺の和尚さんに嘆願した。和尚さんは、最も戦闘が激しかった茶畑の真ん中に、彫りたてのお地蔵さんを建立し霊を慰めた。以後は、怪しげで、おぞましい声は聞こえなくなり、人々も安らかに眠れるようになったんだとさ。 |
 |
大生寺「茶畑のお地蔵さん」に関連した、筑紫次郎の伝説紀行H.Pへリンク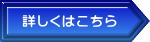
筑紫次郎の伝説紀行 第191話 娘落とし
浮羽町域の3分の2は深い山岳地帯にある。山に降った雨のほとんどは、斜面を北に向かって駆け下り、やがて筑後川に合流する。
滝のような急流は、長年の激突を繰り返し足がすくむほどの深い川底を造り出した。そんな新川に、「娘落とし」と名づけられた谷がある。
執拗な年貢の取り立てと飢饉が続き、村人は、娘も売り飛ばすまで生活が困窮していた。将来を契った恋人のいるお里のところにも人買いがやって来た。「おらは甚作さんの嫁になる」と泣き叫びながら甚作の住む村に向かい逃げた。土橋にさしかかると、山林地主の万四郎が「おまんは女郎屋に売られるちゅうじゃないか。おれの妾になれ、不自由なこつはさせんけん」と抱きついた。お里は、必死で男の手から逃れた。隙を突かれて、万四郎から背中を押され、新川に真っ逆さまに落ちていった。それから毎夜娘の抵抗する「いやです、いやです。甚作さん、たすけてー」の悲鳴が金ヶ淵あたりで聞こえるようになった。村人たちは、お里の幽霊と恐れをなして金ヶ淵に近づかなくなった。そして、土橋のあるあたりを誰言うとなく「娘落とし」と呼ぶようになった。 |
 |
娘落としに関連した、筑紫次郎の伝説紀行H.Pへリンク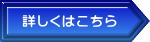
筑紫次郎の伝説紀行 第330話 七つの厄年
正和二年(1313)に問註所康行氏が築城した長巌城跡が在る新川に伝わるお話です。
旧浮羽町の中心部から隈上川に沿って登って行くと、川に沿って民家が並ぶ典型的な山村、姫春村(姫治)がある。この村では、12月1日にぼた餅を作って、子供の成長を願う風習がある。
近所に住むサト婆さんが、重箱いっぱいにぼた餅を詰めてやってきた。寒いのか悲しいのか、ミソノさんは、グジュグジュ水っぱなをすすり上げながら言った。7歳になる娘を、底なしの淵に棲む大蛇に捧げる日が明日12月1日なのだ。もし、大蛇への捧げを怠ろうものなら、大災害が起こって村の全てが壊滅すると言われている。母は村の犠牲になる娘のために、”晴着”をこしらえていた。「選ばれたことを、幸運ち思わなきゃない」ミソノさんは今諦めたような口ぶりで、指先だけは縫い針に集中していた。「ミソノさんよ、こんぼた餅ば玉江に腹いっぱい食わせろ」サト婆さんが、下げてきた風呂敷包みを解いて差し出した。「なしですか?正月にはまだひと月も間があるちいに」「七つ(7歳)の玉江にぼた餅ば食べさせて、ひと月早か正月ば迎えさせたらよかとたい。そうすりゃ玉江も一つ歳ばとって八つ(数え年齢)で大蛇のもとへ行けるじゃろが」母は、サト婆さんの言うことを飲み込めぬまま、必死に涙をこらえながら、「もう一つ食え」と娘に勧めた。「うまかよ、母ちゃん。うちこれで八つになって、大蛇さんのとこに行けるとじゃね」無邪気に笑顔を振りまいて言った。
寺の鐘が鳴って、いよいよ運命の日がきた。慣わしによって、淵までの見送りは村長が1人で勤めることになっている。2人が闇夜に消えてから1刻(2時間)も経った頃。ずぶ濡れになった村長と玉江が戻って来た。村長が話すには、長岩城近くの淵の水辺に玉江が立つと、10間(18m)ほどもある大蛇が、鎌首を宙に浮かせ耳まで裂けた真っ赤な口から吐く炎が、今にも玉江に飛び掛かろうとする。「うちは七つじゃなかよ。八つになったと!」玉江が叫ぶと、大蛇は大きくジャンプしてそのまま水中に沈んでいき、再び水面に姿を現すことはなかった。その時の大蛇のジャンプのしぶきで、2人の着物がずぶ濡れになったという。
サト婆さんが話すには、大蛇は7歳の娘を生贄にと要求した。だが、正月のぼた餅を一ヶ月前に食って、8歳になった玉江には大蛇の方が何の興味も示さなかった。それから姫治村では、大蛇の要求を退けるために、ひと月早い正月をと、7歳の娘にぼた餅食べさせるようになった。
それがいつしか、子供の健やかな成長を願うためにと、毎年12月1日にぼた餅を作る習慣ができた。
|
七つの厄年に関連した、筑紫次郎の伝説紀行H.Pへリンク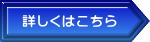
|
|
|

