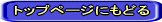グローバリゼーション、世界秩序、そして人権−沖縄の行方を考える−/コージ・タイラ
沖縄国際大学編『グローバリゼーションの中の沖縄』(編集工房東洋企画2004)所収
はじめに(略)
一 経済のグローバリゼーション(略)
二 世界秩序(world order)(略)
三 市民社会、人権(civil society,human rights)等
世界は実に危険な状態にある。経済ばかりは、グローバリゼーション下「世界は一つ」という文句に実感がこもる。しかし世界政治は国民国家時代である。200に近い大小様々の諸国が人類統治を分担しているが、人間の権利、安全、幸福等への貢献度は千差万別である。しかし、民族、文化、信仰、価値観の多様性を是認するとしても、人類が同類である以上、ある種の普遍的共通価値があるに違いない。国連の条約、規約、宣言、勧告等はこの共通価値を明文化する営みであるといえる。
中でも、国連憲章、人権に関する世界宣言、及び二本の国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)は、人間が要求し国家が保障すべき最低限度の共通価値が何であるかを、よく示している。人権規約は「ピープル」(people)の権利と個人の権利を規定しているが、個人の人権に関する限り、現代民主主義諸国では常識的とも言えるほど浸透し実践されている。「ピープル」の権利は、そもそも「ピープル」の意味が不透明であるため、議論が絶えない。
国連憲章は、国連の目的の1つとして(第一条の二)、「ピープルズ」(peoples)の同権と自決の原理への敬意に基づいて「ネイションズ」(nations)間に友好関係を開発することである、としている。人権規約第一条は、「すべてのピープルズは自決の権利を有する」という普遍的原理を確立した後、「この権利に基づき、すべてのピープルズは、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」と敷衍している。自決権が「ピープル」と公認される人間集団のみの権利である点が重要である。
自国内の「ピープル」が自決権を行使して、その政治的地位を、独立国家たることに決定した場合、国家は果たしてこの新国家の誕生を歓迎するであろうか。人権規約は歓迎することを義務付けているが、独立運動がどこでも権力によって弾圧されていることから見れば、諸国の国際人権規約遵守の状況は芳しくないとも言える。国際法と諸国の政治的現実との衝突である。
国内のピープルズが次々と独立して行けば、国家の従来通りの存続は危うくなる。国家の滅亡と再生の好例がユーゴースラヴィアである。旧「ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国」では、国内諸民族の離脱独立後残ったセルビアとモンテネグロが「ユーゴースラヴィア連邦共和国」と称して再出発したが、国連はこれを旧ユーゴースラヴィアの後継国家とは認めなかった。新しい加盟手続きが要求され、数年後、市民社会の反乱蜂起によって民主主義的「市民革命」が成功した後、国連総会が漸く新ユーゴースラヴィアの加盟を認めた、という経緯がある。また、旧ユーゴーの構成諸国は、独立過程または独立後、国内の民族関係の悪化に悩まされて来た。民族自決の論理に忠実になろうとすれば、新国家はそれぞれ、再分裂、再々分裂の可能性を秘めている。
ユーゴーの新独立国が独自の「民族」(ethnos)ごとに成立したことから見れば、「民族」は国連憲章及び国際人権規約にいう「ピープル」とされる資格があるように見える。しかし、それは民族ごとの独立闘争が成功したから言えることであって、一般的にすべての民族が、尊重さるべき自決権を持つ国際人権規約上の「ピープル」である、とは言えない。事実、「市民的及び政治的権利」に関する国際人権規約の第27条は、国内の「少数民族」に属する者(個人)の権利を保護していながら、「民族」の集団的権利については無言である。本条からは、「民族」が第一条にいう自決権のある「ピープル」であるとは、到底言えない。従って「民族自決権」というものは、実は、国際法上存在しないということになる。
それでも、民族であることを自認し、またそうであることが広く世界に知られている民族集団(ethnic groups)の多くは、「民族自決」(national self-determination)を主張し、政治的独立を要求している。しかし、国際人権規約に、ピープル自決はあるが、ナショナル自決がないことは気にかかる。自決権を求める集団は、民族集団であっても、ピープルであることを自認し、世界にそのような自己認識(identity)を認知され、さらに現在所属する国家を相手に独立へ向けて政治運動を続けなければならない。その途上で何が起こるかは、大方当該国家及び社会の近代化、民主化、市民社会化の程度に依存する。
国境不安定の一因として、民族の異同とは関わりなく、地域の特殊性に根ざす独立運動もある、これを地域主義(regionalism)とか地方主義(localism)とか呼ぶ。西欧先進諸国でも、中央従属の現状に満足していない地域や地方は多い。中には独立運動の激しいところもある。しかしさすがに西欧先進国である。民主主義の政治過程は、政府対市民社会の利害調整に当たって極めて柔軟である。また、独立を求める地域、地方住民も民主主義のルールに従って、政府との交渉に節度と規律を守っている。選択肢は独立か否かの二者択一ではない。不服な現状と至福の独立との間には、当面、最終目標へ向かって「前進」と評価できる幾つかの選択項目がある。忍耐強く前進に前進を重ねて行けば何時かは目的地に到達できるはずである。
中央政権にとって譲ることのできない抵抗線は、現有領土の保全である。地域の独立は領土の縮小であり、この抵抗線の侵犯である。政権の性格や体質の如何によっては、地域の独立運動は弾圧すべきであり、関係者は処罰すべきである、ということにもなる。民主主義政権には別の見方もある。例えば、国家統治を中央と地域の共同統治と見れば、統治権の分け前に関する地域の不服に関して、中央政権は、中央・地域間の統治権分担をどう改編すればよいか、と問うこともできる。つまり、地域の攻撃を柔らかく、前進のための交渉で受け止めるのである。今のところ、連邦制国家が独立志向の地域を繋ぎ止める最適の国制であるとされる。
目下、西欧諸国は国家主権を上位の主権主体である統合ヨーロッパに移譲する作業に従事している。主権の上方移譲が可能なら、下方移譲も不可能ではない。イギリスではこれをdevolutionと呼び、独立が視界に入ってきたと言われるほど、「合同王国」を構成する周辺のネイション(スコットランド、ウェールズ、北アイルランド)への幅広い権限移譲を行っている。スコットランド等はかつてネイションでありステイトであったので、そのステイト部門がイングランドと合同して「合同王国」に参入した後も、ネイションとしての本質は失われなかったのである。ナショナル自決は、ここでは、空念仏ではないと言える。
価値観、社会、政治、経済等における進歩は、明らかに相関関係にある。すべてのピープルズの同権と自決の原則を尊重することは理想であるが、ピープルズ間に進歩の格差がある以上、同権と自決に伴う責任や負担の平等は期しがたい。理想と実力間の隔たりを、後進ピープルズがどう埋めるか、またその現実に先進ピープルズがどう対処するか、国際の平和と世界秩序の安定はこれらの問いにどう答えるかに懸かっている。
結 論
総合評価では、ヨーロッパが「進歩」の最先端にある。しかし、その平和主義、法治主義、軍事的消極性等では世界の覇権は取れないかもしれない。世界秩序は依然として、軍事的威圧を辞さない大国を必要としているらしい現状では、この種の選好を隠さない米国に、世界の覇権を譲らざるを得ないであろう。それでも、米国は軍事力の行使にあたっては、その正当化のために、国連の公認及びヨーロッパ諸国ほか多くの同盟国の合意及び協力を必要とする。この度のイラク戦争におけるように、イラクの体制改革の望ましさについては高度の合意が得られたにもかかわらず、軍事的行動の方法やその開始の時期については、激しい意見の衝突があったことは、米国の軍事力偏重戦略が世界秩序維持の手段として十分な正統性を得ていないことを示している。米欧衝突は価値観の衝突ではなく、イラク改革の方法と手段を巡る意見の不一致である。イラクに民主主義、市場経済、市民社会への移行を望む点では、米欧は価値観の同一次元にある。問題はその移行をどう促進するか、それにどのくらいの時間と困難を覚悟するか、等である。アメリカは、フセイン大統領の即時追放に始まる体制の瓦解と再編を望んだ。ヨーロッパはフセイン大統領を含む現体制の漸進的改革を望み、万策尽きて初めて多国籍軍の介入を導入すべしとした。両者の立場の調整は決して不可能ではなかったはずであるが、アメリカが早急の軍事力行使を主張し、フランスが同意を与えなかったために、国連安保理の意志決定は麻痺した。その結果、国連はイラク改革の意欲を示すことが出来ず、結局イラクの現状維持容認という好ましくない立場に追いやられた。同様に、反米に旗頭であるフランスは、意図せずしてフセイン支持の汚名を被ることになった。安保理常任理事国であるロシアと中国は、無責任とも見える事なかれ主義でフランスに同調した。アメリカは国連非公認の単独行動で、独善独行主義の醜さを衆目に曝した。こうして勝者なきイラク介入が始まり、今も続いている。
前述の状況から得られる教訓は、緊急の軍事力行使を必要とする場合の意志決定が、国連機構の現状下では極めて困難であるということである。この状況は気の早い大国には、単独行動を許し、日和見的大国には、事なかれ主義の議事妨害を許すことになる。その中間にあって、動きの取れない国連は、面目を失う羽目に陥ることになる。国連改革が望まれる所以である。
緊急の軍事的介入(先制攻撃を含む)を要する場合とは、大量殺戮兵器等で武装したテロ集団による平和への脅威が歴然たる場合、広範な人権侵害やゼノサイドが発生するおそれがある場合、等である。国連事務総長は、この種の鎮圧方法を国連がすばやく認可できる条件について討論を始める必要がある、と主張する。
民主主義、市場経済、市民社会党の発達・成熟度の高い先進諸国では、このような緊急事態は極めて稀であるはずであるから、国連公認の軍事的介入は、後進国へ向けられる先進国の行動とならざるを得ないと思われる。軍事的介入のこのような傾向性は、国際不平等の証左として必ずしも歓迎できないものであることは、明らかである。といっても平和の攪乱、人権侵害、ゼノサイド等の国家またはテロ集団の犯罪を見過ごすわけにはいかないであろう。
要するに、世界にはまだ落とし穴が一杯ある。社会的、経済的、政治的発達の不均等が、多くの国際的緊張の原因である以上、相当の資源の移転を含む後進国への粘り強い平和的働きかけが望まれるところである。これには、先進国の間でも、威信競争のようなゼロ・サム・ゲームを避けて、国益の自制と地球的公益の尊重に基づく協調的ガヴァナンスとしての世界秩序の構築が必須である。
勿論、言うは易く行うは難し。世界の大国リーグの該当国は長い目でみれば、極めて流動的である。アメリカ、ヨーロッパ連合(緊急に一大国になりつつある)、ロシア、中国は当分大国として世界に「君臨」するであろう。今のところ、アメリカの地位が突出しているが、比較的平準化の兆しが見える。このような図式における、英国と日本の地位は微妙である。英国は多くの点で、安全にヨーロッパに溶け込むことを拒んで、アメリカと組んで、アメリカ並の威容を世界に誇示しようとしたりするが、結局EUの有力な一員となることであろう。
日本の立場はもっと微妙である。経済大国として、経済のグローバリゼーションを梃子に諸国に影響を与えることは出来る。しかし、EUのような帰るべき家のあるイギリスとは違って、日本は帰るべき「アジア連合」を持たない。国連でも非常任理事国にはなれるが、これでは影響力が限られる。結局、日本が帰れることのできる家は日米安保同盟しかない。この家でも、日米関係は不平等関係で、アメリカの核の傘とアメリカ駐留軍によって守られ、対米従属の専守防衛に勤しんで来た。この状態は、冷戦下の米欧関係に酷似するが、アメリカに対してNOと言えるヨーロッパとは違って、日本はそれが言えない。アメリカの保護国としての日本の地位は覆うべくもない。この地位では、日本の国際政治への影響力は極めて限られたものとなり、アメリカを通さなければ行使できないものになっている。
そのような日本国の一県として沖縄県がある。国際関係上、日本国がアメリカ合衆国の「臣」であれば、沖縄県はさしずめ「陪臣」というところであろう。日本にとってもアメリカにとっても、沖縄県の地政学的価値は著しく高い。その他の諸外国も、国策レベルでは、全く同様な見方をしている。沖縄の島々及びその水域、空域の地政学的活用の表れが、沖縄県所在の日本及びアメリカの軍事基地である。これらの基地は、専ら戦略的見地から建設され、維持されて来たものである。基地面積の広大さ、基地内軍事活動の激しさ及びその外部効果の凄まじさ等は、沖縄の島々が本質的には日米共同軍事占領下にあることを思わせる。
沖縄県域に占める基地の比重がこれほど高いということは何を意味するか。それは、沖縄県における軍用地の位置と広さが、戦略的考慮のみによって決定されたからである。沖縄県には土地を必要とする人々が住んでいるという事実に対する配慮が全くなかったのである。所有地に定住して生活する人々を追い出してまで、軍用地を確保した日米両国の沖縄基地政策史が、それを物語る。
現代経済においては経済資源としての土地は、市場メカニズムを通して需要供給の法則に従って流通する。膨大な面積が基地用地として土地の供給から排除されていることは、市場メカニズムを通しての沖縄住民による土地の適正活用を妨げていることを意味する。
このような土地接収にまつわる人権侵害と沖縄住民による土地利用の妨害という事実は、国際人権規約に照らして見る必要がある。日本の国際人権規約に共通する第一条の全文は、日本語訳(国際法上正文ではない)によれば、次の如くである。
第一条
1 すべての人民(Peoples)は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
2 すべての人民は、互恵に基づく国際的経済協力から生ずる義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民はいかなる場合にも、その生存の手段を奪われることはない。
3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
第一項についてはすでにコメントした。ここでは、第二項が極めて示唆的である。沖縄住民を人権規約にいうピープルであるとすれば、土地のような「天然の富及び資源」をピープルとして(個人としてではなく)、自由に処分することが出来るわけである。ピープルが天然資源を処分するということは、ピープルが「領有」する地域内の資源に関してその活用方法について集団的に、民主主義のルールに従って、基本的方針を決定することを含意する。つまり、この条項は「領内」の天然資源の活用に関するピープルの自決権を意味するものである。この見地からみれば、日米両国が、沖縄ピープルの土地の膨大な部分を、沖縄ピープルの意志に反して、沖縄ピープルの政治的、経済的意志決定過程の外で、沖縄ピープルの望まない用途に役立てることを決定したということは、国際人権規約違反であると言える。
第三項は、自決権を有するピープルを包含する国家の義務を規定している。これを沖縄県に則して言い換えれば、日本国は沖縄ピープルの「自決の権利が実現されることを促進」すべきである、となる。米国から日本国へ沖縄施政権の返還が決まった頃、沖縄県内では現行の都道府県制下の一県となることを拒否する意見や提案があった。この時期に沖縄ピープルの自決権に基づいて「その政治的地位を自由に決定する」ことを求めたとしたら、日本国はこれにどう対処したであろうか。この段階では日本国はまた国際人権規約を批准していなかったので、沖縄ヒープルの自決権を尊重し、「自決の権利が実現されることを促進」する義務はなかった、と言えるのかも知れない。
このシンポジウムは、「沖縄の歴史が常に他律的に決定され、沖縄人の主体性(自決権)がないがしろにされてきた」ことが、沖縄の「基本的問題」であるとの認識を掲げている。日本復帰直前の両三年間は、沖縄人がピープルとして国際人権規約第一条を楯に自決権を主張し得るまたとない政治環境であった。その時、沖縄人は、国際人権規約を持ち出して、真正面から日米両政府に沖縄ピープルの自決権を主張し、沖縄の政治の政治的地位を決定する主体は、沖縄ピープルであって他の何者でもないことを、宣言し実行すべきであった。その時なら、国際人権規約第一条の大義の手前、沖縄ピープルの自決権主張は相当の説得力を持ったに違いない。
一つの機会はこうして風と共に去った。しかし、沖縄の人々が「ピープル」である限り自決権は失われない。グローバリゼーションの進展、世界秩序の変動、というような地球的マクロ現象に対して、沖縄の人々は「ピープル」として決して無力ではない。国連憲章は、「ピープルの同権及び自決の原則の尊重」を諸国間の友好関係及び世界平和の基礎であるとしている。独自のピープルとして、他の多くのピープルズと共に自決権を行使して行くためには、沖縄の人々は何よりもまずピープルとしての自己認識を維持し続ける必要がある。ピープルとしての地位と権利は、自主的に歴史を作って行くエネルギーの源泉である。
EUの視点からみた沖縄のカルチュラル・アイデンティティと自立性/パトリック・ベイヴェール
パトリック・ベイヴェール(フランス国立科学研究センター研究主任/社会科学高等研究院日本研究所所長)
この論述は、日本における沖縄の特殊な位置を、ヨーロッパ連合構成の経験に照らして検討することを目的としている。正確には、大和と沖縄の関係を念頭に置きながら、沖縄の文化的アイデンティティの概念と、そこからくる政治的影響の関連を、ヨーロッパの観点から注意深く考察していくことにある。
一 ヨーロッパ内戦時代を超越した新政治体制(略)
二 ヨーロッパ連合のカルチュラル・アイデンティティのゆくえ(略)
三 地方権威の強化へのヨーロッパ連合と沖縄の状態
(前略)
海外の現在の状況を紹介する際、あるいは理解をしようとする時に直面する問題の一つに、沖縄県民の意見の多様性がある。言うまでもなく、私がまず思う沖縄の問題に、米軍基地、環境保護問題と地域開発、あるいは琉球語や琉球文化の擁護がある。また、特にアメリカ駐留軍基地や環境問題に対して人々が個人的に表明する不安や不満は、政治的責任者の発言のなかで、例外を除いて、和らげられて言及されるのが一般的であることも見逃すことができない。思うに、ここが日本全土に見られ、沖縄社会ではさらに顕著な合意に対する慣習や、とりわけ東京への沖縄県の財政的依存、そしておそらく、歴史の中で培われた諦観姿勢がまさに問題なのである。この財政的依存は、沖縄県が経済開発の点で他の都道府県に比較して遅れを取るであろうという恐れ、または経済的充足を目指す意見に根差している。
米軍基地の問題も同様に、悪循環となっている日本政府に対する依存に関係する。つまり、沖縄県の面積からすれば不均衡な規模は、日本政府からの沖縄県への高額の経済援助を正当化する代わりに、県民の不満を和らげながら基地を確保する。だが、同時に沖縄の米軍基地の存在は、重大な心理的影響をもたらしている。米軍基地の存在は、歴史が、さもなければ日本政府が沖縄県民に与えた不当な運動や今なお生々しい過去の苦しみの記憶をそのままに残しながら、大和と沖縄の境界を具体化する。
四 さらなる正義なり地方自立なり、政治的対立は免れない
沖縄の歴史や伝統文化の特異性は、将来的には、政治的な自立を高めていけるようになることを目指す沖縄県民に、確実に強い論拠を与える。この点に関して、歴史学者や民俗学者がこの何十年の間、沖縄文化やその他東アジア諸国との関係についての評価に対し、多大な貢献をしてきたことを称えずにはおれない。しかしながら、いかなる時代、場所でもであっても、カルチュラル・アイデンティティは一つとして一定のものはない。アイデンティティというものは、常に他者との関係において、また自己の一部であり、そこから解放されることのできない外界との関係において確立されていく。たとえ目立った人種的な均質性を持つ社会に所属しているとしても、解決しえない相違を有するという確信は想像から生まれ、これは政治的な構想において常に理解を要するのである。
このように、琉球王国の文化の美しさやその独立性がどうであれ、弱者に服従を強いる歴史の不当性がいかなるものであろうと、これらの要素が沖縄の将来を先験的に決定することはない。独創的な開発の道を、沖縄のために決定する確固とした政治的意志により引き継がれるという条件で、過去の記憶が強力な心理的要因となり得る。もし、この政治的意志が日本から遠ざかる方向を取るのであれば、日本風発展・開発モデルに見切りを付けること、つまり、都市計画の拡大を制限し、ある種田舎的な面を受け入れることにより、間違いなく生活水準のなかでの犠牲を受け入れなければならないであろう。しかし、沖縄の素晴らしい自然を実際に保護することは、周知のように、大きな切り札なのである。逆に、単独開発政策意志が障害になるのであれば、沖縄の特徴は単なる観光事業目的の説得手段にとどまるであろう。
とはいえ、私のような外国人観察者にとって、沖縄住民の日常生活は、特に若者の間でますます本土の大衆文化に染まっていることに留意せずにはおれない。沖縄独自のものにもかかわらず、宗教的分野においても本土の影響がますます顕著になってきている。ともかく、教育制度自体が基本的に日本全土の統合や均一化の強力な要因である。ヨーロッパのように、伝統文化は生活習慣のなかにはすでに重きをなさなくなっている。伝統文化は、近代性を特徴付けるその他多くの娯楽イベントと同格に見なされている「博物館的」形態で、余興や見世物として存続しようとする傾向がみられる。いずれにしても、時間を逆行できると考えることは幻想的なことであろう。
幾分不適切であることを承知であえて付け加えるが、あたかも明確に定義された概念であるかのように沖縄の文化を単一のものとして、また沖縄の歴史も単一のものとして語ることは、問題を生じさせる。実際は、過去を単純化する経験に基づいた概念構成が問題となっているのである。特に、琉球王国の文化的・地理的多様性とブルジョア階級の不在という点から考慮すれば、私の意見では、琉球王国民にとって同じ文化共同体に所属しているという意識があることは考えにくい。言い換えれば、この意識は、国民国家のそれといえる。
五 おわりに
いずれにせよ、沖縄の近代史の変遷の中、沖縄県民は幸運にも沖縄の文化的特質への誇りを取り戻し、このことにより他の日本人から部分的に認められている。しかしながら、沖縄県民の大部分は、日本に深い愛着を覚えているし、今では日本の将来とは別に沖縄の将来を予測することができない。このような背景から、日米協力合意から生ずる米軍基地への社会的負担の平等が、他の都道府県と対等であることも含め、経済的平等を沖縄県民が望んでいるように思える。
現在の国際情勢と、アメリカ合衆国が世界の中で優位を維持することを望んでいることからすると、近い将来にアメリカが沖縄に対する影響力を放棄すると考えることは、非現実的であるように思える。今日、北朝鮮、フィリピン、そしておそらく台湾との緊張関係がある。中国との対立関係が、東アジアにおける米軍の存在を維持することを正当化するようになると考えることは非現実的ではなくなるかもしれない。予測可能な将来において、沖縄は政策上の重要性を維持することになる。
日本が、世界の中で今より重要な軍事的役割を果たすことを決断したとしても、米軍の判断に倣うだろうということは、大いに想像できることである。日本の他都道府県に移動、あるいは海外への移転による沖縄の米軍駐留基地の縮小は、沖縄の政治家が県民の支持を得ながらワシントンや東京への圧力を緩めることなく維持し続けるならば、不可能なことではない。国際舞台、特にヨーロッパで沖縄をよりよく紹介することは、同様にこれら軍事基地縮小の動きを強固にすることにつながるであろう。
しかしながら、これらの働きかけは、少数派の活動家によってではなく、沖縄県政の代表によって行われるべきである。これら活動家の努力により沖縄県民を被差別少数民族として認めさせることができたとしても、世界の中で上位に位置づけされ、かつ日本国民としてのあらゆる権利を得ている(米軍基地の問題を除けば)沖縄の住民を北アメリカのインディアンやニューカレドニアのカナカ族、あるいはビルマの少数民族と比較し得るとは考えにくい。
経済的観点から言及すれば、香港やシンガポールに倣って沖縄の開発計画を立てることは、現実味に欠けているように思われる。なぜならこれらの都市は非常に異なった地政学的背景と大英帝国の強力な後押しの上に成り立っているからである。もっとも、沖縄県民は国際的な環境を受け入れる準備ができているのであろうか。余談ながら、19世紀中頃にフランス人が沖縄を東アジアの商業中心地にしようと計画していたことに触れておく。しかし、中国と日本の実り多い貿易構想は早々に通用しないものとなった。新しいFTZ(自由貿易地域)の設置は県の財政の均衡を回復させるのに役に立つであろう。近い将来、中国からの投資が沖縄の経済状況を立て直すのに貢献するかもしれない。いずれにせよ、沖縄の生活環境と社交性の維持は優先事項であると考える。Small
is beautifulではないだろうか。(以下略)
このページのトップにもどる
<風游・図書室>にもどる