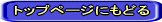独立論の系譜
「特集 沖縄にこだわる―独立論の系譜」(新沖縄文学53号1982年9月30日発行)
「復帰10年」、川満信一は、編集後記でまず「独立の可能性もないのに“琉球独立論”だなんて、あまりにも非現実的ではないか。知識人たちのアソビばかりやっていないで、もう少しは現実に役立つような特集をやったらどうかね。」との声を紹介しつつ、しかし現実とせめぎ合うことの意味を<日本−沖縄>の関係で捉え返すことの必要性に、こだわり続ける。そして、戦後の様々な位相で構想され――立ち消え――た「独立論」を解きほぐす。
『うるま新報』〔1951.4.23〕に「帰属問題めぐり街の声を聴く/反映させよ/住民の希望」との見出しで報道された「街の声」を再録してある。以下、リード。
「マ元帥の解任によって今秋締結を予想されていた対日講和もおそらく遅れるのではないかと見る向きもあったが、新最高司令官リツジウエイ中将は去る十四日日本国民にあてた新任第一声の中で「既定方針に基き早期講和をぜん面的に促進する」と発表、続いてマ元帥と入違いに日本を再訪した米大統領特別代表ダレス氏も入京の翌日発した声めいの中で「対日講和条的の早期締結を熱心に推進するという米国の決意をトルーマン大統領が再確認した、マ元師の対日政策はとりもなおさず米国の政策であり、今後ともそれに変りはない」と言っているので再び早期講和に大きな期待がかけられるに至った、沖縄の運命を決する対日講和を前に控え、既に群島議会並びに、政党は各々態度を決定してそれぞれ運動を展開しつつあるが、今や巷にもき属問題をめぐり甲論乙駁なかなか活況を示している模様であるので本社では該問題について街の声をきくことにした。
これによると日本復帰を叫ぶ声、国連信託希望、独立論或は一定期間の米国信託の後日本復きを望む等さまざまであり「き属決定には吾々の意志を反映させよ」と力づよく叫んでいる。」
さらに「沖縄自立・独立論関係図書目録」が付け加えられている。
巻頭言として川満信一自らが「独立論の位相――ナショナリズムの敗北を超えて」を執筆。以下、目次。
・沖縄人連盟/新崎盛暉
・沖縄民主同盟――立ち枯れた沖縄独立共和国の夢/仲宗根勇
・宮古社会党――帰属の不安と独立の思潮を背景に「米国沖縄州」を構想/平良好児
・不発の独立論――帰属論議欠いた八重山戦後政治のスタート/大田静男
・琉球国民党――琉球人による琉球人の政治を志向/島袋 邦
・琉球独立党――“十年遅れの問いかけ”として/平良良昭
・ふたば会――崎間敏勝氏の歴史観を中心に/太田良博
・琉球巴邦−永世中立国構想の挫折――屋良朝陳作『巴旗の曙』をめぐって/仲程昌徳
・山里永吉瞥見/岡本恵徳
沖縄人連盟/新崎盛暉
一 連盟設立のころ
敗戦の年、すなわち1945(昭和20)年11月、東京や大阪、兵庫などで相次いで結成された沖縄人連盟は基本的にどのような性格をもつ集団だったのであろうか。東京の場合は、伊波普猷、大浜信泉、比屋根安定、比嘉春潮、永丘智太郎の五名が発起人となってつぎのようによびかけている。
吾々本土在住沖縄出身者は、(1)沖縄諸島に於ける現存者は誰々か、何処に、どうして生活しているか、を知り、(2)至急に沖縄と本土間の通信交換、金銭及び救援物資の送付等が出来るようにし(3)又、沖縄戦の実相はどんなものであったかを知りたい、と熱望しています。さきに財団法人沖縄協会が設立されましたが、同協会は主として引揚県民の救援、復員兵士の就職斡旋等本土在住者を事業対象とする結果、沖縄在住者の上には手を延ばしてはゐません。茲に沖縄出身同憂の士を以て沖縄新生協会(仮称)を組織し、前述各項の達成を講じたく存じます。……御賛同御参加の程懇願致します。
ここにいう沖縄新生協会(仮称)が、1945年11月11日、沖縄人連盟として発足する。
このよびかけ文の段階では、連盟の主要な関心事は、戦火に焼かれ、日本から切り離された郷土沖縄の実情を知り、これの再建に寄与することであり、疎開者、復員兵士などを主体とする在本土沖縄出身者(在日沖縄人)の問題は、沖縄協会が取り組むべき課題であるとされていた。しかし、沖縄協会はもともと報国沖縄協会の流れをくんでいるのみならず、基本的には政治問題である在本土沖縄人問題に、行政的実務的にしか対応しえないという限界をもっていたこともあって、政治的行政的に放置されていた疎開者や引揚者の問題解決は、いやおうなく沖縄人連盟が取組まなければならないもっとも重要な任務になってくるのである。 連盟結成の10後にGHQに提出された請願書は、つぎのように訴えている。
吾々ハ日本々土ニアル民主々義的傾向ノ沖縄人同志ヲ代表スルモノデアリマス。日本人中今次ノ誤マレル戦争ニ依ッテ最モ多クノ犠牲ヲ払ワサレ、而モ悲惨ナ境遇ニオトシ入レラレタモノハ沖縄人デアリマス。シカルニ日本政府ハ沖縄人ノ直面セル困難ニ関シテハナハダ冷淡デアリ、吾々ハ最早コノ無力ノ政府ヲ信頼スルコトガデキヌノデ、茲ニ謹ンデ、マッカーサー元帥ニ吾々ノ悩ミヲ被瀝シ、ソノ御賢察ニ依テ左記解決ノ一日モ早カランコトヲオ願ヒ致ス次第デアリマス。
一、日本々土二在ル沖縄カラノ避難民若クハ南方カラノ引揚民ニシテ日本々土扶養義務者ヲ有セヌ老幼婦女子ガ速カニ彼等ノ郷土ニ帰レル様取計テ頂キ度
二、沖縄及ビ南洋、布哇等トノ通信連絡、送金、救助物資ノ送付等ヲ格別ノ御配慮ニヨリ御許可アリ度
三、沖縄在住生存者ノ安否及ビ軍閥ノ暴逆行為ノ真相ヲ調査シ帰来後、沖縄人及日本人民ニ報告スル為、連盟ヨリ選抜シタ十名ノ派遣員ノ渡航ヲ許可相成度
この請願書に対しGHQは、翌46年1月2日付の日本政府への覚書によって、つぎのように回答してきたという。
(一)沖縄人に関する請願書の内容を点検するに、食糧、住宅、衣料等に不足し、生活水準を低下せしめる結果、ここ二、三ヶ月以内に多数の死者が続出しさうな状況である。
(二)日本政府は沖縄人に左の事項を告知せしむべし。
(イ) 当分沖縄島は軍事的理由に依り復員(帰還)を許さない。沖縄(本島)への帰還の可能性については、尚調査中である。
(ロ)調査団派遣に関する沖縄人からの請願は今許可することが出来ない。
(ハ)沖縄人の希望する金銭取引の管理(送金の如き)は禁止される。
(ニ)日本政府は窮乏せる琉球人避難民に対し、遅滞なく十分な食糧、住宅、医療、寝具、衣料等を支給すべし。
(三)この覚書の内容は適当な米軍当局にも通牒してある。(『自由沖縄』第3号、昭和21年1月25日)
この回答のうち、とくに(二)の(ニ)の指示は在本土沖縄人を感激させたのだが、絶対的権力者GHQのこのような指示も、当時の社会事情のもとでは、おいそれと具体化はしなかった。連盟の機関紙『自由沖縄』には、学童疎開の児童をはじめとする九州地方の疎開者や、浦賀や博多に上陸したダバオ等からの引揚者の悲惨な状態が、くりかえしくりかえし掲載されている。
「当面の救済問題の解決と自由沖縄建設を目標に結成された沖縄人連盟」(前掲『自由沖縄』第3号)も、実践的には焦眉の急務である前者の問題にそのほとんどのエネルギーを割かれざるをえなかった。その意味で、沖縄人連盟の基本的性格は、在本土沖縄出身者の相互扶助的な援護団体であったといえるだろう。
二 沖縄県人から沖縄人へ
では、この団体がなぜ「沖縄人連盟」を名のったのか。
ここで、戦中戦後の在本土沖縄出身者団体(県人会)の移り変わりを、『自由沖縄』などによって簡単に整理しておこう。
戦時中、東京や関西の県人会は、自然消滅ないしは有名無実化していたが、沖縄戦の最終段階のころから、大日本興亜同盟の山城善光らが伊江朝助男爵をかついで県人会の再建をめざして動き、これに九州疎開者の救援のため沖縄救護協会設置を構想していた永丘智太郎らが合流して、報国沖縄協会が設立された。しかし間もなく敗戦となったため、会名から「報国」の二字を削り、目的からは国家主義的文句を払拭して、厚生、内務両者からの助成金を得、本土在住沖縄出身者の救援活動を行なうことになった。
半官半民的な沖縄協会の限界をこえて、より大衆的に沖縄出身者の結果をはかろうとしたのが、沖縄新生協会(仮称)であり、五人のよびかけ人のうち永丘智太郎と大浜信泉は、(報国)沖縄協会の理事でもあった。
沖縄新生協会(仮称)がなぜ「沖縄人連盟」に落ち着いたのかについては、「沖縄人連盟創立大会報告書」にも何らの記述もない。会の名称については、ほかに「沖縄民主同盟」、「沖縄救援委員会」などが検討された痕跡もあるが、沖縄県が事実上消滅している状況のなかで、大衆団体にもっともふさわしい一般的名称として沖縄人連盟が使われたということだろう。もちろん、この名称採用に積極的だった部分が、すでに活動をはじめていた朝鮮人連盟にヒントを得、新しい時代的雰囲気のなかで、これに一定のシンパシイを感じたことは当然考えられる。
いずれにせよ、正式に発足した沖縄人連盟は、その規約で、「沖縄出身者相互ノ連絡及救援ヲ図ルト共ニ民主々義ニ依ル沖縄再建設ニ貢献スルヲ以テ目的トス」と定め、この「目的ヲ達成スル為、左ノ事業ヲ行フ」としていた。
一、沖縄諸島へノ通信、救援物資ノ募集又ハ其ノ送付ノ斡旋
二、避難民又ハ引揚民ノ帰還ノ斡旋
三、沖縄諸島現存者の調査
四、沖縄戦ノ実相ニ関スル調査
五、其ノ他本連盟ノ目的達成ニ資スル一切ノ事業
同時に、「本連盟ハ前条ノ目的ニ賛同スル者ヲ以テ組織ス。但シ軍国主義者、既成政治家極端ナル国家主義者ヲ除ク」とする規約第四条が注目された。
一方、戦前から沖縄出身者が多く、県人会活動も活発だった関西では、敗戦後間もなく、地域別にいくつかの県人会が再建されるが1945年11月26日、これらが合同して関西沖縄人連盟創立大会を開いた。
九州では、大分、熊本、宮崎、鹿児島など各県別に県人会が組織されていたが、十一月下旬、大分の沖縄県人会長真栄城守行を会長に九州連合会が組織された。
こうした点からいえば、1945年11月11日に東京で結成された沖縄人連盟は、厳密にいえば、関東沖縄人連盟とでもいうべきものであった。
ところで、沖縄人という名称は、当初から沖縄県という名称に明確に対置されるかたちで用いられたわけではない。1945年12月9日に東京で開催された沖縄人連盟主催の最初の大規模な大衆集会は、参加者の少なかった11月11日の連盟創立大会に代わる事実上の連盟の大会とでもいうべきもので、連盟役員人事の承認をはじめ、沖縄県選出衆貴両院議員の不信任決議、沖縄協会の民主的改組要求決議など重要な内容の決議を行っているが、その名称は、「引揚民救済沖縄県人大会」であった。
さて、各地で結成されはじめた沖縄人連盟は、その目的達成の必要性からいっても、全国的な横のつながりをつくらなければならなかった。かくして、1946年二月23日〜25日、事実上の沖縄人連盟の全国大会ともいうべき全国沖縄(県)人(団体)代表(者)協議会が、関東沖縄人連盟と関西沖縄人連盟の提議によって開催され、沖縄人連盟は、関東、関西、東海、九州などに本部を置く全国組織、沖縄人連盟総本部となった。総本部の会長は、沖縄人連盟首席総務委員伊波普猷、副会長は、永丘智太郎(関東)、名渡山安憲(東海)、幸地長憲(関西)、宮里栄輝(九州)、中央委員には、仲原善忠、八幡一郎、山城善光、松本三益、古波津英興などが、相談役には、比屋根安定、瀬長良直、比嘉春潮、伊元富爾、井之口雅雄などが顔を並べ、徳田球一、翁長良保、豊川忠進の三人が顧問であった。
連盟総本部規約は会の目的としてつぎの六項目を挙げていた。
一、民主主義による平和日本建設への貢献
二、郷里沖縄の復興促進
三、引揚者、避難民、学童・生徒、微用工、復員者の生活確保
四、沖縄への帰郷、出郷及通信送金の自由
五、内外在住沖縄人の連絡提携
六、郷里沖縄に於ける戦災の完全補償
これで連盟の基本的性格はほぼ確定的なものとなるが、これと前年11月11日に発足した沖縄人連盟規約と対比して注目されるのは、第一項と第六項が加わったかわりにGHQへの請願書のなかでも重視されていた沖縄戦の実相調査および軍国主義者や既成政治家の排除という項目が抜け落ちていることである。
ともかく、こういうかたちで沖縄人連盟が全国組織としての体制をととのえていく背景では、GHQの日本と沖縄を分離する方針がより明確なものとなりつつあった。
すなわち、1945年1月29日付で、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」が出され、二月十八日には日本政府に対し、「三月十八日迄に在日朝鮮人、琉球人、台湾省民の登録を行ふやう命令した。右登録には、氏名、年令、性別、その生国における住所、日本での住所、職業、帰還希望の有無を申告させる筈である。登録の通知を受け登録を怠った者は帰還の希望なきものとみなされ、その特権を失うことになろう」(『自由沖縄』第四号、昭和21年2月24日)とのGHQ発表がなされた。沖縄人という言葉が、現実的重みを増してくるのである。
三 連盟と沖縄独立論
この段階になっても、沖縄人連盟は、積極的に独立を主張していたわけではない。それどころか、伊波普猷の後を継いで1946年12月、二代目の沖縄人連盟総本部会長となった仲原善忠などは「沖縄人」という呼称にも特別の意味付与は行っていない。
すなわち彼はつぎのようにいう。
「われわれ沖縄人は」という時、私は鹿児島人、或は東京人というやうに生まれた土地という意味に解している。而し沖縄の歴史から考へ(中略)もっと深刻に考へている人も少くないと見るがそれもまちがっているとは言はない」(『自由沖縄』第13号、昭和22年2月20日)
また、つぎのようにもいう。
「結論を先にいへば、沖縄民族と言ふ日本民族と区別するほどのものはないと私共は考へる。而しいやおれは日本民族ではない、沖縄民族だという人があればたゞ苦笑する丈で学問上まちがいだとは言わない。かりに八丈島の人がおれは八丈民族だとっても左様ですかと云ふだけである。自分は沖縄民族で非日本民族だと信じている人でもどうか自分の感情を他の人々に押し付けない様にして貰い度い」 (同)
では、沖縄人連盟は、沖縄の現状をどのようなものとして認識しその将来をどのようなに展望し、その認識と展望をふまえて連盟はどのような路線を歩もうとしていたのだろうか。『自由沖縄』の論調からこれらの点を個条書きで列挙すれば、およそつぎのようになるだろう。
(一)、ポツダム宣言第八項には、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあり、どの諸小島を日本領とするかは連合国側の決定事項事項であって、ポツダム宣言を受諾した日本にはこの問題に関する発言権はない。
(二)、沖縄の最終的帰属は講和会議によって決定されるであろうが、アメリカを唯一の統治国とする信託統治制度の下に置かれることはほぼ確実であろう。
(三)、1946年1月29日付GHQ覚書等によって現実に日本の統治権は沖縄に及ばなくなっている。すなわち、好むと好まざるとにかかわらず、沖縄県は存在しなくなっており、沖縄人は非日本人になっている。
(四)、したがって沖縄人はGHQの方針に逆って日本復帰を主張するような軽挙妄動はつつしみ、一致協力して、在日沖縄人の救援問題や日本と沖縄の民主化に努力すべきである。
沖縄人連盟は、一度として積極的な独立論を展開したことはない。むしろ、連盟指導部のかなりの部分が連盟に「独立を祝ふ」メッセージを送った日本共産党の影響下にあることによって、内外から連盟が独立運動をしているという「誤解」を受けないようにと気をくばり、こうした非難を打ち消すのにやっきになっていた。
初代連盟会長伊波普猷はいう。
「……一体独立とか何とか今こちらで問題に出来るか。連盟は勿論郷里沖縄の復興に貢献するといふ大目標は樹てているが、当面喫緊の問題は本土在住沖縄人の救援である。沖縄帰属の問題は連合国の方で決定するのであり、将来郷里在住沖縄人の一般投票に問うふことになるかも知れないが、それは吾々こちらにゐる人々の現在の問題ではない。連盟が独立運動をするなどあり得ないではないか。」(『自由沖縄』第九号、昭和21年8月15日)
だだ、連盟指導部は、時代の流れに乗っているという自信をもって、在日沖縄人大衆に現実直視を訴える。たとえば、『自由沖縄』でもっとも積極的な論陣を張った永丘智太郎はつぎのようにいう。
「なるほど沖縄県と云ふ呼称は、置県以来六十七年の長い間われわれ同胞の耳朶を離れなかったのであるから、これに恋々たるの情を持つ人々のあることは当然で、決して無理はないのである。けれどもわれわれは、眼前の事実に眼を蓋ふことできないではないか。(中略)……兎も角、銘記しておかねばならぬことは、われわれの故郷沖縄は現在の段階として既に『大和世』から『アメリカ世』になっていることである。したがってわれわれ沖縄人は『非日本人』となってゐると云ふ事実である。」(『自由沖縄』第6号、昭和21年5月5日)
またつぎのようにもいう。
「日本と沖縄は語源学的に見ても同一であり、また人種的にも血の繋がりがある。ことは、吾々も充分認めるが、日本への領土的帰属は将来日本が完全に民主化した場合にのみ考へ得べきことで、現在は問題とならぬのである。問題にならぬことを問題にせんとする者は、かの慶長の役に際し島津藩と徹底抗戦を固執して沖縄を破滅に陥れた謝名親方の後塵を拝するもので、真に沖縄人を愛するものではない。」(『自由沖縄』第10号、昭和21年11月15日)
連盟指導部の日本復帰論批判は、世界的な民主革命の歴史の流れに乗っているという自信とGHQ(解放軍)への信頼に依拠していたが、大衆説得の論理が長いものには巻かれろ式の事大主義的においをただよわせていたことも否定しえない。このことは逆に少数異端の積極的日本復帰論者に謝名親方の気負いと誇りを与えることにもなったのである。
沖縄人連盟は、独立論を主張したのでもなく、独立運動をしたわけでもなかった。しかし、連盟の主導権を握っていた部分は、明らかに信託統治制度の下でも民主化と自治の徹底は可能だとして、信託統治是認論とでもいうべき立場に立っていた。しかし、それは主体的かつ積極的な自巳主張としてなされたわけではなく、むしろ既成事実の追認(歴史の流れを逆行きさせようとする復帰論の否定)としてなされていた。
また、連盟指導部が、積極的な信託統治論の展開を避けながらも日本復帰論を激しく非難したのには、もっと別な現実的理由もあった。
四 沖縄人連盟から沖縄連盟へ
すでにみたように、沖縄人連盟は、在日沖縄人の唯一の総意代表機関たることを目指し、沖縄協会を完全にその影響下においていたが、さらに、沖縄県特別行政機構の解体、吸収をも意図していた(たとえば、『自由沖縄』第8号、昭和21年6月15日、社説「連盟の旗の下に」は明確にそのことを主張していた)。沖縄県特別行政機構というのは、事実上沖縄県が消滅してしまったことに対応して、沖縄出身の引揚者、復員兵士の援護指導、沖縄関係官吏及び家族への給料恩給等の支払い事務等を行うため、1945年9月20日付の内務省通牒に基づいて設置されたもので、九州行政事務局書記官北栄造に沖縄県内政部長を兼任させ、九州各県や東京、大阪に沖縄県事務所を置いていた。
沖縄県は既に存在せずとする沖縄人連盟にとって、これは目ざわりな存在であり、また一定の政府予算をもつこの機関を解体、吸収することは、連盟の勢力拡大を意味した。しかし、日本復帰派はこれを手掛りに沖縄県の復活を意図していたから、日本復帰派、特別行政機構の関係者、それに「今をときめく日本共産党書記帳、郷土出身唯一の代議士徳田球一」(前掲『自由沖縄』第六号)を顧問にいただく沖縄人連盟に疎外感をいだく「既成政治家」たち−といっても彼らのほとんどは、やがて連盟の幅広路線のなかで顧問にまつりあげられるのだが−は、彼らが共産党とその独立論の影響下にあるとみている沖縄人連盟の沖縄特別行政機構解体要求に強く反発した。こうした対立は、特別行政機構があり、疎開者が多く、彼らに対する援護活動が相互に錯綜する九州地方において、連盟派対県人会というかたちをとって表面化した。
九州連合県人会のなかでも熊本県人会の宮里栄輝などは、いち早く沖縄人連盟への参加をめざしたが、九州連合県人会長真栄城守行などはこれに反対した。このため沖縄人連盟九州本部の成立は、他の地域に比べかなり難航し、九州本部設立後も県人会派との対立はなお続いていた。沖縄人連盟九州本部が、1946年5月26日の全九州沖縄人大会の決議に基づいて、真栄城守行、親泊政博、渡名喜守徳の三名を地方的戦争責任者として名指しで非難したりしているのもこうした状況の反映である。
連盟対県人会というかたちで対立が表面化したのは九州地方だけであったが、似たような対立は、連盟内部に常に存在しており、連盟設立間もない段階から、連盟には内部抗争がたえなかった。1947年9月の連盟第二回中央委員が、49対52で正副会長(仲原善忠会長、伊元富爾副会長)の辞表受理を決定し、その後正副会長の解任権は中央委員会にはないとして次期大会まで正副会長の留任を決めたことなどは、こうした内部抗争の表面化にほかならなかった。
こうした事態は、連盟の主導権は日本共産党の影響下にある信託統治是認派(独立派)が握っていたものの、連盟員大衆のなかには日本復帰派の影響もまたきわめて大きいことを示していた。信託統治是認派が、GHQに依拠しつつ、既成事実の積み重ねと現状追認の論理しか展開しえなかった理由の一つはここにあったのかもしれない。しかし、こうした論理は、方針転換の際の自己弁護には便利だが、大衆への説得力をいちじるしく欠くことはまちがいない。
この時期、主体的な沖縄社会の将来構想をめぐる論義として、信託統治是認論(独立派)と日本復帰論が正面切って闘わされていたならば、ある程度生産的な思想的あるいは理論的な遺産を残しえたかもしれない。だがそうした試みはなされなかった。両派は、それぞれの思惑を秘めながら、別の次元で勢力争いをしていた。
こうした状態のなかで中立的連盟執行部は、もっぱら連盟が「思想団体でもなく政治団体でもなく寧ろ一種の援護団体であり、生活協同体である」(『自由沖縄』第17号、昭和21年11月5日)ことを強調して連盟の統一を推持しようとしていた。こうした姿勢は、第二代目会長仲原善忠の場合も、一九四八年八月の第四回臨時大会で第三代会長の選出された神山政良の場合も、たてまえ的には同じであった。しかし、時代的状況は大きく変わりつつあった。
第一に占領軍の政策は大きく転換しつつあった。解放軍(GHQ)の法衣の下からは鎧がまるみえであった。
第二に、疎開者の沖縄引揚げなどもある程度進行し、援護団体としての連盟の任務の一部は終了しつつあった。
加えて、引揚者の援護活動などに関して、連盟の主導権を握っていた部分から横流し問題などが発生した。後に比嘉春潮は「日がたつにつれ、連盟は一種利権追求の機関となった感があった」
(『沖縄の歳月』中公新書・1969年)と述べているが、沖縄人連盟の設立よびかけ人の一人であり、連盟機関紙『自由沖縄』の創刊号(昭和20年12月6日)から第10号(昭和21年11月15日)までの編集発行人であり、初期数号の『自由沖縄』は自らガリ切りをしてこれを発行していた比嘉春潮をしてこう嘆かせるような状況が表面化してきたのである。当初は成立の必然性をもちながらも、時流に便乗して勢力を拡張してきた組織にありがちな自壊作用が始まっていたともいたともいえるだろう。
こうした状況を背景にしながら、沖縄人連盟は、さりげなくその名称から「人」を削って沖縄連盟となった。団体等規制令が発布され、朝鮮人連盟がまっさきにそのヤリ玉にあげられて解散させられるという時代に。
註
①沖縄人連盟に関する資料は、新崎盛暉編『ドキュメント沖縄闘争』(亜紀書房、1969年)に収録されており、我部政男が簡潔な解説を書いている。また、新崎盛暉編『沖縄現代史への証言』(沖縄タイムス社、1982年)の神山政良、宮里栄輝、国吉真哲の項には沖縄人連盟に関する具体的な証言がある。
②朝鮮人連盟と懇談会をもったり(1946年11月)、機関誌(沖縄人連盟の青年部ともいうべき沖縄青年同盟中央機関誌『青年沖縄』(第1巻第3号)の誌上座談会で沖縄問題への意見を求めたり、ある程度意識的に接触をもとうとした痕跡はあるが、沖縄人連盟が朝鮮(人)問題に何らかの見解を発表したり、具体的に両者に共通の課題を追求しようとした形跡はほとんどみられない。
③ 関西で最初に沖縄人連盟を名乗ったのは、尼崎沖縄人連盟(1945年1月3日)のようであるが『ここに榕樹ありー沖縄県人会兵庫県本部三十五年史』(1982年6月20日、80頁)、11月26日大阪中之島公会堂における関西沖縄人連盟の創立大会に参加したのは、良元村沖縄県人会、神崎川沖縄県人会、城東沖縄県人会、泉州沖縄県人会、堺沖縄県人会、和歌山沖縄県人会で、尼崎沖縄人連盟は参加していない。
その後尼崎沖縄人連盟も参加して、沖縄人連盟関西本部となるが、間もなく沖縄人連盟兵庫県本部として独立し、関西本部は大阪府本部となる。大阪府本部は、奄美出身者と共に南西諸島連盟関西本部として活動したりもする。なお『自由沖縄』の関西版は、兵庫県本部によって発行されている。
④関西地域で旗上げをした沖縄人連盟は、当初から自らに関西沖縄人連盟という限定的名称をかぶせているが東京の沖縄県人連盟は、当初から沖縄人連盟をいわば僣称している。東京は日本の中心であるという意識が働いていたのだろうか。ただ、1946年2月、関西沖縄人連盟と共催で全国沖縄(県)人(団体)代表(者)協議会を開催したときだけは、便宜上関東沖縄人連盟と名乗っている。
⑤伊江朝助男爵、当間重民多額納税議員の両貴族院議員、伊礼肇、桃原茂太、漢那憲和、仲井間宗一、崎山嗣朝の五衆議院議員は、いずれも、沖縄出身者の援護活動に趣意がないというのがその理由であった。
⑥沖縄協会の役員には地方的戦争責任者がおり、かつその選任方法も非民主的というのがその理由で、結局その決議を入れて沖縄協会は改組され、つぎのような陣容となった。(理事長)翁長良保(理事)瀬長良直、比嘉良篤、比嘉春潮、比屋根安定、仲原善忠、永丘智太郎(常任理事)伊元富爾(顧問)伊江朝助、漢那憲和、伊波普猷(相談役)高嶺明達、伊礼肇、桃原茂太、仲井間宗一、大浜信泉、仲宗根玄醅(評議員)(省略)この改組によって連盟は、「かくて懸念された連盟との対立感は全く解消し、協会は救済施設機関となり、全沖縄人の総意代表機関たる連盟と表裏一体となり山積せる沖縄問題解決に乗り出すことになった」(前掲『自由沖縄』第三号)と満足の意を表明している。 参考までに発足時の役員構成はつぎのとおりである。
(会長)伊江朝助(理事)伊礼肇、伊元富爾、仲宗根玄醅、仲井間宗一、永丘智太郎、翁長良保、大浜信泉、桃原茂太、瀬長良直、(監事)久高将吉、護得久朝光(顧問)漢那憲和、高嶺明達
ここに連盟のいう民主化と戦争責任追及の実態が示されているといっていい。わがべ雅男は、前掲『ドキュメント沖縄闘争』の解説のなかで、「石垣島事件」の戦犯減形運動を引き合いに出して、沖縄人連盟の戦争責任追及の限界を指摘している。興味深い問題だが、ここでは紙数と時間の余裕がないのでこの点にはふれないでおく。
⑦1946年1月29日付のGHQ覚書の発表(二・二宣言)による奄美諸島の分離は、一方では、沖縄人という言葉の重みを増すことになったが、他方、GHQの方針に忠実な連盟幹部に、奄美分離に対する対応を迫った。当初連盟は奄美人も沖縄人連盟に包括されるべきだと考えた。初代沖縄人連盟会長伊波普猷は、「最近関西で、奄美大島出身者が連盟に参加したので名称を南西諸島連盟と改めたがよいという議(論)があるそうですが」という質問に対して「そんな必要はないと思ふ。沖縄という名称は私――の『沖縄考』に詳しく論証しておいたが――もと那覇一地方の名称であった。それが三山統一の頃には沖縄本島全体の名になり、近世は支那人は琉球と呼び、沖縄人自身は沖縄と称へた。慶長の頃は大島まで含めて沖縄だった訳だ。南西諸島といふのは本土中心に附けた 便宜的な称呼に過ぎない。大島出身者が参加しても沖縄人だから沖縄人連盟で少しも差支へないではないか」(前掲『自由沖縄』第九号)と答えている。
「沖縄人で差支へない」かどうかは、奄美人の主体的選択の問題である。そして、註③で述べたように、沖縄人連盟大阪本部が奄美出身者の南西諸島連盟(後に奄美連盟)と合流して、一時期、南西諸島連盟関西本部を名乗ったことはあっても、奄美出身者が、沖縄人連盟のなかで、沖縄人として活動したことは、当然ながらない。歴史的、社会的条件の違いは、日本からの分離という現実に直面しても、そう簡単には埋められなかったのである。
それでも信託統治是認派は、「琉球人の一部が琉球の日本復帰運動を潜行的に展開しつつある」(『自由沖縄』第20号、昭和23年1月20日)こと――具体的には、伊江朝助、仲吉良光、神山政良ら62名が参議院に日本復帰請願書を提出したことなどを指すものと思われる――を憂えて、奄美大島出身者と共に「琉球民族問題懇談会」を結成(1947年12月27日)するなど、奄美出身者と共同戦線を張ろうと努力しているが、さしたる効果はあげていない。
⑧すでに『試論・沖縄戦後史』(1974年『沖縄タイムス』連載)や『戦後沖縄史』(1976年・日本評論社)で指摘しておいたことだが、この時期には、保守、革新を問わず、沖縄などの諸小島のうちいずれが日本領に残るかについては、連合国が決定すべき問題であると理解していた。
ポツダム宣言の第八項は、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルヘク、又日本ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」となっており、カイロ宣言は、「三大同盟国(米英中)は、日本国の侵略を制止し且之を罰する為今次の戦争を遂行しつつあるものなり、右同盟は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非ず、又、領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」としていた。
にもかかわらず当時は、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」という前段部分に注目することはなく、「又」以下の後段部分にとらわれていたのである。これはひとり沖縄人連盟に限らず、仲吉良光ら日本復帰派も同じであった。だが、仲吉良光らが沖縄の地位は未決定になっているからこそ民意を結集し、連合国の決定に影響を与えるべきであると主張していたのに対し、信託統治是認派は、ひたすらGHQないし連合国の決定を遵守すべきことのみを説いたのであり、琉球民族問題懇談会の結成も、復帰派の具体的行動に後追い的に対応したものにすぎなかった。
(あらざき もりてる・沖縄大学教授)
沖縄民主同盟――立ち枯れた沖縄独立共和国の夢/仲宗根勇
一 断頭台上に釘づけされた民主同盟=沖縄独立論
苛酷な沖縄戦によって、廃墟と混乱のさなかにあった戦後の早い一時期、戦後沖縄の現実政治と鋭く切り結びながら、他方、同時に、先駆者的な使命感をもって沖縄の未来構想を探り、沖縄独立の「夢」を真摯に語りつつ、歴史の暗い闇の中に、一瞬の光芒を放って、消え去ろうとしている男たちがいる。
戦後初の政党といわれている、沖縄民主同盟に結集した、その一群の男たちのドラマは、未完のまま今なお、沖縄の否定的な現実を突き刺す遺恨の「黙示録」となって、沖縄民衆の心の底の暗部に、隠微な形で息づいている。
「1947年の夏だったか、民政府スタッフ以外の在野のいわゆる『有名人』は民主同盟に入っていた。民政府を批判する当時の沖縄では、唯一の政党らしい存在だったために趣旨賛同者が得やすかったのであろう」(平良辰雄著・『戦後の政界裏面史─平良辰雄回顧録』・南報社・18頁)という事情などによって、民主同盟は、戦後沖縄のその後の政治、経済、教育など、各界で活躍することとなる多種多様な人間群像の貯水池たる様相を呈している。当時の沖縄社会における体制─内─的状況変革者としての相貌をもって出発した彼らの思想と行動は、戦後沖縄の政治思想史上、瞠目すべきひとつの到達点をそれなりに示していると考えられる。だが、復帰運動と復帰思想を疑うべからざる自明の前提としている沖縄多数派の「正統」的な沖縄現代史の中では、すでにして彼らは、永遠の断頭台上に釘づけされたまま、やがて消えゆく歴史の風雪にさらされたままである。つまり復帰主義者の高慢と偏見によって無視されるか、政治=党派主義的裁断によってその積極的な思想性をも含めて、彼らの風貌には、時代の鬼子としてのマイナス・シンボルがまるごと決定的に刻印されてしまっている。しかしながら沖縄が、たぎり落ちる悔恨の涙で、「復帰」の現実に立ち会わされている現在、彼らの軌跡を解明する作業は、「死児の齢を数える感」(大田昌秀著・『沖縄人とは何か』・グリーンライフ・106頁)といった退嬰的な骨董趣味をはるかに超えた思想的意味を持つことは、疑うことができない。その作業の中に、復帰思想に自縛され「国家」に囲い込まれていった戦後沖縄の民衆敗北の原点を探りあてる契機が潜んでいるかも知れないからである。
とはいえ、結党当時の関係者の多くが、あるいは死亡しあるいは第一線をしりぞき、あるいは沈黙しているとしても、なお一方では、現役でバリバリ活動している者も少なくない状況にあっては、民主同盟への照射がその後の各人のそれぞれの政治遍歴のありようを反射的に浮かび上がらせる場合もあることなど、新資料の出現を妨げる要因が多い。そのため、政治結社としての民主同盟の全体像を明らかすることは、著しい困難を伴なっている。まして、その場合不可欠な前段作業となる民主同盟構成メンバー個々人の、組織内における人間的葛藤の力学的分析は、今のところ、ほとんど不可能に近い。そして、彼らとともにあった、敗戦から数年しかたたない当時の沖縄民衆の具体的ありようとその意識を明らかにする基礎的作業も、その際、重い課題として背負わねばならないことは必至である。
そうすると、散在していると思われる多量の資料を蒐集し、かつ多数の証言を聞き書きする共同作業による以外、民主同盟の歴史の真実を全的に彫琢することはできないであろう。従って、わたしは、今ここで、限られた資料に基づいて、歴史「学」小僧よろしく、彼らの思想と行動を科学的に跡づける風の、見てきたような嘘をひとつの断定文に仕立てあげ、わたしなりの歴史的評価を下そうとは思わない。今わたしが目にし得ている資料の範囲で、特殊的にわたしの心を動かす事実を呈示し、さらに、いかなる状況の論理に引きずられて、彼らが挫折し敗北し歴史の地平線の彼方に沈んでいったのか。そしてさらに、彼らのそうした道行きの全体こそが、もしかして、現在および将来における沖縄の少数派的政治=思想の悲劇的運命を、歴史の上で予告的に演じ切って見せたひとつの思想的実験の構図にほかならないのではないのか。そうしたことが、わたしのさしあたりの序論的問題関心のあり方である。言いかえれば、手垢にまみれた政治主義的断罪によって、「買弁イデオロギ−」とくくられてしまいがちな彼らの沖縄独立論の思想の核は、真正な沖縄自立論つまり、「復帰」後の今日と明日の沖縄の最尖端的思想課題である沖縄自立の思想的系譜の中に、正しく位置づけられねばならないということにほかならない。敗者の伝説を洗い出す足下に、沖縄自立を展望するひとつの思想的鉱脈が横たわっているかも知れないからだ。
二、独立論から復帰論への転轍のダイナミズム
1945年4月、沖縄上陸間もないアメリカ軍は、読谷山村に海軍軍政府を設立、布告第一号(ニミッツ布告)で「南西諸島および其近海並びに其の居住民にたいする日本帝国政府のすべての行政権の行使を停止」することになった。
かくて、沖縄は、悪夢のような大日本帝国の支配から離脱した状態におかれた。同年8月には、いち早くアメリカ軍は、軍政府の協力機関として、沖縄諮詢会を設立し、「つづいて同年9月には諮詢会に地方行政緊急措置要項(仲宗根源和著『沖縄から琉球へ―米軍政混乱期の政治事件史』・月刊沖縄社・巻末資料編では要綱となっている―筆著注。)を作成させて全島十二市で市会議員と市長の選挙を行なった。これにより米軍の沖縄占領から大体三ヵ月後には、軍政府――諮詢会――住民の形であらわされる統治構造がなんとかでき上がった」(『沖縄の証言』・沖縄タイムス・103頁─傍点筆者)のである。諮詢会は、翌46年4月には、沖縄民政府に発展し、戦後沖縄の政治世界もアナーキーな政治的真空状態を脱して、スタティックな政治人脈が秩序的に形成されていく。
ところが、こうした政治人脈につながり、「統治構造」の中へ各地の避難村から入ってきた人々の多くは、すでに戦争前の旧秩序アンシャンレジーム、すなわちヤマト世において「立身出世」をはたし終えていた教育関係者や警察関係者、役人や県会議員であり、何らかの形で、戦争に加担協力した「有名人」であった。(戦後、彼らの多くは、戦争体験を内省せず、何らの戦争責任をも問われることもなく、アメリカの植民地的沖縄支配体制の内側に入り込み、スンナリ生き残っていく。うるわしき日本への甘い思い出を持ちえた彼らの戦後支配秩序での指導性の回復は、戦後沖縄の政治的社会的性格を大きく規定することになった。こうして、日本への救済願望をかけた復帰思想の人的培養基は、すでにして構造的に準備されていたのである。)
そうした事情をおさえれば、「沖縄民政府は、いわば単なる人のつながりみたいなもので、何とか生命をつないでいたような感じだった。私が、以前にすすめられても、民政府入りをしなかった理由の一つはその辺にもあった」(平良辰雄著・前掲書・45頁)という回顧は、率直に受けとってよいであろう。
一方、「逆光線の/背後から追い立てる/アメリカ兵を/気にしながら/豚のように歩く」(牧港篤三 詩・儀間比呂志 版画・『沖縄の悲哭』・集英社・四四頁)民衆、いくさば(戦場)の地獄をかろうじて這いくぐり捕虜収容所、そして変りはてたわが村わが家に落ちのびた民衆の精神風景を彩ったのは、えも言われぬ自由感、国家や権威や、その他もろもろの呪縛から解き放たれた、心地好い真空意識とでも言うべきものであったに相違ない。そこには、「日本」や日本「国家」に対する陽気な期待感も、気重な疎外感もともになく、原始的な自然状態の中で、民衆は、生きていることの心底からの喜びを、ものみな崩れゆく崩壊感覚の中で実感していたであろう。
明らかに民衆は、「母なる祖国」というような甘ったれの国家幻想とは無縁の地点に立っていた。つまり、戦後初期のように横溢していたことは、ほとんど自明なことと言ってよい。要するに、「沖縄自立=独立論」こそが、当時における正統かつ多数派的な沖縄の思想にほかならなかった。そのことの歴史的立証はそれほど困難なことではない。そして、戦後初期に支配的な自立思想の誕生を表現したひとつの政治的結晶が、まさに沖縄民主同盟そのものであった。
だが、言うまでもなく、戦後初期の沖縄自立の思想は、沖縄戦後史の中を主流のまま突き進んだのではなかった。それはいつしか、沖縄の未来イメージを欠如させたやみくもな日本復帰論に挟撃され立ち枯れていく。その時点においてすでに、戦後沖縄の民衆運動の敗北が、ほぼ決定的に告知されてしまったと言ってよい。
しかしながら、このように、「沖縄独立論」が「日本復帰論」に転轍されてゆく社会史的ダイナミズムを明らかにする試みは、これまでのところ、ほとんどなされていない。むしろ、個人であれ政党組織であれ、当初何らかの形での沖縄自立論者であった者たちは、その前科(!?)を縫合・隠蔽し、「はじめに復帰論ありき」という体の詐術の体系の中に身を隠し口をぬぐって恥ないというのが実相である。
限られた資料によってであれ、沖縄独立論の主張者としての沖縄民主同盟の生成、発展、消滅の過程を検証することは、独立論から復帰論への転轍のダイナミズムを解き明かすための、ひとつの重要な手がかりを与えることになるであろう。戦後沖縄の民主化など多様の政治的主張をかかげた民主同盟を、いまここで「独立論」にしぼって素描しようとするわたしのモチーフはそこにある。
三 沖縄民主同盟の生成
1982年3月15日から「沖縄戦後史シリーズ」と銘打つ企画の一環として、『琉球新報』に連載された山城善光氏の「荒野の火」には、まさに民主同盟結成の索引車となった当事者自身によって同盟結成の歴史的経緯が仔細に跡づけられており、新しく公開された資料として貴重なものである。このほか、今回わたしは、未公開と思われる資料を含む数点の資料を入手できた。既存既知の資料のほかに、民主同盟に関する今回の新しい資料をあわせ検討してみると、自立した沖縄社会を構想した彼らの“見果てぬ夢”の質と量が、いかなるレベルのものであったのか、その甘さと限界、彼らが何のため、だれの意志を表現したのか、従って、分離・独立へ向うべきはずの沖縄の時代状況の下で、その民衆の願望を終局的に統合できず、彼らの思想と行動が歴史の主役たる地位からすべり落ちる歴史の構造が、おぼろげながら析出できるような気がする。
沖縄民主同盟の中心的イデオローグとして、また精力的な組織者(結成当初は事務局長、後に委員長)として活躍した仲宗根源和氏は、前掲『沖縄から琉球へ』の中で、「(同氏が戦後にとってきた基本的立場・考え方に)一致共鳴する人々が集まって志喜屋政府に対する批判者の役割を果した。それは民主同盟という政治結社の形をとっていたけれども、実質的には政治啓蒙運動であり、官次主義に対する自由民権の運動であった。此の運動は沖縄に帰還した人々(日本及び南洋方面から)の参加により活発化した。大城善英、照屋規太郎、山城善光、上原信雄、添石良恒、桑江朝幸、中山一等の諸君は此の運動の中心をなす活動分子であった」(同書・231頁)と述べている。
その山城善光氏は、1946年12月1日、本土から帰還した。(「荒野の火」1)。氏は、戦前すでに大宜味村政革新運動及び消費組合運動、そして日本共産主義者団事件に連座した社会運動家である。灰燼の戦後沖縄の姿に衝撃を受けた氏は、若き日の「山原の火」の心をよみがえらせ、いち早く社会的活動を再開する。
当時、民政府批判が強かった中で、山城氏らを中心に在野の人々が急速に糾合されていく。その政治的結実が1947年5月5日、知念高等学校講堂に300名の全島代表を集めて開催された「沖縄建設懇談会」であった。「荒野の火」(10)によれば、その趣意書及び発起人は次のようであったという。
沖縄建設懇談会趣意書
戦争終結後軍政府当局及び民政府当局が、沖縄建設の為其の蘊蓄を傾け盡瘁された事に対し、吾々島民は感謝に堪えない次第であります。然るに熟々沖縄の現状を凝視します時、民心は五里霧中まことに混沌として、未だに虚脱の域を脱し切れず、その帰趨に迷い、道義的には頽廃の一途を辿りつつありまして、文字通り憂慮すべき事態に立ち到って居る様に思われます。之は今次世界大戦に於いて、精神的に物質的に、最大多数の最大犠牲を蒙って来た処に基因する無理からぬ事でしょうか。しかし吾が郷土の有史以来嘗て見ざる道義の頽廃、経済の混乱は、吾々の断じて黙過し得ざる事であります。
抑々荒廃し切ったこの沖縄の建設は、吾々に負荷された歴史的大事業でありまして、申すまでもなくその前途には幾多の苦難が横たわって居るのであります。この苦難を乗り切る事は、官も無く民も無い処の軍に呼應する官民を打って一丸とする総立ち上がりの力のみがよくする処であります。茲に於いて吾々は相寄り相諮り、その淵源する処を究明し、以て或いは陳情し、或いは建築的意欲を旺盛ならしめる契機たらしめんとして居るのであります。
凡そ人心交替の根本は正しい世論によるものでありまして、之は人に光明と自由とを喚起し、新展開を迫るものであります。茲に局面展開を図る本懇談会を通じ、新沖縄建設に挺身せんとする同志諸君の賛同を願うと共に、奮起を促す次第であります。
一九四七年四月二十三日
沖縄建設懇談会起人(イロハ順)伊中皓 南風原朝保 桃原茂太 富山徳潤 当間重剛 当山寛光(遠山謙) 与儀喜宣 平良辰雄 平良助次郎 嘉数昇 仲宗根源和 仲里朝章 具志堅興雄(真喜志) 桑江朝幸 山田真山 山城善光 真栄城守行 真栄城守仁(前川) 金城田助 宮里栄輝 宮城友信 比嘉信光 瀬長亀次郎
懇談会のテーマは、(一)民意を代表する機関設置問題、(二)道義昂揚問題、(三)生活安定問題等を中心とするものであった。
それぞれのテーマについて、出席者が活発に論議しあったが、(二)に関連してなされた仲宗根源和氏の次の発言が注目される。
現在の青年層に希望が與えられてないから道義的には頽廃しているのだとの点はもっともだ。闇の中で道義昴揚を云々したところで求められるものではないが、しかし前に光がある希望は自らわいてくることである。青年に接する時は沖縄に希望が持てる点を語ることである。すなわち沖縄は民主共和国になるのだと叫ぶ時、彼らは雀躍するのだ。沖縄はこのまま放置すれば米国一国による信託統治になる。信託統治は将来独立を約束されているのであるが、沖縄は元々独立国家であったのであるから、われわれは独立するんだとの意気で行きたい。そして米国とも親善関係を結び、ひいては国際連合にも加入するのである。今日かくの如くになったその根本的原因の一つは、食物がないということである。ゆえに将来、世界と親善関係を結んで南方諸地域にも進出し、次々と新しい土地を開拓して、沖縄移民をどしどし送って行けば、沖縄は健全に確立されて行くのである。もし沖縄が信託統治になるにしても、信託の年間をわれわれの手で縮めることができる。それはわれわれが自主的に政治をとることができるか否かによって決まる。アメリカは宿を借りているだけに過ぎない。(「荒野の火」(15)─傍点は筆者)
この発言について、山城氏が次のようにコメントしていることは重視すべきだと思う。つまり、氏によれば、仲宗根源和氏の独立論の公的表明が早くもこの日になされたということになるからである。
ただし、仲宗根源和氏自身は、一九五一年五月一日琉球経済社発行の雑誌に書いた「琉球独立論」の中で、ポツダム宣言の日本語訳を読んだ一九四五年八月中旬に「私の腹の底には琉球独立論がはっきりした形をとって出来あがったのであります。……翌一九四六年の秋頃から私ははっきりと『琉球独立論』という表現をとってその理由を明かにしました。」とのべている。
仲宗根先生の右の発言中に、沖縄の将来の将来の在り方について、沖縄はそのままほっておけばアメリカ一国による信託統治を経て独立国になる。然し沖縄は元々独立国であったから、我々は直ちに向って邁進するんだとの沖縄独立論を公的な場において、初めて発表されたことである。
それが沖縄民主同盟は独立論者だと、規定される原因となった。また事実、仲宗根先生は演説会においても独立論をぶち上げておられた。(「荒野の火」(16)─傍点筆者)
この懇談会の模様は、それから約二週間後の一九四七年五月二十一日付で、沖縄建設懇談会懇談記録報告の件」と題して、「沖縄建設懇談会與儀喜宣外発起人一同」から「沖縄民政府知事志喜屋孝信殿」宛提出される。そして、それから一週間後の五月二八日、石川市の中央ホテルで、仲宗根源和、大宣味朝徳、平良助次郎、伊波久一、山城善光、真栄城守行、桑江朝幸、吉元栄真、桃原茂太などが集まり、第二回目の懇談会が持たれた。「懇談会の発起人全員に集まっていただくようにお願いしてあった。それは懇談会の事後処理報告と向後の運動方針設定のための会合であった。ところが、どうしたことか、参加者が……わずか十名前後の淋しい集まりとなってしまった」(「荒野の火」(20))
その日は、前述の懇談テーマ(一)の「民意を代表する機関設定の具体的方法」について協議したが、議論は沖縄の帰属論にまで及んだ。(同、(21)─傍点筆者)
伊波 久一氏 沖縄人は一国としての国民的な性格を持っていると思われるが、一体沖縄はいかなる統治形態になるかについて伺いたい。
山城 善光氏 沖縄の運命はカイロ宣言、大西洋憲章によって規定されている。即ち沖縄から日本勢力は駆逐されてその権力は及ばなくなっている。沖縄の辿る経路としては、国際連合による信託統治、または米国一国による信託統治を経て、将来ある時点になると、沖縄人自体で沖縄の在り方を決めなくちゃならなくなる。今のところ、米国や一国による信託統治の線が強いけれども、信託統治が沖縄にとっては望ましい。最終的には民族自決の法則によって沖縄の独立は可能である。今の段階では、飽くまでも沖縄人の沖縄だという自主性を守り続けることが重要である。
真栄城守行氏 沖縄処分について、ある人の話だが、アメリカの管理下における沖縄の独立。アメリカと沖縄人との共同による沖縄の管理。日本へ返す。支那に与える。この四つの方法があると話していた。
仲宗根源和氏 沖縄は沖縄人による沖縄であって、将来は民主独立国を建設すべきである。
そして、その日、満場一致で「沖縄民主同盟」という名称の政治結社を発足させることが論議・決定された。
引続き事務所の設置、会員獲得の方法、スローガンの必要性等を論議し、出席者全員が設立準備委員の候補者になることを決定した。そして最後に、結社設立準備委員の候補者になることを決定した。そして最後に、結社設立大会の日を6月10前後とし、石川市で盛大に結党式をあげることを決定して散会した。(「荒野の火」(23))
こうして、「沖縄建設懇談会で口火を切られた民主化運動が発展して、約ひと月後の1947年6月15日、石川市宮森初等学校で、『沖縄民主同盟』が結成された。」(前出『沖縄の証言』・202頁−傍点筆者)(同書をはじめ他の著書や、後で述べる政策協議会等に関する石川署長の状況報告書、そして山城氏も結成月日をそれぞれ6月15日とされているが、1949年12月10日付、沖縄民主同盟事務局から、「沖民同庶第五號」として、沖縄民政府総務部長に提出された「政党調査照曾囘答」と題された文書には「政党組織期日一九四七年七月十五日」と記載されている)。
山城氏によると、党結成式には、石川市の38名を筆頭に北部を中心に中部南部の15の各市町村からそれぞれ1〜5名の有力者たちが集まり、同氏が経過報告をし、仲宗根源和氏が結党の趣旨を述べ、次のような宣言とスローガンを決定し、さらに役職員も決定したという。(「荒野の火」(24)─傍点筆者)
宣 言
吾等は沖縄人による沖縄の解放を期し、新沖縄の先駆として行動する者なり。沖縄は日本政府の圧政と侵略主義の為に斯くも惨憺たる運命に遭遇せり。焦土沖縄は沖縄人の沖縄なりとの自覚によってのみ再建さる。吾等茲に沖縄民主同盟を結成し、悲願達成へ奮然と起ち上がり、世界平和に寄與せん為スローガンを掲げて茲に宣言す。
一九四七年六月十五日 沖縄民主同盟
スローガン
一 沖縄人の沖縄確立
二 民主々義体制の確立
三 内外全沖縄人の連絡提携
四 講和会議への参加
五 日本政府による戦災の完全補償
六 民営事業の促進と重要事業の官営
七 土地の適正配分
八 最低生活の保証
九 悪性インフレの徹底的防止
四 沖縄民主同盟の独立論
右の宣言とスローガンをみる限り、その中には、直截な形での独立論の主張は含まれないかに思える。新崎盛暉氏が、「民主同盟が、独立論を掲げて結成されたということはありえない。民主同盟が、独立論といわれるものは、むしろ、設立から解散(50年10月共和党に合流)まで民主同盟の中心的位置にいた
仲宗根源和の主張であったが、彼が全面的に独立論を展開するものも、50年代にはいってからのことである」(『戦後沖縄史』・日本評論社・23頁)と述べるのも、一応、首肯しがたいことではない。しかし、果して、そうであろうか?
ここにひとつの資料がある。1947年9月8日付石川警察署長から沖縄民警察部長にあてた、「民主同盟政策協議会並発表演説会開催ニ関スル件」と題する状況報告書である。今も変わらぬ公安警察の、当時における活動の一端を示す興味ある一種の密偵資料と思われるが、それは「1948年一月以降 沖縄民主同盟に関する書類 總務部」と表紙に記された、ひとつづりの書類の中の一部として残されている。
それによれば、沖縄民主同盟は、結成から三ヵ月もたたない9月6日と7日の両日にわたり、石川市大洋初等学校で政策協議会と政策発表演説会を開催している。
六、七日の協議会の出席人員は、仲宗根源和、桑江朝幸、山城善光、真栄城守行、大城善英、伊波久一、平良助次郎氏など26名、7日の演説会聴衆男約60名女なしというものであった。「自九月六日午后一時至同日午后六時半自九月六日午前十時至同日午后二時迄二日間ニ亘り左記(第一)政策ヲ各自提案シ意見ヲ開陳審議ノ結果朱書ノ通リ補足又ハ追加訂正削除ノ上萬場一致ヲ以テ可決シタ」(同報告書)。
そしてその「沖縄民主同盟政策表」は上下に区切られ、上部に「緊急対策」、下部に「恒久政策」として次のようなものが記載されている。まず、「緊急対策」は政治、経済、社会、教育、産業、交通運輸の六分野にわたっている。
政治の部は、一 民主政治ノ確立─議会政治ノ促進、三権 司法 立法 行政 分立、二 講和会議へノ代表派遣、三 内外沖縄へノ連絡提携、四 中心都市ノ設定(軍官民ノ協議ニ依リ)、五 農業組合並に水産組合ノ民主化、六 預貯金各種保険金ノ(在外資産戦時災害保護法ニヨル給与金)接受促進、七 完全復興ニ対スル連合國へノ陳情、八 出版報導ノ自由の八項目である。
経済の部は、一 島内生産品公定値ノ徹廃(買占防止、外地へノ横流防止)、二 生産組合ト消費組合ノ直結、三 沖縄独自ノ貨幣発行、四 各種工場ノ促進(取消)となっている。
社会の部は、一 民主的労働者ノ設定ト労働者ノ待遇改善、二 土地所有権ノ確立(削除)、二 俸給生活者ノ生活保証、三 元居住部落へノ復帰促進、四 阜頭倉庫ノ設置ト市町村配給所トノ直結(地區中央倉庫ノ廃止)、五 日常生活必需品ノ円滑ナル供給、六 医療衛生薬品ノ整備補給ト医療制度改革、七 規格家屋ノ補強(カバ屋ノ解消)建設促進、八 薪炭対策ノ樹立と、きめが細かい。
教育の部は、一 教育制度並施設ノ整備確立、一 留学制ノ確立、二 教育界ノ革新、三 文化施設ノ整備拡充がうたわれている。
産業のうち農業の部には、一 農耕地ノ拡張ト各市町二即應セル使用権ノ適正配分、二 家畜移入促進ト畜舎ノ家敷内設置容認 飼育ノ簡易化、三 農業ノ富力化ト機械化、四 肥料種苗優良農具等ノ移入促進ト適正配分、五 農産加工施設ノ促進、林業の部には、六 林道開発、七 計画植林ト計画伐採、漁業の部には、八 爆発物毒物使用ノ撤底的取締、九 遠洋漁業ノ促進、一〇 漁具ノ移入促進ト適正配給、工業の部には各種工業ノ促進、地下資源ノ開発が番号をうたずに並列される。
交通運輸の部は、一 陸海交通運輸業ノ合理化、二 陸海運輸難ノ解消(削除)、三 港湾ノ解放の三項目である。
次に、「恒久政策」としては、以下のようになっている。
(政治)
一 独立共和國ノ樹立
二 税制ノ確立
三 移植民ノ促進
(経済)
一 国際自由貿易ノ促進(保留)
二 重要産業ノ沖縄人ニ依ル支配(半民半官)
三 地下資源ノ開発(削除)
四 金融機関ノ整備
(社会)
一 婦人ノ政治意識ノ昂揚
一 婦人ノ権利伸張
一 恒久住宅ノ建設
一 救済制度並施設ノ完備
(教育)
大学専問学校ノ設置
(産業)
各種工業の促進
電化ノ促進
地下資源ノ開発
灌漑施設ノ促進
以上が、警察資料が伝えている「沖縄民主同盟政策表」の内容である。政策協議会に「臨監」した警察官は、警部補一、巡査部長一、巡査三の計五人であり、報告書は三人の巡査によって速記されたことになっている。
すると、報告書の内容は、ほぼ正確に近いと考えられる。そこで、われわれは、同盟の「恒久政策」の筆頭に「独立共和國の樹立」が麗麗しく揚げられることに注意したい。現時点でも部分的に通用しうる各人の多方面にわたる議論・発言の内容(例えば、照屋規太郎氏の医療制度の合理化=自由開業と公営開業の二本建案など)が、同報告書で報告されている。(この部分はひらがな文字が使用されている)。その中で、
仲宗根源和氏は、婦人の政治意識の昂揚、スト権を認めた労組法の必要性、移植民の促進、民主政治の確立などについて先駆的な意見を述べた演説の最後に次のように語っている。
「次は独立共和國の樹立でありますが、英帝國の連邦会議の意見としても小笠原と沖縄は米國の主権であると言ふことを認るのであります 此れも一つの謀略であります米國に向ふを渡し又向ふではどの國を貰ふと言う風に一つの謀略であります 現在に於て日本復帰の希望も相當にある模様ですが若し人民投票に依って日本に帰るとなった場合一番危険を考へるもので御座います 米國は沖縄の土地を總ての方面から考へても決して帰しはせないはずです 仮に日本に帰へすにしても事質の上に租借地として永久に浮べない民族にならなければならなければ苦しい立場になるのは當然のことです これを独立共和國としてアメリカと親善関係を結びアメリカの主権の下に置かれた場合でも市民権を認めてくれるとか言ふことも考へらますのでこの際我が党は民族戦(線?)として人民党と一緒になり又日(内)外沖縄縣人が連絡して提携し打って一丸となり虚心担攘(坦懐)現状の打開に邁進して行き度いと思ひます」(傍点筆者)
この政策協議会で満場一致で可決され、「沖縄民主同盟政策表」に書かれた事項が、その後、同盟の中でどのように政策化され綱領化されたかあきらかではない。しかし、それは、1948年5月頃に開かれたという第二回党大会で決定された「沖縄民主同盟綱領」と「宣言」の中に反映されていることは疑いない。その綱領は、「一、本同盟は全琉球民族の速かな統合を図り、その自主性の確立を期す一、本同盟は民族多数の名に於いて一部の階級の利益を貪らんとする一切の不正と斗い、共存共栄を本旨とする琉球の建設に努力す一、本同盟はポツダム宣言大西洋憲章等の国際公約の連合国による履行を確信し、琉球の速かなる解放を期す」とし、続けて「宣言」は、「琉球は厳として琉球人のものなり。吾等は琉球の民主化を阻む一切の封建的陰謀と断々乎として斗うと共に琉球の自主性確立のために勇敢にその政策を推進す。右宣言す。」(「荒野の火」(50)─傍点筆者)
この綱領と宣言は、明らかに、「政策表」の「恒久政策」の筆頭にかかげられている「独立共和國の樹立」と脈絡をなしている。そして、これまでみてきた沖縄建設懇談会から党結成、そしてその後に至るまでの党員相互の議論や宣言、スローガン中の発言や文言(特に筆者が傍点を附した部分)は、民主同盟自身が全体として、沖縄独立論の主張者であったことを示している。だが、一般には独立論は、
仲宗根源和氏の個人的見解にすぎないとし、民主同盟と独立論とは切り離して考えられている。例えば、「沖縄民主同盟の政治的立場は、同党幹部の個人的発想の反映とみてよい」(大田昌秀著・前掲書・107頁)とか、はては前に引用した新崎氏のように「民主同盟の独立論といわれるものは、……
仲宗根源和の主張であった」のであり、「民主同盟の場合は……同盟としての主張のなかに独立論をみることはできない。」と断定されている。いずれも明文化した綱領がないとされていること、党の目的の文言を、その根拠としているかのようだ。(ちなみに、新崎氏が「設立当初の党の目的」とされている「沖縄の政治、経済、社会、文化、教育等の民主化を促進し、その展開確立するを以って目的とす」という文言は、前述(30頁)した1949年12月10日附、つまり同盟解散10ヵ月ほど前の沖縄民主同盟事務局から沖縄民政府総務部長あての「政党調査照曾囘答」中に記載されているもので、設立当初のものではない。より当初の資料としては、民同庶第一号として、1948年2月20日附、沖縄民主同盟事務局長仲宗根源和から沖縄民政府知事志喜屋孝信にあてた「政党ノ職責報告ノ件」と題する、「1947年10月15日発米國軍政府特別布告第二十三号ニ付一九四八年二月日所轄首里警察署ヲ通ジ正式ニ書類提出方ノ指示アリタリ。依ッテ同布告第二条 a項、b項、c項、d項 ニ基キ別紙ノ通リ報告書及提出候也」という事情の下で出された文章資料がある。その中に記されている目的は、カタカナ文字で「一、目的 沖縄ノ政治、経済、社會、文化、教育等ノ民主化ヲ促進シ、ソノ確立展開ヲ期スルヲ以テ目的トス」となっていて、文言に微妙な差がある。)
右の報告文書中に「三 綱領 明文化シタル綱領ナシ。右ノ目的ノ條項ノ主旨ニ基キ、全島的ナ組織ノ確立ヲ見タル上、全支部ヨリ提出サレタル政策ヲ綜合シ、更ニ要約シテ初メテ綱領ヲ掲ゲル方針ナリ。」と言っていることは、文字どおりには受取れない。その報告書の性質、出された状況、当時の反民政府感情等を考慮すれば、文言の背後に、彼ら民主同盟の政治戦略的配慮を読み取る必要があろう。
沖縄民主同盟に関する誤謬の歴史は、曇りのない眼によって、たださなければならない。
五 沖縄民主同盟の消滅・歴史の審判
戦後沖縄の政治、経済エリートの貯水池となり排水口ともなった民主同盟の指導者たちは、現実問題として、独立共和国の夢を現実化する政治指導の軌跡を示してはいない。のみならず、「独立共和国の樹立」という、彼らの、いわば「最大限綱領」を、当時の軍政府−民政府下での民主化の諸要求という「最大限綱領」と架橋するいかなる政策的思想的展開も語られてはいない。しかし、独立共和国の樹立が、近い将来の沖縄社会の理論的目標として、彼ら民主同盟員の共通の観念の中に厳然と存在していたことはもはや疑うことができない。まさに時代は、戦争・敗戦・混乱という外的衝撃によって、旧来の支配機構、価値観が崩壊したときである。数千名(前述の「政党調査照曾囘答」では全党員数2000名となっている)の党員をはじめ、広範な沖縄民衆に、沖縄独立の少なからぬ思想的=政治的影響を及ぼしながら、民衆のエネルギーを、新たな歴史的地平へ嚮導することができず、そのエネルギーを、「盲目的日本復帰論者はやがて日本に対してえんさの声を放つ可能性さえある」(
仲宗根源和・「琉球独立論」)と彼ら自身によって、的確なる予見をたてられた単眼短見の手中に委ねてしまった。
時代状況に翻弄され必ずしも明確に歴史の方向を透視しえなかった沖縄民衆に、彼らは、当面の争点(例えば、「民政府の独裁」(仲宗根源和)、生活問題など)を提示し、民衆に・救い・を与えようとした。だが、「敗戦という大きな挫折の体験を思念の挺子として、戦後へ出発することもできなかった」(川満信一著・『沖縄・根からの問い』・泰流社・29頁)彼らには、当然のことながら当時の国際的な政治力学、アメリカ占領軍の権力規定を明らかにし、“解放軍”幻想からさめる契機を持ちえなかった。「親米反日的な琉球独立願望」(祖根宗春、前出琉球経済社)というようなドンキホーテ的悲劇が、ここに胚胎する。群島知事、議会議員の公選要求等の建設的政策の提起、そして、ときに志喜屋民政府へのプレッシャーグループ的活動を、本部のほか国頭村、大宜味村、名護町、今帰仁村、上本部村、本部町、屋部村、石川市、越来村、首里市など各支部への地域的広がりの中で繰りひろげた彼らは、軍政が投げ与えた群島知事、議会議員選挙をめぐって粉糾、内部分裂・離反する。各々が、既存の体制に安住しそれに依拠して、いびつな権力階梯を志向する政治・思想的破局の訪れである。そして、定員20名の群島議員に五人の候補者(山城善光、中山一、照屋規太郎、桑江朝幸、仲宗根源和)を立てた民主同盟は全員落選という冷厳な結末を迎える。
こうして、1950年秋、沖縄民主同盟は結党三年余にしてついに瓦解する。ほぼ同じ頃、元大政翼賛会沖縄県支部壮年団長平良辰雄氏を委員長とする復帰政党=社会大衆党が結成され、復帰運動の組織的胎動も間もなく始まる。─―それから二十数年ののち、歴史は沖縄に仮借なき審判を下すことになる。「72年核抜き本土並み返還」という出口なき処分を…‥。(なかそね いさむ・評論家)
琉球独立党――“十年遅れの問いかけ”として/平良良昭
はじめに
新沖文の編集部の方から琉球独立党について書いてくれという依頼をうけた時、はじめ今の自分には無理な仕事だと思われ、断わりたい気持ちだった。なりわいに追われ、関わっている進行中の運動に時間をさくのに手いっぱいという自分の状況を考えると、先ず書く時間をひねり出すのが容易でないということがあった。その上、琉球独立党について批判的に見直していくという作業をするには、それをしようとする自分自身の足場がまだそれを充分にやれる程しっかりしたものとは思えない。かといって歴史研究者的な客観主義的な立場やジャーナリスティックな立場からこの対象をとらえるには、自分は不適格者であることは明らかだった。それらの方法をこなしていく自信はさっぱりない。せめてこのテーマに関して研究者やジャーナリストたちの仕事が先行し資料として蓄積されていれば、自分の足場がたとえあいまいなものでも評論家風に何か書けるかもしれないとも思うのだが、それもない。少くとも自分には思い当るものがない。
とすれば、琉球独立党より十年遅れで、自立−独立問題を自分のテーマにしている人間としてやってみるしかないことになる。<自立>ということばはともかく独立ということばを主体的責任をもって公開の場でテーマにしはじめたのは僕にあっては丁度十年、遅れている。そういう立場でやってみるしかないことになる。
概ねそういうことで断りたいと告げたのだが、それでよいからということであったので引きうけてみることにしたのである。テーマそのものは、僕のテーマでもあった。しかし81年1月1日発行の自費出版パンフ『沖縄――自立と独立』でこのテーマに触れた時から、作業は一歩も前進してない。やってみるとしても、次の半歩か一歩くらいしか前に進めないだろう。だから読者は、たいして期待せずに読んで欲しいのである。
さて、書くということを前提に考えはじめてみたものの、気重な感じがつきまとって、考えは進まない。その原因のひとつは琉球独立党が運動、組織としてはすでにその生命力をつかい果たし、解体して過去のものになっているらしい様子なのに、その運動を担った当の人々は同時代人であって、まだ沖縄のあちこちで生活しているという事実にあるようだ。その人々のうちの一人とはいささかのつき合いがあるということも災いしているようだ。
「今は思想や構想や志、理論よりも、それを言った人の方が長生きする時代だ……」と現代の特徴を指摘して僕の友人が言ったことがある。「ほんとだァ、ハハ…」とその時は笑ってすましたのだが、こういう立場に立ってみると、笑ってはいられない。せめて琉球独立党が生きて活動していればもう少し果敢な気持ちでこの仕事に取り組めたと思うのだが…。
何はともあれ、とっかかってみるしかあるまい。
Ⅰ 野底氏に会う
この7月24日、あらかじめ電話で意図を伝え、了解を得て、野底氏宅を訪ねた。
那覇商業高校のすぐ近くに、努迦土南公認会計士事務所の看板が掲げてある。市内にしては広大といえる敷地に無造作とも見える住宅があり、事務所らしいプレハブが継ぎ足されている。
幼児から小学校低学年までの活発な明るい子供たちが三人、にぎやかな家庭と見受けられた。
氏とは初対面であったが、毒舌家野底土南の文章から受ける印象はそこにはなかった。色白、中年も終りに近い子供になつかれている父親、という感じがした。
新沖文48号の特集「琉球共和国へのかけ橋」がすぐに話題になった。ヤマトにいる友人からの電話でこの特集について知らされたとのことだった。それはそのまま新沖文編集者への不満・批判につながった。
さて、僕が琉球独立党のことを考える時、真先に浮ぶ疑問がある。それは、<彼らの運動、組織はなぜ持久しきれなかったのか>ということである。
残された文献の日付は72年8月発行の『三星天洋』(琉球独立党教育出版局)が最後のものらしい。
琉球独立党がつぶれた原因は、一体何なのか。権力の弾圧をうけて、組織が破壊されたということではなさそうである。そもそも弾圧を招くほどの行動が組織されたのかどうか? そんなニュースにも接していない。返還後の沖縄闘争の全般的退潮――チルダイ状況のなかで、彼らの運動も例外でなかった。というよりむしろ、モロにその状況を反映したくちといえそうだ。それは彼ら自身の主体的な要因にあると思われるのである。
どうしてか?
復帰、返還後の十年の現実は、よくも悪しくも復帰返還の内実が具体化していく過程であり、日本国家の沖縄再支配・統合の過程だったこと、それへの民衆の抵抗の過程だったことを考えるならば、そしてそれ故に復帰への幻滅と自立の志向が少なからず芽ばえる時代でもあったことを考えるならば、琉球独立党にとっては、支持者や共感者を増やして当り前といえる時期であった筈である。にもかかわらず、 その時期に彼らの活動は停止する。これをどう考えればよいのか?
僕は前述の様な関心をもって、氏の話を聞き続けたが、氏の話は概ね72年8月発行の『三星天洋』に述べられていた氏の持論と重なっていて、やむなく直截に質問を発してみる。
問 琉球独立党の発足はいつごろでしたか?
答 1970年の夏だった。
問 そのところ中心になったメンバーはどういう方々でしたか?
答 崎間敏勝さんや私、それにヤラ君という青年が熱心だった。また復帰によって不利益をこうむる経営者たちなどがあつまって、「沖縄人の沖縄をつくる会」の動きもあった。けれどもある大物になだめられて、立ち消えになった。
問 現在のところ、外からみる限り解散状態にある様に見えますが……
答 そういう状態だな。
問 運動として続かなかった原因のうち、内部的な原因もあると思いますが、その点はどう考えていますか?
答 沖縄人の性格ではないかね。島津以来のドレイ教育で自立心を失くしてしまった。また僕は当時再婚して、子供が次々できて、子供を育てるのが先決問題になって、動けなくなってしまった。
しかし、あの時期、我々が独立を主張したことは、沖縄人のみんながみんなバカではないことを示したと思っている。これは将来必らず生きてくる。我々の当時の主張が理解される時がくる。成功しなかったという結果だけが重要なのではない。
問 今、復帰後十年たって自立ということばは当り前となり「独立」問題も考えようとする気運が芽ばえていますが、再び運動を起す考えはありますか?
答 やっぱり子供を育てるのが先決だからな……独立ということを言わなくとも地方自治をめぐっていろいろな矛盾が出ている。その矛盾に取り組んでいる。与那国の僕の土地が、土地改良事業ということで勝手に現状変更されてね、裁判に訴えて国に補償要求をつきつけ闘っている。国家財政をそういう形で窮地に追い込むのも闘いだ。反省させるのも目的だ。(ノートより再現・文責―筆者)
機を見ては関心に沿って質問を繰り返してみるが、かみ合わない。僕の一人ズモウになってしまう。どうやら、氏に答えてもらおうというのがそもそも無理な様だ。運動家というよりは啓蒙家、組織人というよりは生活者、革命家というよりは毒舌家、理論家というよりは激情家、行動者というよりは計算家、指導者というよりは構想家、……それが氏の身上というものかもしれない。氏の諸側面がどうつながり一つの個性を形づくっているのか? 僕にはモザイクの断片を見る思いがし、その組み合わさり方が見えない。さて、氏への僕の不満・批判は多々ある。氏の限界も多々あろう。けれどもそれらの不満、批判をこえて僕が氏に負うと自覚する一点がある。「なぜ独立を恐れるのか!琉球人よ!」「踏みにじられても、しぼられても、さげすまれても、殺されても、なおも母親ジャパンと慕うあさましさ! なぜ独立を恐れるのか!」彼の発したこの憤怒こそは、彼の真骨頂と見なければなるまい。この憤怒の矢は僕を射ぬく、名護宏明氏から文献のコピーを入手した5年前からこの矢は僕の精神に刺さりつづけてきたと僕は思う。そして抜き捨てるよりは溶かし込むことを僕は選んだのだと思う。
この憤怒こそ島津侵攻以来の琉球の、琉球処分以後の沖縄の歴史への沖縄の指導者と民衆への、トータルな批判たり得ているからである。歴史学者や「沖縄学」者のどのような分析的批判も、この一言の総体的批判に及ばないと僕は感じる。
そこを確認した上で琉球独立党についての批判的見なおしをはじめたい。しかし、ここでいう琉球独立党とは、彼らが残した文献のほんの一部を通して見える限りのもの、しかもその文献がほとんど野底氏の手になるものらしいこと、その限りのものでしかないことは、あらかじめ断っておきたい。
Ⅱ 独立十訓・琉球独立党綱領
「独立」の論議は沖縄の歴史の曲り角で必らず噴出する論議であると言われる。琉球独立党の発足もまさにこの曲り角であった。
1970年の夏だったという。
69年11月には佐藤首相の訪米があり、返還の時期と条件が最終的に合意に達していた。世界ではベトナム戦争、日本ではベトナム反戦、大学紛争、沖縄と安保、沖縄では返還協定をめぐって、政情はまさに騒然としていた頃である。
琉球独立党の残した文献は今日かなり入手困難なようである。僕自身、『音楽全書』という雑誌で紹介された文献の一部をコピーして持っているだけで、それも五年前に入手したものである。野底氏のお宅に訪ねた時、文献資料の提供をお願いしたのだが、探し出すのが大変ということで結局入手できなかった。新沖文の編集部の方にも資料の入手を依頼してみたのだが、ここでもうまくいかなかった様である。手持ちのコピーから独立十訓と綱領を全文紹介してみよう。
独立十訓
1、独立なくして人立たず
何故なら独立尊厳なきものは人間でなく、動物だから。
邪蛮(ジャパン)復帰は他力本願・劣等感・無知・無能・怠惰・怒隷根性等を斉らす邪蛮教育罪業の帰結。真の人間改造のためにも吾々は独立を必要とする。
道理国家琉球共和国万才!
2、独立なくして権利なし
何故なら一切の権利は国が付与し、保障する。但し、真に保証できるのは琉球人民の発意による琉球共和国だけだ!
3,独立なくして平和なし
何故なら和戦の大権は国に属するから。この362年に及ぶ外国武力支配・殺りくの苦しい体験から真に恒久平和をうち建てんと欲せば、完全主権国家たる琉球共和国の創建あるのみ。
4、独立なくして繁栄なし
何故なら経済の大権(財政・金融通貨・通信・運輸・教育・資源等の管理権)は国に属するから。尖閣一兆ドル油田、西表四兆ドル銅山を思え! 重税インフレ強奪国家(邪蛮国)に見切りをつけ、無税・安定・恵与国家即ち琉球共和国をうち建てよう! 僅かばかりの為替差損補償に甘んずることなかれ!
5、独立なくして実質平等なし
何故なら差別そのものが国家権力の作用だから。いや逆に独立できないから差別と軽蔑を受けるのだ!「琉球人を甘やかせるな」とか「国でもないのに主席とか……」「里子に出した子供が帰ってくるのにアイスクリームをたくさんやれば腹をこわす」とかさんざんに侮蔑されているのをなんと心得るか? ジャパニーは、琉球人は本来別個の民族であったことをちゃんと知っている。歴史はあらそえない。屋良ボンクラペテンを先頭に自ら「日本人」と称してもアチラはそう見ていない。アワレ忠犬沖縄県(ウチナーイングワー)!「琉球処分」とか泣きごとを言うなかれ!独立できないから処分を受けるのだ!
6、独立なくして自由なし
自由すなわち必然を知り、これを応用して、オノレの政策を完全に決定できるのは、主権国なかんずく道理国家だけ。武力より道理へ! 軍事野蛮国家より平和道理国家へ!
7、独立なくして友好互恵なし
何故なら、わが琉球民族利益に即応すべく外国と友好互恵を楽しむためにも、吾々は外交権を必要とする。
この外交権も主権国の地位より生ずる。世界の大勢は被抑圧民族が独立する方向に進んでいる。吾々は孤立しているのではない。世界にはアジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国等、かつて我々と同一境遇にあった国々が大勢だ。「民族自決の原則」と「主権平等の原則」はわが民族の伝統に全く適合する。真の民族主義は真の国際主義に通ず。
8、独立なくして科学なし
何故なら、わが琉球民族利益に奉仕する科学、例えば地下資源、殊に海洋に眠る巨大な石油資源の開発等、巨額の資金と研究開発体制を必要とする。今日の教育制度では到底無理。政府予算の過半は教育予算が占めるが、その教育が無気力、琉球民族否定、ジャパン優等・琉球劣等の恐るべき動物教育を行なっている。まるでアヘンだ。この百年に及ぶアヘン症状から、人間を、科学を解放するためにも、吾々は独立を必要とする。
9、独立なくして文化なし
何故なら文化とは前各項の集積総合だから。世界一の生活水準、世界一の文化を創造できる物理的基礎と民族伝統(道理)は既に与えられている。ただ足りないのは人間の自覚だけだ! 自覚せよわが民族の文化遺産と資源の巨大さを!
10、独立なければ何もない
何故なら、以上見たように、人間としても、民族としても、独立なければ人も民族も立たない。要するに何もないのだ!
琉球独立党綱領
Ⅰ道理の支配する社会と国家、琉球共和国をうち建てよう!
系1,米日帝共同支配を廃絶し、完全独立主権国家をつくろう!
系2、武力より道理へ
系3、民族自決こそわが憲法!
系4、一切の権力を琉球人民の手へ!
Ⅱ恒久平和友好互恵をかちとろう!
系1、永世中立保障を世界各国より勝ちとろう!
系2、国連に加盟し、平和と安全をかちとろう!
系3、独立なくして平和なし!
系4、独立なくして友好互恵なし!
系5、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ諸国と連帯しよう!
系6、人民の手による国防を勝ちとろう!
Ⅲ税金等収奪のない国をつくろう!
系1、経済自立なくして独立なし!
系2、収奪国家より恵与国家へ!
系3、西表4兆ドル銅山、尖閣1兆ドル油田等一切の重要資源を社会化しよう!
系4、即時、通貨の発行管理を実行しよう!
系5、外為、貿易の管理を実行しよう!
系6、関税政策を強化し、生産力を発展させよう!
系7、消費者物価安定、為替安定資金を創設しよう!
系8、一切の重要物資の生産供給体制の一元化と合理化、価格規制を実行しよう!
系9、戦争損害300億ドル、戦後の損害の完全補償を実現しよう!
系10、経済の計画化、財政金融の一元化、能率化を実行しよう!
系11、円切換はジャパンの支配に屈服するだけだ!
系12、受託者階級の監視強化と官僚主義の打破!
系13、公正な経済秩序と公正な配分!
(以上『三星天洋』・琉球独立党教育出版局・1972年8月発行)
Ⅲ 何故持久できなかったのか
a、論風
十訓や綱領、「被抑圧民族としての自覚を(抄)」(72年8月発行・『三星天洋』)「祖国琉球の世界における地位(抄)」(「琉球独立党パンフレット」・琉球独立党教育出版局発行・71年10月付)(いずれも筆者は野底土南)などの文献を一読して気になるのは、その論風である。
−−何故なら独立尊厳なきものは人間でなく、動物だから、
−−邪蛮(ジャパン)ジャパニー、
−−屋良ボンクラペテンを先頭に……
−−アワレ忠犬沖縄県(ウチナーイングヮー)……
−−琉球民族否定・ジャパン優等・琉球劣等の恐るべき動物教育…
−−魂なき虫ケラどもが蟠踞していたドンガラ、その名を琉球政府
−−コイツラの一番の関心事は、現在の地位だけだ!
−−沖縄犬議会
−−迷血政府
−−恥ずべきメカケという地位……
彼らの作風を僕は知らない。けれどもその論風から察するに、自己の激情と憤怒に対し、余りにも被支配の状態にあると思えるのである。それともこうしたあて字を多用するのは戦術的考慮に基づいているというわけであろうか? 政敵・論敵に向けられる侮蔑にいろどられた論風は、彼らがまさにその政敵・論敵に対して対極に位置する思想と認識を持っていることを明らかにするのに役立つ戦術的効果を全く発揮しないとはいえない。また、表現を求めている民衆の状況への憤満に、火つけの効果を全く発揮しなかったともいえまい。けれども批判とは常に両刃の剣ではないだろうか。論争と対話はぜひ持続させ、発展させねばならぬ闘争形態の一つである筈だ。ことに琉球独立党のような政治的少数派にとって、持久的発展の道は唯一不可避の道であった筈だ、論争にも「作風」が問われる。
道理と真理の体現者としての確信が傲慢に堕すのはよくあることだ。また勇気が激情に堕すのもよくあることだろう。
僕にも経験がある。かつて「CTS・埋立竣工認可阻止!」「埋立地を三菱に渡すな!」の要求を掲げて、一週間のハンストを闘った。屋良知事がついに要求とは正反対の決断を下した時、当時書いていた沖縄タイムスの文化面唐獅子欄で、「屋良犬知事」と書いて削除・訂正の事後通告を受けたことがある。「犬知事」と書いたその時の澄んだ確信を今も忘れてはいない。しかし削除訂正されたことを今ではマスコミの限界だとか、不当な扱いを受けたとかは思っていない。今では彼を犬として見下すほど、自分が立派ではないことを骨身にしみて知っているからだ。彼の決断を批判し、蔑すむことと、彼を蔑むことはやはり別だ、と今では思う。自分の判断を他人の判断の上に置くことは、時により場合により必要でもあり不可避でもあり、許されないことではないと思う。だが自分を他人の上に置くことは果して許されるのか? それも時により場合によるのかも知れない。けれど最小限確信しうるのは、その時と場合の限定が必要だということだ。そのことの自戒を忘れる時、論争そのものの成立と継続は不可能となる。力と力のぶつかり合いとなる他なくなる。無視も力の発動のひとつの形だ。そしてこの「無視」こそ彼等にとっての主要な危険のひとつであった筈だ。殊に民衆の側の無視に最大の警戒を払うべきだった筈である。誇りと唯我独尊は区別されねばならなかったのではないか。
b、民衆運動との結合はあったか?
琉球独立党は民衆と知識人の希望と信頼を集めるのに失敗した、と僕は思う。独立−という言葉は無視して通りすぎる程軽くどうでもよい言葉ではない、少くとも沖縄戦以後の沖縄民衆にとって、それは歴史のひとつの選択肢としての関心を少なからず集めうる言葉だったと思う。独立とひと声あげれば、少なからず論議の的となり、耳目を集める。その程度に比して、琉球独立党が起し、組織しえた論議は余りに少く、しかも発展・深化の道をたどらなかった、と判断するからである。この判断もしかし遠くにいて感じるという限りのものである。
例えば知識人の反復帰論と独立論とは、相互形成の関係を作ることが不可能だったとは思えない。その試みがなされたのかどうか?この辺はむしろ当の人々に語って欲しいところである。
労働運動との結合関係はどうだったか?労働運動の側にも主流、反主流があり、多数派、少数派、実に様々な流れがあったし、それは今もある。そのどこかと何らかの結合関係が創られただろうか?相互批判という結合関係すら創られなかったのではないだろうか?少くとも僕は寡聞にしてそうした事実を知らない。
反米軍統治・反基地・反戦・自治の闘いは復帰運動として総括されていたとはいえ、相対的独自性を有していた筈である。復帰運動があったから労働運動があった訳ではない。労働運動はじめ反米・反基地・反戦・自治の民衆運動は、支配−被支配関係のなかで必然的に発生したのであり、復帰のための手段として派生せしめられたのではなかろう。
そういう民衆の戦後の抵抗・自立の闘いのなかで、民衆は独立党を見たことがあっただろうか?あるいは独立を志す人々に接する機会を得ただろうか?
琉球独立党は、戦後沖縄民衆にとっての強権的支配権力であった米軍政に対して、どれ程抵抗しただろうか? 民衆の抵抗闘争に対して、どれ程共闘しえただろうか? どのような人のなかにも、自立性−独立性は潜在力として備わっていると僕は信仰する。どのような支配も教育もそれをゼロにすることは不可能だと僕は信仰する。(同時に完全無欠といえる程成長したそれを備えている人にも会ったことはない)支配に抵抗している民衆は、その内なる自立性−独立性をまさに証し成長させているのではないのか?
琉球独立党の発足以前のことを問うのは不当であるかも知れない。では、返還後の現実に対する民衆の抵抗に対する関係はどうだっただろうか。例えば金武湾の反CTS闘争に関わり、共に闘う機会は琉球独立党のメンバーに対しても開かれていたと僕は確信する。しかしそこで彼らを見かけることすらなかったことは事実だ。
そもそもと僕は考えざるを得ない。琉球独立党は、どれ程の自立性−独立性をその内に備えていただろうか? と。現実の矛盾を媒介としてのみ運動は前進するという眼を、備えていたのかどうか?と。
c、国権主義、民族主義、国際主義
独立十訓は簡潔明解な表現をとっている。独立の思想と論を簡潔明解に表現することをそもそもの目的に十訓をつくったのであろうということ、その限りのものとしてそれはあるのだろうということを踏まえながら、十訓の解説部分、「何故なら……」以下、そこに特徴的にあらわれている思想に注目したい。
……何故なら一切の権利は国が付与し、保障する……
……何故なら和戦の大権は国に属するから……
……何故なら経済の大権は国に属するから……
……何故なら……外交権も主権国の地位から生ずる。
琉球独立党がそれに無自覚と思われる根源的思想限界は、ここにあらわれている国権主義、国家主義ともいうべき思想と理論の在り方にあると僕には思える。ここに書かれていることが現象認識として間違っているとは思えない。
20世紀の世界史は、被抑圧民族・被抑圧地域人民の独立国家形成への運動をひとつの主軸として展開してきた。被抑圧民族・地域人民にとって、独立によって<国家権力>と対外的<主権>を手にすることは依然として革命と解放の根本問題でありカギである。
しかしまた、革命と解放の運動の勝利によってかち取った筈の国家権力が、たちまち疎外物に、人民にとって抑圧的機構に転化する事実も否定しがたく、ザラに存在する。世界史にとってこの問題は避けて通れぬ深刻な問題として浮上してきていると僕は見る。
世界史はすでに<国家>を制約し、相対化し、引き下げ、<民権>のたずなにつなぐべきことを示している。あるいは<民権>のたずなにつなぎうるところまで国家を小さくし、分割すべきことを要請していると僕には思われる。琉球共和国の創建を、この世界史の要請に沿うものとするには、国権を絶対視することを避け、相対化するところから出発することが是非とも必要だと僕は考える。その上で沖縄のような被支配地域で国家形成をすることの意義を強調することに僕は反対でない。むしろ賛成に傾いている。けれども今は自分がそのことを呼びかける立場に立つ程の自信は持てない。その理由は徐々に明らかにしよう。今は、ただ自分の思想的作業を公開する程度のことしかできない
さて、独立十訓は、一度逆転させ、また逆転しかえすという思想的作業を必要としていると思う。
<独立なくして人たたず>と<人立たずして独立なし>の、また<民権なくして国権なし>と<国権なくして民権なし>の、各々の弁証法的把握と持久的実践が必要とされていると思う。
もっとも、今の僕は<民権>を絶対視しうる程人間というもの、民衆というものに楽観的ではない。僕を含め、ウチナーンチュを含め、支配・指導層を含め、労働者・民衆を含め、およそ人間というものが、その内なる自然性に被支配状態であることを克服することのスピードと、そのことによって破滅を準備することのスピードとは明らかに後者の方が速いと思われるからである。人類は核と環境破壊による破滅的事態を避けて、21世紀を迎えることができるかどうか、そのことについて僕は楽観をしていない。政治的処方箋と宗教的処方箋が相互形成の過程に入ることが唯一の可能性とさえ見える。
野底氏の「被抑圧民族としての自覚を」のなかに次の一節がある。
省みよ!
朝秀――朝保――朝病に貫かれる売国の系譜を。
ああ、病める現代琉球人民大衆!
汝は恥ずべきメカケを指導者とあがめ、365年間も追随してきた。
汝の言葉はこの事理をあらわす。
「アメリカ世」から「ヤマトゥ世」ヘと。
だが、祖先は、とっくに予言していた。「唐ぬ世」から「ヤマトゥ世」「ヤマトゥ世」から「アメリカ世」「アメリカ世」から「ニーマぬ世」と。
このニーマぬ世こそ琉球の世のはずだった。
歴史のテンポはタキナムンヌチャーによって狂わされた。
だが歴史の流れをいつまでも押し止めることはできない。
このニーマぬ世こそ琉球の世のはずだった、と野底氏はいう。しかし僕は疑う。この予言は狂っていないのではないかと。第二次のつまり72年以後のヤマトゥ世とはアメリカ世に包含されていると見ることができるし、ニーマぬ世とは人間でないものの支配する世という意味ではないのか、つまりアメリカ世を最後に自滅する人間の世に代わって、それを救済する、「神々」の支配する世の意ではないのかと。
僕らは押しなべて仏陀の手のヒラを飛び回ってそのことを知らなかった孫悟空の類ではないのかと。白状してしまったけれども僕の疑いと迷いと自信のなさはかくも深い。人間であることに誇りを失いかけている時に、琉球民族としての誇りなどはなかなかに持ちにくい。
氏は「真の民族主義は真の国際主義に通じる」と述べている。僕は強調のポイントをズラして考えている。民族主義や国家主義に基礎を置いた国際主義の限界が世界史の危機と苦悶を招いていると。
民族利益や国家利益よりも、地球の住民としての利益、核や戦争で殺されたくない、地球を破壊したくない、されたくないものとしての、人類としての利益、生きものたちの一員としての利益を優先させたいと思う。そのことによって、民族利益や国家利益、人間中心主義の尺度で計られる利益、要するに自我や我利の相対化こそ、必要なことだと思われる。
もちろん、そのことを真先に要求されるべきなのは、大民族、大国家、帝国主義であり、北の工業国であろう。けれども沖縄は、まさに今、この相対化を真先に要求されるアメリカ・日本ヤマトの系列環の中で、自己を荒廃させ、腐敗させていると僕は見る。半分の責任はまさに我々自身あろう。我身、我心の洗い直しが必要であろう。
「独立」が沖縄人自身の内部格差と差別をそのままにして、これ以上の物的豊かさを求める欲望の上に求められるならば、僕にはその意義がまるきりつかめないのである。
野底氏の独立論の中で、ゾッとする部分がある。それは次の一節だ。
尖閣一兆ドル油田、西表四兆ドル銅山を思え! 重税インフレ強奪国家(邪蛮国)に見切りをつけ、無税・安定・恵与国家、即ち琉球共和国をうち建てよう、僅かばかりの為替差損補償に甘んずることなかれ!
世界一の生活水準、世界一の文化を創造できる物理的基礎と民族伝統(道理)は既に与えられている。ただ足りないのは人間の自覚だけだ! 自覚せよわが民族の文化遺産と資源の巨大さを!!
尖閣一兆ドル油田、西表四兆ドル銅山なるものがほんとにあるのかどうか僕は知らない。けれども、そんなものがあるとしたら、恐ろしさの方が先に立つ。今の我々には無い方がよいとさえ思う。
恐らく、氏と僕とが最もズレルところはここなのだ。独立の物理的基礎をここに求めている氏と、沖縄の海と大地(われらの生態系)とに求めている僕とは多分、この点対極に立っている。
油田や銅山がなければできない独立なら、そんな独立は僕はいらないと思う。具志川市の名護宏明氏の「在来種シマーグワーを守る会」の運動は広くマスコミに紹介され、共感を呼んだ。僕も彼の仕事と運動には心から共感し学んだ一人だ。彼もまた独立の志を持つ人で野底氏を尊敬しているということを彼から聞いたことあるのだが、彼の実践と感性が独立党の思想と理論、実践のなかにどれだけ反映され生かされたか気になるところである。
V 運動としての独立、自立と独立
野底氏は「被抑圧民族としての自覚を」のなかで「独立とは何か」と設問し、端的に次のように述べている。
独立とは何か
完全なる主権国家、琉球共和国をうち建てることである。琉球人民が共和国政府をとおして、自己の政治、経済、文化の地位を自由に決定することである。
この主権という地位をぬきにして、いかなる経済、いかなる文化がありえようか。国の本質と機能に関する深い理解と世界史の進展に対する洞察なくしては、政治、経済、文化について語る資格がないのである。
ここで言われていることを否定しようとするつもりはない。しかし、僕はポイントをズラして、先ず「独立運動」について考える。「独立運動」がその成功の一大画期を主権国家の創建という段階に置くこと、それを目標とすることに異議はない。
けれども「独立とは何か」という設問に対して、独立の政治形態論的次元の答しか見ないとすれば、それは短絡というものであろう。
僕なら設問に対し、先ず次の様に運動としての独立を強調する。
①「『独立』、それは(第一に)いうならば足でたつことであって、ひざまずくことではない。(人間存在の自然な姿は直立の姿勢であってひざまずくことではない)。第二番目に、それは借りた仮面のうしろにかくれることではなく、彼自身の顔をもつことである。第三番目に、それは勇気であって怯懦ではない。しかし独立はまた第四番目に、自己自身に対して、そして我々がそこで生きている世界に対して、距離をとることができること。現在からぬけ出しうること、この現在を歴史的総体性のなかに挿入し、現在のなかで、特殊を普遍から、偶然を現実から、野蛮を人間的なものから、真正なものを真正でないものから区別しうることである。(中略)第五番目に、それは他の人々と、そこで自由が産出されうる、すなわち実現されうるような関係をもつことである。独立とは(第六に)歴史性である。すなわち独立は、過去と未来がそこで相互浸透される活動的中心である。それは
(第七に)特殊性 (個別性)のうちで人間に共通のものが再生産され、活性化されるところの総体化である。」
(カレル・コシーク、「個人と歴史」)
②「自立」とはここで言われる「独立」とその次元で同義であろう。
③「自立」も「独立」も、支配−被支配、抑圧−被抑圧、収奪−被収奪の相の下における相互依存関係を、自由と必然、対等の相の下における相互依存関係へと転換する被支配の側からする運動である。
④「自立」と「独立」とに区別を設けるとすれば、それは方法的次元で区別される。
⑤この方法的次元で区別される「自立」は、支配―被支配の相の下にある相互依存関係を、被支配の側の主導性によって、ゆり動かし緊張させる方法によって、対等な相互依存関係へと変革しようとする運動であり、
⑥「独立」は、この支配―被支配関係の一たんの「切断」「分離」を方法的回路・目標とする。
⑦真正の自立と真正の独立は相互に転化しうる。方法的次元における相違は相対的なものであるからだ。
⑧真正の自立は根源のところで独立の方法を恐れない。恐れるとすれば自立でない。独立は根源のところで「切断」「分離」という方法的次元に囚われない。方法は状況の見通しのなかで選ばれるものだからである。
⑨沖縄にとって「自立」は場合によっては「独立」たらざるを得ぬものである。
⑩支配―被支配関係の緊張あるいは切断・分離という脈絡のなかに自立あるいは独立の運動がある以上、沖縄にとっての自立・独立は日本国家からの、アメリカの世界戦略からのというベクトルと、沖縄はもとより日本国家を含めて支配している支配的世界史(米ソの核対決という支配的世界政治、米ソを中軸につくられている現代文明という支配的世界経済)からのというべクトルを合わせ持たざる得ない。
⑪沖縄にとっての「独立」は政治形態の次元では、例えば「琉球共和国」という主権国家の創建を意味しうる。「自立」はこの次元では「日本国」の枠内での国内植民地的地位の変革を意味する。
独立を「運動」としてとらえていれば、それは日々の生き方の中に問われるものとなるのは必然だ。一人一人の生き方が共同の生き方としてつながり重なり合うところに「国家」も育くまれていくのである。共和国は(あるいは共和社会も)先ず生れる前に胎児として育つのではないか。
筆者註 紙数もはみ出してしまった。僕は、野底氏との思想的対話を試みるつもりで、これを書いた。編集部の方にお願いしたいことは、野底氏から応答があれば、それをボツにしないで欲しいということだ。僕もこの稿で書かなかった部分、書けなかった問題意識が多々ある。それはまたいつかの機会を待ちたいと思う。
(たいら よしあき・農業)
ふたば会――崎間敏勝氏の歴史観を中心に/太田良博
大脳喪失の沖縄
月刊「ふたば」第六号(昭和51年5月15日)で、崎間敏勝氏は、琉球銀行調査部報告「主役不在の経済開発」(金融経済182号)を読んだ感想として、つぎのようにのべている。
第一の問題点は、沖縄の経済発展の根本的障害は事物の総合判断とそれにもとずく意思の形成にあずかる大脳機能が沖縄人にはないということではなかろうか。
「経済発展の成否は資本、労働力、技術、資源などを合目的、能率的結合して事業体として機能させる人間の存否にかかる」(註 琉銀調査部)と指摘しているのは正しいと私は思うが、沖縄の現状(社会、政治意議の状況)では、このような企業家が強力に育つ余地はない。その理由は、対外収支の拡大均衛による経済発展=自立経済は沖縄人の最も好ましい選択であるべきはずだったが、復帰運動によって沖縄人はこの選択権放棄したからである。敗戦直後に生じた日本帰属のこの運動は以後ダモクレスの剣のように沖縄人の頭上にぶらさがり、最適な経済発展のモデルの形成をさまたげたと思う。この復帰運動のおかげで、沖縄は工業化の道をすて、戦後日本経済の消費者の地位を自ら作ったのである。復帰運動は純経済的視点からすれば、沖縄経済を一単位の国民経済にしないための運動であった。過去三十年間、生産企業家が育たなかったのは、この大脳機能の否認運動の当然の結果であったし、この状況は今後はさらに急速度に悪化しよう。大脳は東京にしかないことがはっきりしているから。
私は「対外収支の拡大均衡型経済発展」は大脳機能をそなえた一単位の国民経済でなければ達成できないと思う。
沖縄人は自ら切除した大脳を取りもどすことである。大脳とは事態を冷静に分析し、評価判断し、自己の生存と発展に最適な行動を決定し実行する機能をもつ部分である。
以上の、崎間氏の意見を端的に言えば、沖縄人は経済的自立心をなくし、したがって経済自立の大脳機能が働かなくなったということであろう。大脳がその機能を失ったというのは、かなりの誇張的表現だが、つまりは、反射的な運動をつかさどる小脳だけで生きているということになる。
「大脳は東京にしかない」と崎間氏はいう。沖縄は、その指令をうけて、ただ、手足をピクピクさせるだけというわけだ。手足の運動(労働)によって消費物資のほとんどを本土から輸入したり、企業の系列化など、沖縄の大脳喪失現象は、言葉をかえていえば、沖縄の単純地方化ということだとおもわれる。大脳喪失とは極端な比喩だが、沖縄の経済自立は政治的自主性を前提とするのだが、その自覚なしに復帰運動がすすめられた。復帰運動は沖縄の単純地方化運動だったというのが、崎間氏の所説のようにおもわれる。
崎間氏の琉球処分観
日本からの施政権分離、戦後の沖縄がおかれた政治的状況は、経済自立のための、沖縄が「大脳をとりもどす」ための千載一遇の好機だったのが、復帰運動=沖縄の単純地方化運動によって、その好機をのがしてしまったと、崎間氏は見る。
この復帰運動のありかた、一体化の合言葉ですすめられた沖縄の一地方県としての復帰運動のありかたは、明治の琉球処分に、その歴史的淵源がもとめられる、つまり、琉球処分のときに沖縄人は大脳を切除され、その結果、戦後の復帰運動も大脳喪失のままの復帰運動となったとみる。そこで、崎間氏の琉球処分観だが彼はまず伊波普猷の琉球処分論を「安易な合理化の遊び」だとして排斥する。以下、「ふたば」四号(昭和51年3月15日)に載った論文を紹介する。
今年は伊波普猷の生誕百年目にあたるそうで、伊波の業績にちなんで種々の行事が関係者によって計画されているようである。
伊波は明治から大正、昭和にかけて当時の沖縄の先進的な知識人として、秘密主義で秘伝主義で、こそこそした日本的学問の世界で、珍しく開放的な大衆啓蒙詳活動をした人で、沖縄人に自己の歴史に目をひらかせた初期的功績は大きいものがある。
しかし、たしかに伊波普猷が父祖伝来の「おもろ双紙」その他の古文書類を純科学的に解読し解明した業績は大きいけれども、沖縄人の社会的、政治的な問題についての伊波の見識は貧弱なものだったと言わざるを得ない。
私が何故伊波普猷の社会的、政治的見解を貧弱なものだったと考えるようになったかと言えば、私は今日の沖縄の問題の根因についてごまかしのない探求をしようと決心しており、その探求のなかにはいわゆる「明治の琉球処分」の理解と評価が大きい部分を占めているからである。明治の「琉球処分」についての私の理解と評価のしかたの詳細は、いずれ「沖縄自治の理論とプログラム」の題名の論文で述べたいが、そういった問題意識をもって読むと、伊波普猷の例えば「琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文などは安易な合理化の遊びだった、という気がしてならない。
合理化というのは自分が置かれている社会的、政治的境遇を受容するための弁解であって、心中に湧き出ようとする疑問や向上意欲を未然に封殺する精神作用をいうが、これは、はっきり言えば、あきらめの理論化である。私はこういう「合理化」をする心の作用を奴隷根性と呼ぶが、伊波氏の「琉球処分は一種の奴隷解放なり」という一文は、一種の奴隷根性を内包していると思う。
実を言えば、この一文は複雑怪奇で、その真意をつかむのが困難なものである。その理由は三つほどある。
第一に、論旨があいまいで不徹底である。「今から三百年前(即ち慶長役以前)の琉球人は純然たる自主の民であった。それ故に彼等は或程度までその天稟を発揮することが出来た」と明快に書き出しながら、「琉球史の真相を知っている人は、琉球処分の結果、所謂琉球王国は滅亡したが、琉球民族は日本帝国の中に入って復活したことを了解するであろう」と琉球処分を高く評価していることである。しかし、琉球人がその奴隷を発揮した慶長役以前の自主の民の境遇が、日本帝国の中で復活したということは理論的(というのは日本帝国の当時の制度の条件のなかで)に説明されず、また実際にも琉球人の自主性が復活したという記録も今日にいたるまでない。
次に、あれほど古琉球を研究し愛したと思われる伊波にしては、「琉球王国は滅亡したが、琉球民族は日本帝国の中に入って復活した」と述べて、千年近い琉球王国の滅亡になんらの愛惜の情を示さないことである。
「処分」を受けた琉球人は「破壊された『王国のかざり』を夢みて泣き叫んだ」と伊波は書いているが、泣き叫ぶ方が悪かったとのであろうか。
ところが、他方では、伊波は「琉球人は、かつて奴隷になるまいと力んで薩摩で殺された愛国者を嘲り、おまけに彼の名を組踊で悪按司の名にして、島津氏の歓心を買はうとするまでに変り者になった。悪くいへば琉球にはつひ三十六年前まで王冠、紗帽、五彩巾、黄金、紅巾、青巾の色々の冠を戴いた美しい奴隷が数限りなくゐた訳である」とも書いている。
謝名鄭迥愛国者だとする視点は、慶長役以前は琉球人は純然たる自主の民であった、とする視点と同一のものであり、薩摩の歓心を買おうとした美しい琉球貴族を奴隷と見るのも当然であるが、どうして伊波は、この同じ視点で「三十六年前」の琉球処分を見なかったのであろうか。
「三百年前」、純然たる自主の民であった琉球人、愛国者を薩摩に殺された琉球人は、明治維新にさいして再び自主性を自分の手に取り戻すべきだったとするのが、伊波としては論旨の一貫性があっただろう。
そうではなくて、琉球処分を、色とりどりの冠をかぶった美しい薩摩の奴隷である琉球貴族の造った琉球王国の破壊、と限定したところに伊波の重大な誤解があったように思われる。
一九四五年までの歴史の事実にてらして見ると、破壊されたのは琉球王国だけではなかった。伊波の合理化理論で復活したはずの琉球民族そのものも、日本帝国のなかで自主性を復活するどころか、さんざんな目に会ってきたのである。
そこで、伊波の奴隷解放論が複雑怪奇である理由の第三点は、伊波は、薩摩と日本を使いわけたということである。恐らくこれは琉球人を美しい奴隷にし、美人局のように搾取した薩摩への憎しみの反動として、当時の日本との関係をつっこんで考えなかったためであろう。しかし、薩摩といっても独立国ではなく、江戸幕府に参勤して忠誠を誓う一藩にすぎなかったのである。徳川期においてすら、琉球人が美しい奴隷となったのは、日本の政策に他ならなかったのである。この点、伊波は薩摩に憎しみを向けることによって、日本の歓心を買おうとしたかもしれない。
最後に、伊波の視点から大きく欠落しているものは言うまでもなく、明治、大正期の日本帝国の姿である。
明治日本はいろいろな角度から見られるが、その一つはイギリスやフランスから軍艦や大砲を仕入れて、弱小の近隣諸国の領土併合に乗りだしたことである。
伊波が「琉球処分は奴隷解放なり」と論断した大正3年2月は、日本が琉球、台湾、朝鮮の併合を終え、その膨張の最盛期であった。隣りの大国(支那)は近代化のおくれから植民地主義列強に分割され、衰亡と混乱の極みにあった。伊波をふくむ明治、大正期の沖縄人が強国日本にようやく同化の色を見せはじめたのも無理はなかった。
しかし、それにしても隣国の領土を武力で割取することについて、自らその悲劇の主人公であることに沖縄人は気がつかなかったであろうか。
私は、伊波が琉球処分の頃の琉球人は「琉球王国のかざりを夢みて泣き叫んだ」と書いたのは、伊波の政治的見識浅薄さを示すものだと思う。
当時の琉球人は、薩摩の美しい奴隷の地位が失われるのを泣いたのではなく、僅かながらも残されていた自主性、中国との交通が、杜絶されるのを予感して泣いたと思う。
いや私が思うのではなく、それが歴史の記録の示すところである。
琉球民族は日本帝国の中では、遂に復活を許されなかったのである。「慶長役以前琉は球人は純然たる自主の民だった」とした伊波は本物のセンスを示した。しかし、伊波が明治の琉球処分を無理な論法で合理化したおかげで、琉球民族は自己の真の姿を見失い、第二次大戦もなんら政治的開眼をもたさらなかった。
右の崎間氏の伊波批判からすると、伊波普猷でさえ、すくなくとも脳神経中枢をおかされ、沖縄人の大脳喪失に手を借したということになる。
琉球処分は侵略だった
琉球処分に関する伊波普猷の見方を否定する崎間氏は、琉球処分を、日本政府による武力を背景にした琉球の強制的併合、とみている。つまり、言葉をかえていれば、琉球処分侵略説である。
<明治の〝琉球処分〟は現代沖縄県の原点であるが、喜舎場朝賢翁の詳細な記録が残されているにもかかわらず、現代沖縄人は物をまともに見ないクセのせいか、なかなか的を射た性格づけができず、今だに日本史流に「廃瀋置県」と感違いしている。日本の学者や言論人も同様で「琉球処分」の正当性を疑うことはタブーである。しかし、ここに一つの例外がある。それは井上清の見解である>
として、「ふたば」八号(昭和51年7月15日)に井上清「條約改正」の一部を引用紹介している。井上清の琉球処分侵略説に賛成する形で、それは引用されているが、そのなかでつぎの二点に注目してみたい。一つは、琉球処分当時の自由民権派の機関誌「近時評論」にでた琉球処分に関する有名な論説の一部である。
<現在わが国が欧米の圧制に苦しみ国民はいかにもして独立の国権を回復せんとしているが、そのためには、わが国自身が隣国外交において條理にそむき小弱を軽悔するが如きことあるべからず、琉球問題でも、日本がしいてそれを併合せんとするのに反対し、もし琉球の「衆心ノ向フ所独立自治ヲ欲スルノ兆アラバ、我レ務メテ其ノ萌芽ヲ育成シ、天下ニ先立チテ其ノ独立ヲ承認シ、以テ強ノ弱ヲ凌グベカラズ、大ノ小ヲ併スベカラザルノ大義ヲ天下ニ証明」せよ、それこそわが国の名誉をあげ独立の基礎を固くする道である>
との「近時評論」の引用と、もう一つは、井上清自身のつぎの見解である。
<琉球併合は乱暴な手段ではあるが、日本人の民族統一であろうか、それとも侵略であろうか。私は侵略的統一とでもいうほかないと思う。一番よいことは、日本は琉球の分離権をみとめてその自治を助け、日琉両国の経済的文化的関係を深めてゆくうちに、自然と政治的にも何らの無理がなく琉球と日本と統合するようにはかることであろう。琉球が日本と統一融合するのは不可避であった。だからといって、明治政府がこれを併合したやり方は侵略といわざるを得ない>
右の二つの意見、明治の自由民権派の機関誌「近時評論」にでた論説内容と、井上清の見解とは似て非なるものである。「近時評論」は、琉球の独立論を前提とした意見である。井上清も、<日本は琉球の分離権をみとめてその自治を助け>といっているから、いちおう琉球の独立を前提としているようにみえるが、<日琉両国の経済的文化的関係を深めてゆくうちに、自然と政治的にも何らの無理がなく琉球と日本と融合するようにはかることであろう。琉球が日本と統一融合するのは不可避であった>というくだりをみると、井上清の意見は、結局は統合論である。井上清が問題にしているのは統合のプロセスで、統合そのものは不可避であったとするのである。明治政府のとった侵略的統一ではなく、融合的統一がのぞましかったというのである。
市町村や会社の合併で、吸収合併か対等合併かという論議がよく出るが、琉球処分についてもこの議論と似たものがある。
井上清のいう侵略的統一とは、大会社による小会社の吸収合併に相当し、融合的統一というのは対等合併になぞらえることができる。
そこで「近時評論」と井上説のあいだには徹妙なズレがある。「近時評論」は統合ということを念頭においてないが、井上説は究極的には統合論である。
復帰直前の反復帰運動で崎間氏が独立を標榜したのは、「近時評論」でいう〈独立自治の兆〉と、あるいはその萌芽を伸ばそうとしたものと解釈できるし、また同じく「近時評論」の〈強ノ弱ヲ凌グベカラズ、大ノ小ヲ併スベカラザルノ大義〉を琉球の立場から証明しようとしたものともとれる。
ところが、日本復帰後の崎間氏の考えは井上清説に近似してくる。しかも井上説とは微妙な一線を画するようにおもわれる。
井上は<日本は琉球の分離権をみとめてその自治を助け、日琉両国の経済的文化的関係を深めてゆくうちに、自然と政治的にも何らの無理がなく琉球と日本を融合するようにはかること>が最善の道とする。その意見に、崎間氏も異論があるはずはないが、ただ、ちがうところは、<日琉両国の経済的文化的関係を深めてゆく>ことで、政治的に無理のない融合ができるとは、崎間氏は考えていないようである。過去の歴史的関係をきれいに清算しないかぎり、「融合」はありえないと考えているようである。過去の歴史的関係の清算となると、政治的方法でしか解釈されないのではないか、という気がする。
また井上説は、むしろ過去形である。「琉球が日本と統一融合するのは不可避であった」「だが、明治政府の併合は侵略的であった」「一番、望ましかった方法は……」といった文脈である。
崎間氏の発想は、その点、現在形あるいは未来形である。琉球の分離権、自治権といった想定の時間的位置を未来においている。その場合、崎間氏はかならずしも独立に固執するのではなく、独立か融合かは、未来の時運が決めることである。との考えに立っているようにおもわれる。
そこで、崎間氏の考えの中核となっている<過去の歴史関係の清算>について考えてみる。
附庸関係の廃棄
沖縄人再生の唯一の道は附庸関係の廃棄だ、と崎間氏は言う。つまり、清算しなければならない過去の歴史関係というのは、崎間氏によれば日本と琉球の「附庸関係」ということになる。日本と琉球の「附庸関係」ということになる。日本と琉球の「附庸関係」は、琉球処分で琉球が沖縄県となり、日本の一部になったときに消滅したと一般に考えられているが、崎間氏は、「附庸関係」が現在も続いているし、これからも続くとみているのである。
琉球処分以前の日本=薩摩と琉球との関係は、たしかに附庸関係であった。琉球が独立の王国であったから、そういう関係が成立したのである。琉球は中国とも附庸関係があったが、附庸関係をもっていた。琉球処分によって、薩摩とも附庸関係は清算され、琉球は沖縄県(日本の一部)となり、日本の主権の下で、かつての支配者であった薩摩と同等の地位におかれた、つまり、薩摩との附庸関係から解放された、これが伊波普猷の琉球処分観である。薩摩との附庸関係の廃絶によって、琉球は沖縄県として、ただちに日本と一体化すべきだという認識に立って、その一体化のための、学問の立場からの、基礎固めの作業をやったのが伊波学であったともいえる。伊波学は、日本と琉球との類似性、近似性、あるいは親近性の証明に努力の大半を費やしたようにおもわれる。
明治期沖縄の開化党の政治的な立場からの同化努力と並行して、学問的立場からの同化努力が、伊波学を特色づけている。とにかく琉球処分に関しては、伊波の見方が一般的に定着しているようだが、崎間氏は、この伊波の琉球処分観を根底から否定しているのである。琉球処分によって、薩摩との附庸関係は止揚されたが、それによって、日本と琉球(沖縄県)との新たな附庸関係が生じた、琉球は琉球処分によって、伊波のように「解放された」のではない、という見方をとるのである。では、明治以後の、沖縄県となってからの日本と琉球の附庸関係とは何か、その点について、崎間氏のはっきりした説明はないが、薩摩と琉球の関係のような、いわゆる国際法概念でいう附庸関係でないことはたしかである。琉球国が消滅した以上は、そういう関係は成立しない。だとすると、新しい形の附庸関係でなければならない。
つまり、国内的附庸関係である。さいきんは「内国殖民地」という言葉も使われているが、かんたんにいえば国内差別である。最初に法制的差別があった。市町村制、国政参加など時間的にかなりのズレがあった。しかし、これは琉球処分の歴史的成り行きとも解釈できるし、このことは琉球処分が侵略的併合であった逆証ともなりうる。また、法制的ズレはやがて解消される。だから、国内的附庸関係というのは、社会的、文化的、心理的な差別概念を主体とする関係ということになりそうである。
天皇制下の日本で天皇が沖縄県を一度も訪問したことがないとか、沖縄県知事にかつて沖縄出身者をあてたことがなかったとか、沖縄に専門学校以上の高等教育機関をおかなかったとかは社会的差別であり、琉球歴史を日本史のなかで疎外したこと、琉球語や琉球固有の文化に対する無理解と蔑視、ときには圧迫、こうしたことが文化的差別である。それからの証跡また他の例証は、すでに沖縄の近世史研究で問題とされ、解明されつつある。
なかでも、ぬきがたいのは心理的差別である。沖縄戦における日本兵の住民虐殺などは、その最たるものである。
そして、社会的、文化的差別がなくなっても、心理的差別感情は最後までのこる。形の上では判然しなくても深層心理のなかで差別は生き続ける。こういう意味では、崎間氏が言うように戦後の、あるいは施政権が日本に還った現在も「附庸関係」は続いているといわざるをえない。
明治以後のこの新しいタイプの附庸関係のなかで、沖縄人は主体性を失った、いわゆる崎間氏のいう「大脳をぬきとられた」というわけである。
新しい形の附庸関係の存在は、明治以後の沖縄人の「日本との一体化努力」では消し去ることのできないものであった。
日本のなかの「沖縄県」のゆがんだ地位、日本と「沖縄県」のゆがんだ関係は、結局、歴史的産物である。琉球処分という侵略的併合から帰結された当然の結果といえる。
大(日本)が小(琉球)を呑みこんだ凌辱的事件が、いつまでも尾を引いているのである。
琉球処分は歴史的天然痘ともいうぺきもので、琉球併合が強制的に実行されたあとも、その痕跡はみにくいアバタとなって残ったのである。
たんなる一体化努力では、日本との歴史的関係は清算できないことが、これまでの「沖縄県」の歴史で証明されたとすれば、残された道は、崎間氏がいうように「附庸関係の廃棄」以外にはないということになる。
<沖縄人と日本人のちがいは、歴史上の立場、侵略と被侵略のちがいからくるのである>
と崎間氏はいう。そして、さらにつぎのようにつづける。
<私は沖縄人がこのようなむきだしの歴史の真実をタブーにしていることはよく承知している。このタブーあればこそ「一番安易な生き方」もできるわけだ>
ここで、崎間氏が言っている「一番安易な生き方」とは、おそらく日本との国内的附庸関係(ふつう一体化という美辞で表現される)のなかで「大脳をぬきとられた状態」での生き方のことを言っているのだろう。
<私は「誤った民族間歴史は必ず清算される」と思っているが、それは、もちろん日本の侵略を追認しない考え方からである。ではどうするか。それは日本人と沖縄人が「附庸」関係を公式に廃棄することである。それが沖縄人の再生の唯一の道であると私は思う>
というばあい、その附庸関係の内容を崎間氏は、つぎのように説明する。
<沖縄人と日本人との関係を示す琉球処分を考えるとき、日本は沖縄にたいして何をしたかを問うばかりでは真実はつかめない。日本は沖縄にたいして何をしなかったかを問うことがもっと真実をはっきりさせる。そういった目で、琉球処分の記録を読んでみると、明治政府が沖縄にたいしてしなかったことは、明治維新という日本近代化の福音を共にしようとの呼びかけをまったくしなかったことである>
崎間氏の右の考え方によると、明治以後の沖縄がまがりなりにも近代化したのは、日本が沖縄の近代化を積極的に進めたからではなく、日本は近代化のなかで沖縄を内国植民地として利用したにすぎない。たとえば砂糖モノカルチャーの生産地として、あるいは日本商品のマーケットとして利用したということになる。これでは、日本の植民地であった台湾の近代化と、その様相があまりちがわない。考えてみると、沖縄の主要生産物であった砂糖も、沖縄製糖会社という県外資本の支配下にあった。砂糖委託商という中間業者も寄留商人、その砂糖を運ぶ海運も大阪商船の独占であった。生産、集荷、運輸と経済機構の全権が他県人に握られていたのである。また、日本商品のほとんどは県外寄留商人の手を通じて売りさばかれていた。消費経済の実権は寄留商人の手にあった。その実態は、沖縄(領内植民地)が台湾(外領植民地)とあまり変らなかったことの一端を示している。これは、まさしく明治以後の社会的附庸関係を如実に物語っている。
日本政府は、寄留商人や県外資本の跳梁にまかして、何もしなかったのである。また、沖縄としては他県人の知事の下で何もできなかったのである。それどころか「大脳をぬきとられた沖縄」は、こうした近代化のおこぼれを日本からもらって生きることに安住したのである。
崎間氏のいう「一番安易な生き方」というのがそれで、その言葉は、また、こうした歴史的関係を清算することになしになされた日本復帰運動にも向けられる。
日本と沖縄とのゆがんだ関係の歴史的蓄積をそのままにしての日本復帰は、そのゆがんだ関係がいつまでも何らかの形で尾をひくはずだと見るのである。
そのゆがんだ関係の是正を、崎間氏はこれからの課題とし、そのことを「附庸関係の廃棄」という言葉で表現しているわけである。「附庸関係の廃棄」とは、具体的にはどういうことか。崎間氏は、そこで、独立と日本主権下の特別自治という二つの構想をもっているようにおもわれるが、そのことは、ここではふれないことにする。
いずれにしても、「附庸関係の廃棄」と「ぬきとられた大脳機能の奪回」とのかかわりが問題で、附庸関係が廃棄されれば大脳機能は復活するはずだが、大脳機能をとりもどさなければ、附庸関係の廃棄という意志作用は生じてこないことも事実である。
だから、「大脳機能」をとりもどすことが、先決となる。
「大脳機脳」をとりもどすということは、わかりやすくいえば、主体性の確立ということだろう。そのためには自らを知らねばならぬ。崎間氏は、そこで琉球の歴史や文化を探究する。そのために「ふたば会」をつくり、のちに「琉球歴史文化研究会」をつくった。その面の彼の研究をここで紹介する余裕はない。ただ研究を深めてゆく過程で、彼はますます沖縄の歴史や文化に興味と自信と愛着をもつようになっていることは事実だ。
ここでは琉球処分を中心とした日本と沖縄の関係についての彼の考え方のアウト・ラインを私なりに紹介してみたが、その点についての詳論、さらに歴史や文化の問題をふくめた広い展望については崎間氏自身の所論にまつほかはない。
ただ言えることは、琉球の歴史や文化は抹殺できないし、抹殺させてはならない、ということである。それを抹殺する形でなされた明治以後の日本による中央集権化はまちがっていた。琉球の文化を生んだ歴史体系は天皇制日本史のなかにそのまま組み入れることはできないのである。
琉球文化を日本文化のなかに吸収するといっても、その文化の母体である琉球の歴史を無視しては、ほんとの意味での文化の融合とはならない。琉球の歴史や文化の異質性をみとめたうえでの日本との「融合」ならば、それは琉球の単純地方化によっては達成できそうにない。
──一九八二・八・二四──(おおた よしひろ・著述業)
琉球巴邦−永世中立国構想の挫折――屋良朝陳作『巴旗の曙』をめぐって/仲程昌徳
一
比嘉春潮は、有馬頼義の「琉球王国独立運動」を批判し、「琉球王国独立論は暴論なり」を書いた。比嘉はそこで、「琉球王国独立運動」が「現代においてこれまでに二回あった」として次のように書いている。
さて、琉球王国独立運動=実質的には尚家の復権運動が現代においてこれまでに二回あった。
第一回は廃藩直後から日清戦争にかけてのことであった。清国の援助を得て琉球王国の復興を企図した地下運動で、尚家の家紋左三つ巴を旗印にしたもので、巴旗の党とも呼ばれ、首領は当時の頑固党の頭目義村按司だとの噂だった。党員が清国に往来して大いに画策するところがあったが、日清戦争が期待に反し日本の大勝利におわったので、いつの間にか運動は消えてしまった。(中略)
第二回は、地下運動ではない。明治十二年の廃藩置県後、沖縄は県庁をはじめ各役所の役人、各学校の教員、各警察署の警官ことごとく他府県人に占められ、いわゆる〝大和世〟という感じで、これに対し沖縄人は皆不平の念を抱いていた。これが動機となって公同会事件が起こった。明治二十九年、尚泰王の次男尚寅(宜野湾王子)ほか七人の発起で公同会という政治結社ができた。「沖縄県人民の共同一致を謀り、公利公益を振興する手段方法の研究」を標榜したが、その手段方法は「尚家を世襲の沖縄県知事とする特別制度を布くにあり」という、やっぱり尚王家の復権運動であった。
比嘉は、「巴旗の党」や「公同会」が目ざした「琉球王国独立運動」は、「実質的には尚家の復権運動」であり、それらの運動論は、「沖縄国の独立論」とは「よく似ていても内容は全く別」のものであるとして有馬を批判したのである。
「巴旗の党」については、後に見ていく通り、比嘉の指摘と異なった見解がしるされていくことになるが、その「巴旗の党」や「公同会」は、繰り返すまでもなく琉球処分と関わって生まれてきたものである。
明治政府が、琉球処分を断行しようとした際、沖縄側の対応は複雑を極めたものであった。その事は、例えば、我部政男が整理している通りである。我部は、その著『明治国家と沖縄』の中で、「那覇の内務省出張所には、処分官出張所及び沖縄仮県庁を開き新しい標札を掲げて政務を開始した」が、「旧支配層は故意に明治政府への協力を拒み、事務引き継ぎは容易に進捗せず混乱した。(中略)この問題をめぐって『反県庁的』性格の士族集会が頻りに持たれるようになった」と指摘していた。また我部は、「松田は三条実美宛の復命書で、時の琉球士族社会に三つの大きな派閥があると報告している。すなわち、亀川党、漸進派、開化党がそれである」として、処分官松田道之の報告した三派についての記述を引いているが、それは次のようなものである。
亀川党=寧ロ我カ政府ノ処分ヲ受クルモ清国ノ情義ニハ換ヘカタク、又其我カ政府ノ処分ニ於テハ百方力ヲ尽シテ廟議ヲ止ムルノ策ヲ行フヘシトシテ論ス、是清国ヲ恩義アリトスルノ党ナリ。
漸進派=遵奉セサルヲ得サルハ既ニ能ク領知スルト雖トモ、今速ニ遵奉スルトキハ一ニハ清国ニ対シ信義ノ尽キサル所アリ、一ニハ藩内遵奉セサル党ノ人心ヲ鎮撫スルノ難キニ苦ム、故ニ藩吏一度上京直ニ政府ニ向テ歎願シ遂ニ聴許ヲ得サルニ至テ而シテ遵奉スルトキハ内外ニ対シテ答弁スヘキノ辞アリトス。是要路ノ党ナリ。
開化党=政府ノ処分ヲ恐レ速ニ遵奉センコトヲ論シ、遂ニ或ハ哀訴シテ以テ臣道之ノ帰京ヲ止メントスルノ勢アリ、是我カ政府ヲ恩義アリトスルノ党ナリ。
松田の「三つの大きな派閥」区別とその動向とに関する記述であるが、その中で、「明治政府に対し最も強行に反抗した」のは亀川党であった。亀川党は「前三司官亀川親方を指導者とする首里及び久米村の上層部からなる一派で、清国との朝貢関係を保持し、明治政府への統合に反対する立場をとっていた」といわれその目標は「旧藩制への復帰(=琉球王国)であり、いわば『現状維持』であった」とされる。そのような亀川党のことを、普通クルーと呼ぶ。
新川明は、その著『琉球処分以後』の中で、「その呼称ならびに内容には異説があって、なお明確でない点もある」としながら、「『処分』による日本併合に反対した、いわゆる頑固党を〝クルー〟(黒)とよび、新政府に妥協したいわゆる開化党のことは〝シルー〟(白)とよばれた。それは、この両派がそれぞれの標識に『黒』と『白』をもちいたためだといわれている」と記し、「置県後の『クルー党』の反抗は、清国の救援をもとめるために清国へ密航脱走する〝脱清人〟の続出、断髪拒否、就学拒否などの行為となってつづく」として、「頑固党、クルー」の思想と行動を追っている。
「脱清人」とは、「処分」反対運動のために清国政府の救援を求めて清国に密航し、福州の琉球館を本拠にして復藩運動に奔走した人たちをいうのだが、かならずしも「処分」反対の復藩運動のためではなく、新政府の命令に従うことをいさぎよしとしない人びとの「脱清」は、日清戦争後の明治三十年代のはじめまでつづいている。
たとえば、亀川親方とならんで頑固党の領袖として知られた義村按司朝明は、亀川が反日運動から隠退したあとも終始一貫して日本政府に従うことを拒みつづけたあげく、やがて清国に渡って明治三十一年に福建で客死している。
琉球処分前後の沖縄の動向の一端が、引用した比嘉、我部、新川らの文章からある程度解ったかと思うが、ここでは特に、比嘉、新川の指摘と関わりつつ本題に入っていきたい。すなわち、「巴旗の党」についてであるが、比嘉はその党の首領は、「当時の頑固党の頭目義村按司だとの噂だった」と書いていた。比嘉が「噂だった」としてあげている「義村按司」は、新川が「亀川親方とならんで頑固党の領袖として知られた義村按司朝明」と同一人物であることは間違いない。とすると、この「義村按司」は、「頑固党」というだけで亀川親方らと同一に論じられる人でなく、新川も言及していた通り、もっと別のかたちで論じられていくべき人であるということになる。すなわち「巴旗の党」というのは、比嘉が指摘していた「清国の援助を得て琉球王国の復興を企図した地下運動」であったというかたちではなく、もっと別のかたちをもった組織としてとらえていくことができるということであり、実際に比嘉とは別の観点から「巴旗の党」と書いた人がいた。
二
沖縄の独立運動が論じられる場合、必ずといっていいほどに、この琉球処分前後に起ったさまざまな動きをまずもって検討していくことから始まる。そしてさまざまな運動の中でも「頑固党」の動向を中心にして論を展開していくことになるが、それは比嘉がすでに指摘していた通り「実質的には尚家の復権運動」であったわけであり、それを支える意識は「日本一属に帰すれば、すなわち世襲衣冠の階級皆無となりて、登庸任官ことごとく篤学多才の平士等が専有する所となりて我々たちまち凍餒の悲境に陥らんことを恐れる」(喜舎場朝賢著『琉球見聞録』)という、士族階層の汲々とした身分保持からでていた。そのような階層の大勢は、新川も指摘しているごとく、「脅威を防ぎきれないとみると、いち早く新しい支配者に屈服して保身をはかる努力を惜しまない」といった「狡智」にたけていて、「利害の一致」が成立しさえすれば、それでよしとするのである。しかし、少数であったにせよ、例えば「義村按司朝明」のように「かならずしも『処分』反対の復藩運動のためではなく、新政府の命令に従うことをいさぎよしとしない人びと」もいたわけであり、そのようなあり方をした人物に視点をあててみることが、独立論を探っていく際重要になるといえよう。
比嘉、新川が、処分反対運動を演じた人としてあげていた「義村按司」を頭目にした「巴旗の党」を題材にし、沖縄の独立構想を練った少数の人びとがいたことをいち早くとりだして、「史劇」に仕組んだ人はいた。屋良朝陳である。その作品は、『琉球秘史劇巴旗の曙』と題されたものである。
『巴旗の曙』は、序幕から第五幕まで、「その昔」(序幕)、「大評定」(第一幕)、「風雲」(第二幕)、「巴旗の人々」(第三幕)、「悲恋」(第四幕)、「曙光」(第五幕)というように構成されている。
序幕は、昔の那覇港の風景を写し取る。そしてそこに浮かぶ琉球船にはすべて巴旗が掲げられている。それは「海運国の活気を呈しながら」「太平の姿」を象徴するのであり、「四五百年以前の琉球王国の姿を想像して偲んで下さればよい」と、作者自身記しているようなかたちで幕が開いていく。すなわち、処分前の琉球の姿をまず写し取っていく。
第一幕は、「三條大政大臣の命令書を携えて内務大臣松田道之がやって来て藩内制度改革を宣言した」ことから、王城大広間で「大評定」が開かれるその一部始終を書いたもので、「宜湾親方や津波古親方などの開進党と、亀川親方、幸地親方、池城親方などの守旧党」との間にかわされる議論を中心に展開される。
開進党の論拠は、「今明治維新に遇って我々が本来の父母の国に立ち返って朝廷の御為に尽くし、皇恩を浴びることは、まことに理の当然」であり、「隣邦薩摩に征服されて以来、その搾取のまゝに任ぜざるを得ず、王様を始め輔弼の臣達が真に焦熱地獄で熱湯を呑む思い、個人々々は去勢され、奴隷化されて全くの萎縮。ところで斯る桎梏が取り去られて、今や明治聖代の大円光の中に蘇生しようとしている」として、明治政府への積極的な同化を推進していこうとするものである。
それに対し、「今や王国は上下を挙げて、これまで通りに変化のない国家を熱望している」として、異をとなえる一派の主張が開陳される。
開進党に対する守旧党の論拠は、「本国は弱小国ゆえ日、清へ両属の外交はしていても独立王国の実体は今日まで続いて」いるとし、「若し日本の版図にされた時は、本国の文化も政治も教育も、その他、一切のものを」失ってしまうとする。また、「清国は本国を属領という名義丈で占領欲はない」が日本は違う。「日本は武力で威嚇して本国を占領しようとしているもので我々は日本によって亡国民の悲境に陥されるか、幸にしてこれを免かるかの瀬戸際に立っている」。だから「この際薩摩の桎梏から逃れて清国、日本国と隣邦の好みで交り、外交上の名義は属領でも保護領でも構はない。実体に於て是迄通り独立の琉球王国をつづけて行くことが出来れば、結構此の上もない」し、「此に他国の版図にされて亡国の憂目を見ぬよう、永久に琉球王国の独立を失はぬように」しようと主張するのである。そして「琉球は清国の保護の下にありさえすれば、磐石の安泰である」ことからして、「日本政府の処分に就ては百方力を尽して廟議を翻す策を取り」「これ迄通りに差し許され度い嘆願書をもって東京へ使い一方事情を北京政府へ具陳して、万一の場合に備へて黄色軍艦を差し向けて貰うように」しようと訴える。そのことは「慶長の役及びそれ以来の日本政府への怨み! それを忘れてどうしておめおめとその命に従」うことができようかという考えからでている。
開進党はそのことに対し「それは一隣藩薩摩のこと」であり、「日本朝廷とは全然別にして考えねば」ならないと反駁するが、日本政府といえども薩摩と同じ系統を引くものであり、「より以上の桎梏がないと、誰が保証出来」ようかと一蹴されるばかりである。
「大評定」は、そのように守旧党の優位のまま展開され、その結果「守旧党の主張が入れられて、是迄通りに差し許され度き段、直接朝廷へ嘆願に上京すべく」人選が行なわれ、決着する。
「大評定」の場面は、処分をめぐって守旧党、開進二党の代表者たちが論議していくかたちで展開されるが、そこにはそのどちらの党にも属さず、発言する機会さえなかったあと二人の重要な人物が登場している。一人は巴党の首領神田親方であり、あとの一人は「首里三ヶで侮り難い潜在力を有ち領地屋良邑から北谷一円にかけて」絶対的な勢力をはりながら、どの党にも属しない屋良親雲上である。
第二幕「風雲」は、舞台を「普天間権現の境内」に移し、三党どちらにも属しない屋良親雲上を中心にして展開される。
まず「薩州の樺山権太郎」が、屋良に戦いを挑み組伏せられてしまう。彼は開進党の使いの者で、彼が屋良に挑んだのは、屋良が開進党の味方になってくれると期待したにもかかわらず、その期待に添ってくれなかったからであり、屋良はともすれば、守旧党へ味方するかも知れないという恐れからであった。
樺山を屋良に挑ませた津波古親方は、樺山が組み伏せられ、襲った動機を白状するよう屋良にせまられている所へ出て行って、その屋良に「開進党は守旧党に圧されて気息奄々というところ、屋良親雲上なぜ味方になって下さらぬ」と逆に問う。屋良は、そこで己れの心情を彼等に披瀝していく。
それは、「琉球は開闢以来独立の王国を形成し、独自の芸術が芽生え、繁茂して」きた「神々の別荘地としての平和境」であり、「全く夢の竜宮城」であり、「世界無比の独特の芸術がこゝに生きて」いるが、戦乱にでもなれば、それらがすべて烏有に帰してしまうことは、すでに「慶長の役」が示した通りであり、どんなことがあっても戦乱は避けねばならない。屋良一派が、もし開進党に力を借せば「勢力伯仲して直ちに内輪揉めの内乱になる」おそれがでてくる。それゆえ「開進党は、気息奄々でも是非存在し、決して守旧党に刃向うことはせず、日本朝廷と連絡をとる役目。屋良一派は洞が峠をきめこんで暗々裡に守旧党を威嚇し、戦乱を避けて、祖先代々築き上げた郷土文化の守護を以て使命」としたいとうちあける。そして「開進党が危急の場合は、屋良一派、蔭ながら助太刀」すると伝える。
守旧党の一派林世功らも屋良を討つため彼の後を追っているが、樺山が組み伏せられたのをみて、見合わせてしまうというのが第二幕である。
第三幕「巴旗の人々」は、「宜野湾松並木」を背景に、守旧党の林世功らが、屋良と別れた津波古、樺山の二人をとり囲む所から始まる。津波古らが、まさに危機一髪のところへ「屋良親雲上配下の壮士たち」が助太刀に入り助けられる。
屋良とその同志喜納親雲上がその後登場し、屋良がこれから「巴旗の人々」に会うこと、「事情に依っては巴党に助勢」することになるかもしれないこと、そのときには「配下の指導督励」を頼むと喜納に伝える。喜納を帰した後、巴党の一人仲本筑登之があらわれ、首領神田親方の所へ屋良を案内する。屋良と神田が面会し、問答が始まり、そこで巴党の方針が述べられていくことになるが、それは「永世中立の平和境を建設する」というものであった。その説明を仲本がしていくが、琉球を「ヨーロッパに於けるスイス、東洋に於ける唯一の永世中立国」にするというように展開される。そのことに対し屋良は、「日、清に依存せずして一国の経済は確保され」るであろうかと問うと、神田が「観光都市計画と相俟って貿易」でもってそれは解消されるであろうと説明する。屋良はさらに日、清は簡単にその実現を許さないと思われるが、たとえ許したにしても世界の列強、英、米、佛、蘭は許すまいと言うと、それに答えて神田は「日、清が癌」であって、先進文明国をもって自任している他の強国は「決して武力で圧制して琉球のような武器のない唯平和の守礼之邦を武力占領はしない。文明大国の襟度よりしてむしろ東洋唯一の小さい平和国をお互で守り育てて呉れる」であろうという。仲本は、神田のその説をさらに補なう形で、ペルリが「琉球国を訪問する前、海軍卿」に呈出した意見書をとりあげ、「琉球を永世中立国にすることは列強も希望」していること、また「米国は琉球王国を絶対独立国と認めている」ことを説明していく。その後で、神田が、君主制でもなく民主制でもなく、「君民が巴の中心国体」である「琉球巴邦の実現」を訴えると、屋良は「歴史的に、大観的に進むべき方途がはっきりと」わかったとして、「粉骨砕身を巴旗の下に誓」う。
しかし、そのような「永世中立琉球巴邦として理想の国家が実現されるのは、先ず一世紀近くも後のことであろう」と神田はいい、「吾々は唯秘密裡に子々孫々の胸へ強くこの理想を植えつけて置くこと」であるという。
屋良は神田のその言に対し「尊い理想を自覚しながら坐視傍観すること」は許されないことであり、「理想実現のため邁進」したいと述べる。屋良のその言には同調者が多く、神田も「今は時機でない」という考えを翻し、「日、清の眼を隠れて東京在住の各国公使に密に会い、極力説得して援助を乞う」という計画を出し、その実行を、屋良、仲本そして自分の一子卍丸にいいつけ、覚書を渡す。覚書は「琉球国是について」「琉球芸術の保存、顕揚に就け」「永世中立『琉球巴邦』建設の根本理念」の三箇条からなるもので、「提出書類や口頭陳述などの参考に」として渡される。そして役目遂行のための離別の酌をくみかわす所で第三幕は終わる。
第四幕「悲恋」は、「大道松原の黄昏時」を背景にした場で、開進党宜湾の娘玉津と守旧党亀川の嫡子山戸との恋を扱った場面である。
第五幕「曙光」は、「普天間権現案内」の場で例祭の日の一日。すでに状況は移り変わっている。「廃藩という声に喧々囂々、上下の者が迷い、はては守旧党、開進党の両党が鎬をけずって今にも戦乱が捲き起りはせぬかと……人心は戦々兢々たる」ものであったが、「天佑、神庇」というか、戦乱もなくてすみ、「嵐の危険はもはや全く過ぎ……今こそ誰に憚るところなく、わが沖縄が一天万乗大君の皇恩に浴するようになったこと即ち父母の国に帰った復興沖縄を朗に祝福すること」ができるというような時になっている。そして、そのような時をえたのも「これ偏に御稜威の然らしむるところで、御稜威の下我々の期待はきっと実現されること」であろうとして、「新しい我々の国旗」である「日章旗」を高く掲げ、「大日本帝国万歳」を群集と三唱し、「奉納の余興は朝から日没にかけて、一そう賑かにつづけられて」いく。
夜に入り境内から人影が全く途絶えた後、巴党の首領神田親方を先頭に普天間権現に参拝する一団の姿があらわれる。そこへ使者としてたっていった者たちも帰ってきて、報告がもたらされるが、成功の見込みはなく「巴党の解散」が宣言される。彼等は「永世中立琉球巴邦万才」の三唱をなし、「二百数十年以来は圧迫、厳禁のもとに陽の目を見ず、国民からも忘れられ文書からも抹消され唯同志から同志へとゆずり渡されて秘蔵して来た巴旗」が神田の手で焼かれ、神田もやがて息絶えてしまう。そして屋良親雲上も「巴旗の曙」と一声を残して息を引取る所で幕になる。
三
琉球処分の際、親日派、親支派に分かれ、帰属をめぐって闘争が行なわれたことはよく知られている。が、その両派のどこにも属せず、琉球の独立を願って奔走した人々の一派、すなわち「巴党」なるものがあったことは、それほどよく知られてない。というより、それは比嘉春潮が指摘していたようなかたちでしか知られてない。
屋良朝陳の『琉球秘史劇巴旗の曙』は、親支派(頑固党、亀川党、クルー)を守旧党に、親日派(開化党、シルー)を開進党におきかえ、それぞれの主張をとりだしながら、守旧党の方向から開進党の方向へと、琉球処分が終結するまでを書くと同時に、「永世中立琉球巴邦」の建設を夢みながら結局挫折せざるを得なかった巴党の転末を描いたものであった。
守旧党、開進党というあり方は、琉球歴史の担った特異なかたちを背景にしているわけであって、保守、革新というかたちや、単なる左右対立の図式とは違うといえよう。日、清両属というどちらつかずの長い状態が、それぞれに日、清いずれかにより強い帰属意識を生みださせることになっていったと考えられるのであり、そしてそのことは、利害観と一体にあったとするより、出自意識あるいは文化意識と結びついたものであったと考えられる。そして単純化してしまえば、親支派はより出自意識と関わり、親日派は文化観をより所にしたとすることもできるかと思えるが、両派ともに大国主義(意識)に金しばりにされていたことは間違いない。
『巴旗の曙』は、そういう大国主義(大国依存意識)から解放され、自立自存を希求した党のあったことを書いているが、両派のどちらにも属さず独立を主張した側に、より汎世界主義的傾向があったというふうに書いている。すなわち、中国、日本というように一国だけに眼がむいているのでなく、広く進んだ多くの国々のことを学び、その上にたって独立が考えられていたというかたちにしているわけである。そのことは、より開かれた思想が、当然にいきあたっていく本質的な姿といえるものであろうし、屋良朝陳の思想といえるものであったともまたいえよう。
屋良が、琉球処分の際、頑固党でもなく開化党でもなく、「永世中立国」を構想した「巴党」なる一派のあったことを史劇にしえたのは、しかし屋良の独創によるものではなく、それが実際にあったものであるということによっている。屋良自身「作者曰く」というかたちで、次のように記してある。
父、屋良朝信また叔父屋良朝恕は、僕が15、6才の腕白時代からぼつぼつ機会さえあれば僕に巴党の話をした。あの時僕は喜んで聴き感激したことも確かですが、聴き洩らしたか、忘れたか、よく捉めなくて曖昧なところがあるようです。他には久米邑の儒者、楚南能任、名嘉山大昌、桑江克英の老先生から断片的に聴かせてもらったのみです。
屋良は、続けて実際にみてはいないけれども「首里大中の神田殿内、北谷桑江前の向氏屋良家、泊前道の雍氏仲本家には文書が厳封秘蔵されて」いるという話を聞いたと書いている。そのことだけでは、巴党なるものがあったというだけで、それが、どのような目標を持っていたかということについては解らないが、「緒言」で「廃藩置県当時、日、清の孰れに依存すべきかと白、黒の両党に分れて闘争したことは史書に明らかであり、その何れの党にも属せず、巴旗を護りとおして、永世中立として琉球巴邦の建設を企図した一党があったことも古老に依って伝えられている」と書いていて、明らかにしている。
我部の引用していた松田の報告書には、そのような党のあったことはみあたらない。それは恐らく屋良が、巴党の首領神田親方に「吾々は唯秘密裡に子々孫々の胸へ強くこの理想を植へつけて置くことです」と語らせているように、「秘密裡」になされた運動であったことによっているのであろうか。
『巴旗の曙』は、「古老に依って伝えられている」史実ということだけで、書かれたわけではないと思える。屋良が、それを書きあげて刊行したのは1946年3月である。ということは、屋良の意図がどこらあたりにあったかということを暗々裡に語っているはずである。その屋良の意図を探っていく前に、見ておきたいものがある。それは次のような文章である。
さて、沖縄の帰属問題は、近く開かれる講和会議で決定されるが、沖縄人はそれまでに、それに関する希望を述べる自由を有するとしても、現在の世界情勢から推すと、自分の運命を自分で決定することの出来ない境遇におかれてゐることを知らなければならない。彼等はその子孫に対して斯くありたいと希望することは出来ても、斯くあるべしと命令することは出来ないはずだ。
「沖縄歴史物語」の結びの文章からの引用である。「地球上で帝国主義が終りを告げる時、沖縄人は『にが世』から解放されて、『あま世』を楽しみ十分にその個性を生かして、世界の文化に貢献することが出来る」と続いていく、この伊波普猷のあまりに有名な文章の書かれたのは1947年である。敗戦後2年目に書かれた文章であるわけだが、それは、占領された沖縄の帰属をめぐって、伊波の心中をのべたものであった。
伊波はそこで、帰属問題に関し「希望を述べる自由」はあっても、それを「自分で決定することの出来ない境遇」にあることを、無念の思いをこめて書きとめ、「帝国主義が終りを告げる時」沖縄は「世界文化に貢献することが出来る」と希望的観測を述べたのであった。
伊波がそれを書いた時、琉球処分に際し沸騰した帰属問題が、胸中に去来しなかったはずはないであろう。そしてそれは、沖縄の歴史に関心を持っていた人々が、それぞれに思いおこさざるをえなかったことであろうが、そのもっとも早い反応として、屋良朝陳の「史劇」があったのは間違いないし、さらに積極的な帰属問題への対応を訴えたものであったととれるのである。
屋良は「緒言」で次のように書いてある。
今般沖縄が如何に処置せられるだろうか、如何に処理すべきであるかは世紀的に重大なる問題である。この際沖縄の現状を知ると共に其の歴史を弁えることは後世如何なる世界に至っても肯定せらるべき大道に立脚した処理の判定を下す上にも極めて緊要だと思われるのである。
如上の意味で開闢以来の琉球歴史を有りの儘に、而も平易に誰にもわかり安く、読み易くして大勢を認識せしめたいという点を考慮して書き出した劇作であって、沖縄を如何に処置して欲しいとか、如何に処理すべきであるとかいう希望、意見などの書では勿論ない。作者は唯有りの儘の事実を提供して、此際参考に読んで貰うことを、沖縄の人々は申すまでもなく、内、外国の各方面、各層にお願いするのみである。
「1945年大東亜戦争終末の乙酉歳12月8日」という日付の入ったこの文章は、「唯有りの儘の事実を提供」したというだけで、沖縄の処遇問題への意見をさしはさんだものではないとことわっているが、素材の選択はその言葉を裏切っていたといえるであろう。
屋良が、日、清への帰属問題がたたかわれている中で「独立構想」を持って奔走していた人々のあったことを取り出して書いたということは、占領され、しかも帰属問題が持ちあがりつつあるときであっただけに、はっきりとした意図というものがそこになかったとはとても考えられないのである。すなわち、沖縄の進むべき道を、歴史の動乱の中に探りつつ、いままさに動乱の中にいる同胞へ訴えようとしたものであったと考えられるのである。
処分時に展開された一種の独立運動とでも呼べるものを、敗戦後すぐに書いたこの書について、触れている人は少ないようである。恐らく、多くの人の目に触れなかったか、あるいは無視されたのではないかと思う。確かにそれを「史劇」という観点のみからみるとすれば、それほど価値のある作品とはいえないであろう。陳腐な歴史活劇としかいいようがないかも知れない。
屋良のこの作品について、ほとんど唯一の批評をした人として金城朝永をあげることができるが、金城はこの作品について次のように論じていた。
沖縄における親支・親日両派の対立は外にもいろいろの話題を提供していて、その一部は文人の作品の題材になっていることは、前に述べてある通りであるが、終戦後、新たに屋良朝陳氏もまた、維新当時のこの両派の抗争を取り上げ「巴旗の曙」と題する単行本を出版している。琉球秘史劇と冠してあるものの、実は登場人物はすべて、事件の筋を運ぶための傀儡の感があり、あるいは酷評かも知れぬが、旧来の講談本の亜流に過ぎない作品である。
金城の作品評は、まさに当を得たものであり、屋良の作品は「旧来の講談本の亜流」であるとしか言えない。が、金城はさすがにそれだけで終わってしまうことなく、「ただ一つ特筆に値することは、その中に今までほとんど世に知られなかった『巴党』に称する一派の黒・白両党の外にあったという伝承を初めて紹介してある点であろう」として、その梗概をしていることである。そして、金城は「この琉球国永世中立を標榜する巴党の話が単なる伝説の類に過ぎないか、あるいは確かな史実にもとづくものであるか、ここではにわかに断定を下し得ないが、今その真偽は別として、日支両強国間に挟まれて、永い間不自然な施政下に窮屈な生活を続け、しかも親支親日両派の党争に苦杯を飲まされることの多かった沖縄人の間に、そのいずれにも禍いされることのない、のびのびした中立の桃源境を夢みる者の居たらしいというこの伝承は、今の私共にとっても決して興味のない話ではない」と記していた。
金城が論じている通り、『巴旗の曙』は、文学作品としてはほとんど評価されることのないものであるが、その扱った題材の持つ意味は、作品評価の問題を越えて「決して興味のない話ではない」のである。
(なかほど まさのり・琉球大学教養部助教授・近代文学)
山里永吉瞥見/岡本恵徳
一
今から360年前まで、琉球は「完全」な独立国であった。そして、その以後(つまり慶長十四年以後)薩摩に攻略されてから明治12年の廃藩置県まで、琉球は「完全」とは言えないながら独立国であった(略)。
三度くりかえしていうが、琉球は明治12年に独立を失い、日本の一部になった。そしてすべての琉球人(というのがいやだったら沖縄人といってもよい)は日本人ということになった。
しかし、われわれは日本人である前に沖縄人であることを忘れてはならない。したがってわれわれは、日本の利益を考える前に、まず沖縄人全体の利益を考えるべきである。沖縄は今まで、あまりに日本の犠牲になりすぎた。薩摩の搾取はいうまでもないが、廃藩置県以来の日本政府の沖縄県に対する苛斂誅求は、むしろ悪辣といってもよいくらい無慈悲なものであった。
そういう日本を祖国とよんで、戦後いちはやく日本復帰をとなえたのは、沖縄の歴史を知らない政治家どもであった。しかし、私は日本を祖国とは思わない。われわれの祖国は厳然として沖縄であり、沖縄以外にわれわれの祖国があるはずがないのである。したがって施政権の返還はどこまでも沖縄人への返還であって、日本政府に返還すべきものではない。
話はとぶが、私は沖縄と沖縄の文化にかぎりない愛着をもつものである。けれども、沖縄人が日本復帰を叫んでいるうちは、沖縄に特性のある立派な文化が生まれるはずはない。日本復帰ということは、つまり沖縄の文化が、いつまでも日本の後塵を拝するということである。(以下略)
これは、「沖縄人の沖縄」の題名で、1969年6月9日付『琉球新報』に掲載された文章である。この文章は、のちに『沖縄人の沖縄−日本は祖国に非ず−』という小冊子(B6判・46頁)の巻頭に収められ、1969年8月、沖縄時報社から刊行された。ついでに、この小冊子の内容についてふれておくと、前記の「沖縄人の沖縄」の他、「日本は祖国に非ず」「私の沖縄」「われわれの先祖は自主独立の気概をもっていた」の三篇、いずれも原稿用紙にして五、六枚の文章を収めてあって、冊子の題名と同じ主張を繰り返したものである。そして、その主張の基本的なものは、さきに引用した部分に端的に示されるものであった。いわば、先に引用した部分は、著者の立場を明確に示す、宣言ともみなされる部分である。
この宣言文にみまがうような文章が、山里永吉によって、しかも1969年の時点で発表されたことは、きわめて象徴的な意味をもつ。最も書くにふさわしい人によって、そして最も必然的な時期に発表されたということで、象徴的な意味をもつにいたっているのである。そこで、ここでは、まず、この文章の発表された時期がどのようなものであったか、を確認しておきたい。そしてそのあとで、何故それが山里永吉によって書かれたか、その意味するものを検討したい、と考える。
二
1969年という年は、前年11月の主席公選につづいて、11月の佐藤・ニクソン共同声明によって「72年返還」が確定された時期である。その過程をやや詳しく年譜ふうに確認しておくと、1965年8月の佐藤首相沖縄訪問に始まり、66年8月教育権分離返還構想、67年2月下田外務次官による〝核つき返還論〟の提起、同年11月には、佐藤・ジョンソン共同声明によって、〝返還について両三年内でのメドづけ〟が発表されている。そしてその声明にもとづいて主席公選が認められ、68年11月主席公選が実施、屋良主席が就任する。ところが同じ月にはB52が嘉手納基地に墜落事故を起している。翌69年2月には墜落事故に対する抗議の全島ゼネストが計画された(いわゆる2・4ゼネスト)が、それは失敗に終る。6月には全軍労のゼネストが決行され、11月の佐藤・ニクソンの会談で「72年返還」が確認されるということになる。すなわち、65年に始まった佐藤政権下での施政権返還問題が、返還のありかたをめぐってさまざまの紆余曲折をたどりながら、次第に明らかな形を見せ始め、最終的に決定されるのが1969年11月であり、先の文章の書かれた時期は、まさにその決定的な瞬間にいたる寸前であったといえるのである。
返還交渉の動きをみると、67年の佐藤・ジョンソンの共同声明では、「日米間で沖縄の施政権返還を日本に返還するとの方針のもとに、沖縄の地位について共同かつ継続的な検討を行う」ことが明らかにされているものの、これは返還が近いうちに実現されることを約束したものではないと受けとられていたと考えられる。つまり、いずれは返還するが、一年先かあるいは百年先かは約束できないという主旨として受けとめられるようなものであった筈である。ベトナム戦の激化、B52の常駐化態勢(68年2月以降)等、状況は返還の方向にむいているようにはみえなかったこと、また、1961年のケネディ声明、日本の潜在主権を認めた声明が結局何の変化も沖縄にもたらさなかったという経験等にもとづく、共同声明についての不信等があって、佐藤・ジョンソン声明は、〝いずれは返しましょう〟ということを意味するだけのものであると受けとられたふしがみえるのである。
このことは、たとえば、1968年の主席公選で、保守側が、積極的に「イモ・ハダシ論」を展開したことにもうかがえる。「イモ・ハダシ論」は、〝復帰〟すれば沖縄は再び戦前と同様な貧しいくらしに陥る、ということであった。これは、復帰尚早論と結びつく。復帰尚早論は、復帰するにしても、もっと沖縄が経済的な力をつけてから復帰してもおそくはないし、むしろそうすべきであるという主張である。「イモ・ハダシ論」にしても「復帰尚早論」にしても、その底に、日本に対する不信が根づよくわだかまっているのは事実であろう。「イモ・ハダシ論」には、日本政府が沖縄の面倒をみることはあまり期待できないし、「尚早論」には、いま復帰すれば、資本力の大きい企業に沖縄の企業は圧倒されるに違いないという危惧があった筈である。
そのような日本不信をかかえこみながら、「保守」側の人たちに「イモ・ハダシ論」があり「尚早論」があったこと、そしてそれが主席公選における一つの争点としてあったことは、この時期において、施政権返還の方向は決定的ではあるが、なお流動的な要素を残している。場合によっては、施政権の返還はずっと先の事かも知れない、あるいは何時までも引きのばすことが可能かも知れない、という認識のあったことを示すといえる。そしてそこに、復帰尚早のみならず、復帰に反対する論議の登場する余地があったとみることができるのである。
一方、これと並行する形で、復帰運動に加担している人々のあいだで、復帰についての疑問が公然化するのもこの時期である。1960年代後半、67、68年頃には、復帰運動についての疑問がさまざまな形で登場してきている。いわゆる「民族主義的偏向」という形での批判、たとえば階級的な視点の欠如とか、あるいは「日の丸復帰」批判という形の批判である。しかし、これは「復帰運動」のありかたについての批判ではあっても、「復帰」そのものに対する疑問や反対ということではなかった筈である。むろん、なかには「復帰すること」そのものについての疑問につながる見解もあったが、それほど公然化してはいない。68年の主席公選の前までは、「本土の革新勢力」についての期待が根強くあって、むしろそれがそういう人達を復帰運動につなぎとめていたと考えられる。(吉原公一郎『沖縄―本土復帰の幻想』所収の座談会参照)
ところが、その期待も、主席公選とほとんど同時に起きた、B52墜落事故に始まり、翌69年の初めにかけて盛りあがった全島ゼネスト体勢が、日本政府と「革新」の双方によって挫折に追いこまれるという事態が生じ、「本土の革新」に対する不信感をつのらせることになった。そしてそれをきっかけに、「復帰」そのものについての不信と疑問が公然化することになったのである。
「保守」側の「尚早論」は、69年11月の佐藤・ニクソン会談によって「72年返還」が確定すると共に急速に転換し消滅していくが、後者の復帰運動に加っていた人達の復帰に対する疑問は、やがて70年の「国政参加選挙」拒否闘争として展開し、「反復帰論」としてその主張は論理化されることになる。
先に引用した、山里永吉の「沖縄人の沖縄」が執筆され、一つの冊子として公刊される1969年6月から8月というのは、「保守」側の尚早論や復帰批判が、最後の華を咲かせて急速に消滅する寸前であると同時に、復帰運動にかかわっていた人達の間に「復帰」についての疑問や批判が噴出する時期にあたる。すなわち、「復帰」についての批判や疑問が「保守」側と復帰運動に参加していた人達の双方から出てくるという二つの動きが渦まいていた時期に、その二つの渦にのって登場したものとみえるのである。
この山里永吉の論が、「保守」的な、「復帰尚早論」の立場にくみする形で登場しながら、「尚早論」をつきぬけて、「復帰反対」の論理にまで達したのは、そのような状況のもとで書かれたことによるといえよう。しかし、むろん、山里永吉が「復帰反対」論を展開したのは、そのような状況ばかりによるとはいえない。山里永吉の内部に、「日本復帰」ということに対する疑問や日本に対する不信がすでに根づよくあって、それがこの時期の前述のような発言になったことは否めない。それは、これより十年も前の、1960年11月から翌61年8月まで『琉球新報』朝刊に連載した随筆「壺中天地」の冒頭におかれた、「日本人と琉球人」と題する文章によっても明らかである。
今から80年以前の琉球人は、けして自分達が日本人であるとは思っていなかった。そういうものの言いかたは、ちょっと語弊があるかも知れないが、琉球の一般庶民が自分達は日本人であるという自覚をもつようになったのは、日清戦争以後の教育の力である。もっとも羽地王子向象賢は300年以前、すでに日琉同祖論を唱えており、それに間違いはないが、庶民の多くは、彼ら日常の生活、文化、政治、経済の面から、たえず自分達と日本人を区別して考えていた。(中略)
そういう琉球人が、太平洋戦争の沖縄戦で、日本人として喜んで死んでいったのは、すべて教育の力である。しかし、その教育も日本人がそうしたのではない。琉球人自身で、自分達の子弟に日本人としての教育をしてきた結果である。
日本復帰が叫ばれている。そして、日本を祖国と呼んで誰も疑わない。百年以前の琉球人が聞いたら、きっと頭をかしげて考えるであろう。日本復帰は琉球人の悲願だというが、中国復帰の間違いではないかと考える亡霊もあるかも知れない。笑いごとではない。それが時勢というものであり、われわれも、いずれ批判される日が来るのである。
以上、長々と引用したが、この文章では、「日本に復帰する」ことに「反対する」ことを明確には述べてはいないものの、冒頭に引用した「沖縄人の沖縄」と基本的には同じ考え方を示している。ということは、1960年の段階と、1969年の段階と山里永吉の考えや立場はいささかも変らなかったのである。
三
先に「日本人と琉球人」「沖縄人の沖縄」と、およそ10年をへだてて書かれた文章を引用し、その間にいささかも変化の現われていないことを示した。「日本復帰」に反対ということを明言するしないの相違はあるにせよ、その見解を支えている歴史認識、すなわち、慶長以前は完全な独立国、薩摩支配下の沖縄は半ば独立を保っていて、明治に入って完全に独立性を喪った、とする認識は不変である。
薩摩の支配下に入る慶長十四年以前の沖縄が〝独立国〟であったということは、一般に認められている事実である。が山里永吉の論で注目されるのは、そのあとの「薩摩に攻略されてから明治十二年の廃藩置県まで、琉球は『完全』とは言えないながら独立国であった」という部分である。そして、明治の廃藩置県でもって「完全」に独立性を喪ったという認識に、山里永吉独特の歴史観をみることができる。
これは、たとえば伊波普猷らの認識とは明らかに異なる。周知のように、伊波普猷は、明治の廃藩置県を「一種の奴隷解放」と捉えている。伊波の「琉球人の解放」や「進化論より見たる廃藩置県」等の論文で展開されたものは、薩摩治下の琉球がまさに「奴隷的生活」にあったという認識である。むろん、この伊波の評価については、仲原善忠をはじめ多くの人々からの批判がある。その意味では現在の歴史学の認識からすれば否定されている見解ということになろう。しかし、その伊波論を否定的にみる立場にたつ人々の見解にしても、いわゆる「琉球処分」のありかたやその評価に見解の相違はあるものの、薩摩の支配下にあった時期にくらべて明治の廃藩置県以後の沖縄の状態を相対的に進歩したものと捉える点では伊波とそれほど異なっているわけではない。すくなくとも「薩摩の搾取はいうまでもないが、廃藩置県以来の日本政府の沖縄県に対する苛斂誅求は、むしろ悪辣といってもよい」とする山里永吉の論は、そのなかにあって、特色のある見解といわなければならないし、そこに、山里永吉の伊波をはじめ多くの歴史家たちと決定的に異なる立場が現われているといえるのである。おそらくこういう立場のちがいは、一般の認識が、沖縄を日本民族の一部とみなしてそれを前提として成立しているのに対し、山里永吉の場合は、沖縄と日本をあくまで切り離して、沖縄を沖縄として捉えようとする志向をもっていたことによろう。そこに薩摩属領下の沖縄を「完全」とはいえないまでも「独立国」であり、それに対して廃藩置県後を完全に独立を喪ったものとする評価が生まれてくるのである。
ところで、それでは、山里永吉が琉球に対する薩摩の支配の苛酷さを過小に評価していたかといえば、必ずしもそうではない。そのことについて山里永吉は次のように述べている。
考えると、薩摩の琉球侵略ほど惨酷な戦争はないような気がする。戦意のない琉球に、言いがかりをつけて、兵を送り、抵抗しない相手に無条件降伏させた上、叛意のない国王を捕虜にして、日本国中をひきまわし、そしてその後三百年間、子々孫々の時代までも、搾取をつづけていたのである。(改行)こういった惨酷さは、同一民族の間では、とうていできるものではない。異民族と思えばこそ、できる侵略であり、搾取である。(略)そこには文明もなければ、人権もない。ただ、野蛮と、暴力と、貪欲と、残忍な権力ばかりがある。それが薩摩であり、島津であった。(『沖縄歴史物語』164頁)
山里はこの文章では、冒頭にあげた文章の、不完全ながら独立性をもっていた、という評価と矛盾しかねないほど、薩摩の圧制について酷しい評価を下しているのである。
そして、そのような一見矛盾とみられかねないような評価が、決して矛盾でなく結びついているところに、山里永吉の歴史認識の特色がみられるのである。山里永吉は、薩摩の支配が、苛酷であったことは認める。しかし同時に琉球が不完全ながら独立性を保っていたことも認めるのである。これは山里が、形式的であれ何であれ、中国に対して独立国として冊封を続けていたという形式を重視しているからでもあるが、必ずしもそればかりによるのではない。もし、山里永吉が、単純に日中両属の形を捉えて、だから不完全ながらも独立性を保っていたのだとするならば、このことをとりあげて、山里永吉の独特の認識とするほどのことにはならないであろう。
山里永吉の歴史認識の独特なところは、そこにあるのではなく、沖縄内部の状況に着目してその論を展開しているところにあるのである。すなわち、あれだけの抑圧をうけながら、そのなかで沖縄が何故独自の文化を喪わずにいたか、というところに着目することから、逆に沖縄の独立性を評価する論理を導きだしているところに、その論の特質があるのである。おそらく、山里永吉はもし薩摩の侵略によって沖縄の独立が完全に喪われたとすれば、あれほどの沖縄の独自の文化が保持される筈はないという認識を基本的にもっていたに違いない。であるからこそ、
尚寧王以後の琉球の歴史は、薩摩の搾取にあえぎながら、いかにして琉球の全住民を飢えさせず、独自の文化を守っていくかという、苦難の歴史である。羽地朝秀も、程順則も、蔡温も、宜湾朝保も、そのために骨身をけずった。そういう苦境にありながら、むかしの琉球人は、よくも自国の文化を温存し、育んできたものである。征服者の薩摩には、まるで文化らしい文化はなかったが、被征服者の琉球には、そのころから、逆にすぐれた固有の文化がいくらでもあったのは皮肉である。(『沖縄歴史物語』165頁)
という評価が出てくるのであろう。この論をさらに強調すると、「当時の琉球の政治家の苦悩は、薩摩の搾取にあえぎながら、いかにして人民を飢えさせることなく、自尊の精神を忘れずに、琉球の伝統的文化を守っていくかということであった。言葉をかえていえば、薩摩に対する平和攻勢である。武力では敗けても文化の面では、むしろ薩摩を指導してやろうという意欲である。(中略)われわれの先祖はどんな逆境におかれても自国の伝統を守り、自主独立の信念だけは持ちつづけてきた。彼らは、彼らの祖国がどこまでも沖縄であり琉球であることを忘れなかったのである。(改行)沖縄人が、事大主義におちいり劣等感をもち、優柔不断、自尊の精神を捨てたのは、廃藩置県以後である。それは沖縄県庁のまちがった植民地教育の結果だろうと私は考えている」(「日本は祖国に非ず」『沖縄人の沖縄』212頁)ということになるはずである。
すなわち、山里永吉にとって重要なことは伝統的なものや独自な文化をどのように保持し、育んできたかということであり、その点に着目するがゆえに、薩摩の掣肘を受けながらも独自な文化を保持した琉球は、まさに「完全」ではないにしても独立国として評価できるとするのである。そしてだからこそ、逆に琉球の独自の文化を全く喪ってしまった明治以後の沖縄は、独立性をもっていないものと評価することになるのである。
この論では、「民衆」が「飢えないように」という政治的・経済的な問題についての論及はむろんあるけれども、中心はそこにあるのではなく、あくまで独自の「文化」を保持したかどうか、ということにある。あえていうならば「文化論」的歴史認識ということになる。そしてさらにいえば、その「文化」についての把握は、たとえば薩摩の「武力」に対して沖縄の「文化」を提示している所に示されるように、さらに「平和攻勢」という言葉に示されるように、現象的な面でとらえているところに特徴がある。そこには、たとえば、薩摩の「武力」を支えているのが、他ならぬ「薩摩の文化」であるというような認識、一つの社会の文化の質や水準が「武力」として現象することもあるのだという認識をみることはできない。こういう「文化論」的立場にたつ限り、「文化」は、結局、芸能や建築や、工芸やそういうたぐいのものに限られてくるにちがいない。事実、山里は次のようにも述べている。
私は、すぐれた芸術は自由の所産だと思っている。だから自由のないところに、すぐれた芸術が生れるはずはないのである。つまり、政治的統制の下にすぐれた芸術は生れないともいえるのであって、言論とか、思想の統制下にある国家に、すぐれた芸術が生れた例はあまりないような気がする。
だから、芸術とか文化というものは、どんな場合でも自由が必要である。したがって、自由を失った国の芸術文化はすでに固有の文化ではない。それは芸術の死滅であって、琉球の文化の歴史を調べて行くと、当然そこに行きつくのである。(『沖縄人の沖縄―物喫ゆすど吾お主―』126頁)
右の文章に明らかにみられるように、山里永吉にとって「文化」は「芸術」とほぼ等しいものとしてとらえられるものである。したがって先にふれたように、薩摩の「武力」が薩摩の文化の質や水準の現われたものという視点は、そこからは出てこない。そしてそこに、薩摩支配下の琉球の文化について、ひいてはその時期についての歴史認識の独自性が現われているのである。
この山里永吉の独自な視点は、たとえば向象賢(羽地朝秀)の評価にもうかがうことができる。山里永吉は、羽地朝秀の事績について、『沖縄歴史物語』を始め、『壺中天地』『沖縄人の沖縄』(第一法規版)等で繰り返しとりあげている。が、その評価はそれほど高くない。政治家としての羽地についての事績はそれほど言及されず、「日琉同祖論」の提起者として、「綱紀粛清」をとなえ人心の振興を図ったこと、「羽地仕置」を出したこと等についてふれるだけである。しかも、「羽地仕置」についても、「仕置」の政治や経済にかかわる他の条々については全くふれず、「学問之事」以下、日本的な学問や芸に熟達することを奨励したくだりにふれるばかりである。そして、そういう事績とほぼ同じ比重でもって「綱紀粛清」でもって田場賢忠(湛水親方・琉球音楽の湛水流の始祖)の公職追放事件をとりあげる。そのうえで、「羽地は、日本芸能に心酔するあまり、自国の郷土芸能をむしろ嫌悪していたのではあるまいか。つまり、羽地は彼の政治的理念とも言える、日琉同祖論によって、人心をその方へ誘致するのに急で、たとえば、大正時代の沖縄県庁が、教育の指針とした標準語奨励、方言追放のごとく、郷土的なもの、あるいは琉球固有の芸能に対して、かえって反感をもっていたのではあるまいか」(『沖縄歴史物語』1九三頁)と評するのである。この対比の仕方はきわめて単純といえば、単純であるが、つまり、そのような対比の仕方に、逆に山里永吉の文化論的な立場や歴史認識の独特な性格が現われているといえるのである。
山里永吉の『沖縄歴史物語』をはじめ、多くの歴史に関する著述が、その大半を工芸や芸能・文学・音楽等についやされるのは、そういう独特な視点によるものであるといえよう。
その山里永吉の独特な視点は、薩摩の掣肘下にありながら18世紀の琉球が、何故固有の文化を育てあげたか、というその理由の把え方についてもうかがうことができる。先に指摘したように、山里永吉の文化論は、文化を芸術とほとんど同様なものとしてとらえているところに特徴があり、だからこそ「自由」がなければ文化は隆盛にむかうことはないという認識がでてくる。そこから山里永吉は、薩摩の圧政下にあって政治的、経済的には「自由」はなかったが、琉球は中国との関係でもって半ば独立国としての体面は保っていて、そこに「薩摩も容喙できぬ」「自由」が残されていた、そしてそこに沖縄の文化が華ひらく余地があったとするのである。たとえば組踊りについて「御冠船踊りという国家的行事が、なにごとにつけても政治的自由をもっていなかった琉球王府をして、自由奔放に、どこからの拘束を受けることなく、思いのままの公演ができたということで、こればかりは国王即位の一世一代、琉球人にゆるされた、ただひとつの自由による文化的所産であった(略)つまり、冊封に関するあらゆる式典、およびそれに付随する行事については、薩摩はまったく何の干渉も指図もできなかった」(『沖縄人の沖縄』第一法規版・126頁)というように考えているのである。
このような文化論から「いったん他国の攻略を受け、他国の支配下に呻吟するようになると、文化は低調となり、独立自営の精神はぜんじ稀薄になって、依頼心ばかり濃厚になり、あらゆる面に劣等感をもつ、優柔不断な民族性に堕落していく」という評価が導き出されるのは、必至である。
この歴史認識はそれだけとりだしてみれば至極当り前のようにみえるけれども、その立場で過去の歴史をとらえかえすとき、往々にして、すぐれた文化=芸術の有無によってその時代の自由の有無を論証することになり、そのことによって独立か非独立かを結論づけることになる。事実、山里永吉の独立論はそのような論理構造をとっているのである。したがって、その認識のありかたに対して、抑圧下においてもすぐれた文化=芸術は生れうるという視点がみられない、とか、文化=芸術の問題が国家の問題と無媒介に結びついている、など多くの批判が出てくることは避けられないこととなろう。
しかし、文化=芸術における自由の問題をすべてに優先して考える一種の文化=芸術至上主義の立場にたつ山里永吉にとって、そのような歴史認識にたどりつくのはいわば必至であった。薩摩の抑圧下にありながら、何故あれだけすぐれた文化=芸術が生れえたのかという疑問は、そのように考えないかぎり解決つかない問題であったに違いないからである。
したがって、山里永吉の独立論の問題は、いかにしてすぐれた固有の文化を保持するかという問題に帰着することになり、問題の根は、彼の文化=芸術観にひそんでいるということになる。
四
以上、山里永吉の独特な歴史認識とそれにもとづく独立論がその文化=芸術観に由来することにふれたが、その文化=芸術観の特質や、それがどのように形成されたかということについては、いまのところ明らかではない。ここでは、簡単にその経歴をたどりながら、その形成の過程を瞥見するにとどめたい。
山里永吉は、明治35年那覇の上之蔵に生をうけている。父永昌は、漆器店の経営を行うかたわら、安富祖流の音楽家であった。(『壺中天地』)。従って幼少から沖縄の音楽と工芸に親しんでいたことになる。小学生の頃、伊波普哲(月城の息子)、金城朝永らと親しく、伊波普猷主宰の子供会に参加した。一方、山之口貘の兄重啓にあい絵画に興味を抱くようになったという。一中在学中、絵画のグループ「丹生協会」「ふたば会」に参加、絵画に専念、そのため落第し五年生の時には退学している。伊波普猷の組合教会が結成されると毎週のように通ったという(「壺中の日月」『サンデー沖縄』125号)。大正12年春、絵画の道に進むため上京、日本美術学校に編入し、そこで田河水泡と親交を結び、彼を通して村山知義を知って村山のダダイズム芸術論の影響を受け、村山の「マヴオ」に参加、昭和二年父の死により帰郷、帰郷後は山城正忠らの「珊瑚礁」に同人として参加、昭和四年沖縄芝居とのつながりが出来て脚本執筆の依頼をうけ、「一向宗法難記」以下の脚本、を書くようになる。昭和9年から11年にかけては那覇市立商業学校で絵の専科教師をつとめながら新聞小説を執筆する。昭和12年『月刊琉球』を刊行し、その縁で尚順を知り多大の影響をうける。さらに、尚順とのつながりから柳宗悦、河合寛二郎を知る。戦中は京都に疎開、戦後は琉球政府文化部を経て博物館に移り、博物館長、文化財保護委員をつとめる一方、新聞小説を執筆したり絵画を発表したりしている。(以上『壺中の日月』「サンデー沖縄」連載及び『私の戦後史』第二集 沖縄タイムス刊参照)。
以上、簡単に経歴を述べたが、ここで注目されるのは、伊波普猷や尚順の影響によって沖縄の文化について目を開き、深い愛着をいだいたということである。伊波の影響について、恩納ナベの歌を伊波から学んだことをあげ、「考えると、私が自国琉球の古い文化の高さを見直すようになったのは、おそらくそれが最初ではなかっただろうか」(『サンデー沖縄』昭和48年6月9日)と述べている。また陶業その他沖縄の文化について尚順からいかに多くを学んだかは「尚順男爵と私」(『松山王子尚順遺稿』)で詳細に述べているところである。
さらに、この経歴で目をひくのに、山里永吉が村山らのダダイズム芸術論の影響を受けながらも、結局は、沖縄にこだわり続けそれから離れることはできなかったということがある。村山知義は、大正十二年ドイツから帰国すると、「意識的構成主義」を唱え、その理論に基づいて、柳瀬正夢らと、「前衛芸術団体マヴオ」を結成、機関誌「MAVO」を刊行している。山里の作品もその誌面を飾ることになるが、この時期すでに有力な同人であった柳瀬正夢はマルキシズムに接近、村山知義も大正14年には日本プロレタリア文芸連盟に参加するようになっている。同じグループに属しながら山里はついに左傾化することなく沖縄に帰るのである。
大正末から昭和にかけての日本の芸術理論では、ダダイズム・アナーキズムからはプロレタリア芸術へ移行するというのが一般的な傾向としてあったが、山里永吉の場合はそういう動きを示していない。
その理由の一つとして、当時のダダイズム芸術論が(村山の意識的構成主義を含めて)既成の芸術の形式を破壊する方向を打ち出しても、破壊したのち、どのような方向で再構築するかという方向性はもっていなかったということをあげることができる。そのことが、山里に、「ダダの虚無をくぐりぬけてきた結果、芸術に新旧の差別をつけること自体がナンセンスであり、アブストラクトなどひとつの流行にすぎず、つまり芸術に絶対があるはずがなく、表現手段の新旧など一世紀もたてば区別がつかなくなる」(『サンデー沖縄』131号)という信念をいだくにとどまらせたのである。
山里永吉がダダイズムを一種のニヒリズム的観点で把握していたことをこの発言は示しているわけであるが、この観点は村山の意識的構成主義の理論に既に含まれているものでもあった。そして、山里永吉にとって、こういうダダイズムの影響は、彼を〝近代〟へむかわせるのではなく、却って沖縄の文化にこだわる契機となっているようにみえる。言葉をかえていえば、「近代」を真の意味で自らの問題としてつきつめる以前に、「近代」の理念を否定するダダの理論に接したことによって、山里永吉は逆に沖縄に向うことになったのである。
昭和2年、左傾化するマヴオ同人たちと別れて沖縄に帰った山里永吉は、「一向宗法難記」以下、沖縄の歴史に取材した戯曲を書き始める。が、この時期の作品に共通する特色は、廃藩置県によって琉球国が崩壊していく過程に取材していることであり、その崩壊する世界に対する限りない愛惜の思いであった。それは、薩摩の圧制下にありながら、なお不完全ながらも独自の文化をもった独立国としてあった琉球が、完全にその独立性を喪っていくという認識に支えられているといってよい。つまり前に述べた山里永吉の独特の歴史認識はすでにこの時点で成立しているのであり、松山王子尚順との出合いや、柳宗悦との出合いは、山里永吉のそのような歴史認識を強める役割を果たしたものと考えられる。
マヴオとのかかわりから、この尚順との出会いに至る時期の山里永吉については、もっと詳細にふれるべきであろうが、これについては別の機会にとりあげることとして、ここでは、山里永吉の独特な歴史認識が、マヴオから離れて帰郷し戯曲を執筆する昭和の初期にすでにきざしていたことを指摘するだけにとどめたい。
(1982・8・10/おかもと けいとく・琉球大学教授)
このページのトップにもどる