| Toppage | Critic | �k�b��(BBS) | �}���� | �����N | Emigrant |
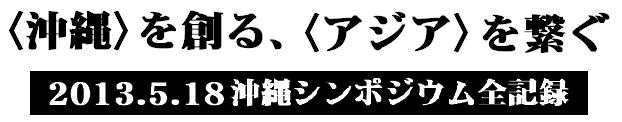

���V���|�W�E���o�Ȏҁi�������B�h�̗��j��
�@�@���ǎ��q�i������@���Ƃ��j�@�@�c�c�ߔe�s�c��c���B����Љ��O�}�����L���B
�@�@�������_�i�Ȃ����Ɓ@�Ƃ��Ђ�j�c�c����^�C���X�Ў�����E�_���ψ���
�@�@���@�ߌ��i��[�@�������j�c�c����c��w����
�@�@�ې�N�j�i�܂邩��@�Ă��j�@�c�c������w����
�@�@��c�Òj�i�������@�������j�@�@�c�c���d�R���y�j��
�@�@�����@���i�Ȃ����Ɓ@�������j�@�c�c�f����]��
�@�@�얞�M��i����݂@�����j�c�c���l�B�l���w�J�I�X�̖e�x��ɁB
�@�u�}�~�́v�u�����̋��Ёv�u���זh�q�v�u�ŗL�̗̓y�v�L�̗̓y�v�u�匠�̓��v�ȂǂȂǁA����̌o����u������ɂ��āA�E�܂�����ь�����a�ȃR�g�o�����B
�@���܁A���A�W�A�̗̓y��̊C���߂���ْ���ʂ��āA�匠�A�����Ƃ����ߑ�̘g�g�݂����{����₢������悤�Ƃ��Ă���B
�@�T���t�����V�X�R�u�a���U�O�{�P�N�\ ����͕�������A�A�����J�̂ނ������̓������ɂ����ꂽ�B
�@����A���{�̐��Љ�̓A�����J�̎P�̂��ƂŁu����v�Ɓu�o�ϐ����v�𐋂����B���Ɏ����̐�オ����B
�@�����āA�u���A�v�S�O�{�P�N�\ �ɓ��̌R���I�ȗv�Ƃ��Ẳ���̈ʒu�͕ς邱�ƂȂ��A���Ă̌R���ĕ҂ɂ��炳��Ă���B
�@���A�W�A�̕��f�̋N�������������A�V���ȁq�P �r�ɂ��邱�Ƃ͂ł���̂��B�I���Ȃ���̂ƐA���n��`����n�܂�̃A�W�A�ցA���j�ӎ��̐[�w�̔��������J���A�q����r��n��A�q�A�W�A�r�Ɍq���v�z�͐��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������ꂩ��B
�@���ǎ��q�i�����i��j�@��N�́u���A�v40�N�A�T���t�����V�X�R�u�a���60�N�̐ߖڂ̔N�ł����B����ɂƂ��Ă��̈�N�́A�l�X�Ȃ��Ƃ��₢�������A���̂悤�Ȉ�N�������Ǝv���܂��B�I�X�v���C�z���ɂ��ẮA�����̈ӎv����ɂȂ�Ƃ����V���Ȑ��������܂�A�������s���A����̈�̎��Ȍ��茠�̏Ƃ��āA�u�I�X�v���C�m�[�v�A�u�����ڐݔ��v�M���܂����B�������A�����S���������āA�I�X�v���C�z���͋��s���ꂽ�B�܂��A�Ӗ�ÂɐV���ȕČR��n�����݂��悤�Ƃ��Ă���B�u�����ڐݔ��v�������Ă��������}�̍���c�����ǂ�ǂ�������Ă���B�܂��k���N�́u�~�T�C���̋��Ёv�������ɂo�`�b�R������ɋ��s�z������B�����ĂS�E28�́u�匠�̓��v���T�B�����������̂��Ƃ͉���ɑ��Ăǂ̂悤�ȃ��b�Z�[�W�Ȃ̂��B�����Ă܂����߂Ō����A�������s���́u�Ԉ��w�v�e�F�����B���邢�́A�킴�킴����̊�n�����@�ɗ������ŁA�C�����Ɂu�����Ɗ��p�v��i������悤�Ȃ��Ƃ��������B���̔w�i�ɂ́A����Ɋ�n�����邱�Ƃ����R�ł��邩�̂悤�ȁA���������O����B�����č��A�Q�c�@�I���̒��O�ł͂���܂����A�}���Ɉ��{���������@�����Ɍ������Ă���B���Ƃ����z���Ă���u�}�~�́v��u�������И_�v�A�u���זh�q�v�A�u�ŗL�̗̓y�v���X�̌��t�ŁA��������ł����B�����Ől�������Ă���Ƃ������Ƃ����āA��������ł����B
�@���̂悤�ȏŁA�������ɉ����ł���̂��B�A�W�A�ƌq�����āA���ꂪ���ꂩ��u60�N�v���X�P�N�v���ǂ������Ă����̂��B�n���Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A�݂Ȃ���Ƌ��ɍl���Ă��������B���̊�@�I�ȃA�W�A�̏A����̏̒��ŁA�V�����������\�z���Ă�����̂��B���ꂼ��̎��Ȍ��茠�d���Ă�����悤�ȁA�A�W�A��n���Ă�����̂��B���̂��Ƃ��l�������Ǝv���܂��B
�@����ł̓R�[�f�B�l�[�^�[�̒������_����Ƀ}�C�N��n�������Ǝv���܂��B��������͉���^�C���X������E�_���ψ����Ƃ��āA�A�W�A�̎��_���牫��̌�����������A�_���Ă��܂��B
�@�������_�i�R�[�f�B�l�[�^�[�j�@���ɂ�����ɂȂ������A�܂����̉��f�������ēx�̂��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��قǃp�l���X�g�̗��搶�ƎG�k�����Ă��܂�����A����܂Ō������ň�Ԍ|�p�I�ȉ��f�����Ƃ���������Ă��܂����B���̉��f���ɂ��āA�����t�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł����A�����Đ��������������Ă��������܂��B�l�����ɗ��ď��߂Č����̂ł����A�^�ɃT���O���X���`����Ă��āA�T���O���X�Ɂu�d�`�r�s�@�`�r�h�`�v�Ɓu�n�j�h�m�`�v�`�v�̕��������Ԃ��ɉf���Ă���A���̍��E�Ɂu40�{�P�v�u60�{�P�v�Ƃ���܂��B��N���T���t�����V�X�R�u�a���60�N�Ƃ����ߖڂ̔N�ł����B�܂�1972�N�́u���A�v���炿�傤��40�N�ɂ�����܂����B�����č��N���u�{�P�v�N�ڂɓ�����܂��B�������������ɁA���A�W�A�̂��Ƃ��l���Ă݂悤�Ƃ������Ƃł����A���̃T���O���X����̂Ȃ�Ȃ̂��B����삵�Ă������������͉���ł͒����ȉ�ƁA�A�[�`�X�g�ł��B���̕����T���O���X�������Ă���̂ŁA���̃T���O���X���Ƃ��v���܂����i���j�A��������Ȃ��āA�}�b�J�[�T�[���g���Ă����T���O���X��������܂���B���̂��Ƃɂ��ẮA���ƂŖ{�l�Ɋm�F�������Ǝv���܂��B���̉��f���ƁA�e�p�l���[�̖��O�����Ȃ�B�M�ȕ����ŏ����ꂽ���́A�^��u�ׂ���ł��B�i����j
�@���肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ���̓I�ȋc�_�ɓ����Ă����܂��B���傤�̃V���|�̎�|�ɂ��ẮA��قǕ��ǂ������������܂����B����������ĕt�����������̂ł����A����܂ʼn�X������̒��ŁA���ɂ��̐��N�ԁA��n�������ꍇ�ɂ́A�ЂƂ̌����A�A�v���[�`�̎d��������܂����B��͊C�����̋@�\�Ƃ������͂ǂ�Ȃ��̂ł��邩�B���邢�͓��{���{�����̐���ߒ��B�ǂ������`�Ő����肳��A�������Ȃ̂��B���邢�͓��Ĉ��ۂ̂��肩���A�u���ۃ����v�Ƃ������̗��v�����̖̂��Ƃ��B������������ʼn���̊�n����_���邱�Ƃ����������B���̒��ŁA�u�}�~�́v�Ƃ��A�u�n���I�D�ʐ��v�Ƃ����T�O���A����܂Ő�`����Ă��������͂邩��凋C�O�̂悤�ȁA�Ǝ�ȁA�܂肻����g�������ǂ��ɂł��ł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����Ȃ��Ƃ����̊Ԃ̋c�_�̒��ŁA�����Ԗ��炩�ɂȂ����B
�@���傤�́A���������b�Ƃ͑S���Ⴄ�A�v���[�`�̎d�����������B����́A���A�W�A�Ƃ����t�@�N�^�[���d�����āA���A�W�A�̗��j�A���A�W�A�̗�풁���A�����̑䓪�A�������猩���Ƃ��ɉ���̊�n���͂ǂ��������Ɍ�����̂��B���邢�͉���̊�n��肩�瓌�A�W�A�������Ƃ��ɁA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��B���������傤�̋c�_�̒��S�ɂ������B
�@���̋c�_�ɑ������������l���A���Ăт��Ă��܂��B
�@�܂��A���ߌ��i���[�E�W�����E�H���j����ł��B������͗�����w�ŋ����Ă��炵�āA���N���瑁��c��w�̋����ɂȂ��Ă��܂��B�m�g�j�̒��̓��_�ԑg�ɂ悭�o����̂ł����m�̕��������Ǝv���܂��B���傤�͎l���̕��̒��������ꂼ���_�����Љ�܂��B�������1953�N�Ɋ؍��ł����܂�ɂȂ�A������w��w�@�Ŋw���Ƃ��̖{���o����܂����B1996�N�́w���A�W�A���Ɗؕē��W�x�i����o�ʼn�j�ł��B���̖{�͍��ې����w��ł͖����Ƃ��Ēm���A�啽���F�L�O�܁A�A�����J�w������܁A�č����j�Ƌ��c��O���꒘��܂���܂��Ă��܂��B���̌�����N�����̍��ې�������������Ă��܂��B
�@���̂��ׂ�������w�����̊ې�N�j����ł��B�ې삳��́A���傤�Ǘ������10�ΈႢ�ŁA1963�N�ɘa�̎R�ł����܂�ɂȂ��Ă��܂��B�ꋴ��w��w�@���o���āA��p���w�Ɠ��A�W�A�����_�����ŁA���ɂ�������̒������o����Ă��܂��B��������A��g���X����2003�N�ɏo���ꂽ�w���[�W���i���Y���x�����Љ�܂��B���̖{�̒��Ŋې삳��́u���A�W�A�̗��\���̒��ŁA���{�͂��̍őO���ł͂Ȃ��A������������Ƃ���ŁA������a�E��������`�����Ă����B�v�Ǝw�E����Ă��܂��B���̖{�̍Ō�Ɋ�{�����ē�������܂��āA���̒��ŁA������̘_�������܂��Ă��܂��āA�l�I�ɂ�����Ȏh�������A�Ə����Ă��܂��B
�@���ׂ̗���c�Òj����A����������ł��B����l�́A���ʂ̒m�I�o�b�N�O�����h�������Ă�������Ⴂ�܂��B��c����͔��d�R�Ƃ������Ő��܂�āA�����֏o���āA���͔��d�R�ɂ܂��߂��Ċ��Ă��܂��B��������������悤�ɑ哌���Ƃ������Ő��܂�āA�����̑�w���o�āA�����ĉ���̒n���ɖ߂��Ċ���Ă���B��c����̒����Ƃ��āA�w���d�R�̐푈�x�i1996�N��R�Ɂj�����Љ�܂��B����͓��{�n�����������y�����܁A����^�C���X�o�ŕ����܂���܂��Ă��܂��B���d�R�̐푈��Ղ��t�B�[���h���[�N���āA��ύ����ɋL�^����Ă��܂��B�ŋ߂ł͔��d�R���������܂���܂���Ă��܂��B�w�Ƃ���[�܂̐��E�x�Ƃ����b�c�t�̖{���o�ł���Ă��܂��B�Ō�ɉE�[�̕��A�f����]�Ƃ̒���������ł��B1947�N�ɓ�哌���Ő��܂�A�����̒����������]�Ƃł����A���̒�����A�w�߂���������с`����E��������A���n��`�x�i2012�N�����Ёj���Љ�܂��B�{�̑тɂ́A�u����̌����V�[���̐[�w������قNj��͂ɂ�����o���𖾂����E�`�i�[���`�����g�ɂ���]�͂���܂ő��݂��Ȃ������v�Ƃ���܂��B
�@���ꂼ�ꕪ�����U���قȂ�l�l�ł����A���傤�̃e�[�}�ɊS�������Ĕ������Ă���ꂽ���X�ł��B����ł͂܂�������20������N���Ă������������Ǝv���܂��B
����P�F���A�W�A�̒��ōl������{��A�W�A�E���N����
�@���@�ߌ��@ ���̉��ɓ����Ă��āA���f����q�����āA�����ɐZ���Ă���Ƃ���ł��B�T���O���X�Ɣ��]���������A���̈Ӗ��͂Ȃ낤�ƍl���Ă��܂����B�����҂Ƃ����͉̂��ł��܂�������T�����Ƃ���B�����ē����炵�����̂������āu���ꂪ�������v�Ƃ����̂ł����A�|�p�Ƃ����̂͂���ȊȒP�ɓ����͏o�Ȃ��B��߂����A�d�|���̂����i���Ǝv���܂��B
�@�����g��30�N�O�ɓ��{�ɗ��܂����B�A�����J�̃A�W�A�������{�ɂ��Ȃ���A���̒��ł̊؍��E���{�̊W������Ă��܂����B���{�̒��ł����Ɨ}�����Ă�����肪��C�ɕ��o����悤�ȁA�������������ɗ��Ă���B�傫�ȓ]���_���낤�A���������v���������Ȃ���A����������J��Ԃ����b������܂�������̊�n�����A���ژ_����Ƃ��������A������ƉI��悤�Ɏv���邩������܂��A���̓_�͂������������������Ǝv���܂��B
�@�S��28���A���{���{�������I�Ȉʒu�Â��m�ɂ������ƂŁA�u����ɂƂ��Ă̂S�E28�̈Ӗ��v���l���邫�������ɂȂ����B�����o�������ǂ������p�x���猩�邩�ňقȂ��Ă���̂́A���R�̂��Ƃł��B�{�y�ɂ����Ă�����Ƃ̊W���l������Ȃ��B�����ɂ���Ӗ��ł͐ϋɓI�ȈӖ��������A���������邾�낤�B
�@����1982�N�ɗ��w�̂��߂ɓ��{�ɗ��܂����B�����ĎO��s�Ő��������Ȃ���A���{�͂��������Ǝv���܂����B�؍��͑S�l�������̎���ł����B�l���E���ꂽ��A�x�@�ƌR�̃v���[���X�����ɍ����Љ�ł����B�X������Ă��Čx�@������ƁA�ǂ������Ă��������܂��l�����B�������������R�̂悤�ɑ����Ă����B�؍����痯�w�ɗ������ɂƂ��ẮA���{�̌x�@�́u���܂�肳��v�Ƃ����A���������Ă����l�Ƃ����C���[�W�ŁA�������{�Ɗ؍��͈Ⴄ�ȂƊ������肵�Ă��܂����B�������A���{�̌x�@���ʂ̏�ʂł͕ʂ̊炪�������̂��Ǝv���܂����A���Ȃ��Ƃ������̊؍��Ɣ�r����ƁA���{�͂ƂĂ����a���ȂƎv�����B
�@���̂��Ƃ��A���ɂƂ��āA���ƂƂ͉������l���邫�������ɂȂ�܂����B�ŋ߂����ԕς���Ă��܂������A����30�N�O�ɓ��{�ɗ������ɂ́A�u���Ɓv�Ƃ��u�����v�Ƃ��u�����v�Ƃ������t�́A���{�̑�w�̋����ł��A����ȂɑO�ʂɏo�Ȃ������B�����̊؍��ł́A���{���ł��낤���A�����{�ł��낤���A�u���Ɓv�u�����v�u�����v�̌��t�͓��R�̂��Ƃ̂悤�Ɏg���Ă����B�����g�������҂��Ǝv���Ă��܂������A���{�ɂ��Ă���͂��܂�g��Ȃ��Ȃ����B�����̏a�J�ŋv���Ԃ�Ɂu�����v�̕������������̂́A���{�����}�̃|�X�^�[�ł����B�����ɓ��{�́u�����v���������i���j�B�����ɑN���Ɋo���Ă��܂��B���̌�A�؍��ł́u�����v������g��Ȃ��Ȃ����B����Ɠ���ւ�邩�̂悤�ɁA���{�̖{�y�ŁA�u�����v�u���Ɓv���ȑO���͑����Ă��Ă���B���̋t�]���ۂ��A���낢��Ȍ`�ŏo�Ă��܂����A�؍��̎q�ǂ��̓L���`�����܂�H�ׂȂ��̂ɁA���{�̎q�ǂ��͑�D���Ƃ��i���j�B������L���`�͓��{�̂��̂ɂȂ��Ă��������m��Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B���̂悤�Ɂu���Ɓv�u�����v�u�����v�Ƃ����̂�����ւ�낤�Ƃ��Ă���B������w��I�ɂ��ǂ��ʒu�Â��悤���ƍl���Ă���Ƃ���ł��B
�@�F�X�ȈӖ��Łu�����{�v�́u��O���{�v�Ƃ͈Ⴄ�B�P�Ȃ鎞��敪�ł͂Ȃ��āA�V���������o�ώЉ���܂�ł���u�����{�v�A���̒��ɉ���͊܂܂�Ă���̂��B�܂�2006�N�̑�ꎟ���{�����̎��ɂ́A�u��ヌ�W���[������̒E�p�v�������ɌJ��Ԃ�������ꂽ�B�u�����{�v�̒��ɂ́A�]�����ׂ����̂Ƃł��Ȃ����̂�����̂ł͂Ȃ����B�u�����{�v�̕]�����ׂ����̂W�����Ă����A�u�����{�̔��W�I�����v�Ƃ����̂͂���̂ł͂Ȃ����B�u�����{�v���ǂ��l���A�������Ă����̂��A���ꂪ�傫�ȃe�[�}���Ǝv���B
�@�u���a���ƁE���{�v�Ƃ����̂̓J�M�������Ŏg�킴��Ȃ����A�u���a���@�v�ɏW�������{�̒~�ρA���т́A�|�W�e�B�u�ɕ]�����ׂ����̂��낤�B���a���@������A�u�����t����ꂽ�v�Ƃ����������ŋߐ���ɔ�ь����Ă��邪�A���ۘA�����̂��̂́A���Ƃ�����ɐ푈���Ă͂����Ȃ��Ƃ����A�����������O�̏�ɗ����Ă���B������͌`�[�����Ă��܂������Ă��܂��A���ۘA����������p�������A���͂̎�|�́A�������̌���̒��ŁA���q�̂��߂̍Œ���̌R���s���͂��ꂼ���炴��Ȃ��B�������푈�Ƃ������͍̂��Ƃ�����ɂ��Ă͂����Ȃ��B���ꂪ�O��ɂȂ��Ă���B���������ӂ��ɍl����ƁA���{�̌��@�͗�O�ł��Ȃ���A���A�Ƃ����̂͂����������E�����o����ŁA���̔��Ȃ��琶�܂ꂽ�B�l�ނ��Nj����ׂ����O�̂��������ł���ƍl����ƁA���@����̗��j�I�ȈӖ��͔��ɑ傫���B���̂������������āA���{�̓A�W�A�̐��̕����Œ��ڊ������܂�邱�Ƃ͂Ȃ������B����͑傫���ւ��ėǂ����Ƃł͂Ȃ����B
�@���������́u���a���ƁE���{�v�̌��̗��ʂ́A���ē����ł���A���Ĉ��ۂ�����B���̈Ӗ��ł́A���{�͕��a���ƂƂ��������u��n���Ɓv�ł���A�A�W�A�̗��A�M��ɂ��A���낢��Ȍ`�Ŋւ���Ă���B���ꂾ���ł͂Ȃ��āA��������l�X�ȗ��v�Ă��Ă���B���̂悤�ȕ��̕��������R���邪�A���̗��ʂ����Ȃ���A�����{�̐����������B���́A�|�W�e�B�u�ɕ]�����A������ǂ̂悤�ɒn��I�ɂȂ��Ă����̂��A������l����ׂ��B�l�X�Ȉӌ����o�āA�������������Ă���̂����݂̓��{�̐����ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@��قǂ��Љ�����������̒����́A1950�N��̃A�����J�̃A�W�A�O���̒��ł̊E���W��T����̂ł����B���̎��Ɏ�����ǂ݂Ȃ��犴�������Ƃ�����B�A�����J�̃A�W�A����̒��ŁA���{�Ɗ؍����n��I�ȕ��Ƒ̐��ɑg�ݍ��܂�Ă����B���N�푈�̎��ɁA�A�����J�͓��{�������ƕ��������悤�Ƃ����B���{�̌R���͂����p���悤�Ƃ����B�������g�c�́A�R�����ƂɂȂ邱�Ƃ͔ނȂ�ɂ͒�R���āA���q���̑O�g�g�D�����������ǂ��A�{�i�I�ȌR�����͒�R���Ȃ���A�u�y�����E�o�Ϗd���v�H����W�J�����B���{�͋���ȌR�����S��w���킸�ɉ���ł��A�o�ς̕����ɗ͂𒍂����Ƃ��ł����B
�@�ڂN�����A�؍��A��p�ɓ]����ƁA���������ɏd�����̌R�����ƂɂȂ��Ă����B���{�ł�1957�N�ɁA���N�푈�ƂƂ��ɐݒu���ꂽ���A�R�i�ߕ�����������\�E���ֈړ]���A�ݓ��ČR�̓P�ށE�ړ��������o���B���{�̖{�y�Ɏc�������Ƃ����ČR�̈ӌ����������̂ł����A�{�y�Ŕ���n�^�����������Ȃ�A�j���������n��R����{�{�y�ɂ͒u���Ȃ��Ȃ����B���̖{�y�̔���n�^���̃v���b�V���[���āA�ČR�̎i�ߕ����؍��Ɉڂ��A�C���t�c������Ɏ����Ă���B���{�̖{�y�ɂ͒n��R�̐퓬�����͎c��Ȃ��B���{�̕��a�^���̐��ʂƂ��Ēn��R�͎c��Ȃ��������A���̑���Ɋ؍��Ɖ���̕ČR�͋������ꂽ�B����͂܂��ɕč����S�̃A�W�A�̐�㒁���̒��ł̓��{�Ɗ؍��̖������S������A����Ƒ�p�������悤�Ȗ�����S�킳�ꂽ�B�؍��E��p�E���ꂪ�A�O�����ƁE�O���n��ƂȂ����B�܂��ɂ��̂悤�Ȓn��I�ȍ\�}���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���_��O�|�����Đ\���グ��ƁA�؍����������풁���̍őO���Ɉʒu�������ƂŁA����ȕ��S��w���킴��Ȃ������B���̗�풁����ς��邽�߂ɂ́A���n�ł̗l�X�Ȏ��g�݂��������K�v�ł����A�����ʂ��āA�n�悻�̂��̂�Η����狦����ւ��Ă����K�v������B�u�n���n��v���Ƃ��j�S�ƂȂ�B
�@�����̃V���|�̃^�C�g���́u�q����r��n��@�q�A�W�A�r���q���v�ł����A��������̒��ɂ��铌�A�W�A���ǂ��q���āA�n���Ă����̂��B��p�ł��嗤�Ƃ̊W�ł��������w�͂����Ă��܂����A�؍��ł����̂悤�Ȗ͍�������Ă���B����ł����̂悤�Ȕ��z���K�v�ł͂Ȃ����B
�@��퉺�̐푈������A���Y��`�̋��Ђ�����A�ۉ��Ȃ��ɃA�����J���S�̌R���Ɉˑ����钁�����`�����ꂽ�B�A�����J�̊֗^�����̂悤�ȗ�풁����K�R�������Ƃ����������ł��܂����A�f�E�����f�X�^�b�h�̌��t�����A�u���҂��ꂽ�鍑�v�A�����������č����������ꂽ�ʂ�����܂��B�n��̎w���҂����{��`�������`�����悤�Ƃ��ăA�����J���������ꂽ�B���B���A�W�A�Ɠ����悤�ɁA�A�����J�̌R���͂Ɉˑ�����悤�ȏ����ꂽ�B�������A���B�́A���l����Ɣ��ɂ��������ȒE���O����W�J�����B�\�A�̋��ЂɑR���A����̕����𐬂������邽�߂ɁA�A�����J�̗͂��t���ɗ��p���āA���̑Η��ɂ�����������Ă����킯�ł͂Ȃ��āA��������z���邽�߂̓w�͂������B�܂��͏]���̃i�V���i���Y���𐼉������ł������Ă������Ƃ������ƂŁA�d�t���ł����B���ꂾ���ł͂Ȃ��āA�����ɂ܂Ŏ��L�����B�܂����h�C�c���A���������ł��o���u�ڋ߂ɂ��ω��v�Ƃ����X���[�K�����f�����B���ꂪ�S���F�ɍL����A1975�N�̉��B���S�ۏዦ�͉�c�b�r�b�d�̑n�݂ɂȂ������B����10�N�ȏ�̒~�ς��o�āA1989�N�Ƀx�������̕ǂ����A��킪���a�I�ɁA����قǑ傫�ȍ������Ȃ��X���[�Y�ɑ̐��]���𐬂��������B
�@����͉��B������ł����ʂ�����܂����A�������玄�����͑����̋��P�邱�Ƃ��ł���B�A�����J�̗͂𗘗p���Ȃ�����A���̘g�̒��ň��Z�����̂ł͂Ȃ��A�A�����J�̘g���āA����̒n��I�ȗ��Q���m�ۂ��邱�Ƃ��ł����B����̓A�W�A�e���ɑ傫�ȋ��P��^������̂ł��B
�@���{�قǂ܂��͂͂���܂��A�O�����Ƃł���A�����R�����Ƃł������؍����A�o�ϐ����𐬂������A���剻���i�W����ɏ]���āA�O�������B�^���u������悤�ɂȂ����B�k���N�ɑ��ėZ�a�I�Ȑ�������ƁA���{�̃��f�B�A�́u���h�����v������������܂����A����͋��咆�����Aḕ��鐭���Ɍ��炸�A�k���ɖڂ������A�k�ւ̊֗^������ŏ��ɐi�߂��̂́A�R�l�o�g��ḑ𐭌��ł����B�؍����őO���̑O�����ƂƂ��Ă̕��S���y������̂ɁA���\�����̂��̂�ς��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���A�k���N��V�A�ɖڂ������A�k���O����i�߁A�k���A�W�A�̈��S�ۏዦ�͋@�\������B�O�����Ƃł���؍����A��킪�����ƍ������͑Η����������Ȃ�B���̑Η��������ɕς���ƁA�������͌𗬂̋��_�ɂȂ�B����ȗ��؍��ł́A�������ς���Ă��A����E���Ɏ����Ă������ƂŁA���N������Η��̍őO���ł͂Ȃ��āA�k���A�W�A�̌𗬂̋��_�ɂȂ肽���B���ꂪ�ێ�v�V�A�E�����Ȃ��؍��̈�т�������̗��ꂾ�Ǝv���܂��B���݂̖p�یb�������Z�ҋ��c���g�債���u�\�E���v���Z�X�v�̍\�z���f���A�ĊA�Ē��̘A�g��͍����Ă���B
�@�����̑䓪�̒��ŁA���A�W�A�́u�V���v���}���Ă���B������A�P�ɋ��ЂɑΏ�����A������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�����悤�Ɋ֗^���Ă����B���Ђ��̂��̂��V�X�e���̒��Ɏ�荞��ł����Ƃ������z���K�v�ł��B���́u�V���v�̒��ł̓��{�̈��S�ۏ���l�����Ƃ��ɂ́A�����K�v�Ȃ̂��B��������ƍ��h�R�̑n�݂��œ_�����悤�Ƃ��Ă��邪�A����͖��炩�ɋt���B�͍̂������̂́u���h�v�ł������A�������������̂͌R�������ł͂Ȃ��B��蕝�L�����̂ŁA�u���S�ۏ�v�Ƃ����l�������o�Ă���B���Ƃ����ł͂Ȃ��A�����ɕ�炷�l�X�����S�łȂ��ƈӖ����Ȃ��B������������̒��ŁA�u���h�R�v�Ȃǂ̔��z���o�Ă���̂́A19���I�I�ŕ��ÓI�ƌ��킴��Ȃ��B
�@�����ЂƂA�̓y�ɂ��Ă��A��������V���������Ă��܂������A��t���u����̊C�v�ɂ��ꂽ�r�[�ɁA�������C�ɏo���Ȃ��B�|�����A�ْ������܂�ƁA�����ŋ������Ă��鋙���͑�������B�u�̓y�v�����L�����ōl����̂��B�ނ���u�@�\�v�ɒ��ڂ���K�v������B���L�̓[���T�������A�@�\�͕������������Ƃ��ł���B
�@�Ō�ɁA���A�W�A�Ƃ����u�n��v��n�邱�Ƃō��Ƃ�ς���B���̂��Ƃ��d�v�ł͂Ȃ����B
�@�������_�@���肪�Ƃ��������܂����B�O�����ƁE�n��Ƃ��Ă̊؍��E��p�E����Ƃ������b������܂����B�T���t�����V�X�R�u�a���60�{�P�N�ł����A���{�̕\���ɂ��A�m���ɓ��{�{�y�͎匠�����܂����B�ł����̍u�a���ɂ���āA�؍��E��p�E����Ƃ����n�悪�A���̍őO���ɒu���ꂽ�B���Ɍ�������������ꂽ�Ƃ������Ƃɂ��āA���{�̒��ŁA�S�����������̂ł͂Ȃ����B����Ɠ��{�{�y�́A�푈���I��������Ƃł������A���ʂ̍����̋L������Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��āA���ꂪ���ɔ��������Ă���B�������A�����b���ꂽ�悤�ɁA�܂��ɉ���̏ꍇ�́A���a�̔z�����Ȃ��܂܂ɁA�u�V���v���}���āA�܂��܂����������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�ł͊ې삳��ɂ��肢���܂��B
����Q�F�u��t�v�Ɓu�ދ��v�̂�������
�@�ې�N�j�@���̎��ȏЉ�̂悤�Ȃ��Ƃ���b�͂��߂܂��ƁA����1990�N����93�N�܂ŁA��p�ɎO�N�ԓ��{��u�t�Ƃ��čs���Ă��܂����B�����Œ�������o�������Ƃ��A���̒��ؐ��E�A���邢�͓��A�W�A���E�ւ̍ŏ��̐ڋ߂̎d���ł����B�����ꂪ�ł���悤�ɂȂ�ƁA���R�ɑ嗤�����̕��Ƃ�������ׂ�ł���悤�ɂȂ����B���X�̐�U�͓��{�̐�㕶�w�������̂ł����ǁB
�@���ɗ^����ꂽ�e�[�}�ł����A�u�w��t�x�Ɓw�ދ��x�̂������Łv�Ƃ������̂ł��B����͏ے��I�Ȍ������ɂȂ�܂��B�Ƃ����̂́A���͓�����ł͂Ȃ��킯�ł��B�u��t�v�Ƃ����̂́A"The Pinnacle Islands" �̈Ӗ�ł���A�p��N���ł���킯�ł��B���̃G���A�ɂ��������{�l�̗��j�L���̍����ɂ���邱�Ƃł��B��������A�������́u�ދ��v�Ƃ����̂��s�v�c�Ȍ������ŁA�t���܂ɂ���Ɓu������v�ƂȂ�܂��i���̃G���A�ŋ��J���s���Ă����{�Â̐l�X�͂��̂悤�ɌĂ�ł��������ł��j�B�����đ嗤�����ł́u�ދ����v�A��p�́u�ދ���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������������̖��O�̗��܂肠���ɗ��ӂ��Ă����K�v������A�Ƃ������Ƃł��B
�@�ŋ߁A�����̎Љ�Ȋw�@�̊w�ғ�l���A���ŁA�u�����̒n�ʂ͂��܂�����ł���v�Ƃ����l������̘_���u�w���֏��x�ƒދ�������_����v���o����A�b��ɂȂ�܂����B�����̃V���|��40�N�i�{�P�j��60�N�i�{�P�j�Ƃ������Ԏ��ŋc�_����Ƃ�����|�ɂȂ��Ă��܂����A�����E��p�̏ꍇ�ōl�����120�N�O�̏o�����\�\�����푈�O�ォ��l������Ȃ��Ǝv���܂��B��̌������ł́A�p��o�R�́u��t�v�Ƃ����T�O���g���͂��߂Ă����Ƃ������Ƃł��ˁB�����ŏے��I�Ȃ��Ƃ������܂��ƁA���݁A���ۏ��̐��Ƃ������͉̂p����O����Ƃ��ĈӖ����m��Ƃ��邱�ƂŐ��藧�������̂ł���A�Ⴆ�Γ��{�ƒ����ŏ������킷�Ƃ��ɂ��K���p��ɖ|�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ��J���ԍ��ۏ��̊�{���W�b�N�Ȃ̂ł����A��O���ɂ���Ē��߂��Ă���Ƃ����킯�ł��B�������܂����̂���܂ŁA���{�ƒ����̊ԂŌ�����ۂɂ́A������O�̌��t�Ŋm�肵�Ă����킯�ł͂Ȃ������B�Ⴆ��1895�N�̉��֏��͉���������̊����Ɗ��ꕶ�������B���݂��ɁA���������̂����Ȃ���m�F���Ă����͂��ł��B�p�ꂪ�������ꂽ�̂́A1905�N�̃|�[�c�}�X���ł��B���V�A�Ɠ��{�̐푈�����̏��ł����A�����������y�n���č����������Ƃ�����܂��B���{��ƃ��V�A��A�����čŏI�R���Ƃ��Ẳp��ŏ�����ꂽ�B���������ӂ��ɂ��āA���̓��A�W�A�n��ɂ����āA���ۏ��̐��̃��W�b�N�����X�ɓ����Ă���A���̉ߒ��Ƃ���120�N�̗��j���l������Ȃ��B�ȏ�A��w�̍u�`�ł��Ɣ��N�����N�����ĉ��������ł����A�[�܂��Ă��b�����Ă��܂��B
�@��ڂ̖��́A���͓������痈�����̂Ȃ̂ŁA�����ō��N�����Ă���V�������ۂ��������Ȃ��炨�b�����Ă��������܂��B�܂�1960�N���ۈȗ��̕��L���K�w�̐l�X������c���������͂�Ńf�����s���Ă���Ƃ����o�����ƂƂ��ɁA����̖����l������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���̏o�����Ɋւ��Ă��A���A�W�A�̒n�}���v�������ׂĔ��z�����ꍇ�ǂ��Ȃ邩�B�܂�A���A�W�A�ɂ�����ČR��n�ƌ������ǂ��Ȃ��邩�\�\���̂��Ƃ��R�E11�ȗ���N�ԍl���Ă��܂����B���|���́A�������̂̂��Ƃ̕ČR�́u�g���_�`���v�ł����B�Ċ͑������˔\������Ȃ���Ôg�̔�Вn�Ɍ������A�����ɏ㗤���A�~���������s���Ă���\�\���̉f�����}�X���f�B�A�ŗ���܂����B���̎��ɂ����������Ƃ��r�e�I�ɍl���܂����B�����A�������̂��N�������ꏊ���A�����m�݂łȂ��āA���N�����Ƃ������嗤�̑��̉��݁i��������{�C���j��������A�ǂ��Ȃ��Ă������B���̏ꍇ�ɁA�u�g���_�`���v�͂ǂ������Ӗ������̂��B�����C��ł͏�ɁA���N�����̖k�����^�[�Q�b�g�ɂ��ē����\�͑��u�����X�ƌR�����K������Ă���B�ČR�́u�g���_�`���v�Ƃ������̂̓�d�̐��i���@���ɕ����яオ���Ă����͂��ł��B
�@�����ɂ��Ă��ČR��n�ɂ��Ă��A���̓��{�̂���������肵����̑傫�ȑ��u�Ƃ��āA�A������ꂽ���̂ł��B���������̑��u�́A���{�����ł͂Ȃ��āA���A�W�A�S�̂̃G���A�̒��ő��݂��Ă���B�ł���Ȃ�A�ČR��n�͂ǂ̂悤�ɑ��݂��Ă��邩�Ƃ������ƂƁA�����͂ǂ̂悤�ɓ��A�W�A�̒��ɑ}�����ꂽ�����A��Ȃ���d�ˍ��킹�čl����K�v������Ǝv���܂��B
�@�@��̖\�͑��u�̔z�u�i���ƂłȂ��̂Ő��m�ł͂���܂���j
| �嗤 | ��p | ���{ | �؍� | �k�̋��a�� | �č� | |
| �@�@�j���� | �� | �~ | �~ | �~ | �� | �� |
| �@�@�Z�k�Z�p | �� | �~ | �� | �� | �� | �� |
| �@�@���T�C�N������ | �� | �~ | �� | �� | �~ | �~ |
| �@�@���� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
| �@�@�����A�o�\�� | �~ | �~ | �� | �� | �~ | �~ |
| �@�@�ČR��n | �~ | �~ | �� | �� | �~ |
�@���̕\������Ă݂Ă킩�����̂́A���{�Ɗ؍��͔��Ɂu�i��ł���v�Ƃ������Ƃł��B�č��ɂ���Č������ݒu����A�܂������A�o���ł���\�͂����Ɏ����Ă���B����A�嗤�ƕč��͊j����������đΓ����Ă��莗�ʂ��Ă���ƌ�����B���ʂ��Ă��郂�����g�Ƃ��āA���҂Ƃ������A�o�͉\�ł͂Ȃ����Ƃ��܂݂܂��B�����̏ꍇ�͌㔭�������ł��̂ł��ꂪ�܂��ł��Ȃ��A�������j�p�����̏����ɂ�����鎖�Ƃɂ͏��o�����Ƃ��Ă���悤�ł��B�����ĕč���1979�N�̃X���[�}�C�������i�s�l�h�j���̈ȗ��A�����̊J����������߁A�A�o���Ȃ����j�ɂȂ��Ă���B�������������Ɍ����肳���Ă���A�Ƃ������Ƃł��ˁi�܂��j�p�����̃��T�C�N�����ƁA���������ɂ�点�悤�Ƃ��ė����j�B����ɁA�ȏ�̓��k�A�W�A�̒n�}�ɖk�̋��a���i������k���N�j�����荞�����Ƃ��Ă���B���߂́A90�N��Ɏ�ɕč����狖���Z�p���^�Ƃ��Ďn�܂�A���̓��ɂ����Z�k�Z�p�ւƓ]�p�����A�j��������Ƃ��Ƃ��Ă���i�K�ł��B
�@�����ŋ����[���̂́A���̐��̈�ł����p�ł��B�j����͂Ȃ��A�Z�k�Z�p���Ȃ��āA���T�C�N���������Ȃ��B�����͂��邪�A�A�o�\�͂͂Ȃ��B�����Ă܂��ČR��n���Ȃ��B����͉����Ӗ����Ă���̂��B1979�N�Ē������̔N�ɁA�����̏����Ƃ��đ�p�̕ČR��n���P�����ꂽ�i�܂�k�����{�ɗ͂ɂ���Ă��ꂪ�ׂ��ꂽ�j�B����͎��́A���A�W�A�̗��̍\����ς����o�����ł��B�s�l�h���̂Ɠ����N�ł��B������ɂ����p�ւ̕č��̊֗^������A�č��o�R�̑�p�ɂ����錴�������Ă��ςȂ��ƂȂ�A���̂܂ܒu������ɂ��ꂽ�킯�ł��B
�@������ł����A�u�R�E11�v�̃f���ŁA�����ł͈ꖜ����l�ł������A��p�ł�10���l����20���l���f�������Ă���B��p�����A�W�A�̊j�]�����l�b�g���[�N���珙�X�ɔ����o�����Ƃ��Ă��钥��ƌ�����ł��傤�B���ꂱ���A�č��̃v���[���X���ቺ�������ʂł�����킯�ł��B����p�ł͑�ꌴ�������O�����܂ł��ғ����Ă��܂����A�s�l�h���̈ȗ��A���{���č��ɑ����đ�p�ɍ�낤�Ƃ��ė�����l�����̌��ݑ��s�̉ۂ����ɂȂ��Ă���B�Q��25���ɍs�������i�j���u���ݒ��~�̍������[�����܂��傤�v�ƌ����o���āA���ꂪ�������ɂȂ�A����̑傫�ȃf���ɔ��W�����B�����ł����ЂƂd�ˍ��킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��p�Ƒ嗤�����Ƃ̊W�ł��B2011�N�Ɏ����킳�ꂽ���݂e�s�`�i���R�f�Ջ���j�̒��Ɍ��q�͂̏����������Ă���܂��āA����͑����A����Ɋւ��đ�p�̊j�p������嗤�������������邱�Ƃ��Ƃ���A���̂悤�ȈӖ���������ł͂Ȃ����i�ڍׂ͏�����Ă��܂��j�B�܂�A�E���̓��荬�������O���[�o���[�[�V�������i�s���钆�ŁA���\�������X�ɕό`���Ă���킯�ł��B
�@���āA���̂悤�Ȃ��ƂŁA�嗤�����E��p�E���N�����E���{�E����A�e�n��ŋN�����Ă���Љ�^�����ǂ̂悤�Ɍ��т��čl����̂��\�\���̔O���ɂ���킯�ł����A�����ň�����嗤�����̃P�[�X�����グ�܂��B
�@��N�i2012�N�j�̂W������X���ɂ����āA��t�^�ދ������Ɋ֘A���đ傫�ȃf���������嗤�ŋN����܂����B�Ό��s�m���̐�t�w�����������c���t�ɂ�鍑�L���̓���������܂������A���̕\����7��7����ḍa�������̓��ł����B�����ĂX��18���̖��B���ς̓��A�����ƐÊς̑ԓx���Ƃ��Ă����������{�����D���t�ɔh�����A���ꂪ��̍��}�ƂȂ��āA�嗤�����e�n�̃f�������܂��Ă����\�\���̂悤�ȏo�������ώ@���ꂽ�킯�ł��B
�@���ꂼ��̒n��̎Љ�^�����A�����ɂ��������Ƃ��āA���ꂼ��̒n��⍑�Ƃ������Ă����\���A�����V�X�e�����Ⴄ�Ƃǂ����Ă������ŋN���Ă��錻�ۂ���������Ȃ��B�嗤�����ł͂����鍑���I���͂Ȃ��B���̂��ƂŁA�ނ���f���������ɑ��鋭�����b�Z�[�W�ɂȂ�\���������B�������f�����댯���������āA1989�N�̎��̂悤�ɒe������邱�Ƃ�����B�������A�f���ɑ��āA�������{�͂��Ȃ炸����𒍈Ӑ[���ώ@���Ă���B������Ō����ƁA�ォ�牺�ւ́u�����v�A�������́u���f�v�Ƃ����̂ł����A���{����������\�����������Ƃ����z���āA���O�̓f�����s���̂ł��B����̏ꍇ�A�u���{�͓��{�ɑ��Ď㍘���v�Ƃ����˂��グ�̃f���ł���A����ɑ��Ē������{�����D��h�����A�f���͎��܂����B���̂��Ǝ��̂́A���낢��Ȗ����܂�ł͂���̂ł����A����Β��ږ����`�I�ȓW�J�������Ƃ�������B�����̓Ǝ��̂�����ŁA���O�̈ӎv�Ɛ��{�̈ӎv����v�����W���������Ƃ������Ƃł��ˁB���̂悤�ɒ����̃f���̂���l�����Ă����ƁA�����ɂ͖����`�͂Ȃ��Ƃ����u���{�̐��_�v�͂ǂ̂悤�ɉ��߂�������̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
�@���ꂼ��̒n��́A���ꂼ��̗��j������A���L�̑�\���̌`������B�����̏ꍇ�A�����Ă��܂��A�܂��\���Ƃ͋��Y�}�̂��Ƃł��B���̋��Y�}�̋@�\���ǂ��������̂ł��邩�͂��Ȃ�����́A�����̒��̖����`�Ƃ͂ǂ��������̂��A���邢�͂��ꂪ�ǂ̂悤�ɔ��W���čs���̂��z�肷��͓̂���B���݂��̐����V�X�e���i��\���j�̈Ⴂ�����z���Љ�^�����q���Ă����ɂ́A�e�n��̃V�X�e���i��\���j�̈Ⴂ���l���Ȃ���A�g�ł���A���̂悤�ȑz���͂���I�ȃ��W�b�N���������܂��K�v������A�ȏ�ł��B���������肪�Ƃ��������܂����B
�@�������_�@���܁A����̒��ł͏œ_������Ă���n�悪����������܂����A��c����ɔ��d�R�̏���������܂��B
����R�F���d�R�̔g��
�@��c�Òj�@���d�R���痈�܂����B�݂Ȃ����l�ЂƂ肪�����̐��܂ꂽ���̌��t�Ŏ��ȏЉ��ƁA���̍��̕����̑��l����m�邱�Ƃ��o���Ėʔ����ȂƎv���܂��B
�@���d�R�̂悤�ȁA�����ȁA�~�N������n�т̓��ɁA���������z�G���Ƃ������̓��זh�q�v��Ƃ����̂������āA�^�ߍ����ɗ��㎩�q�����݊Ď�������ړ��x������z������Ƃ������ƂŁA������đ呛�����Ă���B
�@��t�A��t�Ɛ������b���o�Ă���킯�ł����A��t�͔��d�R�̕����Ō����܂��ƁA��̂��Ƃ��C�[�O���Ƃ����܂��A�N�o�̓r���[�̂��ƂŁA���ɑ�R�������Ă���Ƃ������ƂŁA�u�C�[�O���N�o���v�ƌ����Ă��܂����B���̓����A�����̂��̂��A���{�̂��̂��A�ƌ����Ă���킯�ł����A�����猩��ƁA���d�R�̐l�����͓��̎��ӁA�C�m�[�ŊL�⋛���̂��ĐH�ׂ�悩�����B���������C�[�O���N�o���܂Ő����̂��ߑD�𑆂��ł����K�v�͂Ȃ������B����ƒ�������������D�̑D�������́A���̓������Ă������낤�B���{���{�͗��������ɂ���ĉ�����ꌧ�Ƃ��āA���̗��N�ɋ{�ÁE���d�R�𐴍��Ɋ�������Ƃ����u�����E����āv���Ă���B�Ƃ��낪�����̍���������������������A���ǂ܂Ƃ܂�Ȃ������B���̌�A��t�͌É�C�l�Y���J���\�����邪�A�������{�͂����F�߂悤�Ƃ��Ȃ������B���W���������Ă����Ȃ������B�����푈�ŁA���{�̏������m��I�ƂȂ�ƈ�]���ė̓y�ɑg�ݍ��ށB
�@���d�R���r���𗁂т�̂́A���\������ΒY���Y�o���邱�Ƃ��m��n��悤�ɂȂ�A���A�W�A�̏����ϋٔ�����B�܂萴���푈�ł��ˁB������b�R���L���炪�A���\���Y�B�����@����Ȃǂ��āA��ϗL�]������Ă���B�������{�́u�����Ɋ�������v�Ƃ����A�����́u���낾�炯�̓��͂���Ȃ��v�ƌ������A���̓����A���x�͕�̓��ɂȂ����B1960�N��ɂ͐�t���ӂ̓��V�i�C�ŐΖ����o��ƂȂ��āA�����A��p�A���{�A�����Ƃ݂�Ȃ��u������[���v�ƌ����o���đ���ƂȂ����B���ꂪ����B���{�́u�䍑�ŗL�̗̓y�v�Ǝ咣���A�������邽�߂ɁA���q�����݊Ď�������^�ߍ��ɔz�u����B�^�ߍ��ł́A���ꌧ���ŏ��߂Ē��c����q���U�v�̌��c�������B���{�h�q�Ȃ͊��ŗp�n�擾����2012�N�\�Z�A�o��10���~���v�サ���B
�@���d�R���ȏ����ł́A�R���ɕ��ȏȂ̖�l���|�x������ψ���ɏ�荞��ň��͂��������B��N�A�ʒÐΊ_�s���璷�����ςȎ�@�ɂ���Ĕ��d�R�n�拳�ȏ��̑����c��Ő��E�����Ă��Ȃ���Q�Ђ̌������ȏ����̑�����A����s���͍��������B�Ί_�s�Ɨ^�ߍ�������ψ����Q�Ђ̋��ȏ����̑����A�|�x���������Ђ��̑�����B���̈�Q�Ђ̌������ȏ��Ƃ����̂́A�ǂ�Ō��ċ����܂����B�������ł��ˁB�����̑��Ɉ�l�̈ψ����^���������R�́A�u��t�̓y��肪�L�`���Ə����Ă��邩��v�Ƃ����B������l�̈ψ��́A���d�R�̕����ŁA���t��Y�ꂽ�瓇��Y���B����Y�ꂽ��A����Y���B�����瓇�̂��Ƃ��A�܂��t�̂��Ƃ��ɏ����Ă��鋳�ȏ����ǂ��Ƃ����B
�@���͂��̋���ψ���̉E�X���Ƃ����̂́A�Ί_�s�̒��R�s�����V���R��`�j�ςŁA�ނ��x�����Ă����h�q����̐l�ԂƂ��A�E���ƊW�̂���l�����A�ێ炪�c��ő������߂�B���璷�ɂ͎����}�������ƊW�̐[���l�����A�����B����ψ������������l�����ɂ���ċ������Ă���B�ێ狳��ψ����A�o�b�N�A�b�v���Ă���l�����̍��́A�����Ɛ[���Ƃ���ɂ���Ǝ��͎v���B1968�N�̎�Ȍ��I�Ŋv�V���牮�ǒ��c����ƕێ炩�琼������������₵���B���̎��v�V�̒��j�͉��ꋳ�E����ł����B���̋��E�������A�ێ�̐����������낤�ƁA�����̎����}�͎v���āA���������������B�����ē����g���U�����Ă����l���d�R�ɔh�����A�l�������_�@�ɕ�����������āA���d�R���E�����c��Ƃ����̂��ł���B���̐l�����̎c�}���A���������Ă��āA�w��Ŏ��������Ă���B
�@��ɏq�ׂ܂������A�R���ɋ`�ƍO��ȏȐ�������h�����܂��āA��Q�Ђ̋��ȏ����g�p����悤�|�x������ψ���Ɉ��͂������Ă��܂����B�������A�|�x���̋���ψ���́A��������ۂ��A���ꂽ���̃J���p�ɂ���āA�������Дł��w�������k�ɔz�z���܂����B�����ĂT���ɓ����āA�|�x���ɕ��ȏȋǒ����ŐΊ_�A�^�ߍ��Ɠ�����Q�Ђ̋��ȏ����̑�����悤�ǒ����ł̎w�����������B�������A�|�x������ψ���͂���ɋ������撣���Ă���B
�@�����h�q�v��ɂ���āA�擇�A�^�ߍ����ɂ��Ί_���ɂ����㎩�q�����z������悤�Ƃ��Ă���B����A����{���k���Ƃ��Ȃ��������̂悤�ɕ⏕�����g���āA�z����i�߂邾�낤�B
�@���{���{�����ē����̍����ł����n�����艻�����邽�߂ɁA�����ɂ����F�߂����悤�Ƃ��Ă���B����͊�n�̌Œ艻��F�߂Ȃ��B���Ή^�����������Ă���B�������Ί_�s�c��ł͔��ɂ������Șb�ɂȂ��Ă���B�u�匠�̓��v���{���T�ɍR�c����ӌ����ƕӖ�Ö����\���ɍR�c����ӌ������^�������ʼn������B���̌��c��ی������悤�Ǝ����}�c���������H��������B�����������}�ƒ����̈ꕔ�c�����^���ɉ��A�H��͎��s�����B����́A���V�Ԋ�n�̌��O�ڐ݂�Ӗ�Ö��ߗ��Ăɔ����錧�����_�Ƌt�s���A����́u��n���v�Ƃ����ꖇ��ɁA�������J���āA�u����ł͊�n�^������Ƃ���������v�ƌ����悤�Ƃ����B�c��͂̎ア�Ƃ��낪�_����������Ă���B��������������Ă���̂��A�u���d�R����v�Ƃ����}�X�R�~�ł��B���d�R����̘_���ψ����Ƃ����̂��A���q���o�g�҂ł��ˁB�������И_�����A��t�̋L�����Ȃ����͂Ȃ��B�Y�o�V�����d�R�x�ǂƌ�����V���ł��B����ɔ��d�R�o�g�̓��U���̑�ꍆ�ƌ����Ă���l���A�R�l�������ւ�J�ߏ̂��āA�Ȃ����Ƃł���������Ȃ����Ƃ����_�������Ă���B���ꂩ�甪�d�R�h�q����̉���A���d�R�̃}�����A���Ɋւ��āA�u�R���͂Ȃ������v�ƌ������Ă���B����ɁA�R���ɗ^�ߍ����ōs��ꂽ���N�l�Ԉ��w�̈ԗ�Ղɂ��Ă��A�u����Ȏ����͂Ȃ��v�ƁA���j��c�Ȃ��悤�Ƃ��Ă���B����Ȑl�������A�����͂��܂��Ă��Ă���B
�@���d�R�́A��������O�������ςȏ�ԂɂȂ��Ă��Ă���B���ꂩ��A���䋙�Ƌ���ɂ��Ă��A���z���Ō��������B���d�R�̃E�~���`�������Ɉꌾ�̑��k���Ȃ��B����͓������Ƌ���������������B�������Ƌ���ŁA�����̋��D�����V�i�C���r�炵����Ă���Ɠ��{�̃}�X�R�~�͔��Ă��邯��ǂ��A�����F�߂��͓̂��{���{�ł��B���̎��ɂ��A����̋��������Ɉꌾ�̑��k���Ȃ������B���܂܂��A�������Ƃ��J��Ԃ���Ă���B���͌��߂����ƂŁA�����ɂ���ė���B�Ƃɂ��������A������n���ɂ��Ă܂��ˁB�����̋���������������t�ɑ勓���������Ă��ď㗤����B�C��ۈ����Ɖ��ꌧ�x�����̒����l��ߕ߂���B�����́A�u�ǂ����ĉ䂪������ߕ߂��邩�v�Ƃ������ƂŁA�ߕ߂��ꂽ�����l��D�҂��邽�߁A�C�����Ȃ���ߕ߂����D��ǂ������ĐΊ_�`�ɂ���ė���B���̎��Ɏ��q�����o�Ă��邱�ƂɂȂ�B�푈�ł��B���������V�i���I�����q���W�҂ł͑z�肳��Ă���B����͂����݂̂Ȃ��푈���Ƃ������Ƃł����A���Ⴀ�A���d�R�ɏZ��ł���l�����͂ǂ��Ȃ�̂��B
�@�����ی�@�Ƃ����̂������āA���͎��ԁA�푈���ɏZ���͂ǂ�����悢�̂������߂Ă���B���ꌧ���Ί_�s�����߂Ă���B����ɂ��Ε��͎��Ԃ��N����A�����̓��X����D�ɏ���ĐΊ_���ɗ��āA�Ί_������D���s�@�Ŗ{�y�ɑa�J������Ə����Ă���B�Ί펞��̘b�ł͂Ȃ��B���ߑ㕺��A�j�~�T�C����������ł��B�D�ȂŔ��ł���킯���Ȃ��B���d�R�̐l�́A�푈�ɂȂ�����I���ł��B���ʈȊO�ɂȂ��B�D�Ȃ������ł����B�H���Ȃ�Ă������ł����B�~�T�C����ł����܂ꂽ��A�ǂ��Ȃ�܂����B�R����n��D���A��s��̂���Ƃ����_���̂͌R����̏펯�ł��B�����玄�͌�����ł����A�R���̗��_�Ő�t��������Ă���l�����͍l���Ă݂Ă��������B���������ǂ��Ȃ邩�Ƃ������Ƃł��B�������͖{���ɁA���S�ґ䒠�̒��ɂ������Ȃ��B������A�푈�͂���Ă����ȁA����Ă����ȂƔO����������ȊO�ɂȂ��B���ē��������Ƃ������ڂŐ�t�̊�@������āA����̊�n������}��Ƃ����̂́A�ԈႢ�Ȃ����Ƃł��B���{�̌��������ƁA�܂��܂�����^���ÁB�������A�����ł����Ă��A�E���Ă͂����Ȃ��B�푈���Ă͂����Ȃ��B���a������B�������Ƃ��������͑i���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���͔��d�R�̐�Ղ͂قƂ�nj��܂����B�܂��s���Ă��Ȃ��̂͐�t�ƒ��V�_�����炢�ł��Bꀂ������h��A�^���ÂȈł̒��œH�̗�����ߓ������猩�������́A��������w���Ƃ́A�푈����U�N����ΏI���Ƃ������Ƃł��B
�@�������_�@���d�R�̑�ό���������Ă��������܂����B�Ō�ɒ��������낵�����肢���܂��B
����S�F����̎����̎v�z�I���_
�@�����@���@�����͑傫�������ē�̂��Ƃ�b���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B���܁A����̖��O�ӎ��͊m���ɕς����邱�Ƃ������������܂����A�����A�ǂ̂悤�ɕς��Ă���̂����l���Ă݂�A��͂�1995�N�̎O���̕ĊC�������m�ɂ�鏭���\�s�����̃C���p�N�g�̑傫��������킯�ɂ͂����Ȃ��B���̎��������������ɂ��āA����̐��̂������u���A�v�Ƃ͉��ł������̂��Ƃ������Ƃ����炽�߂Ė₢�����Ă����Ƃ������Ƃ��N����܂��B�����\�s�����ɋÏk���ꂽ���s�s�Ȍ����͂��܂��I����Ă��Ȃ��A����ނ���A�I��炷���Ƃ��ł��Ȃ��������ꎩ�̂ɑ���ɂ݂������ȂƂ��Č���Ă������B�����炱���A���ꂪ����������̍\���ւ̊S����ė����{�ւ̍R�c�̐�������قǂ̍��܂���݂��A���˂�ƂȂ��Ă��������Ƃ́A�����ł��炽�߂ċ������Ă����Ă��悢�ł��傤�B�����ć�95�N���㇁�����̂��鎩�ȔF�����������Ⴂ���オ�o�ꂵ�����Ƃ́A�u���A�v��̉���ɂ����Ă͂܂������V�����o�����������Ƃ����܂��B����ɂ��̇�95�N���㇁�̂Ȃ�����A70�N�O��̏Ɖs���茋�u�����A�_�v���������Ă����Ƃ������Ƃ��N�������B
�@���̕ω��̎��Ȃ�̗����������A��68�N�̐������ɂ₩�����m���ɕ���Ɍ������Ă������A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��68�N�̐����Ƃ͉����Ƃ����A1968�N�ɇ��O��I�����ƌ���ꂽ�A���߂Ă̎�Ȍ��I�����C���ɗ��@�@�c���I����ߔe�s���I�����s�Ȃ�ꂽ�킯�ł����A���̂Ƃ��ɓ��{���A�^�����̂Ƃ������}��J�g����Ȃ釀�v�V������c���Ȃ���̂���������܂��B���̋����̐�������̋ɂɂ��č\�z���ꂽ����I�ۊv�̐������ۂ��w���ć�68�N�̐����ƌ����Ă��܂��B���̑̐��͂���ȑO�̉���̐�����Љ�^�����W��ƂƂ��ɁA����Ȍ�̉���̐����̂�����܂ŕ����Â��Ă������Ƃ����Ӗ��ő傫�ȉe���͂������Ă����B���̇�68�N�̐������A���{�ł̇�55�N�̐����Ɣ�r���Ă݂�ƁA�A�����J��̉��̉���̓���Ȑ����E�Љ�̂Ȃ��Ő��܂ꂽ���{���A�^�����V�X�e���Ƃ��ċ@�\���Ă�����肪�����яオ���Ă���̂��킩��܂��B���\�����Ƃ͂����A���{�Ɖ���Ƃł́A�قȂ�̐������݂������ƂɂȂ�܂��B
�@��68�N�̐����͕��A�^�����̂Ƃ��Ă��܂��̂ŁA���{�{�y�Ƃ̓��ꉻ���̉�����ɂ��Ă��܂����B���������āu���A�v��̐��}��J�g���͂��ߎЉ�̂�����̈�ɐZ�����Ă����n�ɖ��h���ł����������ł͂Ȃ��A����ǂ��납���č���̉��ꋤ���Ǘ��̐���⊮���Ă���������S���Ă����܂��B����͑傢�Ȃ����ƌ����܂����A��������ނ���A���A�^�������݉�����������`�I���z���A���Ƃ̉��ꕹ����s��I�ɌĂэ���ł������A�ƌ����ق�����萳�m�Ȃ̂�������܂���B�u���A�v��́A�ȑO�قǂ̋ÏW�͂͂Ȃ��Ȃ����ɂ��Ă��A����̐�����Љ�╶��������Â��A�n�ƈ�̉��̕����ł̓����@�\���ʂ����Ă������ƂɂȂ�܂��B����·�68�N�̐����̑̐������Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̂��Ƃ��͂����肳�����̂�95�N�̂��̎����ł����B���j�̘A�����ɋT����A���̋T�牫��̏I���Ȃ�����O��ԇ��ɖڂ������A���ɂ��Ă����B��68�N�̐����Ɏ��܂�Ȃ������������������N���������ƁA���̂��Ƃɂ���Ė��O�ӎ��͗��������A���������Ă��������ƁA���̂悤�ɉ��߂��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̓����̓������������������ݍ���ł����A���{���Ƃ̘g�g�ݎ��̂�₤�A����̎����Ǝ��Ȍ��茠�ւƌ����������ւƂ���オ���Ă����悤�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ��\�ł��B����̖��O�ӎ������������o�������߂Ă������Ƃ��铮���̓������A����܂łɂȂ����܂�������Ă������Ƃ���A���̓���������̋ߌ���j�̍\���Ƃ��ċ��ݎ�肽���A�Ƃ����v��������܂����B
�@���܂ЂƂ́A������������̎����Ǝ��Ȍ��茠�����߂�������A������̂Ă��T���t�����V�X�u�a����������S��28�����u�匠�̓��v�Ƃ��鐭�{���j���ł��o����Ă���Ƃ������́A����ɉs���������������ƃV���N�����Ȃ���L����������Ă��������Ƃ̈Ӗ����ǂ�������悢�̂��A�Ƃ������ł��B�͂��炸���u�匠�̓��v�̐��{���j�ŁA����̕s�𗝂̋N���Əo��������ƂɂȂ����B���̏o������́A95�N�̏����\�s�������N�����Ă��܂�������ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ̓��ȂƐ[���Ƃ���Ōq�����Ă����B��68�̐����̈͂��ɂ͎��܂�Ȃ��������͂△���ł��Ȃ��Ƃ���܂ł��Ă��āA��68�̐����̌������ɂǂ̂悤�ɐ����I���������\�z���Ă������Ƃ��ł���̂��A�Ƃ������ӎ��ɂ܂Ő[�߂��Ă����܂��B
�@
���ꎩ���_�̂��߂̃R�����^�[��
�@�͂��߂ɁA����̋ߌ�����т��\���Ɩ��O�ӎ��̑ԗl�ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B��N�́u���A�v40�N�̐ߖڂł����������Ƃ���A�u���A�v�Ƃ͉��������̂������炽�߂Ė₢�������l�Ȏ��݂��Ȃ���܂������A���̖₢�ւ̎��Ȃ�̉����A��N���肩���[���犧�s���ꂽ�w�q���A�r40�N�̉���Ɠ��{�\�����̍z�����@��x�Ɋ��u���I���E�Ǝ����̎v�z�I���_�\�E���^�}�M���[�̔��Ԃ̑��͔����ꂽ���H�v�Ƃ����٘_�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B���̖{�̒��ڂ̂��������͓����O���w�̐��J�C����𒆐S�Ƃ��������O���[�v�ɂ���Ď��g�܂ꂽ�V���|�W�E���ł��B����15�N�߂��A����f��̓��W��f�≫��\�͘_���e�[�}�ɂ����V���|�W�E���ȂǁA�������̊��ɋ��͂����Ă��炢�܂������A��N�g�{�������S���Ȃ������Ƃ��V���|�W�E���̓��e�ɏ��Ȃ���ʉe����^�����Ƃ������Ƃ͔ۂ߂܂���B�g�{����̎��Ɖ���́u���A�v40�N���d�Ȃ������Ƃ͂���Ȃ���R�ɂ��������Ȃ��ɂ��Ă��A�������A����������ʂ��̂����������Ƃ��������ł��B
�@����Ƃ����̂́A�g�{���������70�N�O��ɁA����̖��ɐϋɓI�ɏ������蔭�������肵�Ă��܂������A���̂Ƃ�������ꂽ���t�͏̐[���ɓ͂��˒��������Ă��܂����B
�@��68���㇁�i��68�̐����ł͂���܂���j�Ƃ������鎄�����ɂƂ��ẮA�g�{����̎��ɂ���Ă��̎���̂��̎v�z��z�N������ꂽ�B����������́u���A�v40�N�Əd�Ȃ������Ƃ͗]�v���̎v���������������B���J����̂Ȃ��ɂ́A�g�{�v�z�̓��ٓ_�����Ƃ�������u�[���̏I���v�Ɓu�����̎v�z�I���_�v�Ƃ����������牫��́u���A�v40�N��U��Ԃ��Ă݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��������B����Ő��J���g�́u�[���̏I���v����A���ɂ́u�����̎v�z�I���_�v����_���Ă������Ƃ��ۂ���ꂽ�A�Ƃ����킯�ł��B
�@�u�����̎v�z�I���_�v�Ƃ������_���牫��̖��ɐڋ߂���ɂ������āA�����Ēʂ�Ȃ��̂́A��͂�g�{���u�쓇�_�v��u�쓇�̌p�����J�ɂ��āv�̂Ȃ��Œ����q�O���t�g���Ɓr�_�ł����B���́q�O���t�g���Ɓr�_�Ƃ̂������ŁA�����ƕ����ƍĕ����ɂ���Ă����ǂ����E������������ꂽ����̖��O�ӎ��̂��肩�����l���Ă݂����Ƃ������Ƃł����B����̖��O�ӎ��́q���I���E�i�����j�r�̖��Ƃ��đ����������Ƃ��\�ł��B���Ƃ���A����̎����́q�O���t�g���Ɓr�Ɓq���I���E�i�����j�r�̔����̂�����ƌq�����Ă���͂��ł��B���̎��݂́A����̋ߌ�����т��\�����ǂ��ɂ����Ē݂͂����Ƃ������Ȃ�̖��ӎ����瓱���ꂽ���̂ł��B�ڂ����͒��ړǂ�ł��炢���̂ł����A�����̃e�[�}�Ƃ������Ǝv����悤�Ȃ������̘_�_�������܂�ŏЉ�邱�ƂŖ���N�Ƃ������Ǝv���܂��B
�@�܂��q�O���t�g���Ɓr�Ƃ����T�O�ł��B����͋g�{�������u���A�v�̖{�������Ɠ����̖��Ƃ��đ����邽�߂ɕ҂ݏo�����T�O���Ƃ����܂��B�O���t�g�Ƃ����̂́u�ږv�̈Ӗ��ŁA�ЂƂ̋����̂��ʂ̋����̂���荞�����Ƃ���Ƃ��ɁA��荞�����Ƃ��鋤���̂̃C�f�I���M�[�I�Ȋj��ږ��A���ꂪ��荞�����̂̂Ȃ��ɂ��������ȑO���炠�����悤�Ɍ��������邱�ƂŁA�����╹�������R�̂悤�Ɏv�킹��I���ȑ��u�ł��邱�Ƃ��͂����肳���Ă��ꂽ�B�u���R�v�̂悤�Ɍ�����Ƃ������Ƃ́A�p���ڂ��������Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B����́u���{���A�v�Ƃ́A���A�^���̂Ȃ��ɂ�����������`���A���Ƃ̕����̘_�����ږ������Ƃɖ{���I�Ȗ�肪�������Ƃ������Ƃł���A���̌p���ڂ�������邱�Ƃɂ���Ă��������u���ɖ߂����v�Ƃ����n�삪�Ȃ����B����͖��炩�ɋ[���ł��B���������̋[�������R�̂悤�Ɍ���������Ƃ���Ɂq�O���t�g���Ɓr�́q�O���t�g���Ɓr����䂦�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�g�{���A����͖{�y���S�̍��Ƃł���قǂ̗��j��`���������Ȃ���A���{�̈�Ӌ��Ƃ��āu���A�v����̂͂��̂������Ȃ����s�ł���A�V�c���𑊑Ή��ł��Ȃ���A�u�A����n���A�Ƃǂ܂���n���v�Ɗ��j�����̂����������q�O���t�g���Ɓr�_���炷�鍪���I�Ȕᔻ�ɂȂ��Ă����B����̎����̎v�z�́A���́q�O���t�g���Ɓr�ƌp���ڂ̎��_��������Ă͂����Ȃ��A�����v���܂��B�p���ڂ�����̏ɕs�f�ɖ��������邱�Ƃ͔������Ȃ���Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł��B
�@���ɁA��قǗ�����̔����ɂ�����܂����u�O�����Ɓ\�؍��E����E��p�A�Ӌ����邢�͋��E���̎��_�v����̃C�j�V���e�B�u�Ƃ������ƂƊW���邱�ƂɂȂ�܂����A���̂��Ƃ�����̖��O�ӎ��́q���I���E�i�����j�r�̖��ɒu�������Ă݂�Ƃǂ��Ȃ邩�Ƃ������Ƃł��B���E�͎�荞��͂����肷����E�̋@�\�������Ă��܂����A�����ɊO�ւނ����ĊJ������ʂ̋@�\�����������Ă��܂��B����Η��`�I�ł��B���̗��`���͉���̋ߌ���j�̍\���Ƃ�������Ă��܂��B1879�N�̂�����u���������v�œ��{�̔Ő}�̂Ȃ��ɋ����I�ɕ�������A���{�����c�����̗��j��H�炳��A�����͂��̂����Ƃ��ߎS�Ȍ���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂����A1952�N�̃T���t�����V�X�R�u�a���œ��{����̏�Ԃ���E����̂ƈ��������ɁA����̓A�����J�̔r���I��̉��Ɋu�������B������1972�N�ɍĂсu���A�v�Ƃ������œ��{�ɕ��������A�Ƃ������j��H���Ă����B�����������j�I�o���͉���̖��O�ӎ��ɕ��G�ȉe�𗎂Ƃ����ƂɂȂ����B���ĉ���̕����A�v�z�̓������u�����ƈى��v�Ƃ����^�[���Ő���ɘ_����ꂽ�̂����̂��ƂƖ��W�ł͂Ȃ������͂��ł��B����ɂ����ẮA���ƂƂ������Ƃ����T�O�́A������܂��̑O��ł͂Ȃ��A�������^�╄��t���Ă��炵���l�����Ȃ��B���̋^�╄��t���ӎ��������͂Ƃ��Ắq���I���E�i�����j�r�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����������A����ɂƂ��Ă̎����̎v�z�I���_�́A�q���I���E�i�����j�r���ǂ̂悤�ɔ������Ă������ɂ������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@��O�ɁA70�N�O��́u�����A�_�v�Ƃ����80�N��ɉˋ������u�������a�Љ�@�^�������a�����@���i���j�āv�̂��\���ł��B�u�����A�_�v�Ƃ͂����ł��炽�߂Č����܂ł��Ȃ����Ƃł����A���Ƃ̕����̘_���ɉ���l���g���������Ă����S�I���ۂɍ��ꂩ��ًc���������A�N�`���A���Ȏv�z�I���H�̂��Ƃł��B���́u�����A�_�v�ɂ���ĉ���̋ߌ���j�̍\���Ɖ���l���g�̓�����`�̕a�����������z���Ă����������l�������Ƃ����܂����A�u�V���ꕶ�w�v48���i1981�N�j�Ɍf�ڂ��ꂽ��̌��@�\�z�́A����̎������u�\���I���́v�Ƃ��Ē������߂Ă̎��݂��ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��܂��B
�@��l�ɁA���ꓬ���ɂ͂��߂āq�����r�̎��_�����ꂽ�A��c�m����́u�����E���ƁE��O�����������v�Ƃ����_�l�̌���I�Ӗ��ł��B���̘_�l�́u��v��1971�N�S�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł����A���ǂݕԂ��Ă��V���Ȕ����������Ă���܂��B����ǂ��납��t�������߂���̓y�����l���邤���łƂĂ������I�ŁA���I�Ș_�l�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă��������ĕs���ɂ͎v���܂���B���̐�c����́u�����E���ƁE��O�����������v�́A�g�{��������́q�O���t�g���Ɓr�_�Ƃǂ����Ōq����A�����㐫�������Ă����B����̋ߌ���j���O�x�́u���������v�Ƃ������������Ƃ��������ߒ��̃p�[�X�y�N�e�B�u�ő����A�Ȃ��ł���O�����������Ƃ��Ă�72�N�Ԋ҂��߂����āq�����r�������������Ƃ��w�E�����Ƃ���͍��ł��Q�Ƃ���ɏ[���ς�������e�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�u�T�q����r�́q�����r�����m����^�U���{�\����\�A�����J�^�Ō�̔s�폈���Ƃ��Ă̍����E�̓y���^�V���{�]����]�����^�q���������r����A�W�A�ց^�W�q�����r��従�����^�q�����r�Ɓq���Ɓr���邢�͓��{�̒��̔���{�v�Ƃ����\���ɂȂ��Ă��܂����A�����̃V���|�W�E���̃e�[�}�Ƃ̊֘A�Ō����A�T���t�����V�X�R�u�a����O���̔F���̖��ɂ��Ę_�����Ƃ�������Ă݂�ƁA����̓��{���A�^����{�y���{�̉���Ԋ҉^���������ɏ]���i�V���i���Y���Ɏ�������Ă����̂����킩��܂��B���̑�O���ɂ���ĉ��ꂪ���{�̗̓y����藣���ꂽ�A������O����p�����邱�Ƃɂ���Ď���ꂽ�̓y������Ƃ����F���̂��Ƃɉ^���͐��i����Ă����܂��B�����ł͂Ȃ��A�O���ɂ���ĉ��ꂪ�͂��߂ē��{�̗̓y���Đ錾����A�A�����J�ɔ���n���ꂽ�A�Ƃ������_���c����͒��Ă��܂��B���̎��_�͋ߌ���j�̍\���I�c�����Ȃ���łĂ��܂���B
�@����ɁA�ߑ���{�̍ő�̑��҂Ƃ��Ă̒����ɑ��閳�m�Ɩ������������Ă��܂����A���̂��Ƃ͓��{�ߑ�j�̊��v���т����点�邱�Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂��B�O���́u���������v�͂�����������̑��݂��ɂ��Ă͌��Ȃ��Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���Ȃ킿�A��ꎟ���������͂���܂ł̐����Ƃ̊W��ؒf���邱�Ƃł��������A����������Ƃ��ẴT���t�����V�X�R�u�a���́A1949�N�̒����v���̉e�ւ̃f�B�t�F���X�̐��i������A72�N�̑�O�����������́A��t�̗̗L���߂����Ē������Ăъ��A�Ƃ����B���̘_�l�̖����Ō���ꂽ�u�q�����r�Ƃ͌��͎x�z�́q�Ӌ��r�ł��邾���ł͂Ȃ��B���́q�����r���s�C����従����J�n����Ƃ��A����́q���Ɓr���̂֔g�y����^���_���������Ă������v�Ƃ������t�́A��t�����̓��{���{�ɂ�鍑�L�������������ɂ��Đ�s�������̓y��匠���߂��铮�Ԃ̊j�S���������ĂĂ���B�܂��ɊC���m���X�Ɖ����Ă��錻�ۂ����肵�ēǂݍ��܂�Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@��܂ɁA���䍄�ḗu�E���^�}�M���[�v�̃��X�g�V�[���������f��I�z���͂������ɓǂނ̂��Ƃ������Ƃł��B���ꂪ���{�Ɂu���A�v����1972�N�T��15���̂��̓��A�u���ꂩ��͉���͓��{���v�Ƌ���ŁA�e�����d���ȃ}���[�A��Ɏ�������B���̎����̃��X�g�V�[���́A����́u���A�v�̌��E��\�o�������̂ł���Ɠ����ɁA�������邱�Ƃɂ���ăI�L�i�����h���[�����t���I�Ɏ�����A�Ƃ������Ƃ������Ă���悤�ɓǂ߂܂��B���̎����V�[���Ɖ��ڂ���悤�Ɏ�l���̃M���[�����Ԃɓ˂��h���������̂܂܁A�C�ӂ�f�r���V�[���������^�[�W������Ă����킯�ł����A�M���[�̜f�r���͉���́u���A�v��̍�����Î�����Ă���͂��ł��B�M���[�̐_�ʗ͂����Ă��������Ԃɓ˂��h���������́A���ꂪ���{�ł͂Ȃ���������̖��̑r�����Ӗ����A�I�L�i�����h���[�����˔��������́q�O���t�g���Ɓr�̋��ӂ��ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B
�@�ȏオ�A����ɂ����鎩���̎v�z�I���_�̎��Ȃ�̎��_�Ƙ_�_�ł��B����������g�I�Ȍ������ɂȂ�܂����A����̎����̓E���^�}�M���[�̔��Ԃ̑��������ɔ������Ƃ��ł���̂��A�Ƃ����₢�ɒu�������邱�Ƃ��ł���B�q�O���t�g���Ɓr�ƕ����̌p���ڂɎ��o�I�ł��邱�ƁA�q���I���E�i�����j�r������ɓ��݂���A�W�A���Ăяo�����Ƃɂ���Ĕ������邱�ƁA���̂��Ƃɂ������Ă���悤�Ɏv���܂��B
��Ώ̓I�Ȑ��Ɨ��������閯�O�ӎ�
�@���ɂS�E28�́u�匠�̓��v���߂����ĉ����I�o�����̂��A����͂ǂ����������Ƃ��Ă���̂��ɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B�S�E28�̐��{��Î��T�ŘI�o�����̂́A�܂��ɉ���Ɠ��{�̔�Ώ̓I�Ȑ��Ɖ���̖��O�ӎ��̕ω��ł͂Ȃ��ł��傤���B�ǂ��������Ƃ��Ƃ����A���{���j�ւً̈c�┽��ʂ��āA�T���t�����V�X�R�u�a���́A����ɂƂ��Ă͔r���Ƌ[���̃V�X�e���ł������Ƃ��������Əo������Ă������A�Ƃ������Ƃł��B����͗��搶���w�E�����A�؍��A����A��p���O�����Ƃł��������ƂƂ��W���Ă��܂����A���A�W�A�ɂ͓�́A���m�ɂ͎O�̈قȂ�^�C�v�̐�オ����Ƃ������Ƃɂ��炽�߂ċC�Â����Ă���܂��B����������A�W�A�̗��\���ɐ[���K�肳��Ă��܂����A���̂ЂƂ́A�A�����J�̎P�̉��ŁA�u����v�Ɓu���R�v�Ɓu�o�ϐ����v�𐋂������{�^�ł��B��ڂ́A���͂Ȕ����u���b�N�Ƃ��Ă̌R���ƍقƊ�n�ꐧ�Ƃ�������؍��E����E��p�^�B���{�^�̐��Ɗ؍��E����E��p�^�̐��͔�Ώ̓I�ȊW�ɂ���܂��B����Γ��{�����@�������A�J�b�R���́u����v�Ɓu�o�ϐ����v�́A����i�����Ċ؍��Ƒ�p�j�����Ӊ��i�R���ƍقƂނ��o���̕ČR�x�z�j���邱�Ƃɂ���Đ��藧�����A����[���̃V�X�e�����Ƃ������Ƃ��ł���͂��ł��B�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A���͂Ŋv���𐋂��A�ꎞ�͑�O���E�̉���̑z���͂����N���������̑��݂ł��B���A�W�A�̐��͒����̑��݂����Ă͌��Ȃ��̂��͂����肵�Ă���Ƃ������Ƃł���A����܂ŃA�����J�̎P�̂��ƂŃh���X�e�B�b�N�Ȑ��������{�́A����A�؍��A��p�A�����Ē����̑��݂����̎���̂Ȃ�����r�����Ă����B�q�S�E28�r���u�匠�̓��v�Ƃ������{���j�ɂ���ĘI�o��������Ɠ��{�̐�オ��Ώ̓I�ł���Ƃ����Ƃ��A�����������A�W�A�̈قȂ����������̂Ȃ��ɓ���邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����������ɖ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B
�@�����ŁA����̖��O�ӎ��̕ω��ɂ��āA�p�ӂ����V�����������Ȃ����̓I�ɒH���Ă݂����Ǝv���܂��B�����͂S��28���̐��{��Î��T�ɍR�c���錧�����̗����̉���^�C���X�Ɨ����V��̎А�����̗l�q��`����L���A�����ăI�s�j�I���̗�����E���Ă��܂��B�܂��A�匠�̐��{���T�ƈꖜ�l�����W�����X��p�s�C�l�����ōs��ꂽ�R�c���ɂ��ĉ��������29���̎А����`�F�b�N���Ă������Ƃɂ��܂��B����^�C���X�́u�V�������������n�߂��v�A�����V��́u�^�̎匠�����̎�Ɂv�̌��o�������Ă��܂��B�^�C���X�̎А��́A���Ŗڗ��������ƂƂ��ē����Ƃ��ɍR�c�̈Ӗ������߂��l�������������ƁA���L������̎Q���҂����������ƁA���{���T�ʼn���̏W�c�I�L�����ӒD����邱�Ƃ≫��̃R�A�̌o�����t�Ȃł��ꂽ���Ƃւ̊�@�������������ƁA�����ēo�d�҂���Q���҂̊��z�̂Ȃ��Ɂu�匠�v�u���Ȍ��茠�v�u�����v�u�����v�u������v�Ƃ������t�������������ƂȂǂ������A�u�����Ɏ�����Ă���͎̂����ւ̊��]�ł���A�C�T�ł���v�Ǝw�E���Ă��܂��B�ΏƓI�ɐ��{��Â̋L�O���T�ɂ��ẮA�Ȃ��A���Ȃ̂����̗��R�����������Ȃ������Ƃ��āA�q�S�E28�r�͊�n������j�F�����߂���T�������ɂ����A�ƌ���ł���̂���ۂɎc��܂��B
�@�����V��А��̂Ȃ��ł�����̖��O�ӎ��̕ω��ɒ��ڂ��Ă��āA���Ƃ��A�n��̉^���͎���I�����Č��߂�u���Ȍ��茠�v��A����ł͓��Ă̊�n�ێ�������u�A���n����v�Ƃ��đ����Ă��邱�ƁA�u����̐^�̎匠�ɂ͓Ɨ�����ʂȎ������K�v�Ƃ̈ӌ��������Ă���v���ƂȂǂ��Љ�Ă��܂��B����^�C���X�Ɨ����V��̎А��̂�������A����̐l�X�̈ӎ����ς��Ă������ƂɌ��y���Ă��āA���̕ω��̓���������̌���ɂ�锭���Ɓu���Ȍ��茠�v��u�Ɨ��v�̌��t���^�u�[��j�邩�̂悤�ɏo�����ƂɌ��Ď���Ă��܂��B�L�҂̃R�����u�匷�����v�i�u����^�C���X�v�T���P���j��u�����ؐ�v�i�u�����V��v�T���R���j�ɂ����l�̊S���������Ă��܂��B
�@�Ƃ���ŁA�ł́A���������ڂ������O�ӎ��̕ω��́A���ۂɂ͂ǂ��������̂��Ƃ������Ƃ��A�������z�z�����V���L�����猟���Ă݂����Ǝv���܂��B�܂��A�S��28���̐V��Љ�ʂɌf�ڂ��ꂽ�L���ł��B�u�匠������v�̌��o���ŁA�S��27���ɍs��ꂽ�u���������Ɨ����������w��v�������Ấu�����̎匠���l���鍑�ۃV���|�W�E���v��300�l���l�߂����A�M�C�ɕ�܂ꂽ�l�q��`���Ă��܂��B
�@�܂��S��28���̍R�c���ŁA���C���[�W�J���[�̗̕z�Ɂu���{���ɂ��̐\���I�@���͂�e�ł��Ȃ���Ύq�ł��Ȃ��v�Ƃ����X���[�K�����������u������v���f���Ĉӎv�\�������j����A�앗�������Z���^�[��Ấq�S�E28�r���ŁA�n���C�ɗ��w���Ă����Ƃ��ɁA�n���C�̐�Z���̎匠�^���Əo������o�������ɂ��āA����̎��Ȍ���̂��߂ɐ��j����̓I�Ɋw�ԈӋ`�ƁA���Ƃ��Ẳ��������߂��K�v����������u�I�L�X�^�P�O�V�v�̃����o�[�̍��k������グ�Ă��܂��B
�@�q�S�E28�r����W���������V��̃I�s�j�I���̗��ɂ͂���Ȑ����E���Ă��܂��B�u���������̂��Ƃ����������Ō��߂鎩�Ȍ��茠��͍����鎞���ɂ��Ă���v�Ƃ���20��̏����A�u�S��28���͌l�I�ɂ́w����Ɨ����l������x�ɂ������Ǝv���܂��B�Ɨ��Ƃ������Ƃ����ꂩ�琶�U�l���Ă݂����Ǝv���܂��v�Ƃ���60��̒j���A�u�S�E28���w����Ɨ��̓��x�Ƃ��錈�ӂ�V���ɂ��������̂ł��v�Əq�ׂ�80��̒j���ȂǁA�u���Ȍ��茠�v��u�Ɨ��v�����R�ƕ\�����Ă���Ƃ��낪�ڂ������܂��B���������u���R���v�͂���܂łɂȂ����ۂł��B����̖��O�ӎ����m���ɕς����Ƃ��������́A���̂悤�Ȑ��ɗ��ł�����Ă���̂ł��B
�@����^�C���X�́u�S�E28�킽���̎v���v�ł��A�u�Ɨ��v���咣���镡���̐����E���Ă��܂��B���̃R�[�i�[�͑��Q���҂̐����W�߂����̂ł����A60�̒j���́u���܂Ŏ�������{�l�Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B����l���B�����s���̃f�����w���{����o�čs���x�Ɣl���𗁂тĂ������A�{���ɏo�čs�������C�������v�ƃE�C�b�g�𗘂������R�����g���Ă��܂��B���̂悤�Ȑ����ے�������̂Ƃ��ĂS��28���̉���^�C���X�̒d�Ɋ�ꂽ�u�j�b�|���͕ꍑ�ɂ��炸���l�̐S�ɗ����������ނ̂݁v�Ƃ����̂Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���{���J�^�J�i�́u�j�b�|���v�ɂ����Ƃ���ɁA�A�����J�ւ̗ꑮ���܈ӂ����Ă���ɂ��Ă��A�u���{�v�ł�������̂��Ƃ����₢�͎c��܂����A���̉̂͑����Łu���{���ɂ��̐\���I�@���͂�e�ł��Ȃ���Ύq�ł��Ȃ��v�ƃ��b�Z�[�W�����u������v�Ƒ��ʂ���C�T��ǂ�ł��ԈႢ�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�@���������V���L������́A����܂ʼn���Ɠ��{�̊W��e�Ǝq�ɋ[�������A���z�����Ă����\����ǂݎ�邱�Ƃ��\�ł����A�����ǂ����E��������������ꂽ���j�I�o���̖��O�ӎ��ւ̍���Ƃ��Ắq���I���E�i�����j�r�ƁA���̔����̂�������m���ɕς����Ƃ������Ƃ���Ă���͂��ł��B���t�������Č��������A����̐����ԍS�����Ă�����68�N�̐��������E�_�ɂ����Ƃ������Ƃł���A���͂₻��ɂ���Ă͐l�тƂ��������邱�Ƃ͕s�\�ɂȂ����Ƃ������Ƃł���A���̌��E�̌������ɐV���Ȃ鐭���I�Љ�I��Ԃ�͍����Ă������Ƃ���ӎu��������Ԃɖ��o���A�Ƒ����Ă��I���O���������ɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł��B����܂ʼn���̗��j�̕ς�ڂɂ͎����E�Ɨ��_�����ʂĂʖ��̂悤�ɂ��肩������������Ă͏����Ă����܂������A95�N�ȍ~�̕ω��͂��Ă̌��ۂƂ͖��炩�Ɉ���Ă���̂��킩��܂��B
�@���₩�ł͂��邪�n�k�̕ϓ��悤��忓��́A�����ɂ��Ċm���ɂЂƂ̊K������������ƌ��Ȃ��Ă��ԈႢ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ɂ͓����Ă��܂��A�����V��Ў�ẪV���|�W�E���ŁA���_�̒��̂ЂƂɓƗ��_�����グ���Ă���̂ɂ͖ڂ�������܂����B���͂������A�Ɨ��_�̎v�z�I�A���H�I�˒��ł����A�����ł͓˂�����Ř_���Ă������Ƃ͂����ɁA����̖��O�ӎ����[���Ƃ���ŗ��������Ă���Ƃ������Ƃ��w�E����ɂƂǂ߂Ă����܂��B
�@���̂悤�Ɋm���ɕς�������A�ς�Ȃ�������`�̌���I�f�t�H�����ɖڂ��Ԃ�킯�ɂ͂����Ȃ����������݂��邱�Ƃ��܂��������ł��B�q�S�E28�r���߂���I�s�j�I���Ɍ���ꂽ�A�ς�Ȃ�����̓T�^�́u�^�̕��A�v�_�ł��B����̌������l����Ɓu���A�v�͂܂��������Ă��Ȃ��A�u�^�̕��A�v�̓r��ł���Ƃ�����|�̔����ɓǂݎ��铯����`�I�����́A�̂��܂��܂ȋǖʂɕϑt����Ȃ�����J��Ԃ��o�ꂵ�Ă��܂��B���܂��Ȃ��u���A�v���z�⓯����`�͍�������Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�Ɋ��������܂��B���̔ᔻ�I�������Ȃ�������A����̒�R�͌J��Ԃ��q�O���t�g���Ɓr�ɉ������Ă������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@���Ƃ��A�u�匠�̓��v���q�S�E28�r�ł͂Ȃ��A�u���{���A�v�����q�T�E15�r�ɂ��ׂ����Ƃ����ӌ����A���{�����̑�ĂƂ��Ē��ꂽ�肵�܂����B���̌����́A���A�^���≫��Ԋ҉^�������菊�Ƃ����T���t�����V�X�R�u�a���O����j�����A���{�Ɂu���A�v���邱�Ƃɂ���Đ푈�Ŏ���ꂽ�̓y������Ƃ����]���i�V���i���Y��������I�ɕϑt�����ɂ��������܂���B�u�^�̎匠�v�̂��߂ɂ́u�^�̕��A�v���Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������W�b�N���A�q�O���t�g���Ɓr�ɗ��ߎ���Ă����^���͂��������z�肪�ł��܂��B�V���Ȉߑ����܂Ƃ���������`�A���������Ă��ԈႢ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł��B
�@���ĂȂ��قǂ̓��������߂Ă��鉫��̎����ւ̑ٓ����A�����Ɂq�O���t�g���Ɓr�̓����̘_�����o����H�I�Ȏv�z�Ƀ`���[�W���Ă������Ƃ��ł���̂�������Ă��܂��B��68�̐����̎�������邱�ƁA��������u�^�̕��A�v�_�̃��W�b�N���������˂��j�邱�ƁA�����ĂȂɂ����u������j�ɓ��݂��铌�A�W�A�v�i���́j���A����̎��Ȍ��茠�Ǝ����̍\���I�͓��ɂ��Ă������ƁB����̗��j�ӎ��̐����͂Ƃ��Ắq���I���E�i�����j�r���h���X�e�B�b�N�ɕ����q�O���t�g���Ɓr���R�s�[���邱�Ƃł͂Ȃ��A�܂��ŋ߂̉���̌��_�ɗ��ʂ���u�\���I���ꍷ�ʁv�_�̍��Ɓ\���\���Ƃ̘_���Ɏ��܂邱�Ƃł��Ȃ��B������q�n��r���ƁA�����Ă�����A�W�A�Ɂq�q���r���ƁA���̂��Ƃ������̍z���ɐ݉c���������ƂȂ��ɂ͓W�]���J�����Ƃ͂ł��Ȃ��A����Ȃ��Ƃ��v�����肵�Ă��܂��B
�����^���_��
�@�������_�@���肪�Ƃ��������܂����B�x�e���͂���ŁA��ł݂Ȃ���̎���������Ǝv���܂��B���̑O�ɁA�l�̕����痛����Ɗې삳��Ɏ��₵�Ă��������Ǝv���܂��B
�@�ې삳��ւ̎���ł��B�ŋ߁A�������Y�}�̋@�֎��E�l������ɁA��̉���̋A���_�̘_�����o�܂����B������Ċ�������֘A�����А����f�ڂ��܂����B�T��15���ɗ����Ɨ��w������������ƂɃG�[���𑗂�L�����o�܂����B�����̒����̓����́A����ɂƂ��Ă͔��ɊS�̐[�����ł��̂ŁA�����������������A�����l���āA�ǂ������Ӑ}�ł��������_�����o���Ă���̂��B�������̗�����ɂ��āA�����������������B
�@������ւ́A��قǂ̑�c����̂��b�ɂ��������d�R�̌����������̒��ŁA���ȏ�����̘b���o�܂����B����͗��j�F���̖�肾�Ǝv���܂��B��̑��𒆍���؍��A�k���N�ւ̐N���A�A���n�x�z�ƌ���̂��ǂ��Ȃ̂��B���邢�́u�]�R�Ԉ��w�v�̖����ǂ��݂�̂��B���̗��j�F���Ɋւ��Č����ƁA�܂��ɖp�یb�哝�̂��ċc��œ��{���{��ᔻ�����悤�ɁA���j�F�����߂����Ĕ��ɓ��A�W�A���h��Ă���B���搶�������A���B�ł͐��A�����Ɍ������l�X�ȓw�͂��Ȃ���āA���ۓ������ꂽ�Ƃ̘b������܂����B�ł����A���A�W�A�ł͂Ȃ��Ȃ����A�W�A�����̂��������Ȃ��B�ނ���͈���������肶��Ȃ����Ƃ����C�����܂��B���̑傫�Ȍ����̈�����j�F���̖�肾�Ǝv���܂��B���̓_�ɂ��āA������̍l�����������������������B
�@�ې�N�j�@�Ⴆ�A��́w�l������x�ł̘_���ł́u����̋A���͖����ł���v�Ƃ����悤�Ȍ������\�\����͂�͂�����푈�̑O�ɑk���čl���Ă݂Ă��������A�Ƃ������b�Z�[�W�ł��ˁB���ꂪ��{�I�ȍ\�}���Ǝv���܂��B�������̎��_�ł��������c�_���o���Ă���̂��Љ�Ȋw�@�̃g�b�v�ɓ�����l�ނł�����A������x���{�̈ӎv�Ƃ̊ԂŁA�����Ɣ��f�̊W������܂��B���̈Ӗ��ō��Ɛ����I�ȑ��ʂ������킯�ł����A��N�̐�t�w���������獑�L���Ɏ����A�̂����̒�����o�Ă������̂��Ƃ������Ƃ��܂��l����K�v������B�������������Ƃ��Ȃ���A���̂悤�Ș_���͏o�Ă��܂���B�����F�肩�猾���ƁA�����푈�̑O�ɁA�����Ɠ��{���{�̂������ŗ����̋A�����߂����A�̋c�_���������B�擇�̌����Ƃ�����Ƃŕ����镪���ĂƂ������̂��ꎞ���c�_����Ă����킯�ł����A���Ă��܂��B�Ȃ����Ƃ����ƁA1880�N��̊C�R�͂Ō����Ɛ����̕����D���Ă����B�����������Ƃ��炵�āA�����Ă��ނ��됴�������炯�����킯�ł��i�����Ă��̂��̂̃A�C�f�B�A�̓A�����J�o�R�œ��{���炾���ꂽ���̂ł������j�B��͂�����푈���傫�Ȗ��ŁA����ɂ���āA�Ȃ������I�ɁA�\�͓I�ɋA�������߂��Ă������\�\���̂悤�ȗ��j�I�\�}���������Ă���킯�ł��B�����푈�����1885�N�̂P���A��t�ɍY��ł��肪�ׂ���A�����N�̂T���ɉ��֏����B�����Ő������{�Ɩ������{���c�_���Ă������r���A�푈�ɂ���Ēf�����邱�ƂɂȂ�B�������A�������̂��ƁA���������ȑO�A�����ɂ͉������������킯�ł�����A�����̋A���͗����ł���A�Ƃ����v�z���̂͗����E��������Ɏ������Ă������͂��ł��傤�B��̕����Ď��̂��A��͂薾�����{�ɂ�问�������̌��ʂƂ��āA�����O��Ƃ��ďo�������̂ł������킯�ł��ˁB
�@���j�������̂ڂ��čl���܂��ƁA�����̐����Ƃ��ẮA���ۏ��̐��ɍ��킹�悤�Ɠw�͂����A��͂蒩�v�]�����̐��̉�������ōl���Ă����߂����������B�܂�����A���̒������g�͍��ۏ��̐��̒��ő��݂��Ă��܂��B�����Łu�����̕����v�Ɠ����ɁA����Γ�̉��l����Q�荇�킳��A�B���ɂȂ��Ă���\�\���ꂪ���̒����l�̈�ʓI�Ȋ��o�\���Ȃ̂ł͂Ȃ����B2005�N�̔����f���Łu������Ԃ��v�Ƃ����X���[�K�����o�ꂵ�܂����B��̊���B���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ̒���ł��ˁB�A���Ƃ����ϔO���g���A�����炭���̈ꐢ�I�����炢�̊ԂɊ��S�ɕʂɂȂ��Ă���͂��ł����A��͂�L���̒��ŁA�܂��ԓx�̒��ŞB���Ɏc���Ă���B
�@�Ō�ɕt�������܂��ƁA���̉ߓn���̍ł��钥��Ƃ��āA�Ⴆ�J�C����k�ɂ����钆�����i�Ӊ�j�̑ԓx������B�܂�Ӊ�����[�Y�x���g�Ɍ������̂́A�u���N�͓Ɨ������Ă������ł���v�Ƃ����������ł��ˁB����Β��؉����I�ȐU�镑�����܂��g�̉�����Ă��āA���̎���A�܂�Ɨ������ł��č��ۏ��̐��ɓ����Ă����Ƃ��̋��n���I�Ȃ��̂Ƃ��āA�Ӊ�̔��b���������B����Ɂi�Ӊ�̓��L�ł́j�����E����Ɋւ��Ă��A�������@�̐��������ȑO�ɓ��{�������x�z���Ă��܂��Ă���A�����珫���ɂ����Ē���������I�ɂ����̗L������́A�M�������`���A���邢�͕č��ƒ����Ƃ̋����Ǘ��ł��ǂ��\�\�����������Ƃ��J�C����k�̒i�K�Ō��킳�ꂽ�悤�ł��i���͂���ɂ���āA�č��ɂ�鉫����̊Ǘ������F����Ă��܂����A�Ƃ����\��������j�B
�@�������_�@���̘b�ŁA�K�ߕ��̐��̉��ŁA�K�ߕ�����͒��ؖ����̕����Ƃ����̂��������Ă��܂����A���̏ꍇ�̗��j�I�Ȏ˒��Ƃ�����ł����ˁA�����̎���Ɉ�ԔŐ}���L�������B�����̗����͍����E���v�̐����ɂ���̂ŁA������܂߂đ����Ȃ̂����牴�����̂��̂��Ƃ����������A�����̎w���w�Ȃ�l������R�̊����̒��ɂ���̂ł��傤���B
�@�ې�N�j�@�����ł��ˁB�w���w�ł���Ƃ��A����R�Ƃ��ɂ������Ȃ��A�����E���ꎩ�̂ɉ�������o�����Ƃ��A���������Ӑ}�͂Ȃ����̂Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA��v�ɂ͓��{�i�鍑��`�j�ɑ�����J�̊���L�����Ǝv���܂��B�����푈�̔������œ��{���{��`�͌��n�~�ς��ďd�H�Ɖ��ł����B���̂悤�ȗ����{�ɑ�����j�I�ȃ��T���`�}��������B�����ł��̋��J�̃V���{���Ƃ��āA��t�^�ދ������I��Ă��܂��Ă���킯�ł����A�t�ɍl��������ɂ܂����肵�Ă���Ƃ�������B�����E����S�̂ɂ܂ł��̃V���{����p���L���悤�Ƃ͂��܂�l���Ă͂��Ȃ��A�����������܂ōl���邱�Ƃ��ł���̂ł���A�ƌx�����Ă���\�\���̂悤�Ɏ��͉��߂��܂��B
�@���@�ߌ��@���̘b��́A���͐��ł͂Ȃ��̂ł����A���N�����ł��A�K�����������ł͂Ȃ��ł����A������肪����܂��B�����Ɍ��炸�A10�N���炢�O����A�������ӂ̗��j�ɂ��āA��X�I�Ȍ������i��ł���B�P�ɌÑ�j�̌����ł͂Ȃ��āA���ꂩ��̒����̐����O���ɂ��e������悤�ȃv���W�F�N�g�ł͂Ȃ����B�����֘A�ł́u���k�H���v�A���Ȃ킿�����𒆍��j�̈ꕔ�Ɏ�����鎋�_�ł̗��j����������Ƃ��Đi�߂��Ă��܂��B�o�ϐ����𐋂��āA�卑�̊�Ղ�z�������ƂɁA�卑�ӎ����L�������B���̒����̑卑��`�������O�𐭍�R���ɂ��e�����A���j����������ɓ�������Ă���B
�@1991�N�̘p�ݐ푈�̎��ɁA�t�Z�C�����N�E�F�[�g��N�����闝�R�Ƃ����̂��A���j�I�ɃC���N�̗̓y�������A�Ƃ������̂ł����B�����̃g���R�̎��A�u���̗����Ō����Ȃ�C���N�̓g���R�̂��̂��v�������������Ƃ��v���o���܂����B�����Ȃljߋ��̎���������o���ƁA���[���b�p�͂قƂ�ǃC�^���A�̂��̂��Ƃ������������o���邩���m��Ȃ��i���j�B�Ñ�j�܂ł����̂ڂ��ĉߋ��ƌ��݂�������c�_�́A���A�W�A���L�̂��̂ł͂Ȃ����B
�@���j�F���̖��ł����A��c����⒇������̘b���Ȃ���A���͒f�ГI�ɂ����ǂ�łȂ������̂ŁA����̖�肪��ϕ��ɂȂ�܂����B��c����̔��d�R�̘b�ł����A�v���o�����̂́A2010�N�A���ؓ��ɖk���N���C���������Ď����҂��o��������������܂����B�őO���̓��ł����A�؍��S�y�ł́u�k���N���������v�u����v�̐������܂����̂ł����A���̎��Ɉ�ۂɎc���Ă���̂́A�E�C����V���L�҂��Ǝv���̂ł����A���ؓ��̏Z���́u�͂�߂āB���S�ȂƂ��납�疳�ӔC�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Łv�Ƃ��������E���ċL���ɂ����B�������������؍����_�ɂ��e�����������m��Ȃ��B���̌�A�\�E����w���a���ꌤ�����̒���������ƁA�k���N�ɑ���F�������Ȃ舫������B���̎��ɂ��n�捷�������āA�؍��암�̂ق����u���������v�Ƃ������d�_�������A�x�탉�C���ɋ߂��Ƃ���ł͕ێ�I�Ȓn��ł��u�Θb���K�v���v�u���܂�ǂ��l�߂Ȃ������ǂ��v�̐������������B���E���ɏZ��ł���l�́A�����̃��A���Y���̕��a��`������B����͖��͂̂悤�Ɍ����邩������Ȃ��B�������A���Ă̊؍��͔����ŋÂ�ł܂����R�����ƂŁA���ł��푈����悤�ȍ��ł������A�����N�����o�āA�ێ琭���ł����Ă��k�Ƃ̑Θb�����߂�悤�Ȏp��������܂��B����͊؍��ɂƂ��Ă����ł���A�ƁB���ؓ��̏Z���̊��o���A�قƂ�ǂ̊؍��̐l���A�O�����ƂŌR�����ƂŁA�ČR�̊j�ɂ������Ȃ��������ł����Ă����́A�O�����ƂƂ��Ă̋ꂵ�݂���A���������𗬂̏�ɂ������Ƃ����ӂ��ɕς���Ă��Ă���B
�@��������̂��b�ł����A�m���ɕς����鉽��������Ƃ������b�Ɋ������܂����B���낢��Ȏ����̐ςݏd�˂ŁA�A�C�f���e�B�e�B�Ƃ��A���Ƃ̈Ӗ��Ƃ��A���߂čl���悤�Ƃ����ӎ����L�����Ă���Ƃ������b�ł����B���̂悤�ȕω�����A�C�f���e�B�e�B�ƌ����ƁA���d�R�ɑ�\�����悤�Ȍ��������ߕt���A���f��Ƃ����̂́A�����̗��\���Ǝv���܂��B
�@�P�������Đ\���グ��ƁA����1970�N�ォ��A�߂���2000�N�ォ��A�O���[�o�����̓����ƂƂ��ɁA�����̈Ӗ��A�匠���Ƃ̈Ӗ��͋}���ɕς�����B���̎�����č��̔e���̒����������āA���݈ˑ��̌��t���o���̂�70�N��ł���A���ꂪ���̏I�����o�āA�O���[�o�������i�݁A�����I�ɂ͍��������Ȃ�Ⴍ�Ȃ��Ă���B���S�ۏ�̖ʂł���������l�X�ȉۑ肪�����āA���͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ɠ��m���Η��������̂ł͂Ȃ����͂��ĉ������Ȃ�������Ȃ��ۑ肪�����㊄������̂��A�����ł��B�m���ɑ��݈ˑ��Ƌ����́A�������Ⴍ�Ȃ��Ă���B���Ƃ̊_�����Ⴍ�Ȃ��Ă���B�A�W�A�ɂ����Ă��A�}���ɐi�s���Ă���Ǝv���܂��B���A�W�A�����Ɍ������Ƃ����܂�����ǂ��A����̖f�Ղ̓x����������ƁA�m�`�e�s�`����ŁA�d�t��肿����Ɖ��B����ȂɌ��܂��Ȃ�����A���������H�ׂĂ�����́A���Ă�����̂͂قƂ�ǒ������痈�Ă���B�n��̕��Ƃō�������̂Ȃ̂ŁA�n��͂ЂƂɂȂ��Ă���̂������ł��B���A���X�g�͐푈���������ƌ����܂����A�푈�͌����I�ȑI���ł͂Ȃ��B���a�������ł��B
�@�������Ⴍ�Ȃ�A�����̈Ӗ�������ӂ�ɂȂ����肷��̂ŁA����ɑ��锽���Ƃ��Ă�������́A�V���Ƃ����ƂƂ��A���������Ă���B���̓�����߂������Ă���̂��A���㐢�E�ŋN�����Ă��邱�ƁB���{�ł������ł��؍��ł��A�ω����鑊�݈ˑ��ƍ��ۋ��͂ɗ��Q�����o�����۔h���A�����̒��ł��o�ς̒��ł���������B����ɕs����������l�X�����āA�����h�ɂȂ�����A�i�V���i���X�g�ɂȂ����肷��B�������s�ł��߂������Ă���̂��A���A�W�A�̌����ł��B
�@��t�Ƃ����d�R�Ƃ��A�����͗h�炢�ł͂����Ȃ��̂ŁA���߂����������Ă���B���q��������āA���Ƃ̃R���g���[�����������Ă����B
�@���{�������Ă������߂ɂ̓A�W�A�Ƌ��͂��Ȃ�������Ȃ��B���{�̂��߂ɂ��A�W�A�ƈ�ɂȂ�K�v������B���̂��߂ɂ́A���L�ł�����j�F�������K�v������B����ɑ��锽���Ƃ��āA�����S����������悤�ȗ�������猻��łԂ��荇���Ă���B
�@�Ō�Ɉ�_�B�u�����v�ň����S�̃L�����y�[�������肷��l�������A���ۂɂ���Ă��邱�Ƃ͍�����Ⴍ���āA�V���R��`�Ői�߂悤�Ƃ��Ă���B���ۂ̌o�ϐ���́A�ی�f�Ղł͂Ȃ��āA�܂������̔�i�V���i���Y���B���̃o�����X���Ƃ邽�߂ɁA�����I�Ƀi�V���i���Y�����f����Ƃ����\�}������B�܂��A�R���\�Z�����炳����Ȃ��ČR�̌��������钆�ŁA�����ɗ\�Z���m�ۂ��邩���d�v�B�R�l�o�g�̃A�C�[���n���[�哝�̎��g���A�R�Y�����̂̐����ɁA�x����炵���B�s�����o���������o�������āA��ÂȔ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�������_�@�ł͎��Ԃ����܂肠��܂��A��ꂩ��̎���������Ǝv���܂��B
�@����`�@���j������ƁA�������t���p�̗̗L�����ɂ��āA�����̑��̔F���ɕϑJ������悤�ȋC�����܂��B�ې삳��ɂ��̂�������������������B
�@�ې�N�j�@�����嗤�A��p�Ɨ����E����́A��ɐU���������Ȃ���1000�N�ȏ�̎��Ԃ��o���Ă���B���낢��Ȕg���������Ă��A���������W������Ƃ����O��ōl���邱�Ƃ��d�v�ł��B
�@�Ⴆ�ł����A�ɔg���Q�̒�������Ă���ƁA�h��v���̉e�����ȂƎv���Ƃ��낪���X����B������l��_�ł��B�h��v���͖��B������ǂ��o���āA�������̉����𗧂Ă�B����͎��ۂɂ̓t�B�N�V�����ɋ߂��b�ŁA�������Ƃ���ȊO����悤�Ȃ��Ƃ͎��͂قƂ�ǐ������Ȃ��̂ł����A�u�������̉����v�𗧂Ă�Ƃ��������ɂ���Ċv���������������ʂ�����B���̕ӂ�����Ȃ��Ƃɐ��m���痈�����z�Ȃ̂ł����B�ɔg���Q�̒��̐l��_�ɂ͐h��v���̉e��������̂ł́A�Ǝv���܂��B�������A����̏ꍇ�ɂ͂���ł����ēƗ���������ɂ͂����Ȃ��ŁA��荂�x�Ȏ�����v������Ƃ��������Ƃ��Đl��_���N���Ă���B�����������Ƃ�����A�����v���̔g���Ɖ���̎v�z�`���Ƃ������̂́A���W�ł͂Ȃ��̂ł��B���N���Ă��邱�Ƃ��A�F�X�ȈӖ��Ō㐢����]������Ȃ�A�ǂ����ŘA�����Ă��邩������Ȃ��\�\�����l���Ă݂�ׂ��ł��B�������A���̊Ԃɓ��{�̃}�X���f�B�A�Ƃ��������Ă��܂��܂�����A���̂��Ƃ����X�ӎ�������Ȃ��B���͐��ݓI�ɁA���A�W�A�S�̂��ς�낤�Ƃ��Ă��鎞�ɋN�����g���́A���������Ɠ��ݓI�ɊW�����͂��Ȃ̂ł��B�����ɏ�Ɏ��������̃A���e�i���Ă����ׂ����Ǝ��͎v���܂��B
�@����a�@�����̐l������̋L���Ȃǂ�����܂����A�����̓Ɨ���F�߂�Ƒ�p�A�`�x�b�g�̓Ɨ����ɂ��g�y����B�����ɂ��āA�ǂ��ł��傤�B
�@�ې�N�j�@�O�ɂ́A�ʁX�̐��i������܂��B�����ɂ͉���������܂����ˁi���{�����̉�����ׂ����Ƃ����o�܂����݂���j�B��p�ɂ͓Ǝ��̉������������̂ł͂Ȃ��āA�����������A���A�����̌��Z���n��������Đ����̍s���悪�������Ă����n�ł����B�����ă`�x�b�g�̉����̓��}�������ɐM���Ă���l�b�g���[�N�Ƃ��āA�����Ƃ̊Ԃł̏@���I�������g�̋��L������܂����B�u�Ɨ��v�Ƃ����ꍇ�ɁA�鍑��`�����荞�ސ������̏�Ԃ��x�[�X�ɂ��čl����K�v������A�܂����ꂼ��̒n��ɑ��鐴���̊W�\�����ǂ��ł������̂��A�Ȏ@����K�v������B������A�����Ƒ�p�ƃ`�x�b�g���A�����ēƗ�����Ƃ����b�̎d���́A���Ȃ�r�����m���Ǝv���܂��B
�@�������_�@��Ԉ�ۂ��[�������̂́A��c���u�푈���N����ΏI��肾�v�Ƙb����āA����ɓ�����`�ŗ������E���ɋ߂��Ƃ���͕��a�̃��A���Y��������Ƃ������Ƃ���������������Ƃł��B���N�푈���v���o���Ă������������̂ł����A���N�푈���N���ē��{�̑̐����K�����ƕς�����B���N�푈�Ȃ��肹�Γ��{�̐�������̐��������ԕς���Ă����B���ꂾ������I�ȉe���𓌃A�W�A�ɗ^�����̂��A���͒��N�푈�������B����͍��Ɉ������Č����A������t�̗̗L�����߂����āA�������Η����ČR���Փ˂ɂȂ�A����̕��S�y���]�X�̎咣�͈�x�ɐ������ł��܂��Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɂ͐푈���N�����Ȃ����߂̓w�͂����Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�푈�̊댯�Ȉ��q�͗̓y�i�V���i���Y���Ɣr�O��`�I�ȃi�V���i���Y�����Ǝv���܂����A������ǂ��������邩�Ƃ����̂���X�ɉۂ���ꂽ�ۑ�ł͂Ȃ����B�l�l�̕��ɃR�����g�������������������Ƃ���ł����A���Ԃ�����܂���B���傤�͒����Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B
�@���ǎ��q�@�Ō�ɁA�얞�M�ꂳ��ꌾ�A��̈��A�����������܂��B
�@�얞�M���@1997�N�ł������A����Ɨ��̉\�����߂��錃�_�����܂����B���ꂪ�����Ă�����͂Ȃ��Ȃ��_�c���s������܂���B��t�₻�̑��̖����߂����āA�ْ��W�����܂��Ă��܂��B���̏œ_�ɗ����Ă��鉫��Ƃ��ẮA���ƂT���Ԃ��炢�����Ċʋl�Ř_�����邭�炢�̃e�[�}������܂��B���������@���݂��Ď��Ԑ����Ȃ��ŁA������܂ŋc�_����i���j�B���������@���݂������Ǝv���܂��B�i����j